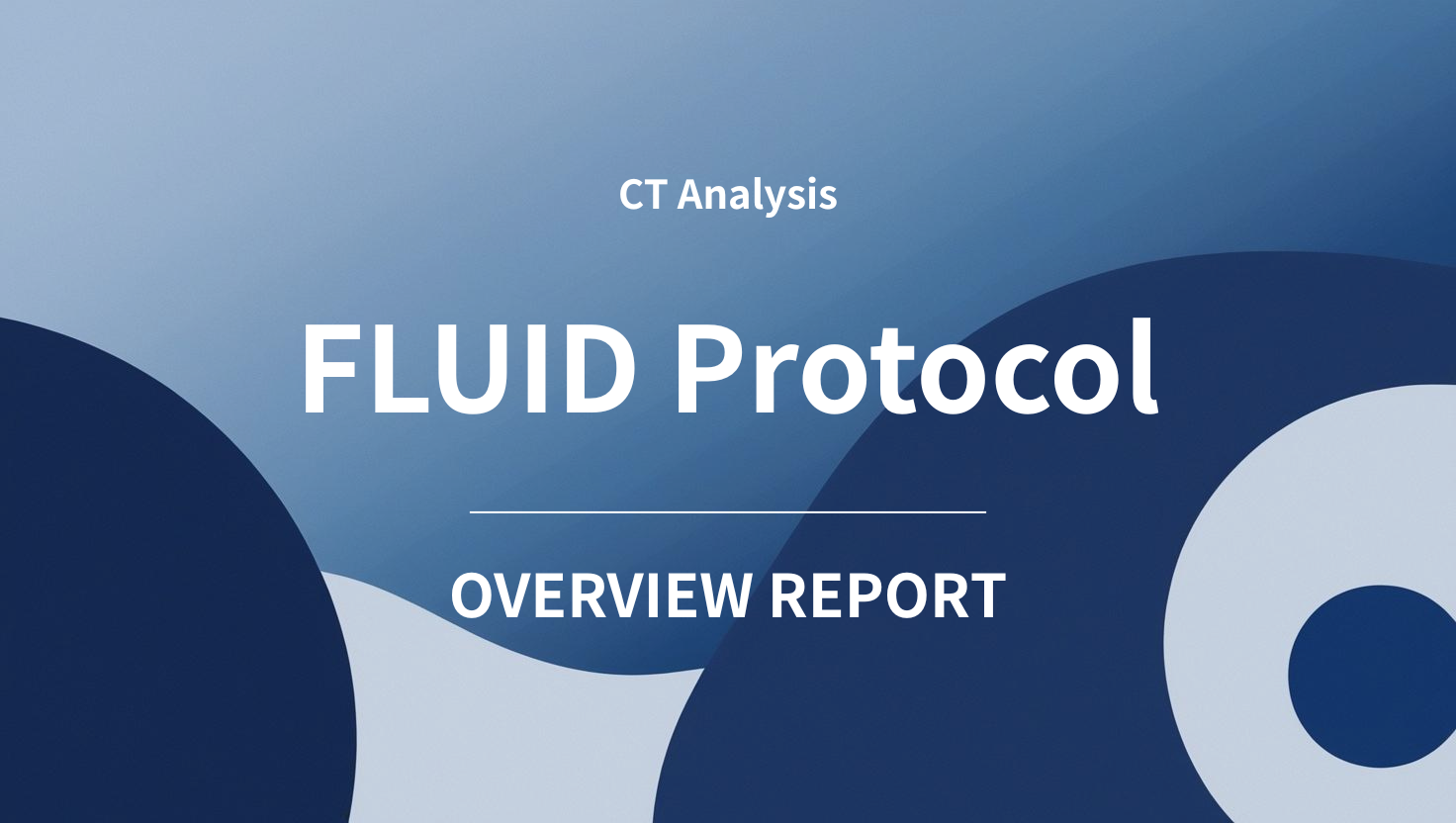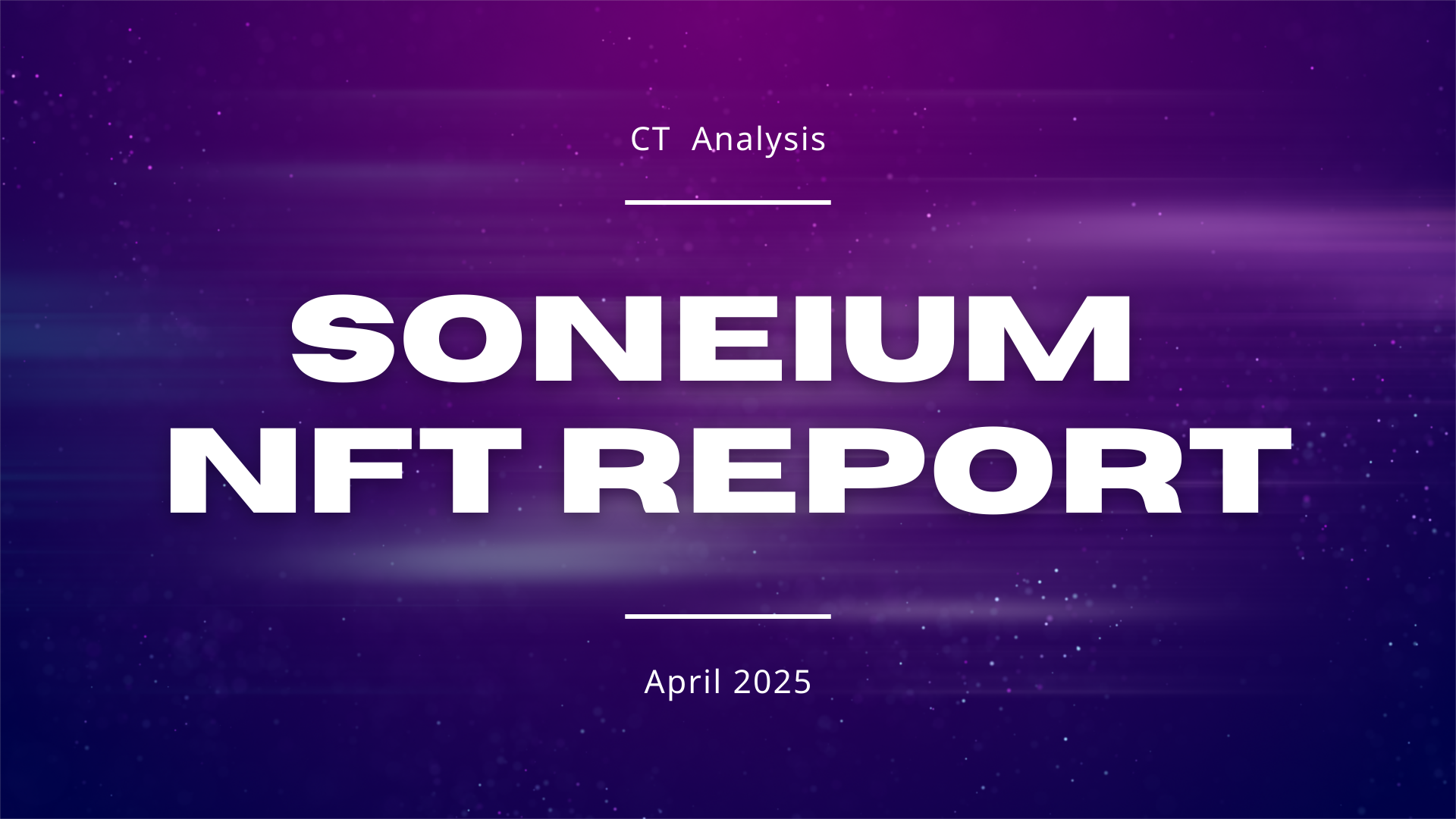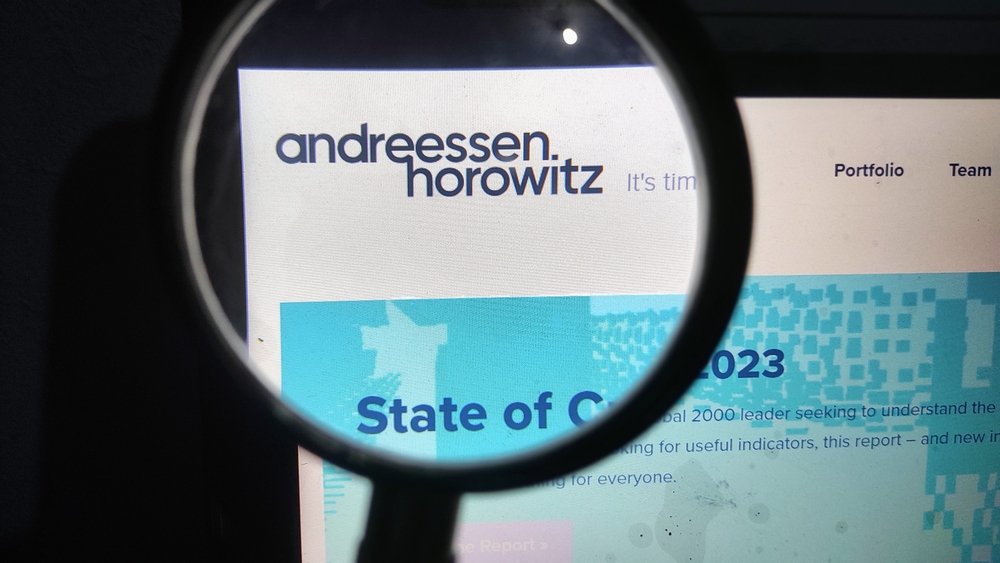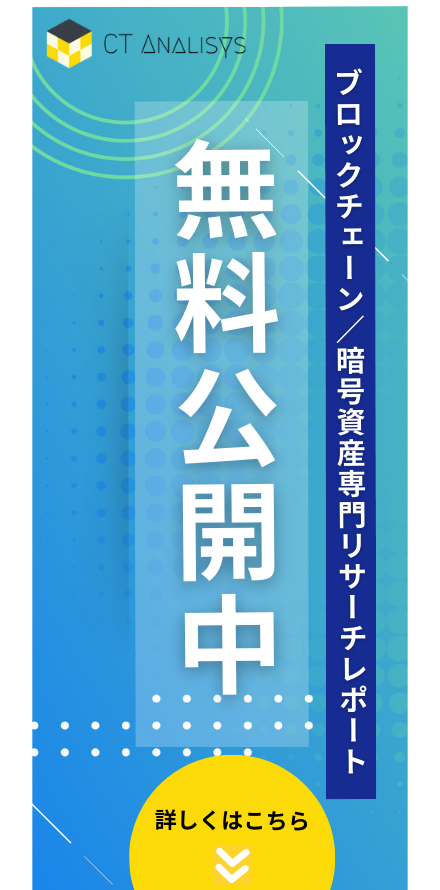スマコンを利用したサブスクリプション(定期購読)型モデルが実現? EIP1337について解説!
Shota

こんにちは。Shota(@shot4crypto)です。
今回は、スマートコントラクトを利用してサブスクリプション型のビジネスモデルを実現するというEthereumの新たな規格『EIP1337』に関して、この概要や特徴を紹介していきたいと思います。
本記事の執筆にあたって、1337AllianceのKevin氏による以下のMediumの記事の内容・構成を参考にさせていただきました。ありがとうございます。
記事ソース:EIP 1337 (Subscriptions) Launches
EIP1337とは?

画像では、『ERC1337』となっていますが、現在はまだProposal段階で『EIP1337』とした方が正しいでしょう。
このEIP1337ですが、タイトルにもある通り、これはスマートコントラクトを利用したサブスクリプション(定期購読)型モデルを実現するための規格です。
サブスクリプション型モデル自体は以前にもEIP948という規格を用いて構想が練られていたそうなのですが、今回紹介するEIP1337は、これに対するフィードバックを受け改善を施したものであるとされています。
なぜサブスクリプション型モデルなのか?

Webにおけるマネタイズ手段は、広告やスポンサーシップから様々ですが、1337AllianceのKevin氏は、『定期購読モデルはWebビジネスにおいて最も健全なものである』としています。
また、多くの場合トークンベースの経済システムと比較しても、サブスクリプション型のモデルの方が優れているケースが多いと考えられます。
以下はユーザー側・運営側・エコシステム全体がこのモデルを採用した場合に享受することのできる恩恵になります。
■ユーザー側の利点
- DAppsのユーティリティを利用するために複雑なホワイトペーパーを読む必要がない
- Dappsを利用するという点以上に複雑なVestingやCrypto-economic的な概念を理解する必要がない
- いつでもキャンセルを行うことができる
■運営の利点
- 購読者やコンバージョン等のデータを活用して、継続的なキャッシュフローを獲得・把握することができる
- 二面的なユーザーの構造(投機家・ユーザー)を考える必要がないので、サービスの質を改善することにフォーカスすることができる
- 長年かけて証明されてきた既存のビジネスモデルを活用することができる
- 規制面での不確実性が少ない
■エコシステム全体としての利益
サブスクリプション型モデルのような既存のシステムを構築していくことは、Ethereumのエコシステム拡大を考える際に、仕組みが非常にシンプルなものとなります。
オンチェーンのサブスクリプション型モデルにより、開発者は複雑なトークン設計などを意識せずとも、UIやUXの改善にコミットすることができるようになるため、Mass-Adoption(大多数への普及)という課題の解決に、より集中して取り組むことが可能になります。
結果として、利用者が増えることでEthereumのエコシステム全体へ対する利益へ繋がります。
EIP1337の現在の状況は?
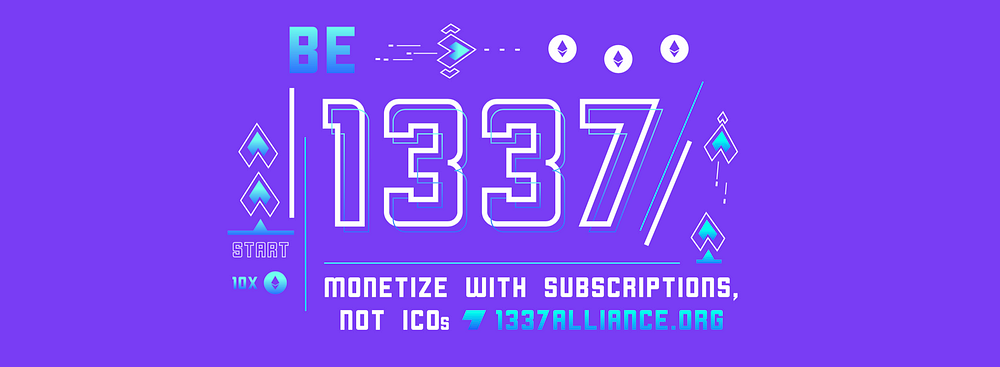
情報ソース:Subscription Services on the Blockchain…Are Here
ConsensysによってMediumにポストされた投稿によれば、このモデルを利用したサービスのプロトタイプがコミュニティから開発されており、サービスの機能面における監査も既に完了しているようです。
- Token Subscription – DAIやWETH等10種類のトークンを利用した定期購読が可能
 上のイメージのように、Metamaskを利用することで、ガス価格や数量、支払い頻度などを指定し定期購読を行うことができます。
上のイメージのように、Metamaskを利用することで、ガス価格や数量、支払い頻度などを指定し定期購読を行うことができます。 - ETH Grants – サブスクリプション型のコントラクトを作成可能

ETH Grantsでは期間やゴールを指定し、サブスクリプションの概要を記載していくことで、自身のサブスクリプションモデルを作成することが可能です。
EIP1337の今後の可能性は?EIP1337まとめ
個人的な意見となってしまいますが、個人的にはサブスクリプション型のモデルは必要であり、これが広く採用されればDAppsは間違いなく流行ると考えています(これに関しては、以前執筆させていただいたContentBOXの記事でも少し触れています)。
今回のリサーチでは、僕自身がエンジニアではないためDApps内の詳細の仕組みまではつかめなかったのですが、サブスクライブ(定期購読)の仕組みを利用することで、DApps内で行われるマイクロトランザクションを開発元が代替してくれるような仕組みまで実現できれば、これまでボトルネックとされてきたUX部分の大幅な改善が見込めるのではと思います。
一方で、記事内イメージのフレーズ「Monetize with subscription, not ICOs (ICOではなく定期購読でマネタイズしよう)」という形で、ICOの代替手段として広がるのみでは、まだまだ課題も残るのかなと感じます。
ありがとうございました。





















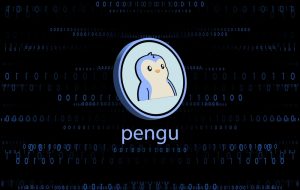




























 有料記事
有料記事