2017年5月に仮想通貨への投資を開始。ブロックチェーンや仮想通貨の将来に魅力を感じ、積極的に情報を渋谷で働く仮想通貨好きITリーマンのブログを通じて発信するように。
最近書いた記事

ニュース
2020/12/01CT Analysis第12回レポート『Ethereum周辺のレイヤー2 スケーリング 概要と動向』を無料公開
CRYPTO TIMESが提供するリサーチレポートコンテンツ『CT Analysis』が、第12回の配信レポートとして『Ethereum周辺のレイヤー2 スケーリング 概要と動向』を無料公開しました。 過去のレポートは全て無料でCT Analysisホームページ ( https://analysis.crypto-times.jp )よりダウンロードができます。 ※1度メールアドレスを登録された方は、レポートが公開される度に登録メールアドレス宛に最新レポートが届きます。(隔週目処) CT Analysis 第12回ダウンロード 第12回『CT Analysis』が提供する無料レポート『Ethereum周辺のレイヤー2 スケーリング 概要と動向』に関して 第12回目となる今回のレポートでは、Ethereum周辺のレイヤー2ソリューションに関してをまとめています。 DeFiが流行った夏以降、Ethereumでは度々スケーラビリティ問題が起こり、ガス手数料が大きく高騰しました。スケーラビリティ問題の解決のために現在、Ethereum2.0の登場が待ち望まれています。 そして、Ethereumでは先日、Ethereum2.0のStaking ContractがDeployされ、そのContractに対象数のETHがDepositされました。これにより、今後徐々にEthereum2.0への移行が始まることからも非常に注目を集めています。 しかし、Ethereum2.0への移行はまだ時間がかかるとされています。そんな、スケーラビリティ問題を解決するべく、現在ではEthereum周辺にてレイヤー2ソリューションが多く存在しています。 今回のレポートはEthereum周辺のレイヤー2ソリューションにフォーカスをして、どういうアプローチで解決しようとしているのかをまとめています。 レイヤー2ソリューションと言ってもステートチャネルやサイドチェーン、Plasma、Rollupなどと様々な分野が存在しており、今回のスライドで網羅的にまとめています。 Ethereumのレイヤー2ソリューションは複雑なものも多く、難しい分野となっていますが、本レポートでは網羅的にかつわかりやすく解説しています。 CT Analysisについて 2020年2月12日より暗号通貨/ブロックチェーン専門メディアCRYPTO TIMES ( https://crypto-times.jp )が2月12日より提供開始した、暗号通貨/ブロックチェーンの分野に特化したリサーチレポートコンテンツです。 今後、暗号通貨/ブロックチェーン分野は更に注目が集まることが予想されるものの、技術者から投資・事業家まで様々な参加者がおり、各々の求める情報は見つけづらく、また議論は英語で行われることが多いため、リサーチコストが高くなる傾向があります。 CT Analysisでは、2年間業界に携わりながら運営してきた知見やデータを活用して一般ユーザーから事業者まで、幅広いデータ・分析需要に応えることを目標として、専門性とわかりやすさを追求したリサーチ・レポートを提供していきます。 また、パートナー企業の強みを生かしたリサーチレポートも提供しており、オンチェーンデータやオフチェーンデータ、クリプト市場に関するセンチメントデータ、ユーザーの予測を機械学習で最適化したデータなどの情報を使ったレポートの配信も予定しています。また、これらは日本だけでなく、世界各国の情報も取り入れたコンテンツの配信を予定しています。 CT Analysis ホームページ

ニュース
2020/11/20Nemの新通貨 Symbol / $XYM ローンチ日やスナップショットなどが「2021年1月」に決定
パブリックチェーンであるNEMのリブランディングであるSymbol (Ticker : XYM) がローンチ日程や事前オプトインの最終日、スナップショット撮影日などを発表しました。 元々のSymbolの公開日は2020年12月17日前後の予定となっていましたが、今回の発表では公開日が2021年1月14日頃に延期になったことが発表されています。 ローンチ日・スナップショット撮影日・事前オプトイン最終日などの日程は下記の通りとなり、正確なローンチ日時は後日、改めて報告されるようになっています。 ローンチ日 : 2021年1月14日(正確な時間は後日確認) スナップショットブロック : 3,025,200 スナップショット撮影日 : 2021年1月14日20時07分前後 事前オプトイン最終日 : 2021年1月9日 日本国内の取引所でもSymbol / $NYM トークンは受け取ることが可能か? NEMは日本人にも人気の暗号通貨で、国内の取引所でも多くの取引所が取り扱いを行っています。 現在、日本国内のNEMを取り扱うcoincheck, bitFlyer , GMOコイン , DMM Bitcoinの4つの取引所では『NEMのオプトイン実施』という発表がされています。 Symbolが発行するXYMトークンが配布されるかどうかは取引所によって対応は異なりますが、スナップショットが撮影されるタイミングでXEMを保有していれば、XYMトークンを受け取れる可能性があると考えられます。 また、取引所にNEMを置いておらず、事前オプトインに間に合わなかったユーザーでもSymbol公開後6年間はオプトイン申請が可能となっているため、"スナップショット撮影時"にXEMを保有していれば、後からでも申請を行うことができるようになっています。 記事ソース : Nem Forum

ニュース
2020/11/191時間で作成されたBTCのウォレットアドレス数が約25,000になり、2018年1月後半と同水準へ
1時間の間で作られたBTCのアドレスが約25000となり、2018年1月後半と同水準になりました。 https://twitter.com/glassnode/status/1329045245212971010?s=20 GlassNodeのデータによると、新しいビットコインアドレスの24時間移動平均は24,807となっていることがわかります。 GlassNode社によると、現在、残高が0以上のアドレスは、合計3250万個あるとされています。ウォレットの作成数はBTCが2018年1月の急激な落ち込みの後、2018年3月以降から今まで継続的に上昇しています。 現在、ビットコインの価格が一時的に18500ドルに達成したことから、ユーザーが市場に戻ってきたり、新しいユーザーが多く増えていることが伺えます。 記事ソース : GlassNode

ニュース
2020/11/16Binance Innovation ZoneにPowerPoolの $CVP が新規上場
DeFiプロトコルのPowerPoolが発行するCVPがBinanceのInnovation Zoneに新規上場しました。 新規上場は2020年11月16日15時となっており、CVP/ETH と CVP/BUSD の2種類のトレーディングペアが上場します。 PowerPoolは、COMP、BAL、LEND、YFI、BZRX、AKROなどのガバナンストークンをプールするためのプロトコルとなっています。 直近ではDeFi系のトークン8種類を利用したインデックストークンであるPower IndexのPIPTや、TWAP(加重平均)のUniswap V2の価格を使用するクロスチェーンオラクルPowerOracleなどのプロダクトも発表しています。 記事ソース : Binance

ニュース
2020/11/16DeFiプロジェクトのフラッシュローン攻撃による資金流出が相次ぐ、AkropolisやValue Protocolなどが攻撃を受け総額10億円以上が流出へ
DeFiがクリプト市場のメインストリームになってから、数多くのDeFiプロジェクトがすごい勢いで市場に登場しています。 ユーザーが自由に自分たちが持っているアセットをDepositしたり、金利を得た後すぐに解除できる手軽さから多くのユーザーが現在では様々なDeFiプロダクトを使っています。 多くのユーザーがDeFiプロダクトを利用し、そのプロトコルに大量の資金がロックされ始めた結果、最近では多くのDeFiプロダクトにおいてフラッシュローンを用いた多額の資金流出が多発しています。 フラッシュローンとは DeFiでは様々なジャンルのプロトコルが存在しています。その中で、ユーザーが担保をもとにアセットを借りることのできるレンディングが存在します。 しかし、このレンディングプロトコルでは通常ユーザーは担保価値に対して75%しかアセットや資金を借りることができません。 フラッシュローンでは、一つのトランザクション内で資金やアセットを借り、最終的に同額の資金やアセットを返せば、担保は不要ながらレンディングを行うことができるサービスです。 Aaveやdydx、bZxなどのサービスが2020年の頭くらいからフラッシュローンのサービス提供を行っています。 フラッシュローンは、コーディングを要するサービスでしたが現在ではノーコードのフラッシュローンサービスFurucomboなども市場には登場してきています。 https://twitter.com/furucombo/status/1288837013634838528?s=20 フラッシュローンによる相次ぐ資金流出 そんな多額な資金がロックされる多くのレンディングやアグリゲータープロダクトに対してのフラッシュローンによる攻撃で、資金流出が相次いでいます。 2020年11月10日(14:36 GMT)にはDeFiプロジェクトAkropolisがフラッシュローンによる攻撃の被害に遭い2億円以上相当の $DAI が流出しました。 https://twitter.com/akropolisio/status/1327036622773374978?s=20 https://twitter.com/Dogetoshi/status/1326963117356625931?s=20 今回のAkropolisではCurveのyPoolにつながっていたアグリゲーターサービスがフラッシュローンの攻撃を受け、DAIが流出しました。 攻撃手法としては、dydxのフラッシュローンを利用し、CurveのPoolの価格の参考価格を下げたものとされています。 攻撃を行ったコントラクト0xe2307837524Db8961C4541f943598654240bd62f ではdYdXのフラッシュローンを利用しつつ、複数回これらの攻撃を行ったことが伺えます。 これらは1回の攻撃にいて0.8-1.2ETHのみのトランザクションフィーで行われており、トータル2億近いDAIが流出しています。 2020年11月15日にはValue DeFi ProtocolがフラッシュローンとフラッシュSwapの2種類の複合攻撃を受け、約7億円が資金流出しました。 https://twitter.com/value_defi/status/1327660571592773632?s=20 https://twitter.com/emilianobonassi/status/1327716769969164292?s=20 Value DeFi Protocolは11月12日にツイートで、フラッシュローンにおける耐性を持っているとツイートしていました (該当ツイートは現在削除済み)が、今回のフラッシュローンでの攻撃者はDo you really know flashloan?(本当にフラッシュローンを知っているのか?) とTxでメッセージを残しています。 現在、Value DeFi Protocolではアタッカーに対して、Txでメッセージを送り、資金の返還の交渉を行っていることが見受けられますが、どうなるかは不明です。 現状のDeFiの課題 10月下旬にもDeFi アグリゲータープロトコルであるHarvest Financeがフラッシュローンを使って攻撃により、約34億の資金が流出し、Harvestにロックされていた資金は半分まで減少し、独自トークンFARMの価格も半分まで下落しました。 筆者もHarvest Financeに資金を入れていたため、資金総額から約15%ほどの被害を受けるにも至り、これらの問題はDeFiに触れるユーザーであれば身近に存在しています。 Harvest Finance,Value DeFi Protocol , Akropolisの3つに共通するのはどれも監査会社からのコード監査を受けたにもかかわらず、今回のフラッシュローンのような攻撃を受け、資金が流出してしまっていることです。 監査をされていないスマートコントラクトに流動性を提供して資金をロックすることは、管理者によるRugPull(資金を回収して逃げられること)のリスクがあると議論されていました。 https://twitter.com/shingen_crypto/status/1328129184141492225?s=20 しかし、現在起きているDeFiでの資金流出問題ではスマートコントラクトに関するバグではなく、市場の歪みを狙ったものが多くなっています。 これらの資金流出の際、プロダクトを提供するサプライヤーは補填金などでユーザーに対しての資金補填が満足にできないケースがほとんどです。 10月下旬に資金流出があったHarvestでは、対象ユーザーに売買可能なIOUトークンを作成し、FARMをDepositしてもらえる利益の一部をホルダーに還元する動きを見せていますが、補填金を賄うまでには多くの時間を要することが考えられます。 これらの問題を解決するために、DeFiプロダクトにおけるスマートコントラクトのバグに対しての保険金が支払われるNexus MutualやNsure Networkのようなプロジェクトも最近では登場してきてます。しかし、これらのプロダクトでは上述されているフラッシュローンによる資金流出の保証は対象外となっていたり、Nexus Mutualに至っては日本人は利用できないなど、まだまだ多くの課題を抱えています。 [caption id="attachment_55513" align="aligncenter" width="800"] Nexus MutualのTotal Pool[/caption] 更にいうと、DeFi市場にロックされている資金が右肩上がりなことに対して、保険金がカバーできるほどの金額(Nexus MutualのTotal Pool)が存在していないこと、更には保険金のカバーはガバナンスによって決定されるため、ハックされた際に資金が必ずしもカバーされるわけではないことが上げられます。 [caption id="attachment_55514" align="aligncenter" width="601"] 殆どのプロジェクトはDenied(否決)のステータス[/caption] 現在でもDeFiのTVL(Total Value Locked)が右肩上がりを続け、DeFiは新たなプロダクトが今後も多くでてくることが容易に想像できます。 今後、DeFiが多くのユーザーに簡単に使われるようになるためにも、『スマートコントラクトのバグの定義』『現在のロック額に対してカバーしきれない保険』などこれらの課題は避けて通れない大きなものであると考えられます。 Flash-loanの実行者は果たしてハッカーなのか? また、最後にAkrpolisに攻撃をした対象アドレスを参照するとAkrpolis Hackerと命名されているものの、フラッシュローンという市場で提供されているツールを使い、市場における価格の歪みをついただけなので正当なものであると筆者は考えています。 コードに不備があって無限にMintをしたり、トークンを流出させたわけではないのでAkropolis Hackerとフラグを付けていることは少々違和感を感じました。 市場にムーブメントを起こすDeFi市場ですが、まだまだ未成熟な部分も多いため、今後のさらなる成長を期待していきたいところです。

ニュース
2020/11/12レンディングプラットフォームBlockFiがヨーロッパに進出と報道
暗号通貨のレンディングプラットフォーム最大手であるBlockFiが来年頭にスイス、オランダ、イタリアのヨーロッパ諸国で個人投資家向けの商品を提供する準備を行っていることが報道されました。 THE BLOCKが報道した情報によると、BlockFiはすでにイタリアにて個人向けの製品のテストを開始しています。 今回、BlockFiはヨーロッパに進出する旨が報道され、アジア圏、ヨーロッパ圏のVicePresidentであるDavid Olsson氏と10人のチームがイギリスのロンドンに拠点を置いているもののイギリスでは当面個人向けの製品を発売する予定はないと報道されています。 イギリスは、10月に個人のデリバティブ取引禁止を発表しています。これらの取引禁止は、BlockFiには直接的に影響を与えないものの英国の個人向けの暗号通貨プロダクトの全体像は「複雑」なままであるとDavid Olsson氏は述べました。 記事ソース : The Block

ニュース
2020/11/05Crust Networkがインセンティブテストネット「ProfitArk」を実施
Polkadotエコシステムにおいて、分散ストレージの実現を目指すCrust NetworkがIncentivized Testnetである「Profit Ark」を11月中旬より実施することを発表しました。 今回のProfit Arkでは、ネットワークノードのソフトウェアとハードウェアのテストに焦点を当てて11月中旬に開始することを発表しており、参加者に対して300,000CRU以上の報酬が準備されています。 Testnetで必要なハードウェア構成はこちらのリンクの通りとなっており、2020年11月中旬から2020年12月上旬の期間中にブロック生成率、作業レポートの成功率、および合計ストレージ容量を考慮して、それに応じて報酬が分配されます。 ネットワークに参加するには、LAN内の単一ノードまたは複数ノードのクラスターのいずれかを選択し、参加することができます。 また、今回のテストネットインセンティブは技術的な要件も必要となるため、非技術者向けのコミュニティ活動も準備されています。コミュニティに貢献する人に一定量のCrust Candyを配布、Crust Candyは、Crustコミュニティでの投票に使用されます。 5人の友達を招待 クラスト絵文字を作成 クラストテストネットアクセサリを開発 コミュニティQ&A クラストまたはテストネットの情報カードの作成 奨励されたテストネット関連の指示を作成 Crust CandyとCRUの変換比は1000:1となっており、Crust CandyとCRUの変換方法、時間、およびその他の特定のパラメーターは、インセンティブ付きテストネットの第1フェーズが開始された後に発表されます。 関連記事 : 分散型ストレージプロジェクトの Crust Networkが発行する $CRU がHuobi Globalへ上場 記事ソース : Crust Medium
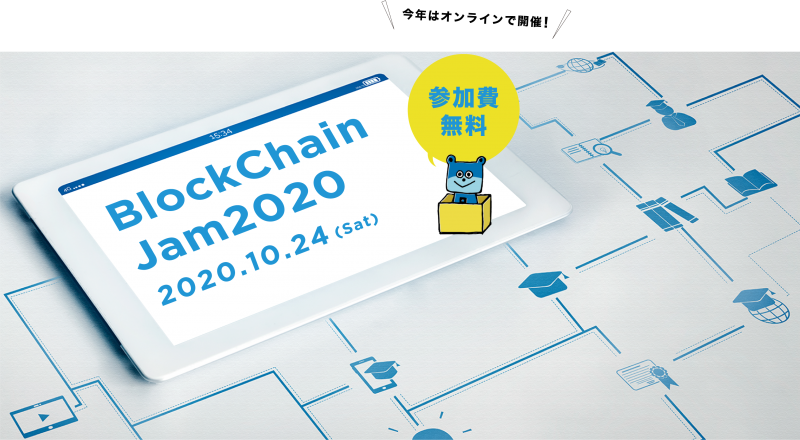
ニュース
2020/10/23ブロックチェーンの最先端技術と未来を知るイベント「BlockChainJam2020」完全オンライン・完全無料で開催
仮想通貨を支えるブロックチェーン技術は世の中にどんな変化を起こすのか?最先端の技術を知り、一足先の未来を知ることができる1日限りのイベント。 BlockchainJam2020が10月24日(土)、完全オンライン・完全無料で、開催されます。 https://twitter.com/BlockChainJam/status/1318763016251273216?s=20 開催概要 名称 :BlockChainJam2020(ブロックチェーンジャム2020) テーマ :ブロックチェーンがつくる新しい金融と社会 日程 :2020年10月24日(土) 時間 :9:00~19:00(予定) 会場 :Youtube(本編生配信)、Zoom(AMA)、BCJオリジナルVR空間 参加費 :完全無料 主催 :BlockChainJam運営委員会(代表・紅谷陽介) 共催 :東京大学 ブロックチェーンイノベーション寄付講座 後援 :一般社団法人 ブロックチェーン推進協会(BCCC) 一般社団法人 暗号資産ビジネス協会(JCBA) 一般社団法人 日本ブロックチェーン協会(JBA) ビットコイナー反省会 協賛 :DigiByte、Pundi X、Function X、Flow Blockchain、BTCボックス株式会社、 株式会社bitFlyer Blockchain、楽天ウォレット株式会社、株式会社withB 【チケット申し込みサイト(Peatix)】 https://blockchainjam.peatix.com/view 【公式WEBサイト】 https://blockchainjam.org/conference/ 【公式Twitter】 https://twitter.com/blockchainjam

ニュース
2020/10/15日本初、株式会社techtecが英Aaveより資金調達を実施。日本初となる日本発のDeFiプロダクト誕生へ
教育分野でのブロックチェーン活用およびブロックチェーンのオンライン学習サービス「PoL(ポル)」を運営する株式会社techtecは、昨今成長著しい分散型金融(DeFi:Decentralized Finance)市場を牽引する大手レンディングプラットフォーム「Aave」より、「Aave Ecosystem Grants」を通した日本初・日本唯一の企業として資金調達を実施しました。 これに伴い、PoLに蓄積された「ラーニングスコア」を活用して、日本初となる日本発のDeFiプロダクトを構築することを発表しました。 Aaveについて Aave(アーベ)は、イギリスのロンドンに本社を構える世界最大手DeFiサービスです。主にレンディング領域でサービスを展開しており、1日あたり1,500億円超の流通額を誇る巨大市場を形成しています。 その他にも、無担保借り入れが可能なFlash Loans(フラッシュローン)や、自身の持つ与信枠を他者へ移譲するCredit Delegation(クレジットデリゲーション)といった先進的なサービスも提供しています。 2020年8月には、英金融行動監視機構(FCA: Financial Conduct Authority)より、「電子マネー機関」としてのライセンスを取得したことも発表しました。これにより、法定通貨とDeFiサービスへの直接的な接続が可能となっています。 Aave Ecosystem Grantsとは Aave Ecosystem Grantsは、2020年4月に開始したAaveによるDeFiエコシステムを拡大するための取り組みです。世界中のブロックチェーン企業に対して資金を提供することで、非中央集権を志向したプロダクトが育ち金融の民主化を促進させます。 今回のようなGrantプログラムは、OSSのカルチャーを背景に持つ産業に特徴的な取り組みであり、日本ではまだまだ定着していません。 techtecでは、”Go Global”をVALUE(価値観・行動指針)に掲げており、創業以来変わらずグローバルスタンダードで闘い続けています。 今回の資金調達について 今回の資金調達は、Grant(グラント)と呼ばれる手法で実施されます。Grantは、今や海外では一般的な手法であり、主にテクノロジー系の研究開発の文脈で利用されます。 株式に影響を与えずに資金を調達できるため、各国の規制に左右されず、海外からの調達といった重要な局面の中でも意思決定をスムーズに行うことができる点が特徴です。GrantはOSS(オープンソース)の文化を背景に持つため、日本ではほとんど定着していません。 現在、新型コロナウイルスの長期化に伴いあらゆる産業のデジタル化が急務となっています。当然、教育業界および金融業界も例に漏れません。そこで注目されているのがDeFi市場です。 ブロックチェーンを活用した金融産業を意味するDeFi市場は、各国の新型コロナウイルスに対する経済施策の恩恵を受けた領域の1つです。それを証拠に、ここ数ヶ月で市場規模が10倍以上に膨れ上がり、今なお急成長を続けています。 我々はこの盛り上がりを当事者として受け止め、日本初となる日本発のDeFiサービスを構築すべく、日本が緊急事態宣言下にあった5月より資金調達に動き始めました。 日本初のDeFiサービスを開発 「PoL(ポル)」は、日本で初めてオンライン学習にブロックチェーンを導入したeラーニングプラットフォームで、PoLのサービス上で蓄積された学習データはブロックチェーンに記録され、改ざんが困難な状態で管理されます。この学習データを「Learning Score(ラーニングスコア)」と呼んでいます。 このラーニングスコアを活用することで、学歴評価に代わる新たな評価軸を導入した「学習歴社会」の実現を目指しています。また、真に正しい学習データを蓄積することができるため、学歴の詐称を防止することも期待できます。実際、株式会社techtecが2019年に経済産業省および株式会社リクルートとの調査事業を行った結果、一定の成果を論文として発表しています。 そして今回、株式会社techtecはこのラーニングスコアをDeFiに接続する、日本初となる日本発のDeFiサービスを構築していきます。一言で表現すると、「学習するほど金融サービスを享受できやすくなる」サービスとなっており、DeFi市場の大きな課題の1つである過剰な担保率を解消するサービスを提供する予定と発表しています。 PoLで学習することによって蓄積されたラーニングスコアを軸に評価することで、DeFiを利用する際の担保率を一部PoLで肩代わりします。まずはAaveとの接続を行い、Aaveを利用する際の担保率(借りる際の利子率)を通常よりも抑えることができるか検証していきます。 海外から資金を調達する理由 ブロックチェーンに限らず、残念ながら日本のスタートアップは世界に遅れを取っています。これには、大きく2つの理由があると考えています。それは、「資金調達」と「日本だけでもそこそこやれてしまう」ことです。 資金調達 ブロックチェーンに限った話でも、先述の通り数百億円サイズのベンチャー投資ファンドが次々と組成されています。 基本的に、企業の持つ資産の流れはバランスシートにおける右側(貸方)から左側(借方)に流れていきます。この右側における資金の大きさが、米国と日本では圧倒的に異なるのです。当然のことですが、スタートアップに限らず企業は元手となる資金次第で展開できる事業が決まってきます。 日本だけでもそこそこやれてしまう 日本は、高度経済成長期を経てGDP世界第二位にまで上り詰めました。現在は中国の後塵を拝し三位に後退しましたが、それでも世界の三位です。そのため、日本発のスタートアップは日本国内だけを戦場にしても「そこそこやれてしまう」。 そもそも、日本発のスタートアップは世界を意識する必要性に欠けてるのです。一昔前の中国や現在のインド、シンガポールなどは、最初から世界を意識しています。国内市場の規模からして意識せざるを得なかったのです。彼らの持つアグレッシブさは、現在の日本の環境からは生み出されにくいといえるでしょう。 しかしながら、ここ数年のGDP伸び率をみても今後の日本で「そこそこやれる」ことは次第になくなっていくと思われます。だからこそ、我々は海外からの資金調達に拘り、世界で戦わなければならない市場を選択しました。 techtecのグローバルパートナー techtecでは、これまでに世界中の著名ブロックチェーンプロジェクトとパートナーシップを締結し、日本の暗号資産・ブロックチェーン業界をリードしてきました。 Primas:中国 MakerDAO:デンマーク Kyber Network:シンガポール Brave:アメリカ SKALE:アメリカ Bitcoin.com:セントクリストファー・ネービス Aave:イギリス ←NEW 今回のAaveとの連携を機に、世界に遅れを取っている日本のDeFi市場を盛り上げていきます。

ニュース
2020/10/13SECのグレースケール投資信託で「ETHE(イーサリアムトラスト)」が認可
米暗号資産ファンドであるグレースケールの「イーサリアムトラスト」がビットコイントラストに続きSECの報告会社(Reporting Company)に認可されました。 https://twitter.com/barrysilbert/status/1315640460690456579 グレースケールは米国においての暗号資産ファンドの最大手となり、今回認可されたイーサリアムトラスト(ETHE)の他にもビットコイントラスト(GBTC)など複数のファンドを持ちます。 これらの投資信託では、財務状況などの監査結果がSECへの報告が義務づけられるため、金融資産としてイーサリアムトラストが投資の対象になったことが期待されました。そのため、今日の市場でもEthereumが発行するETHは価格を大きく伸ばしています。 グレイスケールは去年や今年の8月にも全米にて現在はデジタル通貨の時代だと主張のCMを流したことも記憶に新しいです。 記事ソース :Grayscale, Global News Wire










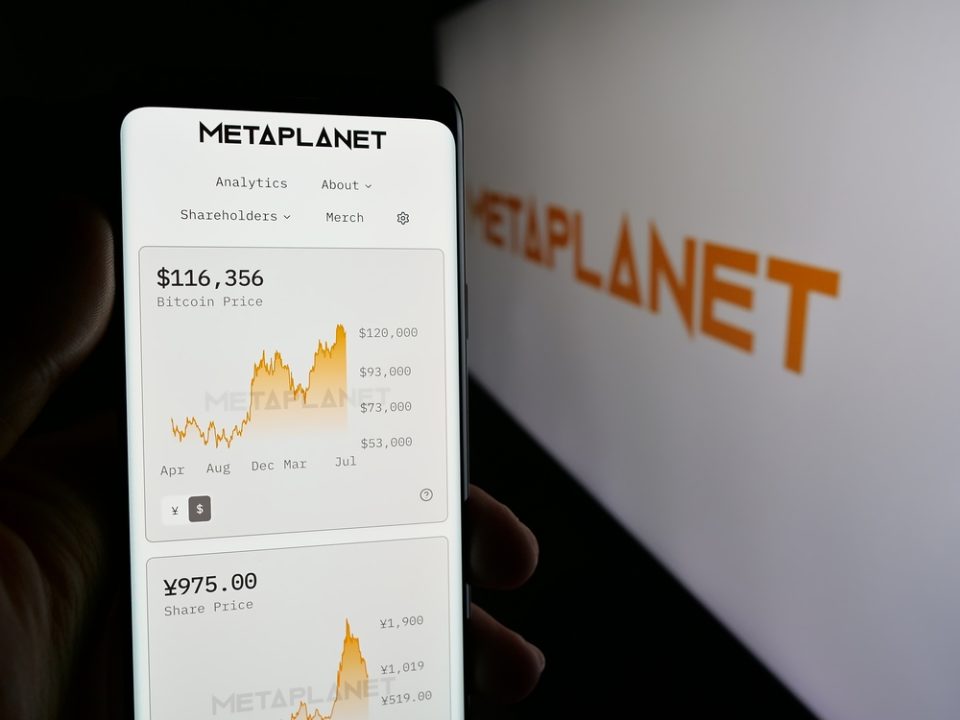

 有料記事
有料記事


