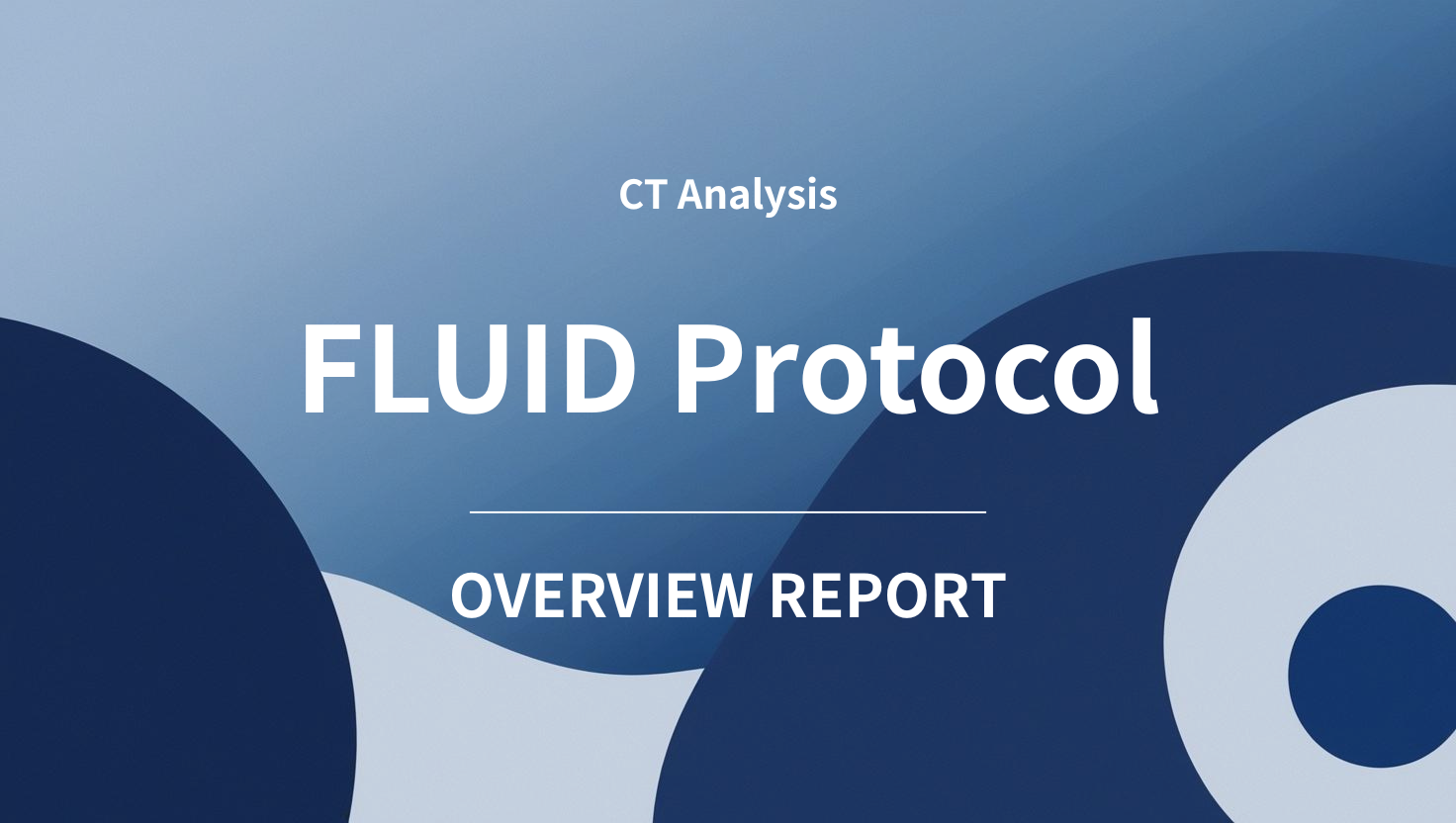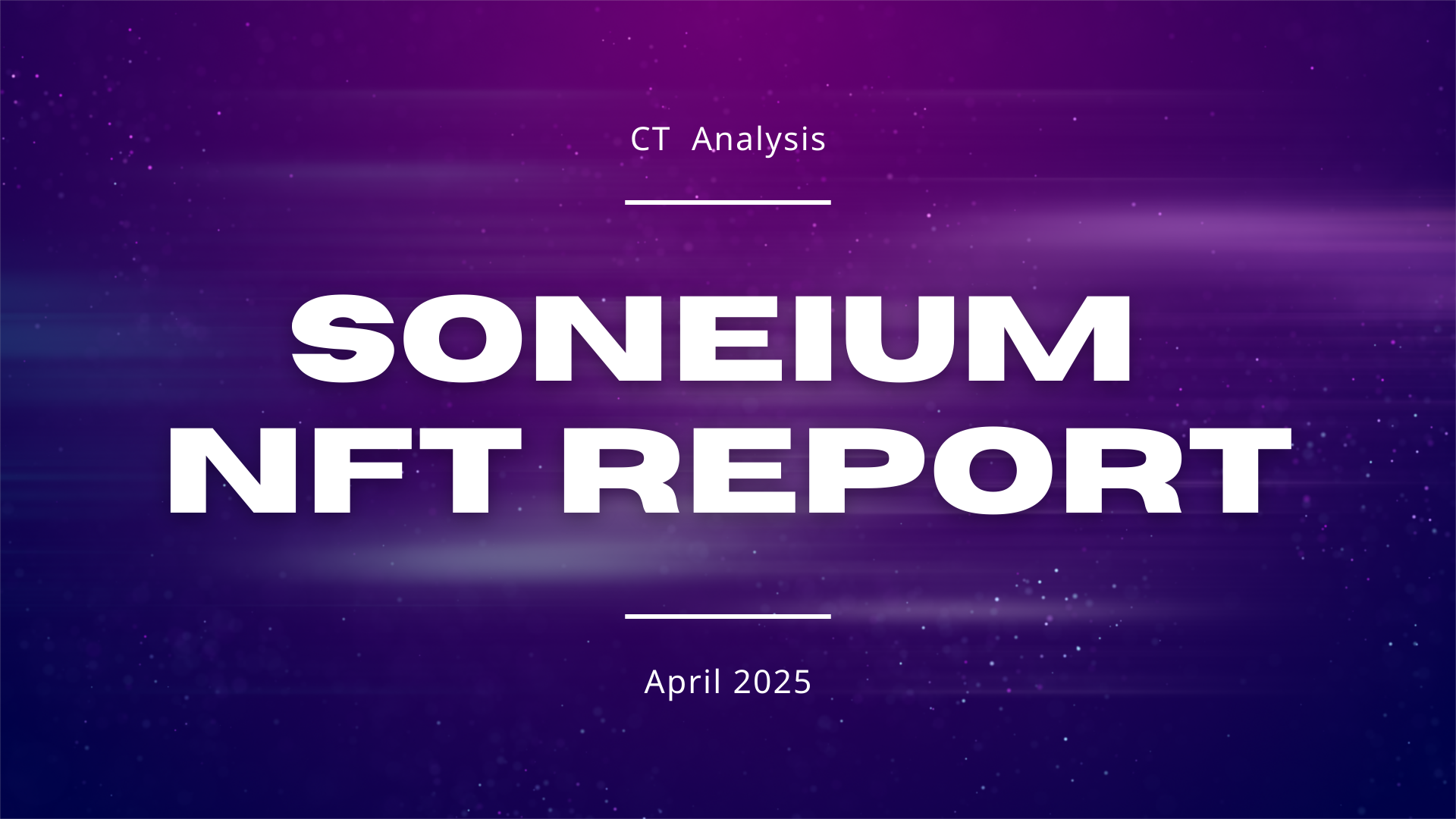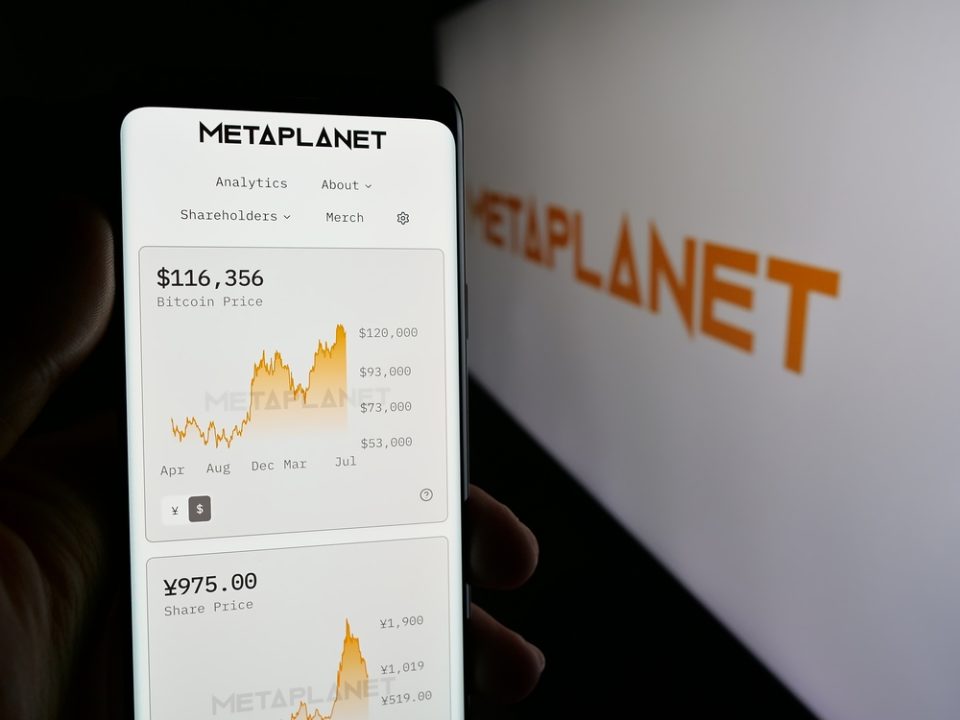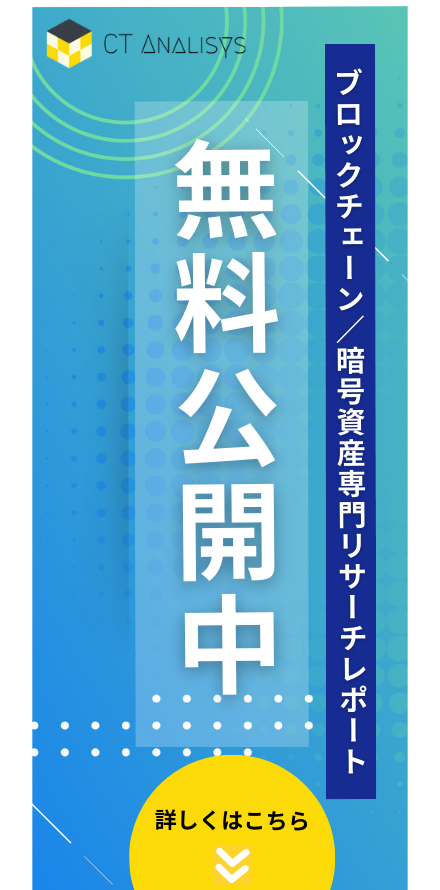Web3の解像度が急上昇した1日 |『Web3 Conference Tokyo Vol2 』CRYPTO TIMES主催イベントレポート
ユッシ

昨日7月15日、CRYPTO TIMES・Mask Networkの共同主催イベント『Web3 Conference Tokyo Vol2』が渋谷で開催された。
本イベントでは国内外から豪華なスピーカーによる、L1、NFT、コミュニティ、ウォレットなどあらゆるテーマでのトークセッションが行われた。
一つのバズワードとしてWeb3が扱われるようになった昨今では、より本質的な知識や思考の必要性が高まってきている。
本記事では、そのきっかけとなるべく『Web3 Conference Tokyo Vol2』の様子を伝えていく。
*イベントの様子はYoutubeで全編公開中です。
目次
会場の様子

画像引用元:https://stream-hall.jp/business-plan-view/
本イベントは渋谷駅直結の「Shibuya Stream Hall」の4F – 6Fをブースエリア、ネットワーキングエリア、トークセッションエリアの3エリアに分けて開催された。

ネットワーキングエリアの様子
平日昼間からの開催にも関わらず、全てのフロアに常に人がいる状態で、広々とした空間の中、それぞれが落ち着いた状態でネットワーキング活動を行なっていた。

ブースエリアの様子
4Fで行われていたブースでも、出店しているプロジェクトや企業の説明を熱心に聞き、名刺交換などを行なっている来場者の姿が多く見られた。

トークセッション会場の様子
トークセッション会場は、ほぼ全てのセッションが満席状態。数十人の来場者が立見で聴いている場面も多くあった。
「日本はトップファンドから相手にされていない」

Astar NetworkのSota Watanabe氏とあたらしい経済の設楽悠介氏
続いてトークセッションの様子を伝えていく。トークセッションの口火を切ったのはAstar Networkの渡辺 創太氏。
PolychainやAlameda Reserchなど大手VCから出資を受けているAstar Networkを牽引する渡辺氏は、世界から見た日本の現状について上記のように語った。
上記の理由として、
- VCは創設者の国籍ではなくプロダクトのクオリティで判断している
- 日本情報を英語で発信している人が少ないため、VCは日本についてよく分かっていない
の2点を挙げ、VCの基本的な思想や日本への見解について述べた。
日本の税制に対する問題意識が国内で高まりつつある中、渡辺氏は昨今の市場について「今は次のGoogleが生まれるゴールデンタイム」と表現し、さらなるプロジェクト推進への意気込みを語った。
「海外だとSBT、日本だとNFT」

LOCK ON CEOの窪田 昌弘氏
こう語ったのはLOCK ONの窪田 昌弘氏。
海外を中心に活動する窪田氏によると、海外イベントでは*SBTやZK Rollupといったワードが話題となるのに対し、日本ではNFTについて言及する人が多く、ギャップを感じるという。
*SBT = Soulboundトークン。Ethereum創設者ヴィタリック・ブテリン氏が最近提唱した譲渡不可能なNFT
モノバンドル株式会社の@y0su1さんも参加して4人でのセッションが行われました。
💫「海外で活動すると飲みニケーションが無くて気楽」
💫「海外だとSBTが取り上げられるが日本はNFTが中心でギャップを感じる」
💫「NFTに関して日本でしか出来ない強みもある」#Web3conferencetokyo pic.twitter.com/MRLDgVJGnB— CRYPTO [email protected] Conference 7/15 (@CryptoTimes_mag) July 15, 2022
日本と海外では捉えてる部分や、中長期的にどんなプロトコルを普及させようと試みているかの部分での思想が全く異なると自身の経験を元に語った。
「NFTを活用して限界集落の復興を」

NishikigoiNFT、山古志住民会議代表の竹内 春華氏
NFTが話題の中心となる日本では、実際にどのような取り組みやプロジェクトがあるのか。
人口800人の新潟県山古志村で行われているプロジェクト「Nishikigoi NFT」の竹内春華氏は、錦鯉をモチーフとしたNFTを発行し”デジタル村民”、”山古志DAO”を作成。デジタルアートと電子住民票を掛け合わせ地域の復興に取り組んでいるという。
💫「錦鯉NFTを発行してデジタル村民、山古志DAOなどを作った」
💫「NFT発行に伴い賞賛と批判の両方の声が」
💫「投票を用いてさまざまなプランを実施中」様々な意見を受けながらも、集落の復興のために取り組みを続けている様子が伝わりました。 pic.twitter.com/X8PvrBrgqq
— CRYPTO [email protected] Conference 7/15 (@CryptoTimes_mag) July 15, 2022
日本発のNFTプロジェクト「BOSO TOKYO」のセッションでは、Operation LeadのTOM氏が登壇。

BOSO TOKYO -暴走東京- のOperation Leadを務めるTOM氏
「ARTWORK」「CREATIVE」「MARKETING」の3つの柱でブランドの構築を目指しているとし、今後はホルダーによるコミュニティ形成の部分などで様々な施策を展開してく予定であると述べた。
「Web2は企業、Web3はコミュニティ」

UNCHAINの志村 侑紀氏(画面)、左からVeryLongAnimalsの河 明宗氏、合同会社ENJOYの西村 太郎氏、SoooN CMOのたぬきち氏
トークのテーマはコミュニティに移る。
web3開発コミュニティ「UNCHAIN」創設者の志村 侑紀氏は上記のように語った。
Web3では、従来のWeb2での企業体制と異なり、運営とコミュニティメンバーの垣根が無い状態が理想だという。
その理想を実現するために、
- コミュニティトークンのユーティリティの構築
- 税制を整えて企業や個人がトークンを保有できる環境作り
の2つの条件が必要になってくると同氏は語った。
「途上国でもモバイルとMetaMaskがあればWeb3に繋がる」

ConsenSys, DirectorのMasa Kakiy氏
「Web3 Wallet in the future 」のトークセッションに登壇したのは、MetaMaskを手がけるConsenSysのMasa Kakiy氏。
同氏によると、昨今のGameFiの成長とともにMetaMaskの利用者は急増。さらに、Infura NFTと呼ばれるSDKや、機能の拡張が可能なMetaMask Snapsと呼ばれるシステムを今後本格的にリリースしていき、さらなる普及を目指していくと語った。
💫「メタマスクのユーザー数は日々増加」
💫「Infura NFT、The Starknet Snap、The Filecoin Snapなど様々なプロダクトが進行中」
💫「途上国でもスマホとメタマスクがあればWeb3に参入できる」Web3ムーブメントを支えるInfuraの取り組みについて理解できるセッションでした。#Web3conferencetokyo pic.twitter.com/WciGP7L6bP
— CRYPTO [email protected] Conference 7/15 (@CryptoTimes_mag) July 15, 2022
Kakiy氏はMetamaskを「Web3のゲートウェイ」と表現し、Web3の実現に向けてコミュニティの共通認識を再確認した。
「特定の成長戦略は無い」

(画面左から)ビニール氏、Roi Senshi氏、(左から)Yoshitaka Okayama氏、木村 優氏、Leona Hioki氏
「How to choose Blockchain」のセッションでは、よりブロックチェーン・暗号資産の技術的な内容によるセッションが行われた。
Polygon、Cosmos、Ethereum、NEAR、Avalancheそれぞれの代表として5人の専門家が登壇した上記セッションでは、各チェーンの成長戦略が語られた。

Leona Hioki氏
Ryodan SystemsのLeona Hioki氏は「公共財として次のインターネットのインフラを目指しているEthereumは特定の事柄にフォーカスすることはない」と、パブリックチェーンとして一つの成長戦略を取ることはないと語った。
UnUniFiの木村 優氏は、Cosmosを「放任主義」と表現し、財団が力を持とうしない姿はサトシナカモトの思想と近いものとし、参加者の自主性が尊重されているとした。
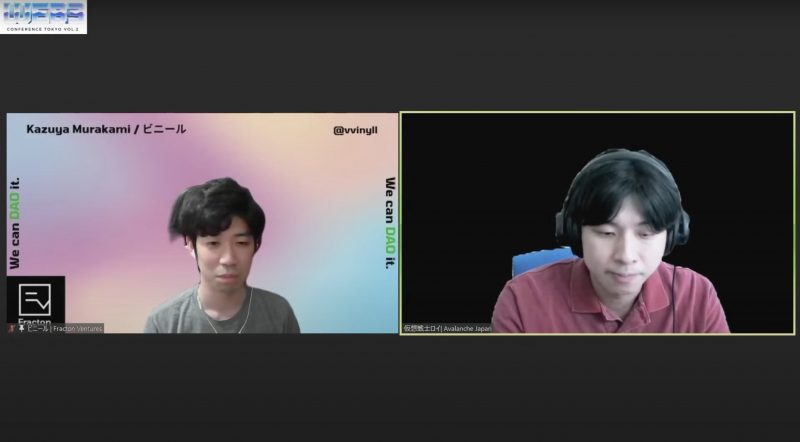
ビニール氏、Roi Senshi氏
一方で、Fracton Venturesのビニール氏は「NEARはまだまだ知名度が低い」とし、新たなCMOの採用を行い知名度向上を図る予定と明かす。Avalanche JapanのRoi Senshi氏は、実用性やUXを重視しさまざまなニーズに対応できるようにチェーンを展開しているとAvalancheの成長戦略を語った。

Polygon Yoshitaka Okayama氏
PolyognのYoshitaka Okayama氏は、Polygon上の開発者が他の企業と一緒にコラボできるような機会を作る「カルチャーレゴ」がチェーンの利用者の満足度に繋がると述べた。
本セッションは各チェーンによって様々な戦略、思想があることが分かる内容となっていた。
ここまで紹介してきた内容以外にも、複数のプロジェクト・企業のゲストによる興味深いセッションが繰り広げられた。*本イベントの様子はYoutubeで公開中
まとめ
CRYPTO TIMESとMask Network主催で行われた「Web3 Conference Tokyo Vol2」。
イベント参加者は各分野の有識者から様々なアングルで現在のクリプト市場についての考えや知識が得られ、よりクリプトに関するモチベーションが向上し、視野が広がったのではないだろうか。
CRYPTO TIMESは、今回のようなイベントと共に、今後もあらゆるアングルで最先端のクリプト情報を読者に届けていくので、是非情報のキャッチアップに利用してほしい。


























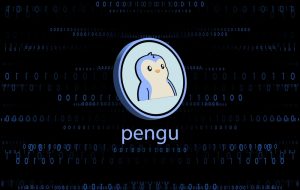























 有料記事
有料記事