
ニュース
2019/08/10OK PoolがEOSのロックアップマイニングを開始
OKExが手がけるマイニング事業「OK Pool」が、EOSのレンディングサービス(ロックアップマイニング)のベータ版を開始したことを発表しました。 同サービスでは、EOSをOK Poolに一定期間預け入れることで、最大年利5.12%が得ることができるとされています。 ロックアップ期間中の中途引き出しは不可能となっていますが、期間を任意で設定できる「フレキシブル」も存在します。また、ロックアップ期間の過ぎた預入額は自動でフレキシブルに転換されることにもなっています。 記事ソース: OKEx

ニュース
2019/08/09Liquid運営のBlockstream、ビットコインマイニング事業に参入へ
暗号通貨取引所「Liquid」の運営などを手がけるBlockstreamは8日、ビットコインの法人向けマイニング代行サービス「Blockstream Mining」とマイニングプールサービス「Blockstream Pool」を開始することを発表しました。 Blocksteram Miningは、機器のロジスティクスやセットアップからマイニング運営までを一括で管理するエンタープライズ向けソリューションとなっています。 Blockstream Poolは同社のマイニングプールとなっており、マイナー個人がブロックに格納するトランザクションを選べる「BetterHashプロトコル」を採用しています。 テストネットをすでに一年余り稼働してきたというBlockstream Poolは当面、Blockstream Miningの顧客のみ利用可能とし、今後さらに顧客層を拡大していくといいます。 記事ソース: Blockstream

ニュース
2019/08/09Overstock、12日からtZEROセキュリティトークン市場を個人投資家にオープンへ
米大手小売のOverstockは8日、子会社のtZEROが展開するセキュリティトークン市場を個人投資家にも開放する見込みであることを明かしました。 tZEROのセキュリティトークン市場は今年1月から適格投資家限定という形でオープンしていましたが、12日からは個人投資家にも市場が開放される予定となっています。 tZEROでは現在、同社の非公開株トークン「TZEROP」とOverstockのシリーズA-1優先株の2種が上場しています。 OverstockのtZEROはSIX Swiss Exchange、Open Finance Networkなどと並んで注目の集まっているセキュリティトークン取引プラットフォームです。 記事ソース: CoinDesk

ニュース
2019/08/09Coin Metrics調査: OMNI・イーサリアム上Tetherの80%が約300件のアドレスに集中
暗号資産・ブロックチェーンのデータ分析を手がけるCoin Metricsが、OMNIおよびイーサリアム上で発行されているTetherのうち80%ほどが318件のアドレスに集中しているとする調査結果を発表しました。 調査によれば、100万ドル以上のUSDTを保有するアドレス群は合計で約33億ドル保有しているといい、10万ドル以上・100万ドル以下のアドレス群(約4.2億ドル)の約8倍となっています。 Coin Metrics共同創設者のNic Carter氏によれば、このような巨額を保有する一部アドレスの保有者の中には、BinanceやBitfinexなどの世界的大手取引所や、中国投資家へのUSDTブローカー、さらにはTether自体などが含まれるといいます。 記事ソース: Bloomberg

ニュース
2019/08/08上値が重いビットコインは荒い値動きを続ける中、BNBが前日比15%の上昇
昨夜のビットコインの動きもまた、激しい値動きでした。一時的に$12,100まで価格を上昇するもその後、下落をし、$11,400を記録しました。 その後に、ビットコインは再度上昇を見せ、現在は$11,900付近を推移しています。 最近のビットコインの値動きは、連日$12,000の価格をつけた後、大幅な下落をしており、触りづらい値動きが続いております。 ゴールドに関しては順調に上昇をし$1,500を超える推移をしており、ビットコインも最終的にこれに釣られる動きをするのかは要注目です。 ビットコインが価格の上昇を続けると、アルトコイン市場は悲惨な相場になりますが、その中でもBinanceがIEOを発表したおかげか、BNB価格が上昇しています。 BinanceのLaunchpadも既に8回目ですが、今回参加する方は、明日よりBNBをホールドして、IEOの参加権利を得る為の期間が始まります。期間中はBNBの価格が下がる傾向にあるので、参加する人はBNBをショートできる取引所でホールドする枚数と同じBNBをヘッジショートすることでリスクを軽減することができるので覚えておきましょう
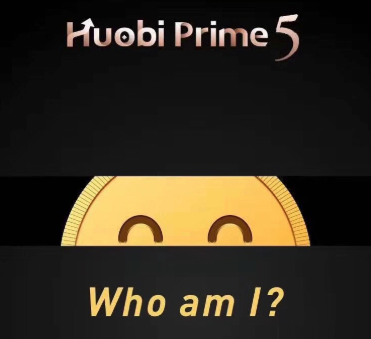
ニュース
2019/08/08Huobi Prime第5段は、IOST上のIRC20のトークンでEMOGI Network ( $LOL )が登場
Huobi Globalは8日、IEO第5弾としてEMOGI Network ($LOL)のトークンセールを行うことを発表しました。 抽選チケットの取得に関わるHuobi Token ($HT)保有量の記録は7月16日(前回のIEO終了時)から8月14日 23時59分までの期間となっています。 EMOGI Networkは検閲耐性のあるメディア構築基盤「Berm Protocol」が開発を手がけるネットワークで、南米を中心としたコミュニティが発展しています。 IOSTのインキュベーションプロジェクト「Berm Protocol」の新ネットワーク「EMOGI」とは? https://twitter.com/jimmyzhong_iost/status/1159134576704253954? LOLはIOSTブロックチェーン上にIRC-20トークンとして発行されることになっており、IOST公式やCEOであるJimmyによるツイートもあってか、$IOSTの価格も上昇しています。 記事ソース : Huobi Global
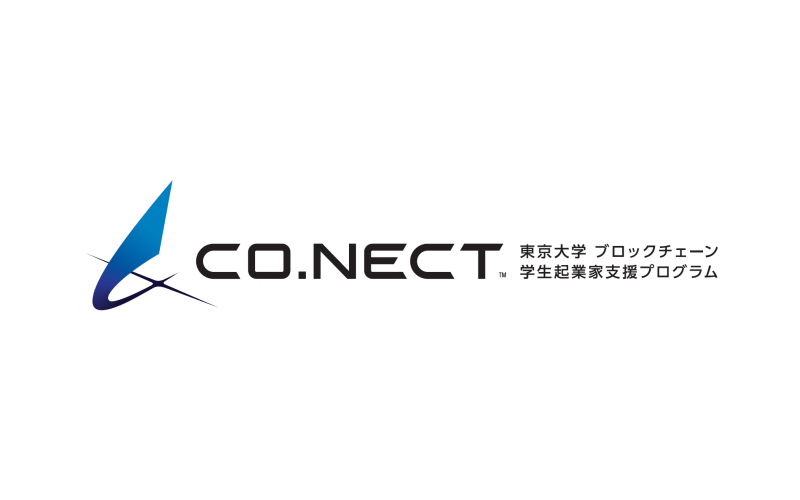
ニュース
2019/08/08東京大学主催のブロックチェーン学生起業家支援プログラム 第3回の応募受付がスタート
東京大学大学院工学系研究科・ブロックチェーンイノベーション寄付講座は8日、「ブロックチェーン学生起業家支援プログラム」の応募受付を開始しました。 参加学生は今年10月から来年2月までの4ヶ月間、人的・環境・資金サポートを受けながら、ブロックチェーン技術に関連した事業立案やソフトウェア開発に取り組むこととなっています。 人的サポートでは、産業や規模の異なる協力企業・団体から事業立案やアプリケーション開発の面などでアドバイスを受けられるといいます。 また、参加学生は本郷キャンパス内で専用スペースを利用できるほか、10万円の予算、さらには最大45万円の報酬が支払われることになっています。 応募資格は参加期間中を通して学生(東大生以外も可)であることで、採用人数は10名(チーム)程度となっています。早期応募の締め切りは2019年8月18日(日) 24時、応募締め切りは2019年9月1日(日) 24時と定められています。 記事ソース: PR TIMES

ニュース
2019/08/08米Amazon(アマゾン)、広告分野でブロックチェーンエンジニアを募集
eコマース大手の米Amazonが、「ブロックチェーン台帳にフォーカスしたフィンテック広告」を手がけるシニア・ソフトウェアエンジニアの求人を出していたことがわかりました。 同社は、オンライン小売データやクラウドサービス、スタートアップの増加などに伴う広告事業の拡大を目指しており、ついてはブロックチェーン技術を活用したプロダクトの事前分析・開発に携わるエンジニアを募集することになったと発表しています。 該当する求人ポジションは現在、申請の受け入れを中止しています。 今週はじめには、マスターカードが暗号資産決済およびウォレット開発の分野で求人広告を発表しており、大型多国籍企業がブロックチェーン技術の活用に次々と乗り込んでいる様子が伺えます。 マスターカードが暗号資産決済およびウォレット分野での求人を募集 - CRYPTO TIMES 記事ソース: Amazon LinkedIn

ニュース
2019/08/08Binance Launchpad 次期IEOは「Perlin / $PERL」に決定 非当選者にもエアドロップあり
Binanceは7日、Binance Launchpadでの次期プロジェクトとして、オーストラリア発のハイスループットDLT「Perlin / $PERL」のIEOを行うことを発表しました。 Perlinは分散型クラウドコンピューティングの実現を目標に開発されているDAGベースの分散型台帳ネットワークです。 分散型クラウドコンピューティングシステムの開発に取り組むPerlinに独占インタビュー! 抽選チケット獲得のためのBNB残高記録は9日午前0時から23日午前0時までの期間にかけて行われ、当選チケットの発表は24日午前8時となっています。 また今回のIEOでは、非当選者(抽選チケットが一枚も当たらなかった参加者)を対象に、3,874,500 PERL(30万ドル相当)がエアドロップされることにもなっています。 非当選者のエアドロップ獲得枚数は(非当選者の抽選チケット枚数 / 全非当選者の抽選チケット枚数) × 3,874,500となっています。 記事ソース: Binance
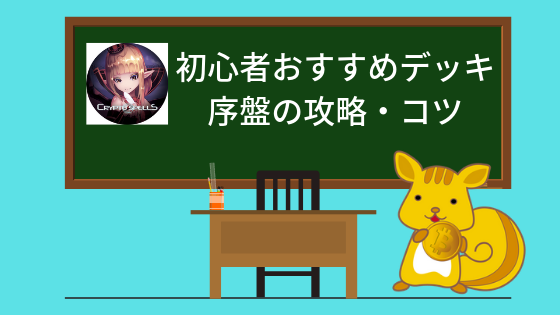
特集・コラム
2019/08/07【クリスペ】初心者おすすめデッキ&序盤の攻略・コツ【CryptoSpells】
こんにちは。しまりすです。 日本初のブロックチェーンカードゲームCryptoSpells(クリプトスペルズ|クリスペ)が正式リリース後からユーザー数が1万人に迫る盛り上がりを見せています。 CryptoSpells(クリプトスペルズ)が炎上を乗り越え驚異的な盛り上がり! - CRYPTO TIMES 2019年7月20日にはCryptospellsリリース記念公式大会βが開催され、過去最大の114名のユーザーが参加しました。 そして、なんと公式大会の初代優勝者になることができました。 https://twitter.com/crypto_spells/status/1152479419757240320 この他にも優勝賞金0.5ETHがかかったクリスペまとめ杯などでも優勝しており、大きな大会は今のところ全て抑えています。 https://twitter.com/tcg_cryspe/status/1143560503983140864 大会に参加して今までに獲得した賞品をまとめると以下のとおりです。(2019年7月執筆時現在) クリスペTシャツ クリスペステッカー 0.5ETH クリスペスマホリング 公式大会優勝記念カード 新カード1枚提案権(シルバーランク) 提案カードのマーケット売買手数料50%永続獲得権 本記事では公式大会優勝者のしまりすがカードゲームをやったことがない初心者向けに、クリスペでの勝ち方のコツや攻略法を解説します。 クリスペはカードの引きなど運要素もありますが、基本的なルールや理論をしっかり押さえれば必ず勝率を上げることができます! この記事が今からクリスペを始めようと思っている方や、クリスペってなんだか難しそう・・・と思っている方の参考になれば幸いです。 CryptoSpells(クリスペ)のルールを覚えよう カードゲームをするにあたってルールを覚えることは必須です。 クリスペの細かいシステムは公式Mediumでも確認することができますが、まずは基本的なルールを押さえてとにかくプレイしてみるのが手っ取り早いと思います。 基本ルール ・ライフ25スタート ・初期MP(マナポイント)1~(ターン経過で1増える) ・手札上限枚数:9枚(ここからモンスター召喚) ・場のユニット上限数:6体(相手に攻撃など) ライフはお互い25スタートで、相手のライフを0にするか、デッキの枚数を0にしてカードを引けなくするとバトルに勝利します。 まずはざっくりこれだけ押さえてとにかくプレイしてみて、分からない点や疑問に思ったことがあったら公式Mediumをチェックしましょう。 これだけですぐにルールは覚えられます。 プレイヤーのレベルを上げる フリー対戦でバトルをして勝利するとプレイヤーレベルを上げることができます。 レベルが上がれば採掘チケットがもらえ、新しいカードを手に入れることができるのでまずはフリー対戦でレベルを上げましょう。 採掘してみよう レベルが上がったら採掘チケットを使ってカードを入手します。 採掘ではレアリティがシルバーまたはブロンズのカードが出ますが、シルバーカードが出ることは稀です。(シルバー採掘の確率は非公表ですが感覚的には1%くらいです) シルバーが出たらラッキーというくらいに考えて、まずはブロンズのカードをそろえましょう。 連勝するとシルバー採掘の確率が上がると言われていますが、初期デッキではカードがとても弱くフリー対戦で勝つことが難しいので、採掘チケットを入手したら積極的に採掘することをオススメします。 クリスペを今から始めようと思っている方は、こちらから登録すると採掘チケットが20枚もらえるのでぜひ。 デッキを組もう クリスペは、初期デッキの構成カードがとても弱いため、始めたばかりの初心者はなかなか勝てないという壁にぶち当たります。 なので最初のうちは勝てなくて辛いですが、採掘でブロンズカードがそろっていくまでの辛抱です。 感覚的に、100枚くらい採掘するとある程度勝てるデッキを作ることができるのでそこまで頑張りましょう。 この項目では「初心者へのおすすめ度」という視点から、おすすめのリーダーとデッキを紹介します。 強さだけではなく、デッキの作成しやすさやプレイ方針の分かりやすさも考慮して選定したのでぜひ参考にしてみてください。 初心者におすすめのリーダー クリスペ初心者におすすめのリーダーは赤:竜騎将 フェルトゴルトです。 序盤から積極的に相手のライフをタイプのアグロデッキは戦い方の方針が非常に分かりやすいです。 バトル開始時に選ぶリーダーのクリプトスペルは、「コスト4 相手ユニット1体に6ダメージ」の方を選択して相手の前衛カード、ホルスの門番などが出てきたときに使うのが有効です。 初心者おすすめデッキ このデッキは序盤から積極的に相手のライフを攻撃していくタイプのアグロデッキです。 相手のリーダー(フェイス)をどんどん殴っていくという方針がわかりやすく、シルバーカードを持っていなくても構築できるので初心者におすすめのデッキとなっています。 ぜひ試してみてください。 強い人と交流をしよう カードゲームで勝つために大切なのは「情報」です。 本記事を書いたのは2019年7月ですが、クリスペにおいても強いデッキやメタゲームの情報は日々移り変わるので、どんなに強いプレイヤーでも高い勝率を上げるには「情報」が非常に重要になります。 そこで僕が実践しているのが、「強いプレイヤーのいるコミュニティに入りそこから情報を得る」とうことです。 コニュニティに入れば、分からないことを教えてもらったり、他プレイヤーのリプレイ映像などから戦略やデッキ情報を集めることができます。 以下、僕がおすすめするコミュニティを2つご紹介します。 Gaudiyのクリスペコミュニティ GaudiyのCryptoSpellsコミュニティには、沢山のクリスペユーザーがいて攻略情報や最新の情報が集まります。 また、コミュニティ内での活動や貢献によって、クリスペコインをGETすることが出来ます! コインはコミュニティ内のギフト(限定カードなど)に交換できるのでGaudiyのコミュニティには必ず入ることをオススメします。 ↓コミュニティ参加はこちら↓ https://gaudiy.com/community_details/avJEInz3EXlxNXKMSWxR/0 CryptoSpells公式Discord CryptoSpells公式Discordでは、ユーザーが企画する大会やイベントなどの情報が集まっています。 過去の大会のプレイ動画などもアップされているので、強い人のプレイングから研究することができます。 ↓CryptoSpells公式Discord参加はこちら↓ https://discord.gg/uY8BuwH とにかく数をこなして経験を積む ここまでクリスペで強くなる方法を紹介しましたが、結局大切なのは試行錯誤―トライアンドエラーを重ねることです。 強いプレイヤーと自分のプレイのどこが違うのかを考え修正する。 地道ではありますが、これを繰り返せば確実に実力はついていきます。 まとめ 以上、カードゲーム初心者が強くなるための方法でした。 参考にしていただければ幸いです。 ではよいクリスペライフを。 Twitterではクリスペの情報など随時アップしているのでしまりすのフォローもぜひお願いします。 CryptoSpells


















 有料記事
有料記事


