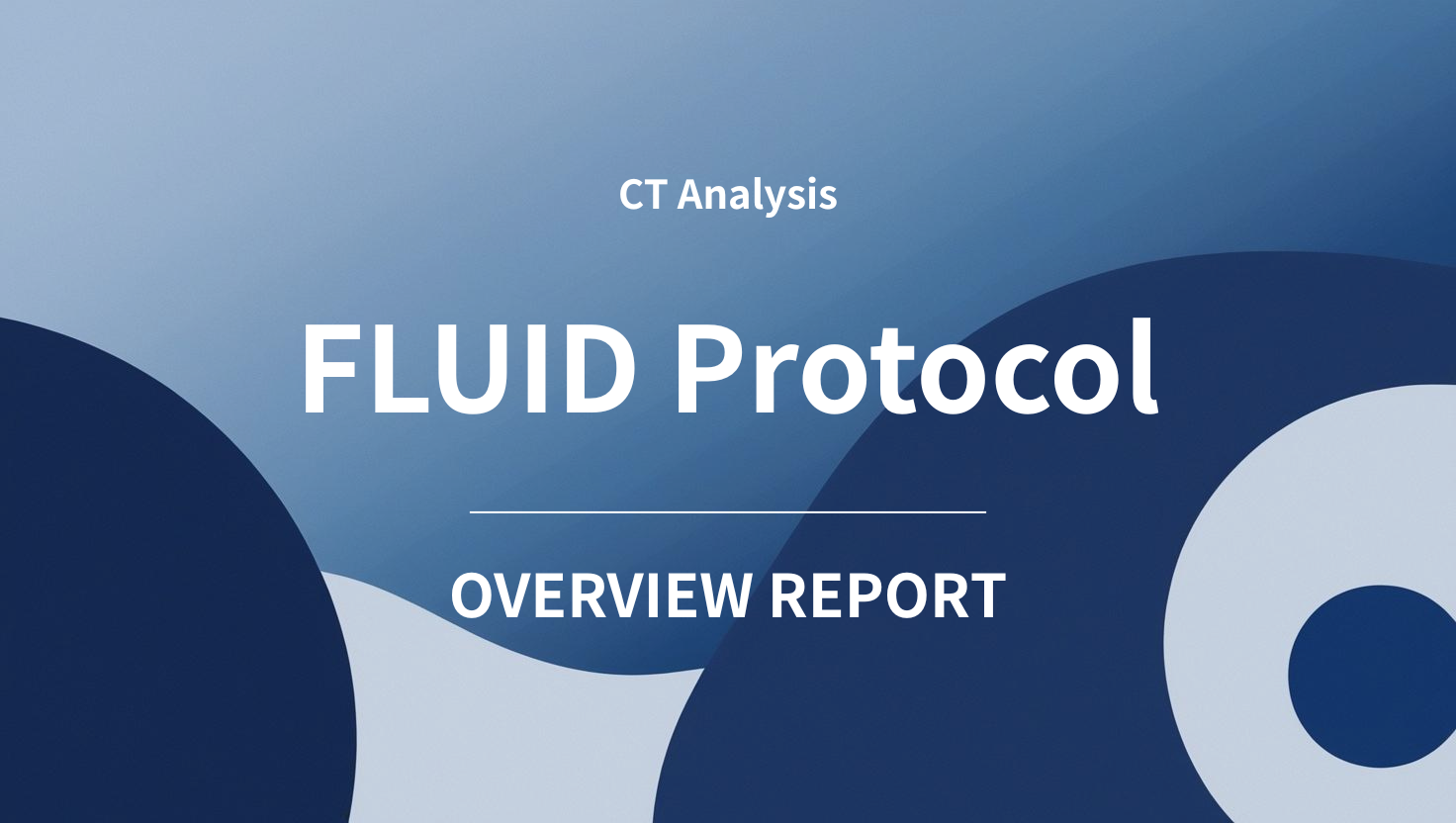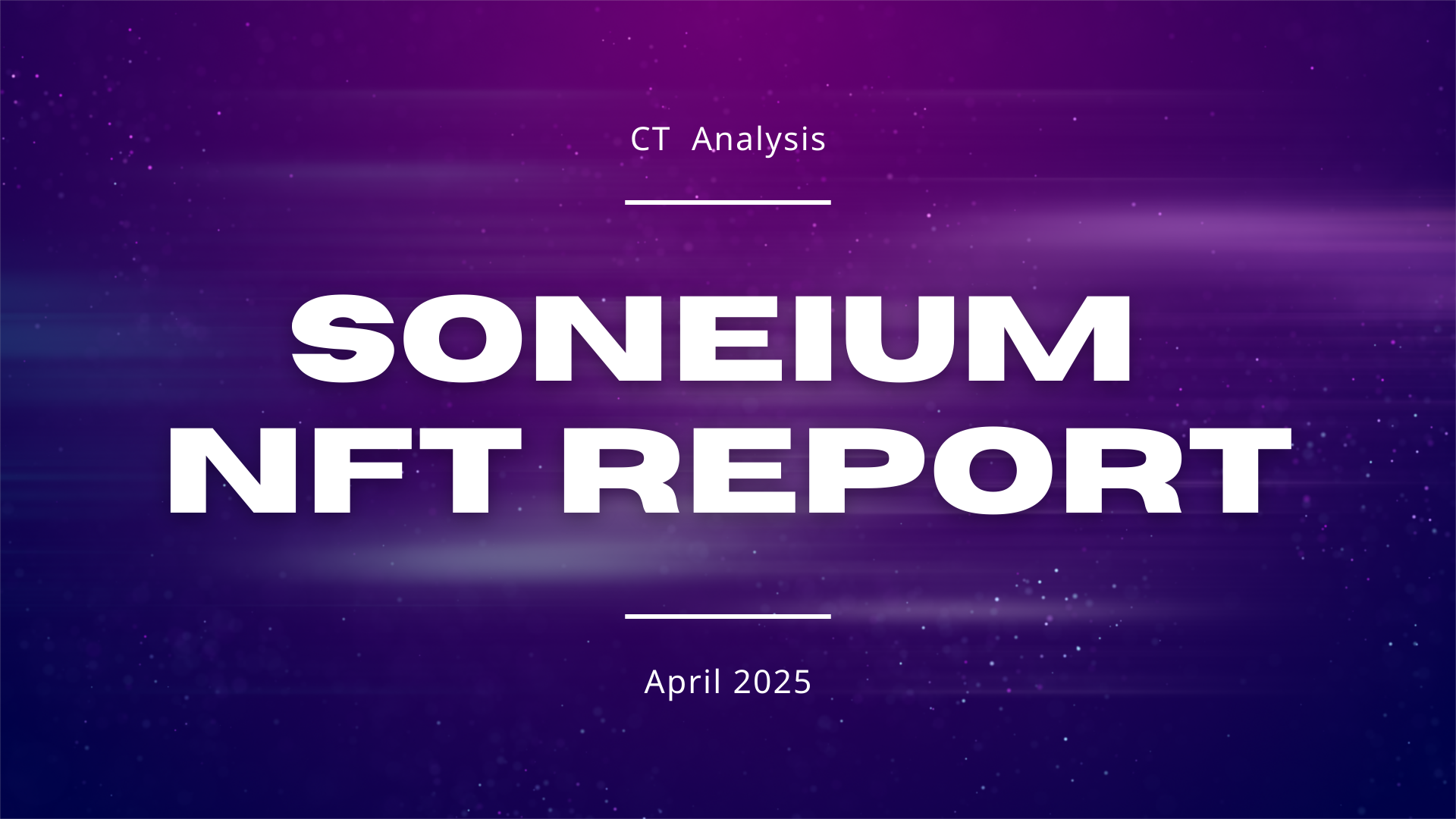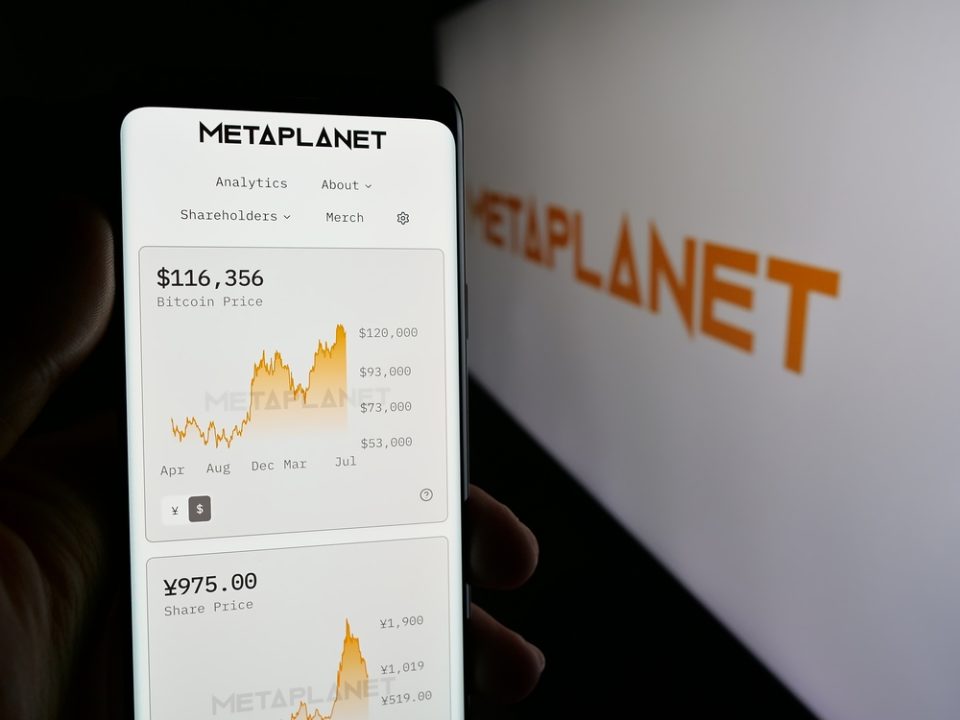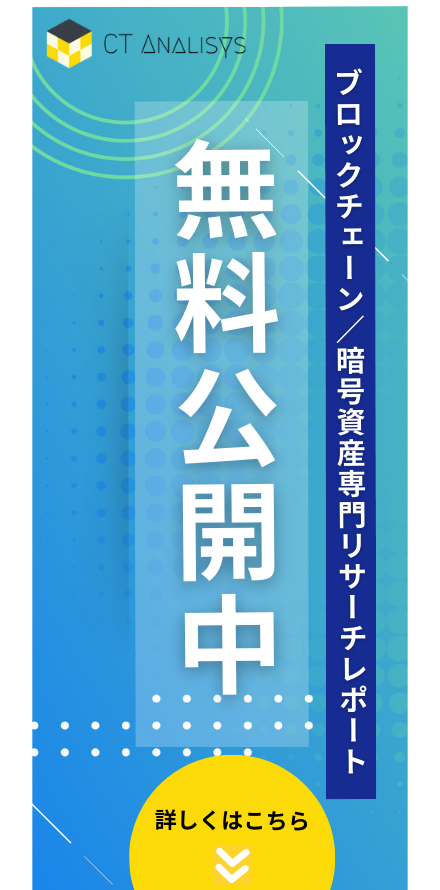なぜXRP(リップル)は中央集権的と言われるの?わかりやすく解説!
Crypto Times 編集部

国際送金の問題解決を目指すデジタルアセット「XRP(リップル)」は、時価総額3位(記事執筆時)の通貨ですが、一部からは「中央集権的では?」という声が上がっています。
そこで今回はXRPが中央集権的な通貨だと言われる2つの理由をRipple社の考えている方針と共に紹介していこうと思います。
この記事を最後まで読んでいただければXRPの正しい実態を知ることができます。
目次
まずはXRP(リップル)の仕組みを知ろう!
まずはXRP(リップル)がどのようなデジタルアセットであるかを説明します。(説明を飛ばす↓)
XRPはRipple社が手がけるRTXP(リップル・トランザクション・プロトコル)というシステムの中で主に利用されるデジタルアセットです。
「RXTP」とは、国際送金の問題を解決することを目的とした送金システムで、通貨と通貨を繋げるシステムの「ILP」とDLT(分散型台帳技術)の1種である「XRPLedger」から構成されています。

(RXTPの構成図)
XRPLedgerではPoCと呼ばれるタイプの合意形成の方式が採用されており、「Validator(バリデータ)=UNL(ユニークノードリスト)」と呼ばれる特定の人・企業が承認作業を行っています。
あらかじめ決められたValidatorが承認作業を行うことによって承認プロセスの高速化を実現し、「数秒で海外に送金する」といったようなことが可能となります。
ちなみにビットコイン(BTC)で採用されているPoW方式では世界中の人・企業がマイニングという行為によって承認作業に参加しています。
本題:XRP(リップル)はなぜ中央集権的と言われるのか?
では本題に入ります。XRP(リップル)はなぜ中央集権的と言われるのでしょうか。
それは以下の2つの理由が考えられます。
・Ripple社が大量のXRPを保有しているから
・Ripple社推しのValidator(バリデータ)が承認作業を行っているから
それぞれどういうことなのか1つずつ見ていきましょう。
Ripple社が大量のXRP(リップル)を保有している?

Ripple社はXRP(リップル)の総発行枚数1000億枚に対して約600億枚(6割)を保有しています。
この6割の半分はエスクロー(第三者預託)に入っており、実質的にRipple社は全体の3割程のXRPを保有しています。
「通貨全体の3割を1つの企業が保有している」ということを中央集権的とみるか否かは人によって感じ方が違うと思いますが、「全体の6割を保有しているから中央集権的だ!」という主張は実態とは少しずれていることがわかります。
ちなみにXRPはビットコインなどの仮想通貨と違い、すでに総発行枚数1000億枚の全てが発行済のため今後マイニングに電力がかからることがないというメリットがあったりします。
承認作業を行うUNLの多くがリップル社の人間?

XRPではPoC(Proof of Consensis)という仕組みの中で、UNL(ユニークノードリスト)に選ばれた人たちが承認作業を行っていることを説明したと思います。(説明に戻る↑)
つい先日まではこのUNLの半数近くをRipple社が管理しており「台帳にデータを記録する人達の半数がリップル社側の人間なんだから中央集権的だ」と言われていました。
しかし、現在はUNLの比率は変わってきており、現在ではRipple社が推奨するUNLの割合が2割ほどになったとされ、UNLにおけるRipple社の権力が徐々に弱まっていることが分かります。
UNLの比率をチェックできるサイトMini Validator Listによると、現在Ripple社が抱えているUNLの割合は2割程であることがわかります。

(画像引用元:https://minivalist.cinn.app/)
「UNLの半数をRipple社が握っているから中央集権的だ」という主張は現在のUNLの状況に対して少しずれていることが分かります。
Ripple社の今後の方針は?
ここまでXRPが中央集権的なデジタル・アセットであると言われる理由をまとめてきましたが、今後Ripple社はどのような方針でXRPを扱っていくのでしょうか。
CEOの発言などから今後のリップル社の方針について見ていきたいと思います。
Ripple社の方針
Ripple社はエスクローにロックアップされている自社のXRP(リップル)を毎月上限10億XRPで少しずつ市場に売り出しています。
これは、特定の企業が大量のXRPを取引することで価格が大幅に増減するのを防ぐためです。
XRPの保有に関してRipple社CEOのガーリングハウス氏は
「XRPはPoS(Proof of Stake)モデルではないから、大量に保有していたとしても何かに対して支配力を持つわけではない。」
と述べています。
また、承認作業を行うことができるUNL(ユニークノードリスト)に関しても、リップル社は「第三者によって認可されたUNLが2つ追加されるごとに、リップル社が選んだUNLを1つ削除する」というプロセスを採用しています。
今後もこれらの内容が実行されるのであれば、Ripple社のUNLやXRPにおける権力は弱まっていくと言えるでしょう。
Ripple社はなんでわざわざ権力を弱めるの?(考察)
ここで1つ疑問が湧いたと思います。Ripple社はなぜ自らXRPに対する権力を破棄していくのでしょうか。
これを考えるには、Ripple社のビジネスモデルを知る必要があります。
Ripple社は「XRPの売却」「銀行などへのソフトウェア販売」の2つで主な利益を得ています。
「XRPの売却」とは、その名の通り通貨XRP(リップル)を売却して利益を得るということです。Ripple社は保有しているXRPを毎月少しずつ売却しているので、そこで利益を上げることができます。
もう一つの利益の柱「銀行などへのソフトウェア販売」とは、Ripple社の主力商品を販売して利益を得るということです。
Ripple社には銀行向けの「xCurrent」、送金業者向けの「xRapid」、企業向けの「xVia」という3つの主力製品があります。
これら主力商品を銀行や送金業者に売ったり、その使い方をコンサルしたりすることで利益を出すことができます。
このビジネスモデルから考えられるRipple社にとっての最良ケースは「自社製品やネットワークシステムが健全なものであると世界中に認知され普及する」なのではないでしょうか。
Ripple社はXRPの売却だけでも多額の利益を得ることができますが、さらにその先を見据え、自らの権力を弱めてシステムの適切な非中央集権化を進めているものと考えられます。
Ripple社のXRP(リップル)の売り流しへの抗議事件
しかし、Ripple社のこういったXRP運用法は当然、利用者の反感を買う事態にも繋がっています。
同社が公開したレポートによると、2019年第2四半期・4-6月のXRP(リップル)売却による売上は2億5151万ドル(約260億円)でした。
これに対し一部からは抗議の声が上がり、約3000人が反対署名を行う事態となりました。
I’m thinking about forking $XRP so we don’t have to deal with the founders dumping.
-This will be a community effort.
Retweet if you’re in 🚀🚀🚀
— CRYPTO BITLORD (@Crypto_Bitlord) August 26, 2019

これらの抗議に対して、Ripple社CEOであるガーリングハウス氏は自身のTwitter上で弁解を行いました。

この見解の要点をまとめると以下のようになります。
・XRPは証券ではない: XRPは証券として認定されていないので発行元のRipple社が売却しても何も問題がない。
・XRPの売却はRippleNet等のユーティリティを拡張するためである: XRPを市場に流すことによってRippleNet等でのXRPの有用性を高めることができる。
・XRP供給量のインフレ率はBTC、ETHよりも低い
この署名活動は注目を集めましたが、最初にRipple社がXRP発行量の6割を保有すると決めた時点で、売る・売らないに関係なく、どちらにしても批判は起こっていたと考えられます。
【初心者向け】XRP(リップル)の買い方とおすすめ取引所を紹介!
まとめ
XRP(リップル)が中央集権的であると言われている理由は
・Ripple社がXRPを大量に保有しているから(←自由に動かせるのは約3割程)
・承認作業を行う人・企業の多くがRipple社側だから(←最近はもう違う)
の2つであることが分かりました。
ブロックチェーン技術が実社会に普及しつつある昨今「全てを非中央集権的に管理するより、部分的に中央集権的に管理した方がよいのではないか」という考え方も出てきています。
最後まで読んでくださりありがとうございました!


























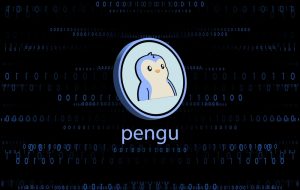























 有料記事
有料記事