
レポート
2018/11/19【イベントレポート】NITech AI研究センター×IOST「ブロックチェーン勉強会」
11月8日、名古屋工業大学にて開催されたNITech AI研究センター×IOST「ブロックチェーン勉強会」というイベントに参加してきました! 本イベントの冒頭では、NITech AI研究センター伊藤孝行教授より開催の挨拶もあり、伊藤孝行教授は、当センターはAIアルゴリズムはもちろんのこと、データ処理の研究を行なっている機関であり、ブロックチェーンは仮想通貨だけでなく様々な分野で応用可能で、人間社会の信頼性を担保できる技術であると述べていました。 そんな冒頭の挨拶から始まったイベントですが、登壇されたIOSTのCO-Founder兼CTOのTerrence Wang氏の講演と参加学生によるワークショップの様子をレポートをまとめています。 #IOST CTO @terrence_iost led a workshop at the Nagoya Institute of Technology, one of Japan's top Tech Universities. 15 students joined the event as well as the CTO of EverSystem, our local tech partner, and a local reporter. #crypto #blockchain $IOST #ecosystem @nitechofficial pic.twitter.com/0Cj8FcICi6 — IOStoken (@IOStoken) 2018年11月13日 IOST Terrence氏の講演 今私たちが使っているインターネットは崩壊している。IOSTはそれを直す事ができる。 という言葉から始まった、インターネットの2つの問題とIOSTについての講演でした。 問題1:人々は自分のデータを自分で持てない インターネットが登場したすぐ後、現在ITジャイアントとして知られている企業たちがインターネットの世界に城を作り、道を塞ぎ、あらゆるデータが自分たちの城を通してやりとりされるような仕組みを作った。これらのデータにプライバシーはなく、エンジニアやFBI等多くの人に見られてしまう問題があると述べました。 インターネット登場前は直接的に繋がっており、自分のデータは自分で所有していたが、現代はITジャイアント達が多くのデータを所有・コントロールしているとのことです。 問題2:データを動かす事ができない 次に、自分が作成したデータのはずなのに、企業によってロックされており自由に動かすことができない問題があると述べました。例えば、食べログのレビューデータは他のレビューアプリにシェア不可能です。データがシェアされないことで、イノベーションが阻害されたり、全体としての利益も減っていると考えているようです。 IOSTが問題を解決可能 インターネット登場から今までの時代は"インターネットの暗黒期"であり、全ての集権化されたサービスは"デジタルプリズン"であると述べました。 そして、IOSTではPoB(Proof of Belivability)という独自のコンセンサスアルゴリズムを使うことで、現在のブロックチェーンプラットフォームよりも高いレベルでの非集権化が可能になります。 【仮想通貨】IOST(アイオーエスティー)の特徴・将来性を徹底解説! by CryptoTimes ワークショップ: ブロックチェーンで問題解決 Terrence氏の講演後は、イベント参加者の学生達が2つのチーム(AチームとBチーム)に分かれてのワークショップでした。 以下のようなテーマから、現在世の中で問題となっていることを1つ選び、ブロックチェーンを活用した解決策をTerrence氏含めたIOSTメンバーに対して発表するといった流れで行われました。 貧困(病気、手当、労働、海外と先進国、、etc.) 健康(食べ物、薬、運動、ストレス、etc.) 教育(学歴成績、教科書、出席、教える、etc.) 慈善(ボランティア、募金、無料、etc.) 社会(業界、不正、詐欺、地方、高齢、マイノリティ、etc.) Aチームは「社会×ブロックチェーン」をテーマに「学術研究における著作権保護や文書紛失防止」を目的とした案を、Bチームは「教育×ブロックチェーン」をテーマに「地域やお金による教育格差を無くすこと」を目的としたトークンエコノミー案を発表しました。 IOST Terrence氏終わりの挨拶 Terrence氏の終わりの挨拶がとても心に残る内容だったので、短いですが原文と日本語訳を載せます。 I really believe the future will be made of many decentralized services and right now I think somehow is already happening. I think we can spread the world and we can help promoting the services. Right now is in early stage and there are many opportunities we can make. That’s why I’m here. I wanna spread the world and we can spread the world and maybe we can make some more decentralized services in the future. 日本語訳私は、これからたくさんの非集権サービスが登場することを強く信じている。もうすでに始まっているサービスもある。私達なら世界を広げ、それらの非集権サービスを世の中に浸透させることができる。(ブロックチェーンは)まだアーリーステージで、様々な機会を作る事ができる。だから私はここにいる。私は、非集権サービスを作ることを通して世界を広げたいし、私達ならそれができると思う。 まとめ 以上、11月8日に名古屋工業大学にて開催されたNITech AI研究センター×IOST「ブロックチェーン勉強会」のイベントレポートでした!

レポート
2018/11/18MALTA Blockchain Summit参加レポート / ブロックチェーン島・マルタを歩いてみて
マルタ共和国はイタリアの南、地中海中心部に浮かぶ小さな島国です。その大きさは東京都23区の半分・人口は約40万人で、ヨーロッパの人気観光名所のひとつとなっています。 イギリス連邦加盟国であるマルタでは、マルタ語と英語が公用語に定められており、日常会話レベルの英語が話せれば旅行する上で特に困ることはありません。 観光業で栄えるマルタのもうひとつの顔が、ブロックチェーン技術を国レベルで推進する「ブロックチェーンの島」としてのマルタです。 世界最大の仮想通貨取引所・Binance(バイナンス)が今年春にマルタに本拠地を移転したことをきっかけに、同国でのブロックチェーン関連事業の誘致に火がつきました。 今では、数々のブロックチェーン系企業が後を追うようにマルタでの法人設立に取り組んでいます。 Crypto Timesは、そんなマルタで11月初旬に開催されたイベント「マルタブロックチェーンサミット」にメディアパートナーとして参加し、「ブロックチェーンの島」の様子を徹底調査してきました。 マルタってどんなところ? 11月のマルタは日本では考えられないくらい暖かく、気温は昼夜常に18~25度くらいでした。割と湿気が高く、少し歩いただけで汗だくになってしまう感じでした。 カンファレンス開催の1日前に上陸したので、観光地として有名な海岸や港を散歩...のはずでしたが、絶賛雨男の記者は約4日半の滞在中、一度も晴空を見ることなく毎日豪雨に見舞われました。 [caption id="" align="aligncenter" width="526"] 雨が止んだ隙の一枚。カンファレンスが開催された「サン・ジュリアン」と、ホテル街のスリーマと呼ばれる地域の境目。[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="527"] 本当はこうなるはずでした。| シャッターストックより[/caption] 観光業が盛んなだけに、食べ物は基本的に美味しいものが多く、ファストフードはだいたい5~10ユーロ(650~1300円)、レストランは10ユーロ(1300円)から、という感じでした。 イギリス連邦加盟国であるマルタには、英国風パブ(日本の居酒屋的な存在)が至る所にあり、ビール一杯4ユーロ(500円)と、他のヨーロッパ諸国と比べると割と安めでした。 [caption id="" align="aligncenter" width="527"] 会場周辺のオシャレなレストラン。雨が降っていましたがせっかくなのでテラスで食べました。[/caption] ちなみに、マルタは観光先の他に英語の語学留学先としても人気が高いらしく、街中ではたくさんの日本人の方を見かけました。 ブロックチェーンの島・マルタ マルタの主要産業は電子・繊維・観光業の3本柱でしたが、近年ではブロックチェーン系産業がゲーミング・映画製作産業と共に急速な成長を遂げています。 同国は租税回避地(タックス・ヘイブン)としても有名で、関連規制も比較的緩いため、金融やブロックチェーン系の企業が集まりやすくなっています。 BinanceやOKEx、BitPayなどといった大手ブロックチェーン関連企業が揃って本拠地をマルタに移転したことを皮切りに、現在では多くの企業が後を追うように同国での法人設立を試みています。 ジョセフ・ムスカット首相率いる政府はブロックチェーン系イベントに積極的に参加したり、同技術を学ぶ学生に奨学金を給付するなどして「ブロックチェーンの島」をアピールしています。 [caption id="" align="aligncenter" width="522"] マルタブロックチェーンサミットで開幕のスピーチを行なったジョセフ・ムスカット首相[/caption] マルタブロックチェーンサミット ブロックチェーンの島・マルタでは、マルタブロックチェーンサミットと呼ばれる大型カンファレンスが11月1日・2日に開催されました。 Crypto Timesは参加者5000人以上の同カンファレンスにメディアパートナーとして潜入し、ブロックチェーンの島・マルタとヨーロッパの仮想通貨コミュニティの様子を見学してきました。 仮想通貨大国・マルタの大型カンファレンス「MALTA BLOCKCHAIN SUMMIT」が11月に開催 首相・金融大臣が自ら登壇・スピーチを行う [caption id="" align="aligncenter" width="635"] シルビオ・シェンブリ金融サービス大臣[/caption] 同サミットでは、初日にジョセフ・ムスカット首相、二日目にはシルビオ・シェンブリ金融サービス大臣が直々に登壇を行いました。 特に、シェンブリ金融大臣は、ブロックチェーンの島・マルタとしての世界的な立ち位置について触れ、今後の国内での規制整備について考えを発表しました。 「ブロックチェーン産業の中心地となれたことを誇りに思う」とした同氏は、「市場の誠実さ」「市場の安定性」「消費者保護」の三本柱を軸とした規制を展開していくとしました。 日本では、日本仮想通貨交換業協会、通称JVCEAと呼ばれる団体が認定協会に指定されており、この非政府団体の自主規制方針が国内におけるブロックチェーン技術の発展の鍵を握る傾向にあります。 対してマルタでは、政府のトップが自らカンファレンスに出向き、関連企業を海外から積極的に誘致しています。 国内企業を軸として法規制を固めていく日本と、比較的オープンな規制を魅力とした国外企業誘致に力を入れるマルタには、ブロックチェーン技術の発展戦略に大きな違いがあると感じました。 街全体によるブロックチェーン産業推進 [caption id="" align="aligncenter" width="525"] 会場付近の街並みに大きく掲示されたTRONの広告[/caption] マルタでは、ブロックチェーン技術の推進や関連企業の広告運動が他国に比べより大規模に行われていました。 カンファレンスが行われたサン・ジュリアンと呼ばれる街では、街中に大手プロジェクトの広告が大きく掲示されていました。 また、会場近くのレストランやバーと提携し、同業界に関わる人々が集まって食事を取れる場を提供する参加企業などもありました。 「ブロックチェーンの祖」や「AIロボット」も登壇 [caption id="" align="aligncenter" width="611"] ブロックチェーン技術の基礎を生み出したスコット・ストーネッタ氏[/caption] マルタブロックチェーンサミットでは、政府・EU議会や有名企業の重役が政治・法律・金融・ビジネス・技術といった様々なトピックについてプレゼンを行いました。 テクニカルなプレゼンテーションが大半でしたが、中にはブロックチェーン・フィンテック界の「大御所」がスピーチを行う場面もありました。 そんな大物スピーカーの一人が、1990年代にブロックチェーン技術の基礎を考案した「ブロックチェーンの祖」ことスコット・ストーネッタ氏です。 ストーネッタ氏の「ブロック・チェイン」に関する文献は、サトシ・ナカモトによるビットコインのホワイトペーパーで度々引用されています。 日本での勤務歴もある同氏は、ステージ上で流暢な日本語で「私はサトシ・ナカモトではありません」と公言しました。 また同カンファレンスでは、「人間以外の」スピーカーも現れ、来場客の注目を集めました。 世界で初めて市民権(サウジアラビア)を獲得したAIロボット・ソフィアは、ステージ上で彼女の能力を披露しました。 [caption id="" align="aligncenter" width="514"] 自身曰く、「サイボーグっぽさ」を出すために後頭部はわざと透明にしているとのこと。[/caption] ソフィアは、ブロックチェーン技術を活用したクラウドソースにアクセスすることで複雑な会話を理解したり、ヒトの表情を読み取ったりできるといいます。 そんな彼女は「世界中の分散型ネットワークを包括する分散型ネットワーク」の構築に憧れを抱いているといいます。 【MALTA BLOCKCHAIN SUMMIT 1日目】余談ですが、AIロボット・ソフィアは登壇早々開発者からの質問を無視し、3分間ほど硬直していました。インターネットの接続環境が悪く、ソフィアがクラウド上の情報にアクセスできなかったことが原因だそうです。 pic.twitter.com/bcS2sVdkny — CRYPTO TIMES@仮想通貨メディア (@CryptoTimes_mag) 2018年11月1日 まとめ ブロックチェーンの島・マルタは、国全体でブロックチェーン関連企業の誘致や技術の発展に力を入れている国であることが目に見えてわかりました。 首相・大臣らや、著名人(またはロボット)を招いた大型カンファレンスは、ただのビジネスの場ではなく、国の素晴らしさをアピールする良い機会となっていました。 こういった戦略は、もとから観光地・租税回避地として海外資産が行き来するマルタでこそできるものなのだろうとも思いました。

レポート
2018/11/16【イベントレポート】BlockChainJam 2018 – Ticket Peer to Peerの概要
10月21日に東京は六本木で、ブロックチェーン業界の最新プロジェクトや次世代の技術などが紹介されるワンデイイベント「BlockChainJam 2018」が開催されました。 当日はCryptoTimesもメディアパートナーとしてイベントに参加させていただきました。 今回はそのイベントの中から、「Ethereumなどからの比較の観点からみたNEMの性質や、NEMの応用例について」と題されたトピックのひとつとして紹介された「Ticket Peer to Peer」の概要を紹介していこうと思います。 プレゼンター 木村優氏 (株式会社LCNEM代表) 今回、NEMの応用例として「Ticket Peer to Peer」の紹介をしてくださったのは、同サービスの開発を行う株式会社LCNEMの代表取締役である木村優氏です。 BlockChainJam 2018ウェブサイトより BlockChainJam 2018のプレゼンター紹介には以下のように紹介されています。 ”京都大学経済学部4年。2018年より株式会社LCNEM代表取締役。日本の資金決済法に則ったパブリックブロックチェーン上の法定通貨移転システムや、経済的インセンティブとブロックチェーンをうまく利用して転売防止機能をつけたチケットシステムを開発。” ここで言及されている同氏が開発したチケットシステムというのが「Ticket Peer to Peer」です。 関連リンク 木村優氏 Twitter 木村優氏 ブログ 株式会社LCNEM 株式会社LCNEM 公式Twitter Ticket Peer to Peerとは? Ticket Peer to Peerとは、NEMブロックチェーンを利用して転売対策ができるチケット管理システムです。 Ticket Peer to Peerの3つの特徴 ① 転売対策が容易になる ② あらゆるサイトに埋め込みできる ③ あらゆる支払い方法に対応する ここからはそれぞれの特徴について説明していきます。 ① 転売対策が容易になる Ticket Peer to Peerの最大の特徴は、ブロックチェーンと経済学的インセンティブを活用することでチケットの転売対策を容易にすることです。 昨今のライブやコンサート、スポーツの試合観戦などのチケットの転売問題は加速するばかりですが、Ticket Peer to Peerはそのような問題に対するソリューションを提案しています。 ブロックチェーンと経済学的インセンティブが転売対策につながる仕組みについてはこの記事の後半で説明しています。 ② あらゆるサイトに埋め込みできる Ticket Peer to Peerはあらゆるウェブサイトに埋め込みをすることができるチケット管理システムです。 従来のネットでのチケット購入の際には、ユーザーは一度イベントのウェブページから別のチケット購入ページへ遷移しなければなりませんでした。 Ticket Peer to Peerではウェブサイトへの埋め込みを可能にすることによって、チケット購入の際のページ遷移の煩わしさを払拭しています。 ③ あらゆる支払い方法に対応する Ticket Peer to Peerでは様々な支払い方法をカスタムすることができます。 従来のチケットシステムには無かったビットコインなどの仮想通貨や、LCNEMなどのステーブルコインによる支払いが可能です。 Ticket Peer to Peerの革新的な仕組み ここからはイベント内にて木村氏より紹介された革新的な仕組みについて解説していきます。 アドレスをチケットとみなす発想 Ticket Peer to Peerではブロックチェーン上のアドレス自体がチケットとみなされ、この発想が革新的であるといいます。 これまでもブロックチェーンを応用したチケットシステムは考えられてきたそうですが、そのどれもがチケットとなる仮想通貨の取引を記録するという非効率なものばかりであったそうです。 しかし、Ticket Peer to Peerではアドレスそのものをチケットとみなすことでより効率的なチケット管理と転売対策を可能にしました。 このアドレスそのものをチケットとみなす仕組みについては現在特許申請中だそうです。 QRコードを活用する Ticket Peer to Peerのアドレス(=チケット)はなんらかのトランザクションを受け取った時点で無効になる性質があります。 そして実際のイベントにおいては、チケットとなるブロックチェーン上のアドレスをQRコードとして参加者に送信します。 こうすることで、誰もがこのQRコードを読み取り、そのアドレス(=チケット)に対してブロックチェーン帖で取引を送信することが可能になります。 つまり、誰もがチケットを無効化することができ、さらに誰がいつ最初に無効化したかがパブリックチェーン上に改ざん不可能な状態で公開されます。 このようにブロックチェーンを最大限に応用し、透明性のある転売対策が可能になります。 3つの経済学的インセンティブ Ticket Peer to Peerの転売対策の仕組みには3つの経済学的インセンティブが応用されています。 このあと解説する3つのインセンティブによって、さらに ここからは転売対策につながるそれぞれのインセンティブについて詳しく見ていきます。 経済学的インセンティブ1 まずチケットを転売する人は、本当にそのチケットを持っていることを証明する必要があります。 転売者からチケットを購入したい二次購入者としても、その転売者が本当にチケットを持っているのか確認できなければ、購入はしません。 しかし、Ticket Peer to Peerの場合、もしチケット(=アドレスのQRコード)を公開してしまうと誰もが無効化できてしまうので、転売者はチケットそのものの存在を隠したまま転売するインセンティブが働きます。 そうなると、二次購入者側から見ると本当にチケットを持っているのか確認ができないので、怪しさとリスクが募るばかりです。 結果として、転売者から二次購入をしないというインセンティブが働きます。 経済学的インセンティブ2 次は、もし仮に転売者からチケットを二次購入したとします。 チケットは誰でも無効化できることは説明しましたが、Ticket Peer to Peerではチケットの無効化(通報)を行うと追加報酬が発生する仕組みがあります。 なので、ここでは転売後に転売者自身が転売したチケットの無効化(通報)をするインセンティブが存在します。 これは二次購入者からすると、転売者からチケットを買ったのに結局ただの紙切れになってしまうリスクが存在します。 なのでこちらも結果として、転売者から二次購入をしないインセンティブが働きます。 経済学的インセンティブ3 Ticket Peer to Peerでは転売の通報を行うと報酬を得ることができます。 イベント運営側のパトロールに加え、正義感の強いファンによる通報が行われることが考えられます。 よって、ここでは転売を通報するインセンティブが働きます。 サイトへの埋め込みができる Ticket Peer to Peerは従来のシステムとは違い、あらゆるサイトへの埋め込みが可能です。 埋め込みの際のデザインや機能などもフルカスタマイズが可能で、Ticket Peer to Peerの埋め込みに必要なGoogle Apps Scriptが公開されており、詳細はこちらで確認できます。 この仕組みの利点は、チケットの購入から決済までがひとつのサイトで完結するということです。 従来のチケット決済では別のページへの遷移が必要であり、この一手間がユーザー行動に影響を及ぼし、イベント主催側とユーザー双方にとって良くない仕組みであると考えられています。 Ticket Peer to Peerではウェブサイトへの埋め込みを可能にすることによって、チケット購入の際の煩わしさを払拭しています。 従来の転売防止システムとの比較 ここからは従来の転売防止システムとの比較を見ていきましょう。 以下に木村氏が用意されていた比較表の内容をまとめて書き起こしました。 プラットフォーム 購入時 改札時 従来の転売防止システム 単一のプラットフォームに大きく依存 身分証明データと紐付け 身分証明データと照合 Ticket Peer to Peer ブロックチェーンを使った仕組みにより決済等を分離でき、プラットフォーム自体への依存が低い 身分証明データとの紐付けは必要なし QRコードを読み取るだけ それではひとつひとつ見ていきます。 プラットフォーム 従来の転売防止システムでは決済時に別サイトへの遷移などが必要でプラットフォームへの依存が大きかったようです。 Ticket Peer to Peerではプラットフォームへの依存が低く、決済等を分離して行うことができます。 購入時 従来のシステムではユーザーは購入時に身分証明データとの紐付けが必須でしたが、Ticket Peer to Peerではブロックチェーンを活用することで身分証明データとの紐付けは必要なくなります。 改札時 これまではチケットに紐付けされた身分証明データとの照合を行う必要がありましたが、こちらもTicket Peer to PeerではQRコードを読み取るだけで完了します。 BlockChainJam 2018で実際に使用されていました 今回紹介されたTicket Peer to Peerですが、実はBlockChainJam 2018で実際に使用されていました! 木村氏のブログによると、もともとはBlockChainJam 2018のために作ったシステムだったらしいのですが、一般化することに決めたそうです。 奇抜な発想でシステム作り上げました。 ステーブルコインとも絡ませていき、ブロックチェーンのマスアダプションを狙っていきます! https://t.co/SN4SRNHM0E — 木村優/Yu Kimura@LCNEM (@YuKimura45z) September 20, 2018 今後様々な機会に目にすることがあるかもしれませんね! まとめ 今回はBlockChainJam 2018にて紹介されたTicket Peer to Peerという転売防止チケット管理システムについてでした。 この革新的なシステムが広まれば、チケットの転売問題だけでなく、あらゆる二次購入や偽物被害などの問題へのソリューションとなるように思えます。 開発を手がけるLCNEM代表の木村氏も現役京大生と若い才能を感じさせ、これからのTicket Peer to Peerのさらなる躍進に期待が高まります! また、LCNEM代表木村優氏のブログではより詳しい解説記事を書かれていますので、気になる方はこちらからどうぞ↓ ちけっとピアツーピアの解説 - スペックの持ち腐れ

レポート
2018/11/01【イベントレポート】Blockchain-Nagoya #1 ブロックチェーン✕コミュニティ
10月26日、名古屋の株式会社スーパーアプリオフィスにて開催されたBlockchain-Nagoya ブロックチェーンとコミュニティというイベントに参加してきました! 本記事は、当イベントで登壇された株式会社Asobica CEOの今田氏と株式会社Gaudiy CEOの石川氏の講演をレポートとしてまとめたものになります。 Blockchain-Nagoyaと今回のイベントについて Blockchain-Nagoyaとは、名古屋を拠点として活動しているブロックチェーンに特化した団体で、東京、大阪、福岡などに集中しているブロックチェーン関連のイベントが名古屋でも行われやすいような環境作りを目的としています。 今回のイベントは、株式会社Asobica CEOの今田氏と株式会社Gaudiy CEOの石川氏をゲストに招き、ブロックチェーン×コミュニティをテーマにした話でした。 Blockchain-Nagoyaはこちら 株式会社Asobica CEOの今田氏の講演 プレゼンテーションは、コミュニティ×ブロックチェーンで世の中がどのように変わっていくのか、そしてAsobicaの提供するfeverというサービスについての話でした。 コミュニティとの出会いのお話 大学在学時に主催していた音楽フェスの事業でたくさんの赤字を作ってしまったことから、「持続的にビジネスを続けるには?」を考えたところ、コミュニティたどり着き、コミュニティについて考えたところ、 貢献した人に対して正当な報酬が支払われていないという不公平さ 1対N型の組織構造によりオーナーに依存してしまう持続性、発展性のなさ という2つの課題があることに気づいたようです。 また、これらの課題に対してブロックチェーンは最適なアプローチであり、ブロックチェーンとコミュニティが融合することで、これまで価値がついていなかったものやことに対して、第3者の承認なしで価値づけが行えると考えました。 あらゆるものがクローズド化され、コミュニティが増えていくお話 今田氏が考えるこれからの世の中は、世界規模でコミュニティが無数に増え、コミュニティの力が大きくなっていくというものでした。 若者のfacebook離れに代表されるように、現代はあらゆるものがクローズド化されていっています。若い世代はfacebookのようなオープンなコミュニケーションツールから、LINEグループやInstagram等のクローズド化されたツール内でのコミュニケーションに変わっていることからも、クローズド化の流れにあると言えます。 今田氏によれば、これからはコミュニケーションだけでなく、価値の交換もクローズド化されていくとのことです。インターネットの出現によりあらゆるサービスがコモディティ化した世の中では、サービスの価値は人で決まります。 そのため、身近な人や協力している人からサービスを受け、そのような人たちにサービスを提供する、村社会のような世の中に回帰するだろうと考えているようです。 feverのお話 feverの目的は、熱量を価値化し、好きなことで生きていく人を増やすことです。 現代のような資本主義社会では、評価軸がとても少なく、仕方なく嫌なことを続けながら生活している人も多くいます。それに対して、経済圏という形で評価軸を無数に増やして行くことにより、今までお金が回っていなかった場所でお金を回し、好きなことで生きていく人を増やすということです。 コミュニティ単位でコインを発行し、ユーザー同士の送り合いやコミュニティ貢献でコインを増やし、それを様々な特典と交換できるプラットフォームを提供することで、上であげた今までのコミュニテイが抱えていた問題を解決できます。 株式会社Gaudiy CEOの石川氏の講演 石川氏からは、まだローンチ前のプロダクトであるGaudiyについての未公開情報たっぷりの話でした。 Dappsはコミュニティを強固にできる話 「プロダクトを作る」ということに対して、コミュニティはすごく適しているため、大手企業や有名スタートアップもfacebookグループやslack等でユーザー間コミュニケーションをしやすくしています。 また、Dappsはストックオプションを渡しているような仕組みなので、今まで消費者でしかなかった人がプロダクトの参加者になり、結果コミュニティを強固なものにすることができるとのことです。ALISやCryptoKittiesが良い例です。 ただ、現状は、 コミュニティに特化したコミュニケーションツールがなく、みんな他プラットフォームを使っている Dappsを作ろうとしても、技術的に難しい という課題があります。 だからこそ、コミュニティに特化しながら、Dappsを使ったユーザーとの共創関係を簡単に作れるプラットフォームが必要だと考えているようです。 Gaudiyのお話 Gaudiyは、プロダクトやコミュニティ独自のコインを発行し、貢献度に応じてトークンが貰えたり、「貢献値」が蓄積・価値化されます。そしてトークン量や貢献値に応じて、そのプロダクトやコミュニティから優待がもらえるようです。 このように、インセンティブモデルがありながらコミュニティに特化したチャットフォームであり、また、ユーザーが当事者意識を持ちやすいような様々な仕組みも実装される予定のようです。 sota まだ未公開の情報が多いため、書ける部分のみまとめました。 まとめ 以上、10月26日に開催された「Blockcahin-Nagoya ブロックチェーンとコミュニティ」のイベントレポートでした! 現状、名古屋でブロックチェーンのイベントが開催されることはとても珍しいことですが、これから名古屋のブロックチェーンコミュニティが発展することを期待しています! Blockchain-Nagoyaはこちら
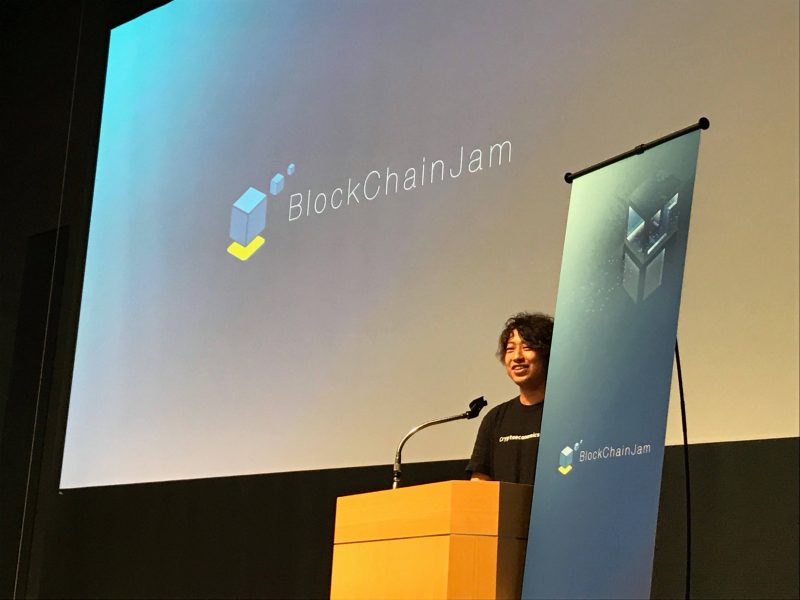
レポート
2018/10/30【イベントレポート】BlockChainJam 2018 『Ethereumの最前線』
10月21日(日曜日)に東京・六本木で、国内外のプロジェクトや技術の最新のトレンドが紹介されるイベントである「BlockChainJam 2018」が開催されました。 イベントにはほぼ満席となるオーディエンスも集まり、ブロックチェーン周りの最新の情報やトレンドに対して、興味深々な様子でした。 CryptoTimesでもこのイベントにメディアパートナーとして参加しましたので、本記事ではラインナップの一つである『Ethereumの最前線』についてを紹介していこうと思います。 プレゼンター 落合渉悟氏 Ethereumの最新のトレンド追いかける中で、Cryptoeconomics LabのCTOとして活動を行っています。 イベント公式サイトには以下のような紹介がされています。 Ethereum、Plasma、zk-SNARKsを専門とするブロックチェーンエンジニア。現在のEthereum開発の基盤となっているCryptoeconomicsに不可欠なStakingやFormal Verificationに関するOSS活動を中心にアジア地域の暗号通貨プロジェクトと協業を多数行っている。マイブームは、RustとIsabelle/HOL。 以下は関連リンクになります。 株式会社Cryptoeconomics Lab Twitter Ethereumの最前線 今回の落合氏によるプレゼンテーションは、技術的な部分に寄せた内容となっていました。 そのため、このプレゼンテーションは質疑応答の形式で行われ、事前に3つの質問が用意されそれをかみ砕きながら複雑な最新技術の概要がわかりやすく紹介されていきました。 様々なスケーリングソリューションが出てくるが、我々はSolidityだけをやっていれば良いのだろうか? 結論から言うとNOであるようです。 落合氏は、現在世界中で開発が進められている Sharding(シャーディング) Plasma(プラズマ) General-State-Channel(ステートチャネル) の3つのスケーリングソリューションについてSolidityを利用した場合のドローバックと周辺の技術仕様の解説を行いました。 プレゼンの内容を確認する前にこれらの技術の概要だけを簡単に把握しておきましょう(内容がかなりテクニカルになっているため)。 #Sharding(シャーディング) Sharding(シャーディング)は、ノードやトランザクションを小さなグループに分けることで並列的に検証作業を行うことが可能になりスケーラビリティ問題の解決策の一つとして注目されています。 #Plasma(プラズマ) Plasma(プラズマ)は、サイドチェーンを利用したソリューションで、スマートコントラクトを利用してメインチェーンとのリレーを行うサイドチェーンを階層的に創り上げることでスケーラビリティ問題の解決を目指します。 #General-State-Channel(ステートチャネル) Raiden(ライデン)やLightning Network(ライトニングネットワーク)などがステートチャネルを利用した技術として有名ですが、このソリューションではトランザクションをオフチェーンで行うことでメインチェーンに対する負担を軽減するようなアプローチがとられています。 一方で、Solidityだけを使ってこれらの実装を目指すのはスライドにもある通り、いくつかのドローバックを伴うようです。 Sharding(シャーディング)とSolidity 現在、Ethereumでは昨日のアップグレードが延期されたCapserとSharding周りの技術を盛り込んだものを融合したShasper(Ethereum2.0)の開発が進められています。 落合氏は先日、同じくEthereumのスケーラビリティ問題に関する研究を行っているPrysmatic Labの森さんと議論を行ったようですが、その中でSolidityを利用してコントラクトを呼び出す際に最大性能が引き出せないことがあるようです。 ちなみに、紹介されている『Hotel&Train Problem』というものですが、これは電車とホテルの予約をする際にこの予約の結果を成功もしくは失敗で一致させようとする際、電車とホテルの予約が別のシャードに存在した場合(Shardをまたいだ一括TXs)、Atomicityが犠牲となってしまうという問題です。 Plasma(プラズマ)とセキュリティ 最初のPlasmaのコンセプトとして紹介されたのは『EVM Plasma』と呼ばれるものです。 スライドにもある通り、EVMを使うことのできるPlasmaはExitのコストが高くなるためParity BridgeなどのPoAを利用して実装するような形となってしまいます。 しかし、この場合EVMと互換性のあるチェーンとメインチェーン間でお金を移動できるという話になってしまうので、Ethereumの分散性やセキュリティを生かし切れていないことになると言えます。 続いて紹介されたのが、『PlasmaLeap』と呼ばれるコンセプトです。 Dogethereumなどでも有名なTruebitですが、このPlasmaLeapは先ほどのEVM PlasmaでExitに高額なコストがかかるという問題へのソリューションの参考とされているようです。 落合氏の説明によれば、Truebitを参考にしたこの仕組みでは、「全ノードが検証を行う代わりに一人に対して検証をさせる」という仕組みを取っています。 確かにExit自体は安く行うことができるようですが、このソリューションの場合新たにセカンドレイヤーに対する攻撃インセンティブを生み出す可能性があるため、Ethereumのセキュリティを完全に引き継いでいるとはいえず、新たにセカンドレイヤーにCryptoeconomicsが生まれるという状況になります。 3つめのPlasmaとして紹介されたのが『Plasma snapp』と呼ばれるものです。 説明によれば、zk-SNARKsのSNARK Proofを利用することで、Plasmaの子チェーンのノードにおける不正が行われていないかどうかを確認することができるようです。 Plasma CashはトークンのIDを利用したものになりますが、EVM PlasmaやPlasma Leapなどと違いEthereumのメインチェーンのセキュリティを完全に引きついだ設計となっています。 しかし、マルチシグやDEXのような処理はSolidity一つでは書けるロジックではないようです。 Plasma CashにDEXなどのDAppを埋め込もうとすると先ほどのスライドでもあった通り、”PlasmaのResearcherが必要になり大がかりなものになってしまう”とありましたが、落合氏によれば、Plasma CashにDAppを埋め込んだものを生成するPlasma Generatorと呼ばれるフレームワークの可能性が注目されているようです。 このフレームワークと相性のいい言語としてBitcoinのivy langと呼ばれる言語と相性がいいそうで、Plasma Solidityとして注目されているとのことです。 EthereumのScalingがもう少しかかりそうなので、EOSや自前オフチェーンに逃げちゃって良いのだろうか? Ethereum以外にもEOS、ZIL、TEZ、NEM、NEOなどがありますが、これらはそれぞれ中央集権性や表現力、コントラクトのイディオムの整い方が大きく異なるので使い道も異なるようです。 結論から言うとサイファーパンク(Cypherpunk)でないのならばEthereum以外を選んでしまって構わないということに加えて、オープンソースのデータ蓄積という点を考えるとパブリックチェーンを選んでいくべきということでした。 以上のテーブルではそれぞれのチェーンの性能比較が行われていますが、落合氏はいくつかの例を使ってどのようなチェーンを利用すべきかという点についても言及していきます。 法人案件で、自社でお客さんのお金を管理したくないとか、パブリックチェーンを使いたいという要望があったら? => EOS・自前のオフチェーン トラストレスで簡単なゲームや金融系の仕組みを作りたくて、表現できるものは少し少なくてもよく、メインネットローンチまで待てる場合 => ZIL チューリング完全なスマコン言語、かつハードフォークが少なく投票方式すら変えられる長期視点なもの。Big blockでスケーリングする。 => TEZ まとめ タイトルの通りEthereumの最前線で活躍する落合氏によるプレゼンテーションをまとめました。 落合氏は、将来に関して過渡的に様々なチェーンに開発者が分散していくことを予想しており、真に分散性を必要とするのかどうかという問いがスケーリング問題によって暴かれる年になるだろうと予測しています。 また、スマートコントラクトの開発自体もSolidityだけで完結するものではなくなってきているとのことです。 技術的にレベルが高く追いつくのも精一杯という感じでしたが、Ethereumに関してとても面白い話が聞けました。 ありがとうございました!

レポート
2018/09/28Stacktical(スタックティカル) Parisミートアップレポート
Crypto Timesは、9月11日にフランス・パリにて開催されたStacktical(スタックティカル)のミートアップにメディアパートナーとして参加しました。 同イベントでは、近頃注目されているDevOps(デブオプス)とスマートコントラクト開発環境の関係性についてディスカッションが行われました。 DevOps(デブオプス)とは? 今回のプレゼンテーションの主題であるDevOps(デブオプス)とは、ソフトウェアの開発チーム(Development)と、サービスの監視・運営チーム(Operations)が円滑にフィードバックをし合うことで、不具合への迅速な対応や、質の高いサービス提供を実現する、という概念を指します。 開発の計画、コーディング、ソフトウェア構築、テスティングを開発部が行い、運営部がリリースされたソフトウェアを監視・開発部へフィードバックする、というのが大まかな流れとなっています。 同イベントでスピーカーを務めたStackticalのJean-Daniel Bussy氏は、DevOpsはDappsの開発環境にも適用できると言います。 「ブロックチェーン系サービスの開発でも、DevOpsならぬBlockOpsを意識することで、サービスの質を大きく向上させることができます」 と語ったBussy氏は、DevOpsの概念に当てはめたスマートコントラクト開発の手順を解説しました。 まず、開発の全てはプログラミングから始まり、続いてソフトウェアの入念なセキュリティチェックを行います。 自社でのセキュリティチェックが終わると、今度はソフトウェアを外部にリリースし、そこで更に脆弱性をチェックします。 その後、開発から運営への移り変わりとして、テストネットを公開し、運営チームは不具合等の監視、および開発チームへのフィードバックを行います。 不具合やフィードバックが開発チームに報告されると、振り出しに戻り、新たなアップデートのプログラミングに取り掛かります。 Bussy氏によれば、BlockOpsを意識することで、不具合やアップデートなどによるサービスの停止期間(ダウンタイム)を短縮でき、サービスの質の向上に繋がるといいます。 円滑なDevOpsを促進するプロジェクト・Stacktical DApps開発環境におけるDevOpsの応用に関するディスカッションの後には、トークンメカニズムを応用してDevOpsを促進するプロジェクト、Stacktical(スタックティカル)が紹介されました。 開発・運営チーム間の連携がうまく取れると、不具合によるサービス停止期間(ダウンタイム)が短くなり、必然的にサービスへの信用が生まれます。 一方で、ダウンタイムをゼロにする、というのはほぼ不可能かつ膨大なコストを要するもので、サービス運営側にとって合理的な選択とは言えません。 そこで、サービス提供者にダウンタイム削減のインセンティブを与えつつ、ダウンタイム発生時にはサービス利用者に補償を行う、というシステムを開発しているのがStacktical(スタックティカル)です。 同システムは、サービスレベル規約(SLA)に見合ったサービス提供者にトークン報酬を与え、不具合などが発生した際にはSLAに応じてサービス利用者にトークンで補償が行われる仕組みになっています。 サービスレベル規約(Service Level Agreement)とは?ITサービス提供者と委託者の間で、サービスの一定の品質を保つための運営ルールや、それが実現できなかった時の対処などを明確にした規約のこと。 ダウンタイムの削減に際する報酬は、サービス提供者にとってDevOpsの連携を強化するインセンティブとなります。 また、サービスの利用者はSLAに基づいた補償をトークンで受け取ることができ、それをさらにプラットフォーム内で使用したり、ウォレットに送金したりできるとされています。 まとめ 今回のイベントには、ブロックチェーンについて学び始めたばかりの人から投資家・エンジニアまで、幅広い層の客が訪れました。 近頃話題に上がるソフトウェア開発手法「DevOps」とブロックチェーン技術に焦点を当てた同イベントは、他のミートアップとはまた違う面白みがありました。 スマートコントラクトを使用したサービスレベル規約施行システムを開発するStackticalは、今月25日~28日にかけて行われる金融庁・日経新聞共同主催のFIN/SUM 2018のスピーカーも務めています。

レポート
2018/09/07【イベントレポート】Coldlar(風神Wallet):安全に仮想通貨ライフを送るために
8月28日、東京・品川プリンスホテルで行われた「日中ブロックチェーン交流会」と呼ばれるイベントが開催されました。 本記事は、当イベントの最後を飾った仮想通貨ウォレット「ColdLar(風神ウォレット)」による講演をレポートとしてまとめたものになります。 同イベントのIOTW講演に関しての記事は以下をご覧ください。 【イベントレポート】IOTW – IOTとブロックチェーン技術の融和について - CRYPTO TIMES Coldlar CMO Wendy Wang氏による講演 プレゼンテーションは従来のウォレットの種類とColdlarのウォレット、またその比較解説から始まりました。 今回はノードの種類だと複雑になってしまうということもあり、インターネット接続の有無がポイントをしてプレゼンは進んでいきます。 インターネット接続の有無で分けるとウォレットは以下の3つの種類に分類されます。 ホットウォレット コールドウォレット Coldlarウォレット ■ホットウォレット ホットウォレットでは、秘密鍵(プライベートキー)はウォレットに保管され、インターネットに接続されています。 持ち運び、管理、復元が容易で複数の端末にも対応している一方で、攻撃に対して脆弱であることが懸念として考えられます。 ■コールドウォレット コールドウォレットでは、秘密鍵(プライベートキー)はウォレットに保管されますが、インターネットからは切断されています。 セキュリティ面では非常に優れている一方で、トランザクション効率が低く更新や管理が面倒な点などが弱点として挙げられます。 ■Coldlarウォレット Coldlarウォレットは上記ホットウォレットとコールドウォレットそれぞれの利点だけを取ったハイブリッド型のウォレットとして定義することができます。 独自のセキュリティ構造やアルゴリズムにより。ユーザビリティや安全性が保証されている上、スケーラビリティや多くの通貨との互換性を持ちます。 これまで、ホットウォレット・コールドウォレットそれぞれにメリットやドローバックがあり、どちらかを選択する必要、用途によって使い分ける必要がありましたがColdlarウォレットを使うことでこれらの問題を解決することができます。 そんなColdlarウォレットですが、2016年11月にブロックチェーン上の資産を安全に保管するためのソリューションとして生み出されました。 2017年末に1000万USDの資金調達が完了し、EU、CE、EU EoHS、FCC、Japan PSEなどでの特許を既に取得しています。 Coldlarウォレットによれば、ハードウェアウォレットの理想として以下の3つの基準があるとします。 セキュリティ ユーザビリティ 進化可能か否か これらの基準は過去に起きた事例をもとに設定されています。 例えば、上のスライドではセキュリティに関するこれまでの事例がいくつか紹介されています。 2017年7月、ハッカーがスマートコントラクトの脆弱性を付き、150,000ETHを盗んだ事件、その他にも2018年2月、2018年7月にウォレットの脆弱性をついた事件が起こっています。 Coldlarウォレットではこれらのセキュリティを原因とする事件に対して多角的なセキュリティのアプローチでこれを防ぎます。 これは、設計、システムアルゴリズム、物理的の3つのセキュリティアプローチからなります。 Coldlarウォレットの設計では、トランザクションの生成や署名はオフラインで行われます。一方で、トランザクションのブロードキャストや残高の照会はオンラインのアプリ(スマホ)で行われます。 そして、オフライン端末であるColdlarウォレットとオンラインのスマホアプリがQRコードで相互に認証しあう形でセキュリティが担保されるので、従来のホットウォレットとコールドウォレットを組み合わせたような設計となっています。 システムアルゴリズム的なセキュリティのアプローチには、以下の4つの特徴があります。 Private Key Calculator(秘密鍵計算) Hierarchical Deterministic(階層的決定性) Burn After Use(バーン) Multi-Signature Algorithm(マルチシグネチャ) 階層的決定性、俗に言うHDウォレットやマルチシグネチャなどは他のウォレットでも見られる機能となっていますが、秘密鍵に関してこれが使い捨てである点(Burn)などに関してはColdlarウォレット独自のものとなっています。 まとめ 日中ブロックチェーン交流会でのColdlarウォレットのプレゼンテーションをまとめました。 セキュリティを担保するアプローチが非常に独特かつ堅牢であることが特徴です。 Coldlarウォレットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。 世界最強のハードウェアウォレット!風神ウォレットの特徴・使い方を解説! - CRYPTO TIMES

レポート
2018/08/31【イベントレポート】IOTW – IOTとブロックチェーン技術の融和について
8月28日、東京・品川プリンスホテルにて「日中ブロックチェーン交流会」と呼ばれるイベントが開催されました。 CryptoTimesでもこのイベントに参加させていただきましたが、会場には200人を超えるオーディエンスが集まっており、非常に大きな盛り上がりを見せていました。 本記事では、そんな数あるプレゼンテーションの中から、CryptoTimesでも以前紹介させていただいたIoTデバイスを利用したプロジェクトである「IOTW」のプレゼンテーションをまとめていきます。 「IOTW」って何?って方は、以下の記事も是非ご覧ください。 IOTW – IoT機器でマイニングができるプロジェクト - CRYPTO TIMES IOTW CEO Fred Leung氏による講演 IOTWではビジョンとして2020年までに「500億のIoTデバイスにブロックチェーンを導入すること」を目指しています。 これにより、効率的な分散化と即座のトランザクション執行を実現することができると語ります。 現状、ビットコインやその他コインの採用するアルゴリズムには主に以下の2つの問題があります。 非常に高い計算能力と高価なハードウェア 取引速度が遅い IOTWではProof of Assignment (PoA)と呼ばれるアルゴリズム、またマイクロマイニングを利用することで、どんなIoTデバイスであってもマイニングを行うことが可能となります。 更に取引速度に関しても100,000TPS以上を実現することが可能です。 以下はトランザクション速度の比較になります。 RippleやEOSなどはもちろん、PaypalやVisaなどの既存の決済インフラにも勝るTPSであることがわかりますね。 IOTWが持つ技術仕様は、このように非常に優れていることがわかりましたが実需面やトークンの価値はどのように裏付けられるのでしょうか? トークンの主な価値はIoTデバイスが日々生み出すビッグデータにあります。 現段階でも、1億のIoTデバイス向けのWifiチップの生産が行われていますが、これらはマイニングを行うだけでなく各デバイスからデータを収集することが可能です。 収集されたデータは、それらを必要とする企業間でトークンを使ってやり取りされるため、これがトークンに対する需要となります。 通常の場合だと、SonyはSonyのIoTデバイス、PanasonicはPanasonicのIoTデバイスにしかアクセスすることができません。 しかし、IOTWトークンを利用することで、これらの企業は互いのデバイスから得られる情報に相互にアクセスすることができるようになります。 IOTWの収益は、これらの情報の売買プロセス、ユーザーのTXs際に発生するTXs手数料の一部となっています。 消費者がIOTWのトークンをEコマースで支払いの手段として利用と書きましたが、IOTWでは既に「The California Wine Company Limited」や「Bortex」など4社と協力関係を結んでいるようです。 その他にも、Wifiのチップ生産に関してExpressifやRealtekと既に提携を結んでいますが、それ以上に1億以上のユニットの生産が完了している点などは注目すべき点の一つです。 経営陣に関しても、多くの経験を持つ人物がそろっています。 創設者兼CTOであるPeter Chan氏はProof of Assignment(PoA)の開発者で現在は20以上の特許を保有しています。また、その一部は香港の政府からも認められています。 Dr. Patrick氏はアカデミックなバックグラウンドを持ち、現在も香港大学で教授として活躍しています。 まとめ 「日中ブロックチェーン交流会」のIOTWの講演の内容やその様子をまとめました。 IOTWの目指す500億以上のIoTデバイスを繋げるという構想は、現状のチップ生産などを見ても期待することができそうですね。 このプロジェクトに関して興味を持った方は、ぜひプロジェクトの紹介記事もご覧ください。

レポート
2018/08/27【イベントレポート】Ontology MainNet Launch Tokyo 20180825
8月25日、東京汐留にて、実社会でのブロックチェーンインフラ構築を目指すDApps開発プラットフォームであるOntologyのイベント「Ontology MainNet Launch Tokyo」が開催されました。 Crypto Timesでもこのイベントに参加し、創設者であるJun Li氏にインタビューなども行いました。 本記事では、イベントでのスピーチの概要やJun Li氏とのインタビューに関してをまとめていきます。便宜上パネルディスカッションやプロジェクトのピッチは割愛させていただきます。 Ontologyに関してもっと詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。 Ontology / ONTの特徴・将来性を解説!取引所・チャート情報まとめ - CRYPTO TIMES Ontology創設者のJun Li氏によるスピーチ イベントの最初には創設者であるJun Li氏によるインフラの重要性やOntologyのプロダクトに関するスピーチが展開されました。 創設者のJun Li氏は、まず「ブロックチェーン技術がメインストリームとなり得るのか?」という切り口でスピーチを始めました。 彼は、ブロックチェーンがインターネットのように広く普及してくためには、実社会との連携が必要であると語ります。現在のところ、例えば机のトークン化を行うとき、この価値を移動するためにはトークンの移動だけでなく机という実体の移動も必要となります。 Ontologyはこのようにデジタル化されたデータなどと実際の人やモノなどの連携を効率よく図るためのインフラ構築を目指しています。 続いて、今年6月30日にメインネットのローンチが行われたOntology 1.0がいかにこのインフラを構築していくのかというスピーチに移ります。 今回メインネットのローンチが行われたOntology1.0は以下の要素によって構成されます。 Ontology Infrastructure ONT Blockchains ONT Blockchain Frameworks ONT Interaction Protocols Ontology Modules and Protocols ONT ID ONT Data ONT Scores Ontology Common Applications ONTO ONT TSE (Trust Search Engine) ONT DDXF (Distributed Data Exchange Framework) またJun Li氏によれば、Ontologyは今年スケジュール通りにメインネットのローンチを行ったプロジェクトはOntologyだけであると語っていました。Ontologyの開発がいかに順調であるかという点に関しても十分に安心することができます。 その後プレゼンテーションはOntologyの技術的な話が続きます。 こちらに関しては、プロジェクトの解説記事などにも紹介されているので本レポートでは割愛させていただきます。 Mathias Glintborg氏による開発者コミュニティの紹介 次にGlobal Development ManagerのMathias Glintborg氏による開発者コミュニティの紹介が行われました。 Mathias氏によれば、Ontologyの特徴の一つである多用な開発言語により、ブロックチェーンデベロッパでなくても開発を行うことができるようです。 また、Ontologyでは開発言語の障壁だけでなく、SDKの使いやすさなども特徴としており、開発者コミュニティは学生なども参加するなど盛り上がっているようです。 Ontologyの発行枚数は10億枚となっていますが、このうちの10%である1億枚は開発者コミュニティに割り当てられています。 このように、コミュニティに対して十分にインセンティブを与えることに成功しており、Chromeの拡張機能など多くのプロダクトが事実としてコミュニティにより開発が進められています。 創設者のJun Li氏にインタビュー イベントの終了後、Ontologyの創設者であるJun Li氏はCrypto Timesのインタビューにも快く引き受けてくださいました。 以下はインタビューの内容になります。 -- 今回は東京でのミートアップ開催お疲れ様でした。2日間実施してみて、日本に対してどういうイメージをお持ちになりましたか? Jun Li氏 : ここ2日間連日でイベントを開催することができましたが、日本のコミュニティは中国国内と比較しても、とてもアツいと思いました。 先ほどの質疑応答の際も非常に高度な質問を受け、日本のコミュニティのブロックチェーンに対する真剣な姿勢を感じることができました。今後は日本との連携もより一層深めていきたいです。 -- ありがとうございます。今回、メインネットがローンチし、Ontologyのエコシステム構築に関して色々なプロジェクトとのパートナーシップも発表されていますが、今後の展望とかはいかがでしょうか? Jun Li氏 : 私たちは、現時点で主に2つの戦略があります。 1つはインフラの整備を引き続き進めていくことです。もう1つは、言うまでもなくエコシステムの構築です。Ontologyのブロックチェーン上により多くのアプリなどを走らせることを目指しています。 しかし、これは私たちだけで行うことは難しいので、他の産業の専門的なチームと連携してこの戦略の実現に向けて現在動いています。 -- 今回、日本の企業もイベントに参加していたと思うのですが、Ontologyはビジネスユースのため安全に個別管理できる(プライベート)ブロックチェーンを作成して、それらを相互に(部分的に)接続するために作られたと思います。日本でも今後、色々と普及していくことを考えてよいのでしょうか? Jun Li氏 : はい。日本に普及をさせていく準備はできています。Ontologyのベース自体は中国国内にありますが、この技術は日本の政府や企業に利用していただくことを考えており、日本向けにも私たちのソリューションを提供していきます。 Ontologyのブロックチェーンはオープンソースですので、公的なサービスから政府系のサービスまで十分に利用していただけます。 -- 今回のイベント内でのピッチでも、いくつかのプロジェクトが提携先として紹介されていました。他にも多くのプラットフォームがある中で、これらのプロジェクトを選ぶ基準、またそれらのプロジェクトがOntologyをプラットフォームとして選択する基準や理由はありますか? Jun Li氏 : プロジェクトが数あるプラットフォームの中からOntologyを選択する理由は、Ontologyが持つ高いパフォーマンスやスマートコントラクトを実装する際のコストなどが挙げられます。 また、新たに開発を行う際の容易さなども考えられると思います。OntologyではPythonやC#などの多くの言語に対応していること、より多くのSDKやAPIなども要因として挙げられます。 さらには、Ontologyがインキュベーションのサービスや技術的なサポートを提供していることなどがそれらのアプリがOntologyを選択する理由の一つでもあります。 EthereumやEOSなどが競合として挙げられますが、これらの技術的なサポートなどをそれらのプラットフォームで術減することは難しく、これは一つのOntologyとしてのアドバンテージでもあります。 まとめ 今回は、Ontology MainNet Launch Tokyoのイベントをレポート形式でまとめました。 2日間に渡るOntologyのイベントは開場にも沢山の人が入っており、大成功と言えたでしょう。 メインネットをローンチし、今後のOntologyのエコシステム普及に対しての期待も高まります。

レポート
2018/08/14【イベントレポート】2018年8月10日 Crypto Kitties(クリプトキティーズ) 東京ミートアップ
今月10日、東京・渋谷にて、イーサリアムの非代替型トークン(NFT)規格を利用した人気DAppゲームであるCryptoKitties(クリプトキティーズ)の初来日ミートアップが開催されました。 今回のイベントでは、クリプトキティーズのサービス内容や開発に至った経緯に加え、モバイル版アプリや新プロジェクト、HTCとの提携などについても説明が行われました。 共同創設者のBenny Giang氏のユーモアある講演に加え、ステッカーやTシャツなどのプレゼントもあり、終始楽しめるミートアップでした。 クリプトキティーズとは? クリプトキティーズは、イーサリアムのトークン規格であるERC-721を利用した「猫育成ゲーム」です。 ERC-721とは、非代替型(=一枚一枚の価値が違う)トークンを作成できる規格で、クリプトキティーズではそれぞれ異なった模様や形をした猫がトークンとして表されています。 Ethereum(イーサリアム)の”ERC”って何?メジャーな規格を徹底解説! ゲーム上には緻密な「遺伝子メカニズム」が組み込まれており、猫を繁殖させることで親やその上の世代の遺伝的特徴を受け継いだ子猫が生まれてきます。 ゲーム上の遺伝子は本物と同じように優性・劣性に分かれており、特定の遺伝子を組み合わせると「スペシャルにゃんこ」も生まれてきます。 それぞれの猫はトークンで表されているため、他の仮想通貨と取引することができます。 レアな猫をコレクションとして集めたり、高額で売却したりできることからこのゲームには人気に火がつき、一時期はイーサリアムネットワーク全体に遅延を生じさせてしまうほどでした。 創設者が語る「クリプトキティーズ」 [caption id="" align="aligncenter" width="560"] 猫Tシャツ・短パン・猫耳で登場した共同創設者のGiang氏。[/caption] 今回のミートアップでのメインイベントは、クリプトキティーズ共同創設者のBenny Giang氏による講演でした。 Giang氏は、プロジェクト開発に至った経緯や、DAppゲームが秘めるポテンシャル、更には「クリプトコレクティブル」が世界に与えるインパクトについて語りました。 クリプトキティーズ開発に至った経緯 Giang氏は、クリプトキティーズを開発した理由は「ブロックチェーンを楽しく、アクセシブルなものにしたかった」からだと語りました。 ブロックチェーン技術はその複雑さから一般的な普及が難しくなっていますが、クリプトキティーズのようなゲームがあれば、確かにこの技術をより身近に感じることができるといえるでしょう。 ブロックチェーン上にゲームを作るメリットとは? ブロックチェーンと聞くと、ビジネスや金融、ガバナンスなどへの応用例ばかり浮かびますが、ゲームをブロックチェーン・ネットワーク上に作る意味はあるのでしょうか? Giang氏は、ブロックチェーン技術を利用することでオンラインのゲームを半永久的に残しておくことができると語りました。 従来のサーバー・クライアント型のオンラインゲームでは、運営者が運営を廃止すると、育てたキャラクターなどのデータもろとも、ゲーム全てが消え去ってしまいます。 対して記録されたデータの変更が不可能であるブロックチェーンであれば、ネットワークが維持される限り運営者の存続に関係なくゲームは残り続けます。 クリプトキティーズは、データ(猫)をブロックチェーン上で半永久的に保存する、DAppゲームのメリットを宣伝する先駆者でもあるということです。 デジタルアートに価値がつく時代 Giang氏は、クリプトキティーズのような「クリプトコレクティブル」が世界に与える影響についても語りました。 「ブロックチェーンの登場により、デジタル上で生み出されたアートに価値がつく時代が到来しています。」 と語るGiang氏は、クリプトキティーズのように、デジタル上のコンテンツを実世界のアートなどのようにコレクションとして取り扱うことができると話しました。 現にクリプトキティーズは、ジェネシス(一番最初に生まれた猫)を10万ドルで売却しています。 また、レア度の高い猫を売却して病院や環境保護活動の資金を調達するなどといった事例もあり、デジタル資産が実世界のモノと同様に価値を帯びるようになってきていることが解説されました。 ミートアップで発表された注目情報を紹介! 今回のミートアップでは、プロジェクトの紹介以外にも、クリプトキティーズについての注目情報も公開されました。 アンドロイド版アプリ・HTCとの提携について これまではウェブ上でのみ存在したクリプトキティーズですが、8月11日をもってアンドロイド版アプリを公開し、スマートフォンからでも遊べるようになりました。 iOS版の公開日程については詳しく発表されることはありませんでした。 また、クリプトキティーズは台湾の大手電子機器メーカー・HTCと提携を結び、U12+と呼ばれる機種のプリセットとしてゲームがインストールされるもようです。 新プロジェクト「KittyVerse」 また、当イベントではクリプトキティーズの新プロジェクト・KittyVerse(キティバース)についても解説がありました。 このプロジェクトは、所有する猫をキャラクターとして使えるゲームの開発促進・共有を行うスペースで、ゲームプレイ・開発共に本家許可なしで行えるというものです。 クリプトキティーズではこのようなゲームの開発者に助成金も配布すると発表しています。 まとめ 終始笑いの絶えない、楽しめるプレゼンを提供してくださったGiang氏は、 「次はもっとビッグなイベントをやりたい。本物の猫とか、バウンシーキャッスルとかも導入して盛り上げていきたい」 と遊ぶ気満々のコメントをしています。 また、イベントの終わりには、一番大きな声で「ミャオ」と叫んだ人に限定Tシャツ一枚をプレゼントするという謎のサプライズもありました。 今回の記事を読んでクリプトキティーズについて気になった方は、ぜひ公式サイトもチェックしてみてください。 公式サイトはこちら


















 有料記事
有料記事


