
技術
2023/06/03BRC-20とは?ビットコイン上で通貨の発行を可能にする技術を解説
BRC-20は、ビットコインのブロックチェーン上に存在するトークンです。 実験的なトークンでありながら、関連トークンの時価総額は4億ドルを超えている状態です。 また、基盤となったOrdinalsのNFTについても注目が集まっています。 この記事では、そんなBRC-20やOrdinalsについて以下の観点から解説しています。 この記事のまとめ ・BRC-20はビットコイン上のトークン ・ビットコインのブロックチェーンに影響を与える勢い ・Ordinalsの仕組みを応用 ・ERC-20とは大きく異なる BRC-20とは?ビットコインのトークン BRC-20は、ビットコイン上のトークン規格です。 イーサリアムなどでは、ブロックチェーン上をさまざまなトークンが行き交うことが一般的です。 一方で、ビットコインのブロックチェーンには、BRC-20のようなトークン規格がこれまで存在せず、主な用途はBTCの送受信といったシンプルな用途に限られていました。 しかし、Ordinalsと呼ばれるプロトコルの登場により、ビットコイン上でBRC-20やNFTの発行が容易となり、昨今大きな注目を集めています。 2023年5月時点で、24,000件を超えるBRC-20トークンが確認でき、全体の時価総額は4億ドルを超えている状態です。 (引用元:brc-20.io) また、BRC-20の基盤となっているOrdinalsのインスクリプション(inscriptions)も4月末あたりから大幅に伸びており、Ordinalsの利用についても拡大していることが分かるでしょう。 (引用元:Dune) 上記のような状況は、ビットコインのブロックチェーンへの影響も大きく、未承認のトランザクションが増加するといった現象も見られました。 BRC-20の特徴 これから、BRC-20が持つ基本的な特徴について、以下の2点から解説していきます。 ・Ordinalsの仕組みを応用 ・現在は実験段階 BRC-20のかんたんな特徴を把握して、大枠をチェックしていきましょう。 Ordinalsの仕組みを応用 BRC-20は、Ordinalsと呼ばれるプロトコルの仕組みを応用しています。 詳しくは後述しますが、Ordinalsについてかんたんにまとめると、ビットコインのサトシという細かな単位にデータを書き込んだり、追跡できたりするものです。 主に、ビットコイン上のNFTを発行できることなどから注目されていましたが、Ordinalsを応用してFTを発行する仕組みをdomo氏という開発者が実現しました。 https://twitter.com/domodata/status/1634247606262964228 上記の流れの中で、登場したのがBRC-20です。 現在は実験段階 BRC-20は熱狂を生んでいますが、まだまだ実験段階の取り組みです。 というのも、BRC-20のドキュメントでも実験であることが何度も記載されています。さらに、今後新たな設計や改善が行われる可能性についても言及されています。 実際に、BRC-20の利用にはいくつか不便な点も見られ、注目されているトークンも主にミームコインや比較的大きな時価総額を持たないものも多いです。 他のトークン規格ほど成熟したものではなく、取引や利用には注意が必要です。 BRC-20とOrdinalの仕組み BRC-20とその基盤となっているOrdinalsについて以下の観点から解説していきます。 ・Ordinalsの概要 ・Ordinalsにおけるインスクリプションについて ・BRC-20の仕組み OrdinalsやBRC-20の仕組みをチェックしていきましょう。 Ordinalsの概要 Ordinalsは、ビットコインのサトシに対して、何らかのデータを添付できるプロトコルです。 サトシとはBTCの最小単位のことであり、1サトシは1億分の1にあたります。 Ordinalsでは、そのサトシに何らかのデータを書き込み、追跡したりすることを可能にします。 具体的には、Ordinalsを通して画像やテキストなどのデータをサトシに添付し、ビットコイン上にあるNFTといったものを可能にしています。 Ordinalsの利用に伴って、新たなソリューションやサイドチェーンは不要です。 そのため、Ordinalsを利用して行ったアクションは全てビットコインのブロックチェーンを通して完結します。 BRC-20が大きく注目されているOrdinalsですが、上記の仕組みを通じて発行されたNFTの取引量も増加傾向にあります。 (引用元:Crypto Slam!) NFTのデータサイトCrypto Slam!によると、5月時点でのNFT売上ランキングでは、ビットコインが2位となっています。 直近1週間のデータを参考にすると、イーサリアムが約9,000万ドル、ビットコインが約4,400万ドルです。(ウォッシュ分を除く) 直近のデータのみを参考にすると、NFTをやり取りするブロックチェーンとして同じく人気の高いSolanaを上回るパフォーマンスを見せています。 上記のような点を参考にすると、ビットコイン上のOrdinalsは後述するBRC-20はもちろん、NFTにおいても高い注目を集めている可能性があるでしょう。 Ordinalsにおけるインスクリプション(Inscriptions)について Ordinalsがデータをサトシに添付していく過程で、特に重要なのが「インスクリプション(Inscriptions)」です。 Ordinalsでは、サトシにデータを書き込むという点は解説しましたが、インスクリプションがその過程に当たります。 ビットコインは過去に、SegWit(Segregated Witness)とTaprootという2つのアップデートを経験しています。 両者とも、NFTなどを想定したアップデートではありませんでしたが、結果的にトランザクションに含められるデータ量、構造などに影響を与えました。 インスクリプションでは、上記のアップデートの恩恵で誕生した領域に、含めたいデータを書き込みます。 また、何らかのものがインスクリプションされたサトシであっても前述したとおり、扱い自体は通常のBTCと変わりません。 BRC-20の仕組み BRC-20はOrdinalsを活用して、あくまで実験的にトークンとして扱えるようにしたものです。 BRC-20では、トークンとして機能させるために必要なルールのようなものを、前述したインスクリプションを活用して書き込み・機能させます。 そのため、インスクリプションする内容が異なるだけで、BRC-20を動かすための仕組み自体はOrdinalsを活用した他のNFTと大きな違いはありません。 Ordinalsの公式サイトでは直近のインスクリプションされたものを視覚的にチェック可能になっています。 BRC-20の人気が高まっているということもあって、直近のインスクリプションがBRC-20関連のものになっていることが分かるでしょう。 (引用元:Ordinals) Ordinalsでは複数の情報をインスクリプションでき、NFTでは画像関連のデータが書き込まれることが一般的です。 一方で、BRC-20では「text/plain;charset=utf-8」というタイプのインスクリプションを行います。 (引用元:Dune) 上記を参考にすると、インスクリプションされたもののうち、ほとんどがBRC-20と同じテキストを用いています。 2つ目に多い画像のタイプとも大きな差が開いており、Ordinals全体を見てもBRC-20が人気の高いインスクリプションの対象であることが分かるでしょう。 BRC-20とERC-20などとの違い ERC-20はイーサリアムに存在するトークンの規格で、BRC-20についてはビットコイン上に存在するトークンの規格です。 両者とも何らかのブロックチェーン上にあるという点は同じですが、その仕様・利便性は大きく異なります。 BRC-20はスマートコントラクトをサポートしていません。 そのため、BRC-20はERC-20のように複雑なことを行うことはできません。また、ERC-20はスマートコントラクトを利用した複雑なプロダクトはもちろんですが、さまざまなソリューションが完備されていて、一般的な方が利用しても利便性が高いです。 一方で、BRC-20も利便性が高くなるソリューションが日々出てきていますが、ERC-20ほどの利便性が高くありません。 BRC-20・ERC-20ともに名前が似通っていますが、その中身自体はほとんど異なるトークンです。 まとめ この記事では、BRC-20について解説しました。 BRC-20のトークンが多数の登場しており話題に上がりがちですが、ERC-20と同じような意識で扱うことはできないため注意が必要です。 その一方で、BRC-20の話題の高まりから周辺の開発に関するニュースも度々登場しているため、今後も注視していきたいと言えるでしょう。 最後まで、読んでいただきありがとうございました。

技術
2019/03/19IOSTがChrome用ウォレット『iWallet』を公開。iGAS、iRAMとノードパートナー報酬受取方法を解説!
IOSTは、先月末にメインネット公開を行い、今月10日からトークンスワップを開始したブロックチェーンプラットフォームです。 当プラットフォームからはMetanyxをはじめとするDAppsも少しずつ登場してきており、今週にはクロスチェーン型ステーブルコイン「iUSD」がローンチを控えています。 そんな中同社は、Google Chrome用ウォレット公開に伴いエコシステムのリソースであるiGAS・iRAMの詳細やノードパートナー(投票者)報酬の具体的な受取方法などを発表したので、こちらのページで詳しく解説していきます。 【仮想通貨】IOST(アイオーエスティー)の特徴・将来性を徹底解説! - CRYPTO TIMES IOSTのリソース構造について IOSTでは、ネットワークのリソースをiGASとiRAMという二つの内部単位に分けています。イーサリアムなどのメジャーなプラットフォームに比べて、内部リソース単位が2つあるというのは特徴的です。 IOSTのシステムリソースは、以下の式で成り立っています。 リソース = NET(帯域幅) + CPU(処理能力) + RAM(メモリ) このうちのNET + CPUがiGAS、RAMがiRAMとなっています。以下では、このiGASとiRAMの詳しい仕組みを解説していきます。 iGASとは? iGASは、IOSTネットワーク上でトランザクションを行う際に発生する手数料のことを指します。この点は、イーサリアムの内部リソース単位「GAS」と同じです。 iGASの入手方法 iGASは、IOSTトークンをステーク(ロック)することで自動生成することができます。 1IOSTをステークするとその場ですぐに100,000iGASを獲得することができ、以降毎日同量のiGASが自動生成されることになっています。 また、必要量のiGASを保有していれば、ステークしたIOSTはいつでも回収できることにもなっています。 iGASを保有できる量には限度があり、3日分の自動生成量(ステークしたIOSTの30万倍)まで、と決められています。 iGAS保有量に限度を設けることで、大量のIOSTを保有するウォレットがiGASをホーディングできないような仕組みを作り出しています。 トランザクションあたりのiGAS消費量について トランザクションの処理速度は支払うiGASの量に応じて上昇する仕組みになっています。IOST公式によれば、特別に急ぎでもない限りはデフォルトの設定で問題ないとされています。 iGAS消費量 = コマンドあたりのガス消費量 * コマンド数 iRAMとは? IOSTでは、ネットワーク上のストレージをiRAMという形で購入することができます。iRAMは、DAppsの開発などで重要な役割を果たすものとなっています。 iRAMはトークンの価格決定プロトコルであるBancor Protocolを活用して作られたもので、各iRAMはそれぞれ一度しか取引できない仕組みとなっています。 ウォレットあたりのiRAMシステムの上限は128ギガバイトに設定されており、購入・売却には2%の手数料がかかることにもなっています。回収された手数料は焼却(バーン)されます。 IOSTウォレットの生成方法 IOSTのウォレットアドレスは、IOSTABCというIOSTのBlockchain Exploreから簡単に無料で生成できます。 上の画面が表示されたら、まずはPubKey(公開鍵)を設定します。 基本的には、下にあるAuto Generateボックスをオンにすると、PubKeyが自動生成されます。その次に任意のAccount(アカウント名)を決めます。 PubKeyとAccountの設定が完了したら、CAPTCHAを行った後、CREATE ACCOUNTをクリックします。 30秒ほど待機すると無事アカウントが生成されプライベートキー(秘密鍵)が表示されます。 秘密鍵は誰にも見せず、安全な場所に保管しましょう。 IOSTでは、アカウント名がウォレットアドレス(公開鍵とは異なる)として機能します。アカウント名は任意で決められるため、早い者勝ちになる点に注意が必要です。 Chrome版iWalletを利用したノード投票報酬の受取り方 今回IOSTは、Google Chromeの拡張機能版としてリリースされたiWalletからノードパートナー報酬を受け取る方法も公開しました。 ノードパートナー報酬とは、今年1月から3月にかけて設けられたノード立候補者への投票期間のうち、自分が投票した立候補者が実際にノードとして選出された者に配布される報酬です。 IOSTのノード投票がスタート!投票者への報酬・配当も必見! - CRYPTO TIMES iWallet Chrome版はからダウンロードすることができます(Google Chrome必須)。 ウォレット拡張機能のダウンロードが完了したら、Chrome画面右上の拡張機能ボタンが並ぶセクションからiWalletをクリックし、IOSTウォレットをインポートします。 手順は、iWallet専用のパスワードを作成し、IOSTウォレットの秘密鍵(プライベートキー)を連携させる、というシンプルなものになっています。 iWalletのPrivate Keyは先程、IOSTABCで作ったウォレットの秘密鍵を連携させても良いですし、他のウォレットを持っているユーザーはその秘密鍵を連携させましょう。連携させることでiWalletにウォレットが同期されます。 ノードパートナー報酬を獲得するには、まずコチラのページにアクセスします。以降は、以下の画面に沿って自分が該当する報酬のタイプ(投票者は投票報酬、ノードはブロック報酬)を選び、送信先のウォレットアドレスを入力します。 記事ソース等: IOST公式Medium: iGASとiRAMについて (英語) IOST公式Medium: ノードパートナー報酬について (英語)

技術
2019/03/17Tippin meの使い方を解説!Twitter上で気軽にBTCを投げ銭できる拡張機能
2019年2月にTwitter上で簡単にLightning Networkを利用したBTCのマイクロペイメントができるTippin meがTippinよりリリースされました。 今回の記事ではTippin meの説明を交えながら、Tippin meの利点、インストールの方法、使い方まで解説していきます! ビットコインを投げ銭できるTippin me とは https://twitter.com/tippin_me/status/1093183245334859780 Tippin meはビットコインのセカンドレイヤー技術であるLightning Networkを利用することで、Twitter上でマイクロペイメントの投銭を実現するGoogle Chrome , Firefox向けの拡張機能となっています。 Tippin meの拡張機能を導入することで、Twitterで気軽に”いいね”を送るのと同じようにビットコインを送ることができます。 Tippin meを利用するには、投げ銭する側と受け取る側の双方が「tippin.me」のアカウントを作成し、投げ銭する側がLightning Networkウォレット「Blue Wallet」などをビットコインを準備しておく必要があります。 Tippin meを利用するための準備 Tippin meを利用するために必要な設定を解説していきます。 利用にはブラウザの拡張機能とLightning Networkに対応したウォレットが必要になります。 拡張機能のインストール Tippin meをTwitter上で送り合うためにはブラウザの拡張機能が必要になります。現在、拡張機能はGoogle ChromeとFireFoxで対応しています。 Chrome用またはFire Fox用のTippin meの拡張機能をインストールします。 ブラウザに拡張機能を追加することでTwitter上に⚡のマークが表示されるようになります。 続けて、Tippin meの公式サイトへ移動しTwitterのアカウントと連携を行ないます。 Join nowをクリックして、 Sign up with Twitterをクリックした後、 Twitterのユーザーネームとパスワードを入力し、Authorize appをクリックしてください。 Twitterとの連携が完了するとTippin meのダッシュボードに移動します。 これでビットコインを受け取る準備は完了です。 Lightning Networkに対応したWalletのインストール 続いて、投銭を送るためにLightning Networkに対応したWalletをインストールする必要があります。 今回は、Blue Walletを例に解説をしていきます。 Lightning Network対応のウォレットであるBlueWalletをインストールします。 アプリを開くと下記の画面が表示されます。 アプリ右上にある+マークをタッチし、Bitcoin(青色)とLightning(黄色) 両方のウォレットを作成します。 作成したビットコインのウォレットを開き、Reciveをクリックします。 BTCを受け取るためのQRコードを表示させます。 表示されたQRコード(または下にあるウォレットのアドレス)を用いて取引所などからBTCをBlue Walletへ送金します。 Lightning ウォレットを開きmanage funds→Refillと順にタップすることで、BTCウォレットからライトニングウォレットへ移動させます。 作成したビットコインウォレットを選択し、送金額や送金スピードを選択し送金します。 ※送金スピードを速く設定すると手数料の割合が高くなります。 しばらくするとLightning Walletに入金されます。これでTippin meを利用して投銭をする準備は万端です! 実際に投げ銭をしてみる Webブラウザに拡張機能をダウンロードすると、”いいね”ボタンと並んで、全てのツイートにtippin.meという稲妻の形をしたボタンが現れます。 この稲妻ボタンをクリックするとトランザクション用のQRコードが現れる仕組みになっています。 BlueWalletのLightning WalletからsendをタップしQRコードを読み取ることで送金することができます。注意が必要で、Lightningに対応していないウォレットから送金しようとするとBTCの送金はできません。 また、相手がTippin meを利用していない場合、下記のエラーメッセージが出て送金できません。 送金した相手へ入金され、トランザクションの履歴が残ります。 通常ビットコインの送金は1ブロック生成されるまでに10分かかり、送金が遅いのが難点です。 しかし、Tippin meはLightning Networkの技術を利用しているので、瞬時にウォレットに反映されます。 Tippin meのメリット Tippin meの最大の特徴はその手軽さと手数料無しで少額送金が可能な点ではないでしょうか。 面倒な手続きや申請などをしなくても Lightning Network対応のウォレット Tippin meの拡張機能 Twitterのアカウント 少額のビットコイン さえあれば誰でもいつでもどこからでもビットコインを送ることができます。 従来とは違い、Twitterで創作物を作ったユーザーなどに対しても気軽にマイクロペイメントできることはニーズが高そうです。 また、既存の手段(銀行振込や小切手など)では手数料がかかるので、少額の送金をしようとすると「手数料が送金額を上回る」ことがありました。 そのため、少額の送金を何度もするのは難しかったのですが、Lightning Networkの技術を利用したTippin meは手数料が殆どかからないのでその心配はありません。 Tippin me を利用してみて 今回Tippin meを使用して、チップとしてビットコインを送りあえるというコンセプトにとても可能性を感じました。 ボーダーレス決済が可能な仮想通貨の特徴と瞬時に手数料をほとんどかけずに、少額送金が行えるLightning Networkの特性を最大限に生かした機能だと思います。 また、Tippin meのユーザーが増えれば、Twitterの投稿でお小遣いを稼ぐなんてことができるかもしてません。 Twitterという大手SNSに拡張機能をつけたことにより、仮想通貨がより広く人々に浸透していくきっかけにもなるかもしれません。 今後よりユーザーに広がっていくためには、拡張機能ではなく、Twitterの機能としてデフォルトに搭載されるとより浸透していくのではと思いました。 皆さんもぜひTippin meを試してみてください! 記事参考:Tippin.me

技術
2019/03/15Kyber Network – EOS-Ethereum間のクロスチェーンコミュニケーションを可能にするWaterlooとは
先日、Kyber NetworkがEthereumとEOS間のクロスチェーンコミュニケーションを可能にするWaterloo (ウォータールー)を発表しました。 この技術により、EOSのライトクライアントをEthereumのスマートコントラクトで、またEthereumのライトクライアントをEOSのスマートコントラクトで効率的かつ完全に分散的に実行することができるようになります。 Kyber Networkの発表によれば、2つのブロックチェーン間のコミュニケーションが可能になるだけでなく、金融・スケーラビリティ・プライバシー分野における応用も十分に可能であるとされています。 本記事では、Warterloo (ウォータールー)の仕組みなどを解説していきます。 Relay Bridgeについて Relay Bridgeでは、2つの異なるブロックチェーン間での双方向のブロックヘッダーのリレーが実現されます。 ブロックチェーンの構造の確認ですが、ブロックヘッダーにはブロック内の各トランザクションのハッシュ値を繋ぎ、さらにそのハッシュ値同士を繋ぎ、と最後にすべてのハッシュ値を含むハッシュであるRoot Hashと呼ばれる最強のハッシュが存在します。 [caption id="attachment_33076" align="aligncenter" width="671"] Bitcoinのホワイトペーパーより[/caption] このRoot Hashが含まれるブロックチェーンAのブロックヘッダーをブロックチェーンBのスマートコントラクトに提出し続けることで、ライトクライアントでブロックの整合性を検証することができるというものです。 Root Hashにはブロック内のすべてのトランザクションのデータが含まれており、これは一般的に数学的に検証をすることが可能です。 同様に、ブロックチェーンBのブロックヘッダーをブロックチェーンAのスマートコントラクトにといった形で、双方向のブロックヘッダーのリレーが実現されます。 これが、今回のWaterloo (ウォータールー)でも使われるRelay Bridgeの基本的な仕組みということになります。 クロスチェーン間での資産の交換 各ブロックチェーンA・Bにおける、ブロックヘッダー内のRoot Hashとスマートコントラクトを利用したトランザクションの検証が可能であるということはわかりました。 では、資産の交換がどのような仕組みで行われるかというと、これは通例通り『Lock(ロック)』『Mint(発行)』『Burn(焼却)』によって行われていきます。 横文字だけだとわかりにくいと思いますので、以下具体例を交えた説明です。 ブロックチェーンAから100枚のトークンをブロックチェーンBに送金するシナリオを想定します。 最初に100枚のトークンをブロックチェーンA上のコントラクトに送金して資産の『Lock』を行います。 ブロックチェーンAのヘッダーにある100枚が『Lock』されているというデータをもとに、ブロックチェーンB上で100枚のトークンの『Mint』が行われます。 通常、これはWrappingなどと呼ばれており、現在でも様々なブロックチェーンで実装されている仕組みの一つです。 続いて、ブロックチェーンB上で、Wrappedされたトークンが『Burn』のコントラクトに送金されると、そのトランザクションのハッシュ値が含まれたRoot HashがブロックチェーンAにリレーされ、Aで『Lock』されていたトークンが開放されます。 この仕組みにより、常に総発行枚数の整合性を保ちながら1:1のペッグが担保されている状態でクロスチェーン間での資産の交換ができるようになります。 EOS⇄Ethereum間のリレーの仕組み これまで説明してきたような仕組みを利用して、資産の交換が可能になりますが、EOS→EthereumとEtheruem→EOSではこの仕組みが微妙に異なります。 EOS→Ethereumのリレー EOSでは、合意形成においてDPoS (Delegated Proof of Stake)が利用されていることから、Finalityに関する定義がEthereumと少し異なります。 [caption id="" align="aligncenter" width="591"] EOSのFinalityの仕組み[/caption] EOSが採用するDPoSの仕組みでは、21のBPs (Block Producer)が存在するのですが、その中でも2/3 + 1 (14+1 = 15, 1は自分)がコミットを行うことで初めてFinalizeされます。 そのため、EOSで行われるアクションをEthereum側にリレーする際、単純にそのトランザクションが含まれたヘッダーをリレーするだけでは、それが無効になる可能性がありProof (of Action)としては不十分となります。 EOSでは以下のイメージのように、15のBPsの署名付きのブロックをProofとしてEthereum側にリレーしなければなりません。 現在、EthereumのKovan TestnetとEOS Jungle2.0 Testnetで実証実験が行われていることが発表されています。 Ethereum→EOSのリレー Ethereumでは、BTCRelay (BitcoinのブロックヘッダーをEthereumに一方向的にリレーする技術)と同様にリレーが行われていきます。 ここでは、EthereumのヘッダーがEOSのスマートコントラクトに対してリレーされ、ヘッダーにはPoWの難易度やRoot Hashなどが記載されています。 Ethereumにおいては、ブロックの有効性は一番長いチェーンに繋がっているということにより証明されるのでEOSよりもFinalityの仕組みがシンプルです。 EthereumのProof of Workのハッシュ関数においてKyber Networkが問題としているのは、この計算において1GB以上のデータを必要とする点であるとしており、今後SmartPool等を利用してこの解決策を模索すると述べられています。 まとめ Kyber Networkによって発表された、EOS-Ethereum間のクロスチェーンコミュニケーションを可能にするWaterpoolについて簡単に解説させていただきました。 その他のクロスチェーンプロトコルでは、セキュリティがそのチェーンに依存してしまいますが、Kyberでは、EOSであればEOS、EthereumであればEthereumのセキュリティをそのまま利用しながらコミュニケーションを実現することができるという点で優れているということができますね。 今後の発表もまた解説できればと思います。 記事ソース : KyberNetwork Blog
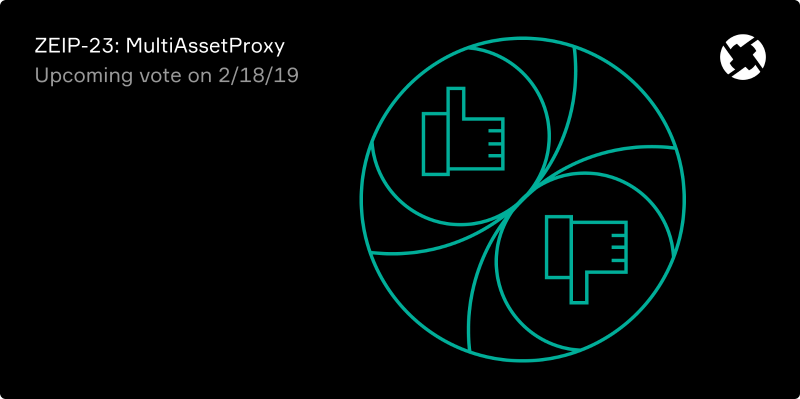
技術
2019/02/120xが発表した改善案「ZEIP-23 MultiAssetProxy(MAP)」の詳細
2月12日、分散型取引所のプロトコルである0xから、ZEIP-23 MultiAssetProxy(MAP)と呼ばれる新たなImprovement Proposal(改善案)が発表されました。 ZEIPとは、0x(Zero- Ex) Improvement Proposalの頭文字をとったもので、開発が行われている0xの改善案を指します。 発表によれば、この改善案に関しての開発は既に完了していますが、実装にはコミュニティによる投票が必要とされることから、その詳細や開発の背景、投票についての詳細な情報が今回発表されました。 本記事ではそんなZEIP-23について発表された内容をまとめていきます。なお、ソースコードなどのテクニカルな部分は便宜上省略させていただきます。 今回の発表の概要・キーポイント 今回の発表のキーポイントは以下になります ZEIP-23 MultiAssetProxy(MAP)について ZEIP-23 MultiAssetProxy(MAP)は、ERC20とERC721をバンドル化し、0xプロトコルを通じて分散的に取引することを可能とするスマートコントラクトを指します。 MultiAssetProxyでは、アセットのトランスファーを行うのではなく、バンドル化されたERC20やERC721のAssetIDと呼ばれるものを認識し、当該のAssetProxyにこれを返すという役割を果たすとされています。 また、アセットの取引において、部分的にこれが約定するということはなく(atomic transaction)、必ずすべてのトランザクションが成功するか、すべてが元の状態に戻るかのどちらかの結果となります。 MAP実装とコミュニティ投票について MAPの開発は既に完了しており、コードのセキュリティ監査もすでに終了しています。 しかし、統合には0xのスマートコントラクトの"hot upgrade"が必要とされ、これにはコミュニティによる監査も必要であるが故、ZRXを利用した投票の後の実装という形となっています。 そのため、ZRXトークンホルダーは2019/02/18から行われるMAPの統合について承認・拒否の投票を行う必要があり(強く奨励され)、この投票結果に応じた統合となります。 また今回の投票は、初の試みでありオンチェーンガバナンスにおける安全性の証明にリスクを伴う可能性があるため、投票は集権的なメカニズムを利用しオフチェーンで行われます。 仮に、承認された場合、0xはv2.0からv2.1へのアップグレードが行われます。 バグバウンティキャンペーンの詳細 0xでは、oxプロトコルのスマートコントラクトに関するバグの発見に対してバウンティ(報酬)を提供するバグバウンティキャンペーンを行っています。 今回のZEIP-23の発表では、ZEIP-23がバグバウンティの対象に追加されたことが明らかになりました。 バグを発見すると、CVSS(Common Vulnerability Scoring Standard)に基づく重要度に応じて最大$100,000USDまでの報酬が提供される仕組みになっています。 また、報酬はすべて0xのトークンであるZRXでの支払いとなります。 ZEIP-23の開発に対するモチベーション Non-Fungible Token(代替不可能トークン)は、EthereumのコミュニティにおいてERC721が正式に採用されたのち、ブロックチェーンゲーム(DApps)やコレクタブル、マーケットプレイスのエコシステムに大きな活気をもたらしました。 Ethereum(イーサリアム) ERC721の特徴は? ERC20やERC223との違いを徹底比較! - CRYPTO TIMES 0xのv2.0では、ERC721トークンのトレードをサポートしていましたが、コミュニティからの要望の多くに、これらのアセットをバンドル化したトレードを可能にすること、というものがありました。 ZEIP-23では、あらゆるERC20・ERC721のバンドルの取引を可能にします。 これには、以下のような様々なユースケースが考えられます; [caption id="" align="aligncenter" width="678"] 2匹のKittiesと1匹のKitty+DAIのトランザクション。[/caption] 複数匹のKittiesと1匹のKitties+ステーブルコインの取引 ERC721のトレーディングカードで、20枚セットのブースターパックを販売すること DecnetralandにおけるLANDのまとめ買い・売り 予測市場においてショートポジションを持つこと。例えば、AugurやVeilを利用して、2020年大統領選挙において、特定の政党以外に対してのロングポジションを持つことで、実質的にその特定の政党に対するショートポジションを持つことになる 今後の実装に関するロードマップ MAPが0xに実装されるためには、ZRXホルダーのコミュニティによる投票での最終的なConfirmationが必要となります。 統合にコミュニティの投票が絶対とされる理由には、今回のアップグレードが"hot upgrade"と呼ばれ、これには0xの既存のスマートコントラクトを修正する権利が含まれ、資産へのアクセス権も同時に必要とされるためです。 ZEIP-23の今回のアップグレードだけでなく、今後の"hot upgrade"に関しても、ステークホルダーはZEIP(改善案)に対する拒否権を行使することができなくてはなりません。 投票は、上記イメージのように2019/02/18から一週間にかけて行われる予定となっており、その結果はシンプルな多数決によって決定されます。 (2018/02/13の日本時間午前4時からは、0xのsubredditでAMA(Ask Me Anything)セッションも行われるため、不明点があればこちらで質問することも可能です。) 0xコアチームメンバーのこの投票に参加することができますが、機関・企業によって保有されているトークンでは参加することができず、自身でZRXを保有している必要があります。 投票が可決された場合、即座にその統合が行われますが、ERC20・ERC721を実際にバンドル化して取引を行うことができるのは、可決後2週間後の2019/03/11からとなっています。 仮に、この提案が否決された場合、0xのフォーラムにおいて事後のディスカッションが行われ、今後の実装に向けてよりよい提案や、必要に応じてより強固なセキュリティの方策に関する議論が行われる予定となっています。 まとめ 0xより、発表された新たな改善案であるZEIP-23 MultiAssetProxyについての発表をまとめました。 この提案がコミュニティにより可決されれば、3月11日より、ERC20やERC721をバンドル化して取引することができるようになり、DAppsのマーケットプレイスの幅がさらに広がるのではないかと考えられます。 また、ソースコードについての詳細は割愛しましたが、詳細は公式発表の以下のリンクから確認指定だたくことができます。 記事ソース:ZEIP-23: trade bundles of assets

技術
2019/02/08Binance(バイナンス)がテストネットリリースを間近に控えるBinance Chainの詳細に関して
こんにちは。Shota(@shot4crypto)です。 昨年、仮想通貨取引所であるBinanceからリリースに関しての予定が明らかにされたBinanceの独自チェーン『Binance Chain』とその分散型取引所『Binance DEX』ですが、先日Q&A形式でこれに関しての更なる詳細が発表されました。 本記事では、Binanceが独自に開発を進めるBinance Chainについてその詳細をまとめていきます。 Binance Chainとは Binance Chainとは、仮想通貨取引所Binanceとそのコミュニティによって開発された独自のブロックチェーンを指します。 以前から公式にアナウンスされているBinanceの分散型取引所『Binance DEX』はこのBinance Chain上に構築される分散型取引所ということになります。 Crypto Timesでも以前に、Binance Chain・Binance DEXに関して紹介をしていますので、以下の記事も是非参考にしていただければと思います; -Binance(バイナンス)が独自のブロックチェーン「Binance Chain」を数ヶ月内にリリースか!デモ動画も新たに公開! -BINANCE(バイナンス)の分散型取引所BinanceChainの開発状況デモが公開 Binance Chainの概要 https://www.youtube.com/watch?v=9R9LrKgL__A Binance Chainの概要 名称 Binance Chain ネイティブコイン $BNB アルゴリズム BFT / DPoS・pBFT(将来的に) 特徴① ブロックタイム1秒・1 Confirmation ファイナリティ 特徴② スマートコントラクト非対応 関連リンク Binance DEX テストネット(未) Chain Explorer テストネット(未) Binance Chainの特徴 Binance Chainは以下のような原理に基づいて設計されています; 一切の資産の預かり・保管をしない:トレーダーは自身のプライベートキー及び資産を自身で管理 ハイパフォーマンス:大きなユーザーベースを想定した高スループット・低レイテンシー、かつ流動性の高い取引を実現。1秒のブロックタイムと1 Confirmationのファイナリティを目指す(トランザクションが即座に完了する) 低コスト:低い手数料及び流動性コスト ユーザーエクスペリエンス(UX):Binance.comと同様のUXを提供 公正な取引:フロントランニング等を最小限に抑える 進化可能:新技術などによる改善が容易 DEX(分散型取引所)と聞くと、ユーザーエクスペリエンスがCEX(集権型取引所)と比較して劣るイメージですが、Binance Chain上の分散型取引プラットフォームでは、従来のBinance.comと同様のUI・UXが提供されるという点が大きな特徴として挙げられます。 1秒のブロックタイム・1 Confirmationのファイナリティという点も、ユーザビリティなどにおいて非常に重要な点の一つです。 また、Binance ChainはCosmos SDK・Tendermintの技術の一部を利用しており、これをフォークする形で設計されていることも大きな特徴です。Cosmos・Tendermintを選択した理由に関しては、後述のAMAにてCZ氏が回答しています。 Binance Chainでできることは? 特徴を見ていくと、Binance Chain及びBinance DEXでは、従来のBinance.com同様或いはそれ以上のパフォーマンスが期待できるということがわかりました。 ここでは、Binance Chain・Binance DEXでは具体的に何ができるのか、既存のDEXとどのような違いがあるのかを見ていきます。 Binance Chain Docsによれば、Binance Chainでは; Binance Chainのネイティブコインである$BNBの送信・受け取り 新規トークンの発行 トークンの送信・受け取り、Burn / Mint、凍結 / 解凍 異なる2トークン間での取引ペア作成の提案 チェーン上に作成された取引ペアの資産(トークン)売買 と記載されています。 バイナンスコインはこれまで、EthereumのERC20という規格で発行されるトークンでしたが、Binance Chainがメインネットへ移行すると同時に、Ethereum上のトークンからBinance Chainのネイティブコインに移行することになります。 しかし、Ethereum上のトークンからBinance Chainへの移行が行われると言っても、同ドキュメントによればコインのBurnなどはこれまで通り引き続き行われるとされています。 二点目にある、新規トークン発行に関してですが、前項同様これに関してもユーザビリティが担保された形で容易にトークン発行を行うことのできる仕組みが準備されるとのことです。 トークン発行に必要とされるのは、『トークン名称』・『トークンティッカー(シンボル)』・『発行枚数』・『Mint可否』の指定及び『少量の$BNB』とされており、Binance Chainを利用することで誰もが簡単に新規トークンを発行することができるようになります。 Binance CEO CZ氏が実施したAMAの内容まとめ 2月7日の日本時間午前11時頃、CZ氏はBinance DEXに関してのAMAを行いました。 https://twitter.com/binance/status/1093328531168276480 上記ツイートのライブ配信録画から内容を確認することもできますが、AMAでCZ氏が回答した質問を以下にまとめていきます; Binance Chainのバリデーターノードの数はどの程度ですか? --テストネットでは11に設定されています。Bitcoinほど多くはないので、どちらかというとNEOやXRPに近い感じだと思います。 ノードとなるために必要とされる要件等はありますか? --実質、誰でもノードになることはできますが、ブロックタイムが1秒なので、比較的高い負荷に耐えられるマシンが必要だと思います。 ノードやステーキングを行う人に対してはどの程度のガス・手数料が支払われますか? --現段階では、支払われたガス・手数料はすべてノードに渡ります。Binanceの現在の主なゴールとして、BinanceのDEXをできる限り早くリリースすることが最優先で、リリースが済んだ後で必要な調整などがあれば適宜調整していく形を取ります。 Cosmos・Tendermintを選んだ理由はなんですか? --一番の理由として、Cosmosの持つアーキテクチャが私たちの求めていたものに一番近いものだったという点が挙げられます。Binance ChainはCosmosの一般的な『Cosmos SDK』を使用しておらず、CosmosやTendermintの持つ技術を細分化してフォークするという形を取りました。 --Binance Chainは、トークンを容易に発行しそれをトレードするためのインターフェースしか持たないので、スマートコントラクトには対応していません。 --Applicationという点だけで見るならば、Binance Chainは非常にシンプルなチェーンですが、負荷耐性という意味では非常に強力なものとなっています。私たちは、スマートコントラクトを実装してより多くの機能性を持たせるよりも、より多くのトランザクションの負荷に耐えうる性能を持たせることの方がより重要であると考えています。 Binance Chainのテストネットのβテスターにはどのように申込みをすることができますか? --テストネットはあと一週間ほどでリリースされる予定となっています。テストネットがローンチすれば、もちろんβテストの受付も行っていきます。 DEXの早期アクセス権はどのようにして手に入れることが可能ですか? --私たちは、既に一部のパートナーに対してDEXへのアクセス権を提供しています。この中でもほとんどがウォレットの開発者或いはブロックチェーンエクスプローラーに対してのものです。 --基本的に、DEXへのアクセス権提供は、DEXを統合するためのツールを持つ人々に対してのみとなっています。 Binance Chain上では、数百万ものプロジェクトが実質的にトークンを発行することができると話していましたが、期待されるTPSはどの程度ですか? --現段階でのTPSは数千程度であると予測されます。ですが、これは容易に引き上げることが可能です。 --現状、Binance ChainのTPSのベンチマークとしては、Binance.comで現在取引が行われているのと同程度の負荷に耐えられるような設計になっています。しばらくの間は、このスループットで問題はないと考えていますが、取引高という観点で万が一耐えられなくなってしまった場合でも、これを水平にスケールさせることが可能です。 どのようにしてバリデーターになることができますか? --当初は、DDoS攻撃などを防ぐために、バリデーターは私たちのパートナーの中から選ばれますが、時間の経過とともにこの数字を増加させていきます。これに関しては、まだ最適な数字を探しているところです。 Cosmosの技術をクロスチェーン間のインターオペラビリティ実現に利用していきますか? --これに関してはまだ決定していませんが、当初はBinance DEXのリリースにフォーカスしていくつもりです。 --もしインターオペラビリティの技術を利用していくとしても、最初のv1.0ではなく、将来的にリリースをしていくv.20やv3.0での実装となるでしょう。 --とはいえ、Cosmosの技術を利用しているという点では、インターオペラビリティの実装も十分に自然なことです。 Binance Chainのネイティブコインとなる$BNBにはどのようなユーティリティがありますか? --基本的にはERC20の$BNBが持つユーティリティと同じで、$BNBを利用することで手数料が安くなるなどのユーティリティが存在します。 トランザクションをプライベートで行うこともできますか? --現状、これに関してはBitcoinなどのようにすべてのトランザクションは透明に記録されていきます。プライベートのトランザクションなどは行うことはできません。 まとめ Binanceがリリースを間近に控えるBinance Chainの概要についてまとめました。 仮想通貨取引所がコミュニティと共に独自にチェーンを開発するというケースは前例がありませんが、プロダクトは十分に期待できると言えるでしょう。 TwitterでもBinance Chainだけでなく、海外の情報を発信していますので、そちらもよろしくお願いします。 記事ソース:Binance Chain FAQ v0.3
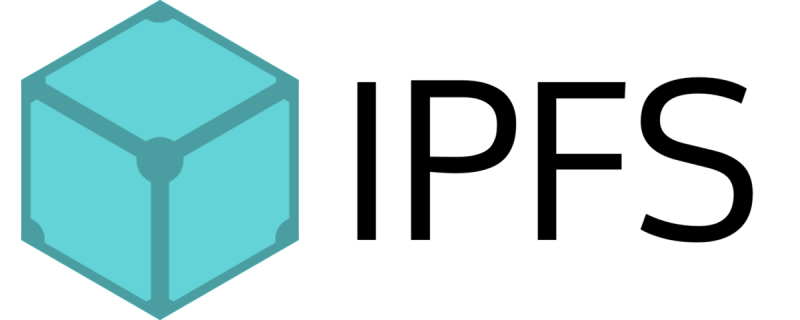
技術
2019/01/22【IPFSとブロックチェーン Part1】IPFSとは?ストレージ問題を解決する技術
ブロックチェーンは革新的なトラストレス・データベースである一方、ネットワークの規模やスケーラビリティの関係からストレージ面で問題を抱えることが多々あります。 そんなブロックチェーンストレージ問題の解決策として注目されているのが、InterPlanetary File System、通称IPFSです。 IPFSは、ブロックチェーン技術でお馴染みの「ハッシング」と「P2Pネットワーク」を融合させたファイルシステム、いわば「ネットワーク上でデータをやりとりする方法」です。 こちらのページでは、IPFSについて技術的な基礎知識からわかりやすく解説していきます。 IPFSとは? 一般的な研究やソフトウェア開発などでは、進捗状況を確認するために新旧バージョンを比較する必要があり、IPFSは当初、異なるバージョンのデータに素早くアクセスする方法として生み出されました。 やがて、同技術はネットワーク上の参加者(コンピューター)全員がアクセスできる分散型P2Pファイル共有システムとしてさらに開発が進められることとなりました。 IPFSを理解するためには、ネットワークプロトコルについての知識が少し必要になります。難しく聞こえるかもしれませんが、わかりやすく解説していきます。 ピアツーピア(P2P)ネットワークを利用している 私たちが普段アクセスしている「インターネット」は「クライアント/サーバーモデル」と呼ばれるものを使用しています。 このモデルは、クライアント(ユーザー)がサーバーに必要なデータを要求し、サーバーがそれを提供する、というものです。 ちなみに、このクライアント/サーバー間のやりとりを確立するプロトコルが「HTTPプロトコル」と呼ばれるものです。 このモデルにおけるファイルのダウンロードというのは、私たちユーザーがサーバーにリクエストを送り、サーバーがそのファイルを提供する、という流れを指します。 この「クライアント/サーバー接続」に対し、サーバーを介さずデータの要求者と提供者を直接繋ぐことをピアツーピア(Peer to peer)、通称P2Pと呼びます。IPFSは、P2Pネットワークにあたります。 IPFSと仕組みが似ているBitTorrent IPFSの基盤的な仕組みは、BitTorrentと呼ばれるP2Pプロトコルに似ています。 BitTorrentでデータをリクエストすると、すでにそのデータを保有しているコンピューターから直接転送が行われます。 クライアント/サーバー接続ではサーバーからのみデータが転送されるのに対し、BitTorrentでは要求データを保有するコンピューター複数から同時にデータをダウンロードすることができます。 したがってBitTorrentでは、多数のコンピューターがデータを保有している場合、ダウンロード時間を大幅に短縮することができます。 IPFSも「必要なファイルをネットワークに要求し、そのファイルを保有するノードからダウンロードする」という仕組みとなっており、この点でBitTorrentに類似しています。 このシステムのもうひとつの便利な点は「特定のデータを保有するノードがひとつでも存在する限り、そのデータはネットワーク上に半永久的に残り続ける」というところです。 クライアント/サーバーシステムではサーバーの消失と共にデータも失くなる(Single point of failure)のに対し、P2Pでは一度アップロードされたデータは良くも悪くも残り続けるのです。 IPFSはハッシング技術を利用している IPFSは、BitTorrentに似たファイル共有システムに加えて、ブロックチェーン技術でお馴染みの「ハッシング」という暗号技術を利用しています。 ハッシングの便利な点は、データそれぞれに固有のハッシュを与えることができる、という点にあります。 ハッシュ関数をわかりやすく体験してみよう 例えば、「我輩は猫である」という文章をSHA256と呼ばれるハッシュ関数に通すと、 "8AFC1EA26B8E95F9BEA48BD55B71AD63E8D1BDA3E955E874C00E2F9ED004AE8F" という「ハッシュ」が出力されます。これが「固有である」というのは、「他にどんな文章を通しても同じハッシュは(ほぼ)絶対に出てこない」ということを意味します。 ここで、猫を犬に変えて、「我輩は犬である」という文章を入力すると、 "68AB96F7ADEBBEA638F8036C15206BF03BD389E7C0A3B49F91F36E756FCC94D9" という全く異なるハッシュが出力されることが確認できます。 ブロックチェーンにおけるハッシュ技術 ブロックチェーンでは、データを特定の長さのランダムな文字列に変換する「ハッシュ関数」を利用することで、ウォレットアドレスやブロックの生成を行なっています。 例えば、暗号資産のウォレットには「プライベートキー」「パブリックキー」「ウォレットアドレス」の3種類が存在します。 実はこの「ウォレットアドレス」というのは「パブリックキー」のハッシュなのです。 【ロケーション VS コンテンツ】IPFSはコンテンツでアドレスを決定する 私たちが見慣れているファイルシステムは、「ロケーションアドレッシング方式」と呼ばれています。 このシステムでは、"abc.com/pictures/cats/favourite-cat.jpg"のように、コンテンツのアドレスを保存されている位置(ロケーション)から決めています。 これに対しIPFSは、要求ファイルのハッシュをそのコンテンツのアドレスとする「コンテンツアドレッシング方式」を採用しています。 したがって、IPFSプロトコルを使用したネットワーク上に存在するコンテンツには全て「固有のアドレス」が存在する、ということになります。 つまり、同じデータに別々のアドレスが与えられるといった事態が発生しないため、ネットワーク上でのデータの重複を大幅に抑えることができるのです。 長々と技術的な説明をしてきましたが、ここでようやくIPFSがいったい何をするのかを解説できます。 IPFSでは、ネットワーク上で目的のデータを保有している人を探し、保有者複数から同時にダウンロードすることができます。ここまではBitTorrentと同じです。 BitTorrentと異なる点はデータのアドレスがハッシュで表されている点で、ロケーションアドレッシングについて考える必要はありません。 まとめ・次回予告 今回は、InterPlanetary File System、通称IPFSとは何かを解説しました。 まとめると、IPFSには以下のような利点があります。 P2Pファイル共有システムを利用しているため、ノードの数に応じてデータのダウンロードが速くなる。 また、特定のファイルはそのデータを保有するノードが存在する限りネットワーク上に残り続ける。 データのハッシュをアドレスとすることで、同じデータの重複を削減できる。 次回は、IPFSのより詳しい仕組みを解説し、その仕組みがなぜブロックチェーン技術のストレージ問題解決に繋がるのかを説明していきます。

技術
2018/12/13KyberNetwork 『ERC1257』がメインネット実装! 概要を解説!
Kyber Networkは、オンチェーンでの分散型取引(ETH/ERC20)を様々なDApps上で実現させるための、分散型のプロトコルです。 先日、アプリケーション上でスマートコントラクトを利用してい行われた決済を追跡することが難しいことから、Kyber Networkはこの問題を解決するための規格『ERC1257』を開発しメインネット上にローンチしました。 本記事では、アプリ上でのスマコン決済を追跡し記録することを可能とする規格『ERC1257』についての解説を行っていきます。 ERC1257の概要を解説! ERC1257は、スマートコントラクトを介して(或いは人間によって)執行されたトランザクションを記録することのできる機能を持つトークン規格です。 ソースとなるKyberNetowrkの公式Mediumでは『Proof of Payment Standard』と記載されており、この規格が『支払いの証明』としてのものであることが示唆されています。 先日、Kyber Networkの公式TwitterにてERC1257のローンチ発表が行われました。 https://twitter.com/KyberNetwork/status/1070307717380694016 現状の支払いのシステムにおける問題とERC1257開発動機 現状、例えば仮想通貨の決済に対応しているE-コマース事業主などのケースでは、ユーザーのアドレスや指定したデポジットのアドレスを利用して支払いの追跡を行うことが通常です。 しかし、マルチシグアドレスなどで行われるスマートコントラクトなどによって執行された支払いを管理するとなると、内部のトランザクションを追跡する方法が存在しないため、支払いの証明を行うことが難しくなります。 日々複雑化していく、スマートコントラクトを利用して行われる支払いの仕組みに、共通して適用することのできるソリューションが存在しないことで、支払いの管理なども同時に難易度を増すことになります。 そこで、注文IDなどの情報を含める際に必要とされた面倒な複数のアドレスの準備を省略し、スマートコントラクトを利用する際に複雑化する支払いの追跡などを可能とする標準規格として『ERC1257』の構想が誕生しました。 ERC1257規格の技術仕様を理解する ERC1257では、上述の問題解決に必要とされる情報をEVM logへと記録していくため、以下の5つの項目を標準化しています。 パラメータとその内容は項目は以下の通りです。 event ProofOfPayment(address indexed _payer, address indexed _payee, address _token, uint _amount, bytes _data) _payer:支払いを行う人物 _payee:支払いを受け取る人物 _token:支払いの対象となったトークン _amount:支払いが行われたトークンの数量 _data:アプリケーション固有の補助データ 以上の情報が標準化されているこのERC1257規格を利用することで、これまで難しいとされてきたスマートコントラクトを利用した支払いなどの追跡などが可能となります。 潜在的なユースケースを考えてみる ERC1257規格を採用した場合、ログとして以上のようなデータがアウトプットされ、その結果支払いの追跡が容易になるという説明をこれまで行ってきました。 この具体的なユースケースですが、Kyber NetworkのMediumでも言及されている通り、支払いにまつわる標準化されたデータを利用する必要がある事業体によって利用されることが主となるのではないかと考えています。 ERC1257のGitHubにはBitcoinでピザが購入されたという事例をもとに、ピザ屋が分散的に支払いを完了させ、ログを排出するためのサンプルコードが記載されています。 まとめ Kyber Networkが分散型決済の更なる促進を目指してメインネット上にローンチした『ERC1257』についてをまとめていきました。 マルチシグアドレスなどにおけるスマートコントラクトを利用した支払いの記録が難しいということは知りませんでしたが、標準化された規格の登場により、さらに幅広く分散型決済が応用されていくための地盤が固まったのかなと思います。 今回執筆の参考にした記事のソースは以下からご覧いただくことができます。 Introducing ERC1257: Proof of Payment by Smart Contracts ERC 1257: Proof of Payment by smart contracts #1257

技術
2018/12/12スマコンを利用したサブスクリプション(定期購読)型モデルが実現? EIP1337について解説!
こんにちは。Shota(@shot4crypto)です。 今回は、スマートコントラクトを利用してサブスクリプション型のビジネスモデルを実現するというEthereumの新たな規格『EIP1337』に関して、この概要や特徴を紹介していきたいと思います。 本記事の執筆にあたって、1337AllianceのKevin氏による以下のMediumの記事の内容・構成を参考にさせていただきました。ありがとうございます。 記事ソース:EIP 1337 (Subscriptions) Launches EIP1337とは? 画像では、『ERC1337』となっていますが、現在はまだProposal段階で『EIP1337』とした方が正しいでしょう。 このEIP1337ですが、タイトルにもある通り、これはスマートコントラクトを利用したサブスクリプション(定期購読)型モデルを実現するための規格です。 サブスクリプション型モデル自体は以前にもEIP948という規格を用いて構想が練られていたそうなのですが、今回紹介するEIP1337は、これに対するフィードバックを受け改善を施したものであるとされています。 なぜサブスクリプション型モデルなのか? Webにおけるマネタイズ手段は、広告やスポンサーシップから様々ですが、1337AllianceのKevin氏は、『定期購読モデルはWebビジネスにおいて最も健全なものである』としています。 また、多くの場合トークンベースの経済システムと比較しても、サブスクリプション型のモデルの方が優れているケースが多いと考えられます。 以下はユーザー側・運営側・エコシステム全体がこのモデルを採用した場合に享受することのできる恩恵になります。 ■ユーザー側の利点 DAppsのユーティリティを利用するために複雑なホワイトペーパーを読む必要がない Dappsを利用するという点以上に複雑なVestingやCrypto-economic的な概念を理解する必要がない いつでもキャンセルを行うことができる ■運営の利点 購読者やコンバージョン等のデータを活用して、継続的なキャッシュフローを獲得・把握することができる 二面的なユーザーの構造(投機家・ユーザー)を考える必要がないので、サービスの質を改善することにフォーカスすることができる 長年かけて証明されてきた既存のビジネスモデルを活用することができる 規制面での不確実性が少ない ■エコシステム全体としての利益 サブスクリプション型モデルのような既存のシステムを構築していくことは、Ethereumのエコシステム拡大を考える際に、仕組みが非常にシンプルなものとなります。 オンチェーンのサブスクリプション型モデルにより、開発者は複雑なトークン設計などを意識せずとも、UIやUXの改善にコミットすることができるようになるため、Mass-Adoption(大多数への普及)という課題の解決に、より集中して取り組むことが可能になります。 結果として、利用者が増えることでEthereumのエコシステム全体へ対する利益へ繋がります。 EIP1337の現在の状況は? 情報ソース:Subscription Services on the Blockchain…Are Here ConsensysによってMediumにポストされた投稿によれば、このモデルを利用したサービスのプロトタイプがコミュニティから開発されており、サービスの機能面における監査も既に完了しているようです。 Token Subscription - DAIやWETH等10種類のトークンを利用した定期購読が可能 上のイメージのように、Metamaskを利用することで、ガス価格や数量、支払い頻度などを指定し定期購読を行うことができます。 ETH Grants - サブスクリプション型のコントラクトを作成可能 ETH Grantsでは期間やゴールを指定し、サブスクリプションの概要を記載していくことで、自身のサブスクリプションモデルを作成することが可能です。 EIP1337の今後の可能性は?EIP1337まとめ 個人的な意見となってしまいますが、個人的にはサブスクリプション型のモデルは必要であり、これが広く採用されればDAppsは間違いなく流行ると考えています(これに関しては、以前執筆させていただいたContentBOXの記事でも少し触れています)。 今回のリサーチでは、僕自身がエンジニアではないためDApps内の詳細の仕組みまではつかめなかったのですが、サブスクライブ(定期購読)の仕組みを利用することで、DApps内で行われるマイクロトランザクションを開発元が代替してくれるような仕組みまで実現できれば、これまでボトルネックとされてきたUX部分の大幅な改善が見込めるのではと思います。 一方で、記事内イメージのフレーズ「Monetize with subscription, not ICOs (ICOではなく定期購読でマネタイズしよう)」という形で、ICOの代替手段として広がるのみでは、まだまだ課題も残るのかなと感じます。 ありがとうございました。

技術
2018/11/08EthereumとEOS間のクロスチェーン取引を可能にするBancorXの仕組みを解説
こんにちは、Shota(@shot4crypto)です。 BancorXは取引所やオーダーマッチングなどを必要とせずに、Ethereum上の資産とEOS上の資産の交換を可能とするプロトコルです。 本記事では、そんなBancorXが具体的どのような仕組みの元で、Ethereum-EOS間のクロスチェーン取引を可能にするのかを開設していきます。 BancorXとは?BNTトークンを利用したクロスチェーン取引の仕組みを解説! BancorXでのクロスチェーン取引におけるカギを握るのが、BNT(Bancor Network Token)です。 BNTのスマートコントラクトは、EthereumとEOS上で同時に機能し、この設計故にクロスチェーンでの変換が可能となっています。 世界初のスマートトークンであるBNTのクロスチェーンでの機能性の軸には、複数のブロックチェーン上で同時にトークンの発行や破壊を行うことのできる点にあります。 BNTトークンはチェーン間を移動する際、送信元のチェーン上の循環からは除去され、送信先の目的アドレスで再生成される形を取ります。 このプロセスにより、クロスチェーンにおけるトークンの変換及びBNTの循環枚数を一定に保つことができるようになります。 例:Ethereum上のトークンをEOS上のトークンに変換する際のプロセス BancorXを利用してEthereum上のトークンをEOS上のトークンに変換するプロセスは以下の通りです。 トークン変換のプロセスは上記イメージのように、左側のEthereum、中央のOracle(オラクル)、右側のEOSの3つに分割して段階的(同時)に行われていきます。 Ethereum側でのプロセス Ethereum上のトークンをBNT(Bancor Network Token)に変換 BNTがEthereum上のBancorXのスマコンに送信される。この時、EOSチェーン上の目的地となるアカウント情報の受け取りも行われる。 BNTと目的地となるアカウントがBancorXのコントラクトに送信されると、Ethereumチェーン上からBNTの循環が除去される。 Oracle側でのプロセス OracleがEthereum上のBancorXコントラクトを監視、EOS上のBancorXコントラクトにBNTの枚数と目的地となるアドレスの情報が受け渡される。 EOS側でのプロセス EOS上のBancorXコントラクトがEOSのブロックチェーン上で同数のBNTトークンを発行 Bancorネットワークのリレーを通じて、発行された同枚数のBNTをEOS或いはEOS上のあらゆるトークンへと変換することができる このように、BancorXのスマコンを通して、BNTトークンの焼却・ミントが同時に行われることで、BNTトークンの循環枚数(Ethereum+EOS)を一定に維持しながらクロスチェーンの取引を行うことも可能となります。 また、逆のプロセス(EOS-Ethereum間)での取引も同様に行われていくようです。この部分の説明に関してはEthereumとEOSを逆にしただけの仕様となっているため割愛させていただきます。 まとめ BancorXのEthereum-EOS間におけるクロスチェーン取引のプロセスについてをまとめました。 クロスチェーン間での取引はまだまだ主流ではありませんが、Web3.0系のウォレットなどと統合していくことで、従来の単一のチェーンではなくよ巨大なエコシステムが完成していくのではないでしょうか? 執筆の参考とした英語の原文はこちらからご覧いただくことができます。


















 有料記事
有料記事


