2017年5月に仮想通貨への投資を開始。ブロックチェーンや仮想通貨の将来に魅力を感じ、積極的に情報を渋谷で働く仮想通貨好きITリーマンのブログを通じて発信するように。
最近書いた記事

インタビュー
2019/05/13ブロックチェーンのスケーラビリティーの問題を解決する技術「Plasma」とは?–Cryptoeconomics Lab 片岡拓
1992年生まれ・現在26歳のCryptoeconomics Lab CEO 片岡拓。Cryptoeconomics Labは、ブロックチェーン技術とCryptoeconomics(行動暗号経済学)の普及に向け、プロトコル開発エンジニアの育成やコミュニティの醸成に取り組む研究チーム。 現在は「Plasma」という技術に注力する。この技術のメリットとは?現在の研究状況、ブロックチェーンを通した未来の社会像などについて聞いた。 ※ 今回のインタビュー記事は、CRYPTO TIMES の新井が協力の下、GRASSHOPPER編集部とインタビューを実施し、株式会社電通様が運営するWEBメディアGRASSHOPPERに掲載されたインタビューの転載となります。 転載元記事 : ブロックチェーンのスケーラビリティーの問題を解決する技術「Plasma」とは?–Cryptoeconomics Lab 片岡拓 - GRASSHOPPER 不動産ビジネス、インドネシアでの飲食業を経てブロックチェーンへ —まず、片岡さんがブロックチェーン・ビジネスを始めるまでの経緯を教えてください。 片岡:慶應義塾大学2年生の時に、農業系ベンチャーでインターンをしていました。その会社の社長に学生が参加できるビジネスコンテストの存在を教えていただき、水耕栽培ビジネスを考えて決勝まで残ったことが今の自分の原点です。その後、大学4年生の頃に不動産ビジネスを起こし、リブセンスに吸収してもらったあたりから、次のビジネスを探し始めるため、アジア諸国を旅する生活にシフトしました。 当初手がけた不動産ビジネスは、既存の不動産業へ少しはインパクトを起こせたとしても業界全体へのインパクトには至らず、「成長しているマーケットで勝負する」必要性を感じていました。それを考えたときに、そもそも日本という市場が伸びているかという疑問が出てきて、リブセンスを退社しインドネシアのジャカルタに移りました。 最初はジャカルタでのITビジネス起業も考えたのですが、リサーチを重ねた結果、IT領域でエンジニアの採用も資金調達も、現地の人に勝つのが難しいと考え、日本食しか勝てるものがないなと思い、WAKI Japanese BBQ Diningという焼肉屋を開きました。 その時に学んだことは、アジアでは日本人が得意な領域なら勝てるということです。そのまま飲食を続けても楽しい仕事だったとは思いますが、まだ挑戦できる歳…ならば、よりやりがいのあることに挑戦していけたらなと。そう考えていたところ、2017年当時Bitcoinについて日本でもみんな語っていて、凄いことになっているなと注目し始めました。 そんな折、インドネシアのVIP PLAZAという大手ファッションECサイトのCTOを務める落合渉悟さんに出会い、ブロックチェーンについて色々と教えてもらい、毎日のように議論をして現在のCryptoeconomics Labの創業に至りました。 初期に一番惹かれたプロトコルは、暗号通貨の流動性を上げられるような(Liquidity系)プロトコルであるBancor(バンコール:分散型取引所の一種)です。また、当時色々なチェーンが出てきて、そのチェーン間で暗号通貨を交換できる必要性があると考えインターオペラビリティ(相互運用性)にも注目しました。 ただインターオペラビリティーは、やればやるほど深く時間もかかり、僕らの見立てではしっかり利用できるまで5年ほどかかると考えています。もう少し、近い将来に起こせるビジネスはどこかと考えていた2017年8月頃、Vitalik ButerinとJoseph Poonが出した「Plasma」というホワイトペーパーを読んだ落合が「これだ」と言い、自分も賛同したのです。 ブロックチェーン技術「Plasma」とは —Plasmaとはどういう技術なのでしょうか? 片岡:ブロックチェーンには“トリレンマ”があります。これは、decentralization(分散性)、security(安全性)、scalability(拡張性)の3つの要素を全部満たすことができないというものです。例えばコンソーシアムチェーン(複数の企業で形成)ならdecentralizationを抑えてscalabilityを上げているわけです。逆にBitcoinではdecentralizationが高すぎるので、どうしてもscalabilityが下がってしまいます。 しかし、decentralizationとsecurityを犠牲にすると、そもそもBitcoinやEthereumを使う理由がなくなってしまいます。なので、この2つを保ったまま、どうにかscalabilityを上げることができないかというのが、Plasmaを含むスケーラビリティソリューションの目指すところです。 今の実態としてEthereumがさばけるトランザクションは、1秒あたり15件です。対して決済ネットワークのVISAなどは諸説ありますが1秒あたり約10,000Txと考えていいでしょう。Ethereumの上にコードを置いて、いわゆるWebのようなことをしようとしたら、何十億トランザクションを毎秒さばけなきゃならないわけです。 これの解決法としてShardingやCasperという、いわゆるSerenity(Ethereum2.0)と言われているものがあります。ただ、これはあくまでEthereum Foundationが研究開発を先導し、Ethereumブロックチェーンそのものに内包されているため、企業として取り組むことが厳しいんです。 もう一つの解決方法は、BitcoinやEthereumなどのメインチェーンに独自のサイドチェーンを接続することです。サイドチェーンの中でも特にsecurityが守られているものがPlasmaです。サイドチェーンなので、自分たちが自由に扱え、サーバーも自分たちが管理できます。ですが、ちゃんとsecurityは守られている。企業の利用には向いています。 —Plasmaのどの点が面白いと思ったのでしょうか。 片岡:前提として、インターオペラビリティーとはいいながらインフラストラクチャーは分断されてはいけないというBlockstream創設者のアダム・バックの言葉があります。 これは例えていうとGoogle Play StoreやiTunes Storeのようなものが100個もある世界と、淘汰·収束されて選択肢が2、3個しかない世界の比較です。後者の方が使い勝手が良いですよね。歴史を見てもかつては様々なOSがありましたが結果Mac、Windows、Linuxのように限られたプラットフォームに収束しています。ブロックチェーンも同様で、今収束していきそうなプラットフォームは、決済としてのBitcoinと、Ethereum、あと第三の何か、という予測があります。それを踏まえBitcoinと、Ethereum以外のチェーンのことを考えるのは一旦やめました。 Bitcoinはとても魅力なのですが、ハードフォークやソフトフォークなどでアップデートできない問題があった為、Ethereumに目を付けました。ただ、decentralizationが高いため、どうしてもscalabilityが落ちてしまう。 このscalabilityをdecentralizationやsecurityを保ったまま上げる方法はあるのだろうかと研究した結果、Plasmaに行き着いたのです。 —Plasmaの開発は落合さんと二人で行っているのですか?それともコミュニティを巻き込んでやっているのでしょうか? 片岡:本当はコミュニティを巻き込んでやりたかったのですが、コミュニティは面白い提案をしないと動いてくれません。まずはキャッチアップしなければいけないんです。 なので、Ethereum Foundationや、OmiseGOのような企業、まず彼らの実装開発 をキャッチアップすることにしました。ありがたいことにオープンソースもあり勉強し放題なわけです。今では彼らがやっているPlasma Groupと、実装レベルで同じ段階まで来ており、かつ提案として彼らより進んでいる部分もいくつかあるところまで来たので、ようやく今コミュニティとしっかり会話ができているという感じになっています。構想から1年半ぐらいはかかってしまいました。 キャッチアップが終わってようやく、4月上旬にシドニーでEDCON 2019というEthereumのデベロッパー向けカンファレンスがあり、日本から弊社とLayerXさんの2社だけ出展し、そこでプレゼンさせていただいたところ、良い評判をいただきました。このおかげもありコミュニティを少しずつ巻き込むことができたというところです。 ブロックチェーンがインストールされた後の世界とは? —片岡さんから見て、Plasma及びブロックチェーンが社会にインストールされると、どうなると思いますか? 片岡:もちろん未来を予想はできませんが、作る方向性は決まってます。iPhoneが生まれた時、みんな「これはなんだ?」となりましたが、そこに内蔵されたGPSやセンサーがあることでUberなどの多くのビジネスが生まれました。ブロックチェーンではトラストレス(信用の不要性)を軸としたものが色々と生まれると思います。 カードの発行会社がいてカードブランドがあって、と色々な人たちを挟んでいる今のカード決済がP2Pで出来るようになったり、P2Pで電力取引が出来るようになったりということが考えられます。今は中央の電力供給から買ったり売ったりしていますが、個人宅の太陽光発電で得た電力を個人に売れる世界が実現された場合、例えば電気を送ってもお金を払ってもらえないということも起こりえます。この場合スマートコントラクトを用いれば、電力を送ったら必ずお金が支払われるというようになります。 それを僕らはプログラマブルマネーと言っているのですが、ブロックチェーンによって、お金がついにデータと同じ領域に入ってきたと考えています。今までもお金をデータとして扱うことは出来ましたが、実際は現実で動いているものを仮想化してやっているだけでした。 データと同じ領域にお金が生まれたことで、スマートコントラクトなどによって即時的で一貫性ある執行が出来るようになったというのが僕らは非常に面白いと思っています。実際に現実のお金の動きとデータの動きが同じになったのが革命的だなと。 —Cryptoeconomics Labでは、電力取引のP2P実証実験なども行っていますね。 片岡:大手電力会社やベルリンのコンソーシアムと組んで共同で実験を行っています。ある地域で電力メーターを置いてやっていますが、まだ彼らも手探りなので、ブロックチェーンを本当に実装したほうがいいのかはわかりません。今は中央集権システムなので、ブロックチェーンじゃない選択肢も普通にありえると思います。 ただ、例えばアフリカのある地域で今から電力インフラを作る際に、電力会社はコストが掛かりすぎる、でも太陽光発電はできるーーとなった場合に、スマートコントラクトをつけて電力を取引するビジネスなどは可能性があります。経産省が構築した月末清算システムが存在しない地域で安全にインフラを作るなら、Plasmaを使えばリープ・フロッグが起こせるのではないかという読みはあります。 —最後に、片岡さんが見る世界は今後どういったものになっていくのでしょうか。 片岡:会社としては、果たしてうちは何屋なのかというのを最近ずっと考えています。今までは、例えるなら高速道路の設計図を描くような仕事をしていたのですが、オープンソース化してしまったほうがOSS開発チームが集まるEthereumコミュニティにフィットしますよね。反対にライセンス化するとコミュニティのパワーを使えない分、負けやすくなってしまいます。 いわば高速道路を大量に作れるソフトウェアハウスのような会社になるのか、それとも高速道路のETCのような、SDKをつくったりAPIを作ったりする会社になるのか、それとも高速道路のユーザーをつかむ車の会社になるのかなど、様々な可能性があると思います。参入障壁をどこで築いて、どこでコラボレーションするかというバランスを見極めつつ、進んでいきたいと考えています。 高速道路としてのPlasmaは、これまで税で賄うしかなかった各国の公共財を安価にしたり、運営主体を不要にする能力があります。パブリックブロックチェーンにしかできないマス・アダプションは、大規模で公共的な部分にこそあると考えます。そういう未来を見ています。 Interview & Text:西村真里子 協力:CRYPTO TIMES 新井進悟 転載元記事 : ブロックチェーンのスケーラビリティーの問題を解決する技術「Plasma」とは?–Cryptoeconomics Lab 片岡拓 - GRASSHOPPER

ニュース
2019/05/01East Asia Data Symposium: AI’s Potential in Japan and China -bitgrit x Matrix AI Networkの合同イベント開催-
AI×データ、AI×ブロックチェーンの関係の重要性は世界中でますます高まってきております。 ブロックチェーン分野とAIを専門とするプロジェクトのbitgritとMatrix AIが今回、東京大学にて合同でイベントを実施します。 本イベントでは、AI大国である中国の清華大学からトップ・データ・サイエンティストとして多方面に活躍するSteve Deng助教授と、データ活用のトップランナーとして国際的に活躍されている東京大学の越塚登教授をお招きし、中国と日本それぞれの観点から、これらの技術の可能性を語り合う会になります。 また、当イベントでは、お二方による登壇に加え、株式会社bitgritのCEO、Frederik Busslerがモデレーターを務めるパネルディスカッションも展開いたします。 イベントページ スケジュール: 13:00- 受付開始 13:30- イベントスタート (Matrix & bitgrit紹介) 14:00-14:45 (Steve Deng助教授スピーチ) “The fusion of AI and Blockchain for industrial intelligence” 5分休憩 14:50-15:35 (越塚教授スピーチ) "AI for Data, Data for AI: Global Data Platform and AI” 5分休憩 15:40 パネルディスカッション 16:30 ネットワーキング 17:30 イベント終了 場所: 東京大学伊藤国際学術研究センター 3F 〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3−1 詳細: 当日は同時通訳(英⇆日)がございます。 Steve Deng教授のスピーチタイトル: The Fusion of AI and Blockchain for Industrial Intelligence 越塚登先生のスピーチタイトル: AI for Data, Data for AI: Global Data Platform and AI Steve Deng助教授についてのご紹介: Steve Deng助教授は清華大学で学士号(1995)と修士号(1998)を取得し、2006年にはCarnegie Mellon大学でコンピュータサイエンスの博士号を取得しました。 彼の主な研究対象は電気設計・並列アルゴリズム・画像処理機械構造の自動化におけるAIです。過去には中国の高速鉄道設計においての危険を予測するAIの設計・開発に携わっていました。 また、代表的な著作であるStructured Integrated Circuit DesingやHigh Level Synthesisは有名な大学の教科書として採用されており、著名ジャーナルにおいて20編以上の論文を掲載しています。2017年にはPascal AIの国際大会において、彼の率いたチームが優勝した実績もあります。 越塚登教授についてのご紹介: 越塚 登教授 東京大学 大学院情報学環・教授 YRP ユビキタスネットワーキング研究所副所長 1994年3月 東京大学 大学院理学系研究科 情報科学専攻 博士課程修了、博士(理学). 1988年以来、TRON(リアルタイムオペレーティングシステムニュークリアス)プロジェクトに参加しています。 約30年間、ユビキタスコンピューティング、IoT(Internet of Things)、組み込みシステム、ヒューマンコンピュータインタラクション、およびコンピュータネットワークを研究してきました。 現在の主な研究対象は、IoT(Internet of Things)、ユビキタスコンピューティング、オープンデータ、組み込みリアルタイムシステム、オペレーティングシステム、およびコンピュータネットワークなど。 中国科学院計算技術研究所 客員教授 パネルディスカッションモデレーター:フレデリック・バスラー 株式会社bitgrit CEO 弱冠19歳で株式会社bitgritの最高経営責任者(CEO)に就任。様々な企業で培ったAIとブロックチェーンのノウハウと経験を活かし、bitgritが目指す「コミュニティ主導の民主AI」の実現に向けて企業を率いています。スマート・コントラクト・コードの脆弱性を特定する会社である「スマート・コントラクト・オーディティング(Smart Contract Auditing)」の創立者兼CEOとしてキャリアをスタートさせ、 さらにアムステルダムのMaven 11 Capitalのデータアナリストや、HealthDexのチーフデータオフィサー、Rare Genomics Instituteのブロックチェーンおよび機械学習の調査分析専門家、Agro Stock Exchangeの戦略アドバイザーなども歴任しました。 本イベントは「コミュニティ主導の民主AI」の実現を目指す株式会社bitgritと、中国に拠点を置くAI/ブロックチェーン企業Matrix AI Networkが共催いたします。 イベントページ

ニュース
2019/04/26Ripple(リップル)社の取締役にSBIホールディングス 北尾会長が就任
Ripple社は2019年4月26日、SBIホールディングス株式会社・代表取締役社長の北尾吉孝氏がRipple社の取締役に就任したことを発表しました。 https://twitter.com/yoshitaka_kitao/status/1121579603942764545 今回の人事異動では、前任である沖田氏(SBI Rpple Asia CEO )と交代する形で4月25日付けより就任となります。 北尾氏は今回の役員就任に関して、「ブロックチェーンとデジタル資産は世界中で送金のあり方に変革を起こしており、Rippleはこのポジティブな変化における立役者です。私は取締役としてこれまでの自分の経験と知見を役立たせ、Rippleの次の成長段階に貢献できる機会に興奮しています」と述べました。 また、RippleのCEOであるChris Larsen氏からは『APAC地域においての利用拡大を推進する完璧なタイミングでSBIグループのCEO/会長である北尾氏を取締役に迎えることができた』とコメントをしています。 https://twitter.com/chrislarsensf/status/1121571640868048897 記事ソース : Ripple
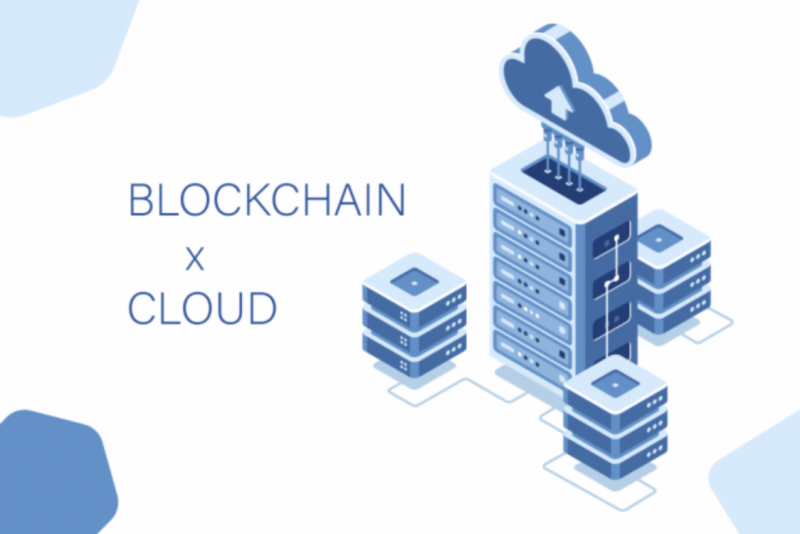
Press
2019/04/24ブロックチェーンのBaaS特化型情報サイトを4/24よりオープン!ブロックチェーン構築に必要な技術情報を集約!
ブロックチェーンのオンライン学習サービス「EnterChain」、ブロックチェーン・AIの導入コンサルティングを行う株式会社digglue(代表取締役社長:原 英之 本社:東京都文京区)は、ブロックチェーンのビジネス開発向け情報サイト【BaaSinfo!】をリリースしました。 【オープン背景】 将来、ブロックチェーンの与える社会への潜在的なインパクトは国内外で67兆円※1に上ると算出されています。今後ブロックチェーンに関連するプロジェクトはますます増え、伴ってブロックチェーン技術者ニーズや開発ニーズが増えてくるものと予想されます。 Blockchain as a Service(BaaS)と呼ばれるクラウドサービスを活用することで、ブロックチェーンプロジェクトを簡易かつ迅速に立ち上げることが容易になってきましたが、それらに必要な情報がまとまっておらず、日本語でかかれた記事も少ないことから導入を妨げる一因となっています。 ※1出典:経済産業省 「ブロックシェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査」 【BaaS info!について】 この度、BaaSを活用したブロックチェーン構築に必要な知識を集約したサイトをオープンします。 こちらのサイトでは、ブロックチェーンの基本から活用メリット、Microsoft Azureを活用したブロックチェーンの構築方法や事例などをわかりやすく記事化しています。 また、イベント情報やBaaSの最新情報などを随時更新してまいります。 ▼BaaS info http://baasinfo.net/ 【特徴】 ①BaaSに特化した唯一の情報サイト BaaSに特化した唯一のサイトとして情報を集約しております。(自社調べ) 特に、実際に構築するにあたり必要となる環境構築やブロックチェーン事例のコード紹介などを行っています。 ②コードやデモを使って事例を紹介 [caption id="attachment_36201" align="aligncenter" width="650"] solidityを使ったコードをコメント付きで解説[/caption] 本や講演などで活用の事例は、概要のみ紹介されることが多いですが、本サイトでは実際に構築するにあたり必要な作業をキャプチャー付きで解説、出来上がったブロックチェーンのサービスイメージをイラストや動画などを使って紹介しています。 ③Microsoft Azureを使ったBaaSの設定方法をキャプチャー付きで紹介 今回BaaSのサービスを展開しているMicrosoft社のAzureをベースとして、 初めてAzureを触るユーザーが躓きやすいポイントを動画やキャプチャーで丁寧に解説しています。 【今後の展開】 実際にBaaSを使われているユーザー企業のインタビューや、 イベント情報の発信などを行っていき、ブロックチェーンプロジェクトを実際に作ってみようとする方が ”最初に触る情報サイト”として展開を予定しています。

ニュース
2019/04/18ブロックチェーンゲーム「CryptoNinja IOST版」がローンチ!ゲーム内通貨がもらえるキャンペーン実施中
エバーシステム株式会社が提供するCryptoNinjaが本日、IOSTブロックチェーン上のDAppsゲームとしてローンチしました。 CryptoNinjaは昨年、Ethereumのブロックチェーン上でもリリースされましたが、ゲームをプレイするごとにマイニングコストが発生し、プレイヤーに負担を強いているという問題がありました。今回、リリースされたIOST版では、わずかなIOSTのデポジットだけでプレイ可能になり、ユーザーの利便性が大きく向上しているとエバーシステムCTOの和田氏は説明しています。 また、CryptoNinja IOST版のリリースキャンペーンとして、4月26日23:59:59までに登録したユーザーはゲーム内通貨エバーゴールド(EG)を10000EG無料で入手することができます。是非ともこの機会に登録を行って、10000EG を獲得しましょう! CryptoNinjaをプレイするにはiWalletが必要になります。iWalletのインストール方法は下記の記事を参考にしてください。 IOSTがChrome用ウォレット『iWallet』を公開。iGAS、iRAMとノードパートナー報酬受取方法を解説! - CRYPTO TIMES CryptoNinja IOST版

ニュース
2019/04/17三菱UFJフィナンシャル・グループがChainalysis(チェイナリシス)へ出資
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が、仮想通貨やブロックチェーン領域におけるコンプライアンス技術を提供するChainalysis(チェイナリシス)に出資したことを発表しました。 今回の出資は、三菱UFJイノベーション・パートナーズを通じてChainalysis, Incへの出資となっており、海外企業向けには初となる第 2 号出資案件であることを明かしました。 MUFGによる出資金は非公開となっていますが、Chainalysis BlogによるとMUFGとSozo Venturesの二つのファンドより合わせて600万USDを受けたと発表しており、日本円にして合計約6.7億円が出資されています。今回の出資により、Chainalysisは今後、アジア太平洋地域における事業拡大を図ると明かしています。 MUFGは、Chainalysisへの出資理由を、仮想通貨の基盤を担うブロックチェーン技術や分散型台帳技術の研究や、分散型金融システムの応用が進む中、システム基盤や法規制遵守への対応がさらに必要であると考えており、同社のコンプライアンス技術は、金融機関が、仮想通貨におけるマネーロンダリング対策においても非常に重要であると明かしています。 Chainalysisは2月にもAccelとBenchmarkから3,000万ドルの資金を調達しており、今回の調達と合わせた3600万ドルでシリーズBラウンドを締めくくることを発表しました。 記事ソース : MUFG Press Release , Chainalysis Blog

ニュース
2019/04/16Binance(バイナンス)が $BCHSV (BitcoinCash SV) の上場廃止を発表
2019年4月15日にBinanceはBitcoinCashからハードフォークして生まれたBitcoinCash SVの取扱を廃止することを発表しました。BCHSVは2019年4月22日にBinanceから上場廃止となります。 BinanceからのBCHSV上場廃止のアナウンスを受けた直後、BCHSVは現在、約10%近い価格の下落が見られました。 Binanceでは過去にも上場廃止のアナウンスを受けた通貨は数種類あり、上場廃止の基準は下記の通りとなっています。 プロジェクトへのコミットメント 開発活動のクオリティとレベル ネットワークおよびスマートコントラクトの安定性 パブリックコミュニケーションのレベル Binanceのデューデリジェンスへの対応の速さ 非道徳的、詐欺行為の証拠 健全で持続可能な仮想通貨エコシステムへの貢献度 今回のBCHSVの上場廃止は、BinanceのCEOであるCZからも4月12日時点で警告が出されており、時間の問題だったことが伺えます。 https://twitter.com/cz_binance/status/1116563034476957699 クレイグ・ライト氏が、Hodlonaut氏を含む、同氏をサトシ・ナカモトであることを否定する者を告訴する準備をしていることが発端となった今回の上場廃止発表ですが、CZは明らかにクレイグ・ライト氏は詐欺であるとも意見をするツイートが見受けられます。 https://twitter.com/cz_binance/status/1117606851351179264 今回、BCHSVが上場廃止になったことは勿論ですが、Binance(CZ)がBCHSVを上場廃止にしたことが世間にとって、どのように映るかということが今後の注目ポイントであると考えられます。 Binanceは今まで、上場に関して自信たちがチェックした上で良いプロジェクトのみをという判断基準で上場を行ってきました。しかし、今回の上場廃止は、自分たちの匙加減で上場廃止になっていることが、ツイートより明らかに伺えます。 今回のBinanceのBCHSV上場廃止という決定が、今後、Binanceやその他市場に対して、どのように影響を及ぼすかに非常に注目が集まります。 Binance(バイナンス)CEOがクレイグ・ライト氏に警告 ビットコインキャッシュSV上場廃止も視野に - CRYPTO TIMES 記事ソース : Binance , Twitter

ニュース
2019/04/15楽天による取引所『楽天ウォレット』が本日より新規口座登録を開始!
3月25日に認可を受けたばかりの仮想通貨取引所『楽天ウォレット(旧みんなのビットコイン』が本日4月15日から新規口座開設の申し込み受付を開始したことを発表しました。 楽天ウォレットは仮想通貨取引サービスを6月より開始予定としており、今後はスマートフォンアプリの提供も予定しているとしてします。 楽天ウォレットの取引口座開設の申込受付において、「楽天銀行」の口座をもっているユーザーの場合、Web申込フォーマット上に必要情報を入力するだけで口座開設が可能となっており、口座開設におけるプロセスが簡略化されています。 楽天ウォレット Website 記事ソース : 楽天Press Release

ニュース
2019/04/15マネーフォワードフィナンシャルが仮想通貨関連事業への参入延期を発表
株式会社マネーフォワードの100%子会社であるマネーフォワードフィナンシャル株式会社が2019年4月15日、仮想通貨交換業の登録手続きを中止し、同事業への参入を延期すると発表しました。 2018年5月にブロックチェーン・仮想通貨事業への参入を発表しており、2018年9月にはブロックチェーン/仮想通貨メディアである「Onbit」をスタートさせていました。 今回の仮想通貨関連事業への参入延期の発表では、下記の4項目を決定事項としています。 1.仮想通貨関連事業の参入延期と交換業者登録に向けた手続きの中止 2.取引所・交換所に関するシステム開発の停止 3.ブロックチェーン・仮想通貨に関するメディア『Onbit』のサービス終了(2019年5月31日予定) 4.ブロックチェーン技術の開発を目的とした研究の継続 今回の決定要因として、仮想通貨市場が急速に冷え込み、事業の収益性におけるダウンサイドリスクが高まったこと、体制整備におけるコストが上昇したことが要因であると発表文で述べました。 記事ソース : マネーフォワード Press Release

ニュース
2019/04/08$ETH の価格が5ヶ月ぶりに2万円に、ビットコインも強気な値動きか?
4月上旬より強気な相場になっている仮想通貨市場ですが、11月16日の下落相場を皮切りに2万円を割ったETHが、5ヶ月ぶりに価格を2万円代へと戻しました。 [caption id="attachment_35571" align="aligncenter" width="666"] 画像引用 : みんかぶETH/JPYチャート[/caption] 今回のETHの価格上昇は特に主だった要因はありませんが、引き続き仮想通貨市場が強気相場になっていることがあげられます。 Bitfinexのデータを参考にしているLSチェッカーを見ると、ETHのロング(買い)とショート(売り)の比率は、徐々にロングの方が大きい割合になっていき、4月8日の5時から10時にかけて、50,000ETHのポジション増加が見られることより、価格も押し上げられたことが予想されます。 [caption id="attachment_35574" align="aligncenter" width="800"] イーサリアムLSチェッカー[/caption] もちろん、取引所はBitfinexだけではないのであくまでも参考ではありますが、同時刻で多く買いが入ったことは事実であり、引き続き、投資家からの注目も集まっています。現在でもETHは2万円台を推移しています。 また、現在の強気市場は中国からの非常に強い購買意欲により、作られていることが考えられます。 https://twitter.com/cnLedger/status/1115070888196464640 上記のツイートによると、現在の中国の仮想通貨市場ではUSDTの需要が非常に高まっており、需供が歪み、USDTの価格が上がるという現象が起きています。 通常だと、1USD = 6.7 CNY(人民元)のレートにもかかわらず、1USDT = 7.0CNY(人民元) のレートのなっており、プレミアム価格になっています。 現状、中国ではOTCを介さなければ、中国人民元を入金して、仮想通貨を購入することができません。今回、このレートがプレミアム価格になっていることは中国からの高い需要があることが伺えます。 Coinlibが提供するデータによると、過去24時間で1億2,700万ドル、7,240万ドル相当の人民元がBTCとETHに流入していることからも、この強気相場は中国人から発生している可能性が高く、どこまでこの熱狂が続くのかに注目が集まるとともに、今後の価格下落に対しての不安も考えて置かなければなりません。











 有料記事
有料記事


