
最近書いた記事

プロジェクト
2018/02/28Stellar(ステラ) ミートアップで今後の動きについて言及!
こんにちは!Shota(@shot4crypto)です!! 今回はStellarのGopax・Mobiusとのミートアップで発表された内容から、期待できる今後の動きや展望についてを紹介していきたいと思います! この記事の3つのポイント! Stellarが近い将来プライベート送金に対応すると発表 14の銀行がStellarとIBMのインターバンクの送受金の試験運転に参加 いくつかの中央銀行にStellarのブロックチェーン上への通貨発行を交渉中 本記事引用元:Transcript of Stellar’s Meetup with GOPAX and Mobius 以下はStellarの業務提携に関しての取締役であるElla Qiang氏(@ellaqiang9)の発表とそれに対する僕個人の見解になります。専門家の意見ではないので参考程度に目を通す程度でお願いします! ライトニングネットワーク実装について 私たちはStellarのトラフィックが増えた際に、スケーラビリティ問題を解決することを目的として、ライトニングネットワークとの統合に向けて動いています プライベートチャネルにも対応しているのでトランザクションを匿名で行うこともできます。 ライトニングネットワーク実装はSDF(Stellar Development Foundation)がネットワーク上で1000~3000以上トランザクションが起こることを想定した動きと捉えることができます。匿名トランザクションに力を入れていることからも、これに関しての何かしらの懸念があることがわかります。 StellarDEX(Stellar分散型取引所)のUIに関して 今年の最も力を入れていく部分はSDEXに使いやすいUIを搭載することです。これに関しては最近ニューヨークでSDEXの初期段階のUIデザインを手掛けてくれる素晴らしいチームを採用しました。 このUI刷新のゴールはユーザーが中央集権型の取引所か分散型かどちらを使っているかわからなくなる、BinanceのようなUIの取引所を創り上げることです。 Stellarの分散型取引所のユーザビリティについては以前から問題視されてきましたが、StellarPortのリリースに続き更なるユーザー目線でのインターフェース改善を目指していくようです。 関連記事:Stellarが分散型取引所(DEX)のStellarportをリリース IBMインターバンクの送受金に関する試験運転について インターバンク間での送受金に関してはIBMのチームが先導しています。現在このプロジェクトには14の銀行が関わっています。 IBMからのアナウンスによれば今年の中旬くらいには何かしらの新たな発表があるのではないかと考えられます。 インターバンクということで、まずは金融資産をサポートすることに力を入れているようです。日本からも三井住友やみずほグループがこれらの動きに参加しているようなので今後の動向に注目ですね! 中央銀行との交渉 また、私たちはいくつかの中央銀行との話も進めています。Stellarのブロックチェーン上に中央銀行が後ろ盾となる通貨を発行できるかといった内容に関してです。Stellarはそれらの中央銀行の一候補となっているようです。 これが実現すれば、国際的な貨幣の流通形態の全体に影響を及ぼすことになりそうです。途上国における決済・取引が改善されることで新たな経済圏の形成まで考えることができます。既に話を進めているということなのでこちらの動きにも注目していきたいですね。 加速する国際送金 今年末までには、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナムなどの私たちの提携先からのより多くのトランザクションを目にすることになるでしょう。 インフラにおいて大規模な需要があるこれらの東南アジア諸国において、こういった提携は開発をさらに加速させるものとなると思います!中東やアフリカ、南米などにも提携を拡大させていくようなので目が離せないですね! 以上が今回のミートアップでの発表を一部抜粋したものになります。 Stellarが知らないところでものすごいスピードで動いているようで、今後のアナウンスも期待ができそうです! ミートアップの動画はこちら

ニュース
2018/02/26ロシアのプーチン大統領 ブロックチェーンに対して前向きな考えを示す
この記事の3つのポイント! ブロックチェーン技術の採用は必要不可欠 将来的に銀行のサービス・製品として仮想通貨取引のプラットフォームを創り上げる 規制とは投資家を保護しビジネスをより円滑に進めるためのものである 本記事引用元:Vladimir Putin Says Russia Needs Blockchain, Cannot be Late in the Race ロシアの大統領であるプーチンは『ロシアにはブロックチェーン技術を導入する必要がある、この革新的な技術の開発と採用に乗り遅れないことが重要』と話しました。 ロシアの市場に個性的な洞察を提供するメディアであるRussian Insightは、プーチンと国内最大手の銀行であるSberbankの総裁のHerman Gref氏の対談の様子を公開しており、その中でプーチンは『ブロックチェーン技術の導入が必要だ。石器時代は石器の枯渇により終わったのではなく新たな技術の登場により終わった。この競争に乗り遅れるならば一瞬でこの技術を操る者に従属することになるだろう』と話し、国、規制する側、地元の銀行がいち早くブロックチェーンの技術を採用していくことの必要性を強調しました。 国内で最も影響力のある金融機関を監督しているGref総裁ですが、彼は長い間、仮想通貨とブロックチェーンに強い興味を持つ愛好家でした。 昨年11月、彼は、『仮想通貨は避けられない事実として生活の中に存在し、世界の金融システムに不可欠なものになる』と述べました。『仮想通貨はブロックチェーン技術が自然ともたらした功績である。禁止されるかもしれないし、快く受け入れられるかもしれない。人々に仮想通貨を利用しないように促すこともあるかもしれない。しかしながらその問題に触れず、避けて通ることは決してできない。』とロシアの起業家連合の会合でも話していました。 1月の後半には、銀行が将来的に仮想通貨の取引ができるプラットフォームを創り上げることも言及しており、それによって急速に成長するビットコイン及びその他の仮想通貨に対する需要を獲得できる見込みです。 同SberbankのAndrey Shemetov氏によれば、銀行は仮想通貨の市場において投資家が必要とするであろうすべてのサービスや製品をカバーすることを目標としているようです。 同月プーチンは、規制とは全ての投資家を効率的に保護し、そのビジネスをより容易に成長させるためのものであり、また、仮想通貨はその規制の中で取引や介在するネットワークの媒体として利用することができると話しましたが、仮想通貨の価値保存の仕組みについては懸念を示しています。 しかし、株や証券、その他の資産も全ては市場が価値を決めています。したがって仮想通貨の内在的な価値の欠如はそこまで重要な問題ではなく、市場が価値を決めている今現在の価値が重要であるとしています。 shota プーチンの力技感嫌いじゃないです!!!!

ニュース
2018/02/23米ニュージャージー州の高校で仮想通貨の授業が行われる
この記事の3つのポイント! アメリカの高校で正式に仮想通貨の授業が行われる 国内の大学では既に人気のある講義として定着している ブロックチェーン関係の企業も成長の絶好の機会として認識 本記事引用元:The crypto craze is here to stay — now it’s even being taught in high school 米・ユニオンカトリック高校で仮想通貨についての授業が行われる アメリカのニュージャージー州スコッチプレーンにあるユニオンカトリック高校で仮想通貨に関する授業が、学内の中学生、高校生向けに行われました。北米の学校のシステムは特に田舎の地域であれば、中学から高校卒業までを6年制とすること通常で、今回は在学する中学生と高校生向けに仮想通貨の授業が行われました。 同校に在籍し、歴史と金融リテラシーなどを専門に教えている28歳のTimothy breza氏は、今年の授業に初めて暗号通貨のセオリーに関してのカリキュラムを担当する授業に取り入れました。昨年の10月から11月にかけて一部の生徒たちから、仮想通貨やデジタル通貨に関しての質問を受けていたことが今回の決断の要因となったようです。 これに関して彼は、『一部の生徒が興味関心を持っていれば、その周りの多くの生徒も関心を持っているはずなので、これをカリキュラムに加えた』と話しました。 彼のクラスでは履修を選択した生徒に対して、お金を稼ぐこと、節約、クレジットカード、税金、投資、会社設立、ビジネスプランの立て方など、主にお金に関係する内容の授業を展開していました。現在では、学校の職員の方々の了解を得たうえで、仮想通貨の歴史的な部分や、ブロックチェーンの世の中への適応可能性などの部分を中心とした授業作りに注力しています。 高校でこのように仮想通貨に関しての講義が行われることは珍しいことですが、アメリカ国内の短期大学ではこのようなことは珍しくもないようです。 スタンフォード大学のコンピュータサイエンス学科の教授であるDan Boneh氏によれば、仮想通貨に関しての講義は同学科の中で2番目に人気のあるものとなっているようです。 業界の人々もこの変化に対して好印象を示している LinkedIn(アメリカのビジネス型SNSサービス)の発表によれば、2013年時点と比較して、プロフィールに仮想通貨関連の技術を持つと記載している人々が28倍、ビットコインに関しての技術を持つと記載している人々が5.5倍に増えているようです。 しかし、現状では会社ごとに仮想通貨の正式な教育に関しての意見は異なっています。 SingularDTVというブロックチェーンエンタメメディアを運営するCSOのShreesh Tiwari氏は『仮想通貨の教育も重要であるが、新しいことを進んで学ぼうとする意欲がある人材を求めている』と話しました。 一方でCoinbaseの人材責任者であるNathalie McGrath氏は『新卒の人材を採用していくうえで、(仮想通貨に関しての教育を受けてきているので)彼らはCoinbaseでなぜ何をすべきか、ということに対して深い知識の土台と理解がある』また、『今このタイミングでの新卒採用は絶好の機会であり、成長するいい機会になるだろう』と話しました。 shota マネーリテラシーの教育は死ぬまでに一回ぐらい受けてみたいです......

ニュース
2018/02/20米大手送金サービス ウエスタンユニオンとRippleの提携 今後の展望
この記事の3つのポイント! 米大手送金サービスウエスタンユニオンがXRPの送金テスト xRapid採用を目論む大手との提携は2社目 今後もRipple社の送金サービス会社との提携に注目 本記事引用元:Ripple (XRP): How the Western Union Partnership is Only the Beginning 米大手送金サービスのウエスタンユニオンがXRPの送金テスト 『速い、安い、数分で届く』をキャッチコピーとしている、アメリカ合衆国に本拠地を置く国際送金サービスのウエスタンユニオン(Western Union)のCEOから、Ripple社のxRapid(仮想通貨XRPを利用した高速送金システム)を利用した送金のテストを行っているとの発表がありました。 1月のRipple社のCEOであるBrad Garlinghouse氏によるアナウンスによれば、送金を担う世界のトップ5社がXRPを利用した送金のテストを開始するとのことでした。 この第一社目にあたるのがMoneygramの送金テストで、今回の発表にもあるウエスタンユニオン社はこれに続く送金テストとなります。この発表によるXRPの市場価格の変動はまだ見受けられませんが、XRPにとってこの提携は大きな好機となります。 ※先日の記事にあった香港のLianLian社との提携は、xRapidではなくxCurrent(XRPを使わない高速送金システム)を使った提携でしたので、この頭数に含まれないと考えます。(関連記事:Ripple社 香港の送金サービス『LianLian』と提携) XRPの今後の展望 提携はまだ始まりに過ぎない 先日、市場規模が100兆円に達したXRPですが、送金スピード、送金手数料を削減するだけでなく、既存の世界中の人々が資産を移動させる仕組みさえをも揺るがすものとなると言われています。 現時点での問題はXRPを買うことのできるプラットフォームが仮想通貨の取引所しか存在しないことです。これらの取引所では、確かに誰もがXRPをはじめとする仮想通貨の購入こそはできるものの、それらのサービスの主要なターゲットはどちらかというと投資家であるように見えます。 こうしたどちらかというと投資家向けにアレンジされたプラットフォームではなく、誰もが参加する市場向けに使いやすい(僕のイメージだとネットバンキングのような)プラットフォームがあれば、FIAT同士のブリッジ役としてより容易にXRPとしての機能が果たせると考えられています。 上述の通りXRPはFIAT同士のブリッジ役としての機能が主であるので、これらの提携は例えばスターバックスでXRPが利用されるようになることを意味しないかもしれません。しかし、Ripple社がより多くの企業と提携を結び成長することができれば、指数関数的に採用され多方面で実用化されていくことがより現実的に見込まれます。 関連記事:【仮想通貨】Ripple(リップル) / XRP とは?国際送金を迅速かつ格安に! shota 送金という一面だけを考えると現在までの提携も相まって最強感ありますね! shota 資産の移動はXRPを使って相当早くなりそうですが、モノがどのようについてくるのかって感じですね~~

ニュース
2018/02/20【仮想通貨】Ethereum Classic(イーサリアムクラシック) / ETCの特徴・仕組みを徹底解説!押さえておきたいEthereumとの違い
こんにちは、Shota(@shot4crypto)です! 現在時価総額14位のEthereum Classic(イーサリアムクラシック/以降ETC)は、Ethereum(イーサリアム/以降ETH)のハードフォークにより誕生したコインです。 この記事ではETHとETCって具体的に何が違うの?という疑問を解決すべく、ETCについてETHの特徴と並行して、異なるポイントを比較・解説していきます。 Ethereum Classic(イーサリアムクラシック) / ETCの概要 Ethereum Classicのスペック Ethereum Classic(イーサリアムクラシック)概要 最大供給量 - 現在の供給量 99,976,807.0ETC アルゴリズム Ethash 承認方式 Proof of Work (PoW) ブロック生成時間 10.2秒 難易度調整 毎1ブロックごと ブロック報酬 4.0ETC 公式Twitter @EthereumClassic 公式Webサイト https://ethereumclassic.github.io/ この中で赤字の部分がEthereumと共通(≠互換)する部分になります。 Ethereum Classic誕生の背景 DAO事件 Ethereum Classicの誕生を語る上で必ず覚えておきたいのが分散型の投資ファンドである『The DAO』の事件です。 The DAOは2016年に発足した、非中央集権の投資ファンドです。ユーザーはイーサリアム(ETH)を使ってDAOを購入し、それによってThe DAOに資金が集まる形で運営されていました。 ところが発足から間もなく、イーサリアムのスマートコントラクトのシステムの脆弱性をハッカーに突かれ、約5300万ドル(日本円約65億円相当の)ETHが不正送金される形になりました。 事件から分裂まで この不正送金を受けて、イーサリアムの開発チームからはこの不正送金に対処するための以下の3つの案が出されました。 ソフトフォーク(以降SF) ハードフォーク(以降HF) 誰も何も行わない HFとは簡単に言えばブロックチェーンの仕様変更のことで、HF後はHF前のブロックチェーンとの互換性がなくなることになります。一方でSFとは、同様に仕様の変更なのですが、SF前後のブロックで互いに互換性を持ちます。 今回のケースだと、約65億円相当のETHがハッカーの手に渡ったことで開発者チームの一部は、『イーサリアムをHFをさせることにより、この不正送金を(互換性を絶つことにより)無効にすることができるのではないか』と考えました。 しかし、開発者チームの中には、『このHFは(最近のBitcoinのHFなどと違い)、イーサリアムを通貨として仕様変更するためのものでも、通貨としての欠陥を改善するためのものでもない』『イーサリアムのシステム上の変更のためではなくDAOのセキュリティに問題があったために仕様を変更するのは恣意的である』とし、旧仕様のチェーンを守ろうとしました。 こうしてHFされた新仕様のブロックチェーン上で動くものが新たなイーサリアム(ETH)となり、HFせずに旧仕様の人為的な変更を許さなかった開発者によって守られたものがイーサリアムクラシックとなりました。イーサリアムクラシックのクラシックの所以は旧仕様のブロックチェーンを引き継いでいることにあります。 HF後のチェーンを利用しているのがイーサリアムで HF前の古い(クラシックの)チェーンを利用しているのがイーサリアムクラシックです。 間違えやすい部分だと思うので覚えておくといいかもしれません! 分裂後は? イーサリウムのHF後も互換性がなくなっただけで基本的にはETHとETCは共に同じシステムをベースにして作られていたので、特に両者に違いはありませんでした。また、HF時にETHを保有していた人々に同量のETCが配られたために、しばらくの間は両者の間に価格の連動が見られました。 しかし互換性がない以上、イーサリアム、イーサリアムクラシックの両者が独自路線で開発を進めたり、あるプロジェクトがどちらか一方を採用すると、その進むべき道に差が生じてくるのは当然のことです。 以下の2枚のチャートは直近1か月のETHとETCのチャートですが、最近になって価格の連動がなくなりその差が顕著に表れていることがわかると思います。 <ETHの直近1か月の値動き> <ETCの直近1か月の値動き> Ethereum Classic(イーサリアムクラシック) / ETCの特徴 イーサリアムクラシックの3本柱 旧仕様のブロックチェーンを利用しているイーサリアムクラシックは『Decentralized(非中央集権的)』、『Immutable(不変的)』、『Unstoppbale(止めることのできない)』という3点を軸にして開発されています。これらは、HF前のイーサリアムでもオリジナルのビジョンとして重要視されていました。 というのも、ETCはDAO事件で恣意的なHFを行った開発チームに賛同できない人々が作り出した通貨ですので、イーサリアムの根幹となる信念のようなものを忠実に引き継いでいることがわかると思います。 イーサリアムクラシックには『Code is Law(コードは法である)』という原則があります。 イーサリアム系トークンの最も大きな特徴にスマートコントラクト(後述)というものがありますが、このコントラクト(契約)もコードによって定められている契約で、コードがあってこそのシステムだとする考えに基づいているということです。 この考えによれば、我々ユーザーが唯一できることは、あくまでも3本柱に則った上で、その中で自発的に契約に介入(例:送金など)することのみであるとします。 スマートコントラクトとは? スマートコントラクトとは、イーサリアムクラシックだけでなくイーサリアムにもあるシステムで、『ある条件(事前にプログラムされている条件)を満たしているときに自動的にアクションが執行される仕組み・システム』のことを指します。 上述の『Code is Law』という考えはコントラクト(契約)は管理者や法の代わりにコードが自動でアクションを執行しなければいけないという3本の柱(『Decentralized』『Immutable』『Unstoppable』)に則る形が原則となっています。 また、これらのコード(管理者を持たざる法)は全てブロックチェーン上で公開されているため、完全に公平かつ非中央集権的なシステムであるという点から注目を浴びています。 Ethereum Classic(イーサリアムクラシック) / ETCのチャート・価格推移 ETCBTC by TradingView Ethereum Classic(イーサリアムクラシック) / ETCを取り扱っている取引所 現段階でETCを取り扱っていて日本から利用可能な取引所はHF当時に比べるとかなり増えましたが、その中でも使い勝手のいい取引所を紹介させていただきます! 個人的には国内だとセキュリティ評価が世界一と謳われているbitFlyer、海外だと取り扱い銘柄が豊富なBinanceをお勧めします! <国内取引所> bitFlyer(ビットフライヤー) Coincheck(コインチェック) <海外取引所> Bittrex(ビットトレックス) Poloniex(ポロニエックス) Binance(バイナンス) Bitfinex(ビットフィネックス) Huobi(ホービ) Ethereum Classic(イーサリアムクラシック) / ETCのウォレット イーサリアムクラシックのウォレットはClassicEtherWalletというウェブサイトで作成することができます。 ClassicEtherWalletではパスワードを入力するだけでウォレットを作成することができ、その後のウォレットは秘密鍵やニモニックフレーズなどを利用して安全に管理することができます。 まとめ イーサリアムクラシックが誕生するまでのストーリーから、イーサリアムとの違いを詳しく解説しましたがいかがでしたか?おそらくここまで読めば、今まであいまいだったETHとETCの違いなどもなんとなくつかめてきたのではないかと思います。 最近ですと、両者の価格の連動性がなくなってきていて、ここ1週間の値動きを見るとETCがETHを差し置いて高騰しているのも十分に面白いポイントだと感じます!

ニュース
2018/02/19スイスの金融市場監督局 FINMAがICOに関するガイドラインを発表
2/16にスイスの金融市場監督局 FINMAからICOに関するガイドラインが発表されました。 このガイドラインはICOを行う機関からの問い合わせを受けた際にどのように金融市場の法律に適用させるかという点を定めるものです。 また、市場参加者に透明性をを与えるために、FINMAがICOの問い合わせを受けた際にどのような情報を処理しなければならないのか、また可否の結果は何を元に判断されるのかという点においても言及しています。 この記事の3つのポイント! FINMAがICOに関してのガイドラインを発表 トークンを利用用途や目的に拠って3種に分類 今後申請されるICOはこのガイドラインに基づいて判断される 本記事引用元:FINMA publishes ICO guidelines FINMAがICOに関してのガイドラインを発表 スイスではICOの計画やICOが実際に行われた件数が急激に増加しており、それに伴ってICOに対して規制がどう適用されていくのかという点に関しての問い合わせの件数も増加していました。 それに伴い、規制や法律がどう適用されていくのかが部分的に不明確であった点について、FINMAは2017年4月のガイドラインを刷新し新たなものを発表しました。 このガイドラインは、FINMAがICOを行う機関からの問い合わせに対してどのような基準で対応していくのかを明確に定める意図があります。高い需要と動的な市場であるという2点を踏まえると、この段階で今回のガイドラインのような透明性を作り出すことは重要であると考えているようです。 それぞれのICOがそれぞれのメリットを元に判断されるべき 金融市場の法律や規制は現状100%のICOに適用することはできません。また、ICOが行われている方式によっては、必ずしもそれらのICOが既存の規制の対象になるわけではありません。 2017年4月に発表され定められたガイドラインでは、金融市場の規制によって潜在的に大きな打撃を受ける可能性のあるICOの分野がいくつかあります。現在では、ICOのみに特化した規制そのものは存在せず、ICOに関しての判例や一貫した法律なども存在しません。 しかし、これらの規制や法律の適用は臨機応変に適用されるべきであるという観点から今回の刷新されたガイドライン発表に至りました。 FINMAのガイドラインは原則トークンの機能と取引可能性に基づく ICOを評価する上でFINMAは、ICOを行う機関から提出されたトークンの経済的機能と発行する目的を重視します。主な要素はトークンの根底となる目的と、それらが既に取引や送金が可能であるかという点です。 現在ではスイス国内にも国際的にも、一般的にトークンの種別を分類する用語はありません。そこでFINMAはトークンの種類を3つに分類しました。(中には3つのうちいくつかが組み合わさる形もあります。) トークンのカテゴライズ FINMAはトークンのICOを行う際、そのトークンの特性に応じてPayment Token、Utility Token、Asset Tokenの3種類にカテゴライズするための基準を設定しました。 Payment Tokens(決済型トークン) 仮想通貨に近いトークンのことで、決済以外の機能やその他の開発プロジェクトへのリンクが何もないものを指す。決済として必要最低限の機能を持ち、そのうちに決済の手段として受け入れられる可能性があるもの。 Utility Tokens(実用型トークン) アプリやサービスにアクセス権を与えるトークンのことを指す。 Asset Tokens(資産型トークン) ネットワークではなく実際に存在する会社や収益源に与したり、配当や利払いにも与するトークンのことを指す。経済的な機能としては、株式や債券、デリバティブに類似している。 ICOの申請に対するガイドライン 上記のように定義されたトークンの分類に基づき、ICOの申請に対してどのようにプロジェクトを扱うのかをICOガイドラインとして発表しました。 Payment ICOs(決済型ICO) トークンが決済の手段として機能することを意図して発行されていて尚且つ送受金が既に可能であるICOを指す。これに対してFINMAはマネーロンダリング防止のための規制へのコンプライアンス遵守を求める。ただしFINMAはこれらのトークンを証券としては扱わない。 Utility ICOs(実用型ICO) トークンがアプリやサービスにアクセス権を与える(既に与えている)事としてのみ機能する場合このトークンは証券としての資格を持ちません。しかし、部分的にでも経済的な側面での機能がある場合、FINMAはこれを証券として認めるとしている。 Asset ICOs(資産型ICO) FINMAは資産型のトークンを証券として扱う。したがって、それらのトークンを取引する際には証券取引法や市民法、スイス債務法の要件を満たしている必要がある。 ICOはこれらの複数を組み合わせてカテゴライズされることもある。例えばマネーロンダリング防止の規制は、決済に使われる可能性のあるUtility Token(実用型トークン)にも適用される。 FINMAによるトークン/ICOの定義 Payment Tokens/ICOs Utility Tokens/ICOs Asset Tokens/ICOs 用途 決済のみ アプリ開発 サービス開発 証券 法の適用範囲 コンプライアンス遵守 一部証券として扱う 完全に証券として扱う まとめ ブロックチェーン技術には革新的なポテンシャルがある この監督を強化するためのガイドラインの発表の後でも、ICOが多様になるにつれて、FINMAが将来的に新たな解釈のガイドラインを発表する可能性はあります。 FINMAはブロックチェーン技術の革新的な可能性を認識しています。したがって連邦政府の”ブロックチェーン/ICO ワーキンググループ”を支持しています。スイス国内で市民法の枠組みに透明性を持たせることは、スイスでブロックチェーンの技術を持続可能かつうまく築き上げる決定的な要因となります。

ニュース
2018/02/18ビットコインが安く掘れる国はどこ? 114カ国徹底比較!
コンピュータをネットに繋いでおくだけで、あるいはリグを組んでおくだけで、無からお金が生み出されるマイニングは非常に魅力的ですよね。 ですが、やはり時間が経つにつれてマイニング業界というものはより洗練され、競争が激しいものになってきています。 この記事の3つのポイント! マイニングにおける採算性って? マイニングをするならこの国だ! 日本は114カ国中、何番目? 本記事引用元:Mining Margins and Where to Make the Most Money マイニングは儲かるのか検証してみた マイニングで儲かるか儲からないかの線引き(採算性があるかないか)は全て費やすリソース(電気料金)に依存しているといっても過言ではありません。 日本国内においてもこの事実に気付いた一部の人々は、電気代の安い田舎に引っ越してマイニングをしているとの話を聞きます。 マイニングコストの検証方法 では、世界で見たときにどの国が最も効率よくビットコインを掘れるのでしょうか? Elite Fixtures社によって行われたリサーチは、3種類の異なるマイニングリグを世界114カ国で使用した場合に1BTCを掘り終えるまでのコスト(電気代)がいくらかかるのかというものです。 今回検証に使用したマイニングリグは AntMiner S7 AntMiner S9 Avalon 6 の3種類で、電気利用料金のデータは各国の政府や地元の電力会社から得たデータをもとに算出しています。 上位5カ国と下位5カ国 上位5カ国は上から、ベネズエラ、トリニダードトバゴ、台湾、ウズベキスタン、ウクライナ 下位5カ国は下から、韓国、ニウエ、バーレーン、ソロモン諸島、クック諸島 となっています。 なお電気代が最も安いベネズエラと最も高い韓国を比較すると、1BTCを掘るのに必要な電気代の差はUSD換算で$25,639となっています。その差約49倍以上です....!! 日本は何番目? 日本の1BTC採掘にかかるコストはUSD換算で$8723で、世界で見るとキプロス、ウルグアイと同率で33番目に高いです。 現在のBTCの価格の$8943(記事執筆時点 / Bitcoin.com参照)を考えると、国内でこれらのマイニングリグを組み立ててビットコインを掘るのは少し微妙な気もしますね。 昨年末のように240万円近くの価値があれば試してみる価値はあるかもしれません笑 参考URLはこちら(外部リンク) まとめ 以上のデータを参考にすると、 西ヨーロッパは比較的マイニングにかかる電気代が高めでこれから事業を設立しようと考えている方にとってはあまり好ましくないかもしれません。 逆にベネズエラなどの南アメリカ地域の国々では電気代が114カ国の中では比較的安くおさまっています。 shota 6万円弱で1BTCが掘れるベネズエラ最強っすね!!!! shota リグを組んでベネズエラに移住するレベルの人間を目指して日々努力!!
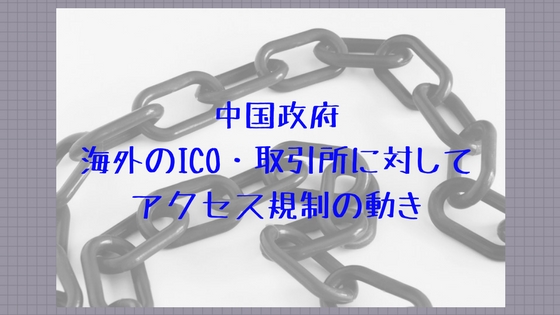
ニュース
2018/02/17中国政府 海外の取引所やICOに関連するサイトへのアクセスを遮断?
この記事の3つのポイント! 中国政府が海外ICOや海外取引所へのアクセス規制の方向へ 約1年前から打たれていた取り締まりへの布石を更に強化 中国政府は国民の投資のリスクを減らすためと発表 本記事引用元:Report: China Cutting Access to Overseas Crypto Trading 海外の取引所やICOへのアクセスを遮断? 報告によると、中国政府は中国国外で行われているICOや国外の取引所への国内からのアクセスをブロックする方向で動き始めたようです。 中国人民銀行が関係する経済ニュースの発表は、当局は約一年前からこういった仮想通貨に熱心な国民の動きに対して、取り締まりを進めていたことを示唆しています。 こうした動きは、中国が正式に違法な資金の流れを生み出すおそれのあったICO(Initial Coin Offerings)への投資を禁止した数か月前から進んでいるようです。 また、当局はICOへの投資だけでなく昨年秋の中国国内の"ビッグスリー(Big Three)"と呼ばれる3つの取引所の閉鎖などにも関与していました。 今回の新たな報告では、国内取引所を閉鎖したのち海外の取引所に流入し、仮想通貨への投資を続けようとする国民が後を絶たないため、今回の動きのターゲットはそうした国民が流れていく海外の取引所へのアクセスに対するものだとしています。 中国語のニュースサイトXinhua(新華社通信)やビットコインソーシャルメディアの8btcによれば、2月4日に発表された海外の仮想通貨やICOのアクセス禁止のみならず、当局は国内外の取引所や仮想通貨に関連するビジネスモデルすべてを禁止していく方向で動いているようです。 shota ちょっと前Binance東京移転とかのニュースありましたけど関連してるんですかね? shota キャピタルフライトを恐れている中国の姿が頭に浮かびます笑

ニュース
2018/02/17米大手取引所Coinbase 顧客から過剰請求の疑い
この記事の3つのポイント! Coinbaseから顧客のクレジットカードに過剰に請求された疑い Coinbase側はVisaのエラーと主張 過剰に請求された金額分については全額返金を確約 本記事引用元:NEWS Coinbase, What a Mess: Users Accounts Dried Up Breaking: VISA officially blames cryptocurrency overcharge scandal on Coinbase Coinbaseが顧客から過剰請求の疑い アメリカの大手仮想通貨取引所であるCoinbaseが顧客のクレジットカードから必要以上の金額を請求していた疑いが持たれています。 アメリカのソーシャルニュースサイトであるredditではCoinbaseがユーザーの銀行口座からから必要以上の金額を請求し決済が行われていたことが数百件以上報告されています。この報告に拠れば、Coinbase側から不正に請求されたは数倍から最大で50倍にまで及んでいます。 https://twitter.com/coinbase/status/964280807836667904 この事実が発覚した数時間後、Coinbase側からは、『問題があることは確認できたが、この原因はVisa側のエラーのためである。』と発表されました。 しかし、この発表の後にVisa側から発表された返答は、『Visa側は顧客から報告されている症状であるトランザクションの複製引き起こすようなシステムの変更はしていない』とのことでした。 さらには、『金融機関に働きかけてVisaカードを利用する顧客が未承認のトランザクションでから守られていることを確認している。』と発表しています。 TheNextWeb(引用元)からのこのニュースを受けてCoinbase側は、直近の銀行と金融機関の業種コードの変更がこの問題に関与しているのではないかとして調査を進めています。 また、顧客が不正に請求された金額分についても、『自動で全額を補填することを保障する』と話しました。具体的な返金の日時などはまだ発表されていません。 <Coinbaseの公式ツイート> https://twitter.com/coinbase/status/964316806411268096 https://twitter.com/coinbase/status/964318109933879297 shota さすがアメリカの大手だけあって顧客への対応が早いですね!!!! shota 日本の取引所もこういったトラブルが起きた際に顧客第一の姿勢でスピーディーに対応してほしいですね!!!!

ニュース
2018/02/16Stellarが分散型取引所(DEX)のStellarportをリリース
本日、Stellar Lumens(XLM)の分散型取引所であるStellarportがリリースされました。 Stellarの分散型の取引所は現在まで様々な形で稼働されていましたが、今回リリースされたStellarportはウォレット機能がついていたりと、最も使いやすいものになっていると考えられます。 しかし、この取引所はStellarを発行したStellar Foundationのモノではなく、全く別の企業がStellarのシステムを使って作ったものだということが確認されています。 この記事の3つのポイント! Stellarの分散型取引所であるStellarportがリリース ウォレット作成機能などを搭載 Stellar(XLM)の出来高が爆発的に増えている 本記事引用元:Stellarport, Stellar Lumens’s Decentralised Exchange, is now live 分散型取引所(DEX)Stellarportとは? 分散型の取引所であるStellarportはブロックチェーン上に存在する取引所のことで、Stellarportを利用するユーザー同士が直接自らの資産を必要に応じて交換できる場所のことです。 売買する資産は取引所を経由せず、取引を媒介する人間も機関もありません。 分散型の取引所とはいわば、買いたい人と売りたい人をマッチさせるサービスのようなものです。 Stellarportは他のイーサリウムのエコシステム上で動く分散型の取引所とは違い、ユーザーのリストを保有しているただ一つの公式な分散型取引所です。 これによって出来高や流動性などの中央集権的な取引所のメリットとセキュリティや費用対効果などの分散型の取引所のメリットを組み合わせた取引所が生まれました。 また、注目すべきは、取引所にウォレットを作成できる機能が備わっている点や、ユーザーに対してフレンドリーなインターフェースで作られている点です。ランディングページは画像のように3つの選択肢のみと非常にシンプルでわかりやすくデザインされています。実際の取引画面も通貨ペアを選んで金額を入力するだけと他の取引所と比べて遜色ない非常にシンプルな作りになっています。 <取引画面> Stellarの2018年のロードマップの1つには分散型の取引所の項目が挙げられており、Stellarportのような分散型の取引所はStellarのエコシステムを成長させるものとなると考えられます。 Stellarの取引のインターフェースは以前から利便性の悪い形でしたが、StellarTerm(別のStellarの取引所)に続きStellarportがリリースされたことで、ユーザーにとって喜ばしい選択肢が増えました。 StellarportがローンチされてからStellar(XLM)、Mobius(MOBI)、Smartlands(SLT)の出来高が爆発的に増えていることからも、より多くのユーザーがStellarportを利用し始めていることを示唆します。












 有料記事
有料記事


