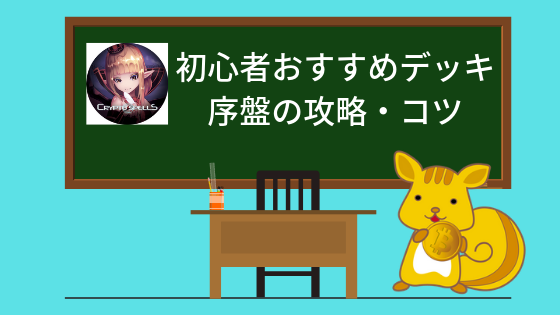
特集・コラム
2019/08/07【クリスペ】初心者おすすめデッキ&序盤の攻略・コツ【CryptoSpells】
こんにちは。しまりすです。 日本初のブロックチェーンカードゲームCryptoSpells(クリプトスペルズ|クリスペ)が正式リリース後からユーザー数が1万人に迫る盛り上がりを見せています。 CryptoSpells(クリプトスペルズ)が炎上を乗り越え驚異的な盛り上がり! - CRYPTO TIMES 2019年7月20日にはCryptospellsリリース記念公式大会βが開催され、過去最大の114名のユーザーが参加しました。 そして、なんと公式大会の初代優勝者になることができました。 https://twitter.com/crypto_spells/status/1152479419757240320 この他にも優勝賞金0.5ETHがかかったクリスペまとめ杯などでも優勝しており、大きな大会は今のところ全て抑えています。 https://twitter.com/tcg_cryspe/status/1143560503983140864 大会に参加して今までに獲得した賞品をまとめると以下のとおりです。(2019年7月執筆時現在) クリスペTシャツ クリスペステッカー 0.5ETH クリスペスマホリング 公式大会優勝記念カード 新カード1枚提案権(シルバーランク) 提案カードのマーケット売買手数料50%永続獲得権 本記事では公式大会優勝者のしまりすがカードゲームをやったことがない初心者向けに、クリスペでの勝ち方のコツや攻略法を解説します。 クリスペはカードの引きなど運要素もありますが、基本的なルールや理論をしっかり押さえれば必ず勝率を上げることができます! この記事が今からクリスペを始めようと思っている方や、クリスペってなんだか難しそう・・・と思っている方の参考になれば幸いです。 CryptoSpells(クリスペ)のルールを覚えよう カードゲームをするにあたってルールを覚えることは必須です。 クリスペの細かいシステムは公式Mediumでも確認することができますが、まずは基本的なルールを押さえてとにかくプレイしてみるのが手っ取り早いと思います。 基本ルール ・ライフ25スタート ・初期MP(マナポイント)1~(ターン経過で1増える) ・手札上限枚数:9枚(ここからモンスター召喚) ・場のユニット上限数:6体(相手に攻撃など) ライフはお互い25スタートで、相手のライフを0にするか、デッキの枚数を0にしてカードを引けなくするとバトルに勝利します。 まずはざっくりこれだけ押さえてとにかくプレイしてみて、分からない点や疑問に思ったことがあったら公式Mediumをチェックしましょう。 これだけですぐにルールは覚えられます。 プレイヤーのレベルを上げる フリー対戦でバトルをして勝利するとプレイヤーレベルを上げることができます。 レベルが上がれば採掘チケットがもらえ、新しいカードを手に入れることができるのでまずはフリー対戦でレベルを上げましょう。 採掘してみよう レベルが上がったら採掘チケットを使ってカードを入手します。 採掘ではレアリティがシルバーまたはブロンズのカードが出ますが、シルバーカードが出ることは稀です。(シルバー採掘の確率は非公表ですが感覚的には1%くらいです) シルバーが出たらラッキーというくらいに考えて、まずはブロンズのカードをそろえましょう。 連勝するとシルバー採掘の確率が上がると言われていますが、初期デッキではカードがとても弱くフリー対戦で勝つことが難しいので、採掘チケットを入手したら積極的に採掘することをオススメします。 クリスペを今から始めようと思っている方は、こちらから登録すると採掘チケットが20枚もらえるのでぜひ。 デッキを組もう クリスペは、初期デッキの構成カードがとても弱いため、始めたばかりの初心者はなかなか勝てないという壁にぶち当たります。 なので最初のうちは勝てなくて辛いですが、採掘でブロンズカードがそろっていくまでの辛抱です。 感覚的に、100枚くらい採掘するとある程度勝てるデッキを作ることができるのでそこまで頑張りましょう。 この項目では「初心者へのおすすめ度」という視点から、おすすめのリーダーとデッキを紹介します。 強さだけではなく、デッキの作成しやすさやプレイ方針の分かりやすさも考慮して選定したのでぜひ参考にしてみてください。 初心者におすすめのリーダー クリスペ初心者におすすめのリーダーは赤:竜騎将 フェルトゴルトです。 序盤から積極的に相手のライフをタイプのアグロデッキは戦い方の方針が非常に分かりやすいです。 バトル開始時に選ぶリーダーのクリプトスペルは、「コスト4 相手ユニット1体に6ダメージ」の方を選択して相手の前衛カード、ホルスの門番などが出てきたときに使うのが有効です。 初心者おすすめデッキ このデッキは序盤から積極的に相手のライフを攻撃していくタイプのアグロデッキです。 相手のリーダー(フェイス)をどんどん殴っていくという方針がわかりやすく、シルバーカードを持っていなくても構築できるので初心者におすすめのデッキとなっています。 ぜひ試してみてください。 強い人と交流をしよう カードゲームで勝つために大切なのは「情報」です。 本記事を書いたのは2019年7月ですが、クリスペにおいても強いデッキやメタゲームの情報は日々移り変わるので、どんなに強いプレイヤーでも高い勝率を上げるには「情報」が非常に重要になります。 そこで僕が実践しているのが、「強いプレイヤーのいるコミュニティに入りそこから情報を得る」とうことです。 コニュニティに入れば、分からないことを教えてもらったり、他プレイヤーのリプレイ映像などから戦略やデッキ情報を集めることができます。 以下、僕がおすすめするコミュニティを2つご紹介します。 Gaudiyのクリスペコミュニティ GaudiyのCryptoSpellsコミュニティには、沢山のクリスペユーザーがいて攻略情報や最新の情報が集まります。 また、コミュニティ内での活動や貢献によって、クリスペコインをGETすることが出来ます! コインはコミュニティ内のギフト(限定カードなど)に交換できるのでGaudiyのコミュニティには必ず入ることをオススメします。 ↓コミュニティ参加はこちら↓ https://gaudiy.com/community_details/avJEInz3EXlxNXKMSWxR/0 CryptoSpells公式Discord CryptoSpells公式Discordでは、ユーザーが企画する大会やイベントなどの情報が集まっています。 過去の大会のプレイ動画などもアップされているので、強い人のプレイングから研究することができます。 ↓CryptoSpells公式Discord参加はこちら↓ https://discord.gg/uY8BuwH とにかく数をこなして経験を積む ここまでクリスペで強くなる方法を紹介しましたが、結局大切なのは試行錯誤―トライアンドエラーを重ねることです。 強いプレイヤーと自分のプレイのどこが違うのかを考え修正する。 地道ではありますが、これを繰り返せば確実に実力はついていきます。 まとめ 以上、カードゲーム初心者が強くなるための方法でした。 参考にしていただければ幸いです。 ではよいクリスペライフを。 Twitterではクリスペの情報など随時アップしているのでしまりすのフォローもぜひお願いします。 CryptoSpells

特集・コラム
2019/08/06専業トレーダーえむけんの仮想通貨市場分析!【8月6日】
みなさん、こんにちは!えむけん(@BinaryMkent)です。 前回更新後から、BTCは再度12000ドル周辺まで大きく上昇しましたね。簡単に売らせてはくれないだろうなとは思っていましたが、さすがにこの勢いには驚きました。 そんな絶賛荒ぶり中のBTCですが、今回も仮想通貨市場全体を踏まえて、今後の価格推移について分析していきます。今回は、やや立ち回りに重きを置いてお話しをしていきますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね! それでは、早速BTCの分析から進めていきましょう。 BTCチャートの分析 BTCチャート(長期) まずは、BTC長期チャートから見ていきましょう。 直近高値である14000ドルをつけた後、ダブルトップを形成して調整転換。そして、その後の戻り売りを見た限りでは、再度安値を大きく更新しそうな状況でしたね。しかし、中期チャネル(黄)に下落を阻まれ、結果ダブルボトムを成立させ大きく上昇していきました。 このように、現状としては買い優勢といった状況ですが、前回トレンドと比較して出来高も少ないため、ここから乗っかるには不安が残ります。そのため、買いで入るのであれば今からではなく、もう少し様子を見てからの判断が妥当だと思われます。 またその際には、この中期チャネル(黄色)だけでなく、14000ドル以降の高値を結んだ緑チャネルも踏まえた売買判断が賢明でしょう。 では次に、中期チャートの分析に移りましょう。 BTCチャート(中期) こちらがBTCの中期チャートになります。 こちらを見ていただくと、「中期チャネル(黄)と緑チャネルが如何に重要な指標か?」というのがお分かりいただけると思います。 そして現状、レートはその中期チャネル(黄)と緑チャネルの交点周辺であり、ある程度の利食い売り、新規売りが見込めるポイントです。そのため個人的には、中期チャネル(黄)下限をネックラインとした三尊推移の可能性を視野に、この緑チャネルを背に売り(ショート)を入れてみています。 恐らく、ここから出来高が急増しない限り、上抜けは難しいと見ていますが、直近の短期トレンドはいうまでもなく上昇トレンドです。ですから今後、押し目を付けて再上昇する可能性も見据えておくべきでしょう。 では、これらを元に現状から考えられる今後のシナリオ、その考察に移りましょう。 BTCチャートの総評 さて、それではBTCチャートについてまとめていきましょう。今回、考えられうるシナリオは以下の3通り。 押し目を付けて再上昇(白) ⇒2本のチャネルを上抜け 中期チャネル(黄)で下げ止まり(青) ⇒三尊非成立により再度上昇の可能性 中期チャネル(黄)下抜け(橙) ⇒三尊成立により下落。8500ドル周辺まで視野に 大体こんな感じでしょうか。 恐らく、黄色チャネルと緑チャネルの2本を基準にした保ち合い形成をメインに見ている方も多くいらっしゃると思いますが、三尊形成に向かったにも関わらず、非成立となった場合には「一時上昇」と判断するのがセオリーであり、その時点で若干の「買い優勢」と判断すべきです。 ですから、三尊を成立させず保ち合いに向かった場合には、下げに向かう絶好のタイミングをスルーしたわけですから、その時点で「この保ち合いは上抜けの目のほうが高い」と少し買いに偏って分析してみることをお勧めします。 では次に、ドミナンス分析を進めていきましょう。 ドミナンス分析 ドミナンスチャートに関しては、「Trading View」を参考することにしております。(外部リンク:https://jp.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/) まず、注目すべき点としては、「BTCドミナンスが節目である70%を越えた」という点ですね。次の節目は75%になりますが、ドミナンスの直近高値を抜けたことも踏まえると、75%到達までは再びアルトからBTCへと資金が吸い取られていく可能性が高いと思われます。 では、次に少し拡大して見てみましょう。 直近の転換点としては7/30、ここを境にBTCドミナンスは上昇、アルトドミナンスは下落と、7/30を機に市場内の資金が大きく動いております。 個人的には、以前もお話ししていたLTC半減期に向けて、少しはアルト市場活性化に向かうのでは?と思っていたのですが、恐らく仮想通貨市場だけでなく、金融市場全体がリスクオフに転換し、BTCがその流入先になったのを機にBTCへと資金が集中したのでしょう。 主要アルトコインの動向 現状、「BTCが上がっても下がる、BTCが下がっても下がる」と、やや混沌としているアルト市場ですが、直近の好材料でもあったLTC半減期を終えたのもあり、今から無理に手を出す必要はないでしょうね。 仮に攻めるのであれば、主要アルトでもBTC建てでなく、USD建てを中心に攻めていくのが無難だと思われます。 ということで今回は主要アルトの中でも注目度が高い2通貨のUSD建てチャートを対象に分析を進めていこうと思います。 ETH ETH/USDについては前回も取り上げましたが、依然悪くないといった状況です。 青サポートへの接触後上昇、その後白ラインのように底値を示唆するチャートパターン「アダムとイブ」を形成しています。節目としては、アダムとイブの成立ラインである「235ドル」。これを上抜けると、少しは現状の雰囲気も変わってくるのでは?と見ています。 今から直接、BTCに買いで乗っかるのはRRも悪いため若干気が引けます。しかし、ETHには235ドルという明確な節目が存在するため、直接BTCを買うよりも比較的買いやすい状況にあります。ですから、これまでのようにBTC上昇に引っ張られる可能性も踏まえて、「BTCショートに対するヘッジ」として活用するのも1つの手でしょう。 LTC 半減期を終えても尚、事実売りに向かわず、未だに同価格帯にて推移していますね。個人的にはこれがちょっとしっくり来ていません。 ファンダというのは事実売りがセオリーです。つまり今回で言えば、「半減期による価格上昇」を見込んで買い集めていた投資家らが8/5の半減期を機に売却(利益確定)する、という動きです。 ですが今回、好ファンダを前に大きく上昇してきたにも関わらず、出来高を見てもその後の事実売りが非常に少ないんです。しかもその上、上昇パターンとされているアセンディングトライアングルっぽい形で調整に入っています。 こちらも先ほどのETH同様、103ドルあたりと節目が分かりやすく、買い方でも乗っかりやすい状況のため、個人的にはBTCの上昇に乗っかるよりもそれに引っ張られるETH、LTCに乗っかる方向で・・・、と考えています。 総評(まとめ) さて、それでは最後にまとめに入りましょう。 BTCは黄チャネル+緑チャネルを注視 →一時調整(下げ)が妥当 USD建てアルトにも注目 →BTCがチャネルを上抜けたとしても、天井判断が難しく乗りづらい。そのため、より節目が明確なUSD建てアルトで上げを取る 以上になります。 これは余談ですが、今年に入って以降、ビットコインの性質が若干変わりつつあるように思います。これまでは、株や為替などの金融市場からはやや独立したものとして認識していたのですが、最近では明らかに株や為替、中でも新興国通貨などに対する避難先として動いているように見えます。 現状のビットコインは以前ほどの注目度もなく、出来高も減少傾向にありますが、こういった流れを経て、金融商品として徐々に世の中へと浸透していくのかなと思ったら、「仮想通貨市場としてはいい方向、あるべき姿へと進んでいるのかな?」と思いました。 今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 現在、私えむけんが制作した動画教材『7日間でマスター!テクニカル分析とそれを元にしたトレード戦略』、好評販売中です! 今回のような、BTC分析やアルトコイン投資などの立ち回り方についても解説しておりますので、是非ご覧ください!(詳しくはコチラ)

特集・コラム
2019/07/25専業トレーダーえむけんの仮想通貨市場分析!【7月25日】
みなさん、こんにちは!えむけん(@BinaryMkent)です。 前回更新後、BTCは一時1万ドルを割りはしましたが、再度勢いづき、現在9500~11000ドル間のレンジ推移を見せています。出来高も今月始めと比べれば、やや減少傾向にありますが、それでも尚しぶとい・・・、そんな状況ですね。 ファンダ面においても、好材料や悪材料が入り乱れており、やや長期の方向感が掴みにくいポイントではありますが、今回もBTCチャートやドミナンス、主要アルトらの動向から仮想通貨市場全体について、分析していこうと思います。 それでは、早速BTCのチャート分析に参りましょう。 BTCチャートの分析 BTCチャート(長期) まずは、BTC長期チャートから見ていきましょう。 状況としては、前回記事とそこまで大差ありませんね。13000ドルの抵抗帯(黄色ゾーン)への到達を機に推進波5波が完了し、「さらに調整が進むのか?」といったポイントですね。 ではそれらについて、中期チャートを元に掘り下げてみましょう。 BTCチャート(中期) こちらがBTCの中期チャートになります。 黄色チャネル(上限)の下抜け、その後のリターンムーブ(200SMA)成立。これらを踏まえると、方向は依然『下』だと思われます。 しかし、その後の動きがやや気がかりです。これは少し経験といいますか、感覚的な部分が多いのですが、「リターンを終えた後、さらに出来高が少ないにも関わらず、買いがしぶとい」といった印象を受けました。 それらを踏まえると、11000ドル周辺まで上昇し、再度推進波移行の可能性も考えられます。ですから、一概に「下!ショートのみ!」と決めうちしていくような状況ではないと思われます。 では、「どこを元に上下の判断を行うのか?」 まず11000ドルを抜ける展開となると、直近のショートポジション決済(損切り)に向くと思われます。そのため、11000ドルを上抜けた場合には、これまでの下目線、ショートを巻き込んだ上目線優位に運ぶのではないかと見ています。 ですが逆に、11000ドルを超えられなかった場合には、出来高も衰退傾向にありますし、ジリジリと落とされ、黄色チャネル内50%(白ライン)の下抜けを機に、下目線へと向くと思われます。 では、これらを元に現状から考えられる今後のシナリオ、その考察に移りましょう。 BTCチャートの総評 さて、それではBTCチャートについてまとめていきましょう。今回、考えられうるシナリオは以下の3通り。 11000ドル上抜け ⇒再度推進波へ 11000ドル上抜けできず ⇒ジリ下げ、チャネル下限へ リターンムーブを終えたにもかかわらず、直近でしっかりリバウンドしたところを見ると、未だ白シナリオ(11000ドル上抜け)は否定しきれない、と思います。そのため、少なくとも上記のような2通りを踏まえた上で立ち回っていくべきでしょう。 では次に、ドミナンス分析を進めていきましょう。 ドミナンス分析 ドミナンスチャートに関しては、「Trading View」を参考することにしております。(外部リンク:https://jp.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/) 7/15のBTCドミナンス70%到達を機に、ドミナンスは反転下落。そして、それと同時に主要アルトのドミナンスが上昇転換しております。 主要アルトのドミナンス上昇といってもさほど大きな上昇ではありませんが、「以降、資金が主要アルトへと流れるのか?」というのは、非常に重要です。 というのも、ここから再度資金が主要アルトに集中するのであれば、投資家としては「資金が集まるアルト」を買うことで利益獲得が可能になります。そのため、わざわざ資金を撤退させる必要がないのです。 しかし、主要アルトコインらからも資金が抜けるとなると、「ビットコインが下げそう。それに主要アルトも巻き込まれる可能性もある」と考え、そのリスクを回避すべく市場から資金を撤退させる投資家が増加すると考えられます。 そのため、アルトコインが軒並み下落し、若干のリバウンドを見せている現状況において、「引き続きアルトコインらに資金が流れるか?」というのは非常に重要なのです。 では、これらを踏まえた上で、少し拡大して見てみましょう。 主要アルトの中でも、今のところ綺麗に資金が流れてきているのは、「ETH」、「BNB」でしょうか。それに対して、USDTやOthersのドミナンスは比較的停滞傾向にあるため、先ほどお話しした通り「アルトの中でも、主要アルトに流れてきている状況」だと考えられます。 次項目にて、さらに掘り下げて分析を行っていきますが、これらの2通貨の進退については、ドミナンスの観点からも要注目しておくべき通貨だと思われます。 主要アルトコインの動向 やはり白ラインのBTC上昇転換を境に、主要アルトは軒並み下降しており、黄色ラインのBTC下降転換を境に主要アルト上昇転換と、BTC市場とアルト市場が逆相関関係にあるように見えますね。 こちらのチャートからは、XRPなども動きも気になりますが、今回はドミナンス解説の際にも取り上げた、ETHとBNB、そして半減期を控えたLTCの3通貨を対象に分析を進めていこうと思います。 ETH 直近の下落を見ると、少し嫌な下げ方をしていますね。しかし、半値+サポート(青)周辺と損切り幅も少なく、押し目候補として資金流入が見込めるポイントだと思われます。 しかし、すでに半値からは大きくリバウンドしておりますし、ここからは235ドルの上抜けなど、「短期的な底形成を成立させるのか?」に注目しつつ、押し引きしていくのが妥当でしょう。 BNB サポートラインを機に大きくリバウンドしましたが、半値の戻り売りポイントで再度売られ、サポートライン下抜けに向かうか?それとも、戻り売りポイントを上抜けるか?といった状況です。 これまで大きく上昇してきた分、比較的上昇の見込みは少ないですが、アルトが盛り上がる背景にはBNBも相関して動きやすい傾向があるため、チェックしておくべき通貨の1つだと思われます。 LTC 8月に半減期を控えたLTCですが、チャネルを下抜け大きく崩れたものの、半値周辺かつ、200MAの上にて綺麗に下げ止まっています。 率先して買えるような状況ではないかもしれませんが、仮に再度推進波へと移行すると仮定するのであれば、押し目としてふさわしい下げ止まり方もしているようにも見えますね。 とはいえ、今すぐ飛びつけるような状況ではありませんので、現状からは中期チャートにおけるレジスタンス(青)を突破などを機に買い方に回るのが妥当だと思われます。 参考サイト:『Litecoin Block Reward Halving Countdown』 総評(まとめ) さて、それでは最後にまとめに入りましょう。 BTCは11000ドルがポイント →上も下も考えられる アルトがこのまま買われるか? →買われなければ全下げ相場の可能性 BTCだけで見ても、買い場にも見えるし売り場にも見える・・・、そんな難しい相場ですね。しかし、今回ご紹介したアルトコインは3つとも、綺麗にサポートラインや半値といった「買われうるポイント」になっております。 以前から仮想通貨市場では、こういった買い場、売り場といった節目になると、「複数コインが同じようなチャートパターンになりやすい」といった傾向があります。 そして、今回取り上げた3通貨においても、半値やサポートライン上と買い場が一致しており、それに伴った推移を見せています。もちろん、ここから買われると決まったわけではありませんが、BTCだけでなく、このような主要アルトにおける重要ライン等も踏まえて、分析していくと市場全体の動きや流れが見えてくると思います。 今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 現在、私えむけんが制作した動画教材『7日間でマスター!テクニカル分析とそれを元にしたトレード戦略』、好評販売中です! 今回のような、BTC分析やアルトコイン投資などの立ち回り方についても解説しておりますので、是非ご覧ください!(詳しくはコチラ)

特集・コラム
2019/07/17CryptoSpells(クリプトスペルズ)が炎上を乗り越え驚異的な盛り上がり!
ブロックチェーンTCG「CryptoSpells(クリプトスペルズ)」は、2019年6月25日に正式リリース及びクラウドセールを開始し、7月9日の第1回クラウドセール終了の段階でゲーム内通貨SPLの売上金額が累計900ETH(約3000万円)を達成した。 これにより、CryptoSpells(※以後クリスペ)は、累積黒字化見込みであることを発表した。 累積黒字とは?開業までに掛かった費用や運営費など今まで掛かった費用を利益が上回ること。 毎月の費用を利益上回ることは「単月黒字」という。 ソーシャルゲーム業界においては、開発費の回収は通常1.5-2年程度かかるといわれているので、これを2ヶ月弱で達成したクリスペは驚異的なスピードだ。 2018年10月にプレセール中断の炎上騒ぎから不死鳥のごとくみごとに復活し、ブロックチェーンゲーム業界の希望となった。 有名ブロガーやYoutuberも取り上げ始める 素晴らしいスタートを切ってブロックチェーンゲームの存在を世に知らしめたクリプトスペルズ。 クラウドセール成功をキッカケに有名なブロガーやYoutuberが取り上げ始めてきているので紹介したい。 むじょるさん 大人気スマホカードゲーム「シャドウバース」Youtube実況者のむじょるさん。 Youtubeのチャンネル登録者数は17万人以上のシャドバをやっている人なら知らない人はいないほどの有名Youtuberだ。 https://twitter.com/mujol_sv/status/1146427750816681984 そんな有名配信者のむじょるさんもクリスペに参入した様子。 今後、Youtubeでクリスペの配信などが行われれば、かなりの数の新規参入者が期待できるだろう。 イケハヤさん イケハヤさんのことは仮想通貨界隈で知らない人はいないと思うので説明は省略するが、彼もいくつかツイートをしている。 https://twitter.com/IHayato/status/1148914613804601348 イケハヤさんは流行にとても敏感なので、ブロックチェーンゲームが普及する日も近いかもしれない。 ふくみみさん https://www.youtube.com/playlist?list=PL3XL4_Ku1ZqNgliaSZiMsaJLYvrLIO4EU DQMSL(ドラクエモンスターズスーパーライト)やポケモンカードゲームで有名なYoutuberのふくみみさんもクリスペのユーザーで動画をアップしている。 オフ会にも積極的に顔を出していて、クリスペの熱狂的なファンであることが伺えるだろう。 クリスペファンの方はぜひチャンネル登録してほしい。 CRYPTO TIMES編集部 https://twitter.com/CryptoTimes_mag/status/1148204724346212352 我らがCRYPTO TIMES編集部も編集長アラタさんのETHを利用してクリスペに参戦! どうやら、レジェンドカードのパープルミストの最後の1枚を購入しているようだ。 CRYPTO TIMESとクリスペのコラボイベントとか開催されたらアツい! CryptoSpellsの面白さ リアルタイムでの対人戦 クリスペは従来のブロックチェーンゲームとは異なり、リアルタイムでの対人戦を楽しむことができるという点が魅力だ。 画面越しに生身の人間がいるので、いくら強いカードを持っていてもプレイング次第では負けてしまうことも当然あるし、自分のカード出し方で負けそうな試合をひっくり返すことも可能だ。 対戦前のデッキ編成や対戦中の戦略が大切で非常にやりこみ要素が多いゲームとなっている。 始めたての頃は持ってるカードも弱いし、ルールもよくわからないしで負け続けて嫌になってしまうこともあるかもしれないが、対戦を繰り返していくうちにルールやコツは掴むことができる。(今後CPU対戦などカードゲーム初心者でも楽しめるゲームモードも用意されるとのこと) また、有志のユーザーによる大会もほぼ毎週開催されていて、豪華賞品があったり、参加者も30名を超える大会もあったりして盛り上がりをみせている。 筆者もテスト版の頃から大会を開催していたが、現在はプレイヤーとして参加することに集中している。でもまたいつか大会は企画したいと思う。 ゲームにつぎ込んだ時間や情熱が資産になる 従来のDCG(デジタルカードゲーム)では、プレイヤーの課金=カードの生産となるため、カードの供給は実施無限であるため価格が高騰するということはない仕組みになっている。 しかし、クリスペではカード毎に発行枚数が決められているため、需要次第ではカードの価格が跳ね上がる可能性がある。 https://twitter.com/CryptospellsS/status/1148542679807979520 第1回のクラウドセールで販売されたレジェンド以上のカードは完売。 価格も リミテッドレジェンド:開始価格10ETH → 終了価格 15.7ETH レジェンド:開始価格2ETH → 終了価格 6.6ETH ゴールド:開始価格0.1ETH → 終了価格 0.16ETH と全て値上がりという結果だった。 無課金で手に入れることのできるシルバーカード(最大発行枚数9999枚)も0.05ETHほどの価格でユーザー間で売買されているので、無課金であってもETHを稼ぐことは可能になっている。 また、2019年6月15日に大阪で開催されたマイクリ&クリスペ大阪オフ会において以下のようなクリスペ貢献プレイヤーに対するインセンティブの構想について発表があった。 1 コミュニティ育成者にインセンティブ 2 デッキビルダーにインセンティブ 強いデッキのレシピを公開して、そのレシピが他のユーザーに採用されたらインセンティブがもらえる仕組みなど、ブロックチェーンゲームの強みを活かした構想があるようだ。 これからの開発に期待したい。 筆者も1枚50万円近くするカードを購入 僕もクリスペにはかなり期待していて、約15ETHで最高ランクのリミテッドレジェンドカードを購入した。 https://twitter.com/shimaris_coin/status/1145263736296394754 クラウドセール時のETHレートで50万円近くするので少しやりすぎたかもしれないが、今後クリスペに情熱を注いでいく僕なりの決意だ。 クリスペリリース記念公式大会β 開催! https://twitter.com/crypto_spells/status/1150606835818217473 7月20日(土)13:00より公式によるクリスペリリース記念大会が開催 優勝者にはシルバーランクの新カード提案権と売買手数料の50%永続還元権が優勝賞品として与えられる非常に盛り上がりそうな大会だ。 予選は、最大参加人数128名、5回戦のスイスドロー形式で、各試合1本先取 決勝は、予選上位8名で行われる、シングルエリミネーション形式で、各試合1本先取 と1本勝負の運要素がかなり強い大会となっているので、無課金のユーザーでも十分優勝の可能性がある。 エントリーがまだの方はこちらから では大会で会いましょう。 Twitterではクリスペの情報など随時アップしているのでしまりすのフォローもぜひお願いします。 CryptoSpells

特集・コラム
2019/07/15専業トレーダーえむけんの仮想通貨市場分析!【7月15日】
みなさん、こんにちは!えむけん(@BinaryMkent)です。 前回更新後、一度は高値を目指したものの、上値も重く、未だ11000ドル周辺で停滞していますね。 前回記事でもご紹介したとおり、個人的には「その間に資金がアルトへ流れてくるのでは?」と予想していたのですが、残念ながら損切り撤退となってしまいました。 今回は、こういったアルトやBTCにおける資金の動きに重きを置いて、今後の動向について分析していこうと思います!是非、最後までお付き合いください。 それでは、早速BTCの分析から進めていきましょう。 BTCチャートの分析 BTCチャート(長期) まずは、BTC長期チャートから見ていきましょう。 中期保ち合いの上方ブレイクにより大きく上昇しましたが、上値も重く「再度この価格帯で保ち合いを作れるか否か?」といった状況ですね。推進5波を終えた後ということもあり、ここからは調整転換の判断を見切るべく、転換ポイントを抑えておきたいところです。 長期(日足)チャートにおける調整転換基準は、前回高値圏で形成したチャネル(黄)をベースに考えるとよいでしょう。恐らく、これを抜けると以降は買い場も少ないため、比較的売り優勢な展開に進むと思われます。 このチャネル(黄)、並びに支持価格帯(白ゾーン)を元に、調整開始ポイントを推測してエントリー、その後MACDの安値ポイントをつないだサポートライン(黄)、このブレイクを元に推進力の低下、つまり日足スパンでの調整継続判断を行うと良いでしょう。 では次に、中期チャートの分析に移りましょう。 BTCチャート(中期) こちらがBTCの中期チャートになります。 現状、前回高値圏にて形成したチャネル(黄)が依然有効、といった様子ですね。ですから一先ずは、この「チャネル下抜けが調整開始のサイン」として見ておくべきでしょう。 しかし、このチャネルを守りつつ、青レジスタンスとの保ち合いに進んだ場合には、要注意です。 これは前回のお話ししましたが、高値圏でしっかり保ち合いを形成した場合には、その否定に進まない限り、既存ロングポジションの利食い(売り)につながりません。 つまり、ここから保ち合いに進んだ場合には、再度高値を叩きに来る可能性があるわけです。ですから、仮にチャネルの下抜け後に下ひげをつけて、保ち合い形成に向かった場合には、即座にポジションを解消し、再度チャネルの下抜けで持ち直すよう動くべきでしょう。 では、これらを元に現状から考えられる今後のシナリオ、その考察に移りましょう。 BTCチャートの総評 さて、それではBTCチャートについてまとめていきましょう。今回、考えられうるシナリオは以下の2通り。 チャネル(黄)を下抜け ⇒本格調整開始 チャネル(黄)で押し目形成 ⇒青レジとの保ち合い 上では特別取り上げませんでしたが、以降は200MA(赤)についても要注視しておくべきでしょう。また、チャネル(黄)と200MA(赤)を下抜け、調整開始に向かうようであれば、グランビルの法則(MAでのリターンムーブ)までを視野にいれてロット調整を行うとよいと思います。 では次に、ドミナンス分析を進めていきましょう。 ドミナンス分析 ドミナンスチャートに関しては、「Trading View」を参考することにしております。(外部リンク:https://jp.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/) 一時はアルト市場への資金流出を予想しておりましたが、BTCドミナンスは緩やかながら依然上昇しております。しかし、前回高値かつ節目でもある70%を前に、今後転換に向かうのか注目ですね。 主要アルトは依然下落傾向にありますが、7月に入って以降、徐々にUSDTのドミナンスが上昇に向かっています。恐らくBTCドミナンス70%に向けて、徐々に現物BTCやアルトなどが処分され始めているのでしょう。 しかしそんな中、気がかりなのは来月頭に控えたLTC半減期です。LTCはチャート的にもかなり大きく崩れてきましたが、半減期前どこかのタイミングで大きなリバを見せる可能性もあります。 主要アルトコインの動向 先ほどお話ししたように、アルトは全体的に下落傾向にはありますが、その中でも半減期を控えたLTCが気がかりです。そのため今回は、再度アルトブームの火種となりうる、LTCのみを対象に分析を進めていこうと思います。 LTC まずはBTC建てから見ていきましょう。 緑ゾーンまで落ちてきてくれるようであれば、若干買ってみたい気もしますが、現状はそこまで魅力的ではありませんね。 こちらは参考までに軽く見ておく程度で、実際の売買はUSD建てをメインに行っていくのが無難でしょう。 では次にUSD建てを見ていきましょう。 これまで時間をかけて築いてきたチャネル(緑)を下抜け、急降下していますね。チャート的には下優勢といった状況ですから、仮に半減期前のリバを狙うにしても、ポイントを絞った上でエントリーしていく必要がありそうです。 候補としては、支持価格帯である90ドル(白ゾーン)、もしくはチャネル内の安値、高値における半値(85ドル)が妥当でしょう。特にこういった安定的な上昇後に、半値を守れた場合には、大きなリバの契機となりやすい傾向があります。 むやみに攻めすぎず、要所要所BTCでヘッジポジションを建てるなど、若干のリスクヘッジを行いながら動いていくのが妥当だと思われます。 半減期の詳細時間については、下記サイトをご参考ください。 参考サイト:『Litecoin Block Reward Halving Countdown』 総評(まとめ) さて、それでは最後にまとめに入りましょう。 BTCはチャネル(黄)を基準に押し引き →下抜けで本格調整開始 アルト⇒BTC→USDT(?) →LTC半減期リバ警戒 今回の分析を通して、アルト市場から大きく資金が抜け、BTCとUSDTドミナンスが上昇と、ややリスクオフに向きつつあるように感じました。 地合いとしては、更なる資金流入というよりは、流入してきた資金が抜けるかどうか?といったポイントですし、無理せず要所要所で付き合っていくのが妥当でしょう。 今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 現在、私えむけんが制作した動画教材『7日間でマスター!テクニカル分析とそれを元にしたトレード戦略』、好評販売中です! 今回のような、BTC分析やアルトコイン投資などの立ち回り方についても解説しておりますので、是非ご覧ください!(詳しくはコチラ)

特集・コラム
2019/07/05専業トレーダーえむけんの仮想通貨市場分析!【7月5日】
みなさん、こんにちは!えむけん(@BinaryMkent)です。 前回更新後、BTCは一時11500ドルを突破し、14000ドルを目処に切り返してきましたね!勢いも強く、この値動きに振り回された方も多いんじゃないでしょうか?(私もその一人ですが…笑) さて、依然11000ドル周辺にて激しく推移しておりますが、今回も今後の動向について、アルト市場なども絡めて分析していこうと思います!是非、最後までお付き合いくださいね。 それでは、早速BTCの分析から進めていきましょう。 BTCチャートの分析 BTCチャート(長期) まずは、BTC長期チャートから見ていきましょう。 前回記事でもお話ししたように、現状は推進波の5波目が完了した状態ですね。ここからどのように調整波が展開されるのか?についてですが、日足ですとサポートやレジスタンスなどの参考材料も少ないため、ここからは中期チャートをメインに分析、判断していくのが妥当でしょう。 では早速、中期チャートの分析に移りましょう。 BTCチャート(中期) こちらがBTC中期チャートになります。 中期チャートを見ると、過去のチャネル(黄)が目立ちますね。このチャネル(黄)は、過去2ヶ月近く、「分析材料」として機能してきた実績もありますし、恐らく今後の推移を予想する際の最注目ラインになってくるかと思います。 現状、チャネル(黄)上限がサポートとして機能しておりますが、これを下抜ける展開となった場合には、本格調整開始としばらくはゆったりとした推移が続くものだと思われます。 また、もう少し短いスパンで見ますと、先月末を起点とする中期レジスタンス(青)、逆三尊の右肩を想定した緑ゾーンについても要注目でしょう。 恐らく、「BTCが再度最高値を目指す展開」となる場合には、中期レジスタンス(青)と逆三尊右肩を想定した緑ゾーンの2つが鍵になってくると思います。 では、これらを元に現状から考えられる今後のシナリオ、その考察に移りましょう。 BTCチャートの総評 さて、それではBTCチャートについてまとめていきましょう。今回、考えられうるシナリオは以下の3通り。 緑ゾーンで押し目作れず ⇒チャネル(黄)下抜け チャネル(黄)で押し目形成 ⇒青レジとの保ち合い 緑ゾーンで下げ止まり ⇒逆三尊成立へ 個人的には、このまま調整が本格化するとなると、青シナリオでの推移が濃厚になるのでは?と見ていますが、可能性としては緑シナリオの保ち合いを形成したのち、そのブレイクで今後の方向を決める展開もあり得ると思います。 また、ファンダをベースに見ると、先月から一転してちょくちょくUSDT関連の悪ファンダが出始めてきていますから、方向としてはとりあえず一旦下かなと見ています。 では次に、ドミナンス分析を進めていきましょう。 ドミナンス分析 ドミナンスチャートに関しては、「Trading View」を参考することにしております。(外部リンク:https://jp.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/) BTCドミナンスを見ると、現状の高値である14000ドルをつけた後、7/3にドミナンス直近高値を更新し、66.0%を記録していますね。 ドミナンスだけを見ると、このままドミナンス更新に向かいそうですが、今回はBTCが14000ドルをつけた後のドミナンス上昇ですから、恐らく「BTC下落を危惧したBTC建てアルトからの撤退が、BTCのドミナンス上昇につながった」のだと思われます。 では、その点も踏まえてアルトコインドミナンスを見てみましょう。 主要アルトドミナンスは、全体的に下落傾向にありましたが、6/26のビットコイン14000ドル到達以降、若干のリバを見せています。中でも前回記事にて、BTCとの逆相関をご紹介したLTC、Others(その他)がその筆頭ですね。 しかし同時に、USDTのドミナンス上昇も気になるところです。恐らく先にもお話ししたような、「BTC下落の危惧による撤退」が原因でしょう。 仮にBTCが本格調整開始と仮定した場合、アルトに資金が回りづらい展開が想定されますが、アルトブームの起爆剤ともなりうる「LTC半減期」まであと1ヶ月…、という状況が市場にどういった影響を与えるか?次第でしょうね。 ですから個人的には、先週からBTCショート+アルト(LTC、NEO)買いで、BTC急落によるアルト売りになってしまった場合のヘッジをかけながらポジション取りを行っています。 主要アルトコインの動向 こちらを見ていただければ分かるよう、基本的に主要アルトの推移とBTCの推移は逆相関にあります。中でもやはり、大型ファンダを控えたLTC、他の通貨と異なる推移を見せているNEOはかなり気になりますね。 今回は前回同様にはなりますが、LTCとNEOについてBTC建てとUSDT建ての2つの観点から分析を進めていこうと思います。 LTC まずは、BTC建てから。 黄色ゾーンのサポートを下抜け、ダブルトップを成立させたものの、大きく下落することなく、白ゾーンでやや大きめのリバウンドを見せました。 しばらくは、この白ゾーンと黄色ゾーン間のレンジになるとは思われますが、特に黄色ゾーンを抜けるとなると、ダブルトップ成立→リターンムーブ否定により、一気に勢い付いてくると思われます。 半減期のカウントダウンに関しては、下記外部リンクをご参考ください。 参考サイト:『Litecoin Block Reward Halving Countdown』 次にUSD建てを見ていきましょう。 パッと見、あまりいい状況とはいえませんが、このようなチャネルを引いてやると、一気に買えるチャートになりますね。 BTC建てだと、いまいちINポイントも掴みにくいですし、USD建てチャートを参考に黄色ゾーンでの現物買いもありだと思います。 NEO 先週ご紹介した状態から一切変わらず、依然アダムとイブの成立前となっています。 恐らく、今週末から来週にかけてが山場だとは思いますが、このままズルズルと進んでしまうと、時期に売り浴びせられる可能性もあるため、なるべく早めに動いてほしいところですね。 すでに仕込み済みの方はストップロスを、慎重派の方は0.001680satsのブレイクまで見守ってからINするとよいでしょう。 では次に、USD建てを見ていきましょう。 USD建ては言わずもがなめちゃくちゃ綺麗ですね。先月末にカップアンドハンドルを成立させ、現在はその後の押し目部分です。 できれば14ドルあたりまで引き付けてから仕込みたいところですが、これだけ綺麗なチャートであれば、14ドルまで買い下がる方針でもアリだと思います。 総評(まとめ) さて、それでは最後にまとめに入りましょう。 BTCはチャネル(黄)を基準に押し引き BTCとLTCが逆相関 →LTC半減期を前提に BTC↓or→、アルト↑ →BTCでヘッジ推奨 BTCが高値圏から調整開始か?といったポイントなのもあり、ややアルト仕込みが怖い相場ではありますが、こういった時こそ、BTCでヘッジSを打ちながらのアルト現物仕込みだと思います。 ヘッジはあくまで、「万が一のときの損失を減らすのが目的」です。BTCヘッジS、アルト現物、両方で利益を取ろうとせず、しっかりバランスの取れたロット調整を心がけるようにしましょう! 今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 現在、私えむけんが制作した動画教材『7日間でマスター!テクニカル分析とそれを元にしたトレード戦略』、好評販売中です! 今回のような、BTC分析やアルトコイン投資などの立ち回り方についても解説しておりますので、是非ご覧ください!(詳しくはコチラ)
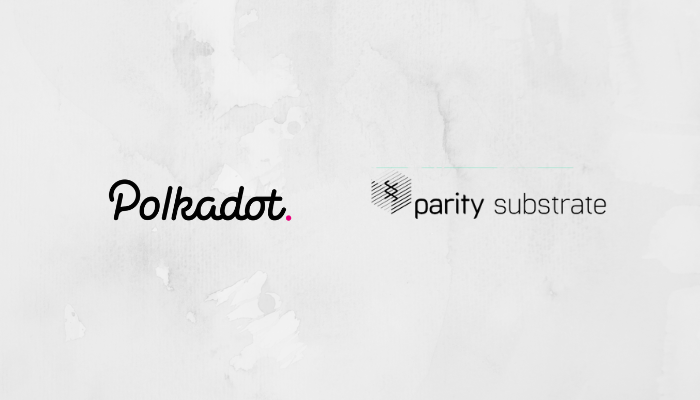
特集・コラム
2019/07/02Polkadot(ポルカドット)とSubstrate(サブストレート)の概要と仕組み、取り巻くエコシステムに関して
Polkadotは、異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティを実現するプロトコルで、トリレンマの問題も解決しWeb3.0のエコシステムの構築を目指すプロジェクトです。 またPolkadotの開発に利用されたフレームワークであるSubstrateも、簡単にインターオペラブルなブロックチェーンを開発できるとしてPolkadotと並んで注目を集めています。 本記事では、そんなPolkadotとSubstrateについて、概要から詳細まで解説していきます。 Polkadot(ポルカドット)とは? Polkadotとは、異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティを実現するためのプロトコルです。 BitcoinやEthereumなどのブロックチェーンは革新的である一方で、それぞれが独立しており、これまでのウェブのような一つの大きなエコシステムであるとは言い難い状況にあります。 Polkadotでは分散型のウェブ、つまり個人情報やデータをすべて各自が管理するような世界を創り上げることをミッションとしており、これは単一のブロックチェーンではなく無数のブロックチェーンが繋がっていくことにより実現されていくと考えられます。 Polkadotは異なるブロックチェーン同士の情報のやり取りを可能にし、それぞれを繋ぐだけでなく、後述のSubstrateと呼ばれるフレームワークを利用することで、簡単にインターオペラブルなチェーンを実装することも可能になります。 また、EthereumのVitalik氏が提唱したトリレンマ問題(セキュリティ・分散性・スケーラビリティ)も解決しうるポテンシャルを持ち、プロトコル層の開発というステージからアプリケーション層の開発へと移行するための土台としても期待されています。 Polkadot(ポルカドット)の特徴 異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティを実現 Polkadotの一番の特徴は、Polkadotのチェーン(Parachain)だけでなく、BitcoinやEthereumなどの異なる様々なチェーンを相互に接続できる点です。 Polkadotは、相互運用性(インターオペラビリティ)を持つプラットフォームとなることで、仲介者を必要としない資産の取引、コミュニケーションを可能とします。 なぜこれが重要かという話ですが、単純な利便性だけでなく分散的なウェブの実現において、分散的な資産が存在する一方で、分散的な交換方法は存在しませんでした。 そのため、Bitcoinを別の資産に交換したいとき、これは分散型のウェブのrealmで行われず、取引所などの集権性が必要とされてきました。 インターオペラビリティによるP2Pでの資産の取引が可能になることで、Web3.0と呼ばれる真に分散型のシステムを実現することができます。 DOTトークンによる単一のグローバルステートと強力なセキュリティ Polkadotでは『Pooled Security』と呼ばれるセキュリティのモデルを採用しています。 BitcoinやEthereumは強力なセキュリティを持つとされていますが、これはコミュニティの大規模なプロトコル参加が前提となっており、この前提無しでは十分なセキュリティを確保できず攻撃の対象とされてしまうこともあります。 [caption id="" align="aligncenter" width="1239"] 引用:https://www.parity.io/a-brief-summary-of-everything-substrate-polkadot/[/caption] 複数のチェーンが相互に接続されている状況を考えるとき、経済的に弱いチェーンが狙われる可能性があり、そこを軸とした穴が生まれてしまう可能性を無視することはできません。 Polkadotでは、Relay Chain(後述)とネイティブで互換性を持つブロックチェーンのセキュリティを一か所に集約させることで、チェーン毎に強弱があるセキュリティではなく、一つの強力なセキュリティによりPolkadot全体の攻撃を防ぐことが可能となります。 アプリケーション別のステート遷移 Ethereumの場合、アプリケーションはすべてEthereumのSpecificationに依存するため、トランザクションやブロック生成、合意形成など、各シャードがこの制約を受けます。 例えば、あるDAppでユーザー数が急激に増加し、トランザクションの詰まりが発生した場合その影響はネットワーク全体に及ぼされます。 Polkadotではアプリケーションが全てParachainsと呼ばれるサイドチェーンに乗っかる形になるので、同様のケースにおいてPolkadotのネットワーク全体に影響が及ぶことはありません。 トランザクションの処理が各チェーン毎に別々に行われるということは、スケーリングの問題を緩和することにも繋がっていきます。 [caption id="" align="aligncenter" width="800"] 引用:https://medium.com/polkadot-network/a-tale-of-two-technologies-presentation-transcript-e7397c1c7a49[/caption] またスケーリングだけでなく、多様なシャードをRelay Chainに接続できるということはそれだけ多様で複雑なアプリケーションがこの上に乗っかってくることも期待することができます。 Polkadot(ポルカドット)の全体像と仕組み 以下の図は、Polkadotの全体像のイメージです。 後ほど解説しますが、Polkadotのチェーンは何種類か存在していて、Relaychainを軸として動いているというポイントだけ抑えていれば問題ありません。。 インターオペラビリティとWeb3のエコシステムを実現するための3つの要素 Polkadotがインターオペラビリティを実現していくためには以下の3つの要素が鍵となります。 Relay Chain(リレーチェーン) Parachains(パラチェーン) Bridges(ブリッジ) これらの3種類の要素が組み合わさることで、プライベート・コンソーシアム・パブリックなど様式を問わないブロックチェーン同士が相互に接続されます。 Relay Chain(リレーチェーン) Relay chainはPolkadotの軸となるチェーンで、ネイティブで互換性を持つチェーン、またブリッジを通じて互換性を待たないチェーンをここに接続することができます。 合意形成やトランザクションの伝播はここで行われ、単一の正当なチェーンとしてPolkadotのエコシステムを守ります。 Parachains(パラチェーン) ParachainsとはRelay Chainに接続される異なる独立したブロックチェーンの呼称で、名前はParallel-chains(平行に走るチェーン)に由来しています。 先ほど、セキュリティは単一のグローバルステートに集約されるという話をしましたが、Parachainsにおけるトランザクションの収集や処理は各チェーン毎に独立しており、チェーン毎に独自性を持たせることが可能です。 Bridges(ブリッジ) BridgesはPolkadotのエコシステムにおけるチェーン同士、また互換性を持たないチェーンをRelay Chainと繋ぐ役割を果たします。 その中にもいくつか種類があり、ブリッジとしてデプロイされるスマートコントラクトである『Bridge Contract』やCross-Parachain Communicationなど各ブリッジがそれぞれ異なる役割を果たすことが特徴です。 Polkadot(ポルカドット)の4種類のプロトコル参加者 Validators(バリデーター) ValidatorはPolkadotエコシステムのメインのチェーンであるRealychainに直接的に関わり、参加者の中では非常に重要です。 彼らは、Nominatorにより選出され、Collatorから送られた各Parachainsのブロックを検証し、有効なブロックヘッダーをRelaychainに追加する役割を果たしていきます。 バリデーションに対してもちろん報酬は付与されますが、RelaychainのフルノードによるDOTのステーキングが必要とされ、悪意を働きかけようとした場合にはペナルティが課せられるため、正直なふるまいをとるインセンティブ設計になっていることが特徴的です。 Nominator(ノミネーター) NominatorはValidatorを選出する役割を果たします。 彼らは、DOTのステーキングを直接行わず、代表するValidatorに対してステーキングを行うことで、Validatorの報酬の一部を得ることができます。 万が一、NominatorとValidatorが結託して、といったケースもあるので(?)悪意のあるノードに対してステーキングを行った場合、Validatorに課せられるペナルティも受けることになります。 Collators(コレーター) Collatorは各Parachainsのフルノードで、それぞれのチェーン発生したトランザクションの照合を行いバンドル化し、これをRelay chainへと提出します。 彼らは、バリデーション自体は行わず、Validatorによりブロックが検証・追加された時点で報酬の一部を獲得する仕組みになっています。 Collatorも同様に、ステーキングが必要とされ、ペナルティが課せられる場合もあります。 Fisherman(フィッシャーマン) FIshermanは主にValidatorの監視を行い、Validatorが悪意のある行動を取らないように見張る感じの役割を持ちます。 他の参加者とは違い、違反を見つけた時点で彼らのステークを没収することができるという権利が付与されるインセンティブ設計になっています。 Fishermanになるためにもステーキングが必要です。 Polkadot(ポルカドット)のその他のポイント Polkadot(ポルカドット)の合意形成・ファイナリティ PolkadotのRelay chainにはGRANDPA(GHOST-based Recursive Ancestor Deriving Prefix Arrangement)と呼ばれるファイナリティガジェットが実装されています。 Bitcoinなどでは6 confirmationで確率的にブロックが覆らないといった、probabilistic finality(確率的ファイナリティ)が採用されていますが、GRANDPAでは数学的に検証可能であるProvable Finality(証明可能ファイナリティ)を実現します。 このアルゴリズムの特徴は、分散ネットワークだけでなくブロックチェーンの特徴を生かして、単体のブロックに対する投票ではなく、ブロック高に対して投票を行うことができるという点です。 これは、子ブロックが有効であれば親ブロックも有効であるという前提に基づいています。 [caption id="" align="aligncenter" width="800"] 引用:https://medium.com/polkadot-network/grandpa-block-finality-in-polkadot-an-introduction-part-1-d08a24a021b5[/caption] イメージCのブロックまでは2/3の投票が獲得できているので、説明可能な状態でファイナライズされており、例えばE1・E2に対する総数が2/3を超えれば、その前にあるD2もファイナライズされていくという感じになっています。 Polkadot(ポルカドット)のガバナンス Polkadotのガバナンス、プロトコルにおける政治(?)はPolkadotのトークンであるDOTのステークホルダーを中心として設計されています。 第一に、上述の参加者(Validator/Collator/Nominator/Fisherman)がプロトコルにおいて悪意のある挙動を取らないように、といったゲーム理論的インセンティブがあります。 これは報酬とペナルティをベースとして設計されており、プロトコルへの攻撃を防ぐ役割を果たしています。 そして、プロトコル内の意思決定においてもDOTトークンが重要です。 0xなどが既に行っているように、Polkadotもチェーンの分岐という形を取らずに、ステークホルダーによる投票でプロトコルのアップグレードを行うことができます。 DOTトークンの保有をベースとした投票により、プロトコル参加者の意思をより如実に反映させることが可能となっています。 Substrate(サブストレート)とは? Substrateとは、Ethereumの元CTO兼共同創設者であるGavin Wood氏が率いるParityによって開発された、ブロックチェーンの開発を行うためのフレームワーク(Tech Stack)です。 これを利用することで、ウェブにおいてアプリケーション毎に独自のHTTPを実装する必要がないように、ネットワーキングや合意形成に関する部分をコードを実装せずにブロックチェーンを新しく作ることができます。 また、Polkadotと同じ文脈で語られることの多いSubstrateですが、これはPolkadotがSubstrateのフレームワークを利用して実装された最初のチェーンである点、Substrateを利用して実装するチェーンとPolkadotのRelay chainの互換性を持たせることができる点などが主な理由です。 Substrate自体は、Polkadotからは独立しているため、必ずしもPolkadotと接続する必要性はなく、今年下旬に予定されているメインネットを待たずとも独自のブロックチェーンを開発することは可能であるとされています。 去年のWeb3 SummitではGavin Wood氏によるSubstrateの実装のデモも行われました。 https://youtu.be/0IoUZdDi5Is?t=3261 Substrate(サブストレート)の特徴 Parachainsとして実装することができる Substrateのフレームワークを利用することで、実装することのできるチェーンには3つの種類があります。 [caption id="" align="aligncenter" width="800"] 引用:https://medium.com/polkadot-network/a-tale-of-two-technologies-presentation-transcript-e7397c1c7a49[/caption] この中には、Polkadotと独立した合意形成を持つより自由度の高いSolo Chainと呼ばれるチェーンあります。 その他、Solo ChainとBridgeが一緒になったものは、上述のBridgeの仕組みでPolkadotのRelay Chainと繋げることもできます。 この二つの場合、Polkadotの持つ強力なセキュリティプールを利用することができず、独自の合意形成を設計する必要があるため、どちらかというとエンタープライズなどに向いているのかなという印象です。 SubstrateがPolkadotとセットで名前が挙げられる通り、Parachainsの一つとして実装することももちろん可能で、これはBridgeを介さずにRelay Chainと繋がることができ、合意形成やセキュリティ(プール)、インセンティブ設計などを考慮する必要性が生じません。 Substrate(サブストレート)の高い開発自由度 [caption id="" align="aligncenter" width="800"] 引用:https://medium.com/polkadot-network/a-tale-of-two-technologies-presentation-transcript-e7397c1c7a49[/caption] Substrateは、Substrate Core・Substrate SRML (Substrate Runtime Module Library)・Substrate Nodeの3つのレイヤーにより構成されます。 イメージのPolkadot Coreでは、PolkadotのRelay Chainに接続するチェーンを実装することができます。 ここでは、ノード、ネットワーキングなどの諸々を自身でコーディングし実装する必要がありますが、その分自由度の高いブロックチェーンを作ることができます。 [caption id="" align="aligncenter" width="800"] 引用:https://medium.com/polkadot-network/a-tale-of-two-technologies-presentation-transcript-e7397c1c7a49[/caption] そこでSubstrate Coreを利用すれば、最低限ランタイム(State Transition Function)のコードを実装するだけで、上記の諸々をコーディングする必要性は一切なくなります。 [caption id="" align="aligncenter" width="800"] 引用:https://medium.com/polkadot-network/a-tale-of-two-technologies-presentation-transcript-e7397c1c7a49[/caption] これはカスタマイズ不可能というわけではなく、用意されているものをカスタマイズしていくことも十分に可能です。 Substrate SRMLでは、ライブラリから必要なモジュールを選択し、あとはパラメータなどを設定するのみで実装ができる機能を提供しています。 [caption id="" align="aligncenter" width="800"] 引用:https://medium.com/polkadot-network/a-tale-of-two-technologies-presentation-transcript-e7397c1c7a49[/caption] 一番下のSubstrate Nodeでは、jsonのコンフィグファイルのみで完全なスマートコントラクトブロックチェーンを作ることができるとされています。 [caption id="" align="aligncenter" width="800"] 引用:https://medium.com/polkadot-network/a-tale-of-two-technologies-presentation-transcript-e7397c1c7a49[/caption] このように、開発者の求める自由度に応じたカスタマイズ性が広いこともSubstrateの特徴の一つです。 フォーク無しのアップグレード Substrateではネイティブのランタイム(実行環境)のほかに、WASM(WebAssembly)のランタイムが用意されています。 [caption id="" align="aligncenter" width="1350"] 引用:https://www.parity.io/a-brief-summary-of-everything-substrate-polkadot/[/caption] ネットワークのアップグレードが行われた場合、一部のクライアントでアップデートが行われていない場合があります。 このとき従来のシステムでは、互換性を持たない別々ネットワークが起こり、フォークという形を取らざるを得なくなります。 Substrateの場合、Substrateに統合されたWASMの仮想マシンで既存のバージョンのランタイムをinterpretし実行できるので、ネットワーク上のすべてのノードがフォークをせずに正しくチェーンと同期することができます。 Substrateを利用してParachainsの開発実装を進めるプロジェクト ChainX [caption id="" align="aligncenter" width="1024"] 引用:https://github.com/chainx-org/chainx-logo/blob/master/assets/ChainXlogo001.png[/caption] ChainXはSubstrateで実装された最初のブロックチェーンネットワークで、PolkadotのエコシステムにおいてはDEXのような立ち位置にあります。 上述のBridges(Parachains)の部分の開発を行い、Polkadotと直接互換性を持たないBitcoinやEthereumなどはChainXを通じて資産の交換を行うことができるようになります。 https://twitter.com/chainx_org/status/1131215820569243655 ChainXは2019年5月25日にメインネットをリリースし、将来的には、ChainX独自のRelay Chainの実装もロードマップに記載されています。 ChainXでは将来、Polkadotにおけるインターチェーンコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしていくことが期待されます。 Zerochain [caption id="" align="aligncenter" width="1748"] 引用:https://medium.com/layerx-jp/%E7%A7%98%E5%8C%BF%E5%8C%96%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3-zerochain-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E5%A7%8B%E5%8B%95-11696bce0b13[/caption] Zerochainは、日本国内の企業であるLayerXによって開発され、Substrateのフレームワークを利用して実装されるプロジェクトです。 主に、ブロックチェーンにおけるデータの透明性・秘匿性についてのプライバシーに関する問題の解決を目指しており、暗号学的なアプローチでブロックチェーン上のデータの秘匿化を可能にします。 公式ブログによれば、ZerochainはBitocoinなどのUTXO型ではなくEthereumのようなアカウントベースの秘匿ブロックチェーンであり、これは世界で初の事例であるため世界中のコミュニティからも注目を集めています。 Edgeware EdgewareはRustで記述されWASM(WebAssembly)で高速に実行される、Polkadotで最初のスマートコントラクトプラットフォームです。 Polkadotのメインネットがローンチされると、PolkadotのParachainsの一つとして実装され、簡単にコードをデプロイすることができるようになります。 Edgewareの開発を行うCommonwealth Labsではガバナンスにも力を入れており、ETH保有者に対して90%以上のトークンを付与するロックドロップや投票などのオンチェーンガバナンスはEdgewareの大きな特徴の一つです。 Plasm PlasmはSubstrate CoreとSRMLを利用した開発が行われ、Polkadotに繋げることのできるPlasmaチェーンであり、独自のSRMLでもあります。 このライブラリを利用することで、親のPlasmチェーンと接続できる独自のPlasmaチェーンを作ることができるようになります。 YouTubeでも既にデモ動画が公開されており、今後はUTXOモデルの対応などに力を入れていくようです。 https://www.youtube.com/watch?v=T70iEgyuXbw#action=share まとめ ブロックチェーンを一段階上のレベル上げるPolkadotと、それに関連してブロックチェーン開発を容易にするフレームワークであるSubstrateについて、できる限りで分かりやすく紹介しました。 Polkadotのメインネットは年内に控えていますが、これがローンチされると、取り巻くプロジェクトやエコシステムが増えていくことで、これまでとは違った進歩が見れると思います。 今後も、より一層注目が集まっていくプロジェクトになると思いますが、基本的な内容の理解に際して、本記事を参考にしていただければと思います。

特集・コラム
2019/06/26専業トレーダーえむけんの仮想通貨市場分析!【6月26日】
みなさん、こんにちは!えむけん(@BinaryMkent)です。 前回更新後、BTCがさらに高値を更新しましたね!前回記事でも「アルト下、BTC上」とお話ししていましたが、まさかすんなり11500ドルまで上げてくるとは思いませんでした笑 依然BTCは高値圏ではありますが、今回も逃げ時や資金循環を踏まえた分析や立ち回りについてお話ししていこうと思います。是非最後までお付き合いください! それでは、早速BTCの分析から進めていきましょう。 BTCチャートの分析 BTCチャート(長期) まずは、BTC長期チャートから見ていきましょう。 前回更新時からさらに高値を更新し、11500ドル周辺まで上昇してきました。前回記事でもお話しさせていただきましたが、やはり高値圏でのチャネル推移は強い証拠でしたね。 ここで、今回の上昇のきっかけとなった逆三尊から今に至るまでの波動をカウントしてみましょう。すると、「今回の上昇が丁度5波目に当たる」ということが分かります。 ダウ理論の『主要トレンドは3段階に分けられる』を元に考察すると、すでにトレンドの3段階目(5波目)ということもあり、ここらで一時利食い撤退に進む可能性が考えられます。ポイントとしても、11500ドルという抵抗帯周辺ですから、ここらでどういった推移を見せるのか?は要注目でしょう。 では、ここからは中期チャートを元に、現状の分析、並びに今後の展開予想について考察していきましょう。 BTCチャート(中期) こちらがBTCの中期チャートになります。 かなり長いスパンのチャネルを形成していますね。個人的には、スイングを前提に11500ドル周辺でSを入れてみていますが、このチャネルが崩れると比較的大きな調整にも期待できるため、チャネル抜けを確認してから本腰を入れてSを打つ・・・、というような立ち回りを考えています。 この長期チャネルと今月から続いている中期チャネル(上限)などを元に、ポジション取りしていくのが妥当だと思います。 BTCチャートの総評 さて、それではBTCチャートについてまとめていきましょう。今回、考えられうるシナリオは以下の3通り。 中期チャネルで押し目形成 ⇒長期チャネル継続 中期チャネル上限を下抜け ⇒長期チャネル継続 中期チャネル上限を下抜け ⇒長期チャネル継続否定 「そろそろ節目の価格帯なため、大きめの調整が始まってもおかしくない」と考える方も多いと思いますが、そういった天井狙いのハイレバSを狩りに来る可能性も大いに有り得ます。 よって、スイング前提であったとしても、万が一の時を想定したポジション分割(INポイントの分割)などを行い、極力リスクを減らすような立ち回りを心がけるべきでしょう。 では次に、ドミナンス分析を進めていきましょう。 ドミナンス分析 ドミナンスチャートに関しては、「Trading View」を参考することにしております。(外部リンク:https://jp.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/) 6/12を節目にBTCドミナンスが大きく上昇、それに対し主要アルトコインのドミナンスが全体的に下落していますね。恐らく5月上旬同様、資金がアルト市場からBTCに流れているのだと思われます。 では、少し拡大して見てみましょう。 主要アルトのドミナンスは、全体的に下落傾向にありますが、その中でも目立つのは「LTC」ですね。基本的に、どの通貨も緩やかに下落していますが、LTCだけBTCドミナンスとしっかり逆相関して推移しているんです。 少し話が逸れますが、ここ最近のBTC上昇、この火付け役となったのはLTCです。 まず、LTCの上昇をきっかけにアルト市場が活性化しましたね。そして、アルト市場に集まった資金が一気にBTCへと流れ、直近高値更新・・・、それを繰り返してここまで上昇してきたわけです。 実際に両者のドミナンス推移を見てみると、赤点線を機に資金がLTCへと集中し、LTCから資金が抜けると同時にBTCのドミナンスが反転上昇、再度BTCのドミナンスが低下すると、それに伴いLTCドミナンスが上昇・・・、というように、「現在の仮想通貨市場はこの2通貨が鍵を握っている」といった状況なわけです。 この後もLTCの見所については掘り下げていきますが、これらドミナンスの観点からも要注目しておくべき通貨と言えるでしょう。 主要アルトコインの動向 先ほどお話ししたように、LTCはもちろん要注目なんですが、直近の動きをピックアップしてみると、NEOとTRXの動きが気になりますね。 ということで今回は、LTC、NEO、TRXの3通貨を対象に分析を進めていこうと思います。 LTC 直近の動きを見ると、かなりアップダウンも激しく手出しづらい状況ですね。 しかし前回記事でもお話しした通り、8月上旬(白点線)に好ファンダ(半減期)を控えているため、拾えそうなポイントがあれば積極的に拾っていきたいところです。 またその際には、純粋なラインで押し引きするだけでなく、先ほどお話ししたようにビットコインの動向を踏まえて、「ビットコインが売られうるポイントとLTCが買われうるポイント」を考えた上で売買を進めていくと良いでしょう。 参考サイト:『Litecoin Block Reward Halving Countdown』 NEO 特別取り上げるほどのチャートではありませんが、少し直近の出来高が気になりますね。以前もお話視しましたが、こういった急な出来高上昇はファンダが漏れている可能性などが考えられるため、チャート次第では無理のない程度に攻めてみてもよいと思います。 またチャート単独で見ると、上画像のように底形成パターン(アダムとイブ)の成立直前であり、成立した場合にはレジスタンス(緑)周辺までは上昇する可能性が高いと見ています。 TRX 正直、チャート的にはかなり買いづらくはありますが、今まで何度も意識されてきた価格帯周辺にて推移しているため、少し長めのスパンで拾ってみてもいいかなと思っています。 とはいえ、これだけサポートの価格帯が広いと損切り幅も大きくなってしまいます。ですから、黄色ゾーン内短期足でのパターン形成などを監視しながら、売買判断を行っていくべきでしょう。 総評(まとめ) さて、それでは最後にまとめに入りましょう。 BTCは緑チャネルを基準に押し引き →中期チャネルも参考に BTCとLTCが逆相関 →LTC半減期を前提に 今回は比較的アルト分析に重点を置いてみましたが、NEOのように事前に何かしら仕込みの形跡が見られた場合には、好ファンダが漏れている可能性も考えられるため要注目です。 しかし地合いによっては、好ファンダであっても買われないときがあります。「BTCが下落傾向の時」、つまりリスクオフムードの時ですね。 現状、BTCが節目の11500ドル周辺にて推移しているため、ここから本格的に調整移行する可能性も考えられますが、昨日VETの好ファンダに対してもしっかり価格がついてきていたため、地合い的には材料さえあればしっかり反応するのでは?と見ています。(当然ファンダがなければ伸びませんが・・・) 今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 現在、私えむけんが制作した動画教材『7日間でマスター!テクニカル分析とそれを元にしたトレード戦略』、好評販売中です! 今回のような、BTC分析やアルトコイン投資などの立ち回り方についても解説しておりますので、是非ご覧ください!(詳しくはコチラ)

特集・コラム
2019/06/21Decrypt Tokyoへの参加と、そこで見たBlockchain業界の未来
2019/6/8-9 に2日間に及ぶ日本最大級のBlockchainハッカソンであるDecrypt Tokyoが開催された。 今、思い返すと、あの2日間は夢だったのではないかと思わせるほどの熱気を纏っており、エンジニア達が口角泡を飛ばす議論を行なっていた光景がありありと脳裏に蘇る。 今回、私、コンソメ舐め太郎はDecrypt Tokyoに本ハッカソンへ参加をさせていただいた。 参加者の視点から見ても、非常によい経験・刺激と今までにない感動を感じたため、イベントは大成功といえる盛り上がりだったように思われる。 これから第2回、第3回と継続して開催されてほしいと切に願う。 [caption id="attachment_38606" align="aligncenter" width="800"] Decrypt Tokyo2019 イベントホームページ[/caption] ◇イベントサイトはこちら:https://www.decrypt.tokyo/ 当イベントのスポンサーとしてBlockchain界の先頭に立つ名だたる企業が肩をならべ、その本気さが窺い知れる。会場は、Speee様提供の広く落ち着いたオフィスにて行われた。 簡単にだが、参加者目線として、初日、二日目のイベントに関してのレポートを書いていきたいと思う。 イベント1日目 開会 私は参加者として、Decrypt Tokyoのイベント会場へと足を運んだ。 8:30頃、中に入るとすでに50名程度のBlockchain enthusiast達が、ある者は用意されていた朝食を手にしながら立ち話をし、ある者はラップトップと向かい合いBlockchainのあれこれに取り組んでいた。事前に主催者側で、参加者の技術レベルに応じてチームが組まれていたようであり、私は指定されたテーブルへ向かった。 そして同じチームになったエンジニア達と自己紹介や雑談をしながらイベントの開始を待っていた。(英語でのコミュニケーションOKと、事前のアンケートに記載していたため、メンバーの半分は海外の方だった。) 会が始まり、イベントのスケジュールや取り組むテーマ、上の階でスポンサー企業のプレゼンが行われていることなどの説明を受け、ハッカソンが開始。櫃を切ったようにHacker達が議論を始めた。 チーム数は20。それぞれテーブルが用意され、それを取り囲むように参加者が座っている。そしてその様子を各スポンサー企業のメンターの方々が見て回ったり、時にメディアの方々が撮影に来たり、プロジェクトの進捗具合を尋ねて来たり、といった具合だ。 開幕 1日目のハッカソンは夜21:00まで行われた。終始、参加者達による喧々諤々の議論が繰り広げられており、非常に活気に満ちた時間に感じられた。 また、各チームにはBlockchain技術に精通しているメンターと呼ばれる人間が1人加えられており、色々な技術的な質問を受け付けたり、ときには実装を行ってくれたりした。 そこで、私はいちIT技術者として、とても強烈な刺激を受けた。今回のテーマは、「ブロックチェーン・スマートコントラクトを使用した新規サービスを考え、プロトタイプを作成」「ユーザビリティが高いdApps」というお題を与えられた。抽象的なテーマだけに参加者達はかなり頭を悩ませた。 ブレインストーミング 我々のチームは、元々4名のハッカーがチームを組む予定であったが、当日は2名の欠席があった。代わりに、Curvegridから1名ヘルプとしてメンバーに加わった。 そしてそれを元に「イベントの欠席者からペナルティとしてETHを没収するプラットフォーム」を考えたが、かなりネガティブなアイデアであるため没となった。笑 我々チームのメンターとして参加していたKyber NetworkのシニアエンジニアであるAntonが、「エアードロップなどで受け取ったユーティリティの低いトークンを売りに出し、その売却額だけETHをレンディングするプラットフォーム」というアイディアを提案した。 非常によいアイデアに思われたが、Hackathon中に実装するのは中々難易度が高く感じられたため、別の案を考えることになった。私の頭の中では、「ユーティリティの低いトークンを買ってくれる人というのは果たして存在するのか」「どうにかして需要を生み出せないだろうか」という考えが頭の中をぐるぐると回っていた。 こうしたブレインストーミングがチームの中で飽和し、一旦の小休止を挟むこととなった。 その時に、「ガチャポンという形式ならユーティリティの低いトークンだとしても、そのブラックボックスでアトラクティブな仕組みを利用するユーザーはいるのではないだろうか」と思いつき、チームに提案した。 そして、Antonが「That’s good idea. It’s easy to implement.(いいアイデアだね。実装も簡単だよ。)」と発し、1時間後にはそれを作り上げてしまったのだ。 これまでウォーターフォールモデルで開発及び保守しかしてこなかった人間であったため、このことには非常に感銘を受けた。民族論や、企業論に話を展開したくはないが、「これが海外スタートアップのやり方か・・・!」と素直に感じてしまった。 今までの自分には考えられないスピード感だった。しかしその反面、こういったプロダクトドリブンなやり方は、非常に本質的な物事の進め方であると感じた。「この世界に飛び込んでみたい」と感じさせてくれただけでも、このDecrypt Tokyoに参加した意味があったと、主催者の方々、スポンサーの方々に感謝をしたい。 その後、私ともう1名のハッカーはAntonの実装したコントラクトを読み、理解し、そしてそれをドキュメントへ落とし込む作業を行った。 帰宅後 その日、Hackathonは熱を保ったまま閉幕を迎えた。私は元々デザインを趣味で行っていたため、帰宅後にプロトタイプのロゴ、パワーポイント用のマテリアル等を作成し、発表に備えた。 2日目 大詰め Hackathon2日目。昨日の会場に満ちた熱量をそのまま持ち込んだように、場は賑わっていた。各チームの発表は午後。 それに向かって、我々のチームは、発表の構成や話す内容についてあれこれとすり合わせながら、スライドをまとめた。プロトタイプのフロントエンドに関しては、割とギリギリのタイミングで完成した。 実際のガチャポンの画像を用いて、レバーの所をクリックすると自動でMetamaskの承認画面が起動し、ボタンを押すだけでETHが他のトークンに代わる仕組みだ。 サイトへのアクセスを含め、たった2クリックでトークンを交換できる。世界一参入障壁の低い取引所であり、取引自体はKyber Networkで実行されるため、ノンカストディアルである。 昼食 正午に差し掛かろうとする頃、発表直前の少しばかり張りつめた空気感が会場には漂っていた。 昼食の際に、Curvegridのインターン生であり、カナダのWaterloo大学の1年生の人と仲良くなった。(英語上手だね!とほめてもらえたのは素直にうれしかった。)そして、この子がとんでもない人物だとはこの時には気づかなかったのだ。 プレゼン プレゼン順は各チーム代表者のくじによって決まった。我々のチームは17番目の発表となった。 もう少し早いほうがよかったが、こればかりは運のため仕方なかった。 審査員には、世界のBlockchain業界の先頭に立つ面々が並んでいた。「こんな人たちの前で発表なんて無理やろ・・・」と背筋が伸びまくった。 各チームの発表が次々と行われ、それぞれとても面白いアイデアが持ち寄られた。個人的には、Bitcoin SVを利用した、パスワード管理のシステムが非常に優れたアイデアだと思った。そして3時間程度の後、我々の発表の番が回ってきた。 いざ始まってみると、そこまで緊張はしなかったが、それでもとんでもない状況にいるとは認識できていた。 本来でれば一番最初に、プロトタイプのデモ動画を再生するはずであったが、諸々のミスによりそれは叶わなかったし、そこで発表時間5分の内の半分を使用してしまったのは、多少なりとも焦った。 その後は、時間を取り戻すため駆け足での発表となってしまった。このあたりもHackathonの経験の差など出るポイントだと感じた。 そして、結局、時間の制約上、最後のスライドで発表するはずであった「将来の展望」についてはお蔵入りとなってしまい、悔しい思いをした。個人的には最も発表しておきたいポイントであった。 そして、人生初めてのHackathonの発表は、かなり足がもつれながらもなんとかゴールとなった。 プログラミングコンテスト Hackathonの順位集計の間、プログラミングコンテストが実施された。1時間に5問の問題が提示され、それを解くスピードと正確さを競う。問題に関しては、通常のプログラミングコンテストのそれと似たような形式と内容であった。 たまに暇つぶし程度にプログラミングコンテストには参加していたため、少しだけ気張っていたのだが、いざ蓋を開けてみると自分は1問しか解けなかった泣 結果発表 Hackathonの結果発表の時間となり、会場のセットアップが行われた。まず最初に、プログラミングコンテストの結果発表である。 なんと1位は、昼食休憩で知り合った1年生の子だったのだ。わずか20分ですべての問題を解き終わったらしい。ニュータイプの人間である。実際に問題を見てみるとわかるが、20分で解ける問題では到底ない。 そして、Hackathonの結果発表。 3位⇒2位⇒1位⇒特別賞3つ の順で発表された。我々のチームは3位以内には選ばれなかったものの、オリジナリティ賞を受賞した。この時の喜びは、一生忘れられないと思う。前日に知り合ったハッカー達と一つの目的に向かってスクラムを組み、がむしゃらに取り組んだ結果が認められるというのはこの上ない喜びがあった。 Decrypt Tokyoに参加してみて 実際にプロダクトを一緒に作っていくという共同作業で、たった2日間ではあったものの強い絆を感じることができたこと。世界の最前線で戦うエンジニアの働きをすぐそばで見れたこと。 初めてのHackathon、かつ英語というハードルを乗り越えてなんとかゴールできたこと。個性豊かな友人ができたこと。色々な経験ができたし、自分の人生に影響を与えてくれた、とてもよいイベントだったと、心から思った。 All Photo by Taishi Masubuchi from Quantstamp

特集・コラム
2019/06/20北京ブロックチェーン紀行 GMGC Beijingへの参加、IOSTオフィス往訪
今回、私は2019年6月16日から18日にかけて、北京で行われたブロックチェーンのイベントに参加し、IOSTのブロックチェーン開発拠点を訪問してきた。 初日 中国への旅路 中部国際空港 セントレアから北京までは約3時間のフライト。往復ともちょうどいい時間にフライトがある。北京に着いたのは正午少し前で、意外にも入国は比較的すんなり終わった。 ATMでキャッシングをして、ホテルへ向かおうとした。事前に教えて貰っていたDiDiという中国版のUberのようなアプリを使って、いざ呼ぼうと思ったが、どこへ呼べばいいかわからない。 Googleで検索を重ねて、駐車場で呼べばいいらしいことがわかった。通常はブロックされているGoogleだが、世界定額はありがたい。すぐにやってきたDiDiに乗り込んで、やれやれと思ったが、なにか中国語で話しかけてくる。 もちろん中国語はさっぱりである。行き先を確認しているようで、行き先をBaiduで示して一段落。ちなみに3回DiDiを使ったが、2回がHonda車、1回がNissan車だった。北京は、街が広い東京のような感じで、かなりの大都会だ。 2日目 GMGC Beijingへの参加 2日目は、6/17-18の2日間開催されたGMGC Beijingというゲームのイベントに参加した。 実は、今回のイベント参加費を銀行にて送金したのだが、手数料だけで参加費を上回り、送金日数まで3日以上かかり、仮想通貨での支払いができればずいぶん楽になると思った。 イベントは15社ほどが参加しているミニEXPOと1つの会場でカンファレンスが行われていた。詳細は、こちらのサイト (http://en.gmgcongress.com/)を確認していただきたい。 [caption id="attachment_38699" align="aligncenter" width="522"] CHAIN PLUSのボード[/caption] その中で、CHAIN PLUS (http://www.chainplus-me.com/)というブロックチェーンゲームに特化したサミットが開催されていた。今回の主な目的は、これだ。 [caption id="attachment_38709" align="aligncenter" width="800"] CHAIN PLUSのスピーカー[/caption] 講演者は、Blockchain AlianceのプレジデントやGumiの國光宏尚氏、HPBやGXChainといったトークンエコノミーを実際の応用したサービスの紹介など幅広いもので、ゲームサイドというより、ブロックチェーンサイドからゲームに関わる技術の紹介の色彩が強かった。 国光氏は、「FiNANCiE」というSNSと「MyCryptoHeroes」の紹介をされていた。唯一の日本からの講演ということもあり、参加者は熱心に聞き入っていた。 講演を聞いて思ったのは、すでにブロックチェーンが、中国では実用段階に入って来ているということだ。それと、ハードからソフト、サービスなどいろいろなところでビジネスを展開しているのが印象的だった。 3日目IOSTオフィスへの訪問 3日目は、今年メインチェーンをローンチしたIOSTの開発拠点を訪問した。CTOのテリー氏の熱烈な歓迎をいただき恐縮した。 開発拠点は、北京の経済の中心地にある保険会社のビルの15階にある。とても大きな立派なビルで、セキュリティもきちんとしている。 オフィスは、フロアの半分を占めていて、かなり広いガラス張りの今どきのデザイン・レイアウトだ。入って正面のカウンターバーにIOSTの光るロゴがとてもマッチしていてセンスを感じる。 [caption id="attachment_38702" align="aligncenter" width="800"] IOSTのオフィス[/caption] 部屋からはオフィス街を一望できる好立地で、開放感に溢れている。ゆったりとした空間に30名ほどのメンバーが仕事をしていたが、羨ましい環境だ。 [caption id="attachment_38704" align="aligncenter" width="800"] オフィス街を一望できるIOSTのオフィス[/caption] やはり勢いのあるオフィスというのは、活気があって、未来を感じさせる。エンジニアの人たちを中心にメンバーを紹介していただいたが、みな若く陽気な人達だ。 私の会社もIOST上でゲームアプリをローンチしているが、彼らの大いなるサポートがあって、問題を解決してきた。本格的にスマートコントラクトを利用したシステムを構築するには、開発し易いプラットフォームだと思う。 いろいろなビジネス展開も進んでいるという話もテリー氏からお聞きし、ますます先が楽しみなブロックチェーンプラットフォームである。 ブロックチェーンに関しては、中国は進んでいる面も多く、これからも注目していきたい。 本記事は、エバーシステム社のCTOであるDr.和田氏による寄稿記事です。 エバーシステム社ではEthereumとIOSTのブロックチェーン上にてCrypto NynjaというDAppsゲームを開発しています。 Crypto Ninja
















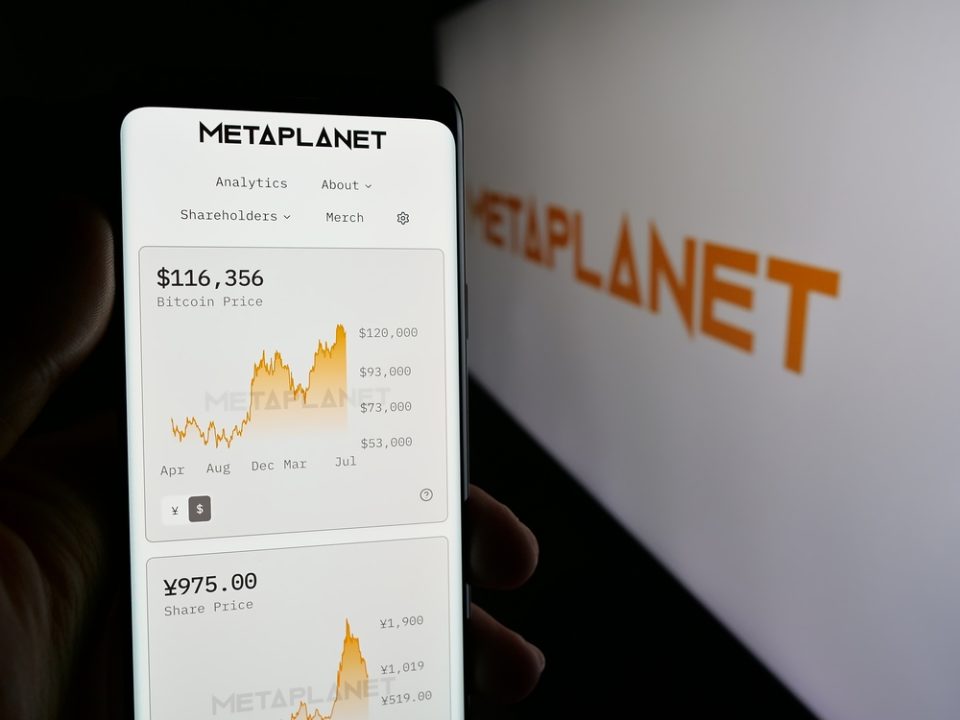

 有料記事
有料記事


