
初心者向け
2023/09/09「秋田県災害復興支援NFT」の購入ガイド【初心者向け】
本記事は、秋田県災害復興支援を目的とした「A Love Movement」の大久保 鉄三氏がデザインした「スマイルくん」のNFTを初めて購入する方向けの記事です。 関連:「自然災害復興支援NFTプロジェクト」立ち上げと「秋田県災害復興支援NFT」販売開始のお知らせ PCでNFTを購入するまでの過程をステップバイスッテプで分かりやすく解説しています。 NFT初心者の方でも手順に沿って一つ一つ行えば決して難しくありませんので、ぜひこの機会にNFTの世界に入ってみてください。 NFT「Smile-kun Akita」の概要 「自然災害復興支援NFTプロジェクト」では、ロサンゼルスの現代アーティスト、大久保 鉄三氏とコラボレートし、2023年7月の秋田県豪雨災害の復興を支援するNFTを販売致します。 今回のデザインでは、背景色を秋田県のシンボルカラーに近づけ、A Love Movementでも初期の頃から長く多くのお客様に愛されている「スマイルくん」を採用。秋田美人のようなキレイな「まつ毛」を従来のデザインに組み込みました。 寄付の方法として今回選択されたNFTとは、"Non Fungible Token ( ノンファンジブルトークン )の略で、直訳すると非代替性資産となります。 NFTではブロックチェーンの技術が活用されることで、デジタルデータに固有の価値が付くようになり、「誰 ( どのウォレット ) が所有しているのか。」、「 いつそのデータが他に譲与されたのかが」分かることで偽造不可な鑑定書・所有証明書付きのデジタルデータとも言いかえれます。 今では、様々なシーンでNFTの活躍が始まりましたが、今回のチャリティ活動の参加により獲得できるNFTには、「秋田県への自然災害への復興支援の証明」、そして「その証明書で獲得したNFTは同じデザインではあるものの、唯一無二の偽造不可のデジタルアートである」と認識ください。 事前準備 まず、NFTを購入する前の事前準備として取引所の開設からウォレットに$ETHを送金するまでの手順をご案内します。 取引所と$ETH、ウォレットの準備が既にお済みの方は、NFTの購入方法まで飛んでください。 4つの事前準備 1、取引所の口座開設 2、ウォレットの準備 3、取引所へ入金 / $ETHの購入 4、ウォレットへの$ETH送金 取引所の口座開設 NFTの購入には仮想通貨$ETHを日本の取引所で購入する必要があります。おすすめの国内取引所はOKCoinJapanです。 OKCoinJapanは、日本の金融庁に、暗号資産交換業者の第00020号として登録されており、24時間365日、入出金に即時対応、セキュリティの高さや丁寧なカスタマーサポートが特徴の取引所です。また、現在はeKYCが主流のため、登録から入金までが最短即日で可能です。 本人確認と二段階認証の手順も併せて解説するのでぜひ目を通してください。 OKCoinJapanの登録方法 メールアドレスとパスワードでアカウント作成する まず、OKCoinJapanの公式サイトにアクセスします。 右上の「アカウント登録」をクリックしてください。 メールアドレスとパスワードを入力します。 メールアドレスを入力後、送信ボタンを押すと認証コードが届くのでこちらも入力してくださいね。 こちらでアカウント登録は完了です。そのままアカウント設定に進むをクリックしましょう。 携帯電話番号を登録する 続いて基本情報を入力していきます。携帯電話番号の右にある「設定」へ進みましょう。 日本が選択された状態で携帯電話番号を入力してください。SMS認証コードを送信して、届いたコードを入力します。同じくメール認証ももう一度行いましょう。 基本情報を入力する 住所や職業などの情報を入力していきます。この後、本人確認に進むので本人確認書類と同じ住所を入力してくださいね。 入力内容を確認したら「次へ」をクリックします。 次に取引目的を選択し、取引経緯やその他の情報を選択し「保存」→「次へ」をクリックします。 本人確認を完了する 続けて、本人確認を完了させましょう。本人確認は審査期間が短いeKYCのご利用をお勧めします。今回はeKYCのやり方を説明していきます。 eKYCにはOKCoinJapanのアプリが必要なので先にダウンロードしておきましょう。(OKCoinJapanアプリ:iOS/Android) まず、パソコンに表示されたQRコードをスマホで読み取ります。本人確認の作業が開始されるので手順にそってeKYCを進めましょう。 本人確認作業が済んで問題がなければそのまま「申し込む」→「提出」をクリックして完了です。 ウォレットの準備 - Memaskのインストール方法 取引所の口座開設の申請をしている間にウォレットの準備を行います。今回はウォレット「Metamask」を例にして実際の手順を解説していきます。 Metamaskのインストール方法 まずMetaMaskの公式ページにアクセスします。 (MetaMaskは現在Chrome、Brave、Firefox、Edgeの4つのブラウザに対応しており、今回はChromeを例にして解説します。) またスマホアプリからでも利用可能になります。ぜひこちらの記事をご覧ください。 MetaMask(メタマスク)モバイル・スマホの使い方を解説! まず、公式HPの「Download for (Chrome)」をクリックしてブラウザに直接インストールしましょう。 下記のような画面が出てくるので、「Chromeに追加」をクリック。 画面が切り替わるので右側の「Chromeに追加」をクリックするとインストールされます。 ダウンロードが完了すると、サイト画面が切り替わり上記のような画像が表示されるので「開始」をクリックして、そのままウォレットを作成していきます。 次画面で「ウォレットを作成」をクリック。(インポート方法は後述しています。) 上記の項目に問題が無ければそのまま「同意する」を押して次に進みましょう。 次にパスワードを設定します。 *ここで作成したパスワードはMetaMaskにアクセスする際に今後必要となるので、忘れないよう紙に書いての保存するなどをしっかりと保管しておきましょう。 パスワードを入力し、利用規約に問題が無ければ「作成」をクリックします。 次の画面でシークレットリカバリーフレーズ(ウォレットを復元できるパスワード)の解説動画が流れます。 右下の設定から日本語字幕が選択できるので、知識に不安がある方は動画を見て勉強しておきましょう。問題無ければ「次へ」を押します。 上記のようなシークレットリカバリーフレーズの確認画面が表示されたら、赤枠の部分をクリックし、表示される英単語を紙にメモしましょう。 *シークレットリカバリーフレーズは金庫における「鍵」のような存在で、作成したウォレットにアクセス出来てしまう非常に重要なものです。必ずオフラインでしっかりと保管しておきましょう。 メモが終わり「次へ」をクリックすると、英単語が表示されるので先ほどメモした英単語を左上から順番に選択していきます。 上記画像のような画面が表示されれば、ウォレットの作成が完了となります。 MetaMask(メタマスク)のバックアップ・復元方法を覚えておこう 取引所への日本円入金 | $ETHの購入方法 取引所での口座開設が完了したら、取引所へ日本円を入金して$ETHを購入しましょう。入金時の手数料は無料です。 *こちらはOKCoinJapanの公式サイトより引用しております。 入出金口座の利用ガイド PC、スマホ、アプリからの3通りの方法が選択できますが、今回PC版からの入金方法について記載します。 *それ以外の方法については、OKCOIN JAPANのサイトよりご確認ください。 ①ホームページ右上にある「資産管理」より「日本円入金」をクリックします。 ②ページ中央にある「振込入金」をクリックし、ポップアップの「はい」をクリックします。 ※一度クリックすれば、入金が完了するまで③の振込先口座情報画面が表示され続けます。 ③振込先口座情報が表示されます。 内容を確認し、振込みをします。なお、振込先口座情報を登録したEメールアドレスに送信する場合は「メール送信」を押してください。 取引所で$ETHを購入する方法 *こちらはOKCoinJapanの公式サイトより引用しております。 1.ログイン後、画面上部の「現物取引」をクリックします。 2.画面左上①の「取引銘柄」より、取引したい銘柄(今回は$ETH)をクリックします。 3.画面中央②の「(暗号資産名)を購入」をクリックします。 4.③の注文タイプを選択のうえ、注文内容を入力してください。 5.④の「(暗号資産名)を購入」ボタンをクリック。取引パスワードを入力し、購入が完了します。 販売所/取引所のどちらで購入するべきか 販売所で購入する場合は、購入時の価格と売却時の価格でスプレッドが生じています。 もしトレード等を行わないで、今回のNFTのみを購入したいという方は販売所で写真のように5,000円と金額を指定して購入するのが簡便です。 販売所での購入方法はOKCOIN JAPANの、こちらをご確認ください。 取引所からウォレットアドレスへの$ETH出庫方法 まずは、自身のウォレットアドレスをコピーしましょう。 アカウントの下の英数字部分をクリックすると自動でアドレスがコピーされます。 また、設定ボタンから「アカウントの詳細」をクリックすると、QRコードが表示されるので、こちらを読み取れば送金画面で自動的にアドレスが入力されます。 次に、口座開設した取引所から、Metamaskへ購入した$ETHを出庫します。 *こちらはOKCoinJapanの公式サイトより引用しております。 取引所からの出庫手順 ホームページ右上にある「資産管理」より「暗号資産出庫」をクリックします。 出庫したい暗号資産の種類を選択します。 出庫先アドレスを入力します。( 先程コピーしたMetamaskのアドレスを貼り付けてください。) 受取人との関係を選択します。ご自身宛に出庫する場合は「本人」、それ以外の場合は「本人以外」を選択してください。 受取人所在国・地域を選択してください。※受取人との関係を「本人以外」と選択した場合のみ 受取人名を入力してください。 出庫先の取引所名を選択します。※該当する選択肢がない場合は「その他」を選択し、下に表示される枠に取引所名を入力してください。 当社指定取引禁止国および外国PEPsの内容を確認し、チェックを入れてください。 ラベルを入力します。(任意) 出庫数量を入力します。全て出庫する場合は「全て出庫」をタップしてください。※「入出金口座」と「取引口座」の利用可能な数量の範囲内で出庫可能です。 手数料を入力します。※手数料を高く設定するほど、より早く送付が完了します。 取引目的を選択します。 「実行」をクリックします。 出庫内容の確認ページが表示されますので、取引パスワードと認証コードを入力し、「確認」をクリックしてください。 出金申請が受付けられたら「確認」をクリックしてください。 NFTの購入 ( ミント ) 方法 ManifoldでA Love Movement のNFTを購入 ( ミント ) する方法 ウォレットに$ETHが反映された事を確認したら、NFTを購入してみましょう。 まず、こちらの販売ページにアクセスください。 アクセスしたら、下記の画面になります。 上記の画像赤枠内の「BUY NOW」をクリックしてください。 「BUY NOW」をクリックしたら、上記の確認ウィンドウが出てきます。 購入時の内訳は、下記になります。 NFT 代金 - こちらはNFTの金額になります。 Manifold Fee - こちらのプロジェクトでは、「Manifold」というNFTプラットフォームを利用しており、その利用手数料となります。 ガス代 - 後の画像で紹介しますが、当該取引を実施する際に利用するEthereum上で発生する手数料です。 上記の「BUY NOW 0.0062ETH」をクリックしたら、インストールしたMetamaskから上記のウィンドウが表示されます。「確認」というボタンを押して取引所「承認」しましょう。 そしたら、NFTの発行が完了します。 NFTの購入後 購入 ( ミント )したNFTの確認方法 - Openseaの使い方 購入したNFTは、複数のNFTプラットフォームで確認できます。 こちらで、「Opensea」というプラットフォームで確認する方法をご紹介します。 まずは、Openseaへアクセスください。 上記のトップ画面になったら、画面右上の「ウォレットを接続」を選択してクリック。 Metamaskから下記のウィンドウが表示されます。 「Sign In」をクリックしてください。 文字列が表示されたことを確認。 これで、OpenSeaとウォレットの接続は完了したことになります。 接続完了後、画面右上から「Profile」を選択すれば自身の保有しているNFTが一覧化して表示されます。 保有している「スマイルくん」のNFTをクリックしたら、上記の画面が表示されます。 その他、Openseaでは購入したNFTの売買などやメールアドレスの登録等が出来ます。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。 トランザクションの確認方法 - DeBankの使い方 ここでは、DeBankというウォレットを一括で管理できる便利ツールをご紹介します。 このツールを用いれば、購入したNFTの取引履歴を確認する方法できますので、実際に発生したガス代なども正確に確認していただくことが可能です。 まずは、DeBankへアクセスください。 上記画面の、「Conect MetaMask」をクリックしてください。 「Conect Wallet」をクリックして、MetaMaskが起動したら接続をしてください。 アドレスが表示されれば、ウォレット接続は完了です。 「History」をクリックすると直近30日間のトランザクション履歴の確認ができます。画像はBSCのチェーンを選択した履歴になっています。 直近のトランザクションでは、上記のように表示されており、合計利用$ETHやガス代に使った$ETHを確認いただけます。 その他、DeBankの詳しい使い方は、こちらの記事をご覧ください。 FAQ NFTとは何ですか? A. NFTとは、"Non Fungible Token ( ノンファンジブルトークン )の略で、直訳すると非代替性資産となります。現在、様々なシーンで活用され始めていますが、今回のNFTは「秋田県への自然災害への復興支援の証明」及び「その証明書で獲得したNFTは同じデザインではあるものの、唯一無二の偽造不可のデジタルアート」と認識ください。 $ETHとは何ですか? A. 暗号資産の一種です。主にEthereum 上で利用される基軸通貨となります。 仮想通貨やNFTって危険じゃないの? A. 一部、詐欺行為などに利用するツールとしてNFTが活用されていますが、詐欺行為を助長するものではりません。ブロックチェーンの技術を活用したツールの一つで、正しく理解していただければこれから様々なシーンで既存のテクノロジーだけでは解決しなかった事が解決する事が予測されています。 販売価格は$10ですが、何ETHを準備しておけば良いでしょうか。 A. 暗号資産は日々価格が変動するため、明確な数字は出せません。CoinGeckoやCoin Market Capで現在のレートを確認してください。ガス代も考慮して$30程度のETHを保有しておくことを推奨します。 Openseaでの二次市場販売は可能ですか? A. 可能です。詳しくは「NFTの二次流通出品方法 – Opensea」記事をご参照ください。 今回のNFTはチャリティとのことですが、NFT購入で税制優遇はありますか? A. 税制優遇はありません。税制優遇を希望される方は直接、社会福祉法人 秋田県共同募金会の「秋田県大雨災害義援金」へ寄付をお願いいたします。 購入したNFTの画像をTシャツにプリントは可能ですか? A. 私的使用等の著作権法上許容される態様であれば可能です。商用利用目的でプリントする場合は認められませんのでご注意ください。 リンク 寄付先情報 NFT購入ページ プロジェクト公式サイト (日本語版) プロジェクト公式サイト(英語版) 「秋田県災害復興支援NFT」NFT販売に関して | 利用規約 Encrypto A Love Movement 公式オンラインストア A Love Movement 公式インスタグラム

初心者向け
2023/09/08Discord(ディスコード)の通知の設定方法を徹底解説!
Discord(ディスコード)はもともとオンラインゲームのユーザー同士のコミュニケーションツールとしてリリースされましたが、現在では仮想通貨やNFTの領域でも多く使われています。 参加者が限定されたコミュニティ内での情報発信がメインなので、他ではアクセスできない情報を収集するには必須のツールです。 この記事では、Discordの通知機能の設定について詳しく解説しています。 フレッシュな情報をいち早くキャッチするには、Discordを開いていない状態でも情報の発信がわかる通知機能が重要です。 最後まで読んで、Discordの通知機能を使いこなしましょう。 仮想通貨の情報収集ではDiscord(ディスコード)の通知機能が有効 仮想通貨やNFTの領域では、正確な情報をなるべく早いタイミングでキャッチすることが重要です。 仮想通貨やNFTのプロジェクトの動向に関する最新情報 仮想通貨のエアドロップやNFTのフリーミントの情報 仮想通貨やNFTの価格のトレーディングに役立つシグナル Discordのコミュニティの中ではこういった情報が世界中の参加者から発信されるので、重要なメッセージを見逃すと大きなチャンスを失う可能性があります。 そのため、仮想通貨やNFTの領域でDiscordを使う場合には通知機能が重要です。通知機能により、Discordにつながっていないときでも発信を逃さずキャッチすることができます。 ただし、選別することなく通知を受け続けると重要な情報がノイズに埋もれてしまうため、通知には適切にフィルターをかけなければなりません。 Discordの通知機能では通知するメッセージを絞るための細かい設定ができるので、重要な情報のみ通知を受けられるよう適切に設定しましょう。 Discord(ディスコード)の通知機能の特徴 Discord(ディスコード)の通知機能の特徴 アプリ版・ブラウザ版どちらからでも通知設定ができる サーバー・カテゴリー・チャンネルごとに通知設定が可能 @mentionを利用して通知するユーザーを限定できる @mentionを利用して通知受け取るメッセージを絞り込める PC版を利用中にはスマホにはプッシュ通知がされない Discord(ディスコード)の通知機能は、非常に細かく多様な設定が可能ですが、その分少し複雑に見えます。 ここでは、Discordの通知機能を理解するためにその特徴を5点にまとめました。ひとつひとつ確認していきましょう。 アプリ版・ブラウザ版どちらからでも通知設定ができる DiscordはWindows PCやスマホで利用可能なアプリ版と、Webブラウザ経由で利用するブラウザ版があります。 アプリ版でもブラウザ版でもどちらでも通知設定が可能なので、Discordを使用している環境ごとに適切な通知を行うようコントロール可能です。 ただし、PCのアプリとブラウザ、さらにスマホでもDiscordを使用している場合には、それぞれに設定しなければならないので少し手間がかかります。 Discord(ディスコード)の使い方を解説 | 仮想通貨の便利ツールを活用する Discord(ディスコード)ブラウザ版の使い方を解説! サーバー・カテゴリー・チャンネルごとに通知設定が可能 Discordの通知設定の種類 ユーザー設定の中での通知設定 Discordの環境全体の通知を設定する サーバーの通知設定 参加している特定のサーバーの通知を設定する カテゴリーの通知設定 サーバー内の特定のカテゴリーの通知を設定する チャンネルの通知設定 サーバー内の特定のチャンネルの通知を設定する Discordの通知は、ユーザー、サーバー、サーバー内のカテゴリーやチャンネルごとに設定を行うことができます。 サーバーで通知をオンにしていていも、カテゴリーやチャンネルでオフにすれば、カテゴリーやチャンネルの設定が有効になります。 細かく設定すれば自分が注目しているチャンネルだけ通知をオンにすることが可能です。 @mentionを利用して通知するユーザーを限定できる @mentionsの種類 @+ユーザー名 指定されたユーザーにのみ通知を送る @+ロール名 指定されたロールにのみ通知を送る @everyone オフライン状態も含むすべてのユーザーに通知を送る @here 現在オフライン状態ではないすべてのユーザーに通知を送る Discordには、メッセージの前に「@+ユーザー名」や「@+ロール名」を付けることで、通知を送る相手を限定する機能があります。 この機能を@mentionsと呼びます。 メッセージの送信側から通知をする範囲を指定できるので、無用な通知を減らすことが可能な便利な機能です。 @mentionを利用して通知を受け取るメッセージを絞り込める Discordの通知設定では、通知を受ける側も@mentionsを使って通知を受けるメッセージを限定できます。 たとえば、自分がmentionされたメッセージのみ通知を受ける設定や、@everyoneや@hereの通知は受けないといった指定が可能です。 この機能をうまく使えばメッセージの受信側がより適切に通知を絞り込めるので、さらに有効に通知を利用することができます。 PC版を利用中にはスマホにはプッシュ通知がされない Discordは、PC版のアプリやブラウザ版を使用しているときにはスマホには通知を行いません。 通知の重複を防ぐことが目的で、PCとスマホを同時に使うことは多いので重要な機能です。 さらに、PC上で一定時間操作が無かった場合にスマホへの通知を再開する機能もあります。 利用者の実際の使い方に寄り添って、細かい点まで行き届いた通知制御の仕組みですね。 Discord(ディスコード)の通知の設定方法を徹底解説 Discord(ディスコード)の通知の設定方法 ユーザー設定の中での通知設定 サーバー・カテゴリー・チャンネルの通知設定 ここまでDiscord(ディスコード)の通知設定の特徴について説明しました。 きめ細かいコントロールが可能な点が、Discordの通知設定の強みでしたね。 ここからは、実際の通知設定の方法を操作画面のキャプチャ画像とともに説明します。 ユーザー設定の中での通知設定 まずはDiscordのユーザー設定から行う通知設定から解説していきましょう。 こちらでは、サーバー・カテゴリ・チャンネルによらない共通の通知設定が可能です。 PC向けのアプリやブラウザ版と、スマホ向けのアプリ版では設定内容が異なるので、個別に説明します。 PCアプリ版・ブラウザ版のユーザーの通知設定 PC向けのアプリやブラウザ版でユーザー設定を呼び出すには、Discordの画面下部のユーザー名の右にあるユーザー設定のアイコン(歯車の形)を選びましょう。 ユーザー設定の画面が開くので、画面左側のメニューで「通知」を選べば通知設定の画面に切り替わります。 ここでは、通知機能に関するさまざまな設定が可能です。主な設定項目を説明していきましょう。 デスクトップ通知を有効にする PCのデスクトップに表示される通知をオン・オフできます。 未読メッセージのバッジを有効にする 未読のメッセージがある場合に、Discordアプリのアイコンに赤色のバッジを表示するかどうかを、オン・オフできます。 タスクバーの点滅を有効化 通知が来たときに、タスクバーにあるアプリのアイコンを点滅させるかどうかを、コントロールします。 プッシュ通知非アクティブタイムアウト Discordでは、PC版のアプリ版やブラウザ版を使っているときは、スマホには通知をしません。ただし、一定時間以上PCの操作が無かった場合にはスマホへの通知を再開します。そのタイムアウト時間を設定できます。 テキスト読み上げによる通知 通知があった場合に内容を音声で読み上げるかどうかを設定できます。 画面を下にスクロールすると、通知音に関する設定項目が表示されます。 同じチャンネルのメッセージの通知を有効にする 開いているチャンネルで新たなメッセージがあったときに、通知音を鳴らすかどうかをオン・オフします。 通知音をすべて無効にする これをオンにすると、Discordの通知音がならなくなります。 その下には、イベントごとの通知音のオン・オフの設定が並んでいます。 スマホアプリ版のユーザーの通知設定 Discordのスマホアプリ版でユーザー設定を呼び出すには、Discordのアプリ画面右下部のユーザーのアイコンを選択してユーザー設定画面を呼び出します。 そこで「通知」を選べば、通知機能をコントロールする設定画面に変わります。 Discord内の通知を取得します。 Discordアプリを開いているときの通知をオン・オフします。 Discord外の通知を取得します。 アプリを開いていない状態でも通知を受け取るかどうかを設定します。iOSやAndroidのDiscordアプリに対する通知設定画面が開きます。 サーバー・カテゴリー・チャンネルの通知設定 次はサーバーごとや、サーバーに含まれるカテゴリー・チャンネルごとの通知設定の方法を解説します。 これらの設定方法は、PC向けのアプリ版・ブラウザ版とスマホ向けのアプリ版で共通です。 サーバーの通知設定 サーバーの通知設定を行うには、Discordの画面左にあるサーバーのアイコンを右クリックして、サーバーに関する設定メニューを呼び出します。 メニューの中で通知設定に関するものは、「サーバーを通知オン/オフ」「通知設定」の2つです。 そのサーバーで発信されたメッセージの通知の状態をオフからオンに変えるときには、「サーバーを通知オン」を選びましょう。すぐに通知が始まります。 メッセージの通知がオンの状態からオフにするには「サーバーを通知オフ」を選びます。 オンに戻るまでの時間設定がメニューで表示されるので、所望の時間を選びましょう。ずっとオフにしておきたい場合は「ミュート解除するまで」を選びます。 通知を受けるメッセージをコントロールしたい場合は、メニューから「通知設定」を選びましょう。 通知を受け取るメッセージの範囲を限定するメニューが開くので、ここで通知を受け取るメッセージを絞り込みます。 たとえば「@mentionsのみ」を選択すれば、自分宛ての@mentionsがついているメッセージのみ通知を受け取ることができます。 また「@everyoneと@hereの通知を行わない」を選べば、@mentionsがついているメッセージのうち@everyoneと@hereのものは通知されません。 カテゴリーの通知設定の方法 カテゴリーの通知設定を行うには、カテゴリー名を右クリックしてカテゴリーに関する設定メニューを呼び出します。 メニューの中で通知設定に関するものは、「カテゴリーを通知オン/オフ」「通知設定」の2つです。 そのカテゴリーのメッセージの通知をオフからオンに変えるときには、「カテゴリーを通知オン」を選びましょう。すぐに通知が始まります。 メッセージの通知がオンの状態からオフにするには「カテゴリーを通知オフ」を選びます。 サーバーの設定と同様にオンに戻るまでの時間設定がメニューで表示されるので、所望のものを選びましょう。 通知を受けるメッセージをコントロールしたい場合は、メニューから「通知設定」を選びましょう。 通知を受け取るメッセージの範囲を特定するメニューが開くので、ここで通知を受け取るメッセージを絞り込みます。ここで何も選ばなければ、サーバーに対する設定が踏襲されますよ。 チャンネルの通知設定の方法 チャンネルごとの通知設定も可能です。 チャンネル名を右クリックして、チャンネルに関する設定メニューを呼び出しましょう。 カテゴリーの通信設定と同様に、「チャンネルを通知オン/オフ」「通知設定」の2つのメニューが利用できます。 使い方もカテゴリーの通信設定と同様です。 こんなときどうする?Discord(ディスコード)で困ったときの通知設定 Discord(ディスコード)で困ったときの通知設定 Discordの通知が来ないときの対処法 Discordの通知を一時的にオフにするには? Discordの通知音を消したい! 通知音で相手を邪魔したくないときは? iPhoneでDiscordの通知をオン・オフに設定する方法は? Discord(ディスコード)を利用していると、思い通りに通知が来ない、欲しくないときに通知が来てしまう、といった状況がよく発生します。 ここでは、そんな困ったときの通知設定の方法について解説します。 Discordの通知が来ないときの対処法 Discordで通知が来ないときには、Discordの通知設定を確認しましょう。 通知は、「ユーザー設定」のなかで設定できるだけでなく、参加しているサーバーごと、さらにはサーバー内のカテゴリーやチャンネルごとに設定できます。 すべての通知が来ないのか、特定のサーバーやチャンネルの通知だけが来ないのかを見極めてチェックしましょう。 すべての通知が来ない場合は、WindowsやiOS・AndroidのOS自体の通知設定に問題があるかもしれないので、そちらの確認も必要です。 Discordの通知を一時的にオフにするには? ちょっと離席するなどでDiscordの通知を一時的にオフにしたいときは、自分のアカウントのステータスを「取り込み中」に変えましょう。 PC向けのアプリ版やブラウザ版では、画面左下のユーザー名の部分をクリックしてプロフィール画面を開いて、「オンライン」になっているステータスを「取り込み中」に変えます。 するとすべての通知がミュートされます。 スマホ用のアプリ版の場合は、アプリ画面右下のユーザーのアバター画像をタップすれば、ユーザー情報の設定画面が開くので、ここからステータスを「取り込み中」に変更しましょう。 離席が終了してDiscordでのコミュニケーションが再開可能になったら、ステータスを「オンライン」に戻せば通知が再開されます。 Discordの通知音を消したい! 通知は受けたいが通知音のみ消す方法は、PC向けのアプリやブラウザの場合と、スマホアプリ版では異なります。 PC向けのアプリ版やブラウザ版では、ユーザーの設定画面で「通知」を開き、「通知音をすべて無効にする」をONにしましょう。 通知は来ますが、通知音は鳴らない状態になります。 スマホアプリ版ではこれと同様の機能がないので、iOSやAndroidのマナーモードやサイレントモードで通知音を消すのが簡単です。 通知音で相手を邪魔したくないときは? 夜遅くメッセージするときや、相手が仕事中で忙しい場合には、不意の通知音で相手に迷惑をかけてしまうかもしれません。 そういう場合は、メッセージの頭に「@silent」を付けましょう。 メッセージの相手に通知はされますが通知音は鳴らないので、相手の状況がわからないときでも安心です。 iPhoneでDiscordの通知をオン・オフに設定する方法は? iPhoneでDiscordの通知をオンあるいはオフにする最も簡単な方法は、iOSの通知設定でDiscordの通知をコントロールすることです。 iPhoneで「設定」→「通知」→「Discord」を選択して、Discordに対する通知設定を呼び出しましょう。 その画面で「通知を許可」をオン・オフすれば、Discordの通知を変更できます。 まとめ この記事ではDiscordの通知機能について、その特徴と使い方を解説しました。 仮想通貨やNFTの領域に関するフレッシュな情報を見逃さないためには、通知の機能はとても重要です。 しかし、うまく使わないと頻繁に通知が来てしまい、結果的に重要な情報が埋もれてしまうことになります。 Discordの通知設定を利用して通知を受け取るメッセージを適切にフィルターし、重要な情報を効率的に収集しましょう。 なお、Discordのアプリ版やブラウザ版の使い方については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてご覧ください。 Discord(ディスコード)の使い方を解説 | 仮想通貨の便利ツールを活用する Discord(ディスコード)ブラウザ版の使い方を解説!
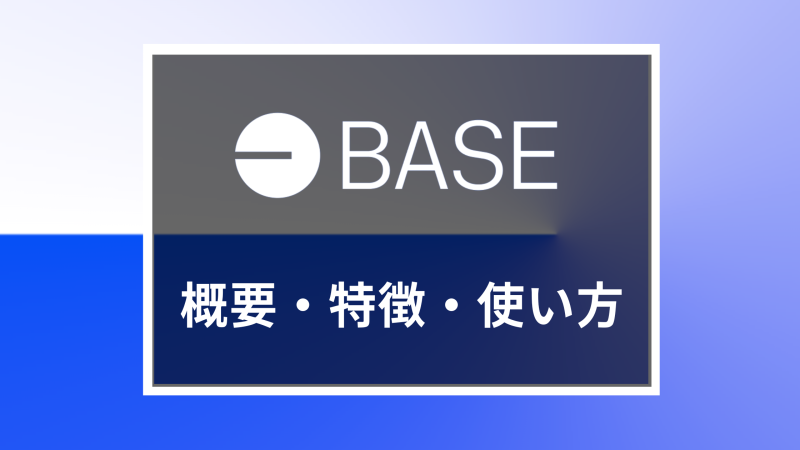
初心者向け
2023/09/01コインベースのL2「Base」の概要や特徴、使い方を徹底解説
本記事では、米大手仮想通貨取引所Coinbase(コインベース)が開発を主導するレイヤー2 「Base」について解説します。 記事執筆時はメインネットのローンチから間もない状態でありながら、既にTVL(Total Valued Locked)は3.5億ドル以上を記録しており、L2全体ではトップ5位にランクインしています。 この記事では、そんな急成長中のBaseについて以下のポイントから解説しています。 この記事のまとめ ・BaseはCoinbase発のロールアップ ・OP Stackで構築されている ・Coinbaseとの高いシナジーが期待できる ・UniswapやCompoundなどが展開 Baseとは?= Coinbaseのレイヤー2 Baseは、Coinbaseが主導するレイヤー2(以下:L2)のオプティミスティック・ロールアップ(ORU)です。 これから、BaseとL2やロールアップの概要について、以下の観点から解説していきます。 ・L2とORU ・Baseの概要 ・BaseのTVL Baseについて大枠を把握していきましょう。 L2とORU Baseは、ORUのL2です。 ORUとは、イーサリアムなどのL1(Layer 1)を土台に構築されているL2のロールアップを指します。 L2は、L1のセキュリティを一定引き継ぎながら、別の場所・方法でトランザクションを処理可能です。 ベースとなっているL1とは別の場所でトランザクションを処理することで、手数料の低下・処理性能の向上といった効果が期待できます。 L2の中でも、ロールアップはL1と強い関係で構築されているので、L1のセキュリティを高いレベルで引き継ぐことが可能です。 ロールアップの中にも、トランザクションの処理方法によって大きく分けて2種類があります。 不正証明で楽観的な処理を行うロールアップ(ORU)と、ゼロ知識証明を活用したロールアップ(ZKRU)が存在します。 Baseは前者のORUに該当し、類似のロールアップには、同じORUのOP Mainnet・Arbitrum oneなどが挙げられます。 Baseの概要 Baseは、Coinbaseが開発したORUです。Coinbaseは、アメリカの代表的な仮想通貨取引所(CEX)です。 CoinMarketCapによると、現物の取引量ではBinanceに次いで第2位の規模を持っています。 (引用元:CoinMarketCap) そんなCoinbaseによって、主導されているプロジェクトのため注目が集まっています。 一方、詳細は後述しますがOPスタックによって構築されており、概ね全体的な設計や仕様は他のORUと仕様は変わりません。 BaseのTVL (引用元:L2BEAT) Baseは、7月に開発者向けにメインネットを公開し、8月上旬に全ユーザーを対象にしたメインネットの公開を行いました。 まだ、本格的な稼働から1ヶ月も経っていない状況ですが、L2BEATによるとTVLは2億ドル以上で第5位に位置しています。 1週間平均の推移では40%以上の伸びとなっており、資金が集まりつつあります。 Arbitrum oneやOP Mainnetほどの規模ではないものの、TVLの伸び率だけで見ると勢いのあるL2プロジェクトです。 ちなみにBaseはCoinbaseによるサポートや勢いから注目されているものの、現時点では独自トークンを発行する予定は無いと明言されています。 Baseの3つの特徴 これから、Baseの特徴について以下の3点から解説していきます。 ・ロールアップに付随する恩恵 ・OP Stack関連のプロジェクト ・Coinbaseとのシナジー Baseの特別なポイントをチェックしていきましょう。 ロールアップに付随する恩恵 BaseはORUのため、ロールアップが持っている基本的な特徴を持っています。 具体的にはガス代の低下、処理性能の向上、L1チェーンによる高いセキュリティといったポイントです。 Baseの利用者は、イーサリアムの高いセキュリティを引き継ぎながら、利便性の高い環境でさまざまなアプリケーションを触ることが可能です。 また、Baseではオンチェーンの利用に伴う諸問題を解決するアカウント抽象化をサポートしています。 CT Analysis 『Account Abstractionの基本理解 提案やユースケースの紹介・解説』レポートの配信開始 OP Stack関連のプロジェクト Baseは、OP Stack関連のプロジェクトの1つです。 OP Stackとは、L2を立ち上げる際のさまざまな要素が揃ったツールで、OP Mainnetを開発するOptimismが主導して提供しています。 Optimismは現在、OP Stackを元に構築されたさまざまなL2チェーンが利便性の高い状態で集まるスーパーチェーンというムーブメントを志向しています。 OP Stackはそんなスーパーチェーンというムーブメントの土台となる存在です。 CoinbaseはOP Stack・スーパーチェーンの構想に賛同し、OP Mainnetに次ぐスーパーチェーンとしてローンチされました。 OP Stack・スーパーチェーン共にまだまだ発展途上のトピックではあるものの、OptimismやCoinbaseが推進しているため注目したいトピックの1つと言えます。 Coinbaseとのシナジーが期待できる Baseが注目されているポイントの1つがCoinbaseとのシナジーです。 前述した通りCoinbaseは世界トップクラスの仮想通貨取引所であり、多数の認証済のユーザーを抱えています。 Base上のプロジェクトとCoinbaseに関連する数百億ドル規模の資産や製品との統合が期待できます。 CoinbaseはBaseを自社のオンチェーン製品の拠点として利用する旨を明らかにしています。 ただし、あくまでCoinbaseが主導していくのは初期段階のみで、今後成熟していくに伴って分散化される可能性についても発信されています。 Baseへのブリッジ方法を解説 これから、Baseのブリッジの使い方を解説していきます。 BaseはL2のため、Ethereumにある資金をそのまま利用することはできません。 一度、EthereumからBaseに資金をブリッジによって転送することで、Base上でトークンの購入やDeFiの利用が可能です。 以下のポイントから、ブリッジの方法と注意点について解説していきます。 ・ブリッジの手順 ・ブリッジの注意点と出金 ブリッジの手順 Baseに興味がある方は、以下の手順でBaseにブリッジしましょう。 公式のブリッジサイトにアクセスしウォレットを接続 金額と資産を選択 承認を行う (DEPOSITをクリック後、ウォレットが起動します) 他のブリッジと利用方法は、大きく変わりません。 Baseのdocで推奨されているネットワーク設定は以下のとおりです。(ネットワークのやり方) Network Name:Base Mainnet Description:The public mainnet for Base. RPC Endpoint:https://mainnet.base.org Chain ID:8453 Currency Symbol:ETH Block Explorer:https://basescan.org 前述したのはイーサリアム To Baseの手順で数分程度で完了し反映されていきますが、タイミングなどによって変動します。 ブリッジの注意点と出金 一方、注意点としてBase からEthereumといった出金の際には、1週間程度かかります。 これは他のORU全体を通して見られる現象で、ORUにて不正やトラブルが発生しないためのクールタイムのようなものです。 この撤退時間をショートカットしたい場合は、Baseによって提供されている以外の方法(サードパーティの製品)でブリッジすることで、クールタイムが圧縮される可能性があります。 Base公式のものであれば、入金と同じような手順で、以下の箇所から可能です。 「1週間も待てない」という方は分散型クロスロールアップブリッジの「Orbiter Finance」なども活用してみましょう。 【トークン発行予定】分散型クロスロールアップブリッジ「Orbiter Finance」を解説 Baseで利用可能・展開するかもしれないプロジェクト これから、Baseへの転送が完了したら利用できる・利用できるかもしれないプロジェクトを、既に他のチェーンで一定の支持を受けているものを中心に、以下の3点から解説していきます。 ・Uniswap ・Compound ・GMX Baseで使えるものをチェックしていきましょう。 Uniswap Uniswapが、Baseで利用可能です。 8月上旬にUniswapは、Baseをサポートすることを発表しており、現時点で既に利用可能になっています。 Uniswapを利用することで、仮想通貨の交換が可能です。 Uniswapとは、AMMを実装している著名な分散型取引所(DEX)で、もっとも著名なプロジェクトの1つです。 Uniswapの利用方法などはコチラ。 Compound Compoundも、Baseに展開されています。 Compoundはレンディングを提供しているプロジェクトで、仮想通貨の貸し借りが可能です。 Compoundについても、Uniswap同様に著名なプロジェクトです。 Baseにおいて対応している通貨は限定的ですが、Compoundについても早期の段階でBaseへのサポートを発表しました。 Compoundの使い方についてはコチラ。 GMX GMXについては現時点で、Baseをサポートしていません。 そのため、確定的なものではありませんが、今後Baseに展開される可能性があります。 過去にGMXのコミュニティにおいて、Baseへの展開を提案する旨が提案されました。 そのため、GMXがBaseにおいて展開されることもあるかもしれません。 Baseについてまとめ この記事では、Baseについて解説しました。 Baseは、Coinbaseが主導していることなどから大きな注目を受けています。 TVLの伸びなども顕著なので、今後注目したいロールアップの1つであると言えるでしょう。 Base 公式リンク 公式HP:https://base.org/ Twitter:https://twitter.com/BuildOnBase Discord:https://discord.com/invite/buildonbase Github:https://github.com/base-org 免責事項 ・本記事は情報提供のために作成されたものであり、暗号資産や証券その他の金融商品の売買や引受けを勧誘する目的で使用されたり、あるいはそうした取引の勧誘とみなされたり、証券その他の金融商品に関する助言や推奨を構成したりすべきものではありません。 ・本記事に掲載された情報や意見は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性、完全性、目的適合性、最新性、真実性等を保証するものではありません。 ・本記事上に掲載又は記載された一切の情報に起因し又は関連して生じた損害又は損失について、当社、筆者、その他の全ての関係者は一切の責任を負いません。暗号資産にはハッキングやその他リスクが伴いますので、ご自身で十分な調査を行った上でのご利用を推奨します。(その他の免責事項はこちら)

初心者向け
2023/08/27LINEとPaypayだけでビットコインが購入出来る!? 1円から始められる暗号資産投資
財布の持ち歩きが不要な電子決済サービスは非常に便利です。 その中でも、PayPayは多くの人々に広く利用されています。PayPayは日常の決済だけでなく、実はビットコインの購入にも使用できることをご存知でしょうか? この記事では、PayPayを利用してビットコインを購入する方法を詳しく解説します。 LINE BITMAXとPaypayが提携 [caption id="attachment_96835" align="aligncenter" width="580"] 画像引用元:https://paypay.ne.jp/merchant-share/logo/[/caption] まず、なぜPayPayで暗号資産を購入できるようになったのかを解説します。 2023年7月、LINE BITMAXとPayPayは業務提携を発表しました。 LINE BITMAXは、LINE上から手軽で簡単に暗号資産取引ができるサービスです。LINEに登録し、本人確認を済ませていれば、わずか1円からでも暗号資産を購入できます。 これまでは、LINE BITMAXはLINE Payを通じた入出金に対応してきました。しかし、今回のPayPayとの業務提携によって、PayPayを使用した入出金も可能になりました。 LINE BITMAXの特徴 [caption id="attachment_96836" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:https://creative.line.me/ja/guide/in-app-brand/170[/caption] 今回の発表の内容は、PayPayを使用してLINE BITMAXの残高チャージが可能となることであり、取引自体はLINE BITMAX上で行われます。以下にLINE BITMAXの特徴をいくつか挙げてみます。 利用可能時間:通常365日24時間利用可能 買付時手数料:無料 出金時手数料:無料 買付および出金の下限:1円 買付および出金の上限:24時間で50万円、30日で200万円 上記が、LINE BITMAXの特徴です。手数料は無料であり、また普段使っているLINEアプリ上で手軽に売買を行えるのも大きなメリットです。さらに、1円から購入が可能であることも注目すべき点です。 Paypayを使えば面倒な入金手続きが不要 通常、暗号資産の取引を行おうとする際には、口座に入金する必要があります。この点において、LINE BITMAXでも同じように、まず口座に入金し、その後LINE BITMAX上で暗号資産を売買する必要があると思われるかもしれません。 しかし、PayPayを利用すれば、PayPayマネー残高から直接暗号資産の取引が可能です。 つまり、入金手続きという手順を省略し、一般的な店舗で会計するのと同じ感覚で、暗号資産を購入できます。 以下では、具体的な購入方法について解説していきます。 Paypayを使ってLINE BITMAXで暗号資産を売買する手順 以下では、LINE BITMAX内でPayPay支払い機能を利用した暗号資産の購入手順を詳しく解説します。この例ではビットコインを対象にして、実際の購入手続きを行ってみます。 LINE BITMAX上で本人確認 LINE BITMAXで取引を行うには、まずは本人確認を完了する必要があります。以下にその手順を詳しく説明します。 なお、すでに本人確認が済んでいる方は、直接購入手順の解説に進んでいただけます。 LINEを開いて、右下の「ウォレット」をタップして下さい。 「LINE BITMAX」をタップして下さい。 「口座開設に進む」をタップして、お客さま情報を入力して下さい。 次に身分証明書を使用した確認画面へと移ります。 運転免許証やマイナンバーカードなどを使用して、本人確認手続きを行います。LINE BITMAXはこれらの情報を用いて本人確認を行いますが、その手続きには時間がかかることがあります。しかし、たとえ週末に申請を行っても、翌日には本人確認が完了することが一般的です。 本人確認が完了すると、LINE BITMAXから本人確認完了の通知が届き、それ以降は暗号資産の売買が可能となります。 ビットコインを購入する まずは、ビットコインの購入手順について解説します。 初期画面から購入したい銘柄をタップします。左下の「買う」をタップしてください。 「Paypayマネーで購入」をタップして下さい。 初めての場合、Paypay連携サービス利用規約の確認画面が表示されますので、それぞれの規約や同意文書を読んだ上で、チェックを入れて下さい。 下部の「確認しました」をタップして、連携して下さい。 LINE BITMAXでは、1円からビットコインを購入することが可能です。実際に1円分のビットコインを購入してみます。手順は簡単です。 購入画面が以下のように表示されます。 銘柄画面を開いて「買う」をタップすると、このよう画面が表示されますので、購入したい金額を入力します。 「買う」をタップすれば購入が完了します。 最初に表示された1BTCの価格は「4244537円」ですが、実際の購入価格は「4302540円」となっています。およそ1.4%分の開きがありますが、これはLINE BITMAXにおけるスプレッドが考慮された金額となっているためです。 以上が、ビットコイン購入の手順となります。 ビットコインを売却する 次は、ビットコイン売却の手順を解説します。難しいところはなく、購入の手順とほぼ変わりません。 銘柄を選択し「売る」をタップします。 売却する数量を選んで下さい。 数量を選ぶ際、右枠の「選択」をタップすると%表示が25%ごとにされています。これは自身が所持している暗号資産のうち何%を売却するかを指定するためのものです。今回は全て売却するので、100%としています。 ※表示価格と売却価格に差があるのは、購入の際と同じくLINE MITMAXのスプレッドがあるからです。 ※先ほど購入した所持数量と異なっていますが、これは1円で購入した分のBTCが最低取引数量以下だったため、1円分買い足したためです。 日本円を出金する ビットコインを売買すると、口座には日本円が残ります。ここからは、LINE BITMAXからの日本円の出金手順について解説します。こちらも非常に簡単なものとなっています。 「入出金/入出庫」をタップします。 「出金」をタップして下さい 三つの出金方法が表示されますので、お好きな出金先を選んで下さい。 出金をする際には手数料がかかりますので、ご注意下さい。今回はPaypayへの出金を選んでいるため、110円の手数料が表示されています。LINE Payへの場合は、110円。銀行口座の場合は、400円の手数料がかかります。 他取引所と比べ、価格に開きはない。 取引所選びにおいて、容易に購入が出来るかどうかということと同じくらい、適切な価格で購入出来るかどうかは非常に重要です。 ここで、先ほどのLINE BITMAXでの取引とほぼ同時刻の、coincheckとbitFlyerのビットコインの価格を見てみましょう。 このように大手取引所とほぼ変わらない価格であることが分かります。 LINE BITMAXは、スプレッドはありますが手数料はなく、購入・売却・出金が簡単で分かりやすく、LINEアプリ上で全てが完結します。 加えて、Paypayでの支払いも可能となったため非常に手軽であり、暗号資産初心者にとっておすすめの売買手段となっています。 まとめ これまで暗号資産に興味を持ちつつも、取引所の選択や口座開設の手続きに戸惑いを感じていた方も多いことでしょう。 この記事では、PayPayを利用した暗号資産の購入・売却手法を紹介しました。LINEやPayPayは幅広い人々に利用されているアプリケーションです。ビットコインなどの暗号資産の取引は難しそうに見えるかもしれませんが、LINEの本人確認を通じて、どなたでも手軽に暗号資産に触れることが可能です。 また、PayPayを使用することで、LINE BITMAXへの入金手続きや銀行口座の登録の手間が省け、購入から出金まで全てをPayPayを介してスムーズに行えます。特別な手数料も発生せず、まるでコンビニのレジで商品を購入するような感覚で暗号資産を取引できることもポイントです。 もし、この記事で興味を持った方がいらっしゃれば、ぜひ実際にPayPayを使って暗号資産の購入を試してみてください!

初心者向け
2023/08/12Discord(ディスコード)のパスワードを忘れたときの対処法を解説
Discordは、仮想通貨やNFTの領域で活発に使われているコミュニケーションツールです。 参加者が限定されたコミュニティ内での情報発信がメインなので、他ではアクセスできない情報をいち早くキャッチするのに適しています。 Discordを利用するには、ユーザーIDとパスワードによる認証が必要です。そのため、パスワードを忘れてしまいDiscordが使えなくなるリスクが常に伴います。 この記事ではDiscordのパスワードを忘れた場合の対処法について解説しています。 この記事を最後まで読めば、Discordのパスワード管理に必要以上に悩まされることがなくなりますよ。 Discord(ディスコード)のパスワードを忘れたときの対処のポイント Discord(ディスコード)のパスワードを忘れたときの対処のポイント 仮想通貨やNFTのコミュニティ数は膨大!アカウントの作り直しは避ける Discordにリクエストすればパスワードリセットできる ChromeやMicrosoft Edgeに保存しているパスワードをチェックする iPhoneなら設定アプリからDiscordのパスワードを見ることが可能 最初に、Discord(ディスコード)のパスワードを忘れたときの対処のポイントを解説します。 パスワードを忘れてログインできなくなるとついつい焦ってしまいがちですが、適切な知識を持っていればいざというときに落ち着いて対応できますよ。 仮想通貨やNFTのコミュニティ数は膨大!アカウントの作り直しは避ける Discordのアカウントの作り直しをおすすめしない理由 多くのサーバーに参加するため、すべてのサーバーに参加しなおすのは大きな手間 Discord内でのこれまでのコミュニケーションとの連続性が失われる 同じメールアドレスによるアカウント登録はできない パスワードを忘れてDiscordにログインできなくなった場合、多くの人が行うのはアカウントの作り直しです。 一見簡単な対処法に思えますが、問題点が多いためアカウントの作り直しはおすすめしません。 最大の問題は、新アカウントで情報収集ができる環境を再度作り上げるのに大きな手間がかかることです。 仮想通貨やNFTの領域でのDiscordコミュニティの数は膨大なため、情報を収集するために多くのサーバーに参加するのが通常です。 アカウントを作り直した後に以前参加していたすべてのサーバーから招待リンクを再度取得し、もとどおりに参加しなおすのは大変です。 また、アカウントが新しくなることでサーバー内でのそれまでのコミュニケーションが一旦リセットされる点も問題です。 サーバー内での活動にコミットして、コアなメンバーと密な関係性を構築するほど質の良い情報が入手できますが、アカウントが変わってしまうとそれまでの関係性が消えてしまいます。 Discordにリクエストすればパスワードリセットできる パスワードを忘れた場合に備えて、Discordにはパスワードを新しいものにリセットする機能が用意されています。 アカウントに紐づいて登録されているメールアドレス宛に、パスワードリセット用のリンクを送る方法です。 簡便ですが安全に新しいパスワードに変えることができ、アカウントはこれまで使用していたものを継続できるので、おすすめの方法です。 ChromeやMicrosoft Edgeに保存しているパスワードをチェックする Google ChromeやMicrosoft Edge経由でDiscordを使ったことがある人は、忘れてしまったパスワードが保存されているかもしれません。 Google ChromeやMicrosoft Edgeには、ログインしたサイトのIDやパスワードを記憶して、再度アクセスしたときに自動的にログインする機能があります。 過去にDiscordにログインした際にブラウザにパスワードを保存していれば、Google ChromeやMicrosoft Edgeが記憶しているパスワードを確認できます。 パスワードを新しくする必要がなく、これまでのパスワードを使い続けられるので、便利な方法ですね。 Discord(ディスコード)ブラウザ版の使い方を解説! iPhoneなら設定アプリからDiscordのパスワードを見ることが可能 iPhoneでDiscordを利用している人も、忘れてしまったパスワードが保存されている可能性があります。 iPhoneはアプリのログイン時にIDやパスワードを記憶しておく機能があります。 iPhoneが保存しているパスワードを確認すれば、忘れていたパスワードを見つけることが可能です。 Discord(ディスコード)の使い方を解説 | 仮想通貨の便利ツールを活用する Discord(ディスコード)のパスワードリセットの手順 Discord(ディスコード)のパスワードリセットの手順 PC版Discordでパスワードをリセットする スマホ版Discordでパスワードをリセットする Discord(ディスコード)のパスワードを忘れてしまったときの対処法で最もおすすめできるのは、パスワードのリセットです。 ここでは、Discordのパスワードリセットの手順を解説します。 リセットせずに保存されたパスワードを確認するなら「環境に保存されたDiscord(ディスコード)のパスワードを確認する手順」をチェックしてください。 PC版Discordでパスワードをリセットする PCのアプリやブラウザでDiscordのパスワードをリセットする場合は、まずログイン画面を呼び出しましょう。 「メールアドレスまたは電話番号」の部分にDiscordに登録しているメールアドレスを入力して「パスワードをお忘れですか?」を選択すると、入力したメールアドレス向けにパスワードリセットのメールが届きます。 届いたメールを開いて、「Reset Password」あるいは「パスワードをリセット」のボタンをクリックしましょう。 「パスワードを変更」の画面が表示されるので、ここに新しいパスワードを入力して「パスワードを変更」のボタンを選べば、パスワードのリセットは完了です。 新しいパスワードでログインすれば、Discordをこれまでどおり使うことができます。 スマホ版Discordでパスワードをリセットする Discordのスマホアプリでパスワードをリセットする場合も、PC版同様まずログイン画面を呼び出しましょう。 「メールアドレスまたは電話番号」の部分にDiscordに登録しているメールアドレスを入力して「パスワードをお忘れですか?」を選択すると、入力したメールアドレス宛にパスワードリセットのメールが届きます。 届いたメールを開いて、「Reset Password」あるいは「パスワードをリセット」のボタンをクリックすれば、PC版同様に「パスワードを変更」する画面が表示されます。 ここで新しいパスワードを入力して「パスワードを変更」のボタンを選べば、パスワードのリセットは完了です。 環境に保存されたDiscord(ディスコード)のパスワードを確認する手順 環境に保存されたDiscord(ディスコード)のパスワードを確認する手順 Google Chromeが記憶しているパスワードの確認手順 Microsoft Edgeに保存されているパスワードの確認手順 iPhoneの設定アプリからのパスワード確認手順 Discord(ディスコード)のパスワードをリセットしなくても、ブラウザやOSが記憶しているパスワードを見ればまたログインすることができます。 こちらではブラウザやOSが記憶しているパスワードを確認する手順を解説しましょう。 Google Chromeが記憶しているパスワードの確認手順 ChromeブラウザでDiscordにログインし、パスワードを保存したことがあれば、GoogleのパスワードマネージャーでDiscordのパスワードを確認することができます。 パスワードマネージャーを呼び出すには、Google Chromeを開いてGoogleアカウントのパスワードマネージャーのページにアクセスするのが最も簡単です。 パスワードマネージャーのページを開いたら、discord.comを探して選択しましょう。DiscordのユーザーIDとパスワードが表示されます。 Googleアカウントの本人確認を求められることもあるので、その場合はGoogleアカウントのパスワードを入力しましょう。 Microsoft Edgeに保存されているパスワードの確認手順 Microsoft EdgeでDiscordにログインし、パスワードを保存したことがあれば、Microsoft Edgeが記憶しているパスワードを確認することができます。 Microsoft Edgeのパスワード管理の画面を呼び出すには、Microsoft Edgeから「edge://settings/passwords」を開きましょう。 Microsoft Edgeが記憶している各サイトのIDとパスワードのリストが表示されます。 ただしパスワードは伏せ字になっているので、discord.comの欄を探して目のマークをクリックしましょう。 Windowsのパスワード入力による認証が行われ成功すると伏せ字が解除されて、パスワードが確認できます。 iPhoneの設定アプリからのパスワード確認手順 iPhoneでDiscordを利用していたなら、iPhoneが記憶しているパスワードを確認することができます。 iPhoneで「設定」→「パスワードとアカウント」→「WebサイトとAppのパスワード」を選択して、パスワードを記憶しているWebサイトやアプリの一覧を表示し、「discord.com」を選びましょう。 DiscordのユーザーIDとパスワードが表示されます。 まとめ この記事では、Discord(ディスコード)のパスワードを忘れた場合の対処法について解説しました。 操作画面を交えて手順を細かく解説したので、パスワードを忘れてしまってもあわてることはありませんね。 Discordには、仮想通貨やNFTの領域で活動しているサーバーが多く存在します。うまく使いこなしてフレッシュな情報を効率的に収集しましょう。 なお、Discordの使い方については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてご覧ください。 Discord(ディスコード)の使い方を解説 | 仮想通貨の便利ツールを活用する Discord(ディスコード)ブラウザ版の使い方を解説!

初心者向け
2023/06/18NFTアグリゲーター「OpenSea Pro」の使い方、出品・購入を解説【完全ガイド】
NFTのマーケットプレイスは大小さまざまありますが、OpenSea Proはこれらを集約したNFTマーケットプレイスアグリゲーターです。 大手NFTマーケットプレイスであるOpenSeaが、定評のあったプロNFTトレーダー向けアグリゲーターのGemを買収してリブランドしたもので、2023年4月から稼働しています。 この記事では、OpenSea Proの特徴と使い方について説明しました。 操作画面のイメージを交えて解説したので、最後まで読めばOpenSea Proを使ってNFTの取引ができるようになりますよ。 OpenSea Proの7つの特徴を解説 最初にOpenSea Proの特徴について説明します。 単なるNFTマーケットプレイスではなく、マーケットプレイスアグリゲーターであるがゆえの有利さをしっかり確認しておきましょう。 OpenSea Proの7つの特徴 1. 170を超えるNFTマーケットプレイスを集約したアグリゲーター 2. NFTマーケットプレイスの情報をリアルタイムで反映 3. 先行のNFTアグリゲーターBlurと並んでトップクラスの規模 4. まとめ買いなどの高度な注文が可能 5. NFTのマーケット分析機能が豊富 6. ライブミント機能でNFTがリアルタイムでミントできる 7. OpenSeaでの手数料は期間限定で0% 170を超えるNFTマーケットプレイスを集約したアグリゲーター OpenSea ProはNFTマーケットプレイスではなく、たくさんのマーケットプレイスを集約したアグリゲーターです。 集約しているマーケットプレイスは170以上の膨大な数で、それらに出品されているNFTを最も有利な価格で取引可能です。 多数のマーケットプレイスを探し回って比較検討する必要がないので、労力が大幅に削減できますよ。 NFTマーケットプレイスの情報をリアルタイムで反映 リアルタイム性はOpenSea Proの重要な特徴です。 OpenSea Proは集約しているマーケットプレイス上でのNFTの動きやユーザーのアクティビティを、OpenSea Proの画面にリアルタイムで反映するので、OpenSea Proだけにアクセスすれば、マーケットプレイス群全体の状態をリアルタイムに把握することができます。 また、OpenSea Proでのユーザーのアクションも個々のマーケットプレイスに即座に展開されるので、多数のマーケットプレイス群を同時に利用するのと同様の効果が得られます。 先行のNFTアグリゲーターBlurと並んでトップクラスの規模 これまでNFTアグリゲーターのリーディングプレーヤーはBlurでしたが、2023年4月4日の立ち上がり以来OpenSea Proは多くのアクティブユーザーを獲得し、一気に互角に近いレベルにまで成長しました。 アクティブアドレスのシェアと取引回数はすでにBlurを超えており、取引総額もBlurにせまりつつあります(※)。 メジャーな2大NFTマーケットプレイスアグリゲーターとして、OpenSea ProとBlurで市場を2分しているのが現在の状態です。 ※Dune Analyticsのデータによる まとめ買いなどの高度な注文が可能 OpenSea Proでは複数のNFTをまとめて購入する機能が用意されています。購入するNFTを複数選択してカートにいれて、それらをまとめて購入することが可能です。 またスイープ機能を利用すれば、同一コレクションのNFTのうち指定された個数のものを購入してくれます。 まとめ買い機能のメリットは単に便利というだけではありません。単品で購入する場合と比較してガス代が少なくて済むため、NFT一点あたりの購入コストが下がりますよ。 NFTのコレクションとは? 複数のNFTをとりまとめたものをコレクションと呼びます。同一シリーズのNFTをまとめるフォルダのようなものでコレクション名が付与されており、NFT群の管理単位として利用されています。 NFTのマーケット分析機能が豊富 OpenSea Proの長所のひとつにNFTのマーケット分析の機能が豊富な点があります。 NFTは日々増え続けており様々なマーケットプレイスで取引されるため、それらの情報を集約して分析することは困難でした。 OpenSea Proは、NFTコレクションに含まれるNFTの取引量や売買価格のトレンドを、様々なマーケットプレイスから情報を取り出して集約して見せてくれます。 さらにはNFTを保有しているウォレットの情報も詳細に確認できるため、分析の時間が大幅に効率化できます。 ライブミント機能でNFTがリアルタイムでミントできる 多くのコレクションが、購入成立時にNFTのミントを行うLazy Minting方式でNFTを配布しています。 OpenSea Proでは、Lazy Mintingを行っているコレクションを様々なマーケットプレイスから集約し、購入とミントを同時に行うことができるライブミント機能を提供しています。 ライブミント機能のダッシュボードからその時点でミント可能なコレクションを一覧してミントできるので、とても便利です。 Lazy Mintingとは? NFTをミントしてから販売するのではなく、NFTの取引が成立したときにミントする方式です。ミントのためのガス代は取引が成立した時点で発生するため、NFTがまだ売れていない状態でガス代を支払う必要がありません。 OpenSeaでの手数料は期間限定で0% OpenSea ProからNFTを取引する場合の手数料は、対象のNFTが出品されているマーケットプレイスによります。 ただし、OpenSea ProからOpenSeaにNFTを出品した場合は、取引手数料が0%です。通常はOpenSeaの取引手数料は2.5%なので、OpenSea Proから出品したほうがずっとお得です。 このメリットについてOpenSeaは「期間限定」と明言しているで、今後変更される可能性がある点には留意しましょう。 OpenSea Proの基本的な使い方を紹介 OpenSea Proの特徴が理解できたので、次は基本的な機能の使い方を説明します。 操作画面の画像を交えて解説したので、順を追って確認していきましょう。 この記事ではウォレットとしてMetaMaskを使用した場合の画面イメージを使用していますが、他のウォレットでもほぼ同様です。 OpenSea Proの基本的な使い方 使い始めるまでの事前準備 OpenSea Proの画面構成 NFTを購入する 自分が保有するNFTを確認する NFTを出品する NFTをミントする 使い始めるまでの事前準備 OpenSea Proを使うには、OpenSea Proと接続するウォレットと取引の原資となるETHが必要です。 これらの準備は、OpenSea Proを使い始める前にすませておきましょう。 仮想通貨のウォレットの準備 OpenSea Proに接続可能なウォレット MetaMask WalletConnect Coinbase Wallet Rainbow Phantom Rabby Ledger Live OpenSea Proを使用するには、OpenSea Proに接続できるウォレットを準備する必要があります。 OpenSea Proに接続可能なウォレットは複数ありますが、使用できるウォレットをインストールしていない場合は事前にインストールしておきましょう。 仮想通貨ETHの準備 OpenSea Proで扱えるのはイーサリアムのブロックチェーン上のNFTです。 そのため、OpenSea ProでNFTの取引を行う場合にはETHが必要になります。 ウォレットにETHが無い場合は、仮想通貨取引所で購入してウォレットに送金しておきましょう。 OpenSea Proとウォレットを接続する ウォレットとETHの準備ができたら、OpenSea Proのサイトにアクセスしましょう。 画面の右上部の「Connect Wallet」をクリックし、開いたダイアログで自分が使用するウォレットを選択します。 ウォレット側でのパスワード入力などの認証が成功すれば、OpenSea Proとウォレットの接続は完了し、OpenSea ProでNFTの取引が可能になります。 OpenSea Proの画面構成 OpenSea Proの画面構成 構成要素 説明 ナビゲーションバー 詳細情報表示エリアに表示する内容を選択するメニュー 検索ボックス 詳細情報表示エリアに表示される情報を検索によって絞り込むボックス ウォレット情報表示ボタン 接続中のウォレットに関する情報を表示するボタン カートボタン カートに入っているNFTのリストを表示するボタン 詳細情報表示エリア ナビゲーションバーでのメニュー選択に応じて、情報を一覧表示する部分 OpenSea Proの基本的な画面構成について確認しておきましょう。 OpenSea Proの画面は、左にナビゲーションバー、中央に詳細情報の表示エリア、上部に検索ボックスや各種ボタンという配置です。 ナビゲーションバーのメニュー選択によって、それに応じた内容が詳細情報表示エリアに表示されます。 NFTを購入する 次は、出品されているNFTを購入する手順について解説します。 数多くのNFTの中からターゲットとなるNFTを見つけ出して購入する方法を、順を追って確認していきましょう。 出品されているコレクションやNFTを確認する OpenSea Proから購入できるNFTを探す場合は、ナビゲーションバーで「Market」を選びましょう。すると、現在出品されているNFTを含むコレクションが一覧表示されます。 コレクションのリストが表示された画面で個々のコレクションを選択すると、そのコレクションに含まれるNFTがリスト表示されます。 そして個々のNFTを選択すると、そのNFTの詳細情報が表示されます。 クリエーターや現在のオーナー、出品価格や過去の売買履歴など、このNFTに関するすべての情報をこの画面から確認することが可能です。 NFTを購入する 購入するNFTが決まったら、個別のNFTの情報画面で「Buy now」を選びましょう。 するとウォレットからの支払い画面が立ち上がります。ここで「確認」を選択すれば、NFTが購入されます。 支払い画面には必要なガス代の見積もり額や、NFTの購入額を合わせた支払総額が表示されているので、しっかりチェックしましょう。ガス代は刻々と変わるので、安くなるタイミングを待ってNFTを購入するのも賢い方法です。 複数のNFTをまとめて購入するには 複数のNFTをまとめ買いするときには、カートを使います。 購入したいNFTにチェックをすれば、選択したNFTがカートに入ります。カートの画面で「Buy Now」を選べば、カートに入っているすべてのNFTをまとめて購入します。 まとめ買いをするならスイープ機能を使うのも便利です。 コレクションに含まれるNFTのリストが表示されている状態で、画面最下部にNFTの購入個数を入力すれば、指定された数のNFTが選択されてカートに入ります。 NFTのまとめ買いはガス代がお得 複数のNFTを購入する場合は、個々のNFTを個別に購入するよりも、カートに入れてまとめて買いましょう。個別購入よりもガス代が節約できるのでお得です。 自分が保有するNFTを確認する 自分が保有するNFTを確認するには、画面左部のナビゲーションバーで「Profile」を選択しましょう。すると自分が保有しているNFTがリスト表示されます。 またこの画面では、タブを選択することで自分が保有しているNFTに関するさまざまな情報を表示することが可能です。 保有しているNFTの状況や出品中のNFTのステータスなど、接続中のウォレットに紐づいているNFTの詳細をすべて確認できますよ。 NFTを出品する 保有しているNFTを出品する時には、ナビゲーションバーで「Profile」を選択して自分が保有しているNFTのリストを開き、リストするNFTを選びましょう。 そして「List Items」を選択すると、出品内容の設定画面が開きます。 ここで出品価格や出品期間を入力し、出品するマーケットプレイスの選択を行って「Start Listing」を選択すると、出品処理が実行されます。 基本的には出品にはガス代はかかりません。しかし、コレクションごとに初回の出品時にのみコレクションを承認するためにガス代がかかります。 コレクションの承認 自分が保有するNFTを出品するためには、そのNFTを含むコレクションの販売を承認する必要があり、それにガス代が必要になります。一度承認すれば同一コレクションのNFTの出品時に承認は不要です。 NFTをミントする Lazy Mintが可能なコレクションのNFTは、OpenSea Proからミントすることが可能です。 ミントするには、ナビゲーションバーから「Mints」を選びます。するとミント可能なコレクションのリストが表示されるので、リストの右端の「Mint」のボタンをクリックしましょう。 「Mint Now」のダイアログが表示されるので、そこでミントするNFTの数を入力し、Term & Conditionsに同意するチェックを入れて、ダイアログの下部にある「Mint Now」のボタンを選択しましょう。 Mintに必要な金額の確認画面がウォレットからポップアップするので、ガス代の見積もり額を含めた支払総額をしっかりチェックし、「確認」を選べばミントが始まります。 ミントが終わると、自分が保有するNFTのリストにミントされたNFTが追加されます。 OpenSea Proを使うときの5つの注意点 ここまでOpenSea Proの使い方について説明してきました。OpenSea ProでのNFTの取り扱いについて、だいぶイメージできてきましたよね。 ここからはOpenSea Proを使う上で注意すべき点について紹介します。 OpenSea Proを使うときの5つの注意点 1. 不正に入手されたNFTを避ける 2. フィッシング詐欺に気を付ける 3. ウォレットのシードフレーズをなくさない・教えない 4. 取引時は必ずガス代を確認する 5. イーサリアムの価格に敏感になる 不正に入手されたNFTを避ける NFTマーケットプレイスでは、盗品や改造品などの不正に入手したNFTが販売されていることがあります。そういったNFTにかかわるとトラブルに巻き込まれる可能性が高いので、購入することは避けましょう。 OpenSea ProのUI上では、怪しいNFTに対しては警告のマークがついており、注意を喚起しています。 フィッシング詐欺に気を付ける NFTマーケットプレイス関連のフィッシング詐欺が多く発生しています。 メジャーなマーケットプレイスを偽装したメールをユーザーに送り、不正なスマートコントラクトに署名するよう誘導してNFTを盗むといった事例が報告されています。 届いたメールに反応する前に、心当たりのあるメールかどうか、クリックするURLに怪しい所はないかなどの基本的な確認を怠らないようにしましょう。 ウォレットのシードフレーズをなくさない・教えない ウォレットのインストール時に12個の単語からなるシードフレーズが割り当てられます。 シードフレーズはウォレットをリカバリーする際に使用するもので、ウォレットを紛失したり削除したりしても、シードフレーズがあれば以前の状態に復元できます。 シードフレーズの保管には細心の注意を払う必要があります。 なくしてしまうとウォレットのリカバリーは不可能です。また、誰かに知られてしまうとウォレットを自由に使われるリスクを抱えることになります。 取引時は必ずガス代を確認する NFTを取引するときには、NFTの売買価格以外にネットワークに支払うガス代がかかります。 常に一定の金額ではなくネットワークの込み具合によって変動するので、ガス代が高い時期に取引を行うと、NFTの買値に加えて想定以上のコストがかかることになります。 NFTの取引時には、取引を確定する前にガス代がいくらかかるのかを必ず確認しましょう。 またネットワークの状況を確認し、ガス代が比較的安い時を狙って取引を行うことも重要です。 >>イーサリアムのガス代の状況を確認するにはこちら イーサリアムの価格に敏感になる OpenSea ProでNFTを売買する際に使用する暗号資産はイーサリアムです。OpenSea Pro上では、NFTの取引価格やガス代はすべてETHの単位で表示されています。 しかし、法定通貨に対するイーサリアムの価値は日々大きく変動するので、ETH単位での値段が変わっていないNFTでも、法定通貨に換算した場合の価値が大きく変動していることも多くあります。 OpenSea ProでNFTを取引する場合には、イーサリアムの価格に常に目を配っておくことが必要です。 まとめ この記事ではOpenSea Proの使い方について解説しました。操作画面の画像を交えて順を追って説明したので、しっかりイメージできましたよね。 OpenSea Proは、たくさんあるNFTマーケットプレイスを集約したアグリゲーターです。 OpenSea Proにアクセスするだけで、さまざまなマーケットプレイスに出品されているNFTを比較検討して最良の取引ができます。 まとめ買いなどの機能を使いこなせばガス代も節約できるので、NFTをトレードする機会の多い人にはとても便利ですね。

初心者向け
2023/06/04NFTプロジェクト「Blur」の使い方を解説|購入や出品方法も
この記事では、近年新たに注目を集めてきたNFTマーケットプレイス兼アグリゲーターサービスであるBlurについて解説しています。 この記事のポイント Blurは2022年にローンチされたNFTマーケットプレイス兼アグリゲーターサービス 手数料0%、最高水準の処理速度、BLURトークンのエアドロップなどの特徴があり、OpenSeaの取引ボリュームを上回るなど注目を集めてきた 機能や操作方法など、具体的な使い方を画像付きで解説 Blurの概要 画像:Blur 名称 Blur サービス NFTマーケットプレイス/アグリゲーター 対応チェーン Ethereum (ETH) ウェブサイト https://blur.io/ Twitter https://twitter.com/blur_io Discord https://discord.com/invite/blurdao Blurは2022年にローンチされたNFTマーケットプレイス兼アグリゲーターサービスで、2022年3月にParadigmが主導するシードラウンドにて1,100万ドルの調達に成功したことで注目を浴びました。 同年10月の正式ローンチから数日後には過去24時間の取引ボリューム1位を記録し、その後12月には取引ボリュームにおいてOpenSeaを上回ったことが発表され、大きな注目を集めてきました。 その後もBid機能の公開や、BLURトークンのローンチとエアドロップなど、注目のアップデートが続いています。 Blurの3つの特徴 画像:Blur 注目を集めるBlurの主な特徴を3つご紹介します。 ① 手数料0% 主要なNFTマーケットプレイスでは取引手数料がかかる一方、Blurの手数料は0%になっています。 また、手数料だけでなくガス代を抑えることもでき、入札とその取り消しの際にガス代は不要で、一括購入によりガス代の節約が可能です。 NFTの売買を行うトレーダーにとってはこのようなコストを削減できるのは大きな魅力ですね。 主要なNFTマーケットプレイスの手数料の比較 Blur 0% OpenSea 2.5% LooksRare 2.0% X2Y2 0.5% ② 最高水準の処理速度 Blurのウェブサイト上では「最速のNFTマーケットプレイス」と謳われています。 また、一括購入機能の実装により、他サービスよりも10倍速い取引が可能との説明もあります。 取引処理や情報更新などの速度が速いことは、とくに多くの売買を行うトレーダーにとっては魅力になりそうです。 ③ BLURトークンのエアドロップ シーズン1と称されたエアドロップでは総計3.6億のBLURが配布され、こちらも多くのユーザーを呼び込む要因となりました。 すでにシーズン2が開始しており、ビッディング/リスティング/レンディング等によって獲得できるポイント数に応じて総計3億ほどが配布される予定のようです。 Blurの使い方 画像:Blur ここからはBlurの使い方について、以下の通り順を追って解説していきます。 事前準備 ウォレットを接続する 購入したいNFTを探す NFTを購入する 入札 (Bid) する スイープ (Sweep) で一括購入する NFTを出品する エアドロップ (AIRDROP) 設定 事前準備 Blurを利用する前に以下の事前準備を完了しておきましょう。 事前準備 ① ウォレットの用意 (メタマスクがおすすめ) ② イーサリアム (ETH) の購入 ③ 購入したETHをウォレットに送金 ウォレットの準備がまだという場合は、以下の記事でメタマスクの始め方を解説しています。 MetaMask(メタマスク)の使い方まとめ!入出金・トークン追加も超簡単 また、イーサリアム (ETH) の購入について不安がある方は以下を参考にしてみてください。 イーサリアム(ETH)を購入するのにおすすめの取引所TOP3! ウォレットを接続する 事前準備が完了していたら、さっそくBlurとウォレットの接続からはじめましょう。 まずはBlurのウェブサイト (https://blur.io/) にアクセスし、右上の「CONNECT WALLET」をクリックします。 表示される選択肢から接続したいウォレットをクリックします。(今回はメタマスクで進めます) ウォレット側で接続の認証を終え、画面右上に接続済みのウォレットが表示されていれば完了です。 購入したいNFTを探す 購入したいNFTを探すときは、まずはトップ画面左上のタブから「COLLECTIONS」をクリックしてみましょう。 すると、トップコレクションのテーブルが表示されます。 左上のタブ (下の写真の①) からTRENDING (トレンド) をクリックすれば、トレンドコレクションの表示に切り替えることが可能です。また、テーブルの各項目名 (下の写真の②) をクリックすることで、各項目別に並び替えることが可能です。 また、画面上部の検索窓を利用すれば、任意のキーワードで検索することもできます。 コレクションをクリックすると、コレクションやそのアイテムの様々な情報が表示されます。 画面の上部にはそのコレクションの概要、中央部にはアイテム一覧とその詳細、右側には直近のアクティビティなどが表示されています。 また、左側にある以下の項目からさらに絞り込みを行うことも可能です。 STATUS・・・ONLY BUY NOW (販売中のみ) / SHOW ALL (すべて表示) RARITY・・・レアリティ PRICE・・・価格 ATTRIBUTES・・・NFTのパーツ また各アイテムの名前をクリックすると、アイテムごとの詳細な情報を確認することもできます。 NFTを購入する NFTの購入は、アイテム詳細画面の左下にある「BUY NOW」をクリックし、ウォレット側で認証を行うことで完了します。 また、アイテム一覧から、購入したいアイテムの左横にあるチェックボックスをクリック (複数選択可) した後に「BUY NOW」をクリックすると、まとめて購入することもできます。 入札 (Bid) する 入札 (Bid) を行いたい場合、まずPOOLにETHを入金 (デポジット) する必要があります。 アイテム一覧上部のタブから「BIDS」をクリックします。 画面下部に表示される「PLACE COLLECTION BID」をクリックします。 POOLへの入金に伴う説明が表示されます。主な内容は以下の通りです。 * 入札 (Bid) を行うためにはPOOLへの入金 (デポジット) が必要 * Bidとそのキャンセルにはガス代は不要 * POOLの残高はいつでも引き出すことが可能 * NFTを購入する場合はPOOLの残高から使用されるため、引き出さずにそのままでもOK 確認したら、「ADD ETH TO START BIDDING」をクリックして入金に進みます。 入金額を入力したら、「ADD TO POOL」をクリックします。 ウォレット側での認証を終えて数十秒ほど経つと、POOL BALANCE (POOL残高) に反映されます。 再度「BIDS」一覧に戻り、Bidしたいものをクリックします。 BID PRICEとSIZEを入力したら、「CONFIRM BID」をクリックして確定します。残高が足りない場合は「ADD FUNDS」をクリックして、先程の要領で入金しましょう。 ウォレット側の認証を終えるとBid完了です。 自分のBidの状況については、画面左上タブの「PORTFOLIO」をクリックした後「BIDS」を選択すると確認できます。また、Bidをキャンセルしたい場合は、該当のBidの右端にある「×」アイコンをクリックします。 また、余ったPOOLの残高を引き出したい場合は、画面右上の残高アイコンをクリックし、「WITHDRAW FROM POOL」を選択したら、あとは入金のときと同じく金額を入力して「WITHDRAW FROM POOL」をクリックします。 スイープ (Sweep) で一括購入する スイープ (Sweep) 機能を使うことで、ひとつのコレクション内のアイテムを価格が安い順に一括購入することが可能です。 コレクションのアイテム一覧を表示し、画面下部に表示されるスライダーを左右に動かして購入数を調整します。 スライダーで購入数を調整したら、選択済みのアイテムが反映されます。問題なければ画面左下の「BUY 〜 ITEMS」をクリックし、購入を確定します。 ウォレット側で認証を進めて、購入完了となります。 NFTを出品する NFTを出品する際は、接続済みのウォレットにNFTが保管されていることを確認しておきましょう。 問題なければ、画面左上のタブの「PORTFOLIO」>「INUENTORY」と進み、出品したいNFTにチェックを付け (複数選択可) 、画面下部の「LIST 〜 ITEM(S)」をクリックします。 以下の情報を設定して、問題なければ「LIST 〜 ITEM(S)」をクリックして出品を確定します。 ① MARKET PLACES・・・出品するマーケットプレイスを選択 (複数選択可) ② AUTO ADJUST FOR FEES・・・オンにすると手数料込みの価格を自動調整 ③ 販売価格の入力・設定 ④ DURATION・・・期間を選択 ウォレット側で認証を終えたら出品完了です。 エアドロップ (AIRDROP) 画面左上のタブから「AIRDROP」をクリックすると、エアドロップのダッシュボードが表示されます。 ここには現在実施中のエアドロップに関する情報がまとまっています。 執筆現在 (2023年5月) ではシーズン2のエアドロップが実施中です。 中央にビッディング/レンディング/リスティングの獲得ポイントとリスティングロイヤリティが表示されており、さらにスクロールするとこれらのポイント/ロイヤリティに基づくリーダーボードが表示されています。 設定 画面下部の歯車アイコンをクリックすると簡単な設定にアクセスできます。変更可能な項目は以下の通りです。 ビューの変更 (TRADER / COLLECTOR) ・・・TRADERビューはより多くのチャートやデータが集約されており、COLLECTORビューは全体的に大きく見やすい表示になります。 COLOR THEME・・・カラーテーマの変更 (DARK / MEDIUM / LIGHT) Sync with operating system theme.・・・システムのテーマに合わせる まとめ NFTマーケットプレイス兼アグリゲーターサービスとして注目のBlurについて、概要や特徴、その使い方を解説しました。 取引ボリュームではOpenSeaを上回るほどの注目度を誇るBlurですが、利用者数の観点ではまだOpenSeaの方が多いということもあり、今後この2つのマーケットプレイスがどのように展開していくのかも見どころです。 OpenSeaはより直感的に操作できるシンプルなUIが特徴的ですが、一方Blurは情報集約型のトレーダー向きUIとなっているため、好みも分かれる部分かもしれません。 新たなエアドロップも予定されているので、とくにトレーダーの方はぜひ一度Blurを試してみてはいかがでしょうか。 CT Analysis『NFTマーケットプレイス Blur概要と考察、OpenSeaとの比較』を公開

初心者向け
2023/06/03BRC-20とは?ビットコイン上で通貨の発行を可能にする技術を解説
BRC-20は、ビットコインのブロックチェーン上に存在するトークンです。 実験的なトークンでありながら、関連トークンの時価総額は4億ドルを超えている状態です。 また、基盤となったOrdinalsのNFTについても注目が集まっています。 この記事では、そんなBRC-20やOrdinalsについて以下の観点から解説しています。 この記事のまとめ ・BRC-20はビットコイン上のトークン ・ビットコインのブロックチェーンに影響を与える勢い ・Ordinalsの仕組みを応用 ・ERC-20とは大きく異なる BRC-20とは?ビットコインのトークン BRC-20は、ビットコイン上のトークン規格です。 イーサリアムなどでは、ブロックチェーン上をさまざまなトークンが行き交うことが一般的です。 一方で、ビットコインのブロックチェーンには、BRC-20のようなトークン規格がこれまで存在せず、主な用途はBTCの送受信といったシンプルな用途に限られていました。 しかし、Ordinalsと呼ばれるプロトコルの登場により、ビットコイン上でBRC-20やNFTの発行が容易となり、昨今大きな注目を集めています。 2023年5月時点で、24,000件を超えるBRC-20トークンが確認でき、全体の時価総額は4億ドルを超えている状態です。 (引用元:brc-20.io) また、BRC-20の基盤となっているOrdinalsのインスクリプション(inscriptions)も4月末あたりから大幅に伸びており、Ordinalsの利用についても拡大していることが分かるでしょう。 (引用元:Dune) 上記のような状況は、ビットコインのブロックチェーンへの影響も大きく、未承認のトランザクションが増加するといった現象も見られました。 BRC-20の特徴 これから、BRC-20が持つ基本的な特徴について、以下の2点から解説していきます。 ・Ordinalsの仕組みを応用 ・現在は実験段階 BRC-20のかんたんな特徴を把握して、大枠をチェックしていきましょう。 Ordinalsの仕組みを応用 BRC-20は、Ordinalsと呼ばれるプロトコルの仕組みを応用しています。 詳しくは後述しますが、Ordinalsについてかんたんにまとめると、ビットコインのサトシという細かな単位にデータを書き込んだり、追跡できたりするものです。 主に、ビットコイン上のNFTを発行できることなどから注目されていましたが、Ordinalsを応用してFTを発行する仕組みをdomo氏という開発者が実現しました。 https://twitter.com/domodata/status/1634247606262964228 上記の流れの中で、登場したのがBRC-20です。 現在は実験段階 BRC-20は熱狂を生んでいますが、まだまだ実験段階の取り組みです。 というのも、BRC-20のドキュメントでも実験であることが何度も記載されています。さらに、今後新たな設計や改善が行われる可能性についても言及されています。 実際に、BRC-20の利用にはいくつか不便な点も見られ、注目されているトークンも主にミームコインや比較的大きな時価総額を持たないものも多いです。 他のトークン規格ほど成熟したものではなく、取引や利用には注意が必要です。 BRC-20とOrdinalの仕組み BRC-20とその基盤となっているOrdinalsについて以下の観点から解説していきます。 ・Ordinalsの概要 ・Ordinalsにおけるインスクリプションについて ・BRC-20の仕組み OrdinalsやBRC-20の仕組みをチェックしていきましょう。 Ordinalsの概要 Ordinalsは、ビットコインのサトシに対して、何らかのデータを添付できるプロトコルです。 サトシとはBTCの最小単位のことであり、1サトシは1億分の1にあたります。 Ordinalsでは、そのサトシに何らかのデータを書き込み、追跡したりすることを可能にします。 具体的には、Ordinalsを通して画像やテキストなどのデータをサトシに添付し、ビットコイン上にあるNFTといったものを可能にしています。 Ordinalsの利用に伴って、新たなソリューションやサイドチェーンは不要です。 そのため、Ordinalsを利用して行ったアクションは全てビットコインのブロックチェーンを通して完結します。 BRC-20が大きく注目されているOrdinalsですが、上記の仕組みを通じて発行されたNFTの取引量も増加傾向にあります。 (引用元:Crypto Slam!) NFTのデータサイトCrypto Slam!によると、5月時点でのNFT売上ランキングでは、ビットコインが2位となっています。 直近1週間のデータを参考にすると、イーサリアムが約9,000万ドル、ビットコインが約4,400万ドルです。(ウォッシュ分を除く) 直近のデータのみを参考にすると、NFTをやり取りするブロックチェーンとして同じく人気の高いSolanaを上回るパフォーマンスを見せています。 上記のような点を参考にすると、ビットコイン上のOrdinalsは後述するBRC-20はもちろん、NFTにおいても高い注目を集めている可能性があるでしょう。 Ordinalsにおけるインスクリプション(Inscriptions)について Ordinalsがデータをサトシに添付していく過程で、特に重要なのが「インスクリプション(Inscriptions)」です。 Ordinalsでは、サトシにデータを書き込むという点は解説しましたが、インスクリプションがその過程に当たります。 ビットコインは過去に、SegWit(Segregated Witness)とTaprootという2つのアップデートを経験しています。 両者とも、NFTなどを想定したアップデートではありませんでしたが、結果的にトランザクションに含められるデータ量、構造などに影響を与えました。 インスクリプションでは、上記のアップデートの恩恵で誕生した領域に、含めたいデータを書き込みます。 また、何らかのものがインスクリプションされたサトシであっても前述したとおり、扱い自体は通常のBTCと変わりません。 BRC-20の仕組み BRC-20はOrdinalsを活用して、あくまで実験的にトークンとして扱えるようにしたものです。 BRC-20では、トークンとして機能させるために必要なルールのようなものを、前述したインスクリプションを活用して書き込み・機能させます。 そのため、インスクリプションする内容が異なるだけで、BRC-20を動かすための仕組み自体はOrdinalsを活用した他のNFTと大きな違いはありません。 Ordinalsの公式サイトでは直近のインスクリプションされたものを視覚的にチェック可能になっています。 BRC-20の人気が高まっているということもあって、直近のインスクリプションがBRC-20関連のものになっていることが分かるでしょう。 (引用元:Ordinals) Ordinalsでは複数の情報をインスクリプションでき、NFTでは画像関連のデータが書き込まれることが一般的です。 一方で、BRC-20では「text/plain;charset=utf-8」というタイプのインスクリプションを行います。 (引用元:Dune) 上記を参考にすると、インスクリプションされたもののうち、ほとんどがBRC-20と同じテキストを用いています。 2つ目に多い画像のタイプとも大きな差が開いており、Ordinals全体を見てもBRC-20が人気の高いインスクリプションの対象であることが分かるでしょう。 BRC-20とERC-20などとの違い ERC-20はイーサリアムに存在するトークンの規格で、BRC-20についてはビットコイン上に存在するトークンの規格です。 両者とも何らかのブロックチェーン上にあるという点は同じですが、その仕様・利便性は大きく異なります。 BRC-20はスマートコントラクトをサポートしていません。 そのため、BRC-20はERC-20のように複雑なことを行うことはできません。また、ERC-20はスマートコントラクトを利用した複雑なプロダクトはもちろんですが、さまざまなソリューションが完備されていて、一般的な方が利用しても利便性が高いです。 一方で、BRC-20も利便性が高くなるソリューションが日々出てきていますが、ERC-20ほどの利便性が高くありません。 BRC-20・ERC-20ともに名前が似通っていますが、その中身自体はほとんど異なるトークンです。 まとめ この記事では、BRC-20について解説しました。 BRC-20のトークンが多数の登場しており話題に上がりがちですが、ERC-20と同じような意識で扱うことはできないため注意が必要です。 その一方で、BRC-20の話題の高まりから周辺の開発に関するニュースも度々登場しているため、今後も注視していきたいと言えるでしょう。 最後まで、読んでいただきありがとうございました。

初心者向け
2023/05/06ユニスワップウォレットとは?機能や特徴、使い方を徹底解説【NFT対応】
分散型取引所(DEX)を展開するUniswap Labsから、モバイルウォレットアプリ「ユニスワップウォレット(Uniswap Wallet)」のリリースが発表されました。 本記事ではUniswap Walletの概要や特徴、使い方を解説します。 Uniswap Walletとは? 画像:Uniswap Wallet Uniswap Wallet アプリHP wallet.uniswap.org Uniswap - HP uniswap.org Uniswap - Twitter @Uniswap Uniswap Walletは、分散型取引所(DEX)のUniswapを展開するUniswap Labsからリリースされた、オープンソースの自己管理型モバイルウォレットアプリです。 NFTを含む暗号資産の管理に加え、Uniswapでのスワップ、WalletConnectによるDApps接続、法定通貨による仮想通貨の購入など、様々な機能が実装されています。 2023年5月現在ではiOS版アプリのみが提供されており、Android版については開発が進められているようです。 1/ THIS IS NOT A DRILL 🔥🔥🔥 The Uniswap mobile wallet is out of Apple jail and now live in most countries 🎉✨ Download our self-custody, open-sourced app today! 👇https://t.co/yWxuw79xTY pic.twitter.com/QhK06icKBL — Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) April 13, 2023 Uniswap Walletの特徴 画像:Uniswap Wallet 様々な機能が搭載されているUniswap Walletですが、そのなかでも3つの特徴をご紹介します。 シームレスなスワップ機能 Uniswapでお馴染みのスワップ機能がアプリ内でシームレスに利用でき、トランザクション完了の通知の受け取りも可能です。 2023年5月現在、以下の4つのネットワークがスワップ機能にてサポートされています。 Ethereum Polygon Arbitrum Optimism WalletConnectによるDAppsへの接続 WalletConnectにより、メインネットやレイヤー2のDAppsへの接続ができます。 Uniswap Walletでは、任意のアプリのQRコードスキャンにより簡単に接続が行えます。 強固なセキュリティとオープンソース化 Uniswap WalletにはFace IDによるロック解除や、iCloudによるバックアップ(任意)など、より強固なセキュリティを実現する機能が搭載されています。 また、アプリのコードはオープンソースとして公開されているため、誰でも確認することができます。 Uniswap Walletの使い方 画像:Uniswap Wallet ここからはUniswap Walletの使い方を解説します。 ※2023年5月現在、iOS版アプリのみが提供されています アプリダウンロードと初期設定 1.まずはアプリHP<wallet.uniswap.org>からアプリをダウンロードし、完了したらアプリを開きます。 2.「Get started」をタップします。 3. ウォレットの初期設定方法を以下の3つから選択します。 ① Import my wallet・・・リカバリフレーズを入力して既存のウォレットを復元 ② Watch a wallet・・・確認したいウォレットのアドレスを入力して資産を確認 ③ Create a new wallet・・・新規のウォレットを作成 今回は①のリカバリフレーズを入力してウォレットを復元する方法を選択します。 4. リカバリフレーズを入力し「Continue」をタップします。 5. リカバリフレーズに紐付けられたウォレットから復元するものを選択します。 6. リカバリフレーズのバックアップ方法を以下の2つから選択し、指示通りに進めます。すでにバックアップ済みの場合は「I already backed up」をタップして先に進みます。 iCloud backup・・・iCloudでバックアップ Manual backup・・・従来通りのマニュアルバックアップ 7. 通知設定を行います。オンにする場合は「Turn on notifications」、オフのままにする場合は「Maybe later」をタップします。 8. Touch IDを設定します。オンにする場合は「Turn in Touch ID」、オフのままにする場合は「Maybe later」をタップします。 9. ウォレットのQRコードと「You're ready to go!」のメッセージが表示されたら初期設定の完了です。「Let's go」をタップします。 これでアプリダウンロードと初期設定が完了です。 保有している暗号資産を確認する 初期設定が完了したらアプリのホーム画面が表示され、左上に保有資産額の合計が表示されます。 画面中央あたりの Tokens / NFTs / Activity のタブを切り替えることでそれぞれの情報を確認できます。 Tokens・・・保有している仮想通貨 NFTs・・・保有しているNFT Activity・・・トランザクションの履歴 仮想通貨の購入 Uniswap Walletでは法定通貨で仮想通貨を購入することができますが、残念ながら日本ではこの機能は利用できません。 アプリ内の「Buy」をタップすることで購入でき、MoonPay(オンライン決済サービス)を介したデビットカードでの決済となります。 手数料は2.55%と、他の主要なウォレットと比べて安いという点も魅力です。 仮想通貨の送受信 送信 仮想通貨の送信は以下の手順です。 1. 「Send」をタップします。 2.送信先のウォレットアドレスを検索窓に入力し、該当するアドレスをタップします。検索窓の右にあるアイコンをタップすると、QRコードのスキャナーを起動することができます。 3. 通貨や金額を入力したら「Review transfer」をタップし、内容に間違いがなければ「Confirm」をタップします。 受信 仮想通貨の受信が以下の手順です。 1. 「Receive」をタップする。 2. ウォレットアドレスおよびQRコードが表示されるので、アドレスをコピーするか、QRコードをスキャンする。 あとは送信側での操作となります。 スワップ機能 スワップの手順は以下のとおりです。 1. 「Swap」をタップします。 2. スワップする通貨の情報を入力し、「Review swap」をタップします。 3. スワップの内容を確認し、問題なければ「Swap」をタップします。 通貨, NFT, ウォレットなどの情報を検索する ホーム画面左下の「Search web3」をタップすると、あらゆる情報を検索できます。 1. 「Search web3」をタップします。 2. 様々な情報が表示されます。画面上部の検索窓をタップします。 3. キーワードを入力して情報を検索できます。 ここで検索できる情報は大きく分けて、①通貨、②NFTコレクション、③ウォレットの3種類です。 通貨とウォレットに関しては、右側のハートマークをオンにしておくと、「Search web3」をタップすると表示される画面にお気に入りとして常時表示させることが可能です。 また、「Search web3」をタップすると表示される画面から、各項目右側の「・・・」アイコンをタップすると、お気に入りを編集することも可能です。 ウォレットの追加・切り替え ウォレットの追加は以下の手順です。 1. ホーム画面左上のウォレットアイコンをタップします。 2. 切り替えたいウォレットをタップします。ウォレットを追加したい場合は「Add wallet」をタップします。 3. 以下の3つの選択肢から好きなウォレット追加方法をタップして、指示通りに進めます。 Create a new wallet・・・新規ウォレットを作成する Add a view-only wallet・・・確認専用のウォレットを追加する Import a new wallet・・・新しいウォレットを復元する(リカバリフレーズが必要) 各種設定 各種設定へは以下の手順でアクセスします。 1. ホーム画面右上の歯車アイコンをタップします。 2. Settings(設定)メニューが表示されます。 3. さらにウォレットごとの設定メニューを開くには、該当のウォレットの名前が表示されている箇所をタップします。 設定メニューで変更できる設定項目は以下の通りです。 Wallet settings・・・ウォレットごとの設定を行う(後述します) Appearance・・・アプリの見た目のテーマ(ライト/ダーク)を変更する Touch ID・・・Touch IDのオン/オフを切り替える Send Feedback・・・フィードバックを送信する Get Help・・・ヘルプメニューを開く Privacy Policy・・・プライバシーポリシーを開く Terms of Service・・・利用規約を開く また、ウォレット設定で変更できる設定項目は以下の通りです。 Nickname・・・ウォレットごとのニックネームを編集する Notifications・・・ウォレットごとの通知設定を変更する Hide small balances・・・細かな残高を非表示にする Hide unknown tokens・・・不明なトークンを非表示にする Manage connections・・・WalletConnectで接続されたアプリを管理する Recovery phrase・・・リカバリフレーズを表示する iCloud backup・・・iCloudバックアップを設定する まとめ Uniswap Walletの概要や特徴、使い方について解説しました。 シンプルですっきりとしたデザインや、直感的でわかりやすい操作性、Face IDやiCloudバックアップなどによるセキュリティなど、非常に魅力的なウォレットになっています。 2023年5月現在はiOS版のみの提供となっていますが、Android版のリリースも楽しみです。 分散型取引所「Uniswap(ユニスワップ)」とは?始め方や使い方を解説 Uniswap NFT 使い方完全ガイド | 今すぐ始める方法と注意点

初心者向け
2023/04/30ノーコードでNFTが発行できる|Manifoldの使い方を解説
この記事では。NFT市場で注目されている「Manifold」の概要とその使い方について解説します。 この記事のポイント Manifoldの概要 Manifoldの登録方法と使い方 Manifoldとは?= 独自コントラクトでNFTをミントできるツール 出典:Manifold Manifoldの公式リンク集 公式サイト manifold.xyz Twitter @manifoldxyz Discord discord.com/invite/y7eyzgwEdJ ドキュメント docs.manifold.xyz/v/manifold-studio 「Manifold」とは、独自コントラクトを作成してNFTをミントできるツールです。 独自コントラクトは、OpenSeaなどのマーケット側のコントラクトアドレスに紐づく共有コントラクトとは違い、自分で作成し所有するコントラクトアドレスに紐づくものです。 マーケット側に依存しない独自コントラクトによるNFTのあり方はWeb3において注目されており、著名なNFTコレクションにも独自コントラクトのものが多いことも事実です。 その一方、自己所有のコントラクト作成は複雑なプログラミング等の知識を必要とし、誰でも気軽にできるとは言えない側面もありました。 しかし、今回紹介するManifoldでは、独自コントラクトの作成からNFTの発行まで、誰でもノーコードかつ手数料無料でできてしまいます。 さらに豊富なアプリケーションをインストールすることでオークションサイトやSBT(ソウルバウンドトークン)の作成が可能になるなど、その拡張性も魅力のひとつです。 Manifoldの特徴 独自コントラクト作成からNFT発行までノーコードでできる手軽さ 手数料無料 豊富なアプリケーションによる拡張性(オークションサイトやSBTの作成など) Manifoldの主な使い方(独自ドメインの作成〜NFTのミント) 出典:Manifold ここからはManifoldの主な使い方について、以下の通り順を追って解説します。 ① Manifoldへの登録 ② 独自ドメイン作成とデプロイ ③ NFTのミント ① Manifoldへの登録 まずはManifoldへの登録からはじめましょう。 1.Manifold<manifold.xyz>にアクセスし、右下の「STUDIO LOGIN」をクリックします。 2.「Connect Wallet」をクリックします。 3.ウォレット側で接続や署名を進めます。 4.プロフィール設定が表示されたら、①「YOUR NAME」に名前、②「YOUR EMAIL」にメール(任意)を入力し、下の③「SUBMIT」をクリックします。 これで登録は完了です。 ② 独自ドメイン作成とデプロイ 登録が終わったら、早速コントラクトの作成を始めます。 1.「New Contract」をクリックします。 2.コントラクト作成画面が表示されるので、以下の項目を入力・選択します。 ① CONTRACT NAME・・・コントラクト名を入力 ② TYPE・・・トークン規格をERC-721もしくはERC-1155から選択 ③ SYMBOL・・・トークンシンボル(ティッカー)を入力 ④ ASCII MARK・・・アスキーマークを入力 アスキーマークはコントラクト作成時にソースコードのコメントとして記録されるアスキーアートのことで、コントラクトを視覚的に識別するために使用されるとのことです。 ここで設定するアスキーアートは幅120字未満が推奨されており、それ以上になるとテキストの折返しなどで形が崩れてしまう可能性があるとのことです。 アスキーアートはこちらのツールを使って作成することができます。もちろん他のツールや自作のものでも構いません。 5.さきほどの①〜④すべてが入力できたら、右上の「Deploy on Goerli」をクリックします。 6.ウォレット側でネットワークの切り替えを許可します。 7.Goerliテストネットで使用するGoerli ETH(gETH)を持っていない場合は下記のようなメッセージが表示されるため、Faucetから無料でGoerli ETHを入手を進めます。すでにお持ちの方は手順14まで飛ばしてください。 8.表示されているリンク<goerlifaucet.com>にアクセスし、右上の「Alchemy Login」をクリックします。 9.画面下部の「Sign up」をクリックした後、氏名、メールアドレス、パスワード等の必要情報を入力して登録します。 10.受信したメール本文の「VERIFY EMAIL」をクリックしてメール認証を行います。 11.メール認証が終わったらアンケート(全5問)が始まるので進めます。 12.アンケートが完了したら手順8の画面に戻りますので、①ウォレットアドレスを入力し、②reCAPTCHA(私はロボットではありません)をチェックし、③「Send Me ETH」をクリックします。 これでウォレットにGoerli ETHが入金されているはずです。Goerli ETHを入手したらManifoldに戻りましょう。 13.手順5と同じく「Deploy on Goerli」を再度クリックします。 14.進行状況が表示され、ウォレット側でガス代などの確認を進めます。 15.下の画像のような画面になればGoerliテストネットでのデプロイが完了です。 「View On Etherscan」をクリックし、「Contract」を選択すれば、作成したコントラクトの詳細を確認できます。 Contract Creator(コントラクト作成者)が自分のウォレットアドレスになっていることや、Contract Source Code(コントラクトのソースコード)に設定したアスキーアートが反映されていることを確認してみてください。 ③ NFTのミント 次はNFTのミントに移りましょう。 1.前回の続きから、「Go to Dashboard」をクリックします。 2.ダッシュボードが表示されるので、「MINT TOKENS TO A WALLET」をクリックします。 3.トークン管理画面が表示されるので、「Create」をクリックします。 4.ミントの方法が4つ表示されるので、実行したいものを選択します。今回は「Single Token」を選択します。 Single Token・・・1つのNFTをミントする Batch of Tokens・・・複数のNFTをミントする(ガス代の節約) Edition・・・同じNFTの複数のコピーをミントする 5.NFT情報の入力や設定の画面になりますので、以下の情報を編集します。 ① ・・・ここをクリックして画像/動画/音声/PDF/3D/HTMLファイルなどをアップロード ② ARTWORK TITLE・・・アートワークタイトルを入力 ③ CREATED BY・・・作者名を入力 ④ EXTERNAL URL (OPTIONAL) ・・・外部URLを入力(任意) ⑤ DESCRIPTION・・・説明を入力 6.下にスクロールすると「PROPERTIES(プロパティ)」を設定できます。右側の「New Property」をクリックし、プルダウンから追加したい項目を選択します。 Text・・・テキスト Number・・・数値と上限 Hidden・・・OpenSea上には表示されず、NFTのメタデータの記述を確認した場合にのみアクセス可能なプロパティ(詳細) Boost number・・・OpenSea上で円グラフで表示される数値とその上限(詳細) Boost percent・・・OpenSea上で円グラフで表示される割合とその上限(詳細) 7.NFTの情報やプロパティの入力・設定が終わったら、右上の「Mint to Goerli」をクリックしてNFTを発行しましょう。 8.受取方法を選択します。自分のウォレットにミントする場合は「Myself」、他者にエアドロップする場合は「Airdrop」をクリックします。今回は「Myself」を選択します。 9.ウォレットアドレスを確認し、「Mint」をクリックします。 10.進捗が表示され、ウォレット側で確認を進めます。 11.トランザクションが実行され、ミントが完了しました。 12.OpenSeaやLookRareのテストネット版にアクセスしてみましょう。「OpenSea」をクリックします。 13.ミントしたNFTが表示されていることを確認します。 14.準備が完了して問題なければ、最後にメインネットへデプロイしましょう。「Go to Dashboard」をクリックし、ダッシュボードからメインネットへデプロイしたいNFTを選択したら、「Mint to Mainnet」をクリックします。 これでNFTをメインネットへデプロイすることができました。 コントラクトの編集 コントラクトの編集の方法は以下の通りです。 1.画面左上の「マ」アイコンをクリックし、ホーム画面を表示する。 2.ホーム画面に作成済みのコントラクトが表示されるので、編集したいコントラクトをクリックする。 3.「Edit contract」をクリックし、コントラクト情報を編集する。 ※コントラクトがすでにブロックチェーンにデプロイされている場合は、コントラクトを編集しても古いコントラクトが残ってしまい、新しいコントラクトが作成されてしまいます。 ※すでにトークンがデプロイされている場合、コントラクトを編集することはできません。 トークンの削除, コピー, 設定 トークンの削除、コピー、設定などの方法は以下の通りです。 1.コントラクトのダッシュボードから「Tokens」をクリックする。 2.一覧から目当てのトークン(NFT)の「 ︙ 」アイコンをクリックして、以下の操作を選択できます。 Create a copy as draft・・・下書きとしてコピーを作成する Token Settings・・・トークン設定を開く Delete token・・・トークンを削除する 3.トークン(NFT)のアイコンをクリックすると、トークン情報を編集することができます。 アプリケーション Manifoldではアプリケーションをインストールすることで様々な機能の拡張することができます。 アプリケーションメニューへは以下の手順でアクセスできます。 1.画面左上の「マ」アイコンをクリックし、ホーム画面を表示する 2.「Apps」タブをクリックし、アプリケーションメニューを開く 多数のアプリケーションが利用可能ですが、以下にその一例と概要を挙げます。 Claim Page・・・NFTをクレームできるミントサイトの作成 Burn Redeem・・・ミントしたNFTを交換するサイトの作成 Gallery・・・NFTオークションサイトの作成 Curate・・・NFTのギャラリーサイトの作成 Souldrop: Soulbound Claims・・・SBT(ソウルバウンドトークン)をクレームできるサイトの作成 その他の設定 各種設定へは以下の手順でアクセスできます。 1.画面左上の「マ」アイコンをクリックし、ホーム画面を表示する 2.「Settings」タブをクリックし、設定メニューを開く 設定メニューからはプロフィール設定や、TwitterやDiscordとの連携、アドレス、コントラクト、トークンの管理などができます。 まとめ Manifoldの概要とその主な使い方について解説しました。 誰でも簡単に独自コントラクトでNFTを発行できる手軽さと、豊富なアプリケーションによる拡張性が魅力的ですね。 この機会にオリジナルのNFTをセルフミントしてみてはいかがでしょうか。
















 有料記事
有料記事


