
プロジェクト
2022/10/21L2ソリューション「StarkNet」とは?特徴や使い方を徹底解説!
StarkWareによって開発されているStarkNetは、zkロールアップに分類されるL2ソリューションの1つです。 StarkWareは過去に企業評価80億ドルで、1億ドルを超える資金調達にも成功しています。 そんなStarkWareが開発するStarkNetは、ゼロ知識証明を活用しイーサリアムのセキュリティを維持した状態で取引の処理を可能にします。 この記事では、StarkNetについて以下の観点から解説しています。 記事のまとめ ・StarkNetはzkロールアップのL2ソリューション ・StarkNetとStarkExは異なるソリューション ・StarkNetのシェアは限定的 ・ORUと比較してさまざまなメリットが見られる ・アルファ版のため注意が必要 StarkNetとは? =ゼロ知識証明を活用したL2ソリューション StarkNetは、ゼロ知識証明を利用したロールアップ(zk-Rollup)を活用したLayer2(以下、L2)ソリューションの1つです。 StarkNetの全体像を把握するにあたって、L2ソリューションと各ロールアップへの理解が不可欠です。 そのため、背景となるトピックも含めStarkNetについて、以下の観点から解説していきます。 ・L2ソリューションの概要と必要性 ・ロールアップの種類 ・StarkNetの概要とシェア ・StarkNetとStarkExについて StarkNetの概要を押さえていきましょう。 L2ソリューションの概要と必要性 代表的な仮想通貨であるイーサリアムの問題点として挙げられがちなのが、スケーリングです。 イーサリアムでは、さまざまな分野のプロダクトが構築されており代表的な分野にDeFiが挙げられます。 DeFiなどの普及に伴い大量に発生する取引(トランザクション)を、イーサリアムが処理しきれず、ガス代や処理速度が低下する問題が課題として認識されています。 上記の問題を解決するために、イーサリアムのブロックチェーンとは別の場所で取引を処理しようと試みているのが、L2ソリューションです。 ロールアップの種類とStarkNetの分類 L2の中でも、StarkNetはロールアップと呼ばれる種類に属します。 ロールアップは、L1とL2間におけるデータの可用性を確保している点が特徴に挙げられます。 具体的には、ロールアップではL2上で発生した取引のデータをオンチェーンでも記録・検証することが可能です。 また、ロールアップの中でも、取引の検証方法などによって大きく分けて、以下の2種類が存在しています。 Optimistic ロールアップ (例 Arbitrum、Optimistic Ethereum ) zk ロールアップ (例 zkSync、StarkNet) StarkNetは、zkロールアップに分類されます。 StarkNetとzkロールアップの概要 StarkNetは、StarkWare(Stark Ware Industries)によって開発されているzkロールアップの1つです。 zkロールアップでは、ゼロ知識証明と呼ばれる技術を活用し、L2上で行われた全ての取引を検証・証明します。 そんなゼロ知識証明の中でも、StarkNetではSTARKという証明方法を用いています。(仕組みによる特徴は後述) L2 BEATによると、StarkNetに預けられた資金は133万ドルとなっています。 L2全体の順位では18位となっており、大きなシェアを取れている状態ではないです。 ただし、StarkNetはアルファ版であることを考慮する必要があります。 まだまだ、利用できる機能・プロダクトなどには制限がかかっている状態で、本格的なローンチに至っているとは言えません。 今後、開発が進んでいくにつれて、徐々に利用が広がっていく可能性が高いでしょう。 StarkNetとStarkExの違い StarkNetを開発しているStarkWareは、StarkNetの他にも「StarkEx」と呼ばれるソリューションも提供しています。 StarkNetは、誰でもプロダクトを構築可能なパーミッションレスなロールアップ。 対して、StarkExは特定のプロダクトのために提供されているソリューションです。 StarkExは、StarkNetと比較してすでに多数の実績があり、4億ドル以上のロックが行われている代表的なプロダクトに「dYdX・IMMUTABLE X・Sorare」などが挙げられます。 また、StarkExを用いて開発されたプロダクトの中には、StarkNetが分類されるzkロールアップとは異なるソリューションを利用しているプロダクトも存在しています。(代わりにValidiumを利用) 名称や利用している技術などの類似点はあるものの、StarkNetとStarkExでは全体像が異なるため注意が必要です。 CT Analysis 『2022年12月 Ethereumの高いスケーラビリティを実現するStarkExとStarkNetの解説レポート』を無料公開 StarkNetの3つの特徴 これから、前述したようなStarkNetの概要・仕組みによって実現する特徴について、以下の観点から解説していきます。 ・高い処理能力と低いガス代 ・L1への引き出しの速さ ・プログラミング言語にCairoを採用 1つ1つチェックして、StarkNetの強みをチェックしていきましょう。 高い処理能力と低いガス代 他のロールアップと同様に、StarkNetはイーサリアムと比較して、高い処理能力を持ち、低いガス代で利用可能です。*ガス代は変動あり 一例として、StarkNetの記載はありませんが、以下の各ロールアップ間のガス代の比較をご覧ください。 ロールアップを用いた転送の方が、より低く押さえられていることが分かるでしょう。 StarkNetについても似たようなパフォーマンスが期待できます。 ただし、StarkNetはアルファ版であり本格的なローンチに伴って、どのようなパフォーマンスを発揮するのかは、まだまだ不透明な点があります。 今後、StarkNetの普及に伴って、各L2ソリューションとのパフォーマンスの違いには、注視していく必要があるといえるでしょう。 L1への引き出しの速さ StarkNetに預けた資金は、数十分程度でL1に引き出すことが可能です。 現在、大きなシェアを持っているOptimistic ロールアップを利用したL2ソリューションでは、資金の引き出しまでに1週間ほどの期間が必要です。 これは、Optimistic ロールアップが取引を検証・証明する際に必要な期間となっており、利便性や資金効率の観点から好ましくありません。 一方で、StarkNetのようなzkロールアップでは、より早い時間でL1への資金の引き出しが可能です。 (ただし、流動性を用いたソリューションなどを利用することで、Optimisticロールアップでも高速な引き出しが可能なケースもあります) プログラミング言語にCairoを採用 StarkNetでは、StarkNet上のスマートコントラクトなどの開発を行う言語として、「Cairo」と呼ばれる独自のプログラミング言語を採用しています。 StarkNetは基本的にCairoを用いて開発されており、StarkNetで開発を行いたい開発者もCairoを用います。 CairoはStarkNetのネイティブ言語ではあるものの、イーサリアムのSolidityなどをCairoへ変換するトランスパイラ(コード変換が行えるツール)も開発されています。 また、StarkNetはEVMについてもネイティブで対応していません。 StarkNetとArbitrum・zkSyncなど他のロールアップとの違い 現在、多数のL2ソリューションが登場しており、StarkNetもその中の1つです。 「StarkNetは具体的に他のL2ソリューションと何が違うのか?」と疑問を感じた方も多いでしょう。 そのため「OptimisticロールアップのArbitrum」・「zkロールアップのzkSync」と「StarkNet」の違いについて解説していきます。 StarkNetと、他のロールアップの違いについてチェックしていきましょう。 証明する「対象」が異なる:ArbitrumとStarkNet 2022年10月時点で、最も高いTVLを持っているロールアップがArbitrumです。 ArbitrumはOptimisticロールアップに分類され、StarkNetが属しているzkロールアップと、そもそもの検証・証明アプローチが大きく異なります。 両者の大きな違いは「証明する【対象】」にあります。 ArbitrumのOptimisticロールアップは「基本的に正しいブロックが生成される」という前提で設計されたロールアップです。 その上で、不正検知の仕組みとして、Optimisticロールアップでは「一定の検証期間」を設定し「期間内に不正なブロックは無いか?」という観点で検証を行います。 そのため、Optimisticロールアップでは、ブロックの検証に伴い「不正の証明(Fraud Proof)」が行われるのです。 一方で、StarkNetのようなzkロールアップでは「不正なブロックが生成される」という前提で設計されており、全てのブロックに対して「有効性の証明(Validity Proof)」を行います。 上記のような特性から、Optimistic・zkロールアップの間には、さまざまな箇所で大きな違いが見られます。 証明する「方法」が異なる:zkSyncとStarkNet zkSyncは、5,000万ドル以上がロックされるzkロールアップのL2ソリューションです。 StarkNetとzkSyncは、同じzkロールアップのため、両者とも「有効性の証明」を行い、証明する対象に違いはありません。 そのため、使用感(引き出しまでの時間など)について似通った点が見られます。 しかし、StarkNetとzkSyncでは「証明する【方法】」が異なります。 というのも、StarkNetでは「STARK」という証明システムを用いているのに対して、zkSyncでは「SNARK」を用いています。 また、このような違いはOptimisticロールアップに分類されるソリューションの間でも見られることが多いです。 同じロールアップに分類されていたとしても、L2ソリューション間で微妙に仕様・仕組みが異なってきます。 各ロールアップのより詳細な内容について、CT Analysisの「Ethereumを飛躍的にスケールさせるロールアップの概要と動向」で解説しているので、ぜひご覧ください。 StarkNetの使い方 StarkNetの利用には、以下のようなものが必要です。 イーサリアムサイドのウォレット (MetaMaskなど) StarkNetサイドのウォレット (Argentなど) ガス代やDeFiなどで利用する仮想通貨 また、上記の準備に加えて、利用する仮想通貨のStarkNetへのブリッジも必要です。 StarkNetへのブリッジを行うことで、StarkNetに構築されているプロダクトで仮想通貨を利用できるようになります。 StarkNetへのブリッジや、Argentなどの利用手順について、以下の記事で解説しています。 【評価額1兆円】StarkWare手掛ける注目のトークンブリッジ『StarkGate』を解説 StarkNetの注意点 最後に、StarkNetの利用に伴う注意点などについて、以下の観点から解説していきます。 ・利用できるプロダクトが少ない ・アルファ版であり完全な状態ではない StarkNetの利用前に押さえておきたいポイントをチェックしていきましょう。 まだまだ利用できるプロダクトやシェアは少ない StarkNetは、他のL2ソリューションと比較すると、まだまだ利用できるプロダクトやシェアは限定的です。 前述したようにTVLも、他の主要なL2ソリューションと比較して多くありません。 そのため、他のロールアップのようにエコシステムが整備されているとは限らないため注意が必要です。 「アルファ版であり完全な状態ではない」 StarkNetはアルファ版であり、あらゆる箇所で開発途中の印象が否めません。 例えば、StarkNetの開発を行っているStarkWareによって提供されているStarkGateというブリッジでも、アルファ版での運用が続いています。 ブリッジやロールアップの利用にはさまざまな潜在的なリスクが存在していますが、StarkNetの利用についてはその傾向が特に強くなると言えるでしょう。 常に何らかのバグ・欠陥・変更などが見られる可能性を考慮し、StarkNetへのブリッジなどについては、限定的な使用に留めておくのがおすすめです。 まとめ この記事では、StarkNetについてさまざまなポイントから解説しました。 StarkNetは、今後注目していきたいL2ソリューションの1つではあるものの、さまざまな観点で開発途中のソリューションです。 動向を注視しながらも、細心の注意を払った上で利用していきましょう。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 【トークン発行予定】分散型クロスロールアップブリッジ「Orbiter Finance」を解説

プロジェクト
2022/10/16Otherside(アザーサイド)とは?概要や特徴を解説|BAYC関連 メタバースプロジェクト
世界中で大きな盛り上がりを見せているYuga Labs関連の注目メタバースプロジェクト「Otherside」について解説していきます。 CoincheckでのNFT取り扱い開始や、CryptoPunksとMeebitsの買収など、Yuga Labs関連のプロジェクトは、様々な話題で注目を集めています。 この記事では以下の内容について解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。 この記事のポイント! 世界で注目されているメタバースプロジェクト「Otherside」とは? Othersideの土地NFT「Otherdeed」について なぜ世界中で注目されているのか?革新的な特徴について プロジェクトの現状と、今後の計画や将来性について Othersideの「今できること」と「これからできること」 メタバースプロジェクト「Otherside」とは何か? 「Otherside」は、NFT制作スタジオYuga Labsが関与するメタバースであり、現在世界で注目されているメタバースプロジェクトの1つです。 BAYCを制作するYuga Labsが新プロジェクト「Otherside」のティザートレーラーを公開|Crypto Times Othersideは世界中の人々が同時に参加できるメタバースプラットフォームであり、ユーザーは一般的なゲームプレイに加え、創作・対戦・探索ができるなど、その自由度の高さが特徴です。 また、このメタバースプラットフォームはコミュニティによって発展・拡大されることが想定されており、プラットフォームのツールや実用性についてもコミュニティによる参画やニーズによって形作られていくとしています。 運営・開発には大人気NFTコレクションを展開するYuga Labsをはじめ、業界屈指の企業が名を連ねていることも話題を集める要因となっています。 Othersideの概要 世界で注目されているメタバースプロジェクト ユーザーは創作・対戦・探索などができるなど自由度が高い プラットフォームはコミュニティによって発展・拡大していくことが想定されている 運営・開発にはYuga Labsなど業界屈指の企業が名を連ねる 運営・開発を手掛けるのはあのYuga Labs 他2社 引用:Otherside Othersideの豪華な運営・開発陣も注目を集めています。 Othersideの運営・開発企業 Yuga Labs・・・NFTシーンを席巻する注目のNFT制作スタジオ Improbable・・・メタバース関連の開発を手掛けるテクノロジーカンパニー Animoca Brands・・・The Sandboxを運営するゲーム制作会社 まさにWeb3.0を牽引する業界屈指の企業が集まっています。簡単ではありますが、ひとつずつ見てみましょう。 Yuga Labs 引用:Yuga Labs Yuga Labsは、世界のNFTシーンを席巻する注目の制作スタジオで、BAYC(Bored Ape Yacht Club)やMAYC(Mutant Ape Yacht Club)はじめとする多数の大人気NFTコレクションを展開しています。 現在(2022年9月)、大手NFTマーケットプレイスであるOpenSeaの取引高トップ10にYuga Labsのコレクションがランクインしており、その人気ぶりが見て取れます。 また、これらのNFTは何億円以上など極めて高額で取引されることでも知られ、その所有者にはラッパーのエミネム氏や、サッカー ブラジル代表のネイマール選手、日本ではEXILEの関口メンディーさんなど著名人も多くいます。 「Otherside」の土地NFT、約2億円で売買成立 | 同シリーズ最高値更新|Crypto Times 2022年3月にはYuga Labsが、Larva LabsのNFTコレクションである「CryptoPunks」と「Meebits」を買収したことでも話題になりました。 Yuga Labs ウェブサイト Yuga Labs ツイッター Improbable 引用:Improbabale Improbableは、メタバース関連の開発を手掛けるテクノロジーカンパニーです。 Othersideの開発においては、M2(MSquared:エム・スクエアード)というプロジェクトを創設しています。 このM2はメタバース実現に立ち上はだかる課題の解決を目指すもので、この技術を用いることで1万人の同時接続が可能になり、さらに1秒間に3億5000万回以上の操作処理が可能になると説明されています。 まさにOthersideのメタバースの技術基盤を支える企業ということになりますね。 Improbable ウェブサイト Improbable ツイッター Animoca Brands 引用:Animoca Brands Animoca Brandsは、ブロックチェーンゲームとして知られるThe Sandboxを運営するゲーム制作会社です。 ブロックチェーンやNFTに関連する様々な業界に多数出資し、独自のWeb3.0エコシステムの構築を進めています。 また、2022年2月には日本法人が設立されたことでも話題になりました。 Animoca Brands ウェブサイト Animoca Brands ツイッター Othersideの土地NFT「Otherdeed」について 引用:Otherside Otherdeed(NFT)とは?種類や設定についてわかっていること Othersideには土地NFTである「Otherdeed」が存在します。 Otherdeedについてはまだ詳しく公開されていない部分が多いですが、簡単に以下のように整理されています。 Tier(階層) 引用:Otherside Otherdeedには土地の堆積物によって5つの階層に分かれています。 Tier 1 - Sludge INFINITE EXPANSE Tier 2 - Bog COSMIC DREAM Tier 3 - Obsidian RAINBOW ATMOS Tier 4 - Luster CHEMICAL GOO Tier 5 - Crimson BIOGENIC SWAMP その土地の堆積物、環境、リソースなどの組み合わせによって、様々な変化があるようです。また、土地によっては後述のKoda(コーダ)が存在している可能性もあるとのこと。 Koda(コーダ) 引用:Otherside Koda(コーダ)はOthersideの原始の生物で、我々ユーザーをOthersideへ導いた存在です。なぜ彼らが我々をOthersideへ導いたのかはまったくわかっていないそうです。 全区画のうち10%に存在するようで、その希少性からKodaが存在する土地は高値で取引されています。 Resource(リソース) 引用:Otherside Othersideには4つのリソース(資源)が存在し、採取して利用することができるとのこと。これらのリソース(資源)はOthersideの世界を形作る素材をとなります。 Anima(アニマ) Ore(オレ) Shard(シャード) Root(ルート) Artifact(アーティファクト) 引用:Otherside Othersideにおいて一定確率で点在するとされるArtifact(アーティファクト)はレアアイテムです。 なかにはいかなる手段でも作ることのできないものやOthersideの世界の秘密を握っている可能性もあると噂が流れています。 ダイナミックNFTとしてのOtherdeed 引用:Otherside OtherdeedはダイナミックNFTであるため、Othersideに存在する様々な素材などの要素、ユーザーの選択と行動などによって変化・進化していきます。 各Otherdeed(NFT)には、その土地のSediment(堆積物)やTier(階層)、Resource(リソース)やArtifact(アーティファクト)、Koda(コーダ)などの情報が記載されています。 Otherdeed(NFT)購入殺到!記録的なガス代により大変なことに…! Otherdeed(NFT)は、2022年4月30日に5万5000区画が一律305ApeCoin(ApeCoinについては後述)で販売されましたが即日完売し、およそ24時間で3億2000万ドルの調達に成功しています。 また、あまりに人気に購入希望が殺到した結果、イーサリアムブロックチェーンのガス代が高騰し、完売までにかかったガス代は全体で1億2400万ドルにも達したとのこと。 システムへの高負荷に伴って高額なガス代だけを支払いながら購入には失敗するという人も続出したため、Yuga Labsは後日このことについて謝罪し、購入に失敗した人のガス代は払い戻されることになりました。 We are aware that some users had failed transactions due to the incredible demand being forced through Ethereum’s bottleneck. For those of you affected, we appreciate your willingness to build alongside us – know that we’ve got your back and will be refunding your gas. — Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022 NFT即日完売や記録的なガス代など、話題尽くしとなりました。 その後もOtherdeedの人気は続いており、現在(2022年9月)OpenSeaのNFT取引高ランキングでは第4位となっています。 ガバナンストークンのApeCoin (APE) 引用:ApeCoin ガバナンストークンとして機能しているのはApeCoin(APE)です。 人気NFTコレクションであるBAYC(Bored Ape Yacht Club)に関連する仮想通貨として、2022年3月にツイッターで発表されました。 その特色として、「Web3.0を牽引する分散型コミュニティを支える、カルチャー、ゲーム、商業利用のためのトークン」であるとされています。 BAYC関連トークン「$APE」ローンチ。BinanceやCoinbaseなどの取引所への上場も決定|Crypto Times 立ち上げにはYuga Labsが携わっていますが、運営そのものはApeCoin DAOという自立分散型組織によって行われ、トークン保有者はその運営の意思決定に関わる投票券を得ることになります。 BINANCE、Bybit、FTX、Gate.ioなど多くの大手取引所に上場していることからも注目されています。 Othersideが注目を集める理由とは?革新的な特徴について解説! Othersideが世界の注目を集める理由として、その革新的な3つの特徴について解説します。 ① より進化したメタバース開発への挑戦! 引用:Otherside Othersideでは、メタバース開発によって次の3つの実現に取り組んでいくと発表しています。 より進化したメタバース開発への挑戦 クラウドネットワーク技術とレンダリング技術によって何千ものユーザーを同時接続させる 空間オーディオ技術によって何千ものユーザーが同時に会話できるようにする あらゆるデバイスからの接続を可能にし、誰もが手軽にコミュニティに参加できるようにする 最初の2つについては、世界中の何千もの人々が同時に接続すること、そして同時に会話を行うことを目指しています。 とくに会話については、何千もの人々の声が一斉に聞こえるのではなく、距離感なども考慮したよりリアルな「人混みのなかでの会話」を再現することに挑戦しているようです。 また、3つ目については、メタバースへのアクセスに必要なマシンのスペックの壁を越えようという試みです。誰もがスマートフォンやPCブラウザで手軽にアクセスでき、デバイスの制限を取り払うことを目指しています。 ② 「ODK」とメタバース間の相互接続性! 引用:Otherside Othersideには「Otherside Development Kit(ODK)」というクリエイターツールが存在します。 ODKを使用することで、ユーザーは相互運用可能なコンテンツを自ら創造することができるようになると公表されています。 また、実際に作成したオブジェクトに対して、その機能やビジュアルを付与することができるそうです。 例えば、作成したオブジェクトに椅子としての機能とビジュアルを付与することで実際に座ることができるになり、こうして作成されたコンテンツはメタバース内で相互運用できるようになるとのことです。 将来的にはそのメタバース内だけでなく、先述のM2プロジェクトで開発されたメタバースであれば、異なるメタバース間で相互運用可能になることを目指しています。 ちなみに、下記のNFT保有者ついては、Othersideリリース時にそのまま使用可能なNFTの3Dモデルが配布されるとのことです。 ・BAYC(Bored Ape Yacht Club) ・MAYC(Mutant Ape Yacht Club) ・BAKC(Bored Ape Kennel Club) ・CryptoPunks ・Meebits ③ あらゆるモノの取引を可能にする「The Agora」 引用:Otherside 「The Agora(ジ・アゴラ)」はOthersideにおいて予定されているマーケットプレイスのことです。 The Agoraでは、作成したり、育てたり、収穫したりしたものを、購入したり、仕分けしたり、取引したりということができるようです。 Otherside経済圏の利点を享受するには最も簡単で安全な場所となるます。 メタバースが発展するにつれて、The Agoraにおける資源の受容と供給が増していくことが予想されます。 Othersideの現状や今後の計画は?将来性についても考察!(2022年9月現在) Othersideの現状や、今後の計画と将来性について整理していきます。 プロジェクトの現状 初めての「First Trip」で最大同時接続数4620人を記録! まずはPhase 1として、Otherdeed保有者(=Voyagers:ボイジャーズ)と開発者のみが参加できる「First Trip」というデモプレイが2022年7月16日に開催されました。 最大4620人もの同時接続プレイの様子は、公式ツイッターや個人のYoutubeなどで確認することができます。 We came, we saw, we made fart noises. Here, a look back at our unforgettable inaugural First Trip together. 4,620 players, 2,560 live-stream views, and Koda booty for DAYS. Can’t wait for the next one. pic.twitter.com/t3un1xmorZ — OthersideMeta (@OthersideMeta) August 4, 2022 このFirst Tripと題されたデモプレイは今後も複数回実施予定とのことで、現状未定ではありますが、詳しい日時や詳細は追って公式SNSにて発表されるとのことです。 2022年4Qに向けた新トレーラー公開! 2022年9月2日には第4Qに向けたトレーラーが公式ツイッター及びYouTubeにて公開されました。 10月以降にはまた新たな動きがあると思われるため、今後の動向に注目です。 The story continues later this Q4. pic.twitter.com/fSs2AkC7fo — OthersideMeta (@OthersideMeta) September 2, 2022 プロジェクトの今後の計画「The Voyager's Journey」 「The Voyager's Journey」と名付けられた一連のデモプレイのロードマップが公開されており、プロジェクトはこれに沿って進められていくということです。 ただし、詳細が公開されているのはすでに終了している1回目のFirst Tripのみで、他の予定についてはタイトルのみの発表に留まっており、その他の詳細は現状公表されていません。 現在ウェブサイトで確認できるロードマップの各タイトルは以下の通りです(参照:The Voyager's Journey) ・FIRST TRIP ・THE CODEX ・KODA ORIGINS // THE DECOUPLING ・THE GROWTH ・THE AGORA ・THE DREAM ・THE CHOICE ・THE SETTLING ・THE TOOLKIT ・THE AERONAUTS ・THE RIFT あとは次回のFirst Tripの予定が発表されるまでのおあずけとなりそうです。 プロジェクトの将来性についての考察 最後にメタバースプロジェクトOthersideの将来性について考察してみましょう。 Otherside及びYuga LabsでNFT売上高トップ4を独占! 引用:OpenSea 現在(2022年9月)、NFT取引高トップ4をYuga Labsのコレクションが独占、そして第4位がOtherdeedとなっています。 Otherdeedはすでに高値での取引が行われており、NFTシーンにおけるOtherdeed及びYuga Labsの注目度は高い状況です。 今後のロードマップやリリースによってOtherdeedがさらに注目される可能性! 引用:Otherside すでに非常に注目されているOtherdeedですが、今後のOthersideのロードマップ進捗やデモプレイなどのイベント次第では、まだまだプロジェクトが、勢いづく可能性を秘めているのではないでしょうか。リリースが近づけば近づくほど、Otherdeedの注目度が高まっていく可能性が考えられます。 メタバース環境が整えばApeCoin (APE) のユーティリティも増える? 現在、APE DAOのガバナンストークンとして機能しているApe Coinですが、Othersideのメタバース空間が利用可能になることで、ユーティリティが増える可能性が予測できます。 The Agoraでの利用可能やメタバース内でアイテムを購入する際に利用可能になっていくことが考えられます。 例えば、ブロックチェーンを活用したメタバース空間のDecentralandでは、メタバース空間内で基軸通貨であるMANAを利用することで、ゲームプレイやウェアラブルアイテムが購入することができます。 このようなユーティリティが増えることが考えられるので、Othersideの今後の開発状況には注目です。 M2が目指す技術が実現すればメタバースが一気に普及する? 引用:Improbable M2が実現を目指して取り組む開発目標のひとつに、「マシンスペックに制限されず誰でもどのデバイスからでもアクセスできる」という項目がありました。 もしもこのような技術が本当に実現したら、マシンスペックにとらわれずメタバースにアクセスすることが可能になります。現状は、PCやVR機器がほぼ必須となっていますがスマホからもアクセスできる時代がくる可能性があります。 誰もが手軽にメタバースにアクセスできるようになり、Othersideを含むメタバースそのものの敷居が一気に下がり、生活や仕事のなかに急速に普及する可能性を秘めているのではないでしょうか。 まとめ 今世界で最も注目されているメタバースプロジェクト「Otherside」について解説してきました。 まだまだスタートしたばかりですので、今後どうなるかわからない部分が多いですが、今わかる部分だけでもリリースが待ち遠しい限りです。 また、Otherdeed保有者の方は、この革新的なプロジェクトのスタートに携わる貴重な貴重を得られるわけですから、本当にうらやましいですね。 Otherdeedを持っていない方も、メタバースの躍進を見逃さないように今後の動向も要チェックです。

プロジェクト
2022/10/15クロスチェーンアグリゲーター「Rango」の概要や使い方を解説
Rangoは、チェーンをまたいで仮想通貨の交換が出来るクロスチェーンアグリゲーターです。 EthereumやBSCといった主要チェーンだけではなく、レイヤー2ソリューションのArbitrumやOptimismなど40以上のチェーンに対応しており、Rangoはローンチ後急速にエコシステムを拡大しています。 https://twitter.com/RangoExchange/status/1503725992807911424?s=20&t=uPexOgcGsWIGMElAd1vsXw Rangoはトークンのエアドロップ実施を発表しており、配布分の15%に関して、スナップショットが2022年10月31日に行われる予定です。 本記事では、注目のRangoについて実際の使い方も含めて解説していきます。 Rangoとは?=複数のブロックチェーンをサポートするクロスチェーンアグリゲーター Rangoは、複数のブロックチェーンをサポートしているクロスチェーンアグリゲーターです。 クロスチェーンアグリゲーターとは、資産を出発点Aから到着点Bに送金するために、複数あるDEXやブリッジプロトコルの中から最適なルートを提案してくれる機能を1つのプラットフォームに集約させたサービスです。 ブロックチェーン市場が成長を続ける中、幾多のブロックチェーンネットワークが市場を賑わし、ブロックチェーンネットワークの数だけトークンの運用方法の幅が広がりました。 しかし、チェーン間の資産を移動させるのは容易ではなく、例えばUniswapではEthereum(ERC20)規格の資産の交換しか出来ません。 資産を他のチェーンへ変更したい場合、特定のチェーンに対応しているCEXに資産を送金して変更したいチェーンへ送金するか、クロスチチェーンスワップのサービスを利用してチェーンを変更する方法等があります。 しかし、チェーンの変更までに多くの工程を経なければならぅ、ブリッジの選択肢の数だけ最適なルートを探す手間がかかってしまう悩ましい点がありました。 しかし、Rangoのようなクロスチェーンアグリゲーターを特徴としたプロジェクトを活用すると、チェーン間の資金移動の手間が解消され、様々なトークンやチェーンに触れることが可能となります。 Rangoの概要 現在市場には複数のクロスチェーンアグリゲーターのプロジェクトがローンチされていますが、Rangoは、クロスチェーンアグリゲーターの中でも多くのチェーンに対応しており、2022年9月現在で40のチェーンをサポートしています。 またチェーン間の資金移動をより簡単に行えるように15のブリッジ、27のDEXを統合しているため、ユーザーは資産の交換やチェーンの変更の際に最適なルートで自由自在にスワップが行えます。 対応している40チェーン BSC、Polygon、Ethereum、Osmosis、Juno、Avalanche、Arbitrum、Cosmos、Fantom、Optimism、Solana、Cronos、MoonRiver、MoonBeam、Heco、Aurora、Harmony、Evmos、Sifchain、Thorchain、Binance Chain、Stargaze、Bitcoin、Crypto.org、Chihuahua、Comdex、Regen Network、IRISnet、Gnosis、LiteCoin、Bitcoin Cash、Fuse、Akash、Persistence、Sentinel、Starname、BitCanna、Desmos、Lum Network、Boba 統合しているブリッジプロトコル Thorchain、1inch、Binance bridge、Osmosis zone、Across protocol、Hyphen、Via protocol etc.. 統合しているDEX Uniswap、SushiSwap、Bancor、Paraswap、1inch、horchain、Quickswap etc... この他にもTron、Polkadot、Near、ADAなどのブロックチェーン、プロトコルを統合するために大規模な開発が行われています。 Rangoは、クロスチェーンアグリゲーターとして最も使いやすく、どのような資産も簡単に交換出来るよう、究極のUXを追究してユーザーに提供する事をミッションとして掲げています。 上記ミッションを実現するべくフォーカスしているDeFi分野では、全てのDEXとブリッジプロトコル、DEXアグリゲーターを統合し、全ての流動性を集約することを目的に取り組んでいます。 Rangoの3つの注目ポイント 1. Celerのプロダクトと統合 | ワンクリック&ワントランザクションで取引を完結 2. シードラウンドで100万ドルを資金調達 3. 多数のウォレットを統合 Rangoの注目ポイントとして上記3つについて解説していきます。 それぞれチェックしていきましょう。 Celerのプロダクトと統合 | ワンクリック&ワントランザクションで取引を完結 Celer Networkのプロダクトであるインターチェーン・メッセージ・フレームワークと統合したことで、チェーン上のトークンの相互運用性を促進する事が可能になりました。 この統合によって取引の際に生じるブロックチェーン上の複雑な相互作用がなくなり、ワンクリック&ワントランザクションで取引を完了出来ます。 シードラウンドで100万ドルを資金調達 Rangoは、シードラウンドで、分散型クロスチェーンのインフラストラクチャを構築するTHORChainの構築および流動性を提供しているNine Realms 、北京に拠点を構え多数のブロックチェーン企業に投資を行っているD1 Ventures、またVCだけではなく小規模なDAOや個人投資家から100万ドルを資金調達しています。 多数のウォレットを統合 Rango.exchangeでは、以下のウォレットがサポートされており、Rango.exchangeのアクセスで使用する事が出来ます。 各種ブロックチェーンネットワークに対応した8つのウォレットを簡単にみていきましょう。 WalletConnect WalletConnectは、分散型金融(DeFi)などのDAppsとウォレットを、安全に接続して通信できるようにするためのプロトコルです。 総接続数は2022年9月時点で1,107,304,399に達しており、サポートしているウォレットは170、DAppsは450以上を統合しています。 DeFi、NFT、DAOといったWeb3への接続をシンプルに行えるweb3のインフラストラクチャです。 XDEFI Wallet XDEFI Walletは、14のブロックチェーンをサポートしており、暗号資産やNFTを安全に保管、交換、送受信できるマルチチェーンウォレットです。 対応しているチェーンは、主要チェーンであるBitcoinやEthereumをはじめ、THORChain、Avalanche、Fantom、Arbitrum、Polygon、Bitcoin、BNB Smart Chain、Dogeに対応しており、ウォレット内で10,000以上の資産をクロスチェーンによって交換する事が出来ます。 Metamask Metamaskは、2,100万人以上のユーザーがインストールし使用しているEVMをベースとしたウォレットで、ブラウザ拡張機能版とモバイルアプリ版があります。 EVMをベースとしていることからイーサリアムブロックチェーンの資産、NFTを保管・管理できます。 CRYPTO TIMESでは、MetaMaskの使い方に関する記事も公開中ですので是非参考にしてください。 MetaMask(メタマスク)の使い方まとめ!入出金・トークン追加も超簡単 Keplr Wallet Keplr Walletは、Interchainエコシステム向けに開発されたオープンソースのIBC対応ウォレットです。 CosmosエコシステムのDappsに接続するウォレットの中で、最適なウォレットと評価されておりCosmos公認のウォレットになります。 Binance Wallet Binance Walletは、BSCやEthereumのチェーンに接続し、資産の交換を行う事が出来るバイナンス公式ウォレットです。 Binance Walletをサポートしているブラウザは、Chrome、Firefox、Braveがあり、Googleのchrome拡張機能に追加する事で簡単に使えます。 バイナンスのアカウントを作成し口座開設する事で、Binance Walletとバイナンスアカウントを直接リンクすることが可能です。 Phantom Wallet Phantom Walletは、Solanaのチェーンに対応したウォレットで、SPL規格のトークン及びNFTを安全に保管出来ます。 ウォレット内で高速のスワップが可能で、低い手数料で資産の交換が行えます。 Solanaブロックチェーンで構築されたDappsに接続し使用する事が出来るため、Solana上のプロジェクトを利用する多くのユーザーから支持を集めています。 【使えると便利】Phantom Wallet | ウォレットの概要や使い方を解説! Coin98 Wallet Coin98 Walletは、32のブロックチェーンに対応しているマルチチェーンウォレットで、Dapps内でイーサリアムベースのUniswap、BSC上のPancakeSwap、Polygon上のQuickSwapなどへ接続する事が出来るDeFiゲートウェイとしても活用出来ます。 Coinbase Wallet 米国のユニコーン企業であるCoinbaseと連携をとっているCoinbase Walletは、何十万銘柄の暗号資産、イーサリアム&ポリゴンブロックチェーンで構築されているNFTを保管出来ます。 またAMM DEXのUniswap、DeFi protocolのAAVE、自社のNFTマーケットプレイスのCoinbase NFTといったDappsへアクセス出来ます。 Rango Exchangeの使い方 Rangoの特徴で統合されたウォレットを紹介してきましたが、今回はEVMベースのMetaMaskを使い、クロスチェーンスワップの手順を解説していきます。 以下の手順に沿ってRango Exchangeを使ってみましょう。 ①MetaMaskのウォレットを用意する ②サポートされているネットワーク&アセットを準備する ③Rango ExchangeとMetaMaskを接続する ④ネットワーク間でアセットをスワップする ①Metamaskのウォレットを用意する Metamaskのウォレットのインストール方法など使い方は、下記記事で解説しているのでインストールしていない方は、参考にしてください。 MetaMask(メタマスク)の使い方まとめ!入出金・トークン追加も超簡単 ②サポートされているネットワーク&アセットを準備する Rango Exchangeに対応している資産をMetaMaskで保有します。 ネットワークを追加する場合、適切なチェーン&ネットワークIDに接続出来るChainlistの利用をオススメします。 Chainlistは、ほとんどのチェーンを網羅しており、簡単にネットワークの追加が可能です。 ③Rango ExchangeとMetaMaskを接続する Rango Exchangeにアクセスしたら、右上にある「Connect Wallet 」をクリックします。 MetaMaskをクリックします。 接続が完了すると右上のメタマスクアイコンが緑色に表示し、自身の総資産が反映されるようになります。正常に接続出来ているかチェックしましょう。 ④ネットワーク間でアセットをスワップする 今回は、Ethereumネットワークの0.1ETHをArbitrumネットワーク上のWETHへスワップしてみます。 最適なルートとして提案された転送手順は、 EthereumネットワークのETHをAcross protocolにてArbitrumネットワークへブリッジ Arbitrumネットワーク上のETHを1inch経由でWETHへスワップ のルートが最適と提案されています。 手数料(0.37$)とスワップにかかる時間(4分45秒)が表示されていますので、確認したら「Swap」をクリックします。 EthereumネットワークのETHから、ArbitrumネットワークのWETHへ、スワップする最終確認をして「Confirm Swap」をクリックします。 先ず、EthereumネットワークのETHを、Across protocolにてArbitrumネットワークへ、ブリッジする際のトランザクションの承認を行います。 消費するガス代を確認後、「確認」をクリックします。 続いてArbitrumネットワーク上で受信したETHを、DEXである1inchでWETHへスワップするのでネットワークを切り替えます。 一定の時間が経過するとポップアップでMetaMaskが立ち上がるので、1inchでETHをWETHへスワップするトランザクションを承認してスワップを完了させましょう。 以下のようにArbitrumネットワークに、0.09986547WETHの保有を確認出来るので、スワップが完了したことが分かります。 またTx Historyでは、「Inbound tx」、「Out bound tx」、「Swap tx」をクリックすることで、各種ネットワークのスキャンツールにアクセス出来るので詳細を閲覧出来ます。 ユーティリティトークン「RANGO」について Rangoは、独自トークンRANGOを発行しています。 ティッカーシンボル:$RANGO 総供給量:100,000,000 $RANGO 公式ミディアムによると今年の5月頃にIDOを行う予定でしたが、市況により延期されています。 RANGOトークンの主なユーティリティは、ガバナンストークンとしてガバナンス投票に使用出来るだけでなく、Rango.Exchangeを利用した際の手数料の支払いに活用出来るようになるとのことです。 したがって、現在ではトランザクションの承認の際に、EhereumネットワークであればETHをガス代として消費していますが、今後、消費するガス代を独自トークンRANGOで支払う事が可能となり、ガス代をサードパーティーから調達したり、手数料で発生するガス代分のネイティブトークンを残すといった作業が必要なくなる予定としています。 今からでも狙えるエアドロップについて 冒頭でも触れましたが、9月現在の今からでも狙えるエアドロップキャンペーンがあります。 2022年10月31日時点でスナップショットが取られ、Rango.Exchangeを利用したユーザーにRANGOのエアドロップが行われます。 エアードロップの配布量は、取引の量、頻度に応じて配布されます。 まとめ クロスチェーンアグリゲーターRangoについて解説してきました。 Rangoのエコシステムを見ても分かる通り、ほとんどのチェーンを統合しており、統合していないチェーンの統合計画も進んでいます。 プロダクトのRango.Exchangeは、各種チェーンのブリッジプロトコル、DEXを統合しているため、ストレスなくシームレスにトークンのチェーン間移動、スワップを実現出来ます。 既にクロスチェーンアグリゲーターとして頭角を現しているRangoの今後に期待です。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 ―Rango公式リンク― Webサイト:https://rango.exchange/ dApps:https://app.rango.exchange/ ツイッター:https://twitter.com/RangoExchange 日本語ツイッター:https://twitter.com/RangoJapan テレグラム:https://t.me/rangoexchange Medium:https://medium.com/@rangoexchange
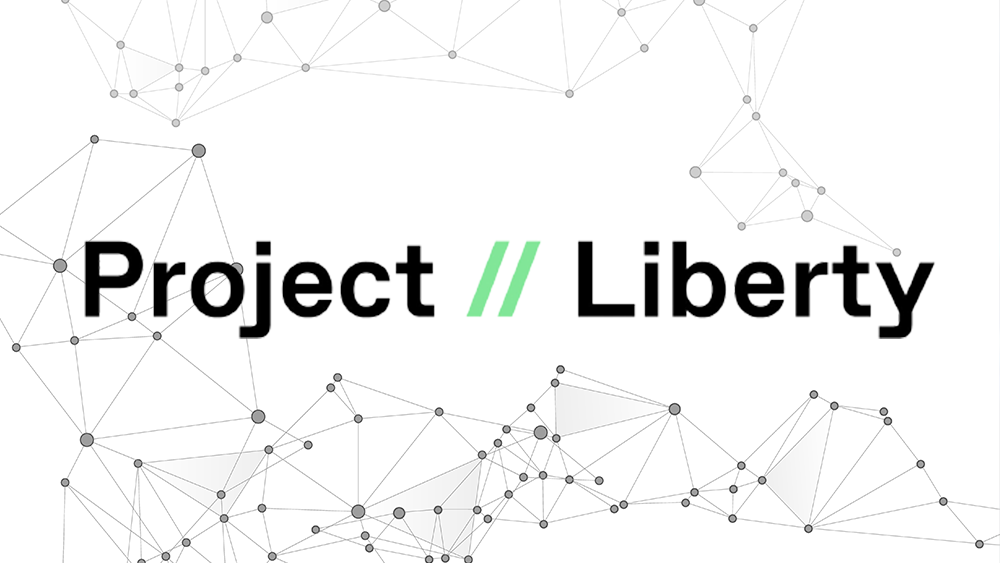
プロジェクト
2022/10/09健全なSNSの構成を目指す「Project Liberty」とは?| 次世代Webインフラの構築へ
インターネットやウェブの発達により、社会や経済の仕組みは大きく変化し、人々の日常の行動がデータとして可視化され価値を持つようになりました。 今回紹介するProject Libertyは、現代社会における個人のデータが持つ課題にアプローチするプロジェクトです。 web2.0からweb3.0への移行でインターネットやウェブの在り方が大きく変わると囁かれている中、Project Libertyのようなプロジェクトは注目しておきたいプロジェクトと言えるでしょう。 是非、最後まで読んでみてください。 Project Libertyが掲げるインターネットやウェブの課題 Project Libertyは広告によるマーケットの活性化自体には反対しておらず、ユーザーが自分のデータに関する所有権を持ち、かつコントロール出来るインターネットに価値があると捉えています。 Project Libertyは、現在のwebインフラには以下の課題があると提言しています。 Facebook等のプラットフォーマーが個人のデータ、およびデータの価値を独占している実状 広告収益モデルにより、注目を浴びやすい過激なコンテンツが優先され、運営企業側には金銭的ベネフィットがあることにより、公衆的な利益が軽視されがちなこと アルゴリズムの設計により分極化されたコンテンツが推奨され、社会分裂が加速されていること それらのアルゴリズムが企業の戦略的優位性となり、透明性が欠如している。それにより、民主主義が脅かされていること 現在のウェブが公営や安全性を基盤に設計されておらず、規制や微修正で修繕することには限界があり、且つ長い時間がかかること Project Libertyの創業者は、上記を示す内容として過去に以下のコメントを述べました。 "「世界中の人々の個人データにより、前例のない価値が生み出されているにもかかわらず、価値を生み出した人が恩恵を受けられていない現状は問題である。」"- Frank McCourt氏 “An unprecedented amount of value is being created by everyone’s data. And yet there’s a total disconnect between the creation of that value and who receives it.” -Frank McCourt, founder of Project Liberty. Story via the WSJ/@patiencehaggin https://t.co/FwbMYk1jmf #web3 #technews — Unfinished Labs (@unfinishedlabs) December 6, 2021 https://twitter.com/unfinishedlabs/status/1467925129988509699 Frank McCourt氏はProject Libertyに合計で1億5千万ドルの財源を開発団体やエコシステムに投資するとしており、非営利的なイニシアティブに加わってくれる協力者を募っています。 Project Libertyについて Projecty Libertyは、次世代の新しいWebインフラストラクチャーの構築を目指しているプロジェクトです。 Project Libertyチームは既存のウェブやSNSにおけるプライバシーの侵害や収益モデルに課題を感じ、社会に健全なインターネットを構築するため、Frank McCourt氏のビジョンを元に結束しました。 web2.0の仕組みの根源であるユーザーのデータを活用した広告モデルビジネスや一部のプラットフォーマーが独占している現状を打破するとともに、収益化を優先したインターネットの仕組みの正常化をコアな目的としています。 Project Libertyのアプローチ Project Libertyは非営利団体として位置づけられており、目的を達成するために以下の3つの柱を定義しています。 ・テクノロジー ・ガバナンス ・ムーブメント 以下でそれぞれ紹介していきます。 テクノロジー Project Libertyの技術チームが開発する、次世代のインフラとなる新しいオープンソースプロトコル 「DSNP(分散型ソーシャル・ネットワーキング・プロトコル)」はProject Libertyが目指すフェアなインターネットにおいて、非常に重要な役割を果たします。https://www.dsnp.org/ データー所有権を保ったままプラットフォーム間で移動することができ、今までと同じ感覚でwebサービスを使うことが可能 一企業が恩恵を受けていた個人データによる経済的ベネフィットを全ての人が受け取ることが可能(Brave Browser のモデルに一部似た構想) サービスとは分離した非営利団体 (DSNP.org) が設計することにより、ユーザーファーストのモデルの維持が可能 DSNPについて:分散型アイデンティティ(自己主義)、データプライバシー、SNS情報(フィード)の整理方法を含むフレームワーク ガバナンス 現在のインターネットにおける課題を解決するために、Project Libertyは新しい技術に基本原則や安全性を事前に統合する必要があると述べています。 ガバナンスフレームワークを健全に開発するために、技術者と社会科学者を招集し、 McCourt研究所が設立されました。 [caption id="attachment_81326" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:projectliberty.io[/caption] McCourt研究所は倫理的テクノロジーの最先端を歩む Georgetown大学(ワシントンDC)と Science Po (パリ)を創業パートナーに迎え、デジタルガバナンスの統合を目指しています。テクノロジーの観点からだけでなく、社会科学者、倫理学者、および政策立案者などと協力し、包括的なフレームワークの設立を試みているようです。 Project Liberty の 目的を達成するために5千万ドルが10年におよびR&D費用や助成金としてあてられます。 ムーブメント Project Liberty はテクノロジーだけでは大規模な一般普及は難しいと考えており、同じ社会課題を掲げている様々なパートナーと健全なデジタル環境の普及を目指していきます。 テクノロジー、学会、アート等の領域に秀でる様々な公的機関や民間企業と共同で社会課題の包括的な解決方法を設計し、エコシステムに対してのサポートを得る Unfinished (DSNP開発元)が開催するUnfinished Live 等のイベントにおいて、テクノロジーやアート、社会アクティビスト等、幅広いメンバーが参加https://live.unfinished.com/ - Facebook の whistle blower として有名なFrances Haugen氏も参加 開発者を巻き込み、DSNPの倫理的なデジタルガバナンスの仕組みの教育により、DSNPを使用した新しいサービスを開発し、より多くの一般ユーザーの方にユーザーファーストの健全なデジタルライフを提供する取り組みを推進 ブロックチェーン選定プロセス Project Libertyはブロックチェーン発のプロジェクトではないものの、同技術が不可欠であると判断し2021年の10月からコミュニティ内でチェーンのセレクションが行われ、同時にProject Liberty のビジョンに共感するパートナーを募っています。 https://forums.projectliberty.io/t/about-chain-evaluation/230 上記で紹介したDSNPの実験台としてイーサリアム上で実装されていましたが、取引コストが高い点とマージの日程が当時不明確だったため、DSNPの本格実装チェーンの選定が開始されました。 以下の判断基準を軸にチェーン選定が行われました。 分散性:分散型ノードがリレーするチェーンの情報に仕組み上関心がないこと コスト:金銭的なコストおよび、環境に対してのコスト。言い換えるとPoWではないこと オープンソース:セキュリティ、汎用性、および持続性の観点から重要である メインネット:ビルドを開始できる環境であること アクティブで責任感のあるデベロッパーコミュニティ:初心者デベロッパーに対してのデベロッパーコミュニティの姿勢 [caption id="" align="aligncenter" width="480"] 2022年1月時点での8つの候補ブロックチェーン[/caption] 30以上のブロックチェーンのメリットデメリットを考察・精査し、最終的にポルカドットがDSNPのベースチェーンとして選定されました。 [caption id="" align="aligncenter" width="530"] 右:Frank McCourt氏 - McCourt Global CEO、左:Gavin Wood氏 - Polkadot 創業者 | 写真:Web3 Foundation[/caption] DSNP活用のファーストステップ DSNPを活用した新しいSNSの第一弾としてFrequencyという新しいSNSが今後ポルカドットのパラチェーンとしてローンチされる予定です。 McCourt Globalによるテクノロジービジネスユニットの Unfinished Labsにより開発が手がけられており、Project Libertyエコシステムにおいて始めてのブロックチェーンの活用事例となります。 https://www.coindesk.com/tech/2022/06/29/meet-frequency-polkadots-new-decentralized-social-media-parachain/ Frequencyを通じてFrank McCourt氏やUnfinished Labsのプレジデント Braxton Woodham氏(DSNPのリード設計者)、その他大勢の思い描いている健全なインターネットの第一歩を踏み出すとしています。 Project Liberty チームの紹介 Project Liberty は独立した非営利団体ですが、McCourt Globalの様々なビジネスユニットがProject Libertyの開発にかかわっています。 Project Liberty創立者、McCourt Global, CEO - FRANK McCOURT Frank McCourt 氏はMcCourt Global - Family企業のCEOであり、数々の不動産、スポーツ、テクノロジー、メディアや金融ビジネスを運営しており、フランスのサッカークラブの Olympique de Marseille の現オーナー、ベースボールチームLos Angeles Dodgersの元オーナーとして幅広く知られています。 彼は数々の学問、民政、文化研究期間のサポーターであり、Project Libertyの創立者です。Project Libertyの重要な一角であるDSNPを通じ、社会全体に健全なオープンソースSNSフレームワークを提供。自身の幅広い人脈によるパートナーシップや研究資金を元にインターネットのガバナンスモデルをユーザーファーストな視点で構築する取り組みを進めています。 Labs, President - BRAXTON WOODHAM Braxton Woodham氏は Unfinished Labのプレジデントであり、DSNPの開発の第一人者です。 彼はテクノロジーの分野において20年間の長い経験を持っており、過去にはFandangoのCTOおよびCPOとして活動していました。又、アメリカ空軍に属し、キャプテンの称号を有していました。 McCourt Institute, Inaugural Executive Director - SHÉHÉRAZADE SEMSAR-DE BOISSÉSON Shéhérazade Semsar氏は2021Inaugural Executive Director として、2021年にMcCourt Instituteに入社しました。プログラミングの監督、イベント開催の取り組みやProject Libertyに当てられる学術助成金資金のとりまとめ等、幅広く活動しています。 彼女は2015年から2021年まで、POLITICO Europeという中立的なメディアのCEOを勤め、強いリーダーシップを発揮し、同社をヨーロッパにおけるトップの出版会社に導きました。 Unfinished, President - PAULA RECART Paula Recart氏はUnfinishedのプレジデントであり、McCourt Globalの社会的影響における取り組みを監督しています。2019年から McCourt Global に在籍しています。 彼女は以前12年間 社会起業家のネットワークを持つことで有名な Ashokaにおいて重要なリーダーシップポジションに就いていました。 考察 Project Liberty は現在のインターネットにおいての個人情報の扱かわれ方に課題を感じ、SNSの仕組みを根本から変えるという非常に大がかりなプロジェクトです。 GAFAを筆頭にプラットフォーマーが大きな力を持つことになり、利益を重視する株式会社というポジションがゆえに、より収益性の高いアルゴリズムが強行されることにより、民主主義が脅かされているという現状について強い課題意識を感じています。 筆者は、以下の理由でProject Libertyに注目しています。 ビジョン・ドリブンで社会課題に向けた解決策に取り組んでいる点。ブロックチェーンを使ったフレームワークを作ることが目的なのではなく、インターネットの健全化という目的を達成するためにブロックチェーンの技術を活用している。 Franc McCourt氏および、複数の関連団体から多額のファンディングを受けており、多くのWeb3プロジェクトが資金調達に重きを置いている中、公的利益を重視している点。 リサーチドリブンなアプローチで、コミュニティを巻き込み、ブロックチェーンを選定。様々なチェーンの特性を考慮した後、最終的にポルカドットを選んでいる点。 テクノロジー視点だけでなく、社会科学、倫理学の視点を取り組んだ包括的なフレームワークを設計しており、その分野の様々なエキスパートを巻き込んでいる点。 今後のポルカドット・パラチェーンオークションにおいてFrequencyがパラチェーンになる可能性がある点。 Facebookに対してのFrances Haugen氏の内部告発が記憶に新しいところですが、プラットフォーマーの問題に対しての課題意識をお持ちになられている方は多いのではないでしょうか? 近年DeFiやGameFiをはじめとしたユースケースは主流になりつつありますが、今後はソーシャル分野のBIGプロジェクトが出てきてもおかしくない頃だと認識しています。 まとめ インターネットやウェブの課題解決を目指すプロジェクト「Project Liberty」について解説してきました。 今回紹介したProject Libertyは、既存プロジェクトと比較してもより本質的なアプローチをしているように感じられます。 本記事を読んで興味を持った方は、是非下記公式リンクより最新情報をキャッチアップしてみてください。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 - 公式リンク - Project Liberty - https://www.projectliberty.io/ McCourt Institute - https://mccourtinstitute.org/ Unfinished - https://www.mccourt.com/projects/unfinished https://twitter.com/byUnfinished Unfinished Labs - https://www.unfinishedlabs.io/ https://twitter.com/unfinishedlabs

プロジェクト
2022/09/20Phiとは?概要や特徴、使い方を解説 | ENSで独自メタバースを構築
2022年8月30日、独自メタバースを構築できるWeb3プロジェクト「Phi」がPolygon Mumbaiテストネットでローンチしました。 https://twitter.com/phi_xyz/status/1564402546642366464?s=20&t=HfQiq01iV68fjH8LFX9wgQ 2つのハッカソン (NFTHACK2022 & BuildQuest)で入賞したPhiには、ENS(イーサリアムネームサービス)とオンチェーンのアクティビティで独自メタバースランドを無限に作成できるといった特徴があり、既存メタバースプロジェクト(The Sandbox等)とは異なるアプローチを取っています。 本記事では、そんな注目プロジェクトPhiの特徴や実際の使い方まで解説していきます。是非最後まで読んでみてください。 Phi = ENS × オンチェーンアクティビティのメタバースプロジェクト Phiは、ENSのドメインやオンチェーンアクティビティによってメタバースを構築する事が出来るプロジェクトです。 ENSのドメインがメタバースの土地の役割を担うPhiでは、ウォレットのアクティビティ(実績やステータス)によって、オブジェクト(アイテム)が付与される仕組みが採用されており、付与されたオブジェクトをメタバースランドに装飾・配置し独自の世界観でメタバースランドを自由にカスタマイズ出来ます。 メタバースで土台となる土地の所有権をENSのドメインを用いて保有出来るPhiプロジェクトですが、ENSのドメインを用いた理由を下記のように述べています。 "「人々のオンチェーン ID に関連する最も分散化された一般的な資産であるためです。他のメタバース ランド NFT プロジェクトのように、非常に高価な NFT を購入した所有者だけがプレイできる独占的なものにしたくはありません。私たちは、web3 のメタバースはより分散化され、誰にでも開かれているべきだと考えています。これが、土地の生成に ENS を使用する理由です。」”- 出典:Introducing Phi, Visualizing Your Web3 World that evolves with your On-Chain Activities Phiは、オンチェーンアイデンティティを可視化し、ENSドメインやウォレットアクティビティといった普遍的なWeb3を構成している要素に基づく包括的なメタバースランドシステムの構築をプロジェクトのミッションとして掲げています。 Phiのチームメンバーについて Phiのコアチームメンバーは、多くの日本メンバーで構成されています。 Co-founder & CEO Shugo Co-founder & COO Consome Co-founder & CTO Zak Frontend engineer Oji3 Pixel artist eboy Pixel artist ta2nb Pixel artist Fuzuki UI/UX designer Oz Backend engineer J Growth Litchman 共同創業者のShugo氏は、This Week in DAOsの共同創設者であり、DAOを構築、追究している業界の創設者や投資家をゲストとして招き、ポッドキャストを行ったりニュースレターの配信を行っています。 また2022年6月22日には、ピクセルアートのゴットファザーであるeBoy氏がコアメンバーとして加わりました。 https://twitter.com/eBoyArts/status/1532150443308027904?s=20&t=INmcwiJBLmpTf0rp6KCPgQ eBoyは世界的ブランドであるPaul SmithやBalenciaga等とコラボしてきたバックグラウンドがあり、web3領域ではNFTをベースとしたオンチェーン・アバターコミュニティNounsを共同設立し、有名ピクセルアーティストとして名高い人物です。 Phiとコラボレーションの申し込みも行える Phiの公式サイトにコラボレーションの募集フォームが設置されています。 プロトコルのオブジェクト作成 共同マーケティング Twitter スペース その他の統合 などを希望する方は募集フォームに記載の上、コラボレーションを申し込めるようになっています。 質問があればメールアドレス宛へ送る事も出来るようなので興味のある方は是非チェックしてみてください。 Phiの始め方を解説 Phiを始めるにあたり、 サポートされているウォレット(メタマスク、コインベースウォレット、ウォレットコネクト) テストネットトークン ENSドメイン 上記3つが必要となります。 本記事では、メタマスクを利用して解説してきますが、メタマスクのウォレットのインストール方法や使い方に関しては下記の記事を参照してください。 MetaMask(メタマスク)の使い方まとめ!入出金・トークン追加も超簡単 また、テストネットトークンであるMATICは 、Mumbai テストネットへ自動で付与されますが、必要に応じて下記リンクからご自身で請求してみてください。 ・MumbaiテストネットのMATICを取得 ・GoerliテストネットのETHを取得 ENSドメインに関しては下記の手順に沿って取得していきましょう。 ①ネットワークにPolygon Mumbai Testnet、Goerli Testnetを表示する ②PhiにMetaMaskを接続する ③ENSのドメインを取得 ①ネットワークにPolygon Mumbai Testnet、Goerli Testnetを表示する メタマスクの設定のカテゴリーに「高度な設定」があるので「テストネットワークを表示」をONにします。 イーサリアムのネットワーク一覧にあるPolygon Mumbai Testnet、Goerli Testnetが表示されている事を確認しましょう。 確認をとれましたらテストネットワークの表示が完了です。 ②PhiにMetaMaskを接続する 公式サイトにアクセスをしましたら「open app」をクリックしてください。 ウォレットを接続するので画面の右上にある「connect」をクリックします。 接続するウォレットが表示されましたらメタマスクをクリックしましょう。 接続は完了です。 ③ENSのドメインを取得 メタバースを構築するにあたってENSのドメインが土地になりますので、ENSのドメインを取得する必要があります。 ENSのドメインを既にテストネット上で保有していると土地の画面に切り替わりますが、本記事の解説ではENSのドメインをテストネット上で保有しておらず、直ぐにドメインを取得したいので「get ENS quickly」をクリックします。 Ethereum Goerli Testnet で ENS ドメインを所有する際は、下記を参考にしてみてください。 ⇒Goerli TestnetでENSを取得する テストネット用のENSドメインである「~phidemo.eth」を取得出来ます。 ENSドメインを設定しましたら「create land」をクリックします。 接続しているメタマスクで取引を確認します。 更新中は待機しておきましょう。 メタマスクが起動するのでトランザクションの承認をクリックするとプロダクトを触れるようになります。 Phiの使い方 メタマスクの接続&ENSドメインの取得を出来ましたのでメタバースランドを構築出来る様になっています。 どのように独自のメタバースランドを構築出来るのか解説していきます。 ①オブジェクトをショップで購入 ②オブジェクトをメタバースランドで配置出来るようにする ③メタバースランドを装飾してみる ④Twitterで自分のメタバースランドを共有 ⑤オブジェクトをウォレットへ撤退する ⑥クエストを行いオブジェクトを請求する ①オブジェクトをショップで購入 オブジェクトをショップで購入する事が出来ます。 テストネットでは、フリーのオブジェクトを入手出来るので、ホーム画面のショップをクリックして試しに入手してみましょう。 購入したいオブジェクトがあれば、「add to cart」をクリック。そして、いくつ購入するか数量を決めて「purchase」をクリックします。 今回は、Phiのロゴがついているストリートを選択してみました。 メタマスクが起動するのでトランザクションの承認を行いオブジェクト(ストリートPhi)を手に入れましょう。 購入したオブジェクトは、ウォレットで保管されるので確認してみてください。 以上がオブジェクトをショップで購入する手順です。 ②オブジェクトをメタバースランドで配置出来るようにする ウォレットに預け入れたオブジェクトをメタバースランドで配置できるようにしていきます。 オブジェクトは、合計3点を揃えてみました。 オブジェクトをウォレットからメタバースランドへ移行するので、ウォレットのアイコンをクリックします。 移行したいオブジェクトを選択し「deposit」をクリックします。 メタマスクが起動するのでトランザクションの承認を行い、オブジェクトをメタバースランドで配置出来るようにします。 ③メタバースランドを装飾してみる それでは、Phiの醍醐味であるメタバースランドにオブジェクトを装飾していきましょう。 「edit」をクリックします。 装飾できるオブジェクト一覧が表示されるので、装飾したいオブジェクトをクリックしてメタバースランドへ移動させましょう。 実際に用意したオブジェクト3点をメタバースランドに装飾してみました。 装飾を完了する時は「keep」をクリックしてメタマスクが起動するのを待ちトランザクションの承認を行います。 メタバースランドのデータがブロックチェーンに保存されランドのイメージが更新されます。 ④Twitterで自分のメタバースランドを共有 作成したメタバースランドをTwitterで必ず共有する必要はありませんが、プロダクトを初めて触った際のガイドにTwitterで共有してみましょうと案内が出ていたので、実際に作成したメタバースランドをTwitterで共有してみました。 https://twitter.com/badhop0603/status/1571171318242115584?s=20&t=2XLwZPwpqx6jVcBoPCfILg ツイート内にアップされているリンクは、直接メタバースランドへアクセス出来るENSドメインになっています。 このように自分が作成したメタバースランドをTwitterのフォロワー様へ公開する事が出来ます。 ⑤オブジェクトをウォレットへ撤退する メタバースランドで装飾していたオブジェクトの撤退手順を行っていきます。 まず「edit」をクリックします。 Twitterツリーをメタバースランドから撤退してみますので削除アイコンをクリックします。 LANDに撤退したことを確認します。 「save」をクリックするとメタマスクが起動するのでトランザクションの承認を行います。 続いてランドのアイコンをクリックします。 Twitterツリーを撤退してみますので「withdraw」をクリックします。 ウォレットにTwitterツリーが撤退されているのを確認出来ます。 以上でオブジェクトをウォレットへ撤退する手順です。 ⑥クエストを行いオブジェクトを請求する クエストで手に入るオブジェクトの一覧、クエストの詳細をみてみましょう。 まず、「quest」をクリックします。 このようにクエストの一覧が表示されます。 今回はこちらのPHI Cabのクエストを行ってみたいと思います。 クリックするとオブジェクトを請求できる要件が記載されていますので確認しましょう。 PHI Cabのオブジェクトを取得出来る要件は、「自分の土地に異なるphi landのハイパーリンクを1つ作成する」とのことです。 一見難しそうな上記クエストですが、同じようにPhiのメタバースランドを構築しているユーザーの土地のリンクを何らかのオブジェクトに貼り付ければOKです。 つまり、上記クエストではリンクを貼り付けたオブジェクトを通して、他のユーザーが構築するメタバースランドにアクセスする事が出来る機能が紹介されています。 こちらの要件をクリアするためには、Phiのディスコードに「share-ur-land」というカテゴリーがあるので、シェアしているユーザーの土地リンクを借りるか、Phiのプロダクトを触っている知人から土地のリンクを教えてもらうことで要件を満たす事が出来ます。 ハイパーリンクの貼り付け方は、土地の編集の画面でオブジェクトにカーソルを合わせてクリックするとオプション表示がされますので、真ん中のリンクをクリックします。 「タイトル」と「土地のURL」を入力してチェックマークをクリックします。 こちらのようにオブジェクトにリンクを貼り付ける事が出来ました。 ワンクリックでリンク先のメタバースランドへアクセスする事が出来ます。 続いて要件を満たしたことでオブジェクトの請求が出来る様になっています。 詳細画面を表示し「claim」をクリックしましょう。 トランザクションの承認を終えるとウォレットにオブジェクトのPHI Cabが付与されているのが確認出来ます。 以上でクエストを行いオブジェクトを請求する手順です。 Phi Connectを使用するとランドを接続して、好きな世界観を構築することが可能です。Phi Connectについてはこちらの記事で解説しておりますのであわせてご覧ください。 メタバースプロジェクト「Phi」ランドを繋げる機能「Phi Connect」を公開 Phiのロードマップ Phiはこれまでに、2022年1月のNFTHACK2022 でENS賞を受賞。 2022年3月にはBuildQuestでIPFS/Filecoin & Covalent 賞を受賞し、同月にはStarkNet Goerli テストネットで最初のデモを開始しました。 次いで8月にMumbai Testnetで2番目のデモが開始となったPhiは、今後のロードマップとして下記を掲げています。 公開されている今後のロードマップ ・2022 年11月:Polygon mainnetでPhi をローンチ ・2022 年 12 月~ 2023 年第 1 四半期 :初期のコミュニティに向けた大規模なイベント 2022年11月にユーザー待望のメインネットローンチに加え、年内から来年である2023年第一四半期までに大きなイベントを開催するとのことで、Phi Landの住人やPhiプロジェクトにとって大きく変化が起きる時期となりそうです。 プロダクトを触ってみた感想 市場に出回るメタバースプロジェクトには、プロジェクトが土地をユーザーへ販売するのが一つのキャッシュポイントとなっており、それらを踏まえて転売目的で土地を買うユーザーもいるのが現状です。 Phiのプロダクトを触ってみて、ただ利益を求めて土地を保有や売買を行うのがメインの目的ではなく、ENSのドメインがあれば無限にメタバースランドを作る事が出来て、さらにウォレットのアクティビティによってオブジェクトを追究でき、独自の世界観を創造できる思想と設計がまさにweb3という印象を受けました。 またクエストの難易度に応じて取得出来るオブジェクトもグレードアップしていくことから、純粋にメタバースを楽しむ探求心がくすぐられ、特定のオブジェクトに他のユーザーの土地リンクを貼り付けるハイパーリンク機能があることで、Phiユーザー同士が繋がるメタバース空間が実現されていると感じました。 メタバースプロジェクト「Phi」がCC0を発表 まとめ ENSドメインに関連させてメタバースを構築できるプロジェクトPhiについて解説してきました。 昨今、The SandboxやDecentralandに様々な大手企業や著名アーティストが参入する事例が増え、世の中全体がメタバースの最適解を探っているなか、独自のアプローチをとるPhiは是非今後も注目したいプロジェクトです。 本記事を参考に是非一度実際にあなたもプロダクトを触ってみてはいかがでしょうか。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 ―Phiの公式リンク― Webサイト: https://philand.xyz/ Web app : https://mumbai.philand.xyz/ Twitter:https://twitter.com/phi_xyz blog:https://medium.com/@phi.xyz discord:https://discord.gg/BNNF2KUYg5 github:https://github.com/PHI-LABS-INC

プロジェクト
2022/09/12Oasysとは?ゲーム特化型ブロックチェーンの特徴や概要を解説
ゲームに特化したブロックチェーンを展開するOasys。 Oasysは「利用者のガス代が無料になる」「特定の環境下のみで利用可能なNFTを発行できる」など、独自のアプローチでブロックチェーンゲーム体験の向上を目指しているプロジェクトです。 2022年7月には2,000万ドルを超える資金調達にも成功しており、今注目のブロックチェーンの1つです。 Oasys successfully completed a private token sale round of USD20 million led by Republic Capital, blockchain financing and investment platform, with participation by other renowned investors. 🎉 1/3 pic.twitter.com/AxvnZQfqH5 — Oasys🏝Blockchain for Games (@oasys_games) July 6, 2022 本記事では、そんなOasysの概要・特徴・注目したい仕組みなどについて解説しています。 記事の内容まとめ ・ゲームに特化したブロックチェーン ・利用者はガス代無料で利用可能 ・WEB2レベルのレスポンス ・IP保護を意識したNFTを作成可能 ・ヴァースを構築することによる柔軟な開発が可能 Oasysとは?= ゲーム特化のブロックチェーン Oasysは、ゲームに特化したブロックチェーンやプロジェクトの総称です。 ゲームに特化しているということもあり、現状のブロックチェーンゲーム(以下:BCG)に関する課題や問題点を解決することに焦点をおいたプロジェクトです。 注目度の高いトピックの1つであるBCGですが、既存チェーンを利用したBCGには現状以下のような課題があり、Oasysはこれらの課題の解決を目指しています。 利用者の参入障壁 DeFiと比較して膨大なトランザクションを高速に処理できない 著名なIPを保有するような開発サイドのさまざまなリスク また、Oasysには著名企業が多数参画しており、初期バリデーターには、仮想通貨やエンタメ・ゲーム関連の企業を中心に以下のような企業が参画しています。 ASTAR BANDAI bitFlyer GREE UBISOFT SEGA PlayArt SQUARE ENIX 既に著名なIPを保有している大手企業も参加し、国内企業も多く参画している傾向が分かるでしょう。 今後もバリデーターに限らず、さまざまなレイヤーで著名な企業の参画が見られるかもしれません。 BCGを進化させるOasysの3つの特徴 ・利用者のガス代が不要 ・高速なレスポンス ・開発者サイドのリスクを回避 BCGを進化させるOasysの特徴について、上記3つの観点から解説していきます。 OasysがBCGをより進化させるために備えている特徴をチェックしていきましょう。 利用者のガス代が不要 Oasysでは、利用者(エンドユーザー)によるガス代の支払いが、原則不要になります。 そのため、利用者はゲームをプレイするために、ガス代などに用いる初期費用を用意する必要がありません。 現状のBCGの多くは、ガス代の支払いなどに伴って初期費用が必要になっており、一般的な利用者にとって大きな参入障壁となります。 ガス代など、運用に関わるコストの多くはヴァースレイヤー(後述)が負担することになります。 高速なレスポンス Oasysでは、1秒未満で完了する大量のトランザクション処理を可能にしています。 現状のチェーンでは、トランザクションが通るまでに数秒〜数十秒ほどの時間が発生します。 このタイムラグは、一般のWeb2のゲームをプレイする利用者にとって大きなストレスになる可能性が高いです。 そのため、OasysではWeb2と同等程度のレスポンスを可能にする設計を行っており、一般の利用者でもストレスを感じない体験ができます。 開発者サイドのリスクを回避 Oasysは、著名なIPを保有する従来の企業が懸念するリスクを払拭しています。 現状のBCGやNFTといった領域への参入は、既存のIPを持つ企業や開発者などにとっては、大きなリスクを抱えています。 その1つが、レピュテーションリスク(ネガティブな評判・風評など)です。 これは、ブロックチェーンが持つ誰にでも開かれたパーミッションレスという特性が要因となっています。パーミッションレスであるがために、現状のWEB3には魅力的なプロダクトが存在している一方で、詐欺的なプロダクト・プロトコルも多く存在しているのが現状です。 上記のような環境では、IPを保有する従来の企業が参入は、評判や風評に対する一定のリスクが含まれます。 また、NFT化した際のIP保護といった問題も存在しています。 上記のような既に魅力的なIP・コンテンツを持つ企業の参入を阻む要因を、さまざまなアプローチでOasysでは克服しています。 高品質な体験を提供するOasysの仕組み 次に、前述したような特徴を実現するOasysの仕組みについてチェックしていきましょう。 Oasysの仕組みで注目なのが多層的な構造を持っている点です。 Oasysでは、以下のように複数のレイヤーが存在しており、各レイヤーがそれぞれ重要な役割を担っています。 アプリケーション ヴァースレイヤー(Verse Layer) ハブレイヤー(Hub Layer) 各レイヤーを、1つ1つチェックしていきましょう。 アプリケーション 具体的にOasysのホワイトペーパーなどで、明記されているレイヤーではありませんが、利用者にとって最も身近なレイヤーがアプリケーション(Dapps)です。 実際にOasysに構築されたゲームなどのアプリケーションを指し、一般的な利用者が認識するのはこちらのレイヤーになるでしょう。 ヴァースレイアー(Verse Layer) Oasysにおけるヴァースレイヤー(Verse Layer)は、前述したようなDapps(ゲームなど)を構築しているレイヤーになります。 ヴァースの基本的な役割は、Dappsなどで発生したトランザクションをOpsitimic ロールアップを用いて処理を行うといったものです。 100万OASをデポジットすれば誰でもヴァースの構築が可能で、構築された各ヴァースは構築者(Verse Builder)によって自由にカスタマイズできます。 具体的にはヴァースの構築者は、 ヴァース上のさまざまな権限を制限 構築されるDApps自体の制限 といったことが可能。ヴァースの構築者の任意で、パーミッションレスな環境にすることも出来ます。 各ヴァース自体は許可型(Permissioned)といった環境を構築することも可能で、これによりヴァースの構築者・管理者は、 権限を用いて詐欺のようなプロジェクトを排除 自社の限られたDappsだけが構築される排他的なヴァースを構築 といった運用も行えます。 また、ゲームの中でもFPS・RPGといったジャンル別のヴァース、DeFi向けのヴァースといったように構築されるプロダクトに合わせたヴァースが構築されるといった可能性も考えられるでしょう。 ハブレイヤー(Hub Layer) Oasysのハブレイヤー(Hub Layer)は、前述したようなOasysエコシステム全体を司る基礎のようなレイヤーです。 ハブレイヤーは、ヴァースレイヤーのように細かなトランザクションの実行・処理などは行いません。 そのため、ハブレイヤーが処理するトランザクションは、ヴァースレイヤーと比較して限定的です。 その代わりに、Oasysのエコシステム全体に関わるような以下のような処理やデータの管理をハブレイヤーで行います。 ロールアップのデータの管理 FT/NFTの管理 ブリッジの管理 前述のとおり、OasysのヴァースレイヤーはOpsitimic ロールアップを使用しており、ロールアップで処理されたデータはハブレイヤーに記録されます。 上記のヴァースレイヤーとロールアップはハブレイヤー上に構築されているため、各ヴァースがダウンしたとしてもハブレイヤーからデータにアクセスすることが可能です。 その他にも、ハブレイヤーではNFTや各チェーン上を行き来させるブリッジの管理などを行います。 ハブレイヤーでのコンセンサスアルゴリズムにはPoSが採用されており、1,000万OASのステーキングで誰でもバリデーターになれます。 Oasysと3種類のトークンの概要 ヴァースレイヤーのみのトークン(vFT/vNFT) 相互運用性の高いトークン 外部のトークン トークンの柔軟な運用を可能にするために、Oasys内では上記3つのトークンが扱えます。(いずれも、FT・NFTを含む) 各トークンごとに、特性が異なっているので一つ一つチェックしていきましょう。 ヴァースレイヤーのみのトークン(vFT/vNFT) Oasys内で、もっとも特徴的なトークンとなっているのが「vFT/vNFT」と呼称されているトークンです。 vFT/vNFTは、ヴァースレイヤーで作成可能となっており「特定のヴァースでしか利用できない」という特徴を持っています。 そのため、他のヴァースで利用できないのはもちろん、他のチェーンへのブリッジなどに対応していません。 実際のユースケースとしては、ゲーム内通貨(FT)やIP(IP)などが想定されているようです。 vFT/vNFTが存在することで、IPが載っているNFTなどを意図しない用途に利用させないなど、NFTの運用におけるIP保護などに応用できます。 例えば、IP保護を重要視する企業が特定のヴァースを構築し、なおかつ特定のヴァースでしか利用できないNFTを作成するといった運用が可能になるかもしれません。 相互運用性の高いトークン(oFT/oNFT) oFT/oNFTは、ハブレイヤーで作成される相互運用性の高いトークンです。 oFT/oNFTは、Oasysに構築されたさまざまなヴァースで利用可能なのはもちろん、他のチェーン(イーサリアムなど)で利用することもできます。 一般的にトークンと言われて、思い当たるのがこのタイプになるでしょう。 oFT/oNFTとvFT/NFTの両者を活用することで「一部のゲーム要素・トークンのみを外部にもオープンにする」といった柔軟な運用が可能になります。 外部のトークン(exFT/exNFT) 最後のOasysで利用できるトークンが「exFT/exNFT」です。 こちらは外部のチェーンで作成されたトークンで、例えばイーサリアムで作成されたFT/NFTのような存在にあたります。 外部のトークンは、ハブレイヤー・ヴァースレイヤーともに利用可能となっており、Oasys内のエコシステムで自由に利用することができます。 OASとトケノミクス Oasysのネイティブトークンは、OASです。 OASの初期の供給は、100億OASに設定されており、各用途ごとに以下の割合が設定されています。 38% エコシステムとコミュニティ 21% ステーキング報酬 15% 開発 14% プライベートセールでの投資家 12% 財団(Oasysをサポートする) 長期的な成長と持続可能性を重視し、OASは段階的に供給されていきます。 ネイティブトークンのため、OASはOasysエコシステムの中核となる存在で、Oasys内におけるさまざまなアクションに対してOASが必要になっています。 一例になりますが、OASには以下のような用途が存在しています。 ガス代 ヴァース構築(100万OAS) ガバナンス PoSでのバリデーターになる(1,000万OAS) エコシステム内での支払い(ゲームアイテムの購入など) さまざまな用途が設定されていることが分かるでしょう。 Oasysの将来性・今後の計画 Oasysは、最終的にDAOによって管理されるパブリックブロックチェーンになることを目指しています。(目標は6年) その最終的な形態に向けて、期間ごとの目標が設定されたロードマップが公開されているので、これを参考に期間ごとのイベントをチェックしていきます。 〜2023年まで Oasysは、2023年6月までに以下のような目標を掲げています。 CEXでの上場 メインネットのローンチ Oasys内でのプロジェクト数 20以上 Oasys内での分散型IDの数 100万以上 2023年までの焦点は「ローンチ」と「トークンの配分」という2点に当てられているようです。 今後、Oasysが成長していくための基礎を作っていく時期であると言えるでしょう。 2023年〜2024年まで Oasysでは、2024年6月までに以下のような目標を掲げています。 Oasys内でのプロジェクト数 100以上 Oasys内での分散型IDの数 1,000万以上 2023年〜2024年までの期間は、主にエコシステムの成長に焦点を当てているようです。 2024年〜2025年まで Oasysでは、2025年6月までに以下のような目標を掲げています。 Oasys内でのプロジェクト数 1,000以上 Oasys内での分散型IDの数 1億以上 2024年〜2025年までの焦点は、大衆に受け入れられるというのがテーマのようです。 そして、最終的には前述の通り、2028年程度を目処にDAOとして機能することを目標にしています。 Oasysについてまとめ この記事では、Oasysについてさまざまなポイントから解説しました。 仮想通貨周りのプロジェクトやトピックは、海外を中心としたものであることが少なくありませんが、Oasysは珍しく多数の国内企業が関わっています。 Oasysと相性の良さそうな企業も多数参画している様子が垣間見れるので、今後も注目していきたいと言えるでしょう。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 -Oasys公式リンク- Webサイト:https://www.oasys.games/ ホワイトペーパー:https://docs.oasys.games/docs/whitepaper/intro ツイッター:https://twitter.com/oasys_games ディスコード:https://discord.com/invite/oasysgames Medium:https://medium.com/@oasys

プロジェクト
2022/09/02Polygon(ポリゴン)・Matic Networkとは?概要や特徴、使い方を解説
Polygon(Matic)は、イーサリアムをスケーリングさせるL2ソリューションの1つです。 Polygonを利用することで、処理性能の向上やガス代の大幅な圧縮が可能となり、DeFiなどの利用に伴うハードルを下げることが可能です。 また、Polygonには3万を超えるdAppsが構築されており、UniswapやAAVEなどの著名プロジェクトも比較的な安価なガス代で利用できます。 本記事では、そんなPolygonの概要・特徴・使い方などについて解説しています。 記事のかんたんまとめ ・PolygonはL2ソリューション ・サイドチェーンとPoSで高い処理能力を実現 ・1秒あたり7,000件のトランザクションを処理可能 ・ガス代を数十分の1に圧縮 ・数万件のdAppsが構築 Polygon(ポリゴン)・Maticとは?高い処理能力を持つL2ソリューション Polygon(Polygon Network / Matic Network)とは、イーサリアムと互換性を持つL2ソリューションの1つです。 L2ソリューションの中でも、PolygonはPlasma・PoSを採用したサイドチェーンに当たります。 そのため、Polygonを理解するためには、その前提となるL2ソリューションやサイドチェーンへの理解が不可欠になっています これから、Polygonの概要をバックグラウンドとなるトピックも含めて解説していきます。 L2ソリューションの概要 前述した通り、PolygonはL2 (Layer 2)ソリューションの1つです。 L2ソリューションとは、L1(イーサリアムなど)の性能を上げるためのソリューションのことを指します。 現在、多数のL2ソリューションが、さまざまな技術を用いて登場していますが、その背景としてイーサリアムの人気の高まりと性能の課題が挙げられます。 イーサリアム上でさまざまなアプリ・プロダクトが構築され、さまざまな取引が行われるにつれて、イーサリアムのブロックチェーンがパンクするようになりました。 具体的には、イーサリアムに取引が集中しブロックチェーンが適切に処理しきれないことから、取引が承認されるまで長い時間を必要としたり、ガス代(手数料)が高騰する事態が発生しました。 [caption id="attachment_79155" align="aligncenter" width="1024"] イーサリアムのガス代推移。盛り上がっている部分では一度の取引に数十ドルかかっているのがわかる[/caption] このような問題を解決するために登場したのが、L2ソリューションです。 L2ソリューションでは、L1(イーサリアムなど)とは別の場所で取引の処理を行うことでL1の負担を減らし、「処理性能の向上」や「ガス代の削減」を行えます。 L2ソリューションは、取引を処理する一連の仕組みごとにさまざまな種類が存在しますが、代表的な仕組みが以下の3種類です。 ステートチャンネル (RAIDEN、connextなど) サイドチェーン、Plasma (Polygon、OMGなど) ロールアップ (zkSync、Arbitrum Oneなど) Polygonは上記の中でも「Plasma」を採用しているL2ソリューションになります。(上記画像ではMatic = Polygonです) 他のL2ソリューションの概要や代表的なソリューションについては、コチラで解説しています。 PlasmaとPolygonの概要 L2ソリューションに続いて、Polygonを理解するためにもう一つ必要な前提知識であるPlasmaについて解説します。 前述の通り、PolygonではPlasmaが採用されています。 Plasmaでは、ルートチェーン(イーサリアムなど)とは別のチェーン(サイドチェーン)で、取引を処理し一部のデータのみをイーサリアムに返すことで、高い処理能力を実現します。 具体的には、一連の取引の流れなどを要約したデータのみをルートチェーンに記録し、取引の検証などはサイドチェーンサイドが担います。 Polygonでは、サイドチェーン(Polygon側)で行われた取引の検証・証明を行うために、コンセンサスアルゴリズムのPoSを採用しています。 安全性と高い処理能力を実現するために、取引を処理する流れに3つのレイヤー(役割)が存在しており、概要は以下のとおりです。 Polygonのスマートコントラクトのレイヤー (イーサリアム上に構築) PoSのバリデーターレイヤー (Heimdall) ブロックに取引をまとめるレイヤー (Bor) (実際の取引内容は、3から1にかけて集約・検証されていき、最終的に要約された内容がイーサリアムへ記録されます ) 中間の「2.PoSのバリデーターレイヤー(Heimdall)」は、「3.ブロックに取引をまとめるレイヤー(Bor)」にて生成されたブロックの検証、イーサリアムに記録するデータの作成などを担っているため、中核的な存在になっています。 また、PoSへのステーキングには、Polygonの独自の仮想通貨であるMATICが使用され、MATICはガス代の支払いなどにも用いられます。 Polygonを利用するときの全体的な流れ Polygonの仕組みは複雑に感じますが、実際に利用してみると難しいものではありません。 利用者観点から見たときに、Polygonを利用する際の全体の流れは以下の通りです。 イーサリアムからPolygon(Matic Network)へブリッジ Polygon上に構築されたサービスを利用 (不必要になったら)Polygonからイーサリアムへ再度ブリッジして出金 他のL2ソリューションやブロックチェーンを利用するときと、大きな違いは無いと言えるでしょう。 Polygon(Matic)の3つの特徴 ・1秒あたり7000件の処理能力と低コスト ・19億件を超えるトランザクション ・3万件超えのアプリと大規模なエコシステム Polygonの特徴について、上記の3点から解説していきます。Polygonの特別なポイントを押さえていおきましょう。 1秒あたり7000件の処理能力と低コスト Polygonの公式サイトでは、1秒間に7,000件のトランザクションを処理できると記載されています。 イーサリアムは15TPS程度のため、両者を比較すると高い処理能力を持っていると言えるでしょう。 また、ガス代についてもイーサリアムと比較して、〜1万倍低い水準(Polygon公式参照)で取引が可能で、1トランザクションあたりのコストは〜0.002ドルまで圧縮可能です。 19億件トランザクションを超える実績 polygonscanを参考にすると、これまで19億件を超えるトランザクション(取引)が確認できます。 それだけ多数の利用者・取引を抱えているということになります。 他チェーンのトランザクション総数は、BSCで約33億件(BscScan)、ETHで約17億件(Etherscan)です。他のチェーンと比較しても、引けを取らない実績があるといえるでしょう。 PolygonScan(ポリゴンスキャン)とは?概要や使い方を解説 3万件超えのアプリと大規模なエコシステム Polygonの公式サイトによると、37,000以上のアプリ(dApps)がPolygonを利用して構築されており、そのジャンルはゲームからDeFiまで多岐に渡ります。 また、Polygonは最もDeFiで資金がロックされているチェーンの1つです。 [caption id="attachment_79167" align="aligncenter" width="936"] 2022年7⽉版 CT Analysis DeFi マンスリーレポートより[/caption] タイミングによってSolanaと順位を行き来していますが、記事執筆時点でのDeFiにおけるTVLランクでTOP4にPolygonがランクインしています。(イーサリアムを除く) 上記のような背景から、多数のブロックチェーンが存在する中でも、Polygonは代表的なチェーンであると言えるでしょう。 Polygonに構築されたプロジェクト 前述の通り、Polygonでは多数のプロジェクトが構築されています。 一例として、DeFiにフォーカスを当ててみましょう。 以下が、Polygonに構築されている代表的なDeFiプロジェクトの一例になります。 AAVE (レンディング) Quickswap (DEX) Curve (DEX) Uniswap (DEX) イーサリアムと互換性を持つこともあり、既にイーサリアムにおいても多数の利用者を抱えているプロジェクトが多数確認可能です。 また、Polygonに構築されているプロジェクトは、DeFiに限りません。 代表的な例として、著名なBCGであるThe SandboxはPolygonへの移行を発表しており、イーサリアムからPolygonにトークンをブリッジする機能などが公開されました。 上記はあくまで一例で、この他にも多数のプロジェクトでPolygonへの移行や構築が発表されています。 Polygonの使い方(ブリッジなど) ①ウォレットと入金 (イーサリアム→Polygon) ②各サービスの接続と利用 ③Polygonからの出金 (Polygon→イーサリアム) これから、Polygonの使い方について上記のポイントから解説していきます。Polygonを利用できるようにしていきましょう。 ①ウォレットと入金 (イーサリアム→Polygon) Polygonを利用するには、はじめにPolygonのチェーン上で、仮想通貨を利用できる状態にする必要があります。 以下がかんたんな手順です。 ウォレットと仮想通貨の準備 ウォレットのネットワーク設定を済ませる イーサリアムからPolygonへ転送(ブリッジ) 上記の手順を完了することで、Polygon上で各仮想通貨が利用できる状態になります。 ウォレットのネットワーク設定やブリッジなどの細かな手順は、以下の記事で解説しています。 METAMASKでのMatic(Polygon)ネットワークへの接続方法を解説 ②各サービスの接続と利用 Polygonが利用できる環境が整ったら、Polygonに構築されているプロダクトを利用していきましょう。 基本的に、各プロダクトとウォレットを接続するだけで利用可能です。よくある流れは以下のとおりです。 利用したいサイトやプロダクトにアクセス ウォレットと各サイトを接続 機能やサービスを利用 前提となる環境(ウォレットなど)が整えば、イーサリアム上に構築されたプロダクトを利用するのと大きく手順は変わりません。 一例として、Polygonの代表的なDEXである「QuickSwap」の使い方を以下の記事で解説しています。 分散型取引所「QuickSwap」の特徴や基本的な使い方を徹底解説! ③Polygonからの出金 (Polygon→イーサリアム) Polygonからイーサリアムに資金を移動させる場合(出金)も、入金と大きく変わりません。 ①で説明した方法と逆の手順で、Polygonが提供するPolygon Bridge等でPolygon上の通貨をイーサリアムに戻します。 Polygonのブリッジには、入金・出金のどちらのケースでも、PoSブリッジ・Plasma ブリッジの2種類が存在しています。 双方にはセキュリティや対応している規格などに違いがありますが、利便性の観点などからPoSブリッジを選択することが一般的です。(PolygonもPoSを推奨) 一方で、Plasmaはよりセキュリティを重視する開発者向けのブリッジになっており、一般利用では触れることは無いでしょう。 Polygon(Matic)の将来性とリスク 最後に、Polygonの将来性やリスクについてチェックしていきます。 ・L2ソリューションとトレンド ・Polygon関連の他のソリューション ・予期せぬトラブルとリスク Polygonの今後の可能性と共に、注意点もチェックしていきましょう。 L2ソリューションとトレンド 現在、Polygonは非常に大規模なプラットフォームですが、将来的にその地位が保証されているのか?は不明です。 というのも、Polygonに限らず、現在多数のL2ソリューションが登場しており、潜在的に競合となり得る存在が多数存在しているためです。 例えば、ロールアップ系のL2ソリューションが注目を集めつつあります。 (ロールアップの1つであるArbitrum oneのTVL L2BEATより) 今後も、他のL2ソリューションと合わせて動向を見守っていく必要があるといえるでしょう。 ・L2ネットワーク「Arbitrum One」の概要や設定方法、基本的な使い方からリスクまで徹底解説! ・次の重要ワードか |「zkSync」の特徴や使い方を徹底解説! Polygon関連の他のソリューション PolygonのPoS・Plasmaを採用したサイドチェーンは、Polygonが提供するソリューションの1つに過ぎません。 その他にも、Polygonは多数のスケーリングソリューションを開発しています。 例えば、EVM互換を実現するゼロ知識証明を採用したロールアップ(Polygon zkEVM)なども開発しており、2022年Q3にテストネット、2023年初頭にはメインネットがローンチされる予定になっています。 今後、複数のソリューションが、Polygonから提供されていく可能性は高いでしょう。 予期せぬトラブルとリスク Polygonに限った話ではありませんが、仮想通貨関連のプロジェクトでは、潜在的なリスクが多数存在しています。 Polygonのホワイトペーパー(Matic network whitepaper)では、代表的なリスクとして以下のようなものが挙げられています。 各国の法規制と執行 競合の登場 開発の失敗 脆弱なセキュリティと攻撃 また、PolygonはイーサリアムのL2ソリューションであり、Polygonに入金した仮想通貨はイーサリアムネットワークへ出金することが可能です。 しかし、ブリッジ(入金した仮想通貨)した仮想通貨は、厳密にはイーサリアムで扱われている仮想通貨とは異なります。 Polygonに致命的な問題が発生した場合には、Polygonに入金した仮想通貨もリスクに晒される可能性があるという点は押さえておきましょう。 まとめ この記事では、Polygonについてさまざまなポイントを解説しました。 Polygonには、イーサリアム発のプロジェクトを含めて、魅力的なプロジェクトが多数構築されています。 ガス代の高さなどから、dAppsの利用をためらっていたという方も、Polygonなら気軽に利用できるかもしれません。 Crypto Timesでは、Polygon関連の最新ニュースなど、以下のようなPolygonに関するトピックも扱っているので是非読んでみてください。 InstagramがNFTシェア機能を実装 | EthereumとPolygonが対象 FilecoinとPolygonStudiosがコラボ。助成金やハッカソンで開発者を支援 Magic Eden、Polygonに対応 | 使い方の解説記事、動画を運営が公開 最後まで読んでいただきありがとうございました。

プロジェクト
2022/08/29分散型投資プロトコル「Syndicate」の概要・特徴について解説 | a16z、スヌープ・ドッグらも出資
2022年5月3日、「投資を民主化する」を使命に掲げる分散型投資プロトコル「Syndicate」が600万ドルの資金調達を実施しました。 https://twitter.com/SyndicateDAO/status/1521483151406600192?s=20&t=o7spfbLPlQbl5UCyLlxQzw Syndicateは1年間で2,800万ドルの資金調達を行ったプロジェクトで、自律分散型組織(DAO)として、コミュニティ主導で投資クラブの立ち上げが可能なプロダクトを提供しています。 「コミュニティ主導の分散型投資プラットフォーム」という従来の投資モデルを変えうるソリューションを提供するSyndicateですが、プロジェクトへの期待を裏付けるように、業界の著名人や企業による資金調達は数百名を超えています。 本記事では、そんなSyndicateの概要や特徴、注目プロダクトについて解説していくので是非最後まで読んでみてください。 「投資を民主化する」Syndicateの概要 Syndicateは、2021年2月にIan Lee、Will Papperによってサンフランシスコのシリコンバレーで設立されたプロジェクトで、「投資の民主化」を使命とし、投資の世界を変革する分散型投資プロトコル、ソーシャルネットワークを構築しています。 具体的には、コミュニティ主導で投資家から資金調達を行える公正で自由な新しい形の投資プラットフォームを提供しています。 「投資クラブ」の概念は、1898年にテキサスで行われた投資クラブが始まりとされていますが、Syndicateが構築する投資クラブは、コミュニティ主導でDAOのように資金調達や投資管理を行えることから、従来の資金調達より時間とコストを省く事が可能です。 Syndicateの3つの特徴 Syndicateの特徴を以下の3つの観点から解説していきます。各ポイントをチェックしていきましょう。 ・有名企業、著名人から合計2,780万ドルの資金調達 ・web3 Investment Clubがβ版でローンチ ・低コストで簡単に投資クラブの立ち上げが可能 有名企業、著名人から合計2,780万ドルの資金調達 Syndicateは5月に行われた戦略的ラウンドの他にも資金調達を行っており、a16z主導のシリーズA資金調達ラウンドでは、多数の投資家からの支援を受け、2,000万ドルを調達しています。 初期の投資家の数は150以上を超えていますが、その中でも暗号資産・ブロックチェーン業界では、グローバル最大手の米国企業Coinbaseの投資部門であるCoinbase Ventures、暗号資産の貸し借りを行えるDeFiレンディングプロトコルのAAVEなどが参加しています。 またヒップホップMC兼俳優であるSnoop Doggといった著名人も参加しており、クリエイティブを仕事としている層からも注目を浴びています。 web3 Investment Clubがβ版でローンチ Syndicate protocol上に構築された初となるプロダクトweb3 Investment Clubが1月26日にβ版としてローンチしました。 web3 Investment Clubは、イーサリアム、ポリゴンブロックチェーンで展開しており、MetaMaskなどのウォレットとSyndicateを使用して、ガス代のみで投資クラブを作成・管理出来ます。 7月12日に12,000の投資クラブが立ち上げられていましたが、7月22日には、20,000のクラブが立ち上がり、僅か10日で8,000のクラブが作成されています。 低コストで簡単に投資クラブの立ち上げが可能 Syndicateの投資クラブは、現在イーサリアムとポリゴンのブロックチェーンで展開されていますが、他のブロックチェーンや L2 に展開するための準備を積極的に進めているとのことです。 他のチェーンを触るユーザーにも投資クラブを立ち上げる機会を提供し、投資の民主化を拡大するべくインフラストラクチャを構築しています。 ちなみに7月6日のツイートによると、イーサリアムブロックチェーンで投資クラブを立ち上げるのに20ドルのガス費用を見積もっていたところ、ポリゴンブロックチェーンで投資クラブを作成した場合だと0.01ドルで出来たとのことです。 https://twitter.com/SyndicateDAO/status/1544335400516194304?s=20&t=Hj-rjagSIWsdT2i_FopN0w 投資クラブの立ち上げ方、手順を解説 MetaMaskなどのウォレットがあれば、投資クラブを立ち上げてコミュニティ管理が出来るようになっています。 今回はMetaMaskでポリゴンネットワークをつかい、投資クラブの作成を行う手順を解説してみました。 (ウェブサイトでは、実際に作成されている投資クラブのデモが見られるのでこちらも参考にしてください) MetaMaskのウォレットを用意する 最初にウェブサイトを開き「Get started」をクリックします。 SyndicateとMetamaskを繋ぐために「Metamask」をクリックします。 Metamaskのウォレットのインストール方法や使い方は、下記記事で解説していますので、インストールされてない方は、ご覧になってください。 ⇒MetaMask(メタマスク)の使い方まとめ!入出金・トークン追加も超簡単 SyndicateとMetamaskの接続が完了すると、参加している投資クラブの確認や新たな投資クラブを立ち上げが出来ます。 今回は、新しく投資クラブを立ち上げたいので「Create an investment club」をクリックします。 投資クラブの名前とティッカーシンボルの設定 投資クラブの名前と投資クラブで活用するトークンのティッカーシンボルを設定していきます。 投資クラブの名前は、オンチェーンで公開されるため、名前を公開したくない場合は、「Randomize」をクリックしましょう。 投資クラブを管理するために作成するトークンのティッカーシンボルを設定しますが、投資クラブに参加する参加者は、参加の証明として作成したトークンを受け取ることになります。(トークンは譲渡不可にデフォルト設定されています) クラブの名前とティッカーシンボルが決まったら「Next」をクリックします。 入金を受け付けるトークンの選択と上限枚数の設定 入金を受け付けるトークンでは、ETHやUSDCなどのERC-20を選択出来、資金調達の総額も自由に選択可能です。 今回は、入金受付のトークンにMATICを選択し、上限は100,000MATICに設定してみました。 トークンの入力が完了したらそのまま「Next」をクリックします。 入金受け付け期間の設定 次に資金調達がいつ終了するのかを設定します。 1週間 1ヵ月 3ヶ月 カスタム 上記の4通りから選択する事が可能で、カスタムは来年や再来年など長期に設定する事が出来ます。 今回は、2024年の8月11日23時59分に入金受け入れが終了するように設定しました。 投資クラブの参加人数の設定 続いて投資クラブに参加出来る人数を設定します。 Syndicateでは、SEC(米国証券取引委員会)が公式サイトで公開しているファイリングに基づいており、最大人数は99名まで参加可能なので、人数を入力し「Next」をクリックします。 人数を設定しますと上記の同意を求める注意書きが表示されます。 注意書きですが、「Syndicateを証券法に違反しないように使い、誹謗中傷・違法・不法行為を行いません」等の記載がされているため、しっかりと確認して問題がなければチェックを付けて「Confirm wallet」をクリックします。 次に、接続しているウォレットアドレスを投資クラブとして使用するウォレットとして使うか、新しいウォレットを使うかの確認画面が表示されます。 継続して使用する場合は、「Yes,continue with this wallet」をクリックします。 投資クラブで使うウォレットアドレスは、クラブメンバーに中身が開示されること、入金されるトークンは全てこちらのアドレスに集まる事になります。 Metamaskが起動しますのでガス代を確認してトランザクションを生成しましょう。 「confirmation」をクリックします。 これでオンチェーンで投資クラブ(yellow monkey)を作成出来ました。 投資クラブの立ち上げにかかった費用は、ガス代で0.0182008MATIC、日本円で約2.2円です。 投資クラブのダッシュボード Syndicateでは投資クラブの管理状況や設定変更を行う事が出来ます。 資金調達は、最大1,000,000MATICで、投資クラブ用のトークンYEMOの最大枚数が1,000,000、資金調達の受付は2年後まで可能と、設定した通りに作成出来ている事が分かります。 また資金調達用の入金リンクを生成する事が出来るので、クラブに参加したい人へリンクを共有する事が可能です。 非公開でのリンク共有をする事に同意することでリンクを生成出来ますが、入金リンクを公に公開すると証券法に違反する可能性があると注意書きがあります。 こちらについてはSyndicateがSEC(米国証券取引委員会)が公式サイトで公開しているファイリングを確認しますと、公にリンクを公開して入金を受け付けるのは、投資クラブが新会員を探していることを示唆していると見なされる可能性があるため違反になるとのことです。 投資クラブを立ち上げてみた感想 Syndicateで実際に投資クラブを立ち上げてみた感想は、 Metamaskを利用 費用はガス代のトークンのみで作成可能 簡単操作で数分で作成可能 といったシンプルな操作で完結するので、Syndicateの技術に驚きを隠せないですし、「〇〇のような事をやりたい、〇〇を変えたい」といったビジョン、ロードマップを掲げてブロックチェーン・暗号資産で、資金調達が可能になることからWeb3の今と未来は、誰もが主役になれる可能性に満ち溢れた未来がもうそこにきているように感じました。 しかしながらSyndicateの課題として見えた点もあります。 Syndicayeで立ち上げた投資クラブではトークンを取り扱う事になります。自社のサービスでしか使わないトークンは、暗号資産に当てはまらないといった見解もありますが、資金調達後、参加の証明としてトークンを参加者に配布することになることから、現在の日本の法律上、暗号資産交換業の登録を受けなければいけない可能性があります。 DAOとして投資クラブが透明性を維持し賛同者から資金調達を行えるプロダクトは、とても素晴らしくweb3ならではですが、日本の現行法を考えると暗号資産・ブロックチェーンにまつわる法律を全てクリアにしてから投資クラブの立ち上げ、運営をする事が望ましいように感じました。 世界の先進国はweb3に力を入れていますが、日本も経済産業省がWeb3政策推進室を設置して、暗号資産・ブロックチェーンの事業環境整備に取り組む姿勢をみせてきていますので、日本のweb3の未来に期待したいところです。 まとめ 投資の民主化を構築するSyndicateの概要・特徴について解説してきました。 クリプト市場では日々様々なプロジェクトが誕生していますが、Syndicateが手掛ける分散型投資プロトコルはブロックチェーンや暗号資産と相性の良い金融分野であり、今後も成長が期待できる領域です。 今回の記事をきっかけにSyndicateに興味を持った方は、今後も公式Twitterなどで情報を追ってみても良いかもしれません。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 ―Syndicate の公式リンク― Web site: https://www.syndicate.io/ Web app : https://www.app.syndicate.io/ Git book: https://syndicatedao.gitbook.io/syndicate-guide/ Twitter: https: //twitter.com/SyndicateDAO mirror: https://syndicate.mirror.xyz/ 免責事項 本記事は情報を伝えることが目的であり、投資等の勧誘、または推奨を目的としたものではありません。本記事により発生、誘発されたとされるいかなる損失についてもその理由やプロセスに関わらずCRYPTO TIMES、株式会社ロクブンノニ、筆者及び全ての関係者は一切その責任を負いません。暗号資産にはハッキングやその他リスクが伴いますので、ご自身で十分な調査を行った上でのご利用を推奨します。
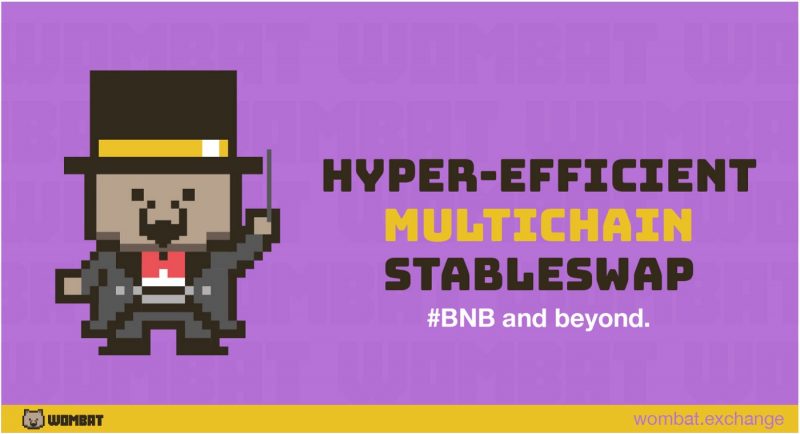
プロジェクト
2022/08/24Wombat Exchangeはスリッページを極限まで抑えたステーブルスワップ、概要と特徴を徹底解説
Wombat(ウォンバット)はBNBチェーン発祥のマルチチェーンステーブルスワップです。 同プロジェクトは数多く存在するステーブルスワップとの差別化として、カバレッジレシオと呼ばれる指標を組み込んだマーケットメイキングモデルを採用しています。 また、シングルアセットステーキングやUI/UXへのこだわり等、ユーザーが使いやすい設計もなされています。 こちらの記事では、Wombatの詳しい仕組みや$WOMトークンの解説、投資家情報や競合プロジェクトとの比較を紹介していきます。 Wombatの公式リンクまとめ 公式ウェブサイト https://www.wombat.exchange Telegram https://t.me/WombatExchange Twitter https://www.twitter.com/WombatExchange Medium https://medium.com/@wombatexchange ホワイトペーパー https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Wombatの特徴と仕組み Wombatは、既存のステーブルスワップが抱える資産の非効率性と、スリッページを起因としたスケーリングの悪さを解決するプロジェクトです。 加えて、今年になり危険性が再確認されているステーブルコインのペグに関するセキュリティソリューションも採用されています。 カバレッジレシオ Wombatでは、マーケットメイキングのカーブにカバレッジレシオと呼ばれる指標を組み込んでいます。 カバレッジレシオは「資産 ÷ 債務」の式で計算され、ここでの債務は、プロトコルがデポジットをしたユーザーに対する債務のことを指します。 このマーケットメイキングモデルは、下図の緑線のような形になります。 赤点線が資産XとYの和が常に一定となる線で、実際の値がこの赤点線から外れるとスワップ時にスリッページが発生します。 図を参照すると、紫線(Uniswap)や青線(一般的なステーブルスワップ)と比べて赤線上に滞在できる範囲が広くなっていることがわかります。 上図は横軸がスワップ額、縦軸がスリッページ(%)を表したものです。 同じBNBネイティブで代表的なステーブルスワッププロジェクトであるEllipsis(オレンジ線)と比べると、Wombat(青線)はスリッページが発生する閾値がより高く、さらに同じスワップ額で発生するスリッページも比べて小さいことがわかります。 このように、Wombatはカバレッジレシオを活用したマーケットメイキングシステムでスリッページの改善を行っています。 シングルアセットステーキング また、Wombatは自分がステークしたい通貨一種類をそのままステークできる「シングルアセットステーキング」を採用しています。 このシステムを採用することでユーザーはステーキングの際にペア両通貨を保有する必要がなくなり、ステーブルスワップ側もより安定した流動性を確保することができます。 これに上記のマーケットメイキングシステムがもたらすスケーラビリティや安定性が組み合わさることで、より効率的なイールドファーミングやレンディングが可能になります。 サブシディアリ・プール 2022年はTerraUSDの崩壊をきっかけに、アルゴリズム型ステーブルコインの安全性が疑問視されるようになりました。 そこでWombatは、USDC, USDT, DAI, BUSDの4通貨をメインのステーブルコインプールに指定し、それら以外にはサブシディアリ・プールと呼ばれる別のプールを設けています。 こうすることで、特定の通貨に起因するマーケットメイキングシステムの崩壊リスクを抑えることができる仕組みになっています。 トークン / インベスター / セキュリティ等 $WOMトークンについて Wombatのトークンとなる$WOMは、以下の4つの役割を担っています。 ガバナンス: WOMトークンを所有することで、プロジェクトのガバナンスに参加できる。 流動性インセンティブ: ユーザーは流動性プールにステーブルコインをステークすることでWOMトークンを報酬として獲得できる。 ボーティング・エスクロー(ve): WOMトークンをロックすることで、ステーキング報酬をさらに増やすことができる。 加えて、ボーティング・エスクロートークン($veWOM)の保有者はエアドロップやホワイトリスト、早期アクセス、インキュベーションプロジェクト関連の割引などといった特典を享受することができます。 インベスター・セキュリティ情報 Wombatは上図のベンチャーキャピタルやリサーチ企業から支援を受けています。 加えて2022年Q4には独自のインキュベーションプラットフォームの設立や、周辺プロトコルとの提携などが予定されています。 なおスマートコントラクトのセキュリティの面では、WombatはPeckshield、Hacken、Zokyoの三社によるコード監査を通過したほか、Immunefiとの提携のもとバグバウンティも実施しています。 競合プロジェクトとの比較 Curveなどの代表的なステーブルスワップとWombatの機能的な違いは、具体的に以下のようにまとめることができます。 Curveなどの他のステーブルスワップ Wombat Exchange 流動性プール クローズド型 オープン型 デポジット方法 複数トークン シングルアセット スリッページ 低い さらに低い アセットのスケーラビリティ 限定的 高い アセットの効率 良い さらに良い ペグ崩壊に対する対策 なし あり シングルアセットステーキングで、総ステーク量にも制限がないオープン型はユーザーにとっても参入しやすい点だと考えられます。 また、カバレッジレシオを採用したマーケットメイキングは既存のものよりスリッページ耐性が高く、デポジットされたアセットがより効率的に使われるようになります。 上記で解説した通り、Ellipsis (Curve公認のBNBフォーク)などと比べると単にスリッページが発生するまでの許容額が大きいだけでなく、同じ額で発生するスリッページ自体も小さくなっています。 そして近頃重要視されているステーブルコイン等のペグ崩壊対策も、Wombatはいちはやくメインとサブシディアリにプールを分けることで対応しています。 Wombat Exchangeの使い方 最後に、Wombatの使い方を解説します。まず、ウェブアプリにアクセスすると以下のような画面が表示されます。 右上の"Connect Wallet"からBSCウォレット(近日他チェーンにも対応予定)に接続すると、スワップやプール(ステーキング)が行えるようになります。 "POOL"タブでは流動性プールへのステーキングができ、ボーティング・エスクローあり/なし時のAPRや報酬額が確認できます。 メイン画面右上、"Connect Wallet"の横のボタンからはTVLや取引高、トランザクション履歴などが確認できるアナリティクスページにアクセスできます。 さらにその横の"…"からはエアドロップ情報やドキュメンテーション、各種SNS等へアクセスできるようになっています。 まとめ Wombatは既存のマーケットメイキングモデルに改良を加えることでスリッページ耐性とアセットの効率性を改善したステーブルスワップです。 シングルアセットステーキングによる利便性、サブシディアリプールによる安全性も同プロジェクトの大きな特徴です。 使いやすいUIや、アナリティクス、Medium、ドキュメンテーション等公式が提供する情報が多い点も良いでしょう。 Wombatは現在メインネットローンチを終えてベータ版となっており、今後さらなる機能の追加や他プロジェクトとの提携が期待されます。

プロジェクト
2022/08/23金利スワップAMM「Voltz Labs」とは? | The Mergeの戦略も紹介
イーサリアムのThe Mergeが近づくにつれて、業界ではイーサリアムの大型アップデートに関する情報が頻繁に話題に上がっています。 これまでにテストネット段階である「Ropsten」、「Sepolia」が完了し、8月11日には最後のテストネット「Goerli」で Mergeの実装が完了したことから、メインネットでのMerge実装への期待感がますます高まりつつあります。 そのような状況下で金利スワップを提供するVoltz Labsは、イーサリアムメインネットでのThe Mergeの実装が行われるにあたってVoltz Labsによる取引戦略で収益を得れる機会があるとツイートしました。 https://twitter.com/voltz_xyz/status/1547518179789996033?s=20&t=zqYRFV0w7NtWMcgpJFEk1Q 本記事では、そんなVoltz Labsについて概要や特徴、The Mergeに向けたVoltz Labsの戦略を解説しています。 Voltz Labsの概要 Voltz Labsは、レバレッジを効かせた金利スワップ(IRS)を提供する真新しいDeFi プロトコルです。 金利スワップとは、ユーザーによって望む金利のタイプ(変動か固定か等)が異なる点を利用して、利害が一致したユーザー同士でお互いの金利を負担し合い、実質的に自分の望む金利で取引が行える仕組みです。 合成資産の金利スワップを可能とする自動マーケットメーカーであるVoltzは、他の金利スワップモデルの数千倍資本効率の高い市場を作り出します。 現在はα版のVoltz AMMがローンチされており、流動性があるプールを選択し金利をスワップしたり、流動性を提供して手数料を稼ぐ事が出来ます。 Voltzのユースケースについて Voltzのユースケースは、レバレッジを使った金利の取引です。 金利には「固定金利」と「変動金利」の二種類があり、金利のスワップが可能なVoltzでは、「変動金利を固定金利に」または「固定金利を変動金利に」交換出来ます。 Voltzでは、 Fixed Takers(FT) Variable Takers(VT) Liquidity Providers(LP) の3種類の役割が存在します。それぞれ見ていきましょう。 Fixed Takers(FT) Fixed Takers(FT)は、変動金利を固定金利にスワップできます。 下記は、FTによる合成資産のcDAIを例にした解説です。 1.アリスは $10,000 相当の cDAI を保有しており、現在の変動金利はAPY10%です。 2.アリスはその金利が下がるリスクを冒したくないので、金利を90日間固定したいと考えています。 3.アリスは現在固定金利が10%である90日間のcDAI プールに参加します。 4.アリスは 10,000ドル相当のcDAIを入金し、90日間10%の固定金利でロックします。 出典:公式ウェブサイト:(Voltz Use Cases) FTのメリットは、Aliceが保有しているcDAI の変動金利が、今後90日間10%を下回っても10%の固定金利にスワップしたため、変動金利を気にすることなく10%の固定金利を得られる点です。 Variable Takers(VT) Variable Takers(VT)は、固定金利を変動金利にスワップできます。 続いてVTによる合成資産のcDAIを例に解説してますので見てみましょう。 1.現在のcDAIの変動金利のAPYは10%で、Voltzの90日間のcDAIプールの固定金利も10% です。 2.ボブは、cDAI の変動金利が20%に増加すると考えているため、利益を得れる機会にレバレッジをかけたいと考えています。 3.ボブは10,000ドルのDAIを証拠金として入金し、15 倍のレバレッジを選択してスワップを開始します。 4.これによりボブは、スワップに参加した時点で、cDAIの基礎金利から固定金利10%を差し引いた $150,000を想定したエクスポージャーを得る事が出来ます。 (この例で10%) 仮にcDAI の金利がすぐに APY の 20% に跳ね上がった場合、ボブは大きな利益を上げる事になりますが、以下が例の計算式になります。 (簡単にするために、ボブはプールが作成された時点でスワップに入ると仮定) 上記の様にボブが証拠金として入金した$10,000は、90日後に$13,699になっているということになります。 出典:公式ウェブサイト(Voltz Use Cases) 例のようにレバレッジをかけて、固定金利から変動金利にスワップをした後、金利が跳ねてAPYが増えれば大きく利益を上げる事が出来ますが、逆に金利が下がるとボブの資産は減る事になります。 ちなみにVoltz AMMの固定金利は、変動金利から固定金利にスワップする取引が増えれば増えるほど下がるようになっています。 Liquidity Providers(LP) Liquidity Providers(LP)は、Fixed Takers(FT)とVariable Takers(VT)がVoltz AMMで取引するために必要な流動性を提供します。 流動性の提供は、他のAMMモデルでは、2つの資産を預け入れる必要がありますが、Voltz AMMでは、固定金利と変動金利が両方とも同じ原資産 (eETH、aUSDなど) で行われるため、1つの資産の預け入れで流動性を提供したことになります。 またVoltzは、uniswap v3が搭載している集中流動性を採用しています。 プロトコル内でUniswap v3コードを使用出来る許可を、uniswapコミュニティのガバナンス投票で可決されたためコードの追加を許可されており、Voltz AMMでも導入されています。 この集中流動性により流動性の資本効率が向上し、少ない資本で多くの手数料を発生させる事が出来る様になっています。 Voltz Labsの3つの特徴 ①利益を得るための教育コンテンツを製作 ②シードラウンドで600万ドルを調達 ③ガバナンストークンの発行を計画 これからVoltz Labsの特徴について上記3つのポイントから解説していきます。 Voltz Labsの特徴を1つずつ見ていきましょう。 ①利益を得るための教育コンテンツを製作 Voltz Labsは、多くのトレーディングチームと連携し、トレーダーが金利スワップでどのようにマーケットからリターンを得られるか理解できるような教育コンテンツを制作しています。 またVoltz Labsのクオンツ(数学的手法を用いて市場動向を分析、金融商品開発を行う)チームは、トレーディング戦略の策定に多大な投資を行っているとのことです。 こちらがベアマーケットでAPY100%を獲得するトレード戦略の一例です。 https://twitter.com/voltz_xyz/status/1533775905100812288?s=20&t=-Uz-nOYnTlJvX3qCyOa7Lg ②シードラウンドで600万ドルを調達 2021年12月8日、Framework VenturesがリードするシードラウンドでCoinbase Ventures、Fabric Ventures、Amber Group、Wintermute、Robot Ventures、Mgnr、Entrepreneur Firstなどから600万ドルの資金調達を行いました。 調達された資金は、製品開発やVoltz Labs チームの成長のサポートに使用するとのことです。 ③ガバナンストークンの発行を計画 ガバナンストークンの発行については、6月9日に行われたVoltz Labs× CryptoKudasaiJP AMAのQ&Aで以下のような回答をしております。 Q.企業やプロジェクト、著名な開発者などとの契約はありますか? A.VoltzとUniswapは、Voltzの将来のガバナンストークンの1%と引き換えに、Uniswapのv3コードの使用ライセンス(「追加使用許諾」と呼ばれる)をVoltzに提供する、史上初のDAO2DAO取引の先駆者となりました。これはすべてオンチェーンで実行されました。 出典:Voltz Labs× CryptoKudasaiJP AMA内容まとめ このような回答をしていることから、まだ具体的には発表されてませんが、Voltzはガバナンストークンの発行を将来的に計画しており、Uniswapへ配布する契約を行っているとのことです。 The Mergeについて 8月12日のvitalikのツイートによると、9月15日頃にEthereumのアップデートであるThe Mergeがメインネットで行われる事が決まりました。 https://twitter.com/VitalikButerin/status/1558072902972473344?s=20&t=F8cLM37DSDyuTerC3HpkLQ The Mergeは、6月8日に取り上げたコチラの記事の通り、ブロックチェーンをプルーフ・オブ・ワーク(PoW)からプルーフ・オブ・ステーク(PoS)へ移行する一大イベントであり、検証作業に必要となる電力が削減されることから環境に優しくなるとされています。 ⇒イーサリアムのエネルギー消費について また、アップグレード終了後、ETHの新規発行枚数が90%減少する可能性が高く、デフレトークンになることからETHの価値が上がる可能性がると一部では言われています。 上記に加え、The Merge終了後に実施予定のアップデートThe Surgeでは、ロールアップの膨⼤なデータを圧縮して記憶するシャーディングが予定されているため、スケーリング問題の解決に近づく大型アップデートです。 The Mergeの詳細については、CT Analysisの『Ethereum 2022年夏 次期アップグレード「The Merge」とその後のロードマップを理解する』で、詳しく解説しています。 CT Analysis The Mergeレポートへ そのようなブロックチェーン業界、暗号資産市場の今後に影響を与えるイベントThe Mergeで、金利スワップを可能とするVoltzはどのような戦略を練っているかみていきましょう。 Voltzの取引戦略について Voltz protocolでは、stETHとrETHの金利スワッププールがローンチされていますが、Voltzの強みであるレバレッジをかけて固定及び変動金利の取引を行なう事が出来るのが今回の取引戦略のポイントになります。 現在イーサリアムのステーキングの利回りは4%ですが、The Merge後にPoSへ移行するため、利回りが増加する可能性が高いと予想されています。 そのための影響かVoltz protocolでは、The Merge後の利回り上昇を見据えて、LidoのstETH 、RocketのrETHのプールで固定金利から変動金利へレバレッジをかけ、スワップするユーザーが増えているとのことです。 金利スワップのやり方もシンプルでLidoのstETH 、RocketのrETHを保有する必要がなく、証拠金として預けるETHを用意すればレバレッジをかけて行う事が出来ます。 The Mergeでは、利回りの増加は50%以上、100%も考えられると強気な見解も一部ではあります。プルーフ・オブ・ステーク(PoS)へ移行により、新たなロードマップへの進行が始まりますし、利回りが高ければ高いほどイーサリアムエコシステムの景気が良くなるためこの部分は注目しておきたいです。 まとめ 金利スワップを提供するVoltz Labsについて解説してきました。 Voltzの概要やユースケース、取引戦略について分かっていただけたと思います。 イーサリアムの大型アップデートであるThe Mergeの実装が9月15日頃に行われる事が決まっていますが、運営によるとイーサリアムステーキングの金利スワップの戦略は他にもあり、更なるスワップ戦略の最新情報はTwitterで注目してくださいとのことです。 イーサリアムのThe Merge自体も注目ですが、Voltzのようなその周辺での動向も是非注目していきましょう。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 -Voltz Labs公式リンク- Webサイト:https://www.voltz.xyz/ アプリケーション:https://app.voltz.xyz/ ツイッター:https://twitter.com/voltz_xyz ディスコード:https://discord.com/invite/KVWtUGRumk Medium:https://medium.com/voltz ドキュメント:https://docs.voltz.xyz/getting-started/introduction



















 有料記事
有料記事


