
プロジェクト
2023/06/07データ分析でWeb3ゲームの成長を革新する: MCH Verseのケーススタディ
MCH Verseとは? MCH Verseは、Optimistic Rollupを搭載し、Oasysと呼ばれるゲーム専用ブロックチェーン上に構築されたレイヤー2ブロックチェーンです。 MCH Verseのメインゲームは、2018年にリリースされたEthereum、Polygon、MCH Verse,で構築されたマルチプレイヤーロールプレイングゲーム、My Crypto Heroesです。 Footprint Analyticsは最近、MCH VerseのCOOであるYamatoとTwitterスペースを開催し、ゲームとデータメトリクスにおいてフォーカスすべきポイントについて話し合いました。また、彼らのプロジェクトに関するエキサイティングな最新情報も提供されました。詳細については、Twitterスレッド(英文)をご覧いただくか、こちらの記事をご覧ください。 ゲームのメカニズム MCHでは、ヒーロー、エクステンション、ランドセクター、アチーブメントの4種類のNFTを導入しており、それぞれがゲームのメカニズムに重要な役割を担っています。 MCHのヒーローは、織田信長、劉備、クレオパトラ、ジョーン・オブ・アークなど、主に歴史上の人物で構成されています。NFTであるオリジナルヒーローは、購入、コレクション、販売によって手に入れることができ、その入手方法はレアリティによって異なります。一方、エクステンションは、ヒーローが基本的なアクティブスキルを強化するために装備する武器です。ヒーローもエクステンションも、レプリカ(NFTではない)バージョンとオリジナルのNFTがあります。 MCHはまた、他のソーシャルネットワークゲームにおけるギルドやクランに例えられるような、9つの個性的な土地を備えています。ランドセクターを所有することはMCHをプレイする上で必須ではありませんが、所有することでロード報酬などの特典を受けることができるなど、いくつかのメリットがあります。 NFTの「実績」は、2023年5月に新たにリリースされたもので、ゲーム内の実績に応じて発行することができ、大きく分けて2種類あります: "ピース "と "トロフィー "です。ゲーム内での成績を記録するもので、今後の活用が期待されます。 4種類のNFTを知った上で、このゲームの様々な遊び方を知っておく必要があります。 マイクリプトヒーローズ(MCH)では、江戸時代の職業分類【士農工商】に由来する【士・農・芸・商】にプレイスタイルが分類されています。 MCHには、PvP(Player vs Player)やGvG(Guild vs Guild)といった多彩なバトルモードがあり、プレイヤーは熱いバトルを繰り広げることができます。 MCHの農民は、クエストを通じて貴重な報酬を得ることができ、特にノードと交流することで報酬を得ることができます。ノードは、3人のヒーローで構成されるチームが活動し、Crypto Energy(CE)を獲得できる場所として機能します。プレイヤーはチェストからレプリカのエクステンションと「マテリアル」を入手できます。マテリアルは、プレイヤーがエクステンションをクラフトして、ゲーム内の経験値を得るためのものです。ちなみにMaterialはオフチェーンのアイテムで、Uniswap V3のオフチェーンフォークであるLabで取引可能です。マテリアルとLabは、将来的にオンチェーンに実装される予定です。 アーティストは通常、ユニークなヒーローのアートワークを作成し、ゲーム内通貨で販売します。彼らは通常、異なるアートスタイルでヒーローの外観をカスタマイズします。商人は、NFTを積極的に取引することで、ゲーム経済において重要な役割を担っています。NFTを売買して利益を最大化し、ダイナミックな市場に貢献します。 これらの異なるゲームプレイスタイルは、プレイヤーにMCHの世界に没入するための多様で魅力的な方法を提供し、さまざまな興味や好みに対応することができます。 ビジョン MCH Verseの究極のビジョンは、ゲームベンチャーに投資された時間、お金、情熱が、かけがえのない資産に変わるような、特別なエコシステムを構築することです。これらの資産は、MCHC(MCHコイン)やNFT(Non-Fungibleトークン)の有形価値だけでなく、ブロックチェーンの取引履歴に埋め込まれた魅力的なストーリーや記憶も含み、通常の富の領域を超越したものである。 MCH Verseの壮大なタペストリーでは、仮想の土地とプレイヤーが主役となり、ゲームの魔法が資産の成長と繁栄に絡む自立した経済圏を作り出します。 MCHは、ゲームが非日常の旅となる冒険へプレイヤーを誘います。プレイヤーは、ゲームに没頭し、MCH Verseの歴史に自分の物語を刻むことができるのです。 マイルストーン My Crypto Heroes(MCH)は、2018年11月にEthereumで最初にローンチして以来、長い道のりを歩んできました。この4年間で、このゲームは技術レベルとビジネスレベルの両方で大きな進歩を遂げました。 MCHはEthereumでスタートしましたが、すぐにPolygonに拡張し、より柔軟性と拡張性を獲得し、ユーザーのゲーム体験を向上させました。 2020年10月、MCHはネイティブトークンであるMCH Coinをリリースし、大きな一歩を踏み出しました。MCH Coinのリリースは、ゲーム内でより多くの報酬とインセンティブを提供することで、新規および既存のプレイヤーを引き付けることを目的としていました。このトークンは、ゲームの経済を豊かにし、その持続可能性に貢献しました。 最大のマイルストーンは、2022年2月にMCH Verseをリリースしたことです。MCH Verseは、ゲームが独自のエコシステムとコミュニティを構築することを可能にしました。Verse Layerと呼ばれるレイヤー2のソリューションにより、MCH Verseは拡張性を実現し、より高度なゲームメカニクスを可能にしました。第2段階では、MCH VerseはHub Layerとの接続に成功し、レイヤー間のアセットの相互運用性を確保しました。 より柔軟なネットワークの選択から、ネイティブトークンのリリース、独自のエコシステムの構築まで、MCHは大きな進歩を遂げました。MCHのプレイヤーやサポーターは、ゲームが限界に挑戦し続けることで、さらに魅力的な体験ができることを期待しています。 ゲームの成長を後押しするデータの活用法(チェックするデータの種類とその活用法について) Web3ゲームの世界では、データは、ゲームプレイやプレイヤー体験、ゲーム全体の進化の強化に貢献する貴重な洞察と利点を提供します。様々な種類のデータを分析することで、Web3ゲームの開発者やマーケティング担当者は、情報に基づいた意思決定を行い、ゲームの仕組みを最適化し、ゲームの成長を促進させることができます。 重要なサインを監視する: ゲームの健康状態をデータで把握する方法 Web3ゲームの領域では、健全でバランスの取れたエコシステムを維持することが最も重要です。ゲームを成功させるためには、ゲーム概要、NFT、ソーシャルデータなど、さまざまな指標を綿密に監視することが重要です。 ゲームの概要 ユーザー、リテンション、取引 ゲームそのものに関して言えば、Web3の世界ではユーザー関連のデータが中心的な役割を果たします。ユーザーはエコシステムに直接影響を与え、デジタル資産の価格のような取引データを押し上げることができます。 [caption id="attachment_93767" align="aligncenter" width="921"] MCHアクティブユーザー数・新規ユーザー数・総ユーザー数[/caption] [caption id="attachment_93769" align="aligncenter" width="919"] MCHアクティブユーザー数推移[/caption] DAU、MAUなどのユーザー指標を追跡することで、web3プロジェクトは実際にどれだけの人がゲームをプレイしているかを測定し、ユーザー獲得効率について詳しく知ることができます。 さらに、このユーザーデータをもとに、オンボードファネルレートとリテンション/チャーンレートを分析することになります。 オンボードファネルレートは、ユーザー獲得効率の指標となり、最初のサインアップからアクティブなエンゲージメントまでのコンバージョンを表します。この指標を分析することで、ゲーム開発者はオンボーディングプロセスの有効性について貴重な洞察を得ることができ、改善すべき領域を特定することができます。 リテンションとチャーンレートの指標は、ユーザーのエンゲージメントと、長期にわたってプレイヤーを維持するゲームの能力を直接反映するものです。これらの指標を詳細に分析することで、開発者はプレイヤーの定着や離脱に影響を与えるパターンや要因を特定することができます。この貴重な情報により、プレイヤー体験を向上させ、プレイヤーの長期的な価値を高め、プレイヤーの減少を最小限に抑えるための的を絞った対策を実施することができます。 ユーザー指標も重要ですが、同時に取引データにも注目することが同様に重要です。ユーザーはエコシステムに影響を与え、デジタル資産の価格に直接影響する取引データに影響を与える能力を持っています。 [caption id="attachment_93771" align="aligncenter" width="800"] MCHデイリートランザクション[/caption] トークン価格や流動性といった取引指標を追跡することで、参加者は資産の価値を測り、情報に基づいた取引の意思決定を行うことができます。トークン価格は需要と供給のダイナミクスを反映し、流動性はスムーズな取引を保証し、資産交換時の価格スリッページを最小限に抑えます。 NFTの概要: 価格、保有者・販売者、利益 NFTの価格、保有者、販売者などの指標を追跡することは、健全なゲームエコシステムを維持するために不可欠です。NFTはゲームプレイに使用される重要な資産であるため、NFTの価格が安定していれば、システム全体がより安定した状態にあることを意味するのです。 [caption id="attachment_93777" align="aligncenter" width="800"] MCH NFTデータ[/caption] また、NFT保有者と販売者の数の動的な変動もNFTの価格に直接影響を与えます。これらの指標を監視することで、ゲーム開発者はNFTの需給ダイナミクスを把握することができ、情報に基づいた意思決定を行い、バランスのとれた繁栄する経済を確保するために必要な行動を取ることができます。 NFTの利益は、これらの資産の価値と望ましさを評価するために不可欠です。これらの指標を分析することで、市場内におけるNFTの全体的な価値と望ましさを評価することができます。 [caption id="attachment_93779" align="aligncenter" width="815"] MCH プレイヤー収益[/caption] NFT資産が強い価値を持ち、希少で望ましいと認識された場合、プレイヤーはそれを貴重なデジタル資産と見なします。このような認識は持続的な需要を促進し、NFTベースの経済の健全化に寄与し、プレイヤーがNFTの取引、購入、活用に積極的に取り組むエコシステムを育みます。 プレイヤーにとって利益分析は、ゲーム内の上位入賞者のパフォーマンスを追跡することができ、戦略的意思決定のための貴重な情報を提供します。様々なゲーム要素や戦略の収益性を理解することで、プレイヤーはゲームプレイを最適化し、有利な機会を特定し、ゲーム内で収益を最大化することができます。 開発者にとっても、利益分析は成長機会を特定するための羅針盤の役割を果たします。収益源と収益性を分析することで、開発者はマネタイズの強化、新機能やコンテンツの導入、パートナーシップやコラボレーションの可能性を模索し、さらなる収益を上げることができる領域を発見することができます。 ソーシャルデータ: Twitter、Discord、市場センチメント ソーシャルデータとしては、特にTwitter、Discord、そしてそれらが反映された市場センチメントに注目することができます。 [caption id="attachment_93783" align="aligncenter" width="800"] MCH Twitterアクティビティ[/caption] ソーシャルデータは、ゲームコミュニティにおけるユーザーの行動、好み、エンゲージメントパターンを理解する上で極めて重要なものです。公式ツイートやアナウンスのパフォーマンスを分析することで、開発者は、何がプレイヤーの共感を呼び、興味を引くのかについて貴重な知見を得ることができます。 こうした洞察は、高いエンゲージメントを生み出し、プレイヤーの注目を集める人気のコンテンツ、ゲームの機能、またはイベントを特定するのに役立ちます。ソーシャルデータを活用することで、ゲーム開発者はゲーム体験を調整し、魅力的なコンテンツを作成し、活気あるコミュニティを育成することができます。プレイヤーのゲームへの関わり方、好み、好みのコンテンツを理解することで、開発者はよりパーソナライズされた魅力的な体験を提供し、より強いコミュニティ意識を育み、プレイヤー全体の満足度を向上させることができます。 透明性で信頼を築く: コミュニティーのためのデータダッシュボード ゲームの優れたダッシュボードは、プレイヤーがリアルタイムでゲームのパフォーマンスを監視・分析できる包括的な情報ハブとして機能します。プレイヤーは、ゲーム開発者やプレイヤーが作成したデータダッシュボードを通じて、ゲーム資産、取引、レアリティレベル、その他の関連統計に関するデータにアクセスすることができます。 コミュニティ・ダッシュボードは、メンバーがコミュニティの証人を活用し、さまざまな側面からゲーム戦略を導くためのダッシュボードを構築するのに役立ちます。このような透明性と包括性により、潜在的なプレイヤーとの信頼関係を築き、質の高い参加者を集めることができます。透明性は、ゲームの開発や改善の方向性を決定する際にプレイヤーが発言することで、コミュニティ内での所有感や帰属意識を育みます。 プレーヤーをエンパワーする: 戦略最適化のためのデータツール オンチェーンデータと組み合わせることで、戦略を最適化するための分析も可能になります。オンチェーンデータを活用し、ヒーローの採用率、組み合わせ、勝率、土地ごとのチーム傾向などのインサイトを活用することで、プレイヤーは戦略を最適化し、勝利の可能性を最大化することができます。 [caption id="attachment_93784" align="alignnone" width="927"] MCH ヒーローのスタッツ[/caption] PvP戦闘におけるヒーローの採用率を分析することで、ヒーローの人気と効果に関する重要なインサイトを得ることができます。どのヒーローが人気でよく使われているかを理解することで、プレイヤーは自分のヒーローチームを作る際に十分な情報を得た上で判断することができます。 [caption id="attachment_93785" align="alignnone" width="926"] MCH 最も勝率が高いチーム[/caption] ヒーローの組み合わせも、チームの強さと有効性を決定する重要な要素です。特定のヒーローの組み合わせのパフォーマンスや勝率を調べることで、プレイヤーは相乗効果やカウンター、最適な戦略を見出すことができます。例えば、最強のヒーローの一人であるアルバート・アインシュタインと相性の良いヒーローを理解することで、プレイヤーは各ヒーローのユニークな能力と強みを生かした強力でまとまりのあるチームを作ることができます。 エクステンションNFTは、ヒーローのアクティブスキルを変更し、その能力を強化する重要な役割を担っています。さまざまなエクステンションNFTの採用率を分析することで、メタを把握し、プレイヤーがヒーローに最も効果的なエクステンションを選択するのに役立てることができます。このデータを利用することで、プレイヤーはヒーローのビルドを最適化し、バトルで優位に立つことができます。 バランスを保つ: データから読み解く運用の変化 ゲームのバランスを維持することは、プレイヤーに魅力的で楽しい体験を提供するために不可欠です。このバランスを達成・維持するための運用変更を導く上で、データ主導の洞察は重要な役割を果たします。データを活用することで、ゲーム開発者は、ゲームのさまざまな側面を調整し、微調整するために、情報に基づいた決定を下すことができます。 特にNFTの二次取引に関連して、PvPバトルにおけるヒーローの採用率を分析することが重要な分野の一つです。ヒーローの使用状況を注意深く観察することで、開発者は特定のヒーローの人気と需要を示す傾向やパターンを特定できます。この情報は、ゲーム内のすべてのヒーローがゲームのエコシステムにおいて等しく実行可能で価値があることを保証し、ユーザーにとって公平で多様なゲームプレイ体験を促進するのに役立ちます。 ヒーローの使い方に多様性を持たせることは、ゲームの寿命を延ばし、NFTの流動性を高めることにつながります。 [caption id="attachment_93786" align="aligncenter" width="800"] MCH 最初に攻撃を行ったチームとそうでないチームの出現頻度と勝率[/caption] ファーストアタックとセカンドアタック(最初に攻撃を行うヒーローを含むチーム)のパワーのバランスも重要な検討事項です。データ分析を通じて、開発者はさまざまな攻撃能力の有効性と影響を評価することができます。MCHチームは、ユーザーがダッシュボードを活用して効果的な取引戦略を策定し、取引活動を促進することを期待しています。 [caption id="attachment_93787" align="alignnone" width="934"] MCH ヒーロー使用率トップ10[/caption] データの可視化は、プレイヤーの戦闘戦略や取引戦略の策定を可能にするため、ブロックチェーンゲームプロジェクトの成功に欠かせない要素です。リアルタイムの市場データと分析を提供することで、全体的なゲームプレイ体験を高めるだけでなく、ゲームの経済を活性化させ、ユーザーのエンゲージメントとリテンションを促進します。ブロックチェーンゲームプロジェクトの最終的な目標は、ユーザーが公平で競争力のある環境に参加し、その努力の成果を享受できる、持続可能で繁栄するエコシステムを構築することです。 ゲームの先へ: ゲーミングインサイトのためのデータ解析の課題を明らかにする Web3ゲームにおける手動データ収集の複雑さを理解する Web3ゲームにおけるデータ収集は、複雑で多面的なプロセスであり、クラウドサーバー、Google Analytics、MCHノードなどのソースを含む複数のソースから情報を収集することがよくあります。これらのソースからデータを統合することは、データが互換性のないフォーマットである可能性があり、データを集約し正規化するための調整が必要となるため、困難な場合があります。 収集と統合のプロセスは、時間がかかり、自動化が難しく、人為的なミスが発生しやすくなります。 膨大な量のデータを処理することでデータの力を引き出す Web3ゲームにおけるデータ分析は、デュエルログのような重要な要素など、何百万もの生データを含む膨大な量のデータを扱い、処理する必要があるため、困難な課題となっています。データ分析では、分析技術やアルゴリズムを適用して、データから貴重なパターン、傾向、相関関係を抽出します。 また、効果的なエラー検出と調査には、生データの保存が不可欠です。オリジナルデータを保存することで、アナリストは徹底的な調査を行い、ゲームの公平性やユーザー体験に影響を与える可能性のある異常、不具合、矛盾を特定することができます。このような綿密なアプローチにより、包括的なバグ検出が可能になり、開発チームは問題に迅速に対処し、ゲームの整合性を高いレベルで維持することができるようになります。 Footprint Growth Analyticsによるブロックチェーンゲームのマーケティング予算の最適化 データに秘められた可能性を引き出すには、高度な分析手法とアルゴリズムを適用する必要があります。データサイエンティストやアナリストは、洗練された手法でデータをクレンジングし、変換し、分析します。 Footprint Growth Analytics(FGA)は、データをインデックス化し、マーケティング予算の最適化に役立てることができます。 Footprintは、ブロックチェーンゲームプロジェクトに、オンチェーンおよびオフチェーンデータをインデックス化して分析する包括的なソリューションを提供します。何百もの外部データソースと統合することで、FGAの自動データパイプラインは、ユーザー行動と市場動向の包括的なビューを開発者に提供します。 データのインデックス作成自体のコストを削減するだけでなく、FGAのデータ駆動型アプローチは、ブロックチェーンゲームプロジェクトがマーケティング予算を最適化し、成功を促進するのに役立ちます。コホート機能により、開発者は行動や嗜好に基づいてユーザーをセグメント化し、マーケティング戦略や製品機能を調整するために使用できるユーザー行動に関する貴重な洞察を提供することができます。コミュニティツールは、ゲーマー間のコラボレーションを促進し、開発者はユーザー生成コンテンツや口コミマーケティングを活用してプロジェクトを推進することができます。 著者:[email protected] Footprint Communityは、世界中のデータ愛好家やクリプト愛好家が、Web3、メタバース、DeFi、GameFi、その他ブロックチェーンの発展途上の世界に関する理解を深め、洞察を深めるための場所です。ここでは、活発で多様な声がお互いを支え合い、コミュニティを前進させることができるのです。 Footprint ウェブサイト: https://www.footprint.network Discord: https://discord.gg/3HYaR6USM7 Twitter: https://twitter.com/Footprint_Data

プロジェクト
2023/06/06キャプテン翼RivalsでTSUGTが獲得できる新キャンペーンが開始!
キャプテン翼 Rivalsで、TSUGTキャンペーンが期間限定で開催されます。 ミッションをクリアすると合計4,500 $TSUGT(6/6時点で23,000円相当)を獲得できます。 キャンペーンは2023年6月7日から9月6日まで行われます。 https://twitter.com/TsubasaRivalsJA/status/1665639988451500032?s=20 キャンペーン概要 期間:2023年6月7日(水) 9:00〜 2023年9月6日(水)23:59 報酬:MAX4500TSUGT(6/5時点で27000円相当) 条件:PVEとPVPミッションクリア 報酬内訳 PVEミッション 中学生編 全ステージクリア 200TSUGT Jrユース編 全ステージクリア 800TSUGT ワールドユース編 全ステージクリア 1,000TSUGT PVPミッション ライバルスピース 3回コンプ 1,000TSUGT ライバルスピース 10回コンプ 1,500TSUGT POINT 期間中にステージクリアが必要(既にクリアしてても再クリア必要) 各ステージ3ターン勝利が必要(2ターン勝利ではクリアにならない) 獲得TSUGTはスペンディングから送金できない 新キャンペーンの難易度はどのくらい? キャンペーン概要だけだとTSUGTを獲得する難易度がどれほどか分かりづらいかと思います。 キャンペーンに必要な戦力は以下の通りとなります。 PVE:選手3体以上と、コマンド合計16500以上の選手1体 PVP:RP5000以上の選手3体 最低9体のNFTが必要なワールドユース編がもっともハードルが高いですね。 PVPの10回コンプは時間がかかるため出来るだけ早めに始めることをおすすめします。 実際に筆者はキャプテン翼Rivalsを始めてちょうど1ヶ月ほど経ちましたが、PVP10回コンプ以外は達成できている状況です(改めてクリアしなければなりませんが。) 今回の新キャンペーンは3ヶ月とかなり長い期間設けられているため、恐らく1~2ヶ月もあればクリアできる内容かと思います。 ぜひ、この機会に始めてみてはいかがでしょうか。 公式サイト:https://tsubasa-rivals.com/ja/ Twitter:https://twitter.com/TsubasaRivalsJA discord:https://discord.com/invite/captain-tsubasa-rivals

プロジェクト
2023/06/04NFTプロジェクト「Blur」の使い方を解説|購入や出品方法も
この記事では、近年新たに注目を集めてきたNFTマーケットプレイス兼アグリゲーターサービスであるBlurについて解説しています。 この記事のポイント Blurは2022年にローンチされたNFTマーケットプレイス兼アグリゲーターサービス 手数料0%、最高水準の処理速度、BLURトークンのエアドロップなどの特徴があり、OpenSeaの取引ボリュームを上回るなど注目を集めてきた 機能や操作方法など、具体的な使い方を画像付きで解説 Blurの概要 画像:Blur 名称 Blur サービス NFTマーケットプレイス/アグリゲーター 対応チェーン Ethereum (ETH) ウェブサイト https://blur.io/ Twitter https://twitter.com/blur_io Discord https://discord.com/invite/blurdao Blurは2022年にローンチされたNFTマーケットプレイス兼アグリゲーターサービスで、2022年3月にParadigmが主導するシードラウンドにて1,100万ドルの調達に成功したことで注目を浴びました。 同年10月の正式ローンチから数日後には過去24時間の取引ボリューム1位を記録し、その後12月には取引ボリュームにおいてOpenSeaを上回ったことが発表され、大きな注目を集めてきました。 その後もBid機能の公開や、BLURトークンのローンチとエアドロップなど、注目のアップデートが続いています。 Blurの3つの特徴 画像:Blur 注目を集めるBlurの主な特徴を3つご紹介します。 ① 手数料0% 主要なNFTマーケットプレイスでは取引手数料がかかる一方、Blurの手数料は0%になっています。 また、手数料だけでなくガス代を抑えることもでき、入札とその取り消しの際にガス代は不要で、一括購入によりガス代の節約が可能です。 NFTの売買を行うトレーダーにとってはこのようなコストを削減できるのは大きな魅力ですね。 主要なNFTマーケットプレイスの手数料の比較 Blur 0% OpenSea 2.5% LooksRare 2.0% X2Y2 0.5% ② 最高水準の処理速度 Blurのウェブサイト上では「最速のNFTマーケットプレイス」と謳われています。 また、一括購入機能の実装により、他サービスよりも10倍速い取引が可能との説明もあります。 取引処理や情報更新などの速度が速いことは、とくに多くの売買を行うトレーダーにとっては魅力になりそうです。 ③ BLURトークンのエアドロップ シーズン1と称されたエアドロップでは総計3.6億のBLURが配布され、こちらも多くのユーザーを呼び込む要因となりました。 すでにシーズン2が開始しており、ビッディング/リスティング/レンディング等によって獲得できるポイント数に応じて総計3億ほどが配布される予定のようです。 Blurの使い方 画像:Blur ここからはBlurの使い方について、以下の通り順を追って解説していきます。 事前準備 ウォレットを接続する 購入したいNFTを探す NFTを購入する 入札 (Bid) する スイープ (Sweep) で一括購入する NFTを出品する エアドロップ (AIRDROP) 設定 事前準備 Blurを利用する前に以下の事前準備を完了しておきましょう。 事前準備 ① ウォレットの用意 (メタマスクがおすすめ) ② イーサリアム (ETH) の購入 ③ 購入したETHをウォレットに送金 ウォレットの準備がまだという場合は、以下の記事でメタマスクの始め方を解説しています。 MetaMask(メタマスク)の使い方まとめ!入出金・トークン追加も超簡単 また、イーサリアム (ETH) の購入について不安がある方は以下を参考にしてみてください。 イーサリアム(ETH)を購入するのにおすすめの取引所TOP3! ウォレットを接続する 事前準備が完了していたら、さっそくBlurとウォレットの接続からはじめましょう。 まずはBlurのウェブサイト (https://blur.io/) にアクセスし、右上の「CONNECT WALLET」をクリックします。 表示される選択肢から接続したいウォレットをクリックします。(今回はメタマスクで進めます) ウォレット側で接続の認証を終え、画面右上に接続済みのウォレットが表示されていれば完了です。 購入したいNFTを探す 購入したいNFTを探すときは、まずはトップ画面左上のタブから「COLLECTIONS」をクリックしてみましょう。 すると、トップコレクションのテーブルが表示されます。 左上のタブ (下の写真の①) からTRENDING (トレンド) をクリックすれば、トレンドコレクションの表示に切り替えることが可能です。また、テーブルの各項目名 (下の写真の②) をクリックすることで、各項目別に並び替えることが可能です。 また、画面上部の検索窓を利用すれば、任意のキーワードで検索することもできます。 コレクションをクリックすると、コレクションやそのアイテムの様々な情報が表示されます。 画面の上部にはそのコレクションの概要、中央部にはアイテム一覧とその詳細、右側には直近のアクティビティなどが表示されています。 また、左側にある以下の項目からさらに絞り込みを行うことも可能です。 STATUS・・・ONLY BUY NOW (販売中のみ) / SHOW ALL (すべて表示) RARITY・・・レアリティ PRICE・・・価格 ATTRIBUTES・・・NFTのパーツ また各アイテムの名前をクリックすると、アイテムごとの詳細な情報を確認することもできます。 NFTを購入する NFTの購入は、アイテム詳細画面の左下にある「BUY NOW」をクリックし、ウォレット側で認証を行うことで完了します。 また、アイテム一覧から、購入したいアイテムの左横にあるチェックボックスをクリック (複数選択可) した後に「BUY NOW」をクリックすると、まとめて購入することもできます。 入札 (Bid) する 入札 (Bid) を行いたい場合、まずPOOLにETHを入金 (デポジット) する必要があります。 アイテム一覧上部のタブから「BIDS」をクリックします。 画面下部に表示される「PLACE COLLECTION BID」をクリックします。 POOLへの入金に伴う説明が表示されます。主な内容は以下の通りです。 * 入札 (Bid) を行うためにはPOOLへの入金 (デポジット) が必要 * Bidとそのキャンセルにはガス代は不要 * POOLの残高はいつでも引き出すことが可能 * NFTを購入する場合はPOOLの残高から使用されるため、引き出さずにそのままでもOK 確認したら、「ADD ETH TO START BIDDING」をクリックして入金に進みます。 入金額を入力したら、「ADD TO POOL」をクリックします。 ウォレット側での認証を終えて数十秒ほど経つと、POOL BALANCE (POOL残高) に反映されます。 再度「BIDS」一覧に戻り、Bidしたいものをクリックします。 BID PRICEとSIZEを入力したら、「CONFIRM BID」をクリックして確定します。残高が足りない場合は「ADD FUNDS」をクリックして、先程の要領で入金しましょう。 ウォレット側の認証を終えるとBid完了です。 自分のBidの状況については、画面左上タブの「PORTFOLIO」をクリックした後「BIDS」を選択すると確認できます。また、Bidをキャンセルしたい場合は、該当のBidの右端にある「×」アイコンをクリックします。 また、余ったPOOLの残高を引き出したい場合は、画面右上の残高アイコンをクリックし、「WITHDRAW FROM POOL」を選択したら、あとは入金のときと同じく金額を入力して「WITHDRAW FROM POOL」をクリックします。 スイープ (Sweep) で一括購入する スイープ (Sweep) 機能を使うことで、ひとつのコレクション内のアイテムを価格が安い順に一括購入することが可能です。 コレクションのアイテム一覧を表示し、画面下部に表示されるスライダーを左右に動かして購入数を調整します。 スライダーで購入数を調整したら、選択済みのアイテムが反映されます。問題なければ画面左下の「BUY 〜 ITEMS」をクリックし、購入を確定します。 ウォレット側で認証を進めて、購入完了となります。 NFTを出品する NFTを出品する際は、接続済みのウォレットにNFTが保管されていることを確認しておきましょう。 問題なければ、画面左上のタブの「PORTFOLIO」>「INUENTORY」と進み、出品したいNFTにチェックを付け (複数選択可) 、画面下部の「LIST 〜 ITEM(S)」をクリックします。 以下の情報を設定して、問題なければ「LIST 〜 ITEM(S)」をクリックして出品を確定します。 ① MARKET PLACES・・・出品するマーケットプレイスを選択 (複数選択可) ② AUTO ADJUST FOR FEES・・・オンにすると手数料込みの価格を自動調整 ③ 販売価格の入力・設定 ④ DURATION・・・期間を選択 ウォレット側で認証を終えたら出品完了です。 エアドロップ (AIRDROP) 画面左上のタブから「AIRDROP」をクリックすると、エアドロップのダッシュボードが表示されます。 ここには現在実施中のエアドロップに関する情報がまとまっています。 執筆現在 (2023年5月) ではシーズン2のエアドロップが実施中です。 中央にビッディング/レンディング/リスティングの獲得ポイントとリスティングロイヤリティが表示されており、さらにスクロールするとこれらのポイント/ロイヤリティに基づくリーダーボードが表示されています。 設定 画面下部の歯車アイコンをクリックすると簡単な設定にアクセスできます。変更可能な項目は以下の通りです。 ビューの変更 (TRADER / COLLECTOR) ・・・TRADERビューはより多くのチャートやデータが集約されており、COLLECTORビューは全体的に大きく見やすい表示になります。 COLOR THEME・・・カラーテーマの変更 (DARK / MEDIUM / LIGHT) Sync with operating system theme.・・・システムのテーマに合わせる まとめ NFTマーケットプレイス兼アグリゲーターサービスとして注目のBlurについて、概要や特徴、その使い方を解説しました。 取引ボリュームではOpenSeaを上回るほどの注目度を誇るBlurですが、利用者数の観点ではまだOpenSeaの方が多いということもあり、今後この2つのマーケットプレイスがどのように展開していくのかも見どころです。 OpenSeaはより直感的に操作できるシンプルなUIが特徴的ですが、一方Blurは情報集約型のトレーダー向きUIとなっているため、好みも分かれる部分かもしれません。 新たなエアドロップも予定されているので、とくにトレーダーの方はぜひ一度Blurを試してみてはいかがでしょうか。 CT Analysis『NFTマーケットプレイス Blur概要と考察、OpenSeaとの比較』を公開

プロジェクト
2023/05/14NFT音楽プラットフォーム「Gala Music」登録方法と使い方を解説
この記事では、P2E(Play-to-Earn)ゲーム開発を手掛けるGalaが新たにリリースしたNFT音楽プラットフォーム「Gala Music」について解説します。 この記事のポイント Gala MusicはP2Eゲーム開発を手掛けるGalaがリリースしたNFT音楽プラットフォーム 分散型エコシステムにより仲介者を排し、アーティストとファンの双方に適切な報酬が発生する仕組み トラック (楽曲NFT) 購入やノードへのペアリング、再生回数などに応じてトークン報酬を獲得できる トークンをホールドすることでさらに特典やポイントを獲得、ポイントを使用してグッズやイベントパスを購入できる Gala Musicの登録からウォレット接続、具体的な機能や操作方法について写真付きで解説 Gala Musicとは? 画像:Gala Music 「Gala Music」は、P2E(Play-to-Earn)ゲーム開発を行うGalaがリリースしたNFT音楽プラットフォームです。 ブロックチェーンを利用することで、仲介者を介することなくアーティストとファンの双方に適正な報酬が発生する分散型エコシステムを目指しています。 Web3における音楽エンターテイメントの新たなあり方を提案するプロジェクトとも言えるのでないでしょうか。 And so it begins ...https://t.co/m8tGuMuGSH#ANewWayToPlay #Web3Music #Web3 #Day1 pic.twitter.com/K0WjqX6sgd — Gala Music (@GoGalaMusic) March 29, 2023 公式リンク集 Gala Music ウェブサイト music.gala.com Gala ウェブサイト gala.com Gala Music 各種SNS Discord Twitter Medium Instagram Youtube Gala Gamesや$GALAのプロジェクト概要については以下の記事で詳しく解説しています。 Gala Games / $GALA とは?プロジェクトの概要を徹底解説! Gala Musicの特徴 画像:Gala Music Gala Musicの主な特徴を2つご紹介します。 分散型プラットフォームによる音楽体験の価値向上 現代の音楽体験というと安価なストリーミング商品などが浸透しており、しばしばアーテイストへの報酬が適正ではないのではないかという議論も耳にすることがあるでしょう。 Gala Musicでは分散型プラットフォームによって仲介者を排し、アーティストとファンがより近い距離で交流し、双方が適正な報酬を得ることができるエコシステムを目指します。 このような変化により、音楽体験そのものの価値の向上や、新進気鋭のアーティストの促進などが期待されます。 システム貢献で獲得できるトークン Gala Musicではシステムへの貢献に対する報酬としてトークン(BEAMS)を獲得することができます。 トークンは主に以下のような行動の報酬として獲得することができます。 トラック(楽曲NFT)を購入する トラックをノードにペアリングする これらの報酬に加え、所有するトラックの再生回数に応じた報酬も発生します。 さらに、このトークンをお気に入りのアーティストに対してホールドすることで同等のポイントを獲得することができ、ホールドし続けることでそのポイントが一定倍率で増加していく仕組みとなっています。 こうして貯めたポイントは「ALL ACCESS」という機能(リリース予定)を介して、アーティストのグッズやイベントパスの購入に使用することも可能になるようです。 このようにトークンを介してアーティストとファンがよりインタラクティブな関係となるエコシステムの実現を目指しています。 Gala Musicの使い方 画像:Gala Music ここからはGala Musicの主な使い方について、以下の通りに順を追って解説します。 1.アカウント登録からウォレット接続 3.アーティスト/トラック/アルバムを検索する 3.トラックを購入する 4.購入したトラックをノードにペアリングする 5.トークン (BEAMS) をホールドする 6.その他の主な機能や操作 1.アカウント登録からウォレット接続 まずはGala Musicへのアカウント登録から始めましょう。 1.Gala Musicへアクセス 2.右上の「Sign Up」をクリック 3.以下の情報を入力/選択したら、最下部の「Create an Account」をクリック ① First Name/Last Name・・・氏名(名/性) ② Email・・・Eメールアドレス ③ Display Name・・・ディスプレイネーム(文字/数字/アンダースコアのみ使用可能) ④ Password・・・パスワード(最低8文字、小文字/大文字/数字/特殊文字のすべてを1つ以上使用) ⑤ Referral Code・・・紹介者がいる場合はリファラルコードを入力(任意) ⑥ 利用規約とプライバシーポリシーを確認したらチェック(リンクを開いて最後までスクロールして読まないと次の画面で再確認されます) ⑦ ニュースやオファー、プロモーション等を受け取りたい場合はチェック 4.メール認証を求められるため、受信したメールから「Verify My Account」をクリック(届かない場合は「Resend email」をクリック) 以下の画面になればアカウント登録完了が完了です。 次にウォレット接続を行います。 6.「Connect Wallet」をクリック 7.設定画面に切り替わるので、再度「Connect Wallet」をクリック 8.表示される選択肢から接続するウォレットをクリック 9.ウォレット側で確認や署名を進める 10.以下の画面が表示されればウォレットの接続が完了です。 以上でアカウント登録からウォレット接続までが完了です。 2.アーティスト/トラック/アルバムを検索する さっそく気になるアーティストやトラック (楽曲NFT)、アルバムなどを検索してみましょう。 ホーム画面上部のタブから「Discover」をクリックします。 Tracks (トラック)、Artists (アーティスト)、Albums (アルバム) のタブがあるので、探したいものをクリックしてみましょう。トップには注目のトラックが表示されています。 下にスクロールするとランキングが表示されます。右側のアイコンからはチェーンの切り替えや、フィルターでの絞り込みが可能です。キーワードで直接検索したいときは、左側の検索窓を利用できます。 トラックをクリックすると詳細を確認できます。スクロールするとたくさんの情報が表示されますが、主な情報は以下の通りです。 ① トラックのアートワーク・・・マウスオーバーすると再生ボタンが表示され、クリックすると再生できます(トラックのコントロールは画面下部に表示されます) ② アーティスト名・・・クリックするとアーティストページに遷移します ③ トラック名 ④ Date Available / Available NFTs・・・購入期限 / NFT残数 ⑤ Like / Share・・・ライク / 共有 ⑥ Purchase・・・購入 ⑦ Total Listens / Total Likes・・・再生数 / ライク数 ⑧ Genres・・・ジャンル ⑨ Rarity・・・レアリティ(ダイヤモンド/ゴールド/シルバー/ブロンズ) ⑩ Top 10 Collectors・・・トラックのコレクター(所有者)トップ10 ⑪ Description / List of utility・・・説明 / ユーティリティ ⑫ Blockchain / Token Standard / Token ID・・・チェーン / トークン規格 / トークンID 3.トラックを購入する 気に入ったトラックがあれば、以下の手順で購入することができます。 1.気に入ったトラックの詳細画面を表示 2.「Purchase (購入)」をクリック 3.購入内容を入力/選択 ①Quantity (数量)、②Selected wallet (ウォレット選択)、③Payment Method (支払方法) の順に入力し、④Review order (購入内容確認) をクリックして購入を進めます。 4.購入したトラックをノードにペアリングする トラックを購入したら、さっそくノードにペアリングしてみましょう。 ノードにペアリングすることで報酬としてトークンを獲得でき、さらに自分が所有するトラックの再生回数に応じてさらにトークンを獲得できるチャンスもあります。 まずは購入したトラックを確認してみましょう。画面右上の人形マークをクリックし、表示されたリストから「My Collection」をクリックします。 購入済みのトラックがある場合はここに表示されるので、個々のトラックへの操作からノードへのペアリングを進めてみましょう(下記画像には購入済みトラックがないため何も表示されていません)。 ペアリングしたトラックとそのパフォーマンスを確認するには、画面右上のタブから人形アイコンをクリックし、表示されたリストから「My Player Nodes」をクリックします。 左上のタブから「Overview」と「Your Music」を切り替えながら、ペアリングした自分のトラックのパフォーマンスなどを確認できます。 「Your Music」で確認できる項目は左から順に以下の通りです。 Track hosted・・・ホストしているトラック Last day rewards・・・前日の報酬 Weekly rewards・・・週間の報酬 Total rewards・・・合計 (全期間) の報酬 5.トークン (BEAMS) をホールドする トークンが貯まってきたら、次はホールドを試してみるとよいかもしれません。 お気に入りのアーティストに対してトークン(BEAMS)をホールドすることで、以下のような様々なメリットを得ることができます。 トークン (BEAMS) の主な仕組み トークンをホールドすることで同等のポイントを得ることができ、ホールドしつづけることで時間経過とともにポイントが一定倍率で増加していきます。 時間経過によるポイントの増加倍率はアーティストのレアリティ (ダイヤモンド/ゴールド/シルバー/ブロンズ) に基づいており、レアリティが低ければ低いほど倍率も高くなります。 貯まったポイントは「All Access」機能 (リリース予定) においてアーティストのイベントパスやグッズの購入に使用できます。 ホールドしたトークン量に基づいた3段階のレベル (Level 1〜3) が設定されており、各レベルが要求する量以上のトークンをホールドすることで一定の特典を得ることができます。(詳細は後述) ホールドはいつでも解除できますが、ホールドによる特典と貯まったポイントも同時に失われます。 すこし複雑な印象を受けるかもしれませんが、実際に見てみるとよりわかりやすいかと思います。 まずはアーティストページから「Hold BEAMS」をクリックしてみてください。 例えばこのアーティストであれば、500トークンでレベル1、1000トークンでレベル2、1500トークンでレベル3の特典を得ることが確認できます(下記画像の赤枠内を参照)。 試しに1500トークンを入力してみるとレベル3の特典が反映されました(下記画像の右赤枠内を参照)。 また、1500トークンをホールドしたとすると、 Yearly rewards (年利):16% Estimated balance after 365 days (365日後の推定残高):1740ポイント (16%増) であることも確認できます(下記画像の左赤枠内を参照)。 トークンが貯まってきたら、お気に入りのアーティストに対してホールドし続けることでポイントを継続的に貯めることができ、より多くの特典や報酬を得ることができるようになるということですね。 また、ホールドしたトークンやアーティストの確認や解除をする場合は、画面右上の人形アイコンをクリックし、表示されるリストから「My Access Pools」をクリックします。 すると、現在ホールドしているアーティストやポイント報酬などを確認することができ、ホールドの解除もここから行うことができるとのことです。 6.その他の主な機能や操作 All Access 画面右上のタブの「All Access」をアクセスできます。 現在はまだリリースされていませんが、獲得したポイントを使ったお気に入りのアーティストのグッズやイベントパスの購入などが可能になるとのことです。 Charts (チャート) 画面右上のタブの「Charts」からアクセスできます。 当日/週間/月間/全期間ごとのトラックやアーティストの様々なランキングを確認できます。 ランキングはトップトラック/トップアーティスト/再生回数などがあります。 各アーティストへのホールドによる報酬の推移や、各トラックの再生回数の推移、トレンド比率なども確認可能です。 テーマ切り替え (ダーク/ライト) 画面右上のタブの太陽/月のアイコンからテーマ (ダーク/ライト) の切り替えが可能です。 サーチ (虫眼鏡アイコン) 画面右上の虫眼鏡アイコンから素早く全体へのサーチ (検索) が可能です。 アーティスト、トラック、アルバムなどなんでもここからクイックサーチができます。 My Notifications (通知) 画面右上のタブのベルアイコンから通知の確認が可能です。 ここにはトラックの購入や報酬の獲得などの様々なアクティビティの通知が届きます。 パーソナルメニュー (人形アイコン) 画面右上のタブの人形アイコンをクリックするとパーソナルメニューが開きます。 表示される各項目でできることは以下の通りです。 My Collection・・・購入したトラックなどの確認 My Access Pools・・・トークンをホールドしたアーティストの確認や解除、ポイント報酬などの確認 My Player Nodes・・・ノードにペアリングしたトラックとそのパフォーマンスの確認 My Notifications・・・アクティビティの通知 Account Settings・・・アカウント設定 Refer A Friend・・・リファラル(友達紹介) まとめ 音楽NFTプラットフォーム「Gala Music」の概要や使い方について解説してきました。 安価なストリーミングでしか味わうことがなくなってしまった音楽という体験の価値が、Web3によって新たに塗り替えられる日が来るかもしれません。 Gala Musicはまだリリースされていない機能も残しており、これからのアップデートも見逃せません。 アーティストとファンがよりインタラクティブに関わり合いながら、ともに音楽という体験の価値を取り戻すエコシステムの挑戦に注目です。 免責事項 ・本記事は情報提供のために作成されたものであり、暗号資産や証券その他の金融商品の売買や引受けを勧誘する目的で使用されたり、あるいはそうした取引の勧誘とみなされたり、証券その他の金融商品に関する助言や推奨を構成したりすべきものではありません。 ・本記事に掲載された情報や意見は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性、完全性、目的適合性、最新性、真実性等を保証するものではありません。 ・本記事上に掲載又は記載された一切の情報に起因し又は関連して生じた損害又は損失について、当社、筆者、その他の全ての関係者は一切の責任を負いません。暗号資産にはハッキングやその他リスクが伴いますので、ご自身で十分な調査を行った上でのご利用を推奨します。(その他の免責事項はこちら)

プロジェクト
2023/05/11正式サービス版ローンチで注目上昇中!PROJECT XENOのガバナンストークンGXEとは?
PROJECT XENOは、NFTキャラクターを駆使して対人バトルを楽しむブロックチェーンゲームです。 プレイを楽しんで稼げるGameFi要素の強いゲームで、東京ゲームショウ2022出展の成功や、アンバサダーに人気Youtuberのヒカル氏が就任するなど、何かと注目が集まるプロジェクトでした。 そして正式サービス版のリリースを完了し、ガバナンストークンGXEの国内取引所BITPOINTへの上場も決まって、ここへきていよいよ本格的に動き始めました。 この記事では、そんなPROJECT XENOの特徴とそのガバナンストークンであるGXEについて紹介します。 GXEを購入するならBITPOINT BITPOINTの概要 取引の種類 現物取引(販売所・取引所) 取扱銘柄数 16種類 日本円入金手数料 即時入金:無料 通常入金:振込手数料負担 日本円出金手数料 振込手数料負担 仮想通貨出金手数料 無料 取引手数料 無料 GXEはMEXCやGate.ioなどの海外の取引所で購入できますが、国内の取引所ならBITPOINTで買うことができます。 BITPOINTは初心者でも使いやすい取引所で、簡単に注文を出せる販売所形式と板取引を行う取引所形式(BITPOINT PRO)を利用できます。 仮想通貨の出金手数料や取引手数料が無料なので、使い勝手がとてもよいのが特徴です。 GXEに興味をもったら、まずはBITPOINTに取引口座を作りましょう。 BITPOINT(ビットポイント)の登録手順・口座開設方法を解説! BITPOINTの公式HPはこちら PROJECT XENOの公式リンクまとめ PROJECT XENOの関連公式ページ 公式サイト http://project-xeno.com 公式Twitter(英語) https://twitter.com/PROJECTXENO_GLB 公式Twitter(日本語) https://twitter.com/PROJECTXENO_JP 公式Telegram https://t.me/projectxenoglb 公式Discord https://discord.gg/G4bk9nhJpG Whitepaper(英語) https://project-xeno-1.gitbook.io/d-en-project-xeno-whitepaper-en/ Whitepaper(日本語) https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-jp/ Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epochstudio.xeno AppStore https://apps.apple.com/app/id6446313010 PROJECT XENOの関連公式ページをまとめました。 公式リンクのブックマークやSNSアカウントをフォローして、PROJECT XENOの動きをリアルタイムでウオッチしましょう。 正式サービス版ローンチで話題のPROJECT XENOの注目ポイントを解説 2023年5月10日、PROJECT XENOはプロジェクト発足から約一年の短い準備期間で正式サービス版をリリースしました。 この一年間、東京ゲームショウへの出展成功や著名人とのアンバサダー契約など、話題を提供し続けています。 ここでは、PROJECT XENOの注目すべきポイントを説明していきましょう。 PROJECT XENOの注目ポイントを解説 GameFiの要素を備えたPvPゲーム Play to Earn(P2E)で遊んで稼げる 人気Youtuberヒカルがアンバサダーとしてサポート 正式サービス版ローンチで人気沸騰 GameFiの要素を備えたPvPゲーム PROJECT XENOは、NFTキャラクターを駆使して対人バトルを楽しむブロックチェーンゲームです。 開発はクルーズ株式会社の子会社でブロックチェーン技術をコアに活躍しているCROOZ Blockchain Lab株式会社、サービスを運営するのはEPOCH FACTORY社です。 XENOと呼ばれるNFTキャラクターを獲得・育成しWEAPONやCHARMといったNFTアイテムを装備させて、他のプレーヤーのXENOと戦います。 NFTキャラクターやアイテムの収集と育成、キャラクターとアイテムそしてスキルを組み合わせて勝てるデッキを組む戦略性、相手の行動を読みながら自分のターンでの最適な動きを決める戦術性が高度にバランスした、奥の深いタクティクスゲームです。 GameFi(Game + Finance)の要素が強く盛り込まれており、ゲームをプレイして楽しむだけではなく、ゲーム内での報酬の獲得や育成したNFTキャラクターの売買が可能です。 NFTの流通量などをコントロールするエコサイクルがゲームシステムにしっかりと組み込まれているため、NFTの価値は長期的に維持されます。 Play to Earn(P2E)で遊んで稼げる PROJCET XENOの利益獲得方法 ゲーム中のユーザー間のバトル報酬で獲得する NFTの取引で獲得する トークンを売買して稼ぐ PROJECT XENOはP2Eが可能なゲームで、利益を得ることができる様々な方法が用意されています。 まず、ゲーム中の対人バトルで勝利すると報酬として仮想通貨やNFTを得ることができます。 2番目の利益獲得方法は、PROJECT XENOのマーケットプレイスでのNFTの取引です。より希少性の高いNFTはゲームを有利にするため、より高額で売れることになります。 3番目の方法はPROJECT XENOで使われるトークンの売買です。すでにPROJECT XENOのガバナンストークンGXEは市場に上場されており、売買することができます。 GXEを購入するには? 人気Youtuberヒカルがアンバサダーとしてサポート PROJCET XENOではワールドワイドでの認知度を上げるため、地域ごとに著名人と提携しています。 日本国内向けには、チャンネル登録者数約487万人(2023年5月10日現在)を誇るトップYouTuberのヒカルがPROJCET XENOのアンバサダーに就任しました。 僕がアンバサダーをしているゲーム #XENO ついに5月10日にリリースされます! ゲームを遊んで稼げる夢みたいだけど実際の話、それをYouTubeで実際に公開します。お楽しみに!! 無料で遊べるのでアプリ事前登録をぜひお願いします Android https://t.co/VQrNxCQb3g iOS https://t.co/4dqvnsPDk0 — ヒカル公式アカウント (@hikaru2nd1031) May 4, 2023 ヒカルとPROJCET XENOがコラボしたNFTセールを行うなど、PROJECT XENOのマーケティングに大きく貢献しています。 他にも、ボクシング8階級制覇のマニー・パッキャオが東南アジア担当のアンバサダーに就任しています。 正式サービス版ローンチで人気沸騰 PROJECT XENOの正式サービス版は2023年5月10日にリリースされました。 これに先立ち2023年4月20日から3日間限定で先行リリースが行われ、PROJECT XENOに早くから注目していた多くのプレーヤーが参加して3日間ゲームをやり込みました。 その結果、ゲームとしての戦略性の深さやグラフィックの美しさに驚きの声が多く上がり、正式リリース版への期待は一層の盛り上がりを見せています。 Google PlayからのPROJECT XENOのダウンロードはこちら AppStoreからのPROJECT XENOのダウンロードはこちら PROJECT XENOのガバナンストークンGXEの特徴 GXEは、PROJECT XENOのエコサイクルを支えるガバナンストークンです。 すでに複数の仮想通貨取引所に上場されており、活発に取引が行われています。 ここでは、GXEの特徴を説明し、PROJECT XENOの投資対象としての魅力を確認します。 PROJECT XENOのガバナンストークンGXEの特徴 XENO Governance Token(GXE)の概要 PROJECT XENOにおけるGXEの役割 GXEのTokenomics XENO Governance Token(GXE)の概要 XENO Governance Token(GXE)のスペック トークン名 XENO Governance Token テッカーシンボル GXE 発行者 EPOCH FACTORY PTE.LTD. 発行数量 60億GXE ブロックチェーン BSC(BNB Chain) 売買できる取引所 BITPOINT、BTCEX, Gate.io, MEXC, LBank GXEはPROJECT XENOのガバナンストークンです。 正式名称はXENO Governance Tokenで、PROJECT XENOの運営を担当するEPOCH FACTORY社が発行しています。 BSC(BNB Chain)上で発行されており、発行数量は60億GXEに限定されています。 すでにMEXC、Gate.ioなどの大手海外取引所に上場しており取引可能です。日本国内でもBITPOINTへの上場が決まり、より簡単にGXEを購入することができるようになりました。 GXEを購入するには? MEXCの登録方法を見る Gate.ioの登録方法を見る PROJECT XENOにおけるGXEの役割 GXEはPROJECT XENOのエコサイクルを安定的に機能させ、NFTの価値を上げるために使われます。 一定の条件を満たしたGXEの保有者はGXEパートナーになることができ、NFTのエアドロップやセールでのディスカウントの特典を得ることが可能です。 また将来的には、トークン・NFTなどの発行やゲーム仕様の決定など、PROJECT XENOの運営に関する投票の権利が付与される予定です。 PROJECT XENOのコミュニティが拡大すれば、必然的にGXEの価値は上がって行きます。 これによりPROJCET XENOの提供者とプレーヤーに加えてGXEの保有者をステークホルダーに加えることができ、単なるゲームにとどまらず、経済活動とシームレスにリンクしたエコサイクルを構築することができます。 GXEを購入するには? GXEのTokenomics GXEの配布比率はチーム・アドバイザー・パートナーなどのステークホルダーに27%、今後の開発やマーケティングの費用として14%が割り当てられています。 目立つのは、PROJECT XENOのゲーム内外でプレーヤーに報酬として配布されるPlay and Earnの部分に39%が割り当てられている点です。 この部分の割り当てが大きいのは、GameFiの要素が強いブロックチェーンゲームのガバナンストークンならではの特徴ですね。 市場で実際に流通するGXEは、PROJECT XENOのプレーヤーが集まり関連コミュニティが広がっていくにつれて徐々に増えていきます。そして、流動性の高いより魅力的な市場へと成長していくでしょう。 GXEを購入するには? PROJECT XENOってどんなゲーム? PROJCET XENOの本質はGameFi、つまりGame & Financeです。まずはGameそのものとして長く楽しめるものでなければ、Financeにつながりません。 ここでは、PROJECT XENOのゲームとしての面白さに焦点を当てましょう。 PROJECT XENOってどんなゲーム? NFTキャラクターXENOを駆使したPvPのブロックチェーンゲーム XENOは個性的な6つのクラスに分かれている! XENOにスキルを組み合わせてバトル! XENOにWEAPON・CHARMをセットして強化 バトルに勝てばトレジャーを獲得! XENO・WEAPON・CHARMはマーケットプレイスで売買可能 NFTキャラクターXENOを駆使したPvPのブロックチェーンゲーム PROJECT XENOは、3体までのNFTキャラクターXENOを使って、対人でバトルするタクティクスゲームです。 3体のXENOにWEPONやCHARMを装備し、攻撃や防御のアクションをさせるためのスキルカードをセットしてデッキを組み、ターン制のバトルで相手のXENOを倒していきます。 【育成】レベルの高いXENO・WEPON・CHARMをどう集め、育成するか? 【戦略】XENO・WEPON・CHARMとスキルカードをどう選び、勝てるデッキを組むか? 【戦術】バトル中で相手の戦略を読み、どう対処するか? 育成・戦略・戦術のサイクルをうまく回して初めて勝利できる奥深さが、PROJECT XENOの面白さの核心部分です。 XENOは個性的な6つのクラスに分かれている! XENOの6つのクラス GUARDIAN 高い耐久力を持ち、味方を守ることが得意なXENOです。 SAMURAI 高い攻撃力を持ち、近接攻撃が得意なXENOです。前線の敵への範囲攻撃で相手の陣形を崩します。 PSYCHIC 遠距離攻撃が得意なXENOです。相手の陣形にかかわらずピンポイントに敵を攻撃できます。 NINJA 最も早く行動できるXENOです。連続攻撃や罠・状態異常を引き起こすトリッキーな存在です。 GRAPPLER 最大の攻撃力を持つXENOです。単体攻撃に特化しており、カウンター攻撃で大きなダメージを与えます。 XENOは役割が違う6つのクラスに分かれています。 それぞれHPや攻撃力・スピードなどの特性値が異なり、クラス間の相性もあるので、デッキにどのクラスのXENOを組み込むかはバトルに勝利するために最も重要な戦略です。 XENOはブロックチェーンで管理されるNFTです。各種セールでの購入や、マーケットプレイスで売買することができます。 発行数が限定された特別のXENOに、GENESISと名前が付いたものがあります。バトルでトークンを稼ぐ能力が高められたXENOで、より希少性が高いNFTです。 XENOにスキルを組み合わせてバトル! スキルカードをXENOにセットすると、バトル中で使えるアクションスキルになります。 クラスごとに異なるスキルカードが用意されており、攻撃や状態異常の発生、召喚ユニットの召喚などの様々なアクションが可能です。 1体のXENOにセットできるスキルカードは4つのみなので、どのスキルカードをXENOにセットするかはバトルの勝敗に大きく影響します。 XENOにWEAPON・CHARMをセットして強化 XENOにセットできる装備にWEAPONとCHARMがあります。 WEPONは、スキルカードによるXENOのアクションの効果を強化します。 「Common」「Uncommon」「Rare」「Epic」「Legendary」の5段階のレアリティがあり、レアリティが上がるほど多くのスキルカードに影響します。WEPONの合成によってレアリティを上げて行くのがXENO強化のコツです。 CHARMもXENOにセットできる装備で、1体のXENOにネックレス・ブレスレット・リングをそれぞれ1つずつの最大3つまでセット可能です。 攻撃力のUPや必殺技が出しやすくなるなど、CHARMをセットしたXENOに対してバトルを有利にする効果をもたらします。 WEPON同様「Common」「Uncommon」「Rare」「Epic」「Legendary」の5段階があり、レアリティが上がるほどより多くの効果があります。WEPON同様、CHARMも合成によってレアリティを上げることができます。 XENOにどういうWEPONやCHARMをセットするかで、バトルにおけるXENOの強さは大きく変わります。効果的な組み合わせを見つけて戦略が嵌れば、安いNFTの組み合わせでも強い相手に勝てる可能性が十分あるゲームです。 バトルに勝てばトレジャーを獲得! バトルに勝利するとトレジャーを獲得することができます。トレジャーには、スキルカードやNFTなどの報酬が入っています。 各プレーヤーにはバトルの勝敗に応じたアリーナクラスが割り当てられており、よりレベルの高いアリーナクラスでのバトルに勝利するとより多くの報酬が手に入ります。 バトルを繰り返して報酬を獲得し、その報酬を使ってより強いNFTを集めてさらに強いデッキを組み、獲得できる報酬を増やしていくのが、PROJECT XENOの楽しみ方です。 XENO・WEAPON・CHARMはマーケットプレイスで売買可能 XENO・WEAPON・CHARMはNFTなので売買することが可能です。 そのためのマーケットプレイスがすでに稼働しており、NFTが取引されています。 マーケットプレイスで使用するマーケットマネーはクレジットカードで購入できます。 マーケットマネーを購入すれば、あとはシンプルな操作でNFTを購入でき、すぐにゲーム内で使用できます。 仮想通貨に詳しくない人でも快適に使えるマーケットプレイスです。 PROJECT XENOのロードマップ(2023年5月時点) PROJECT XENOは2022年Q1の発足後約1年で正式サービス版のリリースに漕ぎつけた、とても勢いのあるプロジェクトです。 2022年9月には早くも東京ゲームショウ2022でデモ版を出品するとともに、人気YouTuberヒカルのアンバサダー就任を発表し、開発とマーケティングの双方を順調に進めて行きました。 平行して、同9月にガバナンストークンGXEのMEXC Global上場を果たし、その後、LBank、Bittrex Global、Gate.ioと大手取引所への上場を重ねて、投資対象となる仮想通貨としてのポジションも固めてきています。 2023年4月にはマーケットプレイスα版をリリースしてNFTの取引環境の準備を完了し、さらにPROJECT XENOの3日間限定で先行リリースを行って、正式版リリースに備えました。 そして2023年5月10日に、PROJECT XENO正式サービス版のリリースに至っています。 まとめ この記事では、正式サービス版リリースを迎えて大注目のPROJEXT XENOとガバナンストークンGXEについて紹介しました。 PROJEXT XENOはGameFiの要素が詰まったブロックチェーンゲームです。 バトルの戦略性の奥深さとキャラクター育成を楽しみながら、トークンやNFTを獲得して利益を得ることができます。 うれしいことにPROJEXT XENOは無課金でも始められます。ゲームをインストールして、さっそく試してみましょう。 Sponsored Article by Project XENO ※本記事はProject XENOさまよりいただいた情報をもとに作成した有料記事となります。プロジェクト/サービスのご利用、お問い合わせは直接ご提供元にご連絡ください。

プロジェクト
2023/05/07Magic Eden (マジックエデン) とは?使い方、NFT購入・出品方法を解説
Magic Edenは、主にSolanaのNFTを扱うNFTマーケットプレイスです。 SolanaのNFTの取引において高いシェアを持っており、Solanaに絞ったNFT取引量ではOpenSeaを上回っています。 Magic Edenは、SolanaのNFTを扱うなら、一度はチェックしておきたいNFTマーケットプレイスであると言えるでしょう。 この記事では、そんなMagic Edenについて概要から特徴、各機能の使い方などについて解説しています。 この記事のまとめ ・Magic Edenは主にSolanaのNFTを扱うマーケットプレイス ・SolanaのNFT取引において高いシェアを持つ ・Ethereumにも展開している ・Eden Gameから各ゲームのプレイとNFTの購入をダイレクトに可能 Magic Edenとは?SolanaのNFTマーケットプレイス Magic Edenは、主にSolanaのNFTを扱うNFTマーケットプレイスです。(詳しくは後述しますが、他のチェーンでも展開されています。) NFTマーケットプレイスとは、NFTを売買することが可能なサービスのことです。 NFTマーケットプレイスは、NFTを買うにも売るにも必要ですから、NFTを扱う方にとって必須な存在であると言えるでしょう。 そんなNFTマーケットプレイスの中でも、Magic Edenは主にSolanaのNFTを扱っています。 また、Solanaをはじめ、以下の4つのチェーンに対応しています。 対応チェーン(2023年5月現在) Solana(SOL) Ethereum(ETH) Polygon(MATIC) Bitcoin(BTC) 代表的なNFTマーケットプレイスとしてOpenSeaが挙げられますが、Magic EdenについてもOpenSeaと基本的な機能・できることは似通っています。 既にOpenSeaなどで、NFTマーケットプレイスの利用経験があれば、Magic Edenについても問題なく利用できるでしょう。 NFTマーケットプレイスOpenSeaの使い方、出品から購入、ミント方法までを完全解説 Magic Eden 4つの特徴 これから、Magic Edenが持つ特徴について以下のポイントから解説していきます。 ・Solanaで展開 ・Solanaにおける圧倒的なシェア ・他チェーンへの展開 ・ゲームとの親和性 Magic Edenの取り柄や魅力的なポイントをチェックしていきましょう。 Solanaで展開 Magic Edenは、SolanaのNFTを扱っています。 SolanaはEthereumと比較して、処理能力が高い・ガス代が低いといった特徴を持つブロックチェーンのことです。 そのため、そんなSolanaのNFTを扱うMagic Edenを利用した取引にも同様の傾向が見られ、Ethereumを利用したNFTマーケットプレイスよりも高い体験が可能です。 Solanaにおける圧倒的なシェア 前述したようなSolanaのNFT領域において、Magic Edenは圧倒的なシェアを誇っています。 以下は、2022年8月のSolanaにおけるNFTマーケットプレイスの取引ボリュームの比較となっていますが、Magic Edenが大きなシェアを持っていることが分かるでしょう。 SolanaのNFTマーケットプレイス領域において、著名なOpenSeaと比較してもMagic Edenの取引ボリュームは非常に大きいです。(ただし、Ethereumなど複数のチェーンを含めた取引ボリュームでは、OpenSeaが優位) 上記のような各NFTマーケットプレイスの取引量の比較や、各チェーンにおける注目のNFTなどについては、CT Analysisの「NFT マーケット市場レポート」で毎月取り扱っています。 「押さえておきたいNFT市場における動向」を毎月まとめているので、NFTを保有している方・NFTに興味がある方は、ぜひご覧ください。 NFT市場レポートへ 他チェーンへの展開 🧵 OUR ETH PLATFORM IS NOW LIVE! Today is day 1 of many. We're proud of - Partnering w/ 17 ETH Launchpad creators - Respecting royalties on native listings for ALL collections - Providing ALL ETH Launchpad partners royalties AND our 2% fee for 6 months Follow @MEonEthereum! pic.twitter.com/OcGdz4kr9Z — Magic Eden 🪄 (@MagicEden) April 6, 2023 これまで、SolanaのNFTを扱っていたMagic Edenですが、Ethereumに対応したマーケットプレイスを発表しました。 Solanaのマーケットプレイスとスムーズに切り替え可能となっており、名称や利用するウォレットは異なってくるものの、同じような操作性で利用可能です。 Magic Eden、ETHマーケットプレイスのローンチ|17のプロジェクトとパートナーに ゲームとの親和性 Magic Edenには、Eden Gameという機能があります。 Eden Gameからゲームへのアクセスが可能で、そのままブラウザーベースで各ゲームをプレイすることが可能になっています。 Eden Gameには、上記のように多数のゲームが提供されており、各ゲームで使用するNFTなどをダイレクトにMagic Edenから購入することも可能です。 Eden Gameを利用することで、ゲームのプレイと各NFTへの売買を、Magic Edenで済ませられるようになっています。 Magic Edenの使い方を解説 これから、Magic Edenの使い方について以下の観点から解説していきます。 ・前提として必要になるもの ・ウォレットの接続 ・NFTの購入方法 ・NFTの出品方法 ・ローンチパッドの参加方法 ・Eden Gameのプレイ方法 一つ一つチェックして、Magic Edenの使いこなせるようにしていきましょう。 事前に必要なもの Magic Edenを利用するには、各チェーンに対応したウォレットが必要です。 2023年5月現在時点でサポートされている4つのチェーンごとの対応ウォレットは以下の通りです。 チェーンごとの主な対応ウォレット Solana(SOL)・・・Phantom Wallet、その他 Ethereum(ETH)・・・メタマスク、その他 Polygon(MATIC)・・・メタマスク、その他 Bitcoin(BTC)・・・Xverse、Unisat、Hiro 仮想通貨やNFTを扱う方の大半はメタマスクを使用されていることと思いますが、Solana(SOL)を利用したい場合はPhantom Walletを準備する必要があります。 Solana関連のプロダクトに触れることがある方、この機会にPhantom Walletを作成しておいて損はないでしょう。 Solanaの概要やPhantom Walletの使い方については以下の記事で解説しています。 Solanaとは?概要や特徴、注意点を解説【始め方】 【使えると便利】Phantom Wallet | ウォレットの概要や使い方を解説! また、メタマスクについても以下の記事で解説しています。 MetaMask(メタマスク)の使い方まとめ!入出金・トークン追加も超簡単 Magic Edenとウォレットの接続 ウォレットが用意できた方 or 既に作成済みの方は、以下の手順でMagic Edenとウォレットを接続していきましょう。 Magic Edenにアクセス 左上の各チェーンアイコンから利用したいものをクリックして選択したら、右上の「Connect Wallet」をクリック 利用するチェーンを再度選択し、その下に表示される選択肢から接続するウォレットをクリック(接続したいウォレットが表示されていない場合は「Show more」をクリック) ウォレット側で接続を進める 上記の手順で、接続が完了したらMagic Edenを利用するための準備は完了です。 Magic EdenでNFTを購入する方法 Magic Edenでは、以下の方法でNFTを購入することが可能です。 画面上部の検索や「Popular collections」などからコレクションを探す コレクションからほしいNFTの「Details」から詳細を確認 「Buy now」へ 承認を行う Magic Eden内で各コレクションにアクセスしたら左側にある項目から、価格などを指定した上でNFTを探していくこともできます。 Magic EdenでNFTを出品とキャンセル方法 以下の手順で、Magic EdenにてNFTを出品とキャンセルをすることができます。 ウォレット接続したアカウントのアイコンをクリック ページに移行したら下へスクロールして、売り出したいNFTをクリック 価格を設定 List nowをクリック List nowをクリックすると、Phantomウォレットが起動しますので、トランザクション実行して完了すると出品されます。 出品されたNFTは「上場したアイテム」に入ります。出品キャンセルをする場合は、下記の動作になります。 「上場したアイテム」をクリック 「Details」をクリック 「上場をキャンセル」をクリック 「上場をキャンセル」をクリックすると、Phantomウォレットが起動しますので、トランザクション実行して完了次第キャンセルされます。 Magic Edenでローンチパッドに参加する方法 Magic Edenでローンチパッド(Launchpad)に参加する方法は、以下のとおりです。 左側の「Launchpad」へ 参加したいものを選ぶ スクロールして、プロジェクトの詳細などを確認することも可能 現在実施されているものを選択 (画像内のようにENDEDと表示されている分は既に終了済み) 各プロジェクトによって、ローンチパッドに参加できる条件は異なっています。 特に、ホワイトリストが必要なものも多く、全てのローンチパッドに参加できるわけではありません。(特に条件が設定されていなものあります) Eden Gameのプレイ方法 Eden Gameからアクセスできるゲームをプレイする方法は、以下のとおりです。 「Eden Game」の「Home」へ (「All Games」を選択すると全てのゲームを表示することも可能) スクロールし、プレイしたいものもを選択 (Play on Meの欄にあるものが、Magic Edenでプレイ可能なゲーム) 概要をチェック可能 スクロールして「Play Now」へ また、概要が記載されている箇所の「Explore Collection」から、各ゲームに関連したコレクションを閲覧可能できます。 マーケットプレイスを利用する上での注意点 マーケットプレイスの利用には、いくつかの注意点・リスクが存在しています。 これは、Magic Edenに限ったことではなく、他のマーケットプレイスでも潜在リスクとして存在しますので、頭の中に入れておいてください。 NFTに関連する盗難・詐欺といった事例は日常的に発生しており、身近なリスクとして以下が挙げられます。 訳のわからないウォレット承認・認証(オファー等)をしてしまって盗難に遭う 偽物のNFTを購入してしまって詐欺的行為に遭う 2020年〜2022年における盗難被害額は1,200億円に及び、日々増加傾向にあります。 上記のようなリスクは、一部になり手段を挙げれば数え切れないほど存在しています。このような形で悪意のあるユーザーがNFTを狙っていることを常に想定して、NFTの利用・管理は慎重に行っていきましょう。 盗難・詐欺に遭遇し失ったNFTの多くは取り戻せません。 イギリス税務当局、詐欺事件調査でNFTを押収 Magic Edenについてまとめ この記事では、主にSolanaのNFTに強みをもつマーケットプレイスであるMagic Edenについて解説しました。 Magic EdenはSolanaのNFTにおいて圧倒的な存在感を持つマーケットプレイスでありながら、現在では4つのマルチチェーンに対応するなどその幅広い展開も魅力のひとつです。 今後も動向を注視していきたいトピックのひとつであると言えるでしょう。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 ー Magic Eden 公式リンク ー Webサイト:https://magiceden.io/ ツイッター:https://twitter.com/MagicEden ディスコード:https://discord.com/invite/magiceden ブログ:https://blog.magiceden.io/

プロジェクト
2023/04/30ノーコードでNFTが発行できる|Manifoldの使い方を解説
この記事では。NFT市場で注目されている「Manifold」の概要とその使い方について解説します。 この記事のポイント Manifoldの概要 Manifoldの登録方法と使い方 Manifoldとは?= 独自コントラクトでNFTをミントできるツール 出典:Manifold Manifoldの公式リンク集 公式サイト manifold.xyz Twitter @manifoldxyz Discord discord.com/invite/y7eyzgwEdJ ドキュメント docs.manifold.xyz/v/manifold-studio 「Manifold」とは、独自コントラクトを作成してNFTをミントできるツールです。 独自コントラクトは、OpenSeaなどのマーケット側のコントラクトアドレスに紐づく共有コントラクトとは違い、自分で作成し所有するコントラクトアドレスに紐づくものです。 マーケット側に依存しない独自コントラクトによるNFTのあり方はWeb3において注目されており、著名なNFTコレクションにも独自コントラクトのものが多いことも事実です。 その一方、自己所有のコントラクト作成は複雑なプログラミング等の知識を必要とし、誰でも気軽にできるとは言えない側面もありました。 しかし、今回紹介するManifoldでは、独自コントラクトの作成からNFTの発行まで、誰でもノーコードかつ手数料無料でできてしまいます。 さらに豊富なアプリケーションをインストールすることでオークションサイトやSBT(ソウルバウンドトークン)の作成が可能になるなど、その拡張性も魅力のひとつです。 Manifoldの特徴 独自コントラクト作成からNFT発行までノーコードでできる手軽さ 手数料無料 豊富なアプリケーションによる拡張性(オークションサイトやSBTの作成など) Manifoldの主な使い方(独自ドメインの作成〜NFTのミント) 出典:Manifold ここからはManifoldの主な使い方について、以下の通り順を追って解説します。 ① Manifoldへの登録 ② 独自ドメイン作成とデプロイ ③ NFTのミント ① Manifoldへの登録 まずはManifoldへの登録からはじめましょう。 1.Manifold<manifold.xyz>にアクセスし、右下の「STUDIO LOGIN」をクリックします。 2.「Connect Wallet」をクリックします。 3.ウォレット側で接続や署名を進めます。 4.プロフィール設定が表示されたら、①「YOUR NAME」に名前、②「YOUR EMAIL」にメール(任意)を入力し、下の③「SUBMIT」をクリックします。 これで登録は完了です。 ② 独自ドメイン作成とデプロイ 登録が終わったら、早速コントラクトの作成を始めます。 1.「New Contract」をクリックします。 2.コントラクト作成画面が表示されるので、以下の項目を入力・選択します。 ① CONTRACT NAME・・・コントラクト名を入力 ② TYPE・・・トークン規格をERC-721もしくはERC-1155から選択 ③ SYMBOL・・・トークンシンボル(ティッカー)を入力 ④ ASCII MARK・・・アスキーマークを入力 アスキーマークはコントラクト作成時にソースコードのコメントとして記録されるアスキーアートのことで、コントラクトを視覚的に識別するために使用されるとのことです。 ここで設定するアスキーアートは幅120字未満が推奨されており、それ以上になるとテキストの折返しなどで形が崩れてしまう可能性があるとのことです。 アスキーアートはこちらのツールを使って作成することができます。もちろん他のツールや自作のものでも構いません。 5.さきほどの①〜④すべてが入力できたら、右上の「Deploy on Goerli」をクリックします。 6.ウォレット側でネットワークの切り替えを許可します。 7.Goerliテストネットで使用するGoerli ETH(gETH)を持っていない場合は下記のようなメッセージが表示されるため、Faucetから無料でGoerli ETHを入手を進めます。すでにお持ちの方は手順14まで飛ばしてください。 8.表示されているリンク<goerlifaucet.com>にアクセスし、右上の「Alchemy Login」をクリックします。 9.画面下部の「Sign up」をクリックした後、氏名、メールアドレス、パスワード等の必要情報を入力して登録します。 10.受信したメール本文の「VERIFY EMAIL」をクリックしてメール認証を行います。 11.メール認証が終わったらアンケート(全5問)が始まるので進めます。 12.アンケートが完了したら手順8の画面に戻りますので、①ウォレットアドレスを入力し、②reCAPTCHA(私はロボットではありません)をチェックし、③「Send Me ETH」をクリックします。 これでウォレットにGoerli ETHが入金されているはずです。Goerli ETHを入手したらManifoldに戻りましょう。 13.手順5と同じく「Deploy on Goerli」を再度クリックします。 14.進行状況が表示され、ウォレット側でガス代などの確認を進めます。 15.下の画像のような画面になればGoerliテストネットでのデプロイが完了です。 「View On Etherscan」をクリックし、「Contract」を選択すれば、作成したコントラクトの詳細を確認できます。 Contract Creator(コントラクト作成者)が自分のウォレットアドレスになっていることや、Contract Source Code(コントラクトのソースコード)に設定したアスキーアートが反映されていることを確認してみてください。 ③ NFTのミント 次はNFTのミントに移りましょう。 1.前回の続きから、「Go to Dashboard」をクリックします。 2.ダッシュボードが表示されるので、「MINT TOKENS TO A WALLET」をクリックします。 3.トークン管理画面が表示されるので、「Create」をクリックします。 4.ミントの方法が4つ表示されるので、実行したいものを選択します。今回は「Single Token」を選択します。 Single Token・・・1つのNFTをミントする Batch of Tokens・・・複数のNFTをミントする(ガス代の節約) Edition・・・同じNFTの複数のコピーをミントする 5.NFT情報の入力や設定の画面になりますので、以下の情報を編集します。 ① ・・・ここをクリックして画像/動画/音声/PDF/3D/HTMLファイルなどをアップロード ② ARTWORK TITLE・・・アートワークタイトルを入力 ③ CREATED BY・・・作者名を入力 ④ EXTERNAL URL (OPTIONAL) ・・・外部URLを入力(任意) ⑤ DESCRIPTION・・・説明を入力 6.下にスクロールすると「PROPERTIES(プロパティ)」を設定できます。右側の「New Property」をクリックし、プルダウンから追加したい項目を選択します。 Text・・・テキスト Number・・・数値と上限 Hidden・・・OpenSea上には表示されず、NFTのメタデータの記述を確認した場合にのみアクセス可能なプロパティ(詳細) Boost number・・・OpenSea上で円グラフで表示される数値とその上限(詳細) Boost percent・・・OpenSea上で円グラフで表示される割合とその上限(詳細) 7.NFTの情報やプロパティの入力・設定が終わったら、右上の「Mint to Goerli」をクリックしてNFTを発行しましょう。 8.受取方法を選択します。自分のウォレットにミントする場合は「Myself」、他者にエアドロップする場合は「Airdrop」をクリックします。今回は「Myself」を選択します。 9.ウォレットアドレスを確認し、「Mint」をクリックします。 10.進捗が表示され、ウォレット側で確認を進めます。 11.トランザクションが実行され、ミントが完了しました。 12.OpenSeaやLookRareのテストネット版にアクセスしてみましょう。「OpenSea」をクリックします。 13.ミントしたNFTが表示されていることを確認します。 14.準備が完了して問題なければ、最後にメインネットへデプロイしましょう。「Go to Dashboard」をクリックし、ダッシュボードからメインネットへデプロイしたいNFTを選択したら、「Mint to Mainnet」をクリックします。 これでNFTをメインネットへデプロイすることができました。 コントラクトの編集 コントラクトの編集の方法は以下の通りです。 1.画面左上の「マ」アイコンをクリックし、ホーム画面を表示する。 2.ホーム画面に作成済みのコントラクトが表示されるので、編集したいコントラクトをクリックする。 3.「Edit contract」をクリックし、コントラクト情報を編集する。 ※コントラクトがすでにブロックチェーンにデプロイされている場合は、コントラクトを編集しても古いコントラクトが残ってしまい、新しいコントラクトが作成されてしまいます。 ※すでにトークンがデプロイされている場合、コントラクトを編集することはできません。 トークンの削除, コピー, 設定 トークンの削除、コピー、設定などの方法は以下の通りです。 1.コントラクトのダッシュボードから「Tokens」をクリックする。 2.一覧から目当てのトークン(NFT)の「 ︙ 」アイコンをクリックして、以下の操作を選択できます。 Create a copy as draft・・・下書きとしてコピーを作成する Token Settings・・・トークン設定を開く Delete token・・・トークンを削除する 3.トークン(NFT)のアイコンをクリックすると、トークン情報を編集することができます。 アプリケーション Manifoldではアプリケーションをインストールすることで様々な機能の拡張することができます。 アプリケーションメニューへは以下の手順でアクセスできます。 1.画面左上の「マ」アイコンをクリックし、ホーム画面を表示する 2.「Apps」タブをクリックし、アプリケーションメニューを開く 多数のアプリケーションが利用可能ですが、以下にその一例と概要を挙げます。 Claim Page・・・NFTをクレームできるミントサイトの作成 Burn Redeem・・・ミントしたNFTを交換するサイトの作成 Gallery・・・NFTオークションサイトの作成 Curate・・・NFTのギャラリーサイトの作成 Souldrop: Soulbound Claims・・・SBT(ソウルバウンドトークン)をクレームできるサイトの作成 その他の設定 各種設定へは以下の手順でアクセスできます。 1.画面左上の「マ」アイコンをクリックし、ホーム画面を表示する 2.「Settings」タブをクリックし、設定メニューを開く 設定メニューからはプロフィール設定や、TwitterやDiscordとの連携、アドレス、コントラクト、トークンの管理などができます。 まとめ Manifoldの概要とその主な使い方について解説しました。 誰でも簡単に独自コントラクトでNFTを発行できる手軽さと、豊富なアプリケーションによる拡張性が魅力的ですね。 この機会にオリジナルのNFTをセルフミントしてみてはいかがでしょうか。

プロジェクト
2023/04/18NIKE(ナイキ)NFT・Web3への参入動向の一覧 | スニーカー、プラットフォームを展開
NIKEは、NFT・Web3への参入に成功している企業の1つです。 これまで、NIKE関連のNFT(子会社のコレクション含む)は250億円以上の収益を上げており、取引高も1,000億円を超えています。 仮想通貨市場全体が落ち込みを見せている中、プラットフォームの立ち上げなど積極的な動きを見せており、今後もチェックしていきたい動向がいくつかあります。 この記事では、そんなNIKEとNFTのこれまでの主な動向やこれからについて、取り上げています。 NIKEとNFT [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元: pixfly / Shutterstock.com[/caption] 2021年から2022年にかけて、知名度の高いブランドを持つ多数の企業が、NFTやWEB3への参入を表明してきました。 関連:ハイブランド企業によるNFT活用一覧 その中でも、NIKEはもっとも積極的な企業の1つとして挙げられます。これまで、関連企業(RTFKT)の買収からスニーカーをモチーフにしたNFTの販売等の積極的な動向を見せています。 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元: NFT Brand Case Study[/caption] NFTの流通・収益額を見ても、これまで1.8億ドル以上(約250億円)の収益を上げており、NIKE(CloneXなどを含む)の存在感は圧倒的です。2位のドルチェ&ガッバーナとも大きな差が付いていることが分かります。(2022年12月時点) これまでの取り組みやすでに発表されている動向などから、今後もNIKEではNFTやWeb3にまつわる取り組みが発表されていく可能性が高いと言えるでしょう。 NIKEとNFTの主な動向まとめ [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元: Kidney Stone / Shutterstock.com[/caption] これから、NIKEとNFTに関する主な動向について年代別にいくつか取り上げていきます。NIKEのこれまでの取り組み・事業などについてチェックしていきましょう。 2019年~2020年 - 商標と特許 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元: Benjamas_Photovec / Shutterstock.com[/caption] 具体的なNFTの発行などは見られなかったものの、2019年から既にNIKEはクリプト周りの特許や商標を取得しようと試みていました。2019年4月には、仮想通貨関連と見られる商標「CRYPTOKICKS」の申請を提出しており、こちらの商標は後述するプロジェクトと関連があるものと見られます。 2019年の年末には、スニーカーをトークン化する特許も取得していました。特許の内容としては、NIKEがスニーカーに対してIDを生成し、各スニーカーに対応するトークンを発行するというものです。 こちらも、後述するプロジェクト(Cryoto kicks iRL)と親和性の高い特許であると言えるでしょう。 2021年 - RTFKTの買収 Welcome to the family @RTFKTstudios Learn more: https://t.co/IerLQ6CG6o pic.twitter.com/I0qmSWWxi0 — Nike (@Nike) December 13, 2021 2021年に、NIKEは「RTFKT」の買収を発表しました。RTFKTは、バーチャルなスニーカーやClone Xを展開するNFTのプロジェクトの1つです。著名なアーティストである村上隆氏と提携し提供されたCloneXのアバターコレクション(NFT)などでも知られています。 著名なブランドとNFTプロジェクトのコラボはいくつか見られた事例ではあるものの、買収を行うというのは初めての事例でした。 買収以降、NIKE関連のNFTの動向はRTFKTが中心になったりコラボが行われることが少なくないため、NIKEの動向に注目している方は、RTFKTもウォッチしていくのがおすすめです。 2022年 - NFT・プラットフォーム・スニーカーの展開 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元: Nattawit Khomsanit / Shutterstock.com[/caption] 2022年はNIKE、RTFKTの動向が活発的になった年でした。これから、主な動向についてまとめていきます。 Dunk Genesis CRYPTOKICKSの発表 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元: RTFKT x Nike Dunk Genesis CRYPTOKICKS[/caption] 2022年4月に、NIKEが買収したRTFKTは、スニーカーをモチーフにしたNFTであるDunk Genesis CRYPTOKICKSを発表しました。NIKEとコラボしたNFTということもあり、各シューズには、NIKEのロゴがデザインされています。 直近では、フロアプライス・取引高ともに下落傾向にあるものの、これまで7,900ETH以上の取引ボリュームがあります。(2022年12月時点) .SWOOSHの発表 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元: dotSWOOSH[/caption] 2022年11月には、WEB3プラットフォームである.SWOOSHを発表しました。 .SWOOSHは、バーチャルな製品の共同制作を行う機会などを提供するプロジェクトの総称で、デジタルコレクションの立ち上げなどさまざまな動きが見られると考えられています。 プラットフォームということもあり、コミュニティに向けたさまざまなサービス・イベント・体験などが立ち上げられていく旨が示唆されています。 関連:NIKE(ナイキ)web3プラットフォーム「.SWOOSH」を立ち上げ 2023年4月18日に.SWOOSHは、初のデジタルコレクションになる「Our Force 1」のサービス提供を開始します。(海外時間) 🚨 AIRDROP IS TOMORROW 🚨 Now that we have your attention, let’s talk about what that means 👇 pic.twitter.com/n79QO9dpeH — .SWOOSH (@dotSWOOSH) April 17, 2023 .SWOOSHにOur Force 1を購入する機会を提供しています。Our Force 1は、Air Force 1をモデルとしたユニークなデジタルスニーカーです。所有していることで今後、ユーティリティも解除されていく予定です。詳しくは下記の記事をご覧ください。 関連:NIKE(ナイキ).SWOOSHのOur Force 1 ビジュアル公開|ユーティリティも発表 サッカーユニホームのドロップ Through the wormhole ☄️ RTFKT Clone X 🧬 in the Footballverse 🌐 with @nikefootball legends ⚽ 👇 pic.twitter.com/dq9bk0ORgN — RTFKT (@RTFKT) November 16, 2022 同じく2022年11月に、サッカーユニホームのNFTを抽選でドロップする発表を行いました。 抽選の参加に伴って必要なのはRTFKTアカウント、MetaMaskといったものでしたが、CloneX保有者は当選確率が上がるという特典が見られました。時期的に2022年ワールドカップに伴ったドロップと見られます。 関連:サッカーユニホームNFTを抽選でドロップ Cryptokicks iRLの発表 Our next-gen innovation drop Cryptokicks iRL 👟⚡️ 1st native web3 sneaker Combining decades of @Nike tech 👨🔬 & RTFKT vision to merge worlds 🌎🌐 Details & FAQ: https://t.co/0I5cwrd8bb pic.twitter.com/A1jP8xg0NZ — RTFKT (@RTFKT) December 5, 2022 2022年12月には、RTFKTによってNIKEとコラボしたスニーカーであるCryptokicks iRLが発表されました。Cryptokicks iRLは、NFTを購入することによって現物のCryptokicks iRLスニーカーを手に入れることが可能です。(米国居住者向け) 現物のスニーカーは、さまざまな技術を搭載した最先端のスニーカーとなっており、NFTとスニーカーを連動させる機能や自動で足にフィットさせる機能などが付与されています。 さまざまな取り組みから、2022年はNIKEとRTFKTの動きが積極的になっていると言えるでしょう。 関連:スニーカー「Cryptokicks iRL」を発表 RTFKT × Air Force 1 SZN 1 Lookbook is now live! 👟 pic.twitter.com/TcEfaYCGHj — RTFKT (@RTFKT) April 11, 2023 RTFKTとAir Force 1のフィジカルアイテムが提供されることが発表されました。2023年4月24日から5月8日まで、デジタルコレクティブルNFT(デジタルスニーカー)の所有者は、フィジカルスニーカーと交換できます。 このForging EventはRTFKTの公式ウェブサイトで開催され、フィジカルスニーカーは2023年第4四半期に出荷予定です。参加者はERC-1155トークンをバーンし、ERC-721トークンを受け取ります。これは後でRTFKT WM NFCチップを介してフィジカルアイテムにリンクするために必要とのことです。 Air Force 1がRTFKTとコラボすることで、フィジタルアイテムとして提供されることが予定されています。 関連:NIKE × RTFKT、4月24日からフィジカルスニーカー獲得可能に 今後のチェックしたい予定・動向 新たなスニーカーなどの取り組み プラットフォームを軸にした活動 これから、NIKEとNFTの今後について注目していきたいトピックをいくつか取り上げていきます。NIKEとNFTのこれからをチェックしていきましょう。 新たなスニーカーなど従来どおりの取り組み これまで、NIKEはRTFKTとのコラボなどを通して、NFTや現物(Cryptokicks iRL)などのシューズを発表しています。 上記のような傾向を考慮すると、今後も何らかの形でNFTを用いたサービス、プロダクト、作品を世に出していく可能性が考えられます。 また、NIKEはROBLOXにて「NIKELAND」を提供しているのでNFTのみならず、今後メタバースの領域においても何らかの動向を見せる可能性があります。 プラットフォームを軸にした活動 まだ、はっきりとした全貌が明らかになっていないものの、NIKEが発表したプラットフォームである.SWOOSHではさまざまな活動を行っていく旨が公表されています。 そのため、.SWOOSHを通したさまざまな活動についても注目していきたいです。特に2023年には、デジタルコレクションを.SWOOSHから展開していく旨が示唆されています。 NFT・Web3の領域としてどのように関連していくは、まだ正確にはわかっていませんが今度の動向が気になるところです。 他ブランドの登場 INTRODUCING ADIDAS VIRTUAL GEAR Unveiling the genesis collection of adidas Virtual Gear 🧵👇1/6 pic.twitter.com/FUt9Qhj8VO — adidas Originals (@adidasoriginals) November 16, 2022 NIKEがNFTやWEB3周りの参入に積極的ではあるものの、NIKEのみではありません。前述した通り、NIKE以外にもNFTを発行しており、既に収益を上げているブランドは多数見られます。 例えば、NIKEと同じくスニーカーとして著名なadidasもデジタルファッションNFTやBAYCとコラボしたNFTプロジェクトを発表する動きを見せています。 NIKEの成功事例から今後ファッション、スポーツブランドや企業から、同じような動きをする可能性が考えられます。どういった企業がNFTに参入していくのか楽しみです。 関連:adidas(アディダス)デジタルファッションNFTを公開 NIKEとNFTについてまとめ この記事では、NIKEとNFTの動向についてご紹介しました。 NIKEは、非常に積極的にNFTやメタバースに参入しており、プラットフォームの立ち上げなども行っていることから、今後も何らかのイベントが期待できると言えるでしょう。 一方で、ハイブランドがNFTに続々と参入している状態なので「ブランド × Web3」というのは、業界を盛り上げる領域になっていく可能性が考えられます。 【ハイブランドNFT】ハイブランド企業によるNFT活用一覧 – 参考リンク– dotSWOOSH 公式サイト:https://www.swoosh.nike/location RTFKT Twitter:https://twitter.com/RTFKT NIKE Twitter:https://twitter.com/Nike OpenSea:https://opensea.io/collection/rtfkt-nike-cryptokicks
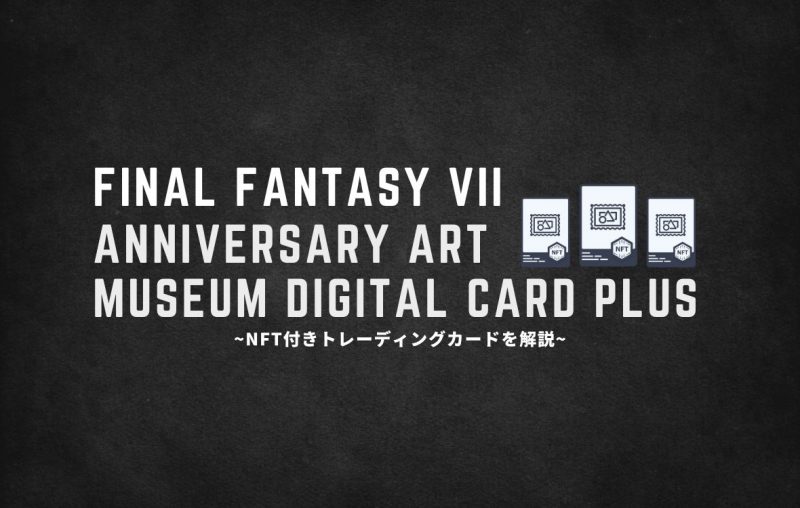
プロジェクト
2023/04/17FF7 アニバーサリートレーディングカード|NFTデジタルカードの取得方法を解説
ファイナルファンタジーVII(FF7)の25周年を記念した「FFVII ANNIVERSARY ART MUSEUM DIGITAL CARD PLUS」を1BOX購入しました。この記事では、商品解説とNFT取得解説を行なっています。 フィジカルの商品は、トレーディングカードなので困ることはないと思いますが、1パックに1NFTの引換券が入っており、購入者にファイナルファンタジーVIIを提供しています。こちらの取得方法がわからない方は、ぜひご覧ください。 FFVII ANNIVERSARY ART MUSEUM DIGITAL CARD PLUS この商品は、ファイナルファンタジーVIIの25周年を記念して、2023年3月31日に販売されたトレーディングカードです。ゲーム内の名場面が詰まったこのカードセットは、公式販売(オンライン)ではすでに売り切れとなっています。 さらに、スクウェア・エニックスはEnjinのEfinityプラットフォームを活用して、NFTとしてデジタルカードも購入者に提供しています。全207種類の中から任意のデジタルカードをゲットすることが可能で、ファンのコレクションに新たなサービスをもたらしています。 Enjinが開発するブロックチェーン Efinity / $EFI の特徴、概要を徹底解説 カードBOXの内容 1BOXあたり、20パック入っています。上記の画像は、1BOX開封してパックを並べた画像となっています。 1パックに含まれるカード枚数と種類 全コレクション207種 内容:1パック7枚入り(内1枚はデジタルカード引換カード) ノーマルカード:99種類 アナザーノーマルカード:3種類 プレミアムカード:99種類 アナザープレミアムカード:3種類 シークレットカード:3種類 販売価格:440円(税込) カードサイズ:L89xW63mm 1パックに入っているカードは通常のトレーディングカードのように上記の種類のどれかが入っています。全コレクション207種類となっているので、1BOXでコンプリートするのは不可能です。コンプリートしたい方は、2BOX以上購入する必要があります。最もレアリティが高いカードでは、箔押しのカードがあります。現在、メルカリ等の二次流通で約7,000円~10,000円の相場で取引が行われていました。 カードサイズが、ポケモンカードや遊戯王のカードより若干大きいサイズとなっているので、綺麗に保管したい方はサイズを合わせたスリーブ等を準備しておくといいでしょう。 獲得カード(一部) プレミアムカードの表面 プレミアムカード裏面 ノーマルカード表面 ノーマルカード裏面 今まで様々な表現をされてきたファイナルファンタジーVIIのキャラたちがパックの中に入っています。裏面にはプロフィール等が記載されており、よりキャラクターの情報を知ることができます。 NFT取得方法の解説 ここからNFTの取得方法に移ります。NFTの取得に必要なものは、以下になります。 スマホ Enjinウォレット(アプリ) デジタルカード引換券 必要なものは、この3つだけになります。NFTを扱ったことがない方でもスマホとアプリのみで完結することが可能なので、誰でも受け取ることが可能となっています。 アプリ版のEnjinウォレットが必要になってきますので、こちらのウォレット管理の知識は勉強する必要があります。 1パックに1枚含まれるNFT引換券 こちらのカードが1パックに1枚入っています。このカードの裏面にあるコードを使用することで、1枚のNFTを獲得することが可能です。 裏面を確認すると、QRコードとコードが記載されています。カメラで読み込むか、コードを入力するか任意で選ぶことができます。引換期限は、1年後の2024年3月31日となっているので、期限内にNFTを獲得しましょう。 NFT取得 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] まず、こちらの公式ウェブサイトにアクセスをしてください。 https://bc-goods.square-enix.com/ Enjin Wallet連携 Enjin Wallet連携 承認する この順番でタップを行なってください。簡単にWebサイトでEnjin Walletを連携させることができます。 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] 右上のメニューアイコンをタップ 引換所 引換コードを入力 引換コードを入力する際は、手入力とQRコード読み込み入力があります。枚数が多い場合はQRコード読み込みのみで、コードが反映されるので、QRコードを読み込む方を推奨します。引換コードの入力が終了したら、3枚目の画像の右側にある「引換券を使う」をタップしてください。これで、カード選択画面に移行することができます。 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] カード選択画面は、このようになっています。引換券の枚数だけ任意で好きなデザインのNFTを選ぶことが可能です。ページ下部には、スクロールボタンがあるので全てのデザインを見てから好きなカードに決めることを推奨します。 また、最終ページには「SECRET」が準備されています。「01/May/2023」と記載されているので、こちらは追加カードとして後から出てくることが予想されます。このカードまで待ちたい方は、引換券を大事に取っておくのも選択肢としてはありです。 選択方法 + - をタップで選択 選択後「確認へ」をタップ [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] 「確認へ」をタップ後、確認ページに遷移します。こちらで規約に同意をして、ページ下にある「引き換える」をタップすると引換が始まります。選択し直しをしたい場合は「選び直す」をタップして、選択し直してください。 引換完了の画面が出たあと、数分待つとNFTが接続したウォレットに届きます。 NFT確認方法 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] NFTがウォレットに届いたら、下記の手順でNFTを確認することが可能です。 コレクティブル ウォレット選択 カード(NFT)選択 詳細確認 デザインは、基本的にフィジカルカードと同じものとなっています。フィジカルカードで獲得できなかったカードも選択可能です。フィジカルと合わせてNFTも選択するのか?それともデジタルのみで所有するのか?これはユーザー次第となっています。 ここまでで、NFTの取得は完了となります。基本的にスマホ1台で全ての工程を終えることができるので、NFTに馴染みのない方でも取得可能となっています。 しかし、ウォレットの管理だけは注意してください。Enjinウォレットを作成する際にバックアップのシードフレーズ等が出てきます。シードフレーズの保管は必ず行なってください。紛失、流失してしまうとNFTの所有ができなくなるケースがあります。厳重に保管を行いましょう。 シードフレーズに関しては、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧下さい。 シードフレーズとは? | 管理方法、秘密鍵との違いを解説 PCでの閲覧方法 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] PCでNFTの閲覧も可能となっています。PCから下記のウェブサイトへアクセスをしてください。 https://bc-goods.square-enix.com/ アクセスをしたら「Enjin Wallet連携」をクリックします。 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] QRコードが出てきますので、Enjin Walletのアプリのカメラ機能で読み取ってください。その後、Enjin Walletがウェブサイトとの接続を確認してきますので、該当ウォレットを接続してください。 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] 「引換アイテムを見る」をクリックします。 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] カードをクリックします。 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] 黒いカードパックの方をクリックします。 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] ご自身が保有しているNFTが閲覧できるようになります。カードフォルダーのようなスクラップブックというところで、好きな順番にカードを並べることが可能となっています。 [caption id="attachment_78035" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:Square Enix BCGoods[/caption] カードをクリックすると、詳細を確認することができます。絵柄をクリックするとカードの裏面も確認することが可能となっているので、閲覧してみてください。スマホアプリだと小さくて見応えがないという方は、PCで閲覧するとよりNFTの所有感が味わえるかもしれません。こちらの方でもぜひご覧になってみてください。 まとめ・所感 海外のトレーディングカード × NFTでは、HroというDCコミックスのIPを活用したプロジェクトがありますが、国内でトレーディングカードとNFTを連携させたプロジェクトはおそらく初のものだったと思われます。フィジカルのカードの開封だけでも満足感のある商品となっていましたが、その後にデジタルのカードを取得できるという体験は新鮮でした。 デジタルカード(NFT)の二次流通マーケットが現在はないので、デジタルカード(NFT)の取引が行えないのが少し残念ですが、サービスとしては十分楽しめるものでした。日本のトレーディングカードはポケモンカード、遊戯王、ワンピース、ドラゴンボールなどと世界的にも人気な商品がありますので、今後デジタルと融合する未来があれば楽しみです。 NFTの取得も初心者に優しい設計となっており、可能性を感じるものとなっていました。ただ、ウォレットの管理という部分は初心者の方は気をつけてください。シードフレーズ等の管理は必ず行なってください。 今後、この領域がどのように発展していくのか、注目していきたいところです。 - FFVII ANNIVERSARY ART MUSEUM DIGITAL CARD PLUS 関連リンク - https://www.jp.square-enix.com/goods/ff7_artcard/ https://bc-goods.square-enix.com/

プロジェクト
2023/03/18BSC(BNB Chain)とは?バイナンス主導のブロックチェーンの特徴や注意点を解説
BSC(BNB Chain)は、EVM互換性のあるスマートコントラクトに対応したL1ブロックチェーンです。 DeFiにおいて50億ドル近くのTVLを持ち、周辺のエコシステムとの親和性の高いBNBの時価総額は500億ドルを超えています。 どちらの指標もETHに次いで大きな規模を持っており(時価総額はUSDTを除く)、代表的なプロジェクトであると言えるでしょう。 この記事では、そんなBSCについて以下のような観点から解説しています。 この記事のまとめ ・Binance主導のブロックチェーン ・一定程度の中央集権を許容しながら高い処理能力を持つ ・さまざまな面でETHに次ぐ規模を持つ ・デフレを期待できるバーンを積極的に行っている BSCとは?Binance主導のブロックチェーン BSC(BNB Chain)は、スマートコントラクトを扱えるL1のブロックチェーンです。 Defi Llamaのデータによると、BSCはトップ3に入るTVL(Total Value Locked)を記録しています。 これから、BSCの概要や特徴などについて、以下の観点から解説していきます。 ・概要 ・かんたんな特徴 ・ビーコン・ZK・サイドチェーンなどとの違い ・BSCの現状 BSCの基本的なポイントをチェックしていきましょう。 BSC(BNB Chain)の概要 BSC(BNB Chain)は、スマートコントラクトを実装したL1のブロックチェーンです。 もともと、Binanceは高速で大量の取引を処理可能なBinance Chainの開発を行っていました。 しかし、DeFiにおけるイーサリアムの台頭などによって、さまざまなプロジェクトを構築可能なスマートコントラクトを実装したブロックチェーンを開発することになり、BSCが登場します。 Binance Chain・BSCともにガス代の支払いなどにBNBに用いるものの、ブロックチェーンが備えている機能には大きな違いがあります。 BSCは、スマートコントラクトを扱えることから、イーサリアムなどと同じようにさまざまなプロジェクトが構築されており、例えばDeFiではPancake Swapといった代表的なプロジェクトがBSCで運用されています。 かんたんな特徴 BSCはEVMと互換性があり、同じようなプロジェクトが構築されているという特性上、イーサリアムと基本的な要素は似通っています。 しかし、以下のようなポイントにBSCの特徴、イーサリアムとの違いが見られます。 高速なファイナリティと高いTPS 安いガス代 四半期ごとの大規模なバーンイベント 限定的なノード数 上記特徴をまとめると、BSCは限定的なノードで若干の中央集権的な側面を持ちながら高い処理能力を持ち、定期的に大規模なBNBのバーンを一定期間で実施しているプロジェクトです。 特に高い処理能力と安いガス代は、DeFiの流行によってイーサリアムにおいて諸問題が発生した際に、BSCの大きな魅力として多数の利用者を抱え込むきっかけの一つとなりました。 ビーコン・ZK・サイドチェーンなどとの違い Binanceが主導しているプロジェクトは多岐にわたっており、BSCとの違いが分からない・・・という方もいるかもしれません。 そのため、BSCと他のブロックチェーンの違いをかんたんにチェックしていきましょう。 プロジェクト名 BNB Beacon Chain Zk BNB BSC BNB GreenField 概要 L1 ロールアップ L1 分散型ストレージ 特徴 TendermintとCosmos SDKで構築 より低コストで高い処理能力 汎用性の高さ 分散性の高いデータ管理 期待される用途 BNBにおけるステーキング、 ガバナンスなど 高頻度のトランザクションが 要求されるプロジェクトなど 高い構成可能性・小規模プロジェクト 分散型ストレージ、NFTなど 上記のプロジェクトをまとめて「BNB Chain(Build N Build Chain)」と言います。 Beacon Chainは、BNBにおけるステーキング・ガバナンスを担います。 Zk BNBは、BSCをベースにしたロールアップ(ガス代軽減などが期待できる)、BNB GreenFieldは分散型ストレージのプロジェクトです。 また、この他にもBNBサイドチェーンが展開されていたり、OPロールアップを利用したプロジェクトのローンチも示唆されているため、BSCと近しいプロジェクトはいくつか見られます。 BSCの現状 これから、いくつかBSCのブロックチェーンの利用状況や、DeFi市場における状況などについてチェックしていきます。 BSCには、2023年3月時点で2.6億以上のアドレスが存在しており、直近の数カ月はユニークなアドレスが毎日100万程度、アドレスは毎日20万~80万程度のスピードで増加傾向にあります。(タイミングにより増加具合は大きく上下します) (引用元:BSC Scan) これは、イーサリアム(合計アドレス:約2.2億)などの競合と比較しても大きな高い数値となっており、後発であることも踏まえるとBSCがアクティブに利用されているチェーンである事がわかるでしょう。 DeFiにおけるTVLは50億ドル程度でイーサリアムに次いで2位、その中でも最もTVLが大きいのはPancakeSwapで、BSC上TVLの約半分近くがPancakeSwapによってロックされています。 (引用元:DefiLlama) その他のプロジェクトにおけるTVLでは、venus(約7億ドル)、Alpaca Finance(約4億ドル)、BiSWap(約2億ドル)、Coinwaid(約1.7億ドル)などが続いています。 BSCの注目したいポイント これから、BSCが持つ注目ポイントについて以下の点から解説していきます。 ・高い処理能力 ・PoSAを採用するコンセンサス ・デフレを期待できる仕組み BSCの特別なポイントにチェックしていきましょう。 高い処理能力 BSCはEVM互換性を持ち、イーサリアムと同じような利用方法ができるのに加えて、高い処理能力を持ちます。 2,000TPSを実現するポテンシャルを持ち(2023年には5,000TPSになる可能性も)、3秒間に1度ブロックが生成され、ファイナリティまでは30秒〜45秒程度です。 また、処理能力・ガス代ともにイーサリアムと比較すると優位性があり、低いコストでさまざまなブロックチェーン上のプロダクトに触れることができます。 今後も、さまざまな取組によって処理能力を向上させる方針のようなので、より快適な利用が可能になっていくかもしれません。 PoSAを採用するコンセンサス BSCでは、DPoSとPoAを組み合わせた「PoSA」というコンセンサスを採用しています。 概ね、DPoSと似たもので、多くの投票力(BNB)を委任された主体がバリデーターとなります。 【初心者向け】仮想通貨(ブロックチェーン)におけるコンセンサスアルゴリズムとは? 前提として、バリデーターの候補となるには10,000BNBをステークする必要があり、そのバリデーター候補にBNB保有者がBNBを委任していきます。(BNBの委任は一般の方でも気軽に可能) BSCでは、一定時間内でもっともBNBを委任されたバリデーターをまとめて「バリデーターセット」となり、バリデーターセットが中心になってトランザクションを処理していきます。 2023年3月時点で、バリデーターセットには29のバリデーターが選ばれます。(詳しくは後述しますが、29の中にも選出方法に違いがあるバリデーターが含まれます。) このバリデーターセットは、一定時間で交代する仕組みになっていて、再度一定時間が経つと委任されたBNBを元にバリデーターセットが選出されます。 記事執筆時点において、BSCには52のバリデーター(候補)が確認でき、この中からバリデーターセットになるバリデーターが選出されることになります。 (引用元:BNB CHAIN) ただし、前述したとおり、基本的には上位のバリデーターが選出され、各バリデーターによってステータスも異なっているため、全てのバリデーターが常にネットワークに参加している状態ではありません。 また、他のPoSやDPoSを採用するブロックチェーンと同様に、バリデーターはトランザクションを処理すると、ガス代を原資にした報酬を受け取ります。 デフレを期待できる仕組み BSCはもちろん、他のBNBチェーン全体の基盤となっているBNBには、バーンを用いた供給を絞る試みが実装されており、デフレを期待できる仕組みが存在しています。 (バーン = Burnは、仮想通貨を利用できない状態にすることで、間接的に市場の仮想通貨を無くしていくこと) BNBは、約2億枚が発行されており、そのBNBが徐々に減少していく仕組みが実装されていることになります。 BNBには、主に2つのバーンが実装されており、1つ目が「ガス代を元にしたバーン」、2つ目が「四半期ごとのバーン」を元にしたバーンです 1つ目のガス代を元にしたバーンでは、ブロックチェーンの利用者によって支払われたガス代の1部をバーンすることによって、市場に流通するBNBを自動的に絞る仕組みです。 これまで、このバーンを通して15万枚以上がバーンされました。 次の四半期バーンは、価格と四半期ごとに生成されたブロックの数を参考にした計算式を元に、四半期ごとにBNBを大量にバーンしていくものです。 直近のバーンでは、200万枚以上がバーンされており、ガス代の取引手数料を元にしたバーンよりも非常に影響力が強いです。(1億枚を切るまで続く) 上記のような取り組みによって、これまで4,400万枚がバーンされており、20%程度の供給が減少していることになります。 BSC上の代表的なプロジェクト 前述したように多数の利用者が存在しているBSCには、さまざまなプロジェクトが構築されています。 代表的なプロジェクトには、以下のようなものが挙げられます。 PancakeSwap (DEX) Venus (レンディング) Alpaca Finance (レバレッジファーミング) イーサリアムほどではないものの、大規模なプロジェクトが複数展開されており、BSCの恩恵を受けて低いコストで利用可能です。 実際に利用するには、ウォレットの設定などが必要になるので、気になる方は以下をチェックしてみてください。 メタマスク(MetaMask)でのBNBチェーン(BSC)への接続方法を解説 BSCの注意点・リスク これから、BSCの注意点やリスクといった観点から、いくつか注目したいポイントをご紹介していきます。 ・イーサリアムやビットコインよりも中央集権的 ・Binanceの影響力によるリスク ・使用に伴う潜在的なリスク BNBの購入やBSCの利用前に押さえておきたいポイントをまとめました。 EthereumやBitcoinよりも中央集権的 BSCは、EthereumやBitcoinなど、一般的に代表的なチェーンに向けられるイメージとは、少し特色が異なるポイントがあります。 それは、分散性を一定程度犠牲にしているという点です。 前述したとおり、BSCのバリデーター候補は50程度、その中でアクティブに取引を処理するバリデーターセットは29に限定されます。 どちらも特有の批判はあるものの、分散性の高さに定評のあるEthereumやBitcoinに対して一般的に想像される分散性とは異なります。 (29のバリデーターのうち、何らかの問題が発生した場合は、他のアクティブではないバリデーターが補完する仕組みなどはあります) BSC特有の問題ではなく、似たような構造を持つブロックチェーンが同様に持つ問題ではあるものの、リスクの1つとして注視が必要でしょう。 https://twitter.com/BNBCHAIN/status/1506730488727285771?s=20 ただし、徐々に分散性を上げていこうという取り組みも確認できます。というのも、元々BSCのバリデーターの数は現在よりも少なくなく、より中央集権的でした。 現在はアクティブになるバリデーターの数を拡大していることに加えて、これまでアクティブではなかったバリデーターも、バリデーターセットに加えられる余地が与えられました。 具体的には、バリデーター候補の中からランダムに選出する枠を設け、アクティブではないバリデーターにBNBを委任するインセンティブや、非常時にバックアップとなるバリデーターが品質を維持するインセンティブが期待できるようにしました。 (現在は29のうち、8が候補のバリデーターから選出されていますが、セキュリティ維持のためブロックを生成する機会は限定的です) また、今後アクティブなバリデーターを29から100に拡大する計画も存在しており、より分散性が高く、安定性を保つブロックチェーンにするための開発が進んでいます。 Binanceの影響力によるリスク BSCのエコシステムはコミュニティによってさまざまな開発が進んでいますが、さまざまな面でBinanceが大きな影響力を持っています。 仮にダイレクトにBSCに影響を与える問題でなかったとしても、Binanceに何らかの問題があった場合にレピュテーションリスクが発生する可能性は考えられるでしょう。 例えば、FTXが破綻した際にはSolanaが他の仮想通貨と比較して、SOL価格やDeFiのエコシステムにおいてよりネガティブな影響が及んだ事例がありました。 類似するようなリスクは、BSCやBNB Chain関連のプロトコル・プロジェクトにも存在している可能性があります。 使用に伴う潜在的なリスク BSCのエコシステムを利用したさまざまなユースケースには、DeFiやBSCが持つ潜在的なリスクを含んでいます。 DeFiを利用したさまざまなリスクはもちろん、BSCでは直近でブリッジのトラブルでブロックチェーンが停止するトラブルがありました。 致命的な被害はでなかったものの、今後も類似のトラブルが出てくる可能性はあるでしょう。 https://twitter.com/CryptoTimes_mag/status/1578187238504292352 BSCに限らず、どの仮想通貨にも見られるリスクではありますが、常にバグやハッキングといった潜在的なリスクは警戒しておく必要があります。 BSCについてまとめ この記事では、BSCについてさまざまなポイントから解説しました。 BSCはEthereumに次いで、規模が大きなブロックチェーンです。 それに加えて、業界最大手のBinanceが主導していることもあり、今後もさまざまな方面で影響を与える可能性が高いため、注視していきたいと言えるでしょう。



















 有料記事
有料記事


