
プロジェクト
2024/04/29Stacking DAO:流動性スタッキングでビットコインのレイヤー2革命を牽引
ビットコインのレイヤー2市場は2025年までに240億ドル規模(現在約3.7兆円)まで成長すると予想されており今後のクリプト市場を牽引する重要なテーマとして認識されています。 本記事では、そんなビットコインのレイヤー2の主要プロジェクトであるStacksの課題を解決する「Stacking DAO」について解説します。 Stacking DAOに預け入れられた資金は1億ドルを超えており、Stacksエコシステムにおいて圧倒的なシェアを誇っています。直近では、リワードが期待できるポイント20倍ブーストのキャンペーンも行うなど注目点も多いです。 是非、本記事でStacking DAOについての見識を深めていきましょう。 前提知識:Stacksの仕組みや最新情報 Stacking DAOはStacksと密接に関わりのあるプロジェクトであるため、前提知識としてStacksの概要や仕組みを簡単におさらいします。 Stacksは、ビットコインチェーンを土台のレイヤーとして使用した上で処理能力を向上させ、イーサリアムのようにスマートコントラクトとアプリケーションの実装に焦点を当てているビットコインのレイヤー2プロジェクトです。 同プロジェクトは先日、「ブロック生成速度の大幅短縮」「ビットコインのフォークによるTx再編成の影響無効化」などを達成する大型アップグレードを開始しました。また、このアップグレードが終了した後、$BTCと1:1の価値を持つ$sBTCがStacksネットワーク上で正式にローンチされることが決まっています。 Nakamoto has begun rolling out 🧡 At Bitcoin block 840,360, the first fork kicked off the two-step rollout process that will bring us Nakamoto! This means there's only one more step left before fast blocks, Bitcoin finality, and more are available to all! Read more 🧵 1/6 pic.twitter.com/dvE0QkSlGt — stacks.btc (@Stacks) April 22, 2024 StacksではPoX (Proof of Transfer) と呼ばれる、独自コンセンサスメカニズムが採用。また、ガス代やネットワークの保護のユーティリティを持つネイティブトークン$STXが発行されています。 Stacksの重要な要素であり、Stacking DAOとも密接に関わってくる機能として「スタッキング (Stacking)」があり、これは$STXを一定期間ロックすることでコンセンサスに参加し報酬を得る行為を指します。 [caption id="attachment_112508" align="aligncenter" width="537"] スタッキングのフロー[/caption] 一般的に知られるステーキングとスタッキングの違いは、預け入れた通貨と報酬の通貨が同じか否かで、イーサリアムのステーキングでは$ETHを預けると報酬として$ETHが獲得できるのに対し、Stacksのスタッキングでは$STXを預けると報酬として$BTCが得られます。 本題:Stacking DAOとは?=流動性スタッキングプロジェクト [caption id="attachment_112447" align="aligncenter" width="889"] 引用元:Stacking DAO[/caption] Stacking DAOは、前述したStacksの流動性スタッキング (Liquid Stacking) プロジェクトです。 Stacking DAO経由でのスタッキングにより「$stSTX」が発行され、この$stSTXはDeFiエコシステムなどで使用可能であるため流動性が確保されます。 現在、Stacksでスタッキングを行う場合、以下のような課題が存在します。 スタッキングの解除までに2週間かかる スタッキングに最低90,000 $STX(現在約3,500万円)が必要 "ナカモト"アップグレード後、ライブ性のあるノードが必要 Stacking DAOでは、$stSTXを介したスタッキングにより上記の問題を解決できます。 Stacksでは、OKXやCoinbase Custodyなどに委任してスタッキングする方法やコミュニティプールに委任してスタッキングを行う方法がありますが、その場合、通貨の流動性は確保できません。 ユーザーはStacking DAOを介して$stSTXを活用することで流動性が確保可能です。また、いつでもDEXにて元の$STXに戻せるなど、UXのさらなる向上ができます。 Stacking DAOのTVLと利用状況 DeFiLlamaを参考にするとStacking DAOのTVLは約1.1億ドル程度(STXでは4,200万枚程度)です。 Stacking DAOはStacksエコシステムにおいて最も多くのTVLを集めており、後にはDEXの「ALEX」や「Bitflow」などが続きます。Stacks全体のTVLが約1.5億ドルであることを考慮するとStacking DAOの影響力が非常に大きいことが窺えます。 [caption id="attachment_112493" align="aligncenter" width="874"] StacksエコシステムのDeFiプロジェクトのTVLランキング[/caption] Stacking DAOと同類プロジェクトと言える「Jito」はSolana全体のTVLの約1/3、「Lido」はEthereum全体の約1/2となっており、全体のTVL規模が異なるため単純な比較はできないものの、Stacking DAOが現状のStacksチェーンにおいて圧倒的な存在感を誇っていることが分かります。 Stacking DAOの使い方 Stacking DAOの使い方について、以下の点から解説していきます。 ・事前準備:ウォレットと$STXを用意する ・Stacking DAOで$STXをスタックする ・Stacking DAOでアンスタックする ($stSTX→$STX) Stacking DAOを通して、スタッキングする方法をチェックしていきましょう。 事前準備:ウォレットと$STXを用意する Stacking DAOでスタッキングを行い利回りを得るために、まずはウォレットと$STX用意する必要があります。 Stackチェーン上の$STXを扱える代表的なウォレットとしては以下があり、それぞれの特徴から自身の好みのものを選びましょう。 Stacksエコシステムの主要ウォレット(一部) Leather Wallet:ブラウザ対応ウォレットでStacksエコシステムの人気ウォレット Xverse:ブラウザだけでなくiOS/Androidにも対応する使い勝手の良いウォレット OKX Wallet:OKXが手がけるブラウザウォレットでEthereum等のEVM系やSolanaなど他チェーンも扱える*一部dAppはOKX Walletに対応していないため注意 $STXの入手方法は仮想通貨取引所で$STXを購入するか、Stacks上のDEXで$sUSDTなどの他の通貨からスワップする方法があります。 $STXは、Bitget、Bybit、OKX、Kucoin、Gate.ioなどの主要取引所で取り扱われています。$STXを取引所で購入したら、用意したウォレットにStacksチェーンを選択して出金しましょう。 [caption id="attachment_112517" align="aligncenter" width="1116"] Bitgetで$STXを購入し、OKXウォレットの$STXアドレスに送金している様子[/caption] オンチェーン上だけで$STXを用意したい場合、まずはStacksチェーン上に仮想通貨をブリッジして資金を用意する必要があります。 Stacksエコシステムのナンバー1DEXであるALEXのブリッジでは、以下の主なチェーンペアと通貨が対応しているので、自身の通貨の保有状況に合わせて適切なルートを利用しましょう。(Bitcoin Chain上からStacksチェーンに$BTCをブリッジする手数料は無料) *ブリッジには時間がかかるため特に理由がなければCEXからの$STXの出金をおすすめします ALEXのブリッジ対応チェーンと対応通貨 Bitcoin Chain ⇄ Stacks Chain|対応通貨:$BTC BNB、Ethereum、Core Chain ⇄ Stacks Chain|対応通貨:$USDT、$WBTC等 Stacksチェーン上に購入資金を用意できたら、そのままALEXにて$STXにスワップを行えば事前準備は完了です。 [caption id="attachment_112520" align="aligncenter" width="1029"] ALEXでブリッジとスワップをしている様子。手数料や時間がかかるので注意[/caption] Stacking DAOで$STXをスタッキングする ウォレットと$STXの準備ができたら、実際にStacking DAOに$STXを預け入れます。 まずはStacking DAOの公式アプリにアクセスしてください。 「Connect Wallet」から任意のウォレットを選択して接続し、「Start Stacking STX」をクリックします。 [caption id="attachment_112524" align="aligncenter" width="1247"] 公式ページからスタッキング画面に遷移している様子[/caption] 以下の画面から金額などを入力し、下のボタンからトランザクションを送信します。数分経って"Stacking STX"の画面(以下画像右側参照)に数字が表示されていれば$STXの預け入れは完了となります。 [caption id="attachment_112498" align="aligncenter" width="851"] スタッキングが完了した様子[/caption] 2024年4月時点でのAPYは約〜6%で預けた金額に応じてリターンが返ってきます。また、Stacking DAOではプロトコルで発生した利回りに対して5%の手数料を徴収しており、これがStacking DAOのプロトコルとしての収入となっています。 受け取った$stSTXは、下記のようなStacksエコシステムのさまざまなDeFiプロジェクトで利用可能です。 $stSTXが利用可能な主要dApps Bitflow:DEX Arkadiko:CDP Zest:レンディング Stacking DAOでアンスタッキングする ($stSTX→$STX) スタッキングと同じページから「UnStack stSTX」で$stSTXを元の$STXに戻せます。 方法は簡単でStacking DAOのページでウォレットを接続し、表示に従いアンスタッキングするだけです。 [caption id="attachment_112527" align="aligncenter" width="601"] 自分のスタッキング画面から簡単にアンスタックできる[/caption] ここでいくつか注意点があります。 Stacking DAOの出金に関しては最大で14日のタイムラグが発生します。 Stacking DAOは、預けられた$STXをStacksのコンセンサスに対してロックしているので、Stacking DAO経由でも$STXを引き出す際には時間がかかります。 また、引き出しを行った際には出金額に相当するNFTが発行されますが、これを譲渡したり・バーンしたりするとプロセスが正しく進みません。 サイクルの終了後はNFTを使用して$STXをいつでも請求可能です。 上記のような点を考慮するとシンプルに$STXが欲しい場合は、$stSTXと$STX間をBitflowなどでスワップするほうが利便性は高いでしょう。*手数料やスリッページなどに注意 Stacking DAOのポイントプログラム 現在、Stacking DAOでは以下の条件を満たしたユーザーに報酬(詳細不明)が配布予定のポイントプログラムが開催されています。 ポイントの獲得条件 $stSTXの保有 $stSTXのDeFiなどでの使用 紹介 OG/ジェネシスNFTの保有 「$stSTXの保有」では、ウォレット内の1 $stSTX毎に1日当たり1ポイントが与えられます。例えば、1,000 $stSTXを保有すると毎日1,000ポイントを獲得可能です。 「$stSTXのDeFiなどでの使用」では、1 $stSTXの貸し出しで1日1ポイントを獲得できます。また、$stSTX/$STX のペアに流動性を提供した場合は1 $stSTXあたり2.5ポイントが獲得可能です。*記事執筆時でArkadiko・Bitflow・Velar・Zestのみが対象なので注意 「紹介」では、自分が紹介したユーザーが獲得したポイントの10%を受け取れます。 「OG/ジェネシスNFTの保有」では、対象のNFTを保有するユーザーは特別なポイント倍率が適用され、より多くのポイントの獲得が可能とされています。 【期間限定】ポイントブーストプログラムが実施中!! Stacking DAOは"ナカモトオデッセイ"と呼ばれるポイントブーストキャンペーンを4月より開始しています。 The Nakamoto upgrade is a once-in-a-lifetime event for @Stacks. Only for this release, a 20x point bonus on new STX deposits is live. pic.twitter.com/3ieknaMZhr — Stacking DAO (@StackingDao) April 22, 2024 Stacksのアップデートを記念した上記キャンペーンでは、新規入金に対して、キャンペーン開始後2週間「20倍」のポイントブーストがかかります。(紹介では2倍のブースト) キャンペーンの終了は84サイクル目(サイクルはスタッキング画面右側の表示のデータベースで確認できます)となっており、まもなく終了となるのでポイントを多く獲得したい方は急いでStacking DAOを利用しましょう。 ポイントの用途については"リワード"としか記載されていませんが、こういったポイントは他のプロジェクトにおいてもコミュニティへの還元の際に考慮されることが通例です。また、公式ブログ記事ではStacksのアップデート後に「ビッグサプライズ」がある旨が示唆されています。エアドロップなどが実施された際の判定基準となる可能性もあるでしょう。 Stacking DAOのTGE Stacking DAOのTGEの詳細・スケジュールなどは不明です。 トークンをローンチすると仮定した場合、 直近数ヶ月はポジティブな点がいくつか見られます。 ここ数ヶ月でStacksは成長を続けているのに加えて、ベースレイヤーのビットコインは半減期を迎えており、Stacking DAOのTVLやユーザー数も増えつつあります。 Stacksはアップデートで利便性が大きく向上すると見られており、Stacking DAOはその点を記念するポイントブーストイベントも開催しました。 また、Stacking DAOはリブランディングなども行っており、直近で注目を集めるイベントが多いです。 通常、TGEは熱が高まったタイミングで行うことが多いため、何らかの動きが見られる可能性があると言えます。 まとめ この記事では、Stacking DAOについて解説しました。 Stacking DAOは直近で注目ポイントが多く、周辺の環境もポジティブな話題が多いです。 ビットコイン周辺のエコシステムが注目されつつあることも考慮すると、Stacking DAOは注目したいプロジェクトの1つであると言えるでしょう。 是非、本記事を参考にして、Stacking DAOを通して実際にStacksのスタッキングを試してみてはいかがでしょうか。 Stacking DAO 公式リンク 公式HP:https://www.stackingdao.com/ アプリ:https://app.stackingdao.com/ X:https://twitter.com/StackingDao Medium:https://medium.com/@stackingdao Discord:https://discord.com/invite/bFU8JSnPP7 Github:https://github.com/StackingDAO/contracts Docs:https://docs.stackingdao.com/stackingdao Sponsored Article by DeSpread ※本記事はDeSpread様より発注いただき作成した有料記事となります。プロジェクト/サービスのご利用、お問い合わせは直接ご提供元にご連絡ください。

プロジェクト
2024/04/22Light創設者Shun Kakinoki氏にインタビュー|Lightが目指す「チェーンの抽象化」とは?
日本発プロジェクトである「Light」は先日、スマートウォレットであるLightを公開しました。Lightは異なるチェーン上のトークンでガス代の支払いを可能とするなど画期的なソリューションを提案しています。 https://t.co/56qJDjgQX3 — Light (@LightDotSo) March 19, 2024 様々なチェーンの乱立が続きユーザー体験があまり良くない状況が続く中、Lightはチェーン抽象化に関する仕組みを提供し、Web3ユーザーのさらなるUX向上を目指しています。 本記事ではそんなLightのFounder兼CEOを務めるShun Kakinoki氏へのインタビュー内容をお届けします。 - 「自己紹介とLightの概要について教えてください」 25歳のKakinokiと申します。クリプトへの参入は2021年、サンフランシスコの起業家たちと共にWagumi DAOを立ち上げたことから始まりました。 Wagumi CatsというNFTを扱いながら、ガバナンスやDiscordコミュニティのモデレーションなどの活動を通じてクリプトの面白さに魅了され、深く関わるようになりました。 「Light」は、スマートウォレットという形態で取り組んでいるプロジェクトです。 Lightでは、EVM互換のチェーンを円滑かつなるべく使いやすくできるような機能を提供しており、例えば、自分が使ったことがない新しいチェーンでガス代の支払いが必要となった場合、自分がすでに持っているどのチェーン上のアセットでもガス代の支払いが可能となります。 参考ポスト↓ 1. Network abstraction Light enables you to instantly interact across chains seamlessly, and pay gas in ANY asset you hold across chains. Here's a quick demo: Sending USDC on Arbitrum & Optimism, while paying gas w/ USDT on Polygon, all in one transaction. pic.twitter.com/bJHfGH5nsR — Shun Kakinoki (@shunkakinoki) March 18, 2024 また、複数のチェーンにわたるトランザクションを1つの署名で行うことができます。 現在、様々なチェーンが乱立しているかと思いますが、全てのチェーンをあたかも1つのチェーンで使っているようなUXを実現したいというのがLightのビジョンです。 - 「Lightは以前、Web3 Socialのプロダクトも開発していたかと思いますが、現在はどのような状況になっていますか?」 現在公開しているLightはプロジェクトとして3つ目のプロダクトです。 1つ目がWeb3 Socialのプロダクトで、CyberConnect上でお互いの共通のDAOやNFTなどを可視化できるソリューションの提供に取り組んでいました。 2つ目が、iOS Safari内でメタマスクの概念や要領で使えるモバイル上のweb拡張機能のようなアプローチのモバイルウォレットです。 そして、今取り組んでいるのがスマートウォレットのLightとなっています。 - 「Lightではどのような仕組みで、別チェーン上のアセットでガス代の支払いを可能としているのでしょうか?」 Lightではガスの抽象化レイヤーを独自で開発していて、ここではガスの支払いを誰かが負担してくれる設計になっています。 ガスを支払う"ソルバー"と呼ばれる事業者のようなポジションの人たちがいるのですが、これらの人達がどのチェーンにも参加できるようになっています。 そしてこのソルバー達が「Polygon上でUSDTを後で受け取れるのであれば3つのチェーンのガス代を負担してあげるよ」といった形でユーザーが希望するチェーン、アセットでのトランザクションが通るよう協力してくれます。 - 「ソルバーはガス代を一時的に負担するインセンティブとして、手数料収入が入ってくるのでしょうか?」 その通りです。ただ、そうなるとユーザーにとって不利な状況が発生しかねないため、Lightでは複数の事業者が競売するような仕組みが採用されています。 また、ガス代が無料になるといったケースも発生します。DeFiのアプリケーションを作っている事業者がいたとして、自分たちのプロトコルを伸ばしたい時に「自分達のプロトコルを使ってくれればガス代を無料にする」といった施策も可能です。 - 「今回公開されたLightの主なターゲットはどんなユーザーですか?」 最初は複数のL2を使っているクリプトのコアユーザーをターゲットにしています。 スマートウォレットの面白い点として汎用性が高い部分が挙げられます。そもそも秘密鍵やシードフレーズを覚える必要が無くなったり、ソーシャルリカバリーのように鍵を無くした場合に友達に復旧してもらうことが出来るんです。 また、ウォレット自体をプログラミングできるのも魅力の1つですね。 最近はRhinestoneのように、アプリストアのような形のアプローチでウォレットに色々な機能を付けれるようにするのがスタンダードになりつつあります。 [caption id="attachment_111849" align="aligncenter" width="666"] 画像引用元:blog.rhinestone.wtf[/caption] Lightでもそういったことを将来展開していくつもりで、ウォレット自体が色々と拡張したり、ユーザーが好きな拡張機能を入れられるようになればウォレットの幅は大きく広がると思います。 チェーンを意識しないであらゆるトランザクションをワンクリックで出来るようになれば、コアユーザー以外の一般の方にも普及するかと思っています。 - 「基盤としてLightの仕組みがあり、その上に開発者たちが考える最適なUI/UXのアプリを構築できるといったイメージでしょうか?」 はい、おっしゃる通りです。 Lightとして提供している基盤は、ワンクリックでどのトランザクションも完結できるソリューションで、このユーザー体験はクリプトのマスアダプションには必須だと考えています。 今だとコアのクリプトユーザーであっても、新規で使いたいチェーンがあっても、実際に使った経験がなければ「ブリッジして、ネットワークをメタマスクに追加して、ガス代を補填して、ようやく使える」みたいな形だと思います。これだと絶対に一般のユーザーは使えないですよね。 これらの複数のチェーンを跨ぐトランザクションをワンクリックで出来るようになればクリプトのマスアダプションに向けた大きな一歩となるかなと思っています。 世界中の色んな人の生活にどれだけクリプトを根付かせられるかをLightの最終的なゴールとして考えていて、手軽さや分かりやすさ、いかに障壁をなくせるかは常に意識しています! - 「メタマスクや取引所のウォレットしか使ったことがないユーザーが一般的かと思いますが、そのような人たちにLight、またはLightのソリューションを活用したプロダクトを実際使ってもらうようにするためにどのような戦略を持っていますか?」 戦略は2つあります。 今は色んなチェーンが毎日のように誕生していると思いますが、これだとメタマスクや取引所のウォレットだと限界があると思っているんですよね。そこで有効なマーケティング戦略を描けるかと考えています。 メタマスクを使っている以上、ネットワークを追加したりブリッジしたりは必要で制約として存在します。そういった意味で1つでもチェーンが増えるごとにLightとしての優位性は増していくと考えています。現在の状況で1クリックで全てが完結するようなLightのソリューションが提供できたら、多くの人がこれを好んで使ってくれるのではないかと思っています。 長い目で見ると、マルチチェーンがデフォルトの世界というのはLightの観点からすると絶好の機会かと思います。 「チェーンアブストラクション(チェーンの抽象化)」といった概念があるんですが、いかにあらゆるチェーンをあたかも1つに感じさせるか、もしくはチェーンの存在すら感じさせなくするかというUXを実現することが、マーケティングの側面でもUXの側面でも非常に重要かなと思います。 2つ目がグループウォレットです。 これはあまり日の目を見ていない分野だと思っているのですが、マルチシグのように、例えば誰かとの間で議決権を半々にして何かしらのアセットを持てるというのは、人類の歴史上初だと思います。真の意味で複数の人と平等な立ち位置で何かを所有できるんです。 例えば土地とかだと結局は政府が握っていたり、銀行に資金を預けていても政府と銀行と自分だと自分以外が2/3の権利を持っていたりしますよね。 「友達とNFTを一緒に管理する」といった形で複数人で平等な立場で何かを所有できるのは、今まで不可能だっただけに面白いことが起こる可能性があると考えています。 -「Lightはどのチェーンから対応していくのでしょうか?」 現状ではメインネットでは10個くらいのチェーンにすでに対応しています。 [caption id="attachment_112235" align="aligncenter" width="797"] Light(デモ)で対応しているチェーン[/caption] 比較的新しいチェーンのBlastにも対応予定だったり、Berachainのような新しい切り口のプロジェクトともパートナーシップを提携するような形で進めたいと思っています。 チェーン側からするといかに自分たちのチェーンの特性をアピールするかが重要視されると思います。なので、個々のチェーンの特性をユーザーにわかってもらえるような仕様にしたいと考えています。 - 「Lightとして日本ユーザーにどのように認知をしてほしいのでしょうか?また、日本でどのようなポジションを取りたいと考えていますか?」 毎日使ってるWeb2アプリで日本製のものは1つあるかないかといった感じです。 Web3の世界で世界中の人たちが使っているインターフェースだったり、基盤となるネットワーク的な部分はまだまだ黎明期だと思います。 今後10年100年単位で見るとスマートウォレットの数は何百億個と存在するようになると思いますし、EVMチェーンのTVLは何兆、何百兆となっていくでしょう。 そうなるとクロスチェーンでデフォルトで使えるスマートウォレットが、大きな規模のアセットを保有するのみならず、チェーン抽象化の基盤インフラをもとにユーザーが毎日そこからトランザクションを発生させるのは考えられる世界線かと思います。 私も日本人として頑張りたいですし、日本人ユーザーの方の声には耳を傾けたいと強く思っています。 現在はクローズドでやっていて申し訳ない気持ちでいっぱいなのですが、前回のLight Walletは本当に多くの方に使っていただきました。進化したプロダクトとして戻ってくる予定ですので、楽しみにしていただければ幸いです! - 「2024年のロードマップや読者の方に向けた抱負を教えてください」 2024年に入り、L2を始めとしたスケーリング・ソリューションのお陰で多くのチェーンを高帯域・安価で使える時代に突入しました。それと同時に、多くのチェーンを同時に用いることはユーザーにとっては複雑なプロセスとなり、体験を損ねているのは紛れもない事実だと思います。チェーン抽象化によって老若男女が使い得るシンプルな体験を実現して、世界中の多くの人にクリプトの素晴らしさと利便性を届けたいです。 Light 各種情報 Website:https://light.so/ Twitter (X):https://twitter.com/LightDotSo Discord:https://discord.com/invite/Vgfxg2Rcy8 Telegram:https://t.me/LightDotSoSupport Github:https://github.com/LightDotSo/LightDotSo

プロジェクト
2024/04/06イオス($EOS)はどんな仮想通貨?特徴と将来性を完全解説!
イオスはDAppsのプラットフォームとして開発されたネットワークです。イオスネットワーク上で使われる仮想通貨も、同じ名前のイオス($EOS)です。 高負荷に弱いイーサリアムの課題を解決した高速・低コストのネットワークとして、立ち上がり当初は大いに注目を集めました。 しかし、その後大きな伸びはなく低迷し、現在ではソラナやカルダノといったイーサリアムキラーに大きく水をあけられた状態になっています。 それでも2022年になって運営主体が変わったことで、前向きな開発投資が行われるようになり、コミュニティのサポートもあって状況は変わりつつあります。 イオスってどんなプロジェクト? EOSは今後伸びる可能性はあるの? EOSが取引できる仮想通貨取引所は国内にあるの? そんな疑問をお持ちの人に向けて、この記事ではイオスの特徴と将来性を解説しました。EOSを取引するのにおすすめの取引所も紹介しています。 最後まで読めば、イオスに関する必須な知識をしっかり獲得できますよ。 仮想通貨イオス($EOS)とは? 5つの特徴を解説 最初にイオスがどんなプロジェクトかを解説します。 イオスネットワークと仮想通貨イオス($EOS)の特徴を5つ紹介したので、ひとつひとつチェックしていきましょう。 仮想通貨イオス($EOS)とは? 5つの特徴を解説 イオスネットワークはDAppsのプラットフォーム 2022年に運営主体がEOSネットワーク財団に交代 コンセンサスアルゴリズムがDPoSで高速・低コスト トランザクションの承認手数料が無料 21のブロックプロデューサーによるガバナンスで運営 イオスネットワークはDAppsのプラットフォーム イオス($EOS)のスペック 名称 イオス ティッカーシンボル EOS 運営者 EOSネットワーク財団(ENF) 発行日 2018年6月 時価総額ランキング 86位(2024年3月12日のCoinMarketCapの集計による) 時価総額 約1960億円(2024年3月12日のCoinMarketCapの集計による) コンセンサスアルゴリズム Delegated Proof of Stake(DPoS) 公式サイト https://eosnetwork.com/ 公式X https://twitter.com/EOSNetworkFDN 公式Discord https://discord.com/invite/eos-network 公式Telegram https://t.me/EOSNetworkFoundation イオスは2018年6月に稼働を開始したネットワークです。 イーサリアムが持つスケーラビリティ問題を解決し、高速で低コストのDAppsのプラットフォームを実現することを目的としたプロジェクトで、そこで使われる仮想通貨がイオス($EOS)です。 2018年の立ち上がり時はBlock.one社によって運営されており、技術的な評価は高く、イーサリアムキラーの最右翼として注目を集めていました。 Block.one社はEOSのICOによって40億ドル以上の資金調達に成功し、時価総額ランキングで5位に入るほどの勢いがありました。 スケーラビリティ問題とは? ネットワークが大規模になりトランザクションが混みあうと、処理の遅延やガス手数料の高騰が発生するリスクを指します。ビットコインやイーサリアムといった比較的古くからあるネットワークで課題となっています。 2022年に運営主体がEOSネットワーク財団に交代 イオスはローンチ直後の2018年には勢いがありましたが、それ以降は低迷していきます。 Block.one社はイオスネットワークの開発に十分な資金を投入せず、イオスへの世間の関心は徐々に薄れていき、EOSの価値も低迷を続けます。 この状況から脱却するために、イオスにかかわるコミュニティが立ち上げたEOSネットワーク財団(ENF)が、2022年からイオスの運営主体となりました。 現在ではイオスネットワークに対するBlock.one社の影響力は、基本的には排除されています。私企業からコミュニティ主導の非営利団体に運営主体が移った数少ない例として、今後の動向が注目されています。 コンセンサスアルゴリズムがDPoSで高速・低コスト イオスネットワークのコンセンサスアルゴリズムは、Delegated Proof of Stake(DPoS)です。 ブロックの生成はブロックプロデューサー(BP)によって行われます。BPの数は21ノードに限定されており、少数でブロックの生成を行うことで、高速で低コストのネットワークを実現しています。 BPはEOSの保有者による投票によって決まります。投票は126秒ごとに行われ、そのたびにブロックプロデューサーとそのリザーブであるスタンバイノードが選ばれます。 投票権の大きさはEOSの保有量によって決まるため、イオスネットワーク全体への影響力を分散してセキュリティを高めることに成功しています。 トランザクションの承認手数料が無料 イオスネットワークの重要な特徴が、トランザクションの承認手数料が無料な点があります。 ビットコインやイーサリアムなどの多くのネットワークでは、トランザクションの承認に手数料がかかります。この手数料はブロックの生成者への報酬の一部になっているため、ゼロにすることはできません。 これに対してEOSでは、ブロックを生成するBPへの報酬はすべてEOSの新規発行でカバーされます。トランザクションの手数料は報酬に含まれません。 その結果イオスのトランザクション承認には手数料がかかることが無いため、低コストで利用できるネットワークになっています。 21のブロックプロデューサーによるガバナンスで運営 ブロックプロデューサーの主な役割 ブロックの生成 イオスネットワークの管理・監視 イオスネットワークのセキュリティ維持 イオスネットワークの改修などの議論・決定 イオスのBPはトランザクションを承認し、新たなブロックを生成するだけの存在ではありません。イオスネットワークが正常に機能するよう、協力してガバナンスを発揮します。 BPは、ネットワークが正常に動作し他のノードと正しく同期がとれているかの確認や、ハッキングからの防御などのセキュリティ維持を継続的に行っています。 また、ネットワークの改修などイオスの方向性を左右する議論を行い決定を下すのもBPの役割です。 運営主体がBlock.one社からENFに変わる際も、BPの合意が大きな力となりました。 現在までのイオス($EOS)の価格動向 次はEOSのこれまでの価格動向を確認しておきましょう。 EOSの価格のピークはICO直後の2018年です。立ち上がり時に多くの注目を集めていたため、この時期には時価総額5位にランクされていました。 その後はBlock.one社の動きの悪さが影響したためか、価格が下がります。価値を上げる大きなニュースも少なく、下降線をたどっていきます。 仮想通貨全体に勢いが出ていた2021年に若干盛り返しましたが、それ以降も基本的には低迷のトレンドを抜けることができていません。最近の2年間は80~200円の範囲を上下しています。 最新のEOSのチャートは以下で確認してください。 イオス($EOS)の今後は? 将来性を左右する3つのポイント 2024年3月の時点でのEOSの価格は170~180円です。2024年に入ってから、仮想通貨全体の伸びに呼応して上昇傾向にあります。 イオスがこれまでの低迷を脱することができるかは確定的なことは言えませんが、将来性を左右する重要なポイントについて考察していきましょう。 イオス($EOS)の将来性を左右する3つのポイント 仮想通貨市場全体の活性化 EOSネットワーク財団による健全なリーダーシップ EOS EVMによるイーサリアムとのブリッジの成功 仮想通貨市場全体の活性化 EOSの値動きは、仮想通貨全体の価格の推移に影響されている部分は否定できません。 過去の動きを見ても、上昇している時期は仮想通貨市場全体が勢いのあった時期と一致しています。 2024年に入り、米国でのビットコインの現物ETF承認や半減期への期待から、仮想通貨市場全体は盛り上がりを見せ始めています。 今後仮想通貨全体がさらに伸びていけば、EOSの価格にも影響を与えるかもしれません。 EOSネットワーク財団による健全なリーダーシップ スタート時には脚光を浴びていたイオスが低迷した原因の一つは、当初開発・運営を担っていたBlock.one社がイオスに十分な投資をせず、開発やプロモーションが停滞していたことにあります。 この点については現在はBlock.oneの手を離れ、EOSネットワーク財団(ENF)が引き継いでいます。 ENFはイオスの運営や開発を支えるコミュニティから構成されており、企業による利益追求とは別の価値観での運営が可能です。ENFによるイオスネットワークへの安定した投資と運営は、EOSの今後を左右する重要なポイントになります。 EOS EVMによるイーサリアムとのブリッジの成功 既存のチェーン、特にDAppsのメジャーなネットワークであるイーサリアムにどう対峙するのかは、イオスにとって重要な選択です。 ENFは、イオスとイーサリアムの間での相互運用を実現するために、イーサリアム互換の仮想マシンであるEOS EVM(Ethereum Virtual Machine)を開発しています。2024年3月の時点ではβ版がすでに稼働中です。 これにより、イーサリアムネットワーク上で構築されたプロジェクトを イオスネットワーク上に展開できるようになります。 EOS EVMが定着し、イーサリアムとイオスの相互運用が進めば、高速・低コストのイオスネットワークを採用するプロジェクトが増えることが予想されます。 イオス($EOS)でおすすめの仮想通貨取引所 EOSを取引できるおすすめの仮想通貨取引所はBitgetです。 Bitgetはどんな仮想通貨取引所? 取り扱い通貨の種類が多い大手海外取引所 125倍までのハイレバレッジの取引ができる ハイパフォーマンスなトレーダーのコピートレードができる しっかり日本語対応された使いやすいサイト ハウストークンBGBを使えばお得に取引可能 Bitgetは2018年創設の海外の仮想通貨取引所で、取り扱い通貨数は600種を超える豊富さとなっており仮想通貨に関する現物・先物などの取引サービスだけでなく、ステーキングなど、多様なサービスがBitgetに集約されています。 Bitgetの公式サイトはこちら イオス($EOS)に関するよくある質問 ここまでイオスネットワークの特徴や仮想通貨EOSの将来性について、解説しました。イオスのイメージがだいぶ明確になってきましたよね。 最後にイオスに関してよく出る質問にまとめて答えていきましょう。 イオス($EOS)に関するよくある質問 EOSを管理できるウォレットはありますか? イオスのロードマップは公開されていますか? イオスのブロックチェーンの状態を確認するには? EOSを管理できるウォレットはありますか? 仮想通貨を取引所に預けることなく自分の手元で管理する場合は、PCやスマホで使えるウオレットアプリが必要ですよね。 EOSを保管できるウオレットアプリは複数あります。 特におすすめなのはTrust WalletとMetaMaskです。PCでもスマホからでも利用でき、ユーザーが多く実績があります。 使い方に関する情報もネットで多く見つかるので、戸惑うことなく利用できますよ。 仮想通貨ウォレットを種類別に解説!おすすめ10選も紹介 イオスのロードマップは公開されていますか? EOSネットワーク財団は、イオスの開発に関するロードマップを公開しており、定期的に更新しています。2024年2月に更新されたロードマップを見てみましょう。 イオスのメインネットワークの開発では、現バージョンの100倍のパフォーマンスのコンセンサスアルゴリズムへの変更を含んだLeap 6への移行が佳境です。ハードフォークは2024年の7月31日に予定されています。 Mark your calendars for instant finality on #EOS! 🗓️⚡ 162 days until the hard fork to Leap 6 ⏰ https://t.co/qQRxfgZ821 pic.twitter.com/eQyF0gvzEq — Yves La Rose (@BigBeardSamurai) February 20, 2024 イオスのメインネットと並行してEOS EVMの開発も精力的に行われています。EOS EVMは現在βバージョンですが、2024年のQ2にはv1.0.0がリリースされる予定です。 またイオスとビットコインのネットワークとの連携に関する検討も始まっています。 EOSの開発チームの中には、ビットコイン用の EVM 互換ソリューションを構築するためのBTC L2 ワーキンググループが設置されており、ホワイトペーパーの作成も進んでいます。 The WP draft also goes into detail about how $RAM will play a role in the #EOS $BTC L2. exSat 🤔 https://t.co/ymsgvzQn3T pic.twitter.com/U0HsAZaQ7e — Yves La Rose (@BigBeardSamurai) February 27, 2024 イオスのブロックチェーンの状態を確認するには? イオスネットワークの状態や個別のトランザクションのステータスを確認するには、イオスのブロックエクスプローラーを活用しましょう。 おすすめなのはBlocks.ioとEOS Authorityの2つです。 どちらもイオスネットワークの状態やブロックプロデューサーの投票結果などを、リアルタイムで確認できます。 仮想通貨イオス($EOS)のまとめ 仮想通貨イオス($EOS)のまとめ DAppsのプラットフォームとしてローンチ当初は注目を浴びた コンセンサスアルゴリズにDPoSを採用し、高速・低コストを実現 低迷していたが、運営主体がEOSネットワーク財団に変わり巻き返し中 仮想通貨市場の活性化やイーサリアムとの相互運用の成功が今後のカギ 国内でEOSを取引できるのはBitTradeとBinance Japanの2社のみ この記事では、DAppsのプラットフォームであるイオスの特徴と将来性を解説しました。加えて、EOSを取引できる国内の仮想通貨取引所も紹介しています。 イオスは、イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決できるネットワークの最右翼として、ローンチ当初は注目を集めましたが、その後低迷を続けてきました。 2022年になって、プロジェクトを主導する運営主体が私企業からコミュニティ主導の非営利団体に変わり、前向きな投資やパートナーシップが目立つようになっており、今後に期待が持てます。 この記事を読んで興味が出たら、これからのイオスの動きにしっかりアンテナを張っておきましょう。

プロジェクト
2024/04/05仮想通貨IOST(アイオーエスティー)とは?今後・将来性を徹底解説!
IOST(アイオーエスティー)は、DAppsの開発プラットフォームとして2018年にローンチしたプロジェクトで、発行された仮想通貨の名称もIOST(アイオーエスティー)です。 日本国内での活動が活発なので名前だけは耳にしたことがある人も多いでしょうが、プロジェクトの詳細までは把握していない人が大半かもしれません。 IOSTってどんな仮想通貨? IOSTが今後伸びる可能性はあるの? IOSTを売買するなら、どの仮想通貨取引所がおすすめ? そんな疑問をお持ちの人に向けて、この記事ではIOSTの特徴と将来性を解説しました。加えて、IOSTを取引するのにおすすめの取引所も紹介しています。 最後まで読めば、IOSTに関する知識をしっかり把握できますよ。 BitgetでIOSTを購入する IOST(アイオーエスティー)とは? 5つの特徴をおさらい 最初にIOST(アイオーエスティー)の基本的な事項について解説します。 IOSTの主な特徴を5つあげたので、ひとつひとつ確認していきましょう。 IOST(アイオーエスティー)の5つの特徴をおさらい DApps開発のプラットフォームとして2018年から発行開始 コンセンサスアルゴリズムにProof of Believability(PoB)を採用 Efficient Distributed Sharding(EDS)でスケーラビリティ問題を解決 スマートコントラクトの開発言語がJavaScript 日本の仮想通貨コミュニティとのかかわりが深い DApps開発のプラットフォームとして2018年から発行開始 IOST(アイオーエスティー)のスペック 名称 アイオーエスティー ティッカーシンボル IOST 発行元 IOST財団(シンガポール) 発行日 2018年1月20日 時価総額ランキング 265位(2024年2月17日のCoinMarketCapの集計による) 時価総額 約284億円(2024年2月17日のCoinMarketCapの集計による) コンセンサスアルゴリズム Proof of Believability(PoB) 公式サイト https://iost.io/iost/ 公式X https://twitter.com/IOST_Official 公式Telegram https://t.me/officialios IOSTは、分散型アプリケーション(DApps)のプラットフォームを開発・運営するプロジェクトです。 シンガポールを拠点とするIOST財団が中心となっており、イーサリアムを超えるハイパフォーマンスで手数料の安いネットワークを提供しています。 IOST上でメインに使用される仮想通貨の名称もIOST(アイオーエスティー)です。 IOSTネットワーク上の取引の支払いや手数料・マイニング報酬に使用され、IOSTネットワークのエコシステムを支えています。 コンセンサスアルゴリズムにProof of Believability(PoB)を採用 Proof of Believability(PoB)のメリット Proof of Work(PoW)と比較してブロック生成のコストが安い Proof of Stake(PoS)と比較してブロック生成機会の分散性が高い 自己の信頼性を証明したノードがブロック生成するため、ネットワーク全体の信頼性が向上する IOSTのコンセンサスアルゴリズムは、Proof of Believability(PoB)です。 PoSのようにブロック生成者を通貨の保有量だけで決定せず、ネットワークへの貢献度を数値化した信頼度を加味して決定します。 ビットコインのPoWのように多大な時間とコストをかけることなくブロック生成が可能です。 また、イーサリアムのPoSのように通貨を多く保有するノードが必要以上に有利になることなく、より公平にブロック生成者を決定できるため、ネットワークの分散性が高まります。 Efficient Distributed Sharding(EDS)でスケーラビリティ問題を解決 イーサリアムは、処理集中時にパフォーマンスが落ちたり、ガス手数料が高騰したりといった、いわゆるスケーラビリティ問題を抱えています。 スケーラビリティ問題を解消するためにIOSTが採用した仕組みが、Efficient Distributed Sharding(EDS)というシャーディングシステムです。 EDSでは、IOSTのネットワーク全体をシャードと呼ばれるグループに分割します。それぞれのシャードが並列に作業を行うため、スケーラビリティ問題に耐性のあるネットワークになっています。 これによりIOSTは、高速かつ低コストで利用できるネットワークを構築することに成功しました。 スマートコントラクトの開発言語がJavaScript 主なブロックチェーンのスマートコントラクト開発言語 プロジェクトの名称 スマートコントラクト開発言語 説明 IOST JavaScript ウエブページの開発で広く使用されている言語で、言語仕様がシンプルなため初中級者でも使いやすい イーサリアム Solidity C++やJavaScript、Pythonなどの言語に似た専用言語 カルダノ Plutus Haskellをベースに設計された専用言語 EOS C++ ソフトウエア開発全般で広く使用される言語で、中級以上のプログラマー向き イーサリアムと同様にIOSTにもスマートコントラクトの機能が用意されています。IOSTが特徴的なのは、スマートコントラクトを開発するためのプログラミング言語が、ウエブページの開発で使用されるJavaScriptである点です。 多くのブロックチェーンでは、スマートコントラクトの開発のための専用言語を使っています。 イーサリアムではSolidity、カルダノではPlutusという言語が使われており、スマートコントラクトの開発を行うには最初にプログラミング言語の学習から始める必要があります。 IOSTでは多くのプログラマーになじみのあるJavaScriptが使われるため、スマートコントラクト開発のためのハードルが低く、多くの開発者が参入しやすいのがメリットです。 日本の仮想通貨コミュニティとのかかわりが深い IOSTは日本の仮想通貨コミュニティとの関係が親密な点が特徴的です。 IOSTのノードパートナーには、OKCoin JapanやBitPointなどの仮想通貨取引所やHashKey DXなどのWeb3領域の国内企業などが参画しており、IOSTのエコシステムを共に支えています。 また、IOSTは立ち上がりの2018年当初から国内の複数の大学でブロックチェーンの教育プログラムを展開しています。 2023年にも近畿大学や秋田国際教養大学でweb3ハッカソンやワークショップなどを開催しており、若年層を対象とした開発者の育成とコミュニティづくりを積極的に行っています。 こういった地道な活動がしっかり身を結び、時価総額が200位台にもかかわらず日本国内では比較的知名度が高く、取り扱う仮想通貨取引所が多い通貨になっています。 BitgetでIOSTを購入する 今後の動きは?IOST(アイオーエスティー)の将来性を左右する3つのポイントを徹底解説! ここまでIOSTの特徴について説明しました。IOSTがどんな仮想通貨かがしっかりイメージできましたね。 次は、IOSTが今後伸びる可能性があるかどうかについて考察していきましょう。 IOST(アイオーエスティー)の将来性を左右する3つのポイント 仮想通貨市場全体の盛り上がり 具体性がある大規模プロジェクトとの提携 大手仮想通貨取引所への上場 仮想通貨市場全体の盛り上がり CoinMarketCapの2024年2月18日のデータによる IOSTは2018年1月の発行開始から6年経過しています。 価格が大きく伸びたのは、発行当初の2018年と2021年の2回です。どちらも仮想通貨全体が勢いづいていた時期にあたります。 2022年以降は、仮想通貨全体が下降線をたどるのと歩調を合わせるように価格が下がっていき、2023年からは1IOST=1.2円前後の価格で低迷しています。 「ここから大きくは上がらない」「IOSTは終わった」といった予想をする人もいますが、どちらかと言えばIOSTは仮想通貨全体の動きに追従して価格が上下している傾向にあると考えるほうが妥当です。 仮想通貨全体は、ビットコインの半減期、ビットコイン・イーサリアムのETF承認の動きによって盛り上がりつつある状態です。IOSTもこの動きに乗って伸びていく可能性は十分あります。 具体性がある大規模プロジェクトとの提携 仮想通貨が大きく伸びるには、しっかりしたプロジェクトと連携して、具体的な応用事例を着実に開発していくことが必要です。 IOSTはこれまでにも、医療領域でのメディカル・ヘルステック企業との連携や、DeFiでの活用が進んでいます。 さらには、IOSTの2024年のロードマップに「Web3とAIを組み合わせたDAppsプロジェクトのインキュベーション強化」があげられているので、この方面でも今後の動きが期待できます。 具体性がある大規模プロジェクトとの新たな提携が発表されれば、爆上げする可能性も十分にありますよ。 IOSTの2024年上半期ロードマップはこちら 大手仮想通貨取引所への上場 IOSTが大きく伸びるためには、多くの仮想通貨取引所で取引可能な状態になることも重要です。大手の仮想通貨取引所への上場が決まれば、それだけで価格が上昇することも多くあります。 2024年2月時点で、Bitgetなどの大手取引所でIOSTを取引できます。しかし、IOSTをまだ扱っていない取引所も多く残っています。 2024年のロードマップにも、「グローバルな仮想通貨取引所への上場促進」という活動項目が入っているので、こちらの動きにも注目しましょう。 BitgetでIOSTを購入する IOST(アイオーエスティー)を取引できる仮想通貨取引所3選 ここまでIOSTの特徴と将来性について解説しました。IOSTがどういう仮想通貨か、徐々につかめてきましたよね。 ここからはIOSTを売買するのに便利な取引所を3つ紹介しましょう。 IOST(アイオーエスティー)を取引できる仮想通貨取引所3選 Coincheck BitPoint OKCoin Japan Coincheck(コインチェック) Coincheckのスペック 名称 Coincheck 運営会社 コインチェック株式会社 提供サービス 販売所、取引所、暗号資産つみたて、レンディング、ステーキング、IEO 公式サイト https://coincheck.com/ja/ 取り扱い通貨数 30種 Coincheckは、日本国内の仮想通貨取引所の中で最初にIOSTの取り扱いを始めました。 各種金融サービスを展開しているマネックスグループの傘下にあるコインチェック株式会社が運営しており、販売所や取引所における仮想通貨の取引サービスはもちろん、レンディングやステーキングのサービスもあり、いろいろな使い方ができます。 IEO(Initial Exchange Offering)による新規発行通貨の販売も活発に行っているので、チャンスが多く中級者にとっても面白い仮想通貨取引所です。 【Coincheck(コインチェック)の登録方法・使い方】入出金・仮想通貨売買まで徹底解説 BitPoint(ビットポイント) BitPointのスペック 名称 BitPoint 運営会社 株式会社ビットポイントジャパン 提供サービス 販売所、取引所、暗号資産つみたて、レンディング、ステーキング 公式サイト https://www.bitpoint.co.jp/ 取り扱い通貨数 21種 BitPointは2022年からIOSTの売買サービスを開始している取引所です。 単にIOSTを取り扱うだけでなくノードパートナーとしてIOSTと提携し、IOSTのエコシステムへの積極的な貢献の姿勢を見せている点が特徴的です。 国内では比較的古くから稼働しており、安心して使える仮想通貨取引所です。 BITPOINT(ビットポイント)の登録手順・口座開設方法を解説! OKCoin Japan(オーケーコインジャパン) OKCoin Japanのスペック 名称 OKCoin Japan 運営会社 オーケーコイン・ジャパン株式会社 提供サービス 販売所、取引所、暗号資産つみたて、ステーキング 公式サイト https://www.okcoin.jp/ 取り扱い通貨数 34種 OKCoin Japanは国内では最もIOSTを熱心にサポートしている仮想通貨取引所です。 IOSTのノードパートナーとしてエコシステムの維持に貢献しているだけでなく、年末恒例のWeb3コミュニティ忘年会をIOSTと共同で主催するなど、とても積極的です。 IOSTの取引だけでなくステーキングも可能なので、IOSTを取引するならおすすめです。 OKCoinJapan(オーケーコイン・ジャパン)の登録方法から使い方まで解説! IOST(アイオーエスティー)に関するよくある質問 ここまでIOSTの特徴と評判、将来性について説明してきました。IOSTがどういう仮想通貨かしっかりイメージできましたよね。 最後にIOSTに関してよく出る質問にまとめて答えていきましょう。 IOST(アイオーエスティー)に関するよくある質問 IOSTの主な用途は何ですか? IOSTのブロックチェーンはどのようなセキュリティ機能を持っていますか? IOSTはステーキングできますか? IOSTは海外の仮想通貨取引所でも取引可能ですか? IOSTに関する日本語の情報はどこで入手できますか? IOSTの主な用途は何ですか? IOSTは、DAppsのプラットフォームであるIOSTネットワークのエコシステムを支える仮想通貨です。 IOSTネットワーク内でのサービス提供や取引の決済手段として利用されます。またスマートコントラクト実行時のガス手数料の支払いにも使われています。 さらには、IOSTトークンの保有者はIOSTネットワークのガバナンスに関する投票に参加することも可能です。 IOSTのブロックチェーンはどのようなセキュリティ機能を持っていますか? IOSTは、コンセンサスアルゴリムとしてProof of Believability(PoB)を採用しています。 ノードの信頼性を加味してブロック生成を行うノードを決める方法で、不正行為や攻撃を抑制しながら分散型のネットワークを構築できます。 また、ブロックの生成に関与するノード数は常に数百の規模が維持されており、恒常的に分散性が高い状態が実現されています。 IOSTはステーキングできますか? IOSTのステーキングが可能な国内仮想通貨取引所 仮想通貨取引所 ステーキング期間 利回り OKCoin Japan 最大60日間 年率8.8% Binance Japan 最大120日間 年率4.8% CoinTrade 最大90日間 年率11% IOSTをステーキングして報酬を得ることが可能です。 国内ではOKCoin Japan、Binance Japan、CoinTradeの3社でステーキングできます。 取引所によって利回りは大きく異なるので、IOSTのステーキングを考えている人はしっかり比較して選びましょう。 IOSTは海外の仮想通貨取引所でも取引可能ですか? IOSTを売買できる主な海外仮想通貨取引所 Bitget IOSTを取り扱っている海外の仮想通貨取引所は複数あります。 その中でも取り扱い通貨が豊富で日本人にも使いやすいBitgetがおすすめの取引所となっています。 IOSTに関する日本語の情報はどこで入手できますか? IOSTに関する日本語情報の主な入手先 IOST公式Twitter(日本版) IOST公式Telegram(日本版) IOST情報局 IOST日本コミュニティ IOSTは日本国内での活動が活発なので、日本語での情報源も多くあります。 公式の情報は公式Twitterや公式Telegramから入手しましょう。 IOST情報局は、自らIOSTのパートナーノードになっている「IOSTに人生託したマン」さんによる個人のサイトです。基本的なことからノード運営に関する詳細まで、わかりやすくまとまっていますよ。 IOST(アイオーエスティー)の今後に関するまとめ IOSTの今後に関するまとめ IOSTはDAppsのプラットフォームとして2018年から稼働 PoBやEDSなど先進的システムで安全・低コスト・高速なネットワークを実現 IOSTの価格の動きは仮想通貨市場全体の勢いに強く影響される傾向がある 大規模プロジェクトとの提携や大手取引所上場で注目されれば大きく伸びる IOSTを売買するならCoincheck、BitPoint、OKCoin Japanがおすすめ この記事では、IOST(アイオーエスティー)の特徴と将来性に関して解説しました。 IOSTはProof of Believability(PoB)やEfficient Distributed Sharding(EDS)などの先進的なシステムを導入しており、技術的にはイーサリアムを超える部分も多く見られるプロジェクトです。 開発者の育成やコミュニティ形成もグローバルに地道に積み重ねてきており、今後大規模プロジェクトとの提携などのインパクトのあるニュースが飛び込めば、大きく伸びる可能性がある仮想通貨です。 この記事を読んでIOSTに興味が持てたら、今後の動きから目を離さないようにしましょう。

プロジェクト
2024/04/01セロ($CELO)とはどんな仮想通貨?特徴と将来性について徹底解説!
世界には銀行口座すら持てない人々が多く存在します。基本的な金融サービスから隔離された状態にあり、貧困から抜け出すことが難しく、格差が広がる大きな原因になっています。 セロ (Celo) は、すべての人が公平にアクセスできる金融サービスの提供(金融包摂)を、ブロックチェーンの技術で実現することを目指したプロジェクトです。 セロ (Celo) ってどんなプロジェクト? $CELOの価値が大きく伸びる可能性はあるの? $CELOを買うならどの仮想通貨取引所を使えばよいの? そんな疑問をお持ちの人に向けて、この記事ではセロの特徴と将来性を解説しました。加えて、$CELOの取引におすすめの仮想通貨取引所も紹介しています。 最後まで読めば、セロ($CELO)がどういうプロジェクトかしっかり理解できますよ。 仮想通貨セロ($CELO)とは? 5つの特徴を解説 最初にセロ($CELO)の基本的な事項を説明します。 セロプロジェクトとそこで使用される仮想通貨セロ($CELO)の特徴を5つ上げたので、ひとつひとつチェックしていきましょう。 仮想通貨セロ($CELO)とは? 5つの特徴を解説 全ての人への金融サービス提供(金融包摂)を目指すプロジェクト PoSによる高速・低コストで環境負荷が少ないネットワーク ステーブルコインcUSD・cEUR・cREALを提供 仮想通貨CELOはネットワークのガバナンストークン スマホがあれば誰でも使えるモバイルファーストなウォレット 全ての人への金融サービス提供(金融包摂)を目指すプロジェクト セロ($CELO)のスペック 名称 セロ ティッカーシンボル CELO 発行者 セロ財団 発行日 2020年8月 コンセンサスアルゴリズム Proof of Stake(PoS) 時価総額ランキング 141位(2024年3月24日のCoinMarketCapの集計による) 時価総額 約880億円(2024年3月24日のCoinMarketCapの集計による) 公式サイト https://celo.org/ 公式X https://twitter.com/Celo 公式Discord https://discord.com/invite/celo 公式Medium https://blog.celo.org/ 世界には、銀行口座すら持てず基本的な金融サービスにアクセスできない人々が多くおり、格差を生む大きな原因となっています。こういった人々にも公平に金融サービスを提供する試みを金融包摂(Financial Inclusion)と言います。 セロは、仮想通貨の仕組みを使って金融包摂を実現することを目的としたプロジェクトで、「すべての人に繁栄の条件を作り出す」をビジョンに、人々が公平に金融サービスにアクセスできる世界を作り出そうとしています。 セロ財団は、セロの目的に賛同する企業・団体が多く集まっている非営利団体です。セロネットワークの開発を支援し、セロ上で活動する様々なプロジェクトに資金を提供して、エコシステムの発展に貢献しています。 PoSによる高速・低コストで環境負荷が少ないネットワーク セロは、環境負荷が少ないネットワークを構築しています。 コンセンサスアルゴリズムは、Proof of Work(PoW)ではなく、エネルギーコストが低いProof of Stake(PoS)を採用しました。セロチェーンのブロックを生成するバリデーターは、セロの保有者による投票によって決定します。 この方法によりセロは、ブロック生成時間が約5秒、ガス代が平均0.0005米ドルの高速で低コストのネットワークを、PoWよりも圧倒的に少ないエネルギー量で実現しています。 ステーブルコインcUSD・cEUR・cREALを提供 セロのステーブルコイン cUSD:米ドルにペッグ cEUR:ユーロにペッグ cREAL:ブラジルレアルにペッグ セロには、セロネットワーク独自に発行されている上記のステーブルコインがあります。 さらに、複数のネットワークで利用されているステーブルコインのUSDCやUSDTも、セロネットワークで利用できます。 これらのステーブルコインを利用して、セロネットワークの参加者は他の通貨の価格変動とは無関係に安定した経済活動が可能です。 テザー社、CeloチェーンでUSDTの発行を発表 仮想通貨CELOはネットワークのガバナンストークン セロネットワークにおける仮想通貨CELOの主な役割 Proof of Stakeによるネットワークのセキュリティ維持 セロネットワークの意志決定への参加 トランザクションの手数料支払い cUSD・cEUR・cREAL発行のための担保資産 仮想通貨セロ($CELO)はセロネットワークのエコシステムを支えるガバナンストークンです。 セロネットワークは、CELOの保有量によってネットワークへの影響力が決定する仕組みです。 セロのコンセンサスアルゴリズムは、CELOの保有量を反映した投票によってブロックの生成者を決定するPoSです。また、ネットワークの参加者は、CELOの保有量に応じて、ネットワークの意思決定に関与する投票権を持ちます。 また、セロネットワークにおけるトランザクションの手数料支払いにもCELOが使われます。 cUSDやcEURなどのステーブルコイン発行のための担保資産としてもCELOが使用されており、ネットワークの円滑な運営やセキュリティの維持に必要不可欠な役割を果たしています。 スマホがあれば誰でも使えるモバイルファーストなウォレット Valoraの公式ページより セロは、スマートフォンさえあれば誰でも簡単に使えるモバイルファーストなウォレットValoraを提供しています。 仮想通貨の購入・管理・送金、DAppsの利用など、仮想通貨に関する基本的な機能をValoraから利用できます。 特徴的なのは、Valoraでは相手の電話番号を指定すれば仮想通貨の送金が可能な点です。これを実現するために、電話番号とウォレットの公開鍵とを紐づける仕組みを開発しています。 他のウォレットでは送金時にアドレスの公開鍵を指定する必要があります。公開鍵は複雑で長い文字列のため、Valoraによって利用者の負担が大きく軽減され、資産の受け渡しに対するハードルが下がります。 セロ($CELO)のモバイルアプリ「Valora」の使い方 セロが提供しているスマホ向けのウォレットアプリがValoraです。モバイルファーストが特徴のセロらしく、シンプルで使いやすいウォレットです。 ここからはValoraの使い方について説明します。 Valoraは残念ながら日本語対応はされていません。以降の説明は使用言語で英語を選んだ場合を想定しています。 セロ($CELO)のモバイルアプリ「Valora」の使い方 アプリダウンロードから新規登録までの手順 入金・出金する方法 DAppsにアクセスする方法 アプリダウンロードから新規登録までの手順 最初に、Valoraをスマホにインストールして初期設定する手順を説明します。 Valoraをダウンロードして起動したら、まず言語選択の画面が出ます。日本語は使えないのでそれ以外の言語を選択しましょう。 使用する言語を選択すると、初期設定開始の画面が表示されるので「Get Started」を選びましょう。 Terms of Conditionへの同意と6桁のPINの設定を要求されるので、画面の指示に従って設定を進めます。 PINの設定が終わると、12個の文字列からなるリカバリーフレーズが表示されます。 リカバリーフレーズは、既に使用しているウォレットが失われた場合に復元するための情報なので、確実にバックアップを取っておきましょう。不正使用を招くので他人に預けるのも避けます。 バックアップが取れたら、画面下部の「I’ve saved it」をタップして次に進みます。 最後に、スマホの電話番号とウォレットの接続設定の画面になります。 表示された電話番号を確認して「Continue」をタップしましょう。これを設定しておけば、他のValoraユーザーがあなたに送金する際に、アドレスではなくあなたの電話番号を使えます。 電話番号とウォレットの接続が完了したら、Valoraのインストールと初期設定は完了です。 入金・出金する方法 自分のウォレットに入金する場合は、Valoraのトップ画面で「Receive」を選びましょう。 自分のウォレットのアドレスがQRコードと文字列で表示されるので、こちら宛に送金すればウォレットへの入金は完了です。 Valoraのウォレットから他へ出金する場合は、Valoraのトップ画面で「Send」を選択します。 「Select a recipient」の画面に切り替わるので「Scan or Show QR Code」を選びましょう。 出金先のアドレスのQRコードを読み込む画面に切り替わるので、QRコードを読み取り、出金する通貨の種類と出金金額を指定すれば、出金の指示は完了です。 DAppsにアクセスする方法 Valoraから、セロチェーン上で稼働しているDEXやDeFiサービスなどのDAppsを利用できます。 DAppsにアクセスする場合は、Valoraのトップ画面左上のメニューを開き「Dapps」を選択しましょう。 利用可能なDAppsのリストが表示されるので、使いたいものを選べばアプリケーションの画面に切り替わりますよ。 現在までのセロ($CELO)の価格動向 2024年3月28日のCoinMarketCapのデータから引用 セロ($CELO)の現在までの価格動向を確認しておきましょう。 2020年8月の発行開始から2022年前半までは、価格が比較的高い状態が続いています。特に仮想通貨全体に勢いがあった2021年の後半には、1CELO 800円を超える高値がついていました。 2022年の後半から仮想通貨市場全体の冷え込みとともに価値が下がり、1CELO 100円前後の価格で低迷を続けます。 2024年に入って、仮想通貨市場全体の勢いが盛り返すのに合わせて上昇の機運を見せており、2024年3月の時点では1CELO=200円付近まで上がってきています。 最新のCELOのチャートは以下で確認してください。 セロ($CELO)の今後は? 将来性を左右するポイント CELOのこれからの値動きに関して確定的なことは言えませんが、将来性に大きく影響する要素は複数あります。 次は、仮想通貨CELOの今後を左右するポイントを解説します。 セロ($CELO)の将来性を左右するポイント 仮想通貨市場全体の活性化 発展途上国への浸透 セロネットワーク上のDeFiサービスの拡充 200を超える広範なパートナーシップ 仮想通貨市場全体の活性化 CELOのこれまでの価格推移を見ると、大きく上昇している時期は仮想通貨市場全体に勢いがあった時と一致しています。CELOの値動きが仮想通貨市場全体の動向の影響を受けている点は、否定できません。 米国でのビットコインの現物ETF承認や、ビットコイン半減期への期待などから、2024年に入って仮想通貨市場全体は勢いを増しつつあります。 既にCELOも上昇の気配を見せています。2024年の後半から2025年にかけて仮想通貨全体が伸びれば、それに合わせてCELOの価値が上昇する可能性は十分にあるでしょう。 発展途上国への浸透 Opera社の公式ページより グローバルな金融包摂を目指すセロプロジェクトでは、発展途上国への浸透が重要な目標になります。 そのため、スマホを持っていれば誰でも使えるモバイルファーストなウォレットValoraをリリースしており、すでに100か国以上で100万を超える人々にダウンロードされています。 この動きをさらに加速するために、セロプロジェクトはOperaと提携してモバイルブラウザOperaMini用のウォレットMiniPayを開発しています。 最初はナイジェリアから展開されますが、これが順調に広がりを見せれば、CELOの価値の上昇が期待できます。 セロネットワーク上のDeFiサービスの拡充 セロネットワークを通して誰でもDeFiサービスを利用できる世界を実現するのも、セロプロジェクトのターゲットです。 現在セロネットワーク上では、さまざまなDeFiサービスが展開しています。セロチェーンをターゲットにしたUbeswapはもちろん、CurveやUniSwapなどのイーサリアムチェーンを基盤としたDeFiプロジェクトにも連携できます。 しかし、2024年3月の時点のDeFiLlamaのデータによれば、セロチェーンのDeFiの預かり資産額は約2億米ドルでDeFiサービス全体の0.2%程度でしかありません。 利用できるDeFiサービスを拡充して、世界中の誰にでも豊富な選択肢を公平に提供できれば、セロプロジェクトは着実に成長するでしょう。 200を超える広範なパートナーシップ セロ公式ページより セロプロジェクトは、目的に賛同する多くの企業や団体とパートナーシップを組むことで活動を加速する戦略をとっており、そのためのパートナーシッププログラムがCelo Alliance for Prosperityです。 例えば、以下の企業がパートナーシップに初期から参加しています。 ベンチャーキャピタル大手のa16z ウォレットのLedger 人道支援の非営利団体MERCY CORPS 貧困層への少額融資を進めるGRAMEEN 2023年にはGoogle Cloudがパートナーシップに加わりバリデーターとなるなど、既に200以上の企業・団体がメンバーに加わっており、セロネットワークのバリデーターや個別のプロジェクトの推進に貢献中です。 セロは金融包摂という重要な社会課題の解決を目指すため、単独での活動ではインパクトがありません。今後のパートナーシップの広がりには注目しておきましょう。 セロ($CELO)でおすすめの仮想通貨取引所 セロ($CELO)でおすすめの海外仮想通貨取引所 取引所 Bitget Bybit Gate.io 取引量ランク (2024年3月時点) 12位 3位 8位 取り扱い通貨数 (2024年3月時点) 750 576 2,005 最大レバレッジ 125倍 100倍 125倍 現物取引手数料 (各種優遇なしの場合) 0.1% 0.1% 0.1% 日本語対応 あり あり あり 2024年3月の時点では、セロ($CELO)の取引が可能な取引所は日本国内にはありません。 CELOを取引する場合は、海外の取引所を使う必要があります。おすすめはBitget、Bybit、Gate.ioの3社です。 Bitgetは、ハイパフォーマンスのトレーダーの取引をコピートレードできるのが最大の特徴です。サイトもスマホアプリもしっかり日本語化されているので、使いやすい取引所ですよ。 Bybitは、取引量が世界3位(2024年3月時点)の大手取引所です。最大で100倍のレバレッジ取引ができ、こちらも日本語対応されています。 Gate.ioは、取り扱い通貨の種類が多く2024年3月時点で2,000種を超えています。CELOに限らず多様なアルトコインを売買したい時に重宝する取引所です。 Bitgetの登録方法まとめ!口座開設とKYC認証まで徹底解説 Bybit(バイビット)の完全ガイド!登録方法から使い方、評判まで徹底解説! 【Gate.io(ゲート)の登録方法】初期設定から基本の使い方まで解説! セロ($CELO)に関するよくある質問 ここまで、セロ($CELO)の特徴や将来性について解説しました。重要な社会課題に目を向けた地道な活動が印象的なプロジェクトでしたね。 ここからはセロに関してよく出る質問にまとめて答えていきましょう。 セロ($CELO)に関するよくある質問 CELOはステーキングで稼ぐことができる? セロはどうやってカーボン・ネガティブを実現している? セロのステーブルコインの価格安定化の方法は? CELOはステーキングで稼ぐことができる? セロネットワークではCELOのステーキングにより報酬を得ることができます。 セロのProof of Stakeでは、CELOの保有者の投票によりブロックを生成するバリデーターが決まります。 投票する際には保有するCELOをステーキングしなければなりません。ステーキングしたCELOはロックされますが、ステーキングに対する報酬としてCELOを獲得できます。 セロはどうやってカーボン・ネガティブを実現している? セロではネットワークの稼働による二酸化炭素排出量をマイナスにするカーボン・ネガティブを実現しています。 コンセンサスアルゴリズムとして、PoWよりも大幅に二酸化炭素排出量を削減できるPoSを採用しています。 さらに、セロネットワーク上のトランザクションの承認手数料の一部をカーボン・オフセット基金に送り、オフセットの購入に充当しています。 「カーボン・オフセット」とは? 特定のプロジェクトでの温室効果ガスの排出量を削減するために、他の地域やプロジェクトでの同等量の温室効果ガス排出を削減することを言います。森林保護、エネルギー効率の向上などへの投資によって行われます。 セロのステーブルコインの価格安定化の方法は? セロネットワークではステーブルコインcUSD・cEUR・cREALを発行しています。 コインの価値が米ドルやユーロなどの法定通貨に準じるように、セロではステーブルコインの発行量に対する十分な担保資産をロックしています。 担保資産の約70%はCELOです。他はBTC・USDC・ETHといったメジャーな仮想通貨で構成されています。 仮想通貨セロ($CELO)のまとめ 仮想通貨セロ($CELO)のまとめ セロはすべての人への公平な金融サービス提供(金融包摂)を目指す セロチェーンは高速・低コストでカーボン・ネガティブなネットワーク スマホがあれば使えるモバイルファーストなウォレットValoraを提供 発展途上国への浸透やDeFiサービスの拡充がCELOの今後伸びを左右する CELOは国内の取引所では扱っていないので海外の取引所で売買する この記事では、セロプロジェクトの特徴や将来性を解説しました。セロチェーンで使われるモバイルファーストなウォレットValoraについても使い方を説明しています。 セロは、すべての人への公平な金融サービス提供(金融包摂)を目指しています。 そのために、カーボン・ネガティブでモバイルファーストなネットワークを開発しています。また、200以上の組織・団体とパートナーシップを組み、活動の裾野を着実に広げてきました。 セロに投資することは、単に仮想通貨を買うというだけでなく、重要な社会課題の解決に間接的に参加することでもあります。この記事を読んでセロに興味が出たら、今後の動きにしっかりアンテナを張っておきましょう。
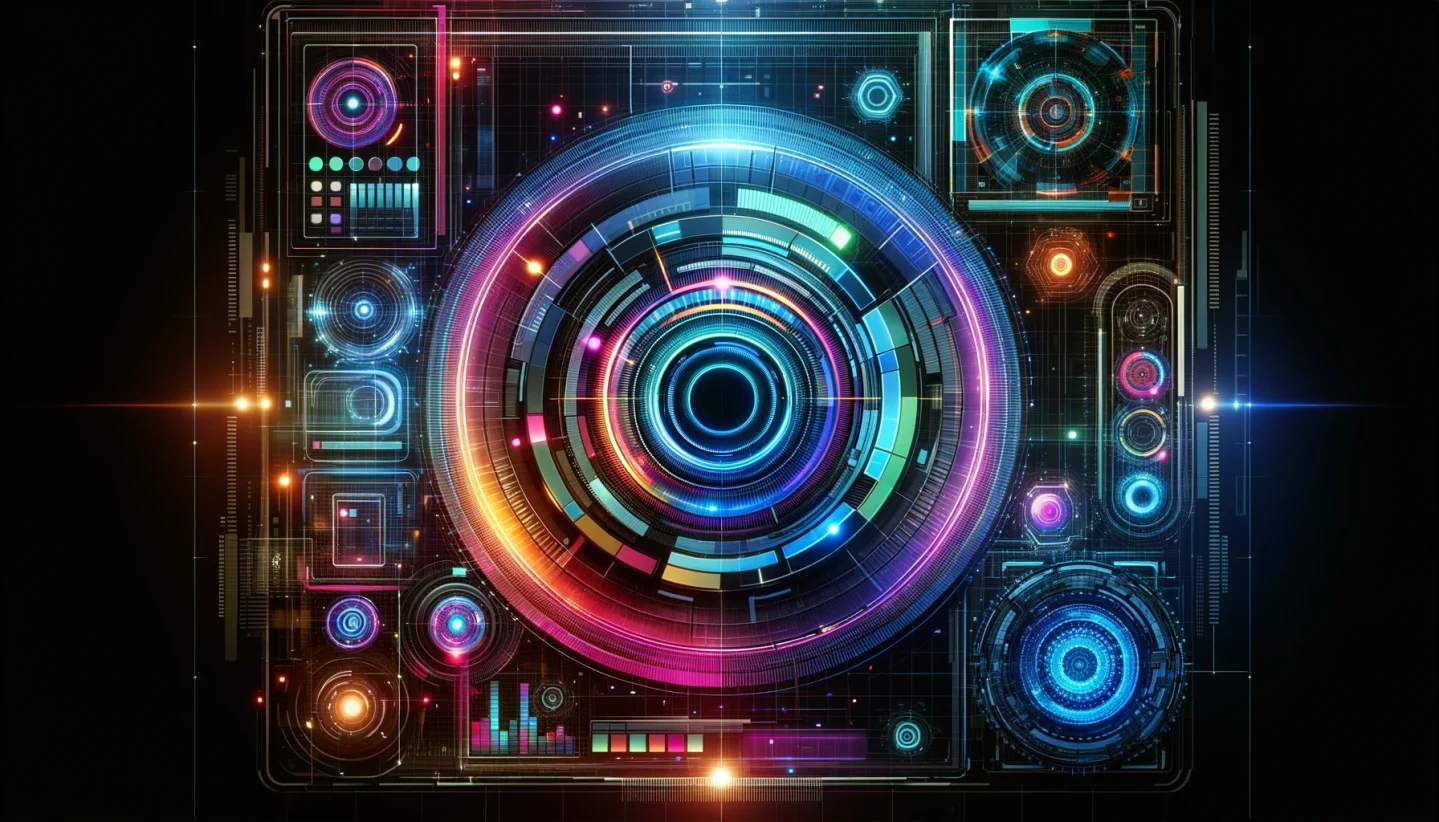
プロジェクト
2024/03/28NFT活用のWeb3コンテンツプラットフォーム「Mirror」の使い方を解説
– 著者:Henry(@HenryWells1837) これまでに、ブロックチェーンの技術を社内に導入するためのツールとして、HedgeyやSablier、Intmax Walletなどをご紹介してきました。 今回の記事では、会社の外へアウトプットする際の出版プラットフォーム「Mirror」について、概要や実際の使い方について解説していきます。 Mirrorとは = Web3出版プラットフォーム Mirrorは、Web3技術を活用した出版プラットフォームです。 ユーザーは自身で所有しているEthereumのウォレットを接続することで、プロジェクトのアカウントを設定し、コンテンツの作成、配信、ブロックチェーン技術を通じた収益化を行えます。 同プラットフォームで発行されるコンテンツ(記事)は、NFTとして生成され、Arweaveという分散型ストレージに永久保存されます。 Arweaveとは 永続的なデータストレージとホスティングサービスを提供する分散型ネットワークプロジェクト。2024年3月時点で時価総額4,155億円の仮想通貨$ARがインセンティブとして働くことで仕組みが保たれている次世代のストレージ/ホスティングソリューションを提供している。 Mirrorの強み [caption id="attachment_110573" align="aligncenter" width="634"] 画像引用元:Koshiro K / Shutterstock.com[/caption] Mirrorの4つの強み 1.多面的な収益化モデルを実現可能 2.多様なコミュニティ構築手法の模索が可能 3.コンテンツの改ざん、消失リスクを低減可能る 4.コンテンツクリエイターのプライバシー保護が可能 上記4点について、人気パブリッシュプラットフォームのnoteと比較しながら紹介していきます。 1. 多面的な収益化モデルを実現可能 Mirrorではコンテンツクリエーターは自身の作品を「Writing NFTs」として発行し、読者側がこれを購入してコレクションできます。さらに、独自のNFTを作成し、購読者がミントすることも可能です。 これに対して、noteは購読料や「投げ銭」等の支援金モデルを採用しており、読者が直接クリエーターをサポートする形式を採用しています。 Mirrorでは、文章内にNFT購入までの導線を埋め込む機能も付いています。一般的なパブリッシュサービス同様、定期購読の設定も可能となっており、従来のプラットフォームと比較しより多様な収益化モデルが実現できます。 2. 多様なコミュニティ構築手法の模索が可能 Mirrorでは、NFTを介したインタラクションにより、クリエイターを中心とする読者コミュニティの結束力を高め、クリエーターとファンの間に新たな関係を築くことが可能です。 読者側はEthereumのアドレスを登録して出版物 (NFT) の購入や購読などを行うため、コンテンツクリエイター側は自身の読者のアドレスの傾向などをオンチェーンデータから分析し、多様な施策が展開できます。 noteではコメント機能やお気に入り機能、著者のフォロー機能を通じて、より従来型のソーシャルエンゲージメントを提供しています。 一般的なプラットフォームと比較して、Mirrorにおいてユーザーはより読者との多様な関係構築が行えます。 3. コンテンツの改ざん、消失リスクを低減可能 Mirror上のコンテンツはNFTとして生成され、ブロックチェーン上で管理されるため改ざんや消失のリスクが低減され、コンテンツの不変性と真正性が保証されます。 noteなどの一般的な集中型な管理を行うパブリッシュサービスでは、プラットフォームが継続して運営されている限りコンテンツが保存されますが、ブロックチェーンのような不変性や分散型の保証はありません。 ビジネスの場面で情報発信を行う場合、Mirrorを活用することでコンテンツが消失するリスクを抑えられるのは大きな強みと言えます。 4. コンテンツクリエイターのプライバシー保護が可能 ブロックチェーン技術を基盤としているMirrorにおいて、ユーザーはEthereumウォレットを通じてプラットフォームにアクセスするため、自身の個人情報を明かす必要がありません。 noteでは集中型のサーバーを使用しており、過去にはユーザーのIPアドレスが流出するというセキュリティインシデントも発生しています。 【お詫びとご報告】 noteでソースコードからIPアドレスが確認できた事態に関して、その後の対応および本件を受けた安全性確保のための施策と、再発防止策についてご報告いたします。 多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めて心よりお詫び申しあげます。https://t.co/ilFqxU6JSk — note (@note_PR) September 30, 2020 Mirrorは、ユーザー側が自身の情報をどこまで明かすか選択できるため、よりコンテンツクリエイターの意思が尊重されたプラットフォームと言えます。 Mirrorの使い方 [caption id="attachment_110691" align="aligncenter" width="718"] 画像引用元:https://mirror.xyz/[/caption] 事前準備 事前に、Metamaskなどでウォレットアドレスを作成ください。ウォレットアドレスをお持ちでない方は、過去のこちらの記事を参考にしながらアカウントを作成しましょう。 ウォレットアドレス作成後は、利用したいメインネットにETHを準備します。 現在は、以下のチェーンに対応しているので予め利用したいメインネットにETHを入れておきましょう。 Base Linea Optimism Polygon Zora MirrorへのアクセスとNFT(コンテンツ記事)の購入方法 まずは、Mirror ( https://mirror.xyz/ )にアクセスします。 アクセスしたら、画面右上の Connect をクリックしてウォレットを接続しましょう。 *Rabby Walletには対応していないのでご注意ください。 Walletを接続したら、以下のように Inbox と Explore で画面を選択することができます。 また、初回登録時はオススメのコンテンツクリエイターが画面右側に表示されるので定期購読を選択できます。 Explore では、以下のように表示されます。こちらの、一番上のコンテンツ記事をクリックしてみましょう。 記事をクリックしたら、記事単体の画面に移行します。こちらは、The Optimism Collectiveが発行している記事になります。 この記事自体は最後まで無料で読めますが、従来の雑誌などと同様に購入して自分のウォレットにNFTという形式で保有したい場合は、Mint ボタンを選択することで、当該コンテンツを購入できます。 上記の画面では、既に89名のユーザーがCollect(購入)したと表示されており、その内訳を以下のように見られるのもブロックチェーンの特徴の一つです。 例えば、事業会社の方がアプローチしたい潜在的な顧客がOptimismユーザーであった場合、このように購入したユーザーのウォレットアドレスを別途DeBankなどで閲覧することで、ユーザーの属性、好み、趣向などのデータを収集できます。 コンテンツの記事は、発行者が自由に決められる仕様になっており、コンテンツ料金、プラットフォーム手数料、ガス代の3つの費用をユーザーが払います。 今回の例として紹介している記事では、コンテンツ料金が0.001 ETH、プラットフォーム手数料が0.00069 ETH、そしてガス代が加わる形になります。 *Mirror上で取得したNFTはセカンダリ市場でも売買可能です。その際に発生する手数料も同様に0.00069ETHが発生します。 定期購読の設定方法 Mirrorでは、定期購読もできます。 Subscribeボタンを押した後、対象のウォレットアドレスとメールアドレスを紐づける作業が発生します。 下記のように、発行者がコンテンツを発行した際に通知を受け取れるようにメールアドレスを入力してください。 メールアドレス入力後、Continueボタンを押したら指定のメールアドレスに認証メールが届きます。 認証を完了させたら、Subscribeも完了します。 実際にSubscribeが完了したクリエーターのトップページに行くと、画面右上がSubscribedと表示されています。 コンテンツを発行する方だけに限らず、Defiユーザーなどにとっても役立つ情報がMirrorでは飛び交っています。 エアドロップに関する情報が発信されている場合もあるので、気になるコンテンツクリエイターは見逃さないようにSubscribeしておきましょう。 コンテンツの作成と発行方法 記事の作成方法 こちらでは基礎的なコンテンツの作成方法をご紹介します。 まずは、自身のウォレットをMirrorにConnectしてください。 その後、画面右上に + Createというボタンが表示されますので、そちらをクリックしてください。 そしたら、以下の記事作成ページが表示されます。 基本的な作りは、WordPressと同じです。WordPressで記事の作成経験がある方は問題なく作成いただけます。 初めて作成される方は、まずは上記画面のように「タイトル」と「本文」に入力してみてみましょう。直感的に記事コンテンツが作成できるかと思います。 執筆が完了したら、画面右上のPublishボタンをクリックします。 クリック後、発行する記事を無料にするか有料にするかを決められます。もし有料にしたい場合は、下記のように赤枠の所に希望の金額をETH単位で入力ください。 その後、Sign and Publish を押すと発行が完了します。 NFT販売ページの効果的な埋め込み方 NFTを作成し販売する際には、販売ページとMintページの作成が一般的です。 例えば、私達が昨年立ち上げた「自然災害復興支援NFTプロジェクト」の秋田県災害復興支援NFTでは、以下のように構成されていました。 NFT 紹介ページ : https://nft4recovery.my.canva.site/jp-001-akita NFT Mintページ : https://app.manifold.xyz/c/nft4recovery-001-akita 当該プロジェクト紹介記事 : https://crypto-times.jp/nft-for-recovery/ NFTミントページ以外を用意する主な目的は、ユーザーにプロジェクトについて詳しく知ってもらい、関心を持ってもらうことです。しかし、このアプローチには制作コストがかかり、費用対効果を慎重に検討する必要があります。 また、ユーザーに複数のサイトを遷移させる必要がありその分離脱率が高まります。 MirrorでのNFT販売ページ埋め込み Mirrorでは、販売するNFTを直接エントリーに埋め込めます。これにより、ウェブサイトを離れることなくNFTを展示でき、購入プロセスをよりタイトにできます。 以下は、Manifoldを利用したNFT埋め込みの手順です。今回は、上記のManifoldをページ内に埋め込みます。 上述したコンテンツ作成の際に、Blocks を選択して、NFT Embed を選択したら下記のウィンドウが出てくるので、右側を選択してください。 すると、下記のウィンドウが表示されます。 ManifoldのURLを入力します。 入力後、URLの内容が反映されたら上記の画面のように対象のNFTの画像が表示されます。 反映後、Create Blockが表示されたらクリックして完了です。 この埋め込み機能は、ウォレットに接続している読者を直接NFT販売ページへ誘導する効果的な手段です。これにより、新しいマネタイズ方法としてMirrorを活用できます。 まとめ:Mirrorの利点を活用する この記事では、ブロックチェーンベースの出版プラットフォーム、Mirrorの使い方を紹介しました。 Mirrorはコンテンツの永久保存、真正性保証、そして収益化の新しい手法を提供します。これらの特徴は、情報の配信だけでなく収集においても、Mirrorを有効な選択肢にします。また、当該プロジェクトはトークン発行がされていないことから、活用することによりエアドロップの期待もできるかもしれません。 情報の収集においても非常に優れたプラットフォームになりますので、ぜひ一度活用してみてください。

プロジェクト
2024/03/2630分毎に3回DAIが貰える?INTMAXのエアドロップキャンペーンでPlasma Nextを体験
[no_toc] ブラジルのEthereum開発者コミュニティを支援を目的に、INTMAXはETH Sambaのキースポンサーとなりました。それに伴い、2月にETH DenverでPlasma Nextを発表したINTMAXからPlasma Nextを体験できるエアドロップキャンペーンが開催中です。 Chance to win nanoMoney ! Plasma Next partners with @ethsamba to Empower Brazil's vibrant Ethereum developer community and introduce the nanoMoney. Click nanoMoney icon on https://t.co/3GYATpTzrJ and win between $0.000000001 and $100 in DAI! pic.twitter.com/Wn6H4NR4zE — Plasma Next (Intmax) (@intmaxIO) March 23, 2024 本キャンペーンは、日本在住の方々も参加できるキャンペーンになります。 開始前の注意点 今回のキャンペーンは、ユーザーがガスレス送信などの体験をするためのものです。実際のメインネットのローンチは2024年内を予定しています。 ETH Sambaのサイトで生成されたウォレットは一時的なものとして扱われます。 生成されたウォレットは、以下のいずれかの条件に該当する場合に消滅する可能性があるため、ご注意ください。 ブラウザのクッキーを削除した場合。 プライベートモードで開いたブラウザを閉じた場合。 ブラウザアプリを閉じた場合。 iOSでブラウザを使用していて、該当サイトに7日間アクセスしなかった場合。 これらの点を踏まえて、キャンペーンをお楽しみください。 $DAIを獲得するための手順 ETHSamba ( https://ethsamba.org )へアクセス。 画面左下の"Nano Money"をクリック。ウォレットが自動で生成されます。 "Airdrop"をクリック。 Twitterアカウントを連携。 *アカウントを連携しない場合、受け取れるDAIの数量は0.000000001に限られます。 "Receive Now"で0.000000001〜100 DAIをランダムで受取。 *受け取った$DAIは、0.01 DAIよりArbtirumの指定ウォレットへ送信することができます。 受け取ったDAIをArbitrumの指定ウォレットへ送信する方法 "Spend"→"Withdraw"で、受取先のアドレスを入力してArbitrumに送金。 送金手続き後、1時間ほどで指定のアドレスに届きます。 Plasma Nextとは "Plasma Next"は、Ethereumのスケーラビリティとプライバシーの課題を解決するために開発された、オープンソースの最新の技術です。元々、2017年にJoseph PoonとVitalik Buterinによって構想されたPlasmaを基にしていますが、Plasma Nextはその時の問題を克服し完成させた技術になります。 特に、Plasmaが抱えていた「時間拘束」の問題、つまり引き出し時に7日間の待機が必要だったことや、ユーザーがトランザクションを常に監視する必要があった点を改善しました 。この技術は、高度なゼロ知識証明とステートレスなアーキテクチャにより実現されています。この構造により、ユーザーはPlasmaチェーン上のトランザクションを常時監視する必要がなく、引き出しの際の長期待機も不要になりました。 また、非常に低いガス代が混雑時であっても常にキープすることが出来る点は、業界でも他に例がありません。これにより、Ethereumのセキュリティを持ちながら、トランザクション処理能力を大幅に向上させ、同時にユーザーのプライバシー保護もカバーしています。 Plasma Nextは、オープンソースとしてEthereumの拡張性とプライバシーの課題に対する実用的な解決策を提供し、ユーザーへこれまで以上に高速かつ安全なEthereumネットワークを利用する体験をもたらすことを目指しています。 SNS等:Website|X|GitHub|Docs

プロジェクト
2024/03/24仮想通貨トロン($TRX)とは?特徴と将来性について徹底解説!
トロンは、DAppsのプラットフォームとして開発されたネットワークです。ここで利用される仮想通貨もトロン($TRX)と呼ばれます。 映像や音楽などのエンターテイメントの領域をターゲットにして低コストで高速なネットワークを構築しており、近年ではDeFiの領域でも存在感を増しています。 トロンってどんなプロジェクト? TRXは今後伸びる可能性はあるの? TRXを売買するなら、どの仮想通貨取引所がおすすめ? そんな疑問をお持ちの人に向けて、この記事ではトロンの特徴と将来性を解説しました。加えて、TRXを取引するのにおすすめの取引所も紹介しています。 最後まで読めば、トロン($TRX)に関する必須の知識をすべて得ることができますよ。トロンを使って快適な資産の送受金も可能となります。 トロン($TRX)とは? 5つの特徴を解説 最初にトロン($TRX)の基本的な事項を解説します。 トロンネットワークと、そこで使用される仮想通貨トロン($TRX)の特徴を5つ上げたので、ひとつひとつチェックしていきましょう。 トロン($TRX)とは? 5つの特徴を解説 DAppsのプラットフォームとして開発されたネットワーク 創始者のJustin Sun氏は何かと話題が多い人 コンセンサスアルゴリズムがDPoSで高速・低コスト TRXのステーキングで稼げる DeFi領域での進展がめざましい DAppsのプラットフォームとして開発されたネットワーク トロン($TRX)のスペック 名称 トロン ティッカーシンボル TRX 創始者 Justin Sun(ジャスティン・サン) 運営者 TRON DAO 発行日 2017年8月 時価総額ランキング 13位(2024年3月4日のCoinMarketCapのデータによる) 時価総額 約1.85兆円(2024年3月4日のCoinMarketCapのデータによる) コンセンサスアルゴリズム Delegated Proof of Stake(DPoS) 公式サイト https://tron.network/ 公式X https://twitter.com/trondao 公式X(日本) https://twitter.com/TronDao_JPN 公式Instagram https://www.instagram.com/trondaoofficial/ トロンはDAppsのプラットフォームとして開発されたネットワークです。そこで使用される通貨がトロン($TRX)です。 中国発のプロジェクトで、中国がICO(Initial Coin Offering)を禁止する直前にICOを行いました。当初はシンガポールにあるトロン財団が管理していましたが2021年12月に解散し、現在はTRON DAOに引き継がれています。 2017年のローンチ当初はイーサリアムのブロックチェ―ン上で開発されており、TRXもERC-20のトークンでしたが、2018年に独自のチェーンに移行しています。 当初は、映像や音楽といったエンターテイメントの領域をターゲットにして開発されましたが、DeFiや分散ファイルストレージの分野でも活用が広がっています。 その結果、2024年3月の時点で時価総額約1.85兆円の規模にまで成長しました。 創始者のJustin Sun氏は何かと話題が多い人 Wikipediaより引用 トロンの創始者はJustin Sun氏です。 中国生まれで大学まで中国で教育を受け、その後ペンシルバニア大学で仮想通貨に出会い、2013年からはRipple Labsで活動しています。2014年には、音声ベースのSNSアプリである Peiwo を設立した後、2017年にトロンを創設しました。 2017年のトロンのICOは、中国がICO(Initial Coin Offering)を禁止する直前のタイミングで行われました。Justin Sun氏は中国政府の動きを事前に知っており、ICOを仕掛けたと一部では言われています。 2018年にはメジャーなファイル共有サービスのBittorrentを買収して注目を集め、TRXの価格急上昇へと繋げました。 2019年には、バークシャー・ハサウェイ(Berkshire Hathaway)のウォーレン・バフェット(Warren Buffett)氏と昼食を共にする権利を約5億円で落札しました。バフェット氏は稀有な投資家として有名ですが、仮想通貨に否定的なことでも知られていました。 2023年には、未登録証券の提供・販売の疑いて米証券取引委員会(SEC)から提訴されており、この件は2024年現在も係争中です。 Justin Sun氏は良くも悪くも何かと話題が多い、仮想通貨業界の有名人です。 コンセンサスアルゴリズムがDPoSで高速・低コスト トロンのコンセンサスアルゴリズムはDelegated Proof of Stake(DPoS)です。 ブロックの作成はスーパー代表と呼ばれるノードが行います。スーパー代表を決定するためにTRXの保有者による投票が6時間おきに行われ、上位27位までがスーパー代表になります。 28位から127位まではスーパーパートナーと呼ばれます。スーパー代表のリザーブ的な存在です。 投票では、より多くのTRXを保有していればより多くの投票権を持ちます。結果的に、TRXをより多く保有していれば、ネットワークのガバナンスへの影響力が強くなります。 DPoSは、ブロックの作成を限られたノードによって行うことで、高速・低コストのブロックチェーンを実現しました。また、TRXの保有者による投票システムにより、ネットワークのガバナンスへの影響力を分散化しています。 TRXのステーキングで稼げる TRXの保有者がスーパー代表の投票をする時は、TRXをステーキングして投票権を得る必要があります。 ステーキングしたTRXはロックされるので売買できません。その代わり、ステーキングに対して報酬としてTRXを得ることが可能です。 スーパー代表やスーパーパートナーのノードは、トロンのネットワークから報酬としてTRXが提供されます。 スーパー代表やスーパーパートナーは、自分に投票してくれたTRX保有者に対して報酬を分配するため、これがTRX保有者へのステーキング報酬になります。 国内の仮想通貨取引所でTRXのステーキングサービスを提供しているのは、BitPointとOKCoin Japanの2社です。 DeFi領域での進展がめざましい DeFiLlamaの2024年3月4日のデータより トロンは、当初エンターテイメント領域を狙ったプロジェクトでしたが、ここ数年はDeFi領域での動きが目立ってきました。 特に、2022年5月に新しいステーブルコインであるUSDD(Decentralized USD)がトロンネットワーク上でローンチされてからは、その傾向が強くなっています。 DeFiLlamaのデータによれば、2024年3月の時点で、トロンのDeFi領域での預かり資産額はイーサリアムに次いで2位です。DeFi全体の10%以上がトロンのネットワークを利用していることがわかります。 今後の動きは?TRXの最新価格動向 トロンの特徴が理解できたところで、次はTRXの価格の動向について確認しておきましょう。 こちらでは、TRXのこれまでの値動きとTokenomicsについて解説します。 今後の動きは?TRXの最新価格動向 最高値更新目前!現在までのTRXの価格動向を解説 トロン($TRX)のTokenomics 最高値更新目前!現在までのTRXの価格動向を解説 [caption id="attachment_108633" align="aligncenter" width="816"] 2024年3月4日のCoinMarketCapのデータより[/caption] TRXのこれまでの価格動向(vs USD)を確認してみましょう。 TRXはこれまでに2度の価格の上昇がありました。1度目はICO直後の2017~18年、2度目は2021~22年です。 どちらも仮想通貨全体に勢いがあった時期と一致しており、ビットコインやイーサリアムをメインとするトレンドにある程度影響されている傾向が見て取れます。 現在も2024年の年頭からの仮想通貨市場全体の盛り上がりに合わせて、TRXの価格も上昇しています。発行以来の最高値更新も目前の状態にまで伸びています。 トロン($TRX)のTokenomics ICO時点でのトロン($TRX)のTokenomics 割り当て先 割り当て率 ICOでの売却 40.25% トロン財団 34% 投資家へのプライベートセール 15.75% Peiwo Huanle Co. 10% 2017年のICO時のTRX発行量は1,000億TRXでした。このうち、ICOで売却されたのが40%強です。プライベートセールをあわせて56%が投資家に割り当てられました。 残りの44%は、トロン財団及び創始者Justin Sun氏の会社であるPeiwo Huanle Co.の持ち分となっています。 ICO後はスーパー代表などへの報酬としての新規発行によって総流通量は微増していましたが、継続的なバーン(焼却)により現在の総流通量は微減傾向にあります。 トロン($TRX)は100円になる? 将来性を左右するポイント 2024年3月の時点でのTRXの価格は約21円です。仮想通貨全体の伸びに呼応して上昇傾向にあります。 今後も順調に伸びていくかは確定的なことは言えませんが、将来性を左右する重要なポイントについて考察していきましょう。 トロン($TRX)の将来性を左右するポイント 仮想通貨市場全体の活性化 大規模プロジェクトによるトロンネットワークの採用 ビットコインネットワークとの相互運用ロードマップを発表 TRXの積極的なバーン(焼却)による価格維持 仮想通貨市場全体の活性化 他の多くの仮想通貨と同様に、TRXも仮想通貨市場全体の勢いに大きく影響されています。TRXの値動きのピークは、仮想通貨全体の価格のピークとほぼ一致しており、今後も同様の傾向が続くと予想できます。 2024年に入り、米国でのビットコインやイーサリアムの現物ETF承認の動きや、ビットコインの半減期への期待から、仮想通貨市場全体は盛り上がりを見せています。 既にTRXも上昇の気配を見せていますが、2024年の後半から2025年にかけて仮想通貨全体がさらに伸びていけば、TRXの価値も上昇する可能性は十分にあるでしょう。 大規模プロジェクトによるトロンネットワークの採用 TRXの価値が安定的に伸びるには、将来性のあるさまざまな領域のプロジェクトでトロンネットワークが採用されることが重要です。 この点ではトロンは一定の成功を収めつつあると言えるでしょう。 DeFiの領域ではすでにイーサリアムに次ぐポジションを獲得しており、市場に不可欠な存在になっています。 また、以下の世界各国の企業と早くから連携しています。 韓国のITメーカーである「Samsung」 ウェブブラウザの「Opera」 スイス最大の通信事業「Swisscom」など さらに、ドミニカ連邦ではTRXが政府公認のデジタル通貨として認められており、正式な決済手段として利用されています。 今後も大きなプロジェクトや組織との連携のニュースが飛び込めば、トロンに注目が集まることが予想されます。 ビットコインネットワークとの相互運用ロードマップを発表 トロンのビットコインレイヤー2ソリューションロードマップ 【Stage α】クロスチェーン技術によるビットコインの相互運用性の拡大 【Stage β】ビットコインのレイヤー 2とトロンの間のコラボレーション拡大 【Stage γ】統合レイヤー 2 ソリューションのローンチ TRON DAOは、トロンネットワークとビットコインの相互運用に関する3ステップからなるロードマップを2024年2月に発表しています。 この統合で、トロンからビットコインの大きなネットワーク資産への直接的なアクセスが可能になり、トロンの豊富なDeFiサービスはより大きな市場を視野に入れることができます。 具体的なスケジュールはまだ展開されていませんが、トロンの今後を大きく左右する転換点になるかもしれません。 TRXの積極的なバーン(焼却)による価格維持 TronScanの2024年3月4日のデータより トロンはTRXの価値を維持するため、TRXを積極的にバーン(焼却)して流通量をコントロールしています。 複数回にわたる大規模なバーンを実施し、さらに取引手数料の一部のバーンを継続中です。 その結果、ブロック生成による新規TRX発行は続いているにもかかわらず、2021年の1,020億TRXのピーク以降は流通量が継続的に下がり続けるデフレ状態にあります。 この傾向は今後も継続することが予想されるため、TRXの価値が下支えされる可能性が高いと言えます。 トロン($TRX)でおすすめの仮想通貨取引所 トロン($TRX)に興味がでたら、TRXを仮想通貨取引所で購入してみましょう。 こちらでは、TRXの取引におすすめの仮想通貨取引所を紹介します。売買だけでなくステーキングサービスも提供されています。 OKCoin Japan OKCoin Japanのスペック 名称 OKCoin Japan 運営会社 オーケーコイン・ジャパン株式会社 提供サービス 販売所、取引所、暗号資産つみたて、ステーキング 公式サイト https://www.okcoin.jp/ 取り扱い通貨数 34種 OKCoin Japanは海外の大手取引所OKCoinの日本法人です。取引できる通貨が34種と豊富なのが特徴です。 TRXに関しては販売所・取引所での売買とステーキングが可能です。ステーキングの予想利回りは60日のステーキング期間で年利3.88%です。 ステーキングをするにはまずTRXを入金し、ステーキングのページから期間と数量を指定しましょう。ステーキングしたTRXはロックされ、売買や出金はできません。 OKCoinJapanの登録はこちら OKCoinJapan(オーケーコイン・ジャパン)の登録方法から使い方まで解説! トロン($TRX)に関するよくある質問 ここまでトロン($TRX)の特徴や将来性について説明してきました。トロンに関してしっかりイメージできてきましたよね。 最後に、トロンに関してよく出てくる質問に対してまとめて答えていきましょう。 トロン($TRX)に関するよくある質問 TRXを扱えるウォレットアプリはありますか? トロンのステーキング報酬はどうやって決まりますか? トロンのブロックチェーンの状態を確認するには? TRXを扱えるウォレットアプリはありますか? 仮想通貨を取引所に預けるのではなく、自分で管理したい時にはPCやスマホで使えるウォレットアプリが必要ですよね。 TRXを管理できるウォレットアプリは多くあります。 特におすすめなのはMetaMaskとTrust Walletです。ユーザーが多く実績があり、セキュリティ面でも信頼できます。使い方に関する情報も多く見つかるので、戸惑うことなく利用できますよ。 ・MetaMask(メタマスク)の使い方まとめ!入出金・トークン追加もかんたん利用 ・仮想通貨ウォレットを種類別に解説!おすすめ10選も紹介 トロンのステーキング報酬はどうやって決まりますか? トロンのステーキング報酬は、スーパー代表やスーパーパートナーがネットワークから受け取った報酬を、自分に投票してくれたTRX保有者に再分配することで発生します。 再分配の比率はスーパー代表やスーパーパートナーごとに異なるので、一律の基準値はありません。 仮想通貨取引所のステーキングサービスを利用する場合は、スーパー代表やスーパーパートナーから再分配された報酬から、取引所が経費や利益の分を差し引きます。 その結果、ステーキングの利回りは取引所ごとに大きく異なる結果になります。取引所のステーキングサービスで稼ぎたいなら、取引所ごとの予定利回りをしっかり比較しましょう。 トロンのブロックチェーンの状態を確認するには? TRONSCANのホームページより引用 トロンのブロックチェーンの状態はTRONSCANで確認できます。 ブロックの生成状況や個別のドランザクションの承認状態を詳細に調べることができます。 TRXの流通量やステーキングの状態、トロンのスーパー代表の投票結果も見ることができ、トロンのネットワーク上で発行されているTRX以外のトークンの状況も確認可能です。 トロンの状況をリアルタイムで把握するのにとても便利なサイトですよ。 仮想通貨トロン($TRX)のまとめ 仮想通貨トロン($TRX)のまとめ 2017年に稼働したDAppsのプラットフォーム コンセンサスアルゴリズムにDPoSを採用し高速・低コスト DeFi領域でイーサリアムに次ぐ2位のポジションを獲得 仮想通貨市場の活性化や大規模プロジェクトとの提携が将来性に影響する BitPointやOKCoin JapanならTRXの売買だけでなくステーキングもできる この記事では、DAppsのプラットフォームであるトロンの特徴と将来性を解説しました。 トロンは、コンセンサスアルゴリズムにDelegated Proof of Stake(DPoS)を採用しており、高速で低コストのネットワークを実現しています。 映像や音楽などのエンターテイメントの領域をメインのターゲットにしていましたが、近年ではDeFi領域での採用が目覚ましく、今後も安定的に伸びることが期待できます。 国内の仮想通貨取引所でTRXの売買だけでなくステーキングも可能です。この記事を読んでトロンに興味が持てたら、TRX購入を検討してみましょう。 免責事項 ・本記事は情報提供のために作成されたものであり、暗号資産や証券その他の金融商品の売買や引受けを勧誘する目的で使用されたり、あるいはそうした取引の勧誘とみなされたり、証券その他の金融商品に関する助言や推奨を構成したりすべきものではありません。 ・本記事に掲載された情報や意見は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性、完全性、目的適合性、最新性、真実性等を保証するものではありません。 ・本記事上に掲載又は記載された一切の情報に起因し又は関連して生じた損害又は損失について、当社、筆者、その他の全ての関係者は一切の責任を負いません。暗号資産にはハッキングやその他リスクが伴いますので、ご自身で十分な調査を行った上でのご利用を推奨します。(その他の免責事項はこちら)

プロジェクト
2024/03/19Blast BIG BANGコンペ優勝プロジェクト「YOLO Games」とは?|Blastエコシステム最注目のGambleFi
イーサリアムでは多くのレイヤー2エコシステムが日々成長していますが、現在最も加熱しているのはBlastかもしれません。 [caption id="attachment_109943" align="aligncenter" width="1439"] https://defillama.com/chain/Blast[/caption] Blastは、NFTマーケットプレイス「Blur」創設者のPacman氏(@PacmanBlur)によって開発されるイーサリアムレイヤー2です。2月29日にメインネットをローンチしてからもTVLは右肩上がりに推移しており、そのエコシステムに対する注目は冷めることなく続いています。 Blastでは、1月から「Blast BIG BANG」と題したコンペティションを行っていました。そして、2月23日、3000以上の応募プロジェクトの中から、47の優勝プロジェクトが発表されました。 Blast BIG BANGコンペ特集|3000以上の応募から選ばれた47プロジェクトを全紹介! 今回の記事では、BIG BANGコンペ優勝プロジェクトの1つである「YOLO Games」を特集します。 YOLO Gamesとは? Big BANG BLAST優勝プロジェクトGambleFi:開発者向けエアドロップを全てプレイヤーへ還元予定 YOLO Gamesは、BIG BANGコンペにてGambleFiカテゴリーとして選ばれた6つのプロジェクトのうちの1つです。 Blastでは、BIG BANGコンペ選出プロジェクトに対して、開発者向けのエアドロップを実施すると発表しています。 YOLO Gamesは自身に割り当てされる$BLASTエアドロップを、100%プレイヤーに対して還元すると発表しており、プレイヤーのより良いゲーム体験の実現に努めているGambleFiと言えるでしょう。 全てのゲームを完全にオンチェーンで提供 GambleFiを楽しもうとするプレイヤーにとって、ゲーム結果が運営によって操作されておらず、公平であるかどうかは非常に重要です。 YOLO Gamesでは、全てのゲームが完全にオンチェーンであり、ランダム性と価格フィードのために様々なオラクルを使用しています。 全てのランダム性を常に検証可能とすることで、YOLO Gamesはプレイヤーが求める透明性や公平性を実現しています。 プレイヤー重視のインセンティブを構築:手数料や利回りの100%を還元 YOLO Gamesでは、プレイヤー報酬が重視されています。その試みをいくつか紹介します。 ゲームから発生した手数料の100%をプレイヤーに還元 ネイティブ利回りの100%を還元 Blastインセンティブを100%還元 YOLO Gamesでは、手数料の還元について幾つかの方法を用意しています。ここでは、そのうち主要な2つであるRakebackとくじ(Lottery)について紹介していきます。 Rakeback:30%分の手数料を還元 Rakebackは、手数料還元施策の30%を占めており、一定期間にわたって利用料金の一部をプレイヤーに還元する仕組みです。例えば、とあるプレイヤーが1ETHを手数料として使用した場合には、手数料還元として0.3ETHを請求することが出来ます。 この手数料返還請求の期間は、12時間ごとに4つのフェーズで構成されています。各フェーズでは4分の1ずつ(上記の例だと0.075ETH)の返還を請求することが可能となっています。 フェーズが移ってしまうと、前のフェーズの手数料は請求出来なくなることには注意が必要です。 くじ(Lottery):15%分の手数料を還元 もう1つのプレイヤーにとって身近な還元は、くじ(Lottery)です。これは、手数料還元施策の15%を占めています。 プレイヤーはYOLO Gamesで遊ぶことによってポイントを獲得出来ますが、1000ポイントごとにチケットを1枚獲得可能です。 このチケットを使うことで、賞金を獲得できるくじに参加することが可能です。この賞金プールは手数料によって構成されています。 くじは、デイリー抽選とウィークリー抽選が用意されており、プレイヤーは好きな方で抽選に参加することが可能です。 その他にも多くの手数料還元を実施予定 ここまで紹介してきた手数料還元は、全体の45%を占めるものです。 残りの55%については、30%が将来のプロモーションやインセンティブに使用される予定とのことであり、20%の用途についてはまだ未発表となっています。 勝っても負けてもポイントを稼ぐことが可能 YOLO Gamesが提供するゲームでは、勝っても負けても報酬がもらえます。ゲームに参加するたびにポイントを獲得し、リーダーボードのランキングも上がっていきます。 デイリークエストをこなしたり、マイルストーンを達成することで、シーズン終了ごとに多くの報酬を得ることも可能です。 YOLO Gamesのゲーム紹介 オンチェーンゲームのスイートを提供 YOLO Gamesは、オンチェーンゲームのスイートを提供しています。 勝者が1人のみのハイリスク・ハイリターンなゲーム(YOLO)から、敗者が1人だけのローリスク・ローリターンなゲーム(Poke the Bear)まで、幅広く提供されています。 ここでは、現在、YOLO Gamesで提供されている3つのゲームを紹介していきます。 MOON or DOOM:BTCやETHの価格傾向を予測 一定時間の間に暗号資産の価格が、上昇(MOON)するか下落(DOOM)するかを予想します。的中すれば、勝利となります。 予想する暗号資産は、ETHUSDとBTCUSDのペアとなります。これらの価格情報は、Pythのフィードから直接取得されたものです。 実際のプレイ画面 上記添付画像が、実際のYOLOの画面となります。 一定時間ごとの価格を基準に、その価格よりも上昇しているか下落しているかを予想します。基準となる価格は「Current」となっている価格です。(上記画像の場合、$68,562.9) 価格を予測する期間は、BTCとETHで異なっており、BTCの場合は5分間、ETHの場合は1分間となっています。 時間が経過した後は、最終結果が表示され、予想が的中した人には報酬が与えられます。 ここで注意が必要なのは、最終価格は画面に表示されている価格ではなくオラクルによって決定された価格になることです。それぞれに時間差があるため、DOOMの結果がMOONの結果に変わる(またはその逆)こともあります。 また、まずありえないことではありますが、始値と終値が同じとなった場合には、両者(MOONとDOOM)敗北となります。 YOLO:勝者総取りの宝くじ YOLOは、勝者総取りの宝くじです。プレイヤーは共有ポットにETHもしくはUSDB(Blast上のステーブルコイン)をベットします。プレイヤーの勝率はポット総額の自身のベット金額に比例するようになっています。 ベットが終了すると、ランダムに勝者が1人選ばれます。勝者は手数料を除いた全額を獲得します。 このランダム性には、Gelatoが使用されており、結果の透明性や公平性が証明できるようになっています。 実際のプレイ画面 上記画像は実際のYOLOのプレイ画像です。ベットした金額に比例して、それぞれのプレイヤーの領域が多くなっており、勝率が高まっていることが分かります。 プレイヤーはタイマーが切れる前に、ETHもしくはUSDBをベットします。タイマーが切れると、ホイールが回転します。 ホイールが止まったプレイヤーは、そのラウンドでベットされた金額の全てを獲得することが可能です。 最低入金額として、0.01ETHに相当する額をベットする必要があります。 Poke the Bear:熊を起こさないようにつつくゲーム Poke the Bearは、敗者が1人だけになるように設定されたゲームであり、YOLOをローリスク・ローリターンにしたようなゲームです。 プレイヤーは特定の金額をベットし、眠っている熊がいる洞窟に入ります。プレイヤーは交互に熊をつつき、熊が目を覚まさないように祈ります。仮に熊が起きた場合には、他のプレイヤーで賞金プールを山分けします。 これも、YOLOと同じく、Gelatoによって透明性と公平性を証明できるようにしています。 実際のプレイ画面 Poke the Bearでは、幾つかのグループ(Cave)が設定されており、それぞれ参加費やプレイヤー数が異なっています。 上記添付画像の場合、「参加費0.03ETH、プレイヤー数6人、賞金プール0.18ETH」のCaveとなっています。 仮にこの枠に参加し勝者となった場合には、手数料(3%)を除いた賞金プールを5人で山分けすることになるため、一人当たり「0.03582ETH」を獲得することとなります。 Caveは数多く設定されており、中には参加費が25ETHにも及ぶ高額なものも設定されています。 熊をつつくプレイヤーはランダムに選ばれます。熊をつついてしまったプレイヤーは、唯一の敗者となり他のプレイヤーたちが報酬を得ます。(右のプレイヤー枠参照) 熊が起きるかどうかは完全にランダムなため、必ずしも最初の方につついたプレイヤーが有利になる訳ではありません。 独自トークン$YOLOをローンチ予定 YOLO Gamesでは、独自トークン$YOLOをローンチ予定です。 ローンチは、暫定的に2024年5月に予定されています。これは、$BLASTのトークンローンチと同じ時期となっています。 $YOLO獲得方法 現在の$YOLOの獲得方法として、2つあります。 1つ目は、シーズン1でポイントを獲得し、リーダーボードに乗ることです。 2つ目は、LooksRareで$LOOKSをステーキングすることでYOLO Shardsを獲得し、将来的に$YOLOと交換することです。 それぞれ詳しく解説してきます。 ゲームをプレイしてポイントを稼ぐ [caption id="attachment_110008" align="aligncenter" width="1439"] https://yologames.io/rewards/leaderboard[/caption] YOLO Gamesでゲームをプレイすることで、ポイントを稼ぐことが出来ます。シーズン終了後に$YOLOと$BLASTを手に入れることが出来ます。 ポイントは、ゲームの勝敗に関係なく獲得することが出来ます。また。3つのゲームを紹介してきましたが、それぞれのラウンドの最初に参加することで、追加で500ポイントを獲得することが出来ます。特に、YOLOのラウンドに最初に入金した場合には、3000ポイントを獲得することが出来ます。 また、全てのゲームには倍率が設定されており、賭けた金額によっては通常以上のポイントを獲得することが出来ます。 [caption id="attachment_110009" align="aligncenter" width="1439"] https://yologames.io/rewards[/caption] この他にも、デイリークエストやマイルストーン、紹介といった様々な方法が用意されており、自分に合ったポイント稼ぎを行うことが可能です。 LooksRareで$LOOKSをステーキングする [caption id="attachment_109996" align="aligncenter" width="1439"] https://looksrare.org/rewards[/caption] $LOOKをステーキングすることで、YOLO Shardsを獲得することが可能です。 YOLO Shardsを獲得する速さは、1$LOOKにつき、1分間で0.01YOLO Shardsとなっています。 また、長期間のステーキングに対してインセンティブが与えられており、$LOOKのステーキングが1ヶ月継続するごとに0.5倍の倍率が加算されるようになっています。 $YOLOには興味があるけれども、ギャンブルは苦手という方に向けた仕組みと言えるかもしれません。 YOLO Gamesまとめ ここまで、YOLO Gamesについて紹介してきました。 Blast BIG BANGコンペ優勝プロジェクトという知名度だけでなく、プレイヤーの需要に合わせた幅広いゲーム展開や、将来のトークンローンチへ向けたキャンペーンにも余念がありません。 5月のトークンローンチへ向けて注目が集まるBlastですが、その中でもYOLO Gamesは、GambleFi分野において一際注目を集めているプロジェクトと言えるでしょう。 YOLO Games各種information YOLO Games公式サイト:https://yologames.io/ja X:https://twitter.com/YOLO_Blast Discord:https://discord.com/invite/7SHJdtZz37 Sponsored Article by YOLO Games ※本記事はYOLO Gamesさまよりいただいた情報をもとに作成した有料記事となります。プロジェクト/サービスのご利用、お問い合わせは直接ご提供元にご連絡ください。

プロジェクト
2024/03/18pSTAKE Financeとは?Cosmosでのリキッドステーキングを実現
pSTAKEは、リキッドステーキングを提供するプロジェクトです。 Ethereumと比較してまだ発展途上のCosmosにおけるリキッドステーキングに焦点を当てています。 過去には1,000万ドル規模の資金調達にも成功しており、Binance Labsからの出資を受けたプロジェクトでもあります。 この記事では、そんなpSTAKEの概要・特徴などについて以下の点から解説しています。 この記事のまとめ ・pSTAKEはCosmosを中心にLSTを扱う ・CosmosやPersistence Oneを活かしてかんたんにステークが可能 ・ステークするとstkATOMを獲得可能 ・潜在的なエアドロの機会も pSTAKEとは? [caption id="attachment_109897" align="aligncenter" width="1024"] 引用元:pSTAKE[/caption] pSTAKE (pSTAKE Finance) は、Cosmosのエコシステムを中心に展開するリキッドステーキングのプロトコルです。 pSTAKEを通して、ATOMなどをステークすることによって、そのポジションを表すstkATOMを受け取れます。 おおむね、コンセプトはEthereumのエコシステムで見られるようなリキッドステーキングのプロトコルと変わりません。 pSTAKEは、ATOM周りのリキッドステーキングを扱うPersistence Labsが母体となって運用されています。 Persistence LabsはpSTAKEの他にも、DEXのDexterなどの開発を行っています。 また、上記の各プロトコルは、リキッドステーキングに焦点を当てたアプリチェーンであるIBC対応のPersistence One上に構築されています。 pSTAKEの3つの注目点 ・多額の資金調達 ・長期間の運営と1,900万ドルのロック ・マルチチェーンに対応 pSTAKEの注視したい点をチェックしていきましょう。 多額の資金調達 pSTAKEは、過去に大規模な資金調達に成功しています。 2021年11月に、1,000万ドルの資金調達に成功しており、一例として以下のような投資家が参加しました。 Three Arrows Capital Galaxy Digital Coinbase Ventures Kraken Ventures 上記に加えて、2022年にはBinance Labsからの出資も発表されていますが、額などは不明です。 額が大きいのはもちろん、著名な投資家が並んでいると言えるでしょう。 長期間の運営と1,900万ドルのロック pSTAKEは、長期間の運営と1,900万ドル前後の資産のロックが確認でき、アクティブな開発・ユーザーの利用が確認できます。 pSTAKEは、2021年にEthereum上でstkATOMをローンチし、2023年にPersistence One上にてネイティブにローンチしました。 すでに数年間運営されており、上記のpSTAKE自体のアップデートや2023年にDexterのローンチなどアクティブな開発が続いています。 まだローンチしていないものの、"Bamboo"というリキッドステーキングのためのレンディングプロトコルも開発中です。 DefiLlamaを参考にすると、現在のTVLは1,900万ドル前後、原資産の上昇なども要因にあるものの直近でTVLが伸びている傾向が見られます。 [caption id="attachment_109901" align="aligncenter" width="1024"] 引用元:DefiLlama[/caption] 競合はいくつか確認できるものの、上記のような安定した運営とアクティブな利用は、注目点にあげられるでしょう。 マルチチェーンに対応 pSTAKEは、マルチチェーンのリキッドステーキングに対応しています。 2024年3月時点で、pSTAKEがステーキングに対応しているチェーンの一例は、以下のとおりです。 Cosmos Osmosis Dydx STARS BNB Ethereum Persistence One Cosmos関連のエコシステムを中心に、Ethereumなどにも対応しています。 また、Cosmosというエコシステムの特性上、多種多様なチェーンが存在するため、今後よりさまざまなトークンをサポートする意向になっています。 pSTAKEの特徴・仕組み ・リキッドステーキングの概要 ・CosmosでのステークとPersistence ・BNB・ETHでのステーク リキッドステーキングの概要から、pSTAKEにおけるリキッドステーキングの特徴や仕様をチェックしていきましょう。 リキッドステーキングの概要 リキッドステーキングは、PoSに対してステークした資産の流動性を解放し、何らかの形で運用できるようにする行為です。 PoSに対してステークした資産は、通常ステークして利回りを得ている間ロックされ、運用はできません。 リキッドステーキングを通してステーキングすることによって、資産をロックしている証明と利回りが包括されたトークン (LST) を受け取れます。 LSTはDeFiなどで使用可能で、ステークした利回りを得ながら、さらなる運用が可能です。 pSTAKEにおいてはstkATOMなど、トークン名の最初に「stk」と記載されるLSTを受け取れます。 CosmosでのステークとPersistence pSTAKEを通したCosmosでのステークは、主に「Persistence One」を通して行われます。 かんたんにプロセスをまとめると、CosmosにあるATOMをIBCでPersistence Oneに送付し、Persistence One上のリキッドステーキングモジュールを通してstkATOMの発行を行います。Persistence Oneのモジュールからデリゲートが行われ、ステーキングが完了します。 [caption id="attachment_109906" align="aligncenter" width="877"] 引用元:pSTAKE[/caption] Persistence OneとCosmosに搭載された機能を活用し、円滑なステーキングが可能です。報酬の95%は利用者に5%がプロトコルに配布される仕様となっています。 stkATOMは、利回りに応じて、原資産と比較して徐々に価値が高くなる仕組みであるcTokenモデルを元に作成されています。 stkATOMと原資産であるATOMを比較すると、stkATOMのほうがステーキング報酬によって価値がより高くなります。 そのため、ステークを解除し原資産であるATOMを手に入れる際には、タイミングのレートに応じてATOMを交換します。 BNB・ETHでのステーク pSTAKEでは、BNB・ETHでのステークも可能です。 使用しているプラットフォームとプロセスは異なるものの、おおむね同じような仕組みでリキッドステーキングが可能です。 ウォレットなどはCosmosとは異なり、BNB・ETHで一般的に使用されているMetaMaskを使用することになります。 ETHについては他の通貨と異なり、ユーザーへの配分が90%、5%がバリデータ、5%がプロトコルに配布される仕様です。 また、2024年3月時点ではEthereumのアップグレードに対応するために、機能が停止しています。 $PSTAKEの概要 pSTAKEは「$PSTAKE」という独自のトークンを発行しています。 $PSTAKEは、ガバナンス・インセンティブに使用され、例えば前述した配分の割合などは$PSTAKEを通したガバナンスで変更される可能性があります。 $PSTAKEは、以下のような対象・割合で分配されます。 セールやローンチパッド:27% リワード:6% チーム:16% コミュニティや開発:26% XPRTのステーカー:3% 基金:20% ブートストラップ:2% $PSTAKEは、以下のような流れで徐々に供給されていきます。 [caption id="attachment_109909" align="aligncenter" width="868"] 引用元:pSTAKE[/caption] CoinMarketCapによると、2024年3月において0.12$で取引されており、時価総額は約5,200万ドルです。 pSTAKEでステークする方法 [caption id="attachment_109910" align="aligncenter" width="1024"] 引用元:pSTAKE[/caption] これから、pSTAKEでステークする方法について、以下のポイントから解説していきます。 ・ステークする方法 ・エアドロについて pSTAKEを使用する方法や、ステークにあたって気になるエアドロなどについてチェックしていきましょう。 ステークする方法 今回はATOMを活用してステーキングする方法を紹介します。pSTAKEでリキッドステーキングを行うには以下が必要です。 Keplrなどのウォレット ステークするATOM ガス代に用いるXPRT (Persistence Oneのトークン) 上記の準備が完了したら、コチラにアクセスして右上の「Connect Wallet」から、ウォレットを接続してください。 「Choose Asset」にてATOMを選択し、ステークする金額を選択し、「Liquid Stake」をクリックしてください。 右側にある「UnStake」から解除を行うことも可能です。 「Flash Unstake」の場合、即時に引き出し可能ですが、1%程度の手数料が発生します。「Regular Unstake」の場合仕様上、20日前後の日数がかかりますが、手数料は発生しません。 APYは通貨によって異なり、2024年3月時点では以下のとおりです。 ATOM:約14% Osmosis:約9% Dydx:約22% STARS:約13% エアドロップについて pSTAKEには、潜在的なエアドロップの可能性はありますが、ネイティブステークとは異なります。 ATOMの大きな特徴の1つは、ステーカーに対してエアドロップの機会があることです。 これまでさまざまな事例が見られ、今後も増加していく可能性が高いです。 しかし、pSTAKEのようなリキッドステーキングを通したステーキングは、ネイティブのステーキングとは異なります。 上記の点から、pSTAKEはブロックの情報を元に、LST保有者のアドレスをワンクリックで取得できる機能を提供しています。 If a team wants to airdrop their tokens to stkATOM, stkOSMO and/or any stkToken holders, you won't have to reach out to the @persistenceOne team anymore. All you need to do is choose the blockheight and fetch that data in one click. Airdrops --> fairdrops for liquid stakers👀🚀 https://t.co/y2maskvbwh — Mikhil Pandey (@PandeyMikhil) January 31, 2024 pSTAKEでは各エアドロップのプロジェクトサイドが、かんたんにLST保有者にエアドロップを実施できる環境は整っていると言えます。 今後上記のようなものを活用し、LST保有者を対象するエアドロップが登場する可能性はあります。 pSTAKEについてまとめ この記事では、pSTAKEについて解説しました。 Ethereumなどと比較して、Cosmosのリキッドステーキングはまだ発展途上であり、今後成長していくことも期待できます。 前述したようにエアドロップを獲得できる潜在的な機会も増えていく可能性はあるので、Cosmosのエコシステムの1つとして注視したいと言えるでしょう。 pSTAKE 公式リンク 公式サイト:https://pstake.finance/ X:https://twitter.com/pStakeFinance Doc:https://docs.pstake.finance/ Blog:https://blog.pstake.finance/ Sponsored Article by Persistence Labs ※本記事はPersistence Labsさまよりいただいた情報をもとに作成した有料記事となります。プロジェクト/サービスのご利用、お問い合わせは直接ご提供元にご連絡ください。




















 有料記事
有料記事


