最近書いた記事
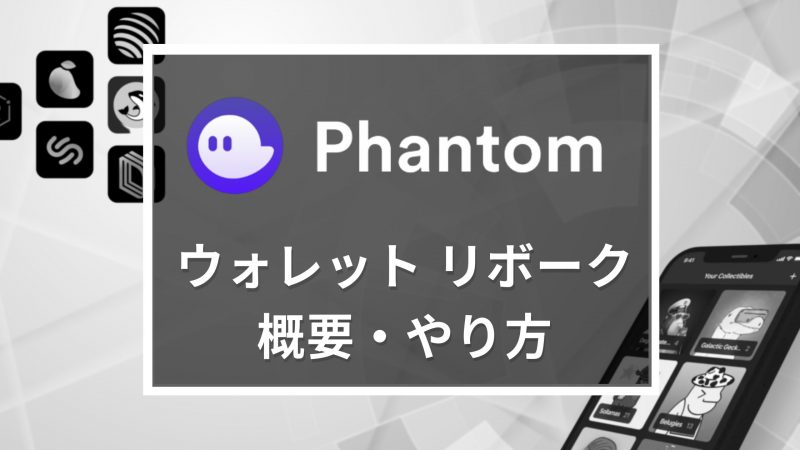
ウォレット
2023/01/03【安全対策】Phantom Wallet(ファントム ウォレット) のリボークの概要とやり方を解説
Phantom Wallet(ファントム ウォレット)では、接続を行ったサイトへの承認をリボーク(取り消す)できます。 サイトへの承認をリボークすることで、潜在的な詐欺やトラブルのリスクを回避することが可能です。 そのため、Phantomを利用している方は、利用方法や必要な背景をしっかりと押さえておきましょう。 本記事では、そんなPhantomのリボークの概要・やり方・必要な背景などについて解説しています。 Phantomとリボーク(Revoke)の概要 Phantomは、Solanaのトークンを管理できるウォレットです。 Phantomで、何らかのサイトに接続すると、承認の画面が出てくることに気付くはずです。 上記の過程を通して、さまざまな承認をサイトに対して行うことになります。 例えば、Raydiumに接続してみると、以下のような項目に対して、承認を行うことになります。 ウォレットの残高とアクティビティの表示 トランザクションの承認に対するリクエスト 上記のような承認は、ウォレットを用いたさまざまなアクションに必要になり、一般的な手順です。 その一方で、接続先が悪意を持ったサイト・アプリであった場合は、ウォレットがリスクに晒される可能性があると言えます。 Phantomでは上記のようなリスクに備えて、サイト・アプリを接続後に削除(リボーク/Revoke)することが可能であり、ウォレットを安全に保つ上で重要なアクションになっています。 Phantomでリボークを行う方法 前述したような背景から、怪しいサイトに接続してしまった場合などは、積極的・迅速にリボークする必要があります。 Phantomで、接続の承認を与えたサイト(Trusted Apps)をリボークする手順は以下のとおりです。 左上のアイコンへ 「Trusted Apps(信頼済みアプリ)」へ 任意のサイト、アプリの項目から「Revoke(取り消し)」へ Solanaエコシステムを頻繁に利用しており、Phantomの利用頻度が高い方は定期的にリボークしていきましょう。 また、仮にリボークを行ったとしても、再度利用したいときに接続しなおすことで、同じ状態に戻すこともできます。 Phantomでリボークが必要な理由 これから、Phantomでリボークが必要な理由とその意味についてもう少し詳しく解説していきます。 Phantomとリボークについて理解を深めていきましょう。 リスク管理のために必要 Phantomの公式FAQでは、信頼し接続したサイト・アプリのリボークについて、以下のような旨の文言が確認できます。 「秘密鍵、リカバリーフレーズを渡していないかぎり、アクセス許可が取り消された後は安全」 悪意や脆弱性のあるサイト・アプリに接続した場合、リボークをすぐに行うことで、リボーク後は安全であるとしています。(左記はあくまでPhantomの見解です) 上記のような背景を考慮すると、何らかのトラブルに遭遇した場合はすぐにリボークを行うことで、何も行わずそのままの状態でいるよりも被害を食い止められる可能性があります。 ハッキング・トラブル・詐欺といった現象が起こりがちな昨今の現状を加味すると、どのようなサービス・プロダクトであっても普段からこまめにリボークしておくのが最も安全性が高い方法と言えるかもしれません。 実際にリボークが推奨された事例 過去に、Solanaエコシステムで大規模なハッキング(Solana系のウォレットから資金が流出)が発生したことがありました。 この際に、複数の著名なSolana系のサービス・機関から、信頼されたアプリのリボークを推奨する発信が確認できました。 https://twitter.com/MagicEden/status/1554620084831674370?s=20&t=kz_oims8zBmYjVRLUUaFXw 最終的に、リボークは直接的には関係がない(秘密鍵情報が流出した)ものであると判明したものの、リボークが推奨された状況を考慮すると、何かあったときにまず取り組みたい対策であると言えるでしょう。 ガス代は掛かりませんし、リボーク後も再度接続が可能であることを考慮すると、コストパフォーマンスの高い対策です。 リボークが全てを解決する訳ではない 信頼されたサイト・アプリに対するリボークは、気軽に行えて効果の高いセキュリティ対策ですが、全てを解決する訳ではありません。 例えば、既に実行されたものを取り消す、削除するといったことはできません。 そのため「トークンが何らかの形で盗まれてしまった」といった場合に、リボークを用いて今後の被害を食い止められる可能性はありますが、一度盗まれてしまったトークンを取り返すことは困難です。 また、秘密鍵、シードフレーズ・リカバリーフレーズを流出するといったトラブルの場合は、サイトに対するリボークを行ったとしても解決しません。 上記のようなケースでは、新たにウォレットを作成し、新たなウォレットにトークンを転送するといった対応が必要になります。 Phantomでリボークを行う基準・目安 これまでPhantomのリボークについて解説しましたが、リボークを行う基準・目安について解説していきます。 以下のようなケースは、リボークを行うのがおすすめです。 URLがおかしいサイト コミュニティが存在しない、アクティブではないプロダクト 知名度が低く、危険性・詐欺などの可能性が判定できないようなプロダクト 直近でハッキングなどのトラブルがあったプロダクト 長期間利用していないプロダクト NFTのミントやドロップ目的など使用頻度が高くないサイト そもそも、信頼性の低いサイトやアプリには接続しない方がベターです。 まとめ この記事では、Phantomのリボークについて解説しました。 Phantomのリボークは、ガス代なども掛からず、気軽に行うことができます。 まだ、利用したことがないという方は、積極的にPhantomのリボークを行っていきましょう。 【安全対策】メタマスク Revoke(リボーク)の概要と方法

プロジェクト
2022/11/26DeFi特化のチェーン「Sei Network」とは?概要や特徴、今後を解説
Seiは、DeFiに特化したL1チェーンです。 高い処理能力とファイナリティまでの速さ、チェーン側でのCLOBの実装、汎用チェーンと固有チェーンのメリットを上手く取り込んでいるなどの特徴が見られます。 まだテストネット段階ではあるものの、7億円規模の資金調達に成功していたり、わずか数日間でテストネットにおけるNFTが10万件ミントされるなど、注目度が非常に高いプロジェクトです。 この記事では、そんなSeiについて以下の観点から解説していきます。 この記事のまとめ ・DeFiに特化したL1チェーン ・フロントランニングの防止を実現 ・高速なファイナリティと高いスループット ・Cosmosエコシステムとの相性の良さ ・ローンチ時期は不明なもののインセンティブテストネットが実施中 Seiとは?=DeFi特化のL1チェーン Seiは、主にDeFiに特化したL1チェーンです。 現在、DeFiではさまざまなプロダクトが登場しており、展開されているL1チェーンも多岐にわたります。 そんな中で、Seiは「CEXと同等程度」の体験を、ブロックチェーン上で実現する可能性があります。 そんなDeFiに焦点を当てたSeiの概要、チーム、資金調達といった基礎的な情報について解説していきます。 ・これまでのDeFiの課題 ・DeFi特化のSeiが解決する問題 ・Seiのチームと資金調達 これまでのDeFiの課題 DeFiは、中長期的な観点から見ると、安定的な成長を続けています。 過去数年間のTVLからも、その傾向が見て取れると言えるでしょう。 (引用元:DefiLlama) その一方で、DeFiにはさまざまな面での課題が存在します。 例えば、取引が処理されるまでの時間、安定性や信頼性、汎用性の高いL1チェーンでの開発におけるカスタマイズ性の少なさなどです。 そのような背景もあり、現在多数のプロダクトやプラットフォームがDeFiにおける諸問題を解決しようと取り組んでおり、より実用性の高いプロダクト・プラットフォームが登場しつつあります。 DeFi特化のSeiが解決する問題 Seiは、DeFiに存在する諸問題の中でも、特に以下のような課題に取り組んでいます。 高速なファイナリティの確保 高いスループットの確保 フロントランニングの防止 上記のような問題を解決することで、例えばSeiではCLOB(一般的な取引所で採用されているような注文システム)などの対応を目指しています。 まだ、試験的な運用(テストネット)に留まっていますが、今後Seiで実用性・利便性の高いDeFi周りのプロダクトが構築されていく可能性があるでしょう。 Seiのチームと資金調達 https://twitter.com/SeiNetwork/status/1564972903916904450?s=20&t=VIMcaiIdzVKieapULW_jWQ Seiは、2022年8月に500万ドル(約7億円)の資金調達に成功したことを発表しました。 資金調達に伴って以下のような企業が見られ、著名なVCが参画していることも分かるでしょう。 Multicoin Capital(主導) coinbase VENTURES Delpi Digital Hudson River GSR また、SeiはAirbnbやゴールドマン・サックスなどで経験・経歴を持つメンバーによって開発が進められています。 経験豊富なチームや、著名なVCからのバックアップなどが揃っていると言えるでしょう。 Seiの5つの特徴 これから、Seiの特徴について以下の観点から5つピックアップしていきます。 ・トランザクションの処理性能とファイナリティの速さ ・フロントランニングの防止 ・取引に特化したさまざまな技術 ・汎用チェーンと固有チェーンの中間に位置する ・Cosmos SDKとIBC Seiが持つ特別なポイントやその仕組みなどについて解説していきます。 トランザクションの処理性能とファイナリティの速さ SeiはDeFiに特化していることから、チェーンにおける処理速度やファイナリティまでの速さは最も重要なポイントです。 Seiの公式サイトで記載されている処理速度は以下のとおりです。 トランザクションのスループットについては22,00OPS、ファイナリティまでの速さについては600msでの運用が可能であるとの記載が確認できます。 (OPS = TPSに近しい指標、ファイナリティ = トランザクションが確定的になるタイミング) DeFiの利用においてはどれだけトランザクションを処理できるのか?と同時に、トランザクションが確定するファイナリティも重要です。 もしも、上記のような数値が安定的に出せるのなら、大きな期待ができるでしょう。 試験的な段階の数値にはなりますが、同等・近しいパフォーマンスが出ていることが確認できます。 https://twitter.com/jayendra_jog/status/1560305088362528768 ただし、Seiに関する数値については試験的な段階であり、ローンチされ本格的に普及した場合のパフォーマンスについてはまだまだ未確定であることに注意が必要です。 フロントランニングの防止 DeFiにおいては、フロントランニング・MEVが重要な課題として挙げられることが少なくありません。 ブロックチェーンでは、トランザクションを処理する前段階で、保留されるタイミングがあります。 ブロックチェーンにおけるフロントランニングでは、トランザクションが保留されているタイミングで、ターゲットよりも高速にトランザクションを処理し、利用者に不利なレートで取引をさせる行為などが挙げられます。 Seiでは、後述する技術・仕組みによってトランザクションの処理を高速化し、高頻度なバッチオークションを行うことでフロントランニングを解決します。 (バッチオークション = 1つずつトランザクションを処理せず、一定時間内において同じタイミングで処理を行う) MEV (Miner Extractable Value) とは ブロック内のトランザクションを任意の順番で配置し、バンドル化(= 別のプロダクトやサービスと合わせて提供)することで抽出可能な金銭的価値。MEVには、MEV Searcher(サーチャー)と呼ばれるMEVを発⾒を狙うグループと、Proposer(プロポーザー)と呼ばれる、ブロックをオンチェーンに伝播するグループが存在する。 MEVのランドスケープには、トランザクションを組み⽴てて利益を出すサイドと、ブロックの⽣成を実際に担うサイドの、⼆種類の参加者がいる。 取引に特化したさまざまな技術 Seiでは、さまざまなアプローチで、トランザクションの処理を高速化・効率化させています。 代表的なものに、トランザクションの並列処理と市場ごとの区分けが挙げられるでしょう。 通常、ブロックチェーンでは、トランザクションを1つずつシーケンシャルに処理していきます。(順序的に処理していく) しかし、上記のような処理方法では、高い処理能力(高いスループットや低いレイテンシ)を実現するには限界があります。 https://twitter.com/goated2EZ/status/1595296006530564096?s=20&t=BI1p7d3FP74UEdmko0BmJg 一方で、Seiではトランザクションを並列処理しています。(各トランザクションを同時に処理) 並列処理は他のブロックチェーンでも見られますが、Seiでは並列処理に一定の条件を設定し、並列処理の懸念を払拭します。 というのも、並列処理には不確定・非決定性的な事態が発生する可能性があります。(ノード間で矛盾が発生する可能性など) 不確定・非決定性は、DeFiに焦点を当てるSeiにとっては致命的な弱みになってしまいます。(価格に矛盾などが出ると利用者の損失につながる) そのため、Seiでは他の市場に依存しない・関係しないものに限定して、並列処理が可能です。 (並列処理の流れと時間軸のイメージ。上部が並列処理なし・下部が並列処理あり Seiのwhite paperより) 具体的には、同じ市場(同じものに対する注文など)は並列処理が不可能で、異なる市場での取引に関しては並列処理が可能です 一方で、同じ市場を取引する注文に関しては、一般的なブロックチェーン同様に1つずつ順序的に処理していきます。 また、効率的なブロック伝播と楽観的な処理を行うコンセンサス関連の技術であるツインターボコンセンサス(Twin-Turbo Consensus)も、処理速度の高速化に貢献している要素の1つです。 https://twitter.com/jayendra_jog/status/1573058056292016128 その他にも、オンチェーンでは処理性能などから実装が難しいCEXに見られるようなCLOBの実装などに対応しています。 上記はあくまで一例で、Seiはブロックチェーンに予め、DeFi(特にDEX)と相性の良い取引周りの仕組み・技術を組み込んでいます。 また、Seiではチェーンレベルで注文のマッチングエンジンを実装していますが、少なくとも初期段階では取引手数料を徴収しない方針です。(ここで言う取引手数料は、ガス代ではありません) しかし、将来的にガバナンスによって変更される可能性もあります。(将来的な変更が可能な旨がWhite paperに記載) あくまで可能性の話ですが、手数料が徴収される方針になった場合、徴収された取引手数料を元にしたユニークなTokenomicsを構築できるかもしれません。 汎用チェーンと固有チェーンの中間に位置する Seiは、汎用チェーンと固有チェーンの中間に位置するブロックチェーンです。 具体的には、汎用チェーンはイーサリアムに代表されるようなどんな用途にも利用可能なブロックチェーン、固有チェーンはdYdXのような固有のアプリに用いられているブロックチェーンを指します。 両者は、以下のような特徴をもっていますが、Seiは汎用チェーン・固有チェーンのメリットを備えています。 汎用チェーン 固有チェーン コンポーザビリティ(構成可能性) 高い 低い アプリサイドでのカスタマイズ性 低い 高い 他チェーンとの相互運用性 場合によるが低い 高い (IBCに対応するチェーンなど) 手数料 主要なイーサリアムでは高い 低いことが多い SeiはL1ブロックチェーンとして、複数のプロダクトをチェーン上に展開可能であり、汎用チェーンと似通った側面を持っています。 その一方で、展開されるプロダクトはパーミッションであり、展開するプロダクトはガバナンスによってホワイトリストに登録される必要があります。 つまり、固有チェーンほどクローズなブロックチェーンではないものの、汎用チェーンほどオープンなブロックチェーンでもありません。 また、Seiでは、ノードのハードに対して高い負荷が掛かる可能性が指摘されています。 その代償として、高い処理能力を持ちながら、Seiは汎用チェーン・固有チェーンの強みをバランスよく持っています。 Cosmos SDKとIBC Seiは、Cosmos SDK・Tendermintを用いて構築されています。 前述したような技術・特徴の基礎的な部分は、Cosmos SDK・Tendermintによってもたらされています。 また、SeiはIBCにも対応しているため、相互運用性が高く、Cosmos周りとのプロダクトと相性の良いです。 こういった他のチェーンとの相性の良さも、Seiの強みとなっていく可能性があるでしょう。 仮想通貨Cosmos/$ATOMとは?特徴や仕組み、注意点を解説 Seiに構築されたアプリの例 Seiはテスト段階ではあるものの、すでにSeiで開発が進んでいるプロダクトが多数見られます。 いくつかピックアップすると、以下のようなものが挙げられます。 Vortex Protocol (デリバティブ対応DEX) Nitro SVM (SolanaとCosmosのゲートウェイとなるSolanaのL2) Axelar Network (複数のチェーンに対応したブリッジ) UXD (Solana系のステーブルコインプロトコル) Synthr (複数のチェーンに対応予定の合成資産プロトコル) DeFi周りのプロダクトも見られるものの、一部ではNitro SVMのようなインフラ系のものも見られます。 Sei自体はまだまだ試験的な段階での運用にとどまっているため、今後も展開されるプロダクトは注視していきたいと言えるでしょう。 その他のプロダクトについてはコチラからチェック可能です。 Seiのこれまでと今後 これから、Seiのテストネットやローンチ時期などについて、解説していきます。 Seiのこれからについてチェックしていきましょう。 テストネットのこれまでと現在 11月時点で、Seiはテストネットを運用している段階です。 Seiは、テストネットの段階ごとにミッションを設定しており、クリアした方に向けてインセンティブを配布する予定になっています。 現在、ACT4まで実施されていて、各ACTごとにミッションの概要は以下のとおりです。 ACTの段階 ミッション概要 実施時期 ACT1 バリデーターの設定や実行、運用 2022年7月~8月 ACT2 ウォレットの接続やVortexなどの利用 2022年8月~10月 ACT3 Seiに対するハッキング、Vortexに対するハッキングなど 2022年8月~未定 ACT4 Vortexの利用や紹介など 2022年10月~未定 各ミッションの詳細はコチラをご確認ください ただし、開催期間などについては記載されているものと実際の運用に一部乖離が見られます。 実際に参加を検討している方は、Discordなどと併用してリサーチを行ったほうが良いでしょう。 ローンチ時期はまだ不明 https://twitter.com/SeiNetwork/status/1586102864295829504?s=20&t=RN1H_4cUZHtz3SKb2yWviA Seiのローンチ時期は、現時点において不透明です。 まだ具体的なトークンのアロケーションなども発表されておらず、上場に関する情報などもチェックできません。 ただし、着実に開発が進んでいる様子は確認でき、すでにテストネットを数ヶ月運用していることなどからそれほど長期間のスパンではない可能性もあります。 特定のトークンの保有者に対するエアドロを示唆するツイートも確認できるため、Seiに注目しているという方は、ウォッチしていく必要があるでしょう。 https://twitter.com/SeiNetwork/status/1581046611647508481?s=20&t=KZv0bm-hvwajgjrMVbgkqw まとめ この記事では、DeFiに特化したL1チェーンであるSeiについて解説しました。 FTXの一件以降、CEXへのリスク意識が高まり、DEXの利用が広まっているという流れも確認できます。 そんな中で、CEXと近いクオリティでさまざまなプロダクトを構築できるSeiは、今後注目したいプロジェクトであると言えるでしょう。 DEX(分散型取引所)の取引高が急増中。FTX騒動の影響か

プロジェクト
2022/11/01仮想通貨Cosmos/$ATOMとは?特徴や仕組み、注意点を解説
Cosmosとは、ブロックチェーンの開発を簡易化し、ブロックチェーン間の相互運用性を実現するプロジェクトです。 現在、多数のプロジェクトがCosmosが提供するソリューションを活用して構築されています。 今後、ブロックチェーンの開発が活発になるにつれて、Cosmosのような相互運用性を実現するプロジェクトは重要になると考えられるでしょう。 本記事では、そんなCosmosについて以下のようなポイントから解説しています。 この記事のまとめ ・Cosmosではブロックチェーンを簡単に開発可能 ・各チェーンはIBCによって接続可能 ・ペグゾーンによって規格外のチェーンとの接続も可能 ・Cosmos Hubはハブの1つ ・IBCを有効にしているチェーンは40以上 Cosmosとは?=チェーンの相互運用性を提供するプロジェクト Cosmosとは、ブロックチェーン間の相互運用性(インターオペラビリティ)を提供するプロジェクトの総称です。 現在、代表的なものではイーサリアムやビットコインなど多数のブロックチェーンが展開されていますが、その多くは相互運用性を持ちません。 各ブロックチェーンが、異なるルール・規格で運用されており、トークンの送付が各ブロックチェーン間で不可能だったり、さまざまなデータをやり取りできないといった課題が見られます。 また、イーサリアムなど代表的なブロックチェーンの裏側の仕組みに依存することで、各アプリケーションの拡張性・柔軟性が失われるといった問題も見られます。 Cosmosは、上記のような課題を解決するために、各ブロックチェーン間の相互運用性を確保や、ブロックチェーン開発を容易するためのソリューションを提供するプロジェクトです。 Cosmosの3つの特徴 ①柔軟性、拡張性の高いチェーンの開発 ②開発されたチェーン間の接続 ③規格外のチェーン同士の接続 これから、Cosmosの簡単な特徴について、上記3つの観点から解説していきます。 Cosmosの魅力・特別なポイントをチェックしていきましょう。 ①柔軟性・拡張性の高いチェーンの開発 Cosmosは、ブロックチェーンの開発が行えるソリューションを提供しています。(Cosmos SDKなど) Cosmosのソリューションを利用することでブロックチェーン開発を容易に行え、アプリケーションを独自のブロックチェーンに構築することが可能となります。 各アプリケーションが独自のブロックチェーンを持つことで、用途にあったチェーンを開発し柔軟性を持たせることが可能です。 イーサリアムに構築されたアプリケーションは、ブロックチェーンの開発を行わない代わりに、多くの部分をイーサリアムに依存するため、設定されているルール内でしかアプリケーションの開発・運用ができません。 一方で、Cosmosのソリューションを活用すれば、各アプリケーションにとって最も望ましいブロックチェーンを開発し、運用が可能となります。 ②開発されたチェーン間の接続 Cosmosのソリューションを利用して開発されたブロックチェーンは、IBCと呼ばれる規格を活用して容易に接続できます。 そのため、Cosmosのソリューションで開発された各ブロックチェーンは、相互運用性を持ちます。 具体的には、各ブロックチェーン同士のトークンの転送等が可能です。 また、IBCの汎用性はCosmos関連のソリューションに留まりません。 IBCを利用する規格にさえ沿っていれば、どんなブロックチェーンでも接続が可能なのも注目すべき特徴となっています。 ③規格外のチェーン同士の接続 Cosmos関連のブロックチェーンは、前述したような規格に沿っていないブロックチェーンであっても、間接的に接続できます。 前述した規格にはいくつか条件があり、その中にファイナリティの種類があります。 例えば、ビットコインのようなPoWを採用するチェーンではファイナリティに至る過程が規格に沿っていないため、IBCを用いて直接の接続はできません。 Cosmosでは、IBCと互換性を持つペグゾーン(Peg-Zone)と呼ばれる専用のブロックチェーンを中間に置くことで、間接的な接続を実現しています。 そのため、規格に沿わないチェーンであっても、ペグゾーンの利用により接続が可能です。 Cosmosの特徴を実現する仕組みを解説 前述したようなCosmosの特徴を実現する仕組みについて、以下のポイントから解説していきます。 ・TendermintとCosmos SDK ・接続を可能にするIBC ・規格外のチェーンを対応するペグゾーン ・接続の中心となるCosmos Hub、ATOM Cosmosの仕組みとその詳細についてチェックしていきましょう。 Tendermint BFTとCosmos SDK Cosmosのブロックチェーン開発者向けに、Tendermint BFTを利用したCosmos SDKが提供されています。 Tendermint BFTとは、ブロックチェーンの裏側の仕組みをまとめたソリューションです。 ブロックチェーンには、主に以下のような層が存在しており、各層が重要な役割を担っています。 アプリケーション コンセンサス ネットワーク これまでのブロックチェーン開発では、上記全ての層を一から開発する必要がありました。 Tendermint BFTは上記の課題を解決するために、コンセンサス部分とネットワーク部分をまとめて処理するソリューションになっています。 Tendermint BFTを活用することで、ブロックチェーンで取引を処理する際に必要となる仕組みを簡単に構築できます。 そして、Tendermint BFTを利用したブロックチェーンを開発するためのフレームワークがCosmos SDKです。 Cosmos SDKには、ブロックチェーンの開発に必要なツールが備わっており、前述した各ブロックチェーンと相互運用性を持つブロックチェーンを容易に開発できます。 接続を可能にするIBC Tendermint BFTとCosmos SDKを用いて開発された各ブロックチェーンは、IBCによって接続が可能になり、相互運用性を持たせることが可能です。 IBCとは、ブロックチェーン同士が通信を行うための規格のことです。 IBCに沿ったブロックチェーン同士は直接接続し合うことが可能で、トークンやデータのやり取りが可能になります。 具体的には、以下のような流れでトークンのやり取りを行います。 送付元のチェーンにトークンをロック (ロックのことを、bondedとも呼称) 送付元チェーンにロックした旨を送付先チェーンに伝達 送付元にてロックしたトークンを、送付先にて発行 ただし、送付先で発行されるトークンは、ロックされたことを証明するトークンのため、厳密には送付元のトークンとは異なるので注意が必要です。 上記の仕組みでは、トークンといった用途に限らず、さまざまなデータが扱えます。 例えば、Cosmos Hub(後述)では、IBCを通して他のチェーンへのセキュリティの提供・共有が可能となります。 IBCと似たようなソリューションに、ブリッジが挙げられます。 ブリッジは異なるブロックチェーン間で、トークンを送付する際に多用されていますが、IBCとブリッジは同じものではありません。 ブリッジはトークンの送付に伴って、送付元・先になるブロックチェーンの間に何らかのサードパーティを利用するため、サードパーティにおいて欠陥が見られる場合、リスクを伴います。 一方で、IBCは送付元・先になる2つのブロックチェーンを直接接続しトークンをやり取りするため、2つのブロックチェーンへの信頼性が確立されていれば、安心してトークンを扱うことが可能です。 規格外のチェーンに対応するペグゾーン IBCを活用できないブロックチェーンとの接続には、ペグゾーンを利用します。 ペグゾーンは、IBCと互換性を持つブロックチェーンであり、IBCと互換性を持たないブロックチェーンとIBCと互換性を持つブロックチェーンの中間に位置します。 前述したとおり、IBCの規格にはさまざまな条件が設定されており、その1つがファイナリティです。 PoWなどを採用するブロックチェーンでは、確率的なファイナリティしか得られません。 IBCを利用するには、決定論・決定的なファイナリティが必要であり(接続後に各チェーン間で矛盾を起こさないため)、この点が互換性を持たせる上での障害となっています。 そのため、ペグゾーンはファイナリティを確立させる場所として利用され、ペグゾーンを中間に位置させることで、互換性を持たせ各ブロックチェーンを接続できる状態にします。 ただし、ペグゾーンは各ブロックチェーンごとに開発を行う必要があり、各ブロックチェーンの特性によって技術的な難易度も異なります。 (イーサリアム用、ビットコイン用といった各ブロックチェーンに合わせた独自のペグゾーンが必要になる) 接続の中心になるCosmos Hub・ATOM Cosmos HubとATOMは、各ブロックチェーンの中間に位置するハブとして機能するブロックチェーンとそのトークンです。 Cosmosには、「ハブ」と「ゾーン」の概念があります。 ゾーンは、Cosmos関連のソリューションを利用して構築されたブロックチェーン、ハブはゾーンを接続させるために、以下のような形で中間に位置するブロックチェーンです。 「IBCを利用して、ブロックチェーンを直接接続可能なのに、なぜハブを通す必要があるのか?」と気になった方もいるかもしれません。 もちろん、IBCを通して各ブロックチェーン同士を直接接続することは可能です。 しかし、直接接続してしまうと、ブロックチェーンが増えるに従って、接続する数も大量に増えていきます。(1つ1つブロックチェーンに対して、接続が必要なため) Cosmosの公式サイトでは、100のブロックチェーンがある場合、必要な接続数は4,950になると記載されています。 そのため、Cosmos Hubのような各ブロックチェーンとIBCによる接続において中間となるハブを利用し、効率的な接続を行えるようにします。 各ゾーンはハブに接続することによって、ハブと接続しているその他全てのゾーンとの通信が可能です。 また、Cosmos HubはATOMというネイティブトークンを持ち、ATOMはCosmos HubにおけるDPoSへのステーキングなどに利用されます。 Cosmos Hubは、Cosmos ネットワークにおいてはじめてスタートしたハブの1つというだけで、ハブ自体は複数展開することも可能です。 また、IBC接続によって直接ブロックチェーン間を接続できるため、仮にハブに何らかの問題があったとしても、前述の通り各ブロックチェーン自体が直接接続しあうことができます。 Cosmosを活用したチェーン・プロジェクト 現在、多数のブロックチェーン・プロジェクトがCosmosを活用して、開発されています。 トークンを実装しているものから、一例として以下のようなものが挙げられます。 BNB (Binance Chain) OKB CRO OSMO また、IBCを有効にしているブロックチェーンは40個以上に渡り、1兆円以上の時価総額を持っています。 [caption id="attachment_82441" align="aligncenter" width="689"] Cosmosエコシステムマップ | 画像引用元:mapzones.com[/caption] また、Cosmosを活用したアプリのジャンルは多岐にわたっており、2022年10月時点で、260以上のアプリが展開されているようです。 Cosmosの注意点・リスク Cosmosの注意点・リスクについて以下のような観点から解説していきます。 ・エコシステムとATOM ・競合の存在 ・その他の潜在的なリスク Cosmos関連のエコシステムの利用などに伴う注意点をチェックしていきましょう。 エコシステムとATOM Cosmosでは、多数のブロックチェーン(ハブやゾーン)を構築することができます。 最も代表的なハブがCosmos Hubであり、Cosmos HubのネイティブトークンはATOMです。 しかし、前述の通り、Cosmosを利用したブロックチェーンの開発は各々が独立しており、IBCにて接続するか否かも選択できます。 そのため、イーサリアムなどと比較すると、Cosmos周りの開発や運用が必ずしも、Cosmos HubやATOMの直接的な需要に繋がる訳では無い可能性があります。 競合の存在 ブロックチェーン間に相互運用性を持たせようという試みを行っているのは、Cosmosのみではありません。 複数のブロックチェーンを開発できるといったプロジェクトには、PolkadotやAvalancheといったプロジェクトが挙げられます。 しかし、各プロジェクトごとに、相互運用性へのアプローチ方法は大きく異なっており、一概に同様のプロジェクトと評価することはできません。 ただ、開発者やユーザーの数は限りがあるため、各プロジェクトとの競争が行われていく可能性は高いです。 そのため、各プロジェクトの動向などについてもチェックしていく必要があるでしょう。 その他、潜在的なリスク Cosmos関連のアプリ、サービス、チェーンなどの利用には、潜在的に多数のリスクが存在しています。 各アプリにバグや欠陥が存在している可能性や、Cosmosエコシステムに触れるにあたって利用する何らかのソリューションでトラブルが発生する可能性も否定できません。 他の仮想通貨の購入や利用と同様に、何らかのトラブル・攻撃などによって損失などが発生する可能性は常に押さえておきましょう。 Cosmosについてまとめ この記事では、Cosmosについて解説しました。 Cosmosは、ブロックチェーン間の接続や、アプリケーション独自のブロックチェーン開発など、多数の特徴を持つプロジェクトです。 今後、ブロックチェーンの開発・運用などがさまざまな分野において加速していく中で、各ブロックチェーンの接続や開発にフォーカスしているCosmosには注目していきたいと言えるでしょう。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 USDCがCosmos、Polkadotなど複数チェーンで対応へ | 2022年末から利用可能予定 ー Cosmos 公式リンク ー Webサイト:https://cosmos.network/ ツイッター:https://twitter.com/cosmos ディスコード:https://discord.com/invite/cosmosnetwork ブログ:https://blog.cosmos.network/

プロジェクト
2022/10/22流動性ステーキング「Lido」とは?概要や特徴、使い方を徹底解説
Lidoは、ステーキングを簡単・便利に利用できるようにするソリューションです。 Lidoを利用することで、ステーキングした資金をDeFiなどで運用することが可能になり、資金がステーキングによって固定化されるのを防ぐことができます。 これまで、Lidoにステーキングされた資産は8,000億円、支払われた報酬は200億円を超えています。 この記事では、そんなLidoの基本的な概要から特徴、具体的な使い方(画像付き)などについて、解説しています。 この記事のまとめ ・Lidoを利用することでPoSなどへのステーキングが可能 ・ステーキングすることでstETHを獲得可能 ・stETHはDeFiなどで運用可能 ・SolanaやPolkadotなどにも対応 Lidoとは?柔軟なステーキングが可能に Lidoは、簡単・柔軟なステーキングを可能にするステーキングソリューションの1つです。 利用者は、Lidoを通して各ブロックチェーンに対してステーキングを行うことで、さまざまなメリットを享受可能です。 最も代表的なものに、ステーキングしたETHなどを間接的に、各DeFiプロダクトなどで利用することが可能になる点が挙げられます。 そんなLidoの概要・基本的な機能について、以下のポイントから解説していきます。 ステーキングの概要と課題 LidoのstETHを用いて運用が可能 stETH、wstETHの違いについて Lidoのコアとなるステーキングの概要から、Lidoが解決する課題についてチェックしていきましょう。 PoSに対するステーキングの概要と課題 イーサリアムを含めた複数の仮想通貨ではPoSを採用しており、PoSに参加するために必要となるなのがステーキングです。 PoSとは、ブロックチェーンのブロックを追加する際の合意方法の一種。 PoSに参加するには、各ブロックチェーンで中心となっている仮想通貨(ETH・SOLなど)をロックする必要があり、そのことをステーキングと言います。 ステーキングを行った方は、各ブロックチェーンで設定されている一定の金額を報酬として得ることが可能です。 PoSにはPoWと比較してさまざまなメリットがありますが、デメリットもいくつか見られ、代表的なものに資金の固定化が挙げられます。 ステーキングをしている間は、ロックしている仮想通貨を動かすことができず、DeFiなどでの運用ができません。 顕著な例では、イーサリアムが挙げられます。 イーサリアム最大のアップグレード「The Merge(マージ)」がまもなく実施予定です。 時価総額で30兆円を誇るイーサリアムの一大イベントであるマージについて、スレッド形式でかんたんに解説していきます。https://t.co/7rGpaWG0ju — CRYPTO TIMES@暗号資産・ブロックチェーンメディア (@CryptoTimes_mag) September 12, 2022 イーサリアムでは、PoWからPoSへの移行に伴うアップデートが実施されており、既に多数のETHが預けられています。 しかし、"Shanghai"というアップデートが実施されるまでは、預けたETHを取り出せません。 つまり、現在、ステーキングされたETHは、何も操作できない状態なのです。 イーサリアムのアップデートが実施されることで、上記の仕様自体は無くなります。 しかし、仮にアップデートを実施してステーキングから資金を取り出せるようになったとしても、PoSへのステーキングによって資金が固定化される問題は依然として解決されません。 また、これはイーサリアムに限らず、PoSを採用している他のブロックチェーンにも見られる問題でもあります。 LidoのstETHを利用してデメリットを解消 Lidoでは、stETHを用いて前述の課題を解決しています。 Lidoの利用者は、Lidoを通してイーサリアムに対してステーキングすることで、ETHと1:1で価格が連動しているstETHを獲得可能です。(市場では若干の乖離が見られる) stETHはステーキングによる報酬を集計して、自動的にstETHの残高が変わる仕様が備わっています。 そのため、ステーキングしたETHに対する報酬の獲得は、自動的にstETHの残高が増えることで反映される仕組みになっています。 また、stETHは各DeFiプロダクトで利用可能となっており、ステーキングしたETHを間接的に運用可能です。 もちろん、stETHはステーキングしたETHを解除することで、ETHとstETHの1:1の変換も可能です。 (現状は前述したアップデートの問題で変換できませんが、アップデートによってステーキングから資金を取り出せるようになると、変換可能になります) stETHとwstETHの違い Lidoのイーサリアム関連のトークンには、stETHの他に「wstETH」というトークンも挙げられます。 stETH・wstETHともに「ステーキングしたETHの報酬を反映させる」という点は変わりません。 しかし、stETH・wstETHでは「報酬を反映させる仕組み」が異なります。 前述の通りstETHは「利用者のアドレスの残高を変更することで報酬を付与」させるトークン。 しかし、この仕様は複雑なため、各DeFiプロダクトやL2では互換性を持たないケースもあります。 An update on Lido’s L2 plans 🏝️https://t.co/rvMSbsyWX2 pic.twitter.com/nfby4S63Ba — Lido (@LidoFinance) August 16, 2022 (L2での対応を発表するTwitterの投稿。しかし、当面L2での対応はwstETHのみとのこと) 上記のような互換性の問題を解決するのが「wstETH」です。 wstETHは、stETHのように自動的に残高が変化しません。(他のトークンと同じような挙動) 一方で、stETH・wstETH同士の変換に対応しており、stETH・wstETHの変換時に報酬分を反映させた変換が可能です。 (stETH To wstETHの変換レート。記事執筆時点で1stETHに対して0.9201wstETHのレート) 例えば、1stETHを1wstETHと変換したと仮定しましょう。 1wstETH保有時に報酬を獲得しており、実質的に10%が上乗せされていたとします。 この際、1wstETHをstETHと変換した場合、1.1stETHを入手できます。(つまり、報酬の10%分、1wstETHの価値が上がります) stETHとの互換性を持たない場所で利用すると、報酬が反映されないといったトラブルも予測されるので、wstETHとの使い分けが必須です。 Lidoの3つの特徴 これから、Lidoの特徴について以下の3つのポイントから解説していきます。 気軽にステーキング可能 ステーキング中でもETHの運用が可能 他の通貨でも利用可能 さまざまなメリット・特徴から、LidoでステーキングされたETHは400万ETHを超えています。 多額のETHが集められているLidoの強みと実際の利用例などをチェックしていきましょう。 気軽にステーキングが可能 まず、はじめに挙げられるポイントとして、Lidoを通すことで気軽にステーキングが行える点が挙げられるでしょう。 イーサリアムのステーキングを直接的に行う方法もありますが、技術的な問題や資金的な問題からハードルが高い面は否めません。 一方で、Lidoなら少額から数クリックで、ステーキングに伴う報酬を獲得できるのはもちろん、イーサリアムなど各ブロックチェーンの安定性を担保する一員になることができます。 具体的には、以下の画像のようにLidoでステーキングすると、Lidoのコントラクトを通して間接的にステーキングできます。 また、報酬もstETHの残高を通して自動的に反映され、計算式を用いて預けたETHに応じた配布される仕組みになっているため、報酬のチェックも容易です。 ただし、stETHの残高を通した報酬の反映には10%の手数料が含まれているため、直接的にイーサリアムにステーキングするよりも報酬は減少するため注意が必要です。 ステーキング中にETH(stETH)の運用が可能 前述のとおり、LidoにETHをステーキングすると、stETHが獲得できます。 このstETH(もしくはwstETH)は、DeFiプロダクトで利用可能です。 例えば、AAVEなどで担保として利用することが可能であり、stETHを利用してETHを借り入れることが可能です。 また、DEXを利用してstETHを売り出すことも可能なので、間接的にステーキングしたETHを入手することもできるでしょう。 上記のように、Lidoを活用すると、ステーキングした資金を柔軟に運用していくことが可能です。 複数の通貨が利用可能 この記事では、代表的なイーサリアムを中心的に解説していますが、Lidoはその他の通貨も扱っています。 以下が、9月23日時点でLidoが扱っているブロックチェーンと通貨になります。 ブロックチェーン APR ステーキング後の通貨名 イーサリアム 5.2% stETH Soalana 5.5% stSOL Polygon 6.3% stMATIC Polkadot 16.5% stDOT Kusama 11.4% stKSM (APRは9月23日時点のもの) 基本的な仕組みは、イーサリアムと似通っていますが、細かな仕様などは各ブロックチェーンによって異なってきます。 ステーキングしたい仮想通貨がある場合は、各ブロックチェーンごとの仕様などを予めチェックおきましょう。 Lidoの使い方を解説 次に、Lidoの使い方について、以下のポイントから解説していきます。 Lidoとウォレットの接続 Lidoでステーキングする方法 これまでの報酬の確認方法 stETHとwstETHの変換方法 上記の手順を参考に、Lidoの使い方をマスターしていきましょう。 また、Lidoの利用には前提として各チェーンにあったウォレットとネットワーク設定、ステーキングする仮想通貨が必要です。 これから解説する手順は、ETHでLidoを利用する手順になっているので、MetaMaskなどのウォレットを作成しておきましょう。 MetaMaskの使い方についてはコチラの記事で解説しています。 ウォレットとLidoの接続 はじめに、Lidoとウォレットを接続していきましょう。 Lidoへアクセス 「Connect Wallet」へ 自身のウォレットを選択 ウォレットの承認を済ませる 上記の手順で、Lidoとウォレットの接続ができたら、利用するための事前準備は完了です。 Lidoでステーキングする方法 次に、Lidoでステーキングする方法をチェックしていきましょう。 Lidoでステーキングする方法は以下のとおりです。 「STAKE」へ ステーキングする量を入力 「Submit」へ ウォレットの承認を行う 一度、ステーキングすると解除はできませんが(イーサリアムのアップデートが実施されるまで)、DEXなどでETHと変換することにより、間接的に解除することも可能です。 これまでの報酬を確認する方法 次に、これまでの報酬を確認する方法をご紹介していきます。 「REWARDS」へ 各項目をチェック 項目ごとに、以下のような点がチェック可能です。 stETHの数量 (stETH balance) 獲得したstETHの数量 (stETH earned) 平均的なAPR (Average APR) stETHの価格 (stETH price) 前述した仕様の影響で、ウォレットの残高は日々変化するものの、これまでの収益を振り返るといった用途で活用すると良いでしょう。 stETHをwstETHに変換する方法 最後にstETHとwstETHを変換する方法をご紹介していきます。(Wrapする方法) 「WRAP」へ 両項目からstETH or wstETHをウォレットに追加しておく 変換したいstETH or wstETHを選択 数量を入力 Wrapへ ウォレットの承認を済ませる stETHと互換性のない利用方法を検討している場合は、上記の手順でwstETHへ変換していきましょう。 Lidoの注意点とリスク Lidoには、いくつか注意点やリスクが存在しています。 特にstETHの取り扱いを誤ると、報酬を獲得できないといったトラブルに繋がる可能性もあります。 そのため、以下のポイントからLidoの注意点について押さえていきましょう。 stETHの残高は減少する可能性 stETHと互換性 stETHとETH間における市場価格 Lidoを正しく使うためのポイントをチェックしていきます。 (これから解説するのは、あくまで一部のリスク・注意点であり、常にさまざまな潜在的なリスクが存在しています。) stETHの数量は減少する可能性 前述したとおり、stETHは ステーキングの報酬によって残高が増加し、報酬が付与される仕様です。 しかし、これは同時に「減少する可能性も存在している」ことを意味します。 というのも、stETHの供給は、LidoにあるETHの総量とETH保有者のシェアを元に計算され、いくつかの経費を引いて残高に反映します。 このため、ETHの総量が減少すると、stETHの残高が減少する可能性があります。 代表的なものに、バリデーターがブロックチェーンからペナリティを与えられるケースが考えられるでしょう。 PoSでデータを検証する主体をバリデーターと言います。 望ましくないバリデーターに対しては、予めペナリティが設定されていることが一般的で、何らかのエラー・不正などを行った場合はステーキングした資金が没収されることもあります。 上記の没収は、Lidoを通してステーキングしているETHも対象となり、Lidoと連携しているバリデーターがペナルティを被った場合、ETHの総量が減少し、stETH残高の減少などが見られる可能性があるでしょう。 stETHと互換性 前述したとおり、stETHはステーキングの報酬を残高にて反映させるといった仕様を採用しており、wstETHなどを採用することで各プロダクト・プラットフォームとの互換性を保っています。 stETHを用いて誤った運用を行ってしまうと、報酬を受け取れないといったリスクがあるため、利用するために予めwstETH・stETHを利用べきか否か?をチェックしておくのがおすすめです。 また、各プロダクトによってstETHに対応している場合でも、対応している範囲が限定的(一部の機能のみサポート)といったケースもあり、こちらも留意しておくと良いでしょう。 市場価格ではETHの価格と乖離が見られる stETHとETHの変換レートは1:1に設定されています。 しかし、これは必ずしもstETHとETH間の市場価格が一致するということを意味しません。 実際に、9月23時点ではstETHがETHよりも若干安く取引されています。(1stETH = 約0.993ETH) (過去一年のETH・stETH間のチャート CoinGeckoより) そのため、市場を通して(DEXなどを通して)間接的に、ステーキングを解除するといった場合は、レートに注意したいと言えるでしょう。 (ただし、Lidoからダイレクトにステーキングを解除できるようになると、ETHとstETHは1:1で変換可能になります) まとめ この記事では、Lidoの概要と使い方について解説しました。 Lidoを用いることで、ステーキングしている資金に流動性を持たせて、柔軟な運用が可能になります。 イーサリアムはもちろん、他の通貨にも対応しているので、ステーキングしているという方は利用を検討してみましょう。 最後まで読んでいただきありがとうございました。

プロジェクト
2022/10/21L2ソリューション「StarkNet」とは?特徴や使い方を徹底解説!
StarkWareによって開発されているStarkNetは、zkロールアップに分類されるL2ソリューションの1つです。 StarkWareは過去に企業評価80億ドルで、1億ドルを超える資金調達にも成功しています。 そんなStarkWareが開発するStarkNetは、ゼロ知識証明を活用しイーサリアムのセキュリティを維持した状態で取引の処理を可能にします。 この記事では、StarkNetについて以下の観点から解説しています。 記事のまとめ ・StarkNetはzkロールアップのL2ソリューション ・StarkNetとStarkExは異なるソリューション ・StarkNetのシェアは限定的 ・ORUと比較してさまざまなメリットが見られる ・アルファ版のため注意が必要 StarkNetとは? =ゼロ知識証明を活用したL2ソリューション StarkNetは、ゼロ知識証明を利用したロールアップ(zk-Rollup)を活用したLayer2(以下、L2)ソリューションの1つです。 StarkNetの全体像を把握するにあたって、L2ソリューションと各ロールアップへの理解が不可欠です。 そのため、背景となるトピックも含めStarkNetについて、以下の観点から解説していきます。 ・L2ソリューションの概要と必要性 ・ロールアップの種類 ・StarkNetの概要とシェア ・StarkNetとStarkExについて StarkNetの概要を押さえていきましょう。 L2ソリューションの概要と必要性 代表的な仮想通貨であるイーサリアムの問題点として挙げられがちなのが、スケーリングです。 イーサリアムでは、さまざまな分野のプロダクトが構築されており代表的な分野にDeFiが挙げられます。 DeFiなどの普及に伴い大量に発生する取引(トランザクション)を、イーサリアムが処理しきれず、ガス代や処理速度が低下する問題が課題として認識されています。 上記の問題を解決するために、イーサリアムのブロックチェーンとは別の場所で取引を処理しようと試みているのが、L2ソリューションです。 ロールアップの種類とStarkNetの分類 L2の中でも、StarkNetはロールアップと呼ばれる種類に属します。 ロールアップは、L1とL2間におけるデータの可用性を確保している点が特徴に挙げられます。 具体的には、ロールアップではL2上で発生した取引のデータをオンチェーンでも記録・検証することが可能です。 また、ロールアップの中でも、取引の検証方法などによって大きく分けて、以下の2種類が存在しています。 Optimistic ロールアップ (例 Arbitrum、Optimistic Ethereum ) zk ロールアップ (例 zkSync、StarkNet) StarkNetは、zkロールアップに分類されます。 StarkNetとzkロールアップの概要 StarkNetは、StarkWare(Stark Ware Industries)によって開発されているzkロールアップの1つです。 zkロールアップでは、ゼロ知識証明と呼ばれる技術を活用し、L2上で行われた全ての取引を検証・証明します。 そんなゼロ知識証明の中でも、StarkNetではSTARKという証明方法を用いています。(仕組みによる特徴は後述) L2 BEATによると、StarkNetに預けられた資金は133万ドルとなっています。 L2全体の順位では18位となっており、大きなシェアを取れている状態ではないです。 ただし、StarkNetはアルファ版であることを考慮する必要があります。 まだまだ、利用できる機能・プロダクトなどには制限がかかっている状態で、本格的なローンチに至っているとは言えません。 今後、開発が進んでいくにつれて、徐々に利用が広がっていく可能性が高いでしょう。 StarkNetとStarkExの違い StarkNetを開発しているStarkWareは、StarkNetの他にも「StarkEx」と呼ばれるソリューションも提供しています。 StarkNetは、誰でもプロダクトを構築可能なパーミッションレスなロールアップ。 対して、StarkExは特定のプロダクトのために提供されているソリューションです。 StarkExは、StarkNetと比較してすでに多数の実績があり、4億ドル以上のロックが行われている代表的なプロダクトに「dYdX・IMMUTABLE X・Sorare」などが挙げられます。 また、StarkExを用いて開発されたプロダクトの中には、StarkNetが分類されるzkロールアップとは異なるソリューションを利用しているプロダクトも存在しています。(代わりにValidiumを利用) 名称や利用している技術などの類似点はあるものの、StarkNetとStarkExでは全体像が異なるため注意が必要です。 CT Analysis 『2022年12月 Ethereumの高いスケーラビリティを実現するStarkExとStarkNetの解説レポート』を無料公開 StarkNetの3つの特徴 これから、前述したようなStarkNetの概要・仕組みによって実現する特徴について、以下の観点から解説していきます。 ・高い処理能力と低いガス代 ・L1への引き出しの速さ ・プログラミング言語にCairoを採用 1つ1つチェックして、StarkNetの強みをチェックしていきましょう。 高い処理能力と低いガス代 他のロールアップと同様に、StarkNetはイーサリアムと比較して、高い処理能力を持ち、低いガス代で利用可能です。*ガス代は変動あり 一例として、StarkNetの記載はありませんが、以下の各ロールアップ間のガス代の比較をご覧ください。 ロールアップを用いた転送の方が、より低く押さえられていることが分かるでしょう。 StarkNetについても似たようなパフォーマンスが期待できます。 ただし、StarkNetはアルファ版であり本格的なローンチに伴って、どのようなパフォーマンスを発揮するのかは、まだまだ不透明な点があります。 今後、StarkNetの普及に伴って、各L2ソリューションとのパフォーマンスの違いには、注視していく必要があるといえるでしょう。 L1への引き出しの速さ StarkNetに預けた資金は、数十分程度でL1に引き出すことが可能です。 現在、大きなシェアを持っているOptimistic ロールアップを利用したL2ソリューションでは、資金の引き出しまでに1週間ほどの期間が必要です。 これは、Optimistic ロールアップが取引を検証・証明する際に必要な期間となっており、利便性や資金効率の観点から好ましくありません。 一方で、StarkNetのようなzkロールアップでは、より早い時間でL1への資金の引き出しが可能です。 (ただし、流動性を用いたソリューションなどを利用することで、Optimisticロールアップでも高速な引き出しが可能なケースもあります) プログラミング言語にCairoを採用 StarkNetでは、StarkNet上のスマートコントラクトなどの開発を行う言語として、「Cairo」と呼ばれる独自のプログラミング言語を採用しています。 StarkNetは基本的にCairoを用いて開発されており、StarkNetで開発を行いたい開発者もCairoを用います。 CairoはStarkNetのネイティブ言語ではあるものの、イーサリアムのSolidityなどをCairoへ変換するトランスパイラ(コード変換が行えるツール)も開発されています。 また、StarkNetはEVMについてもネイティブで対応していません。 StarkNetとArbitrum・zkSyncなど他のロールアップとの違い 現在、多数のL2ソリューションが登場しており、StarkNetもその中の1つです。 「StarkNetは具体的に他のL2ソリューションと何が違うのか?」と疑問を感じた方も多いでしょう。 そのため「OptimisticロールアップのArbitrum」・「zkロールアップのzkSync」と「StarkNet」の違いについて解説していきます。 StarkNetと、他のロールアップの違いについてチェックしていきましょう。 証明する「対象」が異なる:ArbitrumとStarkNet 2022年10月時点で、最も高いTVLを持っているロールアップがArbitrumです。 ArbitrumはOptimisticロールアップに分類され、StarkNetが属しているzkロールアップと、そもそもの検証・証明アプローチが大きく異なります。 両者の大きな違いは「証明する【対象】」にあります。 ArbitrumのOptimisticロールアップは「基本的に正しいブロックが生成される」という前提で設計されたロールアップです。 その上で、不正検知の仕組みとして、Optimisticロールアップでは「一定の検証期間」を設定し「期間内に不正なブロックは無いか?」という観点で検証を行います。 そのため、Optimisticロールアップでは、ブロックの検証に伴い「不正の証明(Fraud Proof)」が行われるのです。 一方で、StarkNetのようなzkロールアップでは「不正なブロックが生成される」という前提で設計されており、全てのブロックに対して「有効性の証明(Validity Proof)」を行います。 上記のような特性から、Optimistic・zkロールアップの間には、さまざまな箇所で大きな違いが見られます。 証明する「方法」が異なる:zkSyncとStarkNet zkSyncは、5,000万ドル以上がロックされるzkロールアップのL2ソリューションです。 StarkNetとzkSyncは、同じzkロールアップのため、両者とも「有効性の証明」を行い、証明する対象に違いはありません。 そのため、使用感(引き出しまでの時間など)について似通った点が見られます。 しかし、StarkNetとzkSyncでは「証明する【方法】」が異なります。 というのも、StarkNetでは「STARK」という証明システムを用いているのに対して、zkSyncでは「SNARK」を用いています。 また、このような違いはOptimisticロールアップに分類されるソリューションの間でも見られることが多いです。 同じロールアップに分類されていたとしても、L2ソリューション間で微妙に仕様・仕組みが異なってきます。 各ロールアップのより詳細な内容について、CT Analysisの「Ethereumを飛躍的にスケールさせるロールアップの概要と動向」で解説しているので、ぜひご覧ください。 StarkNetの使い方 StarkNetの利用には、以下のようなものが必要です。 イーサリアムサイドのウォレット (MetaMaskなど) StarkNetサイドのウォレット (Argentなど) ガス代やDeFiなどで利用する仮想通貨 また、上記の準備に加えて、利用する仮想通貨のStarkNetへのブリッジも必要です。 StarkNetへのブリッジを行うことで、StarkNetに構築されているプロダクトで仮想通貨を利用できるようになります。 StarkNetへのブリッジや、Argentなどの利用手順について、以下の記事で解説しています。 【評価額1兆円】StarkWare手掛ける注目のトークンブリッジ『StarkGate』を解説 StarkNetの注意点 最後に、StarkNetの利用に伴う注意点などについて、以下の観点から解説していきます。 ・利用できるプロダクトが少ない ・アルファ版であり完全な状態ではない StarkNetの利用前に押さえておきたいポイントをチェックしていきましょう。 まだまだ利用できるプロダクトやシェアは少ない StarkNetは、他のL2ソリューションと比較すると、まだまだ利用できるプロダクトやシェアは限定的です。 前述したようにTVLも、他の主要なL2ソリューションと比較して多くありません。 そのため、他のロールアップのようにエコシステムが整備されているとは限らないため注意が必要です。 「アルファ版であり完全な状態ではない」 StarkNetはアルファ版であり、あらゆる箇所で開発途中の印象が否めません。 例えば、StarkNetの開発を行っているStarkWareによって提供されているStarkGateというブリッジでも、アルファ版での運用が続いています。 ブリッジやロールアップの利用にはさまざまな潜在的なリスクが存在していますが、StarkNetの利用についてはその傾向が特に強くなると言えるでしょう。 常に何らかのバグ・欠陥・変更などが見られる可能性を考慮し、StarkNetへのブリッジなどについては、限定的な使用に留めておくのがおすすめです。 まとめ この記事では、StarkNetについてさまざまなポイントから解説しました。 StarkNetは、今後注目していきたいL2ソリューションの1つではあるものの、さまざまな観点で開発途中のソリューションです。 動向を注視しながらも、細心の注意を払った上で利用していきましょう。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 【トークン発行予定】分散型クロスロールアップブリッジ「Orbiter Finance」を解説

初心者向け
2022/10/19PolygonScan(ポリゴンスキャン)とは?概要や使い方を解説
PolygonScanは、Polygonのブロックチェーンで発生したさまざまなイベントをチェックできるツールです。 トークンの追加や、トランザクションの状況をチェックするといった用途はもちろん、リサーチにも応用できるツールになっています。 Polygon利用者なら一度は、チェックしてみたい存在であると言えるでしょう。 この記事では、そんなPolygonScanの概要から利用例、使い方について解説しています。 PolygonScanとは?=Polygonチェーンの中身が見れるツール PolygonScanは、Polygonのさまざまな情報を閲覧できるツールです。 具体的には、Polygonのブロックチェーン上の情報を閲覧・確認できるツールとなっており、さまざまなリサーチや自身のウォレットの状況を確認する際などに利用できます。 トランザクションの内容などを詳細に確認できるので、DeFiの利用に伴い重宝する存在です。 送金やDeFiを活用した運用など、何らかの形でPolygonScanのブロックチェーンを利用する方であれば、利用する機会が多いでしょう。 PolygonScanを利用するメリット・利用例 PolygonScanを利用するメリット・利用例について、以下の観点から解説していきます。 ・ブロックチェーンの状態を観察する ・ウォレットやトランザクションの内容を確認する ・何らかのアクションを加える ・プロジェクトのリサーチに活用する PolygonScanの利用例などから、PolygonScanの活用方法をご紹介していきます。 ブロックチェーンの状態を観察する PolygonScanは、Polygonのブロックチェーンのトランザクション、コントラクト、トークンなどの情報を網羅的に閲覧できます。 また、PolygonScan上の情報は、PolygonScanの利用状況に応じてリアルタイムに更新されており「現在/過去にPolygonで何が起こっているのか?」をチェックできます。 ブロック・トランザクションに関するトピックだけでも、例としてPolygonScanでは以下の点が確認できます。 Polygonの過去のトランザクション、ブロックの総量や直近の動向 ガス代の状況と直近でガスを消費しているアカウントや契約 最新のブロックとバリデーター 最新のトランザクションとそれに伴うガス代や使用されたブロック 上記はあくまで一例で、同様の情報がトークンやコントラクトに関してもチェック可能です。 また、上記のような情報は、PolygonScan以外のブロックチェーンのエクスプローラーでも応用できるポイントです。 上記のような点をチェックすることで「ブロックチェーンがどのくらい利用されているのか?どのくらいの需要があるのか?」といった点もチェック可能ですので覚えておきましょう。 Polygonは比較的普及しているブロックチェーンのため、直近の数分間だけでも多数のトランザクションが確認できます。 一方で、利用されていない・普及していないエクスプローラーの場合は、Polygonのようにアクティブなトランザクションが確認できないケースも少なくありません。 ウォレットやトランザクションの内容を確認する PolygonScanでは、前述したような情報が閲覧可能なため、自身のウォレットやそのトランザクションなども閲覧できます。 つまり「自身のウォレットの利用状況・履歴」が全て閲覧可能になるのです。 具体的には、以下のような点がチェックできます。 アドレスの保有しているMATIC 保有しているMATIC以外のトークンと価格 過去の全てのトランザクション履歴 各トークンごとのトランザクション トランザクションで実行した内容やコントラクト 送付先のアドレス トランザクションに対するガス代 また、上記のような情報は、自身のウォレット・アドレス以外でも閲覧できます。アドレスを入力する or トランザクションの履歴から辿ることによって、他のアドレスにおいても同様の情報が閲覧可能です。 上記は自身のアドレスに関する情報も、PolygonScanを通して第三者から閲覧できることを意味するので覚えておきましょう。 何らかのアクションを加える PolygonScanでは、ブロックチェーンやウォレットに関する情報のみならず、何らかのアクションを加える場合や、PolygonScanをソースに何らかのアクションを行う際のツールとしても応用できます。 例えば、「トークンに対する承認を削除する」、「トークンを追加する際のアドレスをチェックする」といった利用方法です。 上記のようなアクションは、Polygon上に構築されたプロダクトの利用などに伴って必要となることが多いです。 プロジェクトのリサーチに活用する PolygonScanは、前述したような情報を閲覧できるため、プロジェクトのリサーチにも活用できます。 例えば、PolygonScanでは各トークンの上位保有者(アドレス)が保有しているトークンの金額や転送履歴などがチェック可能です。 そのため、上位保有者の動向(例えば、運営・財団など)などをチェックすることで、詐欺のリスク下げられる可能性もあります。 もしも、購入を検討しているトークンに、保有者が著しく偏っている状況や怪しい取引履歴などが観測できた場合、リスクが高い可能性があるかもしれません。 *上記はあくまで仮説なので各プロジェクト・トークンに対しては別途詳細なリサーチを推奨します。 PolygonScanの使い方 PolygonScanの使い方について、以下の観点から解説していきます。 ・Polygon全体の状態を確認する ・PolygonScanでウォレットの履歴などを閲覧 ・PolygonScanを利用してトークンを追加 PolygonScanの使い方をマスターしていきましょう。 Polygon(ポリゴン)・Matic Networkとは?概要や特徴、使い方を解説 Polygon全体の状態を確認する Polygonチェーンの全体の状況を、PolygonScanからチェックする方法をご紹介していきます。 PolygonScanへ 「Resources」から「Charts & Stats」へ 各チャートを確認する (クリックで詳細を確認可能) 各チャートはトランザクションの動向やアドレスの総数など、Polygon全体の利用状況が表示されています。 注目したいチャートのそれぞれの意味は、以下のとおりです。 「Daily Transaction Chart」= デイリーのトランザクション数 「ERC-20 Daily Token Transfer Chart」= ERCトークンが転送数 「Unique Addresses Chart」= ユニークなアドレス数 「Average Block Size Chart」= 平均的なブロックサイズ (ブロックのデータの大きさ) 「Average Block Size Chart」= 平均的なブロックタイム (ブロックがブロックチェーンに追加されるまでの時間) 「Average Gas Price Chart」= ガス代の平均 上記チャートを確認して「Polygonの全体の利用状況はどうなっているのか?」といった点をチェックしていきましょう。 PolygonScanでトランザクションの履歴を閲覧・ダウンロードする方法 次に、PolygonScanで自身のウォレット(アドレス)の履歴を、閲覧・ダウンロードする方法をご紹介していきます。 PolygonScanでアドレスを入力 (自身のアドレスはMetaMaskなどのウォレットからチェック可能) 過去のトランザクションなどをチェック スクロールして「CSV Export」からダウンロード可能 「Txn Hash」からトランザクションの詳細もチェック可能 前述したとおり、入力したアドレスの履歴をチェック可能なので、自身のウォレットのみならず、リサーチしたいアドレスを入力することで各情報を閲覧可能です。 また、トランザクションの詳細を表示した際の項目は、以下のような意味を表しています。(チェックしたい項目から抜粋) 「Transaction Hash」 : トランザクションのハッシュ 「Status」:トランザクションの状況 「From」:転送元などのアドレス 「To」:コントラクトと転送先のアドレス 「Value」:トランザクションで動いた価値 特にトランザクションが上手く通らないときなどに、チェックしたいのが「Status」です。 「Status」にて「Success」と表示されていない場合は、トランザクションが保留・待機中か、失敗している可能性があるので注意しましょう。 PolygonScanを利用してトークンを追加する ウォレットにてトークンが表示されない場合は、トークンのコントラクトアドレスを取得してウォレットに追加する必要があります。 以下の手順で、PolygonScanからアドレスを取得し、ウォレットにトークンを追加していきましょう。 PolygonScanで追加したいトークン調べる 「Contract」からアドレスをコピー MetaMaskを開いて「トークンをインポート」へ アドレスをペースト 「カスタムトークンを追加」から「トークンをインポート」へ また、トークン追加の際に調べたPolygonScanの画面から、以下のような項目でさまざまな情報が閲覧可能です。 「Transfer」:過去の転送履歴 「Holders」:アドレスごとの保有数と% 「Info」:トークンに関する簡易的な情報 上記のようなトークン周りの情報を活用して、リサーチも行っていきましょう。 まとめ この記事では、PolygonScanについてさまざまな観点から解説しました。 PolygonScanのようなエクスプローラーは、トランザクションの履歴を取得したりトークンの追加で重宝しますが、そのような用途に限りません。 リサーチなどにも応用できる便利なツールなので、Polygonのブロックチェーンを何らかの形で利用している方は、是非積極的に利用してみてください。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 CT Analysis 『PolygonによるzkRollup Polygon zkEVM解説レポート』を無料公開

初心者向け
2022/10/18メタマスク(MetaMask)でのBNBチェーン(BSC)への接続方法を解説
代表的なウォレットであるMetaMaskでは、イーサリアムはもちろん、BNBチェーン(BSC)上のプロダクトを利用できます。 しかし、デフォルトのネットワーク設定ではイーサリアム関連のプロダクトやトークンしか扱えません。 MetaMaskでBSC上に構築されたプロダクトを利用するには、予めネットワーク設定を行って、BSCと接続できる状態にしておく必要があります。 本記事では、そんなMetaMaskでBSCと接続するための設定方法や手順について解説しています。 MetaMaskでBSCへ接続する方法 MetaMaskを利用して、BSCに構築されたプロジェクトに接続することは可能なものの、イーサリアムと違ってデフォルトの状態での利用はできません。 BSCに接続する前の段階で、BSCのネットワークを予め追加しておく必要があります。 その際に必要となるBSCへ接続する手順について解説していきます。 接続する前に必要となる準備や、手順などについてチェックしていきましょう。 MetaMaskなどウォレットの事前準備 まず、はじめにMetaMaskなどのウォレットを予め作成しておきましょう。 BSCの利用には複数のウォレットを利用可能ですが、最も代表的なのがMetaMaskです。 ウォレットの作成する自体は数分もあれば完了可能で、PC・スマホのどちらからでも利用可能です。 下記2つの記事で、スマホ or PCのMetaMaskウォレットの作成手順や利用方法を解説しています。 PC MetaMask(メタマスク)の使い方まとめ!入出金・トークン追加も超簡単 スマホ MetaMask(メタマスク)モバイル・スマホの使い方を解説! MetaMaskにBSCの設定を追加する手順 次に、MetaMaskでBSCのネットワーク設定を追加する手順について解説していきます。 以下の手順で、MetaMaskからBSCへ接続できるようにしていきましょう。 MetaMaskを開く 画面上部へ 「ネットワークを追加」へ 必要な情報を入力(*後述) 「保存」へ BSCの接続に伴って必要な情報は以下のとおりです。 ネットワーク名:Smart Chain 新たしいRPC URL :https://bsc-dataseed.binance.org/ チェーンID:56 通貨記号:BNB ブロックエクスプローラーのURL:https://bscscan.com 上記の手順を完了することで、BSC上に構築された各プロジェクトとの接続が可能です。 BSCで利用する仮想通貨の準備 最後に、BSC上に構築されたDeFiなどの利用を検討している方は、予め仮想通貨を準備しておきましょう。 特に準備しておきたいのは、BNBです。 というのも、BSCで取引を行う際はガス代(手数料)の支払いにBNBが必要です。 まだ、BNBを利用していない方は、Binanceなどから購入しておきましょう。 BSCで構築されたプロジェクト例 BSC上に構築された代表的なプロジェクトには、以下のようなものが挙げられます。 PancakeSwap (DEX) Venus (レンディング) Alpaca Finance (Yield) BiSwap (DEX) PinkSale (ローンチパッド) (DeFiLlamaを参考にした2022年10月時点でのTVL上位TOP5) 各プロジェクトは、予めBSCのネットワークを追加したMetaMaskを接続することで、利用することができます。 上記の中でも、TVLランキング2位であるレンディングのVenusについては、以下の記事で解説しているので、気になる方はぜひご覧ください。 DeFiレンディングプロトコル「Venus Protocol」の基本的な使い方・リスクを徹底解説! BSCとMetaMaskの接続についてまとめ 本記事では、MetaMaskのBSCの接続方法について解説しました。 BSCはTVLが高いブロックチェーンの1つであり(イーサリアムに次いで2位)、今後も魅力的なプロジェクトが出てくると考えられます。 予め、MetaMaskにBSCを追加しておいて、気になるプロジェクトが出たときにスムーズに利用できる状態にしておきましょう。 メタマスク(MetaMask)の「Portfolio(ポートフォリオ) Dapp」とは?機能や使い方を解説 【安全対策】メタマスク Revoke(リボーク)の概要と方法

プロジェクト
2022/09/12Oasysとは?ゲーム特化型ブロックチェーンの特徴や概要を解説
ゲームに特化したブロックチェーンを展開するOasys。 Oasysは「利用者のガス代が無料になる」「特定の環境下のみで利用可能なNFTを発行できる」など、独自のアプローチでブロックチェーンゲーム体験の向上を目指しているプロジェクトです。 2022年7月には2,000万ドルを超える資金調達にも成功しており、今注目のブロックチェーンの1つです。 Oasys successfully completed a private token sale round of USD20 million led by Republic Capital, blockchain financing and investment platform, with participation by other renowned investors. 🎉 1/3 pic.twitter.com/AxvnZQfqH5 — Oasys🏝Blockchain for Games (@oasys_games) July 6, 2022 本記事では、そんなOasysの概要・特徴・注目したい仕組みなどについて解説しています。 記事の内容まとめ ・ゲームに特化したブロックチェーン ・利用者はガス代無料で利用可能 ・WEB2レベルのレスポンス ・IP保護を意識したNFTを作成可能 ・ヴァースを構築することによる柔軟な開発が可能 Oasysとは?= ゲーム特化のブロックチェーン Oasysは、ゲームに特化したブロックチェーンやプロジェクトの総称です。 ゲームに特化しているということもあり、現状のブロックチェーンゲーム(以下:BCG)に関する課題や問題点を解決することに焦点をおいたプロジェクトです。 注目度の高いトピックの1つであるBCGですが、既存チェーンを利用したBCGには現状以下のような課題があり、Oasysはこれらの課題の解決を目指しています。 利用者の参入障壁 DeFiと比較して膨大なトランザクションを高速に処理できない 著名なIPを保有するような開発サイドのさまざまなリスク また、Oasysには著名企業が多数参画しており、初期バリデーターには、仮想通貨やエンタメ・ゲーム関連の企業を中心に以下のような企業が参画しています。 ASTAR BANDAI bitFlyer GREE UBISOFT SEGA PlayArt SQUARE ENIX 既に著名なIPを保有している大手企業も参加し、国内企業も多く参画している傾向が分かるでしょう。 今後もバリデーターに限らず、さまざまなレイヤーで著名な企業の参画が見られるかもしれません。 BCGを進化させるOasysの3つの特徴 ・利用者のガス代が不要 ・高速なレスポンス ・開発者サイドのリスクを回避 BCGを進化させるOasysの特徴について、上記3つの観点から解説していきます。 OasysがBCGをより進化させるために備えている特徴をチェックしていきましょう。 利用者のガス代が不要 Oasysでは、利用者(エンドユーザー)によるガス代の支払いが、原則不要になります。 そのため、利用者はゲームをプレイするために、ガス代などに用いる初期費用を用意する必要がありません。 現状のBCGの多くは、ガス代の支払いなどに伴って初期費用が必要になっており、一般的な利用者にとって大きな参入障壁となります。 ガス代など、運用に関わるコストの多くはヴァースレイヤー(後述)が負担することになります。 高速なレスポンス Oasysでは、1秒未満で完了する大量のトランザクション処理を可能にしています。 現状のチェーンでは、トランザクションが通るまでに数秒〜数十秒ほどの時間が発生します。 このタイムラグは、一般のWeb2のゲームをプレイする利用者にとって大きなストレスになる可能性が高いです。 そのため、OasysではWeb2と同等程度のレスポンスを可能にする設計を行っており、一般の利用者でもストレスを感じない体験ができます。 開発者サイドのリスクを回避 Oasysは、著名なIPを保有する従来の企業が懸念するリスクを払拭しています。 現状のBCGやNFTといった領域への参入は、既存のIPを持つ企業や開発者などにとっては、大きなリスクを抱えています。 その1つが、レピュテーションリスク(ネガティブな評判・風評など)です。 これは、ブロックチェーンが持つ誰にでも開かれたパーミッションレスという特性が要因となっています。パーミッションレスであるがために、現状のWEB3には魅力的なプロダクトが存在している一方で、詐欺的なプロダクト・プロトコルも多く存在しているのが現状です。 上記のような環境では、IPを保有する従来の企業が参入は、評判や風評に対する一定のリスクが含まれます。 また、NFT化した際のIP保護といった問題も存在しています。 上記のような既に魅力的なIP・コンテンツを持つ企業の参入を阻む要因を、さまざまなアプローチでOasysでは克服しています。 高品質な体験を提供するOasysの仕組み 次に、前述したような特徴を実現するOasysの仕組みについてチェックしていきましょう。 Oasysの仕組みで注目なのが多層的な構造を持っている点です。 Oasysでは、以下のように複数のレイヤーが存在しており、各レイヤーがそれぞれ重要な役割を担っています。 アプリケーション ヴァースレイヤー(Verse Layer) ハブレイヤー(Hub Layer) 各レイヤーを、1つ1つチェックしていきましょう。 アプリケーション 具体的にOasysのホワイトペーパーなどで、明記されているレイヤーではありませんが、利用者にとって最も身近なレイヤーがアプリケーション(Dapps)です。 実際にOasysに構築されたゲームなどのアプリケーションを指し、一般的な利用者が認識するのはこちらのレイヤーになるでしょう。 ヴァースレイアー(Verse Layer) Oasysにおけるヴァースレイヤー(Verse Layer)は、前述したようなDapps(ゲームなど)を構築しているレイヤーになります。 ヴァースの基本的な役割は、Dappsなどで発生したトランザクションをOpsitimic ロールアップを用いて処理を行うといったものです。 100万OASをデポジットすれば誰でもヴァースの構築が可能で、構築された各ヴァースは構築者(Verse Builder)によって自由にカスタマイズできます。 具体的にはヴァースの構築者は、 ヴァース上のさまざまな権限を制限 構築されるDApps自体の制限 といったことが可能。ヴァースの構築者の任意で、パーミッションレスな環境にすることも出来ます。 各ヴァース自体は許可型(Permissioned)といった環境を構築することも可能で、これによりヴァースの構築者・管理者は、 権限を用いて詐欺のようなプロジェクトを排除 自社の限られたDappsだけが構築される排他的なヴァースを構築 といった運用も行えます。 また、ゲームの中でもFPS・RPGといったジャンル別のヴァース、DeFi向けのヴァースといったように構築されるプロダクトに合わせたヴァースが構築されるといった可能性も考えられるでしょう。 ハブレイヤー(Hub Layer) Oasysのハブレイヤー(Hub Layer)は、前述したようなOasysエコシステム全体を司る基礎のようなレイヤーです。 ハブレイヤーは、ヴァースレイヤーのように細かなトランザクションの実行・処理などは行いません。 そのため、ハブレイヤーが処理するトランザクションは、ヴァースレイヤーと比較して限定的です。 その代わりに、Oasysのエコシステム全体に関わるような以下のような処理やデータの管理をハブレイヤーで行います。 ロールアップのデータの管理 FT/NFTの管理 ブリッジの管理 前述のとおり、OasysのヴァースレイヤーはOpsitimic ロールアップを使用しており、ロールアップで処理されたデータはハブレイヤーに記録されます。 上記のヴァースレイヤーとロールアップはハブレイヤー上に構築されているため、各ヴァースがダウンしたとしてもハブレイヤーからデータにアクセスすることが可能です。 その他にも、ハブレイヤーではNFTや各チェーン上を行き来させるブリッジの管理などを行います。 ハブレイヤーでのコンセンサスアルゴリズムにはPoSが採用されており、1,000万OASのステーキングで誰でもバリデーターになれます。 Oasysと3種類のトークンの概要 ヴァースレイヤーのみのトークン(vFT/vNFT) 相互運用性の高いトークン 外部のトークン トークンの柔軟な運用を可能にするために、Oasys内では上記3つのトークンが扱えます。(いずれも、FT・NFTを含む) 各トークンごとに、特性が異なっているので一つ一つチェックしていきましょう。 ヴァースレイヤーのみのトークン(vFT/vNFT) Oasys内で、もっとも特徴的なトークンとなっているのが「vFT/vNFT」と呼称されているトークンです。 vFT/vNFTは、ヴァースレイヤーで作成可能となっており「特定のヴァースでしか利用できない」という特徴を持っています。 そのため、他のヴァースで利用できないのはもちろん、他のチェーンへのブリッジなどに対応していません。 実際のユースケースとしては、ゲーム内通貨(FT)やIP(IP)などが想定されているようです。 vFT/vNFTが存在することで、IPが載っているNFTなどを意図しない用途に利用させないなど、NFTの運用におけるIP保護などに応用できます。 例えば、IP保護を重要視する企業が特定のヴァースを構築し、なおかつ特定のヴァースでしか利用できないNFTを作成するといった運用が可能になるかもしれません。 相互運用性の高いトークン(oFT/oNFT) oFT/oNFTは、ハブレイヤーで作成される相互運用性の高いトークンです。 oFT/oNFTは、Oasysに構築されたさまざまなヴァースで利用可能なのはもちろん、他のチェーン(イーサリアムなど)で利用することもできます。 一般的にトークンと言われて、思い当たるのがこのタイプになるでしょう。 oFT/oNFTとvFT/NFTの両者を活用することで「一部のゲーム要素・トークンのみを外部にもオープンにする」といった柔軟な運用が可能になります。 外部のトークン(exFT/exNFT) 最後のOasysで利用できるトークンが「exFT/exNFT」です。 こちらは外部のチェーンで作成されたトークンで、例えばイーサリアムで作成されたFT/NFTのような存在にあたります。 外部のトークンは、ハブレイヤー・ヴァースレイヤーともに利用可能となっており、Oasys内のエコシステムで自由に利用することができます。 OASとトケノミクス Oasysのネイティブトークンは、OASです。 OASの初期の供給は、100億OASに設定されており、各用途ごとに以下の割合が設定されています。 38% エコシステムとコミュニティ 21% ステーキング報酬 15% 開発 14% プライベートセールでの投資家 12% 財団(Oasysをサポートする) 長期的な成長と持続可能性を重視し、OASは段階的に供給されていきます。 ネイティブトークンのため、OASはOasysエコシステムの中核となる存在で、Oasys内におけるさまざまなアクションに対してOASが必要になっています。 一例になりますが、OASには以下のような用途が存在しています。 ガス代 ヴァース構築(100万OAS) ガバナンス PoSでのバリデーターになる(1,000万OAS) エコシステム内での支払い(ゲームアイテムの購入など) さまざまな用途が設定されていることが分かるでしょう。 Oasysの将来性・今後の計画 Oasysは、最終的にDAOによって管理されるパブリックブロックチェーンになることを目指しています。(目標は6年) その最終的な形態に向けて、期間ごとの目標が設定されたロードマップが公開されているので、これを参考に期間ごとのイベントをチェックしていきます。 〜2023年まで Oasysは、2023年6月までに以下のような目標を掲げています。 CEXでの上場 メインネットのローンチ Oasys内でのプロジェクト数 20以上 Oasys内での分散型IDの数 100万以上 2023年までの焦点は「ローンチ」と「トークンの配分」という2点に当てられているようです。 今後、Oasysが成長していくための基礎を作っていく時期であると言えるでしょう。 2023年〜2024年まで Oasysでは、2024年6月までに以下のような目標を掲げています。 Oasys内でのプロジェクト数 100以上 Oasys内での分散型IDの数 1,000万以上 2023年〜2024年までの期間は、主にエコシステムの成長に焦点を当てているようです。 2024年〜2025年まで Oasysでは、2025年6月までに以下のような目標を掲げています。 Oasys内でのプロジェクト数 1,000以上 Oasys内での分散型IDの数 1億以上 2024年〜2025年までの焦点は、大衆に受け入れられるというのがテーマのようです。 そして、最終的には前述の通り、2028年程度を目処にDAOとして機能することを目標にしています。 Oasysについてまとめ この記事では、Oasysについてさまざまなポイントから解説しました。 仮想通貨周りのプロジェクトやトピックは、海外を中心としたものであることが少なくありませんが、Oasysは珍しく多数の国内企業が関わっています。 Oasysと相性の良さそうな企業も多数参画している様子が垣間見れるので、今後も注目していきたいと言えるでしょう。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 -Oasys公式リンク- Webサイト:https://www.oasys.games/ ホワイトペーパー:https://docs.oasys.games/docs/whitepaper/intro ツイッター:https://twitter.com/oasys_games ディスコード:https://discord.com/invite/oasysgames Medium:https://medium.com/@oasys

プロジェクト
2022/09/02Polygon(ポリゴン)・Matic Networkとは?概要や特徴、使い方を解説
Polygon(Matic)は、イーサリアムをスケーリングさせるL2ソリューションの1つです。 Polygonを利用することで、処理性能の向上やガス代の大幅な圧縮が可能となり、DeFiなどの利用に伴うハードルを下げることが可能です。 また、Polygonには3万を超えるdAppsが構築されており、UniswapやAAVEなどの著名プロジェクトも比較的な安価なガス代で利用できます。 本記事では、そんなPolygonの概要・特徴・使い方などについて解説しています。 記事のかんたんまとめ ・PolygonはL2ソリューション ・サイドチェーンとPoSで高い処理能力を実現 ・1秒あたり7,000件のトランザクションを処理可能 ・ガス代を数十分の1に圧縮 ・数万件のdAppsが構築 Polygon(ポリゴン)・Maticとは?高い処理能力を持つL2ソリューション Polygon(Polygon Network / Matic Network)とは、イーサリアムと互換性を持つL2ソリューションの1つです。 L2ソリューションの中でも、PolygonはPlasma・PoSを採用したサイドチェーンに当たります。 そのため、Polygonを理解するためには、その前提となるL2ソリューションやサイドチェーンへの理解が不可欠になっています これから、Polygonの概要をバックグラウンドとなるトピックも含めて解説していきます。 L2ソリューションの概要 前述した通り、PolygonはL2 (Layer 2)ソリューションの1つです。 L2ソリューションとは、L1(イーサリアムなど)の性能を上げるためのソリューションのことを指します。 現在、多数のL2ソリューションが、さまざまな技術を用いて登場していますが、その背景としてイーサリアムの人気の高まりと性能の課題が挙げられます。 イーサリアム上でさまざまなアプリ・プロダクトが構築され、さまざまな取引が行われるにつれて、イーサリアムのブロックチェーンがパンクするようになりました。 具体的には、イーサリアムに取引が集中しブロックチェーンが適切に処理しきれないことから、取引が承認されるまで長い時間を必要としたり、ガス代(手数料)が高騰する事態が発生しました。 [caption id="attachment_79155" align="aligncenter" width="1024"] イーサリアムのガス代推移。盛り上がっている部分では一度の取引に数十ドルかかっているのがわかる[/caption] このような問題を解決するために登場したのが、L2ソリューションです。 L2ソリューションでは、L1(イーサリアムなど)とは別の場所で取引の処理を行うことでL1の負担を減らし、「処理性能の向上」や「ガス代の削減」を行えます。 L2ソリューションは、取引を処理する一連の仕組みごとにさまざまな種類が存在しますが、代表的な仕組みが以下の3種類です。 ステートチャンネル (RAIDEN、connextなど) サイドチェーン、Plasma (Polygon、OMGなど) ロールアップ (zkSync、Arbitrum Oneなど) Polygonは上記の中でも「Plasma」を採用しているL2ソリューションになります。(上記画像ではMatic = Polygonです) 他のL2ソリューションの概要や代表的なソリューションについては、コチラで解説しています。 PlasmaとPolygonの概要 L2ソリューションに続いて、Polygonを理解するためにもう一つ必要な前提知識であるPlasmaについて解説します。 前述の通り、PolygonではPlasmaが採用されています。 Plasmaでは、ルートチェーン(イーサリアムなど)とは別のチェーン(サイドチェーン)で、取引を処理し一部のデータのみをイーサリアムに返すことで、高い処理能力を実現します。 具体的には、一連の取引の流れなどを要約したデータのみをルートチェーンに記録し、取引の検証などはサイドチェーンサイドが担います。 Polygonでは、サイドチェーン(Polygon側)で行われた取引の検証・証明を行うために、コンセンサスアルゴリズムのPoSを採用しています。 安全性と高い処理能力を実現するために、取引を処理する流れに3つのレイヤー(役割)が存在しており、概要は以下のとおりです。 Polygonのスマートコントラクトのレイヤー (イーサリアム上に構築) PoSのバリデーターレイヤー (Heimdall) ブロックに取引をまとめるレイヤー (Bor) (実際の取引内容は、3から1にかけて集約・検証されていき、最終的に要約された内容がイーサリアムへ記録されます ) 中間の「2.PoSのバリデーターレイヤー(Heimdall)」は、「3.ブロックに取引をまとめるレイヤー(Bor)」にて生成されたブロックの検証、イーサリアムに記録するデータの作成などを担っているため、中核的な存在になっています。 また、PoSへのステーキングには、Polygonの独自の仮想通貨であるMATICが使用され、MATICはガス代の支払いなどにも用いられます。 Polygonを利用するときの全体的な流れ Polygonの仕組みは複雑に感じますが、実際に利用してみると難しいものではありません。 利用者観点から見たときに、Polygonを利用する際の全体の流れは以下の通りです。 イーサリアムからPolygon(Matic Network)へブリッジ Polygon上に構築されたサービスを利用 (不必要になったら)Polygonからイーサリアムへ再度ブリッジして出金 他のL2ソリューションやブロックチェーンを利用するときと、大きな違いは無いと言えるでしょう。 Polygon(Matic)の3つの特徴 ・1秒あたり7000件の処理能力と低コスト ・19億件を超えるトランザクション ・3万件超えのアプリと大規模なエコシステム Polygonの特徴について、上記の3点から解説していきます。Polygonの特別なポイントを押さえていおきましょう。 1秒あたり7000件の処理能力と低コスト Polygonの公式サイトでは、1秒間に7,000件のトランザクションを処理できると記載されています。 イーサリアムは15TPS程度のため、両者を比較すると高い処理能力を持っていると言えるでしょう。 また、ガス代についてもイーサリアムと比較して、〜1万倍低い水準(Polygon公式参照)で取引が可能で、1トランザクションあたりのコストは〜0.002ドルまで圧縮可能です。 19億件トランザクションを超える実績 polygonscanを参考にすると、これまで19億件を超えるトランザクション(取引)が確認できます。 それだけ多数の利用者・取引を抱えているということになります。 他チェーンのトランザクション総数は、BSCで約33億件(BscScan)、ETHで約17億件(Etherscan)です。他のチェーンと比較しても、引けを取らない実績があるといえるでしょう。 PolygonScan(ポリゴンスキャン)とは?概要や使い方を解説 3万件超えのアプリと大規模なエコシステム Polygonの公式サイトによると、37,000以上のアプリ(dApps)がPolygonを利用して構築されており、そのジャンルはゲームからDeFiまで多岐に渡ります。 また、Polygonは最もDeFiで資金がロックされているチェーンの1つです。 [caption id="attachment_79167" align="aligncenter" width="936"] 2022年7⽉版 CT Analysis DeFi マンスリーレポートより[/caption] タイミングによってSolanaと順位を行き来していますが、記事執筆時点でのDeFiにおけるTVLランクでTOP4にPolygonがランクインしています。(イーサリアムを除く) 上記のような背景から、多数のブロックチェーンが存在する中でも、Polygonは代表的なチェーンであると言えるでしょう。 Polygonに構築されたプロジェクト 前述の通り、Polygonでは多数のプロジェクトが構築されています。 一例として、DeFiにフォーカスを当ててみましょう。 以下が、Polygonに構築されている代表的なDeFiプロジェクトの一例になります。 AAVE (レンディング) Quickswap (DEX) Curve (DEX) Uniswap (DEX) イーサリアムと互換性を持つこともあり、既にイーサリアムにおいても多数の利用者を抱えているプロジェクトが多数確認可能です。 また、Polygonに構築されているプロジェクトは、DeFiに限りません。 代表的な例として、著名なBCGであるThe SandboxはPolygonへの移行を発表しており、イーサリアムからPolygonにトークンをブリッジする機能などが公開されました。 上記はあくまで一例で、この他にも多数のプロジェクトでPolygonへの移行や構築が発表されています。 Polygonの使い方(ブリッジなど) ①ウォレットと入金 (イーサリアム→Polygon) ②各サービスの接続と利用 ③Polygonからの出金 (Polygon→イーサリアム) これから、Polygonの使い方について上記のポイントから解説していきます。Polygonを利用できるようにしていきましょう。 ①ウォレットと入金 (イーサリアム→Polygon) Polygonを利用するには、はじめにPolygonのチェーン上で、仮想通貨を利用できる状態にする必要があります。 以下がかんたんな手順です。 ウォレットと仮想通貨の準備 ウォレットのネットワーク設定を済ませる イーサリアムからPolygonへ転送(ブリッジ) 上記の手順を完了することで、Polygon上で各仮想通貨が利用できる状態になります。 ウォレットのネットワーク設定やブリッジなどの細かな手順は、以下の記事で解説しています。 METAMASKでのMatic(Polygon)ネットワークへの接続方法を解説 ②各サービスの接続と利用 Polygonが利用できる環境が整ったら、Polygonに構築されているプロダクトを利用していきましょう。 基本的に、各プロダクトとウォレットを接続するだけで利用可能です。よくある流れは以下のとおりです。 利用したいサイトやプロダクトにアクセス ウォレットと各サイトを接続 機能やサービスを利用 前提となる環境(ウォレットなど)が整えば、イーサリアム上に構築されたプロダクトを利用するのと大きく手順は変わりません。 一例として、Polygonの代表的なDEXである「QuickSwap」の使い方を以下の記事で解説しています。 分散型取引所「QuickSwap」の特徴や基本的な使い方を徹底解説! ③Polygonからの出金 (Polygon→イーサリアム) Polygonからイーサリアムに資金を移動させる場合(出金)も、入金と大きく変わりません。 ①で説明した方法と逆の手順で、Polygonが提供するPolygon Bridge等でPolygon上の通貨をイーサリアムに戻します。 Polygonのブリッジには、入金・出金のどちらのケースでも、PoSブリッジ・Plasma ブリッジの2種類が存在しています。 双方にはセキュリティや対応している規格などに違いがありますが、利便性の観点などからPoSブリッジを選択することが一般的です。(PolygonもPoSを推奨) 一方で、Plasmaはよりセキュリティを重視する開発者向けのブリッジになっており、一般利用では触れることは無いでしょう。 Polygon(Matic)の将来性とリスク 最後に、Polygonの将来性やリスクについてチェックしていきます。 ・L2ソリューションとトレンド ・Polygon関連の他のソリューション ・予期せぬトラブルとリスク Polygonの今後の可能性と共に、注意点もチェックしていきましょう。 L2ソリューションとトレンド 現在、Polygonは非常に大規模なプラットフォームですが、将来的にその地位が保証されているのか?は不明です。 というのも、Polygonに限らず、現在多数のL2ソリューションが登場しており、潜在的に競合となり得る存在が多数存在しているためです。 例えば、ロールアップ系のL2ソリューションが注目を集めつつあります。 (ロールアップの1つであるArbitrum oneのTVL L2BEATより) 今後も、他のL2ソリューションと合わせて動向を見守っていく必要があるといえるでしょう。 ・L2ネットワーク「Arbitrum One」の概要や設定方法、基本的な使い方からリスクまで徹底解説! ・次の重要ワードか |「zkSync」の特徴や使い方を徹底解説! Polygon関連の他のソリューション PolygonのPoS・Plasmaを採用したサイドチェーンは、Polygonが提供するソリューションの1つに過ぎません。 その他にも、Polygonは多数のスケーリングソリューションを開発しています。 例えば、EVM互換を実現するゼロ知識証明を採用したロールアップ(Polygon zkEVM)なども開発しており、2022年Q3にテストネット、2023年初頭にはメインネットがローンチされる予定になっています。 今後、複数のソリューションが、Polygonから提供されていく可能性は高いでしょう。 予期せぬトラブルとリスク Polygonに限った話ではありませんが、仮想通貨関連のプロジェクトでは、潜在的なリスクが多数存在しています。 Polygonのホワイトペーパー(Matic network whitepaper)では、代表的なリスクとして以下のようなものが挙げられています。 各国の法規制と執行 競合の登場 開発の失敗 脆弱なセキュリティと攻撃 また、PolygonはイーサリアムのL2ソリューションであり、Polygonに入金した仮想通貨はイーサリアムネットワークへ出金することが可能です。 しかし、ブリッジ(入金した仮想通貨)した仮想通貨は、厳密にはイーサリアムで扱われている仮想通貨とは異なります。 Polygonに致命的な問題が発生した場合には、Polygonに入金した仮想通貨もリスクに晒される可能性があるという点は押さえておきましょう。 まとめ この記事では、Polygonについてさまざまなポイントを解説しました。 Polygonには、イーサリアム発のプロジェクトを含めて、魅力的なプロジェクトが多数構築されています。 ガス代の高さなどから、dAppsの利用をためらっていたという方も、Polygonなら気軽に利用できるかもしれません。 Crypto Timesでは、Polygon関連の最新ニュースなど、以下のようなPolygonに関するトピックも扱っているので是非読んでみてください。 InstagramがNFTシェア機能を実装 | EthereumとPolygonが対象 FilecoinとPolygonStudiosがコラボ。助成金やハッカソンで開発者を支援 Magic Eden、Polygonに対応 | 使い方の解説記事、動画を運営が公開 最後まで読んでいただきありがとうございました。

プロジェクト
2022/08/03注目L1チェーン「Sui」とは?概要や特徴を解説
400億円以上を調達したL1チェーンAptosの競合として挙げられる事が多いのが「Sui」です。 Suiは、a16zなどから50億円近い資金を調達しており、今後数ヶ月以内にメインネットのローンチも予定されています。 また、元Diemのメンバーが中心になって開発されているの加えて、Moveを採用するなど話題のAptosとの類似点も多く見られます。 本記事では、そんな注目のSuiについて以下のような内容を解説していきます。 記事内容まとめ ・元Diemメンバーにより開発されMoveを採用 ・オブジェクトを中心とした設計 ・12万TPSを記録する高い処理能力 ・他チェーンのNFTを移植できるツールも ・年内にメインネットのローンチの可能性あり Sui = Moveを採用した新たなL1チェーン Suiとは、Mysten Labsが開発しているL1チェーン(レイヤー1)や、プロジェクトの総称です。 ネイティブトークンはSUIであり、100億枚で供給がストップします。 Suiを開発しているMysten Labsには元Diemのメンバーが複数在籍しています。Diemとは、Meta社(旧Facebook)が主導していた仮想通貨関連のプロジェクトで、発表当初は注目が集まっていたものの、当局からの懸念などによって現在は開発が中止されています。 Mysten LabsのCEO・共同創業者であるEven Chengは、Apple社・Meta社に16年に渡り勤務しており、Diemの開発にも携わっていました。 その他のCTO・CPOなどの重役にも、元Meta社のメンバーが名を連ねています。 また、Mysten Labsはa16zが主導した資金調達で、2021年12月に3,600万ドル(約48億)の調達に成功しています。 https://twitter.com/Mysten_Labs/status/1467903477393158147 詳しくは後述しますが、数ヶ月以内にメインネットがローンチされる可能性もあり、注目が高まりつつあります。 Suiの3つの特徴 これから、Suiの特徴について以下の3つのポイントから解説していきます。 ・高い処理能力 ・プログラミング言語「Move」を採用 ・利用者に優しい設計と技術 Suiの持つ強みやポテンシャルをチェックしていきましょう。 高い処理能力 Suiは、高い処理能力を持っており、その背景にはさまざまな技術的なアプローチが挙げられます。 Suiの発表によると、8コアのM1・Macbook Proを利用したバリデーターで「1秒あたり12万のトランザクション」を実行できたようです。 トランザクションの内容はトークンの転送という単純なものだったようですが、事実なら驚きの処理能力でしょう。 このような性能を実現している背景にはさまざまな技術・工夫が挙げられますが、コアとなる技術の1つに「トランザクションの種類による処理の分離」が挙げられます。 Suiでは、他の要素やアドレスに影響を与えないようなシンプルなトランザクションに対しては、一般的なブロックチェーンで利用されているような厳格なコンセンサスが不要です。 その代わりに、コンセンサスアルゴリズムよりも簡易的な別のアルゴリズムを使用します。 これにより、一般的な用途(トークンの作成や転送など)では、厳格なコンセンサスを通す必要がありません。 一方で、他の要素やアドレスに影響を与えるような複雑なトランザクションに対しては「Narwhal and Tusk」という技術をベースとしたコンセンサスアルゴリズムでの検証が必要です。 このように、一般的なユースケースと複雑なトランザクションを処理する際の流れを別けることにより、効率的にトランザクションが処理されるようになっています。 上記はあくまで簡略化したもので、Suiはオブジェクトを中心に設計されていることから、トランザクションが影響を与えるオブジェクトの種類によって一連の過程は異なります。(各オブジェクトの種類などについては、コチラをご覧ください。) プログラミング言語「Move」を採用 Suiでは、開発を行う際のプログラミング言語にMoveを採用しています。 イーサリアムにおける「Solidity」にあたる存在です。 Moveは、Diemのプロジェクトで開発されたプログラミング言語で、同じく元Diemメンバーによって開発されているAptosなどでも採用例があります。 Suiのドキュメントでは、安全性や拡張性の観点からMoveはSolidityを上回るとしています。 Moveを採用していることにより、SuiはEVMとの互換性を持ちません。 また、Suiが採用しているMoveには若干の改良が加えられており、Suiに関連するドキュメントなどでは「Sui Move」とも呼称されています。 ただし、ベースはMoveとなっているため、一部を除いて他のシステムでも利用されていたMove用コードはSuiでも実行可能で、大まかな仕様・特徴は通常のMoveと変わりません。 利用者に優しい設計と技術 Suiでは「アカウント作成よりも先にアセット(トークンなど)を送信できる」ようになる可能性があります。 詳細は明らかになっていないものの、先にアセットを送信でき、その後にアカウントを作成するといった機能が近日公開されるようです。 恐らく、ブロックチェーンにはじめて触れるような層を対象とした機能と見られます。 上記に加えて、何に許可を与えるのか明確にした人間が読みやすい署名要求など、利用者に優しい設計が行われています。 SuiとAptosなど他のMove系プロジェクトの違い Suiの類似のプロジェクトとして、Aptosが挙げられる事が少なくありません。 Sui・Aptosともに元Diemメンバーによって開発されており、Moveを採用しているなど類似点が多いためです。 しかし、SuiとAptosは同じMoveを採用しているものの、オブジェクトモデルに異なる点があります。 また、他のMove系プロジェクトとの違いについても、他のMove系プロジェクトがアカウント中心の設計である一方、Suiはオブジェクト中心の設計である点を挙げています。 というのも、Suiでは全ての要素(トークンやNFTなど)がオブジェクトに組み込まれており、この特性が前述したような処理能力を実現している要因です。 このようなオブジェクト関連の扱い方が、Aptosや他のMove系のプロジェクトとの違いになっています。 話題のL1チェーン「Aptos」とは?概要や特徴を徹底解説【480億円調達済】 Suiの利用例・ユースケース Suiでは今後数ヶ月程度で構築可能になるプロダクトやユースケースについて、以下のようなものを挙げています。 ・ゲーム ・DeFi ・ソーシャルメディア Suiの利用例・ユースケースをチェックしていきましょう。 ゲーム Sui関連のAMAやドキュメントでは、しばしばゲームに関する記述や発言が見られ、今後力を入れていく可能性が高いです。 実際に、ゲーム開発向けのSDKも提供される予定となっています。 SDKとは、アプリケーションを開発する際に必要なツールをまとめたパッケージのようなもので、SDKがあることで開発における利便性が向上します。 ゲーム開発向けのSDKを活用することで、SuiやMoveに関する専門的な知識が無くとも、Sui上にゲームが構築できるになるようです。 また、Suiは開発者向けに複数のツールを提供していますが、ゲームやNFT関連のユニークなものの1つに「SuiEcho」が挙げられます。 SuiEchoは、他のチェーンにあるNFTの所有権を証明することにより、Suiチェーン上でも同じNFTが扱えるツールです。 以下が、実際にSuiEchoを活用し、ゲーム内のアバターにNFTを使用した例になっています。 https://twitter.com/Mysten_Labs/status/1507000994080591872 上記はSuiEchoを活用した1つのユースケースに過ぎず、SuiEchoのようなツールを活用して、今後もさまざまなゲーム・プロダクトが出てくる可能性があるでしょう DeFi Suiについても他のチェーンと同様に、一通りのDeFi関連のプロトコル・プロダクトが整備されていく可能性が高いです。 今後、他のチェーンでもあるDEXやレンディングが利用できるようになっていくでしょう。 Suiの特性を活かし、低遅延・低コストの金融取引が可能になっていく可能性があります。 ソーシャルメディア Suiのドキュメントでは、分散型ソーシャルメディアが構築される可能性も挙げられています。 既存のソーシャルメディア同様に投稿やいいねなどが可能で、プライバシーに配慮されたソーシャルメディアが構築可能になるようです。 SocialFiを代表するようなプロダクトが、Suiチェーンに誕生するかもしれません。 Suiのロードマップ(今後について) これから、Suiのロードマップなどについて解説していきます。 Suiの今後の予定やメインネットのローンチなどについてチェックしていきましょう。 devnetは実施済み Suiのdevnetは2022年5月にローンチされており、既に実施済みとなっています。 devnetは、Suiの実験や初期開発者に向けた一番初めに公開されるネットワークにあたります。 後述するテストネットの発表も行われているため、恐らく順調に稼働しており大きな問題は発生していない可能性が高いでしょう。 インセンティブテストネットは8月から devnetを経て、より多くの層を対象としたテストネットが2022年8月からスタートします。 上記のテストネットは、メインネットに向けた最終段階のネットワークです。 We're happy to share that registration to participate in Sui Incentivized Testnet is now open! If you are a validator, developer or Sui Enthusiast, we highly encourage you to apply. You can read about the details HERE: https://t.co/C60gjka1zC pic.twitter.com/OPUinr2K94 — Sui by Mysten Labs (@Mysten_Labs) August 2, 2022 現在、テストネットの登録が開始されており、必要事項を記入することでテストネットの参加申し込みが可能となります。 メインネットのローンチは数ヶ月以内? Suiのメインネットがローンチされる時期・日付は、まだはっきりとしていません。 ただし、4月に更新されたSuiのロードマップを参考にすると、今後数ヶ月以内に実施されるものの中に、メインネットのローンチという情報が確認できます。 このことから、テストネットなどが順調に稼働すると、数ヶ月〜年内にはメインネットがローンチされる可能性が高いでしょう。 ただし、はっきりとした時期が発表されている段階ではないため、動向を注視していく必要があります。 まとめ 本記事では、Suiについてさまざまなポイントから解説しました。 類似のプロジェクトであるAptosと比較すると、注目度が低い面は否めないものの、Suiも大きな魅力を持ったプロジェクトです。 今後、テストネットの実施やメインネットが近づくにつれて、よりプロダクトが出てくる可能性も高いので、今後も動向に注視していきましょう。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 - Sui 公式リンク - 公式サイト:https://sui.io/ ホワイトペーパー:https://github.com/MystenLabs/sui/blob/main/doc/paper/sui.pdf Twitter:https://twitter.com/mysten_labs Medium:https://medium.com/mysten-labs Discord:https://discord.com/invite/sui





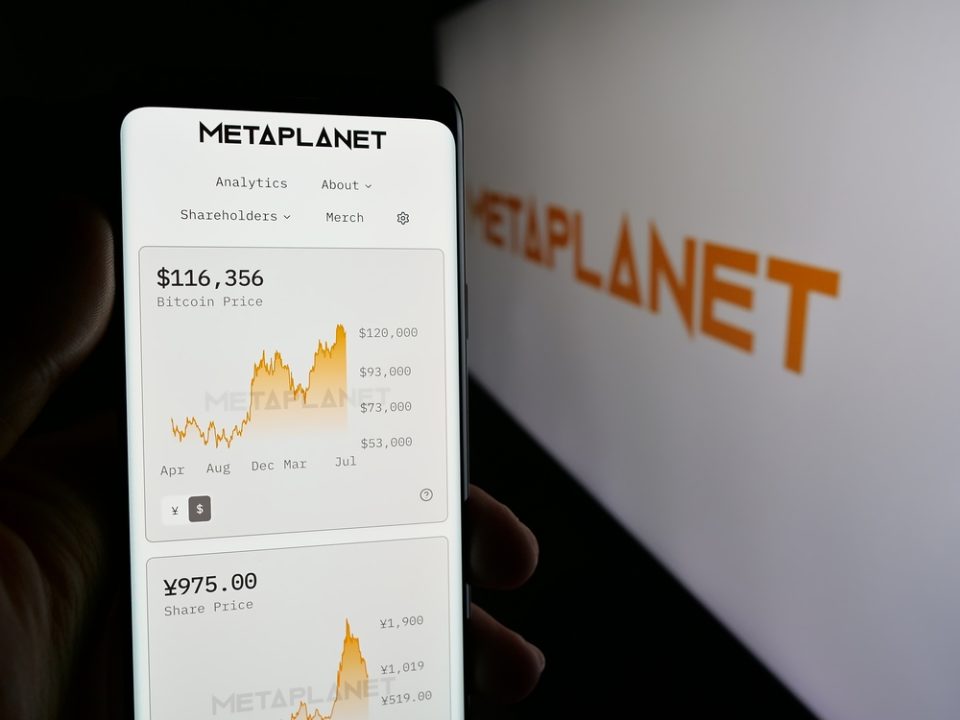





 有料記事
有料記事


