2017年5月に仮想通貨への投資を開始。ブロックチェーンや仮想通貨の将来に魅力を感じ、積極的に情報を渋谷で働く仮想通貨好きITリーマンのブログを通じて発信するように。
最近書いた記事
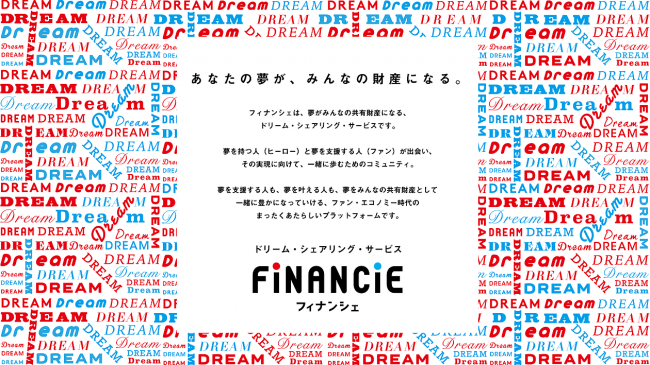
ニュース
2019/03/08ブロックチェーン上で個人をカード化できる『FiNANCiE(フィナンシェ)』のオープンβが公開
株式会社フィナンシェによる"誰かの「夢」がみんなの財産になるSNS"と題した次世代型SNS「FiNANCiE」のオープンβが2019年3月7日(木)にリリースされました。FiNANCiEの正式リリースは5月を予定しており、年内にアプリ版、グローバル版のリリースも予定しています。 既にオープンβでは、運営側で選んだヒーローが10名おり、ユーザーはログインすることでサービス利用が可能となっています。 FiNANCiE Webサイト FiNANCiEを通じたファンエコノミーの仕組み [caption id="attachment_33631" align="aligncenter" width="650"] FiNANCiEスマホ向けイメージ[/caption] 今回リリースされたFiNANCiEでは、叶えたい夢を持つ人をヒーローと呼び、ヒーローはフィナンシェ内にて「ヒーローカード」を発行ができます。参加ユーザーは、ヒーローが発行したカードを取引することで、その売上の一部がヒーロー活動資金となります。 ユーザーは、ヒーローへのファン活動を通して、貢献することでスコアを獲得し、獲得スコアに応じて、コミュニティ内での権限も上がっていく仕組みになっています。更にこのコミュニティ内での権限が上がることで、所属のコミュニティ自体の価値も上がり、ヒーローカード自体の価値も上がっていきます。 ユーザーがヒーローカードを獲得するための2つの方法 今回、ユーザーが、ヒーローカードを入手するためには2つの方法が存在しています。 そのうちの一つとして、新規にヒーローカードが発行されるときに行われるダッチオークション形式での販売が存在します。 [caption id="attachment_33637" align="aligncenter" width="638"] 画像引用 : Qiita「ブロックチェーンで人をカード化して売買できるサービスを作ったので解説する」より[/caption] ダッチオークション形式を採用することで、お金持ちが大量にカードを買い占めて、人々に行き渡らないことを防ぐことを目的としているようです。ダッチオークション形式の仕組みは2017-2018年のICOでも多く見られた手法でもあります。 すでに一部のヒーローではダッチオークション形式でのカードの販売も実際に行われています。 [caption id="attachment_33647" align="aligncenter" width="827"] FiNANCiEオークションページ[/caption] ユーザーがカードを獲得するためのもう一つの方法であるマーケットプレイスでは、Bancorの仕組みを利用して実装がされています。Bancorの仕組みを利用することで、流動性の問題を解決しているとしています。 Bancorの良いところは、いつでもおおむね無条件に売り買いできることです。スマートコントラクトを自販機のメタファーで解説することがありますが、Bancorはまさに自販機です。売る人が多ければ単価が下がり、買う人が多ければ単価が上がる自動ロジックのおかげで、買いたくても買えない、売りたくても売れないという流動性問題をある程度解消することができます。 特に、超有名人でもない限り、毎日毎日注目を浴び続けるわけはなく、そのような状態ではカードを売りたくても買ってくれる人が見つからなかったり、その逆も容易に起こりえます。これを解消するためにBancorによるマーケットプレイスを開発しました。 FinancieにおけるBancorの利用はちょっと特殊で、普通はネイティブトークンと呼ばれるETHとなにかを交換することが多いのですが、今回は都合でJPYとペッグした内部トークンとBancorのスマートトークン、スマートトークンとヒーローカードを2回交換しています(数式上は1回の場合と挙動が変わらない) 文章引用 : Qiita「ブロックチェーンで人をカード化して売買できるサービスを作ったので解説する」より ヒューマンキャピタリスト フィナンシェではヒーローの夢を協力に応援する「ヒューマンキャピタリスト」が存在します。 過去、企業への投資を行なってきた投資家たちが誰かに夢を託すという生き方で自分の夢を実現するため「ヒト」への支援をおこなっていくようで、幻冬舎 箕輪厚介氏やエンジェル投資家の古川健介(けんすう)氏、MERYの元創業者でもある中川綾太郎氏などが参画しています。 記事参考 : Qiita「ブロックチェーンで人をカード化して売買できるサービスを作ったので解説する」 , PR TIMES

ニュース
2019/03/04CoinDeskライセンスを取得した国内メディア「CoinDesk Japan」が本日3月4日創刊
Zコーポレーション株式会社が出資するN.Avenue(エヌアベニュー)株式会社と同社の子会社として2019年2月に設立したCoinDesk Japan株式会社の両社は、世界有数の専門メディア「CoinDesk.com」を運営する米国CoinDesk Incからライセンスを取得し、ブロックチェーン・仮想通貨に関する国内向けのWEBメディア「CoinDesk Japan」を本日3月4日に創刊しました。 CoinDesk Japanは、業界が今後、大きく発展していくために、ブロックチェーンや仮想通貨の可能性や価値を信頼性の高い情報を正しくより多くの層に分かりやすく届けることで、業界の健全な発展に寄与することを目的としています。 今後、「CoinDesk Japan」編集部による国内の企業、専門家などへの取材を通した日本オリジナルの記事や、「CoinDesk.com」から提供を受ける世界のニュースを日本ユーザーに分かりやすいよう補足した翻訳記事などを配信予定のようです。 [caption id="attachment_33385" align="aligncenter" width="800"] CoinDesk Japan Topページ創刊特集より[/caption] 現在、創刊特集として、『ブロックチェーン“価値革命”の新時代へ』と題した特集が組まれており、8本のインタビューが組まれ、本日3月4日から3月12日にかけて、順次公開されていきます。 創刊当日分のインタビューには慶應義塾大学経済学部教授の坂井豊貴氏、CAMPFIRE代表の家入一真氏へのインタビュー記事が公開中です。

ニュース
2019/03/04BitPointで新規口座を作って、リップル $XRP 最大10000円相当を獲得しよう!
株式会社ビットポイントジャパンが、平成最後の新規口座キャンペーンと題して、期間中に新規に口座を開設したユーザーに最大10000円相当分のリップルがもらえるキャンペーンを実施しています。 今回のキャンペーンでは、3月1日〜3月29日の期間内に新規に口座開設と入金を行うことで2000円相当分のリップルを、また取引量に応じて8,o00円のリップルがプレゼントされるようになっています ※本キャンペーンは終了しています。最新のキャンペーンは公式サイトをご確認ください BitPointの登録はこちら BITPointの登録方法はこちら キャンペーン期間 : 【口座開設】2019年3月1日(金)~ 3月29日(金) 【ご入金・お取引】2019年3月1日(金)〜2019年4月5日(金) キャンペーン対象 : 口座開設と10万円以上ご入金で2,000円相当のリップルをプレゼント。 さらにお取引金額に応じて最大8,000円相当のリップルをプレゼント。 プレゼント内容: ①口座開設と10万円以上ご入金で2,000円相当のリップルをプレゼント。 さらに①に該当する方のうち、 ②キャンペーン期間中の現物取引約定累計金額が 50万円以上300万円未満 ⇒ 2,000円相当のリップルをプレゼント。 300万円以上 ⇒ 4,000円相当のリップルをプレゼント。 ③キャンペーン期間中のレバレッジ取引約定累計金額が 50万円以上300万円未満 ⇒ 2,000円相当のリップルをプレゼント。 300万円以上 ⇒ 4,000円相当のリップルをプレゼント。 プレゼント進呈日 :2019年5月10日(金)を予定 https://youtu.be/Ii4mHDg1DrM BitPointの登録はこちら BITPointの登録方法はこちら ※本キャンペーンは終了しています。最新のキャンペーンは公式サイトをご確認ください
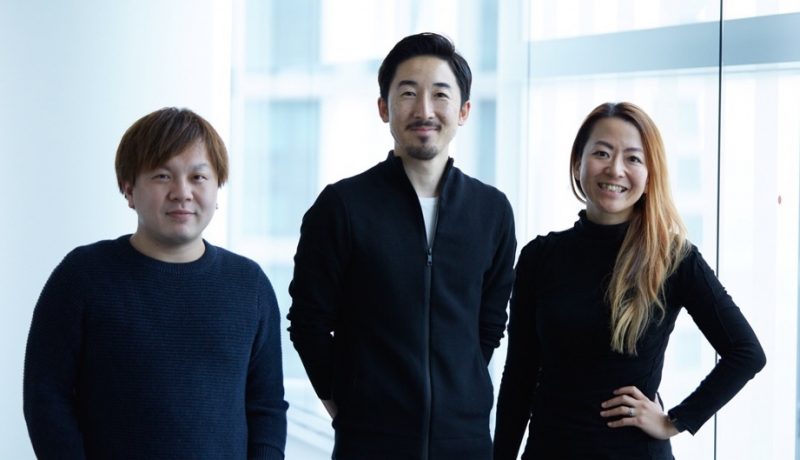
インタビュー
2019/02/28エストニア×ブロックチェーン スタートアップ事例と電子政府化の必然性
2017年よりエストニアと日本の二拠点生活を送っている、blockhive Co-Founderの日下光に、CRYPTO TIMESの協力のもとインタビューを実施。エストニアにおいてブロックチェーン領域に取り組む彼に、移住の背景、ブロックチェーンの魅力、エストニア国民が電子政府から受け取るメリットなどを聞いた。 ※ 今回のインタビュー記事は、CRYPTO TIMES のFounderである新井(アラタ)が協力の下、インタビューを実施し、株式会社電通様が運営するWEBメディアGRASSHOPPERに掲載されたインタビューの転載となります。 ブロックチェーンが生活に浸透して見えなくなっていた –エストニアにはブロックチェーンを利用したスタートアップがたくさんあるのでしょうか? 日下:エストニアはブロックチェーンこそ発達しているものの、スタートアップの数は少ないですね。最近少しずつ増えて来ています。エコシステムがあるともいわれていますが、実際にはありません。むしろそれを我々が現在、作っています。 2017年にエストニアに行ったとき、衝撃を受けたのはブロックチェーンが生活に浸透しているので見えなくなっていたことでした。これはブロックチェーンの成功例と言えるでしょう。ただ、世界的にはブロックチェーンが注目されているので、ブロックチェーンの導入がインビジブルになっているエストニアに飛び込んで、現地でそれを実体験しながら世界に向けて挑戦しています。 今テクノロジー面でのアドバイスを行っているAgrelloというリーガルテックのスタートアップがあります。創業者は19歳で司法試験に合格しましたが、ブロックチェーンの登場で、これからはブロックチェーン、スマートコントラスト、AIが弁護士の仕事を奪っていくだろう=弁護士になる意味はないと考え、この会社を創業したのです。 Agrelloは、電子署名を利用したデジタル契約書などのサービスを提供していて、紙の書類が一切不要になります。Agrelloが提供する「AgrelloID」は、エストニアのIDと同じ仕組みで、日本でもパスポートがあれば、アプリからこのAgrelloIDを作成することも可能です。国境を跨いだ二者間の契約がより簡単になりますので、我々は日本とエストニアでも利用しており相手の方にAgrelloIDの作成をお願いしたりしています。もちろん、契約の情報はブロックチェーン上に記録され、改竄もできません。 –このAgrelloのビジネスモデルはどのようなものなのでしょうか? 日下:AgrelloID発行自体は無償です。企業の導入や、自社システムへの導入時のビジネスが肝となっています。導入したい企業は、契約のプラットフォームをエンタープライズで採用し企業間で利用します。ライセンスでマネタイズするSaaS (Software as a Service) 的なイメージが近いですね。 本人性の担保としては、Agrelloが採用している電子署名を利用することで、証明を確実にすることができます。 さらには、タイムスタンプにより、契約書のサインをお願いして一週間後に紙の書類が返送されてきたなんてこともなく、どのタイミングから契約が執行されるのかわかります。 –他に関わっているブロックチェーン事例を教えてください。 日下:まだ公開前なので名前は出せませんが、保険 × ブロックチェーンで進んでいるところがあります。 エストニアでは既に個人のデータが存在するので、こういった個人が提供する情報に基づく最適化を行った保険を提供していくことが可能となります。そこで、保険にかかわる情報を個人に帰属させるという企業向けアドバイスを我々で行っています。 日本では、行政間での連携が取れていないだけでなく、病歴の移行やインプット・インターフェースの統一など様々な課題があります。我々はよく「データポータビリティ」と呼んでいるのですが、IoTの連携でヘルスケアのデータを自身に帰属させるような仕組みが整えば、あとはサービス・アプリケーションレイヤーでそれをどう扱うかによって、マーケットプレイス的に保険機関との連携もスムーズになっていくのではと思っています。 ブロックチェーンを使うことで、こういった個人に帰属すべき情報を不当に我々が売買できないということを担保・証明できるのも一つのメリットです。 エストニアの考え方はLocation Independent(場所からの独立) –日下さんはエストニアで構想された仮想通貨エストコイン関連でも仕事をしていましたが、その活動についても教えてください。 日下:私はエストコインの規格検討委員会に個人として入っています。前述の通り、エストニアでは行政の方々もブロックチェーンに対する理解があるためブロックチェーンエンジニアやスタートアップは歓迎されます。是非に、とエストニア行政に迎えてもらっています。 彼らは、行政を『Government as a Service』と呼んでおり、行政がインフラを作り、あとは課題も問題も熟知している民間に任せる、OSのような立ち位置にいると言っています。 私のエストニアでのキャリアはe-Residencyのアドバイザーから始まりました。これは、住民だけでなく、会社を作ることもできるボーダレスなコミュニティで、e-Residencyによって世界中の人がエストニアに起業することができるようになります。実際、エストニアにはイギリスやアメリカ、シンガポール、日本などから起業する会社も多く、独自のグローバルなコミュニティも出来上がっています。 フィジカルなエストニアはEUに属しておりユーロという通貨がありますが、バーチャルなエストニアにも通貨があってもいいんじゃないのか?とのことで始まったのがエストコインの構想です。私の役目は民間のスタートアップ側からどのように実現していくかを考えることで、現在でも続いています。 –フィジカルもバーチャルも行き来しているのがユニークなところですね。 日下:そこがエストニアの面白い点で、考え方がLocation Independent(場所からの独立)なのです。エストニアでは、衣・食・住は縛られてしまいますが、それ以外は場所に縛られない生き方として、公共財として行政が提供すべきものは平等に提供していくことで色々な人にチャンスを与えようとしています。 日本では2018年1月、電子政府化5ヵ年計画を発表しています。日本をエストニアのようにしていこう!ということで、エストニアの成功事例を日本に輸入しようとしています。 日本と違い、エストニアの電子政府化には必然性があって、九州ぐらいの大きさの土地に130万人しか住んでいない国なんです。その中で、行政サービスを国民全員に提供する道は、デジタル化しか残されていなかったんです。なぜなら、人もいなくてお金もなかったからです。 これから日本も人口縮小し、過疎地が増えることも予想されます。なのでエストニアの仕組みを導入するのは必要なのですが、その前提となるマイナンバーの普及率もまだ10%(約1,300万人)くらいなんですよね。政府の動きと同様、国民もインターネット上で本人性を担保できるようになる必要があると考えております。 –電子政府時代を迎えるにあたり、企業はどのような準備をすべきでしょうか? 日下:いままさに我々でやっていることの一つで、日本が電子政府化する前提で日本企業をエストニアに誘致しています。 我々社内では『Back to the Future』プロジェクトと呼んでいるのですが、エストニアでは、Xroadのおかげで行政基盤と連携したビジネスを作ることができていて、行政と民間企業は切っても切り離せない状況にあります。様々なサービスがありますが、既に3,000社以上が行政のサービスと連携しています。 もし、日本でも電子政府が実現するのであれば、これに備える必要があると考えています。日本企業が行政と連携したサービスを現状で作る方法としては、エストニアに行ってしまうことが近道になります。 エストニアには法人が作れる上、130万人の個人のデータも存在しているので、アルゴリズムだったり機械学習のモデルだったり、国民のデータを活用することも可能です。例えば、ある製薬会社などが、いずれは厚生労働省などと連携して医療費の削減をしたいと考えたとして、エストニアに行き、処方箋の電子データを活用したサービスを考えることも可能です。 日本での電子政府というアイデア自体が、エストニアの技術を日本が採用して作っていて、マイナンバーもこれらを参考・活用しているので相互互換性が生まれます。そういった意味でも、将来的な日本の電子政府化が完了し次第、エストニアから技術を戻す『Back to the Future』なのです。 −−最後に日本でブロックチェーンをこれから活用しようとしている方々向けにコメントいただけますか? 日下:まだ信用のないスタートアップが何かサービスを作るとき、特にフィンテック・サービスを作る際にはブロックチェーンテクノロジーを活用していくべきだと考えています。自分たちが作るサービスがスケールする際に、信用コストが求められるかどうかがYESなら検討していくべきでしょう。 データを中央集権的に集めてそこでマネタイズではなく、その主権を個人に戻す思想があるサービスであればブロックチェーンは最適です。 個人的に、Freemium戦略の次に現れたのがブロックチェーンだと思っています。みなさまのビジネスでブロックチェーン採用を考える上で「データの保管をどこにおくのか?」を考えるのが重要です。もしもデータを個人に戻すのではなく、自分の会社で管理したいと思うのであればブロックチェーンは不要なのでバズワードとしての「ブロックチェーン」という言葉も使わないでほしいぐらいです。収益性とかエンジニアの単価などを見ても、データの保管や思想がないのであれば、ブロックチェーンを使わない方が圧倒的に安く済みます。 ブロックチェーンは哲学を実現することのできる一つのツールですから、収益性などの観点からではなく、自分がどのような世界を実現したいのか?を 考えた上で活用していく方々が増えていくことを期待します。 エストニア在住日本人 blockhive 日下光 に聞くブロックチェーン事情 〜データ主権を個人が持つ魅力 - CRYPTO TIMES Interview & Text:西村真里子 Edit:市來孝人 協力:CRYPTO TIMES 新井進悟 転載元記事 : エストニア×ブロックチェーン スタートアップ事例と電子政府化の必然性 - GRASSHOPPER

インタビュー
2019/02/27エストニア在住日本人 blockhive 日下光 に聞くブロックチェーン事情 〜データ主権を個人が持つ魅力
2017年よりエストニアと日本の二拠点生活を送っている、blockhive Co-Founderの日下光に、CRYPTO TIMESの協力のもとインタビューを実施。エストニアにおいてブロックチェーン領域に取り組む彼に、移住の背景、ブロックチェーンの魅力、エストニア国民が電子政府から受け取るメリットなどを聞いた。 ※ 今回のインタビュー記事は、CRYPTO TIMES のFounderである新井(アラタ)が協力の下、インタビューを実施し、株式会社電通様が運営するWEBメディアGRASSHOPPERに掲載されたインタビューの転載となります。 エストニアはBitcoinが誕生する前からブロックチェーンを導入 –まず、エストニアに注目することとなったきっかけを教えてください。 日下:日本でエストニアと言えば、2017年夏に政府が構想を発表した仮想通貨エストコインで有名になったと思いますが、私は2015年からエストニアの魅力に取り憑かれておりました。 きっかけはある雑誌と出会ったことです。見出しに『エストニアは(ロシアに)領土を奪われてもデータがクラウド上にあるので存続し続ける』と書かれており、電子政府や仮想住民「e-Residency」についてなど「信用経済」をベースに行われている政府活動に衝撃を覚えました。 先立つこと2012年、TED meets NHKというイベントで、私は『The next stage of social capital』というスピーチを行い、「これから貨幣経済は終わり、信用経済になる。みんなは、お金の稼ぎ方は知っているが信用の稼ぎ方は知らない」という課題を投げかけていました。加えて、日本で信用経済をベースにしたサービスを作っていたということもあり、エストニアが心に大きく響いたのです。 –「信用経済をベースにしたサービス」とはどのようなものですか? 日下:2012年当時の我々が疑問に思っていたのが、インターネット上に「価値」ある数字が存在しないということでした。FacebookのLikeもTwitterのリツイートも、影響度としてはいいのですが「価値」ではない。 信頼や信用をデジタル上で可視化・数値化し、貨幣の代わりに信用の媒体とすることを目指して研究開発とサービス提供をしていました。今でこそ理解してくださる方が増えましたが、当時は早すぎたのですね。なかなかビジネスとして立ち上がるのが難しかったです。 VCからは沢山の話が来たのですが、我々はIPOする気もバイアウトを実施する気も当時はなかったので、運営資金が必要で受託開発をスタートさせました。その受託案件の一つの要件に仮想通貨が含まれておりその際にBitcoinのホワイトペーパーを読み衝撃を受けました。自分たちがもっていた思想が、タイムスタンプや単調性データ構造などでアーキテクチャーとして確立されていて、そこからもうどっぷりはまってしまいました。当時2013年で、そこから2016年末まではブロックチェーン開発案件だけがどんどん増えていきました。 –当時はどのようなブロックチェーン案件が多かったのでしょうか? 日下:金融の取引所とかペイメントが多かったですね。あとは、Ethereum系のプロジェクトで、ICO(仮想通貨の新規売り出し)が始まる前から不動産や再生可能エネルギーのスマートグリッドの話が少しずつ出てきていました。 国際送金に仮想通貨のペイメントを使うとか、ブロックチェーンを使って日中の不動産の送金に仮想通貨を使えないかとか、社内のポイントシステムにブロックチェーンを使う実証実験プロジェクトが多かったです。 –その後、日下さんがエストニアに移住した経緯を教えてください。 日下:私がエストニアに移住したのは2017年ですが、当時の日本はブロックチェーンといえば仮想通貨一色でした。私がブロックチェーンの魅力と考えている「個人のエンパワーメント」「個人に主権を渡すこと」「中央に拠らない仕組みづくり」が日本に浸透するにはまだまだ先だと感じ、ブロックチェーンを使って実現できているところはあるかと探したらエストニアだったのです。 電子政府と呼ばれるエストニア政府は20年近く、ハッキングなどの被害を受けずに運営され続けているという事例があります。実はBitcoinが誕生する前にエストニアではブロックチェーンを導入しているんです。 エストニアではまさに広義の意味でのブロックチェーンを使っています。ここでの広義というのは、ブロックチェーンで改竄を防ぐタイムスタンプや、要素の一つである分散性を利用しているということです。 エストニアでは各省庁のデータベースにこれが利用されていますが、その各省庁のデータベースはそれぞれ別個です。一般的に言われているブロックチェーンでは、それぞれが同じデータを持っていて、違ったデータが見つかればそれを間違った、不正な情報として検出できる仕組みになっていると思いますが、エストニアの場合、情報は複製されていません。 エストニアの国民は生まれた瞬間から、ここに自分の情報が記録されていきます。その運用原則は『Once-Only Principle』と呼ばれ、自分に紐づく情報がそれぞれ必要な場所にのみ保管され、決して重複して複数の場所に保管されることがないという仕組みです。要素技術として以下の技術が採用されています。 まず、x-roadと呼ばれる、各省庁がデータを連携しあうためのデータ連携基盤があり、そして、e-idと呼ばれる電子IDに自分のすべてのデータが紐づいています。例えば、住民票の情報はここ、保険の情報はこの省庁といった具合に各省庁で保管されていて、金融庁が〇〇のデータが必要といった場合には各省庁への問い合わせを行います。 しかし、文字通り自分の個人情報は自分のものなので、データのアクセスに対する許可は自分自身で出します。自分の情報が各省庁に分散されて、暗号化されて保管されていますが、これを復号化できるのは自分だけなのです。 また、ポータルサイトがあって、自分の情報の変更はすべてそこで行うことができます。仮に誰かが自分の情報にアクセスした場合も、誰がいつどこでアクセスしたかがタイムスタンプで記録されています。ここには、KSIブロックチェーンと呼ばれるものが利用されています。 例外は警察です。警察は全員タブレットを持ち歩いていて、彼らが持つIDを使ってログインすることで、特権を使ってデータにアクセスすることが許可されます。でも例えば、警察官が仮に一日に3度自分のデータにアクセスしていた場合、自分側ではポータルを使うことで、いつ何回警察からのアクセスがあったのかがわかるような仕組みになっています。 これらは、すべて個人単位のe-idにより管理されているので、連続して二つの病院に行った場合でも、入った瞬間に「前の病院で何か不満がありましたか?」と聞かれ、カルテの情報もすべて保管されているので、もう一度同じことを説明する必要はありません。 すべて自分自身に紐づくので、自分のデータを誰が扱っているのかというのが見えるという特徴があります。先生が自分の情報に不用にアクセスしている場合、これはrevokeといってそれをClaimすることで、その人はアクセスできないように設定も可能です。これは、データの主権が個人にあるからで、まさにブロックチェーンの特徴を使ったものになっています。 分散型で情報が透明になり、誰かを無理に信用する必要がない –現在、日本の上場企業のブロックチェーン採用率は高いのでしょうか? 日下:実際の数はまだ少ないと思います。例えば、銀行が導入するとなると基幹システムなどのスイッチングコストがかかってしまうので。本質的に、信用のある企業がブロックチェーンを使うメリットはさほどないと考えております。無名のスタートアップが銀行業を行う際にはブロックチェーンはいいかもしれないです。 –どういう企業・団体がブロックチェーンを活用するには適しているのでしょうか? 日下:地方でしょうか? 例えば、行政単位ではなく民泊とか商店街の人たちがコインを作る際には分散型ガバナンスで特定の誰かがデータを持つ必要がなくなるのでブロックチェーンは有効だと考えます。 –日下さんの考えるブロックチェーンの魅力を改めて教えてください。 日下:元々、インターネットはもっと個人のエンパワーメントができるツールだと考えていました。これは、マスメディアの発信やコントロールから離れ、Socialによって個々人が情報の発信源になることができるからです。 フェイクニュースなどの問題はありますが、私は個人のエンパワーメントにワクワクしていました。しかし結果は、GAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)を中心に一部の人々だけが情報をコントロールできていて、情報へ対するアクセシビリティはありません。ここに平等性や公平性は全くないと思っています。 それがブロックチェーンの登場により、『正直者が馬鹿を見る』という昔から抱えているフラストレーションを解消できると思いました。ブロックチェーンは特定の権力でコントロールできない情報の透明性を担保し、より個人が正直者になれる仕組みであると魅力を感じています。 あとは、信用コストという言葉についてよく話しているのですが、人間はお互いを信用することが常にボトルネックになっています。信用できる仲間と仕事すると生産性がものすごく高くなりますが、信用できない仲間の場合には週次レポートや定例ミーティングでの進捗確認などにコストを割く必要が出てきます。ブロックチェーンを導入すると、分散型で情報が透明になるので特定の誰かを無理やり信用する必要がありません。 一点だけ気を付けなければいけないのが、ブロックチェーンは定義がないんです。日本だと、ブロックチェーン技術は”Blockchain Technology”と訳されることが多いですが、海外だとこれは”Blockchain Technologies”と訳されます。 例えばインターネットにおいてインターネットは一つしかないので”Internet”ですし、httpのプロトコルも一つのプロトコルしかありません。しかしブロックチェーンの場合、1970年代くらいからある技術を全部総称し、その複合がブロックチェーン技術になります。 例えば、EthereumとBitcoinっていうのは完全に別々で、インターネットで例えるならhttpとTCP / IPくらいの差があります。イメージで言うと、ウェブサイトはみんな”http://www~~~/”に展開されますが、TCP / IPのプロトコルにアップしても、パブリックには誰も見てもらえません。 今は、一つの単一のブロックチェーンがあるわけではなく、定義としては固まっていない広義のブロックチェーンの定義をすり合わせていっているのが現状です。 –ありがとうございます。後編ではエストニアのスタートアップについて教えてください。 Interview & Text:西村真里子 Edit:市來孝人 協力:CRYPTO TIMES 新井進悟 転載元記事 : エストニア在住日本人に聞くブロックチェーン事情 〜データ主権を個人が持つ魅力 - GRASSHOPPER

ニュース
2019/02/18IOST 日本Node候補者 一問一答インタビュー -AiyaaNet-
2019年2月25日にメインネットをリリース予定のブロックチェーンプラットフォームであるIOSTは現在、ノード候補者を選挙で選出しています。 CRYPTO TIMESでは、IOSTのメディアパートナーとして、今回より数回に渡り、日本のノード候補者に対してのコメントを貰ったので掲載していきたいと思います。 ノード候補者がどんな事を考え、IOSTエコシステム拡大に向けて何をしようとしているのかを理解し、是非ともこの機会に、IOSTのノード選挙にもご参加いただけたらと思います。 IOSTのノード投票がスタート!投票者への報酬・配当も必見! - CRYPTO TIMES 第一回となる今回はAiyaaNetさんのコメントになります。 IOSTノード候補 "AiyaaNet" -- 自己紹介をお願いします。 AiyaaNetを運営しています、RYOHOといいます。 元々中国の金融IT(仕事の都合)とブロックチェーン(仮想通貨)に興味を持っていて、たまたま昨年末にIOSTを発見し「これは面白そうだ」とひとりで興奮。 色々考えて、個人の趣味でパートナーとして見切り発車全開で参加しました。AiyaaNet全然更新できていない上に一緒にやる人もまだ募集中です。気ままに中国エンタメ・IT事情を紹介するメディア一緒にやりたい方募集してます~(´・ω・`) -- IOSTは2月にメインネットローンチですが、今後1年でIOSTがどのようになっていくと思いますか? 年末までには知名度はかなり上がっていると思います。 メインネットローンチ後はIOSTをベースにしたDAppsが数多く登場し「IOSTのスマートコントラクト開発手法・実装例」に係るブログ記事がかなり増えるのではないかと(Qiitaの投稿も増えそうです) -- IOSTが他のブロックチェーンと比較した際に優れているなと思う部分はどこでしょう? ①PoBの仕組み 分散化することとIOSTの自体の普及がほぼイコールになるこの仕組みが素晴らしいです。 数百のノード立候補者がそれぞ票を集めるためにIOSTの普及に努めて、当選したらノードとなって分散化にも貢献する。一石二鳥ですよね。 ②開発者を大切にしているし、何に特化すればいいかわかってる ・スマートコントラクトの開発言語がJavaScript ・世界各国各大学への活発なハンズオンセミナーの開催 ・分散化とスケーラビリティとセキュリティ どれも捨てないための新規設計 ゲーム機もソフトが無ければただの箱、ですよね。 古臭い例えで恐縮ですが、プレイステーションがニンテンドー64やセガサターンその他に勝てたのは大きく2つ要因があったと思うんです。 ・ソフト開発がしやすかった(開発環境・開発支援が充実) ・次世代に必要な要素をちゃんとバランス良く取り込んでいた (3D特化・ディスクメディア・メモリーカード等) この2要因のおかげで、ソフトも充実、ユーザも満足できたのかなと。 (最終的な決定打はキラーソフトが出たから、だとは思いますが) IOSTのメリットもこの辺りちゃんと抑えてると思ってます。 (「ブロックチェーンにそんなの当てはめて考えるなよ!」と突っ込まれそうですが…あくまで例ということで笑) -- IOSTのエコシステムを日本で発展させるためにはどうしたら良いと思いますか? 身近なサービスをDAppsに置き換えてユースケースをどんどん作ってしまうのが良いかと思います。 (予定調整さんをIOST上で実現したら面白いなと考えてます) で、そのユースケースを元に各企業へのアプローチがかけられたらいいのかなと。 -- そのために、支援・貢献できることは何でしょうか ユースケースの企画や宣伝です(開発もできたらやりたいです) 開発者向けになるべく分かりやすく解説・紹介する活動も積極的にやりたいですね。 あと、昨今EthereumやHyperledgerを使ってみて、思ったような成果が出ずに諦めかけてる企業も「IOSTなら」と乗り出す時のお手伝いもできたらいいなと(夢です) -- これから先、IOSTに期待すること、興奮することがあれば教えてください。 今「DAppsといえばゲーム」ってくらいにETHやEOSやTRXをベースにDAppsゲームが生み出されていますよね。 でも、ゲームって本来ならDAppsの実装例の1つにしか過ぎないわけで、もっと私たちのライフスタイルに密着した別のジャンルの実装例ってあるはずなんです。 IOSTからは「今までのDAppsの常識に囚われないDApps」が多数登場することを期待していますし、それらが世界を変えていくことに興奮しています!

ニュース
2019/02/17COSMOSのATOMトークンの先物が韓国新興取引所DFLOWに2月18日に上場
2017年春にICOを実施し、これまで開発を続けていたクロスチェーンプロジェクトであるCOSMOSが2019年2月末にメインネットのローンチを迎えます。 今回、COSMOSが発行するATOMが韓国の新興取引所であるDFLOWに先物として上場することがDFLOWにより発表された。上場は2月18日予定となっており、COSMOSのメインネットがローンチされ、ATOMの移動が可能となった後、1:1の割合でスワップが可能になります。 BlockWater Capitalによりインキュベートされた取引所『DFlow』が2月7日にローンチ! - CRYPTO TIMES COSMOSは直近で、Binance DEXでもCosmos SDKを利用する旨が発表されたりと、世界的にも非常に注目がされています。今回、2年越しのメインネットローンチ、クロスチェーンソリューションということもあり、DFlowへの先物上場の価格にもかなり注目が集まると予想されます。 今回、DFlowに上場されるのはIOUで、DFlowのヘルプページでも書かれているようにリスクもあるので購入を考えている方は慎重に行うことを推奨いたします。 クロスチェーンプロトコル COSMOS(コスモス)に関して徹底解説 - CRYPTO TIMES

ニュース
2019/02/15GaudiyがシードラウンドでJAFCO、毎日新聞社、gumi國光氏などから資金調達を実施
株式会社Gaudiyが2月15日にジャフコ、毎日みらい創造ラボ、株式会社gumi会長の國光宏尚氏、山本治氏らからシードラウンドでの資金調達を実施したことを発表しました。今回の調達額や評価額は非公開とされています。 Gaudiyは2月9日にコミュニティプラットフォームGaudiy β版のローンチを行い、現在、Gaudiyチャレンジというキャンペーンも実施中です。 Gaudiy β版でコミュ活!Gaudiyチャレンジ でGaudiy Coinを獲得しよう! - CRYPTO TIMES 株式会社Gaudiyは2018年5月に設立された、「イノベーションの民主化」を理念に掲げるブロックチェーン企業です。現在、コミュニティとブロックチェーンを掛け合わせたプラットフォーム「Gaudiy」の開発(2月9日β版公開済み)と、どんなプロダクトでも簡単にトークンエコノミーを実現可能にする「Gaudiy Blockchain protocol」のプロトコル開発を行っています。 今回のGaudiyの資金調達に関して、各投資家からは下記のようなコメントをしています。 【プロフィール】 岩澤 武夫 (株)毎日新聞社:執行役員(株)毎日みらい創造ラボ:代表取締役社長(株)SYMES:代表取締役社長 慶応大法学部政治学科卒、通信社を経て85年毎日新聞社入社、福島支局、東京経済部、社長室等を経て12年6月デジタルメディア局長、17年6月から執行役員に就任。 【コメント】 私はGaudiyが持つ技術力と柔軟な発想に、これからの世の中を変える可能性を感じました。AIやブロックチェーン技術などが社会に実装されることによって、働き方、消費、金融など様々な分野が再定義される時代にあって、Gaudiy platform、Gaudiy Blockchain Protocolが取り組むフィールドは広く、設立間もない組織ながら、その技術力と事業戦略においても光るものを感じ、今回支援させて頂きました。 今後、毎日新聞社としても、Gaudiyに対し、広報や事業戦略面でも積極的にサポートして行ければと考えております。 【プロフィール】 井坂 省三 株式会社JAFCO パートナー 2007年の入社以来、新産業を創造しうる事業・テクノジーへの投資・支援を目標に活動。これまで、UUUM、フリークアウト、QUOINE、メディカルノート等の事業支援に尽力。 【コメント】 いま、私の大きなテーマの1つとして、「decentralizedという概念の具現化」がございます。コミュニティの価値は、コミュニティに参加する人達が創り感じるものであり、参加者はその貢献度に応じてインセンティブが付与される。この仕組み・思想が、Sagrada Familiaのように、多くの方に受け入れてもらえるよう、Gaudiyチームの挑戦を応援していきたいと思います。 【プロフィール】 國光宏尚 1974年生まれ。米国Santa Monica College卒業後、2004年5月株式会社アットムービーに入社。同年に取締役に就任し、映画・テレビドラマのプロデュース及び新規事業の立ち上げを担当する。2007年6月、株式会社gumiを設立。代表取締役社長に就任。2018年7月、代表取締役会長に就任(現任)。 【コメント】 ブロックチェーン革命の本質はインセンティブ革命だと思います。トークンを活用することでユーザーのロイヤリティとエンゲージメントを向上させ運命共同体化していく。Gaudiyの挑戦、応援していきます!

ニュース
2019/02/14くりぷ豚 ✗ dApps market(ダプマ)コラボイベント限定カップ『ダプマCUP』が開催!限定豚台やETHを手に入れよう
日本発のDAppsゲームである『くりぷ豚』がDAppsメディアのdApps Marketとのコラボイベントとして、『ダプマCUP』を2月14日から2月21日にかけて開催中です。 https://twitter.com/CryptOink_JP/status/1095885266991046656 期間中にレースへ参加すると限定豚台を獲得できるチャンスに加え、ETHが貰えるキャンペーンまで実施中です。この機会に是非ともくりぷ豚を遊びましょう。 DAppsゲーム「くりぷ豚」開発メンバーへインタビュー!開発秘話から今後の展望まで! - CRYPTO TIMES ダプマCUP期間中のキャンペーン dApps market限定豚台 今回のコラボイベントではダプマCUPに参加して、条件をクリアすることで限定豚台を獲得することができます。 [caption id="attachment_31819" align="aligncenter" width="800"] ダプマ限定豚台[/caption] 配布条件 : ダプマCUPへ参加し、55秒未満でクリアすれば限定豚台をプレゼント。 ※獲得は1アカウントごとに1つまで ※配布はイベント終了後、運営より対象者へ配られます 総額1ETHプレゼント 更に、今回の期間中にダプマCUPへ参加すると総額1ETHが抽選で10名様にプレゼントされます。 参加方法 : ダプマカップへ参加する レース中のスクショ(画像)をツイートにアップする スクショに関しては、レース結果の画面でも問題ないようです。 該当ツイートには、ハッシュタグ #くりぷ豚 をつけて下さい ※配布はイベント終了後に抽選を行い、運営より対象者へ配られます。 ※当選者へDMをお送りする予定ですので、DM設定の解放をお願いします。 さらにダプマからのサプライズも!? 上記のキャンペーンとは別でダプマからETHのギブアウェイなどのサプライズイベントも実施中です。 詳しくはダプマのサイトも御覧ください。

ニュース
2019/02/14確定申告支援サービスGuardianを提供するAerial Partnersが総額1.8億円の資金調達を実施!
仮想通貨の取引支援事業を提供する株式会社Aerial Partnersが、ヤフー株式会社の100%子会社であるZコーポレーション株式会社、株式会社ジェネシア・ベンチャーズ他、複数の個人投資家を引受先とした第三者割当による株式の発行し、資金調達を実施することを発表しました。今回の資金調達の総額は約1億8千万円の予定となっています。 更に、資金調達に合わせ、社外取締役として、Zコーポレーション株式会社の高田徹、ゴールドマン・サックス日本法人技術部門 元Managing DirectorのJohn Flynnが社外取締役に就任するとともに、株式会社グラコネ代表取締役の藤本真衣がアドバイザーとして就任します。 仮想通貨の税金、確定申告についてAerial Partners CEO沼澤氏が語る - CRYPTO TIMES 資金調達の目的・社外取締役就任の目的 今回の資金調達・社外取締役就任の目的として、Aerial Partnersは仮想通貨の損益計算ソフト「Gtax(ジータックス)」の開発体制を強化、仮想通貨取引にかかる確定申告サービスである「Guardian(ガーディアン)」のサービス拡充に注力するとともに、採用をはじめとする組織体制強化、ブロックチェーン技術のR&Dを含む新規サービスの開発にも取り組んで行くとしています。 社外取締役の就任においては、組織のガバナンスの一層の強化と、セキュリティを重んじた開発プロセスの整備の他、ブロックチェーン業界への技術的貢献にも注力していくとしています。 提供サービス Gtax 複雑な仮想通貨取引の損益計算を簡単に行うことができるサービスです。 国内No.1の33の取引所及びウォレット(2019年2月14日現在)に対応しており、仮想通貨取引による損益を無料で自動計算することができます。 また、2018年11月からは仮想通貨税務を行う有料の税理士版の提供も行っており、導入税理士法人・事務所数は50以上、多くの税理士事務所にも選ばれている損益計算サービスになります。税務申告にかかる帳票も無料でダウンロードすることが可能です。 https://crypto-city.net/ Guardian 仮想通貨の確定申告を丸投げできるサービスです。前年度確定申告サポート実績No.1(自社調べ)。 仮想通貨税務に精通した税理士の紹介と、仮想通貨取引の損益計算をあわせて行うことのできるサービスです。 https://www.aerial-p.com/guardian 記事ソース : PR TIMES










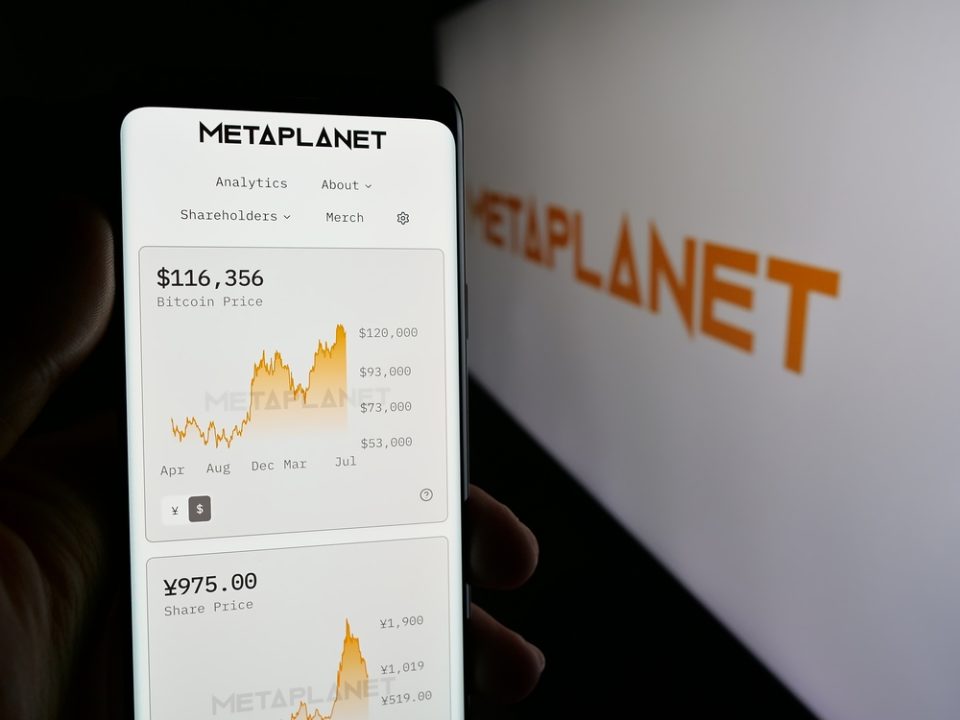

 有料記事
有料記事


