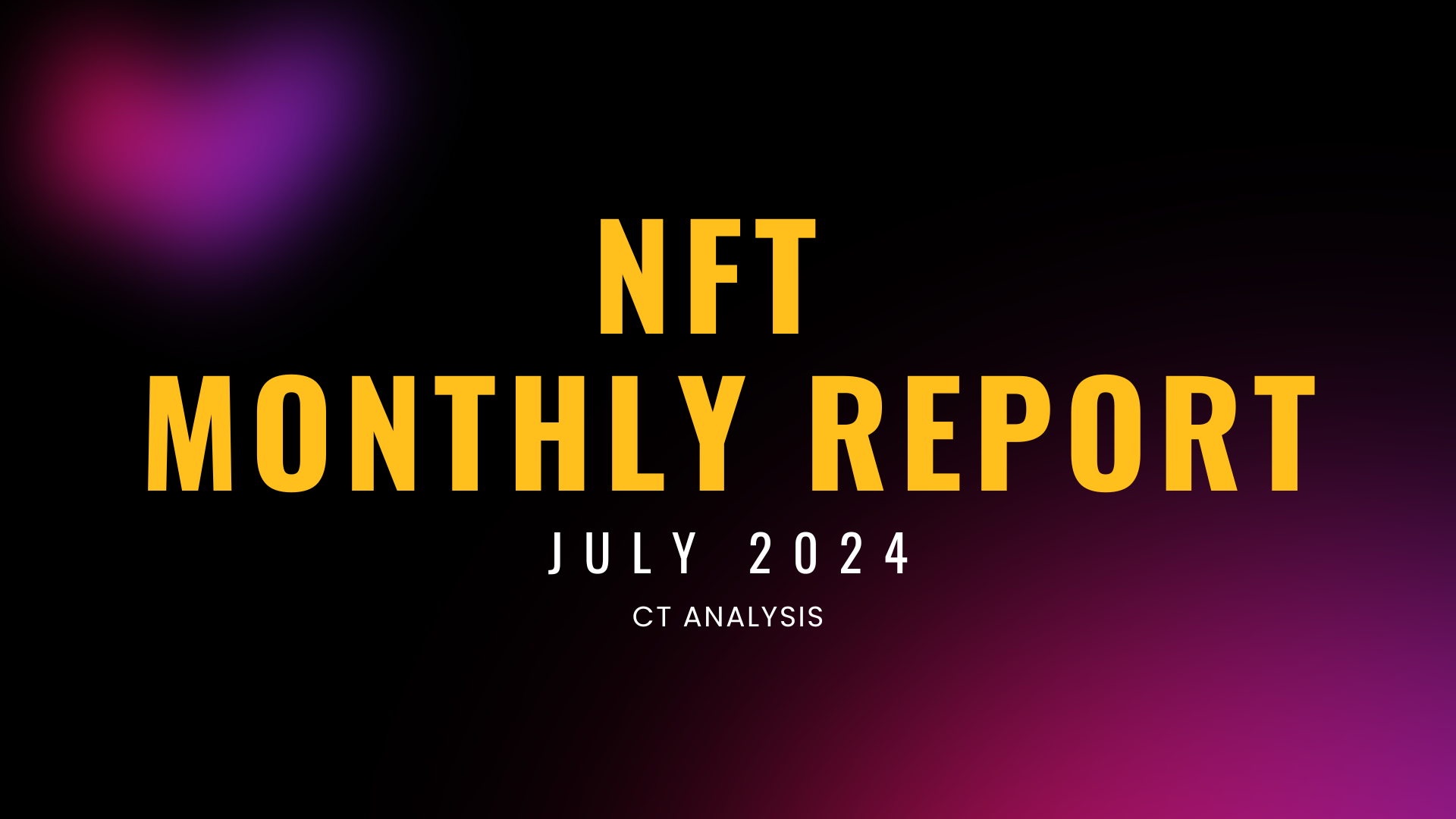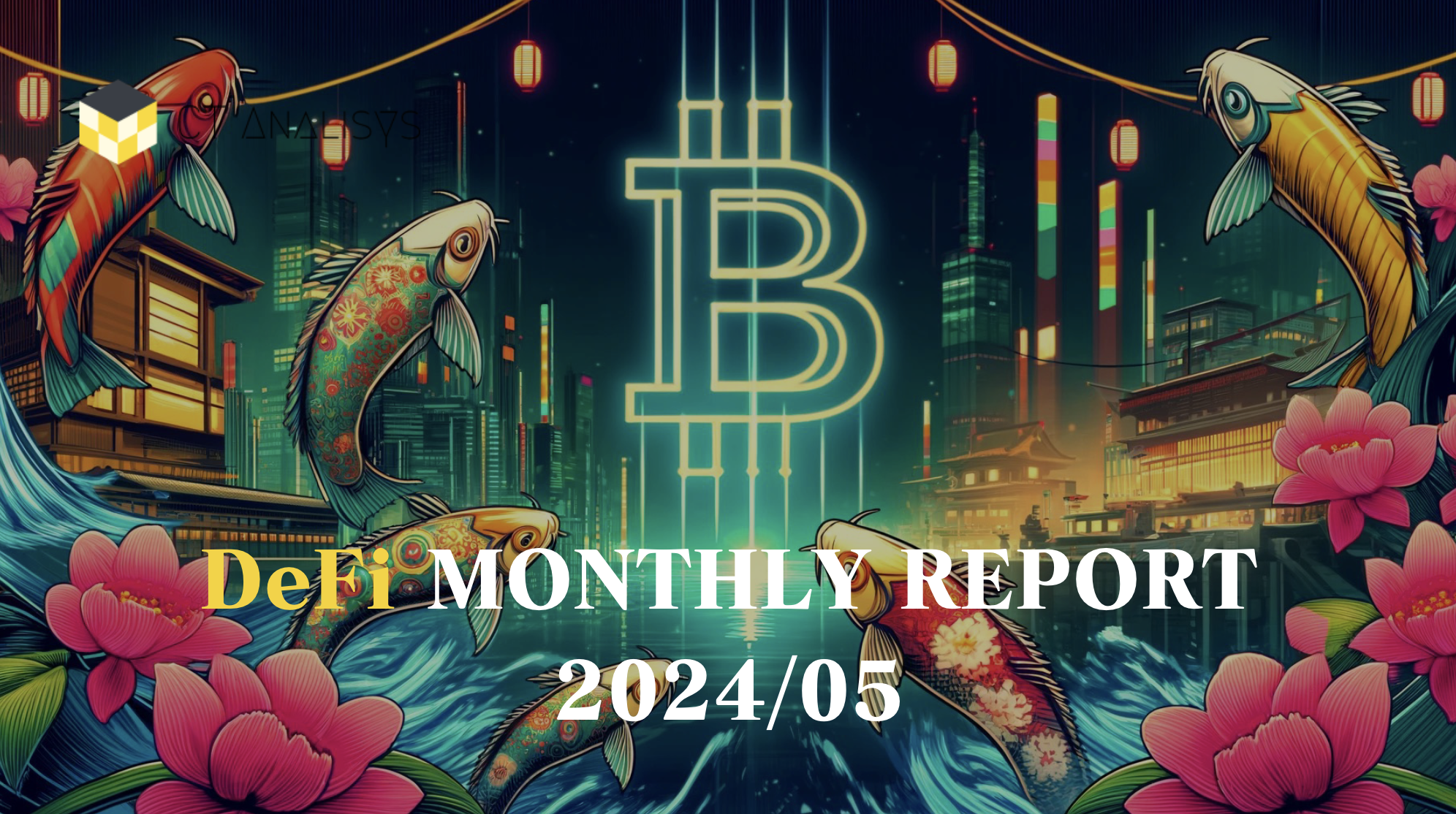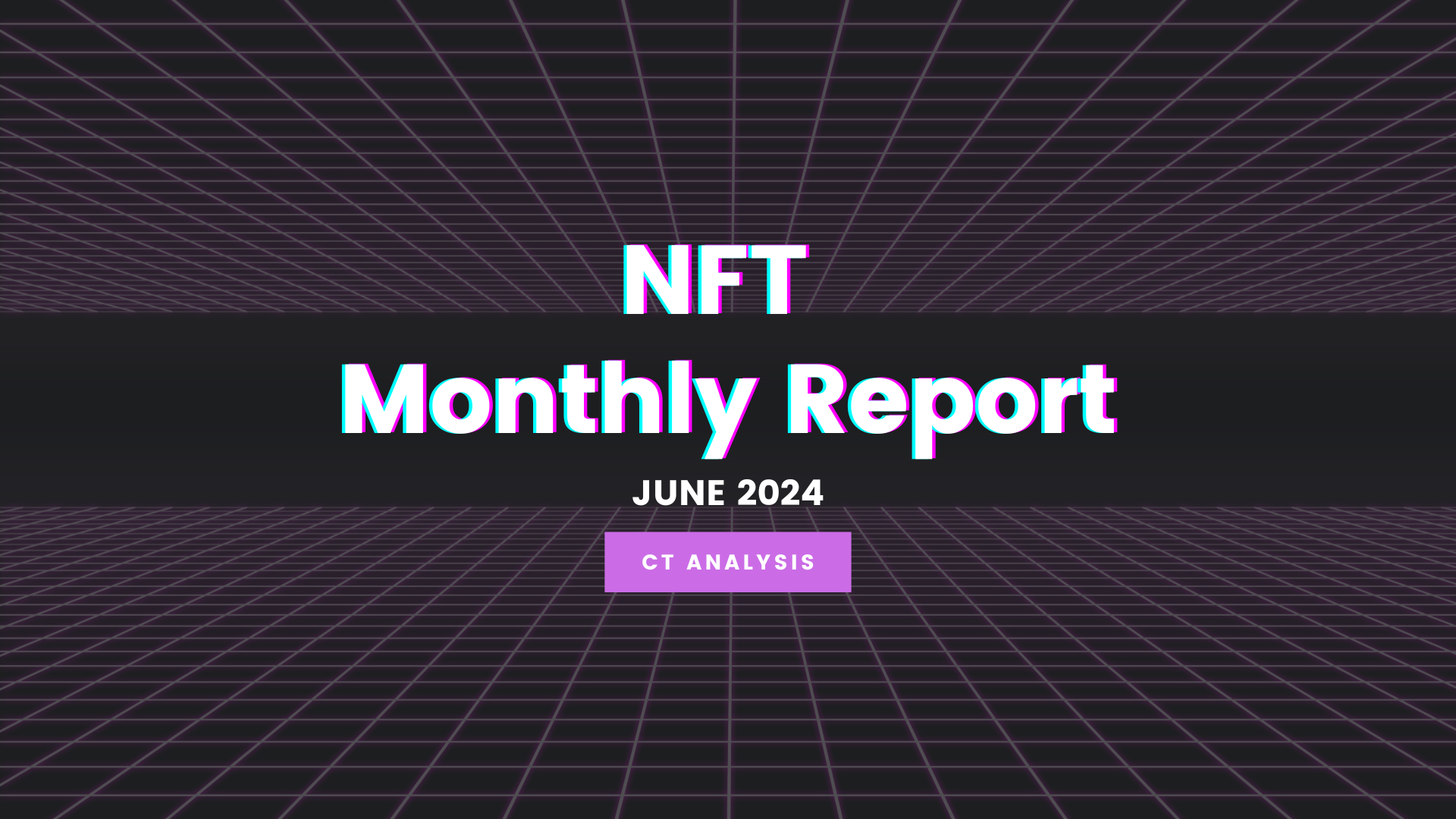【イベントレポート】Binance Blockchain Week Singapore
Shota

2019年1月21日から22日の2日間にわたり、シンガポール・マリーナベイサンズで史上初となるBinance主催のカンファレンスであるBinance Conferenceが開催されました。
シンガポールは、国土的には東京23区と比較してやや大きい程度と非常に小さな国ですが、全世界から多く開発者や業界の関係者が集まり、終始盛り上がりを見せていました。
CryptoTimesでもシンガポールに足を運び、Binance初となるカンファレンスに参加しました。
本記事では、会場の様子やイベントの内容、所感を紹介していければと思います。
目次
Binance Blockchain Weekについて

Binance Blockchain Weekは1月19日から22日の4日間にかけて、Binanceの主催で開催されたイベントになります。
前半2日間では、『Binance SAFU Hackason』と呼ばれるハッカソンが開催され、ユーザーの資産保全をテーマとして10万USD相当のBNBをかけたバトルが行われました。
後半の2日間は、CryptoTimesも参加させていただいた、『Binance Conference』が開催され、これはCZ氏やTRONのJustin氏をはじめとして、世界各国から50を超える著名なスピーカーを招く充実したものとなりました。
Binanceによって開催されるカンファレンスは、シンガポールで開催された今回のものが初の試みとなりましたが、多くの人々が集まり非常に充実した内容でした。
Binance Blockchain Weekの様子
冒頭でも述べた通り、会場はブロックチェーンに携わる世界中の人々で大きな盛り上がりを見せていました。ちなみにチケットは両日とも完売だったそうです。
イベントの内容は次項で紹介しますが、会場の様子も写真でお伝えしていきたいと思います。
エキシビションエリア入り口

会場の入り口には、Binanceの大きなロゴがありました!開幕からものすごい豪華な会場でした。。
今回のイベントのメインスポンサーであるTRONの創設者であるJustin氏の大きなパネル

ここ最近、Binance LaunchpadでのBitTorrentのICOやDAU(デイリーアクティブユーザー)の急激な成長などで話題を集めるTRONですが、会場には大きなJustin氏を目印とするTronのブースが設営されていました。
これまでトップ10には入っていませんでしたが、Coinmarketcapの時価総額を見ると現在は8位に位置しており、今かなりホットな通貨であることが伺えます。
GRAND BALL ROOMの様子

写真では、午前中のプログラムが始まる前の時間だったためあまり人がいませんが、パネルやキーノートには多くの人が釘付けでした。
ちなみに、筆者は午後BinanceのCEOであるCZ氏と一緒に写真撮影をしていただきました!
https://twitter.com/shot4crypto/status/1091618674266464256
パネルディスカッションの紹介
今回のBinance Blockchain Weekのプログラムは、全体的にパネルディスカッションをメインに構成されており、その他でキーノートといった感じでした。
どのパネルも著名な方々による素晴らしい意見が飛び交っていましたが、その中でも面白いなあと思ったものを紹介していこうと思います。
Lessons Learned in Crypto and Token Investment
このパネルディスカッションは、2019年の現在まで、仮想通貨やトークンへの投資によって何を学んだのかというトピックを軸に進行していきました。
パネルメンバー
- Michael Gu氏 – Boxmining 創業者
- John Ng氏 – Signum Capital 設立者
- Dovey Wan氏 – Primitive Ventures 共同設立者
- Jamie Burke氏 – Outlier Ventures CEO
- Vincent Zhou氏 – FBG Capital 創業者
Q: 現在の市場をどうみますか?参加者は合理的だと思いますか?

Dovey氏:現在も合理的だとは思ってません。合理的な投資という点で話すのであれば、まず市場における情報が非対称的であることが一点あります。
投資家はどうしても対称的な情報を手に入れることができず、合理的な投資家でさえもが、このために異なるトークンの価値付けモデルを利用していると考えています。
このトークンの価値付け(Token Valuation)において、コンセンサスが生まれていないので、現在の市場を合理的と呼ぶのは難しいでしょう。
Jamie氏:2016年の段階では、スタートアップの99%は正直言ってくだらないもの(Bullshit)ばかりでした。
状況は好転しているとは思っているが、現在でもブロックチェーンにつぎ込まれている資本とその基礎にある価値が分離しているように思えます。
DAppで~~のように利用可能なトークンと言ってもまだインフラが決してそれを実現させてはくれないでしょう。

John氏:我々(Capital)としてもしっかり戦略を練らなければいけません。
これまで、一部のCapitalではプライベートで購入したトークンの上場後即エグジットなどを行っていたようだが、今の市場でそれをやってしまうと市場が死んでしまう。DUMP=死に繋がります。
もし市場の下落が続けば、その分辛くなるし、それが早ければ早いだけ辛さも増していきます。
そういった意味でもしっかりと戦略を練った投資を行うことが非常に重要です。
Q: 2019年でこれまでのレッスンをどう生かしていきますか?

Dovey氏:これまでの上昇局面の相場では、売り手が売り時を伺う売り手の市場だったのに対し、今は買い手が買い時を伺う買い手の市場になっています。
どちらにせよ、価値が過小評価されているときに投資を行う必要があります。
Jamie氏:市場は構造的に変化を遂げています。
今後、個人ではなく機関の資金が流入することになれば、より合理的な市場になっていくでしょう。
また、プロジェクトではこれまでのプロトコル・オンチェーンガバナンスの部分からより商用化が進められる一年になると思っています。
スケーリング問題などの技術面での障壁はあるが、市場という点で見たときトラディショナルな金融からより特化した独特なものに変化していくでしょう。
Decentralized Apps that Can Scale to Millions of Users: Are we there yet?
日本からも、Miss Bitcoin Maiさん(@missbitcoin_mai)さんが登壇していたこのパネルディスカッションは最近話題にあがるDAppsのMass-Adoptionについてのトピックを中心として進んでいきました。
パネルメンバー
- John Riggins氏 – BTC Media International Operations
- Jason Jeon氏 – NHN Entertainment チーフエヴァンジェリスト
- Patrick Dai氏 – Qtum 共同創設者
- Mai Fujimoto氏 – Miss Bitcoin
- Emma Liao氏 – Ultrain 共同創設者
Q. 現段階で分散型のエコシステムを支えるだけのテクノロジーのレベルに到達していると思いますか?

Patrick氏:まだそのレベルには達していないと感じます。
例えば、BitcoinはそもそもDApps向けにデザインされていませんし、EOSも同様に多くの制約があります。DAppsを取ってもその多くがギャンブルです。
エコシステムを支えるのに確かにテクノロジーは必要ですが、テクノロジーだけがバリアというわけではありません。
分散型のエコシステムを成立させる上では、テクノロジーと同様にアプリケーション自体も重要になりますし、人々による十分な認知もまた重要な要素の一つです。
Emma氏:ブロックチェーンのAdoptionという点で話すのであれば、DAppsが果たす目的をより一層考える必要があります。
エコシステムを支えるという点では、フルDAppsがこの目的を果たすのには一番ですが現状、テクノロジーはそのレベルに達していません。
しかし、それ以上に人々がブロックチェーンを利用して具体的に何ができるのかということを深く理解することの方がエコシステムの成立においてより重要であると考えています。
Q. Emma氏のいうAdoptionを実現において、具体的にこれはどのように実現されると思いますか?

Jason氏:まず、前提としてAdoptionの実現におけるユースケースを考える必要があると考えます。
どの程度のレベルの分散性があるのかといった話題もありますが、ゲーマーはそんなことは一切気にしません。彼らは楽しいものをプレイしたい、それだけです。
現状、ゲームでユーザー数が伸びているのはすべてギャンブルで、ターゲットが単純に仮想通貨のコミュニティのみとなってしまっています。
個人的には、昔ながらのゲームを例えば、コンペティションやスキルに応じた支払いなどの形で業界に持ち込んでいくことがAdoptionに繋がるのではないかと思います。
Patrick氏:音楽やビデオなどの、オンラインのコンテンツだと思います。
現状、AppleのAppStoreでは開発者が30%をApple側に、中国NetEase(网易)やTencent(腾讯)では10%を手数料として支払う必要があります。
マネタイズの部分で、やはりブロックチェーンは有用であり、これが完全に新しいインフラとして普及していく可能性は十分にあります。
Jason氏が言及していたゲーミング同様にオンラインコンテンツもターゲットが広く、業界の外のインフラを持ち込むことが重要になってくるのではないかと思います。
Q: 日本を見ると、特にDAppsの市場にはどのような特徴がありますか?
Thank you again for having me today. I didn't have time to talk about the Japanese current situation. Please see this update: . →【Japan specifically, what is the current market situation for dApps and what are interesting cultural aspects of the market that are relevant 】 pic.twitter.com/lDCqoQDGlY
— Mai🧬 @intmax (@missbitcoin_mai) January 21, 2019
時間の都合上、Maiさんは日本の状況やDAppsについての意見を発表することができませんでしたが、彼女のツイートで自身の『My Crypto Heroes』などの日本のDAppsについての意見を後日発信していましたので、こちらも紹介させていただきます。
Why the Quality of Information Matters: Separating Good from Bad
パネルメンバー
- Angie Lau氏 – Forkast.News CEO・創設者
- Matthew Tan氏 – Etherscan CEO
- Catherine Ross氏 – Cointelegraph Assistant Editor in Chief
- Emily Parker氏 – LongHash 共同創設者
- Ulisse Dellorto氏 – Chainalysis Head of Business Development
Q: 各自、自身のプラットフォームを持っていると思いますが、これの良し悪しをどのように判断し、他との差別化を行いますか?

Emily氏:人々は仮想通貨のメディアを信頼することが難しいと言います。
そのため、情報ではなくデータを求めてデータを発信するウェブサイトなどを訪問しますが、これは実際に情報サイトと比較して信憑性の高いものとなります。
例えば、Etherscanなどは信憑性が高いですが、その他の情報を紹介するサイトと比較してどうでしょうか?
一方で、仮想通貨に熱心な人々というかこのコミュニティでは、その他のコミュニティと比較して非常に優れている部分もあり、例えばサイトに記載されている情報に誤りがあれば、これらはすぐに指摘されやすいため、修正がより容易になります。
もう一つの問題が、客観性です。
仮想通貨メディアでは、客観性が欠如していることが多く、例えば一つのコインを推したりしているのを見かけますが、LongHashではこの客観性を失わないようにデータの解釈を行っています。
客観的であるべき部分で、仮想通貨メディアはより客観性をケアする必要性があると感じます。
Ulisse氏:私たち(Chainalysis)の強みは、10人の経済学者を抱えている点です。
ブロックチェーン上で行われたトランザクションはすべて、ブロックチェーン上にデータが残ります。
しかし、行われているそのほとんどのトランザクションは取引所によって行われており、彼らがホットウォレットへ資産の移動を行っているケースがそれに該当します。
ここで、強調しておきたいのが、決してリサーチを怠らないということです。
異なるタイプの集団によって行われたアクションを適切にカテゴライズし、そのアクションから中にある真のメッセージを読みほどくためには、コンスタントにこのリサーチを続けることが必要とされます。

Matthew氏:私は個人的に、ブロックチェーン内にあるデータを読みほどくのが好きです。
理論上、ノードのコンピュータ内にはすべてのデータが入っているので、個人でも十分にそのデータが正しいものなのか、そうではないのかを検証することが可能です。
データのソースという点に関して、私はいくつか留意するポイントがあります。
–独立したソースであるか:金銭的なインセンティブやその他によって情報に偏りが生じていないか
–データ提供者:これを無料で行っているのかどうか?
このように情報が提示されているといっても、その方向性に大きな差異が生じることがあります。
中には、しっかりとした情報もありますが、常に見る側の視点からメディアのリテラシーを考えていく必要があると思います。
まとめ
ここまで、長文になってしまいましたが、シンガポールで2日間にかけて行われたBinanceのカンファレンスの様子や、プログラムの内容を要約してレポートとさせていただきました。
参加者の熱意や登壇者の洞察力の深さなど、このカンファレンスからは多くの刺激を得ることができました。
プログラムの一部では、独自のコインであるBinanceコイン($BNB)を利用して行っているチャリティの紹介もされており、ブロックチェーンの普及やそれによる問題解決を真摯に目指す素晴らしい取引所であるということを再認識することができました。
プログラムの最後に行われたCZ氏のスピーチによれば、間もなくBinanceの独自チェーンであるBinanceチェーンのテストネットや次回のBinance Conferenceの開催についても言及されました。
個人的にもイベントが終了したからとはいえ、引き続きブロックチェーンの普及や発展を考えていく上では決して見逃すことのできない、2019年要注目の取引所であると思っています。
ありがとうございました。













































 有料記事
有料記事