
特集・コラム
2019/06/17Luniverse(ルニバース):韓国大手取引所Upbitが仕掛けるブロックチェーンプラットフォーム
韓国では大手IT企業が手がけるブロックチェーンプラットフォームが本格的に活動をはじめ、ブロックチェーンプラットフォームの戦争が始まっています。 2017年にはEthereumのような分散化されたブロックチェーンプラットフォームが注目されましたが、dAppサービスを提供する際の速度、拡張性などが問題となり、これらの課題を解決したと主張する新しいBaaS(Blockchain As A Service) (※) サービスを掲げた企業が増えています。 ※BaaS(Blockchain As A Service) : ブロックチェーンを利用したアプリケーション、スマートコントラクトなどをブロックチェーンベースのインフラストラクチャを設定、管理、実行することなく既存のビジネスに適用できるトータルサービス。 そもそも、ブロックチェーン技術について深く理解している開発者は少なく高い水準のブロックチェーンを開発することはとても難しいことなので大手企業が開発しているプラットフォームでdAppサービスを開発することはサービス開発者にとっても大きなメリットになるでしょう。 韓国ではメッセンジャーアプリで多くのユーザーが確保できているカカオ、LINEが開発しているブロックチェーンプラットフォームklaytn、LINKが注目されていますが、実はもう一つ大きなポテンシャルを持つ注目すべきプラットフォームがあります。 それはDunamuの子会社Lambda256が開発している“Luniverse(ルニバース)”です。Liuniverse(ルニバース)はアマゾンウェブサービス(AWS)形態で企業が必要とするブロックチェーン技術を手軽に導入できるソリューションを提供します。 Dunamuは2017年に韓国の仮想通貨取引所Upbitを設立し、ブロックチェーン業界で大きな成長を成し遂げたブロックチェーン業界の風雲児です。カカオやLINEのような大きなプラットフォームではありませんが、ブロックチェーン技術の可能性をいち早く察知し、早いスピードで成長してきたDunamuがルニバースを通じ、韓国国内でまた大きな成長することは間違いないでしょう。 カカオとLINEに関しては、前回と前々回のレポートでも配信していますので、そちらも御覧ください。 - 韓国最大のメッセージングアプリ「カカオトーク」を提供するKAKAOのブロックチェーン戦略 - LINE株式会社とその親会社NAVERのブロックチェーン事業展開 Luniverse(ルニバース)とは? Luniverseは韓国の仮想通貨取引所Upbitを運営するDunamu(株)の100%子会社Lambda256(株)が開発しているブロックチェーンプラットフォームです。 Luniverseはブロックチェーンについて詳しくない開発者でもdAppを簡単に開発し、運営するために必要なもの(ウォレット、開発Toolなど)全ての環境を提供します。 一言で表現しますとLuniverseとは「開発者がいい環境の下で本業である"開発や運営"に集中できる最適なブロックチェーンプラットフォーム」と言えるでしょう。 韓国最大手の旅行予約サイトYanojiなどもLuniverseのパートナーとして参加しており、今後既存の巨大サービスがブロックチェーンに参入して来る入り口として大きな役割を果たしていく可能性があります。 Dunamu(株)の沿革 Dunamu(株)は2012年4月に設立され、E-bookプラットフォームから事業を始めましたが、売り上げがよくなかったためE-book事業は終了させます。 次にSNSで人気のあるニュース記事をまとめて見せてくれるニュースメートサービスでIT業界から注目を浴びました。 2013年にはカカオの投資子会社キューブベンチャーズ(現カカオベンチャーズ)から2億ウォン(約1,800万円)、カカオから33億ウォン(約3億円)ほどの投資を受け証券プラス for カカオ(現|カカオストック)を委託開発・運営を始めます。 カカオストックは色んな証券会社の取引を一つのアプリで完結できるほかSNSのような機能もあり人気を集めました。Dunamuはカカオストックの開発で取引所のノウハウを取得し、このノウハウをもとにBittrexと提携、2017年にUPbitをリリースし本格的に仮想通貨市場へ参入しました。 Dunamu(株)の事業分野 続いて、Datum㈱の事業分野に関しての説明になります。Datum㈱はブロックチェーン関連のサービスと証券関連のサービスの2つに分類されます。 証券関連サービス kakaostock(カカオストック) カカオ(株)との提携でDunamu(株)が開発・サービスする証券オールインワンアプリで韓国の国民的な証券アプリである。(累積ダウンロード250万人) MAP 有数の資産運用会社と投資顧問会社が提供するさまざまな投資戦略で顧客の資産を運用する投資一任サービス。 ブロックチェーン関連サービス ブロックチェーン関連サービスとしては、UpbitとUBCIがありますが、Upbitの内容は情報量が多いので、別項で説明いたします。 UBCI(Upbit Crypto Index) UBCIは仮想通貨市場全体の動きを簡単に把握できるように市場の標準的な指数を提供するサービスです。 Upbit Upbitとは? 2017年にリリースされ、2ヶ月でDAU190万を達成した韓国最大級の仮想通貨取引所です。 UPbitの成長について ETHの価格が急騰し、仮想通貨が韓国で注目されるようになりましたがこの当時のCEOソン・チヒョン氏は”仮想通貨取引所”というアイテムがカカオストックを運営していたDunamuチームに最適であると考えていました。 取引所の企画・開発を始めてから5か月で開発は終わりましたがDunamuチームは仮想通貨に対する知識がなくサービスコンセプトに悩んでいました。当時、海外の取引所では非常に注目を浴びていた仮想通貨の取引所であるBittrexに連絡を行い、提携を結ぶことに至り、Upbitをリリースすることとなります。 2017年の良い市場状況・優秀なチーム・良いパートナーの三拍子を揃えることができたUpbitはリリース2か月でDAU190万人を達成し、韓国最大級の取引所として成長しました。 2016年Dunamu(株)の売り上げは15億ウォン、当期純損失が21億ウォンの中小開発会社でしたがが、2017年Upbitをリリースしたことで、一日の売り上げが数十億ウォンを記録しました。 Upbitの悪い噂と家宅捜査の結果 Upbitはリリース2か月で圧倒的な成長を遂げましたが、一方で保有していない仮想通貨の売買をデータだけで処理しているという疑惑がありました。 疑惑があった当時、Upbitに上場していた仮想通貨は121種類でその中で入出金ができる仮想通貨は20種類だけだったので疑われてもおかしくない状況だったと思います。 Upbitの関係者らはこの疑惑に対して日々ユーザーが増え続け、サーバーダウンの恐れがあるため最終的にはトラフィックの分散のためであると解明しました。 しかし、疑惑は増え続け、2018年の5月に検察から家宅捜査をされることになります。検察が捜査を始めるとUpbitは全ての仮想通貨にウォレットを設け、入出金できるように措置をとり、顧客資産の2倍の仮想通貨を確保したそうです。 そのため、検察は捜査の焦点を"相場操作"に変えました。 家宅捜査の結果 ・Upbit が偽の会員ID通称"8"を作成し、1221億ウォン(約122億円)相当の仮想通貨とKRWが会員のアカウントに入庫されたようにコンピュータシステムを操作したと発表 [Upbitの立場] 法人アカウントの特性上、会社で既に保有している会社の現金と仮想通貨を利用する取引であったため、外部からそのアカウントに入金する手順は必要がない、その手順を省略しただけ ・同じ価格で買い、売り注文を同時に行い、取引を締結させる「クロス取引」を4兆2670億ウォン相当の実行したと発表 [Upbitの立場] 時価総額が小さいアルトコインは取引量が少なかったので、自然に相場(価格)が形成されるが難しかった価格表示のため必要な行為だった。 ・Upbitが仮のアカウント"8"を利用して35種の仮想通貨取引に直接参加し、会員と1兆8817億ウォン相当の取引を締結させたと発表 [Upbitの立場] 流動性を供給するために必要な行為である。 ・締結の可能性が低い価格帯で254兆5383億ウォン相当の偽の注文を出したと発表 [Upbitの立場] 市場価格の変化に応じて、既存の注文をキャンセルして、新規注文を提出する流動性供給の基本的な特性 ・ボット(bot)プログラムを利用して、ビットコインの価格は競合他社の価格よりも高く維持されるようにした。 [Upbitの立場] 急激な取引量の増加で提携会社の障害が発生し、これによる一部のシステムエラーに対応しながら、顧客の資産を保護し、信頼性の高い取引サービスを提供するために、実際の会社が保有する資産にエラーを補正するための取引 これらの事件に関する裁判は現在も進行中です。2019年4月17日初めて開かれ、UPbitの設立者ソン・チヒョン氏を含む3人の役員が召喚されました。 Luniverseの概要 Luniverseは2018年9月14日に開かれたUpbitのブロックチェーン開発者カンファレンスで発表されたブロックチェーンプラットフォームです。 Lambda256のCEOパク・ジェヒョウ氏は企業が簡単にブロックチェーンサービスが開発できるようにブロックチェーン開発ソリューション"ルニバース"を開発したと発表しました。 LuniverseはDunamu(株)の100%子会社Lambda256が開発しているブロックチェーンプラットフォームでブロックチェーン技術に対する理解がなくても誰もがルニバースを通じトークンエコノミー設計し簡単にビジネスに適用することができる次世代BaaS(Blockchain as a Service)プラットフォームサービスです。 CEOの経歴 パク・ジェヒョン代表は韓国の名門、浦項工科大学でコンピュータ工学を専攻し、ソフトウェアエンジニア・起業・ベンチャー投資家をしてきた人物です。 2017年にイーサリアムの研究会も設立したので早い段階でブロックチェーン技術に興味を持っていたと思われます。 勤め先だったサムスン電子ではのサムスンペイとサムスンチャットオンメッセージサービスなどを開発した経歴があります。 また、韓国の大手通信会社のSKテレコムでは、ティーバレーサービス部門マネージング・ディレクターを務め、フリーランスのための共有の経済プラットフォームの開発主導しました。 以後2018年5月UPbitを運営するDunamu(株)のブロックチェーン研究所(2019年3月法人化)Lambda256の研究所長に就任して、わずか10ヶ月にも満たない2019年3月、世界初のコンソーシアムベースブロックチェーンのプラットフォームLuniverseを正式リリースする成果を成し遂げました。 学歴 ・1987年〜1992年中央大学経営情報学部卒業 ・1992年〜1994年浦項工科大学電算学科修士卒業 経歴 ・1994年〜1998年、ヒョウンダイ電子の専任研究員、ヒョウンダイの情報技術責任研究員 ・1998年〜2000年にイジェンテック代表取締役、技術総括 ・2000年〜2005年ワイズフリーの代表取締役、技術総括 ・2005年〜2008年シンクフリーCTO ・2008年〜2016年にサムスン電子無線事業部ペイメントグループ常務取締役、グループ長 ・2016年〜2018年SKテレコムティーバレー、サービス部門マネージングディレクター ・2018年〜現在 Lambda256の代表取締役 Luniverse コンセンサスアルゴリズム ブロックチェーンのようなP2Pネットワークシステムでは、各ノード間の情報到達の時間差やネットワーク環境による重複などの不具合がある可能性があります。 そこで、生成されたブロックの“正当性”を検証し、該当ブロックをブロックチェーン上につなげるためにネットワーク参加者ら(ノード)の合意を得られる方式(アルゴリズム)が必要になります。 最大25のパートナー社がPoAアルゴリズムのブロック検証者になり、そのうちの5社がサイドチェーンの検証を行います。 Luniverseはラムダコンセンサスアルゴリズム(LCA; Lambda Consensus Algorithm)を採用し、検証・認可されたブロック生成者らによってブロックを生成する権威証明(PoA)を基盤にします。 PoA合意過程で参加した検証者らの信頼性を高めるために一定の持分を担保として提供(Staking)し、何か問題を起こした際はこの担保を没収することになっています。 Luniverse 発行トークン LUK 現段階で多くの情報は公開されておりませんが、Lambda256はルニバースプラットフォームを効率的に運営するために、100億枚のルニバーストークン (Ticker : LUK) を発行しました。 LUK はルニバースメインチェーンのガス代とBaaSサービスの利用料金として使われ、今後dAppストーアやソリューションマーケットプレイスでプラットフォーム決済手段として使われる予定だそうです。 また、ルニバースエコノミーシステム活性化のためにLUKトークンの30%はルニバース支援プログラムで使われます。 パク代表はLUKで資金調達をする計画はなく、トークンの発行は資金調達の目的ではないと一蹴しました。 Luniverseの目標とソリューション Luniverseのパク代表は今までのBaaS(Blockchain As A Service)をver 1.0と表現し、今までのサービス型ブロックチェーンの「10大問題」を解決したBaaS ver2.0のプラットフォームを作り上げることを目標としています。 「10大問題」 ・チェーン環境問題 1.性能の強化 2.高い安定性 3.便利な開発環境 ・利便性問題 4.便利かユーザーアカウント管理 5.リアルタイムサービス提供のための自動署名代行 6.ユーザー情報バックアップ及び管理支援 ・セキュリティ問題 7.スマートコントラクトの安定性 8.データープライバシー強化 ・費用問題 9.合理的なガス代 10.使用量に従う効率化 Luniverseが提供する5つのサービス 1.快適で安全な独自的な高性能のサイドチェーン - 2000TPS、1秒のブロックタイムなど 2.便利なトークンの発行/管理ツール - トークンの発行やトークンエコノミーデザインなど 3.APIベースの身近で便利な開発ツール - Atom、Remixなど 4.早くて正確なスマートコントラクト保安監理ソリューション - リアルタイムコントラクト、保安の診断など 5.dAppの利便性を強化したユーザー管理サービス - 遠隔秘密鍵の署名、様々なウォレットと連動、秘密鍵のバックアップ&復元など Luniverseの構造 Luniverseはコンセンサス基盤のメインチェーンとサイドチェーン基盤のプロダクトチェーンとの有機的な結合を通じ、動作します。 メインチェーンとサイドチェーンをベースにポータル階層、API階層、サービス階層、共通階層の4階層で構成されています。 ・メインチェーン メインチェーンはラムダコンセンサスアルゴリズムをベースにしています。ラムダコンセンサスアルゴリズムは、権威証明(PoA)方式の合意アルゴリズムを採用しています。 ・プロダクトチェーン LuniverseではdAppの快適で安全な開発/運用環境を構築するために、プロダクトチェーンを提供しています。 プロダクトチェーンは資産(トークン)をメインチェーン上に発行し、その資産に固定(Pegging)された新しい資産(トークン)をプロダクトチェーン上に発行することでメインチェーンの限界から抜けだし、自由に別途のチェーンを構築、運用できる技術を指します。 ルニバースプロダクトチェーンはルニバースメインチェーンにブリッジに接続され、自由にトークンおよびトランザクションの移動が行われるチェーンでdApp社にプライベートチェーン(Private Chain)の利便性、安全性、高いパフォーマンスとアンカリングなどを介してルーニバースメインチェーンとイーサリアムなどの外部パブリックブロックチェーンにトランザクションデータを公開し、高い信頼性を提供します。 Luniverseの特徴 ・各ビジネス分野に特化されたメインネット提供 Luniverseの特徴は、さまざまな分野ブロックチェーンサービスを一つのメインネットで済ませないことです。 各分野に特化したメインネットを別々で作っています。ゲーム、教育、メディアなど各分野に特化したメインネットを別途開発し、クライアントに提供していきます。 ・高性能 ルニバースプラットフォームは、サイドチェーンに基づく高速のプロダクトチェーンを提供します。これらのプロダクトチェーンはルニバースコンセンサスアルゴリズムを採用し、現在は1秒のブロック生成時の最大2,000TPSを提供できます。 ・チェーンシャディング 環境によって特定のdAppの場合一つのプロダクトチェーンだけではすべてのユーザーからの要請が処理しきれない場合があります。 こういった場合は多数のプロダクトチェーンに渡りチェーンシャディングを支援することで性能の問題が解決できます。Luniverseプラットフォームではこれらの機能をサービスの一環として提供し、dAppが一つのチェーンを使っているかのような環境を提供します。 ・プロダクトチェーンではガス代がかからない トランザクションを実行する時にユーザーの費用負担を除去することにより、dAppの使い勝手を改善しました。 ・ユーザーが使いやすい ユーザーは電話番号、SNS、メールなどで手軽に会員登録とログインすることができます。 ・高い信頼性 プロダクトチェーンとルニバースチェーンの間の“アンカリング”という技術でLuniverseチェーンとイーサリアムのような外部メインチェーンとの間のアンカリングを2段階に提供し、トランザクションの信頼性を高めます。 ・運用しやすい 1.ブロックエクスプローラーを提供しユーザーがブロックチェーンデータを確認することやデーター形式で抽出できる機能を提供します。 2.ノードエクスプローラーを提供し、ブロックを検証するものに本人の所有ノードに関する現在及び過去のデータのリソース現況、イベント発生現況、チェーンデーター再構成発生現況、ブロック生成周期などの基本的な情報を提供します。 3.トラフィックエクスプローラーを提供し、トランザクション要請に対する分析、統計などを視覚化した画面を提供します。 4.プロダクトチェーンに対する総合的なダッシュボードを提供し、プロダクトチェーンの全体現況がモニタリングしやすくなります。 5.別途のスマートコントラクトを開発せずに、トランザクションの処理パータンを選択し、必要な変数だけ入力すればこれらを活用できるAPIを自動生成してくれます。従ってdApp開発者はトークンエコノミーを簡単に作り上げることができます。 Luniverseプラットフォームでブロックサービスを開発しているパートナー yanolja yanoljaは旅行やレジャー分野の様々な大手企業がマイレージを統合することができるAllianceプラットフォームです。 同じ業界にあるが、お互いに競争関係にない、お互いのニーズがよくマッチングされるサービスとの間のユーザーマイレージ交差使用を可能にして顧客に直接利益を与え、サービス企業は、忠実な顧客拡大と新規顧客の流入などの効果を得ることができます。 宿泊の分野1位の企業yanoljaが、その最初の参加会社としてブロックチェーン開発会社キーインサイドと一緒に作り上げます。 DALCOM SOFT DALCOM SOFTはSuperStarシリーズの開発会社であるダルコムソフトはSuperStar SMTOWN、SuperStar JYPNATION、SuperStar BTS、SuperStar PLEDISなど5つのゲームを20以上の国にサービスしているK-POPのリズムゲームのプラットフォームです。 DALCOM SOFTはブロックチェーンを活用した世界のK-POP Fan Communityを作ろうとしています。 E4.NET E4.NETを提供するチェリー(CaaS:Charity as a Service)は、ブロックチェーンベースの寄付プラットフォームで多くの人が助けを必要とされる人々に簡単に寄付をすることができるデジタル環境を提供します。 チェリーアプリを利用して、ユーザー認証をすませばさまざまな寄付団体と個人を支援することができます。 現金と同様のポイント概念のトークンを充電すればいつでも寄付したいとき、自分が選択した団体や個人に対応することができます。 MOSSLAND MOSSLANDは、仮想資産を活用したブロックチェーンサービスを簡単に開発し、使用できるようにサポートしてくれるPaaS(Platform as a Service)です。 開発者は、モスランドを通じて複雑なブロックチェーン技術の理解が深くなくても完成度の高いサービスを開発することができます。 一般ユーザーは、ブロックチェーン、仮想通貨についての知識がなくても分散化された仮想資産を所有し、モスランド上で動作する様々なサービスを自由に利用することができます。 NODEBRICK NODEBRICKは2018年秋に設立されたブロックチェーンを利用したクリプトゲーム開発会社です。 現在、IPを活用したカジュアルコレクション型ゲーム、カードバトルゲーム、放置型RPGゲームを制作中で今年の夏のリリースを目標に開発を進めています。 既存のクリプトエコシステムの上にゲーム性を取り入れた新しい形のゲームを開発しています。 Ziktalk ziktalkは、グローバル言語共有プラットフォームであるziktalkのリバースICOプロジェクトです。 ziktalkは専門チューターだけでなく、一般人にも、携帯を利用していつでもどこでも外国語を教えたり学ぶことができる、グローバルP2P教育プラットフォームです。 現在1,600人の一般的な専門チューターがziktalkで英語と韓国語、中国語、日本語など8つの言語を教えています。 約10万人のziktalkユーザーは、米国と日本、フィリピンなど約25カ国で接続してサービスを利用しています。 KSTARLIVE KSTARLIVEは約900万人のユーザーを保有しているグローバルナンバーワンの韓流メディアであり、ファンの活動を直接的な価値として返す報酬型ソーシャルプラットフォームです。 ファンは活動に比例してKSTARCOINの(KSC)を獲得することができ、このような報酬は、ファンの旺盛な活動につながります。 KSCは、自分とスターのために、様々な分野で利用可能であり、上半期に取引に不合理な点を改善したブロックチェーンベースの公演予約dappサービスをオープンする予定です。 Humanscape Humanscapeは希少難治性疾患を持つ患者のためのサービスを製作するヒューマンスケープはブロックチェーンベースの患者コミュニティを通じて、患者のデータを収集し、そのデータが、患者本人の治療の機会を拡大する方向で活用できるようにサポートします。 「Beaming effect」プロジェクトは、ヒューマンスケープ生態系の大きな軸を担当する寄付環境に関する初の事例です。退行性網膜疾患の患者団体である「失明撲滅運動本部」と商品購入者に仮想通貨“HUMトークン”を支給することにより、キャンペーンの参加を奨励し、販売及び報酬の手続きをブロックチェーン上で実装し、寄付のプロセスを透明に共有することができるようにするプロジェクトです。 SNOWM snowMはソーシャルエンターテイメントプラットフォームです。既存エンターテインメント業界のスター育成システムを段階的に区分し、ユーザーがいつでも好きな段階に参加することができます。 芸能企画社中心のキャスティング、トレーニング、パブリッシングではなく、ユーザーの活動と支援に構成されたソーシャルプロデュース(Social Producing)でアーティストとインフルエンサーが誕生します。 aha ahaは、仮想通貨報酬型のQ&Aサービスです。質問や質のいい回答をして、良質の知識を選別し、ユーザーにトークンインセンティブを提供します。 NAVERの知識人などの既存の知識検索サービスの各種アビューズ行為問題を解決し、高品質のオンライン知識生態系をユーザーと一緒に構築していくプロジェクトです。 Storichain Storichainは、ドラマ、映画、オンライン小説などを読者と総合作用し創作、コラボレーション、流通取引契約するdAppです。 また、ストーリーチェーンは物語のバリューチェーン(Value Chain)のステップごとに生じる価値を参加者と分かち合う創作者、読者、スポンサーのための契約の規約です。 CABINEAT CABINEATは仮想通貨の決済が可能なスマート自販機で構成されたスマートカフェを通じて、コーヒー、お茶とデザートなど様々な飲み物や食べ物をサービスするためのプラットフォームです。 REBORN REBORN は、デジタル機器のアフターマーケットでの取引と流通などの全過程を網羅するグローバルO2Oコマースプラットフォーム実装のために用意されたプロジェクトです。 REBORNによって新たに誕生する価値が付与されたデジタル機器を使用して生活密着型Full-care serviceを具現かします。 まとめ まだ、ブロックチェーン開発者が少ない環境でルニバースプラットフォームが提供してくれるサービスは既存の一般開発者にはとてもうれしい味方になると思います。 開発者は本来の仕事に集中することができ、ルニバースネットワークは成長を図るWINWINの戦略であると感じました。 Lambda256のパク代表はLuniverseはEthereum、Bitcoinのような外部メインネットとの連結を通じグロバールネットワークの中心になり、2022年にはブロックチェーン業界のアマゾンになると公言しています。 今までほかの会社で成し遂げた業績やブロックチェーンに対する思いを見れば叶えない夢ではないと思いました。 日本ではほかの大手企業のプラットフォームよりは知名度のない現状ですが、dAppが実際に運用される段階になると日本でも注目されることになると思います。 また、Upbitの運営で確保してきたインフラや多くの資金で積極的な投資を通じ、ルニバースプラットフォームは成長していくと予想されます。 企業の競争がお互いにいい影響を与え、ブロックチェーン業界が健全に盛り上がることを願います。 参考文献 “람다256 “3년 내 블록체인계 아마존으로 성장할 것” (“ラムダ256 "3年以内にブロックチェーン業界のアマゾンになる”) https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2019/03/165955/ '모회사-자회사?' 오해 받는 카카오-두나무 관계 (親会社 - 子会社?誤解されるカカオとDunamuの関係) http://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2018/07/26/0023 두나무 자회사 람다256, 블록체인 서비스 쉽게 만드는 플랫폼 내놔 (Dunamuの子会社ラムダ256、ブロックチェーンサービスが簡単に作れるプラットフォームリリース) http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=119089 4대 암호화폐 거래소, 주인은 누구? (4大仮想通貨取引所の所有者は誰?) http://shindonga.donga.com/3/all/13/1231807/3 업비트 수사결과 주요 쟁점 총정리 (UPbit捜査の結果、主な争点を総まとめ) https://www.coindeskkorea.com/%EC%97%85%EB%B9%84%ED%8A%B8-%EC%88%98%EC%82%AC%EA%B2%B0%EA%B3%BC-%EC%A3%BC%EC%9A%94-%EC%9F%81%EC%A0%90-%EC%B4%9D%EC%A0%95%EB%A6%AC/ 韓国検察が国内最大の取引所に家宅捜索、仮想通貨市場も反応 https://jp.cointelegraph.com/news/s-koreas-largest-crypto-exchange-upbit-investigated-by-police-markets-react 檢 '허위주문 254조'vs 업비트 '자전거래 4조'…업계 '술렁' (検察「虚偽注文254兆」vs UPbit」クロス取引4超ウォン」...業界「ざわざわ」) https://www.msn.com/ko-kr/news/techandscience/%E6%AA%A2-%ED%97%88%EC%9C%84%EC%A3%BC%EB%AC%B8-254%EC%A1%B0vs-%EC%97%85%EB%B9%84%ED%8A%B8-%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0%EB%9E%98-4%EC%A1%B0%E2%80%A6%EC%97%85%EA%B3%84-%EC%88%A0%EB%A0%81/ar-BBRfxQ3 두나무 BaaS 플랫폼 ‘루니버스’엔 복수의 메인넷이 있다 (DunamuのーBaaSプラットフォーム「ルニバース」には、複数のメインネットがある) https://www.coindeskkorea.com/%EB%91%90%EB%82%98%EB%AC%B4-baas-%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC-%EB%A3%A8%EB%8B%88%EB%B2%84%EC%8A%A4%EC%97%94-%EB%B3%B5%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%A9%94%EC%9D%B8%EB%84%B7%EC%9D%B4-%EC%9E%88%EB%8B%A4/ 카카오와 두나무의 블록체인 플랫폼, 뭐가 다를까요? (カカオとDunamuのブロックチェーンプラットフォーム、何が違うでしょう?) https://byline.network/2019/03/20-46/ パートナー社一覧 https://www.luniverse.io/home/cases 技術参考 Introduction of Luniverse https://www.slideshare.net/LambdatwofivesixDuna/luniverse-intro Luniverse Guide https://guide.luniverse.io/v1.1.0/docs Hash.kr - Luniverseとは? http://wiki.hash.kr/index.php/%EB%A3%A8%EB%8B%88%EB%B2%84%EC%8A%A4

特集・コラム
2019/06/15専業トレーダーえむけんの仮想通貨市場分析!【6月15日】
みなさん、こんにちは!えむけん(@BinaryMkent)です。 前回更新後、BTCは戻り売り路線かと思って降りましたが、短期足でしっかり底を形成して大きく上昇してきましたね。「下を否定した後」というのもあり、未だしっかりした方向感が掴めない相場ではありますが、今回は資金の流れに注目しながら分析、解説していこうと思います。 それでは、早速BTCの分析から進めていきましょう。 BTCチャートの分析 BTCチャート(長期) まずは、BTCの長期チャートから見ていきましょう。 前回更新時には、「チャネル下抜けにより、本格的な調整移行」と判断しておりましたが、異常な底硬さがあったため、持っていたSポジションは記事公開後に解消しました。 また、推移している価格帯は依然変わらず…ではありますが、「すでに高値圏をつけているにもかかわらず、未だ8500ドル周辺に留まれている」というのは、底硬さに対する現れと言っても良いでしょう。 ここからは中期チャートを元に、現状の分析、並びに今後の展開予想について考察していきましょう。 BTCチャート(中期) こちらが、BTC中期チャート(4時間足)になります。ちょっといろいろと書き込みすぎてややこしいかもしれませんが、一つずつ解説していきますね。 まずは、Aのポイント。黄色ライン(太)を見ていただければ分かると思いますが、価格は高値切り上げ、MACDは高値切り下げ、とダイバージェンス(上昇終了示唆)が発生しています。 そしてその後、ダイバージェンス通りに価格が反転下落し、チャネルラインを下抜けます(B)。個人的には、ここを起点に本格調整開始と判断していたのですが、大きく下落したのち7500ドル周辺で下げ止まりました。 すでに、高値圏でのチャネルを下抜けていたのもあり、「ここからは戻り売りを狙うスタンスで…」とリバを待っていたのですが、短期足にてジワジワと底付き推移を見せ、結果戻り売りを否定する流れとなりました。(C) そして現状、このC点の確定により、価格の安値は切り上げ、オシレーターの安値は切り下げと、ヒドゥンダイバージェンス(上昇継続示唆)が発生している、といった状況です。(D) チャートを見ていただいても分かる通り、現状上に控えているレジスタンスラインも少ないため、とりあえずはCの安値確定と同時に濃厚となった緑チャネルを基準に押し引きしていくのが妥当でしょう。 BTCチャートの総評 さて、それではBTCチャートについてまとめていきましょう。今回、考えられうるシナリオは以下の3通り。 緑チャネルを基準にした調整転換シナリオ 緑チャネルのフィボ50%での戻り売り転換シナリオ 緑チャネルを上抜ける推進波継続シナリオ 特に、現状Lを持てていないトレーダーにとってはかなり触りづらい展開ではありますが、少し前の相場でもお話しした通り、高値圏でのチャネル推移は比較的強さを含んだ推移パターンです。 緩い判断材料でのSは命取りになりますから、短期足(15分足など)を元にしたパターン形成などをしっかり追った上でのポジション取りを心がけていきましょう。 それでは次にドミナンス分析を進めていきましょう。 ドミナンス分析 ドミナンスチャートに関しては、「Trading View」を参考することにしております。(外部リンク:https://jp.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/) 特に気になるのは、6/12を起点にBTCドミナンスが上昇し、アルトコインドミナンスが全体的に下落に転じている、という点ですね。ここから、恐らく「アルト市場に流れていた資金が撤退に向かっているのでは?」といった推測ができます。 では、少し拡大して見てみましょう。 拡大して見てみますと、これまで比較的好調であった「ETH」や「LTC」、「Others(その他)」らのドミナンスが大きく下落している事がわかりますね。しかしそんな中、USDTドミナンスが全く反応していないのが気になります。 USDTは、アルトが撤退タイミングに近づくに連れ、利益確保のために買われ始める傾向があります。アルト売買で得た利益をBTCに戻し、その間にBTCが下落してしまったら、せっかくの利益も台無しになってしまいます。それを考慮した上、USDT買って利益をある程度確保しておこう、といった算段ですね。 しかし現状、USDTのドミナンスはほぼ微動だにしていません。これを踏まえると、BTCは依然高値圏で推移しているが、多くのトレーダーは未だリスクオンと判断しているのでは…?「アルトの避難先をUSDTではなく、BTCだと判断してるのでは?」、といった考えに至りました。 もちろん、USDTへの退避は「BTC下落の可能性」を重視しての行動ですから、そもそもBTCが上がるとなれば、わざわざUSDTに退避するのではなく、BTCに退避すべきです。上昇した分、さらに差益が発生しますからね。 これらを踏まえた結果、現状の資金の流れからは「アルト↓、BTC↑」になりつつあるのかな?と結論に至りました。 主要アルトコインの動向 主要アルトコインの中でも気になるのは、やはりLTCですね。 黄色ラインのポイントを見ていただければ分かると思いますが、LTCが高値をつけて反転下落すると同時に、BTCが底形成を終え、上昇に転じています。 この点から、ここ最近の市場におけるLTCの影響力の大きさやLTC半減期に対する期待感、資金移動の転換点が明確になったと思います。 今回は先日まで相場を牽引してきたLTC、そして現状LTCには劣るものの、元祖先行指標であるETHの2通貨をピックアップして分析していこうと思います。(今回はUSDT建てのみの考察になります。) LTC 現状、BTC建ては崩れ始めたものの、USDT建てについては節目である113ドルを上抜けたため、視界も開け、かなり綺麗なチャートになっています。 ここからは参考になるレジスタンスラインも非常に少ないですが、大局的には「半減期直前までは上」でしょうし、可能であれば113ドルを背に押し目買いに徹して行きたいところですね。 参考サイト:『Litecoin Block Reward Halving Countdown』 ETH 現状、LTCほど勢いを感じないETHですが、現在レジスタンス周辺にて推移しているため、これを上抜けることができるか?といった状況です。 BTC建てではいまいちパッとしないチャートになってしまっておりますが、資金もそこまで抜けていない様子ですし、BTCが再度高値を目指す展開となるのであれば、ここから注目の通貨になると思います。 総評(まとめ) さて、それでは最後にまとめに入りましょう。 BTCは緑チャネルを基準に押し引き →高値圏でのチャネルは強含み 資金はアルト⇒BTCへ →主要アルトからも資金が抜ける? 今回は、恐らく資金流入先の転換期というのもあり、若干判断が難しかったですね。 また、つい先日から様々な取引所にて、マイナーコインが上場廃止されゆく傾向にあります。以前から、仮想通貨市場がさらなる繁栄を遂げるためには、これまで「数多くのコインに分散された資金が一部通貨に集中するための下準備」が必要不可欠と考えていたため、少しずつではありますがそれに向けた準備が整ってきているように感じました。 今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 現在、私えむけんが制作した動画教材『7日間でマスター!テクニカル分析とそれを元にしたトレード戦略』、好評販売中です! 今回のような、BTC分析やアルトコイン投資などの立ち回り方についても解説しておりますので、是非ご覧ください!(詳しくはコチラ)

特集・コラム
2019/06/06クリプトスペルズが今、熱い!!
昨年リリースが見込まれていたブロックチェーンのトレーディングカードゲーム「クリプトスペルズ」の正式リリースが間近に迫ってきました。 ブロックチェーンゲームファンの中では熱いブームになりつつあります。これまで、同じく日本初の「マイクリプトヒーローズ」が、ブロックチェーンゲームファンの心を掴んで来ましたが、クリプトスペルズによってマイクリプレーの時間の一部がクリスペに移行しそうです。 クリプトスペルズとは クリプトスペルズはブロックチェーンを用いたトレーディングカードゲームです。 シンプルなルールの対人のオンライントレーディングカードゲーム カードはレベルが上がるごとに得られる採掘で新規カードを手に入れることができる 所有カードはイーサリアムプラットフォーム上での権利の譲渡が可能 アカウントはtwitterに紐付けし管理を行なっている スタンダードなルールのトレーディングカードゲームですが、大きな特徴としてカードは採掘が可能で、多くプレーすることで新たなカードを入手することができます。 自分のカードはイーサリアムのネット上で取引を行うことができ、運営者の手を介さずにトレードも可能な仕組みとなっています。この流通の実現がブロックチェーンを使う理由となっています。 使用されるブロックチェーンはイーサリアムのERC721(説明記事はこちら)であり、多くのオープンマーケットが存在しますので流通経路は確保されているものになります。 ビジュアルは美しい精彩な系統の絵をモチーフにしており、大人も楽しめるものになっています。ゲームは、アプリはなくHTML5で構築されていますのでブラウザーにてプレーが可能です。 実際に現在、私が所有しているカードを紹介します。ビジュアルのイメージを掴んでいただけるかと思います。 クリプトスペルズのリリース予定 クリプトスペルズは2019年5月17日にオープンβ版が開始されました。4月にも一時短期的なベーターが行われましたが、今回は実際にプレーしたデータを本番にも引き継げるということで、多くのプレイヤーが喜び勇んで参加をしています。 本日(記事執筆時2019年5月18日)、朝5時にプレーをトライしたところ、簡単に相手が見つかりどれほど多くの人が参加しているのか肌で感じることができました。今後、6月以降に計画されている本リリースに向けての最終調整が行われていきます。 β時にはカードのトレードはできませんが、レベルや獲得カードは引き継ぐことができますのでプレーをして損はないでしょう。 クリプトスペルズの楽しさ 対人での対戦はとても面白い。そしてこのタイミングでは多くの初心者も参戦しており、トレーディングカードの達人でなくとも勝利の快感を味わうことができます。 複雑なルールがあまり搭載されておらず、カードの効果にてゲームを運ぶことができとてもわかりやすい設計になっています。私自身もあまりトレーディングカードゲームをやったことがなかったのですが、なんどかやるうちに、なんとなくわかってきました。 ただし、プレーを行うには大きめの横長の画面が必要なのでPCか大型画面のスマホでのプレーが快適であると思います。 コミュニティーも今回のタイミングでGaudiyと呼ばれるブロックチェーンベースのプラットフォーム上にオープンしました。プレイヤーとわいわいコミュニケーションが取れると思います。さっそく覗いてみましたら、クリスペ運営さんが商品を用意したユーザーどうしの大会が開催され始めた感じでした。面白いですね。展開早すぎです。 こちらから覗いてみてください https://gaudiy.com/signup/avJEInz3EXlxNXKMSWxR 攻略情報やゲームの詳細サイト 始めるにあたって参考になるサイトを少しだけ紹介しておきます。 *ブロックチェーンゲームの攻略系YouTuberカマモトさんのサイトが情報多いですね カマトモブログ クリプトスペルズ 攻略情報 *初期戦略を簡単に知りたい方はACEさんの記事が参考になるかと CryptoSpells(クリプトスペルズ)BETA版公開!最序盤の勝ち方! トレーディングカードゲームマーケット ブロックチェーンゲーム界隈のトレントとして、2019年はトレーディングカードゲームがくると思っています。特に海外勢の勢いがすごいです。 2018年の末にクリプトタイムズに寄稿させていただいた記事「2019年はオンライントレーディングカードゲームがブロックチェーンゲーム界を変革するか?」では、有望なブロックチェーントレーディングカードゲームを紹介しています。 その記事執筆時のクリプトスペルズは、2018年のリリース予定を延期し、ちょっと今後の動向がみえていませんでした。しかしながら、2019年に入り、突如ベーターの開始で多くのブロックチェーンゲーマの心を掴み不死鳥のように蘇ってきました。 クリプトスペルズのサイト構築ではマイクリプトヒーローズもコード提供などのサポートやSNS上で、公共の場での応援をおこなっていました。クリプトスペルズはマイクリプトヒーローズと肩を並べる可能性が高いですね。 トレーディングカードゲームはeSportsも開かれる、ゲーム会のキラーコンテンツです。クリプトスペルズは簡単なので、入門ゲームとしてふさわしいとおもいます。あなたもいかがですか?ぜひこちらからどうぞ。 クリプトスペルズ 早めに強くなって正式リリースに臨みましょう。ではオンラインであいましょう。はるか先生 のフォローもぜひお願いします。

特集・コラム
2019/06/05専業トレーダーえむけんの仮想通貨市場分析!【6月5日】
みなさん、こんにちは!えむけん@BinaryMkentです。 前回更新後、BTCも大きく下落しましたね。一時はかなり底堅い様子を見せていたため、「これはどうなんだ・・・?」と若干困惑していましたが、おおむね予想通りということで一安心しています。 さて、恐らくここからは、中短期的にもまだ下目線だと思いますが、まだまだ油断できません。今回もBTCとアルト市場、両方を踏まえて、今後の展開を予想していきましょう! それでは、早速BTCの分析から進めていきましょう。 BTCチャートの分析 BTCチャート(長期) まずは、BTCの長期チャートから見ていきましょう。 前回記事にて「ここで止まる可能性が高い」とお話しした、「8000ドル~8200ドル(緑ゾーン)」周辺で無事切り返し、その後7400ドルまですんなり下落してきました。私もずっとSを握りっぱなしだったので、ようやく一安心です笑 ここからは、短期足にて戻り売りポイントを設定し、その否定で短期転換判断を、もし戻り売られるようであれば、引き続き短中期の下落トレンドについていきながら利を延ばしていくのが妥当でしょう。(戻り売りポイントについては中期足分析に記載します) また、堅そうな価格帯としては、7400ドルの黄色ゾーン、そして6700ドル、6100ドルの緑ゾーン、この3つです。ですから、すでにSを抱えているのであれば、これらを基準に利食い判断を行い、スイングLの押し目買いをするのであれば、これらを参照して動くとよいでしょう。 では、ここからは中期チャートを元に、戻り売りポイントやそれを踏まえた今後の展開予想について考察していきましょう。 BTCチャート(中期) こちらが、BTC中期チャート(4時間足)になります。ちょっといろいろと書き込みすぎてややこしいかもしれませんが、一つずつ解説していきますね。 まず前回もお話したように、ここ数週間で最も意識されたのが白ペナントとチャネル(青)です。そして上下の矢印は、それぞれそのポイントで入ったであろうポジションです。左から順に見ていきましょう。 白矢印は、短期二番底をつけて直近高値を更新した際、そしてサポートラインが確定した後のライン接触で入ったと思われるロングポジションです。もちろんこれらのポジションは、チャネル下限割れで解消されている可能性もありますが、損益分岐点を割っていないため、依然ホールドされている可能性があります。 次に、オレンジ矢印。これらも先ほど同様、サポートラインの確定後に入ったと考えられるロングポジションです。しかし、これらのポジションは、損益分岐点を割っているため、すでに解消されている可能性が高いと思われます。 最後に青矢印。これは、チャネル推移濃厚になった後に入ったと思われるショートポジションです。私もこの1つ目、2つ目のポイントでSを入れていますが、現在これらのポジションはどれも含み益状態です。 そして、最も注目すべきは、チャネル下限割れという中期トレンドを否定したタイミングで入ったショート。恐らく、これが解消される展開となれば、再度上を目指す展開にもなりうると思われます。 つまりここからは、「黄色ゾーン下抜けで白矢印(ロング)が解消されるのか?」、それとも「戻り売りポイントであるオレンジゾーンを上抜け、青矢印(ショート)が解消されるのか?」といった状況ですね。 さて今回は、これらの既存ポジションの損益分岐点を元に、サポートポイントや戻り売りポイントを考察してみました。では、それらを総合して、今後のシナリオ考察を行っていきましょう。 BTCチャートの総評 さて、それではBTCチャートについてまとめていきましょう。今回、考えられうるシナリオは以下の2通り。 オレンジゾーンで戻り売り(青) オレンジゾーンでの戻り売り否定で上昇(白) まずは、「戻り売りがしっかり決まるかどうか?」ですね。これを否定するのであれば、先ほどお話したチャネル下限割れSの撤退にもつながるでしょうし、その後押し目を作ることが出来たのであれば、逆三尊の形成にもつながります。 逆に、戻り売りがしっかりと決まるのであれば、「引き続き6700ドル、6100ドルを目指す展開となるのでは・・・?」と見ています。 それでは次にドミナンス分析を進めていきましょう。 ドミナンス分析 ドミナンスチャートに関しては、「Trading View」を参考することにしております。(外部リンク:https://jp.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/) 前回もお話しましたが、5/13を境にBTCのドミナンスが反転下落、それに対して主要アルトのドミナンスが一部上昇しましたね。それ以降、あまり大きな動きはありませんが、少し拡大して見てみましょう。 5/13以降、どれも衰退の一途をたどっていますね。しかしここ数日、「BCHSV」、「LTC」、「TRX」の3通貨のドミナンスが綺麗に上昇してきています。(BTCSVについては、取り扱い取引所も少なく、出来高も少ないため、今回は考慮しません) ここで一度、流れをおさらいしてみましょう。 現状、『5/13以降、BTCからアルトへと資金が流れ、その後、主要アルトからジワジワと上記の2通貨へと流れていっている』といった状況だと思います。 そこで今後、資金流入先となった2通貨が衰退するのであれば、それらからも資金がUSDT(fiat)へ撤退してしまう、つまりBTCの下落がさらに加速してしまう可能性もあるわけです。ということは、ここで見るべきは、先ほどお話しした上記2通貨の推移でしょう。 ということで、今回は主要アルトの動向を踏まえたうえで、上記の2通貨について分析していこうと思います。 主要アルトコインの動向 主要アルトコインの中でも気になるのは、LTC、TRX、ETHですね。 ETHについては、特段ドミナンスが上昇していたわけでないですが、依然「再度推進波に移行するかどうか?」というようなポイントです。 今回はこの3銘柄をピックアップして分析していこうと思います。(今回はUSDT建てについても考察していきます。) LTC まずはBTC建てから。前回もお話ししましたが、依然買えるような状況ではありませんね。むしろ、「戻り売りに警戒」といった状況です。 USDT建てですと、大体BTCと似たような推移をしていますが、コチラも一旦の天井をつけたのでは?といった状況です。 どちらを見ても、「今から買いに動く」というのはやや厳しいですね。ただUSDT建てにおいては、黄色点線(113ドル)を上抜けると一気に視界が開けてきます。ここを抜けると、BTC建ても引っ張られる形で上昇していくと思われますので、リスク覚悟で今から拾うのではなく、「ラインブレイクに付いていく」というスタンスが妥当だと思います。 また、LTCについては、8月に半減期を控えていますので、仮に再度アルトブームが発生するのであれば、それを牽引する通貨となる可能性も大いにあると思われます。 参考サイト:『Litecoin Block Reward Halving Countdown』 TRX 現状、レジスタンスを上抜けているため、目線としては上、もしくは横・・・といった状況ですね。また同時に、チャネルを形成して推移しているため、ここからはこのチャネルを元に押し引きしていくのが妥当でしょう。 ですから仮に、このチャネルを下抜けるのであれば、資金撤退の可能性がある・・・、と判断していただければよいと思います。 USDT建てにおいても同様に、チャネル推移ですね。 BTC建てよりも角度を持って推移しているため、どちらかといえばチャネル下限で買っていきたい・・・、といった状況ですが、「今まで何度も上昇を阻まれてきた黄色点線を下抜けた際に、下げが加速してしまわないか?」という若干の懸念はあると思います。 ETH BTC建てでは、大きく上昇した後、「押し目を作れるのか?」といった状況ですね。 ここで、しっかり押し目を作ることが出来れば、レジスタンス(青)の上抜けも視野に入ってきますし、これを上抜ければ、恐らく黄色点線(0.04sats)も視野に入ってきます。 これらを踏まえると、比較的上目線ではあるんですが、これも「現状の押し目を守りきれるか?」次第ですね。 USDT建てについては、つい先日レジスタンス(黄色)に接触し、一時利食いムード・・・、といった状況だと思われます。 BTC建てではすでに押し目をつけていましたが、USDT建てを見た限りでは、依然高値圏のため、「様子見」がベストでしょう。 総評(まとめ) さて、それでは最後にまとめに入りましょう。 BTCはチャネル下抜け →戻り売り狙いだが、否定上げにも警戒 資金は依然アルトへ →USDTには流れていない(リスクオン) →リスクオフ転換は主要アルトを基準に判断 BTC重視だと下目線だが、アルト重視だとやや上目線 →BTC停滞+アルト上げの展開も 今回は、いつもよりアルト分析に比重を割きましたが、「BTC単体では下目線、アルト単体だとやや上目線」というように、やや判断が難しかったですね。 また、先週あたりから、国産通貨「モナコイン(Mona)」のCoincheck上場など、ポジティブなニュースに対して、市場がかなりいい反応を見せています。 こういった点からも、依然リスクオン相場であり、「アルトを買いながら、適切なポイントでBTCにショートを仕込んでいく」、というのがベストな立ち回りなのかな?と感じました。 今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 現在、私えむけんが制作した初心者~中級者向けの有料note、『7日間でマスター!テクニカル分析とそれを元にしたトレード戦略』、好評販売中です! 今回のような、BTC分析やアルトコイン投資などの立ち回り方についても解説しておりますので、是非ご覧ください!(詳しくはコチラ)
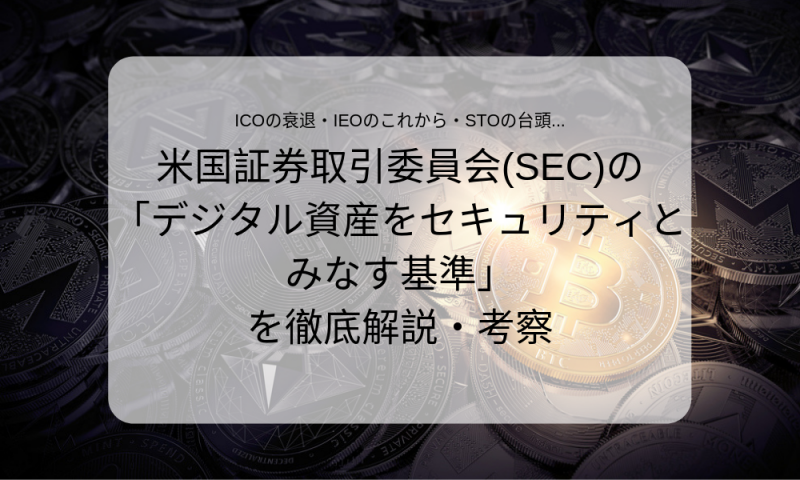
特集・コラム
2019/06/04SECの「デジタル資産をセキュリティ(証券)とみなす基準」に関して徹底解説・考察
米国において暗号通貨がセキュリティ(証券)としてみなされるかどうかにはここ数年大きな注目が集まりました。 業界とマーケットの発展の観点から見て、どれだけ簡単にアメリカでブロックチェーン系ビジネスを運営したり、投資家を募ったりすることができるかはとても重要なことです。 同国で証券発行にまつわる事例を取り締まるのは米国証券取引委員会、通称SECで、2018年に入ってからは同委員会の声明が世界中の暗号資産投資家や関連業者から重視されるようになりました。 同委員会は当初から2019年4月に到るまで暗号通貨がセキュリティかどうかを判断するための明確な基準を公表しておらず、結果として過去に米国投資家を対象に未登録ICOを行なった企業が同委員会から摘発を受けた事例も発生しました。 こちらのページでは、4月に入りようやく公開されたこの判断基準を詳しく、かつわかりやすく解説していきたいと思います。 判断基準の大元「ハウイ・テスト」 [caption id="" align="aligncenter" width="282"] ウィリアム・ハウイが創立した町「ハウイ・イン・ザ・ヒルズ」[/caption] ハウイ・テストとはW. J. Howey Co.という企業の資金繰り法にまつわる裁判を元に1946年に生み出されたもので、「ある商品が投資契約であるかどうか」を判断するためのテストです。 SECは公開した声明のなかで、ハウイ・テストについて次のように述べています。 「合衆国最高裁判所のハウイ判決および関連する法律によれば、他社の取組みに依存した合理的な期待利益が存在する共同事業への投資は"投資契約"であることがわかっている。」 また、暗号通貨という観点から見たハウイ・テストには次のような条件が付くといいます。 「ハウイ・テストでは、商品そのもの(デジタル資産)の形や意義だけでなく、デジタル資産が発行・販売・再販売される周辺環境(セカンダリ市場を含む)にも焦点が当てられる。」 「連邦法では、デジタル資産を含む全てのセキュリティ(証券)の発行・販売は、事前に申請・登録するか、登録免除となる条件を満たしていなければできない。」 これらの声明からは、暗号資産がセキュリティであるかどうかはトークンセール(プライマリ市場)自体だけではなく、一般的な取引所(セカンダリ市場)での状況にも関係する、ということがわかります。 ハウイ・テストの3本柱 ハウイ・テストを用いた分析では、以下の3つの項目を満たしている商品を投資契約(セキュリティ)と判断します。 金銭の投資 SECによれば、この第一の項目の「金銭」は法定通貨だけでなく、デジタル資産も含むといいます。 「デジタル資産の発行・販売は、法定通貨や他のデジタル資産で対象となるデジタル資産を購入・交換する行為を含むため、大体の場合ハウイ・テストの第一の項目を満たす。」 共同事業 共同事業(Common Enterprise)とは、複数の企業がひとつの目標に向かって各々の取組みを行う事業を指します。 SECによれば、共同事業の存在は投資契約の特徴的な側面であり、デジタル資産を取り扱ったものでも大体の場合は共同事業の存在が確認されるといいます。 他者の取組みによってもたらされる合理的な利益の期待 3本柱の最後は「他者の取組みによってもたらされる合理的な利益の期待」と呼ばれ、題名だけでは定義がわかりにくいものとなっています。 以下ではこの項目だけにフォーカスを当て、「他者の取組みへの依存」と「合理的な利益の期待」の意味を詳しく解説していきます。 「他者の取組みへの依存」とは? ここでいう他者とは、開発団体(デベロッパー)や、プロモーターやスポンサーなどの第三者を指し、英語では"Active Participant"または"AP"と呼びます。 「他者の取組みへの依存」とは、「トークン購入者がAPの活動(開発・宣伝等)から発生する利益を見込んでいる」ということを意味します。 SECは、以下の項目のうち、当てはまるものが多いほど「他者の取り組みへの依存」が強い傾向にあるといいます。 APが事業の開発や改善、運営、プロモーションなどに関する重要な責任を負っている。 トークン購入者が、APがトークンを従来の用途に利用できるようにするためのタスクを行ってくれると期待している。 デジタル資産の販売時にその基盤となるネットワークやプラットフォームが出来上がっていない場合など。 APが対象となるトークンの市場や価格を支援している。 APがトークン生成・発行の権限を握っている。 トークンの買い戻しやバーニングなどによる需要供給のコントロール。 APが調達資金の使い道や、デジタル資産の流動性をコントロールしている。 APにデジタル資産の価値を上げる活動をするインセンティブがある。 APが何らかの形で資産をステーキングしている。 APやその他マネジメントの給与・報酬が対象となるデジタル資産で支払われる。 APがネットワークやデジタル資産の知的財産権を握っている。 また、「他者の取組みへの依存がある」という判断をのちに撤回するには、以下のような項目を考える必要があるとされています。 当時のAPやその後継者の活動が未だ対象となるデジタル資産への投資のリターンに影響を及ぼしているかどうか 投資家が未だAPの取組みに依存した利益を見込んでいるか APの活動が未だ対象企業の成功に関わっているか まとめ:こんなケースは「他社の取り組みへの依存」かも? プロダクトがまだ出来上がっていない APによるトークンの買い戻しやバーニング APにトークンの価値を上げるインセンティブがある これらのポイントは「投資家がAPの取組みを見込んでいる」とみなす要素となるようです。 「合理的な利益の期待」とは? 「合理的な利益の期待」とはプロジェクトに関するリサーチなどを経た上で「APが対象となるデジタル資産の価値向上に繋がる取組みをすることがわかっている」ということを意味します。 SECは、以下の項目のうち、当てはまるものが多いほど「合理的な利益の期待」が強い傾向にあるといいます。 デジタル資産の保有者が、発行企業の収益の一部を獲得したり、価値の向上から発生する利益を確定したりする権利を持つ。 配当型トークン(取引所トークンやエクイティトークン)を含む 対象となるデジタル資産を暗号資産取引所などのセカンダリ市場で他の資産と交換できる、または将来できるようにする予定である。 対象となるデジタル資産が、基盤となるネットワークの機能を必要とする者だけでなく、世間一般に販売されている。 特定のプレイヤーがネットワークの一般的な利用に必要な量以上のトークンを購入する場合も含む。 以下のいずれかを利用して、対象となるデジタル資産を投機として売り出している。 対象となるデジタル資産の販売、またその購入者がそれぞれ「投資」「投資家」とラベルづけされている。 調達資金が対象となるデジタル資産やそのネットワークの開発・発展に使われる。 将来的にリリースされるネットワークの正式サービスと、APがそれを開発するという見込み。 「対象となるデジタル資産を他の資産と交換できること」を売りにしている。 ネットワーク運営の収益性やデジタル資産の価値がマーケティングやプロモーションに大きく左右される。 対象となるデジタル資産を取引できる市場がある、またはAPがそういった市場を作ることを約束している。 「合理的な利益の期待」という判断をのちに撤回するには、以下のような項目を考える必要があるとされています。 購入者が、APによるプロダクト発展への努力がこれ以上対象となるデジタル資産の価値向上に繋がると期待していない。 対象となるデジタル資産の価値と、それを利用して得ることのできる商品やサービスの価値が安定した相関性を持っている。 保有者は対象となるデジタル資産をその従来の目的(ネットワークのユーティリティ等)に使用することができる(=プロダクトが完成している・リリースされている) 対象となるデジタル資産の増価は偶然によるものである(=従来の目的とは関係がない) APがインサイダー情報を保有していない まとめ:こんなケースは「合理的な利益の期待」かも? トークンが取引所に上場している トークンの販売対象が必要なユーザーだけに絞られていない トークンの価値がマーケティング・プロモーションに大きく左右される これらのポイントは、「投資を目的としたデジタル資産の購入」とみなす要素になるようです。 セキュリティとみなされない暗号資産 ここまででは、SECの声明のうち、対象となるデジタル資産がセキュリティとみなされる可能性の高いケースについて解説してきました。 SECによれば、合衆国最高裁判所ではデジタル資産をハウイ・テストにかける際、その「トランザクションの経済的な実態」に着目するとしています。 これは、対象となるデジタル資産が将来的な価値の向上を見越してではなく、純粋にネットワークやサービスを利用するために購入されているかどうか、ということを意味します。 同声明によれば、デジタル資産は以下の項目のうち当てはまるものが多いほどハウイ・テストに当てはまらない(セキュリティではない)可能性が高いといいます。 対象となる分散型台帳ネットワークは完全に開発が済んでおり、すでに運営開始済みまたは運営可能である。 保有者は、対象となるデジタル資産を購入後すぐその従来の目的に利用することができる。 対象となるデジタル資産の発行プロセスや構造が、その価値に対するスペキュレーションを起こすものではなく、ユーザーのニーズに沿ったものである。 対象となるデジタル資産はその基盤となるネットワークでのみ使用することができ、購入者は一般的な利用目的に沿った数量のみを保有・交換することができる。 対象となるデジタル資産が増価する見込みがない。価値が一定、または逓減していくようにデザインされたデジタル資産など、合理的な購入者が投資としてリターンを見込まないようなもの。 「暗号通貨」と呼ばれるデジタル資産のケース: 対象となる暗号通貨を購入後すぐ様々なモノやサービスのペイメントに使用することができる、または、法定通貨の代用として利用できる。 他のデジタル資産や法定通貨を介さず、対象となる暗号通貨で直接支払いができる。 商品やサービスの所有・利用権を表す暗号資産(ユーティリティトークン)のケース: 対象となるデジタル資産を完成したネットワーク/プラットフォーム上でそのサービス利用などに使用できる。 対象となるデジタル資産と、それが所有・利用権を与える商品やサービスの価値に相関性がある。 対象となるデジタル資産の増価は偶然によるものである(=従来の目的とは関係がない)。 対象となるデジタル資産の宣伝・マーケティング内容が、その資産の市場価値向上などではなく、資産やネットワーク自体の機能性を強調したものである。 対象となるデジタル資産は、スペキュラティブな市場ができないように譲渡・交換が制限されている。 APが対象となるデジタル資産のセカンダリ市場(取引所上場)を創設した場合、そのネットワークのユーザーのみが資産の取引をすることができる。 まとめ: セキュリティにあたらないトークンとは? ネットワークやプラットフォームがすでに稼働済み・トークンもすぐに利用可能である トークンの価格上下は偶然によるものである(スペキュレーションがない) 該当ネットワークのユーザーのみが適量のトークンを保有・交換している これらのポイントは「デジタル資産がネットワークの利用のみに使用される」ことを証明する要素となるようです。 考察その1: ICO・STO・IEOのこれから ICO(イニシャル・コイン・オファリング)の衰退 今回SECが公表した基準は、かなり厳しいものであると言えます。 そもそもICO(イニシャル・コイン・オファリング)は、ブロックチェーン系プロジェクトが自社のプロダクトアイデアを実現するために、先にトークンを販売することで資金を調達する、というものです。 しかしこれは、「APが将来プロダクトを完成させるという見込み」の元に、未だ完成していないプロダクトに金銭を投資する行為にあたるため、セキュリティとしてみなされるケースが大半になるのではと考えられます。 こうなると、トークン発行に際し証券登録や免除申請を行わなければならず、多くの場合は莫大な費用・時間がかかり、販売できる対象投資家にも制限がかけられてしまいます。 こういった側面を考慮すると、今後少なくとも米国ではICOの数が激減していくのではないかと考えられます。 IEO(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング)はこれからどうなる? IEO(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング)とは、大手暗号資産取引所が、自社セレクトしたプロジェクトのトークン発行市場(プライマリ市場)を設けるというサービスで、2019年に入ってから大きく流行しています。 もっとも有名なプラットフォームはBinance(バイナンス)のBinance Launchpadで、他にもHuobiやOKExなどの大手取引所が類似事業の参入を決定しています。 こういったサービスで取り扱われるプロジェクトは、プロダクトの提供を少なくとも数ヶ月内に収めたものが多いですが、ICOの例に漏れず、他者の取組みに依存した期待利益の存在する共同事業がほとんどと言えるでしょう。 また、IEOによるトークンはプラットフォームを提供している取引所の暗号通貨(バイナンスならBNB)で支払われることが大半であるため、その取引所通貨自体もセキュリティの判断基準に触れかねません。 IEOを行なっている取引所は中国・シンガポール系がほとんどですが、米国で同様のサービスを行うことは当面不可能となるのではと考えられます。 STO(セキュリティ・トークン・オファリング)の台頭 一方、証券発行をブロックチェーン上で行うSTO(セキュリティ・トークン・オファリング)は今後おそらく数を増していくのではないかと考えられます。 企業の株式や債券だけでなく、不動産やコモデティなど、セキュリティではない商品をトークン化し販売するケースもSTOと呼ばれることが多いです。 しかし、STOはICOやIEOとは全く異なるものである点に注意が必要です。STOとは、あくまで既存の金融商品をブロックチェーン上で発行する、というものに過ぎません。 一般的なユーティリティトークンも、今後米国ユーザーを対象に含むネットワークを展開していくには、少なくとも一時的には証券として登録する必要が出てくると言えるでしょう。 STO(セキュリティ・トークン・オファリング)とは?ICOとの違いも交えて解説 - CRYPTO TIMES セキュリティにあたらないデジタル資産を発行するには? 今後、米国投資家を対象にデジタル資産を発行するには、証券登録または免除申請を行うか、プロダクトが完成・成熟してからトークンを販売するかを選ばなければなりません。 ICOが流行していた時に比べると、どちらの選択肢も開発団体や関連企業により多くの資金を要求することとなります。 考察その2:「技術発展を妨げない法規制」は達成できているか? 宣伝(業界の成長)と投資家保護(スキャム防止)のバランス SECの委員長を務めるHester Peirce氏は、同委員会の意見が大きく注目され始めた2018年当初から「技術発展を妨げない法規制」を考案するとしてきました。 これはつまり、ブロックチェーン技術の発展や業界の成長を促す宣伝を許容しつつ、それを逆手にとるようなスキャムが淘汰されていくような決まり、ということです。 [caption id="" align="aligncenter" width="158"] Hester Pierce氏[/caption] 今回の声明を見ていくと、確かにこれまで存在したようなスキャムは今後ほぼ登場してこないだろうと考えることができます。 一方、この判断基準がブロックチェーン技術の発展を妨げてしまうかどうかは、上項で箇条書きにした項目がいくつ当てはまればセキュリティとみなされるのか、そして証券登録や免除申請にどれくらいのコストがかかるのかに依存してくるでしょう。 集権化(セントラリゼーション) 今回公表された判断基準は、分散型・無政府的な世界の到来を期待する人々(若年層に多いと言われる)にとっては残念なニュースであると言えるでしょう。 実際のところ、米国投資家を対象に今後とも問題なく資金調達を行えるのはステーブルコインやトークナイズドアセット、エクイティトークンなどに限られてくると考えられます。 したがって、少なくとも米国では、「アルゴリズム集権型」の経済やガバナンスは違法化され、資金がないとプロジェクトを展開できない「国家集権型」のスタンスが固められつつあると言えます。 まとめ SECによる今回の発表は、今後のブロックチェーン系プロジェクトの発展しやすさに大きく関わってくるものです。 ハウイ・テストを用いた米国の基準では、デジタル資産の「経済的な実態」を基に、そのトークンがプロダクトあるいは投機どちらにフォーカスを当てたものなのかを判断していくようです。 特に、ハウイ・テストの「3本の柱」のひとつである「他者の取組みによってもたらされる合理的な利益の期待」は、開発団体やプロモーターなどの「AP」の役割が重要になってきます。 このルールによると、「未完成のプロダクトが完成すると見込んで投資する」ICOの基本形はセキュリティとみなされるケースが一般的となってくるのではないでしょうか。 現段階では具体的にどのトークンがセキュリティにあたるのかは不明確なため、今後SECが基準公表前に実施されたICOなどにどのような措置を行うのかに注目が集まります。

特集・コラム
2019/05/29暗号資産市場の相関性が2019年に入り低下していることが明らかに − HodlBot調べ
バイナンスやクラーケンで自動リバランシング機能付きのポートフォリオを組めるアプリを提供している「HodlBot」のチームが、2019年の暗号資産市場の相関性(Correlation)に関する調査を公開しました。 市場の相関性は、パッシブ投資の肝である資産の分散(Diversification)をうまくこなす上で重要なインジケーターです。当リサーチでは「暗号資産市場の相関性は2019年に入り低下している」と言う結果が出ています。 これは一体どういうことを意味するのでしょうか?当記事では、実際の計算手法やデータの信憑性について触れつつ、このHodlBotの研究調査の結果を徹底解説していきます。 はじめに: 相関性(Correlation)とは? 相関性とは、ある2つ(以上)の変数が「どれくらい一緒に上下するか」を表すものです。 例えば、「テストの点数と費やした勉強時間」の関係性を調べるためにクラス全体(20人)のデータを取ったとしましょう。 [caption id="" align="aligncenter" width="667"] ※解説のために人工的に作成したデータです。[/caption] 「テストの点数と勉強時間」のグラフを見ると、基本的には勉強すればするほどテストの点数も伸びていることがわかります。そして、相関性は約0.916と出ています(計算方法については後ほど触れます)。 このように、ひとつの変数が上昇するともうひとつの変数も上昇する相関性を「順相関」と呼びます。数学的には、相関性ρが0 < ρ ≦ 1であれば順相関と言うことができ、値が1に近ければ近いほど上昇幅の比率も等しいことを示します。 相関性ρ = 0の場合は変数同士に相関関係がないということになり、-1 ≦ ρ <0の場合はひとつの変数が上昇するともう片方は下降する「逆相関」であるといいます。 例えば、「テストの点数と前日に飲んだビールの本数」はおそらく逆相関の例になるのではないかと予想できます。 調査方法・結果 HodlBotの調査目的は「時価総額トップ200通貨の価格」と「市場全体の時価総額」の相関性を算出することです。まずは、このプロセスをわかりやすく段階分けしてみましょう。 時価総額N番目(N = 1であればビットコイン)の価格データと、市場時価総額のデータを用意する。 市場時価総額から、N番目の価格データを引く。こうすることで、市場時価総額からN番目のコインの時価総額を除外し、重複計算を防ぐ。 N番目のコインの価格データと、それを除いた市場時価総額の相関性を計算する。これをN = 1からN = 200まで繰り返す。こうすることで、トップ200の通貨と市場時価総額の相関性のリストが出来上がる。 [caption id="" align="aligncenter" width="478"] ビットコイン(N = 1)と市場の相関性は、約0.92と出ている。ビットコインが60%近いドミナンスを占めていることを考えると当然の結果と言える。[/caption] 当調査のデータはCoinMarketCapから引用されており、データの対象期間は全て2019年となっています。 こうして出来上がったリストを、相関度と頻度を軸としてヒストグラムにします。 ヒストグラムをみてわかる通り、2019年現時点の暗号資産の相関性は大幅に低下していることがわかります。この結果は「ウェルチのt検定」という手法によって、偶然による可能性が極めて低いことが確かめられています。 また、時価総額トップ20同士の相関性を見ると、TRONのみが目立って逆相関にあることがわかります(拡大図はコチラ)。 相関性が低下したことは良いこと? 相関性の低下は、ポートフォリオのリスク分散という視点からみて良いことであるといえます。これは「あるアセットの価格の上下に他のアセットがつられて動きにくい」ということを意味するからです。 例えば、時価総額トップ20の暗号通貨それぞれに投資資産の5%ずつを割り当てるポートフォリオを作ったとしましょう(実際には時価総額の大きい通貨により大きな割合を充てる「加重平均法」が一般的です)。 2018年の相関性の場合、仮にビットコインの価格が大幅に降下し市場の時価総額が下がったとすると、他の通貨も一緒に下がることになり、大損してしまうことになります。 しかし、2019年の相関性ではその下がり幅が小さくなり、かつ少なからず逆相関にある通貨の価格は逆に上昇して損失をカバーできるため、ひとつの資産(例えばビットコイン)の価格が下落してもポートフォリオ全体はそこまで下がらないことが予想できます。 つまり、投資資産を相関性の低いアセットに広く分散することでリターンを維持したままリスク(ポートフォリオ全体の下り幅)を小さくすることができるということになります。 調査の短所 当調査の結果は、暗号資産市場が少しずつ成熟し始め、市場全体が投機に大きく左右されにくくなってきた証拠であるといえるかもしれません。 ステーブルコインやセキュリティトークン、ユーティリティトークンなどそれぞれ大きな違いのあるアセットが登場してきたのもこの現れであるといえます。 しかし、どの調査もそうですが、結果を鵜呑みにしてしまうのはよくありません。今回のHodlBot調査も、主にデータの信憑性などは疑ってかかるべきだといえます。 データの信憑性 当調査は、価格・時価総額データをCoinMarketCapから引用しています。 しかし、先日のBitwiseのリサーチなどで明らかになった通り、同サイトのデータはマイナーな取引所のボリュームかさ増しなどによって時価総額データなどの正当性が大きく疑われています。 事実、CoinMarketCapの運営チームも各取引所にライブデータの提供などを要請しており、今年5月にはテザー問題などで信用の疑われているBitfinexをリストから除外しています。 したがって、市場の相関性のおおよその動向はあっているかもしれませんが、このようにあまり信用できないデータをインプットとして使っていると「ガーベッジイン・ガーベッジアウト(ゴミを入れればゴミが出てくる)」となってしまう恐れがあります。 Bitwiseによる「BTC取引ボリュームの95%は偽装されている」SECへの調査報告書まとめ - CRYPTO TIMES リニアリティ 当調査で使われている相関係数は「ピアソンの相関係数」といい、相関を調べる2つの変数の「線形関係」を仮定としています。 「線形関係」とは、変数データがおおよそ直線上に分布していることを意味します。例えば、冒頭で解説した「テストの点数と勉強時間」のグラフは、おおよそ線形に分布していることがわかります。 しかし、暗号資産以外の金融商品の価格や、スペキュレーションやアダプションなどに起因する投資家のセンチメントが大きく関わる暗号通貨市場は、線形関係では表せない可能性があります(例えば下記画像の"d"など)。 まとめ: 相関性は常に変わり続けるもの この記事では、HodlBotによるレポートの調査方法を詳しく解説し、その結果の有用性・信用度にも触れてきました。 市場の相関性は常に変わり続けるもので、いずれは4月以降のデータも含めて再度計算し直さなければなりません。これは、HodlBotが公開している過去4年間の相関性の推移を見ればよくわかります。 2019年全体、そして2020年の市場の相関性はもちろんまだ誰にもわかりません。パッシブ投資(分散型投資)では、自己裁量で一定期間ごとに相関性を見直し、それに基づいて各通貨の保有割合を変えていかなければなりません(リバランシング)。 リバランシングのコツについては「行動経済学から見る仮想通貨」シリーズでも詳しく解説していますので、興味のある方はぜひ目を通してみてください。

特集・コラム
2019/05/25専業トレーダーえむけんの仮想通貨市場分析!【5月25日】
みなさん、こんにちは!えむけん(@BinaryMkent)です。 前回更新後、BTCは大きく下落しましたが、再度持ち直し、前回記事更新時とまったく同じ価格帯にて推移していますね。 パッと見、状況は変わっていないようにも見えますが、確実に分析材料は増加しています。今回は、それらを元に「前回更新時からの変化」に焦点を当てて、分析していこうと思います。 それでは、早速BTCの分析から進めていきましょう。 BTCチャートの分析 BTCチャート(長期) まずは、BTCの長期チャートから見ていきましょう。 現在、前回記事にて「ここで止まる可能性が高い」とお話しした、「8000ドル~8200ドル(緑ゾーン)」周辺にて推移していますね。 推移している価格帯こそ変わっていませんが、前回更新後から7000ドル周辺まで振り落とされた後、再度同価格まで急上昇してきました。つまり、それだけ安値が堅い(買いが強かった)ということでしょう。 これについては恐らく、アルトコイン市場の状況などが起因していると思いますが、現状の様子だと、この8000~8200ドルについては、依然上値も重いままだと思われます。 とはいえ、日足だけでは具体的な想定シナリオやそれに対する動き方なども不鮮明なままです。ですから、ここからは中期チャートを元に、「今後、どう動いていく可能性があるのか?」について考察していきましょう。 BTCチャート(中期) こちらが、BTC中期チャート(4時間足)になります。 前回記事でもお話ししましたが、「8000~8200ドルを基点に上げるか?下げるか?」については、この価格帯でのパターン形成、成立を追っていくのが妥当でしょう。 そして現段階から考えられるパターンは、「アセンディングトライアングル(青)」と「上昇チャネル(橙)」、この2通りです。 これらのチャートパターンは、どちらも「安値を切り上げている」ことから、比較的推進力(上昇の力)がしっかりしている際に現れる傾向があります。 ですが現状、このパターンを形成しているのは高値圏。仮に、これが安値圏での成立であれば、パターン成立からのロング(買い)は至極妥当な判断です。しかし、これらのパターンが高値圏で成立…、となると、素直に上抜けるよりも、「ダマシ」になる可能性の方が高くなります。そしてその場合、ロングポジションのロスカットを巻き込んでの下落になるため、下落幅も比較的大きくなります。 そのため、仮にこの2つのパターンが成立(上抜け)したとしても、その上抜けに対して安易についていかない方がよいと思います。 BTCチャートの総評 さて、それではBTCチャートについてまとめていきましょう。今回、考えられうるシナリオは以下の3通り。 アセンディングトライアングル上抜け →チャネルを基準に反転下落(橙) アセンディングトライアングル下抜け(青) アセンディングトライアングル上抜け →引き続きチャネルを基準に上昇(白) 今回は3通りのシナリオをご紹介しましたが、MACDのダイバージェンス(上昇力の衰退)等も踏まえると、橙シナリオ、青シナリオのような転換シナリオが最も現実的だと考えています。 また個人的には、「アセンディングトライアングルを上抜けてチャネルまで上昇した後、アセンディング上抜けで入ってきたロング勢のストップロスを巻き込んでの下落(本格調整開始)」という橙シナリオが一番しっくりきましたね。 それでは次にドミナンス分析を進めていきましょう。 ドミナンス分析 ドミナンスチャートに関しては、「Trading View」を参考することにしております。(外部リンク:https://jp.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/) 5/13を境にBTCのドミナンスが反転下落、それに対して主要アルトの一部ドミナンスが上昇しています。恐らく、BTCから主要アルトへと資金が流れているのでしょう。 主要アルトのドミナンスチャートを少し拡大して見てみましょう。 ドミナンス上昇の中でも目立つのは、ETHやXRP、BNB、Othersですかね。BTCのドミナンス下落に対し、Tether(USDT)ドミナンスが微動だにしていない点を踏まえると、現状は依然「リスクオン相場」と判断するのが妥当でしょう。 ですが、こうしたリスクオン状態の時こそ、逃げ時(リスクオフ転換ポイント)を見抜き、次の動きに備えておくべきです。 今回は、BTCから資金が流れたであろうアルトコインをピックアップし、それらの逃げ時(リスクオフ転換ポイント)という観点から主要アルトコインを分析していこうと思います。 主要アルトコインの動向 主要アルトコインの中でも特別気になるのは、EOS、LTC、BCHABCですね。どれも、BTCよりも先に上昇しており、BTCの初動を作り上げたと言っても過言ではないでしょう。 今回はこの3銘柄、加えてつい先日再度凄まじい上昇を見せたBNBの4銘柄に的を絞って、それぞれの転換ポイント、つまりリスクオフ転換へのタイミングについてお話ししていこうと思います。 EOS 一言で言うと、「買える状況ではない」ですね。 すでにダイバージェンスの発生後、大きく下落し、トレンドラインを下抜け・・・。そして現在、頭上にレジスタンスライン(青)も控えているため、買い場というよりは逃げ時のように見えます。 参考ポイントとしては、レジスタンスライン周辺の黄色□。ここを基準にリターンムーブ(反転下落)してくるようであれば、その後一気に資金が抜ける可能性もあるため要注意です。 LTC こちらも先ほど同様、買える状況ではないですね。 つい先日のBTC上げは、LTCが初動のようにも見えましたが、その初動もリバ狙いによる上昇と判断するのが妥当でしょう。 注目ポイントとしては、EOS同様黄色□。ここを抜けるようであれば、ダブルボトムの成立ゆえ、雰囲気も変わってくると思いますが、ここを抜けれないとなると再度資金が抜けていくのも時間の問題でしょう。 BCHABC こちらも買い場というよりは、むしろ売り場ですね。 水平ライン(黄色)をネックラインにしてダブルトップ成立。そして現在、その後のリターンムーブ(反転下落)になりうるポイントです。 こちらについても黄色ラインを上抜けることが出来るのか?否か?を元に、利食い期(リスクオフムード)に向かうのかを判断すると良いでしょう。 BNB 最後にBNBですね。 ダイバージェンスの発生後大きく下落し、緑チャネルを下抜け。一時目線が下になるかと思いきや、半値(黄色□)を機に急上昇し、現在再度チャネル内に回帰した上に直近高値周辺にて推移しています。 このように、黄色□から恐ろしいほどのV字回復を見せているわけですが、その分短期利食い勢も多いと思われます。そのため、以降は「現在の上昇に対する調整がどこで終わるのか?」が非常に重要になってきます。 現在の上昇を期に、大きく資金が抜けるようであれば、市場の判断はリスク回避ムード。逆に、資金があまり抜けない(下落幅が小さい)ようであれば、その分長期ホルダーが買い支えている、つまり、チャネル内で落ち着いた後、再度高値更新に向かう可能性が高い・・・と判断すべきでしょう。 総評(まとめ) さて、それでは最後にまとめに入りましょう。 BTCは緑ゾーンにてアセンディングorチャネル →上抜けダマシに要警戒 資金はBTC⇒アルト →USDTには流れていない(リスクオン) →リスクオフ転換はアルトを基準に判断 主要アルトのほとんどは売り時→USDTドミナンスに要注目(上昇開始=リスクオフムードへ) 今回の分析を通して、主要アルトコインの多くは、どちらかといえば「売り時」というような印象を受けました。 当然、これを境に主要アルトが売られていくようであれば、今後BTCやUSDTを経由して資金が流出していく可能性があります。そのため、今回分析したアルトコインの動向はもちろん、USDTドミナンスの上昇には要注目しておくべきでしょう。 今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 現在、私えむけんが制作した初心者~中級者向けの有料note、『7日間でマスター!テクニカル分析とそれを元にしたトレード戦略』、好評販売中です! 今回のような、BTC分析やアルトコイン投資などの立ち回り方についても解説しておりますので、是非ご覧ください!(詳しくはコチラ)

特集・コラム
2019/05/19HitBTCで怪しい動き、ビットコイン残高はわずか356BTC – BitcoinExchangeGuide調べ
大手暗号資産取引所・HitBTCで、暗号資産の引出しが数日から数週間にわたって滞っているケースがネット上で多数報告されています。 HitBTCはこの遅延に関し、ツイッター上でこの状況を非難したインフルエンサーの資産引出しを優先確保するなどといった怪しい動きを取ったことがわかっています。 通常、取引所ではサードパーティ側の障害の可能性も含めフィアット(法定通貨)の引出しが滞ることはありますが、暗号資産が引き出せないケースは取引所側が資産を盗難された、あるいは持ち逃げしたなどといった最悪の事態が大いに考えられます。 BitcoinExchangeGuideが顧客資産の在りかに迫る BitcoinExchangeGuide (BEG)はHitBTCの資産の在りかを徹底探索したレポートを公開しており、なんとHitBTCのビットコイン残高はわずか356BTCであるという結果を報告しています。 [caption id="" align="aligncenter" width="721"] (Crystal Blockchainを利用したデータ)[/caption] 上の画像は、顧客口座やホット・コールドウォレットなどを含むHitBTCアドレス宛に送金されたBTCと、HitBTCから出金されたBTCそれぞれの内訳を示しています。 取引所アドレスへのインフロー 画像左側、HitBTCアドレス宛のBTC送金内訳を見ると、40%近くが「ギャンブル」カテゴリのアドレスから送金されていることがわかります。 ギャンブルカテゴリの内訳を見ると、CoinGaming.ioというサービスが送金額全体の41%ほどを占めていることがわかります。 BEGの調べでは、CoinGaming.ioの担当人物・団体はギャンブル関連の犯罪と強い結びつきのあるパナマと関わりがあることがわかっています。 また、BitThumbやZaif(ザイフ)のハッキング事件で盗難された暗号資産もCoinGaming.ioに流れているといいます。 取引所アドレスからのアウトフロー 取引所アドレスからの出金先は主に「信頼された取引所(0.22%)」と「未定義(99.8%)」の2つに分かれています。「信頼された取引所」カテゴリは、HitBTCのコールドウォレットなどとみられるアドレス群です。 出金先アドレス群「未定義」カテゴリの資産の元(インフロー)をたどると、怪しいソースが出てきます。 赤枠・オレンジ枠: HitBTC自身からのインフロー。赤枠の方は「信頼された取引所」としてタイプ付けされている一方、オレンジ枠の方は非公式であることがわかる。つまり、HitBTCは約8647BTCをなぜか別口座に一度移してから取引所へ送金し直していることがわかる。 黒枠: 暗号資産ウォレットサービス・Freewalletからのインフロー。Freewalletでは、運営者が顧客の資産を盗み取ったとする証拠やケースが多数浮上している。 青枠: インフロー内訳で解説したCoingame.ioとの関連性はここにも現れている。 このビットコインのアウトフローは以下のアドレスに出金されています(送金額トップ10)。 Bitfinex Binance Bitstamp Bittrex Poloniex Coingaming.io BitMEX OKEx Huobi Coinbase BTC残高合計−356BTC 「信頼された取引所」および「未定義」カテゴリのアドレス群には、インフローからアウトフローを引いて以下の額が残っていることになります。 信頼された取引所 = 191.60 BTC 未定義 = 166.3977 BTC したがって、HitBTCは未だ一般に知られていないウォレットを持っていない限りたった356BTCしか保有していないことになり、顧客の暗号資産引出しが滞っていることにも説明がつきます。 この調査は当然BEG記者が自己収拾した情報に基づくもので、HitBTCは公式テレグラムで「引出し遅延問題の解決に取り組んでいる」としたままです。 今月15日には、ニュージーランドの取引所・Cryptopia(クリプトピア)がハッキング被害後の事業立て直しに失敗し破産手続きを開始しています。 仮にこの調査が正しいとして、HitBTCが破産手続きを出そうことがあれば、資産持ち逃げなども十分に疑っていかなければならないでしょう。

特集・コラム
2019/05/16Tendermintの概要と仕組み、Cosmosとの関連性、取り巻くエコシステムに関してを解説
異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティに関しての問題を解決するプロジェクトである『Cosmos』は先日メインネットをローンチしました。 そんなCosmosは、Tendermintが提供するフレームワークを利用して開発されたブロックチェーンの一つです。 Tendermintはブロックチェーンの開発において必要とされる要素を提供し、開発をより容易にするだけでなく、異なるブロックチェーン間におけるインターオペラビリティも実現(Cosmos)することができるとされています。 本記事では、Tendermintとは一体何か? どのようにインターオペラビリティが実現されるのか? Cosmosとの関連性や周辺のエコシステムについてをまとめていきます。 Tendermintとは? Tendermintは、分散ネットワークにおける合意形成を安全に行うことを可能にするソフトウェアです。 これはブロックチェーンなどのアプリケーションと組み合わせることができますが、それによりスケーラビリティや開発の難しさといった問題を解決することもできます。 BitcoinやEthereumとTendermint Tendermintをより深く理解するために、ブロックチェーン開発における基本的なアーキテクチャを見ていきます。 ブロックチェーンのアーキテクチャでは、以下の3つのレイヤー(アプリケーション・合意形成・P2Pネットワーキング)がその構成要素となります; BitcoinやEthereumなどのブロックチェーンにおいて、この3つのレイヤーは深く相互に依存(Monolithic的)しており、これがブロックチェーンのアプリケーションの開発を難しくしています。 一方で、BitcoinやEthereumなどのコードベースを利用して開発を行う場合、スループットの問題などからアプリケーションの複雑さに制約がかかってしまいます。 Tendermintを利用すると? Tendermintでは、この3つのレイヤーのうちP2Pネットワーキングと合意形成の部分を切り離し(Decouple?)、Tendermint Core(プラットフォーム)として提供します。 そしてABCI(Application BlockChain Interface)と呼ばれるソケットプロトコルを通じて、アプリケーションとTendermintの合意形成エンジンがトランザクションのメッセージをやり取りすることができるようになります。 Tendermintの合意形成はVoting Powerの総量(総数?)の1/3以上の(作為・不作為的な)故障が起きない限りセキュアで、かつVoting Powerを通貨という単位にDenominateしたProof of Stakeが利用されているため、アプリケーション開発の問題だけでなくスループットの問題も解決できるとされています。 TendermintとCosmos SDK Cosmos SDKはPoS(Proof of Stake)やPoA(Proof of Authority)のブロックチェーンを開発するためのフレームワークです。 CosmosのCosmos Hubもこのフレームワークを利用して開発されたブロックチェーンの一つですが、Cosmos SDKではTendermintの合意形成エンジンが利用されています。 アプリケーションとTendermintはABCIのインターフェースが提供するAPIによってメッセージのやり取りを行いますが、これではインターオペラビリティは達成されません。 Cosmos SDKを利用して開発されたブロックチェーン(アプリケーション)は、ABCIとは別にIBC(Inter-Blockchain Communication)プロトコルと呼ばれるものを利用してメッセージのやり取りを行うことができるようになります。 つまり、構造的にはCosmos SDKはTendetmintの合意形成エンジンを利用し、開発者にこのフレームワークを提供するだけでなく、これを利用して開発されたブロックチェーン同士をつなげることができる感じになっています。 CosmosとTendermintが一緒に使われるというより、CosmosがTendermint Coreを利用することで、決定論的なファイナリティを持つチェーン同士を効率的に繋ぎ、インターオペラビリティを実現することができるといった関係性になっていることがわかります。 Cosmosの詳細に関しては以下の記事をご覧ください; クロスチェーンプロトコル COSMOS(コスモス)に関して徹底解説 - CRYPTO TIMES 既存のブロックチェーンをTendermintに移植する仕組み Tendermintには、ハードスプーンと呼ばれる仕組みがあり、これを利用することで、例えばEVMなどをTendermintに移植(Ethermint(後述))することができます。 基本的にはこれまで説明してきた仕組みと同様で、EthereumであればProof of Workの合意形成アルゴリズムが採用されていますが、これをTendermintの(BFT + PoS)に置き換えるイメージです。 ここでは、EVMのコードをそのまま移植しているため、スマートコントラクトやトークンの発行なども可能、かつこれがよりハイパフォーマンスで実現されていきます。 言うまでもなく、Cosmos Hubに接続することもできるため、インターオペラビリティやトランザクションに対する匿名性の付与などが容易に行われていくことになります。 Tendermintの特徴・利点 以上の点を踏まえたうえで、Tendermintには以下のような特徴・利点があるとされています; PoS(PoA)を利用するため、高いスループットが実現できる トランザクションの承認後即座にファイナリティが得られる フォークが起きない アプリケーションをブロックチェーンとして簡単に開発することができる PoWなどの合意形成を採用する既存のブロックチェーンを移植することができる ブロックチェーンの開発やスループットなどに関する問題を解決することができるため、世界でもTendermintとCosmosに大きな期待が寄せられています。 Tendermint Coreを利用するCosmosのエコシステムと現状 記事冒頭でも触れた通り、CosmosのCosmos HubはTendermintの合意形成エンジンを利用して開発されたブロックチェーンの一つです。 Tendermintの合意形成エンジンを軸とするCosmosのエコシステムは、イメージのように大きく拡大を続けています。 こちらのCosmosのフォーラムによると、既に80以上のプロジェクトがCosmosのSDKを利用して開発を行っていることがわかります。 以下では、Cosmos SDKを利用して開発が行われており、注目を浴びているプロジェクトの一部(イメージのZonesの部分)を紹介していきます。 Cosmos Hub CosmosHubは、Cosmos SDKを利用して開発されたCosmosの最初のZone(Hub)になります。 Inter-Blockchain Communication(IBC)プロトコルというもので、その他のZoneとメッセージのやり取りをすることができ、ここがエコシステムの中核であるとも言えるでしょう。 先日、メインネットがローンチされましたが、今後IBCが実装されそのエコシステムがさらに拡大していくことが期待されます。 Ethermint Ethermintは、GoEthereum(Geth)とTendermintの組み合わせで、Ethereumのスマートコントラクトを高速で実現するプロジェクトです。 EthermintがCosmos Hubと一緒に使われていくことで、インターオペラブルかつ高速にEVMを動かすことができるようになります。 この仕組みは上述のハードスプーンの項目で説明した仕組みの通りです。 通常、GethではEthereumのProof of Workが利用されるため、スループットが低く確率的なファイナリティしか持ちませんが、Tendermintの合意形成によりProof of Stakeかつ高いスループットでEVMを動かすことができます。 Binance Chain Binance Chainは、名前の通り仮想通貨取引所Binanceが発表した独自チェーンになります。 開発にはCosmos SDKが利用されているという点が明記されており、これによりCosmos Hubと接続することも十分に可能となります。 Binanceは大きな顧客ベースを持つだけでなく、このチェーンを利用したBinance DEXなども既にリリースされておりエコシステムの拡大に大きく貢献すると思われます。 Binance(バイナンス)がテストネットリリースを間近に控えるBinance Chainの詳細に関して その他 その他、OmiseGoやHyperledger、Loom Networkなどの有名なプロジェクトも、Cosmosのエコシステムに参加しているとされています。 まとめ Tendermintが提供する合意形成エンジンとその特徴、仕組み、またCosmosとの関連性と拡大を続けるエコシステムについて紹介しました。 今後もTendermintを採用するプロジェクトは増えていくことが予想されます。 現在、Cosmosを取り巻くエコシステムも非常に増えてきており、今後も要注目であるプロジェクトの一つです。

特集・コラム
2019/05/15専業トレーダーえむけんの仮想通貨市場分析!【5月15日】
みなさん、こんにちは!えむけん(@BinaryMkent)です。 前回更新後から、BTCは急上昇しましたね!前回記事でもお話ししましたが、やはり高値圏でのチャネル上抜けは爆上げの火種につながりました。 正直、短期間でこれほどの上昇を見せるとは思っていませんでしたが、おかげで大手メディアなどに改めて仮想通貨が取り上げられ始めました。再び新規参入の可能性も十二分にありえますので、その時に備えて、今回もしっかり分析していこうと思います。 BTCチャートの分析 BTCチャート(超長期) 今回は、参考情報があまりにも少ないため、週足の分析から進めていきたいと思います。 まず、前回記事更新時には、オレンジチャネルに沿ってチャネルを形成して推移していましたね。しかし、チャネルの上抜けを機に出来高を伴って大きく上昇、出来高も減りはしたものの依然良好、といった状態です。 ここからは、一時の上げとまりポイントを探す形となってしまいますが、現状最も可能性が高いのは「8000ドル~8200ドル(緑ゾーン)」だと思われます。 もし、売り時を探すのであれば、この緑ゾーン周辺でのパターン形成を元に、売り買いのパワーバランスを推し量った上でポジション取りを行うのが妥当でしょう。 ただ、その成立パターンによっては、再度高値更新に向かう可能性もあります。そのため、「ここでどういったパターンを形成するか?」について、引き続き要チェックです。 BTCチャート(長期) こちらは日足チャートになります。こう見るとやはりエゲつない上げ方ですね・・・。しかし、その分の戻しも大きくなりそうなので、売り時を見つけるべく、チャートに張り付く価値もありそうです。 また、先述したポイントで頭打ちした場合には、「黄色ゾーン(6100ドル)」周辺までの下落が想定されます。 この黄色ゾーンは、3100~4000ドル周辺の保ちあいブレイクを基準にしたフィボナッチの「半値」だけでなく、前回記事でご紹介した「チャネル(緑)」、過去にディセンディングトライアングルの下限として機能した「水平サポート(水色)」が重なるポイントです。 ですから、「ここまで下落する」というよりは、「この価格帯は堅い」といったイメージで捉えていただけると良いかと思います。 BTCチャートの総評 反発ポイントなどを考慮すれば、数パターン用意することも可能ですが、今現在のチャート状況から、想定できる推移は以下の1パターンのみです。 緑ゾーンにて転換パターン形成⇒調整移行 また万が一、調整移行が始まった場合、「黄色ゾーン(6100ドル)」周辺でどのような動きを見せるかは、「再度推進移行するかどうか?」にもつながりますので、しっかりチェックしておきましょう。 さて、それでは次にドミナンス分析を進めていきましょう。 ドミナンス分析 ドミナンスチャートに関しては、「Trading View」を参考することにしております。(外部リンク:https://jp.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/) やはり前回更新以降、BTCのドミナンスも急激に上昇していますね。 しかし5/13以降、BTCのドミナンス反転下降と同時に、主要アルトコインのドミナンスが反転上昇してきています。 BTC大躍進の間、アルトもBTC建てで急激な下落を見せていましたから、BTCが8000ドル周辺をつけて以降、資金が割安アルトへ流れているのでしょう。 では次に、アルトコインのドミナンスを拡大してみましょう。 5/13以降のドミナンス反転上昇の中でも、ETH、XRP、Othersの上昇が目立ちますね。またそれに対し、Tetherのドミナンスが下降しています。 この点から、「リスク回避ムード(リスクオフ)というよりは、アルト売買で差益を狙う、リスクオン相場に転換した可能性が高い」と言えるでしょう。 では次に、主要アルトの値動きを見ていきましょう。 主要アルトコインの動向 やはり、BTCが8000ドルをつけて以降、一気にアルトコインへと資金が流れていますね。 上昇率で言えば、ETHも非常に優秀ですが、「XRP」や「TRX」、「ADA」などの低単価アルトの伸びも目立ちます。 今回は、すでに大きく上昇してしまった通貨が多いので、現状まだ大きく上昇していない通貨に的を絞ってお話しを進めていこうと思います。 それでは、早速ご紹介していきましょう。 XLM 昔からアルトトレードを行っている方はご存知かもしれませんが、過去の推移を見てみると、「XRPの上昇後にはXLMが上昇する」といった傾向があります。 もちろん、それだけでは根拠も薄いですが、現状ラインに忠実に推移してくれているため、現状の下降ウェッジを基準に押し引きしていくと良いと思われます。 XEM XLM同様、下降ウェッジにて推移していますが、現状その下抜け後にてダブルボトムを形成しています。いまだ出来高が少ないのが気にはなりますが、日本人人気銘柄が奮闘していますし、こちらもここからの推移に期待です。 IOTA 何よりも気になるのが、仕込みとも思われる出来高ですね。チャート的にはそこまで優秀というわけではありませんが、緑点線へのリターンムーブまで落ちてきてくれれば、損切り幅も少なく済みますし、期待値は十分にあると思います。 総評(まとめ) 最後にまとめに入りましょう。 BTCは緑ゾーンでのパターン形成待ち →押し目候補は6100ドル アルト↑、USDT↓(ドミナンス) →リスクオン転換か? 現在、BTCが高値圏にて推移しているため、積極的にSを打ち込みたい状況ではありますが、ここから再度アルトブーム突入・・・となると、アルト需要により、現物主導でBTCが買われ、下値が堅くなる可能性があります。 ですから、Sメインで攻めていく場合には、ブレイクポイントでSを入れるのではなく、より優位な高値圏でのS打ち込みが良いと思われます。 今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 現在、私えむけんが制作した初心者~中級者向けの有料note、『7日間でマスター!テクニカル分析とそれを元にしたトレード戦略』、好評販売中です! 今回のような、BTC分析やアルトコイン投資などの立ち回り方についても解説しておりますので、是非ご覧ください!(詳しくはコチラ)
















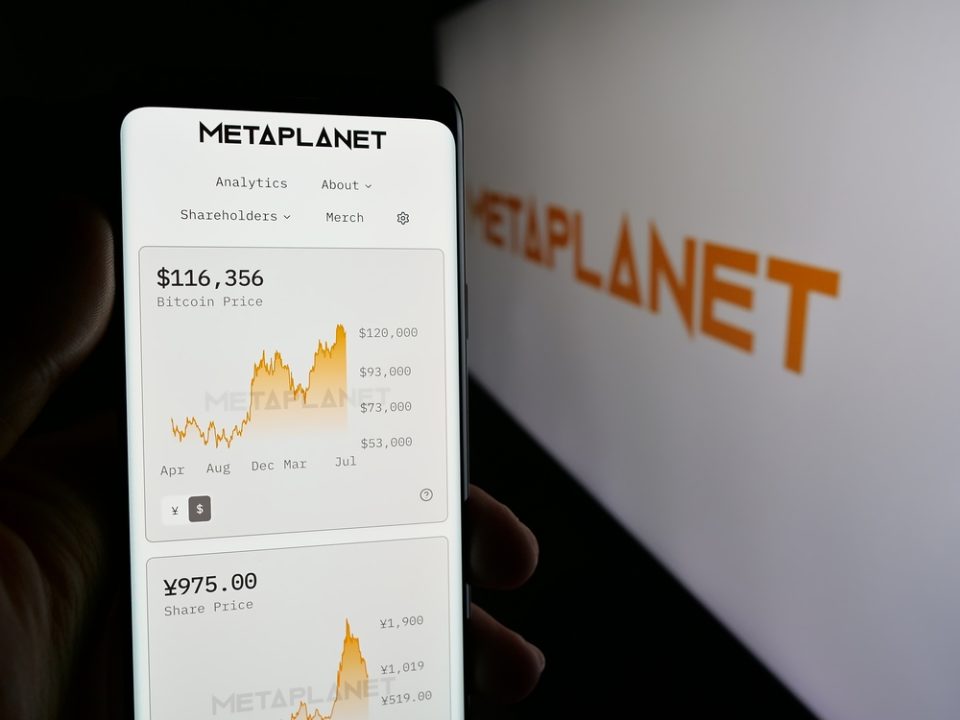

 有料記事
有料記事


