
プロジェクト
2024/01/14Meteorn Run徹底解説|今注目中のランニングゲームPlay to Earn
2023年は、2022年のクリプトの冬相場を乗り越え、ビットコイン価格が年始より160%以上の上昇を見せました。これに伴って、NFT市場にも資金が流入し、相場が賑わい始めています。2024年初めには、ETF承認がされたこともあり、今後より盛況になることが期待されています。 そうした中、GameFi分野もにわかに活気だち始めていますが、現在注目を集め始めているGameFiがあります。それが「Meteorn Run」というランニングゲームです。 この記事では、Meteorn Runの概要から、ゲーム内容、エコシステムまで徹底解説していきます。 Meteorn Runが注目を集める理由 Meteorn Runのプロダクト紹介をする前に、まずはMeteorn Runが注目を集める理由を二つ紹介します。 プレセールで100万ドルの資金調達に成功 Meteorn Runは、プレセールを行い100万ドルの資金調達を成功させました。 また、NFTマーケットプレイスとブラウザ版Meteorn Runゲームの同時ローンチを発表したことも、注目を集めています。 ゲーム内トークンGMTOが上場:価格は687.5%の上昇を見せる 詳しく後述しますが、Meteorn Runにはゲーム内トークンとして、MTOとGMTOがあります。 MTOは既にXT.comにて上場していましたが、GMTOは先月、LBANKに上場しました。 GMTOはセカンダリーマーケットユーザーの間で絶大な人気を得ており、上場後数分で価格が687.5%急上昇しました。これにより、CoinCarpによると、同日、世界のCrypto Gainersのトップ 10にランクインしました。 多くのWeb3プロジェクトでは、多くの場合価格が上昇した後には暴落しますが、それとは対照的にGMTOの場合は、暴落はせず堅実に価格が上昇して行っています。これは、投資家たちの持続的な関心を集めていることが窺えます。 Play to Earnを採用 Meteorn Runは所謂Play to Earnのプロジェクトです。 Play to Earnとは、ブロックチェーンベースのゲームカテゴリーであり、プレイヤーはゲーム内の活動を通じて、通常、暗号通貨や非代替性トークン(NFT)の形で現実世界における利益を得ることが可能となっています。 報酬を得るためのタスクは、クエストの完了、レアアイテムの獲 得、バトルへの参加など様々です。 Meteorn Runとは? Meteorn Runは、ランニングをテーマとしたゲームです。 世界中のプレイヤーがアクセス出来るようになっており、スマートフォンでのプレイやVRグラスを装着してのプレイにも対応しています。また、クリプト・ユーザーにも、クリプトに馴染みのない人に向けても作られています。 ゲームは意図的にシンプルな内容となっており、これは通勤時間でのプレイや、友人とのプレイを想定しているためです。エンターテインメントにとどまらず、プレイヤーの余暇の充実へ貢献することも目的の一つです。 既にブラウザ版の方ではサービスが提供されています。 Meteorn Run:https://game.meteornrun.io/WebGL/index.html ここからは、より詳細なMeteorn Runのプロダクト内容を解説していきます。 ランニングがテーマであり、キャラクターを操作して長距離の走行を目指す [caption id="attachment_104224" align="aligncenter" width="800"] ブラウザ版でのプレイ画面[/caption] プレイヤーは、キャラクターを操作し、左右への移動や、ジャンプ(上操作)や転がり(下操作)をしながら、より長い距離を走れるようスコアを上げていきます。 ステージとしては、Mercury、Venus、Earth、Mars、Jupiter、Saturn、Uranus、Neptune、Plutoの9つのステージがあり、それぞれで稼ぐことが出来るトークン量と難易度が変化します。 二種類のゲームモードを採用:シングルモードと4人でのPvP Meteorn Runは、プレイヤーがキャラクターを操作して障害物を避けてコインを稼ぐゲームです。 基本的には1人プレイのゲームですが、「BETMATCH MODE」というもう一つのゲームモードがあります。 これは、4人で行われ、各プレイヤーは参加費を払って試合に参加し、最も走行距離が長いプレイヤーが勝者となります。 勝者は1人だけであり、全員の掛け金の70%を手に入れることが出来ます。 アプリ版リリースは2024年第1四半期を予定 Meteorn Runは、Polygonブロックチェーンを活用しており、強固なエコシステムやゲーム内キャラクター、NFTによってGame Fiの可能性や価値を実現しようとしています。 エンターテイメントだけでなく資産の増加の両方の機会を提供し、競争力のあるプラットフォームをプレイヤーに提供することを掲げていますが、現在の目標として、ゲームリリース後1年以内に、全世界で20000人のアクティブNFTユーザーを達成することを挙げています。 Meteorn Runのアプリ版リリースは2024年第1四半期を予定しているとのことです。 また、多くの企業やプロジェクトとのNFTパートナーシップやゲーム内広告を通じたコラボレーションが予定されており、それは今後発表されていくとのことです。 NFTシューズを活用してより多くのトークンを稼ぐことが可能 Meteorn Runはランニングゲームです。ゲームを通してプレイヤーはトークンを稼ぐことになりますが、NFTシューズを活用することで、獲得できるトークンを効率的に増やすことが可能です。 [caption id="attachment_104214" align="aligncenter" width="800"] Meteorn Runマーケットプレイス[/caption] NFTシューズには、6つのレアリティが設定されており、上位3つのレアリティには上限が決められており、EPICは1000、LEGENDARYは24、ULTIMATE LEGENDARYは7となっています。 記事執筆時は、NFTシューズは割引価格での取引がされています。(所定の数量が完売次第、自動的に価格が切り替わるとのことです) NFTのスカラーシップを採用し、参入障壁の緩和へ Meteorn Runのその他の特徴として、「スカラーシップ」を採用していることが挙げられます。 スカラーシップとは、NFT保有者がNFTを他のプレーヤーに貸し出すことで、それによって得た利益を分配する仕組みです。スカラーシップを採用しているその他のGame Fiとしては、「Axie Infinity」が挙げられます。 [caption id="attachment_104230" align="aligncenter" width="800"] Axie Infinity[/caption] Game Fiの課題の一つとして、参入障壁の高さが挙げられます。ゲームをプレイするためにはまずNFTを入手するという形で初期投資が必要です。また、より大きな利益を得ようとすれば、その分より多くの資金を投じなければなりません。こうした課題を解決するのが、スカラーシップです。スカラーシップを活用することで、初期資産が少ない人でも、容易にゲームをプレイし稼ぐことが可能となります。 例えば、Axie Infinityは、東南アジアで爆発的な流行を見せましたが、これにはコロナ禍において生活費を稼ぐための手段として用いられたことが挙げられます。東南アジアの人にとってAxie Infinityのための初期投資は非常に負担の大きいものでしたが、スカラーシップを活用することで、そうした参入障壁が緩和され、プレイヤー拡大に寄与しました。 Meteorn Runでも、こうしたスカラーシップを採用することで参入障壁を緩和し、そのエコシステムの拡大を実現しようとしています。 Meteorn Runのエコシステム Meteorn Runでは、MTOとGMTOのデュアルトークンシステムが採用されています。暗号資産取引所での取引に留まらず、プレイヤーが増加するにつれて、MTOやGMTOに対する市場の需要も増加していきます。 MTOはガバナンスに使用される他、Meteorn RunのNFTマーケットプレイスでのNFTシューズの購入にも使われます。プレイヤーはキャラクターにNFTシューズを装備してゲームをプレイすることで、MTOを獲得出来ます。また、MTOをステーキングすることでユーザーはGMTOを獲得することが出来ます。 GMTOは、MTOのステーキングか取引所での購入によって入手することが可能です。GMTOは、プレイヤーが使用したNFTの修繕やレベルアップに使用されます。また、将来的に実装予定のMeteorn RunのNFTマーケットプレイスで使用されるトークンでもあります。 このように、GMTOはNFT周辺に関わる要素のため、プレイヤーは自身の利益を最大化しようとする際には、GMTOを活用することが必須となります。それだけでなく、プレイヤーがゲーム内でGMTOを利用するにつれ、GMTOの総供給量は減少し、最大供給量の半分までバーンされる仕組みとなっています。需要に対して供給を減らすことで、価格が上昇することが予想されています。 以下、MTOとGMTOのユーティリティを箇条書きであげたものが以下になります。 MTOのユーティリティ 総供給枚数:1億枚 プロジェクトのガバナンスに活用。 Meteorn RunのNFTマーケットプレイスで、NFTシューズの購入。 ステーキングすることでGMTOを獲得可能。 GMTOのユーティリティ 総供給枚数:1000億枚(ゲーム内で消費されたGMTOは、総供給量の50%までバーンに使用されます) 消耗したNFTシューズの修理。 NFTシューズのレベルアップ。 ゲームに役立つNFTアイテムの購入。 NFTのミントに使用。 持続的なトークン経済のための6つの試み Meteorn Runは、持続的なトークン経済を構築するための試みを行っています。 P2Eゲームの課題として、トークン価格が安定しないことが挙げられます。トークン価格が安定しないということは、プレイヤーにとっては期待される利益が安定しないということであり、長期的にはプレイヤー人口の減少へと向かってしまいます。 Meteorn Runは、GMTO価格の安定及び上昇のために6つの試みを行っています。 エコシステム内における必須通貨 GMTOは、NFTシューズの購入や修理、レベルアップに必須であり、ゲームプレイにおいて一定の需要が見込めるようにしています。 また、NFTシューズは使うたびに消耗していき、消耗率が高いほど収益率は下がる仕組みとなっています。その消耗の修繕にGMTOが使われますが、その修繕率は30-45%の間でNFTのレア度によって変動します。 GMTOを使わなければ収益獲得を見込めない仕組みとすることで、GMTOへの需要が減らないような仕組みを作っています。 GTMOのバーン:最大で総供給量の50% ゲームユーザーの拡大に伴い、GMTOの使用枚数は増えていきますが、NFTの購入や修繕などに使われる際に、バーンされる仕組みとなっています。最大で総供給量の50%がバーンされる仕組みになっています。 これによって供給量を下げることで、1トークンあたりの価値上昇に努めます。 GMTO取得方法の制限 ここまで述べてきたように、GMTOはゲームプレイに必須のトークンですが、GMTOを取得するためには、「MTOのステーキング」(1MTO=50GMTO)か、「市場での購入」の2つのみしか手段がありません。 取得方法を制限することによって、需要と供給を管理しています。 権利確定(Vesting)スケジュールの調整 2023年12月30日時点でのプレセールの売り上げは、約94万ドルに及びました。 ここで購入されたトークンは、一度に放出されるのではなく、2年間を通して段階的に放出されます。 1年目では、11ヶ月間×0.8% 12ヶ月目 1.2%で、全体の10%が放出されます。 2年目では、2%から始まり1ヶ月ごとに1%ずつ放出量が上昇する形で、残りの90%が放出されます。 収益からの買い戻し(Buy Back) Meteorn Runは、収益モデルとして、「NFTセール」、「広告収入」、「VRグラスのセール」、「NFTマーケットプレイス手数料」の4つを柱として据えています。 そして、NFT売り上げの40%は市場買い戻しのために使われ、GMTO価格の安定化に努めます。 また、将来的にユーザーが一定数増えてきた段階で、ゲーム内に広告の掲載をスタートさせ、この広告費の一部も買い戻しに用いられるとのことです。 ユーザー見込みや買い圧・売り圧について Meteorn Runは、2024年末までの目標ユーザー数を21380人と見込んでおり、目標NFT流通数は106900としています。 それに伴うGMTOの一年目の買い圧及び売り圧を、以下のように予測しています。 買い圧(NFT流通数とNFTの修繕費用を考慮):$11,252,827 売り圧(プレセールとステーキング報酬を考慮):$1,354,397 また、GMTのレートは予測で月約15%ずつ上昇と見込んでいます。 Meteorn Runのロードマップ Meteorn Runは、2023年にはMTOのプレセールや、CEXやDEXでのリスティング、新たなステージ開発などを行ってきました。 2024年第一四半期には、Uranus、Neptune、Plutoのステージ追加やスカラーシップのリリース、MTOの決済機能の開発などが行われる予定です。 おわりに ここまでMeteorn Runを解説してきましたがいかがでしょうか? Game Fiに対する注目はここ数ヶ月でより顕著に増しています。直近では、 Gas Heroが大きな注目を集めています。Gas Heroは、以前にSTEPNを開発したFind Satoshi Labsによって運営されています。その他にも、Chain Colosseum Phoenixや、FusionistといったBCGが注目され始めており、今後こうした流れは加速していくものと思われます。 こうした盛況になっていくGame Fi分野の中で、Meteorn Runも非常に大きな拡大が期待されるプロジェクトです。 Meteorn Runのアプリ版リリースは2024年第1四半期が予定されています。興味が湧いた方がいれば、是非プレイしてみてはいかがでしょうか? Meteorn Run各種Infomartion ホームページ:https://meteornrun.io/ X:https://twitter.com/meteorn_run マーケットプレイス:https://marketplace.meteornrun.io/ Discord:https://discord.com/invite/spv3DpEGWD Telegram:https://t.me/+XlhHtEIQbeo1ZTdl Medium:https://meteornrun.medium.com/ WP:https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run/introduction/overview

プロジェクト
2024/01/01Fuel Networkとは?特徴や今後を解説|モジュール型ブロックチェーンの可能性
この記事では、Fuel Networkについて解説しています。 Fuel Networkは、ブロックチェーンに必要な要素を分業で行うモジュール型のブロックチェーンの実行レイヤーを担います。 モジュールの特性を持つブロックチェーンは、ブロックチェーンが持つ諸問題を解決するとして注目されており、Fuel Networkはその点に取り組むプロジェクトの1つです。 過去には8,000万ドルを超える資金調達にも成功しており、各方面から注目が集まっています。 この記事では、そんなFuel Networkの概要から特徴、高いパフォーマンスを出す仕組みなどについて解説しています。 この記事のまとめ ・Fuel Networkは実行を担うレイヤー ・モジュール型のブロックチェーンでは分業で処理を行う ・Fuel Networkによると世界最速の実行レイヤー ・並列処理が可能 ・EVMを改良したFuelVMを搭載 Fuel Networkとは?=実行レイヤー特化のモジュール型ブロックチェーン Fuel Networkは実行レイヤーに特化し、ブロックチェーンをスケーリングさせるプロジェクトです。 イーサリアムの混雑・遅延・ガス代高騰を改善するために、これまでさまざまな対策が取られてきました。 その代表例が、サイドチェーンやロールアップといったソリューションです。 特にロールアップは、イーサリアムのセキュリティを備えた上で高い処理能力や低いガス代を実現することで、普及が進んでいます。 その一方で、ロールアップが処理できるトランザクションの上限は、仕様上L1の容量・能力に依存します。 そんな中で、新たなスケーリング方法として、Fuel Networkや複数のプロジェクトが提案しているのが、より一連の仕組みを分割するモジュール型のブロックチェーンです。 Fuel Networkは、モジュール型の中でも、特にブロックチェーンの処理における「実行」に焦点を当てたプロジェクトです。 Fuel Networkではさまざまな技術を用いて一定のセキュリティを確保した上で、高いパフォーマンスを発揮します。 また、Fuel Networkを開発するFuel Labsは、Blockchain CapitalとStratosが主導して2022年9月に8,000万ドルの資金調達に成功しています。 上記のようなポイントからも、Fuel Networkへ熱い視線が向けられていることが分かるでしょう。 (Fuel Networkには、Fuel v1というソリューションもありますが、そちらはロールアップで、この記事で執筆しているものとは異なります。) Fuel Networkの簡単な特徴 これから、Fuel Networkのかんたんな特徴について、以下のポイントから解説していきます。 ・モジュール型のブロックチェーンの一種 ・世界最速の実行レイヤー Fuel Networkの特別なポイントや、Fuel Networkを理解する上で必要となる基礎的なポイントをチェックしていきましょう。 モジュール型のブロックチェーンの一種 Fuel Networkは、モジュール型ブロックチェーン、モジュラー型ブロックチェーンの実行レイヤーにあたるソリューションです。 モジュール型のブロックチェーンとは、ブロックチェーンに必要な要素を各レイヤーが分割して担う方式で、分割することで分散性やスケーリングの向上が期待できます。 ブロックチェーンがトランザクションを処理し機能するには、以下の4つの要素が必要です。 実行 決済 コンセンサス データの可用性 利用者がブロックチェーンを通して行ったアクションは、上記過程を何らかの形で通ります。 実行はトランザクションを実行、スマートコントラクトのやり取りなどを実現する過程。決済は異なるレイヤー間でのやり取りや、トランザクションを確定させます。コンセンサスでは検証する主体の間で合意を行い、データの可用性は過去のデータを見られることを意味します。 通常のブロックチェーンは、上記の過程を1つのブロックチェーンで行います。(図の左側"Monolithic"部分) 一方で、モジュール型のブロックチェーンの仕組みでは、各過程を役割に応じて各レイヤーが担当します。(図の右側"Modular"部分) Fuel Networkは、上記の中でも実行レイヤーに焦点を当てたプロジェクトです。 また、モジュールの対義語として、上記の全てを1つのブロックチェーンで行う方式を「モノリシック」と呼称することもあるので合わせて覚えておきましょう。 世界最速の実行レイヤー Fuel Networkによると、Fuel Networkは世界最速の実行レイヤーです。 Fuelは後述する技術により、トランザクションの並列処理(同じタイミングで複数のトランザクションを処理)と新たなVM・言語を実装し、高いパフォーマンスを実現します。 実行レイヤーが高いパフォーマンスを発揮することで、トランザクションの速度が早くなるなど、利用者が高い利便性を享受できます。 また、Fuel Network単体でも全ての機能を持ったモノリシックなブロックチェーンとしての運用も可能ですが、そのような用途は推奨されていません。 Fuel Networkはあくまでモジュール型のブロックチェーンの普及重視しており、その中でも「早い実行レイヤー」の実現に焦点を当てています。 Fuel Networkの仕組み これから、Fuel Networkの重要な仕組み・技術について、以下の観点からさらに詳しく解説していきます。 ・実行レイヤーの役割 ・並列実行を可能にする方法 ・FuelVMと言語 ・FuelVMとEVMの比較 Fuel Networkについて理解を深めていきましょう。 実行レイヤーの役割 まず、はじめにFuel Networkが焦点を当てている実行レイヤーの役割・立ち位置について解説していきます。 モジュール型のブロックチェーンでは、ブロックチェーンを動かすために必要な要素を複数のレイヤーに分割し、複数のソリューションが各レイヤーを担当します。 Fuel Networkが焦点を当てている実行レイヤーは「トランザクションの処理・状態遷移(変化した内容を適用する)」が主な役割です。 実行レイヤーでは、上記のポイントのみを担当します。 実行された内容を検証するプロセスが必要になりますが、その他の別のレイヤーに渡すというのが、モジュール型の基本的な流れです。 前述したブロックチェーンを構成する要素に例えると、実行レイヤーは実行のみを担当します。 実行レイヤーの役割が終わった後は、決済・コンセンサス・データの可用性を別のレイヤーに渡します。 そのため、仮に実行レイヤーで何らかの問題が発生した場合、検証を行う異なるレイヤーに問題がなければ、無効なトランザクションは通りません。 また、設計に組み込まれている場合は何らかのソリューションが複数のレイヤー担うことも可能です。(Fuel Networkであれば、実行・決済など) 並列処理を可能にする方法 Fuel Networkが、高いパフォーマンスを発揮する背景の1つが、トランザクションの並列処理(同時に複数のトランザクション)を可能にしている点です。 並列処理を可能にすることで、トランザクションを処理するコンピュータが持つポテンシャルをフルで発揮できるようにします。 並列処理は、何らかの要素を共有しているトランザクションを同時に処理すると、非決定的な事例が発生する可能性がある方法。そのため、イーサリアムではトランザクションを1つ1つ順番に処理していき、シーケンシャルに実行します。 Fuel Networkでは、上記の問題を発生させず、並列処理を実装するために共有する要素をまとめたリストを作成し、そのリストを元にトランザクションを並列処理していきます。 また、そのリストは UTXO(未使用トランザクションアウトプット)を用いて実装されます FuelVMと言語 Fuel Networkが持つさまざまな特徴を実現するために、Fuel Networkでは「FuelVM」という環境と「Sway」というプログラミング言語を用います。 FuelVMは、EVMにさまざまな改良を加えたVM(バーチャルマシン)であり、同時にSolana・Cosmos・Bitcoinなども参考にしながら開発されました。 Swayは、FuelVMで使用することを想定したスマートコントラクトを扱うためのプログラミング言語で、主に、Rustをベースにして開発され、Solidityも参考にされました。 FuelVMとEVMの比較 FuelVMは、EVM(イーサリアムバーチャルマシン)と比較してさまざまな違いを持ちます。 例えば、複数のトークンをネイティブアセットとして使用可能です。 ガス料金に用いられるのはベースとなるトークンのみですが、ネイティブアセットになることができるトークンはイーサリアムのようにETHのみではありません。 ネイティブアセットのバリエーションが増えることで、利用者の観点から見たときにいくつか、利便性の向上が期待できます。 This leads to poor UX and higher cost: 2 txs instead of 1.To work around this, many apps use infinite approvals, where you approve the contract to use your entire token balance. Problem: if the contract is exploitable, *all* your tokens are gone.https://t.co/5yrXLY8nyY— John Adler | ✨🧱🟣⛺ (@jadler0) June 23, 2022 例えば、DEXの使用時において、FuelVMではETH以外のトークンであっても単一のトランザクションで扱うことが可能です。 通常、DEXを使用する際、イーサリアムではETH以外のトークンは、2つのトランザクションを通す必要があります。 2つのトランザクションを通すことでコストがかかるのはもちろんですが、特にリスクとして認識したいのは「上限のない承認」です。 2つのトランザクションのうち、1つのトランザクションはアクセスを許可するトークンの量を指定する要素があり、実用上、上限のない承認を与えていることが一般的です。(ここでトークンの金額の上限を設定すると、上限を超えると再度コントラクトの承認が必要になるため) これは、承認したコントラクトが悪意のあるものであった場合、全てのトークンが失われることを意味し、DeFiを使用する際の主要リスクの1つに挙げられます。 Fuel Networkでは、上記のような課題を解決していると言えるでしょう。 Fuel Networkとロールアップについて Fuel Networkは、その特性上、OP・ZKロールアップとの類似点が非常に多いです。 ロールアップ、Fuel Networkともに処理した内容を別のレイヤーに渡すという点では似通っています。 モジュール型のブロックチェーンの全体図を考慮すると、ロールアップは「実行」にあたるレイヤーを担っているとも言えるでしょう。 この点もFuel Networkとの類似性を高くしていますが、いくつかの違いもあります。 例えば、ロールアップはL1チェーンとの関係が非常に強く、前述した通り基盤となるL1チェーンが持つさまざまなパフォーマンス・限界に大きく左右されます。 Fuel Networkに関しては、他のモジュール型のブロックチェーンを併用して、より各レイヤーが複数のソリューションが担う構造を実現できる可能性を秘めています。 Fuel Networkの今後 Fuel Networkは、これまでいくつかのテストネットをローンチしています。 2022年9月からBeta-1、2022年11月からBeta-2、2023年3月からBeta-3、2023年9月Beta-4が実施されています。 まだ、テストネットで試験的に運用されており、明確なメインネットのローンチ時期などは判明していません。 現在、FuelではEthereumのSepoliaネットワークとBeta-4 テストネット間のブリッジを公開しています。 Fuel's native bridge is now open 🌉 Anyone can now bridge between Ethereum's Sepolia Network and the Beta-4 testnet. Enter Fuel: https://t.co/I5vq8wewI6 pic.twitter.com/zvkZdOqIPg — Fuel (@fuel_network) October 12, 2023 具体的な明言できないものの、徐々にメインネットに近づいていると考えられます。 どのテストネットについてもインセンティブがついたテストネットではないと明言されていますが、一般の利用者でも参加自体は可能です。 Fuel Networkについてまとめ この記事では、Fuel Networkについて解説しました。 Fuel Networkは、スケーリング問題やブロックチェーンのトリレンマを解決する答えの1つになるかもしれないポテンシャルを持つプロジェクトです。 Fuel Networkや、類似のモジュール型のブロックチェーンを目指すさまざまなプロジェクトには、今後も注視していきたいと言えるでしょう。 最後まで読んでいただきありがとうございました。

プロジェクト
2023/12/21ペルー発、暗号資産プラットフォームMeteor(メテオ)を徹底解説 |ガバナンストークンも12/28に上場決定
Meteorは2022年にペルーでライセンスを取得した暗号資産プラットフォームです。 新興のプラットフォームではあるものの、トレード機能に留まらず、NFTマーケットプレイスやローンチパッドといった機能にも注力しているなど、従来のプラットフォームでは収まらないサービス展開を行っていることが特徴です。 また、グローバル展開も行っており、日本をはじめ、韓国やその他の地域でも現在、進出し始めている暗号資産プラットフォームでもあります。 さらにMeteorはガバナンストークンの発行が決まっており、このトークンは「MTO」の上場を12月28日に控えており、Meteorエコシステムの拡大にも注目が集まっています。 今回の記事では、ペルーの暗号資産市場を踏まえてのMeteorの概要やMeteorの日本における事業展開までを解説します。 ペルーの暗号資産市場は現在、NFTを中心として急成長中 Meteorはペルーの暗号資産プラットフォームですが、現在、グローバル展開に注力しており、現在進行形で日本への進出を行っています。Meteorの概要や、日本におけるMeteorの取り組みについて紹介する前に、まずはペルーにおける暗号資産市場を紹介しMeteorの解説へと繋げていきます。 ペルーの暗号資産市場は将来的に成長をしていくと予測 [caption id="attachment_102720" align="aligncenter" width="800"] データ引用元:statista[/caption] 現在、ペルーの暗号資産市場は急成長を遂げています。 2022年には一時縮小したものの、今年(2023年)にはその勢力を取り戻し、前年比で二倍以上にまで成長しました。また、2028年に向けて右肩上がりの大きな成長をしていくと予測されています。2020年の市場規模と比べても、2023年には7倍以上となっていることから、ペルーには潜在的に大きな暗号資産市場があることが伺えます。 また、ペルーではNFTに対する関心が高く、NFT市場は2億200万ドル以上に及んでいます。また、世界的にもNFT所有者が多い国上位10カ国にランクインしており、NFT保有者のそのほとんどは45歳〜54歳の男性となっています。ペルーではおよそ9.9%の人が少なくとも1つのNFTを持っており、将来的にNFT保有者の数は24.4%に増加すると言われています NFTのジャンルとしては、音楽、アート、スポーツ、マーケティング市場が代表的であり、多種多様な需要があることがわかります。 Meteorによるペルー暗号資産市場のPESTEL分析 [caption id="attachment_102756" align="aligncenter" width="800"] スライド引用元:slideegg[/caption] PESTEL分析という、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)、環境(Environment)、法律(Legal)のそれぞれの観点から、市場分析を行う方法があります。 Meteorはペルーの暗号資産市場に対して、PESTELのそれぞれの観点から以下のように分析しています 政治:ペルー政府はブロックチェーン技術と暗号資産の発展に支持を表明しているものの、規制に対しては未だ不透明な部分がある。 経済: ペルー経済は近年安定しており環境は整っているものの、 暗号資産の普及はまだ限定的である。 社会: ペルーでは、若者を中心として暗号資産の普及が進んでいるものの、その仕組みやメリットについての理解は未だ広まっていない。 技術: ペルーでは、デジタル技術の導入が急速に進んでおり、暗号資産の導入に有利な環境が整っているものの、国内にはまだ技術格差がある地域もある。 環境: マイニングによるエネルギー消費の大きさが環境に大きな影響与えているため、ペルーで事業を展開する企業は二酸化炭素排出量を軽減するための対策を検討する必要がある。 法律: ペルーの現在の法的枠組みにおいては、暗号資産に対する特別な規定は無い。今後の法改正を注視し対応していく必要がある。 上記のように、ペルー政府を中心とした規制周りの不安感はあるものの、経済情勢は安定しており、若者を中心として多くの国民の暗号資産に対する受容度は一定以上あることが窺え、これから先より多くの進展を見込むことが出来ることが分かります。 Meteorの概要 ここまで、Meteorを紹介するにあたり、その背景事情としてのペルーの暗号資産市場の状況について述べてきました。 基本的には、ペルーの暗号資産市場は拡大する見込みがあり、中でもNFTが非常に注目されている分野であることが分かります。 こうした市場状況であることを踏まえて、Meteorは取引所サービスだけではなく、NFTマーケットプレイスやローンチパッドを積極的に取り入れた包括的な暗号資産プラットフォームの構築を行なっています。 Meteorサービスの3つの柱 Meteorは「取引所」、「NFTマーケットプレイス」、「ローンチパッド」の3つのサービスを主軸として事業展開を行っています。 以下、それぞれを詳しく紹介していきます。 取引所 基本となるサービスはやはり、取引所サービスです。2022年は全体として低調に推移していた暗号資産市場ですが、2023年8月の世界市場では1兆ドルとなっています。取引高も向上しており、将来的には2030年まで年間12.5%の成長率が見込めるとされています。 暗号資産市場の拡大に伴って、取引所サービスの需要が増していくことが予測されますが、Meteorは、ユーザーに寄り添った設計にすることによって、より良いユーザー体験の実現に注力しています。 資金の管理・アクセスをいつでもできるようにすることや、ブロックチェーンの安全性を活用することによるデータ保護や改ざんの防止、中央組織による個人情報漏洩リスクの排除は勿論のこと、UX/UI技術ソリューションによる機能的でフレンドリーなプラットフォームや、Situation、Task、Action、Resultの頭文字をとった「STAR」をモットーとして、社内外の問題解決に注力しています。 NFTマーケットプレイス 先述したように、ペルーではNFTに対する関心が高く、その需要は非常に大きくなっています。それに伴い、MeteorはNFT関連サービスに注力しています。 MeteorのNFTプラットフォームでは、体験、商品、デジタルアート、会員権、クーポンを売買することが可能です。 24時間365日稼働するプラットフォームでは、ブロックチェーン技術によって透明性が保護され、エスクローシステムによって安全性と信頼性を実現し、売り上げの最大化を果たすことができるようになっています。 旅行プランもNFTで購入可能 NFTマーケットプレイスといえば、アートの売買を連想するかもしれません。しかし、最近のNFTでは、アートに留まらず、旅行ツアーといった体験を購入することも可能です。 MeteorのNFTマーケットプレイスでも、体験をテーマとしたNFTを購入することが可能です。 近日公開予定の「クスコからマチュピチュへの終日ツアー」(上記画像左上)では、マチュピチュ遺跡での約2時間のガイドツアーや温泉街の散策などを盛り込んだ午前4時出発 - 午後10時帰着のパッケージツアーが計画されています。 ローンチパッド ローンチパッド市場は世界的に拡大をしている分野です。南米のクラウドファンディングの年間売上高は、8500万ドルを優に超えています。また、世界規模で見れば、去年にホストされたクラウドファンディングの件数は640万件以上であり、経済規模は650億ドルに及んでいます Meteorのローンチパッドでは、1つのプラットフォームの中でプロジェクトが一括管理され、トークンやNFTの発行も全てMeteor内で完結します。また大手の大学や大手VCとの連携により事業が促進されています。 こうしたローンチパッドに対してお金を投資するにあたっての懸念事項として、 目標金額に投資金額が達するかどうかがあります。Meteorローンチパッドではプロジェクトごとにマイルストーンが設定されており、それを達成することができない場合には資金提供を得ることが出来ず、投じられた資金は投資家に返却されます。これによってユーザに対して投資の安全性を提供しています。 投資家だけでなく、学生にも資金調達という形でローンチパッドの恩恵を提供 Meteorのローンチパッドの試みの特徴として、学生も視野に入れていることが挙げられます。 暗号資産ビジネスに興味がある学生がいても、十分な資本調達の難しさが障壁として立ちはだかります。そこで、Meteorはプロジェクトのためのトレーニングやガイダンスを提供しながら、投資家とのコネクションを確立し、より多くのビジネスと投資家を繋げるなどしてコミュニティ構築を積極的に行っています。 アンチマネーロンダリングへの注力 暗号資産プラットフォームを運営するにあたって、アンチマネーロンダリング(AML)への準拠は欠かせません。例えば、先日、Binance CEOのチャンポン・ジャオ氏(通称CZ)は、Binanceの米国における事業継続に関して司法取引を行い、米国司法省と43億ドルの支払いで和解を行いました。 その際に指摘された犯罪行為の中に、マネーロンダリング防止法に対する違反が挙げられました。このように、健全な暗号資産プラットフォームの運営に際して、AMLに対して配慮を行っているかは非常に重要な要素となっています。 MeteorはAMLに対する措置もかかしていません。身分証明書や公共料金の請求書を用いたKYC手続きを行い、プラットフォーム上の全てのトランザクションを監視し、参加者に対するリスク評価も行っています。そのほかにも、記録管理や監査とレビューを徹底し、規制当局と協力するといった試みも行っています。 ガバナンストークン「MTO」が12月28日に上場予定 Meteorにはガバナンストークンとして「MTO」があり、12月28日に上場が決定しています。MTOの総発行枚数は1億枚となっています。 また、MTOトークンの用途としては、コミュニティへの積極的な参加を促進するための配布や、プラットフォーム上での取引だけには収まらない多くのユースケースが実装される予定となっています。 多くの主要Web3企業からの支援を獲得 Meteorは、ペルー国内外問わず、多くの主要Web3企業からの支援を獲得しています。 以下、主要な国際的Web3企業を分野別に紹介していきます。 取引所:Crypto.com、Coinbase、Kraken、Bitvavo、Binance、Bitpandaなど NFTマーケットプレイス:Opensea、BakerySwap、Rarible、Super Rare、Larva Labs、Foundation、Magic Edenなど ローンチパッド:Kickstarter、Gitcoin、Meridio、Koinify、Brickblock、Indiegogo、Gofundmeなど その他主要な取り組み ここまで紹介してきたサービスや特徴以外にも、その他多くの試みや機能がMeteorでは提供されています。以下、トピックごとに紹介していきます。 ゲーム Meteorのプラットフォームでは、ブロックチェーンを活用したゲームも搭載されています。 ゲーム収益はその一部がプールとして補充され、ジャックポットとしてユーザーに配分されます。搭載されているゲームとしては、ルーレット、宝くじ、クラッシュ、ベッティングがあります。 Meteorカードの発行 ここまで述べてきたように、Meteorは、通常の暗号資産プラットフォーム以上に、クリプト分野全体に跨った多種多様なサービスを提供しようとしています。ここまで、NFTマーケットプレイスや、ローンチパッドについて述べてきましたが、Meteorカードの発行も計画されています。 暗号資産を日常に持ち込むためには、やはり日々の決済に暗号資産を加えることが重要です。そこで、Meteorが導入するのがMeteorカードです。管理の全てはアプリで行われ、ユーザーは暗号資産をチャージしMeteorカードを使用することで、どこでもカード決済を行うことが可能です。 トークンを保有することでMeteorカードを持つことが可能となり、将来的には決済金額としてトークンの還元やサブスクリプションサービスの付与も予定されているとのことです。 Meteorの今後のロードマップ Meteorは今後一年間のロードマップを公開しています。 2023 Q4:トークンリスティング、パートナー促進、海外プロモーション 2024 Q1:ゲーム、ステーキング、UI / UX改善アップデート、ローンチパッド第一弾 2024 Q2:Meteorカード、ゲームの追加、トークンのリスティング推進、大学と連携 2024 Q3:大規模アップデート、大型オフラインイベント、ローンサービス、数カ国でのライセンス取得 2024 Q4:パートナーシップの公表、大規模なキャンペーン、法人決済サービス 日本でも積極的な事業展開を実施 ここまで、Meteorの概要について詳細を述べてきました。 ペルーの暗号資産プラットフォームとして注目を集めるMeteorですが、グローバル展開も積極的に行なっていることでも知られています。そして、Meteorのグローバル展開先の一つには日本があります。 既に日本語での公式サイトの構築が徐々に始まっており、日本でのイベント主催、スポンサーシップ、各企業とのコラボレーションなどを行っています。 それぞれを詳しく紹介していきます。 日本語で公式サイトがサービス開始:完全対応ではないものの、徐々に対応が進む 海外の暗号資産プラットフォームを利用するにあたって、障壁の1つになるのはやはり言葉の壁です。しかし、Meteorでは5カ国語に対応しており、その中には日本語もあります。 まだ全てのページにおいて完全な日本語対応がされている訳ではありませんが、マーケット概要や、ポートフォリオ、お問い合わせ窓口などは日本語に対応をしており、今後の日本語対応の拡充が期待されます。 「BreakingDown10」にてプラチナスポンサーに就任 [caption id="attachment_102744" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:https://breakingdown.jp/[/caption] Meteorは暗号資産プラットフォームの日本語対応サービスだけでなく、積極的なスポンサー活動も行なっています。 Meteorは、2023年11月23日に開催された「BreakingDown10」にてプラチナスポンサーとなりました。 BreakingDownは、ボクシング、空手、空道、柔道といった様々な背景をもつ格闘家たちが出場し、1分1ラウンドで戦う新しい格闘エンターテイメントです。総合格闘家の朝倉未来がCEOを務めており、人気の番組となっています。 また、Meteorはプラチナスポンサーになるだけではなく、各企業とコラボし観客へ様々なサービスを提供しました。 XANAとのコラボによって、限定NFTを配布 XANA(ザナ)は、Nobordrerzが開発するWeb3.0メタバース及び、Web3.0インフラストラクチャーです。東京オリンピック・パラリンピックや、ミラノファッションウィークでのWeb3プロジェクトを担当しています。 MeteorとXANAの限定NFTは、会場観戦者チケットを購入した人だけに配られたNFTです。NFTを受け取った人には抽選でUSDTやサイン入りグッズなどの豪華特典が当たるキャンペーンが開催されました。 ストレイムとのコラボによって、限定NFTを配布 ストレイムは、NFTマーケットプレイスです。多種多様なオーナーシップや体験などの権利を、日本円や暗号資産で簡単に取引することが可能です。 MeteorとストレイムのNFTは、4000個限定で配布されました。NFT保有者には将来的にユーティリティがつくとの発表がされていました。 Horizonとコラボによって、スマートフレグランスを提供 Horizonは、香りをデジタル化する技術を有しており、香りのレシピデータの解析や、香りのブレンドを提供しています。Smell Marketというデジタルフレグランスのオンラインストアでは、ユーザーは香りのレシピのダウンロード及び、専用ディフューザーを使用して香りの再現を行うことが可能です。 BreakingDown10の来場者には、MeteorとHorizonが協力し特別に開発されたスマートフレグランスが提供されました。 朝倉未来や呂布カルマを招いたクラブイベントを主催 12月8日には、Meteorが主催となり朝倉未来と呂布カルマのトークセッション及び、呂布カルマ・ISH-ONE ・AYUMIのLiveを行うクラブイベントが開催されました。 渋谷BAIAで無料招待という形で行われ、盛況を博しました。 おわりに ここまで、ペルー発の暗号資産プラットフォームMeteorの解説をしてきました。世界的に拡大していくと予測される暗号資産市場ですが、中でも、南米の盛り上がりには注目が集まっています。 MeteorはペルーにおけるNFT人気を背景として、取引所サービスだけでなく、NFTマーケットプレイスにも重点を置いています。また、ローンチパッドを充実させることでより広範な資金調達の手段を提供し、教育支援も行うなどしてコミュニティ構築にも余念がないことが窺えます。ガバナンストークンであるMTOの上場が決定していることも、Meteorエコシステムの発展には追い風です。 グローバル展開先の一つに日本があることも魅力的です。日本語版の公式サイトやXがあり、日本ユーザーに対して日本語で訴求するだけでなく、日本のイベントへのスポンサーシップや主催を行うなどして積極的に日本への進出を行い、知名度の獲得に邁進しています。 Meteorに興味を持たれた方は、まずはアカウント登録からしてみてはいかがでしょうか? Meteor各種Infomarion X:https://twitter.com/themeteor_io_jp 公式サイト:https://www.themeteor.io/ja App(Google Play):https://play.google.com/store/apps/details?id=com.themeteor.app&hl=ja&gl=US Instagram:https://www.instagram.com/themeteor.io/ Linkdin:https://www.linkedin.com/company/themeteorco/ Whitepaper : https://themeteor.link/whitepaper Sponsord Contents by Meteor ※本記事はMeteorからのスポンサード記事となります。サービスのご利用、お問い合わせは直接ご提供元にご連絡ください。

プロジェクト
2023/11/05Scroll徹底解説|他zk系レイヤー2との比較からコントラクトのデプロイまで
10月17日、イーサリアムレイヤー2「Scroll」のメインネットが正式にローンチされました。 pic.twitter.com/BujREyNGqi — Scroll 📜 (@Scroll_ZKP) October 17, 2023 イーサリアムレイヤー2として、ArbitrumやOptimismやBaseなどが既に有名ですが、Scrollはそれらとは用いている技術が異なっています。 Scrollは、ゼロ知識技術を採用した、EVMと互換性のある仮想マシン「zkEVM」を搭載していることが特徴です。 今回の記事では、Scrollの概要から、現在公式が行なっているScroll Origins NFTを例に挙げながら、実際のScrollまでの触り方までを紹介します。 注目を集めるScroll イーサリアムを取り巻くレイヤー2チェーン開発は数多くされていますが、何故こんなにもScrollが注目を集めるのでしょうか? Scrollの詳細に踏み込む前に、まずは周辺情報を見ていきます。 テストネットの段階から多くの注目を集めており、多くの監査やレビューも Scrollは、メインネットの公開前からその開発に多くの関心が寄せられてきました。 2022年8月に開始されたプレアルファテストネットの段階で、1500万件以上のトランザクション処理や、180万以上のブロック証明を完了しています。 他にも、メインネット公開までに3つのテストネットを実施してきましたが、合計で45万回以上のスマートコントラクトのデプロイや、9000万回以上のトランザクション、900万以上のブロック生成が行われました。 また、新興のプロジェクトには、セキュリティが十分かどうかといった不安がつきまといますが、Scrollはこれらにも配慮しています。 Scrollは、OpenZeppelinやZelicによって監査がされています。また、zkEVMに関しては、Trail of BitsやKALOSからレビューをされています。また、ノードのコードについてはTrail of Bitsから分析をされています。 Scrollの開発自体は、2021年から行われてきましたが、今回のメインネットの公開まで2年かかったのは、上述の通りテストネットや監査を十分に行うというように、セキュリティを優先していたのが理由です。 大規模な資金調達を達成済み Scrollは今年3月に、5000万ドルという大規模な資金調達を行なっており、Polychain Capital、Sequoia China、Bain Capital Crypto、Moore Capital Managementといったベンチャーキャピタルが参加していました。 ここ最近ではビットコインの値段も3万5千ドルに復帰するなど、クリプト業界が復調の傾向にありますが、資金調達が行われた3月上旬時点では、2万ドル台前半という厳しい状況にありました。 そうした中での5000万ドルという資金調達は、Scrollへ非常に大きな期待が寄せられていたことの証左と言えるでしょう。 TVLが右肩上がりに増加傾向 [caption id="attachment_99737" align="aligncenter" width="800"] データ参照元:https://dune.com/gasweighing/scroll-on-mainnet[/caption] Srollのメインネットがローンチされてから、およそ1ヶ月弱ではありますが、そのTVLは右肩上がりに増加傾向にあります。 これは、多くの開発者やベンチャーキャピタルから支持を得ているだけでなく、一般ユーザーからの注目も高く、多くの資金が流入していることを示しています。 このように、Scrollを取り巻く環境は非常に充実していると言っていいでしょう。 次の章からは、より具体的なScrollの概要を解説していきます。 Scrollの概要 Scrollのビジョンは、イーサリアムの高額なガス代や混雑、アクセシビリティの改善です。 高額なガス代は少額しか資金を持たない一般ユーザーにとって敷居を高くしてしまいます。これは、新たなアプリケーション開発やユーザーの障害となってしまいます。 イーサリアム開発陣もそれは感知していたものの、技術的な問題により、なかなか実現がされてきませんでした。PoSへの移行などなど多くの取り組みがされてきていますが、未だ多くのソリューションが求められています。 そこで、Scrollはゼロ知識証明(ZKP:Zero-Knowledge Proof)システムを採用することで、上記の問題に対応しています。 zkEVMを搭載したレイヤー2ソリューション イーサリアムのスケーリング問題に対するソリューションはいくつかありますが、Scrollはその中でもゼロ知識ロールアップ(zkRollup)を採用していることが特徴です。 ゼロ知識技術の特徴として、証明者が生成した証明に対して、検証者がより詳細な情報を得ることなく証明を検証することが挙げられます。 特徴はいくつかありますが、「完全性」と「正当性」に関する性質を応用することで、計算を圧縮し、検証のコストを削減していることが挙げられます。 これにより、「素早いアセットの移動」、「ガス代の削減」を実現することが可能となっています。 また、Scrollは、ゼロ知識技術を活用する中で、EVM(イーサリアム仮想マシン)との互換性を有する「zkEVM」を搭載していることが特徴です。 これまでのzkRollupは、EVMと互換性がないアルゴリズムを採用していたため、開発者にとって新たな開発言語を学ばなければならないなど技術的な難易度が高く、有用ではあるけれども多くの面でコストが高くつくものでした。 しかし、EVMとの互換性を有することで、アプリ開発者はイーサリアム上でのdAppsを簡単にScroll上へとデプロイすることが可能になっています。 Vitalik氏によると、長期的には全てのユースケースでzkRollupが勝るとの予想 既に存在するイーサリアムレイヤー2の多くは、Optimistic Rollupを採用しています。 zkRollupとOptimistic Rollupのどちらのレイヤー2が、将来的に勝者となるかに注目が集まりますが、イーサリアム開発者であるVitalik氏は、2021年の段階で、zkRollupとOptimistic Rollupの比較をし、以下のように述べています。 一般的に、私自身の見解としては、短期的には、汎用のEVM計算ではOptimistic ロールアップが、単純な決済や交換、その他のアプリケーション固有のユースケースではZK-ロールアップが勝つ可能性が高いが、中長期的には、ZK-SNARK技術の向上により、すべてのユースケースでZK-ロールアップが勝つだろう。 (引用元:https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html) このようにVitalik氏の分析によれば、zkRollupの方が長期的には勝つと予測されています。しかしながら、現在は、Optimistic Rollupを採用したレイヤー2の方が優勢となっています。それは何故なのでしょうか? 何故、これまでOP系レイヤー2が勢力を増してきたのか? [caption id="attachment_99698" align="aligncenter" width="800"] 画像引用元:https://l2beat.com/scaling/summary[/caption] イーサリアムのレイヤー2といえば、Arbitrum、Optimism、Baseが有名です。 これらは、Optimistic RollupというOP系の技術を採用したものです。上記の画像を参照していただければ、OP系統のレイヤー2が大きなシェアを有していることが分かります。 そして、エアドロ関連を含めて話題となっているzkSyncやStarknet、そして今回取り上げているScrollは、zkRollupというゼロ知識技術を採用したレイヤー2となっています。 これまでOptimistic Rollupのレイヤー2が盛んに開発されてきた背景として、zkRollupの技術的な問題がありました。 既に述べたように、zkRollupに使用される技術は複雑であり、またEVMとの互換性を有しておらず、その分開発コストが高くついてしまいます。こうした事情から、zk系のレイヤー2の開発は、OP系の後ろを走っていました。 しかしながら、処理性能やガス代の観点からすれば、zkRollupの方がOptimistic Rollupよりも優れています。 例えば、Optimistic Rollupの処理速度が500TPSなのに対して、zkRollupの場合は2000TPS以上となっています。他にも、zkRollupの方が出金に際して必要な期間が短いというメリットがあります。 以下の図に、両者の比較が簡潔にまとめられています。 [caption id="attachment_99702" align="aligncenter" width="750"] 画像引用元:https://tokeninsight.com/en/research/market-analysis/zksync-vs-starkware-what-s-the-difference-between-the-top-two-zk-rollups[/caption] zkEVMの開発など、zkRollupを取り巻く技術改善は日々進んでおり、zkSyncやStarknetの発展からも分かるように、多くのdAppsが開発・構築されています。zk系レイヤー2のTVLも増加傾向にあります。 Scrollはまだメインネットが公開されて1ヶ月経っていませんが、こうしたzk系のレイヤー2の代表として、将来的にScrollの名前が挙げられる日が来るかもしれません。 Scrollの設計思想 Scrollは、イーサリアムをzkRollupでスケーリングするためのプロジェクトです。以下、主要なScrollの設計思想を紹介します。 ユーザーセキュリティの確保:Scrollは、レイヤー1の完全なセキュリティを レイヤー2における取引においても利用できるように設計されています。 EVMとの互換性の維持:Scrollは、ユーザーや開発者が既存のdAppsからシームレスに移行できるようにするために、EVMとの互換性を重視しています。 効率性:トランザクション手数料を安くすることで、ユーザーがより良いレイヤー2体験を享受できるようにします。 コミュニティの全レイヤーにわたる分散化:Scrollは、検閲や組織的攻撃に対する弾力性を確保するために、ノードオペレーター、開発者、ユーザーといった多くの面で分散化を確保することにコミットしています。 Scrollと他zkEVMとの比較 ここまで、Scrollの主要な要素であるzkEVMについて、既に大きなシェアを誇っているOptimistic Rollup系のレイヤー2に言及しながら述べてきました。 ここからは、zkEVMに注目しながら、Scrollと他zk系レイヤー2(zkSyncやStarknetなど)との違いを分析していきます。 VitalikによるzkEVMの四つの分類:Scrollは(現在は)Type-3に分類される [caption id="attachment_99703" align="aligncenter" width="856"] 画像引用元:https://vitalik.ca/general/2022/08/04/zkevm.html[/caption] zkEVMは、実は大きく四種類に分類されます。 Vitalik氏は、EVMとの互換性とパフォーマンスの二つの観点から、それぞれをType-1からType-4に分類しています。 以下それぞれの特徴を挙げていきます。 Type-1:完全にイーサリアムと同等。しかし、検証時間(prover time)が長い。 Type-2:完全にEVMと同等(イーサリアムと同等ではない)。改善されているものの、依然として検証時間が長い。 Type-3:ビルドが容易であり、検証時間が短縮可能。しかし、EVMとの非互換性が高くなる。 Type-4:検証時間が非常に早い。しかし、EVMとの非互換性がより高くなる。※高水準言語相当。 このようなzkEVMのTypeは、プロジェクトの開発によって変化する可能性があることには注意が必要です。例えば、今回取り上げているScrollは、Type-3に分類されますが、将来的にはType-2やType-1を目指して開発が進められています。 他にも、ゼロ知識証明の技術として、ZK-SNARKかZK-SHARKのどちらかを使用しているかなどの細かい要素がありますが、大きくは上記のTypeによる分類が分かりやすいかと思います。 zk系レイヤー2の比較 ここからはより具体的な、zkEVMのレイヤー2の比較をしていきます。 zkSync ・互換性はType-4。(言語レベルのEVM互換性) ・ゼロ知識技術として、SNARKを活用。 ・現在、zk系のレイヤー2の中では最大のシェアを有する。 Starknet ・互換性はType-4。(言語レベルのEVM互換性) ・ゼロ知識技術として、STARKを活用。(技術的にはSNARKよりも安全ではあるものの、検証に時間がかかり、ガス代もかかる) ・言語として、CairoとSolidityをサポート。 ・zkSyncと並んで、zk系のレイヤー2として注目を集める。 Scroll ・互換性はType-3であるものの、Type-2(Bytecodeレベルの互換性)を目指して開発中。最終的には、イーサリアム財団と協力し、Type-1に限りなく近づけることも目標に。 ・ゼロ知識技術として、SNARKを活用。 ・10月にメインネットが公開。 Polygon zkEVM ・互換性はType-3であるものの、Type-2(Bytecodeレベルの互換性)を目指して開発中。 ・ゼロ知識技術として、SNARKとSHARKの両方を活用。 ・Polygonのイーサリアムスケーリングソリューションには他にも、Polygon Edge、Polygon Zero、Polygon PoSなどが存在。 実際にScrollを触ってみる ここからは実際にScrollを触るための方法や、Scroll Origins NFTに向けての準備も紹介していきます。 イーサリアムメインネットからScrollへブリッジ Scrollは、イーサリアムのレイヤー2であるため、ブリッジをしてトークンを移す必要があります。 ブリッジに関しては、公式によってサービスが提供されているため、こちらを利用することができます。 Bridge:https://scroll.io/bridge もし、ブリッジにかかる時間が気になるということであれば、代替のサービスを利用してブリッジすることも可能です。 以下、主要なものを二つ紹介致します。 orbiter:https://www.orbiter.finance/ rhino.fi:https://rhino.fi/ Scroll Origins NFTのキャンペーンが実施中:12月14日にclaimが可能に Scrollでは既に多くのdAppsが登場しており、スワップは勿論、流動性の提供も可能となっています。どれからさわればいいか迷うかもしれませんが、まずは最初にScroll公式が発表している「Scroll Origins NFT」を試してみてはどうでしょうか? Scroll Origins NFTは、Scrollのアーリービルダーがミント可能なNFTです。 Scroll Origins NFTは三種類あり、ジェネシス・ブロックを基準として、それぞれScrollメインネットにスマートコントラクトのデプロイをいつまでに行ったかで、どの種類のNFTをもらえるかが決まります。 以下、それぞれのNFTを紹介致します。 「Quintic」:2023年11月9日10:59PM (GMT)までに、デプロイした人が対象。※ジェネシスブロックから30日以内。 「Quartic」:2023年11月24日10:59PM(GMT)までに、デプロイした人が対象。※ジェネシスブロックから30~45日目。 「Cubic」:2023年12月9日10:59PM(GMT)までに、デプロイした人が対象。※ジェネシスブロックから45~60日以内。 該当NFTのclaimは、2023年12月14日10:00PM(GMT)から可能になるとのことです。 コントラクトに対して、特別なサプライズがあることが告知されていますので、報酬も兼ねてScrollを触ってみてはいかがでしょうか? ※NFTはソウルバウンド(譲渡不可)となっていますので、適切なウォレットでclaimをしなければならいことには注意が必要です。 Owltoを使えば即座にデプロイが可能 恐らく、スマートコントラクトのデプロイをしたことがない方にとっては、Scroll Origins NFTの条件を満たすのは難しいかもしれません しかしながら、Owltoを使うことで、ウォレットを接続するだけで、デプロイをすることが可能となっていますので、新規ユーザーの方でも問題なくNFTの適格となることが可能です。 Owlto:https://owlto.finance/deploy 実際に、自分でScrollにスマートコントラクトをデプロイしてみたい方向け 先ほどOwltoを使用したデプロイ方法を紹介しましたが、今回を機に試しに自分で直接デプロイをしてみたいという方もいるかもしれません。 そういった方向けに、筆者が実際に行ったRemixを使用してのデプロイ方法を紹介致します。 ※今回のデプロイ方法は、X上にてDe.Fi 2.0が紹介していた方法をもとにしています。(https://x.com/DeDotFi/status/1640356084106813441?s=20) まず、Remixを開きます。 Remix:https://remix.ethereum.org/#lang=en&optimize=false&runs=200&evmVersion=null&version=soljson-v0.8.18+commit.87f61d96.js ①をクリックします。 ②の箇所に、「EtherWallet.sol」を打ち込みます。 ③の箇所に、以下のGithubのコードを貼り付けます。(https://github.com/whonion/EtherSmartWallet/blob/main/EtherWallet.sol) ④のSOLIDITY COMPILERをクリックします。 ①をクリックし、「0.7.4」のバージョンを選びます。 ②をクリックし、コンパイルします。 ③をクリックし、「Deploy & Run Transaction」へと移動します。 ①をクリックし、「Injected Provider - Metamask」を選択します。 ②をクリックし、ウォレットの確認画面が出ますので、確認をしブロック表示が出れば完了です。 NFT配布対象かどうかは公式サイトで確認可能 実際にスマートコントラクトをデプロイしてみたものの、それが正常に行われておりNFTの配布対象となっているのかどうか気になるかもしれません。 その場合は、以下のURLでウォレットを接続し、「Check eligibility」をクリックすることで、適格かどうかを確認することができます。 Scroll Check eligibility:https://scroll.io/developer-nft/check-eligibility おわりに ここまでメインネットが公開されたScrollを紹介してきました。 既にzkRollupを採用したイーサリアムレイヤー2として、zkSyncやStarknetがありますが、Scrollも注目を集めるzk系レイヤー2です。 他のレイヤー2と比べ、まだメインネットが公開されて日が浅いこともあり、アーリーユーザーとなることも可能です。 今回の記事ではScrollの概要だけではなく、スマートコントラクトのデプロイも紹介してきました。Scroll上では既に多くのdAppsの開発も進んでいるため、これを機にScrollエコシステムの探検をしてみてはいかがでしょうか。

プロジェクト
2023/11/01Celestiaとは?特徴や今後を解説|注目のモジュラー型ブロックチェーン
Celestiaは、DA(データの可用性)レイヤーを担うモジュラー型のブロックチェーンです。 モジュラー型のブロックチェーンでは、ブロックチェーンに必要な要素をさまざまなブロックチェーンやソリューションによって担います。 複数のレイヤーが各レイヤーに特化した技術を提供することで、よりブロックチェーンをスケーリングさせていくことが可能になります。 Celestiaはそんな中でもDAレイヤーを担い、5,000万ドル以上を資金調達している注目したいプロジェクトの1つです。 この記事では、そんなCelestiaの概要や特徴、仕組みなどについて解説しています。 この記事のまとめ ・CelestiaはDAレイヤーを担う ・ロールアップや実行レイヤーの基盤となる ・低いコストでデータの可用性を向上させる ・DASやNMTといった主要な技術を持つ Celestiaとは?DA(データの可用性)レイヤーを担うモジュラーブロックチェーン Celestiaは、モジュラー型のブロックチェーンを志向し、その中で主にDA(データの可用性)のレイヤーを担うブロックチェーンです。 ブロックチェーンにおけるデータの可用性とは、すべての取引関連データが全てのネットワークユーザーにとって利用可能であるという考え方です。 モジュラー型のブロックチェーンにおいて、Celestiaはブロックチェーンの基盤となるコンセンサス・データの可用性を提供します。 これから、モジュラー型のブロックチェーンの概要とCelestiaの概要について解説していきます。 モジュラー型のブロックチェーンの概要 Celestiaについて触れる前に、モジュラー型の基本的な概要についてかんたんに解説していきます。 モジュラー型のブロックチェーンとは、ブロックチェーンに必要な要素を分割して、複数のブロックチェーン・ソリューションで構成するブロックチェーン。 前提として、ブロックチェーンに必要なものには、以下のようなものが挙げられます。 実行 決済、紛争解決 コンセンサス データの可用性 シンプルなブロックチェーンでは、上記の全ての要素を単一のブロックチェーンで処理するのが一般的です。 一方で、モジュラー型のブロックチェーンでは、上記の要素を各ソリューションが、1つまたは複数担当します。 逆に、担当している以外の要素については別のレイヤーに渡して、分業に近い形でトランザクションを処理していきます。 モジュラー型のブロックチェーンでは、各要素において特化したソリューション・ブロックチェーンを活用することで、柔軟性・分散性・スケーリングをより向上させます。 Celestiaの概要 Celestiaは、モジュラー型のブロックチェーンの中でも、コンセンサスとDA(データの可用性)を担うレイヤーのブロックチェーンです。 実行・決済といった要素を担わないため、CelestiaはコンセンサスとDAに特化しており、DAレイヤーにおけるスケーリング・最適化を行っています。 そのため、Celestiaは単体で動くL1ブロックチェーンというよりも、Celestiaの上でロールアップ・実行レイヤーのソリューションが動く基盤となるブロックチェーンです。 Celestiaは、過去に5,500万ドルの資金調達にも成功しており、モジュラー型のブロックチェーンを志向するプロジェクト代表格の1つです。 Today, we announce our $55M raise to launch a modular blockchain network so that anyone in the world can easily deploy their own blockchain.https://t.co/t2FphHuMAN — Celestia (@CelestiaOrg) October 19, 2022 メインネットのローンチについても2023年内を予定しており、何かと直近で注目ポイントが多くなっています。 Celestiaの簡単な3つの特徴 これから、Celestiaの特徴について、以下の3つの特徴から解説していきます。 ・ブロックチェーンの構築とセキュリティの確保 ・さまざまな実行レイヤーの基盤となる ・DAレイヤーにおけるスケーリング Celestiaの強みや、メリットなどをかんたんにチェックしていきましょう。 ブロックチェーンの構築と共有セキュリティの確保 Celestiaは、ブロックチェーンの構築とセキュリティの確保を容易にします。 現在、多数のブロックチェーンが運用されており、さまざまなブロックチェーンを運用することを前提としたプロジェクトも多数登場しています。アプリ固有のブロックチェーンを志向するプロジェクトやプラットフォームも出てきおり、今後もブロックチェーンの数は増加していく可能性が高いでしょう。 しかし、一般的なブロックチェーンは、各ブロックチェーンごとに独自のバリデーター群を用意する必要があります。 人気の高いプロジェクトは十分なバリデーターとセキュリティを確保できるかもしれませんが、全てのプロジェクト・人気の低いプロジェクトが確保するのは困難でしょう。バリデーター群が十分に確保できない場合、ブロックチェーンの安定性やセキュリティに大きな影響を与える可能性があります。 上記の問題に対する解決策の1つがモジュラー型のブロックチェーンであり、Celestiaもその選択肢の1つです。Celestiaを活用すれば、各ブロックチェーンがDAレイヤーにおけるバリデーターを初めから用意する必要がありません。 Celestiaは、必要に応じてブロックチェーンやソリューションを選択できるようにし、ロールアップや実行レイヤーに対して共有可能なセキュリティを提供します。 さまざまなレイヤーの基盤となる モジュラー型のブロックチェーンでは、単一のブロックチェーン・レイヤーが全ての要素を提供しません。 実行レイヤー・決済レイヤー・DAレイヤーなど、複数のレイヤーが用途に応じて組み合わさり、ブロックチェーンとして機能します。 Celestiaが焦点を当てているDAレイヤーは、実行レイヤーや決済レイヤーの基盤となる存在です。 さまざまな実行レイヤー・決済レイヤーをCelestiaが提供するコンセンサス、データの可用性(DA)を元に動かすことができます。 DAレイヤーにおけるスケーリング Celestiaは、DAレイヤーにおけるスケーリングを提供することを目的としたブロックチェーンです。 Celestiaは、スケーラビリティを「TPSをトランザクション検証するコストで割った数」として定義しています。 TPSを向上させる方法はいくつかありますが、その多くのケースで何らかのトレードオフを要求されることが多いです。 例えば、TPSが向上させると、トランザクションを処理する主体に求められる要件も厳しくなるケースが見られます。 要件が厳しくなってハードルが上がると分散性が損なわれ、ブロックチェーン自体も不安定になってしまう可能性も否定できません。 そのため、CelestiaではDAレイヤーをスケーリングするのはもちろん、後述するDAS・NMTといった技術によってコストの高騰を抑え、DAレイヤーとしての安定性も担保します。 Celestiaの仕組み これから、Celestiaで採用されている主要な技術などについて解説していきます。 ・データの可用性と諸問題について ・データの可用性サンプリング:DAS ・ネームスペースマークルツリー:NMT Celestiaの仕組みのイメージをさらに掴んでいきましょう。 データの可用性と諸問題について まず、はじめにCelestiaが担うDAレイヤーの主要トピックであるデータの可用性について解説していきます。 データの可用性とは、データが有効なものか(利用でき公開されているのか)を問うトピックです。 データの可用性が確保されていることで不正を検出したり、ブロックチェーンの状態を確認することが可能になります。 逆に、データの可用性が確保されていない場合、その中に不正なトランザクションが含まれる可能性などが出てきます。 例えば、イーサリアムのロールアップでは、何らかの方法で不正を検知する仕組みを実装した上でトランザクションを処理します。 ただし、その後処理した結果をイーサリアムに渡すことで、データの可用性はもちろん、実行レイヤー以外の要素についてはイーサリアムに依存する仕様です。 ロールアップは、イーサリアムでデータ可用性やその他の要素が補完されていることによりセキュリティを受け継いだ上で、利便性の高い環境を実現しています。 上記のようなデータの可用性を確保するには、フルノードで全てのデータをダウンロードする方法が有効です。 ただし、上記の手法ではノードへの負荷は高まります。そのため、代替案としてライトノード(ライトクライアント)というオプションもあります。 ライトノードは、ブロックの一部分のみ(ブロックヘッダーなど)を参考に、トランザクションの検証はしないノードです。 フルノードよりもノードに対する負荷は低くなりますが、ブロックの一部分のみしか参考にしないので、完璧なセキュリティを確保することは困難です。 一般的なブロックチェーンにおいて、ノードに対する負荷が強くなるとフルノードは減少する一方で、ライトノードが増加する可能性が高くなります。 ライトノードの増加とフルノードの減少は、上記のようなプロセスを担う主体を、より少ないフルノードに集中化させてしまう問題を発生させます。 データの可用性サンプリング:DAS Celestiaは、データの可用性サンプリング:DAS(Data availability sampling)という独自のアプローチで、データの可用性を確認します。 具体的にはDASによって前述の「ライトノード」でデータの可用性を確保できるようにし、セキュリティを確保した上でDAレイヤーにおけるスケーリングを可能にします。 DASは、不正行為とデータの可用性を証明する技術。DASでは、ブロックの一部分のみをいくつか分割し、それをサンプリングします。 サンプリングを複数回行うことによって、ブロックのデータの有効・無効を判断します。(サンプリングを繰り返し、有効なデータが続けば、有効なものである可能性が非常に高い) ブロックの1部分のみを参考にすれば良いので、全ての要素を確認する必要がなく、ノードに対する負荷も低くなります。 How do you do it? By sampling that block multiple times (tossing the coin). With each successful sample (the coin lands heads) you gain 50% more confidence that you have the available block. You repeat this until you have 99.99% confidence the block is available. pic.twitter.com/RBH3CtIsRK — Nick White (@nickwh8te) August 17, 2022 上記のような背景から、DASを利用するとノードへの負荷が軽減され、ライトノードでもブロックの有効・無効(データの可用性)を判断可能です。 前述した通り、通常データの可用性を確保するにはフルノードでブロックの全てを確認する必要があります。 ただし、ブロックが大きくなればなるほどノードに対する負荷は大きくなり、ノードへの負荷増は不安定な状況を生むことに繋がります。 TPSと検証するコストを考慮したCelestiaが定義するスケーリングにおいても、十分な結果が得られません。 一方で、DASを活用すればライトノードでも実行できる比較的負荷の少ない方法で、データの可用性を確保できます。 ネームスペースマークルツリー:NMT もう一つ、Celestiaの仕組みの重要な特徴である「ネームスペースマークルツリー」を見ていきましょう。 ネームスペースマークルツリー:NMT(Namespaced Merkle Trees)は、識別子によってリーフが順序付けされたマークルツリー(データを要約・検証するためのデータ構造)です。 Celestiaでは、NMTを利用して特定のデータが完全に提供されていることを証明し、特定のデータのみを実行 or 決済レイヤーに渡します。 NMTが存在することで、Celestia上に構築されている各ロールアップ・実行レイヤーが、関連するデータのみを取得可能になります。 そのため、Celestiaに構築されたロールアップは、他のロールアップやソリューションのデータを取得する必要がありません。 模索されているCelestiaの使用例 上記のような仕組みで動いているCelestiaの使用例について、模索されているものをご紹介していきます。 まず、はじめに模索されているのが、ソブリンロールアップです。 ソブリンロールアップは、データの可用性・コンセンサスなどをCelestiaが担い、実行・決済を何らかのロールアップが担う方式のロールアップです。 イーサリアムの一般的なロールアップと異なるのは、実行・決済の主体はロールアップが担っている点です。(イーサリアムのロールアップでは実行のみ) 決済のレイヤーをロールアップが担っていることにより、ロールアップの権限をより強めることが可能になり、決済レイヤーの干渉を受けずにアップグレードが可能になるなどの特徴が見られます。 また、その他にもデータの可用性のみをCelestiaが担い、実行レイヤーにロールアップ、決済・コンセンサスレイヤーにイーサリアムを組み合わせたCelestiumなどが挙げられます。 Celestiaの今後 10月末にCelestiaのメインネットがローンチされました。 Celestia mainnet is live ✨https://t.co/Sj7RAfTh4W pic.twitter.com/Sd6CsU2dwL— Celestia (@CelestiaOrg) October 31, 2023 Celestiaの$TIAトークンもBinance、OKX、Kucoin等の取引所に上場しており、トレードが可能な状態となっています。 今後、Celestia以外のモジュラー型のブロックチェーンプロジェクトのローンチも予定されており、同分野のパイオニアとなったCelestiaの今後の動向には注目です。 Celestiaについてまとめ この記事では、Celestiaについて解説しました。 Celestiaは、モジュラー型のブロックチェーンを志向し、今後DAレイヤーとして実行や決済レイヤーの基盤となる可能性があります。 さまざまな方法でブロックチェーンをスケーリングさせる方法が模索されていますが、その一つとしてモジュラー型のブロックチェーンやCelestiaについて注目していきたいと言えるでしょう。 最後まで読んでいただきありがとうございました。

プロジェクト
2023/10/15Mocaverse徹底解説|Animoca Brandsが手がけるメンバーシップNFTプロジェクト
9月上旬、MocaverseというNFTプロジェクトが、2000万ドルという非常に多額の資金調達を行いました。 しかしながら、クリプトの冬が訪れ、NFTの盛り上がりはかつてと比べてひと段落しています。そうした中で、このような規模の資金調達をNFTプロジェクトが獲得したというのは、何か特別な背景があることが窺えます。 実は、このMocaverseは、これ単体のNFTプロジェクトというわけではなく、Animoca Brandsという大手グローバルWeb3企業によるエコシステム構築の一環として行われたプロジェクトでした。 この記事では、Animoca Brandsの概要から、Mocaverse NFTによるエコシステムの構築までを取り上げます。 Animoca Brandsとは? Mocaverseの具体的な説明をする前に、まずはMocaverseプロジェクトを主導しているAnimoca Brandsの説明をします。 というのも、MocaverseのエコシステムとAnimoca Brandsは非常に密接な関係にあるからです。 Web3分野に幅広く投資し独自のエコシステムを構築中 Animoca Brandsは、アジア太平洋地域を中心に活動しており、Web3分野に幅広く投資をしていることで知られています。 同社の投資対象は、Web3プロトコル、ブロックチェーンゲームからEsports、プラットフォーム、マーケットプレイスまで非常に多岐にわたります。Web3を主軸として、現在では380を超えるプロジェクトのポートフォリオを拡大しています。 Deloitte Tech Fastを受賞しており、Financial Timesのアジア太平洋地域の高成長企業リスト2021にもランクインしており、大手のWeb3企業です。 日本にも「Animoca Brands KK」として2021年より進出中 日本でAnimoca Brandsの名前が広く知れ渡ったのは、今年6月に行われた三井物産との資本業務提携及び、戦略的パートナーシップに関する覚書を締結したことでしょう。 この業務提携は、三井物産が保有する幅広い事業や資産、ネットワークを活用することで、日本市場におけるWeb3の普及とイノベーションにつながる新たなビジネスの創出のために行われました。 この発表は2023年に行われましたが、実は、Animoca Brandsの日本市場への進出は2021年には既に行われていました。 日本における戦略的子会社として「Animoca Brands KK」を設立し、2022年1月にはシードラウンドで約 11 億円の資金調達を完了しています。 Animoca Brands KKは、ブロックチェーン技術を活用したプラットフォームを構築・提供することで、日本の知財・IPホルダーがWeb3のエコシステムの中でNFTやトークンを発行できる仕組みを提供し、それによってファンとのコミュニティの構築・拡大を支援する目的で設立されました。 また、2023年3月には、同社CEOに岩瀬大輔氏(NFTプラットフォーム「Kollektion」を運営するKLKTN共同創業者兼CEO)が就任しています。 このようにAnimoca Brandsは、日本における知財やIPを中心とした事業の拡大に数年前から注力していることが窺えます。 Animoca BrandsとMocaverse ここまでAnimoca Brandsが多くのWeb3分野に投資をし、ポートフォリオを構築していることに言及してきました。 しかしながら、その投資対象は多岐にわたるため、一つの大きなエコシステムとしてまとめ上げるのは非常に困難です。そこで生まれたプロジェクトが「Mocaverse」です。 Mocaverseは、この広大なエコシステムの接続と結束力を向上させ、Web3コミュニティの成長を支援することを目的としています。 2000万ドルの資金調達を成功 まず、Mocaverseの資金調達の仕組みについて解説をします。 今回の資金調達は、「将来株式取得略式契約スキーム」(通称:SAFE)という形で行われました。これは、あらかじめ投資家たちが、決められた購入金額を投資家が支払うことによって、会社側がその投資家に対して、一定の株式に対する権利を一定の条件で発行するというものです。 1株あたり4.5オーストラリアドルでの株式発行が行われ、これは六ヶ月後に普通株に転換される予定です。 また、これだけではなくAnimoca Brandsは、このラウンドの投資家たちに対して1対1ドルでユーティリティ・トークンのワラントを無償で付与しました。これは30ヶ月の権利確定スケジュールの中で行われます。 このようにAnimocaBrandによる肝入りのプロジェクトであることがわかります。 半年以上前から「Mocaverse」プロジェクトは進行中 今回Mocaverseが大きな注目を浴びたのは、2000万ドルという多額の資金調達を行ったためですが、「Mocaverse」プロジェクト自体は半年以上前から開始されていました。 2022年12月15日にAnimoca Brandsは公式PFP NFTコレクション「Mocaverse」を発表しました。これは同社のWeb3とメタバース中心のプロジェクトのエコシステムの強化のために作られました。 Mocaverseの概要 ここまでAnimoca Brandsの概要および、何故、Animoca BrandsがMocaverseプロジェクトを始めたのかを述べてきました。 ここからはより詳しく Mocaverseについて掘り下げていきます。 Mocaverse:Animoca Brandsが手がけるメンバーシップNFTコレクション Mocaverseは、Animoca BrandsによるNFTコレクションであり、Mocaverse NFTはこの排他的なコミュニティに参加するための、IDの役割を果たします。 先述したように、Animoca Brandsのポートフォリオには、多くのプロジェクト、子会社、ジョイントベンチャー、パートナーがいます。彼らたちを、ユニークなNFTコレクションでまとめようとするプロジェクトが「Mocaverse」です。 このプロジェクトの背景にあるのは、Animoca Brandsの下にあるすべての人がつながり、学び、交流し、共に成長するエコシステムを持つことです。人と企業との有機的な繋がりの構築を目的としています。 BAYCとは目的が異なる NFTコレクションといえば、代表されるのはBAYC(Bored Ape Yacht Club)でしょう。しかしながら、こうしたNFTコレクションと Mocaverseは目的やエコシステムが異なっています。 BAYCのような評判の高いNFTコレクションは、コミュニティが中心となり、保有者に対して限定特典が提供されます。 その一方で、Mocaverseは、パートナーや企業、従業員、ユーザーのコミュニティを強化することを目的としており、Mocaverse NFTを保有することによるメリットは、コミュニティ強化に沿ったものとなっています。 (メリットの詳細に関しては、詳しく後述します) Mocaversce NFT「Moca」はIDとして機能 Mocaversce NFT「Moca」は、8888個のNFTです。 Mocaは、Animoca Brandsのエコシステムを強化し、同社の多くのパートナーたちとユーザーをNFTコレクションで結びつけることを目的としています。 このMocaは、Dreamers、Builders、Angels、Connectors、Neo-Capitalistsの五つの部族のいずれかに属しており、それぞれはWeb3における各主要なプレイヤーたちの性質を表現したものとなっています。 各部族は以下のように表現されます。 Dreamers:Dreamersは、エコシステムのアイデア、イノベーション、コンセプトの源です。彼らはMocaverseエコシステムを強化するための、新鮮なアイデア・イメージ・価値観を導入する人たちです。 Builders:Buildersは、Dreamersのアイデアを元に行動し、より具体的で理解しやすいものにする人たちです。 Angels:MocaverseにおけるAngelsは、宝物やチャンスを探し求めるキャラクターです。彼らはBuildersによってもたらされたアイデアを探し、そのアイデアをさらに発展させるために協力します。ほとんどの場合、彼らはプロジェクトの開発と完成に資金を提供します。 Connectors:Connectorsは、Mocana(Mocaverseの世界)と外の世界の橋渡しをします。Mocaverseの世界は排他的であるため、誰もが参加できるわけではありません。Connectorsは外部の個人や団体と繋ぐことで、この空白地たちを埋める役割を担っています。 Neo-Capitalists:Neo-capitalistsは、Mocaverse内のキャラクターへの利益分配を管理します。エコシステムへの貢献度に応じて利益を分配するシステムを考案します。 Moca保有者はMocaverseの特典に独占的にアクセス可能 同NFTは、「Moca ID」としてメンバーシップパスとして機能し、メンバーは、Mocaverseのエコシステム体験に独占的にアクセスできます。また、ロイヤリティポイントを獲得できる機会といった様々な特典が提供されます。 Mocaverseは、「学ぶ」(learn)、「遊ぶ」(play)、「作る」(build)、「善いことをする」(do good)というユーティリティの4つの主要カテゴリがあります。これは「Realm」と呼ばれユーザーがアイデアを交換し、新しい知識を求め、コミュニティとして成長するためのチャンネルとして機能します。 Moca所有者は、さまざまな会員特典を受けることが可能であり、それらは「Realm」とそれぞれ関連づけられています。 ・一緒に学ぶ機会(専門家によるAMAや特別授業など) ・一緒に遊ぶ機会(ゲームパスや限定ゲーム内アセットなど) ・一緒に構築する機会(アクセラレーター・プログラム) ・一緒に善を行う機会(社会的活動の組織化や貢献) そのほかにも、NFT保有者は、Moca XPトークンも受け取ることができ、これをステークしてコミュニティ内で使用し、報酬を獲得したりイベントに参加したりすることも可能です。 Mocaverseは、Animoca Brandsが抱えるグループ会社、パートナー、やプロジェクトといったエコシステム全体におけるユーティリティの間に、より強いつながりを形成するように設計されています。Moca保有者は、より深いAnimoca Brandsのエコシステムを体感できることでしょう。 Moca XPの仕組み・使い道:ホワイトリストの抽選でより有利に。 先ほどMoca XPについて述べましたが、より詳しく掘り下げていきます。 Moca XPはMocaverseの報酬プールに優先的にアクセスできる役割を果たします。 Moca XPを貯める方法として、以下の三つが挙げられます。 ステーキング アクティベーション コミュニティへの参加 Moca XPは各Moca NFT(トークンID)に付与されるものの、NFTは変わらず取引可能です。しかしながら、Mocaを他のウォレットに売却した場合、それに帰属するMoca XPは全てNFTとともに譲渡されます。つまり、新しい所有者はMoca XPがリセットされることなく、そのまま享受できる仕組みとなっています。 Moca XPは、Animoca Brandsのパートナーのホワイトリストへの抽選に活用できます。 Moca XPが高ければ高いほど、ホワイトリスト抽選に当選する確率がより高まります。また、抽選はシリーズごとに行われ、その抽選はMoca XPに基づいて行われますが、各シーズン終了後、Moca XPはリセットされるようになっています。 当選した場合に、取得できるBOXには、Animoca BrandsのポートフォリオプロジェクトのトークンやNFT、提携プロジェクトのNFTのリストが含まれることがあります。 Mocaverse NFTの入手方法 Mocaverse NFTは、Animoca Brandsのエコシステムを構築している人に配られます。 Animoca Brandsの機関投資家および個人投資家 Animoca Brandsおよびその子会社の従業員 Animoca BrandsのWeb3投資先企業の経営陣 Animoca Brandsのパートナー Mocaverseの参加資格のある方は、無料のミント枠と有料のミント枠を受け取ることが出来ます。 このように書くと、Mocaverse NFTの入手は、Animoca Brandsの関係者のみに限られるように思えます。 確かに、当初はAnimoca BrandsのWeb3コミュニティ内での配布が行われていましたが、現在では、OpenSeaのようなセカンダリーNFTマーケットプレイスで購入することが可能となっています。また、公式のマーケットプレイスも開設されています。 おわりに ここまでAnimoca Brandsを踏まえながら、Mocaverseの解説をしてきました。 Animoca Brandsは多くのWeb3プロジェクトに投資をしており、関わっているパートナーもプロジェクトも多岐にわたります。 そうした多種多様な企業やプロジェクトを包括的にまとめ上げるMocaverseという試みは、下火となっているNFT分野において非常に特徴的なものと言えるでしょう。 もし興味が湧いた方がいれば、Mocaverse NFTを購入し、Animoca Brandsのエコシステムを体験してみてはいかがでしょうか? Mocaverse:https://www.mocaverse.xyz/

プロジェクト
2023/10/13Over Protocol徹底解説|エアドロが期待される新プロジェクトに迫る
今現在、クリプト分野で話題となっているプロジェクト「Over Protocol」をご存知でしょうか? Over Protocolはレイヤー1ブロックチェーンであり、誰でも自由にバリデーターとなれるよう、分散化に注力しているプロジェクトです。 最近では、エアドロップが公言されていることもあり、エアドロ活動が盛んに行われていることでも知られています。 しかしながら、具体的にどのようなプロジェクトなのかといった、その内容まで追えている方は少ないのではないでしょうか? この記事では、Over Protocolの概要や具体的なソリューションの内容、それらビジョンについて徹底解説していきます。 Over Protocolが注目を集める3つの理由 Over Protocolの具体的な内容に踏み込む前に、まずは基本的な概要について述べていきます。 大規模な資金調達を成功させている Over Protocolは以前より注目をされているプロジェクトであり、大規模な資金調達を行っています。 Over Protocolの開発会社はSuperblockですが、Superblockは、2023年7月に韓国通信最大手のSKテレコム、韓国ゲーム大手Netmarble、Zepetoを開発するNaverZなどから、合計で800万ドルの資金調達を得ています。 現在は主にクリプトVC向けにラウンドを行っています。 このように、多くのVCから注目を集めているプロジェクトであることが窺えます。 Over Protocolの創設者は、韓国最大級のブロックチェーンリサーチグループ「Decipher」の創設者としても知られる [caption id="attachment_98948" align="aligncenter" width="500"] Linkedinより引用:https://www.linkedin.com/in/jaeyunkim/[/caption] Over Protocolは、Ben Kim氏よって創設されています。また、Kim氏は2018年に組織化されたソウル大学のブロックチェーングループ「Decipher」の創設者としても知られています。 Decipherは、現在では、韓国最大のブロックチェーングループに成長しています。Decipherでは、コンピューター工学は勿論、経済学、金融学、法学といった様々な学問分野の知見からブロックチェーン技術の研究が行われています。既に、クリプト業界で活躍する80名以上のメンバーを輩出しています。 エアドロが明言されており、キャンペーン活動が盛ん Over Protocolが一般ユーザーから注目を集める理由の一つとして、エアドロが明言されており、それに伴ったキャンペーンを大々的に実施していることが挙げられます。 「Over Community Access Program」と名付けられたこのエアドロキャンペーンは非常に盛んに行われており、スマホアプリ(Over Wallet)を利用することで、誰でも手軽にエアドロ活動を行うことが可能です。 エアドロキャンペーンについては、記事の後半で詳しく掘り下げていきます。 まずは、Over Protocolの具体的なプロジェクト内容に迫ります。 Over Protocolってどんなプロジェクト? ブロックチェーン開発は、絶えず盛んに行われていますが、Over Protocolの際立った特徴として、「誰でも自由に」ということが挙げられます。 こうした開発理念は、「ホームステーキング」という形で実現され、ユーザーが自宅のPCでバリデーターとなり報酬を稼ぐことを可能にします。 ここでは、Over Protocolが解決しようとする課題から、そのソリューション、ホームステーキングまでを解説します。 Over Protocolのビジョン「誰もが自由に利用できるレイヤー1ブロックチェーン」 Over Protocolは、「Ethanos」と名付けられたプロトコルに基づく新しいレイヤー1のブロックチェーンです。これは、Ethereumを含む多くのブロックチェーンが直面するストレージと依存性の問題を解決することを目的としています。 Over Protocolのビジョンは、ユーザーが誰にも依存することなく、簡単にデータにアクセスし、ネットワークに貢献し、ブロックチェーンを活用できるようにすることです。 また、主な特徴として、軽量でユーザーフレンドリーなフルノードの提供や、個人が自宅のPCでも操作出来るような高いアクセシビリティが挙げられます。 Over Protocolが解決しようとする三つの課題 Over Protocolは、PoSブロックチェーンにおける以下の三つの課題に対処しようとしています。 ノード参加への高いリソース要件 参加者制限 技術的な複雑さ では、Over Protocolは具体的にどのようにしてこれらの問題を解決しようとしているのでしょうか? それぞれのソリューションを解説します。 ソリューション①:「Ethanos」テクノロジーを活用し、誰でも操作できるコンパクトなブロックチェーン・ノードを実現 ブロックチェーン・ノードを動かすには、高性能なマシンと専門的な知識を必要とします。故に、一般ユーザーが自宅で専門的な知識もなくノードを運用することは極めて難しくなっています。 こうした課題を解決するために開発されたのが、「Ethanos」テクノロジーです。 Ethanosは、ブロックチェーンデータのバックボーンである「ステートトライ」(state trie)をより軽量化します。これにより、デバイス上のストレージが削減され、他のノードとの同期時間が短縮されます。そして、トランザクション速度が向上し、他のブロックチェーンとの互換性が高まります。 ステートは新しいトランザクションを検証するために必要なスナップショットです。ブロックチェーンのステートは、「マークル・パトリシア・トライ」(Merkle Patricia Trie)と呼ばれるツリーデータ構造に保存されるのですが、ブロックチェーンがユーザー活動やトランザクションで活発になると、ステートのサイズは大きくなります。これによって、データ保存の容量が非常に大きくなってしまいます。 ノードのサイズが大きくなり、同期の負荷が高まるにつれて、ノードの稼働にはコストがかかります。これをどのように軽量するのかが問題でした。 Ethanosは、非アクティブなアカウントを効率的に削除することでこれらの問題に対処します。 この世に存在するアカウントのその全てが、稼働している訳ではありません。例えば、イーサリアムの場合、アカウントの95%が少なくとも1ヶ月の間非アクティブとなっており、基本的には休眠状態となっています。Over Protocolはこうしたアクティブアカウントと非アクティブアカウントをEthanosを使用して区別することで、システムに負担をかけない運用を可能にします。 前のエポックのステートトライを保持し、新しいトランザクションに特定のアカウントが関係する場合、Ethanos はまずこの「古い」トライでそのアカウントを見つけようとします。 アカウントが存在する場合、その情報は現在のエポックの「新しい」トライに移動されます。 休眠状態のアカウントの場合は、アカウントをアクティブに戻すための復元プロセスが必要となります。復元されることで、現在のエポックに乗ることができます。 アカウントが 3 エポック以上非アクティブな状態が続くと、アカウントは休眠状態に入ります。 このメカニズムにより、ステートのサイズが際限なく拡大することはなくなり、エポックの長さによって制限されるようになります。 このほかにも、Ethanosはフルノードの軽量化を行えます。 ほとんどのブロックチェーンでは、フルノードをセットアップするためには、1 ~ 2 TB、またはそれ以上のストレージを備えたSSDを必要とします。こうした要件は、現在のブロックチェーンとステートの膨大さだけでなく、継続的なデータの増加に対する予測からきたものです。 しかしながら、Ethanosでは、自宅のPC上で完全なノードを構築できるようにし、一般の家庭でもあるような128 GB ~ 256 GB のストレージを備えたSSDでのフルノードを可能にします。 より詳細なノード要件について 現在、Over Protocolでは、クローズド・ベータ・テストネットを行おうとしています。 そちらで参加のためのノード要件が公開されていますので、参考のために記載させて頂きます。 ※Linaxへのサポートはまだであり、近日中にアップデートが行われるとのことです。 ・必要要件 OS:Mac OS X 10.14以上、Windows 10 64ビット以上 CPU:2コア以上 メモリ:4GB RAM ストレージ:SSD 128GB ネットワーク:8MBit/secダウンロードインターネットサービス ・推奨要件 OS:Mac OS X 10.14以上、Windows 10 64ビット以上 CPU:4コア以上 @ 2.8+ GHz メモリ:16GB以上のRAM ストレージ:SSD 256GB ネットワーク:20 MBit/sec Application Form:https://go.over.network/apply_cbt ソリューション②:PoSを採用。誰もが「ホームステーキング」を出来るように試みる ブロックチェーンを運営するにあたって、ノードは非常に重要です。 多くの既存ブロックチェーンは、高速化のためにコンセンサスへの参加を数十から数百のノードに制限しています。高性能なノードを必要としているものの、イーサリアムでさえ物理的なノードの数は約1万と推定されています。 Over Preotocolが取り組むのは、バリデーターの数の増加です。 Over Protocolは、オープンポリシーと検証可能性を重要視しています。それを実現するために、PoW(Proof of Work)ではなく、リソースを大量に消費しない、PoS(Proof of Stake)のアプローチを選択しています。 仕組みとして、ネットワーク参加者は一定量の$OVERを保有し、それを担保としてブロックを生成・検証します。ブロックの生成と検証に成功した場合、ブロックごとに発行される$OVERと、作成したブロックからの取引手数料が報酬として支払われます。 また、Ethereumを参考として、Over ProtocolはGasperを採用しています。 現状、新興のブロックチェーンはDPoS(Delegated Proof of Stake)方式を採用することが多くなっています。これは一握りのバリデーターが選ばれる仕組みであり、欠点としてバリデーターが高い性能基準を維持しなければ、ネットワークの性能に大きな問題を引き起こす可能性があります。 バリデーターにはノード環境の維持が求められます。そのため、一般人がこれらのブロックチェーンのコンセンサスに直接参加するためには、非常に多くのコストがかかります。 一方で、イーサリアムのGasperは、より多くのバリデーターを歓迎し、高度なノード運用環境を有していない人にも対応しています。Over Protocolは、Gasperを若干修正したバージョンを統合することで、一般の人でもブロックチェーンに参加しやすくします。 参入しやすいPoSの仕組みと、先に述べたようなコンパクトなノードを通じて、ホームステーキングを実現します。 ソリューション③:「フロントエンド・エンベディング」を採用することで、リスクとコストを軽減 Over Protocolの安全性は、ブロックチェーン上のフロントエンドデータの管理手法によって実現されます。 これは、「フロントエンド・エンベディング」(Frontend Embedding)と呼ばれる手法であり、サービスホスティングの主体を統合するものです。 フロントエンド・エンベディングによって、サービスの安定性はブロックチェーンネットワークのみによって決定されるため、関連するリスクが軽減されます。 フロントエンドに関する問題は様々あります。例えば、フロントエンドで問題が発生した場合、ブロックチェーンネットワークが完全に稼働していても、データダウンロードが妨げられることがあります。また、フロントエンドサービスを維持するためのコストが継続的に発生します。 ノードの運用コストも無視は出来ない要素です。ノードにはかなりのストレージ容量が必要であり、イーサリアムなどのプラットフォームでは 1 TB を超える場合もあります。 このようなストレージ要件は平均的なユーザーにとって大きな負担となる可能性があり、参加コストが高くなります。 しかしながら、フロントエンド・エンベディングによってこれらの問題を解決することが可能です。 Webアプリケーションデータをブロックチェーン上に直接保存し、事前定義されたルールに従って管理することで、ブロックチェーンインフラがフロントエンドデータを管理するサーバーとなります。これにより、サービスを独立して運用することができ、同じエンティティによってホストされる構造のためサービスの安定性がブロックチェーンの状態のみに影響されるようになります。 ブロックチェーンエコシステム内の各ノードがホスティングサーバーとなり、サービスホスティングへの分散型アプローチが可能になります。これにより、サービスの安定性が向上する仕組みとなっています。 ホームステーキング:誰でも自宅のPCでバリデーターになることが可能に イーサリアムがPoSを採用し、ステーキングをすることで報酬を得られる仕組みは非常によく知られています。 それに伴った流動性ステーキングプロトコルも発達しており、Lidoはその最大手です。ステーキングの知識がない人でも、ETHをLidoに預けることで流動性ステーキングを行うことができます。 そして、Over Protocolでは、そうしたPoSステーキングを自宅のPCで行うことが出来るようになっており、手軽にステーキング報酬を稼ぐことが可能となります。 「自宅のPCがATMになる」と考えてみると分かりやすいかもしれません。 Superblock(Over Protocolの開発元)の創設者であるBen Kim氏は、「誰でもバリデーターを運営できるようになることで、個人がホームステーキングと呼ばれるプロセスを通じて受動的な収入を得る可能性がある」と述べています。 こうしたホームステーキングは、Over Protocolエコシステムの中核をなしており、ユーザーがOver Protocolに積極的に参加するようにするための、強力なインセンティブとなっています。 今後のロードマップ Over Protocolによれば、今後のロードマップは以下のようなものとのことです。 11月:テストネットを公開。 これは、インセンティブ付きのパブリック・テストネットではなく、クローズド・ベータという形で行われる予定とのことです。 12月:よりオープンなパブリックテストネットを公開。 これにより、多くの人々がパーミッションレスに参加することが可能になります。 また、現時点では未確定ですが、2024年Q1にメインネットが公開される予定とのことです。 Over Protocolのプロダクト「Over Wallet」:エアドロ活動の中心 現時点で、一般ユーザーが触ることの出来るOver Protocolのプロダクトは「Over Wallet」です。 Over Walletにはまだ主要な機能は搭載されていませんが、これから紹介するエアドロ活動の場となっています。そのため、エアドロ活動をするためには、アプリのダウンロードが必須となります。 現状、Over Walletは、エアドロ活動の場としての機能しかありませんが、将来的にトークン資産管理や取引機能がアップデートにより追加される予定です。 エアドロキャンペーン「Over Community Access Program」を実施中 Over Protocolは独自トークン$OVERを、アーリーユーザーに対して配布することを公言しており、それにちなんだキャンペーンを実施しています。 ユーザーは誰でもメインネットのローンチに先立って、さまざまなタスクをこなすことで、$OVERを入手するためのポイントを手に入れることができます。 このキャンペーンに参加する方法は非常に簡単です。 手持ちのスマートフォンで、Over Walletアプリをダウンロードし、毎日もらえるポイントや、デイリークイズに回答することでポイントを得ることが可能です。 Over Wallet for Android — https://go.over.network/playstore Over Wallet for Apple — https://go.over.network/appstore 以下、Overポイントを入手するためのタスクを紹介していきます。 毎日のログインポイント Over Walletでは、毎日アプリを起動してデイリーのOverポイントを入手することが可能です。 貰えるポイントは一定ではなく、日によって上下しますが、アプリを起動しタップするだけでエアドロ活動を行える手軽さは、魅力的です。 デイリークイズに答えることでポイントが加算 Over Walletでは、ポイントを稼ぐ一環として毎日一問出されるクイズに答えることで、100ポイントもしくは10ポイントを入手できるミッションを行なっています。 連続して七日間答えることで、追加で300ポイントを貰うことが可能です。(誤答しても、ポイントをもらうことが出来ます) クイズの内容は、クリプト分野やOver Protocolに関係するワードを問うものですが、クリプト初心者の方にとって、クリプト世界の用語は馴染みがないものですし、問題文が英語ということもありハードルは一見すると高いものと思わるかもしれません。 [caption id="attachment_98960" align="aligncenter" width="593"] https://x.com/jin_overweb3/status/1711699567849382043?s=20[/caption] しかしながら、Xの方ではその時々のクイズの答え及びそれをより詳しく解説したものが公式によってリポストされていますので、Over Protocol公式(英語版)Xをフォローし、知識を増やしながらポイントを稼ぐことが可能です。 Over Protocol X(英語版):https://twitter.com/overprotocol 勉強をしながら、ポイントを効率的に稼ぐことができるというのは、非常に魅力的ではないでしょうか。 10月5日のYoutubeライブでは多くの視聴者を集める [caption id="attachment_98963" align="aligncenter" width="800"] https://youtu.be/OPhjotPVScQ?si=4GRz28YatwaOEUuu[/caption] Over Protocolのエアドロ活動のミッションの一環として、Youtubeの公式配信「The 1st Online Meet Up!」で発表されるキーワードを入力することで、2000ポイントをもらえるキャンペーンがありました。 2.7万人を超える視聴者が殺到し、活気に満ちた配信となりました。 キーワード入力は5分間の間となっていましたが、発表された直後にはアプリの起動やログインが過多となり、入力がしにくい事態が発生しました。そこで、入力できなかったユーザー向けに、Googleフォームからの入力でのポイント付与という救済措置が取られました。 結論 ここまでOver Protocolの紹介をしてきましたがいかがでしょうか? 現在、Over Protocolはエアドロ活動の場として多くのユーザーを集めていますが、エアドロキャンペーンだけでなく、プロジェクト内容やプロダクトも興味深いものとなっています。 Over Protocolは、バリデーターとなるハードルの高さを非常に画期的な方法で解決しようとしています。また、ユーザーの側からしても、気軽にバリデーターとなり報酬を受け取り、自宅のPCをATMのようにできるというのも非常に魅力的です。 もしOver Protocolに興味が湧いた方がいれば、エアドロ活動も兼ねて、まずはOver Walletのダウンロードから始めてみてはいかがでしょうか? Over Protocol各種Infomartion X(日本語版):https://twitter.com/overprotocol_JP Discord:https://discord.com/invite/overprotocol Youtube:https://www.youtube.com/@overprotocol Telegram(日本語版):https://t.me/OverProtocol_Chat_JP HP: https://www.over.network/ WP: https://drive.google.com/file/d/1DNK0FFOVhnVDRnz8h9RJ1NoDUN4W0He8/view Sponsored Article by Over Protocol ※本記事はOver Protocolよりいただいた情報をもとに作成した有料記事となります。プロジェクト/サービスのご利用、お問い合わせは直接ご提供元にご連絡ください。

プロジェクト
2023/10/10【年利60%】”期間限定”の$FNCT運用キャンペーンがOKCoinJapanで実施|登録締切は10月18日まで!
国内仮想通貨取引所OKCoinJapanで、$FNCT(フィナンシェトークン)の運用を年利60%で行えるキャンペーンが10月11日(水)より受付開始されます。 / 🎉OKJ×FNCTコラボキャンペーン第4️⃣弾!🎉 \ 【預けて増やす!Flash Deal】 FNCTを60日預けると、年率60%報酬がもらえる! ⏰受付期間 10/11 16:00 〜 10/18 16:00 詳細はこちら👇https://t.co/u8Rrx4Ee6U ご参加お待ちしております✨#OKCoinJapan #フィナンシェ #FinancieToken pic.twitter.com/OP9GVH30f3 — OKCoinJapan(オーケーコイン・ジャパン) (@OKCoinJapan) October 5, 2023 大手海外取引所OKXでの仮想通貨運用で年利が1%~18%となるなか、今回のOKCoinJapanキャンペーンでは左記の数字を大きく上回る年利60%での$FNCTの運用が可能となります。 OKCoinJapanでは運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードを持っているユーザーであれば最短5分で口座開設の手続きが行える"eKYC"も採用されているため、今回のキャンペーンに合わせてOKCoinJapanを使いたい方でもスムーズな口座開設が可能です。 ||口座を開設してキャンペーンに参加する|| 【年利60%】$FNCTキャンペーンが実施! 今回、OKCoinJapanが実施するキャンペーンでは、$FNCT(フィナンシェトークン)を一定期間預けることで、元々預けていた$FNCTとは別に報酬分の$FNCTが獲得できます。 $FNCTとは、国内発プロジェクトFiNANCiE(フィナンシェ)で活用されるトークンで、OKCoinJapanの取引所(板取引)でも売買が可能です。 今回のキャンペーンでは、同取引所が提供する運用サービス「Flash Deals」にて、ユーザーは$FNCTを60日間ロック。ロックした総量に対して年利60%の割合で$FNCTの枚数が60日間の期間限定で増やすことができます。(報酬はキャンペーンの実施期間終了後、自動で入出金口座に付与) 【報酬の例】 1,000,000 FNCTを申請した場合に得られる報酬 →1,000,000 FNCT× 60% ÷ 365 × 60 = 98,630.14 FNCT 注意点 今回のキャンペーンでは最小/最大申請数量が設定されており、記事執筆時換算(1 $FNCT = 0.358 円)で、最小1,790円、最大で35万8000円の申し込みが可能となっています。 キャンペーン情報まとめ 対象通貨:$FNCT(フィナンシェトークン) 受付期間:2023年10月11日(水)〜2023年10月18日(水) キャンペーン実施期間:60日間 最小申請数量:5,000 $FNCT 最大申請数量:1,000,000 $FNCT 今回のキャンペーンでは全ユーザーからの受付上限も設定されており、上限に到達した段階でキャンペーンの受付は終了となるのでその点も注意しましょう。さらに、 一度申請すると、60日間は$FNCTの引き出しが行えない キャンペーンは予告なく変更、終了、期間の延長する場合がある 報酬の付与時点で口座を解約していると、付与は対象外になる などの注意事項もあるので、あらかじめキャンペーンの実施期間や最小/最大申請数量についてなど、各注意事項を頭に入れた上でキャンペーンに参加しましょう。 ||口座を開設してキャンペーンに参加する|| キャンペーンの参加方法 事前準備 ・OKCoinJapanの口座 ・$FNCT(or $FNCTを購入するための資金) 本キャンペーンに参加するにあたり、OKCoinJapanの口座と$FNCTが必要となります。 OKCoinJapanでは、運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードのいずれかを持っているユーザーに対して最短5分で口座開設の手続きが可能なeKYC(本人確認)システムが採用されています。 今回のキャンペーンの受付期間は2023年10月18日(水)迄となっているため、現時点で口座を持っていない方でキャンペーンに参加したい場合は早急に口座開設を申し込みましょう。 OKCoinJapanの口座を開設する $FNCTは、OKCoinJapanにて、板取引で円(JPY)建てで取引が可能。 「キャンペーンに参加したいけど$FNCTを持っていない」 「$FNCTを少し持っているけど、数を増やしてからキャンペーンに参加したい」 といった方は、OKCoinJapanで$FNCTを購入してからキャンペーンに参加すると、外部の取引所との入出金など面倒な手間を省くことができます。 キャンペーンへの参加方法 OKCoinJapanのブラウザページでログイン後、Flash Dealsページからキャンペーン参加の申請が行えます。 また、OKCoinJapanアプリを利用の場合、同様にログイン後、「ホーム」→「収益」にアクセスし、「Flash Deals」のメニューから申請することでキャンペーンに参加できます。 ||キャンペーンに参加する|| $FNCTトークンとは? 今回OKCoinJapanのキャンペーンで取り扱い対象となる$FNCTトークンは、ブロックチェーン技術を活用したトークン発行型クラウドファンディングプラットフォーム「FiNANCiE(フィナンシェ)」内で主に使われるトークンです。 $FNCTの使用用途は主に下記の4つです。 CT(コミュニティトークン)の購入:コミュニティが発行するCT(仮想通貨ではない)の購入に必要なFiNANCiEポイントが購入でき、通常より多くのCTの購入が可能 グレード特典:保有数が多いほどグレードに応じた優遇が受けられる ガバナンス:FNCTに関する投票活動に参加可能 コミュニティへの寄付:特定コミュニティに寄付が可能 フィナンシェのプラットフォームでは、CT(コミュニティトークン)と呼ばれるトークンが資金調達を行いたいプロジェクト毎に発行されており、現在Jリーグのサッカークラブやエンタメプロジェクトチームなど複数のプロジェクト/個人がCTを発行しています。 [caption id="attachment_98926" align="aligncenter" width="408"] フィナンシェの実際の画面|画像引用元:フィナンシェ[/caption] 二次売買が可能なCTですが、初期販売時に限り$FNCTを介したCTの購入が可能。その場合、通常よりもより多くのCTを獲得できる仕組みとなっています。 このように、$FNCTは、フィナンシェの肝となるCTの価値を長期的に向上させるためのプラットフォームトークンとしての役割を果たします。 $FNCTの分布 $FNCTは今年3月に国内取引所によって1 FNCT = 0.41円でIEOが行われました。 トークンの配布分布は下記の通りとなっており、コミュニティの保有率が最も多い設計となっています。 フィナンシェトークン(FNCT)の保有者分布 保有者カテゴリ 説明 保有率 枚数 投資家 IEO参加者に配布されるFNCT 13% 26億FNCT チーム チームメンバーおよび株主へのインセンティブ 25% 50億FNCT コミュニティ FNCTのエコシステムを維持・拡大の活動費 42% 84億FNCT パートナー FiNANCiEと連携する組織や個人に割り当てられるFNCT (スポーツチーム、リーグ、芸能事務所、音楽レーベル、 出版社、取引所、金融企業など) 20% 40億FNCT 今回のキャンペーンでは、60日間のロック期間中は、$FNCTを引き出すことはできません。 トークンのユーティリティや、上記の分布などを見た上でキャンペーンに参加してみましょう。 キャンペーンの受付は2023年10月18日(水)まで! 年利60%のキャンペーンに参加する – OKCoinJapan 公式リンク – ・ウェブサイト:https://www.okcoin.jp/ ・Twitter :https://twitter.com/OKCoinJapan ・Facebook:https://www.facebook.com/OKCoinJapan ・Youtube:https://www.youtube.com/@okcoinjapan Sponsored Article by OKCoinJapan ※本記事はオーケーコイン・ジャパン株式会社さまよりいただいた情報をもとに作成した有料記事となります。プロジェクト/サービスのご利用、お問い合わせは直接ご提供元にご連絡ください。

プロジェクト
2023/10/07Braveブラウザは稼げる次世代高速ブラウザ!特徴・使い方を徹底解説【2023年最新版】
Braveブラウザは、精密な広告ブロック・プライバシー保護機能と、承認された広告を閲覧するだけでトークンを稼げる仕組みを搭載したウェブブラウザです。 一般にウェブブラウザというと、Google ChromeやEDGE(Internet Explorer)、SafariやFirefoxを想像する方が多いと思いますが、BraveはWeb3.0世代のウェブブラウザとして注目を集めています。 また、広告閲覧で獲得できるBasic Attention Token(BAT)も、時価総額は100位ほどを維持しています。BATの詳細に関しては以下を参考にしてみてください。 CRYPTO TIMESではBraveに関してのニュース記事も随時配信していますのでこちらも合わせてチェックしてみてください。 BAT (Basic Attention Token) の特徴・将来性を解説!取引所・チャートまとめ - CRYPTO TIMES 今回はそんな大注目の次世代高速ブラウザ「Brave」の特徴や使い方などを徹底解説していきます! Braveのダウンロードはこちら 次世代ブラウザ「Brave」とは?11個の特徴を紹介! Braveとは、広告ブロック機能やプライバシー保護機能など搭載した次世代ブラウザです。仮想通貨トークンと連携し、新しい広告運用・システムを実現することを目指しています。 まずは、そんなBraveの特徴や便利機能について確認しておきましょう! Braveの特徴 WEBサイトやYoutube広告をブロックできる「Brave Shields(ブレイブ・シールド)」 広告閲覧でBATトークンを稼げる「Brave Rewards(ブレイブ・リワーズ)」 Brave独自の広告システム「Brave Ads(ブレイブ・アド)」 牢固なセキュリティで安全性・プライバシー保護もバッチリ WEBサイトの表示を高速化!ChromeやSafariよりサクサク使える WEBサイトやSNSで投げ銭機能を使える Chromeの拡張機能を使える ブラウザ乗り換えが簡単!ChromeやSafariからブックマークを移行できる Windows/Mac/Linux/iOS/Androidに対応済み!いろいろな端末から使える Brave Sync(ブレイブ・シンク)で複数端末を同期できる セキュリティを強化する「Firewall+VPN」 1. WEBサイトやYoutube広告をブロックできる「Brave Shields(ブレイブ・シールド)」 Braveのメイン機能の1つが、WEBサイトや動画に表示される広告をブロックする機能「Brave Shields」です。 この機能をONにすれば、サイトや動画で表示される不快な広告は一切表示されなくなります。 当記事の後半では広告ブロック機能について検証してみた結果を公開しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。 広告ブロックの検証結果はこちら 2. 広告閲覧でBATトークンを稼げる「Brave Rewards(ブレイブ・リワーズ)」 プライベート広告の表示設定をONにしてBraveブラウザを使用すると、広告閲覧に応じてBraveのトークンである「Basic Attention Token (BAT) 」が付与されるという、「Brave Rewards」という仕組みがあります。 2023年2月よりBrave RewardsによるBATの獲得にはbitFlyer(日本国内’の場合)の口座接続が必要となりました。 獲得したBATはbitFlyerで日本円に換金することも可能ですので、「Braveは利用しているだけで稼げるブラウザ」ともいえますね。 bitFlyerの口座開設や接続方法については、当記事の後半で詳しく解説しています。 bitFlyerの口座開設と接続についてはこちら BAT (Basic Attention Token) の特徴・将来性を解説!取引所・チャートまとめ 3. Brave独自の広告システム「Brave Ads(ブレイブ・アド)」 Braveには、独自の広告システム「Brave Ads」が実装されています。 Brave Adsについて簡単に説明すると、Brave上で「閲覧サイトとは関係なく表示される広告」のようなものです。 Braveに登録されている広告が、一定の間隔(1時間に1回など)で表示されるようになり、広告を見ることでBATを稼ぐことが可能になります。 Brave Adsの表示設定はBraveで設定できるので、 広告なしで使いたい人は表示設定をOFFに BATを稼ぎたい人は表示設定をON・表示頻度を増やす このように、それぞれの好みに合わせて使えます。 トークンを稼ぎたい人、広告なしで快適に使いたい人、どちらも快適に使えるのは嬉しいですね。 4. 牢固なセキュリティで安全性・プライバシー保護もバッチリ Braveはセキュリティ対策やプライバシー保護の観点でも優秀なブラウザです。 搭載している広告ブロック機能とともに、マルウェアなどの有害プログラムをブロックする機能も搭載しています。 また、プライバシー保護の機能も充実しており、閲覧履歴を残さないプライベートブラウジングももちろん利用可能です。 5. WEBサイトの表示を高速化!ChromeやSafariよりサクサク使える BraveはChromeやSafariよりも高速でサイト表示できるブラウザです。 広告をブロックして読み込み時間を削減することで、高速表示を実現しています。 実際にどれくらい高速化できるのか、ChromeとSafariと比較して検証した動画があるので、この後に紹介する「徹底検証!Braveの広告ブロックや高速ブラウジング機能を試してみた」も参考にしてみてくださいね。 Braveのダウンロードはこちら 6. WEBサイトやSNSで投げ銭機能を使える Braveの大きな特徴の1つが、投げ銭機能を使えることです。 気に入ったWEBサイト TwitterなどのSNSの特定ユーザー Braveでは上記のように、サイトやユーザーにブラウザ上で投げ銭(チップ)を付与できます。TwitterもBraveで開くとチップという項目が追加されているのがわかります。 Braveはこの投げ銭機能によって、良いコンテンツの生成を促し、新しい広告の仕組み作りを目指しています。 投げ銭のやり方はこちら 7. Chromeの拡張機能を使える 「Google Chromeの拡張機能が便利だからChromeから乗り換えるのはちょっと…」と、Chromeから乗り換える気になれない方も多いかもしれません。 でも、BraveではChromeの拡張機能のインストールに対応しているので、そんな心配はありません。 BraveブラウザでChromeウェブストアにアクセスして、拡張機能をインストールできます。 Chromeで使えていた便利機能を、Braveでそのまま使えるのは嬉しいですね。 どんな拡張機能でも使えるの? 基本的にどんな拡張機能でも使えます。導入前に警告が出ることもありますが、気にせず導入して大丈夫です。 8. ブラウザ乗り換えが簡単!ChromeやSafariからブックマークを移行できる いまメインで使っているブラウザのブックマーク(お気に入り機能)は、自分でカスタマイズして使いやすいようにしてありますよね。 ブラウザを変えたとして、そのブックマークを再度登録し直すのはとても面倒なことです。 でもBraveなら、ブックマークのインポート機能があるので、ブラウザ移行の手間はかかりません。 いつも使っているChromeやSafariのブックマークを、ワンクリックで簡単にインポートして快適に使ええます。 9. Windows/Mac/Linux/iOS/Androidに対応済み!いろいろな端末から使える Windows Mac Linux iOS Android BraveはWindowsやMac、Linuxはもちろん、iOSやAndroidなどのスマホ/タブレットのOSにも対応しています。 どの端末にも完全対応しているので、使用端末によって機能制限がでてしまうこともありません。 端末のOSを気にすることなく、誰でも使えるので安心ですね。 10. Brave Sync(ブレイブ・シンク)で複数端末を同期できる Braveブラウザは複数端末で設定や閲覧履歴などを同期可能です。この機能をBrave Syncといいます。 Brave Syncを使えば、例えば「スマホで開いていたページをタブレットで見たい」ということなことも簡単にできます。 複数端末でBraveブラウザを使う場合は、ぜひBrave Syncで同期をしておいてくださいね。 11.セキュリティを強化する「FireWall + VPN」 プライバシーを尊重するBraveブラウザが2020年7月27日より、VPNとFirewallのサービスプロバイダーGuardianと提携し、Guardianを搭載したiOSユーザー向けのプレミアム機能「Brave Firewall + VPN」をリリースしました。 「Brave Firewall + VPN」を利用することで、プライベートかつ安全な環境で3倍〜6倍ほど高速なブラウジング体験をユーザーに提供できます。 巷には、沢山のVPNアプリが存在していますが、Braveを利用しているユーザーであれば他のアプリを落とさずともVPNの利用が可能になります。「Brave Firewall + VPN」は月額9.99ドル、年間99.99で利用することが可能です。 Braveブラウザがプライバシー・安全性を強化する「Firewall+VPN」をiOSユーザー向けにローンチ Braveのダウンロードはこちら 徹底検証!Braveの広告ブロックや高速ブラウジング機能を試してみた Brave(ブレイブ)は広告をブロックできたり、サイトを高速で表示できるブラウザということがわかったと思います。 とはいえ、実際にどれくらいの効果があるのか気になりますよね。 そこで、ここでは実際にBraveと別のブラウザを比較した結果を公開しています。実際にBraveがどれくらい優れているのかをチェックしてみてください。 Braveの機能を検証 【検証1】WEBサイト閲覧速度を比較してみた 【検証2】WEBサイトの広告表示を比較してみた 【検証3】Youtube広告をブロックしてみた 【検証4】Youtubeのバックグラウンド再生をできるか確かめてみた 【検証1】WEBサイト閲覧速度を比較してみた この動画はBrave、Google Chrome、Mozilla Firefoxの3つのブラウザで同じ主要ニュースサイトを開いたときの速度を比較したテスト動画です。 これらのブラウザを比較した結果、Braveではその他のブラウザよりも3倍近く早く表示されています。 さらに、公式ホームページでの説明によると、Androidタブレット上ではChromeブラウザの最大8倍もの速度を記録したとされています。 そしてこの高速ブラウジングに加え、広告やトラッカーをブロックすることでマルウェアなどへの感染リスクも下げることができ、より速く安全なブラウジング体験ができるのです。 Braveで新しいタブを開くと、上の画像のようにこれまでにブロックした広告やトラッキングの数、節約した読み込み時間などを表示してくれます。 【検証2】WEBサイトの広告表示を比較してみた ここからは、実際にBraveとChromeで同じサイトを検索した際の広告表示を比較します。 今回使用したのは、デフォルトの広告ブロク機能設定のままのBraveと、広告ブロックの拡張機能を追加していないChromeです。つまり、何もいじってないごく普通のBraveとChromeで比較します。 「価格.com」を閲覧した結果が、上の画像です。Braveで開いた場合は広告がブロックされていることがわかります。 Chromeでは赤枠で示した箇所にバナー広告が表示されているのですが、Braveではデフォルトでこのバナー広告をブロックできています! その他様々なウェブサイトを閲覧してみましたが、Braveではばっちり広告をブロックしてくれます。 Braveのダウンロードはこちら 【検証3】Youtube広告をブロックしてみた 最後に、Youtube内で表示される動画広告もブロックできるかを検証してみました。 Braveの効果をきっちり確かめるため、今回はユーチューブにあがっている「世界一広告の多い動画」という動画を使って検証してみました。 その結果が上の画像です。 再生バーを見ると一目瞭然!動画の途中に挿入されているおびただしい数の黄色の広告動画を、Braveではすべてブロックできてしまっています! 念の為この一時間に及ぶ動画は最後まで閲覧してみましたが、「世界一広告の多い動画」というタイトルとは打って変わって、広告ゼロで非常に快適に見終えてしまいました(笑) その後もいろいろな動画を見比べましたが、動画途中の広告はもちろん、再生開始直後に入りがちな動画広告が入ることもありませんでした! 毎日のようにユーチューブを視聴するヘビーユーザーの方にはかなりの朗報ではないでしょうか。 【検証4】Youtubeのバックグラウンド再生ができるか確かめてみた Brave Youtube Premium バックグラウンド再生 広告ブロック 月額料金 無料 1,180円 スマホ端末からバックグラウンドでYoutubeを開き、音楽や音声を聴きたいという人もいるかもしれません。 Youtube Premiumでは月額料金を支払うことでバックグラウンド再生が可能になりますが、Braveではなんと無料でYoutubeのバックグラウンド再生ができます。 そしてもちろんYoutube Premiumと同じく広告ブロックもしてくれます。 ただし、バックグラウンド再生機能を使用するには以下の手順で設定を変更する必要があります。 Braveアプリの右下の3つの点のアイコン(・・・)をタップ 表示されたメニューを下にスクロールして「設定」をタップ 設定メニューを下にスクロールして「メディア」をタップ 「音声のバックグラウンド再生を有効にする」をオンにする Braveのダウンロードはこちら Brave(ブレイブ)の初期設定方法!3つの手順を解説! ここからはBraveの初期設定手順について確認していきましょう。 きちんと設定できるか不安な方でも、この手順通りに進めていけば、すぐに快適にBraveを使い始められますよ! Braveの初期設定手順 Braveブラウザをダウンロード・インストールする 日本語設定を適用する ブックマークをインポートする 1. Braveブラウザをダウンロード・インストールする まず、Braveのホームページにアクセスして、トップページのダウンロードボタンをクリックしてBraveをダウンロードします。 ダウンロードが完了した後、インストールを実行し、Braveを起動します。 2. 日本語設定を適用する Braveの初回起動時は英語のままなので、まず最初に日本語設定に変更しましょう。 初回起動時に表示される Welcome to Brave というタブに表示されている左のボタンから設定画面に移ります。 もしこのボタンがない場合は、右上のメニューアイコンから 設定 を選択することもできます。 設定画面を開いたら、左側のメニューからAdditional settingsと書かれたプルダウンをクリックし、Languagesをクリックします。 表示されるメニューの一番上に Language という項目があるので、プルダウンメニューを用いて English (U.S.) から Japanese (Japan) に変更しましょう。 言語設定が変更すると、ブラウザを再起動するか聞かれるので、再起動しましょう。再起動が完了すれば日本語になっているはずです! 3. ブックマークをインポートする 次はブックマークをインポートしていきましょう。 設定画面の上部メニューバーからSettings、さらに項目欄からGet startedに飛び、Import bookmarks and settingsをクリックします。 表示されるボックスからインポート元のブラウザを設定しImportをクリックすると、ブックマークがインポートされます。 これでブックマークのインポートが完了です! Braveのダウンロードはこちら Brave(ブレイブ)の基本的な使い方を解説!基本操作をマスターしよう Braveの初期設定ができたら、Braveの基本的な使い方にうつりましょう。 ここでは、Braveの基本的な使い方について解説しています。 広告の表示・非表示の切り替え方や投げ銭の仕方について確認しておきましょう! Braveの使い方 広告表示・非表示を切り替える ネットサーフィンをしてBATを稼ぐ WEBサイトやSNSユーザーに投げ銭する Braveウォレットのバックアップをとる 広告表示・非表示を切り替える BATの受け取りや投げ銭、広告閲覧機能の有効化にはBrave Rewardsの設定に加え、bitFlyerの口座開設と接続が必要です。 1.設定を開き、画面上部の「Brave Rewards」タブを選択し、「Rewardsの使用開始」をクリックします。 2.右上のBATアイコンからポップアップが表示されので、住んでいる国を選択し、「続ける」をクリックします。これでBrave Rewardsの利用が開始されます。 3.Brave Rewardsのホーム画面では広告の表示設定の編集が可能です。各広告のオン/オフの切り替えや、表示頻度の選択をしましょう。広告を閲覧してBATを受け取りたい場合はオンにしておきましょう。 4.最後に、BATトークンを受け取るためにはbitFlyerの口座開設と接続が必要です。「アカウントの接続」をクリックするとbitFlyerのログイン画面へ誘導されるので、すでに口座開設が済んでいる場合はログインして接続してください。まだ済んでいない場合は口座開設から始めましょう。 bitFlyerの口座開設の手順や使い方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。 【最新版】取引所bitFlyer(ビットフライヤー)の登録方法・使い方まとめ! ネットサーフィンをしてBATを稼ぐ! Braveが承認した広告を閲覧することで「広告を閲覧した報酬」としてユーザーにトークンが付与されるため、ネットサーフィンをするだけでトークンを稼ぐことができます。 付与されるトークンはBasic Attention Token (BAT) というトークンで、この仕組みはBraveが創ろうとしている分散型広告システムにより成り立っています。 分散型広告システム Braveの分散型広告システムでは、従来の中央集権的な仕組みでのGoogleなどの仲介者を排除し、Basic Attention Token (BAT) というトークンを利用することでユーザー、サイト運営者、広告代理業者の三者だけでの自律分散型の仕組み作り上げます。 仲介者を排除したこの仕組みでは、トークンを流通させることで従来の仕組みにおいて上述の三者が抱える課題を解決するとされており、次世代の広告システムとしてBraveとともに注目されています。 詳しくはこちらの記事で解説しています↓ BAT (Basic Attention Token) の特徴・将来性を解説!取引所・チャートまとめ - CRYPTO TIMES 下記の記事では、CRYPTO TIMESのライターが実際に広告閲覧でBATを獲得してみた記事になるので、参考にしてみてください。 Brave Browserが広告閲覧でBATを獲得できるプラットフォームをリリース、一足先に使ってみた感想は? - CRYPTO TIMES 気に入ったコンテンツやWEBサイトやSNSユーザーに投げ銭する Braveでは、以上の動画のような手順でWEBサイトやSNSで投げ銭ができます。 基本的にはブラウザ上やサイト内に表示されているBATのマークをクリックすればOKです。 手軽に投げ銭できるので、良いコンテンツには積極的に投げ銭をしてみてくださいね。 もちろんクリプトタイムズにも投げ銭できますよ! Braveウォレットのバックアップをとる どのウォレットでもそうですが、バックアップは必ず取るようにしましょう。 以下の手順でBraveウォレットのバックアップを取ることができます。 設定を開き、画面上部の「ウォレット」タブを選択 パスコードを入力しアンロック ウォレット画面右上の3つの点のアイコン(・・・)をクリックし、「今すぐバックアップ」をクリック リカバリーフレーズの保管・確認 リカバリーフレーズについては表示される説明や注意事項を確認し、安全に保管することを徹底しましょう。 リカバリーフレーズの重要性と管理方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。 シードフレーズとは? | 管理方法、秘密鍵との違いを解説 新たなデバイスでBraveをインストールした際は、Restore項目に飛びリカバリーフレーズを入力すればウォレットをインポートできます。 Braveのダウンロードはこちら 【稼ぐor広告ブロック】Braveのおすすめ設定まとめ! BATを最大限稼げるようにする 広告を最大限減らすようにする Braveの設定は、以上のようにどちらかに振り切るように設定するのがおすすめです。 というのも、中途半端な使い方なら、別のブラウザとの違いがよくわからなくなるからです。 ここでは、稼げるようにまたは広告をゼロにするための、おすすめの設定方法について解説しています。 Braveのおすすめ設定 BATを最大限に稼ぐための設定方法 広告ブロックを最強にする設定方法 BATを最大限に稼ぐための設定方法 BATを最大限稼ぐには、広告表示数を最大化させる必要があります。 広告表示数を最大化するには、Braveブラウザの「Rewards」から設定を行いましょう。 まず、Brave Rewards、広告表示をONにします。次に、メニューアイコンから広告表示数を設定します。 こちらで広告表示数を設定できます。収益を最大化するには、ここの表示数を最大化すればOKです。 広告ブロックを最強にする設定方法 Braveで広告ブロックを最強にするには、Braveブラウザの「Rewards」から設定を行います。 RewardsをOFFにしておけば、広告は表示されません。 念のためにクロスサイト(サイト遷移)でのトラッキングも防いでおきます。 以上で、Braveで広告ブロックを最強にする設定は完了です。 広告なしで快適に利用したい人は、ぜひこちらの設定を適用させておきましょう! BATは獲得できない BATは広告を表示した報酬として得られるものなので、Braveで広告ブロックを最強にするとBATは獲得できません。広告非表示機能とはトレードオフになるものなので覚えておきましょう。 まとめ 今回は、次世代の高速ブラウザとして注目されているBraveの特徴や評判、使い方などについて解説してきました。 革新的な仕組みとなる分散型広告システムの根幹を成すブラウザとして、今後Chromeなどの主要ブラウザとどのように競合していくのかも注目です! まだBraveをインストールしてないという方はこちらからどうぞ! Braveのダウンロードはこちら BAT (Basic Attention Token) の特徴・将来性を解説!取引所・チャートまとめ 画像引用元:rafapress / Shutterstock.com

プロジェクト
2023/10/01Yogapetz徹底解説|NFT領域で新進気鋭のウェルネスビジネスの仕組みに迫る
クリプトの冬が訪れ、NFTの盛り上がりも一服している中、注目されているNFTプロジェクト「YogaPetz」 YogaPetzは、NFTとウェルネスビジネスを融合させた新しい取り組みで、Discordサーバーの参加者数は既に18万人を突破しており、非常に活発なコミュニティ活動を展開しています。 さらに、Discordには日本人専用のチャットルームも設けられています。 一体、YogaPetzにはどんな魅力があって、これほど多くの人々を引き寄せているのでしょうか? この記事では、世界で高まるウェルネスビジネスの需要と、YogaPetzの独自の仕組みについて詳しく解説します。 世界的に注目を浴びるウェルネスビジネス 「ウェルネス」とは、健康や幸福感に関連する言葉として使われます。健康の維持や病気の予防を目的としたビジネスを「ウェルネスビジネス」と称します。 YogaPetzはこのウェルネスビジネスのカテゴリーに属します。しかし、YogaPetzの詳細を説明する前に、まずはウェルネスビジネスの背景や意義について触れていきたいと思います。 年々市場規模が拡大するウェルネス経済 [caption id="attachment_98250" align="aligncenter" width="621"] 画像引用元:https://globalwellnessinstitute.org/press-room/statistics-and-facts/[/caption] ウェルネスビジネスは、近年急速に成長しています。 国際ウェルネス機構(GWI)のデータによると、2019年のウェルネス市場は4.9兆ドルに達していました。しかし、COVID-19の影響で2020年には4.4兆ドルまで落ち込みました。それでも、今後の成長が期待されており、年間平均成長率9.9%で、2025年には市場規模が7.0兆ドルになると予測されています。 2020年には、ウェルネス市場が世界のGDPの5.1%を占めるほどの規模になっていました。 このような背景から、NFTの分野でもウェルネス関連のプロジェクトが登場してきました。その代表例として「YogaPetz」が挙げられます。 次のセクションでは、YogaPetzについて詳しく解説していきます。 YogaPetzの概要 SocialFiとGameFiの組み合わせ YogaPetzはSocialFiとGameFiを組み合わせたプロダクトとなっています。それぞれどのような仕組みとなっているのでしょうか。 SocialFi YogaPetz運営は、ユーザーがコンテンツの共有や収益化を完全にコントロール出来るよう考えており、SocialFiが重要視されています。 以下、それを実現するために実装されるSocialFiの要素を掘り下げていきます。 ユーザー生成コンテンツ (UGC:User-generated content) YogaPetzのユーザーは、ヨガの指導動画やサウンドヒーリングセッションなど、オリジナルのコンテンツを作成できます。 Petzのルールに基づいたコンテンツは無料で利用可能で、これによりユーザー生成コンテンツ(UGC)がコミュニティの中心となり、ユーザー間のつながりを深めています。 また、ユーザーは独自のトークン、$PRANAや$KARMAを使ってチップを送る、コメントを残す、または「いいね!」をすることで、クリエイターとの交流ができます。これがコンテンツの制作やコミュニティへの参加を奨励しています。 Petzland これは一般的なゲームでいうところのクランのようなものです。正式サービス開始後、プラットフォームに統合される予定とのことです。 GameFi YogaPetzは、ユーザーが健康的な習慣を自然に取り入れることを重視しています。そのため、Game-Fiとトークン報酬の組み合わせを利用し、健康的な生活を送るための動機づけを提供しています。 次に、YogaPetzのGameFiの特徴について詳しく見ていきましょう。 トークン報酬 ユーザーは、「呼吸」「睡眠」「ヨガ」「瞑想」の四つをアクティビティを実践することが出来ます。 これらの進捗状況は、スマートウォッチ、ARトラッキング、スマートフォンで追跡することが出来ます。目標を達成すると属性レベルに応じて$PRANAまたは$KARMAトークンの報酬を受け取ることが出来ます。 ゲーム内アイテム 報酬はYogaPetzの独自トークンである$PRANAまたは$KARMAで支払われます。プレイヤーにはゲームをプレイするためのヨガマット(Yogamatt)が配布され、マットをアップグレードすることでセッションごとに獲得できる$PRANAの額を増やすことが出来ます。 プレイヤーはまた、マットやジェム(Gem)などのゲーム内アイテムを両トークンで交換することも可能です。 ヨガマット:ヨガマットは、ゲーム内のメインアイテムのひとつです。マットの形や使い方は様々であり、ユーザーは自分の好みのエクササイズに合わせて、購入したり、戦略的にレベルアップしたりする必要があります。それぞれのマットには異なる属性とキャラクターが設定されており、ユーザーが獲得できるトークンの数に大きな影響を与えます。 ジェム:ユーザーは、マーケットプレイスで取引可能な様々なジェムをYogapetzやマットに使うことで、さらに属性を高めることが出来ます。 Yogapetz(NFT) Yogapetz NFTは、VIP会員権のような役割を果たしており、YogaPetzのエコシステムを十分に満喫するために必要になってきます。 現実世界に特典を還元可能 YogaPetzの独自の特徴として、多数の実世界の企業や個人との提携を通じて、仮想空間だけでなく実生活でもYogaPetzエコシステムのメリットを享受できるようにしています。 特に注目すべき点として、YogaPetzのオリジナルトークン($PRANAと$KARMA)を利用して、実生活での報酬(IRLリワード)を得ることができるという点があります。 ここで、「IRL」とは"In Real Life"の略で、実際の生活や現実世界を指すスラングです。 実際に様々なバーチャルイベントが開催されており、例えば、6月16日~21日の間、ヨガの日を祝う「YGPZヨガウィーク」として、医師から認定ヨガの達人まで、多くの方がボランティアで大量のコンテンツを提供していました。 この他にも、マーケットプレイスにて、 限定ヨガクラス 瞑想リトリート(リトリートは欧米では「日常生活から離れストレスフリーな環境に身を置くこと」の意味で使われています) トレーニング プレミアムオフライン体験 といったIRLリワードと交換することも可能です。 YogaPetzのエコシステム Gamefiの世界を中心として、「Play to Earn」がWeb3領域において盛り上がりました。そこから多くの形態に派生し、例えばSTEPNの「Move to Earn」といったさまざまなものが誕生しています。 そして今回取り上げるYogaPetzは、ヨガ、瞑想、睡眠といった健康に関連する行動を、ヨガをする動物NFTと瞑想することで、独自トークン$PRANAを稼ぐ仕組みとなっています。 呼吸をするだけでトークンを稼げることから、「Breath to Earn」とも呼ばれています。 また、YogaPetzはNFTを中心としたエコシステムを構築しており、それだけでなくクラン方式やデュアルトークンシステムを採用していることも特徴として挙げられます。 ここからはYogaPetzのエコシステムをそれぞれ掘り下げていきます。 YogaPetzのNFT YogaPetzのエコシステムは、NFTを中心として構成されています。 YogaPetz自体のプレイおよびトークン稼ぎは、NFTの保有者でなくとも行うことが出来ます。 NFTを利用したGamefiの例として、STEPNを連想する方もいるかもしれません。STEPNではスニーカーNFTを保有しなければならず、一定の初期投資が必要です。しかし、YogaPetzでは、NFT未保有者でもトークンを稼ぐことが可能です。 とはいえ、NFT保有者には報酬として受け取れるトークンにブーストがかけられているだけでなく、多くの特典も与えられています。 このように、YogaPetzエコシステムを十分に体験するには、NFTが必須となっています。 YogaPetzでは三種類のNFTが出ており、全てOpenSeaで入手することが可能です。 詳しくそれぞれのNFTを掘り上げていきます。 Yogapetz Yogapetz NFTは、YogaPetzの基本となるNFTであり、10000個のNFTコレクションが提供される予定です。 上記の画像はYogaPetzのホワイトペーパーに記載されているNFTですが、未だリビールされていないこともあり、そのデザインの全貌は未だ謎に包まれています。 Yogapetz NFTのフロアプライスは0.133ETHほどで取引されています。 YogapetzのOpenSea URLは以下になります。 https://opensea.io/collection/yogapetz Yogapetz NFTは、YogapetzプラットフォームのVIPパスとして機能し、NFT保有者は通常のユーザーよりも大きな特典を受けることが出来ます。以下が、主要な特典となります。 プラットフォームへのVIPアクセス 1枚のYogaMatt(ゲーム内アイテム)が全ホルダーに配布 プラットフォーム経由の属性ボーナスおよび追加ボーナス 毎月のトレジャーボックスボーナス ホルダー限定のイベントや特典 $PRANAの報酬およびステーキング Yogapetz NFTをステーキングして$PRANAを獲得し、$PRANAをPetzlandの購入に使用可能。 ホルダー限定IRLイベント・トレーニング・商品 NFTホルダーは、ホルダー限定の現実世界にリンクした特典を手に入れることが出来、こうした限定イベントや特典は、プラットフォームのマーケットプレイス経由でのみ交換可能となっています。 Keungz Keungz NFTは、オークションでミントされ、落札価格は5Ether、総供給量は432でした。 当初のオファーは約11ETHほどでしたが、今では、フロアプライスは3.3ETHほどに落ち着いています。 次に紹介するKubzよりも非常に高額になっていますが、その分、多くの特典を受け取ることが可能です。例えば以下のような特典を得ることが出来ます。 Kubzエアドロップ 2つの無料Yogapetzエアドロップ このほかにもYogapetsエコシステムの全ての恩恵を受け取ることが可能です。また、Keungz GenesisはKubz NFTをステーキングで繁殖させること(増やすこと)が可能です。これにより毎月無料でKubzを手に入れることが出来ます。 KeungzのOpenSea URLは以下になります。 https://opensea.io/collection/keungz-genesis Kubz Kubzは、Keungzの子供に位置しており、いわば廉価版と考えてみて下さい。 Kubzもオークションでミントされ、価格は0.469イーサで、オークションの総供給量は5000でした。Keungz NFTによってKubzを繁殖させることができるようになったため、供給量は増えていますが、総供給量は1万が上限となっています。 Kubzにも以下のような特典があります。 ・3つのKubzホルダーは、Petslist(Yogapetz NFTのホワイトリスト)を獲得。 ・6つのKubzホルダーは、Resortlist(Petslistよりも貴重なホワイトリスト)を獲得。 ※YogaPetzには「Petslist」と「Resortlist」という2つのホワイトリストが採用されています。 となっており、つまりは、6つのKubzホルダーは合計で2つのPetslistと、1つのYogaPetz Resortlistを獲得することが出来る仕組みになっています。 KubzのOpenSea URLは以下になります。 https://opensea.io/collection/kubz Petzland:クラン方式を採用 YogaPetzでは、「Petzland」という他のゲームにおけるクランが存在しています。 ユーザーは、Petzlandを購入(クランを開く)するか、レンタル(クランに参加する)を選ぶことが出来ます。 Petzlandの大きさは「S、M、L、MEGA」の四種類に分けられており、大きさによって獲得できる$PRANAの量や、ミッションのブースト率などが異なっています。 また、各Petzlandでは、オーナーや公式が主催する様々なミッションやイベントに参加することが出来、ユーザーにとって$PRANAを稼ぐチャンスが増えます。 二種類のトークン:$PRANAと$KARMA Yogapetzでは他のGame-FiやWeb2ゲームと同様、デュアルトークンエコノミーが採用されており、$PRANAと$KARMAが使用されます。 全体的に$PRANAの方がより多くの用途に使用することが可能となっています。 以下で詳しく、それぞれのトークンの解説を行います。 $PRANA $PRANAは、ガバナンスに使えるだけでなく、YogaPetz内において基本的にあらゆることに活用が可能です。 稼ぎ方と用途は以下となっています。 稼ぎ方 Kubzの保有 Yogapetzの保有 ウェルネスで稼ぐ Petzlandのミッション Petzlandのプール Petzlandのコンテンツ作成 用途 チップ タスクとミッションのスキップ Yogapetzのアップグレード Petzlandの購入および参加 ヨガマットの購入 トレジャーボックスの購入 ゲーム内アイテムの修理・レベルアップ・改造 換金 IRL特典の入手 特別なIRL特典の入手(ホテルリゾートや航空券など) $KARMA $KARMAはプラットフォームトークンの機能を有しています。$PRANAと同じように使うことが出来ますが、最低限の用途しか用意されていないのが特徴です。 稼ぎ方と用途は以下となっています。 稼ぎ方 ウェルネスで稼ぐ Petzlandのミッション Petzlandのコンテンツ作成 用途 チップ Yogapetzのアップグレード トレジャーボックスの購入 ゲーム内アイテムの修理・レベルアップ・改造 $PRANAへの交換 IRL特典の入手 おわりに ここまでウェルネスビジネスとNFTを組み合わせたプロジェクト「YogaPetz」の解説をしてきました。 ウェルネス経済は年々、その規模を拡大してきており、そうしたビジネスの波がWeb3にも波及してきました。 「○○ to Earn」という言葉は最早、馴染みのある言葉ではありますが、「Breathe to Earn」は初耳という方も多いのではないでしょうか。 また、GameFiであるにも関わらず、必ずしもNFTを必要としないことから初期投資の必要がなく、気軽に試してみれるというのも魅力の一つでしょう。 Yogapetz NFTのリビールはまだされておらず、現時点から始めてもアーリーユーザーになることが可能です。 もし、興味が湧いた方がいれば、まずはDiscordに入るとことから始めてみてもいいかもしれません。















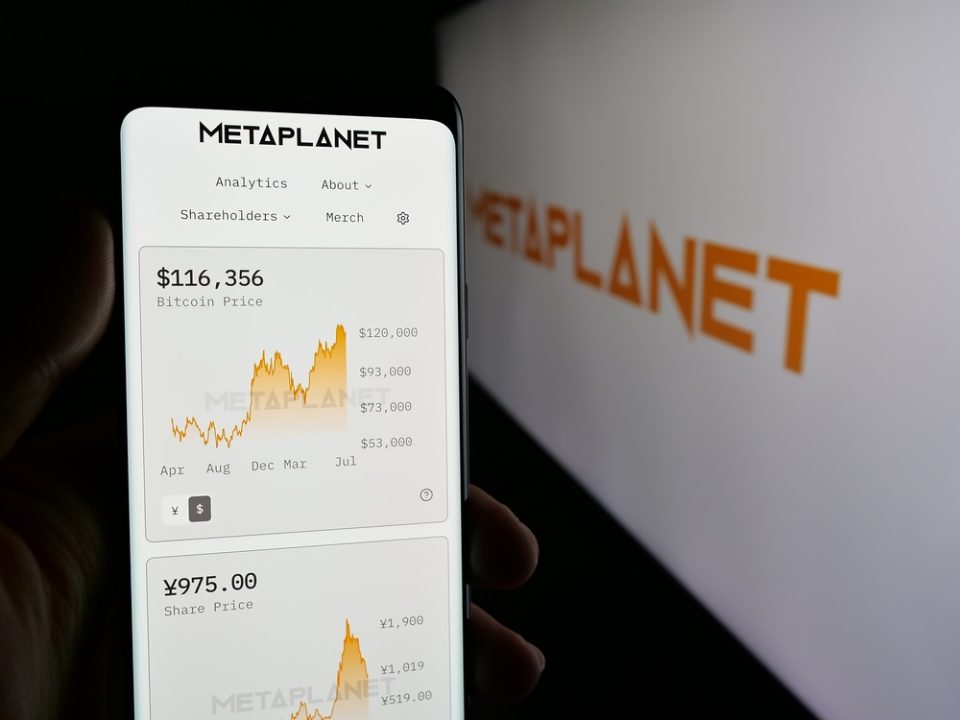

 有料記事
有料記事


