
レポート
2020/08/25【Crypto 2020イベントレポート】ゼロ知識証明~ΣプロトコルとBulletproofs ~ Centrum Wiskunde & Informatica
8月に開催されたCrypto 2020にて、entrum Wiskunde & Informatica (CWI)の暗号学者による特別公演がありました。 登壇者 Ronald Cramer オランダのアムステルダムに位置するCentrum Wiskunde & Informatica (CWI)とUniversity of Leidenの教授を務めています。暗号方式の一つであるクレーマー シュープ暗号を発明した人物の1人で、暗号学界での功績を成し遂げています。 Compressed Sigma-Protocol Theory and Practical Application to Plug & Play Secure Algorithmics 以下、講演の内容になります。 ゼロ知識証明とは、命題(条件づけなど)が真であるという情報以外を伝えずに他者へ命題が真であることを証明する方法です。 ゼロ知識証明に使われていたセオリーにΣ(シグマ)プロトコルセオリーがあります。シグマプロトコルセオリーではゼロ知識証明の際に必要なコミュニケーションの数がO(|C|)*kで定義され、コミュニケーションは一次関数で表されます。コミュニケーションが一次関数的に処理されるため、こちらはリニアーコミュニケーションと呼ばれます。 一方、のちに発明されたBulletproofsではコミュニケーションの数がO(log|C|)*kで定義され、コミュニケーションは対数関数で表されます。コミュニケーションが2次関数的に処理されるため、こちらはクアドラティックコミュニケーションと呼ばれます代入値が同じ(条件が同じ)である場合、Bulletproofsを用いたほうがコミュニケーション数が少なくなるため効率を重視してBulletproofsの使用が広まりました。結果、シグマプロトコルの使用は激減していきました。 Ronald Cramer氏の研究では、シグマプロトコルのリニアーサイズ(一次関数的)なメッセージに数学的/暗号的な処理を行うことで二次関数的なメッセージへ変換できることが証明しました。 これにより、シグマプロトコルをBulletproofsに置換するのではなく、シグマプロトコルを改良することによりBulletproofsに劣らないプロトコルを作り上げることができると説明しています。 最後に Crypto 2020はInternational Association for Cryptologic Research (IACR)により運営される暗号資産とブロックチェーンに関するカンファレンスです。 今回の公演では、ゼロ知識認証に使われる2つのプロトコルの背景から、シグマプロトコルの新たな可能性まで知ることができました。

レポート
2020/08/24【Crypto 2020イベントレポート】Crypto for the People – Encrypted Systems Lab
8月に開催されたCrypto 2020にて、Encrypted Systems Labのコンピューターサイエンティストによる招待公演がありました。 登壇者 Seny Kamara Brown Universityでコンピューターサイエンスを教える准教授で、同大学のEncrypted System Labに所属しています。前職ではMicrosoft Reserchのリサーチャーとしても活動しており、現在はAroki Systemのチーフサイエンティストを努めています。現実世界のプライバシーや安全性などの課題に基づいた暗号学の研究を行っています。 Crypto for the People 以下、講演の内容になります。 Kamara氏は今年話題になった警官による黒人差別問題を紹介し、暗号学を黒人、移民、暗号学者、部外者の4観点から考察しました。 現在、アカデミアの研究は企業にとって有用な技術を生み出すことを目的としていますが、Kamara氏は社会のために研究を行うべきであると主張します。 サイファーパンクと呼ばれる、暗号学を用いて社会を改革し個人の自由を確率しようとする動きがありますが、それは女性や黒人、子供や移民は運動の対象になっていません。そこで、そういったMarginalized People(保護から取り残された人)のために暗号研究を行うことが重要です。 人々のための暗号学の例としてアフリカのケースが紹介されました。ブラックナショナリズムの団体である(アフリカ民族会議)African National Congressが1960年に禁止されて移行、活動がアフリカ国外に広がりました。 禁止に伴って安全なコミュニケーションが必須になり、80年代にコミュニケーションシステムとして開発されたのがVulaです。Vulaは開発された背景からユーザー同士が同時にオンラインでなくても利用でき、使用が隠蔽され、長距離でも使えるパブリックなコミュニケーションという特徴がありました。 コンピューターの使用が怪しまれ、モバイルネットワークもなかった当時、Vulaではユーザーがコンピューターにメッセージを入力し、暗号化したデータを音に変える機械を使い、テープレコーダーに録音します。公衆電話を用いて受信者当ての録音サービスに音として伝えた後、逆の手順でメッセージを復元することができます。 Kamara氏はVulaの例を電話機やテープレコーダーを用いて現実世界に応用された暗号技術であるとして高く評価しています。 「人々のための暗号学は既存の研究や製品を促進するために保護から取り残された人を利用するのでなく、保護から取り残された人が経験した問題を解決するために専門家と相談し新たな研究や技術を生み出すことである」と自身の考えを示しています。 最後に Crypto 2020はInternational Association for Cryptologic Research (IACR)により運営される暗号資産とブロックチェーンに関するカンファレンスです。 今回の公演では社会的に不遇な人々のために暗号技術が使われた例と、社会のための暗号学というKamara氏の考えを知ることができました。技術と研究のあり方という哲学的でもある話題でとても興味深い内容でした。 Crypto 2020の招待公演「Our Models and Us」のレポートもこちらからご覧になれます。

レポート
2020/08/22【Crypto 2020イベントレポート】過半数が善意を持つマルチパーティ計算の安全性
登壇者 Yifan Song 主にブロックチェーンのセキュリティに関する論文を執筆しており、主にMultiparty Computation(MPC)や暗号学に関する研究をしています。 Guaranteed Output Delivery Comes Free in Honest Majority MPC マルチパーティ計算(MPC)では複数のサーバーが決められた手順によってデータを処理し、次のサーバーへ渡すサイクルが有限回行われます。計算では加法と乗法のみが行われ、各サーバーの持っている情報のみでは元の情報が復元できない設計になっています。 今回の講演では、公開されたチャンネルとP2Pチャンネルにおける過半数が善意を持つ参加者である場合の安全性について考察します。 Yifan Song氏は、MPCの中でも公開鍵のような複雑な暗号プリミティブを使わずに簡単なローカルでの計算のみで行えるUnconditional MPCが有用であると主張しています。 MPCの攻撃者は2種類存在し、一方はプロトコルを意図的に無視するfully maliciousと定義され、もう一方はプロトコルには従うものの不正に情報を入手しようとするsemi-honestと定義されます。 Yifan Song氏のチームが開発したMPCプロトコルではFull Security(上記のどちらの攻撃者に対しても有効な安全性)を実現しています。さらに、Full Securityを実現したBSFO 12プロトコルが1つのゲートに対して20個のエレメント(MPCにおけるコスト)を必要とするのに対し、Yifan Song氏のプロトコルは最小で5.5のエレメントで運用できるなど、他のプロトコルよりも効率の良い計算を実現しています。 最後に Crypto 2020はInternational Association for Cryptologic Research (IACR)により運営される暗号資産とブロックチェーンに関するカンファレンスです。 今回の公演では、MPCの課題とされてきた安全性や効率性を改善したプロトコルについて理解することができました。
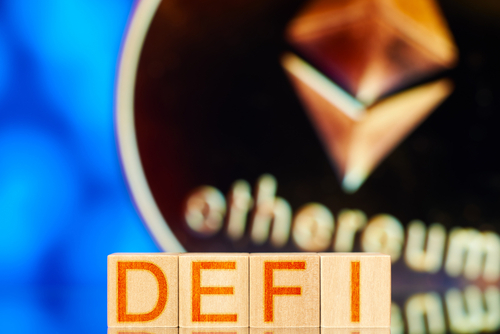
レポート
2020/08/11【イベントレポート】イールドファーミング– Global DeFi Summit
8月6日に開催された「Global DeFi Summit」にて、DeFiを利用したイールドファーミング(流動性供給や貸し出しにより利回りを得ること)についてディスカッションが行われました。 登壇者 [caption id="attachment_53816" align="aligncenter" width="800"] (Global DeFi Summit公式HPより)[/caption] Leeor Shimron(モデレーター) Fundstrat Global Advisorsの副社長でありForbes.comのコントリビューターも勤めています。 Kain Warwick Synthetixの創設者であり、blueshyftのCEOを勤めています。Synthetixはイーサリアムブロックチェーン上に構築されたDeFiレンディングプロトコルで、ドルや円などの法定通貨の価格に連動したアセットを提供しています。ユーザーは独自トークンであるSynthetix Network Token(SNX)を預け入れることでsBTCやsUSDなどアセットに担保されたトークンを発行することができます。 Nate Hindman Bancor Networkの広報責任者です。Bancorは流動性供給を目的とした分散型のネットワークです。Bancorプロトコルを利用することで、書いてや売り手がいなくても暗号資産を別の暗号資産へコンバージョンすることができます。 DeFi Dad DeFiサービスを利用するユーザーです。ポッドキャストなどを通じて情報配信を行っています。 Loong Wang Ren ProtocolのCTOです。Ren Protocolはブロックチェーンを超えてDeFiの相互運用を行うことができるプロトコルです。ユーザーは異なるブロックチェーン 間での価値交換を行うことができます。 The Coming Age of Yield Farming 以下、ディスカッション内での登壇者のスピーチについてまとめています。 Kain Warwick DeFiのイールドファーミングは各プロトコルによって大きく変わってきます。例えば、Uniswapはユーザーに対するインセンティブ設計がしっかりしているので、利用される理由があります。他のプロトコルに関しては、本質的な価値が明確ではない場合もあります。 最近はDeFiのブームが到来していますが、やはり火付け役になったのはCOMPトークンでしょう。COMPは初めて多くの人々から認知されたプロトコルであり、COMPトークンは従来のICOとは異なる新しい方式でトークンを発行、配布しています。 Nate Hindman DeFiでは流動性プールへ流動性を供給したことによる情報が蓄積され、各ユーザーが供給した流動性の割合が把握できます。プールにおける各ユーザーの貢献の割合に応じてプロトコルが自動的に報酬を分配、配布してくれます。 UniswapなどのDEXでこの役割を担うのがAMM(Automated Market Maker)と呼ばれるプログラムで、デポジットされたトークンの量に応じてシステムの利用料をユーザーへ分配することができます。 DeFi Dad イールドファーミングは流動性の供給などを通して行うことができますが、利回りの種類には利子や利用料の分配などいくつかの種類があることを理解する必要があります。 さらに、最近はイーサリアムのガスが高騰していますが、ユーザーにはハック(裏技)が存在するので、それを利用する人もいるでしょう。私の感覚ですが、DeFiにはここ数ヶ月で100ドル以内の少額投資家が増えてきた気がします。大規模なトランザクションであればガスコストの影響はそれほど大きくありませんが、少額投資家にとっては問題になってきます。 ETH Gas Stationなどを使えばGasの計算などを予め行うことができるので、ガス高騰の影響を軽減することができます。ガスが高騰しても、こういった少額の予算を持った一般の人がDeFiを利用するための方法は存在すると思います。 Loong Wang DeFiはまだ初期段階であると言えます。これからさらなる成長をしてくれるでしょう。 最近話題のCompundについてですが、これはイールドリスクを抱えています。COMPが話題になったり高騰したりすることによって、ガバナンスではなくイールドファーミングにしか興味のない人々の手に渡ってしまいます。COMPはガバナンストークンなので、ガバナンスに興味のある人々に保有された方がいいのですが、そこが問題だと考えています。 最後に Global DeFi Summitは取引所やブロックチェーン プロジェクトの運営者、そしてメディアなど様々な分野から登壇者を招待しDeFiに関するディスカッションを行うサミットです。 今回のディスカッションでは、最近DeFi領域にて話題になっているCOMPトークンに関する専門家の意見やDeFiのユーザーが使うガスの節約術を知ることが来ました。

レポート
2020/08/08【イベントレポート】実世界の資産をブロックチェーン上へ – Global DeFi Summit
8月6日に開催された「Global DeFi Summit」にて、実世界の資産をどのようにブロックチェーン上に移行するかという議題でディスカッションが行われました。 今回はそのイベント内容に関して、簡単にではありますがイベントレポートとし、ご紹介いたします。 登壇者 [caption id="attachment_53803" align="aligncenter" width="831"] (Global DeFi Summit公式HPより)[/caption] Dara Albright(モデレーター) Dara Albright Mediaを運営し、金融関係における幅広い情報を発信しています。 Sergey Nazarov ChainlinkのCEOを勤めています。分散型のオープンソース型オラクルであるChainlinkはスマートコントラクトへ処理に必要な情報のアクセスを提供しつつ、オフチェーンから取得した情報の正確性を担保します。(オラクルに関してはこちらのレポートのp15で説明しています。) Greg Keogh DeFi Money Market (DMM) を運営しています。DMMはETH、DAI、そしてUSDCをデポジットすることで利子を受け取ることができるレンディングプロトコルです。ユーザーはデポジット時にDMM dトークン(dETH、dDAI、dUSDC)を受け取り、いつでもデポジットしていた元の資産と交換することができます。DMMはデポジットされたトークンを利用して収益を生む資産を購入して運用し、その様子は全てオンチェーンで記録されています。また、資産運用によって得た収益は配当金を上回るので、十分な担保を保有しています。 Bridging the Gap - Bringing Real-World Assets onto the Blockchain 以下、ディスカッション内での登壇者のスピーチについてまとめます。 Sergey Nazarov ChainlinkはDMMなどの他の団体に対して信頼できるデータを提供しています。私たちは実世界の出来事やデータに関して検証を行い、オンチェーンで使用するためにデータ提供を行っています。 最近のDeFiはまだ初期段階であると言え、まだ成熟していませんがこれからさらに改良される余地があります。人々がインターネットを利用しているものの金融市場には参加できていない現状を考えると、DeFiは巨大なポテンシャルマーケットを有しています。プライベートキーを用いてシステムを利用し、トークンの管理やアドレスの作成を行えるシステムの製品やDeFiに預けられた資金量はいまだ初期段階であるため規模が小さいです。DeFiはさらなる価値を生み出す可能性をひめており、これからの成長が見込まれています。 DeFiの成長には3つのステップがあると考えています。1つ目はクリプトエコシステムの拡大です。クリプトエコシステムが拡大することにより人々がトークンを保有、利用するようになるためDeFiの市場が生まれます。この市場は既存の金融サービスがカバーできない領域であるので、DeFiが大いに活躍することができます。2つ目はフィンテック企業の参入です。フィンテック企業はレイヤー1やその上にあるプロトコルを利用して優れたUXやモバイルアプリを開発するでしょう。フィンテック企業はクリプトネイティブではないため難しさもありますが、決済システムやレンディングプロトコルの開発、ユーザーとの関係を構築したりするでしょう。3つ目は機関やエンタープライズの参入です。どこかのエンタープライズがはじめの一歩を踏み出せば、他の企業も続いて参入してくるでしょう。 DeFiにおいて重要なのは、レイヤー1などのインフラ層がしっかりと作られることで、その上に作られる金融コントラクトのレイヤーが安全に作られるということです。また、様々なインターフェースが開発されていますが、インターフェースはユーザーにとって最大のリターンが得られる資産運用を提示するのみで、コントラクトや金融商品そのものではないということです。 Greg Keogh DMM Foundationは実世界の収益を生む資産に裏付けられたシステムを通して安定した利子を世界規模で提供しています。この取り組みは実世界の資産とブロックチェーン上の資産の連携を実現しています。 DeFiはまだ初期の段階であり、インターネットが誕生してすぐの時代のようにまだ普及していません。しかし、秘めているインパクトや拡大の可能性は凄まじく、Chainlinkのようにインフラも整備されてきています。今後、新たな人々が参入してきて加速度的に成長していくでしょう。大きな変革をおこし、新たな金融の世界を作ると考えられます。 既存の金融業界では低すぎる金利や金融サービスの裏付けの不足などが問題となっていて、資産を預けても利回りを得ることは難しくなっています。これは世界規模の問題であり、解決される必要があります。 ブロックチェーンの発展において軽視されがちなのがユーザーサイドの変化です。これからデジタルネイティブと呼ばれる若い世代が消費者として現れ、ブロックチェーンに関する理解なども進んでいくと思われます。 最後に Global DeFi Summitは取引所やブロックチェーン プロジェクトの運営者、そしてメディアなど様々な分野から登壇者を招待しDeFiに関するディスカッションを行うサミットです。 今回のディスカッションではSergey NazarovとGreg Keoghの2人が共通してDeFiはまだ初期段階であるものの、今後の成長に期待していたことが印象的でした。2人とも、今後新たな人々が業界に参入してくることでさらなるDeFiの発展が起きるという考えを示しています。

レポート
2020/06/10XANGLEがCRYPTO TIMESのリサーチコンテンツ「CT Analysis」の公式データプロバイダに。また、CT Analysisの第8回『韓国ブロックチェーン/仮想通貨業界動向』を本日より無料公開
CRYPTOTIMESは、韓国を拠点とする暗号資産の開示プラットフォームである「Xangle」を公式リサーチ・データプロバイダとしてリサーチ領域における協業を行うことを発表いたします。 また、2月12日より提供開始したリサーチレポートCT Analysisの第8回レポートとして『韓国ブロックチェーン/仮想通貨業界動向』を本日より無料公開いたします。 CT Analysis 韓国業界レポート Xangle(CrossAngle)について Xangleは世界をリードする仮想通貨開示プラットフォームで、60以上の世界の取引所や投資家に不可欠な情報を提供しています。 世界をリードするクリプトインテリジェンスプラットフォームとして、Xangleは、毎日の更新からフルスコープの詳細な360度のオンチェーンおよびオフチェーンの概要まで、700以上のプロジェクトを取り扱います。また、定期的に業界の洞察レポートを公開しています。 また、プロジェクトチームと直接協力し、強力なデータ分析インフラを運用することで、信頼できるデータの調達、フィルタリング、検証を行い、独自の価値を提供しています。 プロジェクトや仮想通貨サービスプロバイダとの直接的なコネクションを生かすことで、プロジェクト正確なデータの取得やTwitter等のソ-シャルメディアでは発信されないような開示事項、また上場審査に必要とされるプロジェクトトークンのDue Diligenceなどの高度なリソースの提供も可能になります。 第8回『CT Analysis』が提供する無料レポート『韓国ブロックチェーン/仮想通貨業界動向』 2月12日より提供を行っている『CT Analysis』の第8回では、『韓国ブロックチェーン/仮想通貨業界動向』を本日より無料公開いたします。 ※過去に公開済みのレポートは全て無料でCT Analysisホームページ (https://analysis.crypto-times.jp)よりダウンロードができます。 今後、レポートが公開される度に登録されたメールアドレス宛に最新レポートが届きます。(隔週目処) 韓国のブロックチェーン活用動向 韓国では、2017年よりICOなどが禁止されていましたが、クリプトの裏では政府や財閥出身の大企業などが2015年寄り大規模にブロックチェーンの社会実装計画を進めています。 メッセンジャー大手のKakaoによるブロックチェーン「Klaytn」や電子部品等を扱う世界最大級のメーカーSamsung社による「Nexledger」などをはじめとして、韓国には非常に多くのブロックチェーン(汎用・特化型)が存在しています。 ICOを実施したICONやFantomなど、エンタープライズ領域での活用を視野にいれた動きも非常に目立ちます。 法規制面では、仮想通貨サービスプロバイダ(VASP)やICO、仮想通貨のキャピタルゲインに関する法改正が提案・実施されており、ますます韓国の業界での立ち位置が注目すべきものとなります。 CT Analysis 韓国業界レポート CT Analysisについて 2020年2月12日より暗号通貨/ブロックチェーン専門メディアCRYPTO TIMES ( https://crypto-times.jp )が2月12日より提供開始した、暗号通貨/ブロックチェーンの分野に特化したリサーチレポートコンテンツです。 今後、暗号通貨/ブロックチェーン分野は更に注目が集まることが予想されるものの、技術者から投資・事業家まで様々な参加者がおり、各々の求める情報は見つけづらく、また議論は英語で行われることが多いため、リサーチコストが高くなる傾向があります。 CT Analysisでは、2年間業界に携わりながら運営してきた知見やデータを活用して一般ユーザーから事業者まで、幅広いデータ・分析需要に応えることを目標として、専門性とわかりやすさを追求したリサーチ・レポートを提供していきます。 また、パートナー企業の強みを生かしたリサーチレポートも提供しており、オンチェーンデータやオフチェーンデータ、クリプト市場に関するセンチメントデータ、ユーザーの予測を機械学習で最適化したデータなどの情報を使ったレポートの配信も予定しています。また、これらは日本だけでなく、世界各国の情報も取り入れたコンテンツの配信を予定しています。 CT Analysis
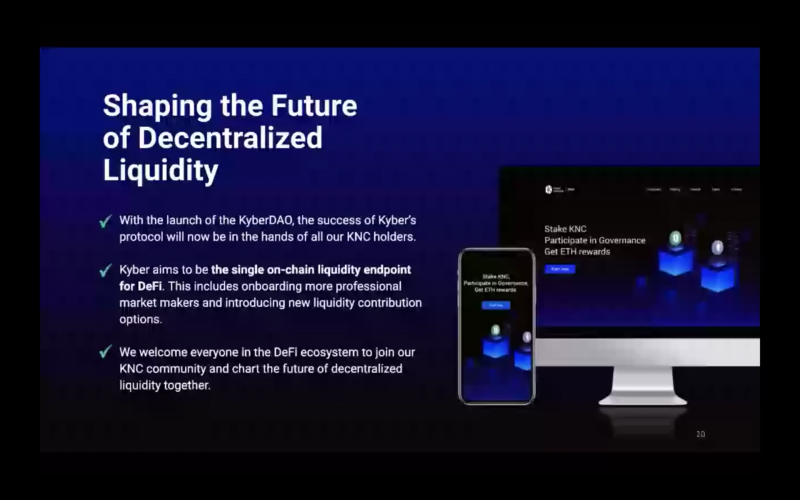
レポート
2020/05/08【イベントレポート】Kyber Network Loi Luu氏;Katalyst, KyberDAOと今後の展望- Ethereal Virtual Summit 2020
本日5月7日~8日にかけて開催されている「Ethereal Virtual Summit 2020」にて、Kyber Networkの創設者であるLoi Luu氏がこれからの展望としてKatalystやKyberDAOについて説明しました。(Kyber Networkに関してはこちらの記事で詳しく説明しています) The Future of Decentralized Liquidity for DeFi Kyber Networkは、DeFiなどのサービスにおける流動性を高めるための、複数のDeFiプラットフォームとエンドユーザーを最適なレートでつなげる流動性プロトコルとして機能します。 Kyber Networkを利用することで、全ての取引がオンチェーンで行い透明性を確保しながらも、一元的にアグリゲート(集約)された流動性にアクセスすることができます。 今後の展望としてKyber Networkが実装を予定としているプラットフォームのプロトコルとKNC(Kyber Network Crystal)トークンモデルを改善する大型アップデート「Katalyst」により、Kyberにはさらなる流動性がもたらされます。Katalystの大きな変更点は以下の4点とされています; プロトコルにおける意思決定がKyberDAOによって行われる KNCトークン保持者への新たなステーキングメカニズム 流動性供給の改善 テイカー・DAppsでの任意の手数料設定 KyberDAOはKNCの保持者がプロトコルにおける決議や重要なネットワークパラメーターに対して投票を行うことができるコミュニティプラットフォームです。 [caption id="" align="alignnone" width="1141"] Kyber Mediumより[/caption] KNCを保有することで、投票権だけ出なく、ネットワーク手数料の一部をETHの配当として獲得することもできます。 KyberDAOの登場により、KNCは”デフレーションモデルを採用し、トークンがバーンされステーキング報酬がDAOによって決定される"世界で初めてのトークンとなります。 Katalystでは、徴収された手数料の一部がプールの供給者へインセンティブとして還元される仕組みになっており、インセンティブの供給者はKNCを保有する必要はありません。 [caption id="" align="alignnone" width="1473"] Mediumより[/caption] 同プラットフォームを使用するDAppは、自身のビジネスモデルに応じて任意にマージンを設定することができます。 また、開発者は流動性の心配をすることなくアプリやDeFiユースケースを開発することができます。 Ethereal Virtual Summitについて Ethereum Virtual Summitは、Ethereum最大のインキュベーターとされるConsenSysによるコミュニティイベントです。 2月の時点ではニューヨークでの開催が予定されていましたが、世界の情勢を受けオンライン・無料で開催しています。 以下のリンクより、ウェブ上で参加することができます; Ethereal Virtual Summit

レポート
2020/05/04IOST x Japan ServiNode Online Conference (English Ver)
This article is a report of IOST x Japan ServiNode Online Conference, which Crypto Times, PHI, EverSystem as Japanese Servi Node, and Terry, the Co-Founder of IOST, joined. IOST Japan ServiNode Online Conference participants CRYPTO TIMES "CRYPTO TIMES" is a web media on blockchain and crypto currency mainly for Japan. It started at the end of January 2018, is trying to share accurate information by reporting primary information and correct information about blockchain. EverSystem Inc. It is a company that researches blockchain to utilize digital asset in Nagoya. It is official partner of "free blockchain education program" provided by IOST, and released the first domestic blockchain dApp game "Crypto Ninja." EverSystem Inc. is a partner that provide IOST Baas PHI Inc. It is developing autonomous decentralized organization platform "GUILD" using blockchain with its mission, technology can change the world. The represent, Oka, joined "Deep Dive into Blockchain," Zurich University blockchain center, and was selected as the first participant of education assistant program provided by IOST. PHI is a partner that provide IOST Baas. IOST ISOT is the project that provide blockchain developing DApps with smart contract. It uses Proof of Believability, a type of consensus mechanism to solve scalability. the main net was released in February 2019, and it has expanded its ecosystem globally for a year. IOST Japan ServiNode Online Conference Ohta (IOST Japan): This is an event with Telly with IOST and communities. Crypto times interviewed Terry a year ago. Therefore, it is a good time for us to share what IOST have achieved and what we are going to do as a long objective lets share with this community. Not many people are surviving in the blockchain field. As IOST, we want to hear their project more deeply so that we can understand and provide proper support. The facilitator is Crypto Times, Mr. Arata, so I would like to pass it to him now, and he will start the interview. Arata EverSystem: Hi everyone, today is IOST x Japan ServiNode Online Conference. First of all, please introduce yourself. At first, I will introduce myself. Two years have passed since Crypto Times wrote about IOST for the first time in May 2018. We are very happy to grow up with IOST. We released such a report in this February. That’s all, and Mr. Oka, please introduce yourself next. Oka (PHI): Thank you, Mr. Arata. I am Takashi at PHI, and I am a CEO. Now we are developing a service which is called GUILD. GUILD can be a digital governance layer of all organizations. Wada (EverSystem): I am Takao Wada, CEO of EverSystem. I was mainly in department of development as an engineer of a software company or freelancer for eight years after graduation from Mie University. I worked for a technical school and classes for IT and game development for about 30 years. In the meantime, as a working mind, I was awarded my doctor's degree at the graduate school of Mie University. Then I funded EverSystem with cofounder about three years ago and worked for blockchain application development mainly in IOST. Our Engineer, Mr. Miyazaki, could you introduce yourself? Miyazaki (EverSystem): Hello, I am Atsushi from EverSystem. I am a software engineer. I joined the company and IOST team community about a year ago. So far, I was involved in 2 projects using blockchain, especially IOST. I also participated in several activities that expand IOST in X system with Mr. Ohta and fine teams. Thank you. Terry (IOST): I'll go next. Hello, I am Terry. I think I have met everyone here before. I am a co-founder and CTO of IOST, and I used to be an engineer of Microsoft and Uber. And in 2017, I moved backed to china, and I started IOST project. We are doing this for about three years. We have many signs of progress, and I will introduce it later. Right now, we are trying to grow an ecosystem and trying to grab more users and make blockchain adapted in more fields. It is nice to be interviewed by Crypto Times again as we have met before. And it is interesting to have a meeting like that (online). It is the first time for me to use Zoom for an interview. It is quite interesting. Let's come back to Crypto Times. What each company did after IOST's main net launch a year ago Arata: It has been since IOST launched the main net. Have you seen any growth in the way people join the ecosystem? And how has IOST grown? Terry: Sure. IOST launched our main net last year in February. It was already one year ago. Within this one year, IOST ecosystem experienced rapid and impressive development. IOST is continuing to show a steady pace of growth. So today, we have been supported by more than 400,000 worldwide community members. And I think, in the market, we influence 20 around countries around the world. In terms of staking, as we are ranked in the first place in staking companies. Right now, we already have more than 4 billion our ST votes staked in the main net. That's roughly over 5% of the circulation supply. We also are growing partner nodes in the ecosystem as here EverSystem and other node partners. We have more than 400 node partners. This is actually a big number and they help IOST grow the whole ecosystem around the world. In terms of implementation, we actually have multiple corporations with global leaders in many fields, such as we are helping drone company in China. We are also working with many different projects in Japan, such as EverSystem and also L-Design of the electricity project. Also, we are working with many traditional game publishers as well as Tahitian blockchain game teams. According to the Dapp Review, we have about 30 to 60 games. So we have about ??? forth other blockchain projects around the world. Also, in terms of internal things, energy, there is an application. We are expanding the field, such as payment, charity, education, and traceability. IOST has become the first public blockchain project in China invited by CCTV. CCTV is China's national TV running by the state. And I also have been invited to the great hall of the people. I was giving a special speech about blockchain in the great hall of the people. In Japan, we are working with also FSA and JBCA, and we are trying to get more integrated in Japan, so there are many efforts. In Indonesia, the government also invited IOST to serve as an Indonesia blockchain technology consultant. There is much progress in terms of ecosystem growth in technology and blockchain adaption. In the years going, we are trying to make the ecosystem even bigger and make applications. Thank you. Oka: Past year, I think I met IOST when I was running a blockchain specialized co-working space that Singularity-Hive I remember I was contacting Mr. Ohta at the beginning on telegram, and we are not even together. At that time, I was involved in IOST as a person in a co-working space, not as a developer. After that, we held blockchain ideathon with Izumisano city, that is a part of Osaka with the mayor, a lot of famous blockchain player and Japanese blockchain base. I miss it and this is a very sweet memory for me. Day after day, the ideathon was over, and we started our own company, called PHI thorough blockchain-related products. At first we actually used Ethereum and EOS but we changed to IOST because I was really impressed by the closeness between community members and core members. That's why I started to use IOST and I give full commitment for IOST. Reflections on the past year, I think I had a demonstration experiment of token economy in Yoron island in Kagoshima prefecture and created an access control system for co-working space and created a top-level voting system for hackathon in Kindai University, which is my home university. I actually just graduated from university. Now we are talking with certain parities in Japan to use this voting system. We will be doing the best in the past year. It looks like that for me. Arata: What is the current progress of PHI’s product? Oka: In terms of GUILD progress, including future development, we are drawing up 3 phases to expand our project. The first one is to achieve a project market for the service, and the second is to enriching the service functionality and expand users. The third is to combine services with global capability like Switzerland. We just released the alpha version of the service on March 31. We are currently conducting a demonstration test with test users from Japanese companies on test nets. For the next 6 months, we will be expanding the number of test users and raising funds. If everything is done according to the plan, we should be able to release the beta version by early November. Personally, I would like to expand our services in Switzerland as well as in Japan. Arata: Thank you very much. Next, Mr. Wada, how was your past one year? Wada: When the main net is launched, we have released a blockchain game crypto ninja on IOST. Mr. Miyazaki, at the blockchain workshop, joined the company as an engineer in April last year. I think we began to develop blockchain applications for enterprises to respond to the growing need for the use of blockchain in the company. After we experienced the development with Hyperledger Fabric in IBM cloud and AWS management of blockchain. We use IOST for enterprise application as a consortium type block chain, which was the first type for us. We are very grateful for the development team of IOST to efforts. Also we have practiced proof of concept for P2P power trading system using IOST. It was successfully completed in March this year. Also, we had many workshops and hands-on in Japan. Mr. Miyazaki, would you explain it? Miyazaki: Ok, I will explain our activity besides the development of IOST products. Last year, we joined some events held bay Mr. Ohta to have the opportunity to develop blockchain technology and IOST itself. As EverSystem, we joined as a mentor to take advantage of our experience in the development of IOST ecosystem. There was a purpose of expanding IOST ecosystem. We gave our experience to take people who had the first step. What Mr. Ohta is showing to us is about an article about an event which was taken place in December 2018 at the university. I also joined this event. In this workshop, I had good opportunity to know about IOST and EverSystem. I talked to Mr. Wada to let me join the company. Arata: Ok, thank you for EverySystem team. Next, I want to ask Terry. You are also the head of AIOU. What is the difference between IOST and AIOU? Terry: The difference is very simple. Let me explain. IOST is now mainly to customers. AIOU's main target is enterprises and governments. This is because we are trying to find a sustainable model using blockchain. We want to have several ways to grow the blockchain projects. To be sustainable, you have to have some revenue to run the project and income in the future. Therefore, establishment of AIOU is actually to have a sustainable model. So we have a streamline of revenue, and this can make the whole project grow and develop for the team. Since IOST is first established in Singapore as a foundation. In order do business in multiple countries like China, we have to have an entity in China. So IOST was first established in China. It can be the partner of Chinese companies, and it can do real business with Chinese companies. This is the reason for the foundation of AIOU technology. Terry: For you to know what IOST is actually quite simple. You can just think of AIOU as an Enterprise of IOST. IOST used to be to customer version, but now it is to business company version. Now we are developing blockchain as a service platform to make it easier to use and to make portals for enterprises. Also, we are developing technology in many different fields in terms of adaption such as supply chain, finance, data asset sharing, and recording anticounterfeit. All those are some areas we are focusing on in the enterprise version blockchain. In the future, IOST enterprise version AIOU will be a substantial part of IOST ecosystem. We will be having more progress in this. It will be targeting and try to ??? different enterprises and trying to make real blockchain use case and make benefits. That is the idea behind AIOU. AIOU had just announced AIOU technology a month ago. Right now, we are still in an early stage, and we are trying to grow AIOU technology. This will be one of the main focuses for us in 2020. Question from IOST Founder Terry to Japan ServiNode Terry: Yes. I was pretty curious about progress in the GUILD project right now. First, is there any working prototype that we can have a look at? Also, is there an international version that we can use? Maybe one that supports the English language. How can people access GUILD, for example, on the browser or smartphone application? Oka: Thank you Terry. For now, we have a web service, and of course, you can use it on the web. However, we are in the alpha version test. Therefore, it is not an official launch yet. If you apply for it, we can provide you the opportunity to try that. And the source cord is not open at this point, but we will disclose after the launch of the beta version, which is planned in November. Of course, we have iOS and Android versions too. Terry: Ok. Now I am looking forward to it and please let me know when you test it. Actually, You can test on the main net because I remember you asked about the test net. There is a simple way to solve it. Now many people are using applications, but use the main net to test. This is because of no matter how you examine the main net. And eventually, you have to test on the main net. Also, we can share your test token to examine our main net, which will be easier for you because you have to test only once with the main net.I know EverSystem is helping us for the promotion of blockchain as a service and enterprise version for IOST. We are developing our products and it will take some time. In the future, we will make our products standardized because the problem in the whole blockchain world for enterprise version is not very standardized projects. We have immigration of this blockchain service with SNS like Telegram in order to make it easier to use. I am looking forward to finding test users and people can benefit from the product. There will be the main focus in this new year if there is more progress, and I will show you the progress. Now we have extensive application in terms of charity. As you know, because of the virus, there are many donations to charity. In China, there is a big problem with the charity as many red cross foundation's finances is not transparent. The best way to solve this problem is to use blockchain to make sure all the charity is transparent. When we record all of the charity to the red cross, it is difficult for red cross to mess up those. We have already launched such a product under AIOU technology and IOST's blockchain as a service. Many news media noticed this approach, and we are collecting 10,000 pieces of data in this platform. This is the starting point for AIOU technology and IOST enterprise version. In the future, we will extend the application beyond the field of charity. Wada: We would like to support the interaction of Baas from IOST and Japanese companies. Now, the use of blockchain requires expertise, which make it complex. It will release companies from primitive tasks and makes it easier and cheaper for enterprises and B2B systems. We believe that this service is also competitive with existing cloud blockchain services, which would be proven by this BaaS. We are developing educational service, which will become the showcase of our IOST BaaS. The market of the educational sector so huge that it is estimated to reach 93billion by 2020. Technology such as AI and virtual reality has already been in the road of the education sector. The use of blockchain is the only matter of time, and also needs for e-learning will increase under this situation. We want to create an innovative learning platform that is truly easy both for educators and learners to use. In the future, we will expand our service abroad, such as southeast Asia. A service currently developed will be released this fall. Oka: I would like to share PHI's service user interface, which we call as an ecosystem map. The circles on the UI represents organizations' information. For example, this circle shows the GUILD ecosystem, which comprises backend, front end, human resources, and finance teams. We can draw a circle based on this information, including what the circle represents, what the entity does, and who are in the area. Next, this is a voting system using blockchain. It works as below when someone proposes a new rule, everyone conducts voting. Ohta: Thank you. Could you tell us what CRYPTO TIMES does recently? Arata: Crypto Times, of course, focuses on media, and we started providing research reports about the blockchain industry recently. The goal of this research is to raise the level of understanding of blockchain in Japan. We now offer a customized report for a particular company, which we put our focus now. I will show you the sample of this research report, called CT analysis. This report summarizes staking information and provides the knowledge about what staking is, staking knowledge, staking mechanism, major staking projects, staking market's data. We provided a staking business report, as in the world, the staking business is growing. For example, staking service started in the past year. This is the matrix of the staking ecosystem. We summaries all the information in this report. We usually provide twice a month. Terry: I see. There are lots of projects, and it looks pretty comprehensive. Ohta: This is why we say that Crypto Times can write proper reports about IOST and the blockchain research center in Zurich deeply. Free discussion Oka: I have a suggestion about IOST. I said, PHI has produced many products using blockchain like token economy stuff and voting stuff, which we are working on now. I am very curious about DAO, Decentralized Autonomous Organization concept. In DAO, protocols are the center of the organization, and people work to maintain the protocol working. Personally, I think IOST is the best protocol in the world, however people to maintain the protocol are still immature. Therefore, we propose autonomous and decentralized growth of this community with the service like voting, which we have created before. More specifically, we would like to visualize all the community around the world which belong to IOST. Currently, in operation, we can move around our community on our services and create a circle to show what community should be working on what. Terry: I agree. I think governance is a pretty interesting issue because we have also plan to have better governance in the future. It will be grateful for us to cooperate to realize better governance. Now, we don't have a voting system, so the GUILD project is fascinating to us. Some blockchain projects have improvement plans such as VIP or EIP. GUILD will serve as an improvement plan for IOST. Ohta: Also, it was good that Takashi said he wants to visualize contribution. We do not ask to submit a report each quarter in GUILD ecosystem because the contribution is automatically visualized and evaluated. Wada: I have a question. When BaaS will be released for developers? Terry: We are still developing, and in the future, we will make it open source. I think we can do it in a quarter, Q2. Now, it is surely working in the limited environment Wada: Terry, how about Chinese encryption law? Is IOST likely to pass the law? Terry: IOST does not pass the regulation as it is a Singapore company. AIOU technology has passed the regulation as a whole company and a service in China related to blockchain and verified by China Cyber Administration. Wada: Did you call for Japanese companies to provide service in China? Terry: I think if you want to do that, you have to have your company in China. If you are in a international company, you don’t have to pass the Chinese regulation, like the case of IOST. Miyazaki: Does it mean every activity in IOST has to be done under the name of AIOU? Terry: No, only the enterprise partnerships must be done under the name of AIOU, but activity with normal customers don’t have to. This is because enterprises are restricted by agreements. Arata: It is finishing, so can you give IOST and Japan your message, Terry? Terry: This time, I am pleased that I could discuss with IOST Servi Node online. We are facing a serious situation of CORONA virus, but i wish everyone's luck. Lastly https://twitter.com/terrence_iost/status/1248107556821561344?s=20 This report was about online conference of IOST with Japanese Servi Node and IOST team. IOST is focusing on not only the expansion of ecosystem, but also providing blockchain for enterprise as Aiou. In addition to that, EverSystem, PHI, and CRYPTO TIMES will continue to help the expansion with each belief. We will commit the development of blockchain.

レポート
2020/05/02IOST x Japan ServiNode Online Conference
この記事は、先日開催したIOST x Japan ServiNode Online Conferenceにて、IOSTの日本からServiNodeとして参加しているCrypto Times、PHI、EverySystem、そしてIOSTのCo-FounderであるTerryがそれぞれの活動などについて話し合った会議について書いてあります。以下、討論の内容となります。 IOST Japan ServiNode Online Conference参加企業 CRYPTO TIMES 「CRYPTO TIMES」は、ブロックチェーン・暗号通貨に関する日本向けのWEBメディア。 2018年1月末にスタートし、一次情報やブロックチェーンに関する正しい情報を発信することで、少しでも多くの人に向けて正しいブロックチェーンの知識を伝えることを目指している。 2020年2月にはリサーチレポートCT Analysisの提供も始め、今後は日本マーケットのブロックチェーンの理解の底上げに努めていく。 EverSystem株式会社 デジタル資産を有効に活用するために、ブロックチェーン技術を適用するための研究開発を行う名古屋を拠点にする企業。 IOST/IOS財団「ブロックチェーン無償教育プログラム」の公式パートナーであり、国内初のIOSTブロックチェーンを利用したDAppsゲーム「CryptoNinja」をリリースする。 IOST Baasを提供するパートナー企業 PHI株式会社 テクノロジーで世界は変えられるをミッションに、ブロックチェーンを用いた自律分散型の組織プラットフォーム「GUILD」の開発を行う。 代表である岡崇は、チューリッヒ大学ブロックチェーンセンター"Deep Dive into Blockchain"に参加し、IOST財団の教育助成プログラムの第一号に選ばれるなどしている。 IOST Baasを提供するパートナー企業 IOST スケーラビリティの問題を解決し、Proof of Believabilityというコンセンサス メカニズムを採用した、スマートコントラクトを利用してDAppsを構築することのできるブロックチェーン・プラットフォームを提供するプロジェクト。 2019年2月よりメインネットがリリースし、この1年はIOSTのエコシステムの拡大のために日本は勿論、海外でも大きく活動を続けてきている。 関連記事 : IOSTとは DApps開発のための次世代ブロックチェーンの将来性を解説 - CRYPTO TIMES IOST Japan ServiNode Online Conference [caption id="attachment_51098" align="aligncenter" width="693"] IOSTの日本ノード一覧[/caption] 太田(IOST Japan): これより、IOSTのCo-FounderであるTerryと日本のServiNodeによるイベントを開始します。CRYPTO TIMESが最後にTerryにインタビューしたのは一年前なので、IOSTがどんな活動を行なってきたかや長期的な目標をコミュニティに共有するいいタイミングだと思います。モデレーターはCRYPTO TIMESの代表の新井さんです。 新井(CRYPTO TIMES): 今日はIOST x Japan ServiNode Online Conferenceに参加いただき、ありがとうございます。まずは自己紹介から始めましょう。2018年5月にCRYPTO TIMESが初めてIOSTに対してのインタビューを行ってから2年間が経ち、IOSTと共に活動ができて嬉しいです。我々CRYPTO TIMESもIOSTの成長とともに成長できてきたと思っています。直近の活動で言うと、私たちは今年2月にリサーチコンテンツを提供開始しました。それでは、PHI株式会社より岡さんお願いします。 岡(PHI): PHIのCEOの崇です。私たちは、全ての組織に応用できるデジタル統治レイヤー「GUILD」の開発を行っています。 和田:(EverSystem) : EverSystemの和田です。三重大学を卒業した後は8年間ソフトウェア会社のエンジニアやフリーランサーとして活動していました。その後ITとゲーム開発の講師として技術学校で40年間勤務し、三重大学の大学院で博士号を贈られました。3年前にEversystemを発足し、主にIOSTでのブロックチェーンアプリ開発を行っています。 宮崎 (EverSystem):こんにちは、EverSystemでエンジニアをしている宮崎です。一年前にEverSystemとIOSTコミュニティに入ってからIOSTに関するブロックチェーンを用いた2つのプロジェクトに関わってきました。IOST以外にも、Xsystemで太田さんやPHIチームと一緒にいくつかの活動をしました。 Terry (IOST): こんにちは、Terryです。皆さんとはあったことがあると思いますが、IOSTのCTOと共同創設者をしていて以前はMicrosoftとÜberでエンジニアをしていました。2017年に中国に戻り、IOSTプロジェクトを初めて3年間が経ちます。現在、私たちはエコシステムの発展やユーザーの獲得、そしてより多くの業界でブロックチェーンを活用するために活動しています。Crypto Timesにまた取材していただいて嬉しいです。 IOSTメインネットから1年で各社が取り組んできたこと 新井: IOSTがメインネットをローンチしてから1年が経ちましたが、それぞれのエコシステムにおける活動の変化やIOSTの発展について教えてください。 Terry:IOSTが去年の2月にメインネットをローンチしてから既に1年が経ちます。この1年でIOSTのエコシステムは急速な発展を見せました。 今日では400,000ものコミュニティーメンバーにサポートされ、 20以上の国々で使われています。ステーキングに関しては、ステーキング企業の中で1位になり、現在メインネットには流通量の5%にあたる40億のIOSTがステークされています。 またまたEverSystemのようなパートナーノードの拡充にも力を入れており、現在400以上のパートナーノードを誇っています。実装に関しては、私たちは複数の業界のグローバルリーダーを利用する企業を持っていて、例えば中国のドローン企業のサポートを行っています。私たちはEverSystemやL-Designの電力計画のような日本のプロジェクトにも参加しています。 また、たくさんのゲーム開発会社やタヒチのブロックチェーンゲームチームなどとも協業しており、DappReviewによると30から60のゲームを開発しました。 内部事情としては、決済、チャリティー、教育、そしてトレーサビリティなどの分野に進出しました。 さらに私たちはパブリックブロックチェーン計画として初めて中国国営のCCTVに招待され、ブロックチェーンに関する特別なスピーチを人民大会堂で行いました。 インドネシアではブロックチェーン技術のコンサルタントとして政府に招かれました。エコシステムの成長面では、 様々な進展があり、近年は更なるエコシステムの発展と応用を目指し活動しています。 岡:私は去年Singularity-Hiveというブロックチェーンに特化したコワーキングスペースを運営している時にIOSTに出会いました。初めは太田さんにTelegramで連絡を取り、開発者としてではなくコワーキングスペースの一員としてIOSTと関わっていました。 その後私たちは大阪の泉佐野で市長とともにブロックチェーンアイディアソンを開催し、 たくさんの有名なブロックチェーン関係者や日本のブロックチェーンベースなどが集まりいいイベントとなりました。アイディアソンが終わり、PHI というブロックチェーン関係の製品を作る自社企業を設立しました。 初めはEthereumやEOSを使用していましたが、コミュニティメンバーとコアメンバーの親密さに惹かれ、 IOSTへ移行することを決めました。去年は鹿児島の与論島でトークンエコノミーの実証実験を行い、コワーキングスペースのアクセスコントロールの開発や私の卒業大学である近代大学でハッカソンのための 高レベルな投票システムを開発しました。現在いくつかの政党に対し、この投票システムについて協議しています。 新井 : PHIのプロダクトであるGUILDについては現状、どうなっていますか? [caption id="attachment_51092" align="aligncenter" width="590"] PHIの提供するGUILD[/caption] 岡: GUILDに関して話すと、私たちは三つのフェーズを想定しています。第一段階としてプロジェクトの市場を確保し、その次にサービスの機能の拡充やユーザーの獲得を目指します。最後に私たちのサービスをスイスなどの可能性のある海外の国と統合させます。 3月31日にアルファバージョンのサービスをリリースしており、現在はテストネット上の日本企業から集めたテストユーザーと共に実証実験を行っています。これから6か月間はテストユーザーの人数を増やし、資金の拡充を進める予定です。計画通りに全てが進めば11月の初旬にベータバージョンのリリースを行える予定です。個人的には日本だけでなく、スイスにもサービスの提供を行いたいと思います。 新井:ありがとうございます。和田さんの去年の活動に関してお話しいただけますか 和田: 去年の4月には、ブロックチェーンワークショップのおかげで、宮崎さんが入社してくれました。 IOSTのメインネットがローンチされた時、私達はちょうどブロックチェーンゲームの『CryptoNinja』をIOSTでリリースしました。 また、企業のブロックチェーンに対するニーズから、企業向けのブロックチェーンアプリの開発にも着手しました。私たちはAWSやIBMクラウドのHyperledger Fabricと共に開発を行ったり、初となるコンソーシアムタイプのブロックチェーンとしてIOSTを使用しました。 IOSTの開発チームの努力にはとても感謝しています。また、IOSTを用いた P2P の電力取引システムのための Proof of Conceptの実験を行い、今年の3月に完了しました。私たちが日本で行ったワークショップについて宮崎さんに説明してもらいましょう。 [caption id="attachment_51093" align="aligncenter" width="595"] 実証実験概要 出典:elDesign[/caption] 宮崎: IOSTの製品開発以外の活動について説明します。去年、私たちは多田さんが主催したいくつかのイベントに参加しブロックチェーン技術やIOSTを発展させる機会となりました。 EverSystemとして私たちはIOSTエコシステムの発展に寄与するためメンターとして参加しました。IOSTエコシステムを拡大させるため、私たちの経験を活かして人々のサポートを行ってきました。太田さんが記事を見せてくれた2018年の12月に行われたイベントに私も参加しIOSTやEverSystemと出会い、和田さんに話して入社させていただきました。 新井: EverSystemの皆さんありがとうございました。Terryさんにお聞きしたいのですが、IOSTとAIOUの違いは何ですか? Terry: IOSTは主に一般ユーザーを対象としており、Aiouのメインのターゲットは企業や政府となっています。私たちはブロックチェーンを用いたサステナブルモデルの実現を目指しており、ブロックチェーンの計画を発展させる複数の方法を確保したかったからです。サステナブルモデルの条件として利益を上げることが必要で、Aiouという収益源があることでチームとして計画を発展させていくことができます。 IOSTはシンガポールに設立されており、 中国に進出するためにはAiouを中国国内に作る必要がありました。Aiouは中国企業と協力しビジネスを行っていく予定です。AiouはIOSTを企業向けに提供していくものだと思ってもらって結構です。 IOSTはエンドカスタマーを対象としていましたが、現在はB2Bビジネスを行っています。現在は企業向けにより使いやすいBaaSの作成を行っています。それ以外にもサプライチェーンや金融、データシェアリングに加え偽造防止などの分野における技術開発も行っています。 これらの分野は企業用のブロックチェーンにおいて私たちが注目している分野です。将来、AiouはIOSTの中でも重要な位置づけになると思います。これからはAiouの理念である新たな企業の共同を行い、実際のブロックチェーンユースケースを作り収益化を図ります。私たちはまだ発展途中ですが、Aiouテクノロジーを発展させていくことが2020年の目標です。 IOST Founder TerryからJapan ServiNodeの取り組みに関しての質問 [caption id="attachment_51091" align="aligncenter" width="639"] 今回のオンラインカンファレンスの様子[/caption] Terry:GUILDプロジェクトについての質問ですが、現在稼働しているプロトタイプはありますか?また私たちが使用できる英語などをサポートしている国際的なバージョンがあるのかも知りたいです。ユーザーはブラウザーやスマートフォンなどからアクセスできるのですか? 岡:現在、使用可能なウェブサービスがありますがまだアルファバージョンのテスト段階です。申し込みをしていただければ、試用することができます。ソースコードは現段階では公開していませんが、11月に予定されているベータ版のローンチと同時にオープンソースにします。もちろん、iOSやAndroid版も用意しています。 Terry:テストに関しては、是非メインネットを試用してください。メインネットを最初から使用することで、開発後にメインネットの環境でテストする必要がなくなるので。メインネットで試運転するためのテストトークンも配布できますよ。 EverSystemはI O S Tの企業向け版やBaaSの宣伝などでお世話になっています。現在は開発段階ですが、最終的には私たちの製品を規格化しようと思います。これは企業向けブロックチェーン界では企画化が行われていないことが問題になっているからです。また、利便性を求めてこのブロックチェーンサービスをTelegramのようなSNS Sと統合しました。 現在私たちはテストユーザーを探して、進展があった場合は報告します。私たちはチャリティ分野における活用を進めています。ご存知の通り、現在蔓延しているウイルスの影響で寄付が行われていますが、中国では赤十字社の資金の流れが不透明であることが問題になっています。 [caption id="attachment_51095" align="aligncenter" width="752"] IOST x Aiouが提供する寄付プラットフォーム[/caption] そこで、ブロックチェーンを用いて赤十字への全ての寄付を記録し透明化を行い、寄付金の不正使用を防ぐ取り組みを行っています。私たちはすでにAiouテクノロジーとIOSTのBaaSでそう言ったサービスを提供しており、ニュースメディアなどにも取り上げられたためプラットフォームには1万ほどのデータが集まっています。これが AiouテクノロジーとIOSTエンタープライズ版の現状であり、将来的にはチャリティ以外の分野にも技術を応用していきたいと考えています。 和田: 私たちはIOSTのBaaSと日本企業とのつながりをサポートしたいと考えています。現在、ブロックチェーンを使用するには複雑な専門知識が必要ですが、この取り組みによりそう言ったタスクを無くし、企業へより簡単に安くサービスを提供できるようにします。 この BaaS計画が示すように、私たちはこのサービスが既存のクラウドブロックチェーンサービスにも対抗できると考えています。現在私たちはIOST BaaSのショーケースとなる教育サービスの開発を行っています。教育部門市場は2020年に930億になると予想されているほど大きなものとなっています。 AIなどの導入が始まっている中、ブロックチェーン技術の導入は時間の問題です。また、この状況下ではe-learningの需要も高まっています。私たちは教育者と生徒の双方にとって使いやすい革新的なプラットフォームを作りたいと考えています。この開発中のサービスはこの秋にリリース予定で、将来的には東南アジアなどの海外にも進出したいと考えています。 岡: PHIはエコシステムマップと呼ばれるユーザーインターフェースを紹介しようと思います。このUI上に表示されているサークルが組織の情報を示しています。例えば、このGUILDエコシステムを表すサークルはバックエンド、フロントエンド、従業員やファイナンスチームで構成されていることがわかります。 このように、なんの団体か、何をしているか、そして誰がこのエリアに参加しているかなどの情報をもとにサークルを書くことができます。次は、ブロックチェーンを用いた投票システムの説明で、これは新たなルールが提案された場合に全員が投票を行うものです。 太田: ありがとうございます。CRYPTO TIMESの直近の活動についても教えてもらえますか? 新井 : CRYPTO TIMESは今までと同じく、正しい情報をという観点からメディアにも力を当てていますが、最近はCT Analysisと言うブロックチェーン産業に関するリサーチレポートの公開も行っています。 これは国内のブロックチェーンに対する理解を深めることを目的としていおり、月に2度の40ページ程度の無料のレポートと、特定の企業に向けてカスタマイズしたレポートの提供をはじめました。 例えば、今、お見せしているレポートはIOSTでも行われている『ステーキングの概要』で、ステーキングとは何か、ステーキングの知識とメカニズム、そして主要なプロジェクトとマーケットデータなどステーキングに関する情報をまとめています。挿入されているマトリックスは、去年始まったステーキングのエコシステムを示しています。このレポートでは、近年成長しているステーキングサービス界の情報を包括的にまとめています。基本的に、このようなレポートは月に2回発行しています。 Terry: このレポートはとても包括的ですね。たくさんのプロジェクトについて書かれています。 太田: CRYPTO TIMESはIOSTのことは勿論ですが、チューリッヒのブロックチェーンリサーチセンターやその他イベントに関して深い記事を書いてくれています。 フリーディスカッション 岡: IOSTのDAOに関する提案があります。PHIは現在取り組んでいるトークンエコノミーや投票システムなどのブロックチェーンを用いた製品をたくさんリリースしてきました。私はDAO、Decentralized Autonomous Orgnizationに興味があります。DAOではプロトコルが組織の中心に存在し、人々はプロトコルの作動を保守するために働きます。 私はIOSTが世界で1番のプロトコルであると考えていますが、保守するための人々はいまだ未熟です。なので、私たちが作った投票システムなどのサービスと一緒にコミュニティの自動化と分散化に取り組むことを提案したいです。つまり、IOSTに関係するコミュニティを全て視覚化し、どのコミュニティが何に取り組んでいるのかをサークルで表したいのです。 Terry:そうですね。私たちもより良いガバナンスを実現しようと考えていたので、とても興味深いトピックであり、共同できたら嬉しいです。私たちが持っていない投票システムを備えているので、他のプロジェクトがVIPやEIPなどを用いて進展している中、GUILDはIOSTを発展させてくれるキーになると思います。 太田:岡さんが言った可視化が実現されれば自動的に評価されるので、GUILDエコシステム内で毎四半期ごとにレポートを提出してもらう必要がなくなるのはとてもいいことだと考えます。 和田: IOST BaaSはいつ開発者向けにローンチされるか教えていただけますか?また、中国のEncryption Lawはどうなっていますか。IOSTはその法律を通過できそうですか? Terry:まだ開発中ですが、将来的にはオープンソースとして公開する予定で、第二四半期に行う予定です。現在はクローズド環境内での作動が確認されています。IOSTはシンガポールの企業なので、その規制を通過する必要はなく、Aiouは中国サイバーアドミニストレーションに認可され、ブロックチェーン関連のサービスや会社として規制を通過しています。 和田: 日本企業に向けて、中国でのサービス開始の呼びかけはしましたか? Terry: もしそれをしたいのなら、中国に会社を作る必要があると思います。国際企業の場合は、IOSTのように中国の規制をクリアする必要はないと思います。 宮崎: それはIOSTの全ての活動はAIOUの名前のもとで行う必要があると言うことですか? Terry: いえ、企業間のパートナーシップのみがAiouの名前のもとで行われる必要があり、一般的な顧客に対する物は必要ありません。これは企業に関しては契約で制限されているからです。 新井 : 時間もそろそろなので、最後にTerryから一言、今後のIOSTや日本に向けてメッセージをいただけますか? Terry:今回、日本を代表するIOSTのServi Nodeとオンラインで色々とディスカッションができたことは非常に嬉しく思います。現在は、世界的なコロナ流行による大変な時期ですが、我々も皆さんもこのつらい時期を乗り越えて切磋琢磨していきましょう。 最後に 今回、IOSTの日本Servi NodeとIOSTチームによるオンラインカンファレンスンスの内容となりました。 https://twitter.com/terrence_iost/status/1248107556821561344?s=20 IOSTはエコシステム拡大はもちろんのこと、Aiouとしてのエンタープライズ向けのブロックチェーン提供など様々な動きを行っています。 そして、EversystemやPHIはもちろん、CRYPTO TIMESもそれぞれの信念をもとにIOSTのエコシステム拡大に取り組んでいます。 今後とも、IOSTのエコシステム拡大に尽力していくとともにブロックチェーンの健全な発展に注力していきます。

レポート
2019/11/18【イベントレポート】BlockChainJam 2019 参加レポート
昨日11月17日(日)、仮想通貨・ブロックチェーン技術の最先端を行く人々が集まるイベントBlockChainJam 2019が東京大学・安田講堂にて開催されました。 会場では、ブロックチェーン技術の実際の現場における活用事例や、現在技術がどこに到達しているのかといった内容の発表・ディスカッションなどが行われました。 CryptoTimesもメディアパートナーとして本イベントに参加してきましたので、その一部を簡単にお伝えします。 マルク・カルプレス氏:ブロックチェーンの最も有効な活用方法 カルプレス氏は、ブロックチェーンの基本的な性質とその誤解について話しました。 マイニングやP2Pネットワーク、新規通貨の発行がブロックチェーンの利活用において必要とされると認識されている一方で、これが間違いであることを指摘しました。 そのうえで、オプションとして各駅をピアにして分散的に乗客の乗車状況などを確認するといった、少し特殊なユースケースについてこれらがいくつか紹介されました。 落合渉悟氏:スマートコントラクトの実社会適用と得られたインサイトの共有 落合氏のプレゼンテーションでは、タイトルの通り実社会におけるブロックチェーンの適用を趣旨として様々な事例・インサイトが共有されました。 Plasma技術は、一般的にレイヤー2技術といわれており、現時点でもこれはHLF(Hyperledger Fabric)やその他の異なるコンセンサスを採用するレイヤー1プロトコルに適用可能であるとします。 その上で、過去の中部電力との実証実験のケースから、将来的にレイヤー2の高速化によって今後産業がさらに拡大していく可能性について語りました。 古瀬敦氏:Tezosとオンチェーンガバナンス - "Kyoto Amendment"に向けて 京都に拠点を置く古瀬氏は、Tezosの開発を専門に行うDaiLambdaと呼ばれる会社で、Tezosのコア開発者として活動しています。 まずは、Tezosの概要について、LPoS(Liquid Proof of Stake), 形式検証, オンチェーンガバナンスについてその特徴が説明されました。 Tezosのアップグレードでは、Aから順にAthene, Babylon...と名前が付けられており、2021年の11番目のアルファベットとなる”K”では、Kyotoの名前を使って貢献していきたいと話しました。 Leona Hioki氏:NFTと分散金融 Leona氏のプレゼンでは、NFT周辺の概要、不動産やアートのオークションでの利活用事例などが紹介されました。 曰く、現在トークンとして機能しているものは、価値の保存、ガバナンストークン、取引所通貨の3種類が主であるとしています。 NFTは非流動資産として、所有権や会員権を示すものとして使われると成功しやすいとし、DeFiにおいては今後NFTを担保としたサービスなどが登場する可能性についても示唆しました。 また、NFTの一つのユースケースとしてToyCash社より新たなプロダクト「Ryodan」のリリースが発表の最中に行われました。 まとめ 業界の最先端を行く登壇者の方々によって行われた発表の一部を簡潔にまとめました。 全体の雰囲気としては、昨年の「~~の問題はどの技術で解決できるか」というフェーズから実社会における浸透に切り替わりつつあるなという印象を受けました。 一方で、仮想通貨を利用したユースケースはまだまだ少ないイメージでした。 昨年のBlockChainJam 2018のレポートは以下から確認いただけます; 【イベントレポート】BlockChainJam 2018 『Ethereumの最前線』 【イベントレポート】BlockChainJam 2018 – Ticket Peer to Peerの概要


















 有料記事
有料記事


