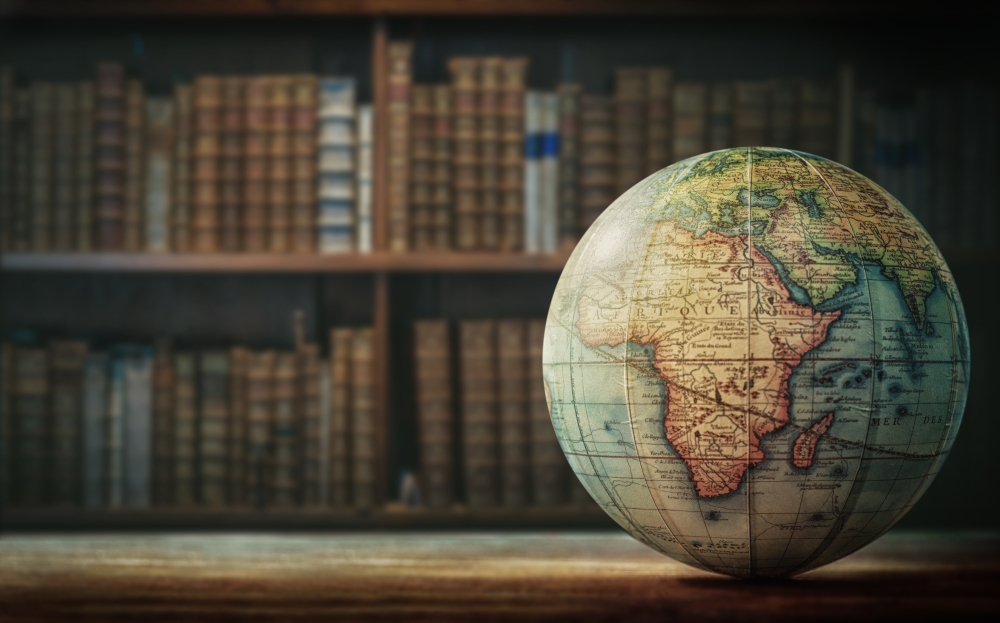
特集・コラム
2018/06/05歴史は繰り返す?人は常に「新しいお金」を追求する
Crypto Times公式ライターのYuya(@yuyayuyayayu)です。 私たちはなぜ、仮想通貨にここまでの期待を寄せるのでしょうか?投資的な側面もありますが、それなら株式やコモデティも一緒です。 しかし、なぜ仮想通貨だけが「未来の新しいお金」としてここまで取り上げられているのでしょうか? 2013年にノーベル賞を受賞した米行動経済学者ロバート・シラー氏は、この疑問をお金の歴史という観点から考察しています。 シラー氏によると、私たちの新しいお金の追求というのは仮想通貨に始まったものではなく、過去にも同例がたくさんあったというのです。 今回は、シラー氏の記事をもとに「なぜ人は新しいお金を追求するのか」を探り、それに基づき「なぜ仮想通貨が注目されているのか」を考えたいと思います。 お金と社会的理念の関係性 「お金とは何か」は解釈によって答えの変わる究極の質問です。シラー氏は、お金は「信仰」であると定義します。 「私たちはお金で人の価値を測ろうとします。お金ほど物事の価値や重要性をうまくまとめるものは存在しません。しかし、お金とはそれでいて延々と消費され続けるただの紙切れにすぎません。」 「つまり、その紙切れの価値は人々がそれを信用するかしないかにかかってくるわけです。言ってみれば、信仰のようなものです。」 と語るシラー氏は、新しいお金の創造にはその必要性を裏付ける思想があるとします。こういった思想がわかりやすく、理にかなったものであるほど、その新しいお金に信用が集まるわけです。 シラー氏は、この仮説の例をいくつか挙げています。ひとつひとつ見ていきましょう。 ユーロと国際的調和 シラー氏は、最初の具体例として現在もヨーロッパ連合(EU)で使用されているユーロを取り上げます。 インド出身の経済学者 Ashoka Mody氏は、当時ユーロ導入に賛成した人びとは「国境をまたいでひとつの通貨を制定することで外交的な調和が得られる」という思想を持っていたとします。 つまり、ヨーロッパー諸国全体でユーロというひとつの通貨を使うということが、同国間での協力や統率感などをイメージさせるものだった、ということです。 労働紙幣 シラー氏は、新しいお金の概念はユーロの件のようにシンプルでわかりやすいイデオロギーとともに誕生するものだとし、次に労働紙幣の例を挙げます。 1827年、アメリカでCincinnati Time Storeというお店が「労働紙幣」と呼ばれる紙幣を支払い方法として導入しました。 労働紙幣とは個人の労働時間を今の法定通貨のように紙面に表したもので、いわば働いた時間がお金そのものになる、というものです。 このお店は約三年で閉店となりましたが、時間をそのまま価値に換算することによって、労働紙幣は当時の労働階級の重要さをわかりやすく表したものと考えられます。 Cincinnati Time Storeの閉店から2年後、労働紙幣の導入はイギリスでも試みられます。 [caption id="" align="aligncenter" width="451"] イギリスで導入された労働紙幣。この紙幣は10時間分の価値を表す。| OISR ORGより[/caption] 共産主義と売買の廃止 お金の概念を変えようとする動きは共産主義者の中でも多くありました。 文献によると、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスはモノやサービスの売買を廃止することで「私有物」という概念を無くそうとしたとされています。 また、共産主義的政府が発行する紙幣の多くは労働階級の人びとが描かれたものが多かったことなどから、やはり当時の紙幣は労働に対し肯定的な価値観を生み出すツールでもあったことがわかります。 テクノクラシー 世界恐慌の最中である1930年には、テクノクラシー (改良主義)と呼ばれる社会思想の中で、電力をお金として扱うという考えが提案されました。 電力をお金として考えることで、失業率を減らすことができると提唱されましたが、当時最先端のテクノロジーを試用したいだけだと批判され、やがてなくなりました。 シラー氏は、電気や電化製品が家庭に少しずつ普及してきたこの時代で、このお金としてのエネルギーというのは「ハイテク時代の到来」という期待を掻き立てるものであったと主張します。 この理由付けは、ユーロや労働紙幣のような「こうなりたい」という思想よりは、未来への期待、いわばハイプに基づいたものといえます。 仮想通貨 前例が示したように、新しいお金の導入の裏には新たな社会や経済の構造に関する思想が存在します。それでは、仮想通貨が注目されているのにはどのような理由が考えられるのでしょうか。 シラー氏が強調しているのは、ブロックチェーン技術の「未知な感じ」や「ハイテク感」が仮想通貨のハイプを掻き立てているということです。 「過去の例のように、人びとの仮想通貨に対する興味というのは、"お金とは何か"という根本的な謎や、新しいお金の基礎となる最先端の技術に大きく関わっています。」 「(ブロックチェーンの)革新的・排他的な感じが仮想通貨に魅力をつけ、続いてそれを信仰する者が生まれる。これは(過去の例を見ると)特に新しいことではありません。」 テクノクラシーの例では、当時は一部の人間しかわからなかったハイテク技術が人々の興味を集め、やがてそこから電力をお金として扱う動向が生まれました。 同様に、仮想通貨もブロックチェーンという得体の知れない技術への期待によってここまで人気が生まれていると考えられます。 シラー氏も「コンピューターサイエンス以外の人間は実質わかっていない」とするように、ブロックチェーン技術を深く理解している人はあまり多くありません。 つまり、仮想通貨やブロックチェーンがここまで騒がれている理由はその中身を深く理解している人が少ないからだということです。 テクノクラシーの例に沿っていけば、ブロックチェーンという技術に対する世間的理解が広まったところで、仮想通貨という新しいお金が本当に必要かが試されることでしょう。 「分散型」ブーム シラー氏は仮想通貨の裏に存在するイデオロギー等についてはあまり触れていませんが、ブロックチェーンの特性上、仮想通貨には無政府主義的な理念が存在するとも考えられます。 ビットコインやライトコイン、モネロなど価値貯蔵を目的に作られた仮想通貨は、当然全てブロックチェーン技術を利用しています。 ブロックチェーンとは非中央集権性と不変性を兼ねつつ、第三者を必要としない記帳技術です。 つまり、この技術を利用するということは、貧富の差や争いの原因となる政府を必要とせずに、透明性と不変性の高いシステムのもとに経済圏を組み立てるといった思想を持つことといえます。 投機に惹かれて市場に参入してきたいわゆる「ウェールインベスター」とは関係はあまりないかもしれませんが、市場には分散型経済圏の発展を強く信じて長期保有をする人もたくさんいます。 まとめ 価値貯蔵としての仮想通貨が今後主流になるかどうかは、法定通貨並みの汎用性と信用を獲得できるかにかかってくるでしょう。 歴史を通して提案されてきた新しいお金は、労働通貨のように汎用性がなかったり、テクノクラシー時の電力通貨のように信用を獲得できなかったりしました。 汎用性の観点からすると、仮想通貨には大きなポテンシャルがあると言えるでしょう。匿名性の確保や国際間送金の容易化など既存の法定通貨にはできないことが仮想通貨では可能だからです。 一方で、現在の価格不安定性は仮想通貨の汎用性を大きく下げている一因と言えるでしょう。 信用度の観点では、世間のブロックチェーンに対する理解を高める運動や、セキュリティの欠陥を最小限に抑えることなどが今の仮想通貨界隈のもっとも大きな課題と言えるでしょう。

特集・コラム
2018/06/04石川県加賀市、始動!!日本初の「ブロックチェーン都市」へ向けて
本記事では、2018年3月16日に発表された、石川県加賀市が社会システム開発企業のスマートバリューとブロックチェーンスタートアップのシビラの2社と共に、ブロックチェーン都市を目指す構想について紹介していきます。 ブロックチェーン都市の概要 地方自治体がブロックチェーンを使った都市を目指すのは日本初とのことで様々な声が上がっておりますが、ブロックチェーン都市とは具体的にどのような都市で、何が目的なのでしょうか? ブロックチェーン都市とは さて、気になるブロックチェーン都市ですが、要するに ブロックチェーン技術で、地域の課題解決と新たな経済圏創出を行い、地域が自律・自走できる都市 です。 sota ブロックチェーンの透明性によってオープンになったデータを分析し、検証や研究を推め、課題解決と経済圏創出をするんですね。 ブロックチェーン都市の目的 このブロックチェーン都市、目的が3つあります。 新たな産業、経済を生み出すこと 新たな教育の場、雇用を生み出すこと 電子行政を推進すること これらの3つを通して、加賀市の教育、文化、雇用、産業を支え、さらなる活性化を促していくようです。 初年度である2019年、なにをするの? とても先進的なこのプロジェクトですが、そのための第一歩として初年度である2019年度は、 ブロックチェーン技術によるKYC認証基盤の構築 ラボの建設 に取り組むようです。 KYC認証基盤 KYCとは、Know Your Customerの略であり、KYC認証基盤のアプリケーションをブロックチェーン上に構築することで、地域内サービスの認証を一元化したり、データ集積を簡単にし、 行政コストの削減と、データを活用した新たなサービス検証を測ります。 ラボの建設 このラボ、スマートバリュー社にとっては、地域活性化のための技術やサービスを研究開発する場に、 加賀市にとっては、IoTやロボット技術の取り組みやICT技術の研究を掛け合わせて新しい地域サービスを研究開発すると供に、IT人材の育成、雇用のためのコミュニティ形成の場となる予定です。 参考画像 出典: 加賀イノベーションシティプロジェクトHP まとめ 本記事では、2018年3月16日に発表された、石川県加賀市のブロックチェーン都市を目指す取り組みを紹介させていただきました。 ブロックチェーン技術を地方に活用したり、地方がICOをしたりすれば活性化に繋がると前々から言われていましたが、やっと実働し始めましたね! sota 幼少期を石川県で過ごした者として、これからの地方創生のモデルケースになることを強く願っています!

特集・コラム
2018/06/04【プレスリリース】仮想通貨ウォレットを提供するGinco、ウォレット事業者として初のマイニング事業進出。モンゴルに子会社を設立し、仮想通貨の入手・保管・利用のトータルソリューションを提供へ
仮想通貨ウォレットサービスを提供する株式会社Ginco(本社:東京都渋谷区、代表取締役:森川夢佑斗、以下Ginco)は、モンゴル拠点の子会社「Ginco Mongol(本社:モンゴル・ウランバートル、代表取締役:古林侑真)」を設立し、ウォレットサービスを提供する会社としては初の試みとなるマイニング事業を開始いたしました。 ウォレット事業者がマイニング事業に進出する背景 Gincoは「お客様と資産の関係を変える」ことを目的に、ブロックチェーンへの窓口となる仮想通貨ウォレットサービスの提供を行ってきました。 仮想通貨のマイニングは、資産が記録されるブロックチェーンそのものを健全に保つもので、ブロックチェーンに関わる全てを支える取り組みです。 Gincoはマイニング事業に参入することにより、誰でも気軽にマイニングに参加できる環境を実現します。また、通貨の入手・保管・利用を一元化することでシナジーを生み出し、日本におけるブロックチェーン業界の底上げに貢献していきます。 ウォレットとマイニングによって実現する「次世代の銀行」 Ginco Mongolのマイニング事業は、お客様の資産活用オプションとして、マイニングに参加するためのサービスを複数構築しています。そのサービスをご活用いただくことで、より多くの方にブロックチェーン技術に触れていただく機会を提供してまいります。 現在提供している「安心・安全に利用できるウォレットサービス」に加えて、「気軽に参加できるマイニングサービス」を提供することで、次世代の銀行として「資産を保管すること」と「資産を増やすこと」を実現します。 Ginco Mongolの事業展開について Gincoが立ち上げたモンゴルの現地法人「Ginco Mongol」では、モンゴル地場の協力企業と緊密な連携のもと、国内外で以下のサービスを展開しており、現地ではすでにマシンが稼働しています。今後も利用者の拡大にともなって、設備を拡大し、現地企業との連携を強化してまいります。 ▼Ginco Mongolが現在提供しているサービス マイニングマシンの販売 マイニング設備のハウジング マイニングマシンの運用代行 また、マイニング事業の拡大にともなって、Gincoのウォレットを通じて、利用者の皆様が直接マイニングに参加し利益を得る、世界初のウォレット直結クラウドマイニングサービスの提供を予定しています。 ウォレット直結型クラウドマイニングは、ご利用希望者がすぐに参加できる気軽なマイニングサービスとなるだけでなく、今後導入が予定されているPoSなどの保有量ベースのコンセンサスアルゴリズムにおいて、競争優位性を発揮するマイニングモデルとなります。 モンゴルでマイニング事業を行うメリット 電力供給の条件がマイニングマシンに適している モンゴルで供給されている電力の定格電圧は、一般で220V、工業用で380Vとなっています。このため、マイニングマシンを稼働させる上では、特殊な工事をしたり、変圧器を導入することなく、既存の回線で最適な電圧の供給をすることが可能です。 また、モンゴルの電気代は1kWhあたり7円台となっており、日本の2分の1程度となっています。気候面でも、亜寒帯に属し年平均気温が-0.7℃のモンゴルでは、年間を通して寒冷で、容易にマシンの冷却を行うことが可能です。 土地代と人件費を抑えてマイニング施設を運営できる 国内事業者の1つがマイニングファームを運営している金沢と比較した場合、約2分の1程度の家賃相場のため、比較的安価にマイニング施設を運営することが可能です。また、月平均所得も低く、マシンの保守・管理に必要な人件費を抑えることが可能です。 仮想通貨に好意的な規制環境である モンゴルは、ブロックチェーン技術に対して非常に好意的で、自由に事業を展開していくことができます。さらに、TOSという独自通貨を発行することが発表されていて、これには、元国会議員なども参画しています。 Ginco Mongolのマイニング事業に関するお問い合わせはこちら ▼Ginco Mongol E-MAIL:[email protected] 担当:古林 【Ginco Mongol 会社概要】 社名:GINCO mongol LLC(現地登記名) 設立:2018年5月23日 所在地:Door 10, apartment 10, 7th khoroo, 11th khoroolol, sukhbaatar district, Irkutsk street, Ulaanbaatar, Mongolia 代表者:古林 侑真 資本金:10万ドル 事業内容:仮想通貨のマイニング・ハウジングサービス・マイニングマシンの卸販売・クラウドマイニングサービス ---------------- 【Ginco 会社概要】 社名:株式会社Ginco (Ginco Inc.) 設立:2017年12月21日 所在地:〒150-0036 東京都渋谷区南平台町15−10 MAC渋谷ビル8階 代表者:森川夢佑斗 資本金:1000万円(資本準備金含む) 事業内容:仮想通貨ウォレットアプリ「Ginco」の企画・開発・運用 ▼本プレスに関する報道関係者の皆様からのお問い合わせ メールアドレス:[email protected] 担当:藤本 ---------------- ▼Gincoアプリダウンロードはこちら https://apple.co/2IoXm57 ▼Ginco公式サイトはこちら https://ginco.io/ ▼Ginco公式Webマガジンはこちら https://magazine.ginco.io/ ----------------

特集・コラム
2018/06/02仮想通貨への51%攻撃は557ドルから可能に
こんにちは、kaz(@kazukino11111)です。 今回は仮想通貨の51%攻撃に関する面白い記事を見つけたので翻訳記事的な感じでご紹介したいと思います。 Vergeが過去6週間で三度目の攻撃に苦しんでいるように、PoWを採用しているコインに対するマイニングアタックは過去最安で行えるようになりました。 これにはレンタルハッシュパワーサービスなど様々なサービスの普及が関係しています。これによって以前は数週間にも渡る計画が必要だった51%攻撃も数分で実行できるようになりました。 51%攻撃は史上最も安い Crypto51.appという新たなウェブサイトではそれぞれのPoWコンセンサスアルゴリズムを採用した通貨に51%攻撃を行う際の理論上のコストが掲載されています。このウェブサイトではその通貨に一時間攻撃を仕掛けると想定した際のコストが最も攻撃しやすい時間帯などを考慮して計算されています。 実際は一時間の攻撃が成功するという保証はどこにもありません。取引所は怪しい入金を素早く検知します。しかし、51%攻撃が実行可能なことに変わりはありません。そして、先日のビットコインゴールド(BTG)のハッキング事件が成功の可能性を示しています。 一方で特定の通貨への攻撃のしやすさはネットワークのハッシュレートやアルゴリズムなど様々な要因によって左右されます。中でも equihashというアルゴリズムを採用した通貨は巨大なハッシュパワーを持つNicehashの影響を受けやすいと言います。 Nicehashとは?スロベニアに本社を置く会社で仮想通貨マイニングに必要な処理能力を売買できるプラットフォームを提供している。 Bytecoinの攻撃コストは557ドルと試算 Bytecoin(BCN)は現在10億ドル以上の時価総額を誇り、仮想通貨全体の上位20位にも入っている通貨ですが、Crypto51.appによると同通貨への攻撃は557ドル程度で可能だとされています(記事執筆時点では1444ドル)。これはアルゴリズムと低いハッシュレートによるものだと考えられます。 一方でJohn McAfee氏の支援するビットコインゴールドは778ドル程度と試算されています(記事執筆時点では4190ドル)。 一方で攻撃への対策も講じられている Bitcoin.comが先日報じたところによると、一つのPoWアルトコインの開発チームがハッシュレートを監視するスクリプトを開発しました。 これにより、10%を超える大きな変化があれば自動的に通知されるようになります。そして、新たに追加されたハッシュレートが未知のプールから発生するか、50%を超える既存のプールに転倒しそうになった場合はNicehashに大量のBTCが用意されており、それらを購入し、攻撃に対抗することができます。 PoWはPoSなどに比べて、比較的安全なコンセンサスメカニズムとして扱われてきました。ビットコインやイーサリアムなど高いハッシュレートを持つ通貨はこれに当てはまりますが、規模が小さな通貨はより少ない保護しか持ち合わせていません。 これらの通貨は今後51%攻撃に対抗する何らかの対策が求められています。 まとめ いかがでしたでしょうか?僕自身51%攻撃なんて仮想通貨の技術に詳しい人が、めちゃくちゃ緻密な計画を練ってやっと成功するかもしれないっていうレベルだと思っていたんですが、この記事を読んでみると以外と攻撃にかかるコストは安いみたいですね。 あくまでこのウェブサイトは攻撃にかかるコストを掲載して注意喚起を呼びかける目的のものなので、決して悪用しないようにしましょう。 記事ソース:You Can Now 51% Attack a Coin for as Little as $500

特集・コラム
2018/05/302018年前半の下落トレンドでも価格を上昇させた銘柄5種類とは
こんにちは、kaz(@kazukino11111)です。 2017年末にブームで過去最高値をつけた通貨は多かったですが、今年に入ってからは下落トレンドが続く一方です。ビットコインに至っては去年の220万円から70万円前半まで落ち込みました。 一方で、そんな相場でも価格を挙げている通貨は存在します。 2018年前半に高騰した通貨5選 ここでは2018年前半に高騰した通貨5種類をご紹介します。 Binance Coin (BNB) Binance Coinは名前からわかるように世界最大の取引所、Binance(バイナンス)が発行している通貨です。Binance Coinの最大の特徴は保有しているだけで同取引所での購入手数料が割引されるという点です。 BNBは今年2月頭に700円を切る程度まで下落しましたが、その後堅調に価格を上げ、5月に入ってからは1300円から1600円のレンジで取引されています。上昇率でいえば数倍とまでは行きませんでしたが、時価総額18位の通貨としては大きな上昇率なのではないでしょうか。 BINANCEは現在、DEXの開発などにも力を入れており、今後も目が離せません。 EOS EOSは企業を対象としてスマートコントラクトを利用した分散型アプリケーションプラットフォームを提供しています。利用料はかからず、一秒間に何百万件ものトランザクションを処理できるとあって注目されているプロジェクトです。 今年のお正月には 900円台で取引されていたEOSですが、4月末から5月頭にかけて2200円を超えて急騰し、過去最高額を記録しました。記事執筆時点では1300円前後にまで落ち着いています。 2018年6月頭にはメインネットのローンチもあり、市場がEOSへの期待をしているのもわかります。 EOSのトークンスワップはウォレットに入れたままだと無価値になってしまうので気をつけましょう。 EOSメインネット移行が近づくも、ユーザーの65%が未登録。EOSトークンスワップ方法まとめ - CRYPTO TIMES 0x (ZRX) 0x(ゼロエックス)はざっくり説明すると、分散型取引所をプロトコルを利用して、簡単に構築できるようにするプロジェクトです。このプロジェクトにより、イーサリアムのブロックチェーン上に存在するトークンはほぼ手数料無料で相互に交換することが可能になります。 0xは年始には100円未満で取引されていましたが、1月後半から2月にかけ、大きな成長をみせ、250円程度まで上昇しました。その後一度下落し、50円程度まで値を戻しますが、5月に再度高騰し、現在は120円程度で取引されています。 最近では、0x Protocolを利用した分散型取引所も非常に増えてきているので今後も要注目です。 VeChain (VEN) VeChainはブロックチェーンの書き換えができないという特性を活用して、商品の真贋を判定するサービスを提供しています。真贋判定と聞くとブランド物に使われるとイメージしがちですが、VeChainは他にも政府関係機関や農家、ロジスティクスなど幅広い分野での活用が見込まれています。 VeChainは昨年末から急激に成長し始め、1月後半には300円から1000円まで急騰し、過去最高値を記録します。その後も昨年に比べて高いレンジで取引されており、記事執筆現在は345円となっています。 VeChain / VEN メインネット移行に伴うトークンスワップ情報 - CRYPTO TIMES TRON (TRX) Tronはエンターテイメントコンテンツをブロックチェーンを使って世界に広めることでクリエイターを支援し、新たな働き方を提案するプロジェクトです。簡単にいえばYoutubeやShowroomなどといったプラットフォームと同じようにエンタメシステムの再構築を目指しています。 昨年Tronは0.5円にも満たない価格で取引されており、なかなか日の目を見ることはありませんでした。しかし、複数の取引所に上場されるという噂から急騰し、今年の正月には23円ほどにまで上昇しました。一月以降は相場も落ち着き、現在の6円前後という価格になっています。 それでも0.5円という価格からの上昇率を考えたらかなり伸びている通貨ではあります。 まとめ いかがでしたでしょうか?数多くのアルトコインがビットコインやメジャーな通貨の下落トレンドに流され右肩下がりな相場が続いた2018年前半ですが、そんな中でも成長していた通貨は存在します。 僕自身、どんな局面でも本当に価値のある通貨を見抜けるようにまだまだ勉強する必要があると感じました。 それでは、また次回の記事でお会いしましょう!

特集・コラム
2018/05/29【プレスリリース】Everus紹介
Sponsored by Alibabacoin Foundation EverusテクノロジーSdn. Bhd.はマレーシアを拠点とするブロックチェーン技術企業で、国内だけでなく世界中にこの技術を提供することを目指している。最近では、韓国の仮想通貨市場に参入し彼らを惹きつけようと尽力している。産業において世界を変えるソリューションを提供するために創り上げられた製品を利用し、Everusは消費者が仮想通貨やブロックチェーンをサービスとして享受できるような遷移を提供しようと試みています。 EverusはEthereumのブロックチェーンネットワーク上のERC20の規格を採用した独自の仮想通貨であるEVRを持ちます。トークンはC-CEX、Cryptopia、Kuna、LocalBitcoinCashなどの取引所で扱われており、現在では、合計枚数の10億枚のうち8,000万枚以上が市場に流通しています。 今年の4月、Everusはマレーシアの中央銀行(BNM)から、資金洗浄防止とテロ資金対策(AML/CFT) – 電子通貨(セクター6)ポリシーに準拠した報告機関であるとの認識を受けました。BNMからこうした認識を受けることは、すべてのEverusのトランザクションが透明性を持ち規制当局による規制を順守する事実に加えて、消費者の更なるEverusに対する信頼につながります。 EVRのウォレット所有者は、自身の保有するEVRを今年の4月にリリースされたEverusモバイルウォレットアプリ内で追跡、送金、受け取り、保管をすることができます。iOSとAndroidの両方で利用可能なEverusウォレットのアプリがあれば、いつでも簡単にアカウントにアクセスすることができます。このアプリの重要な強みはそのセキュリティ面での機能になります;モバイルウォレットは顔認証機能と指紋認証機能の両者に対応した最先端の技術に対応しています。加えて、Everusはモバイルアプリにオールインワンのユーティリティ決済処理機能を搭載することで、Everusのモバイルアプリの多様性を向上させることに成功しています。これによりEverusのモバイルウォレットアプリ利用者は公共料金や携帯料金の支払いなどをウォレット内で完結させることができます。 主に投資の目的で利用される他の仮想通貨と異なり、EverusはEVRを決済の実用的な手段として普及させその立ち位置を確立することを目的としています。Everusは現在、商人からなる世界的なネットワークを構築しており、これによりEVR保有者間でのユーザビリティ向上を目指しています。 Everusのエコシステム拡大の方策として、Everusはまもなく仮想通貨のデビッドカードをローンチします。これにより、Everusウォレット利用者は世界中の広いネットワークの中でEVRを支払いに利用することができるようになります。このデビッドカードの目的は何かを購入する際に便利に支払いが行えることだけでなく、潜在的なユーザーがEVRを利用し始めることで仮想通貨に関する理解を深め、より広くこれを採用させる目的があります。 Everusはマイニングの愛好家向けにマイニングサービスにも取り組んでいます。Yottahashサービスは、場所の提供からリグのセットアップやメンテナンス、規制の順守など、運営における要件を克服するソリューションを探しているマイニング愛好家に対して提供されます。 EverusはYottahashをアジアで最大級の仮想通貨マイニングファームへ成長させることを目指しています:更に、マイニング愛好家の方々向けに信頼のできるマイニングのリグを多岐にわたり販売しています。Yottahashは100%の透明性、24時間の監視、追跡可能性を保証します。 Everusの重要なプロダクトが完成すると、EVRには更なる取引量の増加とユーザビリティに関する大きな変動が見られると考えられます。現在はまだ初期段階ですが、Everusのマイルストーンが実現されれば、東南アジアにおける最もダイナミックなブロックチェーン企業となるでしょう。 お問い合わせはこちら:[email protected] より詳細な情報はこちら: www.everus.org ソーシャルメディアのフォローもお待ちしています: Facebook: https://www.facebook.com/everusworld/ Twitter: https://twitter.com/everusworld Instagram: https://www.instagram.com/everusworld/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/13359278/

特集・コラム
2018/05/28週刊少年クリプト創刊号発刊!世界初!仮想通貨の漫画雑誌爆誕!
CRYPTO TIMESでもコラムを書いているコンソメ舐め太郎さんが編集長となり、5/25(金)20:00に世界初の仮想通貨漫画雑誌の「週刊少年クリプト」が創刊されました。 値段は500円、noteから購入できます。 週刊少年クリプト創刊号 ちょっと中身を見てみたいという方向けにのお試し版は、以下より立ち読みが可能です。 週刊少年クリプト創刊号 お試し版 週刊少年クリプト!気になる内容は? さて、気になる内容ですが、以下のようなコンテンツが掲載されています。 順に紹介していきたいと思います。 クリプトヒーローズ 絵 : おにぎりまん(@onigiriman1998) 脚本:コンソメ舐め太郎(@Ether_takuya) 仮想通貨をモチーフとしたキャラクターの王道格闘漫画 仮想通貨のヒーローたちが敵をバシバシ倒していく姿は必見 ~暗号戦線~ クリプトくん 絵:D@クリプトくん(@D_Critical ) 脚本:Koishi(@kitraum ) 仮想通貨に関する過去の歴史や事件を紹介した漫画 主人公のクリプトくんによるかわいい解説で、初心者でも仮想通貨の歴史を学べます。 マンガでわからなくなる?仮想通貨 絵:風野なつき(@Kazanock ) 脚本:いおんぶてぃっく(@BticIon ) 仮想通貨の概要をチャーミングなキャラクターとともに学べる漫画 無茶苦茶な性格の“はかせ”と冷静沈着な“かれんちゃん”によるクスっときてしまうやり取りが面白いです。 ゼロからはじめるBTCFX 絵:えびてん(@Quubelcrypto ) 脚本:コンソメ舐め太郎(@Ether_takuya) Bitcoin FXをやりたい方、実際にやっている方向けの解説漫画。 マスターノード、その生き様 (記事) 記者:ぐぬぐぬたい(@pukupuyotai ) 仮想通貨における“マスターノード”がどういったものか、その一生を説明した記事。 ぐぬぐぬたいさんは日本におけるマスターノードの第一人者であり、右に出るものはいません。 スマホではじめるDapps ~イーサエモン~ (記事) 絵:コイモン(@soco_illusts ) 記者:はやた(@hayata_sc ) Dappsゲーマー第一人者のはやたさんが、スマホでのEtheremonの始め方を解説。 挿絵にはコイモンもいて、非常に楽しくDappsゲームをはじめることができる内容になっています。 気になる反応は? https://twitter.com/nanzyara/status/1000081264337084416 https://twitter.com/kichigaineco/status/1000516766240509953 https://twitter.com/cancan___can/status/1000045620441235456 https://twitter.com/sabachancoin/status/1000173313434374144 https://twitter.com/blooyetii/status/1000448221158805505 日本だけでなく、海外からも反応があるようです。すごい! まとめ 以上、週刊少年クリプト創刊号の紹介でした。 今までになかった分野への挑戦であり、これからどのように展開していくのか非常に気になりますね。 初心者の方も、仮想通貨に精通している方も読める非常に面白い雑誌になっています。 さて、次回は編集長でもあり、CRYPTO TIMESでもコラムを書いてくれているコンソメ舐め太郎さんへのインタビュー記事もあるとか、ないとか。 乞うご期待!!!

特集・コラム
2018/05/27仮想通貨市場のデータ分析を一目で確認できるツール QUBE(キューブ)100 INDEXの紹介
こんにちは!Shota(@shot4crypto)です! 本記事では、だいぶ前に情報収集をしていた際に見つけて今でもリサーチの際に活用している、仮想通貨市場の動向を簡単に掴むことのできるQUBE100INDEXを紹介していきます。 QUBEを使うことで、多数の通貨の価格の変動や数値化された市場の楽観悲観など、取引の際(特にスイングトレードなど)に役立つ多くの指標を手に入れることができます。 中国系のサービスやプロダクトは、知名度が低いだけで実際は相当優れているものが多く存在するので、是非本記事を参考に活用していただければと思います。 QUBE(キューブ)100 INDEX とは? Qube100Indexとは、ユーザーの取引を円滑にするために中国にて開発がされているプラットフォームであるQubeのサービスのうちの一つです。 本チャンのサービスでは、上の画像にあるような大手取引所の取引をQubeのアカウント一つで一括で管理したり、各取引所の資産を合算したポートフォリオなどを作成することができるようです。 一方で、今回紹介するQube100Indexは以下の情報をチェックできるサービスをすべて無料で利用することができます。 無料で利用可能なサービス Qubeのインデックス カテゴリー(産業)別の出来高や価格変動の一覧 カテゴリー(産業)別の24時間での高騰、低落銘柄の一覧 通貨別の詳細な情報 銘柄別の24時間以内の市場心理とそのパーセンテージ 一般 / 市場 / 投資家の市場心理のパーセンテージとそのインデックス 取引所の基本情報と、メイカー / テイカーの取引手数料、通貨ペア数など 最近ですと、NEO系のAlphacat(中国)などAIを使った市場分析などのサービスが出てきていていますが、上述の通りQube100Indexが提供する幅広く、かつ独自の情報は市場を分析する上で非常に役に立つものだと考えています。 更にこれらすべてがブラウザ上で利用している間、数秒単位のリアルタイムで更新されていきます。 次項で、上述のQube100Indexが提供するサービスの中からいくつか、その指標が何を意味するのか、ユースケースなどを紹介していきます。 Qube100Indexのユースケース カテゴリー(産業)別のデータ 本記事執筆時(2018/5/26現在)ですと、ここ一週間の相場の全体的なトレンドは下落基調ですが、通貨のカテゴリー別でみた場合、一部のカテゴリーではBTC以上に下落している一方で、その他のカテゴリーではその下落幅が0%に近いものなど様々です。 つまり、カテゴリー別で見た場合、どこに資金が流れているのか、市場に参加する投資家はどのようなプロジェクトに目をつけているのかなど、ある程度データに基づいた推測をすることができるようになります。 上の画面は、実際のQube100Indexの画面で、通貨がQubeのチームによってカテゴライズされ、その情報がズラリと並んでいます。 まず、注目していただきたいのは【Price Change 7 Days, %(7日間の価格変動率)】の部分です。 【Price Change 1Hours, %(1時間の価格変動率)】や【Price Change 24Hours, %(24時間の価格変動率)】では、サンプルとなるデータの時間軸が短いためあまり大きな差異を見て取ることができません。 しかし、7日間の部分に注目すると、カテゴリ別に大きな差が出ていることがわかります。 ここ7日間で言うと$BTCの価格変動率が約-9%程度ですので、画像の 【6 Dapp Decentralization】 【8 Side Chain Concept】 【16 Data Storage】 系のカテゴリの下落が極端に緩やかである(=BTCの下落に対し強めの値動きをしている)ことがわかると思います。 また24時間の出来高も【24 Hour Volume $Million】の部分で見ることができるので、そこからいまは何系の銘柄 / トークンがアツいのかを一目でチェックすることができます。 通貨別データ 通貨別の詳細なデータを見るのは、CoinMarketCapが有名で実際に取引所や通貨の情報が載っているため優れていると思いますが、市場を俯瞰するという意味ではQube100Indexの提供するこのサービスの方が優れていると思います。 以下が通貨データの一覧画面になります。 [caption id="attachment_9840" align="aligncenter" width="696"] 執筆時点で1624種類の銘柄に対応(CMCと同数)[/caption] 通貨データに関してはCoinMarketCapやLiveCoinWatchなどの競合がいるので、まずはこれらの競合と比べたメリットとデメリットを紹介していければと思います。 Qube100Indexのメリット 1時間~7日間の価格変動をパーセンテージで比較することができる 時価総額や出来高のランキング、その他数字のデータが圧倒的に見やすい リアルタイムで更新が行われる Qube100Indexのデメリット ある程度銘柄を熟知していないとググる羽目(二度手間)になる 各通貨の詳しい情報の網羅性がない(投資家向け) 適当なタブでソートを行うことができない Qube100Indexはこれらの点を考慮すると、メジャー銘柄や時価総額上位のコインの状況を把握においてに優れていると言えます。 理由として、Qube100Indexは、すべてのデータが順位やパーセンテージで表示され、さらに上昇下落に関してすべて色で確認できるため、パフォーマンスのいいものと悪いものを一目で確認することができるからです。 また、マイナー銘柄に向かないと考える理由は、通貨のティッカーや名前以外に情報を調べることができないので、リサーチが『値動きデータ→通貨の情報』というプロセスになってしまう上、通貨の情報を知りたい場合、CMCの方が単純に優れているからです。 仮想通貨市場の心理データ おそらく仮想通貨の市場心理に関してQube100Indexが提供する以上に詳細かつ包括的なデータを無料で提供しているプラットフォームは存在しません。 (何かございましたら追記させていただきますのでお申し付けください) Qube100Indexが提供するサービスでは、普段僕らが目にする仮想通貨のファンダ情報やおそらくそれ以上のソースからデータを楽観 / 悲観 / 中立にカテゴライズし、これを視覚化してまとめられた一覧データを一挙で確認することが可能です。 画像上部の【Bullish Information】は主に好材料となる情報を表し、逆に【Bearish Information】は悪材料となる情報を表します。 視覚化されている部分で直近24時間の好材料、中立材料、悪材料のパーセンテージを確認することができ、そのスコアが数値化されているので、例えばこれが前日と比べて高いものとなっていれば、市場が上向きであることがわかります。 画像下部では、この好材料、中立材料、悪材料のパーセンテージとスコアが通貨ごとに算出されており、さらにその横には直近1時間 / 24時間の値動きが表示されています。 具体的な使い方はといいますと、第一に上述の通り、仮想通貨市場全体の心理を確認することで、大まかな上昇下落の予測を立て合理的な取引ができるようになります。 例えば、仮想通貨の市場心理のインデックススコアが-10.0であるときに、短期足ベースのチャートを見てロングを入れてしまうようなリスクを極力減らすことができるようになります。 第二に、通貨ごとのファンダメンタルズを完全に網羅して精査する、という人間を超越した技を会得する必要がなくなります。 (ここで、ニュースや上場のアナウンス、提携などのニュースが出た後にそれがチャートに少なからず影響する点は前提としています。上場アナウンスとそのチャートへの影響に関する記事も是非読んでみてください。) この前提をもとに考えると、最速で手に入れた膨大な量のファンダは少なからず直近の価格に影響することが予測できると考えられます。 本記事執筆段階でのBCHのスコアを見ていきましょう。 他の通貨と比較した際に、3つのインデックススコアが他のどの銘柄よりも高く算出されていることがわかると思います。 また、Qube100Indexのリアルタイムで更新されるという性質を生かしてこの変動に注目することで、初動を捉えて取引を行うことができるかもしれません。 shota 現在はまだ先物やデリバティブ商品がマイナー銘柄に浸透していませんが、dydxのようにこれを体系化するようなシステムがでてくれば更に役に立つかもしれません! まとめ 本記事では、中国のQube100Indexと呼ばれる便利なサービスを紹介させていただきました。 Twitterなどで主に情報収集をされている方ですと、日本の界隈の狭い心理しか見えない状況や情報を手に入れるまでに時差が発生してしまうといった状況が考えられると思います。 そのため、デイトレードなどをメインにされる方にはベストなツールだと思います! 僕もあまり使いこなせている自信はありませんが、ぜひ使ってみてください!

特集・コラム
2018/05/26ペトロってどうなったの?ベネズエラの仮想通貨事情を時系列で全部解説!
Crypto Times公式ライターのYuya(@yuyayuyayayu)です。 今回は、定期的に話題にあがるベネズエラの仮想通貨事情についてまとめてみたいと思います。 ベネズエラ政府は昨年12月に石油で裏付けされた仮想通貨「ペトロ」を発表してから、技術面の発展や外交などを通して着実に世間の注目を集めています。 当記事では、同政府による仮想通貨関連の出来事を時系列で完全網羅したいと思います。 ベネズエラの仮想通貨事情・時系列 2017-12-03: 石油裏付け型仮想通貨「ペトロ」公表 昨年12月、ベネズエラ大統領Nicolás Maduro氏はペトロのローンチを会見で発表しました。 ベネズエラでは不穏な政治状況をめぐり法定通貨であるボリバルが暴落、ハイパーインフレーションに陥っています。 価格安定性を謳うペトロは新たな信頼性のある通貨として政府が導入を試みているものです。仮想通貨ではありませんが、過去に新たな通貨の導入によりインフレを脱出した国は存在します。 そんな政府の思惑とは真逆に、ペトロは国内外からその信用性を疑われています。 同通貨は石油を裏付けることによって通貨の価格安定性を図っていますが、その担保である石油と信頼性皆無のボリバルではフェアな取引が成り立たないため裏付けの意味がないと懸念されています。 加えてペトロの価格設定法や価格安定メカニズムは極めて不透明で、実際には政府の都合の良いように価格がコントロールされてしまうのではとも問題視されています。 また、この集権性が懸念される中でPoWが採用されていたことも批判の対象になっていました。しかし、以降イーサリアム、のちにNEMへとプラットフォームも転々と変えていきました。 2018-02-20: プレセールスタート 否定的な意見とは裏腹に、ペトロはプレセール初日で7億3500万ドルを売り上げたとされています。 Maduro大統領がペトロの大成功を讃える一方で、同氏を独裁者だと批判する米国はこれに危機感を覚え、経済制裁等への意向を強め始めます。 2018-03-20: 米国がペトロ購入を禁止 ペトロがロシアの支持を受け始める中、米国はいよいよ市民にペトロの購入を禁止します。これにより、ベネズエラは経済制裁を迂回して外貨を貯蓄することが難しくなりました。 さらに、独裁政治に対する経済制裁として多数のベネズエラ政府関係者のドル資産を凍結し始めます。 2018-04-29: インドにペトロでの石油購入を提案 ベネズエラはロシアに加え、さらにインドからも支持を得ようとする動きに出ます。 政府は、インドに「ペトロで購入すれば石油を30%安くする」と提案します。ペトロの開発チームは実際にインドを訪れるなどもしており、ペトロの普及に大きく力を入れている様子がわかります。 これを受け、インドの仮想通貨取引所Coinsecureはペトロを販売することを決定します。しかし、インド国内でも同通貨に対する批判は続きます。 2018-05-05: ユースバンク開設・ペトロゴールド発表 Maduro大統領は、2000万ペトロ(約12億ドル相当とされる)を元手に学生や若者向けの銀行を開設することを表明します。 反政府活動を活発に行う若年層をターゲットに、ペトロによる経済効果をいちはやく目に見える形にしようとしていることが伺えます。 しかし、同通貨の信用の低さは拭えません。この発表では、Maduro大統領は各大学にマイニングファームの開設を促すともしていますが、NEMベースのペトロにはマイニングという概念が存在しません。 また、同氏はここで新たに金を裏付けにした通貨ペトロゴールドをローンチする方針であることも明かしました。 2018-05-07: パレスチナとペトロファンド開設・取引所リスト公開 Maduro大統領はペトロの信用を上げる新たな外交策として、パレスチナと戦略提携を組み、2000万ペトロの準備金を元手に両国が共同で経営するペトロファンドを開設すると発表しました。 また同時に、ペトロが販売される16の仮想通貨取引所が正式に公開されました。 まとめ 以上がベネズエラの仮想通貨事情の時系列まとめになります。これからさらに進展があるに連れ、都度更新していければと思います。 ペトロの将来には米国、ロシア、インド、中国などの大きな経済母体からの支持・反対や、国内での反政府活動など様々なファクターが関係してくるので、今後の進展に要注目です。 ICO詐欺?救済?ベネズエラの仮想通貨「ペトロ」の概要と問題点とは - CRYPTO TIMES

特集・コラム
2018/05/25モナコイン、バージ、ビットコインゴールドのハッキング情報まとめ
特にメジャーなハッキング事件が起こらなかった四月・五月上旬でしたが、ここにきてモナコイン(MONA)、バージ(XVG)、ビットコインゴールド(BTG)のハッキングが次々と発覚しました。 この記事では、それぞれの通貨への攻撃の手口や被害状況、公式の対応などについてまとめたいと思います。 攻撃の手口 今回のハッキングを受けた通貨は全てProof of Workを採用した通貨で、51%攻撃と呼ばれる手口によって被害に遭いました。 Proof of Workでは、マイニングにより承認されたブロック(トランザクションの集まり)は他のネットワーク参加者全員に共有されることになっています。 同時にいくつか異なるブロックが承認されてしまった場合、様子を見て、その後により多くのブロックが繋がった方が正しいブロックのチェーンとして採用されます。 51%攻撃とは、ネットワーク全体の50%以上のマイニング能力を保持するハッカーが非公開で自分に都合の良いブロックのチェーンを作り上げ、タイミング良く公開するという手口です。 これを悪用すると、現在公開されているチェーン上で送金を行い、その後に送金を行なっていないチェーンを公開し、それが採用されることで送金をなかったことにできます(ダブルスペンディング)。 この攻撃が成功する確率は、ネットワーク全体の50%以上の処理能力を得ることによりほぼ100%成功すると言われています。これが「51%攻撃」と呼ばれる理由です。 モナコイン(MONA) 2013年に誕生した日本初の仮想通貨ですが、今月13日から15日にかけて51%攻撃を受け、約9万ドル相当の被害が生み出されたもようです。 今回の攻撃では、モナコインをLivecoinなどの取引所を通して別の通貨に両替し、非公開チェーンを公開して取引を無かったことにするという手口であったようです。 犯人は未だ特定されておらず、全ハッシュレート(マイニング能力)の約57%を保持していたと推定されています。 また、犯人は同様の手口でのハッキングを半年ほど試みていたと考えられおり、モナコインのマイニング難易度調整システムを悪用しようとしたものとみられます。 モナコイン公式は、攻撃の存在を公式に認めたのち、51%攻撃が既存のProof of Workではどうしても解決できないものであるとコメントしています。 現状ではサービス提供側で入金の承認数を上げる以外に有効な手段はありません。 PoWコインである以上は避けられない問題でもあるので、PoS等への移行も視野に入れていく必要があると考えています。 — monacoinproject (@tcejorpniocanom) May 17, 2018 バージ(XVG) 4月に2千万XVG(時価約1億2千万円相当)の不正獲得事件が起こって間もないバージですが、今月22日、システムのバグを悪用した51%攻撃の被害に遭ったもようです。 今回のハッキングは、同通貨のマイニングプロトコルの欠陥性が悪用されたもので、ブロックの順番を表すタイムスタンプと呼ばれるものが偽装されたことが原因とされています。 これにより、ハッカーは短時間で3500万XVG(約2億円相当)を不正に獲得したと推定されています。 今回のハッキングはBitcointalkのユーザーが指摘したものですが、バージ公式はこれを認めておらず、攻撃は他の原因により生じたと言及しています。 同通貨は大手アダルトサイトの支払い手段として導入されるなど実用化に力を入れていますが、今回の二度目のハッキング事件によって信頼性が大きく疑われています。 ビットコインゴールド(BTG) ビットコインのGPUハードフォークとして登場したビットコインゴールドですが、今月16日から18日にかけて51%攻撃を受け、その被害額は約39万BTG(約2億円相当)に登るとされています。 モナコインと同様、不正にコントロールされたBTGは仮想通貨取引所と犯人のものと思われるウォレットに両方に送金されたことになっているとのことです。 ビットコインゴールドのデベロッパーは、今回の不正なチェーンのサイズが最大22ブロックにも及んだことから、採用を決定するチェーンの長さを50まで延長するようにと助言しています。 まとめ 以上がモナコイン、バージ、ビットコインゴールドのハッキング事件のまとめとなります。 5月24日現時点での情報ですので、追加・変更等あれば随時更新していきたいと思います。
















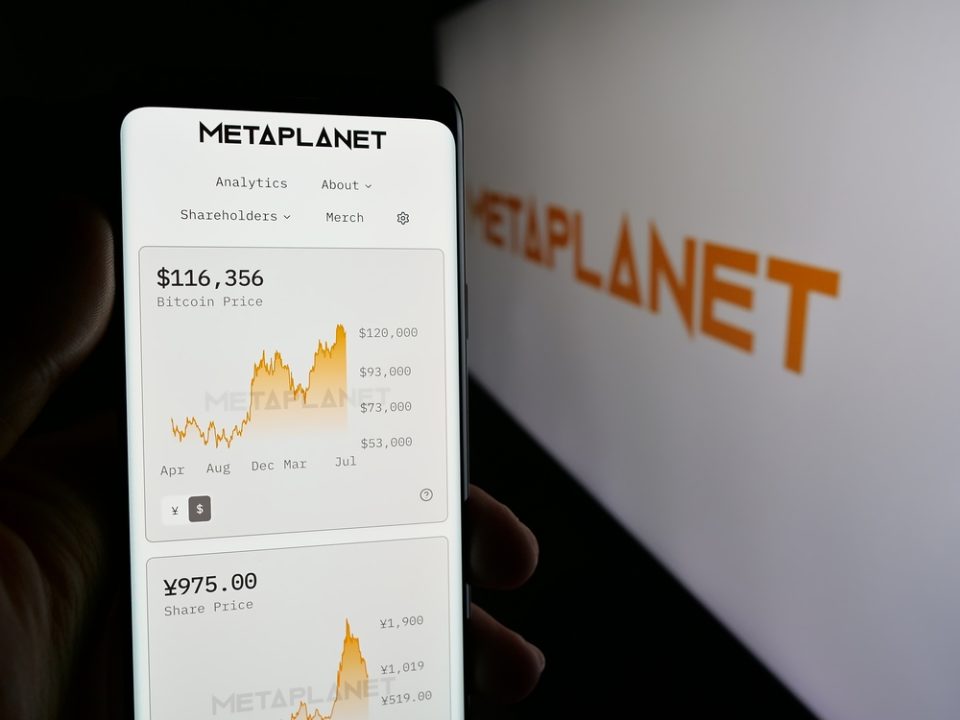

 有料記事
有料記事


