2017年5月に仮想通貨への投資を開始。ブロックチェーンや仮想通貨の将来に魅力を感じ、積極的に情報を渋谷で働く仮想通貨好きITリーマンのブログを通じて発信するように。
最近書いた記事

ニュース
2021/01/13暗号通貨取引所Coincheck(コインチェック)が3年ぶりとなるテレビCMを1月14日より放映
2021年1月14日より、東京、大阪、愛知などの26都府県でテレビCMの放映を開始することを公式リリースにて発表しました。今回Coincheck社が放送するテレビCMは2種類となっており、「ロケット」篇と「タイトル」篇の2種類となっています。 [caption id="attachment_56858" align="aligncenter" width="800"] ロケット篇CM / Coincheckより引用[/caption] 「ロケット」篇では、『宇宙戦艦ヤマト』のイントロパートを軸に、久しぶりに広告展開するコインチェックに対する期待感、ワクワク感をロケットの発射、飛行シーンで表現。 「タイトル」篇では、伝えたいメッセージを1カットで視覚化することで、ボーッと観ていても、どのタイミングからCMを観ても、メッセージが届くように。オンエアでスルーされないように、名曲『宇宙戦艦ヤマト』のイントロパートでキャッチーさを担保。 今回のCMでCoincheckが放映するのは、2017年12月で出川哲朗氏が出演したCM以来、約3年ぶりのCMとなります。 Coincheckの登録方法はこちらの記事より、登録は下記より可能です。 Coincheckの公式HPはこちら 記事ソース : Coincheck
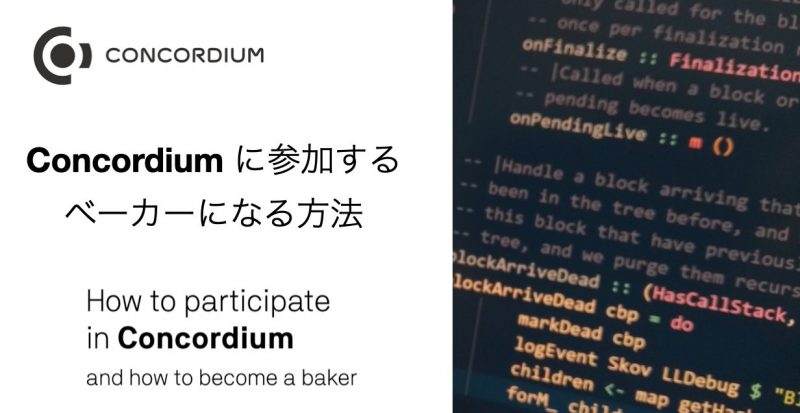
ニュース
2021/01/12PoSブロックチェーンConcordiumに参加する方法、ベーカー(ブロック生成者)になる方法
Concordium はパーミッションレス・プロジェクトとして、ネットワークの安全性確保のためにコミュニティへノードとして参加することを求めます。それにより、コミュニティは報酬を得ることができます。 この記事では、Concordiumネットワークの中核となる概念と重要な特徴と、それに付随するメカニズムと報酬の仕組みを説明します。 PoS Concordiumは Proof-of-Stake レイヤー1のブロックチェーンで、二層のコンセンサスアプローチを採用しており、プロセスの最終確定の部分を独立したサービスに変えることができます。 このようにしてプロトコルを設計したことで、必要なセキュリティを確保し、ブロックを確定する際には適切な速度を実現しています。参加者は、ブロックを検証し、最終確定するように要求されます。 この努力に対して、参加者はGTUと呼ばれるConcordiumのネイティブトークンで報酬を受け取る権利があります。 まとめると、ネットワークには3つの役割が定義されています: ベーカー ファイナライザー デリゲーター(メインネットでは提供しない) ベーカーは、ブロックの生成とコンセンサスの実行により、ネットワークを維持する責任があります。ファイナライザーは、ブロックの最終確定とネットワークの安全性確保に責任を負います。デリゲーターは、後述するようにGTUを委任することでベーカーをバックアップします。 参加者と役割 参加するためには、ノード実行者は潜在的なベーカーになるために1GTUをステークする必要があり、以下で説明するように、全GTUの0.1%を保有していれば、ファイナライザーとなります。 以下の実体は、メインネットローンチ時のトークノミクス・システムに含まれています: 利用者はアカウント (B) を所有し、ブロックチェーン上で取引を実行し、トランザクション手数料を支払います。 Concordium財団は、トークノミクス・システムの全体的な管理と責任を負っています。Concordium財団は、アカウント(A)で、新規マイニング(3)とトランザクション手数料(1)の10%に相当する開発費を受け取ります。 ベーカーは、新しいブロックを作成します。所定のスロットに次のブロックを作成する権利は、抽選により各ベーカーに割り当てられます。各ベーカーがベーカーのバリデーターアカウント(G)にステークしたGTU量(すなわち、期間ごとにロックアップされた量)によって当選確率が決定されます。 自分のアカウント(G)に一定以上のGTUを保有しているベーカー(初期設定では全GTUの0.1%に設定されている)は、ブロックの確定を担当するファイナライザーにも自動的になります。 報酬メカニズム 報酬の仕組みは、2つの活動から生まれます: 利用者によるトランザクション手数料(1)と(2)の2つ。 ミンティング・プロセスから作られたばかりのGTU(3)、(4)、(5)。 トランザクション手数料からのベーキング報酬 Concordiumのユーザーは、トランザクションを行うたびにトランザクション手数料(GASとも呼ばれます)を支払います。トランザクションの複雑さによって手数料が決定されます。手数料はGTUで支払われます。 トランザクションのコストはユーロベースで安定するように設計されているため、企業や他のユーザーはブロックチェーント・ランザクションのコストを予測して計画することができます。 Concordiumの目標は、トランザクション量に応じて0,010ユーロからと低いトランザクション手数料を設定することで、企業がプラットフォームを利用する際のコスト競争力を高めることです。 すべてのGASは、ベーカー(8)に報酬として支払われるまでの間、保持されます。GAS(2)の90%はGASアカウント(F)に支払われます。残りの10%のGASは、開発費の一部として財団(A)に支払われ(1)、財団が運営資金を調達し、ブロックチェーンの普及と更なる発展を可能にしています。 ミンティングからのベイキング&最終確定報酬 新しい検証済みブロックごとに、新しいGTUが生成されます。新たに造られたGTUは、以下のように分配されます: 10%(3)をコンコルディウム財団(A)に支払います 60%(4)を検証報酬アカウント(D)に支払います 30%(5)を最終確定報酬アカウント(E)に支払いします 2つの報酬アカウント(Dと(E)に支払われたGTUは、検証報酬(6)または最終確定報酬(7)としてベーカー(G)に支払われるまで保持されます。 ベーキング報酬は、前回の報酬支払い以降に各ベーカーが作成したブロックの数に基づいてベーカー間で配分されます。最終確定報酬は、ファイナライザーでもある全てのベーカーに分配されます。最終確定報酬は、それぞれがステークしたGTUの数に基づいて分配され、最終確定証明がブロックに追加された時点で分配されます。 ベーカーは、自分の報酬を自動的にステーク合計に追加させるか、ステーク合計に報酬を追加しないかを選択することができ、アカウントから自由に報酬を送金することができます。ベーカーがアクティブの場合、ステークされたGTU量はアカウントにロックされており、移動することはできません。 委任 Concordiumのネットワークが成長し安全性が確保された後、意欲的な委任プログラムが開始されます。このプログラムにより、GTU保有者はGTUをグローバルプールに委譲することが可能になります。 オフチェーンおよびレイヤー2委任ツールは、メインネット開始から始まります。 スラッシング ここでは、Concordiumチェーンの'スラッシング'について説明します。ここでいうスラッシングとは、ベーカーやファイナライザーが望ましくない行動を取らないようにするための一連の措置のことです。 Concordiumは、以下のような行為を望ましくないものとみなし、その行為は罰せられます: 二重署名:スロットでブロック抽選に当選したベーカーは、同じスロットで複数のブロックを公開すること。ベーカーは公開されたブロックに署名することに注意してください。 無効なトランザクション:ベーカーが無効なトランザクションを含むブロックを公開すること。 一貫性のない最終確定メッセージ:Afgjort の最終確定プロトコルでは、ファイナライザーはすべてのメッセージをマルチキャストします、すなわち、すべてのパーティに同じメッセージを送信しなければなりません。ファイナライザーは、異なるメッセージを送信する場合には不正な動作をしています。 2つの最終確定されたブロックに署名すること。これは、一貫性のない最終確定メッセージの特殊なケースです。 Concoridumはどうやってこれらの行動を検知するか? どのノードも二重署名を検出することができます。ノードが二重署名のインスタンスを検出した場合、そのノードは、同じスロット内の2つのブロックを指し示して、告発の特別なトランザクションを送信することができます。ブロック上の署名は、不正な動作をするベーカーを識別します。 無効なトランザクションを含むブロックが目撃者として機能します。そのようなブロックを検出したノードは、チェーン上でそれを報告することができる。ブロック上の署名は不正なベーカーを識別します。 ファイナライザが一貫性のない最終確定メッセージに気づいた場合、そのファイナライザー(上記のベーカーと同様)は両方のメッセージを含む特別なトランザク ションを送信することができます。これらのメッセージは不正な動作をするファイナライザーによって署名されているので、これは公によって検証することができます。 望ましくない行動にどう対応するか? さまざまな対応が考えられます。ソフトウェアのバグなどで正直なユーザーを罰することを避けるために、軽い罰が適用されます。もし、ベーカー/ファイナライザーの望ましくない行為が見つかった場合、その当事者は24時間から168時間の間、深刻さに応じて、ベイキングや最終確定を停止させられます。 パーティは望ましくない行為を発見しても報酬を得ることはできません。これにより、不正なパーティがそのような行為を意図的に実行し、自分たち(または共謀しているパーティ)を非難して報酬を集めることを防ぐことができます。Concordiumノードは、報告として行動できます。 トークン量とパラメータ ローンチ時には、10,000,000,000のGTUでジェネシスブロックが設立します。新しいGTUのマイニングが行われるため、時間の経過とともに存在するGTUの総数は増加していきます。GTUのマイニングはトランザクション数の増加に伴って減少するように設定されています。 成長率は、最初は10%で、トランザクション数が一貫して1.7TPSを超えると6%に減少し、4.2TPSで5%、10.4TPSで4%、16.7TPSで3%、33.3TPSで2%となります。 ベーカーになるためには、ノード実行者は多くは2エポック待つ必要があります。また、ベーカーをやめるためには、ノード実行者は7日間待ってステークのロックを解除する必要があります。 Concordiumベイカーになるための最初のステークを手に入れるには? 2021年第2四半期に設定されたConcordiumメインネットローンチまでは、GTUの"獲得 "とメインネットへの参加は、Concordium インセンティブ・テストネットに参加するしかありません。 2020年10月に開始されたテストネット3では、ノード実行者やテスターに配布するGTUは、最大1000万まで用意されました。2000件以上の提出があり、Concordiumの大勢のコミュニティがテストネット3に参加しました。 Concordiumは2021年1月20日に4つ目で最後のテストネットを開始し、ミッションをクリアするテスターに配布されるGTUは最大1,500万となります。 参加詳細については、近日中に公式発表を行います。Concordium財団は、投資のプライベートラウンドを実施しています。ブロックを検証するための最初のステークを取得することで、プロジェクトに"投資"することを希望するプロのノード実行者を歓迎します。 このプライベートラウンドの詳細については [email protected] までご連絡ください。 公式 Discord 開発者コミュニティ日本語 https://discord.gg/md7ebQr8 公式 Twitter 日本コミュニティhttps://twitter.com/Concordium_JP

ニュース
2021/01/06HashHubが最大年利10%の暗号資産貸出サービス「HashHubレンディング」の先行利用ユーザーの募集を開始
株式会社HashHubが1月6日に暗号資産の貸出サービス「HashHubレンディング」の先行利用ユーザーの募集を開始しました。 HashHubレンディングでは、ユーザーが保有している暗号資産を貸し出しながら、貸借料を得ることができるサービスとなっています。 発表時点での対象通貨として、BTC、ETH、DAIの3種類の通貨が対象となっており、BTC6%、ETH6%、DAI10%の年利となっています。 CRYPTO TIMESではHashHubレンディングに関して代表である平野さんにもお話を伺っています。 HashHubレンディングでは、2021年1月現在、先行公開となっており、ユーザーは100万円相当以上の暗号資産をお申込みのユーザーのみに利用を限定しています。 正式公開は2021年初夏を予定しており、様々な機能を企画して鋭意リリース準備中となっています。 HashHubレンディングの特徴 HashuHubレンディングでは下記の4つが特徴となっています。 国内最高水準の年率 HashHubレンディングの年率は国内最高水準。魅力的な年率で資産の活用が可能。2021年1月時点での募集年率はBTC6%、ETH6%、DAI10% 貸しておくだけ、毎月増える ユーザーは貸出暗号資産に対して毎月貸借料が付与されるため、複利的な効果が得られる。また毎月自動で再貸し出しされるため、ユーザは一度レンディングを始めれば特に何もしなくても暗号資産を増やすことが可能 解約手数料なし、好きな月に引き出し可能 HashHubレンディングでは、長期間のロックアップや解約手数料が発生しない。ユーザーは柔軟なポートフォリオ管理が可能。契約は1ヶ月ごとの自動更新となっており、ユーザーはいつでも引き出し申請が可能。引き出し申請をしてから翌月末までがレンディング期間となる。 セキュリティ重視のサービス設計 HashHubレンディングを行うチーム内でのセキュリティ体制、返還時のホワイトリスト必須化など万全な状態で管理しており、AMLにも対応。 HashHub CEO平野淳也氏へのインタビュー - 今回のレンディングはDeFiとは違い、ユーザーがHashHubに預けて運用する形ですが、これはDeFiの日本法周りの観点からこのようなスキームになったのでしょうか。 日本法周りの観点も理由の一つですが、理由はそれだけではありません。 マスユーザーに使われるサービスを長期的に目指すためにはユーザーが自身でウォレットを保有する形式は望ましくないと思っています。 これは一部の人のDeFiの価値観とは異なるかもしれませんが、私たちはDeFiを誰でも使える世界を想像していますが、その世界においても誰もが使うべきであるとは思っていません。 私たちがつくるサービスはDeFi、あるいはパブリックブロックチェーンの可能性を前提にしていますが、よりマスアダプションするサービスを長期的に作っていきたいです。 - レンディング時のリターンを出すための運用方法などはブラックボックスになっているのでしょうか?CREDの破産申請などもニュースで騒がれていたこともあり、どのような運用を行うかを透明にするのかが気になりました。 いわゆるCeFiのサービスがどのように透明性を担保するかは私たちにとっても重要な課題です。ユーザー目線からは経営陣や株主くらいしか判断がつかないのが現状です。 顧客向けにHashHubレンディングとしてレポートを定期的に報告することなどは考えています。またすぐにではないですが、外部の監査機関を頼ることもありえるでしょう。 -取引所以外からのレンディングサービスも増えてきたと思いますが、日本の今後の暗号通貨関連のレンディングを含むビジネスは発展するとお考えでしょうか?それを踏まえて、HashHub Lendingの目指すべきところを教えて下さい。 とても可能性があると思います。 BTCやETHはアセットクラスとして地位を高めています。 将来、私たちの子供の世代に「お父さんは法定通貨100%で貯金をしていた」などと話したら馬鹿にされる時代がくるはずです。 現代では、法定通貨の価値は希釈し続けており、貯金という概念はあるのに貯金するのに適したアセットがありません。そこで出てきたのがBTCなどでアセットは誕生したので、私たちがそれを貯蓄してインカムゲインを得れるサービスを提供します。 編集長新井からのコメント 2020年の夏には暗号通貨市場ではDeFiが非常にブームになったことも有り、レンディングのサービスが暗号通貨保有者の関心を集めたことも記憶に新しいです。 日本国内においても、Coincheckやbitbankの取引所がレンディングのサービスを提供していましたが、2020年の春以降は取引所以外の仮想通貨事業者がレンディングサービスの提供を始めてきています。 今回HashHubが提供するHashHubレンディングでは、日本国内において最高水準の年率を受け取ることができます。 各自で管理するDeFiとは異なり、HashHubにあずけて運用して貰う形になりますが、DeFiのことがわからないというようなユーザーも、最高水準の年率を獲得できることから選択肢の一つになりうるのではないでしょうか。 海外でもBlockFiのような企業に預けて利率を得るレンディングサービスは非常に流行っており、日本においてもこのような流れが来るのは当たり前と言えるでしょう。 暗号通貨を持ち続けるユーザーにとって、レンディングによる運用が一つの選択肢になるような未来が今後作られていけば良いなと考えています。 その中で、DeFiではない管理者が存在するレンディングサービスにおいては、カウンターパーティリスクも存在するため、どのような運用方法が行われるかなどの透明性も今後の課題であるといえます。

ニュース
2020/12/30CT Analysis第13回レポート『NFT周辺の解説と業界の現状, 動向調査レポート』を無料公開
CRYPTO TIMESが提供するリサーチレポートコンテンツ『CT Analysis』が、第13回の配信レポートとして『Ethereum周辺のレイヤー2 スケーリング 概要と動向』を無料公開しました。 過去のレポートは全て無料でCT Analysisホームページ ( https://analysis.crypto-times.jp )よりダウンロードができます。 ※1度メールアドレスを登録された方は、レポートが公開される度に登録メールアドレス宛に最新レポートが届きます。(隔週目処) CT Analysis 第13回ダウンロード 第13回『CT Analysis』が提供する無料レポート『NFT周辺の解説と業界の現状, 動向調査レポート』に関して 第13回目となる今回のレポートでは、NFT周辺の解説と業界の現状に関してをまとめています。 2020年DeFiと並んで大きくブームとなったNFTですが、それを取り巻くプロジェクトやエコシステムが大きく成長した1年でした。 NFTはあらゆるメタデータを保管することが可能であり、 これはあらゆるデータをNFTとして表現できることを意味しています。 現状、 NFTが持つこの唯一性とブロックチェーンの持つ永続性から、所有権理などの分野、資産性の観点からアートやゲームアイテムなどの活用に向けた 取り組みが世界的に進められており、今回のレポートではNFT関連のユースケースからプロジェクトの動向までをまとめています。 日本でもゲームのアセットにNFTが利用されることが多いですが、世界的に見るとゲーム以外にもデジタルアートやコレクタブル、DeFiなどへの活用と多く使われています。 CT Analysisについて 2020年2月12日より暗号通貨/ブロックチェーン専門メディアCRYPTO TIMES ( https://crypto-times.jp )が2月12日より提供開始した、暗号通貨/ブロックチェーンの分野に特化したリサーチレポートコンテンツです。 今後、暗号通貨/ブロックチェーン分野は更に注目が集まることが予想されるものの、技術者から投資・事業家まで様々な参加者がおり、各々の求める情報は見つけづらく、また議論は英語で行われることが多いため、リサーチコストが高くなる傾向があります。 CT Analysisでは、2年間業界に携わりながら運営してきた知見やデータを活用して一般ユーザーから事業者まで、幅広いデータ・分析需要に応えることを目標として、専門性とわかりやすさを追求したリサーチ・レポートを提供していきます。 また、パートナー企業の強みを生かしたリサーチレポートも提供しており、オンチェーンデータやオフチェーンデータ、クリプト市場に関するセンチメントデータ、ユーザーの予測を機械学習で最適化したデータなどの情報を使ったレポートの配信も予定しています。また、これらは日本だけでなく、世界各国の情報も取り入れたコンテンツの配信を予定しています。 CT Analysis ホームページ

ニュース
2020/12/16ビットコイン / $BTC が2017年より3年の時を超えて20,000ドルを突破
BTCが2017年末より3年のときを超えて、2万ドルを2020年12月16日22:46に突破しました。 一時的にCoinbaseやBinanceでは20400ドルを超えるなど、2017年時に記録した価格の最高値を更新しました。 Binanceなどの取引所や、業界の著名人の多くからも今回の2万ドル突破に関しては称賛の声があがっています。 https://twitter.com/binance/status/1339204276791349249?s=20 2017年のBTCの価格高騰における大きな違いは、個人か企業かで購入者の主体が変わったことがあるのではと考えています。 2020年の夏以降、Square社やMicroStrategy社,MassMutual社など大手企業がBTCを大量に購入していたり、PayPalが4通貨の取り扱いを開始するなどの好ニュースが多く出てきました。 今後もBTCを含めたクリプト市場から目を離せないことは間違いないでしょう。

ニュース
2020/12/14KYCと規制要件を満たす匿名性と解除、エンタープライズ・ブロックチェーン Concordium
Concordiumは、デンマークのオンライン銀行 Saxo Bankの創業者で元CEOのLars Seier Christensenによって開始されたプロジェクトです。プライバシー(自分の情報を管理できる権利)を中心にしたデジタルIDのソリューションを提供し、世界中の異なる管轄区域に拠点を置くアイデンティティ・プロバイダや匿名性リボーカーに対応することができます。 ユーザーは、ConcordiumのGlobal IDアプリケーションを使って、第三者のプロバイダによるKYCプロセスを経る必要があります。プロバイダはユーザーの個人情報をオフチェーンで保存し、ゼロ知識証明をブロックチェーン上に格納します。ユーザーがGlobal IDアプリケーション内でアカウントを作成すると、ゼロ知識証明によりアカウントのアイデンティティを確認できます。 また、Concordiumは、暗号化された転送をサポートしています。送信者が十分な暗号化された残高を持っていることを確認するために、トランザクションにはゼロ知識証明(zk-SNARK)が含まれています。これにより、これらの値を明らかにすることなく、転送の金額が送信者の暗号化された残高を超えていないことを全員が確認できます。 最後のテストネットであるTestnet4を2021年1月にリリース、Concordiumメインネットのローンチは4月に予定しています。 Concordiumでは、最近日本で人材を採用し、日本語でのウェブサイトの公開、SNSでの情報発信を開始しています。 日本語ツイッター:https://twitter.com/Concordium_JP Mediumでの日本語記事:https://medium.com/concordium-japan 日本語公式ウェブサイト:https://japan.concordium.com 基礎研究のサイエンスパートナー デンマークのオーフス大学と、ブロックチェーンの研究センター COBRA(Concordium Blockchain Research Center Aarhus)を設立、COBRAの20人の研究者や科学者が、ブロックチェーン技術、基礎となるブロックチェーン理論、暗号技術の研究を行っています。 さらに、スイス連邦工科大学チューリッヒ校、コペンハーゲンIT大学、インド理科大学院大学の研究員がプラットフォームのひとつひとつの機能設計に協力しています。 Concordiumのオペレーションズチーム CTOのTorben Pedersenは、Pedersen Commitment の生みの親です。 このコミットメントは、秘密の共有スキームを構築する際に、秘密の共有を受け取る人が自分の共有を一人で確認(例えば、誰にも相談せずに)できるようにする、コミットメントのスキームになります。 CEOの Lone Fønss Schrøderは、28歳の若さでStar AirのCEOに任命された後、Maerskの女性最高位の地位の経歴を持ちます。彼女はスカンジナビアのビジネス界でトップの女性の一人に数えられ、イケアやボルボ・カーズなどのグローバル企業の役員を務めています。 Concordiumの戦略アドバイザーには、スカイプの元COOのMichael Jacksonやデンマークの元首相であり元国連事務総長のAnders Fogh Rasmussen、そのほか、チームにはワールドクラスの暗号研究者、優れたソフトウェアエンジニア、様々な分野や業界、政府機関やグローバル企業経験を持つ人々が集まっています。
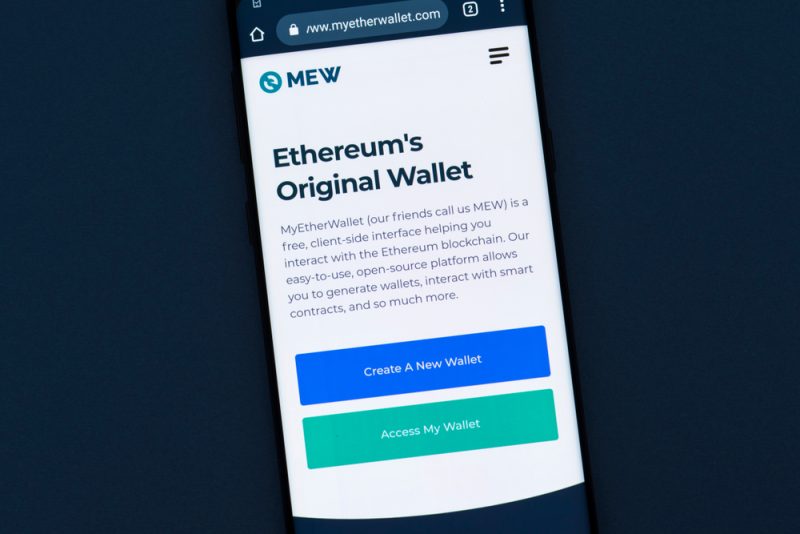
ニュース
2020/12/09MyEtherWalletでEthereum2.0のステーキングが可能に
Ethereumの専用ウォレットであるMyEtherWalletが、Ethereum2.oのステーキングに対応することを発表しました。 Ethereum2.0のステーキングはバリデーターノードを32ETH Depositした後、技術的要件が必要でしたが、MyEtherWalletの発表内容によるとユーザーがノードの立ち上げなどは不要で、ステーキング可能なサービスを提供するものとしています。 https://twitter.com/myetherwallet/status/1336406985093181440?s=20 今回のMyEtherWalletではStaked Protocolと統合して、ウェブアプリやAndroidアプリで、ETH2のステーキングに対応します。 Ethereum2.0は12月7日に創設者であるVitalik Buterin氏のTwitterで総供給量の1%が既にDeposit Contractに預けられたことがツイートされており、現在でもDeposit量は増加しています。 MyEtherWalletのように秘密鍵をユーザーが所持した上でStakingできるサービスは今回が初めての提供となっています。他にも、現在Binanceなどの主要取引所ではETH2.0のStakingの代行も開始しています。 記事ソース : MyEtherWallet Medium

ニュース
2020/12/08bitFlyerにてTezos / $XTZ の取り扱いを12月8日より開始
bitFlyerが12月8日よりTezosのトークン $XTZ の取扱いを開始しました。現在、Tezoの提供するXTZは国内の暗号資産交換業者において取扱いがなく、bitFlyerが国内初の取扱いとなります。 https://twitter.com/bitFlyer/status/1336163859422347267?s=20 また、bitFlyerではTezos の取扱いを記念し、 本日 12 月 8 日(火)午後 1 時から「テゾス取扱開始記念!抽選で 15 名様に最大 5 万円が当たるキャンペーン」を開催しており、2021 年 1 月 7 日(木)午後 11 時 59 分(日本時間)までの開催となっています。 Tezosの取り扱いについては以下の通りです。 暗号資産名:Tezos(テゾス) ティッカーシンボル: XTZ 取扱い開始日時:2020年12月8日 13時 bitFlyerの登録は下記より登録ができます。 bitFlyerの登録はこちら 記事ソース : bitFlyer

ニュース
2020/12/07Ethereum2.0のDeposit Contractに総供給量の1%がロックされる
Ethereum創設者であるVitalik Buterin氏のTwitterによると、Ethereum2.0にETHの供給量の1%が既にDepositされたことをツイートしました。 https://twitter.com/VitalikButerin/status/1335729572633923584?s=20 Ethereum2.0の起動要件として、11月24日から16384以上のバリデーターが32ETH以上をEthereum 2.0メインネットへデポジットする必要がありました。Ethereum2.0ではこれを11月24日に達成し、12月1日に正式リリースされています。 ユーザーは32ETHをステーキングして、イーサリアム2.0バリデータとして参加することで、年間最大21.6%の報酬を獲得することができるようになります。現在、供給量の1%は約83万ETHとなり、17%程度のAPRを獲得することが可能となっています。 また、Ethereum2.0のValidatorは技術的要件も高くなっているため、ETHを単なるDepositすればよいわけでは有りません。これらを解決するべく、現在Binanceなどの主要取引所ではETH2.0のStakingの代行も開始しています。

ニュース
2020/12/01Ethereum2.0が2020年12月1日21時に正式リリース、ジェネシスブロックが生成される
Ethereum2.0が12月1日21時に正式リリースされました。Ethereum2.0の起動要件として、11月24日から16384以上のバリデーターが32ETH以上をEthereum 2.0メインネットへデポジットする必要がありました。 今回はEthereum2.0のメインネットの始動に先立ち、公開されたデポジット用のスマートコントラクトには11月24日に必要相当量のETHが集まり、無事21時にGenesis Blockが生成されました。 今後、ユーザーは32ETHをステーキングして、イーサリアム2.0バリデータとして参加することで、年間最大21.6%の報酬を獲得することができるようになります。今回Ethereum2.0 Beacon Chainでは、Serenityとして今後開発されていきます。 今回、Genesis Block生成時には881,248ETHが集まっており、本コントラクトに預けられたETHは開発がフェイズ2にいくまでにロックされるため、ステーキングに参加するユーザーは注意が必要です。 今回のリリースに先駆け、色々なコミュニティでEthereum2.0を祝うYoutubeのLiveが放送されたりとBitcoinの半減期と同じような盛り上がりを各地で感じます。 参考 : beaconcha.in










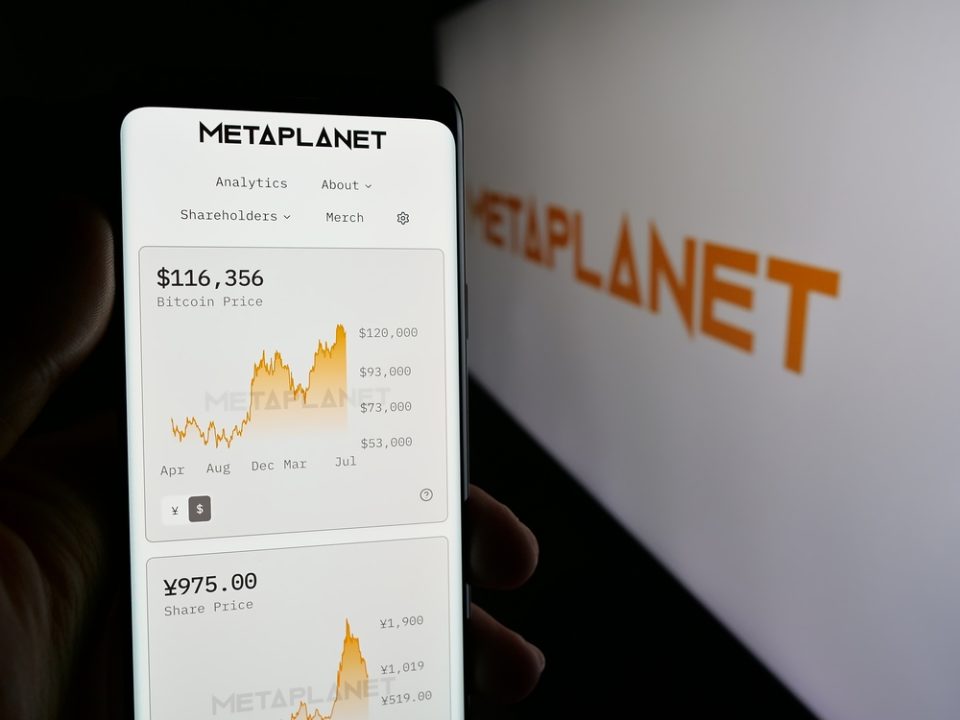

 有料記事
有料記事


