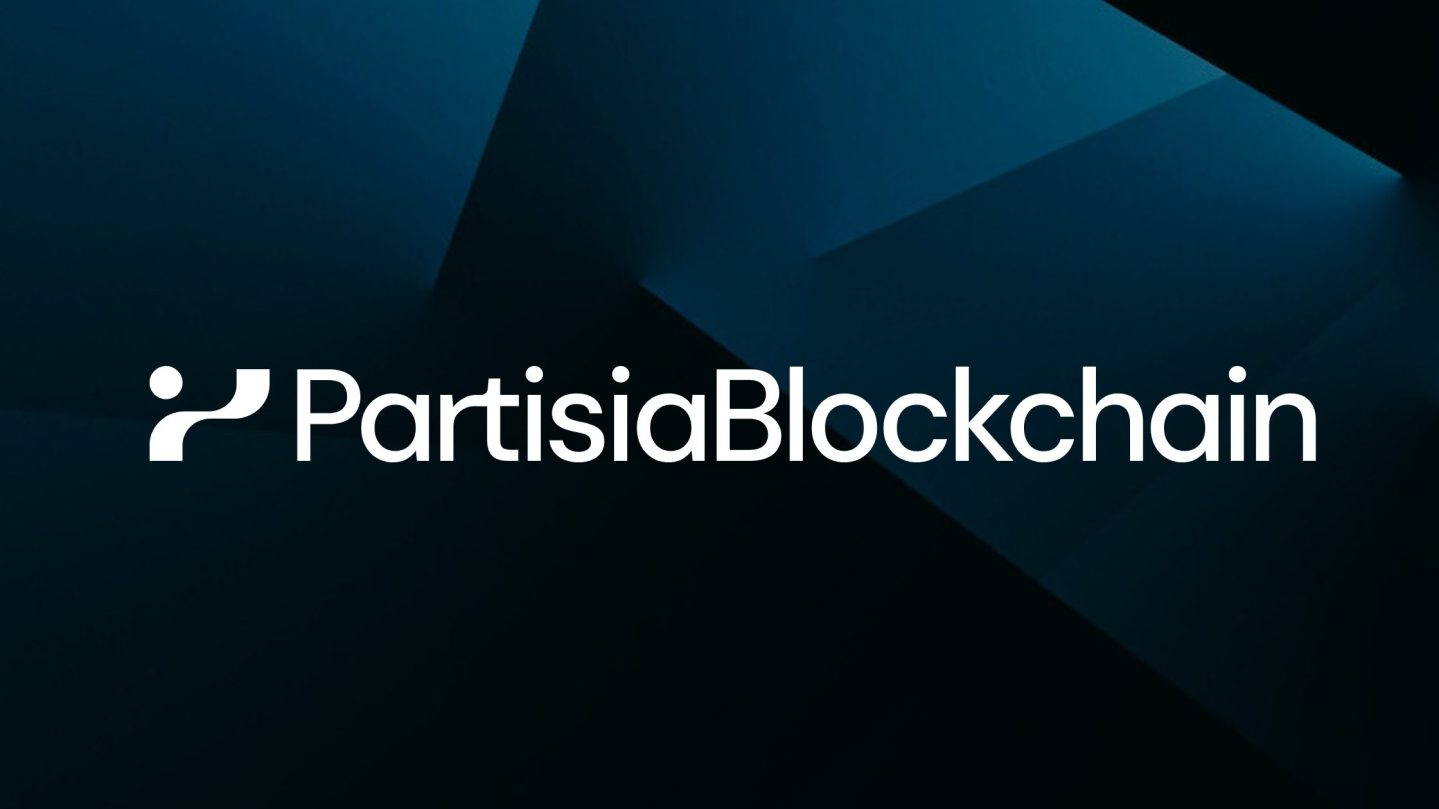
プロジェクト
2024/03/17パブリックチェーンにプライバシーをもたらす「Partisia Blockchain」とは?|2500万$MPCのエアドロップも実施
Partisia Blockchainは、ネイティブにMulti-Party Computation (MPC) の計算をサポートし、プライバシーを確保した上でブロックチェーンを活用できるようにするプロジェクトです。 このプロジェクトは数年間にわたって順調に開発が進められており、過去には2,000万ドル以上の資金調達に成功しています。 上記以外にも3月19日にKuCoin , MEXC, bitfinex , gateなど複数の取引所へトークンの上場が決定している点や現在2,500万$MPCのエアドロップを実施中であるなど注目すべき点が多くあります。 この記事では、そんなPartisia Blockchainについて、以下の点から詳しく解説します。 この記事のまとめ ・Partisia Blockchainはプライバシーを保護できる ・MPCを活用 ・シャーディング、BYOCなどの注目点も ・2,500万$MPCのエアドロも開催中 プライバシー保護が可能な「Partisia Blockchain」とは? [caption id="attachment_109513" align="aligncenter" width="696"] 引用元:Partisia Blockchain[/caption] Partisia Blockchainは、MPCやZK関連の計算をサポートしたプライバシー保護が可能なブロックチェーンです。 ブロックチェーンは透明性が高く、さまざまなユースケースに応用される一方で、過去に記録されたデータは広く公開され、その後変更できません。 そのため、プライバシー保護が要求されるようなケースでは、ユースケースが限られてしまいます。 Partisia Blockchainは、MPCやZK関連の計算をサポートして、上記の課題を解決可能です。 Partisia Blockchainは、スイス当局の監視下にあるPartisia Blockchain財団を中心に開発されており、財団のメンバーはMPCや暗号領域の実業家や教授といった経験豊富なメンバーで構成されています。 Partisia Blockchainの3つの注目点 ・2,500万MPC配布のエアドロップを実施 ・2,000万ドル以上の資金調達に成功 ・Polygonと提携済 Partisia Blockchainの注目点について、上記3つの観点で紹介していきます。 2,500万MPC配布のエアドロップを実施中 Partisia Blockchainは、2024年2月から2,500万MPCが配布されるエアドロップを実施しています。 Partisia Blockchain's exhilarating AirDrop is now LIVE, with 25 million $MPC tokens up for grabs! 🔥🎁 Your support means the world to us, and this is our way of saying thanks! 🙌 Join now ➪ https://t.co/YSEbI53uHh#MPC #PartisiaBlockchain pic.twitter.com/7LrifGIUgA — Partisia Blockchain (@partisiampc) February 1, 2024 詳細は後述しますが、Partisia Blockchainにブリッジし、トランザクション量やアクティブな利用したユーザーなどを対象に2,500万枚のMPCトークンが配布されます。(やり方までスキップする) 複数の取引所へトークンが上場予定であることも公式発表されており、プールサイズも大きいことから大きな注目が集まりつつあります。 前述したPolygonとの提携でサポートされたPartisia Blockchain上のMATICの残高は、エアドロップの影響で6,000%以上増加しました。 2,000万ドル以上の資金調達に成功 Partisia Blockchainは、セールなどを通じて資金調達に成功しています。 2021年5月には以下のような企業から、2,000万ドル以上の資金調達に成功したことを発表しました。 Ausvic Capital P2P.org Kosmos Bitscale Gate.io Labs 巨額の資金調達は仮想通貨の業界において注視されることが多いです。 Partisia Blockchainについても、十分な額を調達できていると言えるでしょう。 Polygonと提携済 Partisia Blockchainは、2022年5月にPolygonとのコラボを発表しました。 Announcing a major privacy collaboration with @0xPolygon, the leading decentralized Ethereum scalability solution provider. @Partisiampc is bridging our #MPC zero-knowledge smart contracts to the Polygon Network and Developers! Read more on our blog: https://t.co/UHWyLYNDBP pic.twitter.com/xYLWGoEHgk — Partisia Blockchain (@partisiampc) May 26, 2022 Polygonの開発者は、Partisia Blockchain上で行ったプライベート計算を実行し、作成したスマートコントラクトを専用のブリッジを通し、Polygon上のアプリとリンクできるようになります。 上記によって、プライバシーを重視した計算が可能になり、新たな可能性を持つスマートコントラクトの作成ができます。 さらに、Partisia Blockchain上でのMATICのサポートも発表している点も注目しておきたいポイントです。 Partisia Blockchainの特徴や技術 Partisia Blockchainの特徴や技術について以下から解説していきます。 ・MPC ・BYOC ・主要な機能と利点 ・今後の開発ロードマップ Partisia Blockchainは、サポートしてる領域や機能が多いです。そんな中で、注目したい点をいくつかご紹介していきます。 MPC Partisia Blockchainの核となる技術の1つが、MPC(Secure Multi-Party Computation)です。 MPCとは、複数の主体がそれぞれの入力データを秘匿したまま計算が行える技術です。計算プロセス全体を通して入力データは秘密のままですが、出力される計算結果は正確なものとなります。 複数の主体間で入力データを開示したくないものの、何らかの計算を行いその結果を得たいというニーズがある場合にMPCが活用されます。 ブロックチェーン分野においては、MPCを活用することで以下のようなユースケースが可能になります。 プラバシーを保護したスマートコントラクトの作成 秘密鍵の保護 MPC計算を実行できる機能としてアプリなどに提供 Partisia BlockchainはMPCを含め、上記のようなプラバシーを重視した機能を実装、提供可能です。 BYOC Partisia Blockchainには、BYOC (Bring Your Own Coin) と呼ばれるコンセプトを持つ機能があります。 Partisia Blockchainでは、他のすでに流動性のある通貨 (ETH・BNB・USDC) を使用して、ガス代の支払いに活用可能です。 Partisia Blockchainに持ち込まれた各通貨は、Partisia Blockchain上で使用可能なものに変換されます。各通貨はオラクルノードによって、ネイティブチェーンと一致するものであると保証されます。 主要な機能と利点 Partisia Blockchainでは、上記のような技術を含めてさまざまなものを活用して、以下のような主要な機能・特性が組み込まれます。 Poseidon:証明可能なファーストトラックコンセンサス Iris:シャーディング Hermes:担保付きトークンブリッジ Athena:ZKレイヤー Demeter:MPC as a Service Apollo:パブリックとプライベートスマートコントラクト Mithra:信頼の市場 PoseidonとIrisは、チェーンの基盤となるコンセンサスとセキュリティ・スケーラビリティに関する領域です。 Poseidon・irisでは、BFTモデルに改良を加えたコンセンサスと、シャーディングの完全なサポートで高い処理能力を実現します。 Hermesはブリッジと相互運用性に関連する機能で、ネイティブで高いセキュリティを持つブリッジが実装されています。 Athena・Demeterは、ZK・MPCによるプライバシーを保護した計算の実行や提供に関する部分で、ApolloはMPCなどを活用したスマートコントラクトの領域になっています。 Mithraは、前述した計算や機能を提供するノードに対する新たなインセンティブに関する領域です。 各機能や領域ごとに開発の段階が存在し、徐々に実装されている予定になっています。 Partisia Blockchainのユースケース ・ランダムな数の生成 ・データエコノミー ・フロントランニングの防止 Partisia Blockchainが挙げているユースケースを中心に紹介していきます。 ランダムな数の生成 [caption id="attachment_109528" align="aligncenter" width="1024"] 引用元:Partisia Blockchain[/caption] ランダムな数の生成は、Partisia Blockchainのユースケースの1つです。 ランダムな数は、さまざまな場所で活用されています。 身近な例では何らかの抽選やルーレットのようなランダム性が必要な事例では、乱数が必要です。しかし、ランダムな数の生成は非常に難しく、人間であってもプログラムであってもバイアスが発生します。 また、ランダムな数を生成する主体が単一のシステムに依存している場合、腐敗のリスクも発生します。 Partisia BlockchainとMPCを通してランダムな数を取得でき、腐敗やバイアスのないランダムな数を生成可能です。 また、開発者はスマートコントラクトを活用して、上記の特性を持つ機能を各用途に合わせてカスタマイズもできます。 データエコノミー Partisia Blockchainは、プラバシーを保護した新たなデータエコノミーを実現可能です。 現在、データエコノミーは大きな産業になっており、Partisia Blockchainによると2700億ドルを超える規模を持ちます。 一方で、SNSやWEBサービスによるデータエコノミーは、プライバシーを無視した活用や、中央集権的な管理などさまざまな問題がみられます。 ブロックチェーンを活用すると分散性の高い方法でデータを管理できますが、プライバシーは確保されません。 前述した通り、MPCを活用すると、入力されたデータを秘密にしたまま、データの計算が可能です。 上記の特性を活かし、Partisia BlockchainとMPCを活用するとプライバシーを保護したまま、分散的な方法でデータの活用ができます。 フロントランニングの防止 Partisia Blockchainでは、フロントランニングの防止も可能です。 ブロックチェーンでは、トランザクションが処理されるまでタイムラグがあり、一時的にMempoolなどに待機します。 このMempoolがフロントランニングの標的となっており、トランザクションの内容を確認し、有利な取引を行う機会を発見することに活用されています。 MPCを活用すると、トランザクションの内容を隠したまま、計算が可能です。トランザクションの詳細は、処理された後にしか分からないので、フロントランニングを行えません。 この点はDEX・DeFiの文脈で、大きく役立つと考えられます。 Partisia Blockchainの使い方とエアドロップ参加方法 [caption id="attachment_109861" align="aligncenter" width="737"] 画像引用元:Partisia Blockchain[/caption] ・ブリッジする方法 ・エアドロの算定基準 ・$MPCの概要 Partisia Blockchainのエアドロップは、ブリッジなどが条件になっているので、ブリッジの方法やトークンの概要をチェックしていきましょう。 ブリッジする方法 まず、Partisia Blockchainのコチラのブリッジを行うページにアクセスしてください。 ウォレットを接続し、さまざまな承認を要求する旨がウォレットから出てくるので、すべて承認してください。 以下のような画面が出てくるはずなので、任意の資産で「DEPOSIT」を選択してください。 (ネイティブトークン以外は、「INTERACT」から一度承認してから、送付してください) 以下のように金額を入力する画面が出てくるので、入金する額を入力し、ウォレットで承認を行います。 ブリッジできる通貨は、以下のとおりです。 ETH BNB MATIC Polygon USDC Ethereum USDT また、前述したBYOCがあるため、ガス代のネイティブコインなどは不要です。 エアドロップの算定基準 Partisia Blockchainは、エアドロに伴って2,500万$MPCをプールしています。 エアドロップの算定基準になるのは以下のとおりです。 ブリッジの金額 ガス代 毎日のアクティブな利用 上記のような点を考慮して、2,500万$MPCプールから各自配布されることになります。 また、公式のエアドロップページでは、コミュニティに参加することが推奨されています。 開始時期は2024年2月からとなっていますが、終了時期は不明です。エアドロップの詳細はコチラ。 $MPCの概要 $MPCはPartisia Blockchainのネイティブトークンで、ステークしたりノードへの追加報酬などに使用されます。 配布割合は以下のとおりです。 プライベートセール:35% パブリックセール:25% エコシステム:20% チーム:15% リザーブ:5% 以下のような形で、4年間で50%程度が段階的に配布されます。 [caption id="attachment_109540" align="aligncenter" width="919"] 引用元:Partisia Blockchain[/caption] 配布される$MPCは、まだ上場していません。 本来では2023年末に向けて上場できるように予定していたようですが、少々遅れが発生しているようです。 ただし、3月に上場が間近であることが旨が公表されており、今後複数の取引所へ上場される運びとなっています。 The wait is over! 🚀🔥❗ Partisia Blockchain's MPC token will be listed on multiple exchanges soon! This milestone reflects the token's recognition and demand in the blockchain industry. Stay tuned for updates, and read the official announcement ➪ https://t.co/4kpZUzISRq pic.twitter.com/bYDn0FwQB9 — Partisia Blockchain (@partisiampc) March 13, 2024 正確な上場日時などは各取引所からアナウンスがあると考えられるので、エアドロップと合わせて最新情報をチェックしておきましょう。 今後の開発ロードマップ [caption id="attachment_109524" align="aligncenter" width="872"] 引用元:Partisia Blockchain[/caption] 前述した通り、Partisia Blockchainが焦点を当てている領域は多岐にわたります。 そのため、各領域(ブロックチェーン・スマートコントラクト・相互運用性)ごとに開発のロードマップが公表されています。 メインネットの"フェーズ6"まで設定されており、直近の"フェーズ4"は2023年6月に、既存機能に新たな改良などを加えた"フェーズ5"は2024年6月に予定されています。 "フェーズ6"のメインネットは2025年6月に予定されており、まだ各機能の開発がすべて完了している訳ではありませんが、開発自体は進んでいます。 まとめ この記事では、Partisia Blockchainについて、さまざまな点から解説しました。 Partisia Blockchainは、メインネットを段階的に公開しており、まだまだ開発されて機能が拡張していくプロジェクトです。 エアドロップやトークンの上場など、今後もさまざまなイベントがあり、注目点が多いと言えるでしょう。 Sponsored Article by Partisia Blockchain ※本記事はPartisia Blockchainさまよりいただいた情報をもとに作成した有料記事となります。プロジェクト/サービスのご利用、お問い合わせは直接ご提供元にご連絡ください。

プロジェクト
2024/03/14NFTの詐欺・盗難対策 -「Delegate」を活用して資産を守る方法
– 著者:Henry(@HenryWells1837) 先日、ビットコインが史上最高値を記録し、市場全体が昨年に比べて顕著な活気を見せています。このような強気市場の状況下では、様々なシーンで盛り上がりを見せる一方でトークンの貸し出しや流動性供給などのDeFi活動を対象としたハッキングやNFTがウォレットから盗まれるなどの事件も増加する傾向にあります。 前回の強気相場では、一般事業会社の参入というのは目立ちませんでしたが、今回の相場では多くの事業会社が参入することが予測されます。それに伴い、多くの法人で生成されるウォレットアドレス内に高単価のNFTが保有される可能性があるなかで、これらの資産を守るための対策方法が十分に共有されていないケースも考えられます。 本記事では、市場の活性化がもたらすリスクに焦点を当て、特にNFTを対象とした犯罪から資産を守るための対策として、分散型プロトコルDelegateの重要性について解説しました。Delegateプロトコルは、個人および法人がNFTを安全に保管しながら、その利用価値を最大限に引き出すための戦略的なツールとして注目されています。 リスク対策の基本 リスク管理には一般に四つの基本的なアプローチがあります。これらのアプローチをNFTの盗難や紛失リスクの観点から具体的に見ていきましょう。 回避 (Avoid) NFTを保持するウォレットが不特定多数のウェブサイトとの接続を避けることで、リスクを回避します。この方法では、安全性を高めるために、ウェブサイトへのアクセスを制限します。 低減 (Reduce) 複数のNFTを一つのウォレットに集約させずに、それらを複数のウォレットに分散させることで、リスクを低減します。これにより、一つのウォレットが攻撃を受けたとしても、全てのNFTが同時に失われるリスクを避けることができます。 受け入れ (Accept) 一部の低価値NFTに関しては、管理コストやリスク対策の労力を考慮して、その紛失を受け入れることも一つの戦略です。これは、リスクとコストのバランスをとるための現実的な選択肢となります。 移転 (Transfer) NFTを保有するウォレットから別のウォレットへの権限移転を行うことで、リスクを転嫁します。これにより、もし攻撃者が元のウォレットにアクセスしたとしても、直接NFTを盗むことができなくなります。 最も効果的な対策は「回避」と「移転」 NFTの盗難や紛失リスクに直接対処するためには、「回避」と「移転」が最も効果的なアプローチとなります。 特に「回避」は、ウェブサイトへのアクセス制限により実践が難しい場合があるため、リスク対策としての「移転」の適用が推奨されます。この戦略では、NFTの保護を強化しつつ、所有権の管理の柔軟性を保持することができます。 今回は、NFTの盗難や紛失リスクに対する「移転」戦略に焦点を当て、その具体的な方法と利点について詳しく解説します。 このアプローチにより、NFTの安全性を保ちながら、デジタル資産の管理と活用のバランスの最適化が可能になります。 ホットウォレットとコールドウォレット リスク対策の話になる前に、「ホットウォレット」と「コールドウォレット」の違いについて復習しましょう。これらの詳細については、筆者が運営しているAir Drop Guide3.0を参照ください。 ウォレットには、オンラインでアクセス可能な「ホットウォレット」と、オフラインで保管される「コールドウォレット」の二種類があります。ホットウォレットはその利便性から日常的な取引に適していますが、セキュリティリスクも伴います。一方、コールドウォレットは物理的に隔離されているため、ハッキングのリスクが非常に低いです。 コールドウォレットへのNFT移転による対策 NFTの盗難を防ぐための一つの方法は、NFTをコールドウォレットに移動させることです。しかし、日常的に取引を行う場合には、ホットウォレットの利便性を犠牲にしなければなりません。ここで「Delegate」プロトコルの利用が有効な戦略となります。 Delegateプロトコルの概要 Delegateは、ユーザーがコールドウォレットに保管しているNFTの保有権限を、ホットウォレットに委任できるようにするプロトコルです。 これにより、NFTの安全性はコールドウォレットによって保護されつつ、ホットウォレットを通じた日常的な取引で利便性を損なわずにNFTを使用できます。現在は、約18万4千のウォレットアドレスがDelegateを利用しており、以下のプロジェクトなどで導入されてます。 Azuki Opensea Yuga Labs HV - MTL Manifold Phaver Collablandその他、公式ドキュメントを参照。https://docs.delegate.xyz/ 利用する前の注意点 当該プロジェクトは、コールドウォレットに自身のNFTを格納し、それに紐づいたホットウォレットで日々のトランザクションを実行することでNFTのハッキングリスクをゼロにできますが、例えばエアドロップの対象となるためには、そのプロジェクトがDelegateを導入していることが条件となります。 例えば、コールドウォレットに特定のNFTを保有、それに紐づいたホットウォレットでLayer 2の特定プロジェクトを利用し、その当該プロジェクトがトークン発行される際の条件がプロジェクトの利用とNFTの保有だったとしましょう。その場合、もしプロジェクト側がDelegateで紐づく2つのウォレットを判定対象としていたらエアドロップの対象となります。一方で、判定の対象外にしていたらエアドロップの対象などにはなりませんので、その点ご注意ください。 Delegateの活用事例 NFTを所有するユーザーは、Delegateを通じてコールドウォレットにNFTを保管しながらも、ホットウォレットを介して取引やその他の活動が行えます。これは、セキュリティと利便性のバランスを保ちながらNFTを管理する効果的な方法です。 Delegate の設定方法 https://delegate.xyz/ にアクセスします。( 先URLをコピペしてアクセスください。) ウォレットを接続します。 次に下記画像の赤枠部分の「Registry」を選択します。 ◇ ウォレットをDelegateする場合 赤枠のWalletを選択します。 委任する先のウォレットアドレスを入力します。 その後、トランザクションを実行して完了です。 重要 Delegateのトランザクションはクロスチェーンには対応していないため、異なるチェーン上での操作を行いたい場合は、各チェーンでDelegateの設定が必要です。 ◇NFTをDelegateする場合 NFTをDelegateする場合は、赤枠のAssetを選択します。 委任先のウォレットアドレスを入力。 対象のNFTのコントラクトアドレスを入力。 委任するNFTのToken IDを入力する。 トランザクションを実行。 その後、画面右上のウォレットアドレス ⇒ Profileをクリックします。 Registryの部分に、委任元のアドレスと委任先のアドレスが表示されていたらトランザクションは完了されています。 まとめ|リスク移転をすることでNFTを守る 本記事では、NFTを紛失 / 盗難から守るための4つのリスク対策とリスク対策の一つ「リスクの移転」を実現するためのDelegateについての概要と使い方を説明しました。相場全体が強気になると、市場参加者の資産を狙う悪意のある第三者が必ず出現します。 前回のブル相場と異なり、今回のブル相場では特定のNFTを保有していることが市場を立ち回るうえで一つの大事な要素となっています。大切な資産でもあるNFTを守るために、Delegate等のツールを駆使してリスク対策を図りましょう。 Delegate 公式リンク https://delegate.xyz/ https://docs.delegate.xyz/ https://twitter.com/delegatedotxyz

プロジェクト
2024/03/11Blast BIG BANGコンペ特集第二弾!|Runner ups選出の31PJを紹介
2月29日、ネイティブイールドを備えたレイヤー2ネットワーク「Blast」のメインネットが稼働しました。また、同月23日にはBlast BIG BANGコンペティションの選出プロジェクトが発表され、チェーンにもプロダクトにも注目が集まっていました。 Blast BIG BANGコンペ特集|3000以上の応募から選ばれた47プロジェクトを全紹介! 前回、優勝プロジェクトとして選ばれた47のプロジェクトを紹介しましたが、今回は、Runner ups(準優勝)として選ばれた31のプロジェクトを紹介します。 Blastとは? Blur創設者による新たなイーサリアムレイヤー2:2月29日にメインネットがローンチ Runner ups選出プロジェクトの紹介をする前に、まずはBlastの基本情報を紹介していきます。 Blastは、ネイティブイールドを備えたレイヤー2ネットワークであり、NFTマーケットプレイス「Blur」の創設者のPacman氏(@PacmanBlur)によって立ち上げられました。 昨年、デポジット量に応じたポイントシステム及びエアドロップの告知をしたこともあり、多くのTVLを集めていました。これらのデポジット資金はメインネットのローンチまでは引き出せないとのことでしたが、Blur創設者による開発という知名度や大手VCがバックにいることもあり、一時期は20億ドルものTVLを誇っていました。 既に、メインネットがローンチし、資金の移動が可能となっています。そうした中で、実際にBlastがどれほどの資金やプロダクトを有することになるのか、その実力に関心が集まっているというのが現在の状況と言っていいでしょう。 ローンチ後のTVLは約420万ドル:チェーンとしては第16位に位置する(記事執筆時) [caption id="attachment_108895" align="aligncenter" width="1439"] https://defillama.com/chain/Blast[/caption] [caption id="attachment_108900" align="aligncenter" width="1439"] https://defillama.com/chains[/caption] メインネットがローンチする前のBlastのTVLは20億ドルを超えていました。 ローンチし、ロックされていた資金を引き出すことが出来るようになりTVLは減少しましたが、減少後のTVLは約420万ドルとなっています。一見すると低いようにも見えますが、チェーン全体のTVLランキングでは、第16位に位置しており、未だ中堅以上のポジションにいることが分かります。 その他、上記画像以外の主要なチェーンのTVL及びランキングは以下のようになっています。(記事執筆時) Starknet:約200万ドル(第24位) zkSync Era:約185万ドル(第28位) Manta:約160万ドル(第29位) 優勝プロジェクト以外に集まる注目 BIG BANGコンペの発表によって、優勝プロジェクトである47PJに注目が集まりました。しかしながら、それ以外のPJが決して劣っているという訳ではなく、中には優勝した47PJよりも多くの注目を集めているプロジェクトもあります。 今回の記事は、Runner ups(準優勝)選出プロジェクトを特集したものとなります。 Runner ups選出プロジェクト ここからは、Runner ups選出の31PJを取り上げていきます。 カテゴリーは以下の8つとなっています。 Spot DEX Perp DEX レンディング GambleFi SocialFi NFTs/Gaming Misc インフラ 全てのプロジェクトが、詳細なプロジェクト内容やドキュメントの公開、サービスの開始をしている訳ではないので、プロジェクトごとに現時点で手に入れることの出来る情報量が異なることには注意が必要です。 Spot Dex BladeSwap:プラットフォーム手数料の100%をトークン保有者に還元 BladeSwapは、プラットフォーム手数料の100%をトークン保有者に還元し、投票を通じて排出をリダイレクトするveDEXです。 Bladeは、ネイティブのバッチ取引、リアルタイムの投票、毎日の無料戦利品ボックスにより、複雑なDeFiをワンクリックで簡素な優れたユーザー体験をもたらそうとしています。 現在は、流動性プールとして「USDB/ETH」のプールのみが提供されています。 公式サイト:https://bladeswap.xyz/ X:https://twitter.com/bladeswapxyz Blaster Swap:バッチスワップ機能を備えたメタDeFiアグリゲーター バッチスワップ(一度の取引で複数のスワップを最良のルートと価格で可能にする)機能を備えており、DeFi機能のナビゲーションを一箇所で簡素化出来るようになっています。 エアドロップは2024年第二四半期に予定されており、現在は「PRE-GENERATION EVENT」が開催されています。トレード量に応じてポイントを稼ぐことが可能であり、日次で100ドル以上の取引をすると、獲得ポイントにブーストが入る仕組みとなっています。また、LPでもポイントを稼ぐことも可能です。 公式サイト:https://blasterswap.com/ X:https://twitter.com/blasterswap MonoSwap:利回り主導型分散型取引 MonoSwapは、エコシステム中心の利回り主導型分散型取引です。また、ローンチパッドシステムに注力しています。 特徴として、MUSDの発行をしようとしていることが挙げられます。MUSDは、USDBに裏付けされているトークンであり、ユーザーはUSDBを預け入れることで、MUSDをミントすることが可能となっています。 MonoSwapでの取引手数料の一部はUSDBに変換され、MUSDを支える担保に預けられます。また、ETH、USDB、ガス収入シェアからのBlastのネイティブ利回りもすべてMono Treasuryに集められ、USDBに変換されてMUSDの担保に預けられるようになっており、MUSDの価格が下がらないような仕組みがとられているとのことです。 公式サイト:https://www.monoswap.io/ X:https://twitter.com/monoswapio Perp Dex Aark:レバレッジに重点を置いた永久DEX Aarkは、プロトレーダー/LPのための世界初のレバレッジパーペチュアルDEXです。既にArbitrum上でサービスを稼働しており、Blastへも進出する形となります。 通常のプラットフォームでは、OI(建玉:Open Interest)とTVLの比率が1:1以下になるように設定されていますが、AarkではTVLに対してOIを10倍以上に拡大することが可能です。これにより、LPのリターンの大幅上昇や、より多くのLPとトレーダーを惹きつけるポジティブなフィードバックループが形成されるようになっています。 公式サイト:https://aark.digital/ X:https://twitter.com/aark_digital DTX:オラクルベースの分散型永久取引所 DTXは、最大100倍のレバレッジを実現するオラクルベースの分散型永久取引所です。また、低手数料、ゼロスリッページ、コピートレーディング機能が特徴であり、完全にオンチェーンでありながら中央集権取引所(CEX)のような取引体験を実現しています。 また、アルトコインにも注力しており、DTXが有するアルトコインプールによって、深い流動性が提供されるようになっているとのことです。 公式サイト:https://testnet.dtx.trade/ X:https://twitter.com/0xdtx HMX:クロスマージンとマルチアセット担保をサポートする分散型永久プロトコル HMXは、クロスマージンとマルチアセット担保をサポートする次世代の分散型永久プロトコルであり、既にArbitrum上でサービスを稼働していました。 報奨金プログラムが多数用意されていることが特徴です。主要なものとして、以下が挙げられます。 ・TLC(Traders' Loyalty Credit):取引量1ドルにつき、最低1TLCトークンが付与されます(レートは取引資産によって異なります)。TLCトークンは、他のTLCステークプールの間で共有されるHMX報酬を獲得するためにステークすることが可能です。 ・オープンポジションのインセンティブ報酬:HMXはesHMXの排出量の一部をオープンポジションに割り当てています。ユーザーは、レバレッジをかけたポジションが有効な期間、esHMX報酬を受け取ることが可能です。 ・LPへの報酬:LPはプロトコル手数料に加えて、esHMX報酬を追加インセンティブとして受け取ることが可能です。 公式サイト:https://hmx.org/arbitrum X:https://twitter.com/hmxorg Opyn:オプション取引プラットフォーム Opynは、ノンカストディの分散型証拠金取引が可能な分散型取引所です。 Opynの戦略として、「カニ戦略」(Crab Strategy)と「Zen Bull戦略」が有名です。 カニ戦略は、USDCに重点を置いたものであり、ETHの価格が市場の予想よりも低く動いたときに、ユーザーがUSDCを積み重ねることを可能にする自動戦略です。 Zen Bull戦略は、ETH入金に重点を置いたものであり、カニ戦略と連動しながら、ユーザーはETHをより多く積み重ねることが出来るようになっています。 公式サイト:https://www.opyn.co/?ct=JP X:https://twitter.com/opyn_ レンディング(Lending) Abracadabra Money:ステーブルコイン$MIMを採用したレンディングとレバレッジのプラットフォーム Abracadabra Moneyは、オムニチェーンのDeFiレンディング・プラットフォームであり、米ドル建てステーブルコインであるMIM(Magic Internet Money)を採用しているのが特徴です。ユーザーは、担保によって利回りを稼ぎながら、米ドル建ての融資を受け取ることが可能です。 ステーキングシステムもあり、ユーザーは利回りの形で報酬を得ることが可能です。SPELLトークンによって実現され、2種類の方法によって、報酬を獲得することが出来ます。 SPELLトークンをステークして、より多くのSPELLを獲得。 SPELLトークンをステークして、MIMを通zひてステーブルコイン収入を獲得。 また、ステーキングによってガバナンスにおける投票権も獲得可能であり、1SPELLあたり1票が与えられます。 公式サイト:https://abracadabra.money/ X:https://twitter.com/MIM_Spell Fortunafi / Reservoir:分散型ステーブルコインプロトコル Fortunafi / Reservoirは、Blast上の分散型ステーブルコインプロトコルであり、流動的な利回り、期間ベースの資産、強固なレポ市場を備えています。FortunafiはBlast上のRWA発行者でもあり、ユーザー、機関、スマートコントラクトがUSDBでRWA資産をミントし、換金することを可能にしています。 また、Tokenized Asset Protocol (TAP) アプリがBlast上で稼働しています。KYCを完了したユーザーはTAPを利用することで、米国財務省短期証券(T-Bills)にアクセスできるようになっており、ポイントを稼ぐことも可能です。 米国のユーザーに対してはfBILLトークンが、米国以外のユーザーに対してはifBILLが発行されるようになっており、24時間年中無休でミント及び償還することが出来ます。 fBILL及びifBILLには、Blast、Arbitrum、Cantoにてアクセス可能となっています。 公式サイト:https://app.fortunafi.com/ X:https://twitter.com/_Fortunafi INFINIT:流動性フックのマネーマーケット INFINITは流動性フックのマネーマーケットです。DAppsの基盤となる流動性レイヤーとして機能しており、プロトコルのシームレスな統合、効率的な流動性の調達、多様なユースケースの育成を可能にし、最終的にDeFi領域における流動性の断片化と持続可能性に対するソリューションを提供しています。 ユーザーは、自動債務返済、信用取引などのフックを介して、貸し借り、利回り/取引戦略へのアクセスが可能です。「フラッシュ借入」、「Multi-Siloポジション」、「担保としてのLPトークン」の3つの主要技術によってこれが実現されています。 公式サイト:https://init.capital/ X:https://twitter.com/infinitcapital_ Seismic Finance:Blastネイティブのレンディングプラットフォーム Seismicは、Blastネイティブのレンディングプラットフォームであり、報酬の最大化や、金利、セキュリティに焦点を当てているとのことです。現在はコード開発が佳境の状態であり、まもなく監査が行われる予定とのことです。 トークンのモデルも完成しており、3月下旬にUSDBとbETHのレンディング市場の初期サポートを開始する予定とのことです。また、ローンチと同時に、ポイント、ボーナス報酬、主要なトークン・インセンティブが用意されることも発表されています。 X:https://twitter.com/seismicfinance GambleFi Blast The Balloon:完全にオンチェーンなバイラルくじゲーム Blast the Balloonは、プレイヤーがボンディングカーブからノード(ポンプ)を購入し、時間が経つとすべてのプレイヤーがポットの一部を獲得する、+EVのバイラルくじゲームです。このゲームは完全にオンチェーンであり、手数料の100%が賞金プールに賄われるようになっています。 また、開発者に対して与えられるBLAST報酬が、ウォレット接続やXでのソーシャルタスクを完了することによって、シェアされるキャンペーンが開催されています。(キャンペーン期限は日本時間3月9日13:00となっています) 公式サイト:https://blastballoon.xyz/ X:https://twitter.com/blasttheballoon Draw The Chart:チャート予測ゲーム DrawTheChartは、お気に入りのコインのチャートの動きを正確に予測すると報酬が貰えるチャート予測ゲームです。 Privyを活用しているため、メールアドレスやSNSアカウントでのWeb3ウォレット作成が可能となっており、プレイヤーのオンボーディングに注力していることも特徴です。 公式サイト:https://drawthechart.com/ X:https://twitter.com/drawthechart FlashBit:オンチェーンギャンブルプロトコルにおける参入障壁に対するソリューションを提供 FlashBitは、Blast上のすべての投機活動へ向けたプロトコルです。手数料をなくし、利回りによって収益化することで、オンチェーンギャンブルプロトコルにおける参入障壁を減らし、より多くのアップサイド、インセンティブ、資本効率を提供しています。 現在は、テストネット・アルファが正式に稼働しており、アーリーアクセス・エアドロップ・プログラムが行われています。Blastにブリッジしている全てのユーザーが請求できるようになっているとのことであり、その他にも招待コードによって割り当てを獲得することも可能となっています。 公式サイト:https://flashbit.xyz/ X:https://twitter.com/flashbitxyz MTRIX3D:映画「マトリックス」にインスパイアされたWeb3宝くじ MTRIX3Dは、Blast上のサイバーパンク宝くじです。タイマーがゼロになる前にピル(チケット)を購入した最後の1人が賞金を獲得することが可能であり、ピルを購入するごとに、カウントダウンが延長されるようになっています。(ピルの値段は、購入するたびに少しずつ上がっていきます) 宝くじの当選以外にも収益を得ることが可能であり、SOURCEトークンを購入してステークすると、取引ごとに収益が増加し、ゲーム収益と賞金の一部を獲得できます。 公式サイト:https://matrix3d.io/ X:https://twitter.com/matrix3d_io SocialFi gm.app:NFTとコミュニティが組み合わさったSocialFi gm.appでは、ボンディングカーブでNFTコレクションを購入・作成することが可能であり、公開フィードとプライベートフィードの両方で新しいコミュニティを見つけることが可能です。 参加、取引、収集によってgmポイントを獲得することが可能であり、Blastのネイティブイールドとガス手数料の分配はクリエイターが決定する仕組みとなっています。 メインネットはまだ公開されておらず、現在はテストネットの段階です。 また、開発者エアドロップの100%をユーザーに還元することを発表しています。 公式サイト:https://gm.app/ X:https://twitter.com/gm_on_blast Sax Trade:Xのハッシュタグを活用した文化取引DEX SAXは、Blastをベースとした流動性の制限なしに人気カルチャーのトレンドに投機することが可能な、Z世代の文化的DEXです。文化は無形ではありますが、その取引をより効率的にするためのソリューションを提供しています。 トークン化する文化指標として、Xのハッシュタグを活用しています。SAX上で、XのハッシュタグをERC-20にミントすることが出来、その価格はハッシュタグの人気に基づいて変動するようになっています。 SAXユーザーは、トレンドのニブ(取引単位)を購入し、ハッシュタグがより多くのエンゲージメントを獲得することを推測、売却によって利益を得ることが出来る仕組みとなっています。 また、”Share to Earn"のインセンティブを用いることで、トレンドをメインストリームで注目されるようにすることも可能とのことです。 X:https://twitter.com/sax_trade DistrictOne (D1):マネーゲームのあるソーシャル空間を提供 DistrictOne (D1) は、マネーゲームを備えたグループチャットSocialFiアプリです。コミュニティはソーシャル活動によって収益を得ることができ、プロジェクトやインフルエンサーはグループを収益化できるようになります。 報酬を獲得する方法として、以下が挙げられます。 Linkup:友達を招待して報酬を獲得することが可能です。 Rally:自身のスペースへサポートを集めることで、賞金プールの分け前を獲得することが可能です。 Space Share:SpaceShareを活用することで、ユーザーはお気に入りのスペースの株式を購入できます。株式を保有することによって、そのスペースの取引手数料の一部を受け取ることが可能です。 Space Sprint:スペースたちが株価に基づいて上位3位を争います。優勝したスペースは報酬を受け取ることが可能です。 公式サイト:https://districtone.io/ X:https://twitter.com/districtoneio Quail Finance:無担保ローンを提供するSocialFi Quail Financeは、社会的信頼に基づいてコミュニティメンバーに無担保ローンを提供するSocialFi dAppです。インドのChit Fundsと呼ばれるグループベースの輪番制貯蓄・信用スキームから着想を得ていることが特徴です。 公式サイト:https://quail.finance/ X:https://twitter.com/quailfinance EarlyFans:クリエイター支援に重点を置くSocialFi EarlyFansは、クリエイターが広告のセールスマンになることなく、コンテンツから直接マネタイズすることを支援しています。クリエイターのファンは、ツイートのパフォーマンスによってETHとクリエイタートークンを獲得し、同時に限定コンテンツにアクセスすることができます。 公式サイト:https://www.earlyfans.xyz/ X:https://twitter.com/earlyfans_xyz Sofamon 情報不足により、割愛。 The Bakery:Mantle DEX「Butter」によって運営される期間限定の体験 The Bakeryは、Butterによって運営されているSocialFiです。ButterはMantle上にてDEX及びNFT先物を提供しています。また、Mantleと戦略的パートナーシップを結んでおり、これによりシードラウンドでの調達額を460万ドルに増額していました。2024年の$BUTTERエアドロップも告知されています。 TheBakeryでは、$MILKによってゲームに参加し勝利することで、より多くの$MILKを得ることが可能です。$MILKの使用用途としては、オークションでのWLの購入や、NFTのラッフルチケットの購入が挙げられます。また、Blastポイントを貰うことも可能になっているとのことです。 今回のコンペでは、TheBakeryの名前で選出されていましたが、Butter(DEX機能)の方も追加されるかどうかはまだ未定です。 公式サイト:https://thebakery.gg/ X(Butter):https://twitter.com/butterexchange NFTs/Gaming AI Waifu:AIコンパニオンゲーム AI Waifuは、AIコンパニオンゲームです。たまごっちスタイルであり、クロスプラットフォーム、生成コンテンツを有したファンタジーアニメとなっています。また、AIに関しては、オープンソースのものが搭載されています。 WAIFUトークンのパブリックセールが、Fjord Foundryを通してBlastメインネットで予定されています。VC、プレセール、ホワイトリスト等がなく、フェアなセールになるとのことです。 トークンセールは当初、3月5日12:00PM(UTC)から3月8日12:00PM(UTC)を予定していましたが、Fjord FoundryがBlastに未対応のため、延期することとなりました。Fjord Foundryの対応次第で、セールが開催されると発表されています。 公式サイト:https://www.aiwaifu.gg/ X:https://twitter.com/aiwaifugg SEKAI GLORY:ブロックチェーン技術を組み合わせたトレーディングカードゲーム SEKAI GLORYは、ストラテジー、アート、ブロックチェーン技術を組み合わせたアニメ、ガチャのトレーディングカードゲームです。 現在、2つのゲームモード「PvP」と「バトルロイヤル」が提供されています。また、将来的には、「PvEゲームモード」や「トーナメント 」も提供される予定とのことです。 独自トークンとして、$GLORYが発行されており、「リーダーボードのランキング50位以内」もしくは「ブースターパックの開封」によって獲得可能とのことです。また、将来的にはゲーム内ネイティブ利回りステーキングも予定しているとのことです。 各種言語に対応しており、日本語でもプレイすることが可能です。 公式サイト:https://www.sekaiglory.com/ja-JP X:https://twitter.com/sekaiglory Pixel Race Club:ソーシャルベッティングエコシステムが特徴のレースゲーム Pixel Race Club (PRC)は、Web3 レースとベッティング体験を提供しており、1人用チャレンジから多人数での対戦といったモードが用意されています。Xterioがパートナーであることも特徴です。 PRCチームは、Tencent、Tiancity、Visual Concept、Glu Mobile、Gameloftなどを経歴として有する集団であり、Mutant RoadkillやG Kart(QQ Speed)などのヒット作の実績もあります。 NFTホルダーに対する特典も数多くあり、ETHロック期間に応じたパッシブ報酬、ブースト報酬トーナメント、Twitterでのソーシャルチャレンジ、Blastネイティブのベッティングオプションを楽しむことが出来ます。また、Blastポイントを獲得することも可能です。 X:https://twitter.com/pixelraceclub Super Sushi Samurai:「Gameme」(Game + Meme)モデルが特徴 Super Sushi Samuraiは、テレグラム・プラットフォームを介してプレイ可能なゲームです。「Gameme」(Game + Meme)モデルであることと、完全にオンチェーンであることが特徴として挙げられます。また、独自トークンとしてSSSがあり、これによりプレイヤーは報酬を獲得することが可能です。 プレイヤーはランダムな土地からスタートし、土地を切り替えてプレイすることができます。各土地は所有者によって税率が設定されたトレード可能なNFTとなっています。また、サムライ(プレイヤー)は自動的にモブと戦い、倒したモブからは「米のかけら」を入手可能です。ペットが自動的に米のかけらを拾い、プレイヤーがそれを俵に集めていきます。 また、レイドボスも登場し、倒したサムライに対しては賞金が付与されます。その他にもクラン対戦機能も搭載されるとのことであり、クランリーダーは報酬の20%が、残りの80%がクランメンバーに均等に分配される仕組みとのことです。 公式サイト:https://sss.game/ X:https://twitter.com/sss_hq Misc BlastOff:ローンチパッド及び利回りアグリゲーター BlastOffは、ローンチパッド及び利回りアグリゲーターであり、「Native Yield IDOs」 (YIDOs) と「YZone」を特徴としています。 YIDOsは、ゼロリスクIDOをコンセプトとしています。従来のIDOでは、プロジェクトが失敗した場合には、ユーザーは資金を失ってしまいます。しかし、BlastOffでは、ETHまたはステーブルコインをプラットフォームにステーキングすることで発生する利回りの一部をYIDOのサポートに割り当てます。これにより、ユーザーの不利益を軽減しようとしています。また、YIDOsは、ユーザーがステークして利回りの一部をYIDOsに割り当てる以外に何もする必要のない、初の資金調達プロトコルでもあります。 YZoneは、利回りアグリゲーターです。これは、Blastエコシステム内の収益機会を中心とした戦略の実行に重点を置いており、Blastのネイティブな利回りよりも高い収益を提供するものです。これは、複数の保管庫(vaults)によって実現されるとのことです。 公式サイト:https://blastoff.zone/ X:https://twitter.com/blastozone Ulti-pilot(Ultiverse):AIを活用し、ゲームエコシステムにおける相互運用性の課題に対処するポータル Ulti-pilotは、AIを搭載した宇宙の多様なゲーム体験への没入型ポータルです。 Ultiverseによって開発されており、同社はAAAソーシャルゲーム、NFT、DeFi、DEXを1つに統合したプラットフォームです。また、Web3と没入型VR互換仮想世界をつなぐ次世代メタバースの構築を目指しており、トークンを使ってエコシステム内での活動やコミュニティ構築にインセンティブを付与している事が特徴です。2月には、IDG Capitalが主導するシードラウンドで、400万ドルを調達していました。 Ulti-pilotではAIとブロックチェーンの統合によるゲームの相互運用性の実現が目的となっており、Gaming Launchpad、Restake Rollup、さらに分散型アプリケーションが発表される予定となっています。 公式サイト:https://www.ultiverse.io/ X:https://twitter.com/ultiversedao インフラ API3 DAO:オンチェーン価格参照の検証可能な分散ソースを提供 API3は、分散型かつ信頼を最小限に抑えた方法で、従来のAPIサービスをスマートコントラクトプラットフォームに提供する共同プロジェクトです。API3 DAOによって管理されています。OEVネットワークにより、DeFiプロトコルがdAPIを利用することで、MEVを通じて抽出されている価値を取り戻すことができることが特徴です。 また、その他の主要な特徴として、「Airnode」が挙げられます。これは仲介者を介さずにオンチェーンでデータを提供できるオープンソースツールであり、APIプロバイダーが独自のオラクルノードを簡単に実行できるように設計されています。また、前後処理、認証、認可などの実装もされています。 公式サイト:https://api3.org/ X:https://twitter.com/api3dao Biconomy:アカウント抽象化SDKを提供 Biconomyは、SDKを開発しており、dApp、ウォレット、またはアプリチェーン上でシンプルなUXを可能にするアカウント抽象化ツールキットであることが特徴です。ERC-4337上に構築されており、スマートアカウントプラットフォーム、Paymaster、Bundlerと連携するフルスタックソリューションを提供しています。 Biconomyスマートアカウントは署名者に依存しないため、スマートアカウントの作成時に署名者SDKに渡すことができる限り、任意の認証パッケージを使用することも可能です。また、スマートアカウントは、userOpを検証する前に任意のロジックを実行できる検証モジュールによってさらに強化されており、開発者は、セッションキー、マルチチェーン検証モジュール、パスキーなどを使用できるモジュールを構築することが出来ます。 公式サイト:https://www.biconomy.io/ X:https://twitter.com/biconomy UNCX Network:完全分散型マルチチェーンサービスプロバイダー UNCX Networkは、B2Bサービスプロバイダーです。また、プロジェクトの作成と立ち上げの簡素化と、それと同時に、投資家にとって可能な限り安全なものにすることを目的としています。 同社は、以下の5つのサービスを主要なものとして提供しています。 Initial Liquidity Offering (ILO):多くのプロジェクトやスタートアップがICOのプロセスを経ずに、分散型取引所でトークンを販売することで資金を調達する資金調達メカニズムです。 Liquidity Lockers:LPトークンのロックが解除されると、開発者がプールから流動性を枯渇させて投資家の資金を持ち逃げするリスクがあります。Lockerは、それを防ぐための仕組みです。 Token Vesting:開発者がトークンを全て一度に販売することでトークンの価格変動を操作することがなくなり、コミュニティへのコミットメントを示すことが出来ます。 Staking:開発者は独自のステーキングプールを作成し、コミュニティが選択したトークンをステーキングしたり、報酬プールを通じて選択したトークンで報酬を与えることがになります。 Token Minter:トークンやセキュリティのスキルを持たない開発者を対象としています。。Minterによって作成されたトークンはすでに事前監査されているため、自分で監査する必要がなくなります。 公式サイト:https://uncx.network/ X:https://twitter.com/uncx_token おわりに ここまで、Blast BIG BANGのRunner ups(準優勝)プロジェクトを紹介してきましたが、如何でしたか? メインネットがローンチし、Blastチェーンの実力がどれほどのものなのか注目が集まっています。優勝プロジェクト以外にも多くのプロジェクトがあり、Blastエコシステムの基盤が構築されていることはTVLを見れば明らかと言えるでしょう。 しかしながら、コンペ選出プロジェクトだからといって、全てが安全なプロジェクトという訳ではありません。今回の記事では、情報がなく詳細を記述できなかったプロジェクトも幾つかありました。他チェーンで既に実績を有しているプロジェクトもありますが、完全に新規のプロジェクトも数多く存在します。資産を守るためにも、DYORを忘れないようにしてください。
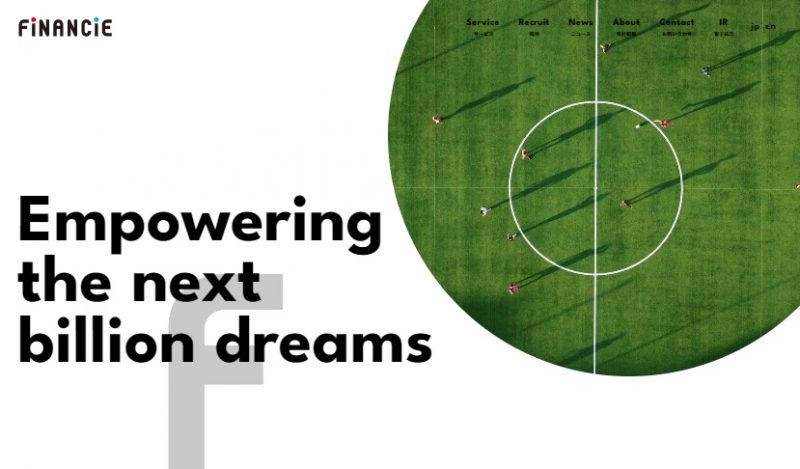
プロジェクト
2024/03/11フィナンシェトークン (FiNANCiE/$FNCT) とは?プロジェクト概要を徹底解説!
「フィナンシェ(FiNANCiE)」は、スポーツチームやクリエイターがサポーターとともに夢を実現するためのプラットフォームです。 従来のクラウドファンディングのような単なる資金調達の手段ではなく、スポーツチームやクリエイターとサポーターが夢に向かって共に進んでいけるコミュニティを作り出すことを狙っており、そこにトークンエコノミーとブロックチェーン技術をうまく組み込んでいます。 この記事では、フィナンシェ(FiNANCiE)のプロジェクトや、そこで使われるトークンであるFNCTについて解説します。最後まで読めば、フィナンシェがどういうプロジェクトなのかをしっかり理解できますよ。 フィナンシェ(FiNANCiE)の公式リンクまとめ FiNANCiEとFNCTの関連公式ページ 株式会社フィナンシェ Webサイト https://www.corp.financie.jp/ FiNANCiE Webサイト https://financie.jp/ FiNANCiE Twitter https://twitter.com/financie_jp FiNANCiE YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@financie9516 FNCT Webサイト https://fnct.xyz FNCT Twitter 日本語:https://twitter.com/Fnct_Official 英語:https://twitter.com/Fnct_Officialen FNCT LINE https://line.me/R/ti/p/@980uysqm FNCT ホワイトペーパー https://fnct.xyz/whitepaper/ja 「フィナンシェ(FiNANCiE)」とそのガバナンストークンであるフィナンシェトークン(FNCT)の関連公式ページをまとめました。 公式リンクのブックマークやSNSアカウントをフォローして、フィナンシェの動きをリアルタイムでウォッチしましょう。 フィナンシェ(FiNANCiE)の特徴・注目ポイントを解説 [caption id="attachment_108776" align="aligncenter" width="770"] 画像:株式会社フィナンシェ[/caption] 最初にフィナンシェ(FiNANCiE)の特徴や注目すべきポイントについて説明します。最後まで読んで、フィナンシェがどういうプロジェクトなのかをしっかりとつかんでおきましょう。 フィナンシェ(FiNANCiE)の特徴・注目ポイントを解説 ブロックチェーン技術を活用したトークン発行型クラウドファンディング CT(Community Token)によるコミュニティ構築 代表はgumi創業者國光宏尚氏、サッカーの本田圭佑氏や長友佑都氏も参加 スポーツ分野92件/エンタメ分野60件など豊富な実績 プラットフォーム共通のガバナンストークンFNCTをIEO ブロックチェーン技術を活用したトークン発行型クラウドファンディング [caption id="attachment_108850" align="aligncenter" width="658"] 画像:株式会社フィナンシェ[/caption] フィナンシェ(FiNANCiE)は、スポーツチームやクリエイターがサポーターとともに夢を実現する新しい形のクラウドファンディングのプラットフォームです。一過性の資金調達ではなく、スポーツチームやクリエイターとサポーターの間に共創的で継続的なコミュニティを構築して、共有する夢や目標の実現に向かって共に進んでいく環境を作り出します。 そのためのキーとなるのが、コミュニティのエコシステムのコアとなるトークンと、それを支えるブロックチェーン技術です。スポーツチームやクリエイターがコミュニティのオーナーとなってトークンを発行し、サポーターがそれを購入することで継続的な協力関係の基盤となるコミュニティを作る、そのためのプラットフォームがフィナンシェです。 CT(Community Token)によるコミュニティ構築 スポーツチームやクリエイターなどのコミュニティのオーナーが発行するトークンはCT(Community Tokenを略したもの)と呼ばれます。オーナーは資金調達時にCTを発行しサポーターに販売して成長のための資金を調達でき、サポーターはCTの保有量に応じてオーナーの活動に関与する権利を得ることが可能です。 またCTはコミュニティの参加権というだけなく、売買も可能です。サポーターはCT購入後の価格上昇による利益が期待できるため(※)、オーナーの活動の価値を高めることに対するインセンティブが働き、サポーターがオーナーの活動に積極的に関与し続ける共創関係がCTを介して構築されます。 CTによるトークンエコノミーにより、オーナーとサポーターが目的を共有し、それに向かって積極的に協力するコミュニティが構築されるのが、フィナンシェ(FiNANCiE)のプラットフォームです。 ※利益を保証するものではありません。CTを購入される際は、サービス内容を十分に理解し、自己の責任で行ってください。 CT保有によって得られる権利 CTを保有することで得られるメリットの内容は、コミュニティごとに異なります。実際のコミュニティ活動では、限定情報・限定コンテンツ・限定イベントへのアクセスや、オーナーの方針決定への投票権などの事例があります。 代表はgumi創業者國光宏尚氏、サッカーの本田圭佑氏や長友佑都氏も参加 フィナンシェ(FiNANCiE)を運営しているのは株式会社フィナンシェで、代表取締役CEOは國光宏尚氏です。 國光氏はモバイルオンラインゲーム業界のメジャープレイヤーである株式会社gumiの創業者で、ブロックチェーンおよび暗号資産テクノロジーへの投資を手がけるgumi Cryptos Capitalのジェネラルパートナーでもあります。ソーシャルゲームやXR、ブロックチェーンに深くかかわってきた日本のWeb3.0のキーパーソンです。 また、アドバイザーに豊富な人材がそろっているのもフィナンシェの注目すべきポイントです。 サッカー元日本代表の本田圭佑氏は、2019年の資金調達時に投資家兼アドバイザーとしてフィナンシェに参画しています。さらには同氏がオーナーであるアフリカ・ウガンダ共和国のプロサッカークラブ「SOLTILO Bright Stars FC」はフィナンシェ上でCTを発行し、コミュニティが稼働しています。 同じくサッカー元日本代表の長友佑都氏も2020年にフィナンシェのアドバイザーに就任しており、出資者でもあります。 他に株式会社GO代表取締役の三浦崇宏氏、株式会社メルカリ共同創業者の石塚亮氏などもアドバイザーに加わっています。 スポーツやエンタメなど様々な分野で250件以上の豊富な実績 [caption id="attachment_108839" align="aligncenter" width="847"] 画像: FiNANCiE[/caption] フィナンシェは2019年にサービスがスタートしてから様々な分野で多くのコミュニティを作り出し運営してきています。 スポーツ分野やエンタメ分野をはじめ、クリエイターやインフルエンサー等の個人分野も含め、2024年3月時点で250件以上のコミュニティがフィナンシェ上で稼働しており、コミュニティメンバー数は約10万人に迫っています。 初期のトークン販売による一次流通と、一次流通後のフィナンシェ上でのトークンの取引(二次流通)を含めた流通取引総額は29.5億円にもなり、これから大きく成長しようとするスポーツチームやクリエイターにとって大きな支えになっています。 プラットフォーム共通のガバナンストークンFNCTをIEO [caption id="attachment_108840" align="aligncenter" width="679"] 画像:FNCT.xyz[/caption] コミュニティごとに発行されるCTに対して、フィナンシェプラットフォーム共通のガバナンストークンとなるのが、暗号資産フィナンシェトークン(FNCT)です。 フィナンシェプラットフォームを下支えし、その上で活動する様々なコミュニティを活性化させることを目的としており、現在コミュニティごとに個別に発行・利用されているCT同士を効果的につなげ、さらにフィナンシェ外のエコシステムとの連携を担います。 フィナンシェトークン(FNCT)は、2023年2月21日にコインチェック(Coincheck)からIEOの購入申込が開始し、申込開始からわずか1時間で販売総額(調達目標金額)である10億6600万円を突破しました。最終的な申込金額は200億円を上回り、倍率18.78倍となりました。その後同年3月16日にコインチェックに上場しています。 フィナンシェ(FiNANCiE)で活動する主なコミュニティ [caption id="attachment_108776" align="aligncenter" width="662"] 画像:FiNANCiE[/caption] フィナンシェ(FiNANCiE)ではすでに多くのコミュニティが立ち上がり、活発に活動を続けています。ここでは、そのうちの主なものを紹介しましょう。 また、FNCT報酬やトークン価格などを含むコミュニティの活動量・成長度をもとにしたコミュニティランキングから気になるコミュニティを探すこともできますよ。(関連:アクティブコミュニティランキング|FiNANCiE) フィナンシェ(FiNANCiE)で活動する主なコミュニティ Support to Earn(S2T)という新たな広告の形「A.E.B Project」 日本初のエンタメDAOプロジェクト「SUPER SAPIENSS」 Jリーグプロサッカークラブ「湘南ベルマーレ」 Support to Earn(S2T)という新たな広告の形「A.E.B Project」 [caption id="attachment_108838" align="aligncenter" width="651"] 画像:A.E.B Project|FiNANCiE[/caption] 2024年3月時点でアクティブコミュニティランキング1位となっているコミュニティが「A.E.B Project」です。 人気NFTプロジェクトでも知られるweb3コミュニティ「AEB」が手掛けるアパレルブランド「DO NUTS」の立ち上げから3DCGショップの設立・販売を目指しています。 トークンを保有しコミュニティに参加することでブランドの企画運営への投票や限定イベントへの参加が可能になり、ファンとともに成長していく共創型アパレルブランドとなっています。 A.E.B Project|ファンディングページ 日本初のエンタメDAOプロジェクト「SUPER SAPIENSS(スーパーサピエンス)」 [caption id="attachment_108847" align="aligncenter" width="603"] 画像:SUPER SAPIENSS[/caption] SUPER SAPIENSSは、堤幸彦氏・本広克行氏・佐藤祐市氏の3名の映画監督が日本初のエンタメDAOを目指して立ち上げたプロジェクトで、2022年1月にCTを販売し、コミュニティがスタートしました。 映像化やグローバル展開を視野に入れたプロジェクト第1弾「WEBTOON」の第1話はすでに公開されており、現在ではプロジェクト第2弾となる俳優オーディション企画が進行中です。 コミュニティでは作品のストーリーやプロモーション方法に関する投票やアンケートを行うことができ、支援者がパートナーとしてプロジェクトに参加できる新しい自主制作のかたちを体現しています。 SUPER SAPIENSS|ファンディングページ Jリーグプロサッカークラブ「湘南ベルマーレ」 Jリーグに加盟する湘南ベルマーレは、チーム運営費調達などの目的で2021年1月にCTをクラブトークンとして発行しました。 クラブトークンの保有者は、クラブの投票企画への参加や、スペシャルデーでの特典抽選への応募が可能です。 バルセロナFCやユベントスなど欧州の主要なクラブチームの多くはすでにクラブトークンを発行していますが、日本のプロサッカーチームによるクラブトークンの発行としてはこれが国内初の事例でした。 湘南ベルマーレ|ファンディングページ フィナンシェトークン(FNCT)とは? [caption id="attachment_108840" align="aligncenter" width="685"] 画像:FNCT.xyz[/caption] フィナンシェトークン(FNCT)のスペック トークン名 フィナンシェトークン 発行者 株式会社フィナンシェ テッカー FNCT 総発行枚数上限 20,000,000,000枚 発行開始日 2023年3月 フィナンシェトークン(FNCT)は、コミュニティごとに発行されるCTと異なり、フィナンシェプラットフォーム内で共通に使われるトークンで、2023年2月21日にコインチェック(Coincheck)のIEOプロジェクト第2弾として販売が行われました。 ここでは、フィナンシェトークン(FNCT)の詳細について解説します。 フィナンシェトークン(FNCT)とは? FiNANCiEプラットフォーム共通のガバナンストークン デリゲート報酬が期待できる FNCTの管理運用のためにLedgerと戦略的パートナーシップを締結 FNCTの初期分布 FiNANCiEプラットフォーム共通のガバナンストークン フィナンシェフィナンシェ(FNCT)は、フィナンシェプラットフォームのガバナンストークンです。FNCTを一定期間ステーキングしている保有者は、フィナンシェプラットフォームを改善・成長させるための投票に参加する権利を持ち、この権利を行使することでフィナンシェのガバナンスに影響力を行使することができます。 FNCTは売買可能な暗号資産であり、2023年3月16日にコインチェック(Coincheck)に上場しています。フィナンシェの価値が上がればFNCTの価格が上昇するので、売却価格が購入価格を上回れば保有者が売却利益を得ることが可能です。フィナンシェ上で活動するコミュニティの活性化はFNCTの価格上昇につながるので、FNCT保有者がコミュニティに積極的に関与する強いインセンティブになります。 FNCTのBuybackとBurn フィナンシェ(FiNANCiE)では、FNCTを定期的に市場から買い上げ(Buyback)、そのうちの一定量を焼却(Burn)することが予定されています。FNCTの流通量を調整し価値を下支えすることが目的です。 デリゲート報酬が期待できる フィナンシェトークン(FNCT)保有のインセンティブとして、FNCTの保有者はデリゲート報酬を得ることができます。 フィナンシェ上でのCTの取引情報はすべて、FiNANCiE Lightningというレイヤー2ソリューションを通してEthereumブロックチェーンに記録されています。Ethereumブロックチェーンへの書き込みはバリデータ―が実行し、この行為に対してバリデータ―はバリデート報酬をFNCTで得ることが可能です。 一般のFNCT保有者はバリデータ―にはなれませんが、保有しているFNCTを一定期間ステーキングしてバリデータ―に委譲することで、バリデーターからバリデート報酬の分配を受けます。これがデリゲート報酬です。 分配の比率はバリデータ―ごとにそれぞれの判断で決定しますが、FNCT保有者は委譲先のバリデータ―を自由に選ぶことができるため、そこにも市場原理が働きます。 FNCTの管理運用のためにLedgerと戦略的パートナーシップを締結 FNCTの管理・運用はLedgerのB2Bソリューション「Ledger Enterprise Platform」を使用します。そのため、フィナンシェはLedgerとの戦略的パートナーシップを締結しました。 Ledgerは、個人や企業が暗号資産を安全に購入・保管・交換・管理できる安全なウォレットやソリューションを提供するワールドワイドのリーディングカンパニーです。このパートナシップにより、安全性の高い環境でのFNCTの管理・運用が可能になります。 FNCTの初期分布 フィナンシェトークン(FNCT)の保有者分布 保有者カテゴリ 説明 保有率 枚数 投資家 IEOによって購入者に配布されるFNCT 13% 26億FNCT チーム FNCTエコシステムを牽引するチームメンバーおよび株主へのインセンティブ 25% 50億FNCT コミュニティ FNCTのエコシステムを維持・拡大するための活動費 42% 84億FNCT パートナー フィナンシェ(FiNANCiE)と連携する組織や個人に割り当てられるFNCT スポーツチーム、リーグ、大手芸能事務所、音楽レーベル、 出版社、暗号資産取引所、金融企業など 20% 40億FNCT FNCTは初期的には、「投資家」「チーム」「コミュニティ」「パートナー」の4つのカテゴリに分けて配布されます。 総発行枚数200億枚のうち、IEOで投資家向けに販売されるのは13%の26億枚です。IEO直後に市場に流通するのはIEOで販売された投資家向けの分がほとんどです。 時間とともに「チーム」「コミュニティ」「パートナー」への割り当て分も徐々に流通し始めるので、流通量は少しずつ増加していきます。 フィナンシェ(FiNANCiE)のコアメンバーを紹介 現在のフィナンシェの経営陣をご紹介します。明確なビジョンをしっかりと共有した上で、フィナンシェ以前の個々人の多様な経験値を生かして経営していることがうかがえます。 フィナンシェ(FiNANCiE)のコアメンバーを紹介 CEO 國光宏尚氏 COO&CMO 田中隆一氏 CSO 前田英樹氏 CTO 西出飛鳥氏 CEO 國光宏尚氏 國光宏尚氏は神戸市出身で、株式会社フィナンシェのCEOを務めています。 海外留学の後、映画やテレビドラマの企画・制作プロダクションである株式会社アットムービーの取締役を経て、2007年にモバイルオンラインゲームベンダである株式会社gumiを設立し、代表取締役社長に就任しています。 その後、2019年に株式会社フィナンシェを創業し、2021年にCEOに就任し、現在はVirtual Realityコンテンツ・サービスベンダである株式会社ThirdverseのCEOも兼ねています。 ソーシャルゲームやXR、ブロックチェーンの領域にプレーヤーとして深くかかわってきた経験を持ち、これからの日本のWeb3.0を牽引する人物です。 CSO 田中隆一氏 田中隆一氏は、株式会社フィナンシェのCSOです。 静岡県出身で、慶應義塾大学卒業後DeNAを経て、2005年にデジタルマーケティングソリューションベンダのノッキングオンに参画し、2008年から代表取締役に就任しました。 2012年にはモバイル開発支援プラットフォームベンダのUnicon Pte.Ltdを創業し、そこでブロックチェーン技術に出会い、現在も同社のCEOを務めています。 2019年の株式会社フィナンシェの創業に参画しCEOに就任していましたが、2021年に國光氏がCEOに就任したのに伴い、COOとしてプロスポーツチームなどのクラウドファンディング事業を統括することになりました。COOを経て現在はCSOに就任しています。 CTO 西出飛鳥氏 西出飛鳥氏は株式会社フィナンシェのCTOで、フィナンシェの技術面での大黒柱です。 小学生のころからプログラミングに興味を持ち、高校から大学の期間はプログラミングに没頭する日々でした。大学在学中に「IPA未踏ソフトウェアプロジェクト」に採択された国産タブブラウザ「Lunascape」に参加し、翌年にはLunascape株式会社を創業してCTOに就任しています。 2012年にはモバイル開発支援プラットフォームベンダのUnicon Pte.Ltdの創業にも加わっており、現在でも同社のCTOとして活動中です。そして2019年の株式会社フィナンシェの創業に参加し、ここでもCTOに就任しています。 根っからのプログラマーで、技術面からプロジェクトを支える役割を一貫して務めてきた人です。 フィナンシェ(FiNANCiE)のこれまでの動きと今後のロードマップ 株式会社フィナンシェは2019年1月に創業し、同年にフィナンシェの最初のバージョンが稼働しています。3月には3億円の資金を調達し、本田圭佑氏がこのタイミングで参画しました。 2020年には2.4億円の資金を調達、同時に長友佑都氏がアドバイザーに就任しています。 2021年は「湘南ベルマーレ」のクラブトークンを皮切りに、様々なスポーツチームのトークンが増えた年です。 2022年には、エンタメDAOプロジェクト「SUPER SAPIENSS」が始動し、エンタメ領域でのフィナンシェのプレゼンスが大きく向上しました。 そして2023年2月には、FNCTのIEOが実施され、FNCTの管理運用を目的にLedger(レジャー)との戦略的パートナーシップを締結しました。その後、同年3月にコインチェック(Coincheck)にて上場を果たしました。 2024年以降は、グローバル版FiNANCiEのローンチ、FiNANCiE独自ブロックチェーン(FNBC)の検討が計画されています。 フィナンシェトークン(FNCT)のIEOの詳細 フィナンシェトークン(FNCT)IEOの詳細 発行トークン フィナンシェトークン(FNCT) 発行者 株式会社フィナンシェ 販売枚数 2,600,000,000枚(総発行枚数の13%) 販売総額 1,066,000,000円 販売価格 0.41円/FNCT 申込単位(1⼝) 10,000 FNCT 申込上限⼝数 2,000⼝ ミニマムキャップ 850,000,000円 販売成⽴条件 申込⾦額の総額がミニマムキャップ以上になること 手数料率 8%(消費税含む) IEO実施業者 Coincheck IEO(運営者:コインチェック株式会社) FNCT IEOのタイムライン 2023 2/21 12:00申込開始 2023 3/7 12:00申込終了 2023 3/7 抽選 2023 3/8〜3/9 抽選結果連絡・トークン付与(ロック解除) 2023 3/16 取引所上場・入出金が可能に 今回のIEOでの販売枚数は総発行枚数200億枚の13%の26億枚です。申込口数が多かった場合は抽選により購入者を決定し、トークンが付与されます。 3/16には取引所に上場され、市場での取引開始です。FNCTのIEOは、CoincheckからのIEOとしては国内2例目になります。 フィナンシェ(FiNANCiE)のまとめ この記事では、ブロックチェーン技術を活用したトークン発行型クラウドファンディングのプラットフォーム「フィナンシェ(FiNANCiE)」とガバナンストークンであるフィナンシェトークン(FNCT)について解説しました。 フィナンシェは、従来のクラウドファンディングが一時的な資金の調達にとどまりがちだった問題点を、トークンによるエコシステムを媒介にして継続的に関係性が持てるコミュニティを作りだすことによって解消しています。 フィナンシェが作り出すスポーツチームやクリエイターと共通の夢に向かって進んでいけるコミュニティは、サポートする側とされる側の理想的な関係と言えるかもしれません。 これからの伸びがとても楽しみなプロジェクトですね。 Crypto Timesでは仮想通貨やweb3をもっと楽しむための初心者向け記事を発信しています。様々なトピックをわかりやすく解説しているので、以下の記事もぜひご覧ください。 初心者向け記事一覧|Crypto Times

プロジェクト
2024/03/11仮想通貨フレアトークン($FLR)とは?プロジェクト概要を徹底解説!
フレアトークン($FLR)はFlare Network(フレアネットワーク)で使用されるネイティブトークンであり、国内仮想通貨取引所でも取引可能です。ステーキングやガバナンスとして使用するほか、FTSOへの委任やラップしてエアドロップ対象になる使い道もあります。 まだフレアトークンの波に乗れていないユーザーのために、本記事ではフレアトークンとフレアネットワークのプロジェクト概要を徹底解説します。 非スマートコントラクトの仮想通貨をEVM互換としてFlare上で運用できるネットワークであり今注目のプロジェクトです。エアドロップの参加方法も解説するので、有力プロジェクトに投資するなら情報をチェックしましょう! フレアトークン($FLR)の基本情報・公式リンクまとめ フレアトークン(FLR)の関連公式ページ 名称 Flareトークン/Flare Network ティッカーシンボル FLR コンセンサスアルゴリズム Federated Byzantine Agreement(FBA) 価格/時価総額 6.11円/72位 ※2024年3月時点 取扱い仮想通貨取引所 DMMビットコイン、ビットフライヤー、GMOコインなど FlareNetworks公式サイト https://flare.network/ FlareNetworksポータルサイト https://portal.flare.network/ ホワイトペーパー https://docs.flare.network/ FlareNetworks 公式X https://twitter.com/FlareNetworks FlareNetworks Discord https://discord.com/invite/flarenetwork FlareNetworks Telegram https://t.me/FlareNetwork FlareNetworks Youtube https://www.youtube.com/c/Flare_Networks フレアトークンの基本情報と関連リンクをまとめています。 必ず公式リンクからアクセスして正しいサイトに接続してください。公式XやDiscordに参加してフレアトークンの最新情報をウォッチしましょう。 フレアトークン($FLR)/Flare Netwworkの特徴・注目ポイントを解説 フレアトークンの特徴と押さえておくべきポイントを解説します。 複数のブロックチェーンに対応して、業界のあらゆるプロジェクトが円滑に開発・運営できる拠点を築いているとわかりますよ。 フレアトークンの特徴・注目ポイント Flare Networkは複数のブロックチェーンでスマートコントラクトの統合を目指す 3つのデータ収集プロトコルから構成される EVM互換でDeFi・NFT・ゲームなどの開発が可能 カナリアネットワーク「songbird」がFLRガバナンスの第一段階を担う CチェーンからPチェーンにFLRを移動してステーキングが可能 Flare Networkは複数のブロックチェーンでスマートコントラクトの統合を目指す フレアトークンを発行するFlare Networkは、EVM(イーサリアムヴァーチャルマシーン)をベースとしたブロックチェーンでありオラクルネットワークです。 EVMをベースとしているので、イーサリアム上で開発されたスマートコントラクトやdApps(分散型アプリ)をそのまま利用したり、Flare Networkへ移動したりと相互運用できます。 ビットコインやリップル、ドージなどのトークンを、Flare Networkのスマートコントラクトで使用できるだけでなく、DeFiなどのdAppsで収益を獲得して他のブロックチェーンにブリッジも可能です。 スマートコントラクトを統合することで、複数チェーンの機能をFlare Networkで最大限に高めて有用性のあるブロックチェーンになることを目指しています。 EVMとは EVMとは、イーサリアム上の自動動作プログラムを作成して、スマートコントラクトを実行するソフトウェア環境です。 レイヤー1のオラクルネットワーク「Flare」がローンチ 3つのデータ収集プロトコルから構成される FTSO 各データ提供者から外部ソースの情報を取得し、分散されたデータを元に価格を計算するネイティブオラクル State Connector 他のブロックチェーンやインターネットから検証可能なデータを取り入れる Layer cake 異なるスマートコントラクト対応のネットワーク間でブリッジできるシステム Flare Networkの主要構成は、上記3つのデータ収集プロトコルです。 開発者は、FTSO(Flare Time Series Oracle)とState Connectorにより、コストを最小限に抑えながら大量のデータを取り込めます。 期待値の高いFTSOの各プロバイダーにFLRトークンを委任してデリゲートも可能です。 Layer cakeでは、スケーラビリティを解決して異なるスマートコントラクト間をブリッジできるので、Flare NetworkにdAppsを移動もしくは他のブロックチェーンに移動も可能となります。 EVM互換でDeFi・NFT・ゲームなどの開発が可能 EVMをベースとした互換性があり、Flare Networkではイーサリアム上で開発していたdAppsの開発が可能です。 また、他のブロックチェーンとの相互運用性もあるので、開発だけでなく他のブロックチェーンと相互に移行もできます。 イーサリアム→Flare Network→別のブロックチェーンとブリッジできるので、dAppsの開発拠点が広がりますね。 Layer cakeによってセキュリティや処理スピード面の問題を解決していてブリッジの障害もありません。 DeFiやNFT、ブロックチェーンゲーム、ソーシャルネットワークのdAppsを作ることもFlare Networkなら可能です。 カナリアネットワーク「Songbird」がFLRガバナンスの第一段階を担う 4. Flare:メインネットワークでFLRがネイティブ通貨 3. Songbird:カナリアネットワークでSGBがネイティブ通貨 2. coston:Songbirdのテストネットワーク 1. coston2:Flareのテストネットワーク Flare Networkは目的の異なる4つのネットワークあります。メインがFlareであり、テスト用のカナリアネットワークは「Songbird」です。 SongbirdはメインのFlareに導入する前に実践として機能をテストしています。基軸トークンは$SGBです。テスト用とはいえ、一般ユーザーが利用できるメインと機能性が変わらないブロックチェーンです。 Songbirdのコミュニティで提案が提出され、投票により方針が決定します。承認されるとメインのFlareに導入するか本格検討される流れです。つまり、SongbirdはFlare Networkのガバナンスの第一段階といえます。 costonとは coston/coston2はどちらも開発者用のテストネットワークです。一般ユーザー向けではありません。 CチェーンからPチェーンにFLRを移動してステーキングが可能 Flareの2つのチェーン Cチェーン:スマートコントラクトに使用されるコントラクトチェーン Pチェーン:ステーキング対応であり報酬を提供するためのプラットフォームチェーン Flare Networkは上記2つのチェーンを使用していて、その間は相互運用できます。 コミュニティとして大部分が使用しているのがCチェーンです。このスマートコントラクトが動作するCチェーンから、ステーキングが行われるPチェーンに$FLRを移動できます。 ステーキング開始時での最少額は50,000FLRなので、2023年12月時点の価格で10万円強です。14日間以上からステーキング可能となっており、2週間ごとにFlareのステークツールから報酬を請求できます。 ステーキング報酬のためにFlare Networkを利用するならまずはFLRを用意してくださいね。 Flare Networkで使えるフレアトークン($FLR)の概要 フレアトークンはFlare Networkで使用するネイティブトークンです。 DMMビットコインやビットフライヤーなどの国内仮想通貨取引所にも上場しているので気軽に購入できます。 そんなフレアトークンの使い道やトークノミクスなどの概要を解説します。 フレアトークンの概要 $FLRはFlare Networkのステーキングやガバナンスなどに使用される $FLRをラップしてWFLRとしてDeFiなどに使用できる フレアトークン($FLR)のTokenomics $FLRはFlare Networkのステーキングやガバナンスなどに使用される フレアトークンの使用例 バリデーターへステーキング ガバナンストークン 取引手数料の支払い FTSOへの委任 WFLRを保有してエアドロップの獲得 フレアトークンはFlare Networkのステーキングやガバナンスとして使用する機会が多いです。 メインのCチェーンからステーキングのPチェーンにFLRを移行できるようになり、FLRの保有で報酬を得やすくなりました。 Flare Network特有なのは、FTSOへの委任も可能という点です。FTSOでは外部データ提供者から情報を受け、トークン価格を正確に計算しており、対価としてFLRやSGBを受け取ります。 このデータ提供者にFLRを委任して報酬を共有できます。ステーキングよりも報酬獲得の頻度が高く、受け取りやすいのがメリットです。 WFLRに変換する必要がある エアドロップ獲得も、FTSOへの委任もフレアトークンをそのまま使用できません。ラップしてWFLRに変換してから使用します。ラップするにはFlareのポータルサイトにウォレットを接続してラップすればOKです。 $FLRをラップして$WFLRとしてDeFiなどに使用できる フレアトークン/FLRは、Flare PortalでラップされたWFLRに変換できます。 メタマスクやレジャーなどのハードウォレットなどでFLRを保有し、Flareポータルでウォレットを接続します。上の画像のようにフレアトークンのバランスで「Wrap」を選択すれば変換可能です。 WFLRは、Flare Network上の他のEVM互換dAppsやスマートコントラクトで使用できます。DeFiやNFT、音楽などさまざまなdAppsにWFLRとして使えるので利用用途が広がりますね。 フレアトークン($FLR)のTokenomics コミュニティへの割り当て(FlareDrops) 58,300,000,000(58.3%) クロスチェーンインセンティブプール 20,000,000,000(20%) チームやアドバイザー、早期後援者 21,700,000,000(21.7%) ※フレアネットワーク公式Xのポストより フレアトークンの総供給数は100,000,000,000FLRです。 コミュニティへの割り当てが58.3%と大部分を占めていますね。これはインセンティブやエコシステムのサポートプログラムを通してコミュニティに再分配されるトークンです。 このうち28,524,921,372FLRがFlareDropsとして割り当てられ、15%は2023年1月に配布完了しました。残りの85%は36か月にわたって段階的に配布されます。 クロスチェーンインセンティブは、他のブロックチェーンからFlare Networkにもたらされる価値の開発のために使用される開発費です。残りはチームやアドバイザーの保有分です。 フレアトークン($FLR)のエアドロップ概要 Flare Networkはもともとリップル(XRP)の機能拡大のために開始されたプロジェクトでした。そして、2020年12月時点のXRP保有者に対してエアドロップを提供しています。 プロジェクト概要は初期から更新され、現在はスマートコントラクト機能を複数のブロックチェーンに統合するネットワークに方針を変えています。 以後のエアドロップはXRP保有者ではなく、WFLR保有者に配布するので配布予定や参加方法を解説します。 フレアトークンのエアドロップ概要 フレアトークン(FLR)のエアドロップ配布予定 フレアトークン(FLR)のエアドロップの参加方法 フレアトークン(FLR)のエアドロップ配布予定 初回/2023年1月 28,524,921,372FLR 35カ月目まで/2023年3月~2025年12月 676,040,637FLR×35回 36か月目/2026年1月 584,760,871FLR 第1回のフレアトークンのエアドロップは予定通りXRP保有者に対して行われました。 2回目以降は、WFLRトークンの保有者かつFTSOにデリゲートした対象者にエアドロップされます。 1か月ごとにウォレットにあるWFLRの保有量が計算され、月末にエアドロップを請求できる流れです。Flare Portalにウォレットを接続して、WFLRにラップしておくと保有量としてカウントされます。 ちなみに、国内取引所「SBI VC トレード」ではフレアトークンのレンディングによってラップ・デリゲートまで委託可能です。SBI VCトレードではラップとデリゲートの代行を行っているので、双方の報酬を獲得できます。 デリゲートの報酬次第では多くのFLRを得られるので将来性に期待して利用するのも良いですね。 【SBI VCトレードの登録方法・使い方】入出金・仮想通貨売買まで徹底解説 フレアトークン(FLR)のエアドロップの参加方法 推奨ウォレット MetaMask Bifrost Wallet Ledger Safepalなど SBI VCトレードなどの国内取引所を使わずに報酬を獲得する流れを解説します。 フレアトークンのエアドロップに参加するため、上記のような仮想通貨ウォレットにFLRを準備しておきましょう。 FLRトークンは国内取引所でも購入可能です。購入後にMetaMaskなどにFLRを移動しておきます。 おすすめの仮想通貨ウォレットを種類別に紹介!自分に合った選び方も解説 Flare Portalにアクセスします。 ウォレットを接続しましょう。 FLRの残高が表示されるので「Wrap」をクリックしてラップします。これでWFLRの保有者となり、エアドロップ対象の保有量のカウントが開始されます。 FTSOのプロバイダーにデリゲートするには「Delegate」をクリックして、移譲する数量を選択してください。 FTSOのプロバイダー一覧はFlareMetricsを見て有望な提供者を決定してくださいね。 以上でWFLRの保有とデリゲートが完了するので、エアドロップの参加手続きは完了です。 Flale Portalに報酬が表示されるので月末に請求しましょう。 フレアトークン($FLR)の将来性 フレアトークンはFlare Networkの展開によって需要が高まると予想されます。 今後、期待のトークンとして将来性があるのか解説します。 フレアトークンの将来性 継続的なエアドロップで注目度が高まる 上場している国内取引所が多く日本人の利用者増にも期待できる スマートコントラクト機能の統合で需要が高まる 継続的なエアドロップで注目度が高まる フレアトークンがユーザーにもたらすエアドロップは、2026年1月まで毎月実施されます。 途中参加するにはWFLRの保有とデリゲートをすれば完了です。簡単なのでエアドロップ目当てのユーザーが増えて需要が高まると考えられますね。 FLRを購入するユーザーが増えるとそれだけ価値が上がります。 受取ったFLRの将来価値に期待するユーザーが、すぐ売却せずに保有し続けると売り圧による下落も抑えられます。 エアドロップ数量は減る 実際に、2023年3月には保有量の20%程度もらえていたエアドロップが、同年10月には6%程度まで減りました。エアドロップ対象者が増えるとそれだけもらえるトークンも減少します。 上場している国内取引所が多く日本人の利用者増にも期待できる フレアトークンは、金融庁と日本暗号資産取引業協会(JVCEA)に上場が承認され、続々と国内取引所で取引できるようになりました。 2023年末、SBI VCトレードをはじめとする国内取引所8社に上場しています。 もともとフレアトークンは仮想通貨XRPにスマートコントラクト機能を追加するためのプロジェクトであり、XRPは日本国内のインフラパートナーが多く日本市場に根強い関係を持っていました。 その関係性もあり、XRP保有者へのエアドロップが開始する前からフレアトークンは国内取引所に上場する審査が始まっていたのです。 XRPを通してフレアトークンへの利用者が増加して、国内の利用者増にもつながると、取引量が多い人気トークンになる将来性はあります。 スマートコントラクト機能の統合で需要が高まる Flare Networkの特徴は複数ブロックチェーンの相互運用性やEVM対応ですが、設立時はXRPにスマートコントラクト機能を統合することが目標でした。その目標は現在も引き継がれています。 「FAsset」と呼ばれる機能により、XRP含めてBTCやDOGEなどの非スマートコントラクトトークンをFlare Network上で使用できるようになります。 上図のように、BTCはFBTC、XRPはFXRPとしてFlare Network上のdAppsで利用できます。 DeFiやNFT、メタバース、レンディングなどさまざまな機能で利回りや報酬が獲得できるのはメリットです。 2023年12月時点ではCostonテストネットでベータ版が公開されており、メインネットでの公開も遠くありません。 Flare Networkの展望が明るいので将来性にも期待できます。 フレアトークン($FLR)を購入できる国内取引所一覧 取引の種類 取扱銘柄数 取引手数料(販売所) 取引手数料(取引所) SBI VCトレード 現物取引 レバレッジ取引 28種類 無料(スプレッド有り) 現物取引・・・メイカー:-0.01% / テイカー:0.05% レバレッジ取引・・・レバレッジ手数料が別途必要(ファンディングレートによる) bitFlyer 現物取引 レバレッジ取引 33種類 無料(スプレッドあり) 約定数量×0.01~0.15% Coincheck 現物取引 29種類 無料(スプレッド有り) Maker:0.000~0.050% Taker:0.000~0.100% Itayose:0.000~0.050% ※Itayose(板寄せ)手数料は2024年3月27日14時(予定)のリリース後から適用 GMOコイン 現物取引 レバレッジ取引 暗号資産FX 26種類 無料(スプレッド有り) 現物取引・・・Maker:-0.01~-0.03% / Taker:0.05~0.09% レバレッジ取引・・・無料 ※ロスカット手数料、レバレッジ手数料、強制決済手数料は別途必要 暗号資産FX・・・無料 ※レバレッジ手数料、強制決済手数料は別途必要 DMM Bitcoin 現物取引 レバレッジ取引 38種類 無料(スプレッド有り) BTC/JPY:73円/取引単位 BITPOINT 現物取引 22種類 無料(スプレッド有り) 無料 bitbank 現物取引 38種類 無料(スプレッド有り) メイカー:0~-0.02% テイカー:0~0.12% BitTrade 現物取引 39種類 無料(スプレッド有り) 通貨・HT払いによる フレアトークンを購入できる国内の仮想通貨取引所をまとめました。 この中では、FLRのラップとデリゲートを代行するSBI VCトレードがおすすめです。 有名どころの取引所ならFLRが上場しているので国内でも売買しやすいですね。 フレアトークン($FLR)のまとめ フレアトークンのまとめ EVM互換のブロックチェーンでFlare上にdAppsを移動しやすい FTSO・StateConnector・LayerCakeからデータ収集する カナリアネットワーク「Songbird」の基軸はSGBトークン FLRをPチェーンに移動してステーキング可能 FLRのエアドロップは2026年1月まで続く この記事では、仮想通貨FLR/フレアトークンとプロジェクト概要を解説しました。 複数のブロックチェーンの相互運用が可能で、EVM互換のブロックチェーンであるFlare Networkは日本でも注目されています。 XRPだけでなくBTCやDOGEなどのスマートコントラクト非搭載のトークンをFlare上で運用できるのはメリットが大きいです。 エアドロップは途中参加できるので、フレアトークンの将来性に期待するなら検討してみてくださいね。

プロジェクト
2024/03/08仮想通貨チェーンリンク/$LINKとは?特徴や将来性を解説 – 2024年度版
チェーンリンク (Chainlink/$LINK) はブロックチェーン外の要素をやり取りするオラクルを扱った仮想通貨プロジェクトです。 2024年3月時点で、Chainlinkの$LINKトークンは時価総額が約1兆7500億円で第14位になっています。 Chainlink($LINK)は、AAVEやCompound、GMXなど著名なDeFiプロジェクトで採用されており、オラクルの代表格と言えるプロジェクトです。 そんな仮想通貨Chainlink($LINK)について以下のポイントから解説しています。 この記事のポイント Chainlink($LINK)はオラクルを扱う代表的なプロジェクト オラクルはブロックチェーン外の情報をやりとりを仲介するシステム 分散性に配慮された設計で、トラブル発生のリスクが軽減されている RWA(現実資産)との親和性も高く、今後も注目点が多い 仮想通貨Chainlink($LINK)は仮想通貨取引所Bitgetで扱われています。 Bitgetでは、$LINK以外にも数百種類の通貨の取引が可能です。是非チェックしましょう。 |Bitgetの口座を開設する| チェーンリンク (Chainlink/$LINK)とは? = 分散型オラクルの代表格 Chainlink($LINK)とは、分散型オラクルを提供しているプロジェクトです。前提知識となる部分も含めて以下の順番で解説していきます。1つずつチェックしていきましょう。 ・オラクルの概要 ・ChainlinkとLINKトークンの概要 オラクルの概要 ブロックチェーンや仮想通貨の文脈における「オラクル」とは、ブロックチェーン外の情報のやり取りを仲介するシステムを指します。 スマートコントラクトはブロックチェーンの可能性を大きく広げましたが、オラクルが無いとそのポテンシャルを十分に発揮できません。なぜならブロックチェーンはブロックチェーンの外にある情報を扱えないためです。 仮にスマートコントラクトを利用して公正に契約を管理できたとしても、トリガーとなる情報が得られないとそのポテンシャルは狭まります。 例えば、農家がスマートコントラクトを利用し、天気に左右されがちな作物の収穫に対して保険を掛けるとしましょう。この場合、天気の情報がないと保険の補償はなにを基準に行うのか?補償のトリガーは何か?という懸念点が生じます。 ブロックチェーン外の情報を提供できるオラクルがあれば、天気の状況に応じて補償を行うトリガーとなる情報をブロックチェーン上で保険を提供するサービスに提供可能です。 実際にChainlinkを活用して、降雨量などをもとに保険を提供する事例もあります。 ChainlinkとLINKトークンの概要 Chainlink ($LINK) は、前述のオラクルの代表格と言えるプロジェクトです。多種多様な商品を展開しており、採用されているプロダクトも多岐にわたります。 また、一般的に想像されるオラクルのみならず、Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP)と呼ばれる相互運用性ソリューションも提供しています。 Chanlinkでは上限が10億枚のLINKトークンが発行されており、2024年3月時点で時価総額ランキング14位に位置しています。 [caption id="attachment_100269" align="aligncenter" width="586"] 引用元:Chainlink[/caption] 詳細は後述しますが、Chainlinkは分散型オラクルのためオラクルの運用に当たりさまざまな主体が関わっています。 $LINKは、Chainlinkのエコシステムに参加する費用や報酬として利用されるなどの用途を持っています。 |Bitgetで$LINKを購入する| チェーンリンク (Chainlink) の特徴 これから、Chainlink($LINK)の特徴について解説していきます。Chainlink($LINK)の特徴をひとつずつチェックしていきましょう。 ・分散性が高い ・多数のプロダクトに採用 ・さまざまなプロダクトを公開 分散性が高い 前述したオラクルには、中央集権型のものと分散型のものがありますが、Chainlink ($LINK) は分散型のオラクルにあたります。Chainlinkは基本的にオラクルの運用に伴い、複数のデータと複数のノードなどで構成されるオラクルネットワークを通してサービスを提供しています。 単一の主体のみによって情報が提供される場合、ハッキングや賄賂による不正・シンプルなトラブルといったリスクが発生し、情報が不正確なものだったときに大きな損害が発生する可能性があります。 例えば、DeFiのレンディングプロトコルの多くはオラクルを採用しており、オラクルや複数のシグナルをもとに清算を実行するのが一般的です。清算のトリガーとなる情報自体が間違っていた場合、清算が上手く働かずレンディングプロトコルの安定性が大きく損なわれる可能性があります。 分散型であってもそういったリスクはゼロではありませんが、単一の主体によって運用されるよりもリスクは下がります。(ただし、データを扱うプロセスは、モデルやプロダクトによって異なります) 多数のプロダクトに採用 Chainlinkは、すでにさまざまなプロトコルに採用されており、もっとも普及しているオラクルの1つです。あらゆるプロジェクトで採用されており、仮想通貨関連のサービス、とくにDeFiでは聞き馴染みのある名前も多いでしょう。 Chainlink ($LINK) を採用しているDeFiプロジェクトの一例 AAVE Compound SYNTHETIX GMX PancakeSwap dYdX さまざまなプロダクトを公開 Chainlink ($LINK) は多種多様なプロダクトを公開しています。 Chainlink ($LINK) が展開しているプロダクトの一例 CCIP DATA STREAMS MARKET & DATA FEEDS PROOF OF RESERVE FUNCTIONS AUTOMATION VRF CCIPは、Chainlinkが公開している相互運用性のソリューションで、異なるブロックチェーン間のトークンの転送やメッセージの転送、プライベートとパブリックチェーンの接続などに対応しています。 DATA STREAMSは、先物などを扱ったプロトコルに採用されることが多く、高速に市場データを提供します。 MARKET & DATA FEEDSは、通貨・商品を含むさまざまなものの価格、気象・経済・企業・スポーツなど幅広いデータを提供するプロダクトです。 PROOF OF RESERVEは、オフチェーンの準備金・担保を証明し、透明性を確保するためのプロダクトで、透明性を確保しにくいオフチェーンベースのプロジェクト・組織に活用されます。 FUNCTIONSはさまざまなAPIからのデータ取得、AUTOMATIONは効率化、VRFはNFTやGameFiなどで使用されがちなランダムの生成などを行います。 |Bitgetで$LINKを購入する| チェーンリンク (Chainlink/$LINK) とオラクルの仕組み [caption id="attachment_100278" align="aligncenter" width="660"] 引用元:Chainlink[/caption] Chainlink ($LINK) のオラクルが具体的にどう機能するのかについて、分散型オラクルネットワークを通して価格を取得するケースを例にチェックしていきましょう。 Chainlinkがスマートコントラクトに送信する価格を作成するために、起点となるのがさまざまな取引所などからデータを取得しているプロバイダーです。そういったプロバイダーの情報の中から、いくつかをChainlinkのノードが参考にします。 複数の情報を参考にしたノードたちは、その情報を1つのデータに集約し、改ざんへの耐性を持つデータにしてスマートコントラクトで使用可能になります。 上記のような形でブロックチェーン上において、利用可能になった価格の情報は前述したレンディングプロトコルの担保の評価などに用いられます。上記はあくまで一例でプロダクトやモデルによって、仕組みは異なるため注意が必要です。 |Bitgetで$LINKを購入する| チェーンリンク (Chainlink/$LINK)の競合との比較 画像:DeFi Llama オラクルを扱っているのは、Chainlink($LINK)のみではありません。いくつか競合プロジェクトが市場には存在し、その1つとしてPyth Networkがあります。 Pyth NetworkはSolanaブロックチェーン上で機能する分散型のクロスチェーン型データオラクルで、2023年11月に$PYTHのエアドロップを実施し、さらに2024年2月にはエアドロップ第2弾を実施し話題となっています。 DeFi Llamaのデータ(画像参照)によると、Pyth ($PYTH)を採用しているDeFiプロトコルの数は2024年3月時点で166、TVS (Total Value Secured) は約35億ドルとなっています。対するChainlink ($LINK)は374のプロトコルで採用されており、TVSは圧倒的首位の約269億ドルとなっています。 その他にもオラクルを扱っているものはいくつか見られますが、現時点ではさまざまな面からChainlink ($LINK) は代表的なオラクルとなっており、時価総額や普及度などから見ると圧倒的な存在と言えるでしょう。 チェーンリンク (Chainlink/$LINK)の今後や将来性 Chainlink($LINK)の今後や将来性については確定的なことは分からないものの、いくつか明るいポイントがあると言えます。 すでにさまざまなプロトコルで採用されているように、オラクルに大きな需要があるのは確かです。Chainlinkはしばしば、オラクルと接続されておらず、現実世界の情報を扱えないブロックチェーン・スマートコントラクトを「インターネットに接続されていないコンピュータ」と表現しています。 今後、Chainlinkが扱っているオラクルの領域は、オンチェーンでの活動が活発になればなるほど、重要になると考えられます。 また、近年ホットな話題になりつつあるRWA(現実資産)のトークン化といったトピックとも非常に相性の良い分野です。 RWAや現実世界のトークン化では、何らかの方法で現実世界のデータをオンチェーンに持ってくる必要があります。そのプロセスにおいて、Chainlinkが扱っている領域は親和性が高いと言えます。 RWAの領域はTradFiとの相性も挙げられることが多いですが、ChainlinkはANZという金融機関とCCIPを活用して、トークン化された資産を扱う実験なども行っています。 |Bitgetで$LINKを購入する| $LINKの購入方法 ChainlinkのLINKは、複数の国内・海外仮想通貨取引所で扱われています。 $LINKを取り扱う仮想通貨取引所 Bitget bitbank bitFlyer Coincheck GMOコイン LINKの購入にとくにオススメの仮想通貨取引所は「Bitget」です。 Bitgetをおすすめする理由 クレジットカード決済で日本円で暗号資産を購入できる ウェブサイトとスマホアプリともに日本語対応で安心 手数料の割引があったり、お得なキャンペーンを利用できる 多くの海外取引所では日本円での暗号資産の購入はできませんが、Bitgetであればクレジットカード決済で日本円で暗号資産の購入が可能です。 また、公式ウェブサイトとスマホアプリの両方が日本語に対応しており、はじめての方でも安心です。 さらに、Bitgetが発行するトークンであるBGBを使用すれば取引手数料が20%オフになったり、新規登録によるクーポン配布や入金に応じたキャッシュバックなど、様々なキャンペーンを利用することができます。 Bitgetの登録はこちら Bitget(ビットゲット)使い方まとめ!ログイン・入出金や取引方法を解説 チェーンリンク (Chainlink/$LINK)についてまとめ この記事では、Chainlink($LINK)について解説しました。 すでにさまざまな場所で採用され普及していますが、まだまだ伸びしろや注目点の多いプロジェクトです。 オラクルの主要な存在として、今後も注視していきたい存在と言えるでしょう。 |Bitgetで$LINKを購入する| 画像出展元:sdx15 / Shutterstock.com 免責事項 ・本記事は情報提供のために作成されたものであり、暗号資産や証券その他の金融商品の売買や引受けを勧誘する目的で使用されたり、あるいはそうした取引の勧誘とみなされたり、証券その他の金融商品に関する助言や推奨を構成したりすべきものではありません。 ・本記事に掲載された情報や意見は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性、完全性、目的適合性、最新性、真実性等を保証するものではありません。 ・本記事上に掲載又は記載された一切の情報に起因し又は関連して生じた損害又は損失について、当社、筆者、その他の全ての関係者は一切の責任を負いません。暗号資産にはハッキングやその他リスクが伴いますので、ご自身で十分な調査を行った上でのご利用を推奨します。(その他の免責事項はこちら)

プロジェクト
2024/02/29Blast BIG BANGコンペ特集|3000以上の応募から選ばれた47プロジェクトを全紹介!
2月23日、Blastは以前より行われてきたBIG BANGコンペティションの選出プロジェクトを発表しました。 Big Bang judging is COMPLETE. 3000+ teams started building on Blast during the competition. We hand-picked 47 winners with help from @Izebel_eth @danrobinson @0xfoobar @_jaechung @loomdart @cl207 @caseykcaruso @santiagoroel @rewkang @will__price @Evan_ss6 Winners below👇 pic.twitter.com/bKrwZuiDA1 — Blast (@Blast_L2) February 24, 2024 コンペには3000以上の応募があり、そこから各VC関係者たちの協力を得ながら、47のプロジェクトが選出されました。 公式Twitterによると、選考に落ちてしまったプロジェクトにも良いプロジェクトが数多くあったとのことであり、 選出された47プロジェクト以外にも、BIG BANGコンペに参加した全チームに追加のエアドロップを割り当てるとのことです。(エアドロップ配布は5月の予定となっています) 今回の記事では、Blastの簡単な説明から、選出された47プロジェクトを簡単な概要とともに全て紹介していきます。 Blastとは? Blur創設者による新たなイーサリアムレイヤー2 Blastは、ネイティブイールドを備えたレイヤー2ネットワークです。Blastは、Pacman氏(@PacmanBlur)によって立ち上げられましたが、Pacman氏はNFTマーケットプレイス「Blur」の創設者でもあります。 昨年から、開発段階であったもののETHやステーブルコインの預け入れを行なっており、預け入れた資産に応じた利回りを受け取れる他、Blastポイントがもらえる仕組みを導入していました。 また、預け入れたステーブルコインは、自動的に新しいステーブルコイン「USDB」へと変換される仕組みとなっており、MakerDAOといった米国債と連動したプロトコルを用いることでUSDB保有者に利回りが還元されるようになっています。(ETHの場合は、Lidoからの利回りとなっています) TVLは右肩上がりに推移:20億ドルをこえる [caption id="attachment_108015" align="aligncenter" width="1549"] https://defillama.com/protocol/blast[/caption] [caption id="attachment_108017" align="aligncenter" width="1501"] https://defillama.com/chains[/caption] DefiLlamaによると、BlastのTVLは22億ドルを超えています。これは単純なTVLだけで比較をすると第5位のSolanaに次ぐ規模となっており、メインネットがローンチしていない開発段階のチェーンとしては異例のTVLを有していることが分かります。(記事執筆時) 2月29日にメインネットがローンチ:1月よりコンペティションが開催 Blast テストネットを公開しました! また同時に、次世代のDapps開発コンペティション、Blast BIG BANGを開催します。 2000億円超のTVLと10万ユーザーを誇るBlastコミュニティ向けのDappsを開発し、業界トップの投資家とネットワーキングする機会や、Blast Airdropの獲得を目指しましょう! pic.twitter.com/BmNWTTgIGj — Blast (@Blast_L2) January 18, 2024 Blastがこれほどの注目を集めたのは、Blur創設者によるレイヤー2という知名度や、ポイント制が導入されることによる将来のエアドロップへの期待、またParadigmといった大手VCが支援していることが要因として挙げられます。 そうしたBlastですが、2月29日にメインネットのローンチを控えています。エアドロップは5月に予定されており、今後のBlastエコシステムの拡大に注目が集まります。 また、1月19日には、BIG BANGコンペの開催を発表していました。当初2月16日としていたプロジェクトチーム提出期限が、現地時間表示の関係で混乱が生じ、最終的に2月19日1:00GMTまで延長されたりといったことがありましたが、無事終了し、2月23日に、コンペの結果発表がされました。 カテゴリーは8つに設定されており、合計で3000を超える応募がされ、その中から47のプロジェクトが選出されました。 次の章からは、選出された47プロジェクトを、カテゴリー別に全て紹介していきます。 Blast BIG BANGコンペ選出プロジェクト ここからは、47つのコンペ選出プロジェクトを紹介していきます。 カテゴリーは以下の8つとなっています。 Spot DEX Perp DEX レンディング GambleFi SocialFi NFTs/Gaming Misc インフラ 全てのプロジェクトが、詳細なプロジェクト内容やドキュメントの公開、サービスの開始をしている訳ではないので、プロジェクトごとに現時点で手に入れることの出来る情報量が異なることには注意が必要です。 Spot DEX Ambient Finance:CrocSwapを前身とする分散型取引所 Ambientは、CrocSwapを前身とする分散型取引所です。シングル・コントラクト・アーキテクチャーを採用しており、手数料を大幅に削減する一方で、ユーザーは単一のプラットフォームで担保をシームレスに管理することが出来ることが特徴です。 Ambientは、AMMの問題点として流動性が少数によって集中的に管理されていることを指摘しています。また同社は、民主的な流動性のためのプロトコルとプロダクトを構築することで、持続可能なDeFiの確立を目指しているとのことです。 昨年6月よりイーサリアムのメインネット上で稼働しているプロジェクトですが、イーサリアムレイヤー2であるBlastにも進出する形となります。 公式サイト:https://ambient.finance/ X:https://twitter.com/ambient_finance Thruster:Degenファーストの分散型取引所 Thrusterは、Degen(投機的投資に夢中な人のこと)を主な対象とした分散型取引所です。公正なローンチメカニズムと流動性ツールを備えることで、ユーザーに対して、より良いLP利回り機会、簡単な取引体験を実現するようになっているとのことです。 Swapや流動性提供も可能であり。流動性の提供に関しては、「V2」だけでなく「V3」(集中流動性)も選択することが可能となっています。 公式サイト:https://www.thruster.finance/ X:https://twitter.com/thrusterfi Bebop:取引アプリとAPIスイートを提供 Bebopは、効率的でシームレスなスポット取引を全ての人に提供するアプリ及びAPIスイートです。 Bebopでは、一度に複数のトークンを取引することで、時間やガス代を節約することが可能です。また、ガス代は最初に提示される価格にすでに含まれているために、予想以上のガス代が請求されることなく取引を行うことが可能です。 その他主要な特徴としては、以下の2つの取引モデルが統合されていることが挙げられます。APIを利用することで、Bebopの機能を活用することができます。 ・プロのマーケットメイカーによる見積依頼(RFQ) ・独立したオンチェーン・アグリゲーション・アルゴリズムのためのオークションを作成するインテント・ベースのシステム Bebopは、これまではイーサリアム、Arbitrum、Polygon、BNBに対応してきましたが、Blastにも拡大することが見込まれます。 公式サイト:https://bebop.xyz/ X:https://twitter.com/bebop_dex Mangrove:流動性のコントロールに注力したオーダーブックDEX Mangroveは、LPが他のプロトコルに滞留している流動性を再ステーク出来るオーダーブックDEXです。 Mangroveでは、オーダーブックに掲載されたオファーにコードを添付することができ、Blastエコシステム内の全ての流動性を集約し、利回りを倍増させることができます。 公式サイト:https://www.mangrove.exchange/ X:https://twitter.com/mangrovedao Ring Protocol:Blast上のAMM促進及びLPの資産利用の強化が目的 Ring Protocolは、流動性プロバイダーが原資産やRWAをステーキングすることで、スワップ手数料や利回りを得ることを可能にします。 テストネットが、1月22日より稼働しており、ユニークユーザー数は3万以上、取引高は100万ドルを超えています。Ring Protocolの正式なローンチは、Blastメインネットの稼働から1週間以内に行うとしています。 ガバナンストークン「$RING」を用いることで、LPにインセンティブが与えられることになっており、またBlastからのエアドロップ全てが、Ringコミュニティに対して確保されるとしています。 公式サイト:https://ring.exchange/ X:https://twitter.com/protocolring Perp Dex 100x Finance:Blast用に構築された高速オーダーブックPerp DEX 100xは、拡張性、資本効率、流動性に重点を置いた低遅延CLOB(Central Limit Order Book) DEXです。Blastのユーザーは、レバレッジをかけながら、あらゆる資産の先物やPerpを取引することができます。 また、他の同様のPer DEXと比較した際の100xの特徴として、ネイティブイールドの獲得や、Blastポイントや100xのポイントを同時に稼ぐことができるインセンティブがあることが挙げられます。 公式サイト:https://100x.finance/ X:https://twitter.com/100xfinance Blast Futures Exchange (BFX):自動ネイティブイールドを備えたオーダーブック永久先物取引所 BFXは、ネイティブイールドを備えた永久先物取引所です。BFXのユーザーは、残高に対して最大5%の利息を自動的に受け取ることが可能です。 また、BFXは、多くの取引所が抱える3つの問題点を指摘し、それに対するソリューションを提供します。 不良資産:現在の永久先物取引所には自動利回りの仕組みがない。 流動性の低さ:既存の自動マーケットメーカー(AMM)ベースの永久分散型取引所(DEX)は、取引可能な市場が限られているため、利益獲得や新規トークン上場の可能性が制限されている。 UI/UXの低さ:複雑で操作しにくいユーザー・インターフェースは、新規ユーザーの獲得の壁となっている。 これらに対するソリューションとして、自動利回りシステムやオムニチェーン流動性、ダイナミックAMMを備えたオールインワン取引プラットフォームをユーザーに対して提供しようとしています。 公式サイト:https://blastfutures.com/ X:https://twitter.com/blastfutures Blitz:Vertex Edge初のクロスチェーン展開。現在はテストネットが公開中。 Blitzは、CEXレベルのパフォーマンスを持つ、セルフカストディアル型の先物取引所、スポット取引所、マネーマーケットです。 また、同期オーダーブック流動性レイヤーである 「Vertex Edge」の最初のクロスチェーン展開でもあります。これにより、サービス開始初日から豊富な流動性および狭いスプレッドが提供されるとしています。また、Blitz(Blast)とVertex(Arbitrum)の間で、流動性を断片化させることなく、チェーン間の流動性を融合し、単一の統一されたオーダーブックとして表示され、BlitzとVertexユーザーの両方がアクセス出来るようにもなっているとのことです。 現在はテストネットが公開されています。Faucetの機能も備わっており、USDB・WETH・USDTの好きなトークンいずれかを用いて、Blitzを試してみることが可能となっています。 公式サイト:https://blitz.exchange/ X:https://twitter.com/tradeonblitz Bloom:リベース資産に特化した初のレバレッジDEX Bloomは、Blastのネイティブイールドとオファーを利用した完全分散型のレバレッジ取引とMMプラットフォームを開発しています。 また、その他にも以下の要素を実現しようとしています。 ガスレス、ワンクリック取引 トレーダーと流動性プロバイダーの双方への利回り 最大50倍のレバレッジ CEXのような合理化されたエクスペリエンスを提供しながら、オンチェーン執行とセルフカストディを実現 USDBを使用したデルタニュートラルなマーケットメイキング保管庫(vault) そして、ETHとUSDB(Blastのステーブルコイン)の両方がBlastとスマートコントラクト上で自動リベースされることによって、LPはUSDBのリベースから利回りを得るとともに、プラットフォーム手数料の一部を得ることも可能となっています。 公式サイト:https://bloom.trading/ X:https://twitter.com/bloomonblast InfinityPools.finance:清算なし、カウンターパーティ・リスクなし、オラクルなしでのレバレッジを提供 InfinityPoolsは、清算なし、カウンターパーティ・リスクなし、オラクルなしで、あらゆる資産に無制限のレバレッジを提供できる分散型取引所です。 多くの先物取引所では、清算リスクを軽減するために最大レバレッジ、取引可能な資産、ポジションサイズを制限しています。またトレーダーには清算リスクが付きまといます。これらは利益を最大化したいトレーダーにとっては、不都合です。そこでInfinityPoolsは独自のレバレッジを導入することで、多くのトレーダーたちからの需要に応えます。 具体的な仕組みの一例として、「清算なし」について解説します。清算がされない(ポジションを常にオープンにしておくことが可能)というのは、レバレッジの利息を支払う限りにおいてという意味合いとなっています。 InfinityPoolsでは、預託された担保やトレーダーの未実現PnLを使用して金利を支払う仕組みとなっており、ポジションが金利を支払うための担保と含み益を使い果たし、トレーダーによって決済されない場合、(TWAPまたは成行注文によって)決済されるようになっています。 公式サイト:https://sandbox.infinitypools.finance/ X:https://twitter.com/infpools SynFutures:Oyster AMMを活用したDEX SynFuturesは、最大レバレッジ100倍のPerp DEXとBlastによるネイティブ利回りを提供するDEXです。また、Oyster AMMを活用していることが特徴です。 Oyster AMMモデルは、特定の価格帯に流動性を集中させ、レバレッジを組み込んで資本効率を高めています。UniSwap v3のようなスポット市場に特化した流動性モデルとは異なっており、デリバティブに特化した証拠金管理と清算のフレームワークであることが特徴となっています。また、単一のトークンを利用しながら、両面流動性の概念を取り入れることでトークン・ペアの両端に流動性を提供する必要性を排除しています。 上記のような単一トークン集中流動性以外にも、完全なオンチェーン・オーダーブックによるセキュリティ向上や、金融リスク管理メカニズムによるユーザー保護も特徴として挙げられます。 公式サイト:https://testnet.synfutures.com/?utm_source=x&utm_medium=link3&utm_campaign=v3testnet_link3#/market X:https://twitter.com/synfuturesdefi レンディング(Lending) Fragment:分散型ノンカストディアル型レンディングプロトコル Fragmentは、利回りの高い資産向けに最適化された分散型ノンカストディアル型レンディングプロトコルです。 Fragmentは、LRTやLPTなどの利回りを向上させるための資本効率の高い方法を提供することで、ユーザーがネイティブ利回り資産の利回りを高めることができる流動性ハブとなることを目的としています。 X:https://twitter.com/FragmentFi Juice Finance:Blastエコシステムでの利回りとポイントファーミングを最大化 Juiceは、レバレッジの効いたクロスマージン取引アカウントを可能にする分散型プロトコルです。ユーザーはJuiceダッシュボードを直接使用して、イールドファーミングやレバレッジスポット取引のためにBlast上の他のプロトコルにアクセスし、様々なトークンやエコシステムの報酬を得ることが出来るようになっています。 また、JuiceはBlastのDAppエコシステムにコンポーザブルなレバレッジをもたらし、貸し手にとってはパッシブAPYの獲得、借り手にとってはDapps間でマージン取引を行うことが出来るようになるとのことです。 公式サイト:https://www.juice.finance/ X:https://twitter.com/juice_finance MetaStreet:利回りインフラプロトコル MetaStreetは、利回りインフラプロトコルであり、あらゆる非流動資産は、MetaStreetのv2 自動トランシュメーカー(The ATM:Automatic Tranche Maker)によって、利回りを持つトークン(LCTs:Liquid Credit Tokens)に変換可能となります。LCTsはETH建てであり、10-125%のETH APRの獲得およびLSDfiに適合するようになっています。 The ATMは、既存の融資プロトコルの欠点を改善するものであり、具体的には以下のように機能するとのことです。 オラクルレス:融資限度額に対する一元的な価格オラクルへの依存を排除。 動的な金利モデル:ガバナンス主導の固定金利モデルを、預金主導の動的な金利モデルに置き換える。 権限なし:ユーザーが任意のコレクションのレンディングプールを権限なしでインスタンス化できるようにする。 また、LCTの利点は以下となっているとのことです。 長期ローンの有効化:これまで資本の非流動性を望まなかった貸し手が、ローン期間中いつでも二次流動性にアクセスに出来るようになることで実現。 下限価格のサポート/安定化:融資市場を深化させ、保有者による売り圧力を軽減するより高いLTVローンを奨励することによって実現。 収益の最大化:LCTは完全にコンポーザブルなトークンであるため、取引、LPの供給、Vaultでのレバレッジなど、DeFiのあらゆる側面で使用可能。 公式サイト:https://metastreet.xyz/ X:https://twitter.com/metastreetxyz Orbit Lending:ネイティブ流動性プロトコル Orbitは、Blast資産の貸し借りを容易にする分散型流動性プロトコルです。 Orbitプロトコルは、保有資産の追加利回りを得たい貸し手と、他の資産を担保に資産を借りたい借り手との間のマネーマーケットに注力しています。貸し手は、Orbit資産(oAssets)と引き換えに、あらかじめ決められた貸出期間の間、Blast資産を提供します。所定の貸出期間が満了すると、oAssetsは元本+経過利回りで償還されます。ユーザーは、サポートされているBlast資産を担保として提供し、プロトコルで定義された融資比率の下で借り入れを行うこともできます。 貸し手資産と提供された担保からのネイティブ利回りは、まずOrbitトークンに蓄積され、将来のブラスト利回り価値を現在に転送する媒体として機能します。その後、Orbitトークンが貸し手と借り手の両方に分配され、利回りを補助するために使用されることとなっています。 公式サイト:https://orbitlending.io/ X:https://twitter.com/orbitlending Pac Finance:Blast初のハイブリッド・レンディング・プロトコル Pac Financeは、Blast初のハイブリッド・レンディング・プロトコルであり、P2PローンとP2プールローンの両方を特徴としています。その他の特徴として、自己返済型ローン、ワンクリックのレバレッジ取引、インスタント・レンディング・ループなども挙げられます。 Pac Financeのプロトコルは、完全にオープンソースとなっています。このオープン性により、スマートコントラクト、ユーザーインターフェイスクライアント、またはAPIを介したイーサリアム・ブロックチェーンとのシームレスな統合と相互作用が可能になっているとのことです。 また、Pac Financeにおけるユーザー資金の保管は、スマートコントラクトによって管理されており、このコントラクトはオープンソースであるだけでなく、信頼できる第三者監査法人による正式な検証と包括的な監査を受けているとのことです。 公式サイト:https://pac.finance/ X:https://twitter.com/pac_finance Particle:あらゆるERC20トークンのレバレッジ取引にするプロトコル Particleは、あらゆるERC20トークンのレバレッジ取引を可能にするパーミッションレスでオラクル不要なプロトコルを構築しており、AMMをより発展させた「LAMM」(Leverage AMM)が特徴です。 トレーダーは、トークンのローンチ時であっても、レバレッジを使ってあらゆるトークンをロング/ショートすることが可能であり、LPは流動性の効率を高め、より高い利回りを得ることが可能となっています。 現在は、ベータテスト版が公開されています。 公式サイト:https://www.particle.trade/ X:https://twitter.com/particle_trade Blume:クロス担保レンディングプロトコル Blumeは、クロス担保レンディングプロトコルです。 詳細な情報はまだ明らかになってはいませんが、現在はwETHとUSDBのレンディングが可能となっています。 公式サイト:https://blume.fm/ X:https://twitter.com/blumefm Curvance:利回りの高い資産を対象としたクロスチェーンマネーマーケット Curvanceは、分散型金融プラットフォームであり、チェーンやプロトコル間の断片化に対処することを目的として、ステーブルコインの入金、収益、借入を容易にしていることが特徴です。また、オムニチェーンマーケット分野において地位を確立しようとしていることでも知られています。 クロスチェーンの資本効率を向上させる試みとして、Curve、Balancer、Velodrome、GMX、Pendleなどの分散型取引所の流動性を利用しています。既にArbitrum、Optimism、Scroll、Baseといったレイヤー2ソリューションをサポートしており、それにBlastが加わる見込みといえます。 公式サイト:https://www.curvance.com/ X:https://twitter.com/curvance GambleFi BetBIG:トークンステーカーに対する利益を重視 BetBIGはすべてのギャンブル活動のためのポータルサイトで、トークンのステーカーに100%の利益が発生する仕組みになっています。 アンチマネーロンダリング(AML)も重視しており、3段階のアカウント認証を用いることで、より良いセキュリティの実現に注力しています。 公式サイト:https://betbig.gg/?ref=twitter X:https://twitter.com/BetBIG_gg Decentral Games:ソーシャルで没入型のゲーム体験を提供するメタバースカジノ Decentral Gamesは、ソーシャルで没入型のゲーム体験を提供するメタバースカジノです。ゲームとしては、ブラックジャック、ルーレット、ポーカーなどがあり、最近ではモバイルアプリも発表されました。 現在、コミュニティ統合のためのガバナンス提案が可決されたことにより、3段階でのアップデートが展開されることが決まっています。 フェーズ 1: BAGトークンの移行及びBAGユーテリティの追加。 フェーズ 2: ポーカーアーケードのアップデート フェーズ 3: ウェアラブル(Wearable)ユーティリティのアップデート トークンの移行やフェーズ間の移行が近づき次第、新たに情報が更新されるとのことです。 公式サイト:https://bag.win/ X:https://twitter.com/decentralgames IKB:クリプト上に構築されたファンタジースポーツプラットフォーム IKBは、クリプトレールに構築されたデイリーファンタジースポーツプラットフォームです。 これまではBase上にてサポートされていましたが、それがBlastにも拡大していくものと思われます。 公式サイト:https://ikb.gg/ X:https://twitter.com/ikbdotgg Insrt:モバイルベッティングマーケットプレイス Insrtは、ユーザーがクリエイター、コミュニティ、ブランドから利益を獲得出来るモバイルベッティングマーケットプレイスです。ユーザーはInsrtをプレイし、他のユーザーが作成した賞品を獲得することが出来ます。また、ユーザーは、10倍から1000倍のベッドを行うことも可能であり、サプライヤー側は手数料とエンゲージメントを得ることができます。 仮に、ユーザーが本賞品を獲得できなかったとしても、プレイするたびに、もしくはのユーザーがミントをすることで報酬を得ることができます。これを実現するのが、$MINTトークンです。$MINTはリベーストークンであり、$MINTトークンを保有しているユーザーは、他のユーザーのミントから$MINTの分配を受け取ることによって報酬を得る仕組みとなっています。 公式サイト:https://app.insrt.fun/mint X:https://twitter.com/insrtapp YOLO Games:オンチェーンゲームのスイートを提供 YOLO Gamesは、オンチェーンゲームのスイートを提供しており、ゲームから発生した手数料の100%をプレイヤーに還元する仕組みとなっています。 また、全てのゲームが完全にオンチェーンであるため、証明可能で公平であり、全てのランダム性が常に検証可能となっていることも特徴です。 公式サイト:https://yologames.io/ja X:https://twitter.com/YOLO_Blast TideFlow:2つの製品を提供中 TideFlowは未だ多くの情報は出ていません。 Blastの発表によれば、TideFlowは現在、2つのプロダクトによって構成されており、GambleFiゲームは、トレーダー同士を戦わせるテンポの速いプライス・アクション・トレーディングのゲームであり、DeFiプロトコルはベンチマークに対する価格の動きをトークン化するものとなっているとのことです。 X:https://twitter.com/TideFlowDAO SocialFi Fantasy:ファンタジーゲームとSocial Fiの融合 Fantasyは、ファンタジーゲームとSocial Fiを融合したSocialFiトレーディングカードゲームです。クリプト分野のX(Twitter)インフルエンサーのカードを収集し、彼らの毎週のXパフォーマンスに基づいて報酬を得る仕組みとなっています。 カード取引量に応じてETHをパッシブに獲得することが可能であり、1.5%のロイヤリティを獲得することが可能となっています。これは、Blastが提供する4%のネイティブETHイールドに追加して獲得可能です。 また、FANポイントシステムも導入されており、同ポイントはBlastやETHの報酬に加えて、新しく発行される限定カードパックや、さらなる特典が提供される予定とのことです。また、最初のFantasyエアドロップは、コミュニティ主導のパックとFANエアドロップで行われることが発表されています。 公式サイト:https://www.fantasy.top/ X:https://twitter.com/fantasy_top_ NFTs/Gaming BAC Games:レーシングカークラブゲーム BAC(Blast Auto Club) Gamesは、レーシングカークラブゲームです。また、BAC Gamesが提供するすべてのゲームでは、$BACトークンが使用されることになっています。 BACは、友人とレーシングカークラブを構築、開発、管理し、$BACトークンの報酬を獲得することをテーマに構築されています。 v1では、PVEモードを中心としています。Role-NFTの保有者は皆、協力して車を製造し、さまざまな都市を走ってBACトークンを獲得する必要があります。十分な数のRole-NFTホルダーのプレイヤーがクラブに参加し、協力して3種類の道具を手に入れて初めてレーシングカーを製造することが出来ます。レーシングカーはクラブに所属し、$BACトークンを獲得し、各メンバーの貢献度に応じて各クラブメンバーに分配されることになっています。 v2では、より多くのプレイモードのロックが解除され、「PVPモード」「3つのレベル(都市、国家、世界)でのレース協会会長選挙」「ゲーム内資産取引のためのオークションハウス」などが提供されるとのことです。 2024年の第一四半期には、v1が稼働する予定とのことです。 公式サイト:https://www.bacgame.io/ X:https://twitter.com/bac_web3 BLASTR:NFTローンチパッドプラットフォームおよびプロトコル BLASTRは、NFTローンチパッドプラットフォームおよびプロトコルです。払い戻し可能なNFTを導入し、Blastのネイティブイールドメカニズムを通じてクリエイターに新たな収入機会を創出することを目的としていますまた、BLASTRのコントラクトは、ERC721 NFT標準に準拠しており、あらゆるセカンダリーマーケットプラットフォームでNFTの譲渡や売却が可能となっています。 BLASTRは、透明な収益モデルを保証するために、生成された利回りに対してわずかな手数料を請求することとなっています。また、NFTの価格を設定する際に注意しなければならないのが、買い手にはタイムロックの期限が切れた時点で払い戻しを受けるオプションがあるということです。例えば、NFTを0.1ETHで鋳造し、0.2ETHで売却した場合、買い手はこのNFTに対して0.1ETHの払い戻しを受けることが可能となっています。 この払い戻しのシステムにより、BLASTRでは実質的に「コストフリー」でのミントが可能になっています。NFTがニーズに合わなくなった場合、返金手続きを開始することができます。払い戻しを請求すると、NFTはバーンされ、ロックされていたETHがウォレットに戻されます。さらに、払い戻されたNFTは後で再ミントすることもでき、クリエイターやコレクターにさらなる選択肢が提供されるようになっています。 BLASTRは、2024年第一四半期をリリース予定としているとのことです。 公式サイト:https://blastr.xyz/ X:https://twitter.com/blastr_xyz Blaze:誰でも利用可能なNFTローンチパッド Blazeは、誰でも利用可能なNFTローンチパッドです。クリエーターやアーティストは、コード不要のBlaze NFTローンチパッドを使用して、1分以内に独自のコレクションを作成し、ローンチすることができます。 Blazeを使用しているコレクションは、必ずしもBlazeチームによって承認されているわけではありませんが、これはBlazeが誰もがBlazeプロトコルを使用し、独自のコレクションを作成できるようにオープン化することをより重要に考えているためです。 Blazeでは、2種類のミントが提供されており、それぞれ以下のようになっています。 Traditional:誰もが慣れ親しんでいる通常のミントです。 Refundable:払い戻し可能なことが特徴です。指定されたロックアップ期間(例:30日間)が終了した後、保有者がNFTをそのNFTのミント価格(ETH)と交換することができます。コレクターはいつでも払い戻しの権利を放棄することも可能であり、放棄されるとミント価格がロック解除されロックアップエスクローからクリエイターに送られる仕組みとなっています。 公式サイト:https://www.blaze.ong/ X:https://twitter.com/blaze0ng Cambria:Runescape(MMORPG)にインスパイアされたゲーム Cambriaは、Degenネイティブであり、Runescapeにインスパイアされたゲームです。最初のミニゲーム「Degen Arena」では、公開アリーナでプレイヤー同士が1vs1の戦いを繰り広げるものとなってます。 Baseでのプライベートアルファでは、10万以上のトランザクションを記録し、23日間の内に5000ETHがステークされていました。また、Blast Dev Airdropチャートを独占し、$BLASTを100%プレイヤーに提供する予定であると発表されています。 X:https://twitter.com/playdegenarena Captain & Company:クロスプラットフォームの壮大な海戦を行うMMO Captain & Companyは、海戦を舞台とした冒険活劇MMOです。最大で10人の仲間を作り、クロスプラットフォームの海戦に参加し、取引可能なプレミアム通貨を奪い合う仕組みとなっています。 多人数プレイのアクセシビリティを重視しており、ブラウザ、モバイルで利用可能なだけでなく、無料でプレイすることも可能となっています。(しかし、船長としてプレイするには、オープンマーケットプレイスで船を購入するか、他のプレイヤーから船を借りる必要があります) 公式サイト:https://capnco.gg/ X:https://twitter.com/capncompany Munchables:現在、Munchablesのアンロックに向けたミッションが開始中 Munchablesは未だ、プロジェクトの詳細が明らかにはなっていません。しかしながら現在は、プレイヤーがBlaset ETHとUSDBをゲームにステークすることで開始できる「 Lockdrop」と名付けられたMunchablesのアンロックに向けたミッションが行われています。 30日間ロックされた1ETH(または同等のもの)ごとに、無料のMunchableミントを受け取ることができます。プレイヤーはLockdrop期間中にネイティブBlastエミッションを受け取り、すぐにMunchableの孵化を開始することができます。また、プレイヤーは、TVLに応じたSchnibblesを受け折る仕組みになっており、このSchnibblesを使ってMunchableを成長させます。Munchableのレベルアップによってポイントが貰えるようになっているため、Munchableを成長させることがプレイヤーの報酬拡大に寄与する仕組みとなっています。 公式サイト:https://www.munchables.app/ X:https://twitter.com/_munchables_ Wasabi:NFTレバレッジプラットフォーム Wasabiは、資産に裏付けされたNFTレバレッジプラットフォームです。既に、イーサリアムメインネットには2,000万ドルを超える取引高と、700万ドルのTVLを記録しています。Blastのスムーズな取引環境にユーザーと流動性をもたらすことを目的としているとのことです。 資産担保NFTデリバティブという仕組みを取る理由として、NFTはその性質上かなりの上昇を見せる可能性があり、合成インデックスに依存するPerpはそれを正当に評価することが出来ない一方で、資産担保デリバティブは、レバレッジのメリットを享受しながら、資産スポットを保持するという安全性がユーザーに提供されることを挙げています。 公式サイト:https://www.wasabi.xyz/ X:https://twitter.com/wasabi_protocol Spacebar:オンチェーンプレイグラウンド Spacebarは、ユーザーがステーキング、プレイ、交流、収益を得るためのBlastのオンチェーンプレイグラウンドです。PFP NFTを導入し、ソーシャル化、オンチェーンアイデンティティの構築を目的としています。 また、以下の2つの主要なコンポーネントで構成されていることも特徴です。 ゲーム:カジュアルなWebベースのオフチェーンとオンチェーンをハイブリッドしたゲーム。PvEとPvPモードを採用。 メタゲーム:メンバーが集まり、交流し、リーダーボードで競争し、ゲーム内コンポーネントやユーザー所有のアセットと接続するスクエアとポータル 公式サイト:https://www.spacebar.xyz/ X:https://twitter.com/spacebarxyz Plutocats:メンバーシップNFTの販売を通じてクリエイターに資金を提供 Plutocatsは、メンバーシップNFTの販売を通じてプールされた資本から得た収益を使用して、Blastエコシステムのクリエイターに資金を提供する方法を構築しています。Plutocatsでは、これを「ソーシャルステーキング」と呼称しています。 Plutocatsは、完全にオンチェーンに保存される生成型NFT pfpです。ユーザーはNFTをミントすることでPlutocatsのメンバーとなることが可能です。各Plutocatsの販売からのETHは、Blastネイティブ利回りを獲得するリザーブに送られます。 メンバーはいつでも退会して、リザーブの比例配分を請求することができます。 メンバー価格は継続的ダッチオークション (VRGDA) に基づいています。 最低価格は動的であり、Plutocatsの帳簿価額 (流通しているPlutocatの数 / リザーブ内のETHの量) に等しくなります。 メンバー価格は毎日の需要に応じて増減することになっています。 公式サイト:https://plutocats.wtf/ X:https://twitter.com/plutocatswtf nftperp:初のNFT永久先物DEX NFTperpは、NFT永久先物DEXであり、完全なオンチェーン指値オーダーブックによる集中したAMM流動性を特徴としています。BAYCやCryptoPunksといったブルーチップNFTプロジェクトをロングまたはショートすることが可能となっています。 NFTエコシステムの課題の一つとして、流動性の低さが挙げられます。NFTperpの試みはこうした課題へのソリューションと見做されます。NFTperpのミッションは、非流動性資産に永久先物をもたらすことであり、これによってより良い価格発見、ヘッジ、NFTの潜在的なユーザーベースの増加が可能になるとのことです。 公式サイト:https://nftperp.xyz/ X:https://twitter.com/nftperp Misc Thunder:初のオンチェーン「仲介」(brokerage) Thunder は、既存のすべてのチェーン、DEX、資産クラスを抽象化して集約するように設計された初のオンチェーン「仲介」です。 ユーザーは、CEXでの取引と同じように、あらゆるチェーン/DEXにわたって資産を取引できるようになります。 現在は、7チェーン上での取引が可能であり、ノンカストディアル型となっています。また、トランザクション手数料が0%となっていることも特徴となっています。 公式サイト:https://thunder.gg/terminal X:https://twitter.com/ThunderTerminal インフラ Baseline Protocol:ERC20トークン用の自動トークノミクスエンジン Baselineは、ERC20トークン用の自動トークンノミクスエンジンです。Baselineは、動的な供給モデルと基本的なマーケットメイク戦略を活用することで、新しいERC20に永続的なオンチェーン流動性と非流動性のレバレッジを即座に提供できるようになっています。 Baselineトークンがデプロイされると、Uniswap V3プールに初期流動性が自動的にシードされます。 ローンチ時には、トークン供給の100%がプロトコルによってオンチェーンに保持され、その価値を永久に保護するために使用されます。 Baselineは、供給全体を買い戻すのに十分な流動性をプール内に確保することで、ERC20 に本質的な「Baseline価格」(BLV)を保証するようになっています。これは、プロトコルが初期供給を所有していることによって可能となります。チームは自分自身や投資家に事前にトークンを発行することはできません。 代わりに、新しく発行された各Baselineトークンをプールから直接購入する必要があるため、プロトコルは流動性を蓄積できるような仕組みとなっています。 X:https://twitter.com/baselinemarkets Tornado Blast:Blastに特化した初の取引ボット Tornado Blastは、取引戦略の開発と実行におけるユーザーのエクスペリエンスを大幅に向上させる、Blastに特化した初の取引ボットです。 Tornado Blastの主要な特徴として、以下が挙げられます。 取引:Blast上であらゆる資産を高速で売買可能。 ブリッジ:ETHからBlastへの資金移動が容易になり、時間を無駄にする必要がなくなる。 パッシブ利回り:BlastでETHのパッシブ利回りを獲得。 スナイピングの起動:条件に応じてトークンの起動後すぐに購入。 スキャンと監査:スマートコントラクトデータの探索と分析を簡素化。 AI分析:過去の損益とパターンを考慮した、過去の取引と現在の保有者に基づくトークンのアップサイドのスコアを提供。 また、入金によるBlastの利回りは全て、Tornado Blastユーザーに還元されるとのことです。 公式サイト:https://www.tornadoblast.bot/ X:https://twitter.com/tornadoblastbot Blast Safe 詳細不明のため、割愛。 Brahma:Safe上に構築された高速かつ安全な実行環境 Brahmaは、Safe上に構築された、Blast上のDeFiをナビゲートするための高速かつ安全な実行環境です。 Blastの個人とチームの両方にとって頼りになるスイートになるように設計されており、プログラム可能な自動化、委任、合理化された実行を実現します。 また、セルフカストディからオンチェーンインタラクションを実行する際のUXの向上と、プロセスに伴うセキュリティ リスクの軽減に重点を置いていることも特徴です。 主要な機能としては、以下の5つが挙げられます。 アクセス制御:コンソール内の中心的なカーネルはメインアカウントであり、そのコンソールの所有者は管理者権限を排他的に保持しています。 実行:コンソールは、手動実行と自動実行の両方の柔軟性を提供しています。 オートメーション:コンソールオートメーションは、ユーザーが定期的なトランザクションやリスク管理などの自動ルーティーンを簡単に設定できるようにすることで、オンチェーンの運用を改善します。 安全性:Safeとシームレスに統合しています。 アクセシビリティ:ユーザーは、https://safe.globalを介して、またはSafeコントラクトと直接対話することにより、Safe Walletへの中断のないアクセスを維持することが可能です。 強力なUX:コンソールは、ポジションとリターンの概要を迅速に把握できる包括的な分析ダッシュボードを備えています。 公式サイト:https://www.brahma.fi/ X:https://twitter.com/brahmafi Banana Gun:TelegramとWebappでで利用できる取引ボット Banana Gunは、Telegramと(近日中に) Webappで利用できる取引ボットです。 今後のローンチをスナイピングしたり、すでに公開されているトークンを安全に取引したりできます。 Banana Gunの主要機能としては、「オートスナイピング」「マニュアルトレーダー」「アンチラグ」「プライベートトランザクション」などが挙げられます。 Banana Gunは、サービス対象のチェーンとして、イーサリアムやSolanaを挙げていましたが、これにBlastが加わる形です。 公式サイト:https://bananagun.io/ X:https://twitter.com/bananagunbot Gelato:Web3のクラウド プラットフォーム Gelatoは、Web3のための分散型バックエンドであり、オールインワンの Rollup-as-a-Serviceや一連の強力なWeb3ミドルウェアサービスを提供しています。これにより、開発者は様々なEVM互換ブロックチェーン上で自動化された効率的なスマートコントラクトを作成することが可能となります。 GelatoはWeb3 Functions、Automate、Relay、Gasless Walletといったサービスを活用しながら、トランザクション実行の合理化を行なっています。これによって、MakerDAOやPancakeSwapのようなDeFiプラットフォームからOptimismのようなスケーリングソリューションまで幅広くシームレスなユーザー体験を提供しています。 公式サイト:https://www.gelato.network/ X:https://twitter.com/gelatonetwork RedStone Oracles:データフィードを提供するモジュラーオラクル RedStoneは、最も急速に成長しているモジュラーオラクルであり、Blast Testnet上のデータフィードを「コア(プル)高性能モデル」と「クラシック (プッシュ) Chainlink互換インターフェイス」の2つで提供しています。また、この両モデルは、初日からBlastメインネットに導入されるとのことです。 モジュール式のアーキテクチャにより、ソースからスマートコントラクトまでデータの整合性を維持することが可能であり、20以上のチェーンをサポートしていることや、ニーズに合わせた3つの異なる統合方法(RedStone Core、RedStone Classic、RedStone X)を提供するなどして、柔軟性がありながら頻繁に更新される信頼性の高い多様なデータフィードを提供しています。 公式サイト:https://redstone.finance/ X:https://twitter.com/redstone_defi Hyperlock Finance:Thrusterの流動性を高めるために構築された利回りブーストおよびmetagovプロトコル Hyperlock は、Thruster上に構築され、Blast用に最適化された利回りブーストおよびmetagovプロトコルです。Hyperlockは、veTHRUSTとHyperlockのネイティブトークンのソーシャルアグリゲーションを通じて、Thruster LPとTHRUSTステーカーに増額された報酬を提供するものです。 THRUSTステーカーのは、THRUSTをロックし、ThrusterのVotingEscrowコントラクトで最大時間ロックされたveTHRUSTを表すhyperTHRUST流動性ステーキングトークンをミントできます。hyperTHRUSTをステークすることで、Thruster報酬、パフォーマンス手数料、HYPERを受け取ることができます。 また、HyperlockのveTHRUST残高により、流動性プロバイダーは流動性のみを提供する場合と比較して最大2.5倍の排出量増加を受け取ることが出来ます。LPは、Hyperlockで追加のHYPER報酬も蓄積するようになっています。 公式サイト:https://hyperlock.finance/ X:https://twitter.com/hyperlockfi Voyager(parsec):Blastネイティブブロックエクスプローラー Voyagerは、parsecによって開発されるBlastネイティブブロックエクスプローラーです。また、次世代ブロックエクスプローラー内に利回りとガスに関するBlastネイティブ機能を組み込んでいます。 parsecでは、ユーザーフレンドリーな方法で、トランザクション、アドレス、転送、ブロックを横断することが可能です。例えば、アドレスまたはトランザクションを入力して「parsec.fi/0x…」と入力するだけで、それがアドレスなのかトランザクションなのかがわかるようになっています。他にも、「トークン」「EOA」「NFT」「レンディング市場」「流動性プール」「ステーブルコイン」「LST」といった様々なタイプのカスタムレイアウトも提供しており、UI/UXの改善に努めています。 EVMチェーンを対象として対応チェーンを拡大していっている最中であり、Blastもその中の1つに加わる形となります。 公式サイト:https://parsec.finance/ X:https://twitter.com/parsec_finance Zap:コミュニティ主導のトークン起動プロトコル ZAPは、コミュニティ主導のトークン起動プロトコルであり、トークン起動スペースにおける現在の問題を軽減し、創設者と投資家の両方に価値を提供するために構築されています。 ZAPを利用する投資家たちは、単なる運(くじ)や多額の資本(ステーク)を必要とすることなく、プロジェクトに貢献することによってトークン立ち上げ時の割り当てを確保することが可能となります。これにより、プロジェクト側にとっても、単なる投機的投資家ではなく、アーリーアダプターに対してアクセスできるようになります。 ZAPプラットフォームでは、次の3つの異なるトークンローンチ方法を選ぶことが可能です。 厳選されたトークンローンチ 公正なトークンローンチ エアドロップ 各ユースケースは特定のニーズを満たし、独自の機能とロジックのセットによってサポートされています。 公式サイト:https://testnet.zap.tech/ X:https://twitter.com/zaponblast おわりに ここまで、Blast Big Bangコンペ選出プロジェクトを紹介してきましたが、如何でしたか? Blastは昨年のデポジットキャンペーンに始まり、レイヤー2の中でも多くの注目を集めているチェーンといえます。そうした中で、コンペに3000以上の応募があったことも、そうした注目を後押しするものと言えるでしょう。 2月29日にメインネットがローンチすることもあり、多くのユーザーがBlastエコシステムに参入することが予測されます。 今回は、47のプロジェクトを紹介してきましたが、コンペに選出されたからといって必ずしも安全なプロジェクトではないということには注意が必要です。他チェーンで既に実績を有しているプロジェクトもありますが、完全に新規のプロジェクトも数多く存在します。資産を守るためにも、DYORを忘れないようにしてください。
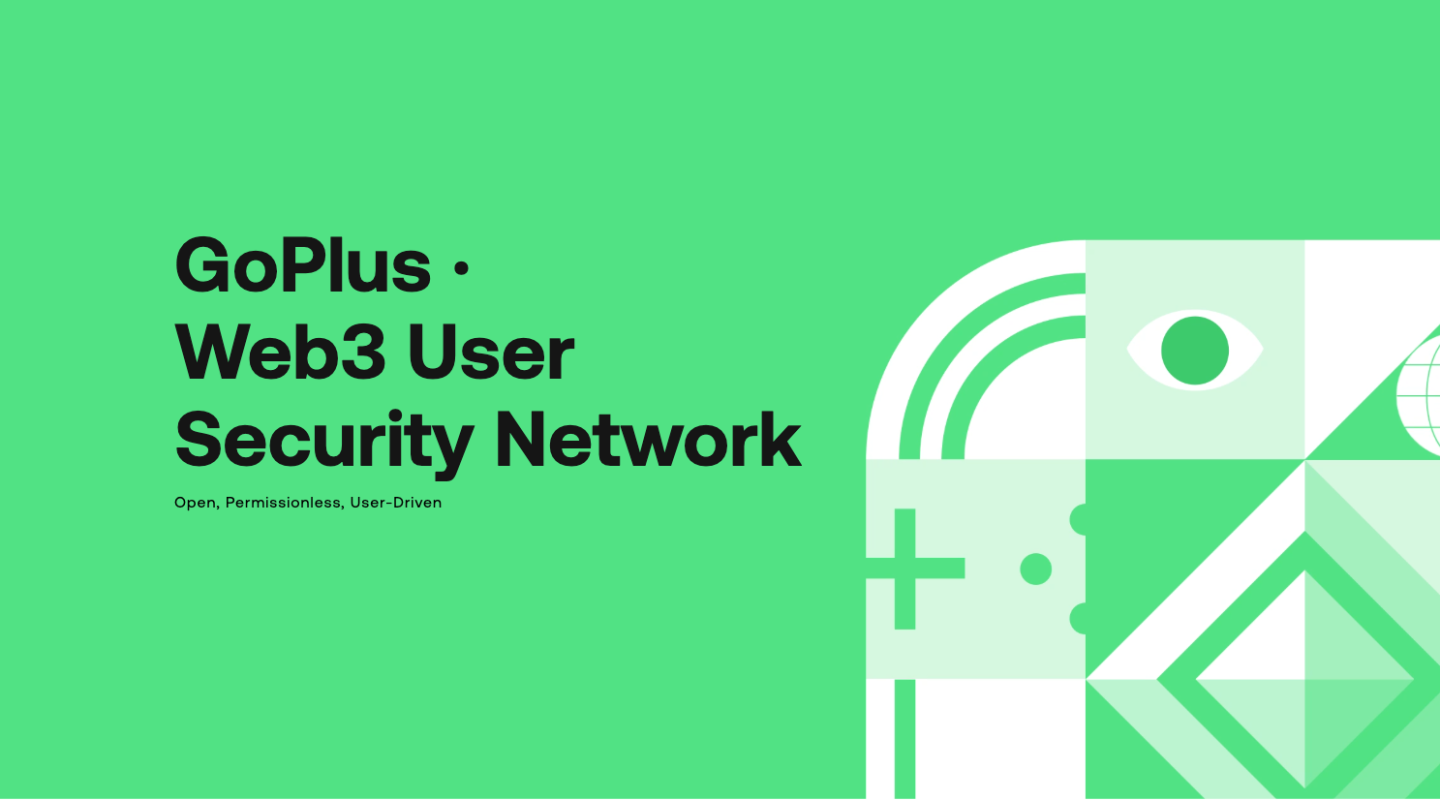
プロジェクト
2024/02/08Binance Labs.からも出資を受けるGoPlusに関して徹底解説、業界最大手のセキュリティデータプロバイダを紹介
本記事では、Web3セキュリティデータプロバイダ「GoPlus Security」の概要などについて紹介しています。 GoPlusはWeb3領域に存在するセキュリティを包括的に検出しユーザーの安心安全なWeb3体験を実現するセキュリティデータプロバイダーです。 GoPlusとは? GoPlusは、自動化されたリアルタイムセキュリティ検出プラットフォームであり、トークン検出、NFT検出、dAppコントラクトのセキュリティ検出など、様々なデジタルアセットのセキュリティ検出サービスを提供しています。 また、コミュニティ詐欺、ウォレットエアドロップ詐欺、フィッシングウェブサイト攻撃など、完全なユーザーインタラクションリスク検出もサポートしています。誰でも自由にAPIを利用して上記のセキュリティリスクを確認できます。 GoPlusが解決する問題 現在の中央集権型取引所(CEX/CeFi)には固有の脆弱性があります。また、パブリックチェーンには多くのセキュリティ課題があり、拡大する分散型アプリケーション(dApps)セクターでは更に多くのセキュリティリスクが存在します。 悲しいことに、個々のユーザー向けのセキュリティサービスはほとんど提供されていません。これらのリスクは、確立されたプラットフォームでの主要な攻撃から大規模なDeFiの盗難、ウォレットの盗難に至るまで、かなりの損失を引き起こしています。 Web3市場の潜在能力はとても大きく、将来的には数百兆円規模に拡大するとの予測があります。この潜在力を実現するためには、ユーザーセキュリティが不可欠です。 GoPlus Securityのミッションは、この激動する環境での主要なリスクを特定・認識し対応を促すことです。ユーザーセキュリティに焦点を当てると、これがweb3の発展の重要な要素であることは明確であり、おそらく最も重要なボトルネックでもあります。個々のユーザーがweb3を単なる受動的お客様であるだけではなく、管理者として使用することに依存しています。 また、Web3生態系全体は興味、教育、警戒心を促進しなければなりません。 そのため、GoPlus Securityは単なるソフトウェアソリューションだけでなく、情報を提供し教育し安全意識のあるユーザーベースに貢献することを目的としています。 投資家 GoPlusは過去に、BinanceLabやCrypto.com,GSRなど著名なVC/投資家から投資を受けていることも特徴です。著名のVCだけでなく、ArweaveやAvalanche、Klaytnなどからも投資を受けています。 パートナー GoPlusのパートナーは、ユーザーシナリオに基づいて独自のセキュリティ機能を開発できます。 既に50以上のパートナーとパートナーシップを結び、現在のAPIデータの呼び出し件数は1日あたり200万を超えており、セキュリティデータプロバイダーとしては最大級の規模を誇ります。 DEX SCREENERなどにも既にGoPlusのAPIがIntegrateされていたり、多くのパートナーとの連携がなされています。 GoPlusが提供するサービス この章ではGoPlusが提供するサービスを紹介します。 Tokenリスク検出 30 種類以上のリスクに対するリスク検出を構築しており、数百のリスク検出項目でトークンを検査します。 トークン検出はリスクを最も包括的にカバーし、業界で最も高い検出率と精度を備えています。 現在、対象となるトークンの数は120万を超え、毎日の検出量は20,000以上です。 NFT リスク検出 膨大な量の NFT データを使用して、現在業界で利用可能なもののうち最も強力な検証を提供します。 現在NFT リスク検出には 1億6,000万件以上の NFT が含まれており、最も完全な認定済み NFT データは 400 万件です。 SmartContractリスク検出 80,000 以上の悪意のあるコントラクトを含む、最大の信頼できる/認可された契約ライブラリを確立しました。 SmartContractリスク検出は、契約認証攻撃を正確に識別でき、毎日2000以上の悪意のあるコントラクトが検出しています。 MaliciousAddress リスク検出 最大規模のMaliciousAddress ライブラリがGoPlusによって構築され、10を超えるリスクタイプを識別します。 現在、MaliciousAddress ライブラリは100,000近くの悪意のあるアドレスをカバーしており、毎日2,000を超えるアドレスが追加されています。 GoPlusのユーザー使用例 今回は、Uniswapのコントラクトを例にとってGoPlusToken リスク検出を利用してみます [caption id="attachment_105861" align="aligncenter" width="792"] Token Security Detection[/caption] コントラクトのアドレスをToken Security Detectionページに訪れ、入力しチェックを押すだけです。 上記の画像のように各項目ごとにTokenがリスクに対してどういう対応を取っているか一目で確認することができます。 またGeckoTerminalやDextoolsなどにも掲載されており、様々なリスクを確認することができます GoPlusのユースケース TokenPocket TokenPocketは主流のパブリックチェーンサポートし、すべてのEVM互換、Polkadot互換、EOS互換のパブリックチェーンに対応する世界有数のマルチチェーンセルフカストディウォレットです。 現在までに、全世界200カ国以上、2000万人以上のユーザーに信頼性の高いサービスを提供し、月間アクティブユーザー数は350万人を超えています。 GoPlusSecurityのセキュリティインフラを搭載したToken Security API、dAPP Security Info API、およびApproval Security APIを統合し、暗号詐欺に対する高度なセキュリティを提供しています。 SafePal SafePalは、2018年に創業された暗号初心者のハードルを取り除くことを目指す開発者、デザイナー、セキュリティエンジニアのチームでBinanceにも統合されています。 人々が暗号通貨の可能性を引き出し、自信を持って資産投資を行い成長させるのを手助けしてます。 GoPlus SecurityのToken、NFT、Contract、dAppセキュリティ用のAPIを統合しています。 これにより、ユーザーは1000万以上の毎日のクエリのサポートを受けて、資産を守ることができます。 GeckoTerminal GeckoTerminalは、特化したDEXアグリゲーターです。基礎的なことからエキスパートレベルに対応した分析ツールと情報に対するワンストップアプリケーションであり、仮想通貨投資家が情報を元にした投資および取引の決定を行うのをサポートするツールを多数ローンチしています。 GoPlus SecurityのToken Security用のAPIを統合しています。 Ave.ai Ave.aiは現在25のブロックチェーンからオンチェーンデータを集約している分散型のオンチェーンデータプラットフォームです。 ユーザーには、トークンのK-Lineデータ、nftの価格、DeFi、GameFi、Web3.0などの各セクターの統計データを提供しています。そして、「より安全で正確で専門的な」集約的データプラットフォームを開発することを目標としています。 GoPlus SecurityのToken Security用のAPIを統合しています。 まとめ Web3体験をサポートする業界最大級のセキュリティデータサービスプロバイダーの紹介でした。上記のサービスは現在GoPlusEcoより利用可能となっています。 今後もっと加熱していくWeb3業界を安心安全に過ごすためにも、今一度セキュリティの確認をしてみてはどうでしょうか? 英語公式Mediumには様々なセキュリティ関係の教材が用意されています。順次日本語に翻訳されるようなのでぜひご覧ください! さらにGoPlusは個人向けセキュリティデータセンターをオープンする予定です。各ユーザーが簡単にセキュリティレベルを測定できるサービスです。 GoPlus 各種Information Website:https://gopluslabs.io/ 英語公式X:https://x.com/GoPlusSecurity 英語Medium:https://goplussecurity.medium.com/ 日本語公式X:https://twitter.com/GoPlus_JP Discrod:https://discord.gg/5cvSsaT8N5

プロジェクト
2024/01/31DeFi特化のブロックチェーン「Injective」とは?特徴や使い方を解説
本記事では、DeFiに焦点を当てたブロックチェーン「Injective」について解説しています。 Injectiveの$INJトークンは2023年1月には1ドル前後の価格をつけていましたが、その1年後の2024年1月時点では34ドルを超えており、2023年に急伸したプロジェクトの1つ挙げられています。 この記事ではそんな注目プロジェクトであるInjectiveの概要や注目点について以下の点から解説しています。 記事のまとめ ・InjectiveはDeFi向けのブロックチェーン ・EthereumやCosmosとの相互運用性 ・買い戻しとバーンによるデフレ ・FBAによるフロントランニングへの耐性 Injectiveの概要 Injectiveは、金融に焦点を当てたブロックチェーンや周辺のエコシステムの総称です。 Cosmos SDKを使用して構築されており、PoS(Proof of Stake)を採用しています。 同じ仕様を持つブロックチェーン同様、Injectiveはトランザクションの通りが早く、Ethereumやbitcoinと比較するとガス代も安いです。 直近ではAIやRWAといった注目トピックと合わせて注目度が高まっています。 ネイティブトークンの$INJには以下のような用途があります。 ・PoSへのステーキング ・ガス代としての利用 ・Injectiveに関連する機能のガバナンス $INJはブロック報酬として用いられ増加しますが、流通に当たり特徴的な機能が加えられており将来的に供給は減少する可能性があります。 Injectiveの3つの特徴 Injectiveのかんたんな特徴について、以下の3点から解説していきます。 1. DeFiに焦点を当てている 2. 高い相互運用性 3. 定期的なBurn Injectiveの強みをざっくりとチェックしていきましょう。 1. DeFiに焦点を当てている InjectiveはDeFiに焦点を当てており、実装されている機能もDeFiに関連するトピックが多いです。 例として、Injectiveが焦点を当てているジャンルとしては以下のようなものが挙げられます。 ・取引所 ・保険 ・オラクル ・デリバティブ また、直近では注目トピックの1つであるRWAに関連するモジュールを提供する旨が明らかにされました。 The Injective Volan Mainnet proposal is live! Volan brings unmatched L1 infrastructure with novel advancements including ✅The world's first ever RWA Module ✅ Enhanced Scalability ✅ New token burn capabilities ✅ And Much More 🗳️ Vote Here (IIP-314): https://t.co/lFOdcoW6PP pic.twitter.com/mvU3Begazw — Injective 🥷 (@Injective_) January 6, 2024 このモジュールを使用することで、金融機関などがトークン化した現実世界の資産を扱いやすくなります。公式によると、Injectiveはネイティブチェーン上でRWA向けのパーミッションレイヤーをサポートする唯一のチェーンとなるようです。 RWAは注目を集めているトピックの1つなのでこちらも注目ですね。 高い相互運用性 Injectiveは、高い相互運用性を持っています。 ブロックチェーンは、各チェーンごとにさまざまなルールや仕様が異なっており、基本的にトークンや情報を自由に行き来できません。 一方で、InjectiveはCosmos SDKをベースに構築されたブロックチェーンであり、IBCにも対応しています。同じくIBCに対応しているブロックチェーンと互換性があり、特にCosmos関連のエコシステムとは相性が良く、IBCに対応しているブロックチェーン間とのスムーズなトークンの移動が可能です。 また、InjectiveはEthereumとの互換性も持ちます。 Injectiveは、EthereumのMetaMaskなどのウォレットを使用してやり取りを行ったり、Injective上でERC-20トークンを扱うことも可能です。 定期的なBurn Injectiveは、定期的に$INJトークンの買い戻しを行う仕組みを実装しています。 買い戻しを行った$INJはバーンされ、市場から取り除かれます。これにより、$INJの希少性が高まりデフレ効果が期待できるとされています。 具体的な例としては、Injective上の取引所などで発生した手数料の一部を回収し、$INJの買い戻しに回されています。 Injectiveの仕組み Injectiveの仕組みについて、以下から解説していきます。 ・DeFi向けのさまざまな機能 ・フロントランニングへの耐性 ・inEVMとinSVM ・$INJのバーンークションと分配 Injectiveの注目したい機能や仕組みをチェックしていきます。 DeFi向けのさまざまな機能 Injectiveは、チェーンベースでさまざまなDeFi向けの機能を提供しています。 Injectiveのチェーンから提供されている機能を使用して、開発者はかんたんに新たなDeFiサービスを構築可能です。 例えば分散性の高いオーダーブックなどがチェーンベースで提供されており、このオーダーブックを活用して取引所などを開発できます。 また、保険やオラクルといったトピックごとにモジュールが提供されています。 フロントランニングへの耐性 InjectiveはFBA(Frequent Batch Auction)を活用して、フロントランニングを防止します。 フロントランニングとは、他のユーザーの取引情報を取得し取引がブロックチェーンに記録されるよりも前に自分が利益を得るためにオーダーを処理する行為を指す言葉です。 そしてFBAは、Injectiveの注文マッチングシステムが使用しているモデルです。 注文の種類によって若干仕様が異なりますが、概ねFBAではブロック内にある一致する注文を同じ価格で処理します。 これにより、フロントランニングを防ぐことができるとされています。 inEVMとinSVM Injectiveは、inEVMとinSVMという2つのVMのロールアップを展開しています。 inEVMはEthereumのEVM、inSVMはSolanaのSVMと互換性を持っており、各開発者はこれまでと同じ方法で各ロールアップにアプリケーションを構築可能です。 各ロールアップとも、モジュラー型ブロックチェーンのプラットフォームでロールアップの構築などを行っているCalderaとInjectiveが協力して開発しています。 $INJのバーンオークションと分配 Injectiveのネイティブトークンである$INJは、買い戻しとバーンが定期的に行われます。 前述したようなInjectiveの機能を使用している取引所などから発生した手数料のうち、40%は取引所などへ提供されます。 残りの60%はプールに集計されて、1週間に1度行われるオークションに出品される仕組みです。 オークションの落札には$INJが用いられ、落札に使用された$INJはバーンされます。 Almost 4,000 $INJ or approximately $130,000 has been burned today via the burn auction 🔥 — Injective 🥷 (@Injective_) January 4, 2024 この仕組みを通して、オークションはこれまで100回以上実施され、500万以上の$INJがバーンされました。 Injectiveの代表的なdApps Injectiveの代表的なdAppsについて、以下から3つのプロジェクトを紹介します。 ・Helix ・DojoSwap ・Talis Art Injectiveエコシステムについての見識を深めていきましょう。 Helix The new @HelixApp_ weekly market overview 🧬 Trending markets include $JUP & $ZRO Pre-Launch Futures along with $INJ $SOL & $SEI. Trading volume up to $1.3 billion in the past week alone! pic.twitter.com/QckOGifzs6 — Helix 🧬 (@HelixApp_) January 29, 2024 Helixは、Injectiveに構築されているオーダーブックの取引所です。 主にデリバティブ及び現物を扱っており、高度な注文のサポートなど多様な取引が可能な取引所になっています。 HelixはInjective上で*最も取引されているDEXで、安定的に取引量を伸ばしています。*DeFi Llamaのデータ参照 DojoSwap Hello Ninjas, In less than 1 month, we have achieved the following: ⚔️ $25,000,000 TVL ⚔️ $95,000,000 Trading Volume ⚔️ 52% Chain Dominance ⚔️ 3 Launchpads ⚔️ 15,000+ Unique Traders Feb will be an eventful month with many feature launch and launchpads lined up! #Injective… pic.twitter.com/s4VATYTwe1 — DojoSwap | 1st AMM Dex on #INJ (@Dojo_Swap) January 29, 2024 DojoSwapは、Injective上に構築されたAMMのDEXです。 さらに、DojoSwapではAMMのみならず、dINJを獲得できるLSDも提供されています。 DojoSwapは2023年末に正式ローンチした比較的若いプロジェクトです。 その一方で、TVLはLSDとAMM合わせて*約2,600万ドルで、DojoSwapを前述のHelixを抜いてもっとも資金が集まっているInjective上のプロジェクトとなっています。*記事執筆時DeFiLlama参照 Talis Art 🚀 Exciting Airdrops Alert! 🚀 Unveiling $TALIS Token Rewards for Talis Community. 🔥 Stakers on Talis' Injective validator & Users of the platform, your loyalty hasn’t gone unnoticed! 🌐💎 #TalisListing #Airdrops #TALISCommunity pic.twitter.com/e791IyxG5s — Talis Protocol (@ProtocolTalis) December 8, 2023 Talis Artは、InjectiveのNFTマーケットプレイスです。 他のNFTマーケットプレイスと同様にNFTの購入・売却・作成が可能です。 Talis Artは2021年にローンチしたマーケットプレイスで、2023年12月には$TALISという独自トークンをHelixに上場させました。 利用者などに対して今後、数回に分けてエアドロを行う旨も明らかにしています。 Injectiveの使い方・始め方 Injectiveに資金を送金する方法は、複数あります。 すでにATOMなどCosmos関連の資金を持っている方は、Cosmos Hub上のATOMなどからInjective上の$INJに、Keplrのスワップ機能から簡単に送金可能です。 Keplrのウォレットの中央下部をタップすると、以下のような画面が出てくるので、スワップしたい仮想通貨を選択(From)し、送金先(To)に$INJを指定してください。 ATOMであれば、複数の国内取引所で取り扱っています。 まだ、何も仮想通貨を持っていないという方は、ATOMを購入しKeplrに送金して、スワップするというのが一番手順が少ないはずです。 また、公式のブリッジを使用して送金する方法もあります。 コチラにアクセスして、ウォレットを選択し、送金元のチェーンと送金先のチェーンを選択して、送金したい仮想通貨と数量を入力し、送金を行ってください。 EVMのチェーンであればMetaMaskなどを使用する必要があり、各チェーンによって行き来できる仮想通貨も異なっています。 2024年1月時点で、以下のような主要なチェーンに対応しています。 ・Ethereumと一部のL2 ・Cosmos Hub ・Solana まとめ この記事では、Injectiveについてさまざまな点から解説しました。 Injectiveは、さまざまなポイントから注目の集まっているプロジェクトの1つです。 今後も注視して行きたいと言えるでしょう。

プロジェクト
2024/01/30Bluefin v2の使い方、特徴を徹底解説|Suiブロックチェーン最大のデリバティブ取引所
Bluefinは、BTCとETHを取り扱うデリバティブ取引所であり、先日Version 2へのアップデートを発表したことでも知られています。 Bluefinは、Arbitrum上において今年3月にローンチされていましたが、そして、Bluefin v2はSui上にてリリースされました。これによりSuiで稼働する最大のデリバティブ取引所となりました。 さらには、12月20日にArbitrumで展開しているをBluefin Classicを縮小プロセスに入ったことを発表しました。今後は、Arbitrum上にてローンチしたBluefin Classicから、Bluefin v2のSuiにて力を入れていくことを発表しています。 今回の記事では、Bluefinの概要からSuiにてv2をリリースした背景、そして実際の使い方までを解説していきます。 Bluefinが注目を集める3つの理由 具体的なBluefinの概要に入る前に、まずはBluefinの周辺情報を紹介していきます。 Suiネットワーク上で最大のデリバティブ取引所 [caption id="attachment_105055" align="aligncenter" width="800"] データ引用元 : DefiLlama[/caption] SuiネットワークのTVLは、3億6200万ドルほどであり、右肩上がりで上昇傾向にあります。 現在のSui上の主要なプロダクトは、DEXやレンディングサービスに重きを置いたものとなっています。そうした中で、デリバティブの分類で見た際には、最大の規模をBluefinは誇っています。 BluefinのTVLは、526万ドルほどとなっており、Suiネットワーク上でみれば未だ規模は小さめと思われるかもしれませんが、Bluefin v2をリリースしてから3ヶ月も経っていない中での成果としてみると、十分な急成長と言えるでしょう。 多くの投資家から支援を受けており、一日の出来高も5000万ドルを超える Bluefinは、Polychain、SIG、Wintermuteといった多くの有名企業とパートナーシップを結んでいます。 また、2021年5月のシードラウンドでは、640万ドルの資金調達を成功させており、その際の投資家にはThree Arrows Capitalがいました。また同年9月に発表されたベンチャーラウンドでは、投資家の中にAlameda Researchがいました。両者とも現在は破産していますが、当時は非常に注目を集めていたクリプト企業です。 これらのことからも、Bluefinが最近だけでなく以前から注目を集めていたことが伺えます。 @bluefinapp hits another all-time high of $401.39 million in 24-hour trading volume 🙌🏼 pic.twitter.com/a4jIms7sjB — Zabi | Bluefin ⛵️ (@zabimx) December 6, 2023 また、これまで累計で15億ドル以上の取引量を処理しており、10月の下旬には、5000万ドル以上の出来高を記録しました。更に12月には24時間で401億ドルを超えるボリュームを記録、1日あたりの平均取引高は1億300万ドルとなり、非常に流動性の高いDEXの一つとして永久取引をユーザーに提供しています。 これら投資家たちからの注目や、既に十分な実績を残していることからも、Bluefinが非常に注目をされていることが分かります。 現在、取引に応じたポイントプログラムが実施中 Bluefinは現在、エポックごとに、テイカーの取引量に応じて各ユーザーにポイントを割り振っています。 これは将来的に発行されるBluefinの独自トークン「$BLUE」を配布するにあたって基準となるポイントです。 これについての詳細は、記事の後半でのBluefin v2の使い方解説の際に記載していきます。 Bluefinの登録はこちら Bluefinの概要 ここからはより詳しいBluefinの紹介をしてきます。 ユーザー体験を重視:中央集権型取引所に近い体験でありながら、資金をノンカストディアルに管理可能 Bluefinはユーザー重視のデリバティブ取引所です。 ユーザーが取引所を使うにあたって、いくつかの懸念事項が発生します。その中の一つに、ユーザーが自身の資金を完全に管理下に置けるのかどうかというものがあります。 例えば、中央集権的な取引所の場合、そこに資金を預けているユーザーは、資金を完全に管理できていません。FTXのように取引所が破綻した場合、ユーザーは自身の資金を失う可能性があります。 Bluefinでは、ノンカストディアルソリューションを提供しており、ユーザーは完全に自身の資金を管理することが可能になっています。 Suiネットワークへの拡大:既にv1(Arbitrum)の取引量を上回る [caption id="attachment_100529" align="aligncenter" width="800"] データ引用元:https://defillama.com/protocol/bluefin[/caption] 先ほど述べたようにBluefinは、v2においてSuiネットワークへの拡大を果たしましたが、その取引量は増加しており、上記の画像を見て頂ければ分かるように、既にv1における取引量を上回っています。 これは、Bluefinが、Suiネットワークにおける最大のデリバティブ取引所であり、またポイントプログラムを行なっていることからも、ユーザーたちからの注目が非常に高かいことを示していると言えるでしょう。 Bluefin v2 では流動性とボリュームが非常に急速に拡大していることを考慮して、Bluefin Classic を終了し、Sui での新機能とアップグレードのリリースに注力する予定となっていると発表済みです。 次からは、より具体的なBluefin v2の要素について紹介していきます。 Bluefin v2へバージョンアップし、多くの機能を搭載予定 Bluefinは、3月にArbitrum上でローンチしました。そして、10月にはSui上にて、Bluefin v2をリリースしました。 異なるチェーンに移行しましたが、この理由として、Suiブロックチェーンのスケーラビリティや性能を重視した結果であることが挙げられます。Bluefinは、Suiでv2をリリースするためにコードベースを書き直したとのことです。 また、v2のリリースに伴い、多くの優れた機能が、今後6ヶ月間の中で徐々にリリースされていく予定です。 現在はまだアーリーリリースであるため、完全な実装とはなっていませんが、将来的に実装される要素を、それぞれを紹介してきます。 その他にも、まだ詳細は明らかになっていませんが、将来的にv2にて多くのマーケットを立ち上げるだけでなく、手数料にtierを設けたりや、モバイルでの取引アプリもサポートする予定とのことです。 パフォーマンスの向上 Bluefinでは、ユーザーが行った取引を即座にUIに反映することを目指しています。 そこで採用されたのが、「オプティミズティック(optimistic)な取引確認」です。 Suiの特徴として、全トランザクションの全体的な順序付けを必要としないことが挙げられます。これにより、オンチェーンで送信された有効なトランザクションの成功率は極めて高くなっています。 Bluefinはこの仕組みを基盤として、オフチェーンオーダーブックレイヤーを再設計し、取引の確認を30ミリ秒でユーザーに送り返すようにしています。これはオンチェーンでの実行前に行われますが、オンチェーンのスマートコントラクトとの最終的な整合性は保証されています。 また、ファイナリティ(決済が無条件かつ取消不可となり完了すること)は、550ミリ秒以内に達成することが可能となっています。 取引コストの大幅な削減 BluefinhはWintermute、Kronosといった大手マーケットメーカーからサポートされることで、取引におけるコストを大幅に削減しています。 スリッページは、為替などの取引時に注文レートと約定レートの間に乖離が発生してしまうことですが、Bluefin v2ではこのスリッページを、0.01%以下に抑えます。 また、取引の際にどうしても発生するガス代ですが、こちらも0.01$以下にすることで、ロスなくデリバティブ取引が出来るようになっています。 フルスタックの提供 完全に非中央集権化されたスポット市場及び、クロスマージン取引が提供されます。 Web3ウォレットの必要性を排除 通常、DEXといったサービスを利用するためには、Metamaskに代表されるような何らかのWeb3ウォレットが必須です。 しかしながら、Bluefin v2では、Suiのzksync技術(zkLogin)を活用することで、ウォレットに接続することなく、アクセスし取引をすることが可能です。 zkLoginは、Googleやフェイスブックといった既存のWeb2の認証情報を利用することでアカウントを作成し、トランザクションのやり取りを可能とさせるものです。また、ブロックチェーンに個人情報が晒されるリスクもなくなるため、プライバシー保護にも繋がります。 これにより、秘密鍵の管理の面倒さや、セキュリティへの不安といったより良いユーザー体験の妨げになる要素を排除することが可能となっており、Web3をまだ触ったことがない方でも、気軽にWeb3の世界へ参入することが可能となります。 Bluefinは、最終的にWeb3ウォレットの必要性を完全に排除するとのことです。 既に多くのブロックチェーンが登場し、それぞれのチェーン上にて多くのDEXが誕生していますが、この要素はSuiにおいてv2をリリースしたBluefin独自の取り組みと言えるでしょう。 Bluefinを実際に使ってみよう ここからはBluefinの使い方を紹介していきます。 この記事では、最近最近アップデートしたばかりの、Bluefin v2の方を解説いたします。 Suiネットワークということもあり、もしかすればSuiウォレットを持っていない方もいるかもしれません。 Suiウォレットの作成やオンボーディング、実際の取引までを詳細に解説してきます。 Bluefinの登録はこちら Suiウォレットを作成する まず、Bluefin v2は、Suiネットワークに構築されていますので、Suiウォレットが必要です。 以下のURLから、Sui ウォレットを作成してください。 Sui Wallet:https://chromewebstore.google.com/detail/sui-wallet/opcgpfmipidbgpenhmajoajpbobppdil Suiウォレットへと資金をブリッジする 次に資金をSuiウォレットへとブリッジします。 恐らく、多くの方はMetamaskを使用しており、イーサリアムチェーン上に資金があることが大多数と思われます。 ここでは、Portalを使用してSuiへと資金をブリッジする方法を解説します。 まずは、Portalへとアクセスします。 Portal:https://www.portalbridge.com/#/transfer 「Tokens」のタブを開くと以下の画面が表示されます。Metamaskを接続し、送金したいトークンと任意の量を指定してください。 そして「NEXT」をクリックします。 すると以下の画面へと進みます。ここで、Suiウォレットを接続し、ブリッジするトークンと量が間違っていないことを確認したら、「Next」をクリックしてください。 すると、次のようなタブが開きますので、「Transfer」をクリックしてください。 その後、しばらくすればブリッジが完了しますので、ご自身のSuiウォレットにて金額をご確認下さい。 現在ガス代の補助として、Bluefin v2に初めてオンボーディングすると$SUIを入手可能 Suiウォレットを作成したのはいいものの、ガス代としての$SUIを持っていないという方もいるかもしれません。 Metamaskにおけるガス代として$ETHがあるように、Suiウォレットでは$SUIがガス代として使用されます。 となれば、どこかの取引所において$SUIを購入し、Suiウォレットに$SUIを送るなどしてガス代を用意しなければなりません。 一見すると面倒のように思われますが、現在Bluefinでは、初めてSuiウォレットを接続したユーザーにガス代として0.2SUIを配布しています。 Bluefin v2:https://trade.bluefin.io/ETH-PERP?utm_source=bluefin&utm_medium=internal&utm_campaign=header こちらのURLから、Bluefin v2にSuiウォレットを接続しオンボーディングすると、自動的に0.2SUIが入金されます。 これにより、初めてSuiウォレットを作成し、$SUIを持っていないという方でも、容易にBluefin v2を試してみることができるようになっています。 実際にデリバティブ取引をしてみる ここからは実際に筆者が行った取引画面を参照しながら、Bluefinでの取引の仕方を紹介していきます。 Suiウォレットから資金を預ける まずは、Bluefinにて取引を行うために資金を預けます。 ①「Deposit」をクリックすることで、ウォレットから資金を預けることが可能です。 もし仮に、Bluefinにて取引を終えるなどして資金を引き出したい場合には、②「Withdraw」をクリックして、資金を引き出して下さい。 ポジションをとる:ロング(買い)の場合 次に、実際に注文をしてみます。今回はロング(買い)の注文を行ってみます。 今回は指値で購入してみますので、①「Limit」をクリックします。 すると、右のような画面が表示されますので(②参照)、それぞれの項目に自身が購入したい金額や数量を入力して下さい。また、レバレッジの調整も可能です。筆者は今回、3倍のレバレッジを選択しました。 そして、③「But/Long」をクリックすれば、指値注文は完了です。 筆者は今回、$2015で指値をしました。指値注文時のETHの値段は$2017でしたが、仮に$2015にまで下がった場合には、自動的に注文がされます。 ※仮に、ショート(売り)注文をしたい場合は、売りたい価格を指定して「Sell/Short」をクリックして下さい。 注文が成立した場合 ETHの値段が下回ったため、筆者が行った$2015での注文は無事成立しました。 成立した場合には、上記画像の赤枠のように、現在の損益といった取引に関わる情報が記載され、リアルタイムで変化していきます。 もし仮に、注文が通らなかった場合には、「Open Orders」の欄に、現在行っている注文が記載されます。 売りの指値を入れる ロング(買い)からポジションをとったため、どこかの段階でショート(売り)をしなければなりません。 今回は、「指値」(Limit)を行います。 指値は、トークンの価格があらかじめ指定した金額に達した場合に、自動的に取引を行うよう注文をしておくことです。 一度成立したポジションを閉じる場合には、上記画像の赤枠の中の注文の中から、ポジションを閉じたい注文の「Limit」もしくは「Market」を選択します。 今回は、成行ではなく指値でのショートを入れたかったため、赤枠の中の「Limit」をクリックします。(成行価格でポジションを清算したい場合は「Market」をクリックして下さい) すると以下のような画面が表示されます。 こちらの画面で、ショート(売り)したい金額を記載し、精算したいポジションの割合を選択し、「Limit Close」をクリックすれば、指値注文は完了です。 筆者は今回、$2060での指値注文をしてみました。 また、下部の「Expected Pofit」を見ていただければ、予測される利益が表示されています。 取引の履歴を確認する 今回無事、ETHが値上がりしたため、ショート(売り)の指値注文が清算されました。 既に行われた注文を見るには、上記画像の赤枠の①「Fills」をクリックすることで参照することが可能です。 また、取引画面上部の②「Account」をクリックすることで、詳細なアカウント情報を見ることが出来ます。 その中で、上記画像の赤枠「History」をクリックすれば、これまでの取引履歴を参照することが可能です。 (上記のHistory画像は、ロングの指値注文をした際のものであり、ポジションを閉じる前のものです) 取引量に応じて$BLUEトークンがもらえる初期報酬プログラムが実施中 Bluefinでは、独自トークンとして$BLUEの発行が予定されています。 その総供給量のうち、6%が初期報酬プログラムに割り当てられており、ユーザーはBluefinで取引をすればするほど、テイカーの取引量に応じて多くのポイントを得ることが出来、そのポイントは$BLUEトークンと引き換えることが可能となっています。 このプログラムは、幾つかのエポックを設けながら2024年3月に終了予定とのことですので、早い段階から利用しアーリーユーザーになればなるほど、より多くの$BLUEを入手できる機会が増えます。 初期報酬プログラムの詳細 初期報酬プログラムは、ユーザーの取引及びコミュニティ参加を促進するために行われます。 いくつかのエポックが用意されており、エポックあたりの報酬は、2298850 BLUEから3076923 BLUEに比例して増加する仕組みとなっています。 報酬プログラムの仕組みは更新される可能性がありますが、過去に獲得した報酬が影響を受けることはない仕組みとなっています。 稼いだ報酬ポイントは、1:1の比率で$BLUEに変換可能であり、2エポックが経過した後にその権利が確定する仕組みとなっています。 報酬ポイントの確認及び変化 筆者は実際にBluefinにて取引をしたため、報酬ポイントを獲得しました。その画面を例にしながら解説していきます。 まず、自身が獲得した報酬ポイントは、画面上部の「Account」をクリックし、左側の①「Trade & Earn」をクリックすることでみることが出来るようになります。 この画面では、「3.65」と今回のエポックで稼ぐことが出来たポイントが記載されています。 しかしながら、このポイントは確定したポイントではなく、時間によって変化していきます。 以下、具体的な推移が以下となります。 この間、筆者は先ほど行った取引以外に一度も取引を行ってはいません。ですが、報酬ポイントが変化しています。 このように数値が変化するのは、時間が経過し多くの取引がされることで総取引量が増えていく中、総取引量における筆者の取引量の割合が少なくなったためです。 上記の推移から分かるように、あくまでも現エポックにおける数値は確定しておらず、変化する可能性があることには注意が必要です。 Bluefinの登録はこちら 結論 ここまで今注目のデリバティブ取引所、Bluefinについて紹介してきました。 Bluefinは、Suiネットワークにおける最大のデリバティブ取引所です。また、高速な取引を実行可能であることや、Web3ウォレットを必要としないユーザー体験など、Suiネットワークの利点を大いに活かしている取引所であるといえるでしょう。 また、Suiエコシステムに馴染みのない方向けに0.2SUIの配布をしたりや、初期報酬プログラムを行い取引の活性化を行うなど、多くのユーザーに対して大いにその活動を促進しようとしているのも大きな魅力となっています。 Suiエコシステムへの参画だけでなく、デリバティブ取引を初めて行うにも非常に良い機会ですので、興味がある方はぜひ一度Bluefinを試してみてはいかがでしょうか? Bluefin各種Infomation 公式サイト:https://bluefin.io/ X:https://twitter.com/bluefinapp Blog:https://bluefin.io/blog Telegram:https://t.me/bluefinapp Github:https://github.com/fireflyprotocol Discord:https://discord.com/invite/bluefinapp 記事引用元 : Bluefin Blog , Bluefin Website Sponsored Article ※本記事はSponsored記事となります。サービスのご利用、お問い合わせは直接ご提供元にご連絡ください。




















 有料記事
有料記事


