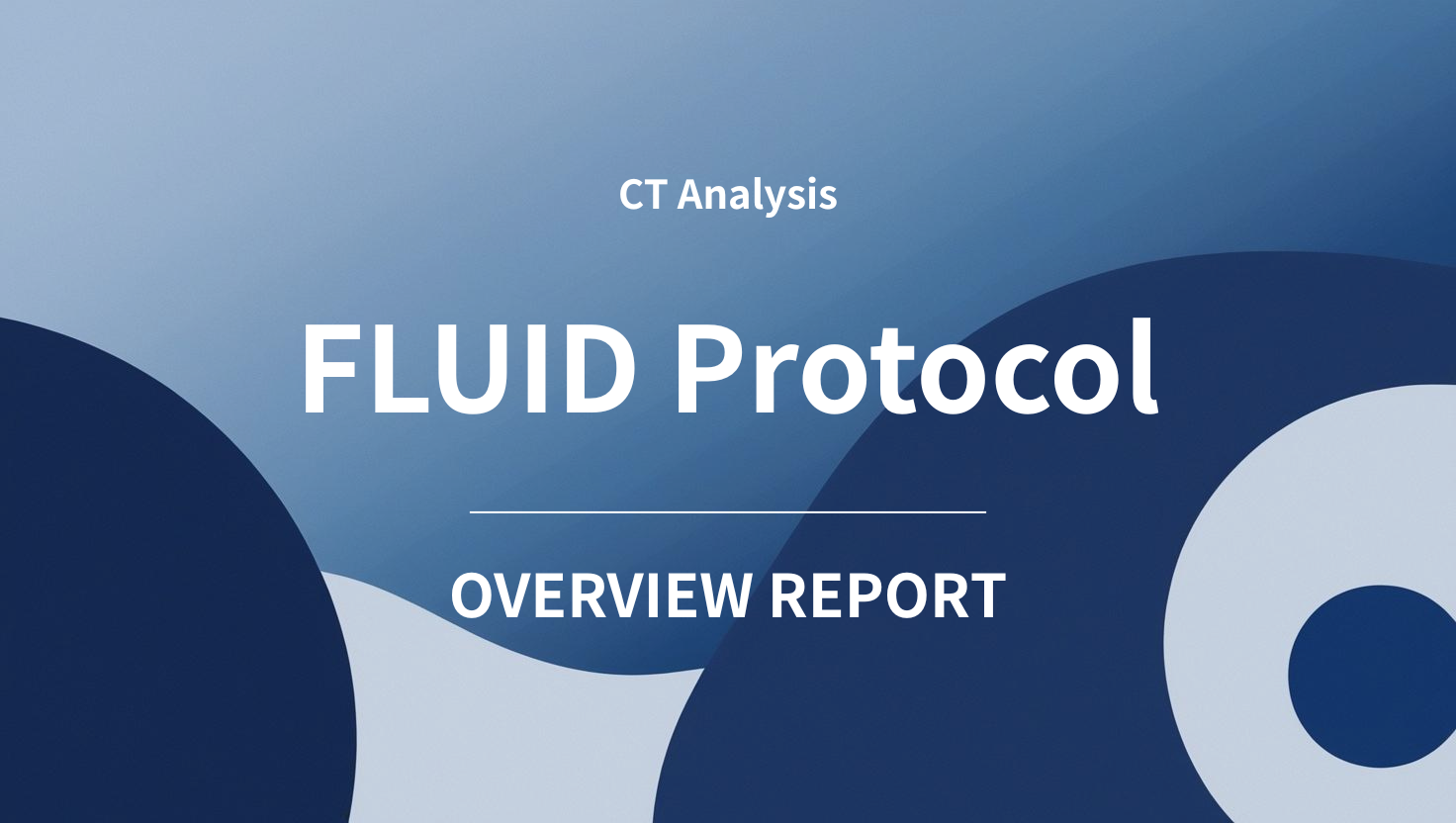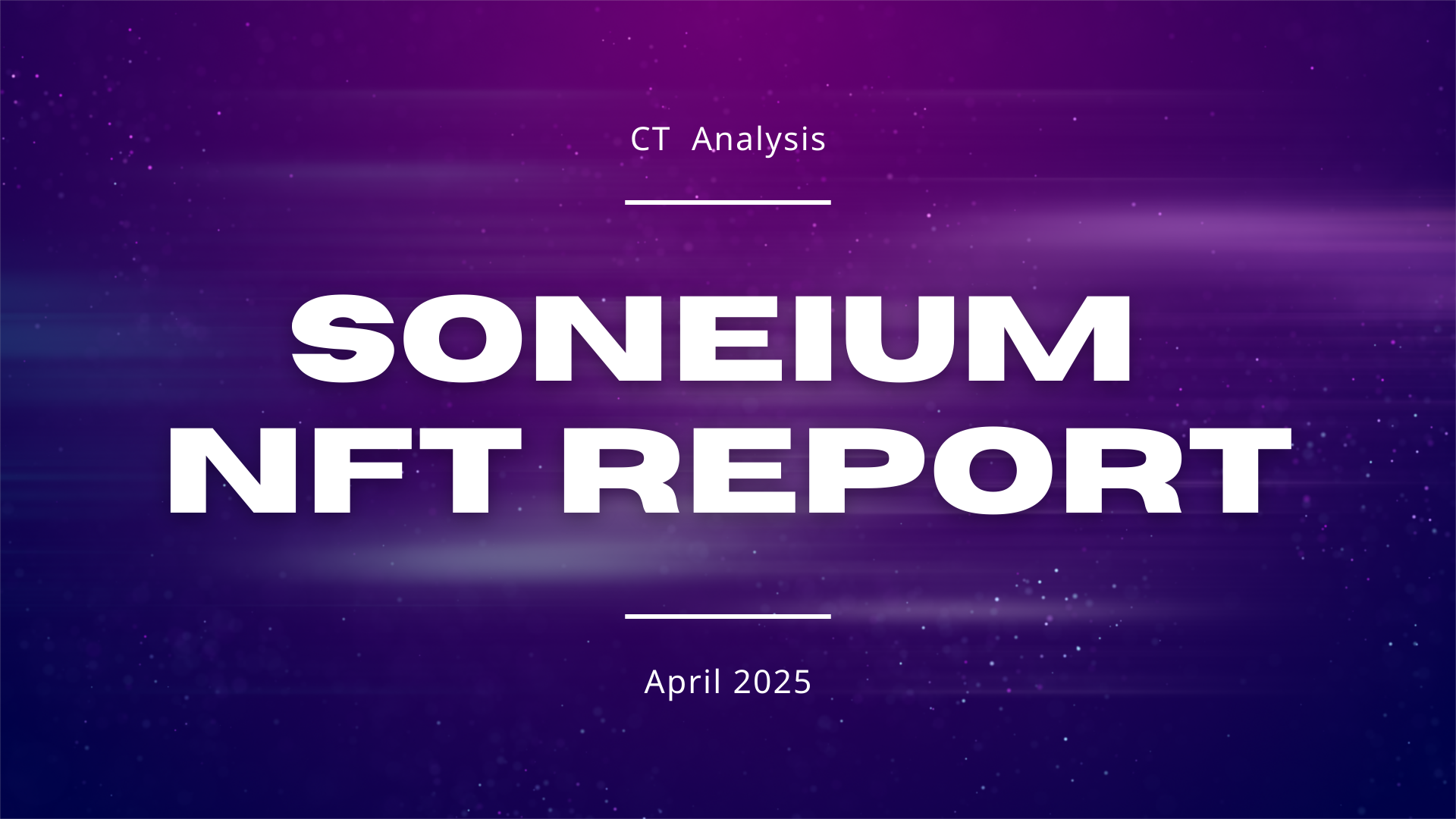仮想通貨とマネーロンダリングの関係【その対策で大丈夫?】
Crypto Times 編集部

仮想通貨には「誰も信用せずに使える」というメリットがあります。
しかしその反面、大きなデメリットがあることはご存知でしょうか。
それは「仮想通貨はマネーロンダリングに利用されている」ということ。
本記事ではそんな仮想通貨のマネーロンダリング事情について詳しく解説していきます。
具体的には下記です。
- ・仮想通貨とマネーロンダリングの関係
・どのように対策されているのか
・「仮想通貨×マネーロンダリング」の今後の課題
「仮想通貨についてもっと深い知識をつけたい」
といった方は是非最後まで読んでみてください!
*本記事はマネーロンダリングを推奨する記事ではなく、仮想通貨の実態を正しく伝えることを目的としています
目次
仮想通貨とマネーロンダリングの関係〜2つのケース〜
②仮想通貨”自体”がマネーロンダリングされるケース
仮想通貨におけるマネーロンダリングには上記の2つのケースがあります。
順を追って説明していきます。
①マネーロンダリングの”手段”として仮想通貨が使われるケース

まず最初に紹介するのが「マネーロンダリングの”手段”として仮想通貨が使われるケース」です。
犯罪者たちは”汚い”お金の足がつかないように、現金を仮想通貨に変えようとすることがあります。
というのも仮想通貨には以下のような2つの特徴があるからです。
- ・物質的な量や重さが存在しない
・国をまたいで瞬時に送金が可能
上記のように仮想通貨には物質的な量や重さがなく、どこへでも送金することが可能です。
米データセキュリティ会社のCiphertraceが公開したデータによると、 2009年1月〜2018年9月の期間でビットコインを介した犯罪関連の送金額は判明分だけで38万BTCにものぼるとされています。
仮想通貨の「いつでもどこにでも送金できる」というメリットは、時としてデメリットにもなってしまうのです。
②仮想通貨”自体”がマネーロンダリングされるケース

もう1つが「仮想通貨”自体”がマネーロンダリングされるケース」です。
ハッキング事件により取引所から流出した仮想通貨は、追跡ができないように様々な仮想通貨に換金されます。
そして、盗まれた仮想通貨は最終的にGoogleに表示されないダークウェブの中で現金に換金されてしまうのです。
みなさんご存知の「Coincheckハッキング事件」で盗まれた約580億円分の仮想通貨の一部が、すでにダークウェブを通じて出金されてしまっています。
仮想通貨は”手段”としてだけでなく”仮想通貨自体”もマネーロンダリングされてしまうのです。
①マネーロンダリングの”手段”として仮想通貨が使われるケース
②盗まれた仮想通貨”自体”がマネーロンダリングされるケース
どのように対策されているのか

仮想通貨とマネーロンダリングに関する対策は、以下のように進んでいきます。
FATF(金融活動作業部会)がガイドラインを発表
↓
ガイドラインを元に各国政府が法律を作る
↓
法律を元に取引所が対策を実施
マネーロンダリング対策は、国際機関のFATFがガイドラインを発表するところから始まります。
FATFはこれまで、
- ・取引記録を最低5年間記録する
・怪しい取引がないか監視する
などと記したガイドラインを発表してきました。
そしてこのガイドラインを元に各国政府は法律を作ってきました。
そうして各国政府が法律を作った後、最後に取引所が仮想通貨のマネーロンダリングへの具体的な対策を実施していくのです。
仮想通貨のマネーロンダリングを監視しているのは「警察や政府ではなく取引所である」というポイントを抑えておきましょう。
仮想通貨×マネーロンダリングの今後の課題
②取引所が監視すべき情報が限られている
③国によって法整備のスピードが異なる
仮想通貨とマネーロンダリングに対する規制には上記の3つの課題があります。
順を追って説明していきます。
①FATFの最新ガイドラインに懸念点がある

最初に紹介するのが「FATFの最新ガイドラインに懸念点がある」という課題です。
その懸念点とは”結局ビットコインの代わりに匿名通貨が使われるだけしょ?”というもの。
FATFが2019年6月に公開したガイドラインには「取引所は、利用者の取引情報を互いに共有するべきである」という内容が記されています。
ここで言及されている共有されるべき情報には、
- ・氏名
・口座番号
・住所
などが含まれています。
取引所の監視が厳しくなる訳なので一見有効そうに思えるこのガイドラインですが、犯罪者達が”匿名通貨”でマネーロンダリングしてしまうとこの対策はあまり意味がありません。
匿名通貨とはMoneroなどを代表とする仮想通貨の一種で、「アドレスや送金した数量がわからない」という特徴を持っています。
仮にFATFのガイドライン通りに、取引所間で情報を共有させたとしても、ビットコインの代わりに匿名通貨でマネーロンダリングされるようになるだけの可能性があるのです。
前述の通り、仮想通貨のマネーロンダリング対策はFATFのガイドラインからスタートするため、根幹であるFATFのガイドラインについてさらなる議論が必要でしょう。
②取引所が監視すべき情報が限られている

次に挙げるのは「取引所が監視すべき情報が限られている」という課題です。
現在、取引所が監視すべきとされている範囲は「取引所内の取引のみ」です。
そのため、ウォレットアプリやハードウェアウォレット間での送受金に関して常時監視を行う公的機関が存在しません。
仮想通貨はウォレットアプリやハードウェアウォレット間でも送金ができてしまうため、監視する組織がないというのはマネーロンダリング問題の大きな課題であると言えます。
③国によって規制スピードやレベルが異なる

最後は「国によって規制スピードやレベルが異なる」という課題です。
仮想通貨のマネロン対策は、
- FATFがガイドラインを発表
↓
政府がガイドラインを元に法律を作る
という流れで進むと前述しましたが、国によって規制スピードや内容に差があります。
なぜなら「規制しすぎるとイノベーションが起きない」ということをみんな知っているからです。
石油も出ない、目立った技術もない、というような国にとっては仮想通貨関連業は大きなチャンスになりますよね。
そのため「できるだけ規制を緩くして色んな企業を呼び込みたい」という力がどうしても働いてしまうのです。
仮想通貨のマネーロンダリング対策は、仮想通貨がどこへでも瞬時に送金できるという特徴を持っているため、各国が同じタイミング、レベルで規制を行わないといけません。
しかし、上記のような「規制とイノベーションの関係」から、国ごとに規制スピードやレベルに差が出てきてしまうのです。
まとめ
・マネーロンダリングの”手段”としての仮想通貨
・仮想通貨”自体”がマネーロンダリング
-3つの課題-
①FATFの最新ガイドラインに懸念点がある
②取引所が監視すべき情報が限られている
③国によって規制スピードやレベルが異なる
仮想通貨やブロックチェーン技術は「AI、5G、VR、ARなどと並ぶ偉大な発明」と言われています。
今回は仮想通貨の悪い面に注目して話してきましたが、当然ながら仮想通貨が世界で注目されているのには理由があります。
以下の記事では、仮想通貨の”凄さ”について説明しているので「なぜ仮想通貨が注目されているのか知りたい」という方はしっかりと目を通しておきましょう。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!






















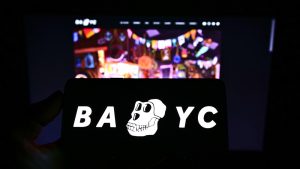



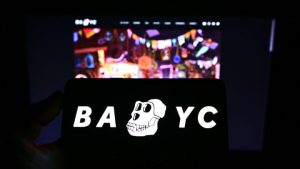

























 有料記事
有料記事