
ニュース
2019/10/17総合コンサル大手EY、政府の公的資金管理をブロックチェーンで透明化できるツールを発表
世界4大総合コンサル企業のひとつであるEY(アーンスト・アンド・ヤング)は16日、政府の公的資金管理をブロックチェーンで透明化できるツール「EY OpsChain Public Finance Manager (PFM)」を発表しました。 EY OpsChain PFMは、公的資金の予算や支出などをブロックチェーンで追跡することで、正確な管理状況や結果を市民に提供することができます。EYは、カナダ・トロントなどを代表に、EY OpsChain PFMの実証実験を世界中で行なっているといいます。 EYはイーサリアムを中心としたブロックチェーン技術の開発に注力しており、以前からサプライチェーン向けコードや、NFTを活用したワイン取引技術、ERC-20/ERC-721トークンを匿名送信できるプロトコルなどを公開しています。 記事ソース: EY

ニュース
2019/10/07クリプトスペルズ(クリスペ)が初の公式大会を実施、2019年Q4のロードマップも公開
クリプトスペルズが2019年10月6日に初の公式大会を行い、無事に大会が終了しました。 今大会の優勝賞品には白のシルバーカードの発行権NFTとなっており、実に参加者は100名を超え、非常に盛り上がったようです。 https://twitter.com/crypto_spells/status/1180809558354083840?s=20 また、公式大会の合間には 2019年4Qステークホルダー総会と称して、今後の開発計画を含むロードマップが公開されました。 クリスペMediumより クリスペは正式リリースより約3ヶ月経った現在、ユーザー数は12,000人を超えるゲームにまで成長しました。 今回のステークホルダー総会内で、クリスペのQ4は運営主体のゲームから、皆で創るTCGというコンセプトのもと運用が行われ、大型アップデートはもちろんのこと、パラメータ投票制β、ギルド機能を実装予定と発表しています。 今後の大幅アップデートや皆で創るTCGの詳しい内容は、公式Mediumを参照ください。 記事ソース : Medium − クリスペ

インタビュー
2019/09/09イーサリアム・ファウンデーション 宮口あやに聞く ブロックチェーンで社会を変えるビジョンとは
ブロックチェーンの主要技術の一つであるイーサリアム・ファウンデーションのエグゼクティブ・ディレクターである宮口あや氏。今回、一時帰国にあわせてGRASSHOPPERでの取材が実現した。宮口氏のブロックチェーンとの出合い、イーサリアム・ファウンデーションへの想い、既存ビジネスとの融合、今後の展望などを伺った。 ※ 今回のインタビュー記事は、CRYPTO TIMES の新井が協力の下、GRASSHOPPER編集部とインタビューを実施し、株式会社電通様が運営するWEBメディアGRASSHOPPERに掲載されたインタビューの転載となります。 転載元記事 : イーサリアム・ファウンデーション 宮口あやに聞く ブロックチェーンで社会を変えるビジョンとは– GRASSHOPPER サンフランシスコでのブロックチェーンとの出会い -ブロックチェーンに興味を持ったきっかけは何でしょうか。 元々、日本で長い間高校教師をしていたのですが、生徒達には外の世界を見に行きなさいと伝えていました。生徒達を海外に送り出しているうちに自分自身ももう一度挑戦したくなり、自ら行動しようとサンフランシスコに渡り、ビザのためにMBA取得から始めました。そのときに Kraken(クラーケン、米仮想通貨取引所大手)を立ち上げたJesse Powellからビットコインの話を聞いたのがブロックチェーンに興味を持ったきっかけです。 ビットコインについてある程度理解してきたところで、ちょうどその頃自分が専門にしていたマイクロファイナンスとすごく相性がいいということに気づきました。途上国の発展についての自分の興味関心と ビットコインの組み合わせで何か面白いことが起こるのではないか、と。 そこで、開発者が3名くらいで取り組んでいたスタートアップKrakenに参加することに決めました。いまではKrakenは800名ほど社員がいるので良いタイミングで参加できたと思っています。ちょうどクリプト業界自体が立ち上がった状態で、その頃から生き残っている取引所だとCoinbase、BitStamp、Krakenの3つぐらいです。その中に女性がいるのも珍しかったし、日本人もいない状態でした。 元々、日本市場担当としてスタートアップに入ったわけではないのですが、メンバーも日本に興味を持っているということで、日本市場開拓を決定した矢先にMt.GOX事件が起こりました。日本でまだビットコインを知っている人が少ない時期に、Mt.GOX事件というネガティブな印象が広まってしまい、Krakenの説明だけではなく、ビットコイン自体のイメージアップを行うためにメディアや政治家に説明する活動や、Bitflyerの加納裕三さんらと業界団体を作る流れにも繋がっていきました。 サンフランシスコと日本を行き来し、日本の業界を立ち上げることにはミッションを感じつつも、「取引所」の仕事というのは 私の情熱からは離れたところにあったため、個人的に途上国の難民支援をするためにブロックチェーンを活用したものなど、ソーシャルインパクトを起こすプロジェクトにアドバイスをしていました。 そのような活動を続けている折、イーサリアム・ファウンデーションのメンバーから仕事を手伝ってくれないかと相談が入りました。エグゼクティブ・ディレクターになってほしいと。因みにこの話があったのは、2017年末にメキシコでDevCon(イーサリアム開発者のカンファレンス)があったときです。イーサリアム創始者のVitalik Buterinも含めて、イーサリアムを作っている人たちは、まったくお金を儲けるのが得意じゃない感じで、純粋に情熱で社会を良くする技術を作りたいという気持ちでやっています。そのような想いにも共感をし、引き受けました。 分散型の究極を考えていくと、日本の「引き算の美学」に落ち着く ーイーサリアム・ファウンデーションで行っていること、現在のミッションを教えてください。 イーサリアムに関わること全部です。研究開発、助成金サポートや教育。サポートしている人たちをサポートする役割もあります。つまり私のポジションは、イーサリアム・ファウンデーションをまとめるだけでなく、イーサリアム全体のコミュニティをサポートしていくことなんだと気づいたときにはプレッシャーで夜も寝られないこともありましたね。 ー現在のポジションについて、世界の見え方はどう変わりましたか? イーサリアム・ファウンデーションにいると、意外と、日本人であることがぴったりだと感じます。イベントでよく日本の「引き算の美学」という言葉を使うのですが、いわゆるファウンデーションの在り方とか、分散型の究極を考えていくと日本の「引き算の美学」に落ち着くのです。世の中がもっと大きくなればいいとか、お金がもっとあればいいとか、資本主義的な流れへのカウンターでもあります。 サンフランシスコにいると、みんな優秀・給料も高い・Macを使っている…などとサンフランシスコが中心に思えてきます。しかし、一歩引いて考えてみた時に、世界の力のバランスがどれだけ悪いかということがより見えます。本来、力はみんな平等にあるべきだということを考えた時に、やはりブロックチェーンにもつながってきます。 ー資本主義の過熱から引く動きがある一方で、EEA(イーサリアムの企業利用を進める団体Enterprise Ethereum Alliance(エンタープライズ・イーサリアム・アライアンス )加入など、ビジネスシーンでの活用を促進する動きもありますよね? 最初はどちらかというと、Vitalikも含めて、イーサリアム・ファウンデーションは資本主義の流れから生まれた大企業とやりとリしない流れを歩く志向がありました。ですが、現在ではイーサリアムを作ったVitalikらファウンダー自身も想像がつかなかった程大きなコミュニティに成長し、大きな力を無視をすると影響力に限界があるということが見えてきました。 完全に一緒になることはなくても、どちらかに転んでしまうなら、私たちの理念を伝えることでなるべく良い方向に行ってほしいですし、こちら側もイーサリアムのスケーリングがある程度進んできたので、足並みを揃えることが可能になってきたともいえます。 ー大企業と足並みを揃えて活動する上で必要になるのはどのようなことでしょうか? 企業でイーサリアムのパブリックのメインネットを利用するために、我々のチームやコミュニティの活動がサポートできればと考えております。 新しく出来上がるスケーリングによってプライバシーでもできることが増えるので、タイミング的にはもっとファウンデーションの研究者などとも話し合って勉強しておく必要性があるのです。 ーイーサリアムがもっとも大企業向けに活用できる領域はどこなのでしょうか。 一番取り上げられやすいのはファイナンスのところなのですが、サプライチェーンや、情報をシェアすることによってメリットがあるもの、またそれによってビジネスが成り立つものですね。 今は保険などの領域でもそういった形が作れます。ただ、注目されるのはファイナンスの方が多いです。金融系のほうが規制や「パブリックかプライベートか」というところにだけフォーカスしてしまうので、それ以外のNFTやゲームや、トークンで作るシステム・社会などが出てくると面白いと思っています。まだまだこれからだと思います。 イーリアサムの活用事例とは? ー「イーサリアムが活きてくる」プロジェクトはどのようなものでしょうか? 自分がアドバイスしているもので、Everestというプロジェクトがあります。分散型アプリケーションを作るときに大事になる利用者の特定・その取引の管理に取り組んでいます。もともとチームのミッションは世界中で大きな問題となっている「人身売買」。誘拐された人の身元を指紋や顔認証などで証明できるようになり、被害を1パーセントでも減らせたら、ということも考えていした。今はさらに大きなレベルで、インドネシアの難民のIDなど、Digital Identityのソリューションを提供しています。 うちの財団はイーサリアムのプラットフォームの開発支援がメインで、あまりdApp(分散型アプリ)の特定のビジネスを応援することをしないのですが、エコシステムの中で欠けている部分が埋めていくためにもある程度啓蒙活動をしていかないと、と思っています。 Etheriskという保険プロジェクトのプラットフォームでは、普通の保険ではカバーできないような自然災害に適用できる保険プログラムを作っていて、すでに実際に使われています。他にも、保険加入率が7%ほどのスリランカの農家を対象に、天候インデックスを絡めたスマートコントラクト型保険などもやっています。 このようなプロジェクトに適用できるイーサリアムに魅力を感じています。 ーよりソーシャルインパクトを起こしていくために、日本では今どういうお話をされているのですか。 日本はオープンソースソフトウェア開発に取り組んでいる人が、優秀でも隠れており、あまり報われない環境だと思います。日本人なのでみんな控えめという性格ももちろんあり、その点をうちのチームにわかってほしいなと色々と話を進めています。 ー日本の大企業側には現在、どういう姿勢でアプローチしてきてほしいでしょうか。 日本は文化的に、まだまだ優秀な個人が大企業にいると思います。また、エンジニアの給料が安いと言われる日本では、自分で興味があることを勉強する時間もあまりないと思います。オープンソースは参加して初めて学べるので、優秀な人がチャレンジできる環境を提供して頂けたらいいなと思いますし、そのためにうちの財団などがイーサリアム・コミュニティの優秀な人を金銭的に支援するなど、研究勉強できる場を提供していくような取り組みが大事だと思っています。将来的には仕事をやめなくてもイーサリアムが勉強できる、というのが理想です。 ー日本では10月に大阪でブロックチェーンの国際イベントDevConが開催されます。日本に対して期待していることは何ですか。 日本のブロックチェーン業界の起爆剤になればいいなと思っています。もっと日本のブロックチェーン業界が中身のある形に育っていかないとと思っていますし、日本もブロックチェーンを引っ張って欲しいと思っています。 Devconを開催する国の選定理由は、ブロックチェーン業界がきちんと活性化する兆しがある国であることです。以前よりブロックチェーン・コミュニティの人たちには、今後、日本にブロックチェーン業界がもっと良くなっていく未来がないとDevconの開催はできないと話をしていました。ですが、私の懸念をよそにコミュニティが中心となって行った東大でのイーサリアムイベントや、大日方祐介さんが企画した、サッカー選手であり投資家である本田圭佑さんとのイベントで、日本の若い方々がブロックチェーンへの熱意持って取り組んでいる姿勢が見えたので、今後に期待しようとDevconの日本開催を決定しました。 ー今後、世界のブロックチェーン業界に日本のプレイヤーが増えていくためにはどのようなことが必要でしょうか。 みんな控えめなので、自信を持ってほしいということです。私も海外でポジションにつくと「日本人でよかった」「日本人だから活かせることもある」「日本人だからわかる細かいところがある」ということに気づくことが多くありました。 イーサリアムは今ちょうど、アプリケーションがどんどん作れる状況になっています。アプリケーション開発にあたってユーザー目線でより良いものを作る、面白いものとかを作ることのも日本人の得意分野だと思うので、自分を殺さずにそれぞれが活躍できる場所を上手に見つけていってほしいと思います。 ー最後に、宮口さんが想像する未来は、ブロックチェーンが社会にどのように浸透していくと考えますか。 不公平のない、不均衡のない世の中というものを目指して現在色々と取り組みをしています。そのため、今の世の中を変えていくというよりは、バランスが崩れているところを適正なものに戻していくという表現が近いと思っていますし、私自身もそういう部分に魅力があります。バランスが崩れてしまった部分をブロックチェーンが正していってほしいと考えています。 Interview & Text:西村真里子 協力:CRYPTO TIMES 新井進悟 転載元記事 : イーサリアム・ファウンデーション 宮口あやに聞く ブロックチェーンで社会を変えるビジョンとは– GRASSHOPPER

ニュース
2019/09/02トークン型SNSのALISが日本仮想通貨ビジネス協会に参加
良質記事の執筆や評価でトークンを獲得できるソーシャルメディア「ALIS」を運営する株式会社ALISが、日本仮想通貨ビジネス協会の準会員に参加しました。 同協会は、暗号資産交換業者や関連事業者に加え、同系統のビジネス参入を計画する銀行、保険会社、金融商品取引会社などがブロックチェーン業界の知見集約や意見交換を行う場を提供しています。 ALISは今後、同協会に所属する国内大手のブロックチェーン・金融・IT企業計113社と肩を並べることとなります。 今年8月には、同協会にも正会員として参加しているコインチェックが、国内で取り扱いのない暗号通貨上場を検討していると発表しており、ALISの協会参加が自社通貨の評判向上に繋がるかに要注目です。 Coincheck勝屋社長、国内で取り扱いのない暗号通貨上場を検討 Libra上場も視野に ALISがNFTを活用した「ライセンストークン」発行機能のα版をリリース 記事ソース: 日本仮想通貨ビジネス協会

ニュース
2019/08/23クリプトスペルズとMyCryptoHeroesがコラボ! ゲーム間で一部アイテムの転送が可能に
日本で人気のDAppゲーム「クリプトスペルズ」と「MyCryptoHeroes」は23日、両ゲーム間で一部アイテムを転送できるコラボ機能を8月29日から実装することを発表しました。 29日11:00〜12:00予定のメンテナンス後から実装されるコラボ機能では、各ゲームから以下のアイテムを転送できるようになります。 【クリプトスペルズ→MyCryptoHeroes】 ゴールド: モーショボー/Moshobo ゴールド: ヴァンパイアロード/Vampire Lord ゴールド: 知恵の女神ミネルヴァ/Minerva 【MyCryptoHeroes→クリプトスペルズ】 Uncommon: アンデルセン Uncommon: アルキメデス Uncommon: 金太郎 変換の詳しい手順はコチラに記載されています。 今回のコラボでは、EthereumのNFT (ERC-721非代替型トークン)を活用したブロックチェーンゲームならではのクロス展開となっています。 ブロックチェーンゲームで各タイトルにて利用されているアセットを他のゲームに持ち込むことができるため、技術的な観点からも面白いものとなっています。 記事ソース: MyCryptoHeroes

初心者向け
2019/08/22【最新版】IEOとは?ICOとの違い・各取引所のパフォーマンスを解説
イニシャル・エクスチェンジ・オファリング(IEO)は、暗号資産取引所がプロジェクトを代行してトークンセールを行う新しい資金調達法です。 イニシャル・コイン・オファリング(ICO)は、ブロックチェーン系プロジェクトの資金調達法として莫大な人気を集めていましたが、近年米国を中心に規制が厳しくなり、最近ではほぼ見かけなくなってきました。 2018年からは、証券法を遵守したセキュリティ・トークン・オファリング(STO)も話題になり始めましたが、ユーティリティトークンの発行が大半を占める中、証券型トークンの発行というのはあまり人気ではないのが現状です。 そこで2019年に入り、「ICOの死」と入れ替わるように登場したのがIEOで、2019年2月に実施されたBinance LaunchpadのBitTorrent Token ($BTT) IEOを皮切りにその人気は急騰し、今では大手取引所の多くが同様のIEO事業を展開しています。 こちらのページではIEOの仕組みや特徴、ICOとの違いなどを詳しく解説し、各取引所でのIEO事業状況などをわかりやすく徹底解説していきます。 IEO(Initial Exchange Offering)とは? IEO(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング)とは、一言で表すならば「暗号資産取引所がプロジェクトを代行して行うICO」です。 一般的にIEOでは、プロジェクトが発行したトークンを取引所へ送付し、取引所はプロジェクトに代わって受け取ったトークンを投資家に販売します。 投資家は取引所を通してトークンを購入するため、必然的に取引所のアカウント(KYC・AMLも含む)が必要となります。 2017年12月に大手暗号資産取引所のBinanceが初めてIEOを行いましたが、当初はあまり注目されず、同社は以降事業を中止していました。 しかし、ブームの衰退や規制の厳格化などからICOが実施困難となった2019年に入り、BinanceはIEOプラットフォームを復活させ、TRONが買収したP2Pネットワーク「BitTorrent」のトークンセールを代行することになります。 BitTorrentの$BTTは18分で完売し、瞬く間に7億7000万円相当を調達します。対象トークンはセール後にプラットフォームの取引所に上場もするため、このシステムは莫大な人気と注目を集めることになりました。 ICOとの違い ICO(イニシャル・コイン・オファリング)は、プロダクト開発段階にあるプロジェクトが、開発資金の投資と引き換えにプロダクトに付随するトークンを先行配布(=テストネットトークンを配布)するという資金調達法です。 Mastercoinと呼ばれるプロジェクトが2013年に初めてICOを行い、翌年にはイーサリアムが12時間で3700BTC(当時で約230万ドル相当)を調達し、ICOはブロックチェーン系プロジェクトの資金調達法として大きく注目されることとなりました。 2017年あたりからICOの数は目まぐるしい勢いで増え、調達資金を持ち逃げする「スキャム」も多く登場しました。優良プロジェクトの選別も当然難しくなっていきました。 そんな中、Binanceなどの大手集権型取引所が優良プロジェクトを選定し、自社プラットフォーム上でそのプロジェクトのICOを代行しよう、というアイデアから始まったのがIEOです。 それでは、投資家が自分でプロジェクト選定をしないこと以外に、大手取引所がICOを代行するIEOにはどのような特徴があるのでしょうか? IEOの特徴 IEOは、ICOにはない特徴をいくつか備えています。ここでは、それぞれの特徴を詳しく説明していきます。 プロジェクトは取引所のユーザーベースにリーチできる 大企業が主導するプロジェクトを除き、ICOを行うプロジェクトはゼロから投資家を勧誘していかなければならないため、マーケティングに多くの労力を費やす必要がありました。 一方IEOでは、すでに多くのユーザーを抱える大手取引所がプロジェクトを告知するため、リーチできるユーザーの規模・削減できるマーケティングコスト共に大きなアドバンテージがあります。 また、取引所によってはIEO実施に手数料を課すケースもあるようですが、ICOにかかるマーケティングコストやリスクを取り除くと、その分の資金や労力を開発など他のことに回すことができるようになります。 取引所が優良プロジェクトの審査を行う IEOでは、取引所がプロジェクトの技術力や正当性などを審査します。例えばBinance Launchpadでは、プロダクトの実用性やユーザーベースの大きさなどが審査項目として挙げられています。 ICOブーム時には技術力や正当性に疑問のあるプロジェクトが多く存在しましたが、IEOではこういった取引所の審査を突破して初めて資金調達ができるため、中身のないプロジェクトは淘汰されていきます。 取引所の審査ポリシーを鵜呑みにすべきではありませんが、上場通貨の精査などをしてきた取引所の判断はある程度信用しやすいといえます。 大型セカンダリマーケットへの流通が確定している ICOでは、トークンセール終了後にどこの取引所にも上場しない、もしくは流動性に欠けるマイナーな取引所にのみ上場するといったケースが数多くありました。 特に投資家にとって、投資したトークンがメジャーなセカンダリマーケットに上場するかどうか、というのは大きな心配であると言えます。 一方、大手取引所が実施するIEOでは、トークンセール終了後にエスカレーター方式で上場されるため、投資したトークンを必ずトレードできるという観点では安心できます。 メジャーなIEOプラットフォームの状況まとめ Binance Launchpadを皮切りに、今では多くの暗号資産取引所がIEO事業を展開しています。こちらでは、メジャーなIEOプラットフォームのこれまで事業状況を詳しく解説していきます。 Binance Launchpad プロジェクト名 上場日 上場日最高価格÷セール価格 Troy 2019/12/5 2.50倍 Kava 2019/10/25 2.78倍 Band Protocol 2019/9/18 5.00倍 Perlin 2019/8/26 3.48倍 WINk 2019/8/1 7.89倍 Elrond Network 2019/7/4 46.15倍 Harmony 2019/6/1 7.55倍 Matic Network 2019/4/26 4.00倍 Celer Network 2019/3/25 5.53倍 Fetch.AI 2019/2/25 6.00倍 BitTorrent Token 2019/1/28 5.48倍 Bread 2017/12/26 2.70倍 Gifto 2017/12/14 4.20倍 Binance Launchpadは2017年末にローンチされた世界初のIEOプラットフォームですが、当初にいくつかのプロジェクトをローンチした後放置されていましたが、2019年にサービスの再開が発表され、毎月1件IEOが行なわれることになりました。 第1弾として行われたBitTorrentのトークンセールは、開始後18分間で約7.7億円を即調達し、IEOブームに火を付けるきっかけとなりました。 Binance Launchpadは「一定期間内での自社トークン($BNB)平均保有量に応じて、IEOトークン購入権利の抽選券を獲得できる」という事業モデルを発明した第一人者でもあります。 このIEO事業モデルには、自社トークンの需要を高める狙いがあります。 Huobi Prime プロジェクト名 上場日 上場日最高価格÷セール価格 EMOGI Network 2019/8/15 7.40倍 Akropolis 2019/7/16 18.60倍 Reserve Rights 2019/5/22 8.48倍 ThunderCore 2019/5/9 8.00倍 Newton Project 2019/4/16 7.18倍 TOP Network 2019/3/27 6.21倍 Huobi Primeは大手暗号資産取引所のHuobiが今年3月にローンチしたIEOプラットフォームです。 第一弾となる「TOP Network」のIEOに参加したユーザーは全世界で13万人に登りました。Binance Launchpad同様、このトークンセールは瞬時に終了し、実際にトークンを購入できたのはわずか3764名となっています。 Huobi PrimeのIEOは、セールを3段階に分ける「Price Limit Rounds」方式を採用しています。また4月からは、従来のPrimeリスティングより短い期間でIEOを行う「Huobi Prime Lite」というものも登場しました。 Huobi Primeが選定するプロジェクトはBinance Launchpadに比べマイナー気味のものが多いのも特徴的です。 KuCoin Spotlight プロジェクト名 上場日 上場日最高価格÷セール価格 Tokoin 2019年8月23日 9倍 Coti 2019年6月4日 17.42倍 Chromia 2019年5月28日 3.0倍 Trias 2019年5月14日 10.0倍 MultiVAC 2019年4月9日 3.67倍 KuCoin SpotlightはKuCoinが2019年3月にローンチしたIEOプラットフォームです。 他者に比べるとまだ取り扱い数が少ないですが、MultiVACやTrias、Cotiなど認知度のあるプラットフォーム系プロジェクトを多く採り入れています。 特にCotiは、ブロックチェーン関連企業への積極的な投資をしている株式会社リクルートから出資を受けているプロジェクトです。 OK Jumpstart プロジェクト名 上場日 上場日最高価格÷セール価格 Pledgecamp 2019/8/22 2.20倍 Echoin 2019/8/9 4.16倍 Eminer 2019/7/31 4.67倍 WIREX 2019/7/1 5.32倍 En-Tan-Mo 2019/6/10 3.36倍 ALLIVE 2019/5/16 2.50倍 Blockcloud 2019/4/11 18倍 OK JumpstartはOKExが2019年4月にローンチしたIEOプラットフォームで、19年7月からは月2件という活発なペースでトークンセールを行なっています。 コインチェック マネックスグループが運営する大手国内取引所・コインチェックは2019年8月、ユーティリティトークンの資金調達を支援するIEO事業の検討を開始しました。 国内取引所のコインチェック、IEO事業の検討開始を発表 - CRYPTO TIMES 現時点では詳細な情報は一切公開されておらず、「検討」の範疇を超えないものとなっていますが、国内取引所初のIEO事業イニシアチブとして期待ができます。 日本ではJVCEA(日本仮想通貨交換業界)が主導して通貨上場に厳しいガイドラインが設けられており、匿名通貨やセキュリティ(配当型)トークンはもちろん、リスティングできるプロジェクトはかなり限られてくるものと推測されます。 IEOの懸念点 IEOは上位互換のような形でICOに取って代わりましたが、ICO時から残る問題点や、IEOならではの新たな課題が存在します。 大手取引所による集権的な資金調達 IEOは、大手取引所が優良プロジェクトをピックし、プラットフォーム上で販売を代行する資金調達法です。 また、上記でも触れた通り、IEO事業は取引所トークン(BNBやHTなど)の需要を助長するためのツールとして機能している点も否めません。 こういった意味合いでは、ブロックチェーン技術に分散型社会確立の可能性を見出している人々にとって、IEOはベストな資金調達システムではないと考えられます。 また、ICOではほとんどのトークンがイーサリアムのERC-20規格を用いたテストネットトークンとして発行されており、資産の追跡などは比較的容易でした。 しかし、取引所が行うIEOでは、セール結果のみが報告される場合が多く、透明性の確立が以前より難しくなっています。 結局、即売りがベスト? IEOプラットフォームの中には、Huobi Primeなど、より安定した価格形成を促す資金調達法を考案しているところもあります。 しかし、大半のケースではICO時同様、上場とともに購入したトークンを即売りして利益を上げるケースが多いように見受けられます。 こういった観点では、IEOはICO時から存在する投機的要素を取り除けていないと言えます。 取り上げられるプロジェクトがVCの出口に? 主要取引所で実施されているIEOには、2018年の5月以降に話題になったプロジェクトが多く存在します。 2018年は市場が悪化した年で、ベンチャーキャピタル(VC)から投資を受けたものの、ICOを実施せずに時を待ったプロジェクトも多く存在しました。 BinanceでIEOを実施したCeler Networkや、Huobi PrimeのTop Networkがその最たる例です。 2018年に有望と言われていたプロジェクトに投資したVCは、投資したトークンが上場するのを待ちわびてきたわけで、エグジットを考えるVCが一気にトークンを売ることで価格が大きく割れることなども出てくるかもしれません。 IEOの参加方法 IEOに参加するには各取引所のアカウントが必要となります。また、KYC(本人確認)や2段階認証などのセキュリテイも参加条件に含まれてきます。 取引所によって参加方法は異なりますが、ここではBinance Launchpadを例に紹介します。 まずはBinanceにログインし、右上の人型のアイコンから「My Account」を選択します。 続いてマイページ上部のLv.2の下にある「Submit Verification Documents」をクリックします。 アカウントの所有者が個人か法人か聞かれるので個人の方はPersonalを選択します。 上の画面が表示されるので以下の順に情報を入力していきます。 名前 ミドルネーム(ない場合は空欄) 苗字 生年月日 住所 郵便番号 都市 国 入力が完了したら「Begin Veritification」をクリックして次へ進みます。IDの認証プロセスが開始されるので「Start」をクリックして始めます。 身分証の発行国を選択し、アップロードする書類を選びます。日本の身分証はパスポート、免許証、保険証などに対応しています。 身分証の写真をアップロードすると、自撮り写真のアップロードを求められます。紙にBinanceと今日の日付を書いて自分の顔と一緒に撮影し、アップロードします。 ここまで完了すると、最後のプロセスとしてアプリ上での顔認証が求められます。Binanceのアプリをダウンロードし、表示されるQRコードを読み込んで認証を完了させます。 これで一連の認証プロセスは完了となります。あとは参加したいIEOのプロジェクトページに受付期間中に行き、「Claim Tickets」を押すと抽選に参加できるチケットがもらえます。 まとめ IEO(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング)は、ブーム衰退・規制強化に伴って消え去ったICO(イニシャル・コイン・オファリング)に代わって登場した、集権的な資金調達法ということでした。 IEOはBinance LaunchpadでのBitTorrent Token即完売を火付け役に大きな人気を集め、今では米国・日本以外の主要取引所の多くが同事業に参入しています。 日本でもIEO参入が検討されつつある中、これからもIEOの動向を追っていくことはとても大切だと考えられます。 *こちらの情報は新たなIEO案件やプラットフォームの登場に応じて随時更新していきます。
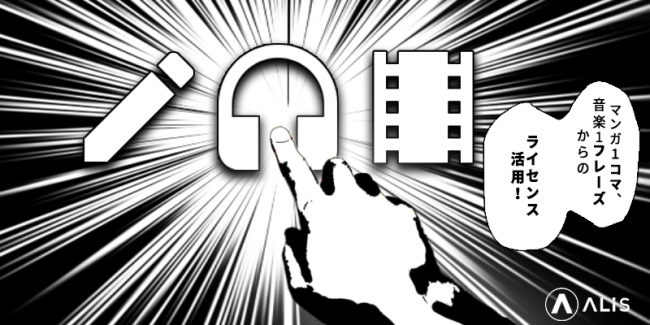
ニュース
2019/08/22ALISがNFTを活用した「ライセンストークン」発行機能のα版をリリース
ブロックチェーンベースのソーシャルメディアを運営する「ALIS」は21日、デジタルコンテンツのライセンスをNFT(非代替型トークン)を用いてトークン化する「ライセンストークン発行機能」のα版をリリースしました。 同機能を用いると、ALIS上のデジタルコンテンツに対して、その利用権を表すERC-721トークンを発行することができます。トークン化された利用権は簡単に譲渡・売買できる設計になっています。 また、ライセンストークンは、有効期間を設定したり、「マンガ1コマ」「音楽1フレーズ」などといった細かい単位を指定することもできるもようです。 記事ソース: ALIS / PR TIMES

レポート
2019/07/05IOST、川崎市とNEDOの起業支援拠点 K-NIC で、初「ブロックチェーン ・スタート」イベントを開催
2019年7月3日(水)に、川崎市、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、公益財団法人川崎市産業振興財団の3者で運営する、起業家支援拠点「Kawasaki-NEDO Innovation Center(K-NIC)」で、IOST/IOS財団(非営利、シンガポール、開発者約50名)が、ブロックチェーン技術にコミットした起業家たちを招いてイベントを開催しました。 本イベントでは、東京と大阪の学生アントレプレナー、藤岡紀光氏(慶應義塾大学、GeekHash Inc.)と岡崇氏(近畿大学、PHI Inc.)、エンターテイメント大手「avex」とエバーシステム株式会社(名古屋)でブロックチェーン事業を率いる石田陽之氏が登壇しました。 起業3ヶ月目、1年目、2年目の起業家登壇者が、どのようにブロックチェーン技術に可能性をみつけて、そして魅せられて、決意から起業まで、どのような活動で大きなチャンスを獲得したのか、彼らが取り組んでいるプロジェクトを熱く語るイベントとなりました。 本イベントのモデレーターを務めた、19歳の渡辺涼太氏(都立小石川中等教育学校卒)は、クラウドファンディングのリターンをトークン化するビジネスで起業を準備しています。 各登壇者のピッチ 岡崇 CEO — PHI Inc.、近畿大学 トークテーマ「ブロックチェーン時代の働き方改革について」 従来の組織では上層部だけがプロジェクトの根幹を担うような現在の多くの企業体質に、ティール組織という自律形態で、個人に見合った最大限の権限を譲渡し、組織の物事を他人事ではなく自分ごとで考えることの重要性を訴えました。 7月3日にはIOSTと共同であらゆる組織をオンラインで可動できるようにするGUIDの開発を進めていくことを発表しています。 PHI Inc. — 2019年4月設立、事業内容:ブロックチェーン技術を活用した製品開発。IOSTプラットフォームを使ったDAO(Decentralized Autonomous Organization、分散型自立組織)のサービスを開発中。 藤岡紀光氏 CEO — GeekHash Inc.、慶應義塾大学 トークテーマ「ブロックチェーン領域でのビジネスの可能性」 国内のブロックチェーン総合メディアに初期から学生スタッフとして参加。その経験が起業で活きていること、起業後、ビジネス拡大の戦略としてのマーケティング事業と開発の資金バランスについて語りました。 GeeKHash Inc. — 2018年8月設立、事業内容:海外ブロックチェーンプロジェクトの日本国内への事業参入およびマーケティング。IOSTプラットフォーム上で、NFT(Non-Fungible Token)を使ったサービスを開発中。 石田陽之 CEO — エバーシステム株式会社 , エイベックス・テクノロジーズ株式会社 ブロックチェーン事業部 トークテーマ「新規事業立ち上げからブロックチェーンの社会実装へ」 20年前の起業の原点、大学の部活資金のために始めた、学生アルバイトと店舗をつなぐ、オンラインプラットフォームをつくったこと。 そして現CTOの和田(Ph.D.)氏との出会いから、まだ誰も挑戦しなかったフルチェーンのブロックチェーンゲームの開発とエイベックスとの出会いについてお話しされました。 エバーシステム株式会社 — 2017年8月設立、事業内容:ブロックチェーン技術を適用するための研究開発。IOSTプラットフォームを使ったDappゲーム「クリプトニンジャ 」を開発。2019年5月、エイベックス・テクノロジーズのブロックチェーン事業部に就任。 パネルディスカッション 起業の先輩である石田氏がモデレーターになり、渡辺氏(起業中)、岡氏(起業3ヶ月目)、藤岡氏(起業1年目)、ブロックチェーンに魅せられたきっかけなど、登壇者たちは熱く語りました。 まとめ 川崎市にある起業家支援拠点「Kawasaki-NEDO Innovation Center(K-NIC)」で行われた、IOST/IOS財団によるイベントのレポートになりました。 IOSTによる次回のイベントは7月9日に大阪で開催されます。『WITH BLOCKCHAIN ブロックチェーン とは?大阪!』と題したイベントで、今回と同様に岡氏、藤岡氏、そして株式会社Xethaを運営する武藤氏が集まるイベントとなっております。 興味のある方、大阪の方は参加してみてはいかがでしょうか?

ニュース
2019/06/27Wavesが大型アップデート「Node 1.0」を公開 スマートコントラクトやNFTの発行が可能に
リースド・プルーフ・オブ・ステーク(LPoS)コンセンサスを採用したブロックチェーン・Wavesが、スマートコントラクトや非代替型トークン(NFT)の発行を可能にするアップデート「Node 1.0」を公開しました。 デベロッパーは、Waves独自のスマートコントラクト言語「RIDE」で分散型アプリケーション(DApps)の開発を行うことができるようになります。 また、アルゴリズム型ステーブルコインや非代替型トークンもNode 1.0実装後からRIDEを用いて発行できるようになります。 Node 1.0が実際に有効化されるためには、ネットワークの80%の同意票を得る必要があります。アップデートは80%到達から1週間で有効化されることになっています。 Wavesは分散性確立のための特徴的なインセンティブ作りを行なっており、コンピューターの処理能力を他者に貸し出してステーク報酬の一部を得るLPoSコンセンサスメカニズムを採用しています。 記事ソース: Waves

ニュース
2019/06/27イーサリアムウォレットなどのWeb 3機能のついたモバイルブラウザ「Opera Touch」がiOSに登場
ブラウザ上でETHやERC-20トークンの送受金・保管ができるイーサリアムウォレットが搭載されたモバイルブラウザ「Opera Touch」がiOSに登場しました。 ステーブルコインや非代替型トークン(NFT)も、ERC-20規格のものであればOpera Touch上で管理することができます。 OperaのWeb 3サポートはアンドロイド、PC、Mac、Linuxにすでに導入されており、今回iOSに対応しメジャーなシステム全てをカバーしました。 また同社は、今回のリリースでイーサリアムDAppsのMarble.Cardsとの提携も発表しました。 Marble.CardsはウェブURLをNFTとして発行し、他ユーザーと取引できるプラットフォームです。それぞれのURLはネットワーク上に一度だけしか発行できないため、希少価値が生まれる仕組みになっています。 Opera Touchでは、Marble.Cardsをシームレスに利用できるようになっています。 ブロックチェーン技術をシステムに組み込むWeb 3ブラウザはBrave Browserが人気ですが、イーサリアムウォレットを標準搭載したOperaも今後注目を集めていくと予想されます。 記事ソース: Opera












 有料記事
有料記事


