
ニュース
2019/05/17ConsenSys・LVMH・マイクロソフトが高級ブランド業界向けコンソーシアムチェーン「AURA」を発表
ブロックチェーン企業のConsenSysが、LVMHとマイクロソフトとの提携のもと高級ブランド業界向けのコンソーシアムチェーン「AURA」を発表しました。 AURAはLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)の子会社であるLouis VuittonやDiorの商品追跡に活用されることが決定しており、今後LVMH傘下の他のブランドにも使われることが検討されているといいます。 消費者は各ブランド商品の購入とともにその品物の原料から店頭販売までの成り立ちをブロックチェーン上で確認することができるようです。 AURAの基盤はJPモルガンのQuorum、非代替型トークン(NFT)規格はイーサリアムのERC-721に基づいてConsenSysが開発したといい、デプロイにはマイクロソフトのクラウドサービス・Azure(アズール)が活用されるようです。 マイクロソフトとJPモルガンが提携を発表 Azure上でQuorumのデプロイが可能に 記事ソース: プレスリリース

ニュース
2019/05/17Binance(バイナンス)がLaunchpad第5弾「Harmony ($ONE)」のIEOを発表
Binance(バイナンス)のIEOプラットフォーム「Binance Launchpad」が、IEO第5弾としてHarmony ($ONE)のトークンセールを実施することを発表しました。 HarmonyはPoSベースのシャーディングプロトコルで、PBFTを改善したコンセンサスメカニズム(FBFT)を実装しています。 開発チームは、代替・非代替型トークン(NFT)のマーケットプレイス確立や、ゼロ知識証明を活用したプライバシー特化型のデータシェアリングなどをHarmonyのユースケースとして挙げています。 ネイティブトークン・ONEにはPoSのステーキング、ネットワーク手数料、ガバナンス参加などといったユーティリティがあります。 トークンセールは5月27日~29日で開催され、購入権利は抽選で選ばれることになっています。抽選券は20日~26日の間の平均BNB保有量が多ければ多いほど枚数も増え、最大で5枚(平均保有量500BNB以上)を手に入れることができます。 Harmonyは未だテストネット段階で、今回ONEトークンはBinance Chain上のBEP-2トークンとして発行されることになっています。メインネットの公開は今年の第2四半期から第3四半期の間とされています。 記事ソース: Binance

ニュース
2019/05/08「進撃の巨人」のアートワーク所有権をトークンとして取引できる日本発サービス「Anique」が登場
アニメやマンガ、ゲームなどのアートワークのデジタル所有権を取引できる日本発のサービス「Anique(アニーク)」が本日5月8日にローンチされました。 Aniqueは、各アートワークの所有権を非代替型トークン(NFT)と結びつけ、ブロックチェーン上で管理・取引できるサービスを展開しています。 トークンの保有者は作品のオーナーとしてその所有履歴をブロックチェーン上に半永久的に記録できるほか、トークンと紐付くアートワークのセル画を実際に購入・所有することもできます。 また、アニークは売買金額の一部をクリエイターに還元することで「創り手の新しい収入源」を創出していくことも目指しています。 今回のローンチのサービス第一弾として、人気アニメ「進撃の巨人」のアートワーク26点のデジタル所有権の抽選販売を5月8日から開始します。 進撃の巨人は海外のファンも圧倒的に多く、大型IPとのコラボということで非常に大きな注目が集まります。 今回のデジタル所有権の抽選の申し込みはキャンペーンページから行うことができ、受付期間は5月8日午前10時から5月20日正午までとなっています。 アートワークは所有権のみで10000円、額装セル画付きで60000円で販売されます。 Aniqueは日本のコンテンツ流通力の向上を推進するとともに、すでに放送や販売が終了した作品のアートワークも取り扱うことで「眠っている資産」も掘り起こしていくこと発表しています。 ブロックチェーンのトークン規格の中には、アートや不動産、コレクタブルなど実在する資産の所有権を「トークン化」して管理できる機能を持つものが存在します。 これらのトークンはそれぞれ固有の資産と結びつき異なる価値を帯びるため「非代替型トークン(NFT: Non-Fungible Token)」と呼ばれています。 「トークン化」された資産はブロックチェーン上でその所有権を細分化管理できるため、資産の流動性とトレーダビリティを向上できる技術として現在注目されています。 CRYPTO TIMESでは今回の取り組みに対して、Aniqueチームへ近日取材を行う予定です。 記事ソース : Anique

ニュース
2019/05/02ブロックチェーンを利用しYoutubeライブでデジタルグッズを配布できる「アポイタカラ」が音声ファイルトークンを実装!
ブロックチェーンを活用した動画配信者向けマーケティング支援ツール「アポイタカラ 」で音声ファイルのトークンが発行可能になりました。 アポイタカラのα版は3月13日に画像ファイルのみをサポートした形ですでにリリースされていましたが、今回は報酬のクリエイティブが追加されたことで画像と音声に対応可能となりました。 アポイタカラとは 「アポイタカラ」は、Youtuber/Vtuberが動画配信中にキャンペーンを企画して、特定の条件を達成した視聴者にトークンを配布することのできるマーケティング支援ツールです。 トークンはEthereum(イーサリアム)のERC721規格を利用しており、NFT(Non-Fungible Token)を活用したデジタルグッズの受け渡しが可能となります。 アポイタカラでは、現在以下の2種類のキャンペーンを企画できます。 ・全員参加型 視聴者が、配信中のライブチャットに何か書き込めば、報酬権利を獲得できます。最大配布人数を設定することもできます。その場合は早いもの順になります。 ・クイズ正解型 事前に配信者が答えを設定します。視聴者が同じ答えをライブチャットに書き込めれば正解となり報酬権利を獲得します。同じ人物が複数発言した場合は、最後の発言が採用されます。 アポイタカラのサービスモデル アポイタカラでは、配信者、視聴者、(デジタルグッズの)クリエイターの3者にそれぞれメリットが生まれるようなサービスモデルを展開しています。 ① 配信者はトークン(ERC721)にデジタル資産(画像、音声、動画など)を紐付けすることで、ライブ配信を見た人だけにデジタルグッズを配布し、視聴者とのエンゲージを強められます。 ② 視聴者は、推しの配信者のグッズを収集できるとともに、そのデジタルグッズを視聴者間で取引することが可能です。 ③ クリエイターは、様々なデジタルグッズを配信者に提供できます。トークンには著作者情報が刻まれているため、取引が行われた時の収益配分を受けることができます。 これらのサービスは全て無料で利用することができます。 革新的なサービスですが、報酬を受け取るにはアポイタカラのサイト内で、自身のYoutubeアカウントの他に、Ethereumのアカウント登録または簡易ウォレットの作成が必要なことに注意が必要です。 Ethereum(イーサリアム) ERC721の特徴は? ERC20やERC223との違いを徹底比較! 記事ソース:PRTIMES, アポイタカラ

ニュース
2019/03/31Ripple(リップル)とForteがゲーム市場向けの大型ファンドをローンチ
分散型台帳技術(DLT)のインフラを開発するRipple(リップル)とクリプトスタートアップのForteが、XRPをゲーム市場に導入することを目的とした1億ドル規模のファンドを設立したことがわかりました。 リップルと提携を結んでいるスタートアップ・Forteは、当ファンドの運用に関してすでに40社以上のゲームデベロッパーと話を進めているといいます。 ForteとRippleの共同ファンドは今年3月上旬に設立された。 交渉の多くは新たにゲームを開発するといったものではなく、すでにユーザーを抱えているプロダクトにブロックチェーン技術を活用したアイテム管理などの要素を加えるというもののようです。 同社はInterledgerプロトコルベースの非代替型トークン(NFT)をゲーム内アイテムに応用することで、ユーザーに「アイテムを所有している感覚」を与え、さらにXRPを介してアイテムの売買などをできるようにするといいます。 Forteはさらに今後、イーサリアムやEOS、TRONなどの他のプラットフォームとの協力も視野に入れて、ブロックチェーン技術とゲーミング市場の融合を推進していくようです。 DAppsゲームにおけるアプリストアを目指すプラットフォーム『Dapp.com』 とは? CEO Kyle Lu氏 独占インタビュー 記事ソース: Modern Consensus

イベント
2019/03/30Paris Blockchain Week Summitが4月16・17日にフランス・パリにて開催!
暗号通貨の普及が進むフランスの首都・パリで、参加者1500人・スピーカー100人以上が集まる大型カンファレンス「Paris Blockchain Week Summit」が4月16・17日に開催されます。 当カンファレンスでは有名なブロックチェーンプロジェクトの重役や、EU議会・調査機関関係者、さらにはSWIFTなど分散型台帳技術に関連する業界の企業も参加することになっています。 プレゼン・パネルの題目は「技術」「規制」「投資」「ビジネス」の4種類が設けられており、それぞれの分野でエキスパートが登壇する予定です。 カンファレンス公式サイトはコチラ 今回のカンファレンスの見どころは? Paris Blockchain Week Summitのステージイベントは、有名企業やEU関係者100人以上のプレゼンテーションおよびパネルディスカッションによって構成されています。 また、トピックも今話題の「STO(セキュリティトークンオファリング)」から「ゼロ知識証明」「非代替型トークン(NFT)」「シャーディング」などといった技術の話まで全て網羅しています。 主な登壇者を紹介! インフラ・プラットフォーム Marjan Delatinne (Ripple/リップル) Robert Wiecko (DASH, COO) Jack Gavigan (ZCash, COO) Dominik Schiener (IOTA, 共同創設者) Kelcey Gosserand (IBM) Patrick Dai (Qtum, CEO) Jordan Fried (Hedera Hashgraph) Max Kantelia (Zilliqa, 共同創設者) Arthur Breitman (Tezos, 共同創設者) 取引所・アセットマネージャー Wei Zhou (Binance, CFO) Andrew Robinson (Coinbase) Andy Cheung (OKEx, COO) Yoni Assia (eToro, CEO) Will Harborne (Ethfinex) Edward Moncada (Blockfolio, CEO) Brian Norton (MyEtherWallet, COO) EU・フランス政府・研究機関 Bruno Le Maire (フランス経済金融大臣) Caroline Malcom (OECD) 関連業界の企業 Leonard Schrank (SWIFT, 前CEO) Pauline Adam-Kalfon (PwC) プラットフォーム系プロジェクトからはRippleやDASH、ZCash、IOTAなどの有名どころに加え、Stellarベースのプロダクトを展開するIBMなどが参加します。 取引所はヨーロッパに拠点を持つBinanceやOKEx、eToroなどが参加するほか、欧米両方で大きなシェアを誇るCoinbaseなども来場します。 その他には、フランス政府から経済金融大臣、さらにはOECDやブロックチェーン推進事業に大きなリソースをさいているPwCなどの名前も挙がっています。 さらに面白いのが、Rippleと金融インフラの王座を争うSWIFTの前CEOも当カンファレンスに参加する点です。アジェンダに二者が対面しそうなトピックはありませんが、それでも要注目なのは間違いなしでしょう。 注目のステージイベントを紹介! 技術 ゼロ知識証明 - 単純なプライバシー保護以外への応用方法 IoT - ヒトのためのウォレットとモノのためのウォレット 公開・秘密鍵マネジメント 非代替型トークン(NFT)について 規制 セキュリティトークンオファリング(STO)について 自主規制 - 取引所とセカンダリ市場のプレイヤーへのソリューション 規制当局のジレンマ - 消費者保護とイノベーションの推進 法執行機関とKYC/AML 投資 ヨーロッパにおけるデジタル資産市場のインフラ作り 分散型機関への投資 ステーブルコインの大流行について ビジネス ブロックチェーンはペイメントの未来となるか? フランスのブロックチェーン事業の現状 フランス政府はICOを合法化しており、暗号資産取引などで発生する利益に対しても特別な納税ブラケットを設けています。 フランス・パリではビットコイン(BTC)などの暗号通貨でのショッピング決済を可能にするマーチャントを取り入れているお店などがたくさんあります。 また、街中のタバコ屋などでビットコインを購入することもできるほか、アートやチャリティーなどの分野でもビットコインでの寄付等を積極的に募っているものもあります。 当イベントはフランス経済金融庁からの支援も受けている。 カンファレンス公式サイトはコチラ

ニュース
2019/03/11Cosmos Hubのメインネットローンチまでのカウントダウンが開始される
クロスチェーン系のプロジェクトであるCosmosが、正式にメインネットのローンチまでのカウントダウンを開始しました。 ローンチに向けた公式サイトでは、カウントダウンまでの日付が表示されており、ローンチは日本時間で3月14日朝8時に予定されています。 2016年にホワイトペーパーがリリースされたCosmosは約3年間に渡り開発が行われ、今年の初旬からセキュリティ監査やテストネット(Game of Stakes)などの準備が進められていました。 先日完了した、『Collecting Genesis Transaction』では初期のバリデーターが選出され、残すはメインネットのローンチのみとなっています。 Cosmos Hubローンチに向けたマイルストーン Cosmos Hubのメインネットローンチ後の予定としては以下の3つのフェーズに分類されています; ローンチ後のネットワークの安定化 トークンの移動が解禁 IBC (Inter-Blockchain Communication)が利用可能に フェーズ1となる14日のメインネットローンチでは、ネットワークが不安定となることが予測されるため、CosmosのトークンであるAtomの移動を行うことができません。 フェーズ2では、オンチェーンガバナンス(Atomを利用したVoting)によりAtomの移動が解禁されるか否かがコミュニティの投票によって決定されます。 フェーズ3では、IBCが利用可能となり、ここで初めてその他のブロックチェーンが連結され、ユーザーはトークンやNFTなどをCosmos上で移動することができるようになります。 また、先日CosmosのAtomトークンの先物が韓国の取引所であるDFlowに上場しましたが、ローンチ後は1:1でスワップを行うと発表しています。 COSMOSのATOMトークンの先物が韓国新興取引所DFLOWに2月18日に上場 - CRYPTO TIMES

特集・コラム
2019/03/01TokenLab ブロックチェーンの技術に興味がある人たちが集まる場所(無料レポートリンク付き)
こんにちははるか先生です。今日もコラムを元気に書いています。 僕は他にも寄稿をしている 最近、クリプトタイムズ以外にトークンラボへの寄稿も行なっている。 まず言っておきたい。クリプトタイムズとトークンラボは競合するメディアではなく、読者層やビジネスモデルが大きく異なっていると信じている。この寄稿が認められて皆が読んでいれば間違えないだろう。クリプトタイムズの編集さんがOK出したのだから(笑) 大まかに僕の中ではクリプトタイムズではライター、トークンラボではリサーチャーとして関係をもっている。 クリプトタイムズはおおむねニュースを中心としたメディアとしての存在意義だと認識。比較的ニュース性のある題材を持ってきてコラムを書いているのだ。 トピックスも自由に決めさせていただいているので、そのトピックスをニュースから少し掘り下げて、私見であったり独自のテクニックなどを付加してクリプトタイムズには寄稿しているわけ。 一方、トークンラボについて。こちらは仮想通貨、ブロックチェーンのリサーチコミュニティーとまとめていいだろうか。論文みたいな形式で比較的ネチネチと書いている ブロックチェーンの技術、プロトコル、新しいビジネスモデル的なところに興味がある方にとっては面白い場所になるかもしれない。 トークンラボでは、他のガチ勢も興味があると思われることをプロトコルの細かいところも含めて詳細に調査、レポートする。万人に理解してもらうことは若干捨てている。 トークンラボ どんなコミュニティー? 実はEthereumのコミュニティーが使っているシステムと同じものを持ってきている。掲示板の少しオシャレになった感じのもの。 全てのやりとりの基本はレポートベースとなる。多くのレポートが主催者のCoffee Timesさんやindiviさん、そして仮想通貨の技術が好きなメンバーから投稿される。 それぞれのメンバーは幅広い素養を持った方から構成されているため、いつもバラエティーに富んだレポートが掲載されている。SNSベースのシステムより個人的には軽くて交換がモテる。フォローとか気の利いた通知はあまりありませんが。 それぞれのレポートを中心にディスカッションを行なっていきます。ただ、発言しないといけない雰囲気もないので、ロム専だからといって特に居心地が悪くなりこともない。 取り上げられている題材の一部を少し紹介。例えば、最近脚光を浴びているMInbleWinbleについて、一歩踏み込んだ題材を取り上げた論文が主となっている。 こちらで紹介したものは会員になると読める論文を持ってきた。MinbleWinble関係だとこちらの論文がお試しで読める。雰囲気を掴んでいただけるかな。 BeamやGrinはMoneroやZcashに勝てるのか - TokenLab 無料で読めてお得なものを選んでみました。その他、BEAMにはアドレスが無いってしっていますか?でもちゃんと送金できます。その仕組みついて議論した論文などもあり、様に一歩進んだやりとりがなされています。ちょっと興味わきませんか? 設立の背景 ビットコインをSatoshi Nakamoto が考案、発明したのは2009年のことであり、たったの10年前のことである。このビットコインが、ブロックチェーンの始まりでもあり孵化装置ともなっている そこからこの10年で、ブロックチェーンならびに仮想通貨は実用に耐えうるべく想像を絶する進化をしている。 冗談抜きで、世界の頭のいい人たちが、よってたかって新しいプロトコルや持続可能な報酬モデルなどを考案して実際にプロトコルを作り上げていっている。 これは、インターネット黎明期の状況と酷似していて、いまはインターネットも比較的安定成長しているけれども黎明期には、覇権を取っている TCP/IP以外の方式も多く提案がされ、バチバチ覇権争いをしていた。 そういった、激動の時代の波を掴んでいくのは、とても労力がかかる。大好きな人たちはこの波を追っている。 トークンラボはブロックチェーンの技術周りをずっと追っている二人の方が設立したリサーチ組織。Twitterでも比較的発言の多い方なので聞いたことある方は多いかもしれない。coffee timesさんとindiviさん。Twitterでみたことありませんか? ターゲットは仮想通貨のベースを理解し、さらに技術的や報酬アルゴリズムの魅惑の世界に入っていきたい人がターゲットである。 下記はトークンラボ公式サイトの言葉である。 特に「基礎は何となく分かった。更に一歩踏み込んだ情報を追っていきたいが、ここからの情報収集コストが高すぎる。過度に技術的な情報を深追いする時間とエネルギーはないが概観はしておきたい」という方をメインターゲットにしている。 公開限定が設定されたサイトに各有志が投稿した論文が掲載されその論文に対するコメントや質疑応答が行える。システム自体はEthereumのコミュニティーが使用しているものと同じシステムを持ってきている。SNSをベースとしたものより軽くまた使いやすい。 会費について 月額: 4,980円となっています。この論文の内容に対しての金額としては特に異論はない金額だと考えている。 もしあなたが、技術的、思想的なレポートをかけるのであればおすすめの方法があry。 トークンラボはリサーチャーとして寄稿を受け付けている。その寄稿論文に対しては金銭的な報酬か会費として還元してもらえる。ここで正確な数字はお話できませんが、会費として還元してもらうことにより無償で他の優れた論文を読み漁れる。 ナレッジやリサーチの労力を提供するのか金銭をもって対価を示すのかが選べるようになっている。 私も論文を2本ほど寄稿をさせてもらった。このレベルでの論文は日本国内では無償で出回ってないものだと自負している。また3本目も現在執筆中。これも日本では無償でこの内容を提供している方は知らない情報を独自調査してまとめている。 NFT(Non-Fungible Token)の基礎と現状 DID(DECENTRALIZED IDENTIFICATION(DID)の概要 DIDについては極端に日本国内での情報も限定されているので、初めての人でもわかるような記事をおいおい自分のサイトかクリプトタイムズ様に寄稿しようと思っている。個人的にはDIDは熱い分野の一つだと思っている。 最後に 今回の記事は特にTokenLabに入った方がいいよとゴリ押しする意図はありません。でも良質な情報ソースは知っておいて損はありません。あなたが企業で仕事をするのであればこういったアウトソース先は知っておいて損はないでしょう。企業向けのプランについてはぜTokenLabにお問い合わせください。 TokenLab公式サイト https://blog.token-lab.org/ TokenLabレポートカタログ http://docs.token-lab.org/ ではまた会いましょう。 ちゃんとはるか先生をフォローしてね。
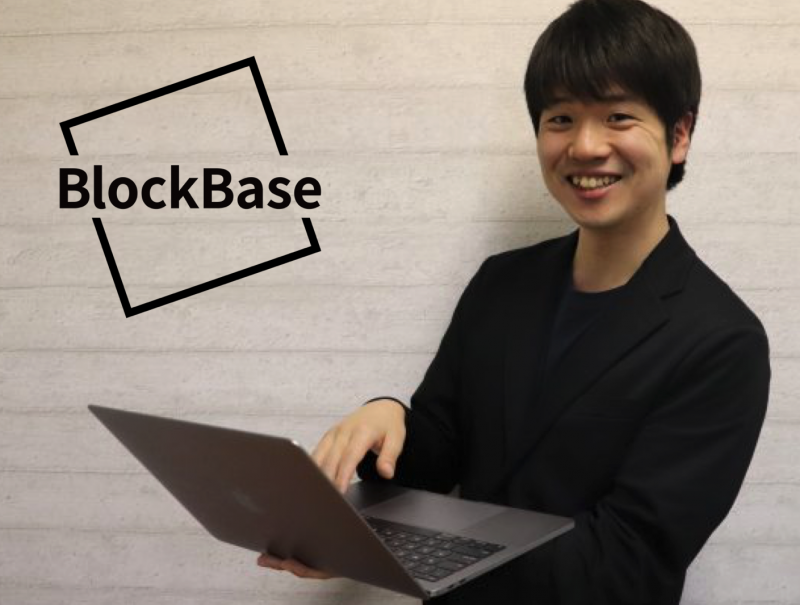
インタビュー
2019/02/23ブロックチェーン開発の良さはシンプルなところ。BlockBase 真木大樹がブロックチェーンを通じて目指す未来とは
2018年9月に設立し、主にブロックチェーンの導入コンサルを請け負いながら、自身たちでプロダクト開発も行なっている株式会社BlockBase。 BlockBaseは家入一真氏率いるNOWからの資金調達や、海外企業ORIGINとの提携、NFTマーケットプレイスである『bazaaar』のリリース発表などと非常に多くの話題が上がりました。今回は、CEOである真木大樹(さなぎたいじゅ)さんにお話を伺いました。 仮説検証を繰り返し、アウトプットを多く行うことでブロックチェーン業界でも一躍有名である真木さんのエンジニアとしてのリアルな話に迫っています。 今回のインタビューは2019年3月21日から23日にかけて開催される金沢工業大学主催・NEO Global Development協賛のブロックチェーンハッカソンの企画のもと実施しています。ハッカソンに参加する学生やエンジニアの皆さんに、先輩ブロックチェーンエンジニアの体験談などのリアルな話を届けていきます。 BlockBase社について 英首相、作家のウィンストン・チャーチルの言葉「Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.」をビジョンに掲げ、ブロックチェーン関連技術のコンサルティング業務、同関連技術を活用したプロダクトの企画・開発を事業ドメインとして、2018年9月に設立。 日本初のNFTマッチングプラットフォームであるbazaaarを2019年1月に公開、注目を集めている。また、ERC-725 ALLIANCE の加盟メンバー。 BlockBase CEOの真木さんはTwitterでオオキマキ名義でも活動中。 BlockBase 公式HP CEO 真木大樹 Twitter - ookimaki | Virtual Developer ブロックチェーンエンジニアとしてのキャリア -- 今回はよろしくお願いいたします。最初に真木さんの簡単な自己紹介とブロックチェーン業界に携わることになったきっかけを教えて下さい。 真木:こんにちは。こちらこそ、よろしくお願いいたします。BlockBaseのCEOの真木です。ブロックチェーンに携わるまでは、外資系のSIerでパッケージの導入コンサルを行っていて、当時からお堅めなクライアントと要件整理や設計開発など幅広くやっていました。もともとブロックチェーンに携わっていたわけではないのですが、副業として2018年2月ごろから仮想通貨に投資したのがブロックチェーンとの出会いです。 -- ちょうど取引所がハッキングされたという事件の直後なんですね。もう少し早くからブロックチェーンに携わっていたものだと思っていました。 そうですね。本当にタイミングとしては、すごい時期に参入しました(笑) 当時は市場そのものが、全体的にダウントレンドでした。そのとき思ったのは、コミュニティを盛り上げることが価値にもつながるのでは?と考えて、ブロックチェーン開発をはじめるようになりました。なので、ブロックチェーンの開発を本格的に始めたのが2018年4月になります。そこからCrypto ZombieなどのサービスでSolidityの学習に取り掛かりました。その後に何個か自作のdAppsをリリースしたりする中で楽しさを感じたことがきっかけで、本格的にブロックチェーン開発を始めました。 -- Solidityの学習にすぐ入れたということは、元々コードを書いていたりなど、エンジニアの経験があったんでしょうか? 真木:前職ではエンジニア職ではなく、会社の新人研修でJavaScriptを学んだことがあるくらいでした。業務もマネージャーという立場だったので、自分で開発をするということはありませんでした。 -- そこから、数々のプロダクトやDAppsを複数作ってきて、ブロックチェーンに触れて見た経験の中で何か気付きみたいなこととかはありましたか? 真木:よく色んな人が誤解していると思うんですが、ブロックチェーンは複雑だというイメージがありますよね。私は、ブロックチェーンは実際にはシンプルだと思っていて、それがブロックチェーンの良さだと思います。P2Pで取引が行われスマートコントラクトもデプロイさえすれば動くブロックチェーンはシンプルだと思っています。 -- ブロックチェーンはシンプルであるとこれは実装してみないと分かりづらいことですね。因みに真木さんはブロックチェーン開発の学習はどのように行っていたのでしょうか? 真木:私はEthereumのSolidityから学習をはじめましたが、Ethereumは学習コストが低くとても助かりました。というのも、Ethereumのコミュニティは国内外問わず盛んですし、Solidity関連のドキュメントやリファレンスも豊富でした。躓いても、すでにStackOverFlowなどでも同じ内容がありました。ほとんどの躓きは先人たちが記録に残していたので、開発の学習は非常にしやすかったです。 BlockBase株式会社の設立とその舞台裏 -- ブロックチェーンエンジニアというと現在だと、個人で受託をやっているようなフリーランスの人も多いですが、会社としてBlockBaseを設立したきっかけは何だったのでしょうか? 真木:会社を設立するまではフリーランスとしてブロックチェーンの受託開発をしていました。しかし、その中で言われたものをただ作るだけでなく、自分の思想を持った上でそれを実現できるエンジニアになりたい思い始めました。そのためにはフリーランスでは限界があり、クライアントと話しながら様々なものを実装していく「箱」として会社を設立しました。ですので、BlockBaseの事業としてブロックチェーン導入のコンサルティングを行っています。 -- 確かにフリーランスと会社ではできることの範囲は変わってきますよね。コンサルティング事業でのクライアントはどういった企業が多いのでしょうか? 真木:実は、クライアントの業界はあまり絞っていません。最近だとHR系や医療系が多いですが、これから業界の幅をより広げていこうと思っています。特に、変わりつつあるブロックチェーン・仮想通貨まわりの法整備の流れも見つつ、技術とビジネスの両軸でコンサルを行うことも心がけています。 -- クライアントがブロックチェーンを導入したいという要望は様々だと思うのですが、例えば、業界やクライアントによって導入するチェーンの選定はどうしているのでしょうか 真木:クライアントによってチェーン選択をすることももちろんあります。ただ、導入においてはEthereumでの開発が、ドキュメントやツールがそろっているということで一番やりやすいと感じています。EOSは確かに送金が速いですがガスやリソースに気を配らなくてはいけません。NEOはスマートコントラクトのデプロイに数十万円要する一方で、送金手数料は無料であるというメリットがあります。また、例えばNEOだとゲームのようにチェーンごとに得意・不得意な分野があるので、それに合わせる必要があると思って選定をしています。 自社プロダクト開発の方向性 -- BlockBaseはコンサルティング事業はもちろん、最近発表されたbazaaarなど自社プロダクトのイメージも強いと思います。自社でのプロダクト開発に関してはどのような考えで作っているのでしょうか 真木:私たちは「仮説があればそれを検証する」というのが行動の基本になります。その検証を自分たちでやるかクライアントのところでやるか、という違いになります。今回のbazaaarですと、仮想通貨まわりのフワッとしている法律解釈を実際に開発することで整理してみることが動機でした。bazaaarにはゲームユーザーの方々から良いコメントをもらっていて、ユーザーのみなさんには大変感謝しています。 日本初のブロックチェーンを使ったNFT のマッチングプラットフォーム"bazaaar" - CRYPTO TIMES -- 確かにプロダクトを開発することで見えてくるものは多そうですね。bazaaarがマッチングを可能にしているNFTは現在だと、ゲームでの活用が多い印象ですが、ゲーム以外のジャンルでの展開はあるのでしょうか? 真木:これからコンテンツ全体へNFTが使用されていき、法的な整備が整っていけばそこに入っていくプレーヤーが増えていくと思っています。少しずつデジタルコンテンツがNFTに移っていき、その交換ができるプラットフォームも増えていくと思っています。その中でbazaaarを使って業界全体を盛り上げていければと感じていますね。 -- 業界を盛り上げるというと、話題が変わりますが、ORIGINのような海外企業との提携を昨年発表したと思いますが、どういう流れで提携にいたり、どういうことを一緒にやっていくのでしょうか? 真木:ORIGINとの話を先にさせていただきますね。HR系のクライアントとのお仕事をさせていただいた際に、パブリックなネットワークを作って個人評価システムを作りたいという声がありました。個人評価システムにはERC725トークンの相性がいいと思い、実際にいくつかプロダクトを出していたORIGINに注目しました。そのなかでORIGINのチームメンバーにアドバイスをいただき、そこから協力をしています。ERC725に興味を持っている人は多く、その中でブロックチェーン×アイデンティティという分野で様々な機関と協力していきたいと思っています。 海外企業ORIGINとの提携を2018年11月に発表済み -- 海外の事例を日本に展開しているということは、ERC-725の事例を日本から海外に向けて発信していったりもしていくのでしょうか? 真木:海外の企業やコミュニティから学ばせてもらっているという意識が強く、その中で私たちからも技術面でこれから貢献できればと思っています。コンサルティングをやりつつも、目に見えづらい技術的な部分も地道に行っています。 ブロックチェーンへの思い -- ここまで会社としての取り組みについて聞かせていただきましたが、個人としてブロックチェーン業界に携わってきて、良かったところ、苦労したなと思ったことに関して教えていただけますか? 真木:実際、ブロックチェーンのプロダクトは動かすまでのハードルは高いと思います。ハッカソンなどにも参加すると、「これ本当に動くのかな」とか心配することもあるとは思います。しかし、最初の一歩だけ踏み出せれば一気に勢いづくとも感じています。また、ブロックチェーン業界は変化が激しいため、キャッチアップが大変かつ軌道修正を必要とすることもありますが、その分長く続けれることが大事な分野とも思います。 -- 確かに変化が激しい業界に間違いないですね。そんなブロックチェーン業界で、BlockBaseや業界全体について今後の展望を教えてください。 真木:会社としては仮説をたくさん立ててそれを検証していきたいです。その中で多くの業界のクライアントと様々な価値が作れればと思います。その中で開発力もビジネス力も上げていきたいと思っています。会社の収益を考えつつも、いい意味で遊べる余力を付けていきたいと思っています。 業界全体としては、やはりブロックチェーンを金融的な側面から切り離すことが大事です。また、Web3.0的な考えをエンジニア以外の人たちにも広げることが重要だと思います。その中で同じ思想を持った人たちが多く参加していくかとは感じてますが、実際これに関しては私もはっきりとはわからないので、これから模索していきたいです。 KITハッカソンに関して --これからのBlockBaseさんの活躍も同じ業界の人間として楽しみにしております。ところで、今回の記事はKITハッカソンに向けてですが、協賛であるNEOの開発や検証もしたことがあるのでしょうか? 真木:当初は「中国版イーサリアム」と言われていたNEOがどういった共通点を持っているのかが気になり調べてみました。結果としては、スマートコントラクトをどちらも搭載しているだけでNEOは「中国版イーサリアム」とは呼べないと思います。適用が向いている分野も違いますし、ガバナンスの方法なども異なります。 -- 確かに色々な記事でも「中国版イーサリアム」と言われていたものを見かけることは多かったですが、実際はそれぞれ異なるものですよね。NEOに関してエンジニアとしてはどのようなイメージをお持ちでしょうか? 真木:私がNEOについて学習し始めた当時はまだNEOの情報も少なく、日本語文献の作成に協力するなかで自分で情報を集めていく楽しさもありました。先程も軽く話したように、NEOはチェーンの特性上ゲームに向いており、運営もその方向性を向いているので非常に良いと思います。 -- NEOの日本語文献作成にも関わるなど積極的に情報発信にも参加されているのですね。最後に、これからハッカソンに参加する学生やブロックチェーン業界に入る人たちに向けたメッセージをお願いします。 真木:これからはブロックチェーンのそれっぽさを求めていくフェーズは終わり、ブロックチェーンの本質について考えていく必要があると思います。どのような価値があるかをしっかり考えるようにして、分かったフリはしないほうがいいかと思います。現状の技術力に満足しないで、その中で時には自分を否定して改善案を考えていくようなことも必要かと思っています。 終わりに 最初は仮想通貨投資からブロックチェーンに触れたという真木さん。自身で色々と学習していくうちにその魅力に取り憑かれていく様子が、今回のインタビューでも感じ取れたと思います。そんな、真木さんのエンジニアとしての体験談やブロックチェーンに関しての意見などを聞くことができた非常に良い機会となったのではないでしょうか。 今回、インタビュー中でも触れたKITハッカソンは、3月21〜23日にKIT(金沢工業大学)が主催しNEO Global Development協賛するブロックチェーンハッカソンです。 「目に見えない資産をデジタルにどう伝えるか」をテーマとして開催され、事前学習としてNEOやIOST、Uniqys Kitのハンズオンも実施されます。興味のある方は是非とも下記ページをご参照ください。 ハッカソンの詳細はこちら インタビュー : アラタ , 文字書き起こし : フジオカ

ニュース
2019/02/20AWSで簡単にVeChainThorのブロックチェーンをデプロイできるように
2月18日、Amazon Web Service (AWS)がエンタープライズ向けに、ワンクリックでVeChainThorのブロックチェーンをデプロイすることを可能にするサービスを開始したことが発表されました。 VeChainのBlockchain as a Service (BaaS)のソリューションは、2016年に最初のローンチが行われています。 このソリューションでは、NFTやRFIDなどのチップやブロックチェーン、個人認証技術、IoT、クラウドコンピューティング他、従来のITサービスが利用されており、ブロックチェーン技術を利用した包括的な企業向けITソリューションが提供されています。 今回のAWSにおけるサービス開始の発表により、顧客はVeChainを利用した以下のような様々なサービス・メリットを享受することができます。 Amazon Elastic Computing Cloud (Amazon EC2)における、VeChainThorをデプロイすることによる、データのアップロードやスマコンのデプロイ。 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)によるデータ永続性の担保とコスト削減。Amazon Redshiftのデプロイにより、エンタープライズ顧客のデータ解析における効率が向上します。これは、企業のERPシステムとブロックチェーンシステムを接続し、標準化されたAPIを通じて恣意的にスマコンの呼び出しやデータのアップロードを行うことができることにより実現します。 Amazon EC2やElastic Load Balancing、Amazon Cloud Frontを利用した、ERPなどからの加工前データの収集。アプリケーションのバックエンドでは、AmazonRDSによりインターフェースを通してブロックチェーン上にデータの保管やアップロードが行われます。 VeChainはAWSの技術パートナーとして、AWS Partner Network (APN)に参加し、企業運営や技術開発、マーケティングのサポートを受けていくことも発表されています。 記事ソース:AWS Services Enable One-Click VeChainThor Blockchain Deployment for Enterprises












 有料記事
有料記事


