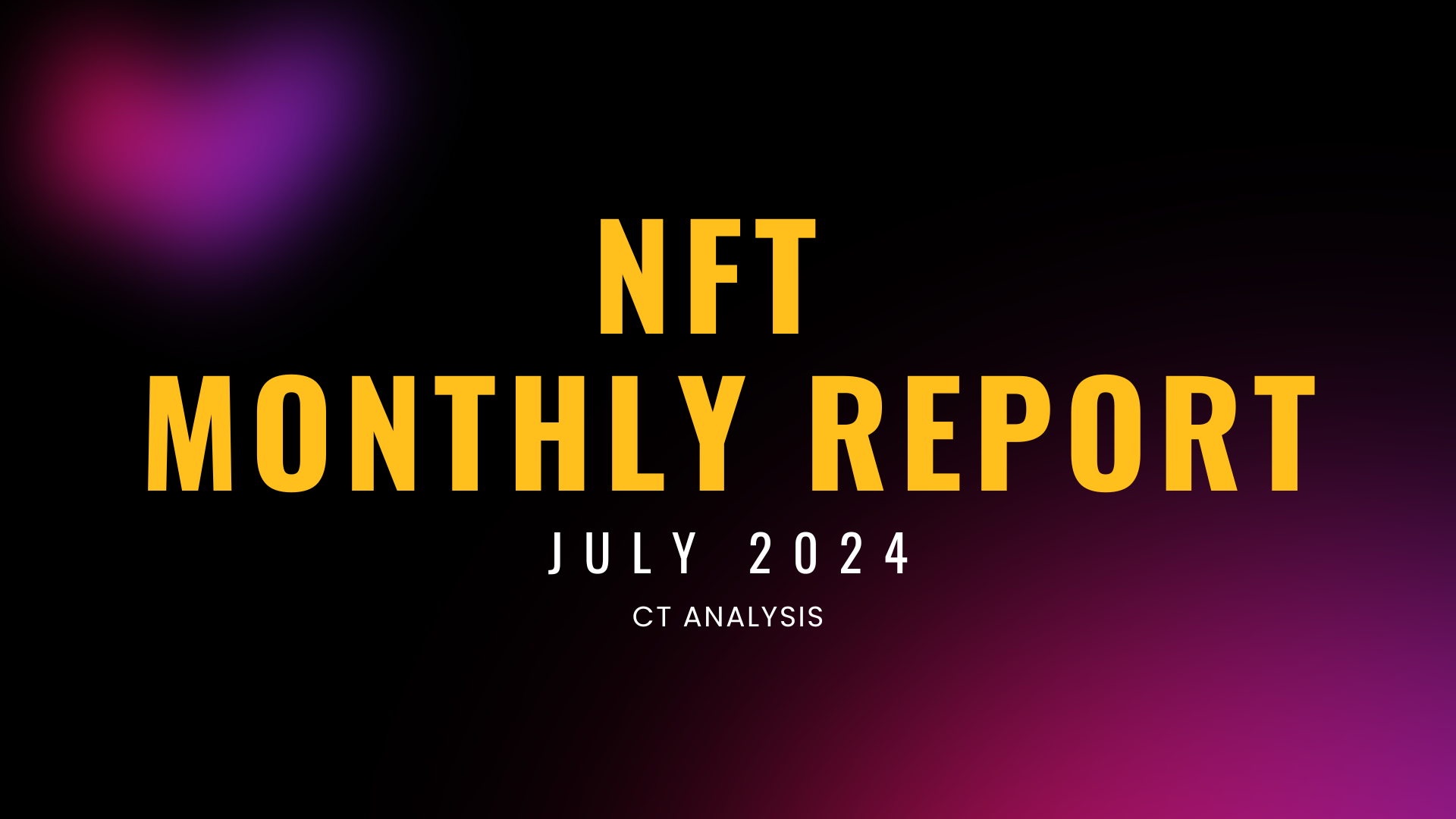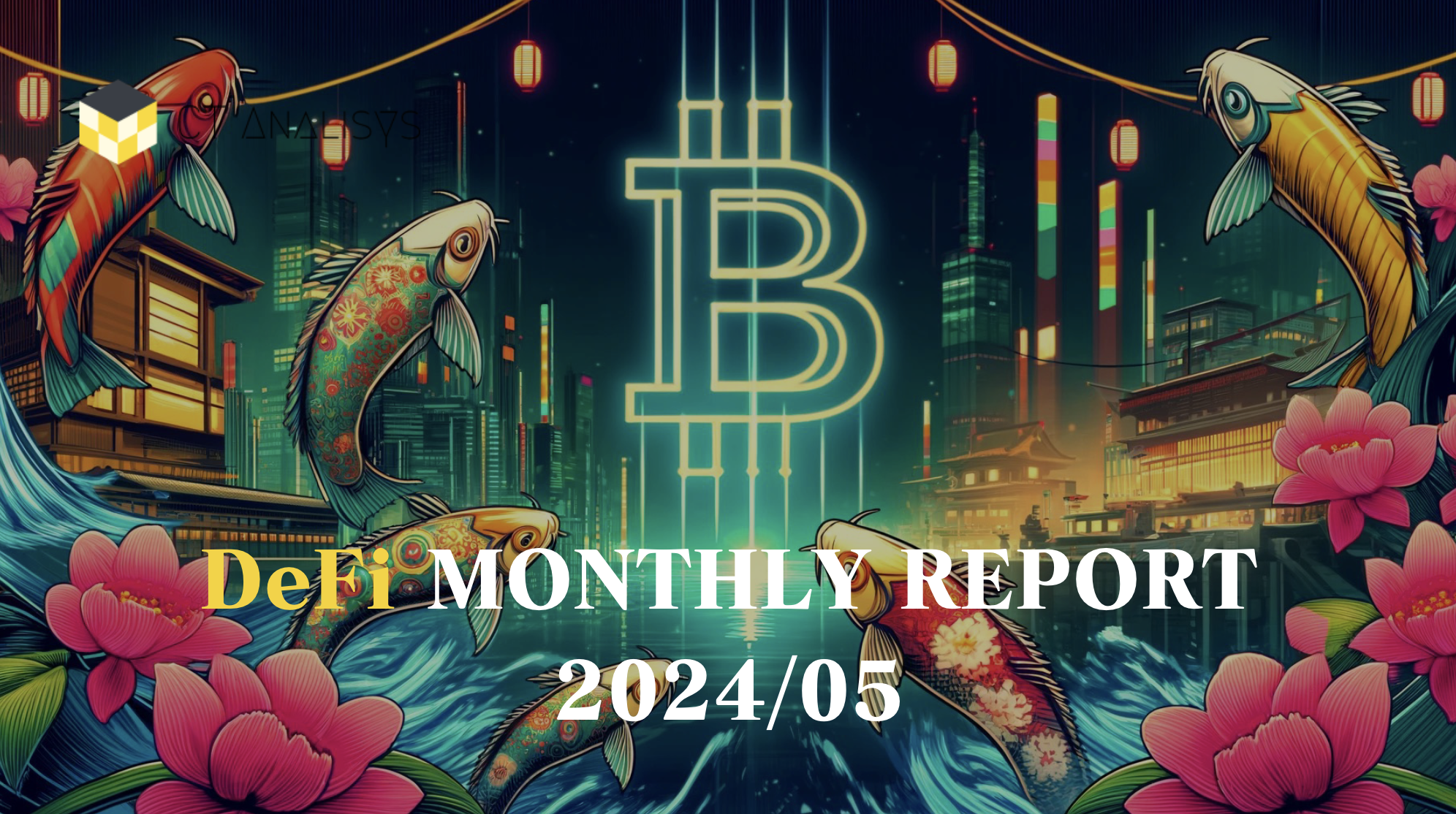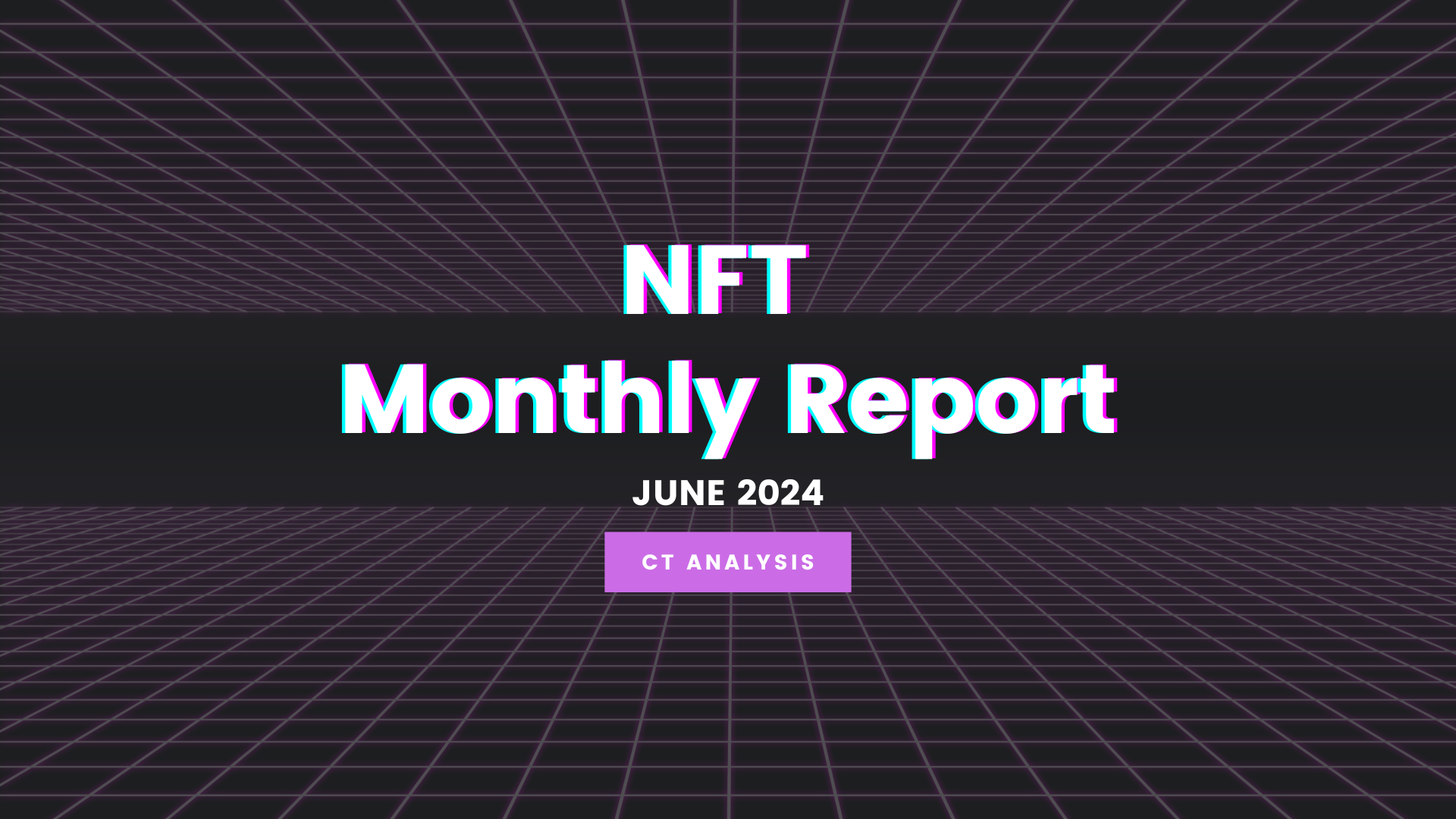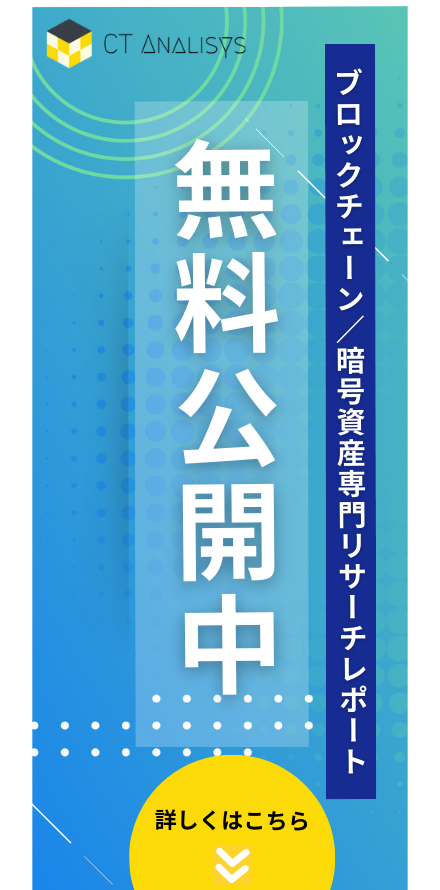仮想通貨のステーブルコインとは?種類や今後について解説
Daichi

仮想通貨ユーザーにとって必要不可欠な存在とも言えるステーブルコイン。
先日、EUやシンガポールでステーブルコインに関する制度をより明確化していくことが発表されるなど、その注目度はこれまで以上に増しています。
本記事ではそんなステーブルコインについて解説していくので是非最後までご覧ください。
この記事のポイント
・ステーブルコイン = 価格変動を抑えた仮想通貨
・ステーブルコインは実用性を持っている
・ステーブルコインの種類は4種類
・ステーブルコインにはメリットとデメリットがある
・今後の発展には法整備が重要
CRYPTO TIMESの公式Youtubeチャンネルでも、ステーブルコインについて取り上げているのでこちらも併せてご覧ください。
目次
ステーブルコインとは?=価格変動を抑えた仮想通貨

ステーブルコインとは、他の資産にペッグ(=紐付け/連動)されることでボラティリティ(=価格変動)が抑えられた仮想通貨です。
名前にもある「ステーブル(stable)」とは「安定した」という意味なので、まさにその意味する通りの特徴というわけですね。
ステーブルコインの発行者は、基本的にその価値と同額の資産(米ドルや金など)を担保として保有しなければなりません。
ステーブルコインの価格はその担保を裏付けに決定される仕組みであるため、価格の暴落などが起きにくく、より安定性に優れた設計となっています。
なぜステーブルコインが注目されるのか?

従来の仮想通貨の課題
ビットコインをはじめとする従来の仮想通貨は、その価値を裏付ける担保がないため価格変動が激しい(=ボラティリティが高い)という特徴があります。
仮想通貨の価格の暴落などがニュースに取り上げられることも少なくないので、なんとなく不安定なイメージを持つ方も多いことでしょう。
こうした不安定な特徴により、従来の仮想通貨は投機的な保有の傾向が強くなり、決済手段としてなどの「実用性」に欠けていると考えられてきました。
そこで考え出されたのが、より安定的かつ実用的な仮想通貨としてのステーブルコインだったのです。
ステーブルコインの「実用性」
従来の仮想通貨の不安定さという課題に対し、ステーブルコインは安定性に優れているという点は先にも簡単に触れました。
この安定性こそが、通貨としての「実用性」につながると考えられています。
価格の変動が激しくない(=ボラティリティが低い)通貨であれば、資産として長期保有もしやすく、決済手段としても利用しやすいと考えられます。
日常生活でも利用される米ドルや金を担保とすることで価格変動が抑えられるため、ステーブルコインはより安定性と実用性に優れた仮想通貨と考えられているのです。
4種類のステーブルコイン
ここからはステーブルコインの種類について解説します。
ステーブルコインは下記の2つの観点で、4つの種類に分類されます。
- 資産を担保にしているか
- どのような資産を担保にしているか
① 法定通貨担保型

引用:Tether
法定通貨担保型はその名の通り、実際に利用されている法定通貨(ドル、ユーロ、円など)を担保に発行されるステーブルコインです。
発行者はステーブルコインと同額の法定通貨を保有することが求められ、それによってステーブルコインの信頼性を維持しています。

一点、USDTを発行するTether社の準備金に関して、米国財務省短期証券がその多くを占めていることが分かっている点は留意しておく必要があります。
しかし、後述のステーブルコインと比較しその安定性から現在最も主流なステーブルコインとも言えます。
- 法定通貨担保型の代表的な例
- Tether(USDT)
- TrueUSD(TUSD)
- USD Coin(USDC)
- JPY Coin(JPYC)・・・1JPYC=1円として利用できる日本円ステーブルコイン
② 仮想通貨担保型

引用:MakerDAO
仮想通貨担保型もその名の通り、仮想通貨(ビットコインやイーサリアム)を担保に発行されるステーブルコインです。
仮想通貨はボラティリティ(価格変動性)が高いため、法定通貨担保型と比べると安定性や信頼性に欠けてしまいます。

- 仮想通貨担保型の代表的な例
③ 商品担保型(コモディティ型)

引用:Tether Gold
商品担保型(コモディティ型)は、金や原油などの現物の商品の価値を担保に発行されるステーブルコインです。
とくに金は経済が不安定な状況においてもその影響を受けにくく、価値が安定している資産のひとつとして知られています。
代表的なステーブルコインはTether Gold(XAUT)、Digix Gold(DGX)があります。
- 商品担保型の代表的な例
④ 無担保型(アルゴリズム型)

引用:Terra
無担保型(アルゴリズム型)は、通貨や商品による担保は行われず、アルゴリズムによって価格の安定を図る手法です。
この手法では、別途用意されたトークンの供給量をアルゴリズムによって自動調整することで、価格の変動を抑える仕組みとなっています。

- 仮想通貨担保型の代表的な例
TerraUSD(UST)は2022年5月のディペッグ騒動(後述)による価格暴落でも知られており、この一件で無担保型の信頼性に対する懸念は強まる傾向にあります。
【ステーブルコイン崩壊】今回のUST暴落は一体何だったのか?今後を考察
ステーブルコインの3つのメリット
ステーブルコインの特徴についてはすでに触れましたが、ここではステーブルコインのメリットをさらに細かく見ていきます。
ボラティリティが低く価格が安定する

ステーブルコインは法定通貨などの比較的安定した資産を裏付けに発行されるため、ボラティリティ(価格変動性)が低く、通貨の価格が安定しやすいという特徴があります。
そのため、決済手段など、日常的な実用性に優れると考えられます。
このような普及例はまだあまりないのが現状ですが、仮想通貨を法定通貨とする国の事例が増えてきているように、今後の発展次第では実現の可能性もあると言えるでしょう。
比較的安全な資産保有手段になる

前述の通り、ステーブルコインは暴落リスクが低いという特徴があります。
そのため、従来の仮想通貨に比べ、資産の保有手段としてもより安全性が高いと言えます。
また、資産保護・運用の観点からもポートフォリオに積極的に組み込むことを考えられるでしょう。
資産の一部が暴落した場合のリスクヘッジや、資産の避難先としても活用可能です。
また、今後の発展次第では、外貨預金に代わってステーブルコインによる預金などが普及する可能性もあるかもしれません。
低コストかつスピーディーな送金が可能

ステーブルコインは法定通貨に紐付いていますが、ブロックチェーン上で送金できます。
そのため、より低コストかつスピーディーな送金が可能です。
一方、クロスボーダー取引など国境を越える法定通貨の国際送金の場合、各国の決済システムの違いなどからより多くの時間や手数料を要してしまいます。
ステーブルコインを活用することで、より安価で迅速な国際送金が可能になります。
ステーブルコインの3つのデメリット
価格の安定性が注目されがちなステーブルコインですが、理解しておかなければいけないリスクも存在します。
セキュリティや詐欺のリスクはゼロではない

法定通貨などとの紐付けによって安心・安全のイメージが先行しがちなステーブルコインですが、ブロックチェーン上の仮想通貨であるという点では他と変わりはありません。
そのため、ハッキングなどのセキュリティリスクもあります。
また、担保となる資産の存在を謳いながらも、実際にはそのようなものはないという詐欺の可能性も考えられます。
セキュリティや詐欺に対しては他の仮想通貨と同じく対策・注意が必要です。
暴落するリスクがある(実例あり)

ステーブルコインは価格の安定性に定評があるとはいえ、暴落するリスクもゼロではありません。
上の画像は、2022年5月に米ドルに連動するステーブルコインであるUST(TerraUSD)の価格がディペッグ(=連動通貨との価格レートが乖離)する事態となり、結果的に暴落してしまった際のチャートです。
【ステーブルコイン崩壊】今回のUST暴落は一体何だったのか?今後を考察
ステーブルコインといえども暴落リスクはあると理解しておくことが必要であり、過信は禁物です。
各国当局による規制の可能性がある

前述の2022年5月のUST暴落などをふまえ、ステーブルコインの規制強化に関する議論が高まっています。
ステーブルコインはマネーロンダリングなどの犯罪に使用されるリスクも指摘されており、日本では2022年6月に世界に先駆けてステーブルコインを規制する法律が初めて成立しています。
2022年10月には金融安定理事会(FSB)がステーブルコインの脆弱性を指摘しつつ、規制指針の見直しを行うことを提案しました。
このように、現在世界中でステーブルコインの規制強化が進められていると言えます。
今後もし国際的に規制が強化された場合、ステーブルコインの新規上場の減少、ビジネスの撤退なども懸念されます。
もしそうなってしまえば、ステーブルコインの価値そのものが大きく下落してしまう可能性もあるでしょう。
ステーブルコインの今後
最後にステーブルコインの今後の将来性とリスクについて整理してみたいと思います。
将来性:法定通貨担保型を中心に決済手段として普及するか

ステーブルコインはボラティリティ(=価格変動性)が低く、価格が安定しやすいことから、投機的な側面が強い現在の仮想通貨市場において特徴的な存在だと言えます。
また、仮想通貨の特性上、低コストかつスピーディーな送金が可能であるため、とくに日常生活における決済手段としての普及が期待されます。
ただし、無担保型はUST暴落によりその信頼性が疑問視されているため、もし普及するとすればやはり法定通貨型が中心となると考えられます。
とはいえ、ステーブルコイン全体に対する規制強化の動きがあるため、普及が期待できるとすればその法整備の先となるのではないでしょうか。
リスク:進む規制強化の波で停滞か、はたまた衰退か

普及が期待される利点がありながらも、UST暴落などによって世界中でステーブルコインに対する規制強化の波があることを説明しました。
ステーブルコインの実用化には期待したいところですが、とはいえ実用化のためには先に法整備が必須となるでしょう。
今後は各国当局の監視も強化されるとすれば、新規上場などの停滞も考えられます。
また、規制強化や法整備の結果によっては市場からのビジネスの撤退を招く可能性もあり、そうなれば市場の停滞に留まらず、衰退につながってしまう恐れもあります。
いずれにせよ、今後のステーブルコインを取り巻く規制の動向に注目する必要があるでしょう。
まとめ
ステーブルコインには従来の仮想通貨の課題を克服する可能性があるものの、まだまだ発展途上のためその脆弱性が浮き彫りになることもあり、直近のUSTディペッグ騒動もそのひとつと言えます。
仮想通貨への規制が進められる中で、日本では世界に先駆けて初めての法整備が行われました。
実用化にはまだ遠いかもしれませんが、今後の国内外の法整備も含め、ステーブルコインの未来に注目していきましょう。
CT Analysis第20回レポート『ステーブルコインの概要と現状 動向調査レポート』














































 有料記事
有料記事