
プロジェクト
2018/06/10ゲーム内でマイニングができるゲーム「Hash Rush」の紹介
新しいdappsゲームがどんどん出てくる昨今ですが 今回は私、ゆっしが注目しているdappsゲームをご紹介させていただきます。 その名は「Hash Rush」!!! 今年の秋にリリース予定のゲームです。 さてさてこれはどんなゲームなんでしょうか!説明していきたいと思います! どんなゲーム? Hash Rushは「コミュニティ形成」「マイニング」「アイテム交換」の3つが大きな要素となっています。 ユーザーはオンラインで繋がっている他のユーザーと共にコミュニティを作り上げます。 コミュニティを襲ってくる敵も存在するので、色々な防衛策も練らねければいけません。 ユーザーはコミュニティの中でETH(イーサリアム)などの仮想通貨をマイニングしたり、アイテムを集めることができます。 そして集めたアイテムや通貨をP2P(ユーザー同士)で交換することが可能となります。 大人気ゲームのMinecraft(マインクラフト)のような感じですね。 鉄やダイアモンドを探す代わりに、イーサリアムなどの仮想通貨を掘り当てるような感じです。 全体の雰囲気を掴むためにデモ動画をご覧ください↓ https://www.youtube.com/watch?v=jE26UFTh0ok ※Hash Lushは去年ICOを行いRCというトークンを発行しており、このRCトークンはゲーム内での利用も可能なようです。 おすすめポイント グラフィック 先ほど動画を見ていただけた方は分かったと思いますがグラフィックがとても綺麗ですよね。 しかも球体を自由に移動できる3D構造となっており、これまでのDappsゲームにはあまりなかった形となっています。 Hash Lushのブログでプログラミングのソースコードも一部公開されています。 トランザクションで発生する手数料が無い Dappsゲームは、アイテム交換などをする際に手数料がかかってしまうことがあります。 しかし、Hash Rushでは独自の「Rush Network」というネットワークを使うことによってトランザクションにかかる手数料がゼロになります。 Rush Coin transactions in Hash Rush (game) will be handled by our own 'Rush Network' meaning that they will be instant and you will not have to pay gas. More details will be on our #steemit blog soon: https://t.co/qebTb3NCKN #cryptocurrency #gamedev #indiegames #blockchaingame pic.twitter.com/fCXEt0bPBr — Hash Rush (@PlayHashRush) May 16, 2018 このゲームの性質上、頻繁にアイテム交換やアイテム加工するので手数料がかからないのはとても嬉しいですよね。 開発状況を確認できる Hash Rushは現在開発中ですが、その開発状況をHPの記事などで知ることができます。 例えばこちらの記事ですが、キャラクターの家などの建築物のデザインに関してどのようにデザインされていったかが細かく記されています。 この記事ではメインキャラクターであるエルナックの家のデザイン作成の過程などが書かれていました。 また、このような解説記事だけではなく開発メンバーへのインタビュー記事や、誰でも参加ができるコンテストなども開催されており、コミュニティを盛り上げるための試みが多く行われています。 RCトークン Hash Rushは去年RCトークンを発行しICOを行っています。 ホワイトペパーによるとRCトークンはゲーム内で以下のことに利用できるようです ・施設の建設やアップグレード ・コロニーの拡大やアップグレード ・ユニットの購入とアップグレード ・仮想通貨の採掘 ・ユニットの動きを早める(作業の時間短縮) RCトークンをゲーム内で利用する場面が沢山ありそうな感じですね。 また、RCトークンは取引所で購入するだけではなくミッションクリアや他のプレイヤーとのアイテム交換などでゲットできるようです。 まとめ いかがだったでしょうか? マイニングを実際の「採掘する」という形でゲーム内で表現しているHash Rushはとても未来的でワクワクするゲームだと思います。 今年の11月にリリース予定なので興味が湧いた方はHPやDiscordなどで情報をチェックしておきましょう!!

プロジェクト
2018/05/13QuarkChain / QKC の特徴・競合比較まとめ!大注目ICOの将来性は?
QuarkChainはスケーラブルでセキュア、分散化されたプラットフォームを作るプロジェクトです。 記事作成時点でICOから10倍以上になっているZilliqaの競合ということもあり、将来性にも期待されています。 こちらのページでは、そんなQuarkChainの特徴やICO情報についてまとめています。 これを読めば、基本的な特徴からZilliqaとの違いまで、QuarkChainについてはバッチリです。 [toc] QuarkChainの概要を把握しよう QuarkChainの概要 通貨名/ティッカー QuarkChain(クォークチェーン)/QKC 創業者(CEO) Qi Zhou 主な提携先 Chihuo、PRIMASなど 特徴 スケーラブルなプラットフォーム 公式リンク Webサイト Twitter Telegram 日本公式Telegram Facebook Weibo github(ソースコード) ICO情報とトークンメトリクス QuarkChainのICO情報 WhiteList 2018/05/07 ~ 2018/05/21 ※抽選あり 規格 ERC20 支払い ETH 発行枚数 10,000,000,000 QKC 調達額 総額 20,000,000 USD PrivateSale 16,000,000 USD ICO 4,000,000 USD ICOレート 1 QKC = 0.00003 ETH QKCはメインネットver1.0(2018年Q4予定)公開までは、ERC-20トークンとなります。 QKCの用途は公開されていて、取引手数料の支払いやコミュニティ貢献者への報酬に利用されることになっています。 QuarkChainの抽選について QuarkChainのICOに参加する(WhiteListに通る)には、Telegramへの加入、Quizの回答ののち、抽選に参加する必要があります。 Telegram参加時期によるポイント、Quizのポイント、その他のプロジェクトへの貢献度に応じてポイントがつけられ、合計得点が60点以上の人に、点数に応じた枚数の抽選権が配られます。その後抽選に当たればICOに参加することができます。 QuarkChainの5つの特徴を紹介!QuarkChainを利用するメリットや将来性は? QuarkChainの特徴について解説しています。 まずはQuarkChainのがどんなものなのか、どんな問題を解決できるのかを知っておきましょう。 dAppsやスマートコントラクトを構築できるプラットフォーム QuarkChainはブロックチェーンのスケーラブルなプラットフォームです。 イーサリアムやNEOのように、QuarkChain上でdAppsを作ったりスマートコントラクトを実装したりすることができます。 スケーラビリティ問題に対応できるイーサリアムと考えるとわかりやすいです。 毎秒約1,000,000のトランザクションを処理できる スケーラビリティ問題解決に関係してくる特徴です。 公式サイトの画像からわかるように、QuarkChainのTPSはBitcoin、Ethereumよりもはるかに大きくなっています。 TPSとは トランザクション・パー・セカンドの頭文字をとったものです。1秒当たりに処理できるトランザクション数を示しています。 VISAは世界で最も利用されている決済サービスです。 このように比較すると、QuarkChainが対応できるTPSどれだけすごいかがよくわかりますね。 イーサリアムのdAppsなどを簡単にQuarkChain上に移行できる QuarkChainが注目されている理由の一つです。 すでにイーサリアム上でdAppsとして稼働しているアプリなどを、簡単にQuarkChain上に移し替えることができます。 これはQuarkChainがEVMのスマートコントラクトに対応していることが理由です。 EVMのスマートコントラクトとは イーサリアムのトランザクションはEVM(イーサリアム仮想マシン)を介して行われます。QuarkChain内にイーサリアムの通訳がいるイメージです。 弱いパワーのマイナーも報酬を得られる(ネットワークの分散化に役立つ) 多くの仮想通貨のマイニングはPoWという方式で、これではハッシュパワー(計算力)が小さいマイナーは報酬を獲得しづらくなります。 PoWとは 計算を一番早く完了させたマイナーだけが報酬を獲得できるマイニングの仕組みです。計算がより早くできる、大きなハッシュパワーのマイナーが有利になります。 PoWの仕組みのために、マイナーはみんなで力を合わせてマイニングをし、獲得した報酬を分割します。(マイニングプールを作る) しかし、これは分散化という観点では良いことではありません。 1つのマイニングプールの権力が大きくなるからです。 マイニングプールの問題点 ブロックチェーンは本来、みんなでネットワークを監視して健全性を保つものです。マイニングプールにより、1人が持つ力が大きくなると、ネットワークの健全性が失われやすくなります。 でもQuarkChainではハッシュパワーが小さいマイナーも、きちんと報酬が得られるような仕組みになっています。 これは、QuarkChainのマイニング報酬の仕組みが、ビットコインやイーサリアムなどのとは少し違うからです。 QuarkChainでは、ハッシュパワーに対する報酬の割合(難易度)を自分で決めることができます。 難易度が低いマイニングを選択することで、ハッシュパワーの大きいマイナーと競合するのを避けることができ、報酬を獲得することができるようになるのです。 わかりやすい例 マイニング報酬 … 100 必要ハッシュ(難易度) … 100 マイニング報酬 … 1500 必要ハッシュ(難易度) … 1000 マイニング報酬 … 20000 必要ハッシュ(難易度) … 10000 ※ここで紹介しているレートはランダムです。 これなら弱いハッシュしのマイナーも報酬を獲得できる。つまり、マイナーが分散化できる! 公式ホワイトペーパーでは、「ハッシュという通貨でマイニング報酬を買うことができる。」という表現がされています。 さっちゃん レートの仕組みは「まとめ買いでお得になる」みたいなイメージですね。 QuarkChainの仕組みを活用することで、結果的にマイナーの分散化にもつながり、より分散化された健全なネットワークが成立します。 クロスチェーンを実装できる QuarkChainではクロスチェーンを実装することができます。 具体的にいうと、"取引所を介さないQKCとビットコインなどの交換"ができるようになります。 クロスチェーンとは ビットコインやイーサリアム、NEOなどの互いに異なるチェーンとの直接取引を可能にする技術です スケーラブルなQuarkChainを支える技術を紹介! QuarkChainの5つの特徴では、QuarkChainは高分散化・スケーラブル・セキュアなプラットフォームといわれる特徴について解説してきました。 そんなQuarkChainを支える技術について紹介していきます。 QuarkChainはコード評価も高い 海外のコードレビューサイトなどではQuarkChainのコード評価(コードの質の評価)がかなり高いです。英語ですがQuarkChain Code Review – Deep Diveの「QuarkChain Code Review Conclusion」のパートを見ただけでも高評価なことがわかります。 シャーディング技術(2レイヤー構造) QuarkChainはシャーディング技術を採用していて、ブロックチェーンの処理を分割することができます。 これによって処理速度を上げることが可能です。 チェーン名 ブロック名 検証時間 主な役割 ルートチェーン層 (第2層) ルートチェーン ルートブロック 数分以内 検証 シャーディング層 (第1層) シャード マイナーブロック 数秒 元帳 シャードレイヤー(第1層) これがQuarkChainのスケーラビリティの秘密です。 シャードレイヤーのポイント トランザクションのすべてではなく"一部を"処理することで処理時間が短縮できる マイナーブロックは増減可能なのでトランザクションが増えても対応できる シャード(マイナーブロック)ではトランザクションの一部が処理されるため、すべてを処理するのに比べて処理速度が向上します。 また、このマイナーブロックの数は増やすことができるので、トランザクションが増えても全体の処理速度は落ちません。 わかりやすい例 道路の拡張工事をイメージすると分かりやすいです。車線(マイナーブロック)を増やすことで、車はよりスムーズに流れます。(トランザクションが増えても問題ありません。) ルートチェーン(第2層) ルートチェーンの役割は第1層のマイナーブロック(各シャード)を束ねて、QuarkChainの全体のネットワークとして構築していくことです。 ルートチェーンには承認されたマイナーブロックの一部(ブロックヘッダ)が格納されていきます。 ここではトランザクションの処理はせず、ひたすらに承認された第1層のブロックを束ねていきます。 このように処理とネットワーク全体の確認を分割することで、トランザクションが増えてもQuarkChainは安定的に稼働することが可能です。 マイニングではルートチェーン(第2層)に50%以上のハッシュが割り当てられる マイニングのハッシュパワーは、第1層と第2層で分割されます。 このときのハッシュパワーの割り当ては、50%以上はルートチェーン(第2層)、残りを全てのシャード(第1層)で分割です。 これにより、悪意のあるマイナーがネットワークを支配するには、最低でも全体の25%のハッシュパワーを持つ必要があります。 Point これがもし逆で第1層が50%以上持っていると、ネットワークを全体を管理する第2層を、より小さいハッシュパワーで乗っ取ることができるようになってしまいます。 これはビットコインなどの「51%攻撃」よりも低い割合になっています。 QuarkChainではこの問題に対して、次に紹介するクラスタリングで対応しています。 クラスタリング クラスタリングは、ミニノードを集めて実質的なフルノードを作れる技術です。 ノードとは ここではマイナー=ノードと考えると分かりやすいです。つまり、クラスタリングで小さなマイナーが協力して大きな1つのマイナーになるイメージです。 QuarkChainのマイニングでは、小さなハッシュパワーでもマイニング報酬を得られるという特徴があるのは「QuarkChainの特徴」で解説した通りです。 各マイナーはQuarkChainのネットワーク内でミニノードであり、その集合体が実質的なフルノードになっています。 マイナーがいくつか集まってフルノードが作られるので、1つの大きなマイナーがネットワークを支配しづらくなります。 ミニノードでは全体のトランザクションを確認することができません。 ほかのノードとデータを照らし合わせることで、全体のデータが確認できます。 クラスタ内の一部のミニノードが稼働不能になっても、ノード(クラスタ)としての機能は保たれるような仕組みが画期的です。 クロスシャードトランザクション クロスシャードトランザクションは、異なるシャード間でのトランザクションを可能にする技術です。 これによって、いわゆる"train and hotel problem"などが解決できるようになります。 シャード1で電車の予約をするためのトランザクション処理をして、シャード2でホテルの予約をするためのトランザクション処理をするとします。 この旅行予約のとき、どちらか一方の予約ができなければ両方の予約をやめるべきであり、両方の予約ができて初めて旅行の予約が完了します。つまり、このような状況において、「どちらも予約できるか」あるいは「どちらも予約しないか」の二択になります。どちらか片方の予約だけして、もう一方の予約はしない、という選択肢はありません。 Sharding Phase 1 の具体的な仕組みとセキュリティ課題 クロスシャードトランザクション技術によって、スケーラブルな環境下でも複雑なスマートコントラクトが可能になります。 クロスチェーン実装はアダプタorシャーディングを利用 QuarkChainは2通りの方法でクロスチェーンを実装することが可能です。 外部トランザクションにアダプタを利用する方法QuarkChainの外部チェーンのトークン(ビットコインなど)を、アダプタで変換してQuarkChain上で扱えるトークンにする方法です。 外部トランザクションをシャードに記録する方法外部チェーンをサブチェーン(またはシャードの1つ)として格納して、クロスシャードトランザクションを利用してやりとりする方法です。 スマートウォレット・スマートアカウント 通常、異なるシャードにある情報を管理したりアクセスしたりするには、各シャードに対応したアカウントが必要です。 でも、QuarkChainのスマートアカウント(ウォレット)があれば、メインアカウントを1つ持っているだけですべてのシャードにアクセスできるようになります。 スマートアカウント(ウォレット)のおかげで、ユーザーは同シャード・別シャードなどを意識せずにQuarkChain上のアプリなどを利用することが可能です。 プロジェクト進行は早い!?QuarkChainのロードマップを確認しよう こちらは2018年5月現在のロードマップ(ライブ版)です。 最新のロードマップはQuarkChainの公式サイトで確認することができます。 QuarkChainのロードマップ 時期 内容 2017年 Q2 スケーラビリティ問題のリサーチ 2017年 Q4 ホワイトペーパー草案 2018年 2月 検証コード0.1 ホワイトペーパー公開 2018年 3月 テストネット0.1 ウォレット0.1 2018年 Q2 テストネット1.0 スマートコントラクト0.1 2018年 Q4 QuarkChainコア1.0 メインネット1.0 スマートウォレット1.0 2019年 Q2 QuarkChainコア2.0 メインネット2.0 スマートウォレット2.0 【2018年 3月】テストネット0.1・ウォレット0.1 テストネットver0.1、ウォレットver0.1がリリースされます。 テストネットver0.1は、シャード内・クロスシャード両方の基本的なトランザクションに対応します。 【2018年 Q2】テストネット1.0・スマートコントラクト0.1 テストネットver1.0がリリースされます。 テストネットver1.0ではスマートコントラクトに対応します。 【2018年 Q4】QuarkChainコア1.0・メインネット1.0・スマートウォレット1.0 QuarkChainコアver1.0(QuarkChainの基本的な機能と最適化を実装しているネットワーク)がリリースされます。 コア、メインネット、ウォレットはすべて同時に公開される予定です。 【2019年 Q2】QuarkChainコア2.0・メインネット2.0・スマートウォレット2.0 コア・メインネット・ウォレットver2.0はver1.0をさらに最適化したものになります。 さらにクラスタリングも実装されます。 主なチームメンバーを紹介!バックグラウンドをチェックしよう QuarkChainの主なチームメンバーを紹介します。 結論からいえば、QuarkChainには優秀な人材が揃っています。Google、Facebookの出身が多いです。 1人1人について見ていきましょう。 【CEO】Qi Zhou ソフトウェアエンジニア。Facebook、Dell EMCでスケーラブル系プロジェクトの経験あり。 ジョージア工科大学博士卒 Facebook 1年 Dell EMC 2.5年 Google 9か月 【エンジニア】Zhaoguang Wang ソフトウェアエンジニア。バックエンドエンジニアとしてFacebookで1年、Googleで5年以上の経験。 ミシガン大学(コンピュータ・サイエンス・エンジニアリング)博士卒 Facebook 1年 Instagram 4か月 Google 5年 【研究者】Xiaoli Ma 研究者。Ratrix Technologies、LLCの共同創業者・CTO。 ミネソタ大学・電気工学博士卒 ジョージア工科大学 (教授) 3年11か月 Ratrix Technologies、LLC 6年6か月 ジョージア工科大学 (准教授) 4年 【研究者】Yaodong Yang 研究者。DEMO++の共同創業者。50以上の論文発表、600以上の引用あり。 バージニア工科大学博士卒 DEMO++ 2年11か月 西安交通大学・フロンティア科学技術研究所 (副学長) 3年9か月 【マーケティング・コミュニティ】Anturine Xiang 多様な業種でのデータ分析の経験あり。 ジョンズ・ホプキンス大学卒 Beepi 1年6か月 Chartboost 1年2か月 LinkedIn 11か月 QuarkChainの問題点・懸念点も知っておこう プロジェクトについてきちんと理解するには問題点・懸念点についても知っておくことも重要です。 主な留意点についてまとめているので、こちらにも目を通しておきましょう。 競合が多い QuarkChainはスケーラブルなプラットフォームの構築を目指すプロジェクトです。 スケーラブルなプラットフォーム系のプロジェクトは競合がたくさんいます。 競合が多い場合ははやくシェアを獲得できたプラットフォームが有利になってくるので、開発のスピードはとても重要なポイントです。 Point 現状のシェア最多のイーサリアム上のdAppsをQuarkChainに移し替えることができるのは、QuarkChainの大きなメリットです。 25%のハッシュパワーでネットワークへ攻撃ができる QuarkChainのネットワークを攻撃するには、最低でも全体の25%のハッシュパワーを持つ必要があります。 これはビットコインなどの50%よりも少ない割合です。 クラスタリングなどでマイナーのパワーを分散する構造にはなっていますが、実際に攻撃を受けずに稼働し続けられるかはわかりません。 【競合プロジェクトを比較】QuarkChainの優位性は? 最後に、QuarkChainと競合する主なプロジェクトについてもチェックしておきましょう。 プロジェクトの時価総額がどの程度になるのかを見極めるときの参考にすることができます。 QuarkChainとNEO・EOSの違いは分散性 NEOやEOSも高速のトランザクションが可能なプラットフォームです。 これに比べてQuarkChainが優れているのは、より分散化された仕組みになっているというところです。 NEOやEOSはノードが開発チームによって管理されているので、真に分散化された仕組みであるとは言い難くなっています。 対してQuarkChainはマイニングを分散化する仕組みによって、たくさんのマイナーが参加しやすい仕組みを作っています。 QuarkChainとZilliqaの違いはシャーディング Zilliqaもシャーディングを実装している、スケーラブルプラットフォームです。 QuarkChainはそんなZilliqaの上位版ともいわれることが多いプロジェクトで、よく比較対象に上がります。 QuarkChainの優位性 vs Zilliqa Zilliqa…シャード=ノード QuarkChain…シャード=ブロックチェーン →Zilliqaはノードが稼働しているときにスケーラブル →QuarkChainはあるノード停止や過負荷でも検証を引き継げる 他 クロスシャード、クロスチェーン(ZILはWANなどで導入予定)、EVMサポートなど — さっちゃん-仮想通貨ブログ (@vcvc_stc) 2018年5月12日 QuarkChainとZilliqaはデータの分割(シャーディング)のところで、大きな違いがあります。 ZilliqaとQuarkChainのシャードの違い Zilliqaはトランザクションを分割して、その処理を分散化してスケーラブルになる QuarkChainはシャード自体がブロックチェーン(2層構造)で、あるノードが過負荷などで稼働できなくなってもほかのノードが引き継いで対応することができる さらに、QuarkChainはEVM対応で最大シェアのイーサリアムから素早く乗り換えができる、というところもかなり大きなポイントです。 【大注目のICO】QuarkChainまとめ QuarkChainの特徴や技術、競合についてまとめました。 スケーラビリティ問題を解決できるプロジェクトは注目度が非常に高いです。 QuarkChainについてもっと知りたいと思った人はホワイトペーパーを読んだり、公式Twitterなどをチェックしたりしてみてください。 QuarkChainの公式リンクまとめはこちら

プロジェクト
2018/05/07SKYFchain / SKYFT -世界初の重貨物用ドローンプラットフォームのプロジェクト-
SKYFchainはブロックチェーン技術と、ドローンを組み合わせることで、物流業界の課題を解決するプロジェクトです。 本プロジェクトの特徴から競合プロジェクトまで徹底解説をしていきます。 SKYFchainの概要 通貨名/ティッカー SKYFchain/SKYFT 総発行枚数 1,200,000,000 SKYFT ICO 2018年3月10日 Start ICO価格 0.065 USD/SKYFT 主なパートナー Syngente AG(売上高-$128億)、Avgust crop protection(売上高-$2億6330万) 特徴 ブロックチェーンとドローンの融合 物流市場の課題解決 公式リンク Webサイト Twitter Facebook Telegram Medium reddit github(ソースコード) Announcement thread SKYFchainの特徴 SKYFchainは、ブロックチェーン技術によりドローンを代表とした無人機のオペレーティングプラットフォームを作り、物流市場に変革をもたらすプロジェクトです。 ドローンを利用した物流と言えば、2016年12月7日に初の民間テストを行ったAmazonの「Prime Air」を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか? 「顧客がタブレットで欲しいものを注文すると、物流倉庫の従業員が箱詰めを行い、ドローンが顧客の元まで届けてくれる」こんな近未来的な技術が、現実に行われ始めているのです。 もちろん、近年多くのビジネス書籍に踊る人手不足やAIと言ったキーワードがこの【次世代の物流技術】の後押しをしていることは言うまでもありません。 SKYFchainは、無人物流により50%もの人件費を削減することで、世界中の物流コストを下げ、産業界からエンドユーザーにまで、幅広い恩恵を与えることが期待できると述べています。 プロックチェーンによって物流に関わる書類作成や貨物運送コストが抑えられれば、より豊かな社会になりますねhttps://t.co/aA3EpaX06v — SKYFchain (@SKYFchain_jp) 2018年4月28日 無人物流市場の概要 SKYFchainのターゲットとする無人物流のマーケットを見てみましょう。 無人物流におけるメインプレイヤーとしてホワイトペーパーに記載されているのは、ドローンと自動運転車です。 ・ドローン PwCのデータによると世界のドローン市場の規模は1270億ドルにも達すると示されており、ビジネスマンにとっては今後非常にチャンスのある市場であると考えられます。 この市場への期待感を表すデータとして、ドローン市場へのVCからの投資額の指数関数的な増加があります。 CBInsightsのレポートによると、年を追うごとにドローン市場への投資額が増加しており、2015年の第二四半期では2012年の第一四半期と比較すると約50倍もの投資額となっていることが示されています。 ・自動運転車 空の輸送を担当するドローンに対し、こちらは陸の輸送を担当する無人トラックなども含まれています。 BIS ResearchのアナリストであるAbhimanyu Rahejaが、「2026年末までには自動運転車両台数は1億1000万台にも昇るだろう。」と述べているように、こちらも今後非常に拡大が予想される市場です。 さらに、Exane BNPパリバのレポートでも、同様の予測がなされています。 半自動運転車両約4000万台も含めると、2026年における自動運転車両の台数は1億2000万台を超えるとの予測です。 無人物流市場の課題 このように非常に注目される本市場ですが、無人物流の普及には大きく2つの壁があるとホワイトペーパーでは述べられています。 ・透明性の欠如 透明性の欠如とは、顧客が無人機の技術や旅程を確認できるシステムが未だにないことを指します。 これにより公的機関の規制強化や高額な保険料といった問題が発生してしまいます。 例えば顧客に商品を運ぶドローンが航路で事故を起こしてしまった場合、考えられる加害者はドローン製造業者、ドローンのサービス会社、顧客、ドローンパイロットなど様々です。 このように利害関係者がとても多い状況で、かつ誰の原因で事故が起きたのかを正しく証明するシステムがない現在では、保険会社も保険料を高額に設定せざるを得ません。 ・技術的問題 こちらは重い荷物を長距離輸送できるかというドローンの性能上の問題を指します。 大きな荷物を運ぶためには大きなプロペラが必要となりますが、プロペラを大きくすると制御可能な閾値を超えてしまいます。 また、エンジンに関しても電気エンジンでは蓄電池の問題が発生し、ガソリンエンジンでは重量の問題が、またハイブリットにするとコストの問題がついて回ります。 このように、これまでの技術では重たい荷物を運ぶためのドローンを作ることは技術的に非常に困難だったのです。 SKYFchainの可能性 SKYFchainでは、上の章で記述した2つの課題を解決し、無人機を利用した物流を普及させることが可能だと言います。 ・ブロックチェーンを利用した透明性 例えば先ほど挙げたドローンの事故において、物流現場に関するすべての情報を改ざんされることなく管理するプラットフォームさえあれば、保険会社にそのデータを提供するだけで支払いがスムーズに行われることが想定されます。 また、そのような事故のデータを金融機関や開発者、エンドユーザーが共有することにより、正しくドローンを社会に適応させていくことが可能になるのです。 ・SKYFchain独自の技術 SKYFchainはガソリンエンジンを利用しているにもかかわらず、独自の空力設計により垂直離着陸(VTOL)機能を備え、重い荷物を運ぶことが可能なドローンの製作を世界で初めて成功しています。 このドローンは、最大積載量400kg、最大飛行距離350km、飛行時間は8時間(積載量50kg)と、物流業界において十分利用可能で、従来では考えられないほどの高性能なのです。 SKYFchainの競合 ドローンに関連するプロジェクトとしては有名なものにDorado、またPrime airを展開するAmazonなども競合となります。 Doradoとの比較 Doradoは2018年2月7日~5月17日までICOが行われる、ドローンを利用したオンデマンドサービスを展開するプロジェクトです。 すでに、Foodoutという前身のプロジェクトが存在し、100万人の顧客から400万件にも昇る受注を経験しています。 Doradoに対するSKYFchainの優位性Doradoは前身がFoodoutという食品を専門に扱うドローンを利用したオンデマンドサービスを展開していました。今後は食品以外も扱うということでDoradoが生まれたようですが、軽量な食品と大きな荷物では運ぶ技術レベルが異なるので、SKYFchainの培ってきた技術は一歩先を言っていると言えます。 Doradoに対するSKYFchainの劣位性Doradoの前身であるFoodoutは2014年からの3年間でなんと6227%もの成長をしており、年間売上高は5000万ドルにも達しています。このような経験を持つチームメンバーを要したDoradoはSKYFchainにとって強敵となり得る可能性はあるでしょう。 AmazonやGoogleとの比較 今や知らない人などいないというほどの超巨大企業となったAmazonやGoogleももちろんこのドローン市場を見過ごすことなどしません。 Amazonは「Prime Air」、Googleは「Project Wing」を稼働させています。 AmazonやGoogleに対するSKYFchainの優位性SKYFchainはドローンにおいて世界初の快挙を成し遂げていますが、ブロックチェーンを物流業界に持ち込み、書類作成の簡素化や許認可鉄ぢ期の自動契約などの機能を持たせることで、コスト削減も謳っています。この点にもSKYFchainに強みがあると考えられます。 AmazonやGoogleに対するSKYFchainの劣位性言うまでもありませんが、企業としての規模が全く違います。企業の規模=経済力や認知は、少なからず開発や販売に影響があるため、このような大企業の参入は脅威となるでしょう。 SKYFchainロードマップ すでに2017年の第4四半期には完全自立の飛行試験に成功しており、今年2018年にはドローンの世界販売に乗り出します。既にベトナムの企業にもドローンの販売の実績も行ったようです。 SKYF Heavy Lifting Drones to Transport Goods in Vietnamese Seaport ドローンの飛行試験は後に述べる超大企業も参加を申し込んでおり、ドローン技術の高さが伺えます。 また、トークンのホルダーとしては上場も気になるところですが、ホワイトペーパーにて「少なくとも4つ、5つの取引所には上場させる予定です」と言った記述があります。 SKYFchainのパートナー SKYFchainのパートナーはかなり豪華です。 CARCIEL Inc.(カーシエル) 航空宇宙防衛コンサルティングファームである日本の企業CARCIELとの提携が今年4月に発表されました。 CARCIEL Inc.は、本田技研や川崎重工業など名だたる大手企業をクライアントに抱えています。 SKYFchainはCARCIELと高層ビルの建設及び消防におけるSKYFドローンアプリケーション開発に共同で取り組む予定です。 「私たちは日本の大手企業や多くの省庁からの要請に応じて、1年以上にわたって適切な技術を探し求めてきました。SKYFの大型ドローンは優れた特徴を持ち、日本で大きな需要があるでしょう」 CARCIEL Inc. 代表取締役兼 CEO 安藤 浩平氏 Syngenta AG(シンジェンタ) スイスを拠点とした種子や農薬を主力商品とする会社で、最近中国の国有企業ChemChinaによる買収のニュースでも話題になりました。 農薬業界では世界一位であり、売り上げは128億ドルにも昇ります。 SKYFchainはSyngentaと第1ラウンドの交渉を完了させ、SKYFドローンの試験を2018年の春に行う計画です。 Pony Express(ポニーエクスプレス) ロシアの物流企業で、世界8か国にオフィスを抱えています。 SKYFchainは現在、Pony Expressとの契約を締結し、2018年の春に飛行試験を行う計画です。 Russian Post(ロシア郵便) ロシア最大の郵便事業者で、約4万の郵便局を抱えています。 郵便事業者とも交渉が進行中とのことです。 SKYFchainのまとめ 物流業界で無人機を活用できるプラットフォームを開発するSKYFchainについて紹介しました。 この企業の強みは何といっても、ドローンの技術力だと言えます。 この技術力をブロックチェーン技術を用いて、ソリューションと一緒に提供することができれば、1270億ドルとも言われるドローンの市場を獲得することができるかもしれません。 また、Syngentaなど世界有数の大企業とパートナーシップを結ぶことができていることも今後の成長に繋がるでしょう。

プロジェクト
2018/05/05TravelBlock(トラベルブロック) – 最適な旅行プランを提供するプロジェクト-
Crypto Timesは今回、舞浜で行われたd10eというカンファレンスに公式メディアパートナーとして参加させていただきました。 今回のカンファレンスは、Crypto Timesでも紹介させていただいたNYNJAなどを含め様々なプロジェクトが参加していました。 メッセージアプリケーション NYNJA(ニンジャ)にプロジェクトインタビュー - CRYPTO TIMES その中でも、旅行代理店(Online Travel Agent : 以後OTA)の既存の仕組みを潰すと宣言していたTravelBlock(トラベルブロック)というプロジェクトが面白そうだったので紹介させていただきます。 従来のOTAの仕組みを軽く説明しながら、このプロジェクトの仕組みや特徴などを紹介していきます。 従来の旅行代理店の仕組み 1996年にExpediaが設立されて以来、22年間の間、OTAはExpediaが提供する仕組みによって成立していました。 図を作ってみましたが、この場合一般のユーザーはExpediaが提示する$500未満の価格でホテルを予約できる可能性はほぼ皆無です。 一方で一般ユーザーと対比させてプレミアムユーザーと書きましたが、これらのユーザーはホテルに対して数千ドルを支払うことでこのPrivate価格で宿泊する権利を得るため、ごく一部の限られたユーザーのみにこの価格が提供される仕組みになっています。 TravelBlockは、トークンを発行して新たな経済を作り上げることで、一般のユーザーに対してもPrivate価格でホテルを提供することを可能にします。 TravelBlockが実現する新たな仕組み さきほど、一般のユーザーが最安値として認識していたExpediaなどのOTAは、実は最安値ではなくExpediaがホテル側と契約した価格に過ぎなかった、というお話をしました。 しかしTravelBlockのウェブサイトを利用すると、すべてのユーザーはPrivate価格でホテルを予約し宿泊することが可能になります。 正確には、トークンを購入することがユーザーによるクローズドな消費者グループを形成することにつながり、TravelBlock側がホテルに対してより安価で契約を結ぶことを可能にします。 このシステムはトークンを発行しなければ、従来のOTAのモデルでは決して行うことができなかった仕組みであると考えています。 TravelBlockの特徴 [caption id="" align="aligncenter" width="841"] β版のウェブサイト[/caption] 旅行代理店としての基本的なサービス 従来のOTAと同様に、ホテルの予約から、航空券、レンタカーなど様々な旅に関連するサービスが提供されています。 ICOを行いトークンを発行するということで、ユーザーの獲得が難しそうにも見えますが、クレジットカードでの決済にも対応しているようです。 独自のプラットフォームなどではなくウェブサイト上で24時間365日、ホテルや航空券などの予約を行うことができます。 TravelBlock独自のサービス クレジットカード決済と書きましたが、TravelBlockではクレジットカードでトークンを購入しホテルの予約を行います。 このトークンを保有することによってPrivate価格で通常より30~60%安い価格で予約をすることができます。 また予約の際には、TravelBlockが提示するPrivate価格とExpediaなどのOTA8社が提供するPublic価格の差が表示されるため、どの程度お得であるかを一目でチェックすることができます。 TravelBlockに対する考察 このプロジェクトは、見る視点によって評価が大きく異なると思うのでそれぞれの立場から考察していきたいと思います。 一般消費者 いままでExpediaで$500であったホテルが$300になるわけですから文句なしだと考えられるでしょう。 問題としては、予約のフローが『クレカ→仮想通貨→予約』となる点で、各国により異なる規制や税制に対してどう適応していくか、消費者の仮想通貨に対するイメージや印象をいかにうまく与えられるかという部分には注目しておきたいですね。 仮想通貨投資家 トークンにブロックチェーンを導入しているが、いまいち透明性や改竄ができないなどの特徴をうまく生かし切れていないのでは?と考える人がいてもおかしくないプロダクトです。 しかし、すでに動くプロダクトが完成していてユーザー数も多いので、大多数への普及を考えると早い段階で仕込んでおくのは悪くないかもしれないですね。 ビジネスサイド 経営側としてはトークンを発行した新たな経済モデルの上で、従来のExpediaでは価格を落とすことが(ROI的な意味で)できなかった問題を解決することのできるWIN-WINのモデルを創り上げることに成功しました。 消費者側・経営側にとって十分満足に値するサービスの提供ができている点だけを見れば、非常によく考え抜かれたモデルだと思います。 個人的な意見 ブロックチェーンを利用してトークンを発行する点において、イノベーションなどの大きな一点にこだわるのも一つの楽しみ方であり評価の基準であると思いますが、結局はより多くの人間が満足する大きなスケールでのWIN-WINを勝ち取れたものが生き残っていくのがビジネスだと思います。 そういう意味ではTravelBlockもトークンエコノミクスこそは他に劣る部分はありますが、より実用的なプロダクトとして名を馳せていくのではないかと考えています。 まとめ d10eへ公式メディアパートナーとして参加した中で、少しイノベーションを盲目的に追うプロダクトとは別の、ビジネスというベクトルから考えられたTravelBlockを紹介させていただきました。 普段は技術やイノベーションについての話ばかり耳にしていたので、あれ?と思う部分もありましたが、全体的に消費者・ユーザー目線で考えられたプロダクトが多かったイメージです。 分散型で透明性があってトラストレスだから善であり、これらをフル活用できていないから悪であるという二元論的な考え方を修正するいい機会になったカンファレンスだったと思います。 公式リンク 公式サイト Telegram(英語) Medium(英語) Twitter

プロジェクト
2018/04/18BitRewards(ビットリワーズ) – Tポイントのようなロイヤリティプラットフォーム提供プロジェクト-
BitRewardsの概要 日本人が一番分かりやすい形で説明すると「Tポイントの仮想通貨バージョン」というのがBitRewardsの正体です。 BitRewards.networkの加盟店で商品を購入したり、サービスを利用すると顧客はボーナスとしてBITトークンをもらうことができます。 もちろん、BITトークンはTポイントと同様に加盟店での決済や割引に利用したりすることができます。 TポイントとBitRewardsの3つの違い ①BITトークンには発行上限が設定されている 発行上限が設定されていることにより、BitRewardsプラットフォームの成長に伴ってBITトークン1枚あたりの価値が変動します。 ②BitRewardsは無料で加盟店として参画できる 基本的にこういったロイヤリティサービスは加盟費用が必要となりますが、BitRewardsは無料で加盟することができます。 加盟店はBitRewardsが収集した膨大なマーケットデータやAIによる分析データの提供を受けることや、BITトークンを購入者にボーナスとして付与するロイヤリティサービスが出来るようになります。(AIの統合は2019年予定) ③ブロックチェーン技術を利用している ブロックチェーンを導入する利点として下記が挙げられます。 仮想通貨資産とすることで、他の流動性資産(他の仮想通貨等)にすぐに変換が可能 セキュリティリスクの低下(既存のロイヤリティシステムは情報流出が激しい) 加盟店が独自のトークン、その他のロイヤリティ、報酬プログラムの作成が可能 既にデモ版が稼働しており、実際に利用して無料でBITトークンを受け取れる 公式サイトTOPページの「機能している製品」ボタンから既に可動しているBitRewardsのデモ版が利用でき、メールアドレスを登録するだけで300円相当のBITトークンが受け取れます。(もちろん出金可能) 他にも Facebookでイイネ Facebookでシェア リファラルリンクの提供 等で「BitRewards」のプロダクトを使って、BitRewardsプロジェクトを宣伝することで、宣伝者はBITトークンを受け取るということができます。 そして前述にもある通り、将来的には 店舗独自のトークン発行・ロイヤリティプログラムの構築を行って、マーケティングやデータ収集 といったサービスも利用可能になる想定です。 他競合プロジェクトに対しての優位点 BitRewardsのようなロイヤリティプラットフォーム型のプロジェクトには下記の競合プロジェクトがあります。 競合プロジェクト INCENT PLUSCOIN LoyalCoin GatCoin ロイヤリティを提供するプロジェクトは上記のように多種存在していますが、競合プロジェクトに対してBitRewardsは下記の優位点が存在しています。 競合プロジェクトとの優位点既にEコマース市場で5年間以上サービスを行った実績がある 店舗が無料でBitRewards.networkに加盟することが出来る 海外レビューサイトの評価 ICOBenchの評価 ICORATINGの評価 TrackICOの評価 ICOHOLDERの評価 レビューサイトでは概ね好意的な評価をされています。 レビューサイトとして一番信頼性の高いICODropsではスポンサード枠として掲載されています。 ICODropsのBitRewards掲載ページ ICODropsはあくまでスポンサード枠の掲載ですが、本サイトはスポンサード枠にもプロジェクトの掲載審査が行われており、枠を金銭のみで購入することはできないため指標のひとつになるでしょう。 関連リンク 公式サイト Twitter(@Bitrewards) 日本Twitter(@BitRewards_jp) ホワイトペーパー(日本語) ライトペーパー(日本語) ホワイトペーパー(英語) ライトペーパー(英語) Medium 公式Telegram(英語) 公式Telegram(日本語) ※プロジェクトのICOへ参加される際には、自身でも利用規約やプロジェクト内容に関して十分理解をした上での投資を行いましょう。投資をおこない損失などが生じた場合、CRYPTO TIMESでは一切の責任を負いません。全て自己責任となります。

プロジェクト
2018/04/17【dApps】ポ○モン系RPGゲーム Chain Monstersの紹介
こんにちは。先日デ○モンのような感覚で遊ぶことのできる『Axie(アクシー)』というゲームを紹介しましたが、今回はポ○モンのような感覚で遊ぶことのできる『Chain Monsters(チェーンモンスター)』というゲームを紹介します。 日本語の対応はまだしていないようですが、プレイしてみた感想は、見慣れたUIで操作もシンプルなため不自由なく遊べると思います。 Chain Monsters公式ページ Chain Monsters(チェーンモンスター)の3つの特徴 100%ブロックチェーン上で動作する 見慣れたUIのため誰もが不自由なくプレイできる レベリング要素(未実装)で課金額がプレイに影響しにくい シンプルなゲームプレイ 基本的に画像のドット絵の主人公を移動させて、草むらで自身のモンスターを戦わせてレベルを上げていきます。 またゲームが100%ブロックチェーン上で動くため、育成のプロセスで従来のPvP(Player vs Player)のMMOなどのゲームで問題となっていたチート・不正などは絶対に行うことができません。 現在のところ、レベルアップ要素やモンスターの捕獲要素は確認できませんでしたが、こちら運営に問い合わせたところ、ロードマップでは2018年Q2で実装とあり、これより遅くなることはないそうです。 多様なモンスターとシステム ロードマップによれば、151体のモンスターがそれぞれ開発の進捗に応じた世代を持つそうです。 現在では、最初に選ぶことのできる3体を含めた23体(第1世代)がリリースされているようで、こちらのモンスターは野生で遭遇することができます。 画像は戦闘の画面で、ゲームのシステムはターン制で能力値に応じて先攻後攻が決まるようです。 またはっきりとは書かれていないのですが"火"⇔”水”⇔”草”などの相性によるダメージの補正もあるようです。 複数のモンスターを駆使し、相性などを考えて戦略を練っていく、シンプルですが奥が深いゲームシステムになっています。 また、現在開発が行われているリアルタイム対戦システムでは、同じマップ上に存在するプレーヤーと遭遇し彼らとバトルをすることもできるようになるそうです。 その他にも今後実装されていく機能が豊富 モバイル版の対応(2018-Q1) モバイル版が対応すれば、空いた時間にスマホでプレイすることも可能になります。 また、スマホのimTokenやTrustなどのETHウォレットを使えば、ウォレットアプリ一つでChain Monstersをプレイできゲーム内でのトランザクションなども容易に行うことができます。 クエスト・ストーリーモードの追加(2018-Q1) 従来のdAppsゲームは対人が主でしたが、Chain Monstersに実装される予定のクエスト・ストーリーモードは、ブロックチェーン上で動くdAppsながらも個人でゲームを楽しむことが可能になります。 ETHを支払うため『投資額を取り戻さなければ』などという感情のために、ゲームをゲームとして楽しむことのできなかった従来のdAppsと比較して、Chain Monstersにはゲーム本来の楽しさがあります。 開発者がオススメするポイント 開発者によれば2つの重要なポイントを日本のプレーヤー達に伝えておきたいそうです。 ①モンスターが無料で手に入る。 ユーザーはログインするのみで、Gen-0(第0世代)のモンスターを無料で手に入れることができるようです。 第0世代は、ERC721トークンのそれぞれのトークンが固有性を持つ機能を利用し、最初の10,000体のみの販売・配布となっています。 更にこれらのモンスターは通常のモンスターより個体の能力が高く設定されているようです。 ②CryptoKittiesと連動 このゲームに実装されるミニゲーム機能では、CryptoKittiesと呼ばれる他のdAppsゲームで育てたキャラクターを使って遊ぶことができます。 他のゲームで育てたキャラクターが別のdAppsで利用できるようになれば、遊ぶゲームを慎重に選ぶ必要性がなくなり、気軽に色々なゲームに熱中することができそうですね。 ゲームの始め方 現在対応しているPCからゲームを始める場合は『Metamask』の利用が必須となります。 他のゲームでは、初期費用が高く設定されていることが多いですが、Chain Monsterでは最初の1体を手に入れるのにかかる費用が執筆時は0.002573ETH(1.30USD)とかなり安めに設定されています。 公式サイトからGameタブをクリックすると、ゲームが始まりますので、博士に言われるがまま主人公の名前を決めて、最初の1匹を選んでください。 従来のRPGゲーム同様、”火”、”水”、”草”の中から1匹選びます。 選択し次に進むとMetamaskのポップアップが表示されますので、ここでSUBMITボタンを押して購入を進めてください。(画像では残高不足のためBUY ETHERとなっています) スマホの『Trustウォレット』などから購入する際は、Chain Monstersのモバイル版対応が現在まだ完了していないのでマーケットプレイスでの購入のみが可能です。 購入後ブロックチェーン上でのトランザクションが終わると冒険が始まります。 Chain Monsters公式ページ 関連リンク 公式サイト Twitter Github Whitepaper Reddit
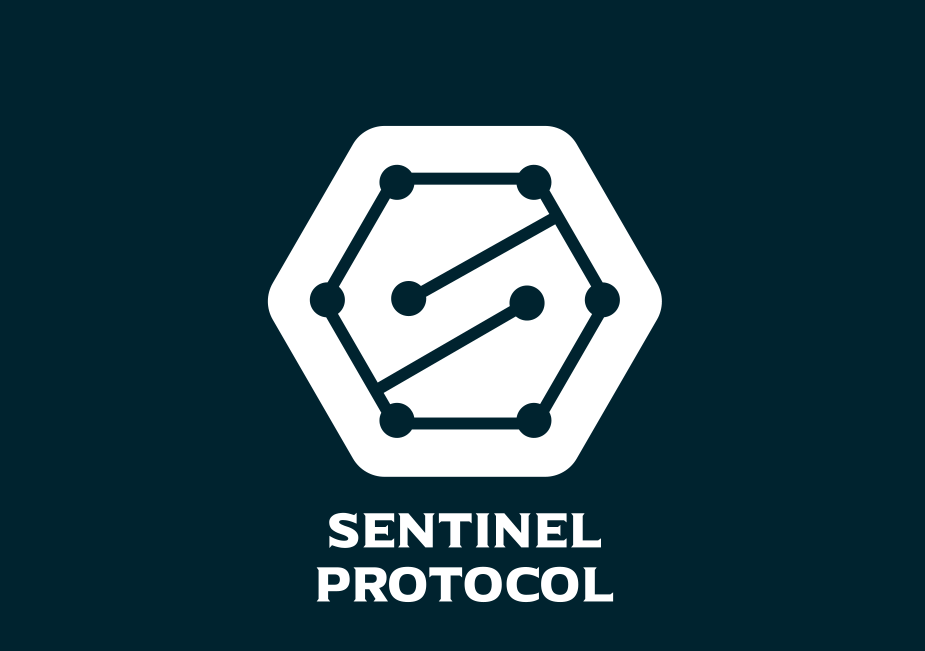
プロジェクト
2018/03/30Sentinel Protocol(センチネルプロトコル) -分散型セキュリティプロトコルのプロジェクト-
今回紹介するのは、Sentinel Protocol(センチネルプロトコル)というセキュリティ関連のプロジェクトになります。 このプロジェクトの3つのポイント! 通貨のシステムでしか解決できなかったハッキングに対しての防衛手段となるプロトコル 人工知能やAIを利用した自律性を持つエコシステムを創造 ハッキング自体のインセンティブを奪い去ることができるので問題の根本的な解決が見込める Sentinel Protocolとは? Sentinel Protocol(センチネルプロトコル)とは、仮想通貨のAutonomy(自律性=管理者の不在)の弱点であるセキュリティを集団的知性や機械学習で解決しようというプロジェクトです。 仮想通貨におけるサイバー犯罪は、分散型台帳を利用したP2Pネットワークの匿名性ゆえ、ハッカー側がターゲット(取引所など)を選ぶことが非常に容易であるにもかかわらず、攻撃者を特定するのが非常に難しい仕組みになっています。 現状これらの被害が全て自己責任という言葉に片づけられてしまうのですが、ではそれぞれが対策を練っていったとしても、根本的な『仮想通貨におけるセキュリティ』は脆弱性を突くハッキングに対する本質的な防衛手段にはなりえません。 Sentinel Protocolはブロックチェーンのそれぞれが自己利益のために動きそれが相互作用する仕組みに目を付け、仮想通貨の自律性という柱を守りつつ、集団的知性や分散型AIを使うことによって、サイバーセキュリティエコシステムのプロトコルの実現を目指しています。 このICOが実現できることこのプロジェクトの本質は分散型エコシステムの健全な環境維持にあります。ハッキングと聞くと対策という枕詞が頭に浮かびますが、このプロジェクトでは従来のセキュリティ対策と比較すると、分散型システムの強みを生かした自律的で健全なセキュリティのシステム創造がビジョンの根底にあると考えることができます。 プロトコルとは?アプリケーションとの違いは? Sentinel Protocolのプロトコルという言葉についてですが、これは皆が共通して対応するどのアプリからでも同様に利用するための基盤となるルールのようなものと覚えておきましょう。 例えば、https(HyperText Transfer Protocol)とはSSLやTLSが提供するセキュアな接続上でhttpのプロトコル通信を行います。 Google ChromeやFirefoxなどのアプリケーションは、基盤となるhttpsのプロトコルを利用することができるため、どのプラットフォームからも同様にセキュアにwebサイトを閲覧することができるようになります。 Sentinel Protocolを利用する場合だとケースがいくつかありますが、基本的にはSentinel Protocolの集団的知性やAIを生かしたネットワーク上で送金や受金などを行うことができ、このプロトコルに疑わしい、危険などと判断されたアドレスへの送金、からの受金をブロックすることができます。 またAI(人工知能)を取り入れることで、アドレスのブロックのみでなく、通常のユーザーの挙動と異なる動きを検出、未然にブロックすることも可能になります。 Sentinel Protocolの特徴 Sentinel Protocolには特徴となる Sentinel Portal(センチネルポータル) S-wallet 分散型マルウェアサンドボックス の3つの柱があります。 Sentinel Portal Anti-Theft System(犯罪防止システム) ネットワーク上での資金のやり取りを管理する一つの例としてクレジットカードがありますが、クレジットカードの場合、それが盗難された際に管理者(カード会社)が利用を停止するなどして、不正な利用を防ぐことができます。 しかし、管理者のいない仮想通貨のシステム上、こういった犯罪と関連した資金の不正な移動を防ぐことができません。 Sentinel Portalによりコミュニティ内の全ての情報を仮想通貨の取引所にシェアすることで、盗まれた資産がFIATに交換されることを防ぐことができると考えています。 Malformed Transaction Prevention(不正取引防止) Scam認定されたアドレスやそれに派生するアドレスは、ブロックチェーンの利点を生かしてコミュニティ内のすべてのメンバーと共有されます。 Sentinel Protocolが適用されている限り、ハッキングの被害の拡大、分散を防ぐこともできます。 一つの例として、ICOの詐欺などにおいて、アドレスに送金したが持ち逃げされた際に、詐欺を行った人物(チーム)のアドレスを追跡することができます。 S-wallet S-walletはSentinel Protocolのコミュニティにいる人々に提供される、従来のセキュリティソフトのにあるような機能を搭載したウォレットになります。 従来の中央集権的なソフトウェアはサーバーにある既知の脅威にしか対応することができなかったのですが、S-walletは脅威の傾向や履歴を分析することでゼロデイ攻撃*などの未知の脅威に対して対抗しうる可能性を持ちます。 集団的知性によって集まったデータベースを参照して、アドレスフィルタリング、URL/URIフィルタリング、データフィルタリング、詐欺検出などを行うことができます。 特に機械学習(後述)を利用した詐欺の検出などは、サイバー犯罪における二次被害を防ぐことができる点において非常に重要な意味を持ちます。 *ゼロデイ攻撃…ハッカーが脆弱性の発見者となるような攻撃 分散型マルウェアサンドボックス サンドボックスとは、未確認のプログラムやコードを仮想マシン上で動かすことでアプリケーションやホストに対してノーリスクで動かすことのできるシステムです。 既存のサンドボックスは中央集権的でサーバー内で仮想マシンを起動させてこれらの未確認のプラグラムを動かす必要があったため莫大なコストがかかりそれがネックとなることもありました。 しかし分散型のサンドボックスは、これをPoWの仕組みと融合させることで、未確認のプログラムやコードのテストの役割をユーザーに担ってもらうことで、従来のシステムにかかっていたコストを大幅に削減することが可能になりました。 言うまでもなく、PoWを利用しているのでサンドボックスのエコシステム維持に貢献したユーザーにはインセンティブが付与されます。 ※Sentinel ProtocolにはPoP(Proof of Protection)(後述)というアルゴリズムが用いられますが、サンドボックスのシステム維持に貢献した人にはPoWによってトークンUPPと互換性を持つSP(Sentinel Point)が付与されます。SPはUPPと交換可能です。 これらのセキュリティ、特に仮想通貨におけるセキュリティを強固にすることには大きな意味があります。それは、ハッカー側の攻撃インセンティブを間接的に奪うことができる点です。 例えば、ハッカーはCoincheckのハッキング後にダークウェブで15%オフでNEMを販売していたことなどからも、実際に奪った資産を換金し利用することを最終的な目標にしていることが伺えます。Sentinel Protocol導入によるアプローチはこういったハッカーの金銭的なゴールを妨げる役割を果たしています。 このプロトコルが世界中で利用されることで、ハッキング自体が不毛であることを気付かせそのインセンティブを消し去ることができるかもしれない、という点で優れていると言えます。 合意形成アルゴリズム『PoP』とは? 上述の通り、Sentinel Protocolでは、Daniel Larimerという人物によって発案されたDPoS(Delegated Proof of Stake)を元にしたPoP(Proof of Protection)というアルゴリズムを採用しています。 簡単に言えば、Delegatedとは代表者のことで、この合意形成アルゴリズムにおいては、Uppsalaによって選抜されたセキュリティの詳しい知識などを持つ機関や個人が合意を形成します。 これによってPoWの電力の無駄を十分に削減し、従来のPoSでも起こり得る51%問題などの脅威を劇的に減らすことを可能にしました。 更にReputation Scoreと呼ばれる内部評価のようなシステムを採用しています。 このスコアがコミュニティ内での影響力を示し、既存のPoS同様そのスコアに応じたステークが与えられるため、個人個人のユーザー、機関があえて犯罪に加担してくような動きを見せることは極めて考えにくいとしています。 集団的知性と機械学習・AI(人工知能) S-walletの項でSentinel Protocolには集団的知性や機械学習が利用されている旨を簡潔にに説明させていただきましたが、これらをセキュリティで利用していくことのメリットをこちらで紹介します。 ブロックチェーンは分散型で書き換えもできないからセキュリティが強いと世間では謳われていますが、実際のところそうではありません。 まず必ず注目しなければならないのが、従来のセキュリティと比較した際に見える中央管理者の有無です。 仮に仮想通貨が集権的で、仮想通貨管理局なるものが存在するとすれば、仮想通貨で行われた不正に対して管理局の専門家が『このトランザクションは無効』などの判断を下したり、『こういうハッキングが流行り始めたから気を付けて』などの注意喚起なり、個人のユーザーの不利益の阻止にある程度は貢献できるかもしれません。 ですが、現状こういった専門家や最新のデータなどに個人がアクセスし情報を得て対策をする、という一連の理想の流れは中央管理者が不在である点などから実現が非常に難しい状況にあります。 第二に注目すべきは、ハッキングやデータの漏洩などから、実際に資産が盗まれた際、そのトランザクションデータはすべてブロックチェーン上にあるという点です このブロックチェーン上の情報を収集して共有(集団的知性)、パターンや不正な挙動などの解析(機械学習)することで、中央管理者の不在による個人へのダメージを解消し、従来の集権的なデータベース以上にスケールする最高のセキュリティプロトコルを創り上げることができます。 Sentinel Protocol のロードマップ この記事の執筆段階でSIPB(Security Intelligence Platform for Blockchain, Sentinel Protocol)のベータテストは既に完了しています。3月にはトークンの発行と同時にテストネットのローンチがあるようです。 Sentinel Protocolのリリースは18年6月を予定していて、機械学習やサンドボックスなどのシステムは11月から12月にかけて随時追加されていく予定です。 2019年には詐欺検出システムがメインネットに追加される予定です。 Sentinel Protocolのチーム概要 このICOを行っているUppsalaという企業ですが、創立者と他数名がDarktraceという最先端の機械学習を使ったサイバーセキュリティの会社の出身です。 その他メンバーは、Palo Alto Network、Penta Security Systemsなどの企業が出身で、いづれもサイバーセキュリティ方面で活動を行ってきたようです。 最初はUppsalaという企業が検索で見つからなかったので不安になりましたが、チームメンバーがれっきとしたセキュリティのバックグラウンドを持つことや、彼らの経歴を客観視した際に、プロジェクトの実現が十分に見込めるなどという理由で紹介させていただきました。 その後、このプロジェクトメンバーと連絡を取ったところ、こちらで会社の存在を確認することができました。このThe centralという場所はKyber NetworkやDigixなども拠点にしているようで、Crypto Buildingなどと呼ばれているようです。 トークンセールの詳細 プレセールの開始は4月中旬とされています。プレセールに割り当てられるトークン枚数は、87,500,000UPPになります。 ハードキャップはプライベートセールの内容を反映して$11,670,000に設定されています。 こちらはホワイトリストの登録を完了させたユーザー向けに以下の内容で行われます。 1ETH = 5,000UPP 15%のボーナス(5,750UPP)とボーナス付与分に対しての6か月のロックアップ ※ホワイトリスト登録にはKYCが必要となります。 クラウドセールはこのプレセールの終了後に順次開始されます。 初期段階で発行されるトークンのうち、33.7%+26.7%がそれぞれ一般向け、初期段階で貢献した人々に、15.0%がUppsalaに分配されます。残りはビジネスなどの用途に使われるようです。 関連リンク 公式サイト Twitter(@s_protocol) ホワイトペーパー(英語) Medium 公式Telegram(英語) 公式Telegram(日本語) ※プロジェクトのICOへ参加される際には、自身でも利用規約やプロジェクト内容に関して十分理解をした上での投資を行いましょう。投資をおこない損失などが生じた場合、CRYPTO TIMESでは一切の責任を負いません。全て自己責任となります。

プロジェクト
2018/03/24SAMURAI-X(サムライエックス) 誰でも世界の不動産へ投資し、賃貸収入を得られるプロジェクト
SAMURAI-Xのポイント! 誰でも不動産投資を気軽にできるようにするプロジェクト 既に不動産売買のプラットフォームは可動済み 賃貸配当はBTC・ETH等で払い出しされる SAMURAI-Xのビジョン 「SAMURAI-X」は不動産資産をトークン化して「誰でも、少額で、簡単に、世界中で」扱えるようにするプロジェクトです。 現在の不動産投資の問題点 取引に時間がかかる お金持ちしか投資できない 海外不動産への投資ハードルがとても高い 流動性が低い 現在の不動産への投資は一般的な収入の人々が参入するには、あまりにもハードルが高くなっています。 「SAMURAI-X」では、これらの問題を解決するために不動産をトークン化して分割し透明性を確保することで 最低1万円から借金リスクなしに、誰でも世界中の不動産へ投資する事を可能にする ことを目標としたプロジェクトです。 当然、不動産ということは投資した物件の保有トークン量に応じた賃貸(家賃)収入が発生し、受け取ることが出来ます。 SAMURAI-Xの仕組み 有限責任会社(LLC)がプラットフォームに不動産を掲載 掲載された不動産の所有権をPATトークンに分割 (この際に不動産価格3~6%のRAXトークンがプラットフォーム利用手数料として消費) PATトークンはETHやBTCで購入可能 PATトークン保有者は保有割合分だけ該当の不動産を所有していることになります。 SAMURAI-Xで扱われる2つのトークン RAXトークン 正式名:Real Asset Exchange Token(直訳で現実資産交換トークン) 目的:ユーティリティ 配布方法:トークンセール 用途:プラットフォームアクセス、又はサービス RAXトークンはプラットフォーム(SAMURAI-X)上で物件を掲載する際と、物件をPATトークンに変換する際に手数料として利用されます。 プラットフォームに支払われたRAXトークンはSAMURAI-X、RAXトークンの利用者拡大に向けて今後利用されていきます。 PATトークン 正式名:Property Asset Token(直訳で所有物資産トークン) 目的:セキュリティ 配布方法:プロパティセール(プラットフォーム上で販売) 用途:賃貸収入と売却報酬の請求 PATトークンは物件ひとつひとつにユニークなPATトークンが新たに発行されます。 POINT例:クリプトハイム11号室をPATトークン化すると「PATCH11」というような物件に紐づくトークンが発行されます。 紐付いた物件トークンの保有割合に応じた賃貸収入・売却報酬が支払われる。 物件をトークン化する際にもRAXトークンが必要な仕組みになっており、RAX・PATのどちらもプラットフォームの成長と密接に関係した存在となっています。 実物資産連動性プロジェクトの強み POINT実物資産とは、不動産、土地、宝石、金、レアメタル、美術品といった実際に形があり、それ自体に資産的な価値があるものの事をいいます。 (仮想通貨や株、外貨等は金融資産となる) 実物資産は物体自体が生み出す価値があるため、連動トークンの価格のボラティリティが抑えられると予想されます。 そのため、今までの仮想通貨での投機的な要素よりも、投資的な要素が強く、安定した収益が見込めるのが実物資産連動性プロジェクトの強みとなります。 不動産売買プラットフォーム「SamuraiLand」と提携済み 「SAMURAI-X」はBTC、ETHで物件の購入ができる「SamuraiLand」という不動産投資プラットフォームと提携しています。 このSamuraiLandは既に仮想通貨での支払いに対応しており、後にSAMURAI-Xと統合されることになっています。 ここに掲載されている物件はSAMURAI-Xの仕組みに出てくる「LLC」の保有する物件に当たるので、RAXトークン発行直後にSamuraiLandに掲載されている物件はすぐにトークン化することが出来ます。(ホワイトペーパーにも記載あり) 公式リンク 公式サイト ライトペーパー ホワイトペーパー 【対談】SamuraiX(サムライエックス) CEOにプロジェクトインタビュー - CRYPTO TIMES ※プロジェクトのICOへ参加される際には、自身でも利用規約やプロジェクト内容に関して十分理解をした上での投資を行いましょう。投資をおこない損失などが生じた場合、CRYPTO TIMESでは一切の責任を負いません。全て自己責任となります。

プロジェクト
2018/03/23Loom Network(ルームネットワーク)とは?-ゲームdAppsに特化したプラットフォーム-
こんにちは!Shota(@shot4crypto)です。 本記事では、Loom Networkと呼ばれるイーサリウム上のdApps(分散型アプリケーション)におけるスケーリング問題を解決するデベロッパー向けのキットを紹介します。 PlasmaやRaiden Networkなどはメインネット側のスケーラビリティ問題を解決するために考えられたものであるのに対し、Loom NetworkはdAppsのスケーリングに関しての初めてのプロジェクトになります。 スケーラビリティ問題とは? 仮想通貨の根幹をなすシステムといっても過言ではないブロックチェーンですが、このチェーン上の個々のブロックには保持できる情報の量が規定されています。 例えば、ビットコインの最大のブロックサイズは『1MB』と定められています。 しかし、利用者が増えより多くのトランザクションが行われるようになると、ブロックに保持できる量が定められている性質上、トランザクションや送受信の詰まりが発生します。 ブロックサイズが定められている設計上、指数関数的なトランザクションの増加と同じスケールでブロックサイズを大きくするといった解決策はとることができません。 この増加する情報量とブロックサイズの制約によって引き起こされる問題をスケーラビリティ問題と呼びます。 スケーラビリティ問題の関連記事はこちら 仮想通貨に送金革命!?ライトニングネットワークとは何かを解説! Segwitとは何か?今さら聞けない仮想通貨 Plasma Cashのモデルが取引所にハッキング耐性を付与する可能性をもたらす スケーラビリティ問題を解決する4つの策とは? Loom Networkの特徴 Loom Networkは次世代のブロックチェーンプラットフォームと呼ばれており、主にゲームやソーシャルアプリ向けのスケーラビリティ問題に対するソリューションとして機能します。 従来のイーサリアム上のDAppsは全てメインチェーン上にコントラクトがありました。 メインチェーン上のコントラクトは、高額なトランザクションに対してもセキュリティを維持するために処理能力や速度を犠牲にしている合意形成アルゴリズムが用いられていた為、ゲームやソーシャルアプリなどのDAppsにおいてこれが障壁となっていました。 Loom Networkでは、DAppsチェーンというアプリケーション特化型のチェーンを使用しており、トランザクションの処理をこのサイドチェーン上で行わせることで、障壁となっていたゲームとは無関係な場所で起こるトランザクション詰まりを解消することに成功しました。 また、記録されたトランザクションはRelayという形で従来利用されていたメインチェーンと双方向でやりとりをすることが可能になります。 既存のソリューションとの違いは? スケーラビリティ問題に対するソリューションは、ビットコインであればLightning Network、イーサリアムであればRaiden Network / Plasma、NEOであればTrinityなどと色々ありましたが、これらのソリューションとの根本的な違いについても解説しておきます。 Raidenなどの従来のソリューションとLoom Networkの比較 従来のソリューション Loom Network 問題 トランザクション増加で送金詰まり DAppsメインチェーンの制約 アプローチ 個人のチャンネル開閉など コントラクトをサイドチェーン上で 対象 個人から法人まで デベロッパー向け 備考 - コミュニティ内の合意でフォーク可能 まずLightning Network, Raiden Network, Trinityについて、これらはオフチェーンを利用したソリューションでユーザーがトランザクションの際にチャンネルと呼ばれるものを作成することでチャンネル開閉時以外の採掘コストを抑えられるというものになります。 つまり、オフチェーン上で極力情報のやりとりを行うことで、メインチェーンへの負担を減らすというのがこれらのソリューションのアプローチです。また、これらは主に上で述べたトランザクションや送受金詰まりに対しての解決策として開発されました。 (※Plasmaに関してはLightningなどとは別の子チェーンを利用するアプローチをとっているのですが、こちらは記事の主旨の都合上割愛させていただきます。) 一方でLoom Networkはサイドチェーンを利用したソリューションで主にデベロッパー向けにDAppsにおいて不要なトランザクション詰まりを解消するために開発されました。 このサイドチェーンとは、Plasmaのような子チェーンではなく、メインチェーンと同列に扱われるDAppsチェーンというもので、あるDAppsゲームにおいてコミュニティの判断でフォークを行ったりすることも可能になります。 また、Solidityという言語を用いることでLoom Network SDKを利用し、独自のDAppsを簡単に作ることもできます。次項でどのようなDAppsが作成できるのか、いくつか例を紹介します。 Loom Networkを利用したDApps DelegateCall DelegateCallはDAppsチェーン上で動く、DAppsチェーンに関してのQ&Aサイトで、ユーザーは質問や回答を閲覧できるほか、これに参加することでトークンを獲得することもできます。 CryptoZombies CryptoZombiesもDAppsチェーン上で動くゲームで、開発に必要なSolidityという言語をから学ぶことができます。利用者は本記事執筆時で13万人を超えています。 詳しくはこちら理系男子コンソメ舐め太郎の『HACK YOU!』 第2回 -CryptoZombies完走してみた- ETHFiddle ETHFiddleはより開発者向けのDApps上コミュニティのようなもので、ユーザーはSolidityのスニペット(コードの切れ端)をシェアできます。 Loom Networkのトークン Loom Networkにはトークンが発行されていますが、こちらの使い道に関しても技術的な面から軽く触れておきます。 この記事では、Loom NetworkはDApps開発におけるソリューションとして新たに生み出されたサイドチェーンを用いたソリューションで、Relayという方式を用いてメインチェーンとのやりとりを行うことを説明しました。 これから色々なLoom Network上におけるゲームの開発が進んでいく中で、ゲーム内で獲得したトークンはそのゲームの中で完結することなく、様々なゲームで扱われるトークンとの互換性を持つことなども期待されています。 このときにメインネットとのやりとり(トークンとETHの交換の作業)が必要になるのですが、その際のアクセス権に該当するものがLoom Membership Tokenになります。 そのため、アクセス権を獲得するのに必要なトークン1枚のみで、購入後は永久的にLoom Network上のDAppsで利用することができます。 更に、仮に将来的にCryptoZombiesで育てたゾンビと互換性を持つ別のゲームが開発された際にも、自身のゾンビをインポートして別のゲーム上で動かすことも、Loom Membership Tokenの購入で可能になります。 まとめ DAppsの開発がここ最近注目されてきましたが、Loom Networkは従来のDAppsのメインチェーン上でのコントラクトによるトランザクションの詰まりなどスケーラビリティの問題を、DApps特化型のサイドチェーンを利用することで解消することに成功しました。 以前のDAppsと違い無料で利用できる点からも、ユーザー数の更なる増加を見込める要素だと思います!今後の動きに注目したいですね!

プロジェクト
2018/03/05World Wi-Fi(ワールドワイファイ) 世界中でWi-Fiを誰でも無料で利用できる社会を作るプロジェクト
このプロジェクトのポイント! 世界中誰でもどこでもインターネットへのアクセスが可能になる ルーターを提供することで報酬が貰えるためビジネス創出に繋がる 本プロジェクトCEOはすでにWi-Fiビジネスで成功経験を持つ World Wi-Fiとは? World Wi-Fiは、世界中誰でもどこでもインターネットを無料で利用できる社会作りを目指したプロジェクトです。 POINT 海外に行く際ポケットWi-Fiを空港で借りていく。 月末に通信制限がかかり公共Wi-Fiを探しても鍵付きWi-Fiしか見つからなかった。 こんな経験をされた方、多くいらっしゃるのではないでしょうか? また、世界的に見ると現在でも約40億人の人々がネットワークへのアクセスができていないという試算もあります。 というのも、ネットワーク利用料は月額平均約30ドルであり、世界人口の76%もの人々にとって大きすぎる数字なのです。 World Wi-Fiでは誰でもどこでもインターネットを無料に利用できる社会を作り、このような個人的な問題から世界的な問題まで解決していくことを目指しています。 World Wi-Fiのカラクリ World Wi-Fiにおけるペルソナは以下の3人です。 ペルソナ インターネットユーザー ルーター保有者 広告主 それぞれのWorld Wi-Fiプラットフォームに関わる登場人物が上の図のような”得”をすることがインセンティブとなりこのプロジェクトが成り立つのです。 インターネットユーザーの役割 インターネットユーザーは、ネットワーク利用料を支払うことなくネットにいつでもどこでもアクセスすることができます。 この時、ネットワークに接続する前に10~15秒の短い広告動画が流れ、バナーも表示されます。 ルーター保有者の役割 自身の保有するルーターをインターネットユーザーに利用してもらうことで、広告主から報酬としてWorld Wi-FiトークンであるWeToken (WT)を獲得できます。 この時、ルーター保有者はオープンネットワークを作成し、インターネットユーザーに無料Wi-Fiを提供します。 広告主の役割 インターネットユーザーに対して広告を閲覧してもらうことができます。さらに、その広告内容は検索履歴、性別、年齢、SNSプロファイル、場所(番地・号室まで特定可能)に基づき、仲介者なしで設定することが可能なので、効率的にターゲット層に広告の表示ができます。 この時、広告主はオープンネットワークを作成したルーター保有者に報酬を支払います。 POINT 広告主の抱えるターゲット層に広告を届けることが難しい問題 ルーター所有者のネットワーク利用料が世界的に見ると高額である問題 この2つの問題を同時に解決することで誰でもWi-Fiが無料で利用できるシステムを構築している! World Wi-Fiの普及可能性 プラットフォーム上の誰もが得をするように設計されていますが、実際に普及する可能性を考察するために、いくつか問題となりそうな部分をピックアップしていきます。 ネットワークの需要はあるのか? そもそもこのプロジェクトはインターネット利用者がいてこそ成り立つものであるため、インターネット利用者の数(需要)を考える必要性があります。 2017年9月18日の国連Global Broadband Progressにて、世界のインターネット利用者数は35億8,000万人(発展途上国では25億人、先進国では10億人)という報告があり、インターネット市場の大きさがうかがえます。 また、2000年から2015年の間に、世界のインターネット利用者数の割合は、6.5%から43%へと約7倍の増加を見せています。 その一方で、アフリカではインターネットに常にアクセスできる状態にある人々は人口のわずか14.5%であり、今後も十分成長の見込まれる市場であることがわかります。 ルーター保有者の負担はないのか? ルーターを保有し、オープンネットワークを作成するルーター保有者が多く生まれることもこのプロジェクトで大きな鍵となるため、ルーター保有者がオープンネットワークを作成する十分なインセンティブが必要です。 World Wi-Fiチームは、以下の仮定をしてルーター所有者の利益の試算を行っています。 広告当たりの一般的な料金:0.03$ 一日の接続回数:60回 1か月の平均日数:30.4167日 この場合、(1か月あたりの収益) = 0.03*60*30.4167 = 54.75$となり、平均的なネットワーク利用料である30$を大きく上回るため、十分インセンティブになり得ると考えられます。 プラットフォーム利用は簡単なのか? いくら優れたプラットフォームであっても利用するための敷居が高いと普及は難しく、頓挫してしまう可能性が出てきてしまうため、利用へのハードルの高さも見ておく必要があります。 World Wi-Fiチームはホワイトペーパーにて本プラットフォームのインターフェイスの簡便さを強く押し出しており、広告主の設定方法からルーター保有者のオープンネットワーク作成方法を記述しています。 ルーター所有者向けのルーターに合わせたそれぞれのソフトウェアの開発も進めていく計画を発表しており、このソフトウェアのインストールは数分で行えるほど手軽なものであると記載もあります。 POINTソフトウェア開発自体はまだ完了しておりませんが、ターゲットとなる市場やルーター保有者へのインセンティブを勘案しても、このプロジェクトの普及そして大きな成長は十分あり得ると考えられます。 World Wi-Fiの競合 「Wi-Fiをどこでも使えるようにする」というプロジェクトは他にもいくつかあり、代表的なものにはNEOベースのプロジェクトであるQlinkや、Softbankユーザーの方には馴染み深いFONなどが挙げられます。 Qlinkとの比較 Qlinkはブロックチェーンを利用することで、安全にルーターの所有者がWi-Fiを提供し、その見返りに利用者から報酬を受け取るというプラットフォームを作るプロジェクトです。 このプロジェクトでもWorld Wi-Fiと同様にWi-Fiを持たない人のネット利用が可能となり、どこでもネットワークにアクセスできるようになります。 Qlinkに対するWorld Wi-Fiの優位性World Wi-Fiでは広告主という特殊なプレイヤーを定義することで、ユーザーが無料でネットを利用できる環境を提供しており、ネットを利用できない貧困層へのアクセスを考慮しています。つまり、より多くのユーザーからのWorld Wi-Fiプラットフォームの利用が期待できると言えます。 Qlinkに対するWorld Wi-Fiの劣位性QlinkのCEOであるAllen Liは2012年にYou You MobileというWi-Fiレンタル会社を運営しているかなりの経験者です。ただし、チームの章で述べますが、World Wi-FiのCEOもすでに80都市でWi-Fiを利用した広告ビジネスを展開している経験者です。 FONとの比較 FONは今から13年も前、2005年からWi-Fiの共有コミュニティを作っているプロジェクトです。 FON専用のWi-Fiルーターを自宅に設置することで、他に専用ルーター設置をしている人のWi-Fiの利用が可能になるという、ルーターをお互いに貸し借りするようなサービスです。 FONに対するWorld Wi-Fiの優位性FONでは専用ルーターの購入が必要である一方、World Wi-Fiでは好きなルーターで共有が可能であるため、参入障壁が低いことが優位性に挙げられます。また、FONはブロックチェーンを利用しているサービスではなく中央集権的なサービスであり、運営会社によるサービス停止の可能性、FON専用ルーター価格の改定などのリスクがあります。 FONに対するWorld Wi-Fiの劣位性FONは非常に古いサービスであるため、すでに150か国2000万カ所での利用が可能であり、かなり根付いていることが優位点であると考えられます。しかし、現在のWorld Wi-Fiも3年後の2020年第4四半期にこの2000万という数字を目指しており、今後の普及次第では十分に達成できると述べられています。 World Wi-Fiのロードマップ 2018年の4月にプレセールが終了し、4月中には取引所に上場される予定と明記されています。 また2018年にはルーター向けのソフトウェアの開発も終了予定であり、プレセール終了後、迅速にプロジェクトが始動していくことが想像できます。 World Wi-Fiのチーム 本プロジェクトの共同設立者であるIlja JaschinとJan Sepiaschwiliは共にWorld Wi-Fiの前身となるWi-Fiを利用した広告ビジネスを手掛ける「Adrenta」と「Radius Wi-Fi」の共同設立者でもあります。 「Adrenta」と「Radius Wi-Fi」はすでに80都市を拠点として、100のパートナーシップを結び、14,000のオープンネットワークを抱える企業として活動を行っています。 POINT「Adrenta」と「Radius Wi-Fi」は2017年にWi-Fiアクセスポイントを784%も伸ばしており、このような成功経験故にWi-Fiに関するビジネスにおける課題の把握とその対策をホワイトペーパーに記載し、迅速なプロジェクト始動が行えると考えられます。 公式リンク Webサイト Twitter ホワイトペーパー Telegram ワンページサマリー Facebook ANNスレッド ICOの詳細 現在1WT=0.1$の価格でプレセール実施中で、投資金額に応じて下表の日程のボーナス分のトークンを受け取ることが可能です。 日程 2/17-2/23 2/24-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 5万ドル未満 15% 12% 9% 6% 5万ドル以上 25% 20% 15% 10% トークンセールはプレセール終了の2日後である3/18より1WT=0.1$で開催される予定ですが、こちらではプレセールのようなボーナスはありません。 総販売枚数:258,000,000トークン 未売却トークン:バーン有り ソフトキャップ:350万ドル ハードキャップ:2500万ドル 個人キャップ:200万ドル ※プロジェクトのICOへ参加される際には、自身でも利用規約やプロジェクト内容に関して十分理解をした上での投資を行いましょう。投資をおこない損失などが生じた場合、CRYPTO TIMESでは一切の責任を負いません。全て自己責任となります。


















 有料記事
有料記事


