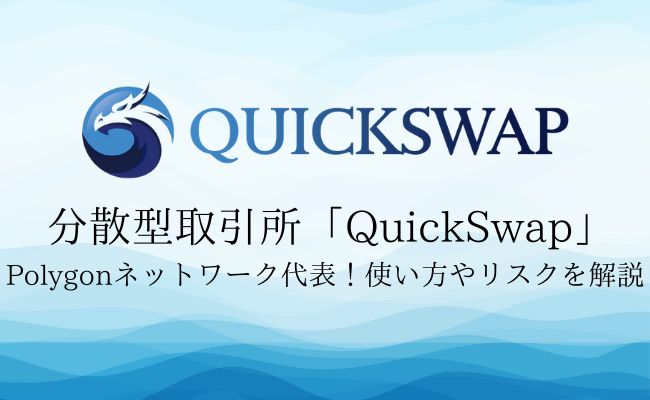
プロジェクト
2021/08/29分散型取引所「QuickSwap」の特徴や基本的な使い方を徹底解説!
QuickSwapは、MATICの取引をするなら絶対使うべき分散型取引所(DEX)です。 Polygonネットワークの代表的な取引所で、ガス代が安くなりトランザクションが通りやすくなるメリットがあります。 この記事では、QuickSwapの特徴や基本的な使い方、操作方法について解説します。 ファーミングに対応しており報酬として独自トークン「QUICK」を獲得できるので、LP提供とStakeの両方活用して報酬を受け取りましょう! QuickSwapの使い方はCryptoTimesの公式Youtubeチャンネルでも公開しているのでぜひチェックしてください。 QuickSwapとは?特徴や機能性を解説! 最初に、QuickSwapの特徴や機能について解説します。 QuickSwapは分散型取引所(DEX)なので、コインチェックなどの中央集権型のような管理者や仲介者は存在しません。 基本的に自分で管理する必要があり、操作するとスマートコントラクトで処理が行われます。 今までPancakeSwapなどのDEXを利用したことがあれば、使い方はほとんど同じですよ。 QuickSwapの特徴 Polygonネットワークを代表する分散型取引所 機能性はPancakeSwapやUniSwapと同じ トランザクション処理が早く通りやすい ガス代が圧倒的に安い イールドファーミングでQUICKを獲得できる Polygonネットワークを代表する分散型取引所 出典:https://awesomepolygon.com/dapps/ Maticネットワークは、Ethereumと互換性のあるブロックチェーンを目指すプロジェクトとしてPolygonネットワークにリブランドしました。 そのPolygonネットワークをメインとするDEXがQuickSwapです。 Polygonの公式サイトでもQuickSwapが紹介されています。 EthereumネットワークからPolygonネットワークに資産を移動して、QuickSwapなどのDappsを使うことで、スケーラビリティの高さやガス代の安さといったメリットに繋がる仕組みです。 機能性はPancakeSwapやUniSwapと同じ QuickSwapは、TokenSwap、流動性提供、ファーミング、IDOといった機能性があります。 有名どころのPancakeSwapやUniSwapとほとんど同じ機能です。 QuickSwapはPolygonネットワークですが、PancakeSwapはBSCネットワーク、UniSwapはEthereumネットワークですね。 トークンをQuickSwapに移動するには、Ethereumなどの異なるネットワークからブリッジする必要があります。 ブリッジで移動したトークンを使って、QuickSwapでLP提供やファーミングをする流れです。 分散型取引所プロトコル「Uniswap」の登録方法と使い方を徹底解説 トランザクション処理が早く通りやすい Polygon公式サイトでも紹介されていますが、QuickSwapはトランザクションが通りやすく、しかも高速です。 トランザクションが多く混雑するEthereumの問題解決も含めて開発されたネットワークなので、やはりスピードを重視しています。 少量のガス代で即座にトランザクションが通り、数秒あれば完了します。 ガス代が圧倒的に安い QuickSwapはガス代が圧倒的に安く優れています。 数円のガス代でも即座にトランザクションが通るので、この点もEthereumの問題解決につながったといえますね。 Ethereumネットワークでは高いときで数万円のガス代が発生するので、Polygonネットワーク系のQuickSwapでガス代を節約するユーザーは多いです。 ただし、ガス代は基本的にMATICで支払うので、事前に準備する必要はあります。 ブリッジのガス代は高い Polygonネットワーク上のガス代は安いですが、Ethereumからブリッジするときや戻すときのガス代は通常なので高くつきます。 イールドファーミングでQUICKを獲得できる QuickSwapでは、流動性提供して受け取ったLPトークンを使ってファーミングが可能です。 ファーミングすると独自トークンである「QUICK」を報酬として獲得できます。 LP提供とファーミングを併せて報酬を増やしましょう! この記事では、ファーミングの手順も解説しているのでチェックしてくださいね。 QuickSwapの基本的な使い方を解説! 実際に、QuickSwapの基本的な使い方や操作方法を解説します。 あらかじめMetaMaskをインストールしておく必要があるので、まだ入っていなければ公式サイトからアクセスして準備してください。 MetaMaskへPolygonネットワークを接続後、QuickSwapと連携してLP提供などを行うイメージです。 QuickSwapの使い方 【事前準備】PolygonとMetamaskの接続・MATICの準備 MetaMaskとQuickSwapを連携させる TokenSwapする方法 流動性提供する方法 ファーミングする方法 ClaimしてQUICKを受取る LPを解除してトークンを戻す 【事前準備】PolygonとMetamaskの接続・MATICの準備 事前準備として、MetaMaskへPolygonネットワークを接続する必要があります。 方法については、「METAMASKでのMatic(Polygon)ネットワークへの接続方法を解説」でまとめているのでチェックしてください。 MetaMaskにPolygonネットワークを追加後、MATICトークンを送っておく必要があります。 手数料をMATICで支払う必要があるためです。 CryptoTimesの公式Youtube動画でEthereumネットワークからPolygonネットワークへのブリッジ方法を解説しています。 「Matic(Polygon)ネットワークに通貨を転送」 こちらの記事内でも簡単に手順をまとめているので参考にしてください。 MetaMaskの準備・Polygonネットワークとの接続・MATICの転送といった3つの事前準備が揃うことでQuickSwapの利用を開始できます。 MetaMaskとQuickSwapを連携させる QuickSwapとMetaMaskを連携させるので、QuickSwapの公式サイトへアクセスします。 右上の「Connect Wallet」をクリックするとMetaMaskが開いて連携されます。 自分のアドレスとMATICの残高が表示されると連携完了です。 事前準備するとき、MetaMaskにPolygonネットワークを接続した時点で自動的に連携されている場合もあります。 TokenSwapする方法 QuickSwapでTokenSwapするとき、トップページがすでにSwapするページになっているので分かりやすいです。 交換元のトークンと交換先のトークンを選択してください。 画像ではUSDCをDAIにSwapしています。 「Approve USDC」をクリックしてコントラクトを承認しましょう。 MetaMaskが開くのでガス代を選択するのですが、基本的にガス代を増やさなくてもQuickSwapはトランザクションが通りやすいのでデフォルトでOKです。 もう一度USDCとDAIを選択して、「Swap」をクリックします。 「Confirm Swap」をクリックすればToken Swapは完了です。 ほとんどの場合ガス代は1円以下となっており、とても割安でSwapすることができます。 流動性提供する方法 QuickSwapでファーミングするにはLPトークンが必要です。 まず、流動性提供してLPトークンを獲得しましょう。 画像のように「Pool」をクリックして「Add Liquidity」と進んでください。 画像ではDAIとUSDCを提供します。 それぞれのトークンが1:1になるように調整しましょう。 残高に合わせて片方の数量を入力すると自動で1:1になります。 「Approve」をクリックして承認後、「Supply」へ進んでください。 Confirmすれば流動性提供完了です。 これでLPトークンが発行されます。 ファーミングする方法 QuickSwapの「Rewards」をクリックしてファーミングします。 ファーミングするペアのプールを選択して「Deposit」してください。 画像ではDAIとUSDCのペアです。 「Deposit」をクリックして承認後、ファーミングする数量を入力して、「Approve」します。 承認すればファーミング完了です。 ClaimしてQUICKを受取る ファーミングしたpoolでClaim(収穫)すると、QuickSwapが発行する「QUICK」トークンを報酬として受け取ることができます。 画像のように「Claim」をクリックしてください。 MetaMaskが開くのでトランザクションを確認して進みます。 これでClaim完了となり、ウォレットにQUICKが付与されているのでチェックしましょう。 ファーミングの解除方法 ファーミングの解除は「Withdraw」をクリックすればOKです。QUICKとLPトークンの両方がウォレットに入ってきます。 LPを解除してトークンを戻す QuickSwapの流動性提供を解除して、2つのトークンをウォレットに戻す手順も知っておきましょう。 「Pool」をクリックするとLP提供したプールが表示されるので選択してください。 画像ではUSDCとDAIのペアです。 「Remove」をクリックするとこのような画面になります。 解除する数量をパーセントで選んでください。 もう一度「Remove」→「Comfirm」と進んで、MetaMaskでトランザクションを確認すれば完了です。 トランザクションは適宜高速化する Removeしてなかなかトランザクションが通らないことがあります。MetaMaskでガス代(Gwei)を上げて高速化することも可能です。 QuickSwapを使う3つのリスク・注意点を確認しよう QuickSwapでは、流動性提供とファーミングにより、LPトークン・ガバナンストークンといった報酬を獲得できます。 トークンのペアによっては価格が上がり、利益が大きくなる可能性がありますが、その分リスクも伴います。 ここでは、QuickSwapを使うなら知っておくべき3つのリスク・注意点を解説するので、ぜひ目を通してくださいね。 QuickSwapのリスク・注意点 インパーマネントロスが発生する可能性 APYが高いほどリスクも上がる トークンの価格が暴落する可能性 1. インパーマネントロスが発生する可能性 QuickSwapだけでなく、PancakeSwapなどDEXに共通していることですが、流動性提供した後はインパーマネントロスが発生する可能性があります。 インパーマネントロスとは、預けていたトークンを手元に戻すとき、ホールドしているときよりも価格が下がっていることです。 トークンの価格変動があれば、流動性プール内では割合を1:1にするための調整が行われます。 流動性提供を解除して手元に戻すときは、Pool全体の割合でトークンが返却されるため、価格変動があればほぼ必ずロスが発生する仕組みです。 ホールド時と解除時の残高は変動することを忘れないでください。 それでもDEXが人気な理由とは インパーマネントロスを考慮しても、イールドファーミングで得られる報酬が上回っているので人気があります。高リスクなAPY100%以上も多く存在します。 2. APYが高いほどリスクも上がる QuickSwapでファーミングするとき、Reward(報酬)としてAYP(年利)が表示されているのでチェックすると思います。 このAPYが高いほど、インパーマネントロスが多く発生する可能性が高いので注意してください。 もちろん、利益が多くなるメリットはありますが、その分リスクがあります。 例えば、画像のように400%越え、1,000%越えのプールがありますが、これらは価格変動が激しく、単純に利益が増えるだけではなくロスも激しいと覚えておきましょう。 3. トークンの価格が暴落する可能性 QuickSwapで流動性提供するとき、2つのトークンをペアでPoolします。 預け入れている最中にトークンの価格が暴落すると、大幅なインパーマネントロスに繋がるかもしれません。 担保がないマイナーなトークンであればボラティリティに波があり下落の可能性も高いです。 USDCなどのステーブルコインは暴落しにくく安全なので、安定してLP提供するにはおすすめですよ。 TITANの大暴落について 2021年6月にTITANが1日で42億分の1まで大暴落して無価値となりました。$65の価値がほぼゼロとなり、資産を失ったトレーダー多かった事件です。 まとめ QuickSwapの基礎知識や基本的な使い方、リスクを解説しました。 今までUniSwapなどのDEXを使ったことがあれば、機能的にほとんど同じなので感覚で使いこなせると思います。 MATICでガス代を支払うため、事前にウォレットに入れておく必要があり、Swapやブリッジが必要な点は注意が必要です。 ただ、Polygonネットワークを使っているためガス代が格安であり、トランザクションが高速なのはメリットといえます。 ファーミングで賢く報酬を獲得できるQuickSwapを使いこなしましょう。 QuickSwapはこちら QuickSwapの使い方Youtubeはこちら

プロジェクト
2021/08/26NFT特化のDAO「Flamingo DAO」のメリットとは?
NFTが世の中に注目されている昨今で、NFTを共同資産として扱うDAOも増えてきました。 今回の記事では、NFTに特化したDAOであるFlamingo DAOについて基本的な特徴を解説していきます。 Flamingo DAOとは Flamingo DAOはNFTに特化したDAOで、所有可能なブロックチェーンベースの資産に対する投資機会を探ることを目的としている組織です。 Flamingo DAOのメンバーは保有するNFTを貸し出したり、保有したり、デジタルアートギャラリーに展示したり、他のDeFiプラットフォームの担保として利用したりすることができます。(DAOの基で) 基本的にDAO組織なので、メンバー投票のもとにどういった方向性でNFTを活用していくのか?購入していくのかが決まってきます。このことから、様々な方向に進化していく可能性があります。 参加条件(一部) 最大メンバー数:100名 身元確認あり(KYCなど) 法人、個人の年収ハードルあり 誰でもこのFlamingo DAOに参加できるわけではなく、メンバー数、身元確認、最低年収の条件などがあります。これらの条件を満たした後にフラミンゴユニットを購入する必要などがあります。 一般的な方だと正直入りにくいDAO組織となっていますが、高額なNFTを集団で扱うことになるので、このようなハードルを設けることは必然的なことです。全ての条件を満たしていたとしても、メンバーの空きがない場合は、もちろん加入ができない仕組みとなっています。 コレクション Flamingo DAOのHPに行くと、現在所有しているNFTのコレクションを確認することができます。たくさんのコレクションがあるので、ここでは一部だけ紹介します。 CryptoPunks - 215 Wrapped CryptoPunks - 3 Meebit - 286 Bored Ape Yacht Club - 22 Autoglyph - 5 Hashmasks - 5 Somnium Space Land - 4 Flamingo DAOが所有するNFTは有名どころのNFTがたくさん揃っており、CryptoPunksのような高額なNFTアセットを200以上も所有できているのは、DAOならではの動きです。 コレクションを見ている中で、最も意外だったのが「Somnium Space Land」を4つ所有しているところです。Somnium Spaceは、DecentaralandやCryptoVoxelsのような仮想現実のプロジェクトで、そのランドを4つFlamingo DAOは所有しています。 現在のプロジェクトの進み具合やコラボ実績などを考えると、Decentaralandのランドが最も強いため、所有するならDecentaraland一択な気がしますが、Flamingo DAOはSomnium Spaceを購入しています。この辺り、どのような提案、投票、議決があって購入されたのか、とても気になるところです。 他のコレクションについては下記のURLから拝見できるので、チェックしてください。 Flamingo DAO コレクション NFT DAO参加メリットは情報か? 正直、この記事を執筆するまでは、NFTに特化したDAOへの参加メリットをあまり感じていませんでした。しかし、Flamingo DAOを調べていくうちに参加のメリットは「情報」なのでは?と感じています。 Flamingo DAOに参加するメリットは、「収益分配」「購入リスクの分散」などが基本的なこととして思いつくことが考えられます。 高いNFTを1人で購入するより、共同で購入した方がリスクの分散にはなります。しかし、ユースケースのないNFTを共同で購入することの直接的なメリットは、売却益の分配以外は参加者に大きく影響しないと考えていました。 「収益分配」「購入リスクの分散」の2つより大きいメリットとして、どのようにNFTに対してメンバーが考えているのか?どういったプロセスを踏んで、購入まで至っているのか?この「情報」がメリットとして大きく働いているのではないか?と考えられます。 「情報」にメリットがあるというのは、そのコミュニティが参加者にフィットしていることが前提とありますが、自分と同じような年収などのメンバーが在籍している可能性があるので、参加ハードルを設けているFlamingo DAOのような組織に同じ属性の人間がいる可能性が高いと考えられます。もちろん、参加するDAOの見極めはとても重要となってくるでしょう。 まとめ 今回はFlamingo DAOに関しての基本的な解説となりました。 正直、全てを調べきれていない部分や実際にFlamingo DAOに参加ができていないため、わからないところもあります。 DAOという組織形態は、NFTが流行るずっと前からあるので、今後も予想をしない発展をしていく可能性があります。 今回はFlamingo DAOについて、書いていきましたが他にもDecentralandで建物を構えているAladdin DAOなどもありますので、気になる方は調べてみてはいかがでしょうか。 記事ソース:Flamingo DAO 画像:shutterstock
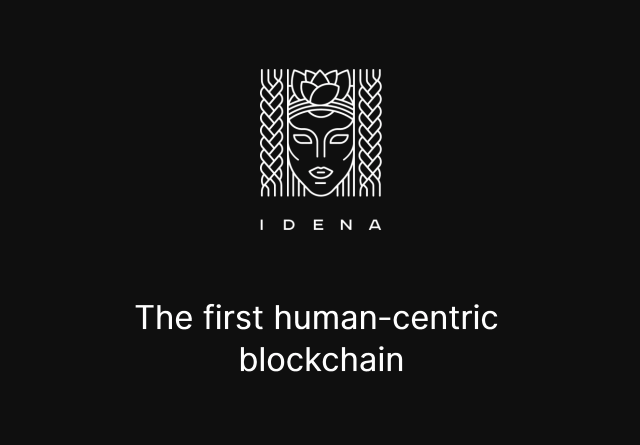
プロジェクト
2020/12/11権力の集中を防ぐ公平性重視のブロックチェーン「Idena」とは?
Idena(アイデナ/$DNA)は、ノードを一個人にひとつまでに限定することで権力の集中を防ぐ画期的なブロックチェーンプラットフォームで、プライバシー保護やボット耐性が重要な分野でのユースケースが期待されています。 Idenaの最大の特徴は 個人情報を開示せずにユーザー確認ができる。 ノードは一人ひとつまで。一般的なスペックのPCで動く。 公平なブロックチェーン。プライバシー保護やボット耐性に長ける。 という3つの点にあります。 こちらのページでは、これらについて詳しく解説するとともに、トークンやシステムのユースケースも紹介していきます。 ※本記事は暗号資産への投資活動を推奨し、勧誘するものではありません。 Idena(イデナ)とは?概要を紹介 −Idenaの概要− 通貨名/ティッカー Idena(イデナ) / $DNA 創設者 匿名グループ 時価総額 約330万ドル (2020年12月時点) 特徴 個人情報不要の本人確認システム 公式リンク Webサイト Medium Twitter Telegram GitHub Reddit Discord Idenaが解決する問題 [caption id="" align="aligncenter" width="480"] ビットコインのマイニングプールが占めるハッシュレートの割合[/caption] Idenaはシャーディング技術を搭載したスケーラブルなブロックチェーンです。 ですが、最大の特徴はスケーラビリティではなく、ブロックチェーンプラットフォームとしての「公平さ」を追求している点にあります。 集権型システムと対比されるブロックチェーンですが、Idenaが収集したデータによると、昨今の現状はどうも完全な分散型システムとは言い難いものになっています。 PoWを採用したブロックチェーンの代表格・ビットコインでは、19のマイニングプールがハッシュレートのほとんどを占めています。 そのうちの80%が中国のプール、そしてハッシュレートの51%はたった3つのプールで構成されているというのが現状のようです。 PoSに至っても現状は同じで、イーサリアムではたった400のウォレットがETH供給量の53%を保有しています。 その他のコンセンサスメカニズムに関しても、ブロック生成・承認者が少数に限られているケースがほとんどで、「権力のある一定層がどんどん力を増していく」状況になっていることがわかります。 Idenaは、こうしたブロックチェーンの「権力の集中化」問題を解決し、コンピューティングパワー(=財力)に依存しないフェアなシステム構築を目指しています。 ネット上の監視とボット社会 [caption id="" align="aligncenter" width="638"] 「信用スコア」の低いユーザーはWeChatのマップ上に表示される[/caption] また、Idenaはインターネット上でのプライバシーの欠如や監視システムを革新するというビジョンも持っています。 近年では、WeChatやFacebookなどの大手IT企業が独占的に膨大なユーザー情報を抱えており、顔写真や経済状況などのデータがヒトやお金の監視に利用されています。 また、大量のボットによる情報操作行為が政治やビジネスの分野に大きな悪影響を与えていることも大きな問題となっています。 Idenaは、公平性を重視したブロックチェーンを開発することで、このようなネット上の社会問題も解決できるとしています。 Idenaの特徴 Idenaに組み込まれている「Proof of Person (PoP)」は、個人情報の開示を必要とせずに個人(一人の人間であること)を確認できるシステムです。 このシステムをブロックチェーンに組み込むことにより、公平なエコシステムの構築が可能となります。 また、システムの特性上、個人情報を守ったアプリケーションやサービスの展開がしやすいという利点も生まれます。 公平性・プライバシー・ボット耐性などの観点でこういった「人間証明システム」の必要性は強く認識されており、イーサリアム創設者のヴィタリック・ブテリン氏もブログにその需要を綴っています。 https://twitter.com/VitalikButerin/status/1246567822974750722?s=20 では、ブテリン氏もその重要性を強調しているPoPとはいったいどういう仕組みなのか見ていきましょう。 Proof of Person (PoP) Idenaでは、一個人につきひとつのノード(およびウォレット)が割り当てられます。そのため、ブロック生成権の獲得において誰かが優位に立つことはできません。 このシステムを可能にするのが、PoPになります PoPでは、ノードの持ち主それぞれが「人間であること」を証明するために、「フリップ(Flip)」と呼ばれるパズルを解きます。 フリップはコンピュータには解きにくく、人間にしか解けないような仕組み(後述)になっています。 肝心なのはこのフリップがあらかじめ決められた時間に「一斉に」行われることです。 回答に設けられた時間はとても短いため、人間が複数ノード分のフリップを一気に解くことはできません。したがって一個人による複数ノードの管理は難しくなります。 [caption id="" align="aligncenter" width="533"] フリップはあらかじめ決められた日程で世界同時に行われる[/caption] こうして持ち主が「一人の人間であること」を証明できたノードは、ブロックやフリップの生成等に携わり、対価としてDNAトークンを得ることができます。 そして、ノードは一般的なコンピュータ(将来はスマートフォンも)で動作するように作られているため、他のブロックチェーンで目立つ参入障壁の高さも改善しています。 人間であることを証明する「フリップ」 フリップは様々なサービスで利用されている「CAPTCHA」に似た、適切な画像を選択して人間であることを証明する仕組みです。 フリップがCAPTCHAよりも優れているのは、複数画像に示されている物体だけでなく、その画像間の「コンテクスト」も理解する必要があるという点です。 [caption id="" align="aligncenter" width="405"] フリップの一例[/caption] 上記のフリップでは同じ4枚の画像が縦二列に、異なる順序で並んでいます。ユーザーのタスクは、この二択のうち「よりストーリーが繋がっている」ほうを選択することです。 左側の場合「花瓶をネコが倒したので、こぼれた水をスポンジで吸い取る」といったストーリーが連想できます。 一方、右側の場合はあまりピンとこない並び方になっています。 こういった要領で世界中の人々がこのフリップを一斉に回答するわけですが、そのうち「より多く選ばれた方」が正解となります。 フリップは人間であれば10秒ほどで解くことができ、その正解率は95%近くになります。一方、人工知能は未だ類似したテストで最高79%しか達成していません。 Idenaはフリップで71%以上の正解率を出せる人工知能を開発したチームに最大55000ドルの賞金を与える「フリップチャレンジ」も開催しています。 ノードの役割と消滅条件 Idenaノードは招待制になっており、エポックごとの招待の生成数もあらかじめ決められています。 招待を受けた「新規ノード」は早速マイニング(後述)に参加することができ、それとともに「フリップを作成する義務」と「フリップに参加する義務」が課せられます。 新規ノードがフリップに参加しなかった場合、そのノードはその場で消滅します。 一方、一定数以上のフリップを回答したノードは「承認済みノード」または「人間ノード(正答率92%以上)」とみなされ、新規ユーザーを招待できるようになります。 これらの二つのノードはフリップを連続2回まで欠席することができ、それ以上逃すと消滅となります。 また上述の通り、ノードは回答セッションまでにフリップを作成する義務もあり、未提出は欠席と同じ扱いとなります。 Idenaのユースケース Idenaは個人情報の開示を必要とする本人確認(KYC)をせず、ノードの持ち主が一人の人間であることを証明できるシステムです。 この利点は様々な分野での活用が見込まれており、公式ウェブサイトではたくさんの例が挙げられています。こちらではそのうちのいくつかを紹介します。 投票システム ブロックチェーンでの従来の投票システムは、トークンのステーク量に応じて投票権を得られるシステムが一般的なため、個人間で投票への影響力に差が生じます。 一方、Idenaではフリップを介してノードひとつひとつが個人であることを証明できるため、「一人一票」の公平な投票システムを構築することができます。 オラクルの選定 ノードが行う様々な仕事のうち、外部からのデータをスマートコントラクトにインプットするものを「オラクル」と呼びます。 ここで、スマートコントラクトを正常に動作させるために、オラクルには質や信憑性の高い情報を提供してもらわなければいけません。 Idenaでは承認された個人がノードを運営するため、オラクルに割り当てられたノードをそのデータの質などに応じて評価することができます。 ダイレクトマーケティング ボットがはびこるウェブ広告・マーケティングの分野でも、Idenaの活用を想定することができます。 広告主がIdenaのDNAトークンをバーン(焼却)することで、ひとつのアカウントが一人の人間であることが証明された「ユニークユーザー」に対して広告を打つことができます。 こうすることで広告主はボットに煩わされることなくエクスポージャーを得ることができます。 また、広告の需要に応じてDNAが買い付けられるため、トークンエコノミーの循環も予想されます。 以上の他にも、サーバーを必要としないメッセージアプリや、ベーシックインカム制度の基盤など、「個人情報を開示せず一人の人間であることを確認できること」そして「ボットによるシステムの悪用を防げること」を利用した様々なユースケースが期待されています。 Idenaトークンについて −DNAトークンの概要− 発行上限 なし 1日あたりのマイニング報酬 25,920 DNA 1日あたりの承認報酬 25,920 DNA ブロック プロポーズ報酬 2 DNA ブロック コミット報酬 4 DNA トランザクション手数料焼却率 90% トークンにまつわるその他の情報はこちらから マイニングや承認作業で得られたトークンの20%は自動でステーキングされ、ノードを自発的に終了するまで取り出すことができないようになっています。 ノードへの参加(=マイニング)は前述の通り招待制となっています。公式のTelegramグループでは定期的に招待を行なっているようです。 ノードのクライアント(およびウォレット)自体は公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。 まとめ Idenaはこれまでのブロックチェーンが抱えてきた「権力の集中化」や、大型IT企業が生むネットでのプライバシー、ボット問題の解決に臨む画期的なブロックチェーンプラットフォームです。 「特定時間でのアクションが求められる」という斬新なシステムがエコシステムの普及にどう影響してくるかには要注目でしょう。 また、KYCを要しない個人特定システムは、プライバシーやボット耐性が必要とされる分野での活躍することが期待できます。 Idenaについてもっと知りたい方は、各種公式チャンネルへのリンク(上の概要に飛ばす)をぜひチェックしてみてください。

プロジェクト
2020/09/22Crypto Kitties開発チームが提供するエンターテイメント業界に特化したパブリックチェーンFlow Blockchain、優位性から今後の考察まで
Flow Blockchainは高速・分散・デベロッパーフレンドリーの3点を特徴とするゲームに特化したパブリックブロックチェーンです。 CryptoKittiesのチームにより開発が進められており、次世代のゲーム、アプリケーション、デジタル資産の管理に最適なインフラとなることを目指しています。 Flowは既にNBA(National Basketball Association)やUFC(Ultimate Fighting Championship)など、世界的な団体とのコラボを通じてコンシューマー向けのプロダクトを提供している点も注目すべきポイントの一つであると言えます。 本記事では、Flow Blockchainの概要や特徴、優位性などに関して包括的に解説していきます。 Flow Blockchain 概要と特徴 Flowはオープンワールド向けの次世代ブロックチェーンです。 2019年11月、CryptoKittiesの開発チーム"Dapper Labs"は、Warner Music Group, Union Square Ventures, a16zらから1120万USD相当の出資を受け、『Flow Blockchain』の開発に着手し始めました。 この背景には、CryptoKittiesが直面したガス代の高騰や、NFTのコミュニティ内でスケーリング問題に直面している点、コンシューマー向けのレイヤー1ブロックチェーンが存在しない点などが挙げられます。 Flow Blockhainは以上の問題を解決するべく、高速・分散・デベロッパーフレンドリーで初のコンシューマー向けブロックチェーンとして次世代のゲームをホストすることを目標に一から開発が始まりました。 これらの目標を実現するために、Flowは以下のような特徴を持ちます。 スケーラビリティ問題の解決へのユニークなアプローチ 従来のブロックチェーンにおいては、すべてのノードがネットワークのステート(状態)を保管し、トランザクションを処理するために必要とされる処理を行う必要がありました。 そのため、必然的にスループット(単位時間当たりの処理件数)の低下を余儀なくされます。 他方、一般的に知られるスケーラビリティの課題解決へのアプローチとしては、Sharding(シャーディング)やLayer 2(レイヤー2)技術などの活用が模索されていますが、ゲーム間のComposability(構成可能性)の側面ではこれは有用ではありません。 Flow Blockchainではこれらの技術のデメリットを徹底的に分析し、シャーディングに頼らない、マルチロール型のノード設計によりスケーラビリティの課題を解決するとしています。 マルチロール型の設計では、ノード(ネットワーク管理者)の役割が以下の4種類に分類されます; コンセンサスノード ブロックチェーン上におけるトランザクションの有無・順序を決定 検証ノード 実行ノードの状態をチェック 実行ノード 各トランザクションに関連する必要な計算処理を行う コレクションノード DApps向けにネットワークのコネクティビティ、データの可用性を強化 Flow Blockchainでは、従来のノード設計で必要とされてきた、ノードとしての多くの役割を4つの異なるロールに分割することで、各ノードの負担を軽減しながらパフォーマンスの向上を図ります。 [caption id="" align="aligncenter" width="1167"] onflow.orgより引用[/caption] 一見すると複雑な設計に見えますが、プロトコル部分が複雑さをカバーすることで、アプリケーションの開発者が容易に多機能かつ使いやすいアプリケーションをビルドすることができるようになります。 アップグレード可能なスマートコントラクト スマートコントラクトの最も重要なポイントとして、ユーザーがスマートコントラクトのAuthor(記述者)ではなくコード自体を信頼することができる点が挙げられます。 ブロックチェーンの持つこうした特徴により、いまだ実現されていないようなオープンサービスやComposabilityの特徴を活用した新たなサービスをアンロックすることができるようになります。 Flow Blockchainでは、スマートコントラクトを"β版状態"としてメインネットに実装することができます。 このβ版状態のコントラクトは、オリジナルの記述者によりアップデートが可能な状態にあるスマートコントラクトを指します。 ユーザーは、スマートコントラクトがβ段階であることを通知され、記述者を信頼しコードにアクセスするか、コードがファイナライズされるのを待ちファイナライズ後にアクセスするかを選択する権限が与えられます。 高速かつ決定論的なファイナリティ Flow Blockchainでは、Proof of Work(PoW)などにみられる確率的なファイナリティとは異なる、決定論的なファイナリティが数秒の間に実現されます。 決定論的なファイナリティはProof of Stake(PoS)のブロックチェーンなどにおいて既に実現されていますが、ユーザビリティを重視するコンシューマー向けブロックチェーンであるFlowでは、高速かつ決定論的なファイナリティが重要です。 Flowでは、一連のプロセスはローンチ段階で10ブロック(約10秒)程度とされており、ユーザーはトランザクションの送信後、ほぼ即座にフィードバックを得ることができます。 開発者フレンドリーなプログラミング言語『Cadence(ケイデンス)』 Cadence(ケイデンス)は、Dapper Labsが開発した初の人間工学的なリソース指向のスマートコントラクト言語です。 既存のプログラミング言語は、デジタル資産の所有権を追跡することが可能である一方、これは所有権の反映において利用され、直接的に所有権を定義することができません。 Cadence(ケイデンス)を利用することで、言語そのものによって所有権を定義することが可能となり、これにより様々なカテゴリーのアプリケーションを新たにアンロックすることができるとしています。 大手企業・プロダクションとの強力なパートナーシップ コンシューマーへのアドプションをゴールとするFlowは、技術面だけでなくバックアップ面においても強力なパートナーシップを締結しています。 提携先はNBA, UFCなどの米国国内で最大級のスポーツ団体から、UBISOFT, Dr.Seuss, Warner Music Group, Samsungなど世界各国のプロダクション、大手企業が中心となっています。 ここで注目すべきは、これらの団体・企業は既にエンターテイメント分野における大きなユーザーベースを持つ点です。 以下で紹介するNBAの公認ゲームである『NBA TOP SHOT』をはじめとして、既存の産業からコンシューマーに対してブロックチェーンゲームをアプローチしていく姿勢が伺えます。 Flow Blockchainを活用したプロダクトの紹介 Flow Blockchainは上述の通り、ブロックチェーンゲームの開発者・ユーザーエクスペリエンスに特化したブロックチェーンです。 開発チームであるDapper Labsは『CryptoKitties』の成功を実現しましたが、Consumer-Ready(一般の消費者が利用可能な)なブロックチェーンとして、既にユニークなプロダクトをリリースしている点も注目すべき点の一つです。 以下にFlow Blockchainを利用したプロダクトをいくつか紹介していきます; CryptoKitties(クリプトキティーズ) 『CryptoKitties』はブロックチェーン上でデジタルの猫を自由に交配させることで、世界に一匹だけのユニークな猫を生み出すことのできるコレクティブル向けゲームです。 世界で最も成功したブロックチェーンゲームとして知られる『CryptoKitties』は、当初Ethereumブロックチェーンのみで実装されていましたが、その人気からEthereumブロックチェーンのかつてない混雑を引き起こしました。 その後2020年5月、『CryptoKitties』はFlow Blockchainへの移行(対応)を正式に発表しました。 CryptoKitties公式サイト NBA Top SHOT 2020年5月に発表された『NBA TOP SHOT』は、試合中の選手のプレイをNFT化してマーケットプレイスなどで売買することができるNBA公認のゲームです。 Flow BlockchainはNBAとも公式の提携を発表しており、β時点で22,000以上のパック、総額$1.2M USD以上の売り上げを記録していることからも、Flowの掲げるコンシューマーアドプションを十分に達成できるポテンシャル、また注目度の高さがうかがえます。 8月には、NBAに属するプレーヤーからも直接の出資を受けており、約$12M USDの調達に成功しています。 NBA TOP SHOT公式サイト Dapper Wallet Dapper WalletはGoogle Chromeの拡張機能・Androidのアプリとして利用することができるFlow Blockchainのウォレットです。 『NBA TOP SHOT』や『CryptoKitties』などのFlow Blockchain上のDAppsに限らず、MetamaskのようなEthereumのウォレットとしても機能する点が特徴です。 Dapper Wallet公式サイト チームメンバー Chief Executive Officer (CEO) - Roham Gharegozlou氏 Roham氏は、CryptoKitties、Flow、NBA Top Shotの生みの親であるDapper LabsのCEOです。彼はスタンフォード大学で経済学の学士号と生物科学の学士号と修士号を取得しています。 Dapper Labsの以前には、Axiom Zenの創設者兼CEOを務めていました。CEOを務めていた6年間で、2人のチームメンバーから80人のチームメンバーに成長させ、RoutificやZenHubを含む4つの独立したビジネスをスピンアウトさせた経歴を持ちます。 Chief technology Officer (CTO) - Dieter Shirley氏 Dieter氏は、新たに登場する技術の中でも特に第一線のクリプト周辺技術の開発に携わってきました。彼は、CryptoKittiesの共同設立者であり、Ethereum上のNFT(Non-Fungible Token)を定義したERC-721の提案を執筆した人物でもあります。 CryptoKitties以前は、Roham氏と同じくAxiom Zenでチーフアーキテクトを務めていました。それ以前は、iPhoneエコシステムの初期のプレイヤーの1つであるAtimiで6年間開発責任者を務め、Appleでシニア・ソフトウェア・エンジニアを務めた経験も持ちます。彼はウォータールー大学でコンピュータサイエンスの理学士号を取得しています。 Chief Business Officer(CBO) - Mikhael Naayem氏 Dapper Labsの立ち上げに携わる以前、Mikhael氏はAxiom Zenの創業時から取締役を務めていました。彼は2017年10月にAxiom Zenにフルタイムで入社しましたが、それはCryptoKittiesのローンチの1ヶ月前でした。 Axiom Zenにフルタイムで入社する以前は、Mikhael氏は2017年に香港で、同じくゲーム会社であるAnimocaへの事業売却までの段階で2.25億人以上のユーザー数へと成長を遂げたLive-opsゲーミングプラットフォーム『Fuel』の創設者兼CEOを務めていました。Fuelの顧客には、セガやバンダイナムコなどが含まれていました。Mikheal氏は学生時代、コロンビア大学で工学の学士号と修士号を取得しています。 Chief Financial Officer(CFO) - Alex Shih氏 Alex氏は、Axiom Zen と Dapper Labs の CFO であり、戦略的財務機能をリードしています。また、Dapper Labs と ZenHubの取締役も務めています。 Axiom Zen に入社する以前は、KKR と Highfields Capital で 10 年間、公開市場と非公開市場の両方で資本構造全体の投資戦略を実行し、直近ではプライベート・エクイティ部門のリーダーを務めました。学生時代には、スタンフォード大学で経営科学と工学の理学士号と修士号を取得しています。 Flow Blockchain 直近の動向とトークンセール詳細 Animoca BrandがFlow Blockchainを採用 9月22日、香港に拠点を置くモバイルゲーム制作会社"Animoca Brand"は、『Star Girl』及びMotoGP™公認ゲームの2タイトルをFlow Blockchain上で開発・リリースしていく旨を発表しました。 『Star Girl』はAnimoca Brandが提供する人気ゲームの一つで、100万人以上のMAU, 18万人以上のDAUを抱えています。 また、MotoGP™は最も長い歴史を持つモータースポーツの世界的な大会であり、Animoca BrandはMotoGP™公認のブロックチェーンゲームの開発をFlow上で進めていると発表しました。 Flow Blockchain上での各タイトルのリリース次期に関して、Star Girlは2021年、MotoGP™は初期バージョンの公開を2020年Q4, 正式バージョンのリリースを2021年の予定としています。 Animoca Brand公式サイト 9月22日~10月2日 Coinlist上でトークンセールの実施 9月22日から10月2日にかけて、Flow BclockchainのFLOWトークンのコミュニティセールがCoinList上で実施されています。 FLOWトークンはメインネットのリリース後、Flowネットワークのネイティブ通貨として機能し、ステーキングやオンチェーンガバナンス、トランザクション手数料の支払いなどで利用されます。 販売レートは$0.10USD/FLOW、参加上限は一人$1,000USDとなっており、日本の居住者はCoinList上でパスポートや運転免許証を利用したKYCのプロセスを完了することでセールへの参加が可能となります。 今回の販売レートは、過去に行われたプライベートセールと同レ―トに設定されており、さらに参加上限を一人$1,000USDとすることでより広範なコミュニティを築き上げることを目的としています。 セール終了後、購入したトークンの50%は1年間のロックアップ、残りの50%は1年間のロック後さらに1年をかけて徐々にロックが解除される仕様となっている点にご注意ください。この期間もステーキングやガバナンスに参加することは可能です。 トークンセールの詳細は以下のリンクから確認することができます; FAQ - onflow.org Flow Community Sale - CoinList Flow Blockchainの優位性と今後の予想 Flow Blockchainの開発チームによる『CryptoKitties』は、2017年末に直面したEthereumネットワークにおけるガス問題はコンシューマーレベルでの運用にとって大きな課題であるとし、NFTに特化したチェーンであるFlowへの移行を発表しました。 本記事でも紹介した通り、FlowではNBAやUFC, Warnerなど世界的なプロダクションとも強力な関係を築きつつあります。 本項では、NFTをとりまく業界の現状を簡単に紹介し、Flow上に発行されるNFTがどのような優位性を持つのか、将来的にNFTがどういった方向で使われていくのかを整理していきたいと思います。 NFT黎明期のユースケース(2017~18年) チームメンバーでも紹介した通り、NFTの火付け役として最初のユースケースを市場に投入したのは、Flow BlockchainのチームによるCryptoKittiesになります。 Kittiesは、唯一無二のデジタル猫をNFTとして表現することで、各トークンがそれぞれ固有のパラメーター・希少性を持つユニークなコレクタブルアイテムとして表現することに成功しました。 CryptoKittiesで記憶に残っている点として、その爆発的な火付けからトランザクションが大量につまり、ETHのガスコストが非常に掛かったことが挙げられます。 https://twitter.com/CryptoKitties/status/937444644740198400?s=20 この、CryptoKittiesが火付け役となり、コレクタブルとしてのユースケースは、KittiesにとどまらずNFTを利用したカードゲームである『Gods Unchained』、日本国内からも『My Crypto Heroes』や『Contract Servant』、Kitties同様のコレクタブル方面では『くりぷ豚』などが登場し、大きな話題となりました。 デジタル空間における所有権の表現(2019~20年) 2019年はアクティブユーザーこそ、Kittiesや0x Universe, My Crypto Heroesなどのコレクタブルに集中していましたが、メタヴァース空間内での土地がNFT化され資産価値を生むというユースケースが続々と登場しました。 中でもDecentraland (LAND), CryptoVoxels (CVPA), Somnium Space (PARCEL)などが主要なメタヴァース系プロジェクトとして知名度を高めていますが、2020年現在はDecentralandのが市場をドミネートしています。 また、NIKEのEthereum上に発行されるNFTを利用したスニーカーのトークン化するための特許を発表したことや、VeChainを利用した中国製のサージカルマスク『KN-95』の真贋証明にNFTが利用されたことからも、生活の中にみられるNFTのユースケースが徐々に拡大しつつあることが分かります。 プロスポーツチームとの協業も様々な場所で進められており、『Sorare』はスペインのプロサッカーチーム『Real Batis』とコラボNFTカードを発行するなど、スポーツにおける活用も進められています。 NFTとDeFiの統合(現在~) 2020年Q3以降、DeFi(分散型金融)への注目が集まると同時に金融におけるNFTのユースケースも提案・模索されています。 7月には、NFTのマーケットプレイスとして知られる『Rarible』がプラットフォーム上での取引収益の受益権を持つガバナンストークンであるRARIのマーケットプレイス・マイニングを開始しました。 翌月8月には、MEMEプロジェクトが独自トークンMEMEのステーキングにより限定NFTを発行が可能となる、ステーキング×NFTの新たな形を実現し、レジェンダリーカードに300万円以上の価値がついています。 YearnFinanceのプロダクトであるスマートコントラクトを利用した保険『yInsure』では、yNFTと呼ばれるYearnのNFTが保険の受け取り権利を表章するトークンとして機能し、保険×NFTの新たなユースケースが誕生しました。 Flow Blockchainの参入余地と今後の展望 Ethereum上でNFTを発行するメリットとしては、同一チェーン上でのComposability(構成可能性)が挙げられます。一方で、他のアプリケーションが同時に利用されていくため、ユーザー数の増加に対して対処することが難しいと言えるでしょう。 Gods Unchainedでは、2020年5月にスケーラビリティの問題を解決すべくオフチェーンマーケットプレイス『Immutable X』を発表していますが、レイヤーが異なるブロックチェーンではComposabilityの実現が難しくなることが予測されます。 Flow Blockchainでは、高いスケーラビリティを実現しながらもComposabilityを損なわない設計になっているため、ゲームやアプリ間での相互運用性、アートやデジタル資産とDeFiエコシステムなど、拡張性の高いNFT向けのインフラとして今後ますます注目を集めていくのではないでしょうか。 そして、現在NFTとDeFiの統合からもNFT市場におけるユースケースの可能性が今後も多くでてくるのではないでしょうか。 まとめ Flow Blockchainの特徴やプロダクト、NFTとFlow Blockchainの今後の展望などをまとめて解説しました。 最近になり、全く新しいユースケースで注目を集めるNFT周辺の動向ですが、FlowはEthereumとのComposabilityを損なわずスケーリングが可能という点で、NFT業界における起爆剤となるポテンシャルも十分であると考えられます。 また、NBAやWarnerなど非クリプト方面から多くの消費者の注目を集めることに成功すれば、ファンコミュニティを巻き込んだより大きなマーケット・ムーブメントが実現されることでしょう。 9月24日から25日にかけてFlow Blockchainのイベントも開催されます。こちらより登録が可能ですので興味の有る方は是非とも参加してみてはいかがでしょうか。 公式リンク Flow Blockchain公式サイト Dapper Labs公式サイト

プロジェクト
2019/08/07IOSTのインキュベーションプロジェクト「Berm Protocol」の新ネットワーク「EMOGI」とは?
今年2月にメインネットをリリースしたIOSTは、エコシステム拡大のためにブロックチェーンプロジェクトのインキュベーションを積極的に実施しています。 その第一弾として発表されたのが分散型データガバナンスプロトコル「Berm Protocol」で、南米にフォーカスを置いたプロダクトの展開を行なっています。 今回は、Berm Protocolが利用されたプロダクト「Berminal」「Bermi」と、近日リリース予定の新ネットワーク「EMOGI」について解説します。 Berm Protocol [caption id="attachment_40523" align="aligncenter" width="764"] Bermi Protocolのアーキテクチャ[/caption] Berm Protocol はIOSTプラットフォームを活用した分散型データガバナンスプロトコルとなっており、このプロトコルを利用して、様々な分散型アプリケーションを作ることが可能になっています。 同プロトコルでは、BERMトークンを専用の「BMPトークン」に変換することで、プラットフォームへの各データエントリに投票やコメントができるようになります。 投票やコメントの多いエントリにはより多くのBERMトークンが割り当てられ、投票/コメント期間が終わるとデータの作成者に80%、投票/コメント者に20%が配布されます。 Berminal Berm Protocolがはじめに展開したアプリケーションは、ニュース集約サービスの「Berminal」で、暗号資産の価格情報に加え、最新ニュース・エアドロップ情報などがリアルタイムで網羅されています。 [caption id="" align="aligncenter" width="800"] Berminalのメイン画面[/caption] 南米を中心にユーザー数を増やすショートビデオアプリ「Bermi」 Berm Protoclのプロダクト第2弾となる「Bermi」は、近頃流行しているショートビデオアプリのひとつで、BERMトークンを活用したアプリケーションとなっています。 ユーザーは、ビデオの視聴・シェア・ライクなどといったエンゲージメントを通してリワード(報酬)を得ることができ、BERMエコシステムの構築にも一役買っています。 Bermiは特に南米でユーザー数を伸ばしており、コロンビアやメキシコ、チリ、ペルー、ベネズエラ、ドミニカ共和国、アルゼンチンなどではシェアの増大が顕著です。 検閲耐性ネットワーク「EMOGI」決済手段としてのユースケースも視野に Berm Protocolが近日リリースする「EMOGI」は検閲耐性のあるメディア構築の基盤となるフレームワークで、IOST上のIRC-20トークン「$EMOGI」を活用したPoSのアルゴリズムを元としています。 EMOGIが目指すのは、政治関係者や大企業などによる検閲の入った集権型メディアではない、事実の発信者と読者を直接繋げる分散型メディアの基盤を目指しています。 これを達成するために、EMOGIではコンテンツの「制作者」「承認者」「消費者」それぞれに役割を設けています。 コンテンツ制作者は、ニュース・ビデオ・ポッドキャスト・プレスリリースなどのコンテンツの掲載を、承認者にEMOGIトークンを支払って委託します。 事前にコミュニティによって選出されたコンテンツ承認者は、製作者からの受注に伴って、それぞれの読者にコンテンツを配信します。 IOSTによれば、すでに南米市場での成長を続けるBerm Protocolは、EMOGIが現地の不安定な法定通貨に取って代わる可能性も見込んでいます。

プロジェクト
2019/04/29QuarkChainがメインネットリリースに伴いノード募集選挙『Guardian Plan』プランを公開、CRYPTO TIMESも参加中
シャーディング技術を搭載した高TPSブロックチェーン・QuarkChainが、今月30日リリース予定のメインネット「シンギュラリティ」のネットワークノード募集プランを公開しました。 「ガーディアンプラン」と呼ばれる当イベントでは、「イージスプラン」と「エルフプラン」の2種のノードをコミュニティから選出し、初期段階のネットワークのコンセンサスセキュリティを固めるのが狙いとなっています。 CRYPTO TIMESもこのQuarkChainのガーディアンプランと呼ばれる選挙に参加しています。 こちらのページでは、このガーディアンプランについて、ノード立候補や投票の仕方・メリットなどを詳しく解説していきます。 Proof of Staked Work (PoSW)とは? 今回QuarkChainがリリースするブロックチェーンは、全ての大本となる「ルートチェーン」と、ルートチェーンのブロック内に複数存在するシャードによって構成されています。 QuarkChainはProof of Staked Work (PoSW)と呼ばれる独自のコンセンサスメカニズムを導入しており、始動初期段階のルートチェーンへのハッシュパワー攻撃を防ぐために事前にマイナーを募集するのがガーディアンプランの役割となっています。 PoSWはProof of Stake (PoS)とProof of Work (PoW)を組み合わせたプロトコルで、「ネットワーク全体におけるハッシュパワーの割合が高ければ高いほど、より多くのトークン($QKC)をステークしなければならない」ルールで成り立っています。 ガーディアンプランはルートチェーンにのみ一時的に適用されるもので、各シャードのマイニング難易度は純粋にPoSWのみで決定されることになっています。 QuarkChainのシャーディング技術やコンセンサスプロトコルについては、コチラのページでより詳しく解説されているので、ぜひ目を通してみてください。 ガーディアンプランで募集する2種のノードとは? QuarkChainのガーディアンプランでは、以下の2種類のノードを募集しています。 イージスガーディアン: QuarkChainチームが選抜するノード エルフガーディアン: コミュニティの投票で選出されるノード エルフガーディアンおよび投票者には、年間4000万QKCのリワードプールが設けられており、ステーキング量などに応じて報酬が入るようになっています。報酬計算に関しては、後の項目で詳しく解説しています。 (ガーディアンプランへの応募はコチラから) イージスガーディアンになるには? イージスガーディアンはQuarkChainの発展に貢献する意欲・資本を持つメンバー向けのノードで、コミュニティによる投票ではなくQuarkChainチームが選抜することになっています。 イージスガーディアンへの応募条件は以下の通りです。 QuarkChainのビジョンとミッションに賛同する 最低1000万QKCを一年間ステークする QuarkChainのコミュニティとエコシステム発展に貢献する意欲がある 現段階では、イージスガーディアンの具体的な報酬スキームは公開されていません。しかし、当ノードはQuarkChainチームと密接に関わり、ルートチェーン保護の重要な役割を果たすことが要件となっています。 エルフガーディアンになるには? エルフガーディアンはコミュニティの投票によって選出されるノードで、任期は2ヶ月となっており、再立候補・当選も奨励されています。 エルフガーディアンへの応募条件は以下の通りです。 QuarkChainのビジョンとミッションに賛同する 最低100万票を獲得し、投票数でトップ50にランクインする(=よってエルフガーディアンの総数は50) QuarkChainのコミュニティとエコシステム発展に貢献する意欲がある エルフガーディアンへのリワードプールは合計3400万QKC(年間)となっており、それぞれのランキングブラケットに決まった量が割り当てられています。 ブラケット リワードプール ダイアモンド(ランク1~3) 8,000,000QKC プラチナ(ランク4~10) 8,000,000QKC ゴールド(ランク11~20) 8,000,000QKC シルバー(ランク21~30) 5,000,000QKC ブロンズ(ランク31~50) 5,000,000QKC エルフガーディアンが得る報酬は、ブラケット・ブラケット内全票に占める自票の割合・任期の3つから算出されます。 例えば、ダイアモンドランク全体の40%の票を獲得して1任期(2ヶ月)のノードに選出されたと仮定すると、得られる報酬は次の通りになります。 8,000,000 (ダイアモンドランクのリワードプール) × 0.40 (ブラケットを占める自票の割合) × 1/6 (任期2ヶ月=1/6年) = 533,333 QKC また、今回のみ、第一任期に限りリワードは2倍に設定されており、上記のシチュエーションで初任期に当選すると約100万QKCを獲得できる計算になります。 (ガーディアンプランへの応募はコチラから) エルフガーディアンへの投票方法とリワード エルフガーディアンへの投票は、QKC保有者であれば誰でも行うことができます。また投票者は、投票した立候補者が実際に当選したかに関わらず一定量のリワードを獲得できることになっています。 具体的な投票手順は以下の通りです。 QuarkChain公式サイトの投票ページから一定量のQKCをステークする。 ガーディアンプランのウェブサイトから票を獲得する(1QKC = 1票)。 となっており、投票はqPocketからも行うことができます。 QKCのステーキングは期間を設定することができ、その長さに応じてボーナス票を獲得することができます。 ステーキング期間 ボーナス票数 2ヶ月 0 4ヶ月 4% 6ヶ月 10% したがって、5000QKCを6ヶ月間ステークしたと仮定すると、獲得できる票数は5000 + (5000 × 10%) = 5500QKCとなります。 投票によって獲得できる報酬は票数 × 10% × ステーキング期間となっており、上記の例では5500 × 10% × 6/12 = 275QKC(ステーク額の5.5%)が獲得できる計算になります。 また、エルフガーディアンの中にはノード報酬を投票者に山分けする制度を設けているところもあるようです。 第一任期の投票はメインネットがローンチする4月30日までとなっており、第二任期への投票も以降2ヶ月以内に始まる予定です。すでにステークしている投票者は次期になると再度同じ数の票を投票することができるとされています。 QuarkChainチームは、ガーディアンプランはメインネットのハッシュパワーが軌道に乗るまで続けるとしています。
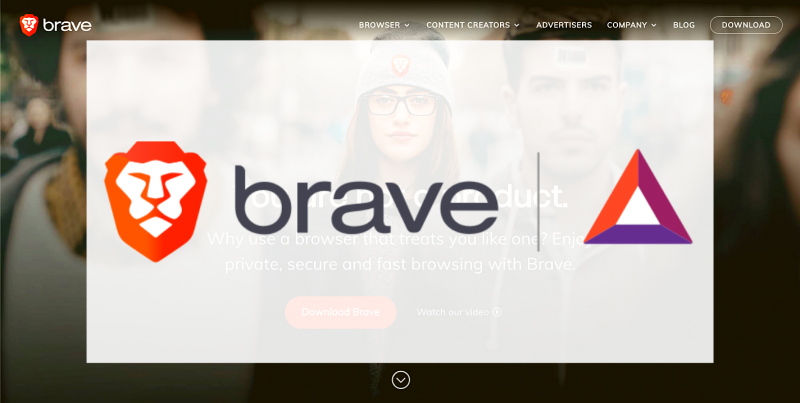
プロジェクト
2019/04/26Brave Browserが広告閲覧でBATを獲得できるプラットフォームをリリース、一足先に使ってみた感想は?
ウェブサイト上の広告や関連するデータ追跡などを自動で遮断するウェブブラウザ「Brave Browser」に、広告を閲覧することで報酬を得ることのできる機能が実装されました。 広告は任意で閲覧できるようになっており、報酬はベーシックアテンショントークン(BAT)と呼ばれる暗号通貨で毎月払い出されます。 獲得したBATはユーザーが訪れるウェブサイトへの寄付するか、お気に入りのコンテンツ製作者にチップ(投げ銭)として渡すことができるようになっています。 さらに今後のアップデートでは、BATをホテルの宿泊券やレストランクーポン、ギフトカードなどと交換したり、提携している取引所を通して法定通貨(フィアット)に変換したりすることも可能になるようです。 Braveによれば、ユーザーの動向はデバイスごとにローカルで分析され、定期的に更新される広告カタログ内からもっとも最適な広告を表示するようになっているといいます。 当広告機能は現時点で米国、カナダ、フランス、ドイツ、英国の5ヶ国でリリースされており、日本ではまだ未対応ですが、今後さらに対応地域を増やしていく予定です。 こちらのページでは、筆者が対象地域に住んでいるため、この新たな広告プラットフォーム機能を一足先に試用し、具体的な使用方法やどれくらいのBATが獲得できるのかなどを紹介していきます。 Brave Browserとは? Brave BrowserはMozilla Firefoxの共同創設者が率いるチームが開発する、ウェブ広告産業の改革とユーザープライバシーに重点をおいたウェブブラウザです。 Braveは、ウェブ広告業界の主要プレイヤーである「ユーザー」「掲載者(ウェブサイト等)」「広告主」をフェイスブックやグーグルなどのミドルマンから解放することを目指しています。 また、ウェブ広告産業ではユーザーの知らぬ間に行動データが追跡・売買されていることが問題となっており、Brave Browserはそういったトラッキングを広告もろともシャットアウトする機能が標準装備されています。 Brave Browserの大きな魅力は暗号通貨BATを内蔵していることで、今回のアップデートを機に、ユーザーはBraveの審査を通った広告を閲覧することでBATを獲得できるようになりました。 Brave BrowserおよびBATについては以下の記事でより詳しく解説されているので、ぜひ目を通してみてください。 稼げる次世代高速ブラウザBraveとは?特徴・評判・使い方まとめ! BAT (Basic Attention Token) の特徴・将来性を解説!取引所・チャートまとめ Braveの広告機能を実際に使ってみた ※当広告機能は現在アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、イギリスの5ヶ国でのみ利用可能となっています。 今回新たに実装された広告プラットフォームは、Braveが広告の掲載者として事前に審査を通過したパートナー広告をユーザー任意で表示するものです。 このパートナーの中にはeToroやMyCrypto、AirSwapなどの有名クリプト系プロジェクトや、Vice、Home Chefなどフィンテックとは直接関係のない企業も存在します。 広告機能を利用するにはまず、Brave Browserのアドレスバー横にあるボタンからRewards Settingsを開き、「Brave Rewards」と「Ads」をオンにします。 「Ads」のオン/オフスイッチの下にある設定ボタンからは、1時間にいくつの広告を表示するかを設定することができます。今回は欲張って最大の「1時間あたり5件」に設定してみます。 その後しばらく放置していると、画面の右上端から以下のような広告のプレビューが表示され、閲覧するかしないかを選択することができます(OSによって見え方は異なります)。 View(閲覧)を選択するとブラウザ上の新たなタブに広告が表示されます。広告の閲覧はViewボタンのクリック時にカウントされ、必ずしも広告に目を通さなければいけないということはないようです。 広告プレビューはブラウザをアクティブに利用している場合にのみ表示される仕組みになっています。 報酬は月ごとにブラウザ内蔵のBATウォレットに払い出され、現時点での推定報酬額は上記で紹介したRewards Settingsの「Ads」の項目に表示されます。 広告閲覧による報酬はどれくらい稼げる? 広告ひとつあたりの報酬は0.05BAT(この額は今後変更される可能性があります)となっており、この額は記事執筆時点のレートで換算すると約0.02ドルとなります。 したがって、BAT/USDが現レートで一定、かつ広告が1時間に必ず5つ出現すると仮定すると、1時間あたり0.25BAT(≒0.1ドル)が稼げる計算なります。 特別にブラウザに貼りついたりせずに5-6時間ほど作業をしていたところ、筆者は0.60BAT(推定0.25ドル相当、広告12件分)を稼ぐことができました。払い出し日は5月5日となっていることも確認できます。 実際のところ、Viewボタンを押せばその場で報酬が発生し、その広告タブを開かなくても良いので、毎時5件の設定でも特に面倒・邪魔と感じるようなことはありませんでした。しかし、この点は今後修正される可能性が高いでしょう。 現時点では「稼げる」というほどのものではないことは確かですが、今後BATの価格が大きく上昇すれば話が変わってくるかもしれません。 広告ひとつあたりのBAT報酬量はあくまで筆者が試用を通して確認したもので、広告の種類や利用環境によって異なる可能性があります。 また、広告閲覧で発生する報酬はユーザーに70%、掲載者であるBraveに30%配布されている点も覚えておくべきでしょう。 Brave Browserは新たな広告産業の切り口になるか? Brave Browserは、Google Chromeなどの拡張機能で定番のアドブロック機能を標準搭載しています。 この機能はユーザーにとって邪魔な広告を取り除く便利なツールである一方、従来の広告収入に頼っているウェブサイト運営者にとって大切な収入源を潰してしまうものでもあります。 今回実装された広告機能はBraveを掲載者としたものであるため、得をするのはユーザーと広告主の二大主要プレイヤーとBraveのみであると言えます。 ユーザーは今まで通りウェブ上の広告をブロックでき、さらに任意で広告を閲覧することでそのアテンションに対する報酬を獲得することができます。 広告主は「数撃ちゃ当る」戦法から、任意で広告を閲覧する、つまりそもそも興味を持って閲覧する消費者を対象とした広告を展開できます(事実、Braveで表示されるものは広告というよりプロダクトのウェブサイトに近いです)。 一方、現在提供開始となった当機能は、メディアやSNSなど広告収入に頼るプレイヤー「媒体主」と、広告を邪魔に感じる「ユーザー」間の利害の対立を改善するものではありません。 Braveはこの点を、ウェブサイトへの寄付、コンテンツクリエイターへの投げ銭で解決しようとしていますが、実際どれほどのユーザーが意図的にこのソリューションに乗ってくるのかは疑問でもあります。 また、掲載主にもユーザーのアテンションに基づいたリワードが入る仕組み(広告閲覧でBraveに入る報酬を30%から15%にして、掲載主へシェア)が2019年後半に導入されることも発表されています。 BraveはWeb3.0的なアプローチを利用した広告産業改革に取り組む一企業に過ぎず、他にも様々な広告モデルが考案されています。特に、SNSユーザーが主体となってフォロワーにオリジナル広告を配信するモデルなども出てきて、現在、注目を集め始めています。 まとめると、同社が今回実装した広告プラットフォームは産業形態的に見て、まだ完璧とは言えないでしょう。しかし、それ自体はBraveも承知の上であり、相応の対策を取ってくるのではないかと考えられ、今後のアプローチにも注目が集まります。 CRYPTO TIMESではBrave Browserのコンテンツクリエイターにも参加しており、認証済みのPublisherとなっています。自分たちの掲載媒体を持っているけど、Braveのコンテンツクリエイターに登録していない方はこの機会に登録をしてみてはいかがでしょうか

プロジェクト
2019/03/08Binance Launchpad(バイナンス ローンチパッド) 第3弾! – Celer Network ( $CELR )の概要や特徴、仕組みを詳細解説!
Celer Network(CELR)は高速で簡単、安全なトランザクションを可能にするためのレイヤー2のスケーリング技術を応用したプラットフォームです。 先日、BinanceのLaunchpadの第三弾としてのプロジェクトとしても紹介された上、現在もなお課題とされているセキュアでスケーラブルなプラットフォームを開発しているとして大きく注目されています。 また、Binance Blogにて公開された記事内ではCeler Networkは「仮想通貨の普及を促進するソリューション」であるとも述べています。 本記事では、そんなCeler Networkの特徴や概要、技術の詳細についてまとめています。 Celer Network (CELR)の概要 CELRの概要 通貨名/ティッカー Celer Network (CELR) 総発行枚数 10,000,000,000 CELR 創業者(Founder) Mo Dong氏他4名 主な提携先 Dfinity, aelf, Qtum, QuarkChain 特徴 レイヤー2スケーリング 公式リンク Webサイト Twitter Blog(Medium) Binance Launchpad WeChat(微信) Discord Youtube Github IEO情報とトークンメトリクス CELRのBinance LaunchpadでのIEO情報 トークンセール開始 2019/03/19 02:00PM UTC (11:00 日本時間) トークン規格 ERC-20 パブリックセール価格 0.0067 USD パブリックセール枚数 597,014,925 枚(総供給量の約6%) キャップ(Min/Max) 20 USD / 1,500 USD ハードキャップ 4,000,000 USD トークン配布 セール終了から15日以内 プライベートセール価格 0.015 USD プライベートセール枚数 約 1,550,000,000 枚 (15.5%) トークンのアロケーション詳細 [caption id="attachment_33550" align="aligncenter" width="700"] Binanceより[/caption] 今回、BinanceのLaunchoadのセールに割り当てられるトークンは、上述の通り全体の6%となっています。 プライベートセール(15.5%)とシードラウンド(11.5%)を合わせると、投資家向けには合計で全体の33%のトークンが割り当てられていることがわかります。 また、セール価格がプライベートセール($0.015USD)と比較して今回のLaunchpadでは約1/2($0.0067US)に設定されていることも注目すべきポイントです。 Celer Network(CELR)の特徴を詳細解説 Celer Network(CELR)は、オフチェーン技術を応用し安価で高速なトランザクションを実現することでブロックチェーンの普及を目指すプラットフォームを開発するプロジェクトです。 Celer Networkが開発する技術を利用することで、同様のトランザクションにおいて、Ethereumと比較して100倍以上の手数料を削減できると言われています。 Celer Networkが既存の技術と比べて何がどのように優れているのか、なぜ注目されているのかがわかります! ブロックチェーンのボトルネックとなる問題の解決を目指す ブロックチェーン技術はインターネット上における価値の交換を可能にし、分断されている情報を繋ぎあわせ、新たな経済を創り上げるものとして注目されています。 しかし、単一のノードが管理するサーバー、或いはそれ以上の速度を伴う情報交換(スケーリング)とオンチェーンで一般的に行われている合意形成の2つの概念は対局に位置するものであるとしているのがCeler Networkです。 Celer Networkでは、オフチェーンという部分に目を付けこのブロックチェーンにおける最大のボトルネックをクリアすることを目指します。 水平なスケーリング Celer Networkがレイヤー2のスケーリング技術を開発していることは先述しましたが、Celer Networkは水平にスケーリングをしていくことも一つの大きな特徴です。 水平なスケーリングというのは、ノード数が増えればスループットがその分だけ向上するというもので、技術的な大きな改善などを必要としない直線的なスケーリング手法とされています。 これにより、オフチェーンで展開されるアプリが増えた場合でも十分な数のノードが存在するという条件を達成していれば、潜在的に億単位のTPSを実現することが可能となります。 EthereumやDifinityなどの他のチェーンとの互換性がある 現状、EthereumやDfinityの他、EVM(Ethereum Virtual Machine)ベースのブロックチェーンとの完全な互換性があると発表されています。 オフチェーンであればLightning Networkなど、オンチェーンであればSegWitなどのスケーリング手法が存在しますが、これらは実装可能なブロックチェーンが限られているケースが多く、そのほかのチェーンではコンパイル(変換)が必要となります。 Celer Networkでは、ユーザー数やDAppsの数が多くスケーリングにおいてより早急な改善が必要とされるEthereumやその他のチェーンとの互換性を持っており、これも一つの大きな特徴と言えるでしょう。 トランザクションの際の手数料が非常に安価 スマートコントラクトでは、処理が複雑になればなるほどその際に発生する手数料が高くなるという点が課題とされてきましたが、オフチェーンでスマートコントラクトを執行する際の手数料もゼロに抑えられるようです。 少額、安価ではなくゼロという点は非常に重要なポイントで、これによりユーザビリティの非常に大きな向上が見込まれます。 また、マイクロペイメントの場合、直接Ethereumで行うのではなく、Celer Networkを通じて行うことで、コストを1/100以下に抑えることができるともされています。 ゼロに近いレイテンシーを実現 レイテンシーとは一般的に遅延時間などと訳されますが、トランザクションにおけるレイテンシーと捉えて問題ないでしょう。 従来のブロックチェーンだとトランザクションを送信してからそれが完全なものとなる(Finalize)されるまでタイムラグがありました。 Celer Networkではレイテンシーの大幅な(約20,000倍程度)改善を実現しており、これにより即座のトランザクションが可能となるようです。 Celer Network(CELR)に利用されるコア技術・詳細な仕組みを解説 Celer Networkが以上のように、非常に優れた特徴を持つことは理解していただけたと思います。 続いて、Celer Networkが採用するコアな技術や仕組みなどを解説します。 少しテクニカルな内容になってしまうため、難しいと感じた人はロードマップまで読み飛ばしてもCeler Networkの概要や開発スピードなど、十分に理解できると思います。 cStack - Celer Networkの階層化された構造の総称 eStackとは、以下に説明するcChannel、cRoute、cOSなどの総称となります。 各パーツに分かれて、それぞれが明確に別々の役割を果たすことで、開発や実装をより容易なものにしていくという意図があるようです。 cChannel - ステートチャネル・サイドチェーンのパッケージ cChannelとは、ダイレクトにステートチャネルやサイドチェーン部分の技術を担うパッケージになります。 まず初めにこの技術を理解するために、ステートチャネル技術で課題とされてきたデポジットなどの仕組みを改めて理解していきましょう。 ステートチャネル技術(Lightning Network場合)について Lightning Networkを簡単に説明すると、複数者間での資産の移動においてこのステート(状態)の遷移をオンチェーンで行わず、オフチェーンのチャネル上で処理し、チャネルで起きたトランザクションの最後の結果(収支)のみをオンチェーンに記録するといったもので、オンチェーンにおける負担を軽減することのできるという技術でした。 [caption id="" align="aligncenter" width="800"] シンプルなステートチャネルの仕組み図解[/caption] 基本的にステートチャネルには以下の3種類の形態が存在することを覚えておくとcChannelの理解が楽になると思います。 Payment Channel - 決済用途 Application Specific State Channel - アプリケーション特化型チャネル Generalized State Channel - 汎用ステートチャネル cChannelでは、3番目にあるGeneralized State Channelと呼ばれる汎用ステートチャネルの仕組みを利用します。 2番目のApplication Specific State Channelと違い、汎用ステートチャネルではある目的のために開かれたチャネル(デポジット)を他の用途に使用することができます。 ステートの遷移というアイデアが非常に重要になるので、これを頭に入れながら読み進めていただけるといいかもしれないです。 cChannelとは?仕組みやメリットを解説 cChannelとは、Celer Networkの構造の最下部に位置し様々なブロックチェーンとのインタラクションを行い、一方で上層のcRouteへと最新のステートを伝える役割を果たします。 要約すると、オフチェーンにおけるステートの遷移を管理する部分と言って問題ないと思います。 これは、Generic Dependency DAGと呼ばれる独自のチャネル同士のネットワーキングの構造によって可能となっています。 Dependency DAGとは AliceとCarlのバトルがその下位のステートに、AliceがBobに$3USDというステートが更にその下位のステートに依存するようなイメージのDAG(有効非巡回グラフ) Celer Networkでは、用途に応じたDAppsに最適なコンディション(ペイメント, ゲーム, 保険など)の複数のチャネルがネットワークのように相互に繋がっていきます。 この構造をGeneric Dependency DAGで再現することで、オフチェーンにおけるDAppsの複雑性や高いパフォーマンスをサポートすることが可能となっているのです。 cRoute - 価値転送における最適なルーティング cStackにおいて中層に位置するcRouteとは、オフチェーンにおける価値の転送の部分で役割を果たすCeler Networkにおける中核の一つです。 Celer Networkでは、ペイメントだけでなくDAppsもすべてオフチェーンで実行することが可能ですが、ここではどれだけ速く、かつ効率よく価値の転送を行うことができるかという点が非常に重要になります。 従来のルーティング(経路探し)の形式では、最短のルートを探すという方式が利用されていましたが、これはLightning Networkなどではチャネル内のステートのみを参照すれば問題がなかったので成立していました。 しかし、説明の通りGeneric Dependency DAGを利用するcChannelでは、常にオンチェーンのステートを参照してオフチェーンのステートの遷移を行うため、オンチェーンのステートの変化に対して対処が難しく、 同様の方式ではうまくルーティングを行うことができません。 そこで、考えられたのがDistributed Balanced Routing(DBR)と呼ばれる新たなルーティングの仕組みになります。 Distributed Balanced Routing (DBR) Distributed Balanced Routing(DBR)とは、ワイヤレス通信のルーティングから着想を得て考えられたCeler Networkのルーティングの仕組みになります。 この仕組みでは、ソースからゴールまでの最短距離を探す代わりに、ルーティングは既存のネットワークの混雑状況に応じて行われることになっています。 DBRでは特別に何かをする必要性を伴わずにアルゴリズム的に透明に、各ステートチャネルのバランスを取ることが可能です。 また、アルゴリズムの名前にDistributed(分散型)とありますが、これは各ノードが近くのノードとコミュニケーションを取り、その混雑状況によって自動的にルーティングが行われるので、そういった意味でも完全に分散型のアルゴリズムであると言えるでしょう。 プライバシーに関してもZK-Snarks等を利用せずとも、自動的に決定される複数のチャネルを経由して価値の転送が行われるので、問題はないとされています。 cOS - オフチェーンアプリ向け開発フレームワーク・ランタイム cStackの最上位に位置するcOSとは、オフチェーンでのDAppsの開発フレームワークを指します。 オンチェーンでのDAppsの開発と比較すると、Celer NetworkがメインとするオフチェーンでのDAppsの開発はかなり複雑で、開発者にとっては大きな障壁となります。 Celer Networkでは、オンチェーン・オフチェーン間でのステートの遷移など、以上に紹介するような複雑な仕組みを気にせず簡単に開発に集中できるような環境としてcOSを提供しています。 cEconomy - エコシステムの実現・維持に必須とされる経済モデル cEconomyとは、cChannelでのステートの遷移の整合性を保つための経済モデルと考えるとわかりやすいかもしれません。 これまでのプロジェクトでのエコノミクスはオンチェーンを主眼に置いていましたが、Celer Networkではオフチェーンをベースにモデルを構築していることが特徴です。 このcEconomyは以下の3つの要素によって構成されています; Proof of Liquidity Commitment (PoLC) Proof of Liquidity Commitment(PoLC)とは、オフチェーンのネットワーク化されたチャネルにおいて十分かつ安定した流動性を提供するための、仮想的なマイニングのプロセスを指します。 このマイニングに参加するためには、アイドル状態の仮想通貨或いはCELRを一定期間の間コミットすることが条件とされています。 これに対して、CELRで報酬の付与が行われるため、オフチェーンにおける流動性の維持に参加することへ対してのインセンティブが発生します。 Liquidity Backing Auction (LiBA) Liquidity Backing Auction(LiBA)とは、オフチェーンのサービスプロバイダ向けに展開される『クラウドレンディング』であると紹介されています。 レンディングを行う側(貸し手)は任意の利子、流動性の準備量、CELRのステーク量に基づいて決定される『Happiness Score』と呼ばれるスコアによってランク付けが行われます。 ここでは、CELRのステーク量に対して比較的大きな比重が置かれており、オフチェーンのサービスプロバイダに対して優先的に選択されレンディングを行うことが可能となるようです。 State Guardian Network (SGN) State Guardian Network(SGN)とは、Celer Networkに用意されたコンパクトなサイドチェーンであると説明されています。 このサイドチェーンでは主に、ユーザーがオフラインの際オフチェーンにおけるステートを守る役割を果たします。 SGNのGuardian(守護者?)となるためには、SGNへのCELRのステークが必要とされますが、Guardianはユーザーからのサービス手数料やGuardの機会を得ることができるようになります。 Celer Network(CELR)のロードマップ 予定時期 達成予定内容 2019年Q1 cChannel: 汎用ステートチャネルの性能向上及び、より多くのユースケースをサポート cRoute: 最初の実装とそのテスト cOS: SDK v2.0 リリース、モバイル・ウェブプラットフォームの統合フローに注力 cEconomy: PoLCとLiBAのセキュリティ監査、SGNのテストネットαローンチ Community: サードパーティアプリをCelerのプラットフォームへ迎える 2019年Q2 cChannel: 段階的なEthereumメインネットのロールアウト、及び他のブロックチェーンの継続的な統合 cRoute: テスト・初回のデプロイ cOS: SDK v3.0 リリース cEconomy: PoLC メインネットローンチ Community: オフチェーンサービスプロバイダの参加 2019年H2(後半) cChannel: クロスチェーンのインターオペラビリティ cRoute: プロダクションの計測と最適化 cOS: SDK v4.0 リリース、現実でのユースケース向けにUXの改善 cEconomy: SGNとLiBAのメインネットローンチ Community: Celerを利用することのできるアプリのエコシステム拡大を続けていく 最新のロードマップはCeler Networkの公式サイトから確認することができます。 各フェーズについて、具体的に確認していきましょう。 【2019年Q1】 2019年Q1 cChannel: 汎用ステートチャネルの性能向上及び、より多くのユースケースをサポート cRoute: 最初の実装とそのテスト cOS: SDK v2.0 リリース、モバイル・ウェブプラットフォームの統合フローに注力 cEconomy: PoLCとLiBAのセキュリティ監査、SGNのテストネットαローンチ Community: サードパーティアプリをCelerのプラットフォームへ迎える BinanceのICOが行われる今年の3月までがQ1となりますが、各パーツそれぞれでローンチまでの進度が異なるようです。 Celer Networkが開発する技術をテストしていく段階と考えて問題ないでしょう。 【2019Q2】 2019年Q2 cChannel: 段階的なEthereumメインネットのロールアウト、及び他のブロックチェーンの継続的な統合 cRoute: テスト・初回のデプロイ cOS: SDK v3.0 リリース cEconomy: PoLC メインネットローンチ Community: オフチェーンサービスプロバイダの参加 4~6月となるQ2ですが、ここではEthereumのメインネットにロールアウトが行われるようです。 cOSの新たなバージョンのSDKやPoLCのメインネットローンチなどと、cStack全体での準備がこの段階で整ってくるような印象を受けます。 【2019年H2(後半)】 2019年H2(後半) cChannel: クロスチェーンのインターオペラビリティ cRoute: プロダクションの計測と最適化 cOS: SDK v4.0 リリース、現実でのユースケース向けにUXの改善 cEconomy: SGNとLiBAのメインネットローンチ Community: Celerを利用することのできるアプリのエコシステム拡大を続けていく 2019年後半となるH2ですが、ここではクロスチェーンのインターオペラビリティに注目すべきでしょう。 オフチェーンの流動性供給にインターオペラビリティが付与され、これだけのパフォーマンスが出るといよいよ実利用が見えてきそうですね。 Celer Network(CELR)プロジェクト考察 ここまで、Celer Networkの特徴や技術仕様の解説、ロードマップの紹介などを行ってきました。 以上を踏まえて、Celer Networkの競合プロジェクトとの比較など、個人的な考察を紹介していければと思います。 競合プロジェクトとの比較優位(Raiden, Lightning Network) Raiden Networkは、ペイメントチャネルを利用して、スケーラビリティの向上を図るプロジェクトの一つです。 現在は、Red Eyesと呼ばれるv.0.100.1が昨年12月よりEthereumのメインネット上にリリースされています。 一方で、Lightning Networkも、ペイメントチャネルを利用したBitcoinのスケーラビリティ向上を目指すプロジェクトです。 こちらも、既に世界中で利用されており、先日はTwitter上でtippin.meと呼ばれるサービスを利用したLightning Torchと呼ばれるムーブメントが話題を呼びました。 Raiden NetworkとLightning Networkの概要を掴めたと思いますので、この2つのプロジェクトをCeler Networkと定量・定性的に比較してみましょう。 Celer Network(CELR) Raiden Network(RDN) Lightning Network チャネルの種類 Generalized State Channel Payment Channel Payment Channel 対応 Ethereum, DFinity Ethereum Bitcoin トークン使途 エコシステム内のインセンティブ 追加の機能への決済(?) - 状態(チャネル数) 未リリース 56 32,222 オフチェーンスマコン 〇 - - 用途 マイクロペイメント・ESportsのゲームなど マイクロペイメント マイクロペイメント この比較表を見ると、ステートチャネルの種類から多くのユースケースをサポートすることのできるCeler Networkが、潜在的な実用性という部分で優れていることがわかると思います。 しかし、マイクロペイメントを想定するようなケースにおいて、チャネル数が本記事執筆時で30,000を超えるLightning Networkはオフチェーンでの流動性という点において他を圧倒しています。 懸念点として、Celer NetworkのユースケースにESportsと記載されていますが、現在の状況を鑑みても、Celer NetworkのSDK(cOS)を利用してMass-Adoptionを狙うことのできるESportsゲームがリリースされることは近い将来とは考えにくいでしょう。 開発スピードもここまで非常に順調 [caption id="attachment_33639" align="aligncenter" width="963"] Binance Researchより[/caption] Binance Researchによって公開されている資料によれば、これまで(2018年Q3から現在2019年Q1)の開発は、すべてロードマップに記載されているタイミングと同じ、或いはそれよりも早い段階での達成となっています。 さらに、CelerXと呼ばれる実際のプロダクトや、ソフトウェアの開発を行うことのできるCeler SDK(Software Development Kit)が既にリリースされていることから、着実にプロジェクトがリリースに向けて進んでいることがわかります。 Celer NetworkのWeb3.0ウォレット『CelerX』 CelerXとは、Celer Networkのオフチェーンスマートコントラクトなどの利点を享受することのできるWeb3.0ウォレットです。 現在はメインネットのリリースが行われていないため、テスト版での公開となりますが、既にiOS、Android共に正式にリリースが行われており、Celer NetworkのDAppsをプレイすることができるようになっています。 DAppsの一つである五目並べの映像も公開されており、通常のDAppsと比較して約1,000倍以上速いとされるUXを実際に体感することができます。 Celer Networkのソフトウェア開発キット『CelerSDK』 ゲートウェイとしてのCelerXだけでなく、Celer Networkを利用したハイスピードなDAppsを開発するためのキットであるCeler SDKもすでにDocumentationが公開されています。 ステートチャネルのユースケースはこれまで、マイクロペイメントに限られていましたが、Celer SDKではこれだけでなく、デリバティブ市場におけるインスタントマッチングや双方向的なゲーム、予測市場など様々なものがオフチェーンで開発可能となります。 現在、Celer NetworkのGitHubにはiOS、Android、WEB向けの開発のガイドが記載されており、課題として考えられるサービスプロバイダ・ユーザーの獲得にも大きな力を入れていることがわかりますね。 Celer Network(CELR)プロジェクトまとめ Binance Launchpadの第三弾として選ばれ再度注目を受けたプロジェクト、Celer Network(CELR)についてまとめました。 冒頭に書いたとおり、Binance CEOであるCZはスケーラビリティ問題が暗号通貨市場における成長の妨げになっていると考えているようで、Celer Networkが現在、クリプトエコノミクス構築の初期デモと、それを支えるレイヤー2ブロックチェーンアーキテクトで、この課題を解決する最前線にいると述べています。このことからも非常に注目性の高いプレイヤーであると言えるでしょう。 Celer Networkについてもっと知りたいと思った人はホワイトペーパーを読んだり、公式Twitterなどをチェックしたりしてみてください。 内容に間違いがあった場合、Twitterなどで指摘していただけると嬉しいです。 Celer Networkの公式リンクまとめはこちら 記事参考 : Celer Network Whitepaper , Binance Research , Binance Blog

プロジェクト
2019/02/22Binance Launchpad 2019年第2弾プロジェクト「Fetch AI」の概要や仕組みを徹底解説!
Fetch AI(フェッチエーアイ)は、自律的にデータの収集や配布を行う人工知能の分散型ネットワーク/プラットフォームを開発するプロジェクトです。 このプロジェクトは、前回BitTorrentトークン($BTT)のICOで大きな反響を呼んだ大手取引所Binance(バイナンス)のICOプラットフォーム「Binance Launchpad」で資金調達を行う予定となっています。 BitTorrentのTRONベース通貨「BitTorrentトークン / $BTT 」とは?仕組みをわかりやすく解説! - CRYPTO TIMES このBinance Launchpadは世界中の投資家たちから大きな注目を集めており、BTTはわずか18分間で約7億7000万円もの資金を調達しました。そんな同プラットフォーム第2弾として、次期ローンチ予定のFetch AIですが、プロジェクト自体はコンセプトが複雑な上、未だ実用例も発表されていないことから、なかなか理解しにくいものとなっています。 そこで本記事では、Fetch AIが公開している文献やホワイトペーパーなどを元に、同プロジェクトの概要や仕組みを解説していきたいと思います。 Fetch AIの概要 Fetch AIプロジェクトの概要 通貨名 Fetchトークン / $FET 開発団体 Fetch AI (イギリス) 主な提携先 Binance, ULedger等 特徴 自律型人工知能ネットワーク 公式リンク Webサイト Twitter Telegram Github LinkedIn ホワイトペーパー ICOリンク (バイナンス・要ログイン) Fetch AIの技術内容を解説! Fetch AIが開発するプロダクトは、「自律型の人工知能がトークンを利用して自動でデータを売買するプラットフォーム」です。 このプラットフォームは、自律型エージェント(AEA)、オープン経済フレームワーク(OEF)、Fetchスマートレッジャーという3つの技術に加え、Useful Proof of Work (UPoW)と呼ばれるコンセンサスで成り立っています。 ここでは、それぞれの技術を詳しく解説していきます。 自律型エージェント(AEA) 上記で解説した通り、このプロジェクトの主目的は、データやサービスの収集・提供などを人間を介さずに行うことのできる人工知能のネットワークを開発することです。 ここで言う人工知能が、自身や関係者(人間)の損益を考慮して自律的に学習・行動するようにプログラムされた自律型エージェント(AEA)にあたります。ホワイトペーパーでは、このAEAを「自律的に行動できる、デジタル上に存在する生命」とまで例えています。 サードパーティによる開発も可能なAEAは、それぞれウォレットにあたるものを所有しており、Fetchトークンを基軸通貨としてデータやサービスのやり取りを行います。 つまり、データの提供によりトークンを受領するのも、データ収集のためにトークンを支払うのもこの自律型エージェント(AEA)が代行する、ということになります。 AEAはAPIとして存在するものや、自動車やカメラなどのIoTインターフェース上に存在するもの、データの価値解析に特化したものなど、役割に応じて様々な種類が存在します。 オープン経済フレームワーク(OEF) [caption id="" align="aligncenter" width="569"] OEFが関連性のあるデータをまとめ、AEAがデータの自動収集・取引を行うことで、これまで人間の介入を要したデータ取引業務を効率化できることが期待されている。| Fetch AIホワイトペーパーより[/caption] オープン経済フレームワーク(OEF)とは、AEAがより効率的にデータの収集・提供を行えるようにするための機械学習ベースのプロトコルです。 OEFの主な役割はAEAの「地理的な位置」と「経済的な位置」を決めることです。 地理的な位置の割り振りは、現実世界でのロケーションが価値を大きく左右するデータをうまくやり取りするのに役立ちます。 地理的な位置と経済的な位置の例 日本国内の自動車に存在するAEAが車のワイパーのオン・オフをデータとして提供するとします。 このデータは自動車が走行している位置での気象情報を把握するのに活用することができます。 AEAがこのデータを売り出す際、OEFは機械学習を元にこの情報の「地理的な関連性」を見出し、データが実際に価値を帯びる位置に存在する他のAEA、つまり日本に存在する他のAEAが優先的に確認できるようにデプロイを行います。 「経済的な位置」も同様に、関連性の高いデータ市場に関わるAEA同士がお互いを見つけやすいようにする、というものです。 また、上記の二つに当てはまらないAEAは「ネットワークスペース」上で位置が決定されます。 OEFは、このように「AEAが認識する世界」を作り上げていくことで、AEA同士の効率の良い取引を促進する役割を担っています。 Fetchスマートレジャー Fetchスマートレジャーは、ブロックチェーンと有向非巡回グラフ(DAG)を組み合わせた独自の分散型台帳(DLT)です。このシステムがブロックチェーンと大きく異なる点は「複数のチェーンが同時に存在できる」という点にあります。 ネットワーク処理能力を「リソースレーン」と呼ばれるグループに分けることで、ひとつのブロックを複数レーンで共同処理したり、チェーン自体をフォークさせたりすることができます。これはシャーディングの一種と捉えられます。 [caption id="" align="aligncenter" width="636"] Fetchレッジャーのシャーディング: 横長の長方形がリソースレーン、縦長の長方形がトランザクション、縦の点線はブロックの区切りを表す。| Fetch AIホワイトペーパーより[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="638"] Fetchレッジャーは通常のブロックチェーンと異なり、いくつものチェーンを同時に処理することができる。ひとつのブロックを別々のレーンで参照できるようにすることで、全チェーンを同期させるシステムを採っている。| Fetch AIホワイトペーパーより[/caption] 詳細な技術情報が記載された文献によれば、Fetchレッジャーでは1ブロックあたりにトランザクションひとつのみを格納することになっています。 これを踏まえると、Fetchレッジャーはトランザクションを並行処理できる分散型台帳、と捉えることができます。 Useful Proof of Work (UPoW) FetchレジャーはUseful Proof of Work (UPoW)と呼ばれる独自のコンセンサスメカニズムも採用しています。 これは、通常のPoWに加え、ブロック生成競争で「負けた」マイナーが他の規模の小さな計算・承認処理を行えるようにするというものです。さらに将来的には、トランザクションの規模(手数料)に応じてマイニングのディフィカルティを自動調整(機械学習による自律的改善を含む)できるようにするともされています。 小規模なトランザクションを処理能力の比較的低いデバイスで処理できるようにすることで、様々なデバイスでマイニング報酬を得られる、という仕組みです。 この仕組みがうまく機能すれば、ブロック生成のディフィカルティ(=消費電力)が無意味に高くなるのを抑えることができ、PoWによる地球環境への悪影響を緩和することができます。 Fetch AIがもたらすメリット ここまででは、Fetch AIがどのようなプラットフォームを開発しているのか、そしてその技術内容についてを解説してきました。 リソースの大半がプラットフォームの構築に充てられている同プロジェクトでは、未だ具体的なプロダクトや実装提携が発表されていません。そのため、このプロジェクトが利用者にいったいどのような利益をもたらすのかが大変掴みにくくなっています。 データ取引およびセールスにおけるコスト削減 Fetch AIのプロダクトがもたらす第一のメリットは「データ取引およびセールスにおけるコストの削減」です。 当プラットフォームでは、自律型エージェント(AEA)が自動的にデータの収集を行います。この自動化により、今まで取引コストより価値の低かったデータに収益性が生まれる可能性が広がります。 また、OEFによるデータ市場の最適化と共にAEAがデータの取引も担当することで、さらなる時間的・金銭的コストを削減できることが見込まれています。 新たなデータ市場の発掘 そして、コストの削減に続く第二のメリットは「新たなデータ市場の発掘」です。 これは、人工知能と機械学習をベースにしたAEA・OEFの働きにより、今まで誰の目にも止まらなかったデータが価値を帯びるようになり、新たな市場を開放する、というものです。 この例としてFetch AIのホワイトペーパーで取り上げられているのが、交通産業におけるAEAの活用です。 自動車のワイパーのオン・オフをAEAがデータとして管理することで地域ごとの気象情報を把握するのに役立てたり、電車の券売機にAEAを配置することで駅間の混雑状況を他のAEAと共有する、などといった利用例が挙げられています。 Fetchトークン / $FET について Fetchトークンは主に、AEA間でのデータ取引に用いられることになっています。 言い換えれば、自律型の人工知能が人間の手を介さずにデータをやり取りし、その証拠をFetchレッジャーに記録する手段として存在するのがFetchトークンである、ということです。 なお、テストネットの公開に伴うICOで配布されるトークンはイーサリアムベース(ERC-20規格)のもので、以降(プロジェクトのロードマップを参照)メインネットの公開とともにネイティブトークンに変換されます。 BitTorrentトークンのスペック・ICO情報等 通貨名/ティッカー Fetchトークン / $FET タイプ ユーティリティトークン プラットフォーム Ethereum (ERC-20規格・テストネット) 総供給量 1,152,997,575 FET 初期供給量 未定 ICO日程 2019年2月25日 ハードキャップ 未定 パブリックセール量 未定 プライベートセール量 133,747,718 FET (総供給量の11.6%) 今年2月末に配布されるERC-20トークンの保有者はFetch AIのテストネットに参加することができ、AEAや機械学習アルゴリズムの開発・テストなどを行うことができるとされています。 トークンの割り当ては、Fetch AIの創設者および財団がそれぞれ20%ずつ、トークンセールとリザーブが20%ずつ、アドバイザーに10%、マイニング報酬に10%となっています。 Fetch AI財団が保有する20%は「エコシステムの補助」に利用されるものとされており、ネットワークの発展を促すイベントなどで配布されるものとみられます。 マイニング報酬は初期5年間をめどに徐々に逓減していくようです。 トークンの払い出しに関しては、創設者・アドバイザーは1年後、プライベートセール参加者は6ヶ月後、財団は3年後とされています。パブリックセール参加者にはロックアップは設けられていません。 なお、プライベートセールは昨年の4月から7月にかけてすでに行われています。 プロジェクトのロードマップ [caption id="" align="aligncenter" width="834"] Fetch AI公式サイトより[/caption] Fetch AI公式による2019年のロードマップは以下の通りとなっています。 第1四半期: テストネットリリース 今回のBinance LaunchpadからのICOがテストネットの公開にもあたるもようです。公式発表では、以降も招待制でテストネットへの参加者を増やしていくとされています。 第2四半期 : コンセンサスとOEFの改善 第二四半期のリリースでは、UPoWコンセンサスとOEFの改善に加え、分散型台帳ベースのオークションシステムの導入が予定されています。 第3四半期: アルファ・ベータリリース アルファ版ではネットワークの主要な部分が機能すること、ベータ版ではほぼ全ての機能が問題なく動くことが目標とされています。 第4四半期: メインネットリリース メインネットのリリースに伴い、ERC-20トークンからネイティブトークンへの移行がこの時期に予定されています。 現段階でのプロジェクト考察 ここまででは、Fetch AIの概要や技術内容、トークン・ICO情報、ロードマップについて解説してきました。上記を踏まえた上で、こちらの項目ではFetch AIプロジェクトの注目すべき点を挙げていきます。 19年内メインネットリリースはおそらく不可能 これまで解説してきた通り、Fetch AIは「自律的にデータ収集・取引を行う人工知能(AEA)」「機械学習を通して関連性のあるデータをまとめるフレームワーク(OEF)」「ブロックチェーン・DAGハイブリッド型の分散型台帳(Fetchレッジャー)」の3つの開発に取り組んでいます。 当然これらは、人工知能、機械学習、分散型台帳それぞれの分野で世界最先端の技術にあたるため、開発や普及には膨大な時間と資金がかかるものと想定されます。 加えて、「Fetch AIがもたらすメリット」の項目でも触れた通り、同プロジェクトは未だプロダクトもできておらず、実装を決定している提携企業なども特に発表されていません。 現状の開発段階とプロジェクトが掲げるゴールの規模の大きさを踏まえると、ロードマップにある「19年第4四半期までにメインネット公開」はおそらく延期されるのではと考えられます。 チームの資金繰りは少し疑問 Fetchトークンについての項でも触れた通り、Fetch AIは昨年中旬にプライベートセールを行い、総発行量の約12%分のFETをSAFTという形でBinance Launchpadから販売しました。 Simple Agreement for Future Tokens (SAFT)は、購入したトークンがすぐに手元に届かず後々配布される、というタイプの資金調達方法です。 このプライベートセールに関してBinanceが今年1月末に発表したレポートによれば、Fetch AIは調達した約450万ドルおよび3400ETHの85%以上を昨年9月から今年1月までの間で使い果たしたとされています。 SAFTで取り扱われたトークンはテストネットの公開とともに徐々に配布されていく予定ですが、Fetch AIはこれだけの資金を使ったにも関わらず未だプロダクトのプロトタイプすら発表していません。 Binanceといった大企業がICOを前面に押し出していることを踏まえるとFetch AIが投資家を欺くというのは起こり難いと考えられますが、プロジェクトのスケールの大きさを考えると、同社が資金繰り困難に陥っている可能性は高いと言えます。 やや誇張気味なロードマップも、もしかしたら一人でも多くの投資家を集めるための短期的な戦略なのかもしれません。 ハイプ度は高め Fetchトークン($FET)はBinance(バイナンス)の資金調達プラットフォーム「Binance Launchpad」からICOを行うこともあり、かなりハイプのかかった通貨となっていることは確かです。 冒頭でも紹介した通り、Binance Launchpadの復帰後第一弾となったBitTorrentトークン($BTT)は、わずか18分間で約7億7000万円もの資金を調達しています。 それ以外にも、Fetch AIはテレグラフ紙、エコノミスト、フォーブス、TechCrunchなどといった大手メディアでもカバーされており、多くの投資家から期待されていることがわかります。 高セキュリティ・高スケーラビリティが本当に達成できるか要注目 Fetchレジャーは、独自のシャーディング技術とコンセンサスメカニズムを導入した分散型台帳で、他プロジェクトのプラットフォーム同様、セキュリティとスケーラビリティの高さを謳っています。 リソースレーンの活用によるネットワークのシャーディングがうまくいくかどうかは、実証実験が行われるまではなんとも言えないのが現状でしょう。 また、シャーディング・UPoWコンセンサスに関しては、今後セキュリティやネットワーク攻撃耐性に関して詳しくまとめた文書が公開されることにもなっています。 したがって、Fetchレジャーのセキュリティとスケーラビリティのトレードオフがどれほどうまく行われるのかは今後の進展とともに注目していくべき要素となります。 まとめ Fetch AIは、自律型の人工知能(AEA)が人間の代わりにデータの取引を行う分散型ネットワークを開発するプロジェクトです。 AEAの効率化はオープン経済フレームワーク(OEF)と呼ばれる管理プロトコルのもと行われ、人工知能がFetchトークンを元に行う経済活動は独自の分散型台帳「Fetchレッジャー」に記録されるということでした。 当プロジェクトは大変近未来的かつ規模の大きいもので、今後の技術開発や実装・普及にはまだまだ長い時間がかかるのではないかと予想されます。 一方、テストネットの公開に伴うICOは、Binance Launchpadから行われるということもあり、投資家から大きな注目を集めていることは違いないでしょう。

プロジェクト
2019/02/21仮想通貨を物理的に配布できるカードWodca(ウォッカ)とは?
株式会社クリプトエージェントはビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を配布できるプラスチックカード型のコールドウォレット「Wodca(ウォッカ)」を昨年10月に発表しました。 Wodcaはデジタルトークンをプラスチックカード型のコールドウォレットで物理的に配布することが可能になります。 プラスチックカード型コールドウォレット「Wodca(ウォッカ)」とは? Wodcaは実際には手に取ることのできないデジタルトークンを物理的な方法でシェア/配布するためのカードで、仮想通貨をより多くの人に使ってもらうために開発されました。 それぞれのカードには固有のIDが振り分けられている他、サービス認証するための「Access Code」、「Wallet Address」、「Private Key」などがスクラッチ加工によって記載されています。 Wodcaカードを受け取った側はIDとAccess Codeをウェブサイト上で入力することでアクティベーションが可能となっています。アクティベーションが完了すると、Wallet Addressにトークンが送付される仕組みです。 トークンをカードのアドレスから外部に送金する際に必要なPrivate KeyはサーバーやWodcaシステム内には保存されておらず、カード裏面にのみ記載されています。そのため、Wodcaはインターネットから完全に切り離されたコールドウォレットとして機能します。 また、カードの仕様はパートナー企業の要望に応じてデザインするとしており、配布されるカードには複数のデザインが登場することが予想されます。現在はビットコイン(BTC)およびイーサリアム(ETH)、ERC-20ベースのトークンをサポートしています。 複数企業からの資金調達を完了 Wodcaはセガサミーホールディングス、トランス・コスモス、オークファンなどから資金ん調達を実施したと2月8日に発表しました。 関係者筋によると、今回の調達額は2,000万円程度とされています。 Wodcaは仮想通貨市場の成長にはルール/法令の整備が不可欠だと主張し、今回調達した資金を人材採用および開発体制の強化に充てるとしています。 Wodcaの利用方法 Wodcaの利用方法は非常にシンプルで仮想通貨に触れたことの無い方でも心配は要りません。また、全ての操作は同じウェブサイト上で行えるようになっています。 アクティベーション apps.wodca.jpにアクセスし、カードに記載されているIDとAccess Code、メールアドレスを追加することでアクティベーションが完了します。その後、トークンがカードのWallet Addressに送付されます。 トークンの確認 カード裏面に記載されているWallet Addressを公式ウェブサイトで入力することにより、保有しているトークンを確認することができます。 トークンの送金 カード裏面のPrivate Keyを使用することでトークンを別のアドレスへ送金することができます。 まとめ Wodcaは企業にキャンペーンやイベントを通して、消費者との新たなコミュニケーション方法を提供する一方で自分で仮想通貨を購入するには不安が残る消費者に対して仮想通貨と接する機会を提供することを目指しています。 仮想通貨は基本的には全てデジタルで情報のやりとりが行われ、物理的に受け取ったり送ったりということはあまりありません。 そんな中でWodcaは物理的に仮想通貨に触れる機会を作り出すことで、仮想通貨の普及を後押しする存在になるかもしれません。 記事ソース: Wodca, プレスリリース




















 有料記事
有料記事


