
ニュース
2020/06/08PundiXが提供する暗号資産に対応したハンディPOSレジ機Pundi XPOS X2が日本アマゾンで発売
世界で利用されているデジタルキャッシュ、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ネム(XEM)などの20種以上の支払いオプションに対応したハンディPOSレジ機「Pundi XPOS X2」の日本アマゾンでの受付を開始しました。 今回のXPOS X2は端末を購入した後に契約する形となっています。 https://twitter.com/PundiXLabs/status/1268798052971606017?s=20 Pundi XPOS X2は専門的な知識を必要とせず店舗や屋台などに簡単に設置できる特徴があり、「ビットコインでも約9秒なシームレス決済」が可能であることが特徴です。 支払いは専用アプリXWalletまたはNFCカードXPASSを用いて行うことができます。現在のアマゾンでの商品価格は35,000円であり、配送料は無料となっています。 暗号資産を用いた簡単な決済の実現を目指すPundi X ($PXS)は Samsungの提供するGalaxy S10でウォレットが利用できるようになり話題になりました。 記事ソース:Amazon
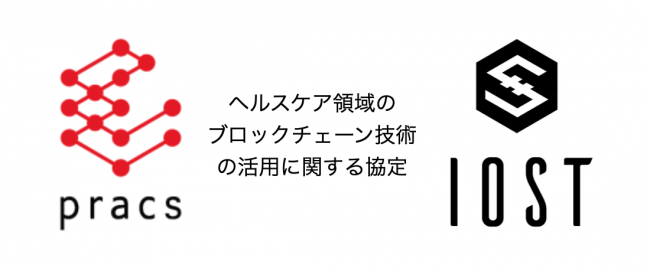
ニュース
2020/06/08IOST財団、大学発ベンチャー、メディカル・ヘルステック"プラクス"と協定、健康管理記録のヘルスケア領域におけるブロックチェーン技術の活用
精密医療や患者ケアのデータ管理ためのブロックチェーンテクノロジーの研究開発は、今後数年間で増加し、2025年までに14億ユーロ(約1,700億円)を超えると、Global Market Insights Inc. は予測しています(*1)。ヘルスケアにおけるブロックチェーンテクノロジーの活用は、データのプライバシーと健康情報交換などの信頼性と機密性を保証するさまざまのアプリケーションの実現が期待されています。 *1 https://www.scitecheuropa.eu/blockchain-in-the-healthcare-market-to-hit-e1-4bn-by-2025/97036/ 大学発メディカル・ヘルステック プラクス株式会社 https://pracs.co.jp 2017年 近畿大学の学生起業支援プログラムで設立。大学の知財を用いた医療系のアプリケーションソフトウエアを自社開発する。疾病管理手帳(FAP PASSPORT)と、大学で行った医療をテーマにした卒業研究「医療用家系図作成支援ソフトウェアの開発」を製品化。同ソフトウエアは、医療機関に導入されています。 疾病管理手帳(FAP PASSPORT)のデータ担保にブロックチェーン技術を活用する プロジェクトでは、医療データをデータ保有者である患者に既存のプラットフォームでは実現できないレベルの保証とデータの有機的な活用を実現するシステムの構築と検証を行います。患者と医療情報の提供者は、健康管理データの共有とプライバシーの保証の恩恵を受けます。 プロジェクトチーム SEYMOUR INSTITUTE 株式会社 https://seymour-inst.com(プロジェクトの企画を担当) アカデミック・シンクタンク。スイスと日本のテクノロジーに関する産学連携を行っている。スイスの複数の大学研究グループと提携。ヘルスケア、デジタル通貨、AI・データサイエンス、ホスピタリティ領域でのブロックチェーンを活用したデジタルトランスフォーメーションの研究・検証を企画・実施する。 エバーシステム 株式会社 https://eversystem.co.jp(システム設計・開発を担当) エンターテイメント領域でのブロックチェーン技術を応用したアプリケーション・サービスを設計開発する。自治体、エネルギーコンサルティング企業が参加するブロックチェーン技術を使った電力取引の実証実験に参加。Hyperledger Fabric、イーサリアム、IOSTプラットフォームでの業務レベルの開発を行う。 株式会社 PHI https://phi-blockchain.com(開発を担当) ブロックチェーン技術の社会実装を目的とした近畿大学生(修士過程学生含む)が設立したスタートアップ。大学でのブロックチェーン技術の理解の普及・ハッカソン/イベントの実施、複数の自治体とデジタルトラスフォーメーションによる地位活性プロジェクトを行っている。

ニュース
2020/06/08Braveブラウザがeスポーツや防弾少年団(BTS)と連携を発表
閲覧するだけでトークンを稼げる次世代高速ブラウザBraveがeスポーツやBTSと連携を発表しました。 今回、Braveを提供するカリフォルニアのブレイブソフトウェアは日本国内で初となるeスポーツや韓国の男性アイドルグループと連携した限定ブラウザをリリースします。 限定ブラウザはプロeスポーツチームの運営「ラッシュゲーミング」と協働して提供され、ブラウザ上にeスポーツの選手が表示されたり、広告閲覧報酬のトークンでチームを支援する機能が搭載されます。さらに韓流アイドル「防弾少年団(BTS)」との連携も行っています。しかしBTSに関しては、ラッシュゲーミングのようにポイントによる支援は現在できないようになっています。 BTSの特設サイトではBraveを利用しているユーザーを対象とした動画も限定配信されており、日本国内でのBrave利用者を増やすことを目的としているようです。 今年6月には同ブラウザが日本AppStoreのランキングで2位、Google Playで7位を記録しています。 Braveブラウザは、精密な広告ブロック・プライバシー保護機能と、承認された広告を閲覧するだけでトークンを稼げる仕組みを搭載したウェブブラウザです。また、広告閲覧で獲得できるBasic Attention Token(BAT)も、人気に拍車をかけています。Braveについてはこちらの記事で詳しく説明しています。 Braveのダウンロードはこちら 記事ソース:日本経済新聞

ニュース
2020/06/07TokenPocket WalletがIOST NFTアセットを正式にサポート開始
TokenPocket WalletがIOST NFTアセットの正式なサポートを開始し、ユーザーはTokenPocketウォレットを使用してIOST NFTアセットを確認し、転送を行うことができます。 https://twitter.com/IOSToken_jp/status/1269192869631463424?s=20 世界をリードする多通貨分散型デジタルウォレットTokenPocket が、IOST NFTアセットを公式にサポートししました。さらにIOST NFTトークン2020の年間イベントからのNFTトークンも、TokenPocket IOST NFTアセットリストに登録されています。使い方は以下の通りです。 1.NFTアセットを確認する TokenPocketウォレットアプリをダウンロードした後、IOSTチェーンを選択し、新しいIOSTメインネットアカウントを登録するか、秘密鍵を介してIOSTメインネットアカウントをインポートします。ホームページの「NFT」ボタンをクリックして、NFTアセットを確認します。 NFTアセットカテゴリをクリックして、そのカテゴリで所有しているNFTアセットの詳細を確認します。 最初のイベントのIOST NFTトークンを例にとると、NFTカテゴリの詳細ページに移動すると、ユーザーはこのカテゴリで所有しているすべてのトークンと各バッジの詳細を確認できます。 2. NFT資産の譲渡 特定のトークンの詳細ページを入力した後、[転送]をクリックし、受信アドレス(IOSTメインネットアカウント)を入力して、転送を完了します。 2020年第1四半期以降、IOSTはNFTエコシステムを導入し、IOST NFT標準プロトコルやIOST NFT資産取引プラットフォームXLOOTを発表しました。 IOSTは、NFTアセットをプロモートするだけでなく、IOSTメインネット始動1年を記念して、9つのNFTバッジを集める1年にわたるイベントを開催します。 記事ソース:Medium

ニュース
2020/06/07BraveブラウザがURLへ入力された検索ワードの一部をアフィリエイトリンクへオートコンプリートしていることが発覚
プライバシー保護に焦点を当て、広告ブロッカーとしても人気ブラウザであるBraveが、Binanceやその他複数のサイトでURLを入力した際、各サイトの招待リンクへオートコンプリートしていることがユーザーの指摘によりわかりました。 オートコンプリートとは、過去に入力した文字を記憶し、次に入力される内容を予想して表示するいわゆるサジェスト機能で、対象のサイトをURLで入力した際、Braveが持つアフィリエイトリンク付きのURLでサジェストをしていました。 ユーザーの一人がTwitterにて「binance.usと入力するとbinance.us/en?ref=35089877という招待コード付きのURLへ自動変換される」ことをTwitterでツイートしています。 https://twitter.com/cryptonator1337/status/1269201480105578496?s=20 これに対してBraveのCo-FounderでありCEOであるBrendan Eich氏は「Braveブラウザの欠陥である。BraveはBinanceのアフィリエイトであるが、ユーザーが入力した文字列の自動変換はされるべきではない。」とコメントしています。さらに、アップデートにより自動変換機能を次回のVerでデフォルトでOFFになるよう修正する旨も発表していますが、期日は明言していません。 https://twitter.com/BrendanEich/status/1269313200127795201?s=20 今回の件に関して、Githubに掲載されたBraveのソースコードを参照すると、Binance以外にもLedgerやTrezor,Coinbaseなどの他の複数のサイトに対しても同様の自動変換を行っていることがわかっています。 https://twitter.com/lawmaster/status/1269321803815673856?s=20 Braveは先日よりe-sportsや韓国のアイドルグループBTSとの日本での連携もスタートしているため、今回のアフィリエイトリンクのオートコンプリート機能を無断で実施したことは日本でも勿論ですが海外でも波紋を呼んだようです。 Braveについてはこちらの記事で詳しく説明しています。

ニュース
2020/06/07OKExがETH/USDのオプション取引の取り扱いを開始
暗号資産取引所OKExが、ETHUSDのオプション取引の取り扱いを開始しました。OKExはETH/USD指標を基にしたETHのコール/プットオプション取引の取り扱いをスタートしました。 オプションの有効期限は、対象となる週の金曜日になります。OKExは払い戻しに対応するために1,000ETHをETH/USDオプションに準備しています。 今年5月25日にはBinanceが $ETH $XRP のオプション取引の提供を開始しており、今後も他社プラットフォームによるオプション取引の競争も激化していくのでしょうか。 記事ソース:OKEx

Press
2020/06/07MASS Net-PoCコンセンサスのパイオニアブロックチェーンプロジェクト
PoWの抱えるエネルギー消費量問題、低TPS問題、計算力の集中化問題を解決するために、多くのブロックチェーンプロジェクトがPoSへ乗り換えました。近時、Filecoinテストネット・メインメットのリリース日時が決定されるにつれ、より多くの人が、Filecoinの採用する高効率、非中央集権性、省エネといった特徴を持つPoC(Proof of Capacity)に注目するようになりました。 PoWにせよ,PoSにせよ、PoCにせよ,いずれのコンセンサスアルゴリズムも、「ブロックノードをランダムに選択する」点では共通します。ノードが選ばれる確率は、ネットワークに投入されたリソースと比例します。確認されたブロックを覆すには、50%以上のリソースが必要とされます。これら3つのコンセンサスアルゴリズムは、投入されるリソースによって区別され、PoWは計算力、PoSは所有する通貨、PoCはストレージスペースです。 PoSでは、所有するトークンが多ければ、ブロック生産者になることができる確率も高くなります。PoSは富める者をより裕福にすることから、懐疑的な意見も多々主張されます。ナカモトサトシがPoWを生み出した意図は、十分な分散性の確保と、ネットワーク構築から安定運営に至るまでの間により一層の脱中央集権化を図ることができるかという点にありました。それに対して、PoC が答えを出しました。 PoCの最も大きな特徴は、誰でも普通のパソコンを用いてPoCプロジェクトに参加し、マイニングできることです。大量の研究・統計によると、クラウドストレージのスケールメリットは、個人のハードドライブに比べ、20%の最適化スペースしかありません。パソコンの普及に伴ってハードドライブが広く分布していることを考慮すれば、通用マイニングマシンと大規模なマイニングがもたらすマイナーの集中化問題がなくなり、ネットワーク全体の分散が実現される可能性があります。 MASS Net-初のPoCブロックチェーンプロジェクト MASS Net はすでにリリースされスムーズに運営されているブロックチェーンプロジェクトです。このプロジェクトは、MASSコミュニティのメンバーたちが協力し開発したものであり、PoCコンセンサスを採用しています。PoCの定義に従い、MASS Netがストレージスペースを利用してマイニングを行っています。現在、マイニングの難易度は35兆Gであり,約45秒ごとに1つの新しいブロックが作られます。 特に注目したいのは、MASS Netが採用しているPoCアルゴリズム『MASSコンセンサスエンジン』です。このコンセンサスアルゴリズムの中核は、マサチューセッツ工科大学(MIT)のトップレベルのコンピュータサイエンティストにより考案されたものであり、安全性、公平性、省エネ、効率性といった優れた特徴を持っています。 安全性 時間と空間を置き換えるという考えを採用したMASS PoCは、改ざん不能性を担保しています。PoC及び検証可能なランダム関数を採用することにより、MASSシステムの耐障害性が 51%になることが保証されます。 フォークス検査懲罰システムを採用することで、Nothing-at-Stake攻撃がもたらすフォークチェーンによるメインチェーン排除の問題に対抗できます。 公平性 現在、一台のPoWコンセンサスアルゴリズムを実行するASICマイニングマシンの販売価格は数万元にものぼります。それに対して、MASSコンセンサスに必要なのは、ノードが有効なストレージスペースを提供することのみです。 MASS PoCにより、ノードのブロック確率は、ノードが提供する有効なPoCにのみ依存し、かつ、有効容量の大きさの証明がデータの記憶媒体に関係ない、といったことが保証されます。そうすると、MASSネットワークのメンテナンスに関与するすべてのノードの限界費用がほぼ同様になります。言い換えれば、スケールメリットがありません。 省エネ PoWコンセンサスは、その実行の際に、莫大な電力が消費されています。ビットコインの一回の取引には、アメリカの一般家庭21日分の電力が消費されます。MASS PoCでは、容量スペースを初期化する時にだけエネルギー消費を計算します。 そして、コンセンサスを実行する際には、ほんの少しの計算力が検索に使われると同時に、ハードドライブの電力消費が極めて低い水準にあります。従って、PoCとPoWのエネルギー消費総量の差は300倍以上となります。 MASSがコンセンサスを実行する際、コンピュータのエネルギー消費が占める比率が極めて低く、コンピュータの使用に支障が出ません。ストレージスペースがMASSネットワークメンテナンスに関与しない時には、容量スペースを初期化して他の用途に使うことができます。 効率性 PoWコンセンサスの最も成功した例であるビットコインでは、10分ごとに1つの新しいブロックが生成されます。それに対して、MASS Netブロックチェーンのメインネットワークの運用データによると、45秒ごとに1つの新しいブロックが生成されるようになり、性能が10倍ほども高められています。 ブロックコンセンサスのプロセスにおいては、ノードがストレージスペースに対して訪問検索のみを行い、データ操作はしません。MASS PoCを採用するノードは、同様な容量スペースを利用すれば、複数のブロックチェーンに対してコンセンサスを提供できるため、その汎用性によりエネルギーの利用率が一層高められました。 MASSについて MASSは、MASS Netにおけるネイティブ通貨です。ビットコインと同様に、1つのブロックが形成されるたびにそれに対応するMASSが生成されます。 業界の他のプロジェクトと異なり、MASS Netにはステークホルダーが存在せず、完全にコミュニティ主導となっており、プレマイニングもありません。つまり、すべてのノードが公平であることを意味します。さらに、ストレージスペースによるマイニングという方式により、ハード面の整備のハードルがこれまでにないほど低下したため、一般ユーザーも参加しやすくなっています。 MASS Netが利用しているMASSコンセンサスエンジンは、汎用性を持つコンセンサスソリューションであり、同時に複数のパブリックチェーンに対してコンセンサスサービスを提供することができます。将来的には、MASSコンセンサスエンジンに基づいて複数のブロックチェーンが開発されることになるでしょう。例えば、スマートコントラクトを執行できるレイヤー1ソリューションや、性能の向上に取り組むレイヤー2ソリューションなどです。MASSコンセンサスエンジンは汎用性を持つコンセンサスを基礎にするという視点で、クロスチェーンという技術の難題を巧妙にクリアしました。 MASS Net上で生成されたMASSはMASSコンセンサスエンジンの価値保存の機能を果たしています。そのため、MASSはMASS Net上で取引できる資産だけでなく、MASSエコシステム内の全ての応用のアンカーとなり、MASSコンセンサスエンジンに基づいたクロスチェーンのエコシステム資産の相互接続を実現することを可能しました。 プロジェクト開発の進捗 MASS Net は2017年に開発が開始され、2018年にブロックチェーンのプロトタイプが開発され、2019年4月にテストネットがリリースされました。プロトタイプシステムの検証、安全性テスト、安定性テスト、可用性テストという4段階のテストを経て、メインネットが2019年9月1日に正式にリリースされました。それ以来、安定して運営されています。 プロジェクト開発当初から、エコシステム構築を目標にしてきました。メインネットリリース後、ユーザー及び開発者にフルノードウォレット、マイニングノード、ブロックチェーン、ブロックチェーンブラウザといったツールを提供しました。MASSコミュニティのメンバーは、自発的にいくつかのマイニングソリューションを提供し、異なるタイプのノードに使用しました。集権化されていない多量のノードは、ブロックチェーンネットワークの安定性・安全性・信頼性の確保のための必要条件であり、ブロックチェーンの改ざん防止機能を果たすことに役立ちます。 チーム紹介 MASS Netは、MASSコミュニティによって作り上げられました。MASSコミュニティは、オープンで非営利のオンライン組織であり、その使命はブロックチェーン技術を普及させることです。“MASS”という言葉は、「より多くの人が技術を活用してルールを守れば、社会がより公平になり、公平な環境がより大きな社会的活力を解放し、社会の繁栄を促す」というコミュニティのメンバー達の初心を言い表したものです。MASSコミュニティは、この目標を達成するために精進しています。MASS Netは、まさに、この目標達成のための第一歩です。 MASSCafe: https://masscafe.cn/ MASSホームページ:https://massnet.org/ja/ MASS日本コミュニティ:https://twitter.com/MASSNet_FansJP MASS日本Telegram group:https://t.me/MASSNet_FansJP Sponsored Article ※本記事は企業が発信するプレスリリース記事となります。サービスのご利用、お問い合わせは直接ご提供元にご連絡ください。

ニュース
2020/06/07BittrexとPoloniexが2017年のビットコイン市場操作で再び起訴される
大手暗号資産取引所BittrexとPoloniexが2017年にビットコイン市場価格の不正操作に関わったとして6月3日に起訴されました。 今回の原告は去年の8月に意図的な価格操作を行なったとしてBitfinexとTetherを起訴したのと同じ人物達です。 起訴の内容によると、Tetherは本来米ドルに裏付けられる必要があるUSDT(Tether)数十億を担保がないまま発行したとされています。さらに、その後ビットコインの購入を行い需要を高め、市場操作をしたとされています。 その後、BittrexとPoloniexの2つの取引所も同様に市場操作に加担したと追加の訴状が提出されました。また、Bitfinexに対しては今回とは別の訴状が提出されています。 記事ソース:Finance Magnates

ニュース
2020/06/06Binance.USがMatic Network (MATIC)を上場
Binance.USがMatic Network (MATIC)の上場を開始し、MATIC/USDとMATIC/BUSDの取引ペアの取り扱いを開始しました。 https://twitter.com/BinanceUS/status/1268527930843336707?s=20 Matic Networkとは、サイドチェーンを利用してスケーラビリティの向上を図るプロジェクトで、テストネットでは10,000以上のTPSを実現していることで知られています。 『Matic Network (MATIC)』はBinanceの 行う暗号資産発行のサポートを行うプロジェクトBinance Launchpadの2019年第4弾となるプロジェクトに選ばれています。 MATICの市場分析はこちらの記事で詳しく行なっています。 記事ソース:Binance

ニュース
2020/06/06Braveブラウザが日本AppStoreのランキングで2位、Google Playで7位を記録
プライバシーを重視したWebブラウザ Braveが日本国内におけるAppStore,Google Playストアの無料ランキングでそれぞれ2位、7位に位置していることを発表しました。 AppStoreでは、TikTokやInstagramなどを抑えてのランクインとなります。 https://twitter.com/BraveSoftwareJP/status/1269092225490669568?s=20 Braveは先日、MAUが1500万人を突破したことを発表しており、着実な成長を見せています。さらに、コロナ対策に伴い、プライバシー保護を備えたビデオ通話機能「Brave Together」の提供を開始するなど著しく成長をしています。 関連 : Braveブラウザは稼げる次世代高速ブラウザ!特徴・評判・使い方を徹底解説 - CRYPTO TIMES Braveのダウンロードはこちら
















 有料記事
有料記事


