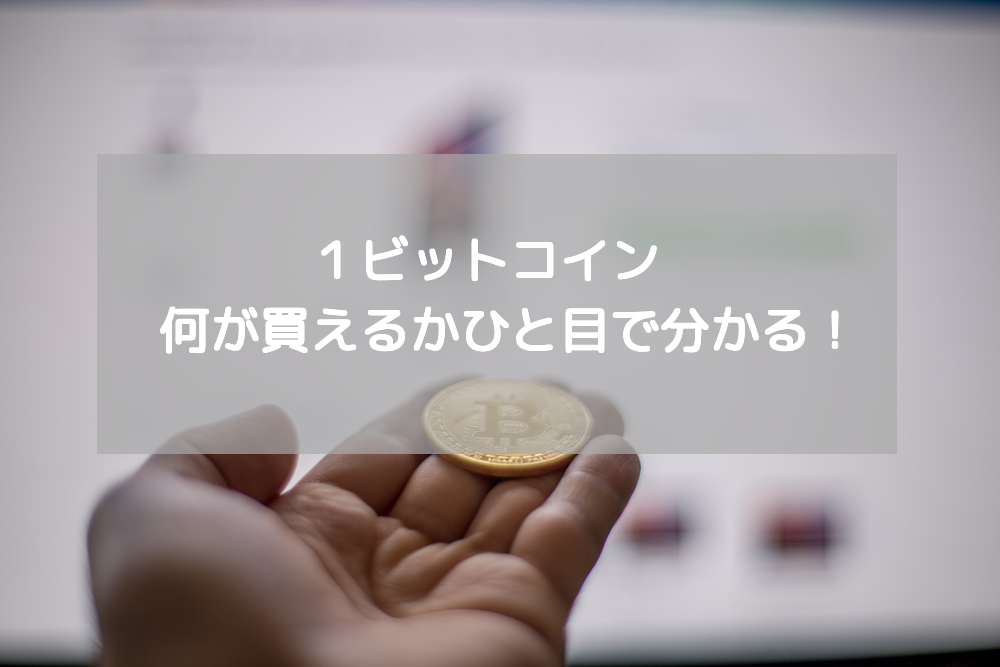
特集・コラム
2018/06/22現在の1BTCの価格で何が買えるかをひと目で分かる便利サイトを紹介!
「仮想通貨」や「ビットコイン」といった言葉を頻繁に耳にするようなった昨今、言葉自体は身近になれど「結局ビットコインってなんなの?」「ビットコインってどれくらいの価値があるの?」といった疑問を抱える方も少なくないはず。 Daichi かくいう僕もそのひとりです(笑) そんな仮想通貨やビットコイン初心者の方のために、わかりにくいビットコインの価値をひと目で理解できるウェブサイトを紹介します。 サイト概要:「How Much is a Bitcoin Worth?」 今回紹介するのは「How Much is a Bitcoin Worth?」というサイト。 このサイトでは、ビットコインの現在の取引価格がドル換算で表示され、加えて現在の1ビットコインでどんなモノが何個買えるかを表示してくれるのです! これなら親しみなれた普段の金銭感覚で1BTCの価値が理解しやすいのではないでしょうか。 使い方:このサイトでできること ビットコイン取引価格等の確認 トップページ中央上部に表示されているのが現在のビットコインの取引価格で、この記事執筆当時の価格は$6,624.54、日本円で約73万円となっています。 現在の取引価格の下に表示されている数字は左から以下のとおりです。 24 HOUR HIGH:24時間以内に記録した最高取引価格 24 HOUR LOW:24時間以内に記録した最低取引価格 24 HOUR CHANGE:24時間前の価格からの変動分 MARKET CAP:時価総額(数字の後ろの「B」は「billion」、つまり「10億」です) POINT時価総額とは「1BTC(ビットコインの単位)×ビットコインの供給量」です。 ビットコインはその特性上、総供給量は2100万BTCと決められています。 ビットコイン総供給量の80%が採掘済み マイニング可能なのは残り420万BTCのみ - CRYPTO TIMES さらに、トップページ左上の「How Many Bitcoins are there?」をクリックすると、現時点でどれだけのビットコインがマイニングされ、残りはいくらなのかが表示されます。 最も大きく白抜きの数字が現在マイニング済みのビットコインの量、その下が中段が残りの量、最後に一番下の変動しない数値がビットコインの決められた総供給量となります。 マイニングとは?ビットコインの取引が格納されるブロックを生成する行為のことで、生成されたブロックが時系列順に繋がったものをブロックチェーンと言います。 マイニングをすることで、新規発行分のビットコインがもらえます。 ブロックチェーンやマイニングなど、仮想通貨ビットコインのややこしい仕組みについてもっと知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。 【仮想通貨】Bitcoin(ビットコイン) の仕組みに関して - CRYPTO TIMES 現在の1BTCで買えるモノを見る トップページ中央に大きく表示されているのが、現在の1BTCの取引価格で購入することができる商品で、一度に3つまで表示されます。 各商品枠の左上に商品名、中央に商品画像があります。 次にひとつの商品にフォーカスして、表示の詳細を見てみます。 例えばこの「Nintendo Switch」。 左上に「1BTC could buy 22」と書いてありますが、これはつまり「1BTCで22個のNintendo Switchが買える」ということです。 Daichi ニンテンドースイッチ22個って!!(笑)業者か(笑) さらに他の商品を見てみると、執筆当時の取引価格では1BTCでMacBook Pro 13インチが4個、Amazon Echo Showが28個買えるということになります。 購入可能な個数の多さも相まって1BTCの価値が逆に分かりづらい感じも否めませんが、だいたいのイメージはつかみやすいのではと思います。 商品画像の左下に表示されている「List: $○○○」は「一個あたりの商品価格」、右下の「○○○BTC」は「一個あたりの商品価格のBTC換算」になります。 この画像の場合、この商品の一個あたりの商品価格は$299.99(約33,000円)、ビットコイン換算で一個0.045285BTCということになります。 さらに商品画像をクリックすると、ちゃっかり該当商品のAmazonページに遷移するようになっています。 ちなみに、サイト右上の「Refresh」をクリックすることで表示商品をどんどん切り替えることも可能です。 仮想通貨の交換と売買取引 トップページ下部、商品画像の下には Buy Bitcoin using Changelly Buy Bitcoin using Coinbase の2つがあります。 「Buy Bitcoin using Changelly」をクリックすると、仮想通貨交換所Changellyに遷移します。 「Buy Bitcoin using Coinbase」をクリックすると、仮想通貨取引所Coinbaseに遷移します。 POINT取引所・交換所は同義で、仮想通貨の売買取引が行われます。 販売所と違う点は、買いたい人と売りたい人の注文によって取引価格と数量が決定される点です。 イーサリアム表示に切り替え これまで紹介してきたこのサイトは現在のビットコインの価値をわかりやすく教えてくれるものでしたが、他にも現在のイーサリアムの価値も同じ方法で知ることができます。 そもそもイーサリアムってなんぞやという方はこちら。 【仮想通貨】Ethereum(イーサリアム)とは?根幹を支えるスマートコントラクト技術を含めて解説 - CRYPTO TIMES さて、イーサリアムでの表示に切り替える方法は簡単で、トップページ右上の「How Much is a Ethereum Worth?」という文章の青色になっている「Ethereum」の部分をクリックするだけ。 するとこのように「How Much is a Ethereum Worth?」というウェブサイトに切り替わり、同じように現在のイーサリアムの取引価格やその変動情報に加え、1イーサリアムで何が何個買えるのかを表示してくれます。 まとめ 今回はわかりにくい仮想通貨ビットコインの現在の価値を、何が何個買えるかで表示してくれる便利サイト「How Much is a Bitcoin Worth?」を紹介しました。 誰でもわかるようなモノに換算して表示してくれることで、初心者でもひと目で感覚的に価値を理解できる点が素晴らしいウェブサイトです。 Daichi これを機に仮想通貨に興味を持つ人が増えて、国内での盛り上がりが加速すればいいなぁと思います。

特集・コラム
2018/06/21上海のEOS BP WORLD SUMMITに参加してきました。
こんにちは。アラタ (@cry_curr_ar)です。 先日、メインネットをローンチしたEOSですが、先月にEOS BP WORLD SUMMITという、SUMMITが上海で行われました。 今回はいろいろご縁があり、SUMMITに参加していたEOS Japanのメンバーよりご招待をいただきましたので、その中で思うことを書いていきたいと思います。 最近ではブログだけではなく、CRYPTO TIMESでもロクに記事を書けていないのですが、今回はEOS BP SUMMITにちゃんとした記事を書いていきたいと思います。 いやはや、どんだけ、レポート記事を書くのが遅いんだよという話でもあります。スミマセン。。 EOS WORLD BP SUMMITへ参加 約一ヶ月前になるのですが、上海で行われたEOS WORLD BP SUMMITへと参加してきました。現在、EOSはメインネットへのローンチを完了しましたが、このときはまだメインネットへのローンチ前でした。 本SUMMITの趣旨としては、EOSのBP(Block Producer)候補を集めたサミットで、第3世代のブロックチェーンエコシステムでBPに必要なことについての発見、そして新たな人をEOSエコシステムへ惹きつけることを目的として行われたようです。 EOSは現在、中国で特に注目されているようで、会場に入ると800名くらいの会場が後ろまで満員!!立ち見でみている人もいるくらいでした。 当たり前なんですが、スピーカーは殆どが中国語で、今回は中国語 → 英語の翻訳機を聞きながらの参戦でした。内容は今回は割愛しますが、EOSのコミュニティやエコノミーの発展みたいなところに関してというところでした。 EOS BPって何? そもそも、EOSのBP(ブロックプロデューサー)って何?という方もいるかも知れません。 EOSはDelegated Proof of Stake、通称DPoSというコンセンサスアルゴリズムを採用しています。このDPoSの投票によって、選ばれたBP(ブロックプロデューサー)がブロックの承認を行っていくというものです。 【初心者向け】仮想通貨(ブロックチェーン)におけるコンセンサスアルゴリズムとは? - CRYPTO TIMES 現在では各国にBPの候補がおり、特に中国ではそのBPの候補数が非常に多いようです。BP候補になるにも条件が必要で、これらの条件をクリアしないとBPにも立候補ができないようです。 https://twitter.com/EosJapancojp/status/1002390720492138496 日本にもEOS Japan以外のコミュニティチームがあったり、DAppsを開発しているチームが会ったりとその属性はかなり多種多様のようです。BPに関して詳しくは近々、EOSの記事を書くのでそちらもご覧ください。 日本と中国の市場を比較して思うこと 今回のサミットを参加してみて、日本のサミットと比較した感想です。一番思ったのは、参加者の属性の違いというのが、非常に感じられました。 日本のカンファレンスに参加しても、外人が殆どで日本人はあまりいなかったり、会場がスカスカだったり、いわゆる胡散臭い人達が沢山いたり、話を聞かずにマッチングアプリをやっていたりと結構酷い空気だったりします。 逆にEOS BP SUMMITでは会場は満員、当たり前に中国人ばかり(EOSが現在、中国で人気だからかもしれません)、登壇者がでてくると、ここぞという感じで皆が皆スマホを取り出して写真を撮っていたり、話もしっかり聞いていて、非常に興味関心を持っているなと思いました。 後は参加者も女性が3-4割程度いて、日本のカンファのように男性ばかりの参加者では無いんだなと思った記憶があります。 また、EOSが特に中国で盛り上がっていることもあるのが原因か、会場の熱というのが非常に感じられました。EOSの中国のコミュニティもかなり多いようなので、今後も更に盛り上がっていくでしょう。 他のカンファレンスなどにも機会があれば、是非とも参加してみたいと思っています。 まとめ 今回、ご招待いただいたEOS Japanのチームの皆様、本当にありがとうございました。 EOS Japanは現在、BP Votingにも参加中なので、EOSホルダーの方は是非ともBP Votingにご参加してください! BPの投票方法は次回の記事にて公開いたします。EOS JapanのTwitterフォローもよろしく! EOS Japan 公式Twitter おまけ https://twitter.com/cry_curr_ar/status/997488357906173952 もう一度泊まりたい...

特集・コラム
2018/06/19Ethereum Classic上に構築されたETCGameを利用して、ワールドカップを10倍楽しもう!
先日、EthereumClassicの近況に関しての記事を書きましたが、現在、EthereumClassicのコミュニティは、日本だけではなく韓国や中国でもコミュニティが立ち上がり、色々と賑わいを各国で見せているようです。 Consensus 2018にも登壇!Ethereum Classic(イーサリアムクラシック) / ETCの最新情報 - CRYPTO TIMES そして、現在、ワールドカップの真っ只中ですが、EthereumClassic上に作られたブックメーカアプリであるETCGameを利用して、ワールドカップが10倍楽しめるようになります。 この記事では、その遊び方を説明したいと思います。 因みにEthereumClassic Japanのツイートでは日本戦の点数予想企画もやっているので要チェックです。 https://twitter.com/etcjapan/status/1007159291466297344 https://twitter.com/etcjapan/status/1009377652552097793 Ethereum Classic上に構築されたブックメーカーアプリETCGameとは? ETCGameとは、イーサリアムクラシック上に構築されたブックメーカー(ベッティング)サービスです。 ブックメーカーサービスは、必ず「胴元」が中心にいるため、偽装などの問題が発生しやすくなります。同サービスではETCブロックチェーンを利用することで公平性・透明性が高く、かつ手数料無料のベッティングを提供するとされています。 また、予測結果が発表された後、リアルタイムでスマートコントラクトに従って自動的に利益が分配されるようになっています。これにより、プラットフォームの運営コストも低下させることが可能です。 ETCGameではベッティングのカテゴリーも豊富で、現在はスポーツ、金融、政治、娯楽,eスポーツの5つのジャンルが存在しています。 現在は、ワールドカップの真っ只中であり、ワールドカップの試合予想なども簡単に行うことが可能です。 ETCgameの遊び方 まずは、ETCgameのサイトにアクセスを行いましょう。 現在のETCgameではワールドカップと、通貨予測の2つが対応しています。 今回は、ワールドカップを楽しむために、ワールドカップを予測しようと思います。 チェニジア VS イングランド戦ですね。そして、我らが日本も明日にコロンビアと戦いです。 遊び方 ゲームに参加するには、ETCに対応したオンラインウォレットが必要になります。 オンラインウォレットのアカウントを持っていない場合は、ゲームを始める前に、ウォレットのアカウントを取得してください ETCに対応しているオンラインウォレットにはClassic Ether Walletがおすすめです。何か馴染み深いウォレットのUIですね。。。笑 注意! 取引所の口座ではゲームに参加できません。 取引所の口座からの送金は、拒否される可能性があります。 さて、どの試合の予想をするか決めたら、その試合をクリックします。 今回は日本VSコロンビアの勝敗や、ハンディキャップ、オーバーアンダーなどを予想します。 例えば、日本がコロンビアに勝つと思ったら、下記のように、日本を選択するとコントラクトアドレスが発行されます。 このアドレスに対して、オンラインウォレットから送金を行うと、準備完了で、あとはゲームを待つだけです。 賭けたゲームが終了したら、結果は自動的に計算されて、スコアに反映されます。 もし、予想が当たっていた場合は、賞金は自動的にオンラインウォレットのアカウントに振り込まれますので、払戻し手続きなどは不要です。 万が一不測の事態が起こった場合(例えば試合が成立しなかったなど)も、賭け金は自動的にあなたのオンラインウォレットのアカウントへ払戻されます。 まとめ EthereumClassic上のブックメーカーアプリETCGameでしたが、是非とも友達と一緒にでも遊んでみてください。 ブックメーカーとスマートコントラクトの相性は個人的にはかなり良いのでは?と考えています。 4年に一度のイベントをブロックチェーンのアプリで遊ぶなんて、なかなかないと思いますよ!私もやってみようと思います。

特集・コラム
2018/06/16中央型から分散型へ:EUが見据えるデータ管理の新しい信頼モデル
はじめまして。五月雨まくら(@samidare_makura)です。 経済活動の活性化には、企業の製品(プロダクト)やサービス、労働者が市場ニーズに応じて柔軟に移転できるシステムが必要です。そのためには「データ」のやりとりが非常に重要な役割を担います。 確かに、インターネットやクラウドサービスのおかげで、データを自由にやりとりすることは容易になりました。しかし、欧州委員会(以下、EC)の取り組みである「Building a European Data Economy」が提起するように、ローカライゼーション制限やデータの移転に関する規則の欠如により、データのやりとりにはいくつか障壁あります。 データの信頼性を保証する検証方法の欠如 ECは、GDPR(General Data Protection Regulation)などの規制を打ち出し、データのやりとりに関する枠組みに対して提案を行い、データのやりとりに関する障壁を取り除くために尽力してきました。 これらの取り組みは重要なステップですが、現在のインターネットにおける最大の問題の一つであるデータの「信頼性」については言及していません。 オンラインでショッピングをした人の誰もが知っているように、インターネット上における信頼の有無は大切な意味を持ちます。 例えば、販売主が商品をきちんと配送してくれることを信頼できますか?商品が偽造されていないと信じることはできますか?これらの懸念に対する対応としては、レイティングシステムがありますが、十分な情報が集まっていない場合は多々あります。 これらはEコマースにおける懸念のほんの一部ですが、重要な示唆を与えてくれます。個人および法人の経済圏がインターネット上で拡大していくにつれて、日常的なトランザクションのために、さまざまな種類のデータを検証する必要があります。しかし、肝心の方法については決定打に欠けているのが現状です。 信頼性モデルの過渡期 現在、データはプラットフォームに基づくビジネスモデルに集中管理されています。さらに、ネットワーク効果により一部のプラットフォームがデータを独占的に制御、成長を続けるとともに影響力が拡大していくと推測できます。 このモデルでは、単一障害点(SPOF)を持つ中央型プラットフォームへの依存により、セキュリティリスクが肥大化する恐れがあります。 例えば、1億4500万人以上の個人データが盗まれた「Equifax breach」や「Facebook」による5000万人以上のユーザデータの漏洩などが印象的だと思います。 このような懸念があるため、データの信頼性を保証する新しいアプローチが求められます。そこで登場したのが、分散型ネットワークに基づく信頼モデル「ブロックチェーン」です。 ブロックチェーン技術が注目されている理由の一つは、中央型の信頼モデルへの依存における問題を解決する方法として期待されているからです。このモデルではデータの真正性を、分散型のP2P(Peer-to-Peer)ネットワークに参加するノード(ユーザ)による検証によって証明することができます。 データを管理することは組織にとっては大きなリスクとなる反面、事業の基盤を強化し得る大切な資産にもなります。それでは、組織はどのようにデータを扱えば、漏洩リスクと規制の圧力を避けることができるのか?これを明らかにすることはGDPRの目標の一つです。 分散型ネットワークによる信頼性の証明 分散型ネットワークによる新しい信頼モデルでは、個人データの持ち主が安全に他者へ情報提供することが可能になります。ここでいう個人データとは、名前、政府ID、住所、健康、学位などを指します。 ブロックチェーン上に直接データを格納することは危険ですので、ブロックチェーンにはデータに対するポインタのみ含まれています。データは、所有者により認証された時のみ、アクセス可能になります。データへのアクセスは政府や企業だけではなく、あらゆる領域のプレーヤーにとって不可欠な要素となります。公共および民間 部門は、分散型ネットワークによるデータの管理を推進するために、試行錯誤する必要があるでしょう。 考察と結論 現在のデータの信頼性モデルの問題は、データを十分に検証できないことです。EUはこの問題を解決しようとしていますが、依然として課題は多いようです。 一方、過去2、3年の間にブロックチェーンに基づく分散型ネットワークが登場して、新しい信頼モデルを提起しました。これは、データを検証するための方法として有力な選択肢です。 ブロックチェーンによる信頼モデルが浸透するためには、ブロックチェーン技術の発展も重要ですが、膨大なデータを抱え込む政府機関と企業組織との協調が不可欠であり、今後の動向を注視する必要があるでしょう。

特集・コラム
2018/06/14仮想通貨業界参入を検討している企業3社とその背景
こんにちは、kaz(@kazukino11111)です。 多くのメインストリームから新規参入のニュースが続いた今年前半の仮想通貨業界ですが、後半においての日本市場も見逃せないものになりそうです。 先日SBIグループが新たな取引所をローンチしましたが、以下の上場企業3社も同様に国内での取引所の開設を検討しているようです。 国内の上場企業は仮想通貨関連事業への関心を強めています。以前マネーフォワードやavexが取引所の設立を検討しているというニュースが流れましたが、今回はそれらの企業とはまた別の企業の名前が上がっています。これらの企業はすでに明確なビジョンを持っており、参入時期は近いと考えられています。 Samurai&J Partners あまり聞きなれないこの名前ですが、Samurai&J Partnersは1996年に創業された会社で、投資銀行サービスやITおよびフィンテック関連のサービスを取り扱っています。同社のウェブサイトでは「上場企業にPIPE(上場株式へのプライベートな投資)というメソッドを使って投資している」と説明されています。 同社の子会社はクラウドファンディングプラットフォームを運営しており、「資産管理を望んでいる個人と資金を必要としている企業を繋げる」と説明されています。同プラットフォームではすでに「仮想通貨マイニングファンド」という目標利回り7%の仮想通貨関連の投資商品が扱われています。 また、Samurai&J Partnersは先日、仮想通貨ホルダー向けの融資サービスを開始する予定があると発表しました。 Appbank Inc(アップバンク) こちらは若者を中心に認知度が高い企業なのではないでしょうか?マックスむらい氏の印象が強いAppbankはストリーミングやビデオコンテンツを通して商品販促を行なっています。同社は2008年にゲームおよびスマートフォン関連のメディア、Appbank.netをローンチしました。 同社は2週間ほど前に@Blastという仮想通貨配布プラットフォームのローンチを発表しました。このプラットフォームではオンライン、オフライン問わずイベントを開催し、仮想通貨の配布を目標としているそうです。 「@Blastはゲームやエンターテイメント関連のコンテンツを通して仮想通貨を配布するWebサービスプラットフォームです。」 Appbankはこのプラットフォームを使って仮想通貨が広く普及していくように努力するとのことです。 I-Freek Mobile(アイフリークモバイル) I-Freek Mobileはスマートフォンユーザーに向けてモバイルコンテンツを提供している企業です。同社は先日、企業プロフィールに仮想通貨取引業を追加したことを報告しています。新たに修正が加えられた企業プロフィールは今月27日に開催予定の株主総会で採用される予定としています。 株式関連の情報を提供しているウェブサイト、みんかぶはI-Freek Mobile社からの引用で以下のように説明しています。 「私たちは、当社および子会社にとってビジネスとなるコンテンツの拡充のほか、将来の事業の発展に備えるべく、仮想通貨交換業を追加しました。」 まとめ 多くの国内企業が仮想通貨事業への新規参入を検討していますが、今後彼らにとって大きな課題となるのは認可のための審査でしょう。みなし業者という法改正後に認可がおりていない仮想通貨取引所が複数社誕生したように、その審査を通過するのは決して容易ではありません。 一方で多くの企業が参入を果たせば市場により多くの資金が流入します。これはすでに仮想通貨に投資している投資家にとっては大きなメリットでしょう。今後の市場規模拡大のためにも新規参入が期待されます。

特集・コラム
2018/06/12世界の大手銀行および金融機関トップ5と仮想通貨の関係性
こんにちは、kaz(@kazukino11111)です。 仮想通貨やそれに関連するテクノロジーが世の中に普及し始めて久しいですが、世界は反仮想通貨派と賛成派にきっぱりと別れています。 しかし、テクノロジーが進歩していくに連れて人々はその魅力を理解し始め、意見を変えることでしょう。 今回は世界トップレベルの金融機関である以下の5つの存在とそれらと仮想通貨との関わり方についてこちらの記事を参考にご紹介していきます。 1.Jamie Dimon(JPモルガン・チェースCEO) Jamie Dimon氏はTime氏が選ぶ世界でもっとも影響力のある人物100人にも選出されている人物で、銀行業で莫大な財を成した億万長者です。同氏は2006年から世界でもっとも大きな銀行のうちの一つでアメリカで最古の銀行でもあるJPモルガン・チェースのCEOを務めています。 Dimon氏は以前から反ビットコイン主義者として知られています。同氏は2014年にビットコインのことを「ひどい価値の保存」と表現しています。また、2017年の9月には以下のようにコメントしています。 「ビットコインは最終的に破裂するだろう。これは詐欺だ。チューリップバブルよりもひどく、決して良い終わり方は迎えない。」 Dimon氏はビットコインが実在しないものだとし、同社のルールに違反するこれに関わる一切の社員を解雇するとしています。 しかし、同氏はただ単に議題について十分な知識を持ち合わせていなかったのかもしれません。今年の1月に同氏は以前の発言を放棄し、「私はあのコメントについて後悔している」としました。そして、「ブロックチェーンは実在する。デジタル円やデジタルドルも実現可能だ。ICOについては個別に精査する必要がある。」と付け加え、仮想通貨に関する味方を大きく変えたことを明かしました。 今年の5月にはアメリカでJPモルガンがブロックチェーンに関連する特許を申請したことが明らかになりました。この特許は分散型台帳などのブロックチェーンに関連する技術で金融機関が支払いの記録を管理する用途などに使われるとされています。 2.ゴールドマン・サックスグループ 世界でもっとも大きな投資銀行のうちの一つであるゴールドマン・サックスは投資銀行、証券取引、資産運用など幅広い金融商品を扱っています。同行は1869年にMarcus GoldmanとSamuel Sachsによって設立されました。20世紀初頭におけるゴールドマン・サックスは新たに創出されたIPO市場でもっとも重要なプレイヤーでした。 ウォール街でも屈指のテクノロジーを兼ね備えた同行は仮想通貨業界においてもその存在感を示し、派遣を握るべく努力しています。 今年の2月26日にゴールドマンサックスが出資するCircle Internet Financialは大手仮想通貨取引所Poloniexの買収を発表しました。 また、5月2日には顧客に対して、ビットコイン先物を取引する為に独自のトークンの提供を開始する可能性を示唆しました。そして、15日にはCircleが法定通貨アメリカドルに価値を裏付けされたステーブルコインを開発していると報じられました。 3.George Soros(Soros Fund Management) George Soros with Michael Ignatieff, recently elected fifth president and rector of the Central European University. https://t.co/MDaZS1uL3y pic.twitter.com/anoqtczX5n — George Soros (@georgesoros) 2016年11月1日 世界的に有名な億万長者であり、金融業者、投機家でもあるGeorge Soros氏はブラックウェンズデーと呼ばれる1992年9月16日にポンドの空売りで10億ドル以上の利益を得たと言われています。彼の創立したSoros Fund Managementは1969年に始まり、現在では260億ドルの資産を管理しています。 同氏は今年1月23日から26日にかけてスイスのダボスで開催された世界経済フォーラムにおいてビットコインを典型的なバブルだとして批判しました。同氏はビットコインに関して「ビットコインは通貨ではない。なぜなら通貨は安定して価値の保存という役割を果たさなければならないが、日に25%も変動する通貨は使い物にならない。」とコメントしました。 一方で、4月6日にはSoros Fund Managementが仮想通貨取引を検討していると報じられました。このニュースによると同社の大規模投資を担当するスペシャリストは内部承認を受け取ったとされています。 4.ロックフェラーグループ(Venrock) ロックフェラーは世界でもっとも裕福かつ影響力のある家系のうちの一つとして知られています。彼らの総資産は一般には公開されていません。 ジョン・ロックフェラーは1870年に弟のウィリアム・ロックフェラーと他のパートナーとともに石油会社を立ち上げました。同社はたちまち規模を拡大し、アメリカの石油市場を独占し、巨万の富を得ました。ジョン・ロックフェラーは歴史上で最初の億万長者と言われ、その資産は現在の価値に換算して4000億ドル(約4.4兆円)と言われています。 ジョン・ロックフェラーの孫の一人のローレンス・ロックフェラーは1946年にロックフェラーブラザーズを立ち上げました。同社は1969年にVenrockに改名され、化学やテクノロジー関連の企業に投資してきました。Venrockはスタートアップに投資することを重視しており、最初の投資ラウンドではAppleとIntelにも投資していたことで知られています。 Venrock Venture Capitalは現在仮想通貨への投資に関して興味を示しています。今年の4月6日にはCoinFundと提携関係を結び、ブロックチェーンのスタートアップに投資していく方針であることを明らかにしました。Venrock社は仮想通貨とブロックチェーンの分野において、長期的な投資に興味があるとしています。 5.ロスチャイルドグループ(Rothschild&Co.) ロスチャイルドはヨーロッパの銀行系財閥として知られており、ロックフェラー家をもしのぐ影響力を誇るとされています。財閥創立者のマイヤー・アムシェル・ロスチャイルドは彼の5人の子供をパリ、ロンドン、ウィーン、ナポリ、フランクフルトといった当時のヨーロッパの主要な金融都市へと送りました。 彼の子供たちはそれぞれの都市で銀行業を拡大させるべく送り込まれました。ロスチャイルド家の資産は家族間で公平に振り分けられたと信じられています。 今年の4月にロスチャイルド家がいくつかの実験的な仮想通貨プロジェクトを計画しているという噂が報じられました。現在まで公に公開された情報はありませんが、IMMOというプロジェクトの名前はオンラインの掲示板でちらほら見かけられています。 Coinspeakerはロスチェイルド家が計画しているとされるIMMOというプロジェクトが同家の資産を管理し、次世代へと継承していく目的の元で開発されているのではないかと予想しています。記事内では、この通貨は基軸通貨的な存在を目指しており、急激な価格変動は起こりづらいとされています。 興味深い話として、ロスチャイルド家がオーナーグループに名を連ねる雑誌The Economistは1988年の時点で世界中で統一された通貨が2018年に登場すると予言しています。(一部ではこれがビットコインを指していると言われていますが。) Are "the Rothschilds" actually remotely as powerful and coordinated as the conspiracy theorists seem to believe, or are they just a group of old-money socialites and all that other stuff is overhyped? Help me learn and decide! https://t.co/rYcyEHhM6F — Vitalik "Not giving away ETH" Buterin (@VitalikButerin) 2018年5月26日 一方でイーサリアム(Ethereum)の創業者であるVitalik Buterin氏は「ロスチャイルド家は現在はそこまで大きな影響力を持っていない。彼らは昔からの資産と高い位に生まれながらにしてありつけた数千の人間のうちの何人かに過ぎない。もし彼らが独自の通貨を作りたいなら自由にすればいい。適度な自由経済の中で会おう」とコメントしています。 ロスチャイルド家の伝記を執筆したFrederick Morton氏はロスチャイルド家の現状を以下のように表現しました。 「今日現在、家族はその存在のうやむやさ、不可視性に気づいている。何名かは、今や、その偉大な伝説のかけらしか残っていないことを理解している。」 つまり、我々が近い将来にIMMOについて新たな情報を得ることはないかもしれない。しかし、我々はロスチャイルド家から何かしらの情報が公開された時の為に準備しておくべきだろう。 まとめ 世界の名だたる億万長者や財閥と彼らと仮想通貨の関係についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか? 今回紹介した5つのプレイヤーの大半が仮想通貨やブロックチェーンに何らかの興味を示しているということは、そこに可能性があるということを意味しています。今後これらの企業や財閥が仮想通貨業界に本格的に参入するとなれば、市場規模は一気に拡大し、技術の発展スピードも加速することが期待できるでしょう。

特集・コラム
2018/06/11世界でビットコインが違法な国5ヶ国とその現状
こんにちは、kaz(@kazukino11111)です。 今回はビットコイン(BTC)の世界各国に置ける法的な定義とそれを取り巻く状況についての記事を見つけたので、そちらを紹介していきたいと思います。 ビットコインは多くの国の政府から好かれているとは言い難い状況にあります。この理由はネガティブな要因殻ではなく、主に各国政府がどのようにそれらを扱っていいかわからないという点にあります。多くの政府は仮想通貨のボラティリティと不十分な規制から取引を控えさせるような勧告を発行しています。 一方で各国の議員は度合いには差があるものの、ビットコインがある程度の市民権を得られるように動いています。 インドやパキスタン、中国などの国ではビットコインに何らかの規制が施行されていますが、以下の5ヶ国ではビットコインは完全に違法なものとして扱われています。 ボリビア ボリビアでは2014年に中央銀行が全ての仮想通貨(政府発行もしくは政府の規制に従うものを覗く)が禁止されています。同国の規制当局は2017年5月に仮想通貨に投資していた投資家60人を逮捕しており、全ての仮想通貨に関連した取引および、使用は違法だとする声明を発表しました。 ボリビア規制当局は仮想通貨取引に関わった場合はピラミッドスキーム(ねずみ講)の普及に関与したとして捜査を進めるとしています。 エクアドル エクアドルは当時の大統領の元で野心的なプロジェクトであるSistema de Dinero Electronico(電子マネーシステム)を2015年前半にローンチしています。これは議会が2014年7月に施行した仮想通貨禁止法と関連していると言われています。 しかし、エクアドル政府のビットコインを禁止した主体と見られたくないという思惑を余所目にビットコインコミュニティは急激に成長していきました。 エクアドル政府の動きは彼らの半仮想通貨の感情と機会主義を反映していると見ることができます。エクアドルは異常なインフレ率と不安定な経済から2000年ごろに自国通貨スクレを放棄し、米ドルを採用せざるを得ませんでした。そのため、エクアドル政府は通貨の支配権を回復することに注力しています。 スクレのハイパーインフレとは?エクアドルの自国通貨であったスクレは1988年には1スクレ硬貨が最高額でしたが、急激な物価の上昇により1996年には通貨最高額が50,000スクレ紙幣となりました。これを受け、エクアドルは2000年3月にスクレを放棄し、アメリカドルを導入しました。 Sistema de Dinero Electronicoはわずか4年未満の期間しか続かず、今年の4月には失効しています。この原因として国民の中央銀行への不信感が挙げられます。彼らにとって2000年のスクレ放棄は記憶に新しく、それを引き起こした原因であるエクアドル中央銀行にお金を預けるということを受け入れませんでした。 エクアドル国民は最悪のケースの際に主権免除の影に隠れる中央銀行よりも幾らかの責任を負うプライベートバンクを好んでいます。そして、電子マネーシステムの普及に失敗したエクアドルは将来的に仮想通貨に対してオープンになる可能性は十分に考えられます。 バングラデシュ バングラデシュ中央銀行は2014年9月に声明を発表し、ビットコインの使用は法の最大限の力を使って処罰される対象になり得るとしました。同国のいくつかの銀行はビットコインおよび他の仮想通貨と関わることによって、半資金洗浄法に基づいて12年以下の懲役が下される場合があると示しました。 一方でこの規制の効果は疑問視されています。バングラデシュ中央銀行は昨年末により詳細な声明を発表して人々に仮想通貨に関して使ったり、取引したり、話すことがないように訴える必要性を感じていると報じられています。そして、このニュースは国民がいまだに仮想通貨に関わっているということを意味します。 アルジェリア アルジェリアの議会はビットコインが薬物売買や脱税、資金洗浄によく使われているという理由からProject de Loi de Finances(PLF)というプロジェクトの一環として仮想通貨の一切の使用を禁止しました。アルジェリアのニュースサイトMaghreb Emergentは「この規制に違反するいかなる行為は法によって裁かれることになる」と伝えています。 マケドニア マケドニアの権力者たちはビットコインが同国の外貨為替に関する法に触れていると主張します。彼らは仮想通貨取引は5年以下の懲役および10,000ユーロの罰金が課される恐れがあるとしています。マケドニアでは、仮想通貨が資金洗浄に使われるという懸念は他国ほど重要視はされていないようです。 まとめ 今回紹介した5ヶ国はあくまで仮想通貨を禁止している国の一例で全てではありません。世界では仮想通貨に関して着々と規制や法整備が進んでおり、状況は常に変化し続けています。 仮想通貨が犯罪などに使われやすいというのはその性質上仕方のないことかもしれませんが、ブロックチェーンなどそれを取り巻くテクノロジーは世界を変える力を持っていると僕は信じています。 また、こちらのHowmuchというウェブサイトでは世界のビットコインに対する規制状況を確認することができるので気になる方はぜひチェックして見てください。

特集・コラム
2018/06/11ママコイナー主婦ミーの仮想通貨ニュース振り返り!【5月まとめ】
ママコイナーのミー(@me_memechan)です。 本コラムでは、前月にあった仮想通貨界隈のまとめニュースをお届けします。 今回は5月に起きた印象に残ったニュースをピックアップしてご紹介します! 毎日の仮想通貨ニュースは私が運営する『主婦が仮想通貨で生活するブログ』で毎日更新しているので、そちらも遊びに来てくださいね♪ さて!では振り返りいってみましょー! 5月の仮想通貨ニュースまとめ 5月は市場の盛り上がりや価格の上昇を期待していた人も多かったようですが、予想とは外れ価格は下降トレンドとなっていましたね。 価格は元気がありませんでしたが、仮想通貨のニュースでは良いニュースが多かった印象です! 規制等のニュースよりも5月は仮想通貨事業に参入すると発表した企業は非常に多かったですね。 価格が低迷する中、たくさんの企業が参入を発表したのでこれから仮想通貨市場が発展していくという判断したと考えられます。 では、まずは印象に残ったニュース4選のご紹介です。 【5/10】DMMの仮想通貨取引所コインタップが開設延期!? DMMグループが2018年の春に開設予定としていたcointap(コインタップ)のオープンが延期となりましたね。 延期の理由としては、仮想通貨交換業の登録の申請に苦戦しているとのことでした。 引き続き準備は進めているようですが、万全な体制が整ってからのリリースを目指すようですね。 期待されていただけに延期は残念なニュースでしたね。 ⇒ 5月10日のその他のニュースをミーのブログでチェック! 【5/18】コインチェックでXMR、DASH、ZEC、REPが取扱い廃止! コインチェック公式より、2018年6月18日をもってモネロ(XMR)、ダッシュ(DASH)、ジーキャッシュ(ZEC)、オーガー(REP)の取扱い廃止となるお知らせがありました。 匿名通貨の取扱いはマネーロンダリングなどの観点から以前から懸念されていました。 新たな体制になるコインチェックとしては、管理体制を整備・強化するのに懸念のある通貨を取扱うことは適切でないということのようです。 ちなみにオーガー(REP)は匿名通貨ではないですが、一緒に廃止となってしまいました。 コインチェックを買収したマネックスの松本社長が、コインチェックを6月中に再開すると語っていたので、この廃止日の6月18日あたりでまた何か発表があるかもしれませんね! ⇒ 5月18日のその他のニュースをミーのブログでチェック! 【5/29】金融庁FX証拠金倍率10倍は見送り 4月末に金融庁は「年内にもFXの証拠金倍率の上限を25倍から10倍に引き下げることを検討する」と発表していました。 しかし、FXの証拠金倍率の上限の引き下げは見送りとなり、現行の25倍に据え置く方針を固めたようです。 投資家のリスクを減らすために証拠金倍率の上限を25倍から10倍に引き下げることを検討していましたが、一方では、証拠金倍率を引き下げることで、高い倍率で取引できる海外業者に顧客が流れる等の問題提起がされていたようです。 投資家のリスクを減らすために、やみくもな規制・規制ではなく、この金融庁の判断は良いニュースとなりましたね! ⇒ 5月29日のその他のニュースをミーのブログでチェック! 【5/30】GMOコインでアルトコインのレバレッジ取引が開始! GMOコインでアルトコインのレバレッジ取引が開始されました! FX対応通貨は、イーサリアム(ETH)、ビットコインキャッシュ(BCH)、ライトコイン(LTC)、リップル(XRP)の4通貨です。 今までは国内でアルトコインのレバレッジ取引が可能な取引所はDMMビットコインのみだったので、GMOコインがアルトコインのレバレッジ取引を開始したことは非常にグッドニュースとなりましたね。 FXを行わない方にはあまり関係のないニュースかもしれませんが、取引所機能が追加されグレードアップしているという良いニュースだと感じました。 ⇒ 5月30日のその他のニュースをミーのブログでチェック! 5月は仮想通貨事業参入の企業が続々と登場した! 5月の後半になると仮想通貨事業へ参入する企業が続々とニュースになり、毎日のように取り上げていました。 ・5/30 gumiが仮想通貨事業への参入を発表! ・5/25 エイベックスが仮想通貨関連事業に参入! ・5/24 大和証券が仮想通貨業界に参入! ・5/23 マネーフォワードが仮想通貨交換事業に参入! ・5/22 イギリスのLMAXが仮想通貨取引に参入! 6月からの仮想通貨ニュースについて 現在分かっている6月の注目されるニュースといれば、取引所SBIバーチャルカレンシーズ(SBIVC)の開業と、新体制のコインチェックの営業再開ではないでしょうか。 ちなみにSBIVCは6月4日に事前登録していた方の先行リリースとなり、一般の本リリースは7月からのようです。(6月8日に執筆。5月まとめ遅くなりすみません…) また、日本の金融庁の規制や取締りもただ単に厳しいだけでなく、正しい規制やルールというものが徐々にできてくるのではないかと考えています。 6月は仮想通貨事業へ企業参入がさらに増えることも期待できますし、仮想通貨市場は良い方向に進展してくのではないでしょうか。 仮想通貨の価格も5月を底に、6月は価格の上昇も考えられるので盛り上がってくれると嬉しいですね!

特集・コラム
2018/06/10無料でビットコインがGETできるゲームアプリ「金塊ハンター」の紹介
今回紹介するのは金塊ハンターというスマホアプリです。 ゲームをプレイすることで、ビットコインがもらえるアプリということでプレイしてみました。 今回の記事では近海ハンターに関しての内容をまとめてみたいと思います!! 金塊ハンターはどんなゲーム? 金塊ハンターはタワーディフェンスRPGと言われるタイプのゲームです。 ダンジョンで自動で動く勇者をゴール地点まで敵から守り続けることがこのゲームの目標です。 ゲーム自体にリアルさはなくデザインはとても可愛らしい感じとなっていますね。 このダンジョン内にところどころに散らばっている青い丸に自分のユニット↓を召喚することができます。 ステージは全部で24個あり、クリアすると次のステージにいけるシステムになっています。 おすすめポイント それでは、金塊ハンターのおすすめすべきポイントを纏めていきます。 ビットコインがもらえる 金塊ハンターの最大のポイントがこの「ビットコインがもらえる」という点です。 モンスターを倒すと稀にビットふくろ↓というのを落とすことがあります。 ステージをクリアすると集めたビットふくろを自分のビットコインとして保有することができます。 集めたBTCは自分のウォレットなどに移すことが可能となります(0.002BTCから換金可能) ビットコインを買ってみたいとか興味ある方向けのきっかけとしてはとても良いですね。 わちゃわちゃして爽快 ゲーム終盤になってくると、敵と自分のユニットが大量にフィールドに存在してお祭り状態になります。 あっちこっちから「ズコッ!バコッ!ブシュー!!ボフボフッ!」と聞こえてきます笑 この状態から上手く切り抜けられた時はめちゃくちゃ爽快です。 タワーディフェンスゲームとして考えても、なかなか面白くなっています。 ユニットの能力を考えたチーム編成 ユニットには大きく分けて4種類のタイプ(遠距離、近距離、回復、魔法)があり、全15種類のユニットから最大5ユニットまで選択することができます。 この組み合わせを上手く考えていくのがこのゲームの大きなキーポイントになります。 また、ユニットを進化させると攻撃がパワーアップされるのでそこも楽しいポイントです。 → どれぐらいビットコインをゲットできるか 気になるどのぐらいの量のビットコインをゲットできるかですが1日でゲットできるBTCの上限があるので一気に沢山ゲットすることは残念ながらできません。 自分がやった時は1時間半ほどで0.0245mBTC程ゲットできました。 もらえるビットコインは少額ですが、ゲーム自体が面白いですしゲームをやってるだけでビットコインが少しもらえるのは嬉しいと思います。 お子さんのお小遣い稼ぎや、ビットコインをまだ持っていない方などは持つきっかけとしても良いと思います。 【トークン実装予定】超面白い!トレーディングカードゲームNova Blitz まとめ ざっくりとした説明でしたがいかがだったでしょうか。 ゲームをしながらおこづかいビットコインがもらえる金塊ハンター。 ビットコインにもらえるもらえないに関わらずゲームとして面白いので気になった方は是非やってみてください! *ダウンロードはこちらからiOS版、Android版

特集・コラム
2018/06/06「メインネットローンチ」とは?トロン / $TRX のメインネット移行手続きも解説!
Crypto Times公式ライターのYuya(@yuyayuyayayu)です。 5月末に入って、トロン / $TRX やイーオス / $EOS などの有名なプロジェクトが次々と「メインネットローンチ」の実施に踏み込んでいます。 メインネットとは一体どういう意味なのでしょうか?また、このローンチによってサービスにどのような変化がもたらされるのでしょうか? そして、ローンチを控えているトークンの所有者は何かしなければならないことがあるのでしょうか? コインとトークンの違い メインネットについて理解する上でまず知っておかなければならないのが、コインとトークンの違いです。 コイン、またはネイティブトークンとは、独立したブロックチェーン上に存在する仮想通貨のことを指します。 例えば、ビットコインネットワーク(ブロックチェーン)を維持する上で使われるのがビットコインです。イーサリアム / $ETH やネオ / $NEO なども同様のカテゴリーに属します。 これに対し、トークンとは上記のような他のブロックチェーン上にDAppsとして存在する仮想通貨のことを指します。 例えば、テザー /$USDTならオムニ / $OMNI、バイナンスコイン /$BNB ならイーサリアムのブロックチェーン上でそれぞれ成り立っています。 ICOは必ずしも「コイン」配布ではない ここで、ICOについてもう一度振り返ってみましょう。ICOはイニシャル・コイン・オファリングの略ですが、実はここで配布される仮想通貨の大体はトークンです。 プロダクトを開発する上で資金が必要なので、先にトークンを配布することで開発費を募る、というのがそもそもICOなのです。 そうなると、上記のトロンやイーオスのような、独立したブロックチェーン開発するためにICOを行ったプロジェクトはどのようにしてプロダクト完成前にコインを配布したのでしょうか? もちろんブロックチェーンの完成前にコインを配布できるはずがないので、こういったプロジェクトはプロダクト完成後に「コインと交換する」という約束の元、別ブロックチェーン上でトークンを生成し配布するのです。 例えば、トロンもイーオスも、ICOで配布されたものはイーサリアムのスマートコントラクトを利用したERC-20トークンです。 独立したブロックチェーンが完成するまでの間は、いわば「仮コイン」または「引換券」のような形でトークンを保持し、完成後に本物のコインと交換できる、ということなのです。 メインネットとは? それでは本題に戻りましょう。トロンやイーオスなどが行う「メインネットローンチ」とは一体どういう意味なのでしょうか? メインネットローンチとはズバリ、独立したブロックチェーン(=プロダクト)の完成・公開を意味します。 従って、ICOなどで配布された、別ブロックチェーン上に存在するトークンを、完成したブロックチェーンに移植できるわけです。 また、そもそも独立したブロックチェーンを必要としない(他チェーン上のスマートコントラクトで成り立つ)プロジェクトにはメインネットローンチというイベントは存在しないことがわかります。 まとめると、メインネットローンチには次のような意義があります。 独立したブロックチェーンが正式に誕生した プロダクトが存在する、開発がきちんと進んでいる=プロジェクトはスキャムではなかった 他のブロックチェーン上に存在するトークンからメインチェーンのコインに変換が行える 移植には手続きが必要? トロンやイーオスであれば、これまでのERC-20トークンはメインネットの公開と共に移植が行われるわけですが、保有者はこれを行うのに特別な手続きが必要なのでしょうか? 厄介なことに、これはプロジェクトによりけりとなっています。よって、それぞれのプロジェクトからの指示をきちんと読む必要があります。 今回は、トロンのメインネットへの移行手続きを例に説明します。 トロンのメインネット移行手続き トロン公式ウェブサイトによると、同通貨のトークン移行手続きは6月21日から25日の間にかけて行われるとされています。 取引所のウォレットで保有しているトークンが自動で移行されるため、それ以外のウォレットで保有しているものは6月24日までに取引所のものに移すようにとされています。 21日から25日の間は全取引所で$TRXの引き出し、また25日には預け入れも一時停止されるもようです。 今回の移植に間に合わなかった場合でも、後日公式サイトから変換が行えるとされています。 まとめ メインネットとは、イーサリアムやビットコインのような独立したブロックチェーンのことを指し、メインネットローンチはこのような独立したブロックチェーンを新たに始動するということでした。 もちろんプロジェクトはメインネットローンチをして終わりではなく、今後もプロダクトの改善を行っていきます。 こういったアップデートの中には今までのチェーンが不成立になるような極端なものも多く、チェーンが二つに分かれてしまうハード・フォークという事態が起こることも少なくありません。 ともかく、メインネットローンチが実施されてようやく、ブロックチェーン・プラットフォーム系のプロジェクトはプロダクトを正式に公開したといえます。
















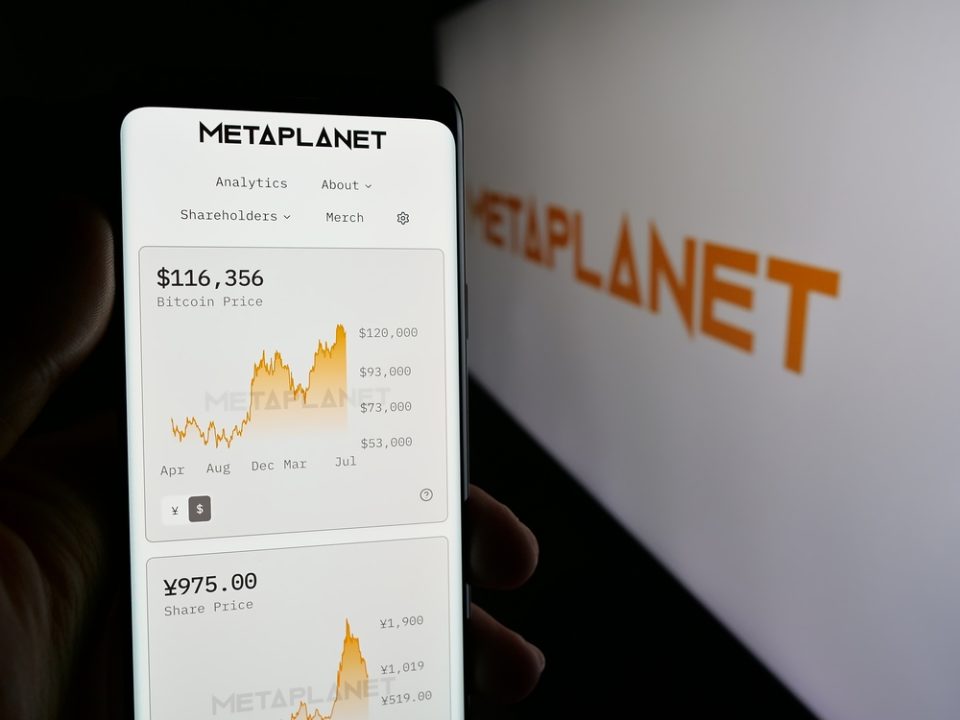

 有料記事
有料記事


