
プロジェクト
2018/07/18DREPの特徴・将来性を解説!競合比較まとめ
DREPは評判データに基づくエコシステムの構築を目指すプロジェクトです。 QuarkChainとの提携が発表されたこと、(チームに美女が多いこと)もあり、注目度が高まっています。 こちらのページでは、そんなDREPの特徴についてまとめています。 これを読めば、基本的な特徴からメリット・デメリットまで、DREPについてはバッチリです。 仮想通貨DREPのICOの概要を確認しよう https://www.youtube.com/watch?v=OL1yRpkiHME DREPの概要 通貨名/ティッカー DREP(ドレップ)/DREP 創業者(Co-Founder) Matt Bennice Stephen Xu Momo Chang 主な提携先 QuarkChain、Zebi、Triipなど 特徴 分散型評判エコシステム 公式リンク Webサイト Twitter Telegram 日本公式Telegram Medium Steemit Reddit Kakao Talk Facebook Linkdin ICO情報とトークンメトリクス DREPのICO情報 WhiteList ~2018/06/31 規格 ERC20 支払い ETH,QKC 発行枚数 10,000,000,000 DREP ICO調達額 総額 19,800,000 USD Privatesale 4,000,000 USD PrivatePresale 3,900,000 USD PublicPresale 7,300,000 USD Crowdsale 4,600,000 USD CrowdSaleレート 1 QKC = 0.00770 USD DREP Chainとしてメインネットがリリースされるまで(2019年Q1(1月〜3月)を予定)は、DREPトークンはERC20トークンとして発行されます。 また、メインネットがリリースされるまでは、一部のDRApps(DREP上のdApps)での決済手段として使われることになっています。 DREPのトークンメトリクス 用途 割合 マーケティング/戦略的パートナーシップ 40% トークンセール 30% コミュニティ発展/貯蓄 15% チーム 15% プライベートセール、プライベート・パブリックプレセール、クラウドセールなどを含めた、セール分は全体の30%と少なめになっています。 DREPが作る評判エコシステムとは?DREPの仕組みを解説 DREPは分散型評判エコシステムを作るためのブロックチェーンです。 よく勘違いされがちですがプロトコルではなく、DREP上にあるプロトコルやプラットフォームを含めてエコシステムを構築していこうというプロジェクトになっています。 レビューをよく見るように、インターネットにおいて「評判」というものは非常に価値が高いものです。 それをブロックチェーンという透明性が高い技術を用いて単一化していこう、というプロジェクトだと考えるととても理解しやすいですよ。 3つのレイヤー(層)で構成される評判エコシステム DREPは3つのレイヤーから構成されていて、ほとんどのユーザーが触れる(使用する)のはアプリレイヤーです。 下のレイヤーの仕組みを用いて上のレイヤーを構成していくイメージですね。 3つのレイヤーに分割することで、より効率的にエコシステムを広げることができます。 レイヤーの概念 洋服で例えると… インフラレイヤー=糸 コアサービスレイヤー=生地 アプリレイヤー=服 このように考えるとわかりやすいですよ。いきなり糸から服を作るのは難しいですが、生地にして加工しやすくすると、より効率的に作業を進めることができます。 各レイヤーでの詳しい役割についても、少し掘り下げて解説します。 インフラ層(DREP Chain)/Infrastructure Layer インフラ層はデータベース、シャード、トランザクション、EVMなど、DREPのチェーンを構成している部分です。 DREPが実現させようとしている、評判エコシステムの構築には様々な障壁があります。 具体的にはスケーラビリティ対策、プライバシー・セキュリティ対策、ネットワークの更新、スマートコントラクト実装、トークン発行機能実装、インセンティブシステム構築などです。 これに対応するため、DREPはインフラレベルからチェーンの開発に取り組んでいます。 DREP Chainの取り組み シャーディングによるスケーラビリティ対策 評判をトークン・収益化するためのインセンティブメカニズムの調整 分散型統治プロトコルによる拡張性 IFPSなどの分散型ファイルストレージへの対応 DREP ID(アカウント)の制御・管理機能の実装 コアサービス層/Core Service Layer コアサービス層は、DREPのエコシステムの仕組みを維持、向上するための機能を蓄えておくようなレイヤーです。 DREPのシステムに関わる機能 評判の数値化アルゴリズム 評判が集まるようにするための仕組み ネットワーク内で評判を共有するシステム(ユーザーデータプール) フェイクアカウントを識別するシステム オープンソースコード統合ソリューション DREPという評判エコシステムが発展するための機能が凝縮されています。 アプリ層/Application Layer アプリ層は、ユーザーが実際に利用するDRAppsやDRApps用のプラグインが実装されていきます。 このアプリレイヤーはいうまでもなくインフラレイヤー、コアサービスレイヤー上にあるので、DREPネットワークのユーザーデータプールやインセンティブメカニズムを簡単に利用することができます。 DRApps・プラグインの例 企業やプラットフォームが作成するDRApps DREPネットワーク内トークンの取引機能 ウォレット ブロックチェーンエクスプローラー 投票プラグインやブログテンプレート DREP・REPXの2種類の基本的なトークンがある DREP REPX 種類 アセットトークン ステーブルコイン 用途 / 目的 ガス サービス利用費 評判資産 DRAPPsの共通通貨 ヘッジツール 評判通貨 DREPネットワークにはDREP・REPXの2種類のトークンがあり、それぞれ用途が違います。 REPXはDREPネットワークがうまく稼働したのちに発行される予定です。 さらにこれに加えて、DREP上のプラットフォームでは独自の仮想通貨(トークン)を発行することができます。 その独自トークンはネットワーク内の各ユーザーの評判値と連携していて、各プラットフォーム内でのマネタイズや信頼性の向上に役立ちます。 Point DREPネットワーク内でのトークン交換ができる取引所のようなものもリリースされていくことになっています。 4つの経済モデル(インセンティブモデル)で自律的なエコシステムを構築する DREPは4つのインセンティブモデルを実装しています。 これによって評判エコシステムが自発的に成長していくような仕組みを実現させることが可能です。 DREPのインセンティブモデル Vote(投票経済モデル) …コンテンツやサービスへの投票 ReputationEndorsing(支持経済モデル) …かけのようなシステム ReputationTipping(評判チップ) …投げ銭のようなサービス ReputationValue-Adding(評判による価値付与) …支持(サポート)に対する報酬 QuarkChainやZebiなどの注目プロジェクトとのパートナーシップがある DREPの注目度が高い理由の1つが注目プロジェクトとの提携・パートナーシップです。 特にICO直後に最大12倍ほどになったQuarkChainとの提携は注目度が高くなっています。 名ばかりの提携ではなく、提携先との連携内容や、なぜ提携するのかなどもきちんと公開されているので、パートナーとの協業内容についても確認しておきましょう。 DREPの提携一覧 Quarkchain Comebey Ziggurat Yozma Group Triip Zebi DREPのユースケースを紹介!可能性・将来性を徹底考察 DREPが実際にどのように世の中で使われていくのかに焦点を当てて解説しています。 インターネット上に分散している評判・評価を誰もが活用できるようになる インターネット上で評判・レビューというものは分散してしまっています。 DREP上にある評判データはすべてDREPネットワーク内で共有されるので、そのように評判が分散することはありません。 多くのプラットフォームがDREP上に作られていけばいくほど、評判データは大規模で信頼性が高いものになります。 具体例で理解しよう ある化粧品について、Amazon・楽天市場・アットコスメ・Twitter・Instagramでは異なる評判があり、それらを単一化して比べるのは面倒です。もしこれらすべてのサービスがDREP上にあれば、ユーザーはより多くの評判を参考にすることができます。 サービスのプラットフォームごとに最適な評判(レビュー)システムを搭載できる DREPのエコシステムを使えば、簡単にプラットフォームに"最適な"レビューシステムを搭載することができます。 "最適な"というのは、プラットフォームごとに独自の評価軸やランキングを簡単に設定できるということです。 "最適な"評判システムとは 例えば、Eコマースプラットフォームではレビューといっても「迅速さ」「丁寧さ」「サポート体制」など、様々な評価軸があります。 DREPのシステムを使えば独自の評価軸を簡単に設定できる上に、それを簡単にランク付けすることが可能です。 また、各ユーザーのデータはDREP内のプラットフォームと共有されるので、より多くのデータを集めることができ、正確性が高いものになります。 ステマや嘘レビューをなくすことができる DREPのシステムを使えば、嘘のレビューやステマ、報酬ありきの高評価レビューをなくすことが可能です。 DREPの評判データは、評判を投稿・発信する個人(DREPアカウント)と結びついています。 もし嘘のレビューや評判を発信して、それが嘘だとわかったときは、その個人(アカウント)はDREP内での評判を下げることになります。 DREP内では評判値が高いユーザーにインセンティブがあること、リクルーティングや金融などの信用性が大切なプラットフォームも参入が考えられることから、評判値はできるだけ高く保ちたいと考えるはずです。 コンテンツ(Blog)プラットフォームで良い記事を書いたり評価したりしてトークンを稼げる DREPネットワーク内では良いコンテンツを作ったり、良いコンテンツを先立ってシェアしたりすると、その見返りとしてトークンをもらう(稼ぐ)ことができます。 ALIS、Steemitやなどに似ていますね。 ただ、DREPはあくまでエコシステムの中の1つの機能として、このような評価機能があるという違いがあります。 この評価機能によってDREP内ではより良いコンテンツが生まれるようなモチベーションが保たれます。 ICOでは確認必須!DREPのロードマップを確認しよう DREPのロードマップについてもきちんと確認しておきましょう。 やろうとしていることが大きいプロジェクトなので、スピード感、プロジェクトの進み方はよく確認しておく必要があります。 DREPのロードマップ 時期 内容 2018年 Q3 南陽センター行政センターとの共同ブロックチェーンラボとトレーニングセンターの設立 評判定量化アルゴリズムライブラリの開発 アプリケーション層でのプラグインの開発 最初のDRAppの稼働開始 2018年 Q4 サードパーティのKYCインターフェイス開発 コンテンツプラットフォーム用のサードパーティIP保護導入 βテスト 2019年 Q1 メインネットリリース DREPウォレットリリース ブロックチェーンエクスプローラリリース サードパーティ評判アルゴリズムライブラリの紹介 2019年 Q2 プラグインと派生アプリのさらなる開発 クロスチェーンの導入 2019年 Q3 AI+意味分析による評判解析 評判コネクタのプロファイリング・フィルタリングの仕組み開発 2018年Q3 2018年 Q3 南陽センター行政センターとの共同ブロックチェーンラボとトレーニングセンターの設立 評判定量化アルゴリズムライブラリの開発 アプリケーション層でのプラグインの開発 最初のDRAppの稼働開始 開発段階である一方、DREP Chain上で運用されることになる最初のDRAppが稼働します。 最初に稼働が予定されているDRAppはBlockbateというSteemitのようなプロダクトです。 Blockbateのテスター募集がされているように、プロジェクトはきちんと進んでいることがわかります。 Here's an illustrated guide to Blockbate #Blockbate #dApps We are now recruiting Blockbate testers! Click the link and sign up to become a tester for Blockbate. You will have the opportunity to receive 20,000 DREP tokens as a reward.https://t.co/SPpbd0KNbJ pic.twitter.com/rY39CRWlZy — DREP Foundation (@drep_foundation) 2018年7月12日 2018年Q4 2018年 Q4 サードパーティのKYCインターフェイス開発 コンテンツプラットフォーム用のサードパーティIP保護導入 βテスト メインネットの稼働に向けて開発が進む段階です。 βテストがきちんと実施されるかが、メインネットまでのチェックポイントになりそうです。 2019年Q1 2019年 Q1 メインネットリリース DREPウォレットリリース ブロックチェーンエクスプローラリリース サードパーティ評判アルゴリズムライブラリの紹介 メインネットがリリースされ、DREPネットワークが本格稼働します。 以降はDREP側の開発はもちろんですが、マーケティング・広報でどれだけ外部プロジェクトをDREPに招き入れることができるかがポイントになりそうです。 2019年Q2 2019年 Q2 プラグインと派生アプリのさらなる開発 クロスチェーンの導入 クロスチェーンソリューションを導入して、より多くのdAppsで評判データを集めることが期待されます。 2019年Q3 2019年 Q3 AI+意味分析による評判解析 評判コネクタのプロファイリング・フィルタリングの仕組み開発 AIにより、テキストデータからより多くの評判データを効率的に取り込めるように開発を進めていきます。 これ以降については随時アップデートされるロードマップを確認していきましょう。 DREPの主なチームメンバーを紹介!バックグラウンドをチェックしよう DREPのチームメンバーについて簡単に紹介しておきます。 どんなバックグラウンドを持っているメンバーが集まっているかを確認しておきましょう。 Matt Bennice/共同創業者 元Google、Xのソフトウェアエンジニア。エキスパート技術者。Google+、YouTube、アクセンチュアなどで10年以上の勤務経験があり。 ジョージワシントン大学(コンピュータサイエンス)修士号取得 X 1年11ヶ月 Google 4年2ヶ月 Accenture 8年1ヶ月 Stephen Xu/共同創業者 QTUMの元開発者。MicrosoftとTencentのソフトウェアで開発経験あり。 中国科学アカデミー大学(コンピュータビジョン)修士号取得 中国科学技術大学 修士号取得 QTUM 1年7ヶ月 Tencent 2年8ヶ月 Microsoft 1年 Momo Chang/共同創業者 FinTechのエキスパート。証券アナリスト、投資マネージャーなどの経験あり。 南陽工科大学(経済)修士号取得 オリエント証券 10ヶ月 Kylin Investment 3ヶ月 TNS市場調査コンサルティング 5ヶ月 Eric Chao/開発責任者 iQiyiとEle.meでシニアエンジニア経験あり。ACM-ICPC、MCMなどでプログラミングコンテストの賞を受賞。 Github Yue Wang/開発責任者 Fengche Techの共同設立者。TencentとLeetCodeにてソフトウェア開発経験あり。 カーネギーメロン大学(コンピュータソフトウェアエンジニアリング)修士号取得 LeetCode 1年7ヶ月 Jiuzhen Tech 5ヶ月 Tencent 1年3ヶ月 Ricial Fan/広報 上海メディアグループで広報を務めた。ブランディング、マーケティング、メディアリレーションで8年の経験あり。 - Parkbox 1年 Bank of Communications 2年 SMG 3年 Belinda Zhou/事業開発 エミレーツ航空、ドバイツアリズムにてコンサルタント経験あり。認定通訳者・旅行コンサルタント。 中山大学(通訳・翻訳)学位取得 Emirates 4ヶ月 Falcon and Associates 10ヶ月 DubaiTourism 5ヶ月 Ms Lien Siaou Sze/ビジネスアドバイザー HPアジア太平洋地域担当の副社長。Fortune誌のビジネスにおけるTop50Women(アメリカ国外)で3年連続トップ10。 ケンブリッジ大学の博士号取得 Hewlett Packard 28年 Qi Zhou/アドバイザー QuarkChainのCEO。ソフトウェアエンジニア。Facebook、Dell EMCでスケーラブル系プロジェクトの経験あり。 ジョージア工科大学博士卒 Facebook 1年 Dell EMC 2.5年 Google 9か月 DREPの懸念点やデメリットも知っておこう 投資するのであれば、きちんとリスクやデメリットについても知っておくことが大切です。 あまり紹介されない部分ではありますが、こちらではきちんと紹介しておきます。 トークンセールは総供給量の30% DREPのトークンメトリクス 用途 割合 マーケティング/戦略的パートナーシップ 40% トークンセール 30% コミュニティ発展/貯蓄 15% チーム 15% ICO概要・トークンエコノミクスでも紹介していますが、トークンセールで販売されるトークンは全DREPトークンのうち30%です。 そして、一番多く配布されているのが戦略的パートナー、マーケティング費用です。 将来的に戦略的パートナーはDREP Concilでマイニング報酬などのパラメーターも決定していくことになるので、マーケットは戦略的パートナーが動かせないこともないのかもしれません。 やろうとしていることが大きい(時間がかかる) DREPが実現させようとしているのは、評判ベースのエコシステムを作り上げることです。 プラットフォームやプロトコルなどの単一のプロダクトを作るだけでは簡単に実現できることではありません。 良いプロダクトはもちろん、スピード感やマーケティングも重要になります。 DREPが目指す世界が実現したら…と考えて投資するのは良いことですが、時間的なリスクがあるということも頭に入れておきましょう。 【DREPの競合比較】ブロックチェーン×評判システムで勝てるのか DREPプロジェクトについてよく理解できたら、競合となるプロジェクトについても確認しておきましょう。 Ink Protocol Ink Protocolはマーケットプレイスのためのプロトコルで、分散管理された評判と決済システムを提供します。 評判を分散管理するという点ではDREPと同様です。 ただし、DREPはそれを数値化して、異なる業種のプラットフォーム(マーケットプレイス以外も含める)に導入しようとしているプロジェクトです。 Inkはあくまでプロトコル、DREPはエコシステムの構築を目指しているという点が一番の相違点です。 STEEM STEEMはオンラインコンテンツを収益化するためのためのプラットフォームです。 STEEMのプロダクトの1つである、SteemitとDREPのコンテンツプラットフォームが類似しているので、競合としてあげられることがあります。 Steemitも、良いコンテンツの投稿者、それをいち早く拡散した人に報酬が付与されるサービスです。 プロダクト自体は似通っていますが、細かいところでは評価のつき方やインフレーションモデルに違いがあったりします。 また、STEEMはコンテンツを収益化すること、DREPは評判エコシステムを作ること、のように目指す先が違うというところも頭に入れておくと良いでしょう。 QuarkChainと提携で注目!DREPプロジェクトまとめ DREPプロジェクトについてまとめました。 実現しようとしていることのスケールが大きいので、長期目線のプロジェクトになる気がします。 私が個人的に日本コミュニティマネージャーを務めていることもあり、ぜひ注目してほしいプロジェクトです(笑) DREPについてもっと知りたい・調べたいと思った人は、ホワイトペーパーを読んだり公式SNSをチェックしたりしてみてください。 日本公式TelegramではDREPの最新情報を日本語で発信していますので、こちらもぜひチェックをお願いします。 公式リンクまとめはこちら

プロジェクト
2018/07/05仮想通貨を利用した信用補完措置が特徴のファクタリング仲介サービス・Versaraとは?
近頃は、仮想通貨を利用して金融商品取引を円滑化するプロジェクトがたくさん現れてきています。 今回はその中で、商品の売り手と買い手のやり取りにまつわるトレードファイナンスと呼ばれる分野で企業の現金調達を援助するプロジェクト・Versaraを紹介します。 Versaraでは、ファクタリングと呼ばれる企業に現金を融資する投機に、フィアットマネーまたは仮想通貨のどちらでも投資を行うことができます。 この記事では、Versaraのより詳しい仕組みやエコシステム、類似プロジェクトとの比較などを一からわかりやすく徹底的に解説していきます。 Versaraプロジェクトとは? 基本情報 プロジェクト名/ティッカー Versara(ヴァーサラ) / $VXR 創業者(CEO) Sean Liu ベースとなるブロックチェーン Stellar / $XLM 特徴 ファクタリング仲介 / フィアットおよび仮想通貨での投資 公式リンク Webサイト Twitter Telegram Medium Reddit LinkedIn Versaraは、企業が売掛金を割引価格で売却して現金を得るファクタリングというサービスを仲介するサービスです。 この現金を利子付きで提供するのがフィアット投資家で、更にデフォルト(売掛金の未払い)時に備えての担保を仮想通貨で提供するのが仮想通貨投資家の役割になります。 まずは、このそれぞれの役割やプロジェクトの仕組みについて詳しく見てみましょう。 売掛金を即座に現金に変えるファクタリング プロジェクトの詳細に入る前に、売掛金とファクタリングとは何かをおさえておきましょう。 企業A(売り手)が企業B(買い手)に1機あたり10万円の機械を10機売ったと仮定しましょう。企業Aは機械の売却により100万円の売掛金(Accounts Receivable)を手に入れたことになります。 売掛金とは、契約で決められた支払日に企業Bから支払われるお金のことを指し、企業Aが現在手元に持っているお金ではありません。 ここで、企業Aが新たなプロジェクトの開発運営のためにどうしても今現金が必要であるとします。 企業Aはここで、先ほど企業Bとの取引で得た売掛金を売却して現金を入手することができます。このように、売掛金を売却して現金を手に入れる方法をファクタリングと呼びます。 通常、この売却によって得られる資金は売掛金自体より低くなります 。この割引率は、売掛金の支払者 (企業B)の信用情報によって大きく左右されます。 売掛金の割引買取と引き換えに現金を企業に提供するサービスを行う会社のことをファクタリング会社と呼びます。Versaraもこのようなサービスを展開するプロジェクトです。 Versaraではフィアットでも仮想通貨でも投資ができる Versaraのユニークなところは、ファクタリングサービスにフィアットと仮想通貨の両方の良さを加えているところです。 フィアットの貸付に仮想通貨の担保を加えることで、Versaraでは売掛金にまつわる商品の売り手・買い手だけでなく、フィアットや仮想通貨の投資家も利益を得ることができます。 フィアット投資家の役割 フィアット投資家(主に機関投資家)が投資したフィアットマネーはVersaraの資金プールに貯蓄されます。この資金が前例の企業Aなどに売掛金の買取と引き換えに提供されます。 売掛金は、Versaraに売却する際に商品の買い手(企業B)がその正当性を認証する必要があり、なおかつこの買い手も外部信用機関などを通して信用情報を精査されます。 期日になると商品の買い手からVersaraに売掛金が支払われ、Versaraはその資金を元にフィアット投資家に元本と利子を支払います。 仮想通貨投資家の役割 もしも商品の買い手(企業B)が売掛金を支払うことができなかった場合、Versaraはフィアット投資家に元本や利子を支払えなくなってしまいます。 このような事態を防ぐために、買い取った売掛金の一部を仮想通貨で担保する役割を担うのが仮想通貨投資家です。 これにより、Versaraでは、商品の買い手が売掛金を支払えなかった時に、担保となっている仮想通貨をフィアットに変換してフィアット投資家に返済することができます。 もちろん仮想通貨投資家側にはこのリスクを取る代わりに、相応のリターンが支払われます。 Versaraの信用補完措置は「二重の壁」 ここまででまとめると、現金を調達したい企業に対しフィアット投資家の資金を売掛金と引き換えに融資するという流れがVersaraのサービスの基軸となります。 しかし、この売掛金支払者(企業B)の中には支払不可(デフォルト)となる者が現れる可能性もあります。 Versaraではこのようなデフォルト時にもフィアット投資家に資金を返済できるように、信用補完措置として「二重の壁」を用意してあります。 プールごとの仮想通貨担保 前項でも解説した通り、Versaraでは仮想通貨を担保として提供することでリターンを得ることができます。 この仮想通貨はそれぞれのプール(売掛金のグループ)の10%から20%を担保すると決められており、売掛金支払者がデフォルトを起こした場合はこの担保がフィアット投資家に返済されるという仕組みになっています。 プラットフォーム全体のリザーブ もし大型のデフォルトが発生して仮想通貨の担保が使い切られてしまった場合、第二の壁として機能するのがこのプラットフォーム全体のリザーブです。 これは、売掛金の取引の際に徴収する手数料(VXRトークン)で構成された貯蓄であり、仮想通貨担保とは違い特定のプールと紐付けされるものではありません。 このように、Versaraではデフォルト時の対策を二段階に設定することでサービスの信用を強固にしています。 新興経済国の中小企業などもファクタリングができるように Versaraによると、アジア圏を主とする新興経済国では銀行の規模が小さかったり多国籍ビジネスが盛んでなかったりすることから、特に中小企業などがファクタリングを行えない状況にあるといいます。 様々なフィアット・仮想通貨を取り扱う予定のVersaraは、サービスをグローバル展開することでこのような中小企業にもトレードファイナンスを行う機会を与えることができると見込まれています。 類似プロジェクトとの比較 Versaraは類似プロジェクトとしてWe.TradeやMarco Polo、Finacle Trade Connectなどを挙げています。 いずれもブロックチェーンを応用したトレードファイナンス系サービスを展開していますが、開発段階初期のものも多い状況になっています。 またどのプロジェクトも基本的には機関投資家向けのプロジェクトとなっています。 名前 Versara We.Trade Marco Polo Finacle Trade Connect 概要 ファクタリング仲介サービス トレードファイナンス全般 トレードファイナンス全般 トレードファイナンス全般 特徴 仮想通貨を利用した信用補完措置 ヨーロッパの銀行9社との提携 ブロックチェーンを利用した業界の統合 B2C・B2B両トレードをカバー 公式にも提言している通り、Versaraのサービスは他社のものと比べ特定の分野(ファクタリング仲介)のみにフォーカスしたものになっています。 ホワイトペーパーによると、Versaraのビジョンは「二重の壁」信用補完措置を他社にも利用してもらい、お互いに共存することとされています。 Versaraプロジェクトの注意点 ファクタリングサービスをグローバルに展開し、フィアットと仮想通貨どちらからも投資に参加することを可能にするVersaraプロジェクトですが、ここでいくつか注意すべき点をまとめておきます。 フィアット投資ができるのは基本的に機関投資家のみ トレードファイナンスにおける投機というのは大口のものが多いため、基本的には金融機関などの大型投資家のみが投資できるものです。 これは、類似プロジェクト比較の項目で紹介した他のプロジェクトも同様です。 VXRトークンはセキュリティトークン VXRトークン(ヴァーサラトークン)は仮想通貨投資家への保証料(リターン)や商品の買い手(企業B)の売掛金認証への報酬として支払われるトークンです。 また、売掛金の売却時に発生する手数料の一部はVXRトークンに変換され、プラットフォームのリザーブに貯蓄されます。 VXRトークンはサービスの利用などに使用されるわけではなく、単純に価値貯蔵の側面や投資的な有用性を持つセキュリティトークンです。 また、VXRトークンはERCトークンではなくStellar(ステラ)ベースであるという点も知っておくべきでしょう。 外部信用機関についての提携情報等の記載は特になし Versaraでは売掛金支払者のKYCやクレジットスコアリングを外部機関に委託するとしていますが、ここで具体的にパートナーシップを結んでいる機関の名前などは公開されていません。 ロードマップ Versaraプロジェクトのロードマップも確認しておきましょう。 2017年10月 Versaraの創設 2018年5月 サービスのプロトタイプ公開 2018年7月 ICOの実施 2019年第一四半期 米国でのプラットフォームローンチ 2019年第二四半期 アジア圏でのプラットフォームローンチ 2019年第三四半期 ヨーロッパ圏でのプラットフォームローンチ 2018年5月: サービスのプロトタイプ公開 このプロトタイプでは、スマートコントラクトの発行や、キャッシュフロー・ロジスティクスの追跡機能に加え、売掛金の支払い受取などができるようになるとされています。 Versaraは6月に入ってから数々のプレゼンや取材などでこのサービスの紹介をしています。 2018年7月: ICO実施 トークンのパブリックセールは今年7月から開始とされています。 また、Versaraではエアドロップなども実施されています。 2019〜: プラットフォームローンチ Versaraは、本拠地である米国からサービスを開始し、その後段々とアジア圏やヨーロッパ圏に進出していくもようです。 特にアジア圏にはファクタリングが行えない中小企業がたくさん存在するため、Versaraにとってはビジネスを拡大する大きなチャンスになると見られます。 まとめ 本記事では、ファクタリングサービスをグローバル展開し、新興国の中小企業にも資金調達の機会を与えるプロジェクト・Versaraを紹介しました。 フィアットでの投資だけでなく、仮想通貨を担保にした信用補完措置などは、とても目新しいものだと思います。 当プロジェクトに興味を持たれた方は、ぜひウェブサイト等をチェックしてみてください!

プロジェクト
2018/07/05DAppsやウォレットを一括管理できる分散型フレームワーク・Essentia(エッセンシア)とは?
ブロックチェーン技術の普及をきっかけに、分散型ネットワークを使用したサービス(DApps)がたくさん登場してきています。 これらのサービスをひとつの分散型ネットワーク上のアカウントで統括しよう、というプロジェクトがEssentia(エッセンシア)です。 このプロジェクトでは、それぞれのサービスに関連する個人情報などをひとつのアカウントに統合することで、各サービスへのログインの簡易化や、個人情報管理の改善などといったメリットが見込まれています。 エッセンシアのプロジェクト・ゴールはインターオペラビリティ(相互運用性)、オンライン上の個人情報の保護・管理と分散型オペレーティングシステムの構築の3つです。 今回は、このエッセンシアの仕組みや、サービスを利用するメリット、uPortなどの類似プロジェクトとの違いなどを徹底的に解説したいと思います。 エッセンシアの概要 通貨名/ティッカー $ESS (ERC-20) 創業者(CEO) Matteo Gianpietro Zago, Mirco Mongiardino 主な提携先 BitFinex, Kenetic Capital, TLDR Capitalと他9社 特徴 デジタル・アイデンティティ・フレームワーク / 分散型オペレーティングシステム 公式リンク Webサイト Twitter Telegram Medium Facebook コンセプト ビットコインの普及をきっかけに、ブロックチェーン技術は大きな発展を遂げ、今では分散型ネットワークを使用したサービス、通称DAppsが次々と登場してきています。 DAppsとは?ブロックチェーンネットワークを利用したサービスまたはアプリケーションのこと。ペイメント、金融、サプライチェーンマネジメント、分散型ストレージ、分散型取引所(DEX)をはじめ様々な分野でDAppsが誕生している。 いくつものサービスを利用していると、都度別のウェブサイト等に移らなければいけないほか、IDやパスワードなどのサービス利用に関する個人データの管理が難しくなります。 そこで、こういった情報やサービスをひとつのアカウントに統合し、あらゆるデバイスからアクセスできる分散型フレームワークを構築しよう、というのがエッセンシアのコンセプトになります。 個人情報を分散型ネットワークを利用してひとつのアカウントに紐付けすることで、他人になりすます「ID詐欺」などを防ぐことが期待されています。 このフレームワークを利用することで、ユーザーはDAppsへのログインや関連する情報の管理などをひとつのアカウントから容易・安全に行うことができるというメリットがあります。 また、エッセンシアでは分散型オペレーティングシステム(OS)の開発も行なっており、プロダクトのコンセプトが可視化されています。 テクノロジー エッセンシアでは、サービス利用に際しメールアドレスや電話番号などといった情報は全く必要なく、シードと呼ばれる文字列とパスワードのみであらゆるデバイスからサービスを利用することができます。 プロダクトのコアとなる部分はフレームワークで、サービスの利用に際しては必ずしも公式から提供されているオペレーティングシステムを使わなければいけない訳ではないようです。 エッセンシアのOSはコンピューター、スマートフォンなど様々なデバイスで利用できますが、フレームワーク自体はIoTやコマンドラインなどでも利用できるとされています。 エッセンシアを利用するメリット ユーザーやデベロッパーは、エッセンシアのフレームワークを利用することにどのようなメリットがあるのでしょうか。 エッセンシアではひとつのアカウントで複数のDAppsへのログインを行えるeLoginという機能が備わっています。 これは、FacebookやGoogle+のアカウントを通じて他のオンラインサービスにログインできる機能と似ています。 この機能のメリットはそれぞれのDAppsでのパスワードが不要になるという点にあります。 また、エッセンシアではDAppsやその他のサービスなどで発生する個人情報も分散型ネットワーク上に存在するアカウントに紐付けされるため、各種サービスでのKYCを円滑に進めることにも役立つことが期待されています。 エッセンシアが提供する分散型オペレーティングシステムは、自分が利用しているDAppsや他のオンラインサービスをひとつのシステムから一括で操作できる便利なものとなっています。 ウォレットや取引所、ストレージなどをはじめとするあらゆるサービスを自分のアカウントと紐付けすることで、様々な種類のデータを一目に管理できるようになります。 ESSトークンとは?7つの特徴を解説! エッセンシアの「ESSトークン」は同分散型フレームワークのネットワーク維持の燃料となる通貨となります。 公式が掲載しているトークンユーティリティに関する文書によると、ESSトークンには7つの特徴があるとされています。 ノード報酬と評判システムの統合 エッセンシアの分散型ネットワークでは、各ノードに一定量のESSトークンをロックさせるPoSコンセンサスメカニズムを採用しています。 悪意のあるブロック承認はロックされたトークンの損失につながるため、各ノードには正当なネットワーク処理をするインセンティブがあります。 スパム対策 ESSトークンには、ボットやハッカーなどによる不正なリクエストを防止する対策が施されています。 スパミングに対しマイナスのインセンティブを施すことで、このような不正行為の阻止が試みられています。 エッセンシアまたはサードパーティへのペイメント ESSトークンはサードパーティの分散型ストレージサービスの容量拡張など一部の有料サービスへの支払い手段にも利用することができます。 価値の貯蔵 - プロダクトやサービスの購入 上記の項目と似ていますが、ESSトークンは導入されているDAppsが提供するプロダクトやサービスへの支払い手段としても利用でき、将来的にはDAppストアの導入も計画されています。 また、この機能はオペレーティングシステム内での通貨の両替のことも指しており、現段階ではESSトークンを含め14種類の通貨に対応しています。 分散型ガバナンス エッセンシアでは、ESSトークンの保有量に応じてプロジェクトの方針決定に際する投票権を得ることができます。 また、一定量以上のトークンを保有するユーザーに何らかのボーナスを与えるという計画も立てられているようです。 評判システム ノード報酬の項目でも紹介した通り、ESSトークンはネットワークへの貢献を助長し、不正行為にペナルティを与える評判システムが導入されています。 インセンティブシステム コンセンサスメカニズムに関わるインセンティブとは別に、エッセンシアではトークンの総発行量の一部が今後プロジェクトの開発貢献者へのリワードとしてリザーブされています。 このリワードの具体的な獲得方法は言及されていませんが、同プロジェクトではハッカソンやカンファレンスの開催も多数計画しているため、このようなイベントでの報酬として利用されるのではと考えられます。 エッセンシアのプロダクトデモ エッセンシアはすでに、上記の分散型オペレーティングシステムのデモを公開しています。 プロダクトの利用に必要なのはパスワードの設定のみで、誰でもこちらから簡単に登録・利用できます。 以下では、現段階でのプロダクトデモでできることを紹介します。 ウォレットの一括管理 エッセンシアのアカウントを作成すると、現段階で14種類の通貨のウォレットが自動で生成され、これら全てをアカウント内で一括で管理することができます。 それぞれのウォレットからの送金などもプラットフォーム内で行うことができます。 また、該当通貨のプライスチャートやアカウント内で所持しているアセットの割合なども自動で表示されます。 ストレージサービスの一括管理 エッセンシアでは、IPFS、SWARM、Storjなどといった分散型ストレージサービスにアップロードしてあるファイルなどもアカウントに紐付けし、一括で管理することができます。 今回作成したテストアカウントでは何もしていませんが、データのアップロードやダウンロード、削除など基本的な操作は全てプラットフォーム内から直接行うことができます。 eLogin eLoginセクションでは、各種DAppsへのログインを行うことができます。 アカウントから紐付けするDAppsへのログインリクエストが一度承認されれば、パスワード不要で自動ログインを行うことができます。 この機能の最大のメリットは個々のサービスごとにパスワードを設定したり記憶したりする手間が省けることにあります。 IDEXへのアクセス エッセンシアでは、分散型取引所であるIDEXにサービス内から直接アクセスすることができます。 オーダーの発注、注文板、取引履歴など全てがプラットフォーム内で完結するようになっています。 今後追加予定の機能 Essentiaでは、フレームワークに対応させたいDAppsなどに投票を行うことができ、公式によると今後さらに多くの機能が追加されるとされています。 類似プロジェクトとの比較 エッセンシアは、類似するプロジェクトとしてCivic、The Key、SelfKey、Remme、uPortを挙げています。 エッセンシアを含め、これらのプロジェクトはすべてデジタル・アイデンティティ系のものとなっており、eLogin、KYC簡易化、ID詐欺防止などといった利点は共通で存在しています。 しかし、エッセンシアではサービスを利用するにあたり特定のアプリやメールアドレス、電話番号などが必要ないという点で類似プロジェクトと大きな違いがあります。 また、uPortやSelfKeyは独自のウォレットを開発していますが、ウォレットも含めストレージや他のDAppsなどを全て統括できるOSを開発しているのはエッセンシアのみとなります。 プロジェクト開発にまつわる長所・短所まとめ ここまででは、エッセンシアのフレームワークの仕組みや、利用するメリット、類似プロジェクトとの違いなどを解説してきました。 ここで、プロジェクトの開発にまつわる優れた点や、懸念点などを挙げてみます。 長所 多数ファンドからの戦略投資・アドバイジング エッセンシアは、BitFinex、Kenetic Capital、TLDR Capitalをはじめとする12社と戦略提携を結んでいます。 これに加え、13種類の仮想通貨・DAppsがすでにシステムに統合されています。 プロダクトデモがすでに公開されている 上記でも紹介した通り、エッセンシアでは分散型オペレーティングシステムのデモがすでに公開されており、実際に誰でも利用することができます。 デジタル・アイデンティティ系のプロジェクトはコンセプトの理解が難しいところがありますが、エッセンシアでは目に見えるプロダクトが存在する点は良いといえるでしょう。 プロジェクトに関する情報が豊富 エッセンシアでは、ホワイトペーパーはもちろん、トークンユーティリティを解説する文書や、ビジネスプラン、さらには専用のウィキなども公開されています。 短所 プロジェクトの内容がとても複雑 エッセンシアには大きく分けて二つのプロジェクトがあります。 ひとつは、複数のDAppsや他のオンラインサービス上に存在する個人情報をひとつのアカウントで管理できるフレームワークの構築です。このプロダクトには、パスワード不要のログインや、ID詐欺防止などといったメリットが見込まれています。 もうひとつは、独自の分散型オペレーティングシステムの開発です。上記で紹介したプロダクトデモなどがこれに当てはまります。このプロダクトでは、複数のDAppsをひとつのプラットフォーム上で利用・管理できるメリットがあります。 エッセンシアはとてもテクノロジー寄りのプロジェクトであるため、上記のようなポイントを理解するのが少し難しくなっています。 他プロジェクトに比べ開発が遅め 紹介した類似プロジェクトは、プロダクトが正式にリリースされているものがほとんどです。 これらのプロジェクトがすでに保有するシェアに対抗し、フレームワークの性能や分散型オペレーティングシステムのマーケティングにどれだけ力を入れられるかに要注目です。 エッセンシアのロードマップ プロジェクトのロードマップも確認しておきましょう。 2018年 Q3 βテスト版の公開、ハッカソンの実施やカンファレンスへの参加 2018年 Q4 政府・法人向けソリューションの提示 2019年 Q1/2 サービスの多言語化、IoTでの応用 2019年 Q3/4 分散型ガバナンスの導入、Essentia主催のカンファレンス 2018年 Q3 上記でも紹介した通り、オペレーティングシステムのデモ版はすでに公開されています。 ハッカソンやカンファレンスの情報はまだ発表されていませんが、ファンドの開設やフィンランド政府との協力などの様々な活動が報告されています。 2018年 Q4 この四半期には様々なソフトウェア・ハードウェアのアップデートがなされる模様ですが、特に注目すべきは政府や法人とのパートナーシップ展開でしょう。 上記の通りEssentiaはすでにフィンランド政府との協力を行なっており、他プロジェクトとのパートナーシップもたくさん結んでいます。 この時期にはより具体的な提携案が登場してくると考えられます。 2019年 Q1/2 公式ウェブサイトおよびOSデモで導入されている言語は現時点で英語と韓国語のみとなっていますが、この時期に言語設定のバラエティを増やすことでより多くのユーザーがサービスを利用できるようになると考えられます。 また、具体的な提案はなされていないものの、同時期にはエッセンシアフレームワークがIoTにも応用される予定です。 2019年 Q3/4 エッセンシアは、ESSトークンの機能性を徐々に向上するプランを立てており、この時期にはトークンにガバナンス機能も付け加えるとしています。 また、EssConと呼ばれる独自のカンファレンスの開催も企画しており、関連・提携するプロジェクトなどを巻き込んだコミュニティの発展が期待されます。 まとめ エッセンシアは、複数のDAppsや他のオンラインサービス上に存在する個人情報をひとつのアカウントに紐付けすることで、eLogin、KYCの簡易化、ID詐欺防止などといったメリットを享受できるフレームワークということでした。 また、エッセンシアは同フレームワークを利用した分散型オペレーティングシステムも提供しており、ひとつのプラットフォームから複数のDAppsにアクセスできるようにもなっています。 先月末に終了したトークンセールでは、ハードキャップの98%(24,815,390USドル)を調達するなど、世界中から支持が受けているようです。 プロダクトの完成にはまだ時間がかかりそうですが、今後のさらなるプロジェクトの発展に要注目です。

プロジェクト
2018/06/10ゲーム内でマイニングができるゲーム「Hash Rush」の紹介
新しいdappsゲームがどんどん出てくる昨今ですが 今回は私、ゆっしが注目しているdappsゲームをご紹介させていただきます。 その名は「Hash Rush」!!! 今年の秋にリリース予定のゲームです。 さてさてこれはどんなゲームなんでしょうか!説明していきたいと思います! どんなゲーム? Hash Rushは「コミュニティ形成」「マイニング」「アイテム交換」の3つが大きな要素となっています。 ユーザーはオンラインで繋がっている他のユーザーと共にコミュニティを作り上げます。 コミュニティを襲ってくる敵も存在するので、色々な防衛策も練らねければいけません。 ユーザーはコミュニティの中でETH(イーサリアム)などの仮想通貨をマイニングしたり、アイテムを集めることができます。 そして集めたアイテムや通貨をP2P(ユーザー同士)で交換することが可能となります。 大人気ゲームのMinecraft(マインクラフト)のような感じですね。 鉄やダイアモンドを探す代わりに、イーサリアムなどの仮想通貨を掘り当てるような感じです。 全体の雰囲気を掴むためにデモ動画をご覧ください↓ https://www.youtube.com/watch?v=jE26UFTh0ok ※Hash Lushは去年ICOを行いRCというトークンを発行しており、このRCトークンはゲーム内での利用も可能なようです。 おすすめポイント グラフィック 先ほど動画を見ていただけた方は分かったと思いますがグラフィックがとても綺麗ですよね。 しかも球体を自由に移動できる3D構造となっており、これまでのDappsゲームにはあまりなかった形となっています。 Hash Lushのブログでプログラミングのソースコードも一部公開されています。 トランザクションで発生する手数料が無い Dappsゲームは、アイテム交換などをする際に手数料がかかってしまうことがあります。 しかし、Hash Rushでは独自の「Rush Network」というネットワークを使うことによってトランザクションにかかる手数料がゼロになります。 Rush Coin transactions in Hash Rush (game) will be handled by our own 'Rush Network' meaning that they will be instant and you will not have to pay gas. More details will be on our #steemit blog soon: https://t.co/qebTb3NCKN #cryptocurrency #gamedev #indiegames #blockchaingame pic.twitter.com/fCXEt0bPBr — Hash Rush (@PlayHashRush) May 16, 2018 このゲームの性質上、頻繁にアイテム交換やアイテム加工するので手数料がかからないのはとても嬉しいですよね。 開発状況を確認できる Hash Rushは現在開発中ですが、その開発状況をHPの記事などで知ることができます。 例えばこちらの記事ですが、キャラクターの家などの建築物のデザインに関してどのようにデザインされていったかが細かく記されています。 この記事ではメインキャラクターであるエルナックの家のデザイン作成の過程などが書かれていました。 また、このような解説記事だけではなく開発メンバーへのインタビュー記事や、誰でも参加ができるコンテストなども開催されており、コミュニティを盛り上げるための試みが多く行われています。 RCトークン Hash Rushは去年RCトークンを発行しICOを行っています。 ホワイトペパーによるとRCトークンはゲーム内で以下のことに利用できるようです ・施設の建設やアップグレード ・コロニーの拡大やアップグレード ・ユニットの購入とアップグレード ・仮想通貨の採掘 ・ユニットの動きを早める(作業の時間短縮) RCトークンをゲーム内で利用する場面が沢山ありそうな感じですね。 また、RCトークンは取引所で購入するだけではなくミッションクリアや他のプレイヤーとのアイテム交換などでゲットできるようです。 まとめ いかがだったでしょうか? マイニングを実際の「採掘する」という形でゲーム内で表現しているHash Rushはとても未来的でワクワクするゲームだと思います。 今年の11月にリリース予定なので興味が湧いた方はHPやDiscordなどで情報をチェックしておきましょう!!

プロジェクト
2018/05/13QuarkChain / QKC の特徴・競合比較まとめ!大注目ICOの将来性は?
QuarkChainはスケーラブルでセキュア、分散化されたプラットフォームを作るプロジェクトです。 記事作成時点でICOから10倍以上になっているZilliqaの競合ということもあり、将来性にも期待されています。 こちらのページでは、そんなQuarkChainの特徴やICO情報についてまとめています。 これを読めば、基本的な特徴からZilliqaとの違いまで、QuarkChainについてはバッチリです。 [toc] QuarkChainの概要を把握しよう QuarkChainの概要 通貨名/ティッカー QuarkChain(クォークチェーン)/QKC 創業者(CEO) Qi Zhou 主な提携先 Chihuo、PRIMASなど 特徴 スケーラブルなプラットフォーム 公式リンク Webサイト Twitter Telegram 日本公式Telegram Facebook Weibo github(ソースコード) ICO情報とトークンメトリクス QuarkChainのICO情報 WhiteList 2018/05/07 ~ 2018/05/21 ※抽選あり 規格 ERC20 支払い ETH 発行枚数 10,000,000,000 QKC 調達額 総額 20,000,000 USD PrivateSale 16,000,000 USD ICO 4,000,000 USD ICOレート 1 QKC = 0.00003 ETH QKCはメインネットver1.0(2018年Q4予定)公開までは、ERC-20トークンとなります。 QKCの用途は公開されていて、取引手数料の支払いやコミュニティ貢献者への報酬に利用されることになっています。 QuarkChainの抽選について QuarkChainのICOに参加する(WhiteListに通る)には、Telegramへの加入、Quizの回答ののち、抽選に参加する必要があります。 Telegram参加時期によるポイント、Quizのポイント、その他のプロジェクトへの貢献度に応じてポイントがつけられ、合計得点が60点以上の人に、点数に応じた枚数の抽選権が配られます。その後抽選に当たればICOに参加することができます。 QuarkChainの5つの特徴を紹介!QuarkChainを利用するメリットや将来性は? QuarkChainの特徴について解説しています。 まずはQuarkChainのがどんなものなのか、どんな問題を解決できるのかを知っておきましょう。 dAppsやスマートコントラクトを構築できるプラットフォーム QuarkChainはブロックチェーンのスケーラブルなプラットフォームです。 イーサリアムやNEOのように、QuarkChain上でdAppsを作ったりスマートコントラクトを実装したりすることができます。 スケーラビリティ問題に対応できるイーサリアムと考えるとわかりやすいです。 毎秒約1,000,000のトランザクションを処理できる スケーラビリティ問題解決に関係してくる特徴です。 公式サイトの画像からわかるように、QuarkChainのTPSはBitcoin、Ethereumよりもはるかに大きくなっています。 TPSとは トランザクション・パー・セカンドの頭文字をとったものです。1秒当たりに処理できるトランザクション数を示しています。 VISAは世界で最も利用されている決済サービスです。 このように比較すると、QuarkChainが対応できるTPSどれだけすごいかがよくわかりますね。 イーサリアムのdAppsなどを簡単にQuarkChain上に移行できる QuarkChainが注目されている理由の一つです。 すでにイーサリアム上でdAppsとして稼働しているアプリなどを、簡単にQuarkChain上に移し替えることができます。 これはQuarkChainがEVMのスマートコントラクトに対応していることが理由です。 EVMのスマートコントラクトとは イーサリアムのトランザクションはEVM(イーサリアム仮想マシン)を介して行われます。QuarkChain内にイーサリアムの通訳がいるイメージです。 弱いパワーのマイナーも報酬を得られる(ネットワークの分散化に役立つ) 多くの仮想通貨のマイニングはPoWという方式で、これではハッシュパワー(計算力)が小さいマイナーは報酬を獲得しづらくなります。 PoWとは 計算を一番早く完了させたマイナーだけが報酬を獲得できるマイニングの仕組みです。計算がより早くできる、大きなハッシュパワーのマイナーが有利になります。 PoWの仕組みのために、マイナーはみんなで力を合わせてマイニングをし、獲得した報酬を分割します。(マイニングプールを作る) しかし、これは分散化という観点では良いことではありません。 1つのマイニングプールの権力が大きくなるからです。 マイニングプールの問題点 ブロックチェーンは本来、みんなでネットワークを監視して健全性を保つものです。マイニングプールにより、1人が持つ力が大きくなると、ネットワークの健全性が失われやすくなります。 でもQuarkChainではハッシュパワーが小さいマイナーも、きちんと報酬が得られるような仕組みになっています。 これは、QuarkChainのマイニング報酬の仕組みが、ビットコインやイーサリアムなどのとは少し違うからです。 QuarkChainでは、ハッシュパワーに対する報酬の割合(難易度)を自分で決めることができます。 難易度が低いマイニングを選択することで、ハッシュパワーの大きいマイナーと競合するのを避けることができ、報酬を獲得することができるようになるのです。 わかりやすい例 マイニング報酬 … 100 必要ハッシュ(難易度) … 100 マイニング報酬 … 1500 必要ハッシュ(難易度) … 1000 マイニング報酬 … 20000 必要ハッシュ(難易度) … 10000 ※ここで紹介しているレートはランダムです。 これなら弱いハッシュしのマイナーも報酬を獲得できる。つまり、マイナーが分散化できる! 公式ホワイトペーパーでは、「ハッシュという通貨でマイニング報酬を買うことができる。」という表現がされています。 さっちゃん レートの仕組みは「まとめ買いでお得になる」みたいなイメージですね。 QuarkChainの仕組みを活用することで、結果的にマイナーの分散化にもつながり、より分散化された健全なネットワークが成立します。 クロスチェーンを実装できる QuarkChainではクロスチェーンを実装することができます。 具体的にいうと、"取引所を介さないQKCとビットコインなどの交換"ができるようになります。 クロスチェーンとは ビットコインやイーサリアム、NEOなどの互いに異なるチェーンとの直接取引を可能にする技術です スケーラブルなQuarkChainを支える技術を紹介! QuarkChainの5つの特徴では、QuarkChainは高分散化・スケーラブル・セキュアなプラットフォームといわれる特徴について解説してきました。 そんなQuarkChainを支える技術について紹介していきます。 QuarkChainはコード評価も高い 海外のコードレビューサイトなどではQuarkChainのコード評価(コードの質の評価)がかなり高いです。英語ですがQuarkChain Code Review – Deep Diveの「QuarkChain Code Review Conclusion」のパートを見ただけでも高評価なことがわかります。 シャーディング技術(2レイヤー構造) QuarkChainはシャーディング技術を採用していて、ブロックチェーンの処理を分割することができます。 これによって処理速度を上げることが可能です。 チェーン名 ブロック名 検証時間 主な役割 ルートチェーン層 (第2層) ルートチェーン ルートブロック 数分以内 検証 シャーディング層 (第1層) シャード マイナーブロック 数秒 元帳 シャードレイヤー(第1層) これがQuarkChainのスケーラビリティの秘密です。 シャードレイヤーのポイント トランザクションのすべてではなく"一部を"処理することで処理時間が短縮できる マイナーブロックは増減可能なのでトランザクションが増えても対応できる シャード(マイナーブロック)ではトランザクションの一部が処理されるため、すべてを処理するのに比べて処理速度が向上します。 また、このマイナーブロックの数は増やすことができるので、トランザクションが増えても全体の処理速度は落ちません。 わかりやすい例 道路の拡張工事をイメージすると分かりやすいです。車線(マイナーブロック)を増やすことで、車はよりスムーズに流れます。(トランザクションが増えても問題ありません。) ルートチェーン(第2層) ルートチェーンの役割は第1層のマイナーブロック(各シャード)を束ねて、QuarkChainの全体のネットワークとして構築していくことです。 ルートチェーンには承認されたマイナーブロックの一部(ブロックヘッダ)が格納されていきます。 ここではトランザクションの処理はせず、ひたすらに承認された第1層のブロックを束ねていきます。 このように処理とネットワーク全体の確認を分割することで、トランザクションが増えてもQuarkChainは安定的に稼働することが可能です。 マイニングではルートチェーン(第2層)に50%以上のハッシュが割り当てられる マイニングのハッシュパワーは、第1層と第2層で分割されます。 このときのハッシュパワーの割り当ては、50%以上はルートチェーン(第2層)、残りを全てのシャード(第1層)で分割です。 これにより、悪意のあるマイナーがネットワークを支配するには、最低でも全体の25%のハッシュパワーを持つ必要があります。 Point これがもし逆で第1層が50%以上持っていると、ネットワークを全体を管理する第2層を、より小さいハッシュパワーで乗っ取ることができるようになってしまいます。 これはビットコインなどの「51%攻撃」よりも低い割合になっています。 QuarkChainではこの問題に対して、次に紹介するクラスタリングで対応しています。 クラスタリング クラスタリングは、ミニノードを集めて実質的なフルノードを作れる技術です。 ノードとは ここではマイナー=ノードと考えると分かりやすいです。つまり、クラスタリングで小さなマイナーが協力して大きな1つのマイナーになるイメージです。 QuarkChainのマイニングでは、小さなハッシュパワーでもマイニング報酬を得られるという特徴があるのは「QuarkChainの特徴」で解説した通りです。 各マイナーはQuarkChainのネットワーク内でミニノードであり、その集合体が実質的なフルノードになっています。 マイナーがいくつか集まってフルノードが作られるので、1つの大きなマイナーがネットワークを支配しづらくなります。 ミニノードでは全体のトランザクションを確認することができません。 ほかのノードとデータを照らし合わせることで、全体のデータが確認できます。 クラスタ内の一部のミニノードが稼働不能になっても、ノード(クラスタ)としての機能は保たれるような仕組みが画期的です。 クロスシャードトランザクション クロスシャードトランザクションは、異なるシャード間でのトランザクションを可能にする技術です。 これによって、いわゆる"train and hotel problem"などが解決できるようになります。 シャード1で電車の予約をするためのトランザクション処理をして、シャード2でホテルの予約をするためのトランザクション処理をするとします。 この旅行予約のとき、どちらか一方の予約ができなければ両方の予約をやめるべきであり、両方の予約ができて初めて旅行の予約が完了します。つまり、このような状況において、「どちらも予約できるか」あるいは「どちらも予約しないか」の二択になります。どちらか片方の予約だけして、もう一方の予約はしない、という選択肢はありません。 Sharding Phase 1 の具体的な仕組みとセキュリティ課題 クロスシャードトランザクション技術によって、スケーラブルな環境下でも複雑なスマートコントラクトが可能になります。 クロスチェーン実装はアダプタorシャーディングを利用 QuarkChainは2通りの方法でクロスチェーンを実装することが可能です。 外部トランザクションにアダプタを利用する方法QuarkChainの外部チェーンのトークン(ビットコインなど)を、アダプタで変換してQuarkChain上で扱えるトークンにする方法です。 外部トランザクションをシャードに記録する方法外部チェーンをサブチェーン(またはシャードの1つ)として格納して、クロスシャードトランザクションを利用してやりとりする方法です。 スマートウォレット・スマートアカウント 通常、異なるシャードにある情報を管理したりアクセスしたりするには、各シャードに対応したアカウントが必要です。 でも、QuarkChainのスマートアカウント(ウォレット)があれば、メインアカウントを1つ持っているだけですべてのシャードにアクセスできるようになります。 スマートアカウント(ウォレット)のおかげで、ユーザーは同シャード・別シャードなどを意識せずにQuarkChain上のアプリなどを利用することが可能です。 プロジェクト進行は早い!?QuarkChainのロードマップを確認しよう こちらは2018年5月現在のロードマップ(ライブ版)です。 最新のロードマップはQuarkChainの公式サイトで確認することができます。 QuarkChainのロードマップ 時期 内容 2017年 Q2 スケーラビリティ問題のリサーチ 2017年 Q4 ホワイトペーパー草案 2018年 2月 検証コード0.1 ホワイトペーパー公開 2018年 3月 テストネット0.1 ウォレット0.1 2018年 Q2 テストネット1.0 スマートコントラクト0.1 2018年 Q4 QuarkChainコア1.0 メインネット1.0 スマートウォレット1.0 2019年 Q2 QuarkChainコア2.0 メインネット2.0 スマートウォレット2.0 【2018年 3月】テストネット0.1・ウォレット0.1 テストネットver0.1、ウォレットver0.1がリリースされます。 テストネットver0.1は、シャード内・クロスシャード両方の基本的なトランザクションに対応します。 【2018年 Q2】テストネット1.0・スマートコントラクト0.1 テストネットver1.0がリリースされます。 テストネットver1.0ではスマートコントラクトに対応します。 【2018年 Q4】QuarkChainコア1.0・メインネット1.0・スマートウォレット1.0 QuarkChainコアver1.0(QuarkChainの基本的な機能と最適化を実装しているネットワーク)がリリースされます。 コア、メインネット、ウォレットはすべて同時に公開される予定です。 【2019年 Q2】QuarkChainコア2.0・メインネット2.0・スマートウォレット2.0 コア・メインネット・ウォレットver2.0はver1.0をさらに最適化したものになります。 さらにクラスタリングも実装されます。 主なチームメンバーを紹介!バックグラウンドをチェックしよう QuarkChainの主なチームメンバーを紹介します。 結論からいえば、QuarkChainには優秀な人材が揃っています。Google、Facebookの出身が多いです。 1人1人について見ていきましょう。 【CEO】Qi Zhou ソフトウェアエンジニア。Facebook、Dell EMCでスケーラブル系プロジェクトの経験あり。 ジョージア工科大学博士卒 Facebook 1年 Dell EMC 2.5年 Google 9か月 【エンジニア】Zhaoguang Wang ソフトウェアエンジニア。バックエンドエンジニアとしてFacebookで1年、Googleで5年以上の経験。 ミシガン大学(コンピュータ・サイエンス・エンジニアリング)博士卒 Facebook 1年 Instagram 4か月 Google 5年 【研究者】Xiaoli Ma 研究者。Ratrix Technologies、LLCの共同創業者・CTO。 ミネソタ大学・電気工学博士卒 ジョージア工科大学 (教授) 3年11か月 Ratrix Technologies、LLC 6年6か月 ジョージア工科大学 (准教授) 4年 【研究者】Yaodong Yang 研究者。DEMO++の共同創業者。50以上の論文発表、600以上の引用あり。 バージニア工科大学博士卒 DEMO++ 2年11か月 西安交通大学・フロンティア科学技術研究所 (副学長) 3年9か月 【マーケティング・コミュニティ】Anturine Xiang 多様な業種でのデータ分析の経験あり。 ジョンズ・ホプキンス大学卒 Beepi 1年6か月 Chartboost 1年2か月 LinkedIn 11か月 QuarkChainの問題点・懸念点も知っておこう プロジェクトについてきちんと理解するには問題点・懸念点についても知っておくことも重要です。 主な留意点についてまとめているので、こちらにも目を通しておきましょう。 競合が多い QuarkChainはスケーラブルなプラットフォームの構築を目指すプロジェクトです。 スケーラブルなプラットフォーム系のプロジェクトは競合がたくさんいます。 競合が多い場合ははやくシェアを獲得できたプラットフォームが有利になってくるので、開発のスピードはとても重要なポイントです。 Point 現状のシェア最多のイーサリアム上のdAppsをQuarkChainに移し替えることができるのは、QuarkChainの大きなメリットです。 25%のハッシュパワーでネットワークへ攻撃ができる QuarkChainのネットワークを攻撃するには、最低でも全体の25%のハッシュパワーを持つ必要があります。 これはビットコインなどの50%よりも少ない割合です。 クラスタリングなどでマイナーのパワーを分散する構造にはなっていますが、実際に攻撃を受けずに稼働し続けられるかはわかりません。 【競合プロジェクトを比較】QuarkChainの優位性は? 最後に、QuarkChainと競合する主なプロジェクトについてもチェックしておきましょう。 プロジェクトの時価総額がどの程度になるのかを見極めるときの参考にすることができます。 QuarkChainとNEO・EOSの違いは分散性 NEOやEOSも高速のトランザクションが可能なプラットフォームです。 これに比べてQuarkChainが優れているのは、より分散化された仕組みになっているというところです。 NEOやEOSはノードが開発チームによって管理されているので、真に分散化された仕組みであるとは言い難くなっています。 対してQuarkChainはマイニングを分散化する仕組みによって、たくさんのマイナーが参加しやすい仕組みを作っています。 QuarkChainとZilliqaの違いはシャーディング Zilliqaもシャーディングを実装している、スケーラブルプラットフォームです。 QuarkChainはそんなZilliqaの上位版ともいわれることが多いプロジェクトで、よく比較対象に上がります。 QuarkChainの優位性 vs Zilliqa Zilliqa…シャード=ノード QuarkChain…シャード=ブロックチェーン →Zilliqaはノードが稼働しているときにスケーラブル →QuarkChainはあるノード停止や過負荷でも検証を引き継げる 他 クロスシャード、クロスチェーン(ZILはWANなどで導入予定)、EVMサポートなど — さっちゃん-仮想通貨ブログ (@vcvc_stc) 2018年5月12日 QuarkChainとZilliqaはデータの分割(シャーディング)のところで、大きな違いがあります。 ZilliqaとQuarkChainのシャードの違い Zilliqaはトランザクションを分割して、その処理を分散化してスケーラブルになる QuarkChainはシャード自体がブロックチェーン(2層構造)で、あるノードが過負荷などで稼働できなくなってもほかのノードが引き継いで対応することができる さらに、QuarkChainはEVM対応で最大シェアのイーサリアムから素早く乗り換えができる、というところもかなり大きなポイントです。 【大注目のICO】QuarkChainまとめ QuarkChainの特徴や技術、競合についてまとめました。 スケーラビリティ問題を解決できるプロジェクトは注目度が非常に高いです。 QuarkChainについてもっと知りたいと思った人はホワイトペーパーを読んだり、公式Twitterなどをチェックしたりしてみてください。 QuarkChainの公式リンクまとめはこちら

プロジェクト
2018/05/07SKYFchain / SKYFT -世界初の重貨物用ドローンプラットフォームのプロジェクト-
SKYFchainはブロックチェーン技術と、ドローンを組み合わせることで、物流業界の課題を解決するプロジェクトです。 本プロジェクトの特徴から競合プロジェクトまで徹底解説をしていきます。 SKYFchainの概要 通貨名/ティッカー SKYFchain/SKYFT 総発行枚数 1,200,000,000 SKYFT ICO 2018年3月10日 Start ICO価格 0.065 USD/SKYFT 主なパートナー Syngente AG(売上高-$128億)、Avgust crop protection(売上高-$2億6330万) 特徴 ブロックチェーンとドローンの融合 物流市場の課題解決 公式リンク Webサイト Twitter Facebook Telegram Medium reddit github(ソースコード) Announcement thread SKYFchainの特徴 SKYFchainは、ブロックチェーン技術によりドローンを代表とした無人機のオペレーティングプラットフォームを作り、物流市場に変革をもたらすプロジェクトです。 ドローンを利用した物流と言えば、2016年12月7日に初の民間テストを行ったAmazonの「Prime Air」を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか? 「顧客がタブレットで欲しいものを注文すると、物流倉庫の従業員が箱詰めを行い、ドローンが顧客の元まで届けてくれる」こんな近未来的な技術が、現実に行われ始めているのです。 もちろん、近年多くのビジネス書籍に踊る人手不足やAIと言ったキーワードがこの【次世代の物流技術】の後押しをしていることは言うまでもありません。 SKYFchainは、無人物流により50%もの人件費を削減することで、世界中の物流コストを下げ、産業界からエンドユーザーにまで、幅広い恩恵を与えることが期待できると述べています。 プロックチェーンによって物流に関わる書類作成や貨物運送コストが抑えられれば、より豊かな社会になりますねhttps://t.co/aA3EpaX06v — SKYFchain (@SKYFchain_jp) 2018年4月28日 無人物流市場の概要 SKYFchainのターゲットとする無人物流のマーケットを見てみましょう。 無人物流におけるメインプレイヤーとしてホワイトペーパーに記載されているのは、ドローンと自動運転車です。 ・ドローン PwCのデータによると世界のドローン市場の規模は1270億ドルにも達すると示されており、ビジネスマンにとっては今後非常にチャンスのある市場であると考えられます。 この市場への期待感を表すデータとして、ドローン市場へのVCからの投資額の指数関数的な増加があります。 CBInsightsのレポートによると、年を追うごとにドローン市場への投資額が増加しており、2015年の第二四半期では2012年の第一四半期と比較すると約50倍もの投資額となっていることが示されています。 ・自動運転車 空の輸送を担当するドローンに対し、こちらは陸の輸送を担当する無人トラックなども含まれています。 BIS ResearchのアナリストであるAbhimanyu Rahejaが、「2026年末までには自動運転車両台数は1億1000万台にも昇るだろう。」と述べているように、こちらも今後非常に拡大が予想される市場です。 さらに、Exane BNPパリバのレポートでも、同様の予測がなされています。 半自動運転車両約4000万台も含めると、2026年における自動運転車両の台数は1億2000万台を超えるとの予測です。 無人物流市場の課題 このように非常に注目される本市場ですが、無人物流の普及には大きく2つの壁があるとホワイトペーパーでは述べられています。 ・透明性の欠如 透明性の欠如とは、顧客が無人機の技術や旅程を確認できるシステムが未だにないことを指します。 これにより公的機関の規制強化や高額な保険料といった問題が発生してしまいます。 例えば顧客に商品を運ぶドローンが航路で事故を起こしてしまった場合、考えられる加害者はドローン製造業者、ドローンのサービス会社、顧客、ドローンパイロットなど様々です。 このように利害関係者がとても多い状況で、かつ誰の原因で事故が起きたのかを正しく証明するシステムがない現在では、保険会社も保険料を高額に設定せざるを得ません。 ・技術的問題 こちらは重い荷物を長距離輸送できるかというドローンの性能上の問題を指します。 大きな荷物を運ぶためには大きなプロペラが必要となりますが、プロペラを大きくすると制御可能な閾値を超えてしまいます。 また、エンジンに関しても電気エンジンでは蓄電池の問題が発生し、ガソリンエンジンでは重量の問題が、またハイブリットにするとコストの問題がついて回ります。 このように、これまでの技術では重たい荷物を運ぶためのドローンを作ることは技術的に非常に困難だったのです。 SKYFchainの可能性 SKYFchainでは、上の章で記述した2つの課題を解決し、無人機を利用した物流を普及させることが可能だと言います。 ・ブロックチェーンを利用した透明性 例えば先ほど挙げたドローンの事故において、物流現場に関するすべての情報を改ざんされることなく管理するプラットフォームさえあれば、保険会社にそのデータを提供するだけで支払いがスムーズに行われることが想定されます。 また、そのような事故のデータを金融機関や開発者、エンドユーザーが共有することにより、正しくドローンを社会に適応させていくことが可能になるのです。 ・SKYFchain独自の技術 SKYFchainはガソリンエンジンを利用しているにもかかわらず、独自の空力設計により垂直離着陸(VTOL)機能を備え、重い荷物を運ぶことが可能なドローンの製作を世界で初めて成功しています。 このドローンは、最大積載量400kg、最大飛行距離350km、飛行時間は8時間(積載量50kg)と、物流業界において十分利用可能で、従来では考えられないほどの高性能なのです。 SKYFchainの競合 ドローンに関連するプロジェクトとしては有名なものにDorado、またPrime airを展開するAmazonなども競合となります。 Doradoとの比較 Doradoは2018年2月7日~5月17日までICOが行われる、ドローンを利用したオンデマンドサービスを展開するプロジェクトです。 すでに、Foodoutという前身のプロジェクトが存在し、100万人の顧客から400万件にも昇る受注を経験しています。 Doradoに対するSKYFchainの優位性Doradoは前身がFoodoutという食品を専門に扱うドローンを利用したオンデマンドサービスを展開していました。今後は食品以外も扱うということでDoradoが生まれたようですが、軽量な食品と大きな荷物では運ぶ技術レベルが異なるので、SKYFchainの培ってきた技術は一歩先を言っていると言えます。 Doradoに対するSKYFchainの劣位性Doradoの前身であるFoodoutは2014年からの3年間でなんと6227%もの成長をしており、年間売上高は5000万ドルにも達しています。このような経験を持つチームメンバーを要したDoradoはSKYFchainにとって強敵となり得る可能性はあるでしょう。 AmazonやGoogleとの比較 今や知らない人などいないというほどの超巨大企業となったAmazonやGoogleももちろんこのドローン市場を見過ごすことなどしません。 Amazonは「Prime Air」、Googleは「Project Wing」を稼働させています。 AmazonやGoogleに対するSKYFchainの優位性SKYFchainはドローンにおいて世界初の快挙を成し遂げていますが、ブロックチェーンを物流業界に持ち込み、書類作成の簡素化や許認可鉄ぢ期の自動契約などの機能を持たせることで、コスト削減も謳っています。この点にもSKYFchainに強みがあると考えられます。 AmazonやGoogleに対するSKYFchainの劣位性言うまでもありませんが、企業としての規模が全く違います。企業の規模=経済力や認知は、少なからず開発や販売に影響があるため、このような大企業の参入は脅威となるでしょう。 SKYFchainロードマップ すでに2017年の第4四半期には完全自立の飛行試験に成功しており、今年2018年にはドローンの世界販売に乗り出します。既にベトナムの企業にもドローンの販売の実績も行ったようです。 SKYF Heavy Lifting Drones to Transport Goods in Vietnamese Seaport ドローンの飛行試験は後に述べる超大企業も参加を申し込んでおり、ドローン技術の高さが伺えます。 また、トークンのホルダーとしては上場も気になるところですが、ホワイトペーパーにて「少なくとも4つ、5つの取引所には上場させる予定です」と言った記述があります。 SKYFchainのパートナー SKYFchainのパートナーはかなり豪華です。 CARCIEL Inc.(カーシエル) 航空宇宙防衛コンサルティングファームである日本の企業CARCIELとの提携が今年4月に発表されました。 CARCIEL Inc.は、本田技研や川崎重工業など名だたる大手企業をクライアントに抱えています。 SKYFchainはCARCIELと高層ビルの建設及び消防におけるSKYFドローンアプリケーション開発に共同で取り組む予定です。 「私たちは日本の大手企業や多くの省庁からの要請に応じて、1年以上にわたって適切な技術を探し求めてきました。SKYFの大型ドローンは優れた特徴を持ち、日本で大きな需要があるでしょう」 CARCIEL Inc. 代表取締役兼 CEO 安藤 浩平氏 Syngenta AG(シンジェンタ) スイスを拠点とした種子や農薬を主力商品とする会社で、最近中国の国有企業ChemChinaによる買収のニュースでも話題になりました。 農薬業界では世界一位であり、売り上げは128億ドルにも昇ります。 SKYFchainはSyngentaと第1ラウンドの交渉を完了させ、SKYFドローンの試験を2018年の春に行う計画です。 Pony Express(ポニーエクスプレス) ロシアの物流企業で、世界8か国にオフィスを抱えています。 SKYFchainは現在、Pony Expressとの契約を締結し、2018年の春に飛行試験を行う計画です。 Russian Post(ロシア郵便) ロシア最大の郵便事業者で、約4万の郵便局を抱えています。 郵便事業者とも交渉が進行中とのことです。 SKYFchainのまとめ 物流業界で無人機を活用できるプラットフォームを開発するSKYFchainについて紹介しました。 この企業の強みは何といっても、ドローンの技術力だと言えます。 この技術力をブロックチェーン技術を用いて、ソリューションと一緒に提供することができれば、1270億ドルとも言われるドローンの市場を獲得することができるかもしれません。 また、Syngentaなど世界有数の大企業とパートナーシップを結ぶことができていることも今後の成長に繋がるでしょう。

プロジェクト
2018/05/05TravelBlock(トラベルブロック) – 最適な旅行プランを提供するプロジェクト-
Crypto Timesは今回、舞浜で行われたd10eというカンファレンスに公式メディアパートナーとして参加させていただきました。 今回のカンファレンスは、Crypto Timesでも紹介させていただいたNYNJAなどを含め様々なプロジェクトが参加していました。 メッセージアプリケーション NYNJA(ニンジャ)にプロジェクトインタビュー - CRYPTO TIMES その中でも、旅行代理店(Online Travel Agent : 以後OTA)の既存の仕組みを潰すと宣言していたTravelBlock(トラベルブロック)というプロジェクトが面白そうだったので紹介させていただきます。 従来のOTAの仕組みを軽く説明しながら、このプロジェクトの仕組みや特徴などを紹介していきます。 従来の旅行代理店の仕組み 1996年にExpediaが設立されて以来、22年間の間、OTAはExpediaが提供する仕組みによって成立していました。 図を作ってみましたが、この場合一般のユーザーはExpediaが提示する$500未満の価格でホテルを予約できる可能性はほぼ皆無です。 一方で一般ユーザーと対比させてプレミアムユーザーと書きましたが、これらのユーザーはホテルに対して数千ドルを支払うことでこのPrivate価格で宿泊する権利を得るため、ごく一部の限られたユーザーのみにこの価格が提供される仕組みになっています。 TravelBlockは、トークンを発行して新たな経済を作り上げることで、一般のユーザーに対してもPrivate価格でホテルを提供することを可能にします。 TravelBlockが実現する新たな仕組み さきほど、一般のユーザーが最安値として認識していたExpediaなどのOTAは、実は最安値ではなくExpediaがホテル側と契約した価格に過ぎなかった、というお話をしました。 しかしTravelBlockのウェブサイトを利用すると、すべてのユーザーはPrivate価格でホテルを予約し宿泊することが可能になります。 正確には、トークンを購入することがユーザーによるクローズドな消費者グループを形成することにつながり、TravelBlock側がホテルに対してより安価で契約を結ぶことを可能にします。 このシステムはトークンを発行しなければ、従来のOTAのモデルでは決して行うことができなかった仕組みであると考えています。 TravelBlockの特徴 [caption id="" align="aligncenter" width="841"] β版のウェブサイト[/caption] 旅行代理店としての基本的なサービス 従来のOTAと同様に、ホテルの予約から、航空券、レンタカーなど様々な旅に関連するサービスが提供されています。 ICOを行いトークンを発行するということで、ユーザーの獲得が難しそうにも見えますが、クレジットカードでの決済にも対応しているようです。 独自のプラットフォームなどではなくウェブサイト上で24時間365日、ホテルや航空券などの予約を行うことができます。 TravelBlock独自のサービス クレジットカード決済と書きましたが、TravelBlockではクレジットカードでトークンを購入しホテルの予約を行います。 このトークンを保有することによってPrivate価格で通常より30~60%安い価格で予約をすることができます。 また予約の際には、TravelBlockが提示するPrivate価格とExpediaなどのOTA8社が提供するPublic価格の差が表示されるため、どの程度お得であるかを一目でチェックすることができます。 TravelBlockに対する考察 このプロジェクトは、見る視点によって評価が大きく異なると思うのでそれぞれの立場から考察していきたいと思います。 一般消費者 いままでExpediaで$500であったホテルが$300になるわけですから文句なしだと考えられるでしょう。 問題としては、予約のフローが『クレカ→仮想通貨→予約』となる点で、各国により異なる規制や税制に対してどう適応していくか、消費者の仮想通貨に対するイメージや印象をいかにうまく与えられるかという部分には注目しておきたいですね。 仮想通貨投資家 トークンにブロックチェーンを導入しているが、いまいち透明性や改竄ができないなどの特徴をうまく生かし切れていないのでは?と考える人がいてもおかしくないプロダクトです。 しかし、すでに動くプロダクトが完成していてユーザー数も多いので、大多数への普及を考えると早い段階で仕込んでおくのは悪くないかもしれないですね。 ビジネスサイド 経営側としてはトークンを発行した新たな経済モデルの上で、従来のExpediaでは価格を落とすことが(ROI的な意味で)できなかった問題を解決することのできるWIN-WINのモデルを創り上げることに成功しました。 消費者側・経営側にとって十分満足に値するサービスの提供ができている点だけを見れば、非常によく考え抜かれたモデルだと思います。 個人的な意見 ブロックチェーンを利用してトークンを発行する点において、イノベーションなどの大きな一点にこだわるのも一つの楽しみ方であり評価の基準であると思いますが、結局はより多くの人間が満足する大きなスケールでのWIN-WINを勝ち取れたものが生き残っていくのがビジネスだと思います。 そういう意味ではTravelBlockもトークンエコノミクスこそは他に劣る部分はありますが、より実用的なプロダクトとして名を馳せていくのではないかと考えています。 まとめ d10eへ公式メディアパートナーとして参加した中で、少しイノベーションを盲目的に追うプロダクトとは別の、ビジネスというベクトルから考えられたTravelBlockを紹介させていただきました。 普段は技術やイノベーションについての話ばかり耳にしていたので、あれ?と思う部分もありましたが、全体的に消費者・ユーザー目線で考えられたプロダクトが多かったイメージです。 分散型で透明性があってトラストレスだから善であり、これらをフル活用できていないから悪であるという二元論的な考え方を修正するいい機会になったカンファレンスだったと思います。 公式リンク 公式サイト Telegram(英語) Medium(英語) Twitter

プロジェクト
2018/04/18BitRewards(ビットリワーズ) – Tポイントのようなロイヤリティプラットフォーム提供プロジェクト-
BitRewardsの概要 日本人が一番分かりやすい形で説明すると「Tポイントの仮想通貨バージョン」というのがBitRewardsの正体です。 BitRewards.networkの加盟店で商品を購入したり、サービスを利用すると顧客はボーナスとしてBITトークンをもらうことができます。 もちろん、BITトークンはTポイントと同様に加盟店での決済や割引に利用したりすることができます。 TポイントとBitRewardsの3つの違い ①BITトークンには発行上限が設定されている 発行上限が設定されていることにより、BitRewardsプラットフォームの成長に伴ってBITトークン1枚あたりの価値が変動します。 ②BitRewardsは無料で加盟店として参画できる 基本的にこういったロイヤリティサービスは加盟費用が必要となりますが、BitRewardsは無料で加盟することができます。 加盟店はBitRewardsが収集した膨大なマーケットデータやAIによる分析データの提供を受けることや、BITトークンを購入者にボーナスとして付与するロイヤリティサービスが出来るようになります。(AIの統合は2019年予定) ③ブロックチェーン技術を利用している ブロックチェーンを導入する利点として下記が挙げられます。 仮想通貨資産とすることで、他の流動性資産(他の仮想通貨等)にすぐに変換が可能 セキュリティリスクの低下(既存のロイヤリティシステムは情報流出が激しい) 加盟店が独自のトークン、その他のロイヤリティ、報酬プログラムの作成が可能 既にデモ版が稼働しており、実際に利用して無料でBITトークンを受け取れる 公式サイトTOPページの「機能している製品」ボタンから既に可動しているBitRewardsのデモ版が利用でき、メールアドレスを登録するだけで300円相当のBITトークンが受け取れます。(もちろん出金可能) 他にも Facebookでイイネ Facebookでシェア リファラルリンクの提供 等で「BitRewards」のプロダクトを使って、BitRewardsプロジェクトを宣伝することで、宣伝者はBITトークンを受け取るということができます。 そして前述にもある通り、将来的には 店舗独自のトークン発行・ロイヤリティプログラムの構築を行って、マーケティングやデータ収集 といったサービスも利用可能になる想定です。 他競合プロジェクトに対しての優位点 BitRewardsのようなロイヤリティプラットフォーム型のプロジェクトには下記の競合プロジェクトがあります。 競合プロジェクト INCENT PLUSCOIN LoyalCoin GatCoin ロイヤリティを提供するプロジェクトは上記のように多種存在していますが、競合プロジェクトに対してBitRewardsは下記の優位点が存在しています。 競合プロジェクトとの優位点既にEコマース市場で5年間以上サービスを行った実績がある 店舗が無料でBitRewards.networkに加盟することが出来る 海外レビューサイトの評価 ICOBenchの評価 ICORATINGの評価 TrackICOの評価 ICOHOLDERの評価 レビューサイトでは概ね好意的な評価をされています。 レビューサイトとして一番信頼性の高いICODropsではスポンサード枠として掲載されています。 ICODropsのBitRewards掲載ページ ICODropsはあくまでスポンサード枠の掲載ですが、本サイトはスポンサード枠にもプロジェクトの掲載審査が行われており、枠を金銭のみで購入することはできないため指標のひとつになるでしょう。 関連リンク 公式サイト Twitter(@Bitrewards) 日本Twitter(@BitRewards_jp) ホワイトペーパー(日本語) ライトペーパー(日本語) ホワイトペーパー(英語) ライトペーパー(英語) Medium 公式Telegram(英語) 公式Telegram(日本語) ※プロジェクトのICOへ参加される際には、自身でも利用規約やプロジェクト内容に関して十分理解をした上での投資を行いましょう。投資をおこない損失などが生じた場合、CRYPTO TIMESでは一切の責任を負いません。全て自己責任となります。

プロジェクト
2018/04/17【dApps】ポ○モン系RPGゲーム Chain Monstersの紹介
こんにちは。先日デ○モンのような感覚で遊ぶことのできる『Axie(アクシー)』というゲームを紹介しましたが、今回はポ○モンのような感覚で遊ぶことのできる『Chain Monsters(チェーンモンスター)』というゲームを紹介します。 日本語の対応はまだしていないようですが、プレイしてみた感想は、見慣れたUIで操作もシンプルなため不自由なく遊べると思います。 Chain Monsters公式ページ Chain Monsters(チェーンモンスター)の3つの特徴 100%ブロックチェーン上で動作する 見慣れたUIのため誰もが不自由なくプレイできる レベリング要素(未実装)で課金額がプレイに影響しにくい シンプルなゲームプレイ 基本的に画像のドット絵の主人公を移動させて、草むらで自身のモンスターを戦わせてレベルを上げていきます。 またゲームが100%ブロックチェーン上で動くため、育成のプロセスで従来のPvP(Player vs Player)のMMOなどのゲームで問題となっていたチート・不正などは絶対に行うことができません。 現在のところ、レベルアップ要素やモンスターの捕獲要素は確認できませんでしたが、こちら運営に問い合わせたところ、ロードマップでは2018年Q2で実装とあり、これより遅くなることはないそうです。 多様なモンスターとシステム ロードマップによれば、151体のモンスターがそれぞれ開発の進捗に応じた世代を持つそうです。 現在では、最初に選ぶことのできる3体を含めた23体(第1世代)がリリースされているようで、こちらのモンスターは野生で遭遇することができます。 画像は戦闘の画面で、ゲームのシステムはターン制で能力値に応じて先攻後攻が決まるようです。 またはっきりとは書かれていないのですが"火"⇔”水”⇔”草”などの相性によるダメージの補正もあるようです。 複数のモンスターを駆使し、相性などを考えて戦略を練っていく、シンプルですが奥が深いゲームシステムになっています。 また、現在開発が行われているリアルタイム対戦システムでは、同じマップ上に存在するプレーヤーと遭遇し彼らとバトルをすることもできるようになるそうです。 その他にも今後実装されていく機能が豊富 モバイル版の対応(2018-Q1) モバイル版が対応すれば、空いた時間にスマホでプレイすることも可能になります。 また、スマホのimTokenやTrustなどのETHウォレットを使えば、ウォレットアプリ一つでChain Monstersをプレイできゲーム内でのトランザクションなども容易に行うことができます。 クエスト・ストーリーモードの追加(2018-Q1) 従来のdAppsゲームは対人が主でしたが、Chain Monstersに実装される予定のクエスト・ストーリーモードは、ブロックチェーン上で動くdAppsながらも個人でゲームを楽しむことが可能になります。 ETHを支払うため『投資額を取り戻さなければ』などという感情のために、ゲームをゲームとして楽しむことのできなかった従来のdAppsと比較して、Chain Monstersにはゲーム本来の楽しさがあります。 開発者がオススメするポイント 開発者によれば2つの重要なポイントを日本のプレーヤー達に伝えておきたいそうです。 ①モンスターが無料で手に入る。 ユーザーはログインするのみで、Gen-0(第0世代)のモンスターを無料で手に入れることができるようです。 第0世代は、ERC721トークンのそれぞれのトークンが固有性を持つ機能を利用し、最初の10,000体のみの販売・配布となっています。 更にこれらのモンスターは通常のモンスターより個体の能力が高く設定されているようです。 ②CryptoKittiesと連動 このゲームに実装されるミニゲーム機能では、CryptoKittiesと呼ばれる他のdAppsゲームで育てたキャラクターを使って遊ぶことができます。 他のゲームで育てたキャラクターが別のdAppsで利用できるようになれば、遊ぶゲームを慎重に選ぶ必要性がなくなり、気軽に色々なゲームに熱中することができそうですね。 ゲームの始め方 現在対応しているPCからゲームを始める場合は『Metamask』の利用が必須となります。 他のゲームでは、初期費用が高く設定されていることが多いですが、Chain Monsterでは最初の1体を手に入れるのにかかる費用が執筆時は0.002573ETH(1.30USD)とかなり安めに設定されています。 公式サイトからGameタブをクリックすると、ゲームが始まりますので、博士に言われるがまま主人公の名前を決めて、最初の1匹を選んでください。 従来のRPGゲーム同様、”火”、”水”、”草”の中から1匹選びます。 選択し次に進むとMetamaskのポップアップが表示されますので、ここでSUBMITボタンを押して購入を進めてください。(画像では残高不足のためBUY ETHERとなっています) スマホの『Trustウォレット』などから購入する際は、Chain Monstersのモバイル版対応が現在まだ完了していないのでマーケットプレイスでの購入のみが可能です。 購入後ブロックチェーン上でのトランザクションが終わると冒険が始まります。 Chain Monsters公式ページ 関連リンク 公式サイト Twitter Github Whitepaper Reddit
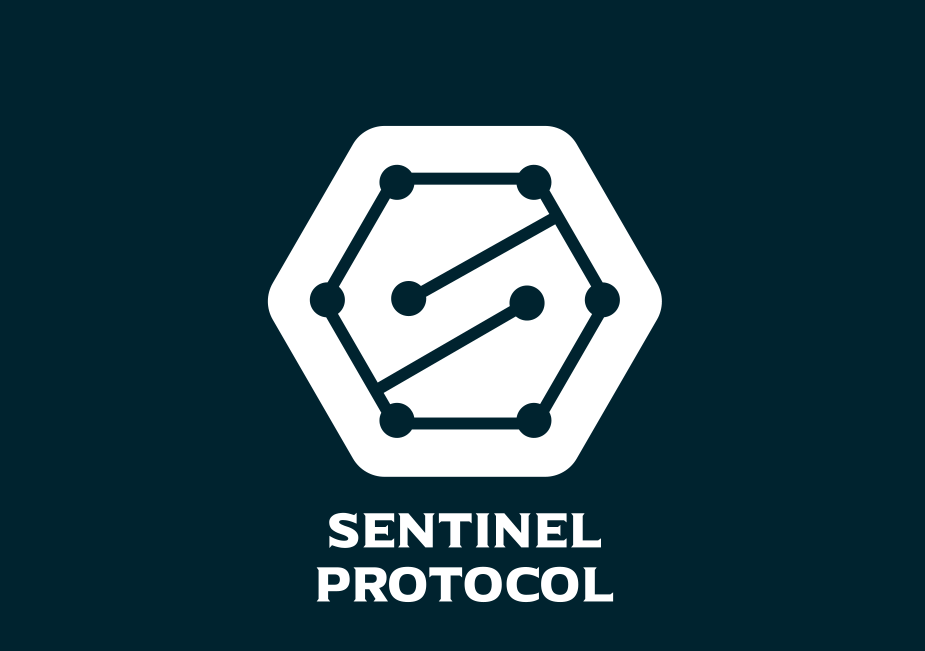
プロジェクト
2018/03/30Sentinel Protocol(センチネルプロトコル) -分散型セキュリティプロトコルのプロジェクト-
今回紹介するのは、Sentinel Protocol(センチネルプロトコル)というセキュリティ関連のプロジェクトになります。 このプロジェクトの3つのポイント! 通貨のシステムでしか解決できなかったハッキングに対しての防衛手段となるプロトコル 人工知能やAIを利用した自律性を持つエコシステムを創造 ハッキング自体のインセンティブを奪い去ることができるので問題の根本的な解決が見込める Sentinel Protocolとは? Sentinel Protocol(センチネルプロトコル)とは、仮想通貨のAutonomy(自律性=管理者の不在)の弱点であるセキュリティを集団的知性や機械学習で解決しようというプロジェクトです。 仮想通貨におけるサイバー犯罪は、分散型台帳を利用したP2Pネットワークの匿名性ゆえ、ハッカー側がターゲット(取引所など)を選ぶことが非常に容易であるにもかかわらず、攻撃者を特定するのが非常に難しい仕組みになっています。 現状これらの被害が全て自己責任という言葉に片づけられてしまうのですが、ではそれぞれが対策を練っていったとしても、根本的な『仮想通貨におけるセキュリティ』は脆弱性を突くハッキングに対する本質的な防衛手段にはなりえません。 Sentinel Protocolはブロックチェーンのそれぞれが自己利益のために動きそれが相互作用する仕組みに目を付け、仮想通貨の自律性という柱を守りつつ、集団的知性や分散型AIを使うことによって、サイバーセキュリティエコシステムのプロトコルの実現を目指しています。 このICOが実現できることこのプロジェクトの本質は分散型エコシステムの健全な環境維持にあります。ハッキングと聞くと対策という枕詞が頭に浮かびますが、このプロジェクトでは従来のセキュリティ対策と比較すると、分散型システムの強みを生かした自律的で健全なセキュリティのシステム創造がビジョンの根底にあると考えることができます。 プロトコルとは?アプリケーションとの違いは? Sentinel Protocolのプロトコルという言葉についてですが、これは皆が共通して対応するどのアプリからでも同様に利用するための基盤となるルールのようなものと覚えておきましょう。 例えば、https(HyperText Transfer Protocol)とはSSLやTLSが提供するセキュアな接続上でhttpのプロトコル通信を行います。 Google ChromeやFirefoxなどのアプリケーションは、基盤となるhttpsのプロトコルを利用することができるため、どのプラットフォームからも同様にセキュアにwebサイトを閲覧することができるようになります。 Sentinel Protocolを利用する場合だとケースがいくつかありますが、基本的にはSentinel Protocolの集団的知性やAIを生かしたネットワーク上で送金や受金などを行うことができ、このプロトコルに疑わしい、危険などと判断されたアドレスへの送金、からの受金をブロックすることができます。 またAI(人工知能)を取り入れることで、アドレスのブロックのみでなく、通常のユーザーの挙動と異なる動きを検出、未然にブロックすることも可能になります。 Sentinel Protocolの特徴 Sentinel Protocolには特徴となる Sentinel Portal(センチネルポータル) S-wallet 分散型マルウェアサンドボックス の3つの柱があります。 Sentinel Portal Anti-Theft System(犯罪防止システム) ネットワーク上での資金のやり取りを管理する一つの例としてクレジットカードがありますが、クレジットカードの場合、それが盗難された際に管理者(カード会社)が利用を停止するなどして、不正な利用を防ぐことができます。 しかし、管理者のいない仮想通貨のシステム上、こういった犯罪と関連した資金の不正な移動を防ぐことができません。 Sentinel Portalによりコミュニティ内の全ての情報を仮想通貨の取引所にシェアすることで、盗まれた資産がFIATに交換されることを防ぐことができると考えています。 Malformed Transaction Prevention(不正取引防止) Scam認定されたアドレスやそれに派生するアドレスは、ブロックチェーンの利点を生かしてコミュニティ内のすべてのメンバーと共有されます。 Sentinel Protocolが適用されている限り、ハッキングの被害の拡大、分散を防ぐこともできます。 一つの例として、ICOの詐欺などにおいて、アドレスに送金したが持ち逃げされた際に、詐欺を行った人物(チーム)のアドレスを追跡することができます。 S-wallet S-walletはSentinel Protocolのコミュニティにいる人々に提供される、従来のセキュリティソフトのにあるような機能を搭載したウォレットになります。 従来の中央集権的なソフトウェアはサーバーにある既知の脅威にしか対応することができなかったのですが、S-walletは脅威の傾向や履歴を分析することでゼロデイ攻撃*などの未知の脅威に対して対抗しうる可能性を持ちます。 集団的知性によって集まったデータベースを参照して、アドレスフィルタリング、URL/URIフィルタリング、データフィルタリング、詐欺検出などを行うことができます。 特に機械学習(後述)を利用した詐欺の検出などは、サイバー犯罪における二次被害を防ぐことができる点において非常に重要な意味を持ちます。 *ゼロデイ攻撃…ハッカーが脆弱性の発見者となるような攻撃 分散型マルウェアサンドボックス サンドボックスとは、未確認のプログラムやコードを仮想マシン上で動かすことでアプリケーションやホストに対してノーリスクで動かすことのできるシステムです。 既存のサンドボックスは中央集権的でサーバー内で仮想マシンを起動させてこれらの未確認のプラグラムを動かす必要があったため莫大なコストがかかりそれがネックとなることもありました。 しかし分散型のサンドボックスは、これをPoWの仕組みと融合させることで、未確認のプログラムやコードのテストの役割をユーザーに担ってもらうことで、従来のシステムにかかっていたコストを大幅に削減することが可能になりました。 言うまでもなく、PoWを利用しているのでサンドボックスのエコシステム維持に貢献したユーザーにはインセンティブが付与されます。 ※Sentinel ProtocolにはPoP(Proof of Protection)(後述)というアルゴリズムが用いられますが、サンドボックスのシステム維持に貢献した人にはPoWによってトークンUPPと互換性を持つSP(Sentinel Point)が付与されます。SPはUPPと交換可能です。 これらのセキュリティ、特に仮想通貨におけるセキュリティを強固にすることには大きな意味があります。それは、ハッカー側の攻撃インセンティブを間接的に奪うことができる点です。 例えば、ハッカーはCoincheckのハッキング後にダークウェブで15%オフでNEMを販売していたことなどからも、実際に奪った資産を換金し利用することを最終的な目標にしていることが伺えます。Sentinel Protocol導入によるアプローチはこういったハッカーの金銭的なゴールを妨げる役割を果たしています。 このプロトコルが世界中で利用されることで、ハッキング自体が不毛であることを気付かせそのインセンティブを消し去ることができるかもしれない、という点で優れていると言えます。 合意形成アルゴリズム『PoP』とは? 上述の通り、Sentinel Protocolでは、Daniel Larimerという人物によって発案されたDPoS(Delegated Proof of Stake)を元にしたPoP(Proof of Protection)というアルゴリズムを採用しています。 簡単に言えば、Delegatedとは代表者のことで、この合意形成アルゴリズムにおいては、Uppsalaによって選抜されたセキュリティの詳しい知識などを持つ機関や個人が合意を形成します。 これによってPoWの電力の無駄を十分に削減し、従来のPoSでも起こり得る51%問題などの脅威を劇的に減らすことを可能にしました。 更にReputation Scoreと呼ばれる内部評価のようなシステムを採用しています。 このスコアがコミュニティ内での影響力を示し、既存のPoS同様そのスコアに応じたステークが与えられるため、個人個人のユーザー、機関があえて犯罪に加担してくような動きを見せることは極めて考えにくいとしています。 集団的知性と機械学習・AI(人工知能) S-walletの項でSentinel Protocolには集団的知性や機械学習が利用されている旨を簡潔にに説明させていただきましたが、これらをセキュリティで利用していくことのメリットをこちらで紹介します。 ブロックチェーンは分散型で書き換えもできないからセキュリティが強いと世間では謳われていますが、実際のところそうではありません。 まず必ず注目しなければならないのが、従来のセキュリティと比較した際に見える中央管理者の有無です。 仮に仮想通貨が集権的で、仮想通貨管理局なるものが存在するとすれば、仮想通貨で行われた不正に対して管理局の専門家が『このトランザクションは無効』などの判断を下したり、『こういうハッキングが流行り始めたから気を付けて』などの注意喚起なり、個人のユーザーの不利益の阻止にある程度は貢献できるかもしれません。 ですが、現状こういった専門家や最新のデータなどに個人がアクセスし情報を得て対策をする、という一連の理想の流れは中央管理者が不在である点などから実現が非常に難しい状況にあります。 第二に注目すべきは、ハッキングやデータの漏洩などから、実際に資産が盗まれた際、そのトランザクションデータはすべてブロックチェーン上にあるという点です このブロックチェーン上の情報を収集して共有(集団的知性)、パターンや不正な挙動などの解析(機械学習)することで、中央管理者の不在による個人へのダメージを解消し、従来の集権的なデータベース以上にスケールする最高のセキュリティプロトコルを創り上げることができます。 Sentinel Protocol のロードマップ この記事の執筆段階でSIPB(Security Intelligence Platform for Blockchain, Sentinel Protocol)のベータテストは既に完了しています。3月にはトークンの発行と同時にテストネットのローンチがあるようです。 Sentinel Protocolのリリースは18年6月を予定していて、機械学習やサンドボックスなどのシステムは11月から12月にかけて随時追加されていく予定です。 2019年には詐欺検出システムがメインネットに追加される予定です。 Sentinel Protocolのチーム概要 このICOを行っているUppsalaという企業ですが、創立者と他数名がDarktraceという最先端の機械学習を使ったサイバーセキュリティの会社の出身です。 その他メンバーは、Palo Alto Network、Penta Security Systemsなどの企業が出身で、いづれもサイバーセキュリティ方面で活動を行ってきたようです。 最初はUppsalaという企業が検索で見つからなかったので不安になりましたが、チームメンバーがれっきとしたセキュリティのバックグラウンドを持つことや、彼らの経歴を客観視した際に、プロジェクトの実現が十分に見込めるなどという理由で紹介させていただきました。 その後、このプロジェクトメンバーと連絡を取ったところ、こちらで会社の存在を確認することができました。このThe centralという場所はKyber NetworkやDigixなども拠点にしているようで、Crypto Buildingなどと呼ばれているようです。 トークンセールの詳細 プレセールの開始は4月中旬とされています。プレセールに割り当てられるトークン枚数は、87,500,000UPPになります。 ハードキャップはプライベートセールの内容を反映して$11,670,000に設定されています。 こちらはホワイトリストの登録を完了させたユーザー向けに以下の内容で行われます。 1ETH = 5,000UPP 15%のボーナス(5,750UPP)とボーナス付与分に対しての6か月のロックアップ ※ホワイトリスト登録にはKYCが必要となります。 クラウドセールはこのプレセールの終了後に順次開始されます。 初期段階で発行されるトークンのうち、33.7%+26.7%がそれぞれ一般向け、初期段階で貢献した人々に、15.0%がUppsalaに分配されます。残りはビジネスなどの用途に使われるようです。 関連リンク 公式サイト Twitter(@s_protocol) ホワイトペーパー(英語) Medium 公式Telegram(英語) 公式Telegram(日本語) ※プロジェクトのICOへ参加される際には、自身でも利用規約やプロジェクト内容に関して十分理解をした上での投資を行いましょう。投資をおこない損失などが生じた場合、CRYPTO TIMESでは一切の責任を負いません。全て自己責任となります。




















 有料記事
有料記事


