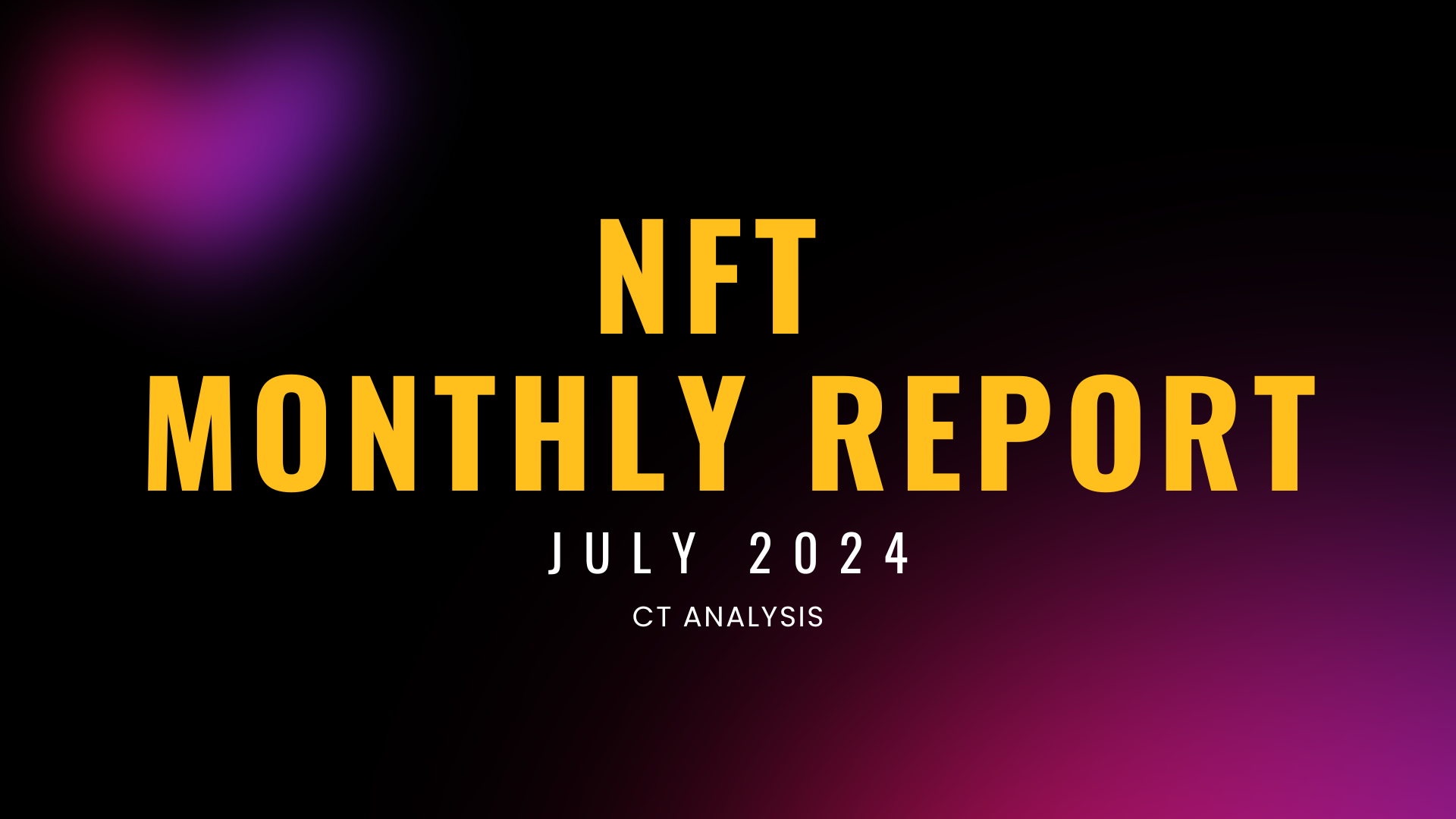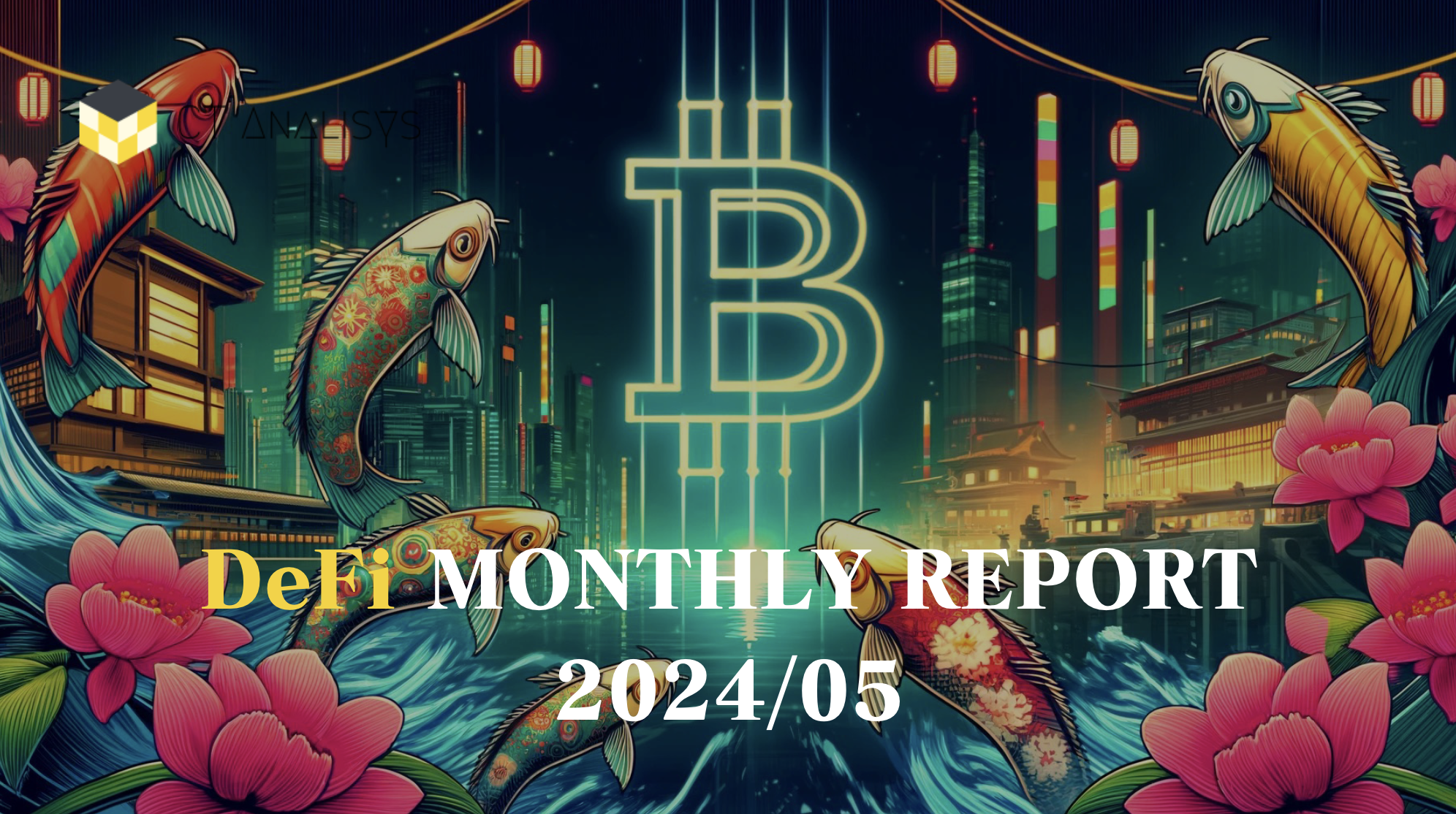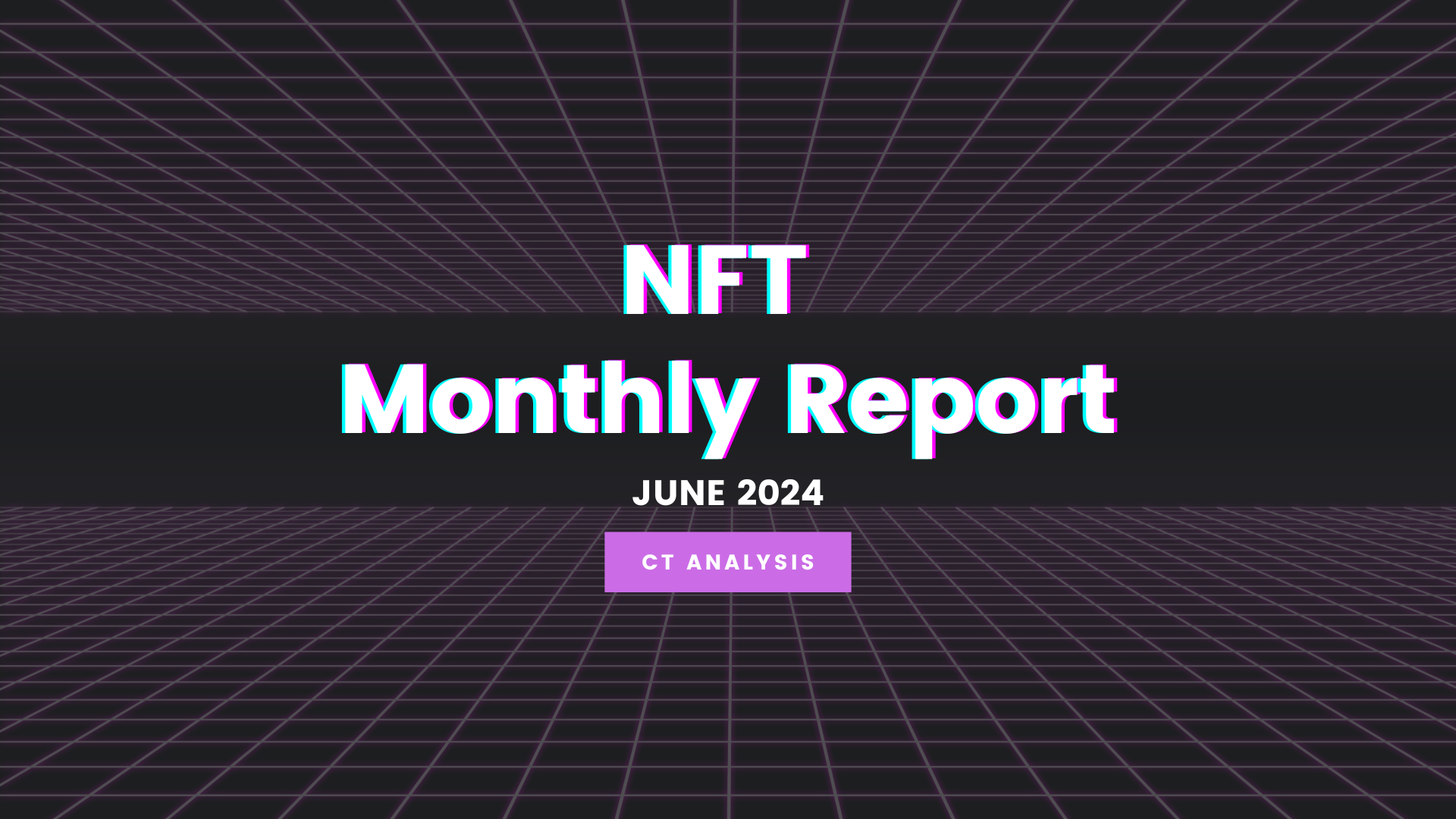ステーブルコインの仕組みとは?種類や特徴を徹底解説
Yuya

デジタルアセットは価値の変動が激しいものですが、中には比較的安定した価格の実現を目指す「ステーブルコイン」というものが存在します。
おそらく最も有名なステーブルコインといえば、テザー社のUSD Tether($USDT)やTrue USD($TUSD)でしょう。
2018年に入り、各国の法定通貨に紐付けされたものや、コモデティにペグされたものなど、数多くの新しいステーブルコインが登場してきています。
こちらのページでは、ステーブルコインとは何かを解説し、今界隈で注目を集めている新参ステーブルコインを紹介していきます。
ステーブルコインとは?
ステーブルコインとは、ブロックチェーンや分散型台帳技術を応用した価格変動の比較的小さい仮想通貨のことを指します。
ここでいう「比較的」とは、ビットコインやイーサリアム、リップルなどのデジタルアセットと比べて価値のボラティリティが低い、ということを意味します。
ステーブルコインの仕組みは一般的な「ペグ通貨」に似ていて、メジャーな法定通貨やコモデティなどもともと価値の変動幅の小さいアセットに通貨を紐付けしています。
例えば、香港ドルは「米ドルペグ通貨」と呼ばれ、通貨の価値が米ドルに比例する仕組みになっています。言い換えれば、香港ドルー米ドルの為替レートは常に一定ということになります。
香港では、香港ドルの需要・供給をコントロールする金融政策を行うことで価値を米ドルに紐付けしています。
一方、ステーブルコインは、分散型ネットワークのインセンティブメカニズムを利用することで価値を紐付け先に連動させることが一般的です。
つまり、ステーブルコインは、香港の例のように価値の安定化を集権的機関が行う代わりに、分散型ネットワークに参加する不特定多数が価値を自律的にコントロールする仕組みになっているわけです。
ステーブルコインの代表例といえば、Tether社のTether USD($USDT)です。USDTとは、USドル:USDT = 1:1になるような仕組みを導入した通貨です。

上の画像を見ると、USDTの価格チャートはほぼ水平で、変動がとても小さい事がわかります。
数時間で何十パーセントもの上下を見せる通常のデジタルアセットに比べ、USDTの価格変動幅は0.1%以内には収まっています。
ステーブルコインのメリット・デメリットとは?
ステーブルコインは、ポートフォリオを構築していく上で低リスク・低リターンなアセットとして役立つことが考えられます。
また、コモデティなどのアセットに紐付けられたものであれば、他の特定の資産に対するヘッジとして利用することもできます。
更に、法定通貨に紐付いたステーブルコインは、仮想通貨市場上でフィアットの代わりとして持てる(法定通貨のデジタル資産化)というメリットもあります。
一方、ステーブルコインでは通常の通貨ほどボラティリティを気にしなくて済む反面、「本当に価値を裏付ける資産が存在するのか」という心配が常に付きまといます。
ステーブルコインの大御所・Tetherも、今年6月に発表した担保に関する報告書で不透明な面が多数あったため、果たしてUSドルと1:1の関係が保たれているのか疑問視されています。
ステーブルコインはなぜ今流行っているの?
ステーブルコインは今、仮想通貨市場外からも大きな注目を集めており、クリプト系メディアのみに留まらず、Bloomberg、CNBC、Forbesなどのビジネス紙でも大きく取り上げられています。
これは、メガバンクや大企業がブロックチェーン技術を視野に入れた事業展開を始め、暗号通貨に対する世間の理解が少しずつ得られてきた証拠なのではないかと考えられます。
ビットコインなどはそのボラティリティの高さから未だ大幅な普及には程遠い段階にある中、ステーブルコインは法定通貨に似た利便性があるため、少しずつアダプションが始まってきているものだと思われます。
こういった状況に、ブロックチェーン技術が国際送金やサプライチェーンなどの分野で活躍していることも加担し、いま世界各国で「自国法定通貨の開発・普及競争」が行われているものと考えられます。
2018年注目のステーブルコインは?
冒頭でも触れた通り、2018年に入りたくさんのステーブルコインが登場してきています。
Gemini Trust Companyのような有名企業が発行しているものから、新興企業が提供するユニークな通貨まで様々な通貨が存在します。
こちらでは、そんな注目の新ステーブルコインをタイプ別(法定通貨、コモディティなど)で紹介していきます。
法定通貨連動型(カレンシーペグ)
まずはじめに、法定通貨と連動した「カレンシーペグ型」の法定通貨から紹介していきます。
Gemini Dollar ($GUSD, ERC-20, USドル)
 米証券取引委員会にビットコインETFの認可申請を初めて行ったことなどで知られるGemini Trust Comapnyは、今年9月にUSドルと1:1で紐付けられたGemini Dollarの発行を発表しました。
米証券取引委員会にビットコインETFの認可申請を初めて行ったことなどで知られるGemini Trust Comapnyは、今年9月にUSドルと1:1で紐付けられたGemini Dollarの発行を発表しました。
同通貨の最大の長所は規制準拠に起因する透明性の高さです。
Gemini Dollarのウェブサイトでは、紐付けに用いられるUSドルのリザーブがどこに保管されているかや、外部機関によるスマートコントラクトのセキュリティチェックレポートなどを確認することができます。
また、Gemini Dollarは月に一度、外部会計機関から両通貨の1:1の連動が保たれているかを確かめるともされています。
Circle USD Coin ($USDC, ERC-20, USドル)

デジタル資産取引所やペイメントソリューションを提供する米企業Circle(サークル)は、今年5月に120億円の開発資金を調達し、USドルと1:1連動型のCircle USD Coinの発行を開始しました。
Circle社は、米大手証券会社のゴールドマンサックスから初期投資を受けていることや、米大手取引所Poloniexを買収したことなどで注目を集めている企業です。
近頃では新規投資家をターゲットにしているとみられるサービスに力を入れており、ワンタップでマーケット投資ができるアプリなどを提供しています。
Circle USD Coinは、同社が買収したPoloniexや、その他大手取引所であるKuCoinやOKCoinで利用することができます。
Paxos Standard ($PAX, ERC-20, USドル)

今年9月に発行が開始されたPaxos Standardは、Gemini Dollarと同様に規制準拠に関する情報公開を徹底しているUSドル連動型コインです。
同通貨に関する月間監査情報は全てウェブサイト上に公開されており、誰でも閲覧できるようになっています。
Paxos Standardは、USドルからPAXへの変換にコストがかからないことや、最低変換額が低い(100USドル)ことなどを特徴としています。
MUFGコイン・Jコイン・Sコイン・GMO Japanese Yen (日本円, 未実装)

日本円と連動したステーブルコインですでに実装が済んでいるものといえばZEN(ゼン)ですが、今年に入り国内の大手銀行が独自のステーブルコインの開発に着手しています。
三菱USJ銀行、みずほ銀行、SBIグループ、GMOグループの四社がそれぞれMUFGコイン、Jコイン、Sコイン、GMO Japanese Yenと呼ばれる日本円と1:1で連動した仮想通貨を開発しています。
価格安定アルゴリズムや、具体的なリリース時期などに関する正確な情報は未だわかっていませんが、大手銀行が実在するリザーブを元に発行するステーブルコインとして大きな注目を集めています。
いわゆる「日本円版テザー」の目指した競争は米国と比べてもひときわ激しいものになっていくと考えられます。
LBXPeg (ティッカー不明, ERC-621, 英ポンド)

法定通貨連動型ステーブルコインは、国際通貨であるUSドルや私たちに関わりのある日本円だけでなく、世界各国で作られています。
London Blockchain Exchange(LBX)というイギリスの取引所は、今年9月に英ポンドと1:1で連動した通貨「LBXPeg」の発行を開始することを発表しました。
同通貨の面白い点は、通貨の規格にイーサリアムのERC-621を採用している点です。
LBXは、ERC-20を拡張したERC-621を利用することで、LBXPegの供給量と英ポンドのリザーブの連動が容易になるとしています。
コモディティ連動型
次に、通貨の価値を貴金属や石油などと連動させる「コモディティ連動型」の新ステーブルコインを紹介していきます。
法定通貨連動型の通貨と違い、コモディティ連動型通貨は分散型投資におけるヘッジや、コモディティ市場の安定した成長を見越した商品として認識されているのではないかと考えられます。
したがって、コモディティ連動型ステーブルコインにおける「ステーブル」とは「有限・発行不可な資産に基づいた」という意味になります。
コモディティ連動型通貨は法定通貨連動型に比べれば注目度は低く、規制もあまり整備されていないのが事実です。
Tiberius Coin ($TCX, ERC-20 / Zilliqa*, 貴金属)
 Tiberius Coinは、銅・スズ・アルミニウム・ニッケル・コバルト・金・プラチナといった、精密機械類の生産に欠かせない貴金属と連動した通貨です。
Tiberius Coinは、銅・スズ・アルミニウム・ニッケル・コバルト・金・プラチナといった、精密機械類の生産に欠かせない貴金属と連動した通貨です。
今年11月から取引可能となる同通貨は、テクノロジーブームにおける貴金属の希少化を見越した投資商品です。
開発・販売を行なっているTiberius Technology Venturesはスイス発の企業で、Tiberius Coinを裏付ける貴金属の買付けは、英国のロンドン金属取引所(LME)で行うとしています。
同通貨は紐付けられた金属の保管コストなども全て加味しているとされており、手軽にコモディティに資産を分散できるツールとして実用性があると考えられます。
Tiberius Coinは現在ERC-20トークンとして発行されていますが、将来的にはZilliqaを採用するとしています。
Tiberiusは今年10月9日に、クレジットカード会社の手数料が高すぎることから資金調達方法を見直すとして、トークンセールを中止し、今年12月ごろ再開することを発表しています。
Petro ($PTR, ERC-20, 石油 / 金*)

最後に紹介したいのが、言わずと知れたベネズエラの「法定仮想通貨」ペトロ(Petro)です。
同通貨は、ニコラス・マデュロ大統領が主導するベネズエラの新しい法定通貨で、価値を同国で生産される石油で裏付けているとされています。
通貨の存在自体は2017年から知られていますが、ペトロは今年10月から正式にベネズエラの法定通貨および会計単位として使われています。
ベネズエラの仮想通貨ペトロが10月1日から国際的に使われる模様
しかしベネズエラは現在、不安定な政治状況や前法定通貨のハイパーインフレーション、米国との外交問題などで警視されており、ペトロを裏付ける石油が果たして実在しないのではないかといった懐疑的な意見が広く支持されています。
また、マデュロ大統領は今年2月に金で裏付けられた新通貨「ペトロゴールド」の開発も発表しています。
クリプトタイムズでは、ベネズエラにおける仮想通貨事情を詳しく報じています。
まとめ
ブロックチェーン技術と仮想通貨が各国政府や大手銀行などから受け入れられ始めるにつれ、ボラティリティを抑えることで実用性を高めたステーブルコインの開発競争が起こっています。
特に日本では上記で紹介した大手銀行3行から日本円連動型のステーブルコインが発表されているため、果たしてどの通貨が普及していくのかといった点に注目が集まります。
米国では証券取引所(SEC)からの認可を受けた米ドル連動型ステーブルコインが登場し始めており、いよいよ通貨のデジタル化が加速してく時期に突入しているのではと考えられます。
一方コモディティ市場では、従来のシステムをブロックチェーン上で行うべくTiberius Coinのような通貨が登場してきています。













































 有料記事
有料記事