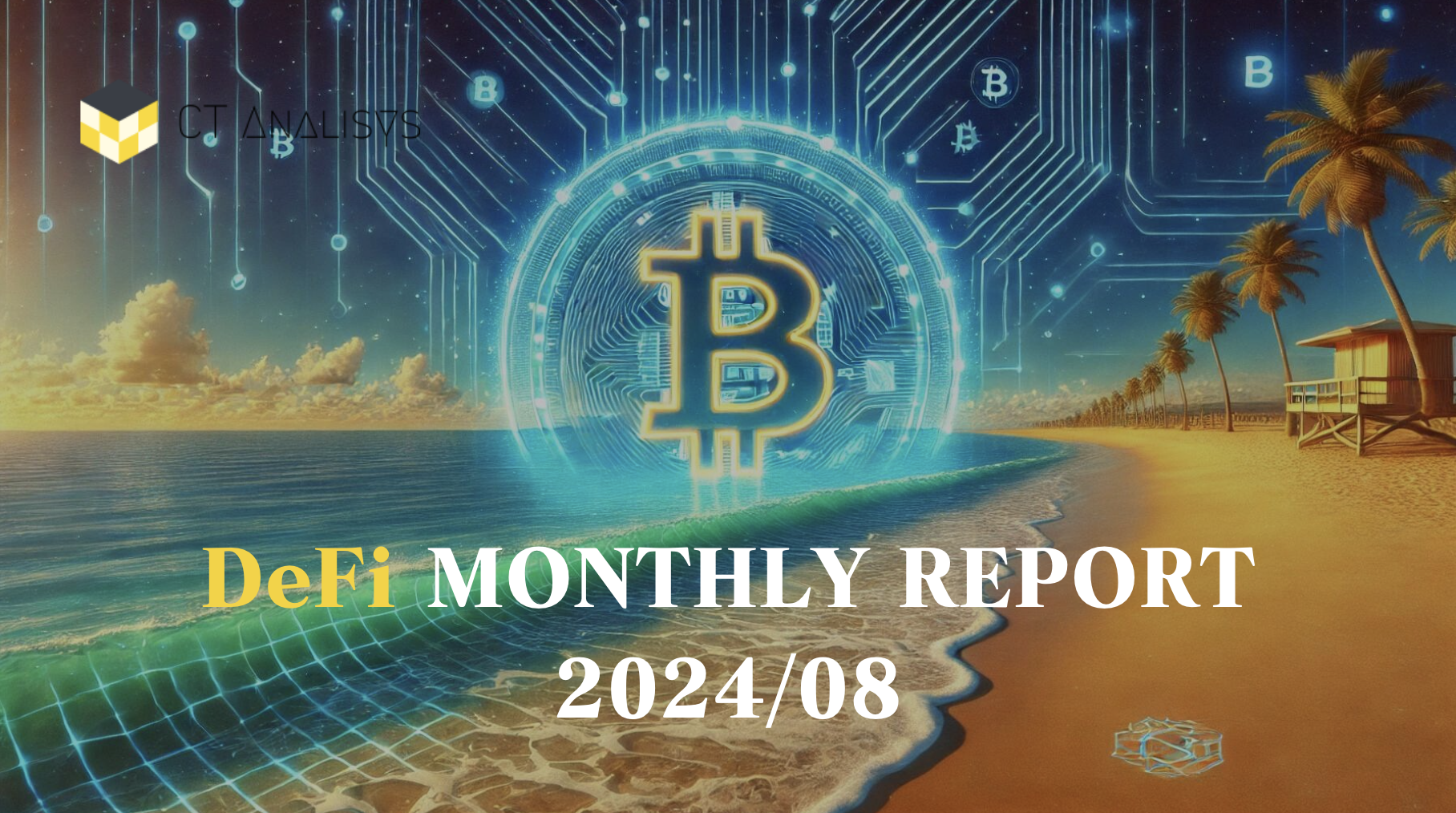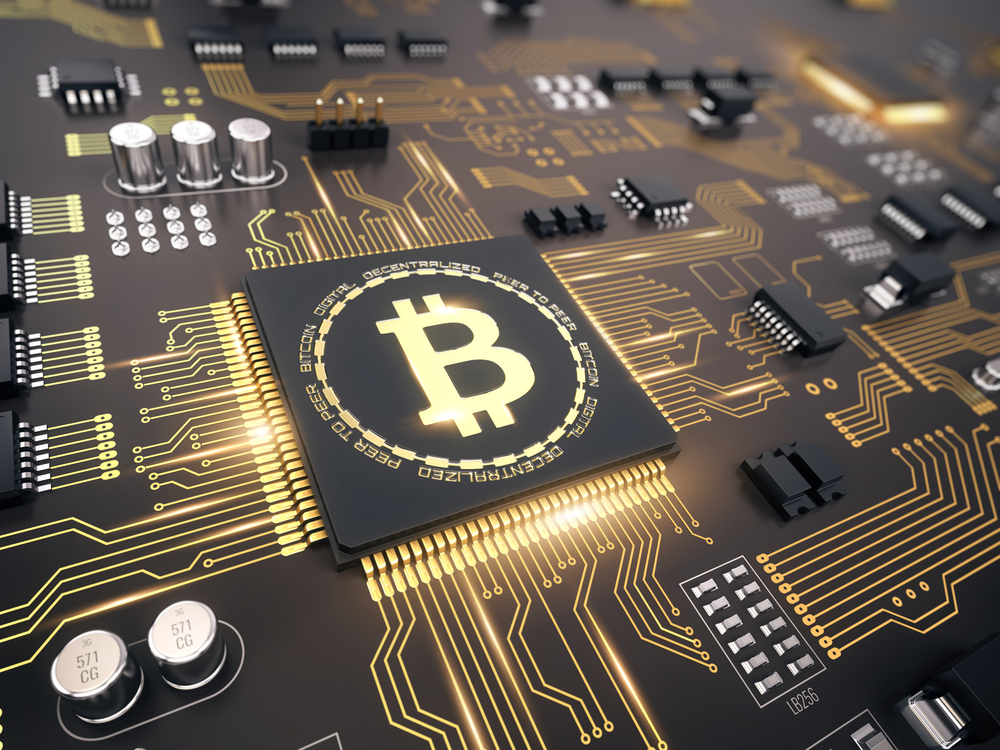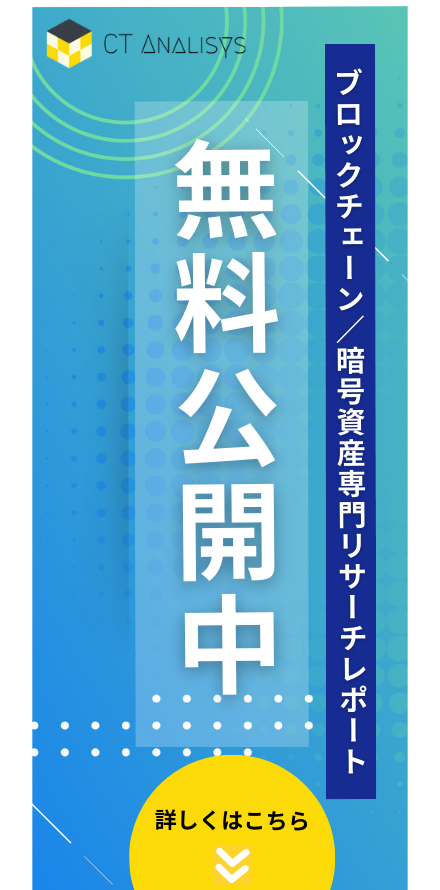$IOST エコシステムにおけるDeFi×NFT×相撲をテーマにしたDeFiプロダクト「Yokozuna Finance ($ZUNA)」アドバイザー / David Dzanis氏へのインタビュー
Yuya

Yokozuna Finance ($ZUNA)はIOST上のDeFiプロジェクトです。
名前・ビジュアル共にインパクトの強い同プロジェクトは、シングルアセットステーキングやダブルマイニング、NFTステーキングなどを組み合わせた画期的なエコシステムを開発しています。
今回、CRYPTO TIMESはYokozuna Financeのマーケティングアドバイザーを担当するデビッド・ザニス(David Dzanis)氏を取材し、同プロジェクトの仕組みや魅力、チームや長期的なプランなどについて聞いてみました。
Yokozuna Fi デビッド・ザニス氏にインタビュー

デビッド・ザニス氏: Yokozuna Financeのマーケティングアドバイザー, マーケティングコンサルタンシーを経営, ペプシコーラ、NASCARなどの大企業に勤めた経験を持つ。
─本日は取材に応じていただきありがとうございます。最初にYokozuna Financeはどのようなプロジェクトなのか教えてください。
ザニス氏: Yokozuna FiはIOST上のDeFiプラットフォームで、名前の通り相撲をテーマにしています。
基本は独自トークンの$ZUNAをステークしてリターンを得るというものですが、Yokozuna FiはこれにNFTを加えることでDeFiにゲーミフィケーションの要素を採り入れています。
Yokozuna Financeにはそれぞれ能力の異なる「力士NFT」が存在し、ユーザーは特定の条件を満たしてこの力士の番付を上げていくことがゴールになります。

Yokozuna FinanceのNFT力士たち。序の口から横綱までの番付でプラスされるリターンが上がる。
この力士NFTが何の役に立つかというと、ユーザーはこのNFTをステークすることで既存の$ZUNAステーキングにプラスしてリターンを得ることができるのです。力士の番付が高ければ高いほど得られるリターンも高くなります。
加えて、この力士と一緒に「化粧廻し(力士が土俵入りをするときに着用する廻し)」や「ちゃんこ鍋」など一定期間リターンをさらに増やす「消費型NFT」もステークすることができます。
この消費型NFTは指定期間を過ぎるとバーンされるようになっています。こうしたNFTステーキングやバーニングは、私たちの「NFTはコレクタビリティだけでなくユーティリティも持つべき」という考えからきています。
それから、Yokozuna Financeはシングルアセットステーキング・ダブルマイニングという強みがあります。
まずステークするのはひとつのアセット(=$ZUNA)だけなので、通常の流動性マイニングのようにインパーマネント・ロス(IL)の心配をしなくてすみます。
さらに、Yokozuna Fiでは$ZUNAをステークすると$ZUNAと$IOSTの両方をリワードとして得ることができます。

─NFTステーキング/バーニングやダブルマイニングなど、面白そうな技術をたくさん採用されていますね。Yokozuna Fiが開発するブロックチェーンにIOSTを選んだのはなぜですか?
ザニス氏: まず技術的な理由としてIOSTの速さと効率の良さ、それから手数料等の安さが挙げられます。また、Yokozuna Financeのようなコンセプトを持ったプロジェクトはまだIOSTにはない、というのもあります。
そしてなによりも重要なのがコミュニティです。Yokozuna FinanceもIOSTコミュニティからとても良いレスポンスを得られています。
相撲好きが集う開発チーム
─そもそもYokozuna Financeはなぜ相撲という日本のスポーツを取り上げたのでしょうか?
ザニス氏: 相撲は約2000年の歴史を持つ日本のスポーツですが、実は世界中にたくさんの愛好家がいます。Yokozuna Financeのメンバーももれなく相撲の大ファンです。
プロの力士として日本で競うには日本国籍を持つ男性である必要がありますが、日本国外ではなんと世界88カ国が集うアマチュア相撲連合も存在します。
IOSTが人気を誇る日本で馴染み深く、さらに世界中の国々でも興味関心を集めるテーマとして相撲はとても良いと考えたことが理由のひとつです。
もうひとつの理由は、DAOとして相撲というスポーツをもっと盛り上げていきたいというものです。
DAOとしてのYokozuna Financeはただステーキングリワードを配るだけでなく、将来的にはユーザーの投票を通して大会に出たり部屋に入る金銭的余裕のない力士をサポートしたり、私たちが愛する相撲をもっと多くの人に知ってもらうイニシアチブを執っていきたいと考えています。
─相撲好きのチームが手掛けるDeFiプロジェクト、というのは面白いですね。
ザニス氏: かなりの相撲好きが集まっていますね。アドバイザーのひとりであるコルトン・ランヤン(Colton Runyan)は現役のアマチュア相撲力士で、イギリスの名門・ケンブリッジ大学では博士号候補として平安時代の相撲文化について研究しています。
私自身も相撲をはじめ色々なスポーツが好きで、ペプシコーラなどの大企業でこれまで25年間スポーツマーケティングに携わってきました。
Yokozuna FiはほかにもIOSTからの技術者や日本のブロックチェーンスペシャリスト、IOSTの黎明期からノードを運営しているMetanyxの人材等を開発やアドバイザーに迎え入れ、日本と世界両方で相撲をプロモートしていくための多様性を持つチーム構成を意識しています。
このように敢えて匿名性を捨てて私たちのプロフィールをどんどん公開しているのは、Yokozuna Fiの長期的な活動に対するコミットメントでもあります。
─MetanyxなどのIOSTエコシステム内の他のプロジェクトと関わりがあるのも良いですね。
ザニス氏: はい。Yokozuna FinanceとMetanyxによる共同のプロダクト開発は当然行っています。まず手始めにMetanyx-IOSTのリクイディティ提供で$ZUNAを得る、というプロダクトのローンチを予定しています。
Yokozuna Financeインタビューのまとめ

Yokozuna Financeは始動したてのDeFiプロジェクトで、NFTキャラクターの育成というゲーミフィケーション要素を採り入れた新しいファーミングを開発しているとのことでした。
チームの相撲に対するパッションはとても熱く、日本と海外の相撲業界を盛り上げるという実世界での長期的な目標がとてもハッキリしたプロジェクト、という印象を受けました。
今月6日には公式ツイッターにてファーミングプラットフォームのローンチが発表され、いよいよプロダクトの輪郭が見え始めました。
画期的なNFTステーキング機能も来年Q2には実装されるとのことで、これからのアップデートにも注目していきたいところです。























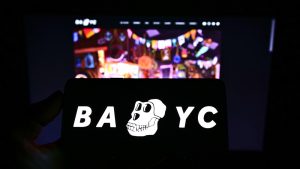
























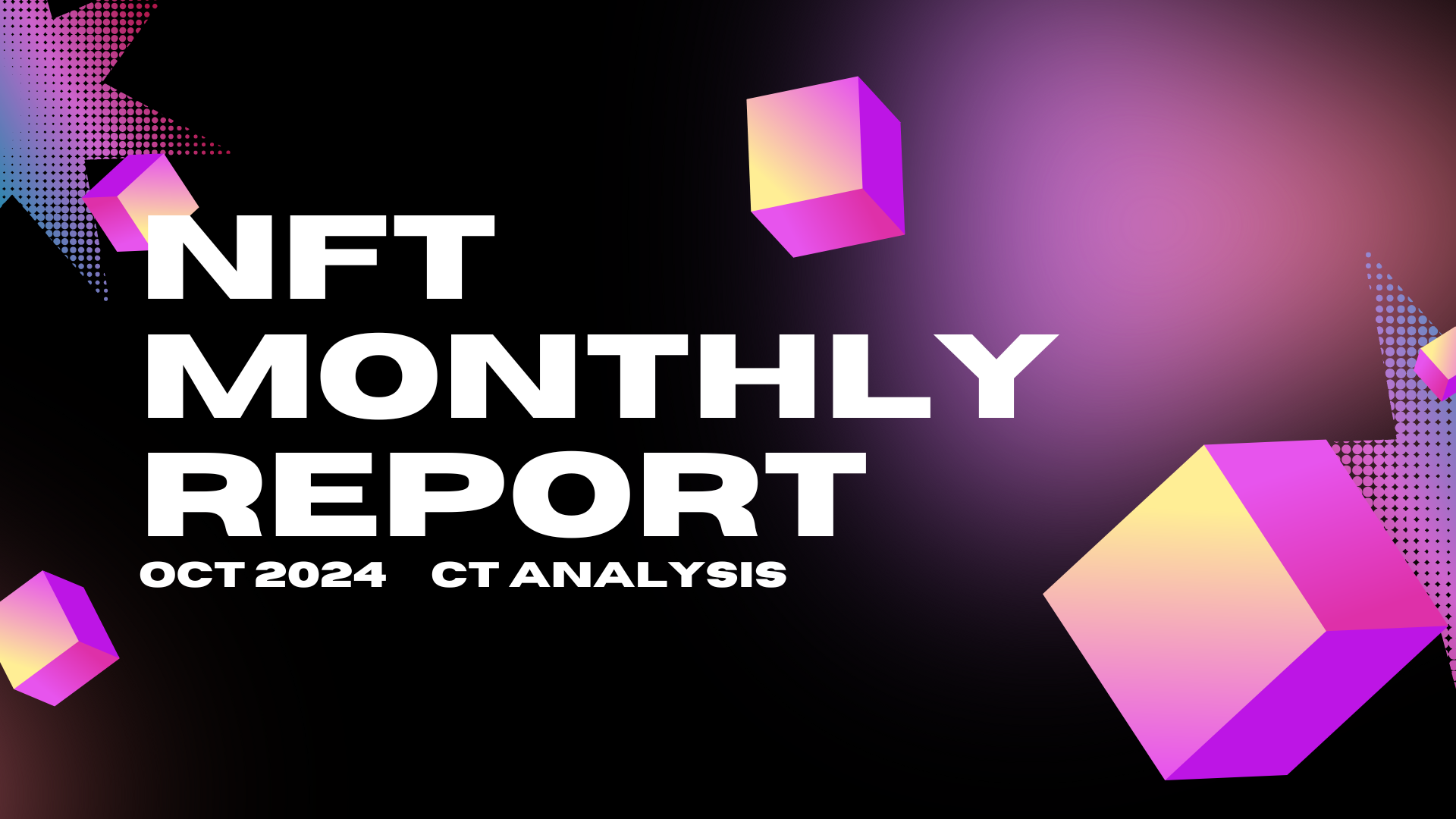
 有料記事
有料記事